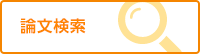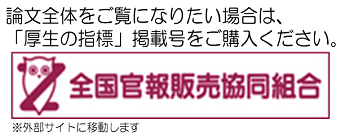論文
|
第72巻第1号 2025年1月 ヤングケアラーの実態把握に関する一考察-ケアを要する家族別にみたケアの特徴-濱島 淑恵(ハマシマ ヨシエ) 宮川 雅充(ミヤカワ マサミツ) 南 多恵子(ミナミ タエコ) |
目的 日本におけるヤングケアラーの実態把握は緒に就いたばかりであり,検討すべき課題もある。そこで,要ケア家族別に,要ケア家族の状態,ヤングケアラーが担っているケアの内容を集計し,その特徴を明らかにすることを試みた。なお,障がい,疾病等は有していない年下のこどものケアをしているヤングケアラーと,障がい,疾病等を有している家族のケアを担っているヤングケアラーとを区別した上で集計した。これらを踏まえて,ヤングケアラーの実態把握(判別と集計方法)に関して,考察を行った。
方法 2021年11月~2022年1月に,大阪市立中学校全128校において,1年生から3年生の全生徒(2021年12月末で51,912名)を対象として,無記名・自記式の質問紙調査を実施した。
結果 46,321票の調査票を回収することができた(回収率89.2%)。そのうち,本質問紙調査の有効回答は41,419票であり,これらを本稿における分析対象とした(有効回答率89.4%)。ヤングケアラーを,ヤングケアラーA(障がい,疾病等は有していない年下のこどものケアを担う者)と,ヤングケアラーB(障がい,疾病等を有している家族のケアを担う者)に分けて集計した結果,前者は848名(2.0%),後者は2,937名(7.1%)であった。要ケア家族の状態については,要ケア家族が父の場合,身体的な障がいを有するケースが,母の場合,精神障がい,精神疾患等が多いほか,外国ルーツのケースが比較的多かった。ケアの内容については,要ケア家族が父の場合,身体的介助が多く,母の場合,感情的サポートをしているケースが多かった。また,きょうだい(ヤングケアラーBの兄・姉,弟・妹)の場合も,感情的サポートを担っているケースが多かった。さらに,弟・妹の場合,ヤングケアラーAに比べ,ヤングケアラーBの方が,感情的サポート,身体的介助等,ケアの内容は多様であった。
結論 ヤングケアラーのケアの状況について,要ケア家族ごとの状態,ケアの内容の特徴を示すことができた。要ケア家族の状態については,父では身体障がいを有するケース,母では外国ルーツのケースが多いこと等が,ケアの内容では,きょうだい間の感情的サポートに留意する必要性が示された。特に弟・妹をケアしている場合については,障がいや疾病等の有無によって,ケアは質的に異なることが示された。ヤングケアラーの実態把握,支援を検討するに際し,要ケア家族の障がいや疾病等の有無に着目する必要がある。
キーワード ヤングケアラー,ケア,家族,きょうだい,中学生