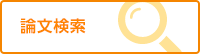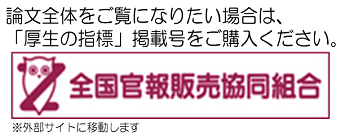論文
|
第72巻第2号 2025年2月 訪問・通所リハビリテーションクライエントの
|
目的 本研究の目的は,訪問・通所リハビリテーションに勤務するセラピストが,リハビリテーション実施計画書を作成する際に,クライエントの「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれをどの程度意識し,目標設定に取り入れ,その目標を達成したと認識しているのかを明らかとすることであった。
方法 全国の訪問・通所リハビリテーション事業所に勤務するセラピストを対象に,質問紙調査を実施した。質問紙では,調査対象者の基本情報と,クライエントの「心身機能」「活動」「参加」に対するセラピストの意識・目標設定・目標達成の認識について回答を求めた。分析では,調査対象者の基本情報について記述統計分析を実施後,クライエントの「心身機能」「活動」「参加」に対するセラピストの意識・目標設定・目標達成の認識の比較として,得点分布の図示およびFriedman検定を行った。さらに,Friedman検定で有意差を認めた変数について,Bonferroni補正による多重比較を行った。
結果 有効回答は670名であった。セラピストの認識の得点分布から,意識,目標設定,目標達成に進むにつれ,「心身機能」「活動」に比べて「参加」については実践の割合が大きく低下していくことが確認できた。次にFriedman検定の結果,セラピストが認識する意識・目標設定・目標達成の程度は,「心身機能」「活動」「参加」の間に有意差を認め(p<0.001),多重比較の結果,「参加」に対する意識,目標設定,目標達成におけるセラピストの認識の程度は,「心身機能」「活動」と比べて有意に低かった(p<0.001,r=0.386-0.614)。一方,全てにおいて「心身機能」と「活動」の間には有意差を認めなかった。
結論 2015年度の介護報酬改定後,クライエントの「活動」と「参加」に焦点を当てたリハビリテーションの実践が掲げられてから7年以上が経過した。この調査時点において,「活動」は「心身機能」と同程度に実践されているが,「参加」の実践には課題が残っている状況にあると捉えられた。クライエントの「心身機能」「活動」「参加」にセラピストがバランスよく働きかけるために,「活動」と「参加」を一体的に扱うのではなく,「参加」を「活動」から区分したうえで,「心身機能」「活動」と「参加」に対するセラピストの実践状況の開きを縮小していく対応が必要であることが示唆された。
キーワード ICF,参加,セラピスト,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション