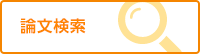論文記事
|
第68巻第13号 2021年11月 日本における主として麻酔科以外の診療科に従事している
|
目的 麻酔科については,厚生労働大臣の許可を得た麻酔科標榜医のみ標榜できる。麻酔科標榜医の実態についての先行研究はなく,2016年の医師・歯科医師・薬剤師調査において初めて麻酔科標榜医の数が明らかになった。外科などを専門とする主として麻酔科以外の診療科に従事している麻酔科標榜医(以下,非麻酔科の麻酔科標榜医)が麻酔科医の不足の緩和に貢献していると推察されるが,その実態は不明である。そこで本研究は,非麻酔科の麻酔科標榜医の配置状況について分析し,医療政策への示唆を検討することを目的とした。
方法 2016年末に実施された医師・歯科医師・薬剤師調査の個票データを,厚生労働省の許可を得て入手し,2016年時点の麻酔科標榜医の状況について記述した。次に,主として非麻酔科の麻酔科標榜医の特徴を明らかにするため,非麻酔科の麻酔科標榜医の有無を被説明変数,性,年齢,施設,地域分類,主として従事する診療科を説明変数とする多重ロジスティック回帰分析を行った。
結果 麻酔科標榜医の4割は,非麻酔科の麻酔科標榜医であった。非麻酔科の麻酔科標榜医の特性として,男性,40歳以上,過疎地域,診療所勤務のオッズ比が有意に高いという特徴がみられた。
結論 非麻酔科の麻酔科標榜医は,過疎地域の麻酔科業務の充実に貢献するなど,麻酔科の充実に貢献している可能性が示された一方で,麻酔科専門医と異なり更新がないことから,教育制度の整備について検討が必要である。
キーワード 麻酔科標榜医,医師・歯科医師・薬剤師調査,医師偏在,更新制
|
第68巻第13号 2021年11月 東日本大震災被災地における
山下 真里(ヤマシタ マリ) 清野 諭(セイノ サトシ) 野藤 悠(ノフジ ユウ) |
目的 東日本大震災の被災地では,新しいコミュニティになじめず孤立や孤独に陥っている者への対策が喫緊の課題となっている。本研究では,被災地在住高齢者の孤独感の実態を把握し,孤独感と関連する可変的要因を横断研究にて明らかにすることを目的とした。
方法 2019年10月,気仙沼市在住の65-84歳の非要介護認定者(要支援者は含む)18,038名から,16社協区別に層化無作為抽出した9,754名を対象に自記式質問紙調査を郵送法により実施した。返送のあった8,150名(回収率83.6%)のうち欠損のない5,034名を解析した。孤独感の評価には,日本語版Three-Item Loneliness Scaleを用い,6点以上を高孤独感ありとした。高孤独感ありと関連する可変的要因として,週1日以上の運動習慣,長時間座位行動,同居人以外との週1回以上の対面交流と非対面交流,孤食,閉じこもり,社会活動(ボランティア,趣味・学習,自治会,交流サロン,スポーツクラブのいずれかに月1回以上参加),ソーシャルサポート(情緒的サポート,手段的サポート),震災後の相談環境の変化について尋ね,マルチレベルロジスティック回帰分析(全変数投入モデル)によりオッズ比(95%信頼区間)を算出した。調整変数は,性別,年齢,独居,婚姻状況,現在の住居,介護保険料の所得段階区分,就労状況,教育歴,既往歴,抑うつの有無,腰と膝の慢性疼痛の有無,移動能力制限,飲酒,喫煙を用いた。
結果 高孤独感を有する割合は,全体で18.2%(916名),男性で19.2%,女性で17.3%であった。また年齢区分別の高孤独感該当者は,前期高齢者で18.2%,後期高齢者で18.3%であった。男女に共通して高孤独感と関連していた可変的要因は,非対面交流なし,孤食あり,社会活動なし,手段的サポートいない,ネガティブな相談環境の変化であった。男性のみに見られた特徴としては無職と高孤独感との有意な関連が認められた。女性のみに見られた特徴としては,情緒的サポートいないと対面交流なしが高孤独感と有意な関連を示した。
結論 孤独感は,人との交流状況や食事環境,ソーシャルサポートと有意に関連していることが明らかになった。また,被災地の孤独の特徴として,震災後の相談環境のネガティブな変化が,現在の孤独感と強く関連していることが示された。被災地の取り組みとして,会食機会の提供等,食を通したコミュニティづくりが効果的であるかもしれない。
キーワード 東日本大震災,孤独感,日本語版Three-Item Loneliness Scale,コミュニティの再構築,身近な相談環境の改善
|
第68巻第13号 2021年11月 不登校発生に関連する家族要因の検討-子育て世帯全国調査データを用いて-白片 匠(シラカタ タクミ) 平 和也(タイラ カズヤ)長尾 青空(ナガオ セイキ) 伊藤 美樹子(イトウ ミキコ) |
目的 児童生徒の不登校は,犯罪行為や様々な疾患との関連が報告されており,公衆衛生上も重要な課題である。しかし,成育環境の中心を担う家族要因と不登校との関連に関する研究はほとんどされていない。本研究では,不登校発生と家族要因との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 労働政策研究・研修機構が行った「第1回(2011年),第2回(2012年)子育て世帯全国調査」を二次利用し,子どもの人数が3人以下の世帯で,子ども全員が小学生から高校生に含まれ,不登校に関する質問に回答のあった1,884世帯を分析対象とした。ひとり親世帯とふたり親世帯を層化サンプリングしていることから,ひとり親・ふたり親の世帯別に分析を行い,不登校発生の有無を従属変数とし,独立変数には家族要因として子どもの人数や性別,世帯年収,しつけの厳しさ,子どもと過ごす時間を投入した多変量二項ロジスティック回帰分析を行った。
結果 ひとり親世帯は789世帯で,うち不登校ありの世帯は99世帯(12.5%)であった。また,ふたり親世帯は,1,095世帯で,うち不登校ありの世帯は55世帯(5.0%)であった。多変量二項ロジスティック回帰分析の結果,不登校のリスクは,ひとり親世帯では,600万以上800万円未満(参照基準:世帯年収200万円未満に対するオッズ比(OR)=0.12,95%信頼区間(95%CI):0.02-0.98)が低く,しつけをやや甘やかしている(参照基準:とても厳しいに対するOR=8.19,95%CI:1.04-64.39)が高かった。一方,ふたり親世帯では600万以上800万円未満(OR=0.07,95%CI:0.01-0.43)と1000万円以上(OR=0.14,95%CI:0.03-0.75)が不登校のリスクが低かった(いずれも参照基準,200万円未満)。
結論 不登校発生に関連する家族要因として,全国平均の世帯年収よりも低いことやしつけの厳しさで甘やかしている家庭では,不登校発生のリスクが高いことが示唆された。
キーワード 不登校,家族要因,子ども,世帯年収,しつけ
|
第68巻第13号 2021年11月 国民生活基礎調査データを用いた学歴と有配偶率との関連の分析-2010-2019年-奥井 佑(オクイ タスク) |
目的 本研究では国民生活基礎調査のデータをもとに配偶状況と学歴との関連についての近年の動向を分析した。
方法 2010年から2019年までの国民生活基礎調査のデータを用いた。対象年齢について,20-24歳から75-79歳までの5歳刻みの年齢階級のデータを用いた。配偶者の有無は,調査時に配偶者を有しているか否かをもとに有配偶者と無配偶者に分類されている。学歴について,小学・中学・高校・旧制中,専門学校・短大・高専,大学・大学院卒の3区分に分け分析を行った。各学歴における有配偶率を年齢階級,性,調査年別に算出した。また,2010年の全対象者における年齢階級別人口を基準人口として,各調査年の年齢調整有配偶率を性および学歴別に算出した。加えて,学歴と所得との関連を確かめるため,役員以外の雇用者に対象を限定したうえで学歴と低所得者割合との関連について同様の分析を行った。
結果 学歴と配偶状況との関係は年齢階級により異なり,20代では男女とも小学・中学・高校・旧制中卒の有配偶率が最も高かったが,以降の年齢ではその他の学歴の方がより有配偶率が高い傾向がみられた。年齢調整有配偶率は,男性では調査年を問わず,大学・大学院卒,専門学校・短大・高専卒,小学・中学・高校・旧制中卒の順番に有配偶率が高くなり,調査年を経るごとに大学・大学院卒と小学・中学・高校・旧制中卒の差が拡大した。また,学歴を問わず年齢調整有配偶率は2010年から2019年にかけて減少した。女性では学歴による年齢調整有配偶率の差は調査年を問わず男性よりも小さかったが,2012年以降においては専門学校・短大・高専卒以上が小学・中学・高校・旧制中卒を上回る結果となっていた。また,雇用者に限定して,学歴と低所得者割合の関連を調べたところ,男女とも学歴が低いほど低所得者割合が高いことが示された。
結論 男性において有配偶率の減少が学歴を問わず顕著であるとともに,学歴による有配偶率の格差も拡大傾向であることが示された。女性では学歴による有配偶率の差は小さかったが,近年,学歴により有配偶率に差が生じ始めていることがわかった。
キーワード 国民生活基礎調査,有配偶率,学歴,公的統計,所得,低所得者割合
|
第68巻第12号 2021年10月 日本の成人女性における院内助産システムに対するケアニーズ黒﨑 直央(クロサキ スナオ) 宮﨑 文子(ミヤザキ フミコ) 朝澤 恭子(アサザワ キョウコ) |
目的 日本では助産師外来・院内助産の普及が推進されているが,その普及率は停滞している。本研究の目的は,院内助産システム推進の示唆を得ることを目指し,成人女性における院内助産システムに対するケアニーズを明らかにすることである。さらに助産所出産経験者(以下,助産所群)と,病院出産経験者および出産未経験者(以下,助産所以外群)におけるケアニーズの相違および院内助産システム認知の有無によるケアニーズの相違を明らかにした。
方法 関東地方の18~39歳の女性697名に対して,無記名自記式質問紙を用いて量的横断的研究を行った。調査内容は,院内助産システムに対するケアニーズおよび利用ニーズであった。分析は記述統計量算出およびχ2検定を実施した。
結果 有効回答は340部(有効回答率48.8%)であり,助産所群62部と,助産所以外群278部のデータを用いて分析した。助産師外来を知っている人は37.1%,院内助産を知っている人は13.2%であった。院内助産システムのケアニーズは,「助産師が誠実」86.8%,「助産師と医師のチームワークがよい」86.5%,「秘密やプライバシーの保持」86.5%,「助産師がよく話を聞いてくれる」84.4%の順に多かった。院内助産システムの利用交通ニーズは徒歩では10分以内と回答する人が55.0%で最も多く,院内助産の分娩費用ニーズは出産育児一時金と同額が54.7%と最も多かった。
結論 院内助産システムに対するケアニーズは,誠実,医師とのチームワーク,プライバシー保持,傾聴といった顧客コミュニケーションが上位を占めていた。助産所群は自然分娩,フリースタイル分娩,分娩部屋選択,産褥マッサージ,家族立ち会い出産という具体的なケアニーズが多く,助産所以外群は送迎バスの利用やスタッフの独自の白衣といったケア以外の利用ニーズが多かった。
キーワード 助産師,院内助産システム,ケアニーズ,助産師外来,横断調査
|
第68巻第12号 2021年10月 市民後見人における受任調整の現状と後見活動時
永野 叙子(ナガノ ノブコ) 小澤 温(オザワ アツシ) |
目的 市民後見人の受任調整の現状を分析し,後見活動時に感じる困難さの内容と,困難さを規定する要因を明らかにすることを目的とした。
方法 2016年12月~2017年3月に,現任の市民後見人142名に対して質問紙調査を実施した。調査内容は,市民後見人の属性,被後見人等の概要,後見活動時に感じる困難さとした。有効回収票は113件(有効回収率=79.6%),分析対象は112件(1件辞退)であった。分析項目の独立変数は,①居所2群:「在宅,施設等」,②申立人2群:「親族(本人含),市町村長申立」,③介護度4群:「要支援1~要介護2,要介護3,要介護4,要介護5」,④受任経験:「有,無」,⑤資格所有:「社会福祉士,介護福祉士,看護師,税理士,教員,その他等の記入があった場合を有,記入なしを無」,⑥支援・監督組織の2群:「独自養成の実績がある3カ所の実施機関(2011年老人福祉法の改正ならびに,市民後見推進事業開始以前より市民後見人を独自研修プログラムで養成してきた成年後見実施機関),それ以外の7カ所の実施機関」とした。従属変数は,「活動時に感じる困難さ19項目」とし,独立変数①~⑥との関連性をみるためにχ2検定を行った。
結果 困難さを規定する要因のうち被後見人等の要件では,市町村長申立案件の場合に,「家族等との意見調整」を「困難である」と感じる傾向がみられた(p<0.05)。次に,市民後見人の要件では,受任経験がある者が「葬儀等の手配」(p<0.01),「財産の引き渡し」(p<0.05)を「困難でない」と感じる傾向がみられた。また,市民後見人を支援・監督する組織での検討では,独自養成の実績がある組織で支援・監督を受ける市民後見人は,「家族同様のかかわり」「保証人等を求められる」「家族等との意見調整」「緊急時の対応」に困難さを感じない傾向がみられた。
結論 死後事務は,1ケース1回限りの非日常的かつ個別性が高い活動であるが,市民後見人の受任経験が死後事務の手続き・手順への理解を促進し,見通しをもった活動につながると考えられた。一方,独自養成の実績がある組織で支援・監督を受ける市民後見人には,困難さを感じない傾向がみられたことから,当該機関は,受任後の市民後見人に対する継続的支援を推進していると考えられた。したがって,受任調整時には市民後見人の受任経験を考慮する一方で,支援・監督組織が市民後見人の育成・支援を通じて自らも実務経験を積みつつ,現任の市民後見人への継続的支援を推進することが,市民後見事業の普及・促進につながると考えられる。
キーワード 成年後見制度,市町村申立,市民後見人,受任調整,困難さ,成年後見制度利用促進基本計画
|
第68巻第12号 2021年10月 世帯の社会的脆弱性尺度の開発
福定 正城(フクサダ マサキ) 斉藤 雅茂(サイトウ マサシゲ) |
目的 本研究は,世帯境界の概念を提示し,その境界を通したさまざまな刺激の出入りや,対人関係における距離感にかかわる評価尺度である世帯の社会的脆弱性尺度を開発し,信頼性と妥当性を検討することを目的とした。
方法 先行研究から抽出した30項目で尺度原案(5件法)を作成し,表面妥当性の検討後,予備調査を行った。予備調査後に4件法への修正を行い,本調査では愛知県内すべての地域包括支援センターに質問紙を配布し,112カ所347名(有効回答307名)から回答を得た。調査期間は2020年6月〜8月であった。評価対象世帯は,①2名以上の世帯員がいる,②65歳以上の高齢者が1名以上含まれる,③生活に困難が生じているにもかかわらず自ら支援を望まない,これらすべてを満たす世帯と定義した。探索的因子分析(最尤法・プロマックス回転)で因子的妥当性を確認した後に,内的一貫性をクロンバックα係数で検討した。そして,社会的孤立,セルフ・ネグレクト,支援困難感にかかわる指標を外部基準とし,基準関連妥当性を検討した。また,世帯構成の違いによる尺度得点の相違について,一元配置分散分析後にScheffe法を用いた多重比較によって確認した。さらに,内容的妥当性を専門家へのヒアリングを行い検討した。
結果 探索的因子分析の結果,スクリー基準と因子の解釈可能性により3因子構造を採択し,第1因子「セルフ・ネグレクト」,第2因子「社会的不適応」,第3因子「社会的孤立」と解釈した。全項目が0.35以上の因子負荷量をもち,因子的妥当性は確保されていた。クロンバックα係数は,尺度全体が0.84,第1~3因子が0.73,0.70,0.78であり,尺度の信頼性が示された。外部基準と尺度得点との間に有意な相関が認められた。多重比較の結果,高齢者と未婚の子世帯は,高齢者夫婦世帯よりも尺度得点が有意に高い傾向が確認された。専門家4名全員から,主観的評価と尺度得点との間に矛盾は認められず,本尺度の項目は世帯の社会的脆弱性を測定するうえで必要な内容をカバーしているとの意見を得られた。
結論 本研究によって開発された世帯の社会的脆弱性尺度は,信頼性と妥当性を有する尺度であることが示された。本尺度は,対象世帯を支援する者にとって,有益な介入効果測定の指標となると考えられる。
キーワード 世帯の社会的脆弱性尺度,世帯境界,家族システム,社会的孤立,セルフ・ネグレクト,因子分析
|
第68巻第12号 2021年10月 子ども虐待と子育て不安や就学前親子のニーズとの関連性-岡山市の就学前親子の居場所に関する調査より-八重樫 牧子(ヤエガシ マキコ) |
目的 本論文では,親子が安全・安心に過ごすことのできる岡山市の就学前親子の居場所のあり方を検討するために,岡山市の就学前の子どものいる世帯を対象に就学前親子が利用する居場所のニーズなどに関する質問紙調査を実施し,子ども虐待と子育て不安や就学前親子のニーズとの関連性について検討した。
方法 調査対象は,2019年5月現在の岡山市住民基本台帳から0歳から5歳までの子どもがいる36,742世帯から2,520世帯を無作為抽出し,同年6月7日~6月30日に郵送調査法による質問紙調査を実施した。1,275人から回答が得られた(有効回答率は50.6%)。子ども虐待意識・経験・子育て不安・居場所ニーズのスピアマンの順位相関係数を算出した。子ども虐待意識・経験については,家計状況・家族形態・子育て不安・居場所ニーズによる違いを検討するためにKruskal-Wallis検定を行った。「子どもをたたいた(経験)」を従属変数,子どもの月数・就園状況・家計状況・子ども虐待意識・子ども虐待経験・子どもの頃の虐待経験・子育て不安・居場所ニーズを独立変数とする重回帰分析を行った。
結果 「子どもをたたいた(経験)」と「子どもの頃親等にたたかれた(経験)」の相関はρ=0.295(p<0.01)で低い正の相関があったが,「子どもをたたいた(経験)」と「子どもの頃親等に怒鳴られた」の相関は,ρ=0.598(p<0.01)でかなり高い正の相関があった。余裕のある人より,普通・苦しい人の方が子どもをたたくことが多く,親等にたたかれた経験も多くなっていた。重回帰分析の結果,子どもの月数が多く,怒鳴ることに肯定的であり,子どもの頃親等にたたかれたり,怒鳴られた経験のある人ほど子どもをたたき,さらに,子育て困難感が高く,子育て相談・支援ニーズが低く,遊び場ニーズの高い人ほど子どもをたたく傾向があることが明らかになった。
結論 子どもをたたいたり,怒鳴ったりすることは体罰であり,しつけとして体罰を用いない,特に怒鳴らない子育ての方法を親子の居場所などで伝えていく必要がある。親子の居場所において,子育て不安が高く,子どもをたたく人や子どもを怒鳴る人,子どもの頃親等に怒鳴られた経験のある人,そして家計の苦しい人やひとり親家庭などを個別に把握し,寄り添っていく伴走的な子育て支援を実践するとともに,子育て支援プログラムや虐待治療プログラムなどを含む福祉サービスにつなげていくソーシャルワークに基づいた子育て支援が求められている。
キーワード 親子の居場所,地域子育て支援拠点,子ども虐待意識,子ども虐待経験,被虐待経験
|
第68巻第12号 2021年10月 若年性認知症者の経済状況に応じた
竹本 与志人(タケモト ヨシヒト) 杉山 京(スギヤマ ケイ) 倉本 亜優未(クラモト アユミ) |
目的 本研究では,居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に,若年性認知症者の経済状況に応じた社会保障制度の選定能力について,事例問題を用いて明らかにすることを目的とした。
方法 近畿,中国(うち1県を除く),四国,九州・沖縄地方に設置されている居宅介護支援事業所16,345カ所(2017年7月時点)から層化二段階抽出法により選定した1,500カ所の事業所を対象に質問紙による郵送調査を行った。調査内容は属性,若年性認知症者の事例問題,社会保障制度の選定能力を確認する項目,事例問題における経済問題の軽減・解決のための相談先の意向等で構成した。調査期間は2017年10月から同年11月の2カ月間であった。
結果 回答は478名から得られ,統計解析には当該項目に欠損値のない386名の資料を用いた。事例問題に対する社会保障制度の利用の可否の回答を用いてクラスター分析を行った結果,5つのクラスターに類型化されると判断した。
結論 5つのクラスターいずれもが社会保障制度の選定能力に課題を有していたが,相談先の意向を確認すると,その選定能力を補完する援助要請を行っている可能性が示唆された。今後は,相談先の人・機関が適切な助言を行うことができているか否かについて確認することが課題である。
キーワード 若年性認知症者,社会保障制度,介護支援専門員,経済問題,経済支援,事例問題
|
第68巻第12号 2021年10月 高齢者介護施設のケア従事者における
富永 真己(トミナガ マキ) 田中 真佐恵(タナカ マサエ) |
目的 本研究は,高齢者介護施設のケア従事者を対象に,現状の組織の受け入れの準備体制と,外国人介護職の受け入れへの期待と不安の実態について,仕事のストレスと人間関係に関わる職場環境の側面から明らかにすることを目的とした。
方法 倫理委員会の承認後,10府県の高齢者介護施設(N=30)のすべての介護士・看護師(N=1,060)を対象に,2019年9~10月に無記名の自記式質問調査票による量的調査を実施した(回収率71%)。調査項目は,基本属性,雇用・労働特性,施設と職場での外国人介護職の受け入れ状況,受け入れへの期待と不安の程度,仕事のストレス,「職場のソーシャル・キャピタルと倫理的風土」の3下位尺度を含めた。欠損のない583票を解析に用いた。外国人介護職の受け入れの有無の2群による期待と不安の回答割合および施設の受け入れの準備体制の有無の回答割合はχ2検定にて,受け入れへの低い期待と強い不安の有無の2群による仕事のストレスと「職場のソーシャル・キャピタルと倫理的風土」の3下位尺度の平均値の差はt検定にて検討した。
結果 対象者の平均年齢は42.6(±12.2)歳,女性が67%で,対象者の36%が現在の施設で,22%が職場で外国人を受け入れていた。施設の受け入れの準備体制について全7項目で「わからない」の回答が最も多かった。受け入れへの期待については対象者全体の8割が「多少・全くない」と回答し,受け入れの不安については3割が「非常に・かなり不安」と回答した。一方,外国人介護職が働く施設の者はそれ以外の者に比べ,施設と自分の職場での受け入れに対し,期待が「全くない」「非常に不安」との回答割合が有意に低かった。受け入れに対し期待が「全くない」者は,それ以外の者に比べ職場のソーシャル・キャピタルと倫理的リーダーシップの平均値が有意に低かった(p<0.05)。受け入れに非常に不安な者はそれ以外の者に比べ,仕事のストレスの平均値が有意に高く(p<0.01),職場のソーシャル・キャピタルの平均値は有意に低かった(p<0.05)。
結論 日本人という同質のケア従事者が異質の外国人を排斥するような職場風土より,むしろ現存する仕事のストレスや人間関係に関わる職場環境の課題が,外国人介護職の受け入れに対する低い期待度や強い不安を抱くケア従事者に認められた。課題の解決の取り組みとともに取り組みの周知の必要性が示唆された。外国人材の長期定着化に向け,受け入れ後の日本語や資格合格を目指した教育・訓練とともに,やりがいのある職場環境の構築がより一層,望まれる。
キーワード 高齢者介護施設,外国人,介護職,職場環境,不安,期待
|
第68巻第11号 2021年9月 共働き世帯における母親の
細川 陸也(ホソカワ リクヤ) 桂 敏樹(カツラ トシキ) 平 和也(タイラ カズヤ) |
目的 近年,子育て世帯における共働きの割合は増加傾向にある。しかし,共働き世帯を支える社会システムの整備はいまだ不十分であり,仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進は重要な課題となっている。親のワーク・ライフ・バランスは,子どものメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性がある。本研究は,共働き世帯における母親のワーク・ライフ・バランスと学童期の児の社会適応との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 2019年10~12月に,愛知県内の小学5年生(10-11歳児)とその養育者1,414名を対象に自記式質問紙調査を実施した。主な調査項目は,親の雇用形態,家庭の世帯収入等とし,ワーク・ライフ・バランス尺度(Survey Work-Home Interaction-NijmeGen),児の社会適応(Child Social Preference Scale)尺度などを用いた。目的変数を児の社会適応,説明変数を母親のワーク・ライフ・バランス,調整変数を性別,家族構成,親の雇用形態,家庭の世帯収入として重回帰分析を行った。
結果 有効回答の得られた709名のうち,基準を満たす共働き世帯の児443名を分析対象とした。分析の結果,仕事から家庭へのネガティブな影響が大きいほど児の社会不適応のリスクが高くなる(シャイネス:β=0.180,p<0.001,社会的無関心:β=0.149,p=0.003)一方,仕事から家庭へのポジティブな影響が大きいほど社会不適応のリスクが低くなる(シャイネス:β=-0.130,p=0.008)傾向がみられた。
結論 母親のワーク・ライフ・バランスは,ネガティブな面でもポジティブな面でも,児の社会適応に関連していることが示唆された。仕事と子育てを両立するための積極的な取り組みは,児の社会適応にとって重要であると考える。
キーワード 共働き世帯,母親,ワーク・ライフ・バランス,学童期,社会適応
|
第68巻第11号 2021年9月 後期高齢者率の高い地区と低い地区における
泉 眞知子(イズミ マチコ) 池田 直隆(イケダ ナオタカ) |
目的 本研究は,後期高齢者率の高い地区と低い地区における住民ボランティアによる独居高齢者への見守り活動状況を比較することを目的とした。
方法 大都市近郊である大阪府寝屋川市の住民ボランティア全数である1,812名に対して自記式質問紙配布による調査を実施した。調査項目は,基本属性や見守り活動状況として,住民ボランティアが実施している見守り活動の対象者数と見守り関連活動の実施頻度を把握した。同市24小学校区において,2017年の全国の平均後期高齢者率である13.8%を基準として,後期高齢者率が13.8%以上の17小学校区を後期高齢者率が高い地区,13.8%未満の7小学校区を後期高齢者率の低い地区とした。後期高齢者率の高い地区と低い地区における住民ボランティアの基本属性,見守り活動の対象者数と見守り関連活動の活動頻度の違いについて,χ2検定により検討した。
結果 有効回答数は764名(42.2%)であった。基本属性は,後期高齢者率の高い地区の住民ボランティアは低い地区の住民ボランティアに比べて,ボランティア自身が75歳以上の者(p<0.05),男性(p<0.001),暮らし向きに余裕がある者(p<0.05),無職者(p<0.05)の割合が高かった。住民ボランティアの見守り活動の対象者数については,後期高齢者率の高い地区では低い地区に比べて,声かけ(p<0.05),ポストや明かりの確認(p<0.01),戸別訪問(p<0.01)の対象者数が0人である者の割合が高かった。一方,見守り関連活動は,後期高齢者率の高い地区の住民ボランティアは低い地区の住民ボランティアに比べて,会食・サロン・喫茶運営を実施していない者の割合が低かった(p<0.01)。
結論 本研究の結果より,後期高齢者率の高い地区では低い地区と比べて,住民ボランティアが実施している声かけ,ポストや明かりの確認,戸別訪問などの見守り活動は頻繁に行われていない一方,会食・サロン・喫茶運営などの見守り関連活動は活発に行われている可能性が示唆された。このことより,後期高齢者率の高い地区にあっても住民ボランティア自身の体力や意欲に応じたボランティア活動を継続していると考えられる。
キーワード 後期高齢者率,住民ボランティア,独居高齢者,見守り活動
|
第68巻第11号 2021年9月 小規模多機能型居宅介護における認知症の人を支える
|
目的 認知症の人を支える家族介護者への心理的支援に関する先行研究では,通所介護を主に訪問介護と短期入所介護の組み合わせ,つまり,小規模多機能型居宅介護の仕組みが有効としている。しかし,小規模多機能型居宅介護を対象とした有効性の検証はほとんどない。そこで本研究は,小規模多機能型居宅介護の専門職を対象に質的研究を行い,専門職の客観的観点から認知症の人を支える家族介護者の心理的支援の有効性に関する要因を明確にすることを目的とした。
方法 小規模多機能型居宅介護における,認知症の人を支える家族介護者の心理的支援の有効性を検討するために,2019年8月から2019年9月に調査を行った。全国における小規模多機能型居宅介護事業所の中で14カ所の専門職14人を対象に質的研究を実施した。調査方法は,半構造化面接によるインタビューの方法で実践体験や事例を自由に語ってもらった。分析にはテキストマイニング手法を行った。
結果 分析の結果,『安心した地域生活の連続』『理解を得る持続的な説明』『柔軟性に富んだサービス』『最期を支える』『臨機応変な支援』『認知症と家族の相互作用による関係性』『心理的支援への取り組み』『変化する状況へのアプローチ』という8つの有効な要因が示され,小規模多機能型居宅介護は併設型か,単独型かによって支援や関わり方の内容が一部異なっていることが明らかにできた。
結論 小規模多機能型居宅介護は他の在宅サービスと比べて緊急時の利用が可能で臨機応変な対応ができることと,いつでも支援を求めることが可能な接近性が容易であること,利用者のニーズによってサービスを組み合わせることができること,認知症の人と家族が必要な時に専門職から相談できる体制になっていること,看取りを支えることで人生の最期まで安心して住み慣れた地域で生活することができて,心理的安定にもつながっていた。
キーワード 認知症の人,家族介護者,心理的支援,小規模多機能型居宅介護,専門職
|
第68巻第11号 2021年9月 周術期における術後せん妄アセスメントシートの検討野末 波輝(ノズエ ナミキ) 斉藤 理恵(サイトウ リエ)鷲見 由紀子(スミ ユキコ) 藤原 美樹(フジワラ ミキ) |
目的 せん妄は病棟の種類を問わず入院患者の1割程度に発症している。急速に高齢化が進行しているわが国においては,今後ますます,せん妄患者が増加することが予想される。また,外科学の進歩に伴い高齢者が手術を必要とする疾患に罹患することも多くなると推測され,高齢者手術で最も多い合併症である術後せん妄の発症も増加すると予測される。術後せん妄は,患者の生命に大きな影響を及ぼすだけでなく,医療スタッフの負担となりマンパワー不足にもつながる。そのため,術後せん妄のリスクをアセスメントし,早期からの予防的介入に組織的に取り組むことは重要である。本研究では,当病棟で使用している簡便な術後せん妄アセスメントシートのリスク因子と因子数の妥当性を検討した。
方法 対象者は2019年6月~2020年3月までの手術予定患者301名とした。入院時,担当看護師が術後せん妄アセスメントシートを記載し,後日研究メンバーによってシートの回収を行った。その他関連因子については,研究メンバーによって情報取集した。各調査項目と術後せん妄の有無についてχ2検定を行った。カットオフ値を算出し,感度,特異度を算出,ROC曲線を作成した。
結果 調査項目のうち,年齢,要支援または要介護認定あり,日常生活自立度A以下,開腹手術,認知症ありまたはMMSE24点以下,脳血管障害の既往あり,ICU入室あり,抗精神病薬の定期内服あり,視覚,聴覚障害ありと術後せん妄に有意な関連がみられた。術後せん妄アセスメントシートのカットオフ値を2項目に設定した時の感度は,94.0%,特異度は76.5%であった。
結論 調査項目と術後せん妄の有無については過去の先行研究とおおむね一致した結果であった。術後せん妄アセスメントシートの感度,特異度が最大となるカットオフ値は2点であったことから,2項目以上にチェックの入る患者にはより注意して介入を行っていくことが必要である。今後も術後せん妄患者は増加することが予想されるため,せん妄予防の取り組みがより重要となると考えられる。
キーワード 術後せん妄,周術期,術後せん妄アセスメントシート,術後せん妄リスク因子
|
第68巻第11号 2021年9月 季節調整法を応用した
有田 帝馬(アリタ テツマ) |
目的 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の報告日別の新規陽性者数は,感染状況を判断する上で重要な指標である。そのトレンド(傾向・循環変動)をとらえる上で週単位の周期性や休日の影響が阻害要因となっている。経済統計の分析で利用される季節調整法を応用し,これらの阻害要因を分離できないか検討した。
方法 全国および東京都の報告日別の新規陽性者数の日次データ(2020年3月下旬~2021年2月上旬)を対象に,主要な季節調整法であるX-12-ARIMAプログラムの一部プロセスを日次データでも適用できるように修正したものを利用し,新規陽性者数の変動を,トレンド,暦による変動(週単位の周期性および休日の影響),不規則変動(一時点の要因による変動)に分離することを試みた。
結果 季節調整法の応用により,トレンド,暦による変動,不規則変動の分離に成功した。新規陽性者数の変動は前日比で約15%内のトレンド,週単位の周期性の約-30%~10%の振れ,不規則変動による約15%の振れで構成されることが確認された。
結論 本分析で行った季節調整法の日次データへの応用は,報告日別の新規陽性者数のトレンドを早期かつ的確にとらえるための有力な手法になると考えられる。
キーワード 新型コロナウイルス感染症,COVID-19,新規陽性者数,変動分析,季節調整法,X-12-ARIMA
|
第68巻第11号 2021年9月 就寝時の「快眠音」が
中田 ゆかり(ナカダ ユカリ) 柴田 英治(シバタ エイジ) 角谷 寛(カドタニ ヒロシ) |
目的 本研究の目的は,不眠症の疑いのある労働者が就寝時に「快眠音」を聞くことにより,睡眠潜時(寝つくまでの時間)が短縮するのかを検証することである。
方法 研究デザインは,個々の研究対象者が「介入群(快眠音)」と「対照群(無音)」をもつランダム化比較試験とした。快眠音システムは音源内蔵スピーカー(ヤマハ社製ISX-80)とベッドマット下生体センサー(EMFIT社製EMFIT-QS)を用いた。日本企業4社の従業員1,185名を対象として事前にアテネ不眠尺度を用いてスクリーニングを行い,531名より回答を得た。不眠症の疑いのある6点以上の162名を抽出し,研究同意・データが得られた42名を対象に分析を行った。データ収集方法は,対象者が自宅に設置した快眠音システムを用いて就寝時にランダムに「快眠音」と「無音」を聞き,それぞれ平日5晩ずつ計10晩の睡眠潜時,睡眠時間,睡眠効率のデータを収集した。睡眠潜時のデータを主要評価項目とし,同様に睡眠時間および睡眠効率のデータを副次評価項目とした。分析方法は,「快眠音」と「無音」での対応のあるt検定を行った。
結果 睡眠潜時,睡眠時間,睡眠効率すべての評価項目において「快眠音」と「無音」で有意な差は認められなかった。
結論 「快眠音」は不眠症の疑いのある労働者に対する睡眠潜時の短縮効果は得られなかった。
キーワード 快眠,音,睡眠,労働者
|
第68巻第8号 2021年8月 大学病院本院群の類型分類と
中島 尚登(ナカジマ ヒサト) 矢野 耕也(ヤノ コウヤ) |
目的 大学病院本院群82施設の,診療件数とMajor Diagnostic Category(MDC)の疾患比率を用い,82施設の特徴と,機能評価係数Ⅱに影響する要因を検討した。
方法 調査項目をクラスター分析し,82大学病院をA~C群に分け,次にMDC比率をクラスター分析し,Ⅰ~Ⅵ群に分けた。そして,調査項目またはMDC比率の,主成分1・2の主成分負荷量と得点を用い,それぞれの群の特徴および機能評価係数Ⅱに影響する主成分を検討した。
結果 A群は,西日本の国公立の施設が多く,「放射線・化学療法-紹介」度と「産婦-筋骨格-新生児」度が高かった。B群は,東日本の国公立の施設が多く,「手術・全身麻酔-病床数-救急医療」度と「神経-新生児-乳房-循環器」度が低かった。C群は関東と近畿の私立の施設が多く,「手術・全麻-病床数-救急医療」度が高く,「放射線・化学療法-紹介」度と「産婦-筋骨格-新生児」度が低かった。機能評価係数Ⅱは,A群とC群は同等であるが,B群は低かった。Ⅰ群は国公立の施設が多く,「産婦-筋骨格-新生児」度が高かった。Ⅲ群は私立の施設であり,「放射線・化学療法-紹介」度と「産婦-筋骨格-新生児」度および「神経-新生児-乳房-循環器」度が低かった。Ⅴ群は「放射線・化学療法-紹介」度と「産婦-筋骨格-新生児」度が高く,「神経-新生児-乳房-循環器」度が低かった。Ⅵ群は「放射線・化学療法-紹介」度が低かった。そして,相関分析より「手術・全麻-病床数-救急医療」度と「神経-新生児-乳房-循環器」度が高い施設ほど,機能評価係数Ⅱが高かった。
結論 西日本・国公立の施設が多いA群は「放射線・化学療法-紹介」度が,関東・近畿の施設が多いC群は「手術・全麻-病床数-救急医療」度が高かった。そして「手術・全麻-病床数-救急医療」度と「神経-新生児-乳房-循環器」度が高いほど機能評価係数Ⅱが高い。
キーワード 大学病院本院群,機能評価係数Ⅱ,Diagnosis Procedure Combination(DPC)制度,クラスター分析,主成分分析
|
第68巻第8号 2021年8月 主任介護支援専門員が行う
青山 貴彦(アオヤマ タカヒコ) 岡田 進一(オカダ シンイチ) |
目的 本研究では,主任介護支援専門員が行うスーパービジョン実践活動とその構造を明らかにすることを目的とした。地域包括支援センターの主任介護支援専門員を調査対象として,スーパービジョン実践に関する「スーパーバイザーの実践活動(意識・態度・行動)」について,実践程度に着目した量的調査を行った。
方法 近畿地方2府5県に所在するすべての地域包括支援センター(830カ所)を対象に,郵送による横断的調査を実施した。回収率は34.3%で,欠損値のない212票の回答を使用して分析を行った。分析においては,まず,探索的因子分析を実施し,そして,因子モデルの構成概念妥当性については,共分散構造分析による確認的因子分析により確認を行った。また,抽出された因子の下位尺度得点を算出し,基本属性との関連を調べるため,相関分析を行った。
結果 分析の結果,「スーパービジョンの実施に関する認識の共有」「バイザー自身の自己コントロール・自己点検」「バイジーの実践力アセスメント」「基礎的な価値,知識,技術に関する助言・指導」「支持的な関わり」「利用者本人に関するより深い理解の促進」「柔軟な思考の促進」という7因子が抽出された。確認的因子分析を行い,構成概念妥当性について検討したところ,一定の適合を示した。また,いずれの基本属性に関しても,スーパービジョン実践活動との相関はみられなかった。
結論 抽出された7因子をもとに,スーパービジョン実践活動の構造について,双方向のコミュニケーションによる「スーパービジョンの実施に関する認識の共有」を基盤として,「バイジーの実践力アセスメント」を行い,バイジーの状況や到達度合等に応じて,「基礎的な価値,知識,技術に関する助言・指導」を行う。さらに,「利用者本人に関するより深い理解の促進」によって,表面的な理解に留まらないよう手助けしたり,「柔軟な思考の促進」によって,より本質的な支援が行えるよう手助けしたりする。実践過程全体を通じて,「支持的な関わり」を基本的態度として保ち続けるとともに,「バイザー自身の自己コントロール・自己点検」を行い,自分自身にも目を向け続けると整理した。
キーワード 主任介護支援専門員,スーパービジョン,実践活動,実践の手がかり
|
第68巻第8号 2021年8月 児童虐待相談件数の増加が児童相談所に及ぼす影響小村 有紀(コムラ ユキ) |
目的 近年,急速に児童虐待が増加しており,それに伴い児童相談所では,量的および質的に人員が不足していることが課題である。本研究の目的は,定量的な実証分析を行い,児童虐待相談件数の増加が,児童相談所に及ぼす影響を明らかにすることとした。
方法 分析対象は,児童福祉法において,児童相談所の設置が義務づけられている47都道府県とし,2015年度と2017年度の2期間によるパネルデータを構築した。児童虐待相談件数が児童相談所に及ぼす影響を分析するために,被説明変数には,児童相談所における未対応件数を採用した。また,児童相談所の専門性の程度を表す代理変数として,スーパーバイザー人数,児童相談所長の福祉職割合を採用し,被説明変数とした。
結果 被説明変数を児童相談所未対応件数とした場合の推計結果は,パネル・ポアソン回帰分析の場合,児童虐待相談件数,養護相談におけるその他の相談件数,視聴覚障害相談件数,重症心身障害相談件数,育児・しつけ相談件数の推定係数の符号はプラスとなり,1%水準で有意であった。また,結果の頑健性を調べるために,被説明変数および説明変数を同様に設定し,パネル・負の二項回帰分析により分析した結果,児童虐待相談件数の推定係数の符号はプラスとなり,5%水準で有意であった。さらに,被説明変数をスーパーバイザー人数および所長福祉職割合として,それぞれパネル・ポアソン回帰,トービット分析を行った。その結果,被説明変数をスーパーバイザー人数とした場合の推定結果は,児童虐待相談件数の推定係数の符号はプラスとなり,1%水準で有意であった。また,被説明変数を所長福祉職割合とした場合の推定結果は,児童虐待相談件数の推定係数の符号はプラスであり,10%水準で有意であった。
結論 推定結果を総合的に解釈すると,児童相談所は,近年急速に増加している虐待相談については,その経験が蓄積されておらず,技術の継承等がなされていないことから,虐待相談件数が増加すると,児童相談所における未対応件数が増加傾向となる。しかし,虐待相談件数が多い児童相談所においては,専門性が高いと考えられるスーパーバイザーを積極的に配置している。また,児童相談所長には,福祉等専門職による採用区分により採用されている者が多く起用されており,児童相談所における専門性の必要性を認識していることが推察される。
キーワード 児童虐待相談件数,児童相談所,専門性,スーパーバイザー,実証分析
|
第68巻第8号 2021年8月 0歳児が受けた予防接種と
|
目的 現在,わが国では感染症の重症化の回避,社会的な感染症防衛力を向上するために予防接種を推進している。予防接種を受けることは,小児期に限らず,生涯の課題でもあり,重要性が増している。本研究は,埼玉県内8市町の0歳児の予防接種の状況から,予防接種の推進のため対応を検討した。
方法 埼玉県で実施された「子どもの生活に関する調査(平成30年8月1日)」で得られた項目のうち,0歳児が受けた予防接種の種類,保護者の子どもに関する困りごと・相談の状況のカテゴリーを2群に分けχ2検定およびFisherの直接確率検定を行い,予防接種の接種群と未接種群に関連する内容を明らかにした。
結果 0歳児が受けた予防接種は,B型肝炎1,385人(92.6%),Hib感染症1,378人(92.2%),小児肺炎球菌感染症1,372人(91.8%),結核1,356人(90.7%)など約9割以上であり,日本脳炎は209人(13.9%)で少なかった。さらに予防接種の接種群と未接種群間で検討した結果,0歳児の保護者にとって「子どもの健康や発育に関する相談先の有無」(p=0.01)(Fisher),「離乳食で困っていることの有無」(p=0.02),保護者が「受診の必要性を感じていながら医療機関に連れて行かなかった経験の有無」(p=0.00),これら3項目が接種群と未接種群の2群に有意に関連した。
結論 埼玉県の8市町の予防接種の状況は,予防接種を受けた0歳児・保護者は約9割あった。一方,成長発達の著しい0歳児の育児であるため,保護者の困っている内容に対して,ニーズに即応しつつ対応方法を見いだせるよう相談機関や保健センターなどに結びつけることが重要である。また,居住地にかかりつけ小児科医師を得て,0歳児の体調に応じた健康管理を行い,予防接種を受けることがより重要になる。さらにワクチン接種について,接種スケジュールが滞る場合は,接種したワクチンの種類と回数の確認,接種に対して保護者の意向の確認を行うこと,予防接種の推進に向けて市町村予防接種担当部署や保健師につなぎ,個別的に解決する方向性を持ちながら保護者に対応することが必要だと考えられた。
キーワード 0歳児,保護者,予防接種の推進,保護者の困りごと・相談,母子保健,保健師
|
第68巻第8号 2021年8月 女子高校生の親準備性の
山田 晴奈(ヤマダ ハルナ) 斉藤 恵美子(サイトウ エミコ) |
目的 本研究は,女子高校生の親準備性と過去の乳幼児とのふれあい体験(以下,ふれあい体験)の実態を明らかにし,ふれあい体験の有無別に親準備性等を比較することを目的とした。
方法 都内の一女子高等学校に在籍している高校生1~3年生245人を対象として,無記名自記式質問紙調査を留置法で2016年10月に実施した。親準備性として「子ども・子育てに関する意識」7項目,「対子ども社会的自己効力感」10項目を設定した。また,学童期から現在までのふれあい体験を尋ね,体験の有無別に,親準備性,将来の育児支援についての考え,乳幼児および妊婦とかかわった際の対応等の項目を比較した。
結果 有効回答者234人(95.5%)を分析した結果,ふれあい体験ありは187人(79.9%)であった。時期では,小学生162人(86.6%),中学生123人(65.8%),高校生91人(48.7%)の順に多かった。ふれあい体験ありと回答した187名のうち,ふれあった乳幼児の年齢は1~3歳(111人,59.4%),きっかけは親戚(86人,46.0%)が最も多かった。親準備性の項目では,「子ども・子育てに関する意識」の平均得点は2.4点,「対子ども社会的自己効力感」の平均得点は2.8点であった。また,ふれあい体験あり群と体験なし群の比較として,ふれあい体験あり群は,「弟妹」(p=0.036),「年下の親戚」(p<0.001)がいると回答した割合が統計的に有意に高かった。また,ふれあい体験あり群は,「子ども・子育てに関する意識」の平均得点(p<0.001),「対子ども社会的自己効力感」の平均得点(p=0.006)が有意に高かった。さらに,ふれあい体験あり群は「赤ちゃんとふれあう教室に参加したい」(p=0.026)と回答した割合が有意に高かった。
結論 乳幼児とのふれあい体験があった女子高校生は,親準備性が高いことが示唆された。少子化に伴い,学童期から青年期の対象が,乳幼児の弟妹等の世話をする機会が減少傾向にあることから,青少年が乳幼児とふれあう機会を地域や学校で意図的に設定することは,地域で子育てを支える社会環境を醸成するだけでなく,青少年自身のその後の妊娠・出産・育児への支援にもつながると考える。
キーワード 女子高校生,親準備性,乳幼児ふれあい体験,少子化,地域
|
第68巻第8号 2021年8月 医師確保計画における
寺裏 寛之(テラウラ ヒロユキ) 小谷 和彦(コタニ カズヒコ) |
目的 日本の医師偏在対策の一つとして,都道府県は2020年度から医師確保計画を策定した。この計画では,医師確保に重点を置く地域として,各都道府県の二次医療圏よりも小さい単位で,局所的に医師が少ないとみなされる医師少数スポットが設定された。一方で,へき地を中心に無医地区は,医師確保策の一つとして以前から設定されている。医師少数スポットと無医地区の設定には,都道府県の実状や方針が反映される。本研究は,各都道府県の医師少数スポットの実態および無医地区との関係を観察した。
方法 各都道府県のホームページに公開されている医師確保計画の文書を収集し,医師少数スポットに関する記載を分析した。無医地区は平成26年度無医地区等調査結果を使用した。その面積は境界不明確な地区があり,地区の中心から半径4㎞の円の面積(50.3㎢)と一致すると仮定した。
結果 全都道府県の医師確保計画(47文書)が得られた。医師少数スポットを設定したのは26(55.3%)の都道府県であり,総数で313の医師少数スポットがあった。医師少数スポットの設定は市町村全域である場合が最多(103地域[32.9%])であった。都道府県の医師少数スポット数と無医地区数の中央値(四分位範囲)はそれぞれ15.0(10.0-25.0),20.0(14.0-38.0)で,医師少数スポット数の方が有意に小さかった(P<0.01)。医師少数スポットと無医地区とでは,地域の面積の中央値(四分位範囲)はそれぞれ69.0(44.4-189.5)㎢,50.3(50.3-50.3;無医地区の面積は一律と仮定した)㎢であり,医師少数スポットの方が有意に大きかった(P<0.01)。医師少数スポットと無医地区との重なりを分類したところ,両者が重複しない方が最多(245[78.3%])で,ほぼ重なって無医地区を包含する型が次いだ(43[13.7%])。
結論 医師少数スポットは,過半数の都道府県で設定され,その多くは無医地区を有さない市町村全域に設定されていた。無医地区と重複するような,都道府県独自の設定も認められた。
キーワード 医師少数スポット,医師確保,医師偏在,無医地区
|
第68巻第7号 2021年7月 高齢者のエンド・オブ・ライフに対する態度尺度の開発辻本 耐(ツジモト タイ) 川島 大輔(カワシマ ダイスケ) 田中 美帆(タナカ ミホ) |
目的 エンド・オブ・ライフ(EOL)の充実に向けた基礎研究として,高齢者のEOLに対する態度を測定するための尺度を作成し,その信頼性と妥当性について検討することを目的とした。
方法 終末期医療・介護・葬儀・お墓・自らの人生の記録などEOLに関する14項目を作成し,文章で意思表示している場合(Advanced Directives:AD)と身近な人と話し合っている場合(Advanced Care Planning:ACP)の2つに分けて回答を求めた。対象者は,2018年1月にシルバー人材センターに登録している高齢者の男女167名であった。最終的に,回答に不備のなかった156名を分析対象とした(有効回答率93%)。尺度の内的構造を確認するために探索的因子分析を実施し,Cronbachのα係数を算出することで信頼性の検討を行った。そして,死に対する態度尺度および対人関係欲求尺度に加え,書字習慣および死に関するコミュニケーション能力を測定するための項目を新たに作成し,EOL尺度との相関分析を行うことで基準関連妥当性の検討を行った。
結果 探索的因子分析の結果から,ADにおいて「死後の儀礼と手続きおよびケアの希望」と「人生の意味」の2因子構造,ACPにおいて「死後の儀礼と手続き」と「人生の意味」,そして「ケアの希望」の3因子構造が確認された。信頼性の検討を行ったところ,各下位尺度のα係数は0.81~0.89であり,基準関連妥当性のために行った外的基準との相関分析では,弱から中程度(-0.16~-0.27,0.16~0.34)の有意な相関係数が認められた。
結論 EOLに対する態度尺度は,ADで2つの下位尺度,ACPで3つの下位尺度から構成され,十分な信頼性と一定の妥当性が確認された。この開発された尺度によって,わが国の高齢者のEOLへの態度の実態をより明らかにすることができると考えられる。
キーワード EOL(エンド・オブ・ライフ),高齢者,死,準備,態度,意思表示
|
第68巻第7号 2021年7月 虐待ハイリスク家庭に対する
|
目的 本研究の目的は,虐待の恐れがある家庭に対して,保育士がその発生予防や養育の改善に向けた機能発揮を促進する要因を明らかにすることにある。子ども虐待対策において保育所の機能が注目される中,子ども虐待予防や早期介入のために保育所における発見・共有・連携の促進に向けた課題を明らかにすることには,大きな意義がある。
方法 調査票は調査協力関係を結んだA市児童福祉担当課を介して,A市内16の公立保育所に勤務する保育士を対象としたアンケート調査を実施した。配票数は300とし,調査対象の地域特性に偏りが生じないよう各地域の利用児童数に基づいて配票数をあん分した。調査票の回収数は210ですべてを有効票として集計した。回収率は70.0%である。調査期間は2019年11月6日から12月20日であった。
結果 保育士が子ども虐待に早期対応ができていると評価することに影響するものは,1点目に保育士自身の従業上の地位や勤務環境である。2点目に虐待対応のマニュアルや発達に課題のある子どもへの対応マニュアルの整備,ヒヤリハット対応の仕組み,研修機会の確保など,ハイリスク家庭への支援について組織的なマネジメント体制である。3点目に保護者への対応について同僚や上司に相談しやすいことや保育士ひとりに責任を押しつけないスーパーバイズの体制整備である。
結論 虐待の恐れがある家庭に対して,保育士が子ども虐待の発生予防や養育の改善を促進するには,保護者のモニタリング機能や支援機能が発揮されることが重要である。そのためには,経験年数の長い非正規雇用の保育士や経験年数の少ない正規雇用の保育士がともに保育所内での認識共有や無理や不安なく要支援世帯とかかわれるよう支援環境の整備が必要と言える。加えて管理職のみならず全保育士へ要保護児童対策地域協議会をはじめとする他機関連携の促進について早急な対応が求められる。
キーワード 虐待,保育士,連携,保護者支援,要保護児童対策地域協議会,マネジメント
|
第68巻第7号 2021年7月 山梨県における救急搬送患者の
小林 克也(コバヤシ カツヤ) 大岡 忠生(オオオカ タダオ) 山縣 然太朗(ヤマガタ ゼンタロウ) |
目的 山梨県の救急医療体制における搬送先の選定時間に関わる要因を明らかにし,救急車内収容から病院決定までを短縮し救命率の向上に寄与することを目的とした。
方法 研究デザインは観察研究であり,研究対象は2018年4月1日から2019年3月31日までで山梨県内の消防本部に登録された救急搬送傷病者データ25,361例のうち,欠損値を除外した15,180例を集計対象とした。さらに,そのデータを用いて救急搬送時において搬送先医療機関の決定のための連絡開始から搬送先医療機関の決定までにかかる時間に関連する要因に関して,単回帰・重回帰それぞれの分析を用いて解析した。
結果 集計調査からは,覚知(傷病者発生を認知した)月,年齢分類,事故種別,疾患分類,傷病程度,Cardiopulmonary arrest(心肺停止)(以下,CPA)判定において,分類ごとに平均搬送先医療機関の決定時間の差が認められた。また,重回帰分析においても,季節,事故種別,疾病分類,傷病程度において有意差が認められた。曜日,平日と土日・祝日と連絡時間帯において,搬送先決定にかかる時間に差はなかった。
結論 山梨県における救急搬送時の搬送先医療機関の決定時間は,季節や傷病・事故の種類による違いは見られたが,時間帯や平日,土日・祝日とで明らかな差は認められなかった。今後,意識の有無やかかりつけ病院の有無などの因子を考慮した検討や患者の転帰との関連についてはさらなる検討が必要である。
キーワード 救急搬送,搬送時間,救急医療体制,搬送先医療機関の決定時間
|
第68巻第7号 2021年7月 食べる速さとBMIに関するメタ分析橋本 泰央(ハシモト ヤスヒロ) 小玉 麻由佳(コダマ マユカ)上田 由喜子(ウエダ ユキコ) 小塩 真司(オシオ アツシ) |
目的 食べる速さによるBMIの平均値差,およびその年齢による違いをメタ分析によって明らかにすることを目的とした。
方法 医中誌,Medlineから検索式「(食べる速さor食事速度or早食いor摂食速度)and(肥満or BMI)」「(eating rate or eating speed or eating rapidly or eating quickly or eating slowly or eating fast(NOT fasting))and(Odds of(overweight or obesity)or body mass index)」にて1,265本の論文を収集した。そこから①大学紀要などを除く査読付き論文で原著論文,②日本語または英語で書かれている,③健常者を対象としている,④食べる速さの尺度が速い,普通,遅いに分かれている,⑤食べる速さと肥満の関係がBMIまたはオッズ比で報告され,⑥過体重が成人ではBMI25,子どもは国際肥満タスクフォースで定められたカットオフ値で定義されている,⑦文献間でデータが重複していない25件(38研究)を分析対象とした。効果量には標準化されたBMIの平均値差を用い,変量モデルを採用した。効果量の異質性はQ統計量およびI2で計測し,対象者の年齢,性別,国籍ごとにサブグループ分析を行った。Egger法を用いて公表バイアスの有無を検定し,failsafe Nとtrim and fill法を用いて分析結果の頑健性を検討した。
結果 食べる速さが速い群と普通群の比較(38件)では速い群は普通群よりも有意にBMIが高く,年齢で分けても,さらに性別で分けて検討しても同様の結果であった。食べる速さが遅い群と普通群の比較(35件)では遅い群は普通群よりも有意にBMIが低かった。この傾向は年齢で分けても,さらに性別で分けて検討しても同様の結果であった。また,いずれの比較においても子どもの方が大人よりも効果量が大きかった。研究全体の異質性はどちらの比較においても高かった。公表バイアスが結果に及ぼす影響はいずれも小さいと考えられた。
結論 食べる速さが普通の群に比べ,速い群はBMIが高く,遅い群は低かった。群間のBMIの平均値差は子どもの方が大人よりも大きいことが示唆された。
キーワード 食べる速さ,BMI,メタ分析,効果量,肥満,やせ
|
第68巻第7号 2021年7月 高齢の大腿骨骨折患者への支援に関する一考察-患者の性別に着目した医療ソーシャルワーカーの支援の特徴-畑 香理(ハタ カオリ) |
目的 大腿骨骨折患者への指導や支援等に関する先行研究は医学的な観点から行われることが多く,ソーシャルワーカーによる退院前後の生活支援に着目した研究はほとんどみられない。そこで本研究では,医療ソーシャルワーカー(以下,MSW)による大腿骨骨折患者への支援内容を分析し,退院後の在宅生活を支える方法を明らかにしていきたい。また,先行研究では日常生活における活動や役割において性別による違いが認められていることから,本研究では患者の在宅復帰を支援する際に,性別による日常生活上の活動や役割の違いが支援の内容や量に影響を与えるかどうかについても検討していきたい。
方法 全国の回復期リハビリテーション病棟を有する医療施設で,2018年8~9月にかけて当該病棟を担当しているMSWを対象者とした。質問紙にて,①調査対象者の属性,②これまでに担当した大腿骨骨折患者のうち高齢入院患者の状況,③大腿骨骨折の高齢入院患者への支援内容,④業務全体の実施状況について質問を行った。調査票は1,181カ所の医療施設へ郵送し,有効回答の339名を分析対象とした。
結果 大腿骨骨折患者の支援では,高齢男性患者よりも高齢女性患者に対し,以下の項目がより多く行われていた。具体的に「家事全般(炊事・洗濯・掃除等)」「屋外活動(散歩・買い物や受診時の移送・庭仕事等)」「受傷前の家事役割維持」に関するサービスや支援の導入・調整,「再転倒の不安・恐怖の訴え」「家庭内で担っていた役割を果たせないもどかしさや情けなさ,同居家族への気遣いや気兼ね」「痛みや疲労感の訴え」などを傾聴し受けとめる,「生活の中で楽しみ・趣味活動を見つける手助け」「社会活動参加(近隣住民や町内会との交わり)の維持」に関する支援である。一方,患者の性別によって支援状況の違いが見られなかった主な項目は,社会資源や制度に関する情報提供や活用の仲介等があった。
結論 大腿骨骨折患者に対してMSWが行う支援の量は,患者の性別によって異なることが明らかになった。さらに,患者の性別の違いによって支援に差が生じる背景として,患者が入手するソーシャル・サポートの違いが関係していると考えられる。MSWは,これまで入手できていたソーシャル・サポートが骨折のため入手しづらくなった高齢女性患者に対し,その代替となるサービス導入・調整やさらなる充実という視点で支援を行っていると考えられる。
キーワード 大腿骨骨折,高齢患者,医療ソーシャルワーカー,性別,ソーシャル・サポート
|
第68巻第7号 2021年7月 労働者のインターネット依存とマインドフルネスとの関連廣江 陸(ヒロエ リク) 榊原 文(サカキハラ アヤ) |
目的 インターネット(以下,ネット)の普及と一般化は,人々のライフスタイルに多くの変化をもたらした。その一方で,ネット使用を制御できず,人間関係や社会生活に悪影響をもたらすネット依存が問題視されている。労働者がこのようなネット依存状態になると,ネットに夢中になるあまり仕事に集中できず,生産性や効率の低下,ヒューマンエラーや事故の原因になることが考えられる。そこで本研究は,「今この瞬間に生じている出来事や経験そのものに気づきながら注意をとどめること」を示すマインドフルネスに焦点を当て,労働者のネット依存とマインドフルネスとの関連について明らかにすることを目的とした。
方法 2019年8~9月,島根県内のA製造業事業所の全従業員530名を対象に,無記名自記式質問紙調査を行った。調査内容は,年齢,性別,勤務年数,生活習慣,精神状態,ネット依存度,マインドフルネスである。ネット依存度は,Young’s Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction score(YDQ)の8項目を使用し,5点以上をネット依存と判定した。マインドフルネスは,Mindful Attention Awareness Scale(MAAS)の15項目を使用した。MAASの90パーセンタイル値である10点でカットオフし,10点以上をマインドフルネス低下と判定した。マインドフルネスを従属変数,ネット依存を独立変数とし,単変数ロジスティック回帰分析を行い,その後,朝食の欠食,睡眠時間,夜勤,気分の落ち込みを共変量として投入し,多変量ロジスティック回帰分析を行った。
結果 有効回収数(率)は384(72.5%)であった。MAASの平均点は5.32点,10点以上は54名(14.1%)であった。YDQの平均点は1.37点,5点以上は23名(6.0%)であった。多変量ロジスティック回帰分析の結果,ネット依存とマインドフルネスとの間に有意な関連を認めた。ネット依存の従業員がそうでない従業員と比べてマインドフルネスが低下する調整オッズ比は,6.72(95%CI:2.53-17.89)であった。
結論 ネット依存の従業員はそうでない従業員と比較して有意にマインドフルネスが低下していることが示唆された。ネット依存の場合,ネットに夢中になるあまり,ネット以外のことに無気力,無関心になることがマインドフルネスの低下につながると推察される。
キーワード インターネット依存,労働者,マインドフルネス,産業保健,労働災害,事故
|
第68巻第6号 2021年6月 難聴者の福祉と生活の質の評価に関する先行研究メタ分析坂本 秀樹(サカモト ヒデキ) 永松 陽明(ナガマツ アキラ) 安川 文朗(ヤスカワ フミアキ) |
目的 これまで難聴者の社会的機能や活動の機会がどのように捉えられ,福祉や生活の質との関係性においてどのような研究がなされてきたのか,国内外で発表された先行研究のレビューを行った。また,これに加えてテキストマイニングの手法を用い,より具体的に難聴者福祉に対する研究の潮流を示した。
方法 難聴の人々の生活の質や社会的機会との関係や影響,また社会モデル的視点からの議論がどの程度深められてきたのかを知るため,1990年から2019年の間に発表された難聴福祉に関する文献を対象にレビューを実施した。また,難聴福祉の理論と生活の質に関する研究の動向を理解するため,レビュー対象とした論文に対し,先行研究の中ではどのような語彙が用いられ,それぞれの関係性がどのように構成されているかを検証し,研究の関心がどの分野に所在するのか明らかにすることを目的として,日本語論文と英語論文それぞれを対象にテキストマイニングによる共起ネットワーク分析を行った。
結果 難聴と生活の質,あるいは福祉に関する日本と海外の先行研究調査の結果,難聴者福祉の視点からの福祉改善に関する研究は発見出来なかった。また,生活の質を測定するICECAP-Oなどの質問項目により難聴者のQOLを測定する試みがなされているが,それらが示す結果は一貫していない。日本語論文4編の共起ネットワーク分析の結果,対象とする文章数は2,048件であり,対象語彙数は1,615件であった。生成した共起ネットワークを見ると,難聴高齢者の生活やそのレベルをどう捉えるか,難聴が社会的ネットワークにどう影響するかに関する論議が中心となっていた。同様に,英語論文13編の文章数は2,304件であり,対象語彙数は5,415件であった。描かれた共起ネットワークによると,“hearing”,“loss”など直接難聴を示す語だけでなく,“health”と“capability”,“quality of life”,“social”など,社会生活を営む上での難聴者と周囲のかかわりに関する語が頻出していた。
結論 今回の分析により,難聴者福祉に関する研究において,日本と海外の潮流は異なることが示された。また,日本国内における難聴者福祉の研究に着目すると,難聴者の生活の質改善に関する論議は充分であるとはいえず,難聴者の視点に立ってその福祉を議論するためには,難聴当事者が必要としている支援や施策についての理解を深め,改善の指標としての生活の質を測定する手法も併せて検討することが必要である。
キーワード 難聴者福祉,生活の質,評価,共起ネットワーク,テキストマイニング,メタ分析
|
第68巻第6号 2021年6月 発達障害児の避難時における
中井 寿雄(ナカイ ヒサオ) 加賀野井 聖二(カガノイ セイジ) |
目的 発達障害児の障害特性および災害時の支援の必要性と,避難時における固有空間の必要性との関連を明らかにすることである。
方法 小児リハビリテーションを実施しているA病院に通院し,機能訓練を受けている(2018年1月)発達障害児の養護者56人を対象とした。調査方法は,訓練を担当している理学療法士2人に,聞き取り調査を依頼した。調査内容は,発達障害児の属性,主病名,必要な医療処置,投薬の有無,障害特性,避難時の支援の必要性等だった。分析は,避難時の固有空間の必要性と各項目との関連について,χ2検定もしくはFisher直接確率検定を実施した。避難時の固有空間の必要性を従属変数とし,大声をあげるへの支援,聴覚過敏への支援,共変量に年代,性別,主病名を強制投入し二項ロジスティック回帰分析を実施した。
結果 障害特性は,目が離せない32人(57.1%),大声をあげる26人(46.4%),偏食25人(44.6%),聴覚過敏20人(35.7%)等で,避難時に支援を必要としていたのは,目が離せないへの支援27人(48.2%),大声をあげる24人(42.9%),偏食21人(37.5%),聴覚過敏19人(33.9%)等だった。避難時の固有空間が必要であることに対して,大声をあげるへの支援が必要であることが関連している傾向(オッズ比(OR):4.32,95%信頼区間(CI):0.96-19.44)があり,聴覚過敏への支援が必要であることが有意に関連(OR 7.61,95%CI:1.23-47.11)していた。
結論 養護者は,固有空間であれば刺激を軽減し大声を防止できる可能性があること,聴覚過敏からの混乱による他者への迷惑を養護者が危惧している可能性が示唆された。
キーワード 発達障害児,災害,避難時の固有空間,聴覚過敏
|
第68巻第6号 2021年6月 中堅前期・後期保健師の職務満足感に関連する要因の検討玉井 公子(タマイ キミコ) 星野 明子(ホシノ アキコ)志澤 美保(シザワ ミホ) 桂 敏樹(カツラ トシキ) |
目的 地域保健活動の中核を担う役割を期待される中堅前期・後期保健師(経験年数4~20年目)を対象に,職務満足感に影響を及ぼす要因を明らかにすることを目的とした。
方法 近畿圏の自治体に勤務する経験年数4年目以降の保健師を対象に,自記式質問紙調査(属性および職場特性,対人支援能力,地域支援および管理能力,自己効力感,自尊感情,職務満足感)を実施した。分析方法は,中堅前期(4~10年目)と中堅後期(11~20年目)の2群にわけて,それぞれ記述統計,2変数間関連分析(相関係数),および職務満足感を従属変数とした重回帰分析による要因分析を行った。
結果 調査票送付数986人のうち回収490人(回収率49.7%),有効回答数は473人(有効回答率48.0%)であった。回答者のうち,中堅前期(4~10年目)117人,中堅後期(11~20年目)109人を分析対象とした。単変量解析の結果,中堅後期は中堅前期に比較して職務満足感,専門職務遂行能力の対人支援能力,地域支援および管理能力のいずれも有意に高かったが,自己効力感,自尊感情は両群に有意差は認められなかった。職務満足感を従属変数として重回帰分析を行った結果,中堅前期はモデルとなる先輩保健師の存在(β=0.349),自尊感情(β=0.298),家庭訪問活動の有無(β=0.267)などが,中堅後期では組織横断的な保健師連携会議の有無(β=0.241),相談できる先輩や同僚がいる(β=0.210),専門職務遂行能力の対人支援能力(β=0.183)などが職務満足感を高めた。
結論 中堅期の前期と後期では,保健師の職務満足感に影響する要因が異なるため,その特徴を捉えた配置と職場における個別性を考慮した人材育成の検討が必要であると考える。中堅前期はモデルとなる先輩の存在が得られ,家庭訪問活動が実施できる部署への配置が望ましいと考える。一方で中堅後期は,専門職務遂行能力の対人支援能力が発揮でき,保健師連携会議や相談のできる先輩・同僚の存在など,チームで仕事を進める職場環境の充実が重要であると考える。
キーワード 中堅前期・後期保健師,職務満足感,専門職務遂行能力,自尊感情,自己効力感
|
第68巻第6号 2021年6月 公立小学校教員の不眠症に関する業務時間分析-公立小学校・中学校等教員勤務実態調査研究より-堀 大介(ホリ ダイスケ) 青木 栄一(アオキ エイイチ) 神林 寿幸(カンバヤシ トシユキ)クリスティーナ・シルビア・アンドレア 高橋 司(タカハシ ツカサ) 白木 渚(シラキ ナギサ) 池田 朝彦(イケダ トモヒコ) 池田 有(イケダ ユウ) 道喜 将太郎(ドウキ ショウタロウ) 大井 雄一(オオイ ユウイチ) 松崎 一葉(マツザキ イチヨウ) 笹原 信一朗(ササハラ シンイチロウ) |
目的 わが国の公立小学校の教員は睡眠を犠牲にして働かなければならないほどに多忙である。多様な業務を担っていることがその一因であり,業務の明確化・適正化が課題である。これまでの研究で,総労働時間が不眠症と関連することが示されてきた。しかし,具体的にどの業務に費やされる時間が不眠と関連するかまでは十分に明らかにされてこなかった。本稿ではどの業務が不眠のリスク因子となりうるのかを所要時間の長さおよび発生時間に着目した解析を行うことで明らかにし,業務の所要時間の削減のための手段について検討することを目的とした。
方法 平成28年に実施された公立小学校・中学校等教員勤務実態調査のデータを二次利用した。同調査は全国の代表的な公立小中学校教員を対象に実施された大規模横断調査であり,無記名の自記式質問紙,および26種の業務を含む業務記録表が用いられた。回答者は月曜日から日曜日までの連続する7日間,どの業務に従事したかを30分単位で記録した。各業務に費やされた時間は四分位でカテゴリ化し,上位7種の業務を解析に含めた。学級担任を受け持つ60歳未満の公立小学校教諭のデータを解析対象にした。アテネ不眠尺度の点数が6点以上の者を不眠群,6点未満の者を健常群と定義した。各業務に掛けられた時間と不眠症との関連を,χ2検定および二項ロジスティック回帰分析を用いて検証した。
結果 3,674名(女性62.7%,平均年齢38.3±10.9歳)のデータが解析対象となり,41.3%が不眠群に分類された。授業準備の時間が最も短かった者と比較して,最も長かった者の不眠に対する調整オッズ比は1.54(95%信頼区間1.23-1.92)であり,統計学的に有意な正の関連を認めた。他の業務では統計学的に有意な関連を認めなかった。さらに,不眠群は健常群と比較し平日時間外に統計学的に有意に多くの時間,業務に従事していた。
結論 公立小学校教員の不眠症は,授業準備の所要時間,および平日時間外の業務の発生時間と関連を認めた。授業準備の時間を短縮するための対策について論考した。
キーワード アテネ不眠尺度,学級担任,教員,業務記録,長時間労働,時間外労働
|
第68巻第6号 2021年6月 大学を拠点とした産後支援プログラムの実践と評価-対象者背景による評価の相違-小嶋 奈都子(コジマ ナツコ) 朝澤 恭子(アサザワ キョウコ)平出 美栄子(ヒラデ ミエコ) 加藤 知子(カトウ トモコ) |
目的 育児中の母親に対して産後うつ病を防止する重要性が提唱されており,研究者らは大学を拠点とした継続的産後支援に取り組んでいる。本研究の目的は,乳児を育児中の母親に対する産後支援プログラムの実践を評価し,対象者の属性による評価の相違を明らかにした。
方法 実践内容はベビーマッサージ,母親へのアロマトリートメント,母乳相談,育児相談,座談会であった。対象者は乳児を育児中の母親であり,1回2時間の開催で,これまでの6回の催行において6~12組/回の母子の参加があった。実践後評価のために無記名自記式調査票で回答を得た。調査期間は2019年4月から2020年2月であった。調査内容は属性,参加目的,現在の悩み,実践に対するアウトカム評価およびプロセス評価であった。分析は記述統計量を算出し,属性による群間比較を単変量解析を用いて行った。
結果 育児中の母親63名に配布し,有効回答である58部を評価対象とした(回収率92.0%)。参加者は子どもが1人いる母親が58.6%であり,年齢は30~34歳の37.9%,乳児の月齢は5カ月の22.4%が最多であった。アウトカム評価は,リラックスできた100%,コミュニケーション増加93.1%,疑問解決82.7%,悩み軽減79.3%,育児仲間ができた75.9%であった。参加者の母親への満足度は8項目すべてにおいて高く,とても満足と回答した割合は,ベビーマッサージ96.6%,アロマトリートメント91.4%,交流89.7%であった。初産婦は経産婦に比べて離乳食の悩み,乳児の病気の悩みが多く,紹介による参加が少なかった。年齢の高い母親はコミュニケーション達成度が高く,乳児の月齢が高い母親はプログラムの時間配分に満足していた。
結論 産後支援プログラムは母親にとってリラックス感と満足度が高く,有用な実践であることが明らかになった。今後の課題は,参加者範囲と実践回数を拡大し,継続的な催行でプログラムを積み重ね評価すること,年齢の若い母親たちがコミュニケーションを取りやすいように配慮すること,低月齢の児を持つ母親たちのニーズに合った参加時間の対応をすることである。
キーワード 産後ケア,母親,プログラム開発,ピアサポート,産後支援プログラム
|
第68巻第6号 2021年6月 医療系学部の未成年非喫煙学生における
薬司 理紗(ヤクシ リサ) 小林 沙妃(コバヤシ サキ) |
目的 近年,急速に普及する新型タバコは,若年非喫煙者の喫煙へのゲートウェイとなる可能性が懸念されているものの,新型タバコの使用防止策について検討した研究は限定的である。本研究では,医療系学部の未成年非喫煙学生の新型タバコに対する意識を調査し,紙巻タバコに対する意識との差異を検討することにより,未成年非喫煙学生に対する効果的な新型タバコ対策の示唆を得ることを目的とした。
方法 研究デザインは単施設における横断研究である。A大学医療系学部1~2年次生の非喫煙学生224名をリクルートし,2018年8月に無記名自記式質問紙調査を行った。調査内容は,基本属性(5項目),心理的ストレス反応(18項目),新型タバコと紙巻タバコに対する意識(知識:6項目,肯定的な認識:6項目,否定的な認識:4項目,周囲の環境:4項目の計20項目)とした。基本属性による変数間の関連にはFisherの正確確率検定を,新型タバコと紙巻タバコに対する意識の各得点の比較にはWilcoxonの符号付順位和検定を用いた。
結果 分析対象は未成年非喫煙学生113名(有効回答率50.4%)であった。全対象者では,「タバコは使用者の身体に害があると思う」などの知識に関する6項目,「タバコの使用者に不快感を持つ」などの否定的な認識に関する4項目,「タバコの入手方法を知っている」の周囲の環境に関する1項目の得点について,新型タバコの方が紙巻タバコよりも有意に低かった。性別による比較分析の結果,女子学生では「タバコは肌荒れの原因になると思う」などの知識に関する6項目の得点について,新型タバコの方が紙巻タバコよりも有意に低かったが,男子学生では有意な差は認められなかった。
結論 本研究の分析対象者においては,新型タバコは紙巻タバコに比べて,1)タバコによる健康への影響は小さい,2)タバコそのものや使用者に対する嫌悪感・不快感を抱きにくい,3)やけどの危険性が低い,4)経済的な負担が軽い,と受け止められていた。これらの結果には新型タバコに関する正しい知識や情報が不十分であることが影響していると推察され,今後は未成年非喫煙学生に対して,エビデンスに基づく新型タバコの正しい情報の発信と普及の必要性が示唆された。また,性差による得点の差異が認められたことから,関心の寄せ方などの性差に配慮した新型タバコに関する情報の発信方法を検討する必要があると考える。
キーワード 未成年,大学生,非喫煙者,新型タバコ,紙巻タバコ,意識
|
第68巻第5号 2021年5月 家庭内ケアと健診未受診との関連:国民生活基礎調査より鈴木 有佳 (スズキ ユカ) 本庄 かおり(ホンジョウ カオリ) |
目的 子育てと介護の両方を行うダブルケアを含む家庭内ケアを担う者の数が増加している。ダブルケアは家庭内ケア提供者に多くのニーズによる負担を与え,家庭内ケア提供者の健康診断(健診)受診を阻害する可能性がある。しかし先行研究では,家庭内ケアの組み合わせによる家庭内ケアの種類と健診未受診の関連については検討されていない。そこで本研究では,2013年国民生活基礎調査データを用い,家庭内ケアの種類と健診未受診の関連について検討を行った。
方法 2013年国民生活基礎調査データを用い,40-59歳の婚姻経験のある女性71,065名を対象とし,解析を行った。家庭内ケアの種類(ケアなし,子育てのみ,介護のみ,ダブルケア)による過去1年間の健診未受診のオッズ比(odds ratio:OR)をロジスティック回帰分析により推定し,さらに就業の有無によるサブグループ解析を実施した。
結果 子育てのみ群,介護のみ群,ダブルケア群の基本属性と社会経済的要因を調整した健診未受診のORは,ケアなし群と比較し,それぞれ1.09(95% CI:1.05-1.14),1.07(95% CI:0.99-1.16),1.49(95% CI:1.31-1.69)だった。ダブルケア群では子育てと介護の両方を行うことにより,健診未受診の追加リスクが生じていた。また,就業の有無によるサブグループ解析の結果,子育てと健診未受診の関連は就業の有無で異なったが,介護ならびにダブルケアと未受診の関連は就業の有無で変わらなかった。
結論 本研究は子育て,特にダブルケアを担う女性は,健診未受診割合が高いことを明らかにした。子育てやダブルケアを行う女性は,自身の健康管理についての優先順位が低い可能性や,健診受診に際して子どもやケアが必要な家族の預け先を見つけることが難しかった可能性が考えられる。健診実施率向上のためには未受診者の家庭内ケアの状況を把握し,それに対応した支援を実施することの必要性が示唆された。
キーワード ダブルケア,介護,子育て,家庭内ケア,特定健診,未受診
|
第68巻第5号 2021年5月 離島・へき地における終末期ケアの現状と多職種連携馬場 保子(ババ ヤスコ) 横山 加奈(ヨコヤマ カナ) 今村 嘉子(イマムラ ヨシコ)赤水 れみ子(アカミズ レミコ) 坂本 雅俊(サカモト マサトシ) |
目的 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう,終末期の過ごし方について比較的元気なうちから家族や多職種で共有することが必要である。人口規模や地域特性,在宅療養支援を行う職種によって,終末期ケアの実施状況や多職種連携行動が異なるかを明らかにした。
方法 調査対象は,東京都,愛知県,長崎県の1,013カ所2,026名(医師400名,訪問看護師426名,保健師400名,社会福祉士400名,介護支援専門員400名)に自記式質問紙調査を行い,調査期間は2019年8月~9月末とし郵送法にて回収した。調査内容は,基本属性の他に,担当地域の人口区分・地域区分,終末期ケアの実施状況,終末期ケアシステムの現状,在宅での看取りを困難にする要因,多職種連携行動尺度であった。『離島・へき地』『離島・へき地ではない』の2群間でマンホイットニーU検定を用いて比較し,多職種連携行動尺度の各因子について平均値を算出し,人口区分,職種でクロス集計を行い,全体の得点平均値を比較し傾向を把握した。
結果 対象者の505名から回答が得られた。終末期ケアの実施状況について,医師,訪問看護師の9割以上は実践経験があった。社会福祉士は終末期ケアの実践経験がある割合は低いが,患者の終末期の過ごし方に対する思いを知る機会は,介護支援専門員や保健師よりも高かった。終末期ケアシステムは,『離島・へき地』のほうが有意に整っていなかった。在宅での看取りを困難にする要因は,マンパワー不足,地理的に訪問困難な地域が多い,病院スタッフに在宅移行の視点がない等であった。在宅での看取りの困難さは,人口5万人未満と5万人以上の地域で境界があり,人口が少ないほうが困難であった。しかし,人口5千人未満の『離島・へき地』では,マンパワー不足や24時間の支援体制構築は困難であるが,医師の在宅での看取りの関心が高く,病院スタッフに在宅移行の視点が高く,医師の多職種連携行動が高いという特徴があった。
結論 離島やへき地で最期まで過ごすためには,地域の医療資源の活用だけでは限界がある。『離島・へき地』の医師が,在宅での看取りへの関心が高いことや多職種連携行動が高いことを活かすだけでなく,地域の強みを活かした疾病予防,介護予防に着目してアプローチすることが必要である。地域のニーズを把握している専門職は,地域住民に対して,比較的元気なうちから“人生の最後をどう過ごしたいか”意思決定支援を行うことなどのアドバンスケアプランニングを推進していくことが望ましい。
キーワード 離島・へき地,終末期ケア,看取り,多職種連携,地域の強み
|
第68巻第5号 2021年5月 就労継続支援事業所を利用する
小長谷 陽子(コナガヤ ヨウコ) 齊藤 千晶(サイトウ チアキ) |
目的 若年性認知症の平均発症年齢は働き盛りの51.3歳であり,発症によって休職や退職を余儀なくされると,本人・家族への影響だけでなく,有能な人材が失われるなどの社会的な影響も大きい。著者らは,現役で働く若年性認知症の人が退職した後の就労先として障害者施設が多いことをすでに報告した。今回は,すべての都道府県に若年性認知症支援コーディネーターが配置された時点で,就労継続支援事業所における若年性認知症の人の受け入れ実態と受け入れ・利用中・退所等に関して,事業所内での工夫や課題,外部の支援者との連携状況について詳細に把握することとした。
方法 全国の就労継続支援事業所A型・B型および就労移行支援事業所に調査票を郵送した。一次調査で該当者ありの事業所に二次調査票を郵送した。調査項目は運営主体,受け入れている若年性認知症の人数,性別,年齢,診断名,発症時期,診断時期,開始からの利用期間,日常生活自立度,認知症の程度,外部の支援者の利用,介護保険申請の有無,若年性認知症支援コーディネーターとの連携の有無等である。
結果 調査時に受け入れている,あるいは以前に受け入れていた若年性認知症の人のうち,詳細が判明した302人の状況について分析した。男性が約7割であった。利用開始年齢は,A型事業所では男性は55~59歳が多く,女性は50~54歳と60~64歳が多かった。B型事業所では男女とも60~64歳が最も多く,就労移行支援事業所では男性は55~59歳,女性は40~49歳が最も多かった。診断名では,いずれの事業所でも「アルツハイマー病」が最も多く約半数であった。利用開始から平均の利用期間は,全体では35.9カ月であった。(Ⅲa)以上の介護が必要な人は,利用開始時には35人であったが調査時には76人であった。外部の支援者の利用は,作業内容に関しては,いずれの事業所でも「あり」は4割以下で,支援者の内訳では「相談支援事業所」が最も多かった。認知症の症状に関する外部支援者の利用は,「あり」が半数以上であり,支援者の内訳では「利用者の主治医」が最も多く,次いで「若年性認知症支援コーディネーター」が多かった。
結論 就労継続支援事業所における若年性認知症の人の受け入れはまだ多くはなかったが,受け入れている事業所では様々な工夫がされており,外部の専門職との連携もみられた。今後は障害者だけでなく難病や認知症など様々な障害を持つ人に開かれた事業所が増えるよう,さらなる支援が必要である。
キーワード 若年性認知症,就労継続支援事業所,就労継続,外部の支援者,若年性認知症支援コーディネーター
|
第68巻第5号 2021年5月 就労継続支援B型事業所における
前原 和明(マエバラ カズアキ) 後藤 由紀子(ゴトウ ユキコ) 八重田 淳(ヤエダ ジュン) |
目的 就労継続支援B型事業所における農業を用いた就労支援の質的向上を図るため,本研究では園芸療法の観点から農業を用いた就労支援の有用性について明らかにすることを目的とした。
方法 秋田県に所在する全119の就労継続支援B型事業所に対して,2020年1月10日~2月20日の期間で郵送調査を実施した。調査票は,基本情報,園芸療法のプログラム評価表に基づいて作成した支援効果達成チェックリストと支援に対する考え方の質問項目から構成される。回答のあった60事業所のデータを分析に用いた。支援効果達成チェックリストへの回答について探索的因子分析を実施した。また,各因子の下位項目の平均得点を用いてクラスタ分析を実施した。クラスタ分析によって分類されたクラスタ間の支援に対する考え方について分散分析と多重比較を実施した。
結果 探索的因子分析を行った結果,「安心感」と「交流の場」の2因子構造が明らかになった。次に,この2因子を用いてクラスタ分析を行い,就労継続支援B型事業所を「居場所提供」「安心感提供」「提供未達成」の3つのクラスタに分類した。群間で支援に対する考え方を比較し,「利用者の希望や可能性を追求するための支援」と「他の支援機関との連携や支援制度の活用」の項目に認識の差がみられた。
結論 園芸療法の観点から就労継続支援B型事業所は,「安心感」と「交流の場」の2つの支援機能を持つことが明らかになった。そして,各事業所は支援機能に基づき「居場所提供」「安心感提供」「提供未達成」の3群に分類できた。特に,3群間は利用者の主体性の尊重と他機関との関わりについての支援に対する考え方で差があった。各群は安心感や居場所の提供に関する達成度と課題改善の認識状況から説明できると考えられた。以上より,就労継続支援B型事業所利用者の自己実現を図るための手段として,支援機能と支援に対する考え方に基づいて,どのように就労支援に農業を取り入れていくかが今後の課題であり,本研究の視点はそのための1つの視点となると結論づけた。
キーワード 農業,農福連携,就労継続支援B型事業所,園芸療法,就労支援,支援プログラム
|
第68巻第5号 2021年5月 児童発達支援ガイドラインが推奨する
植田 紀美子(ウエダ キミコ) |
目的 2017年に厚生労働省により児童発達支援ガイドライン(以下,ガイドライン)が制定され,児童発達支援の質の向上に向けた取り組みが望まれている。ガイドライン制定直前における,ガイドラインが推奨する発達支援内容の取組状況の実態を明らかにすることを目的とした。
方法 全国の児童発達支援および医療型児童発達支援を行うすべての施設4,030カ所(2015年4月時点)に対して,記名式自記式質問票を用いた郵送調査法による実態調査を行った。調査内容は,発達支援内容,発達支援を提供する際の配慮などである。記述統計を行い,各項目について「積極的に取り組んでいる」割合が障害種別によって差があるかを統計学的に比較した。
結果 利用契約児の主たる障害状況に関して回答のあった836施設を解析対象とした。重症心身障害がある子ども(重心児)が主として利用する施設が90施設,肢体不自由がある子ども(肢体不自由児)が主として利用する施設が42施設,知的障害がある子ども(知的障害児)が主として利用する施設が324施設,発達障害がある子ども(発達障害児)が主として利用する施設が372施設,難聴がある子ども(難聴児)が主として利用する施設が8施設であった。重心児が主として利用する施設では,「健康状態を把握するための支援」「日々変化する健康状態に適切に対応するための支援」「生活リズム獲得のための支援」「感覚遊び」「歌遊び」に積極的に取り組んでいた。肢体不自由児や知的障害児が主として利用する施設では,「清潔,食事,着脱,排泄など生活習慣に関する支援」に積極的に取り組んでいた。発達障害児が主として利用する施設では,「友達との関わりを重視した支援」「役割を与えた活動の提供」「代替のコミュニケーションを用いた支援」に積極的に取り組んでいた。「地域社会との連携」を積極的に取り組む施設は少なかった。
結論 ガイドライン制定直前の児童発達支援センター等において,ガイドラインが推奨する発達支援内容の取組状況の実態を明らかにした。今後,ガイドラインの普及状況をモニタリングする上で重要と考える。各施設が積極的に取り組んでいる課題や配慮は,障害種別を反映した結果になっていた。子どもの成長や発達を促すためには,障害特性や発達過程に応じた支援の提供が重要であり,児の成長・発達に応じて,支援内容を定期的に見直すことが必要である。
キーワード 児童発達支援ガイドライン,障害児,発達支援,児童発達支援センター,実態調査
|
第68巻第5号 2021年5月 経済開発協力機構(OECD)諸国の一般病院と
|
目的 日本の一般病院はサービス提供形態が未分化であり,他のOECD諸国の一般病院と同様に急性期ケアを提供する病院群(急性期病院群)以外にも,異なるサービスを提供している病院の類型(療養型施設群,外来型施設群,ケアミックス病院群)があるといわれている。しかし,類型化されることならびに各類型の特徴は十分に検討されていない。本研究では,探索的に日本の一般病院がサービス提供形態別に4類型に分けられることを検討し,分けられた急性期病院群とOECD諸国の一般病院の特徴を比較して類似性や差異を検討した。
方法 2014年医療施設調査・病院報告の個票データを使用して,日本の一般病院のサービス提供における投入と産出等の違いを示す9指標を抽出し,Two Stepクラスター分析を用いて分け,サービス形態の特徴を基に4類型とクラスターを結びつけた。そして,急性期病院群とOECD諸国の一般病院の指標を比較し,差異を検討した。
結果 クラスター分析の結果,4類型に分けられ,急性期病院群は全病院の約2割,ケアミックス病院群は約3割,外来型施設群は約3割,療養型施設群は約2割であった。急性期病院群は,多くの急性期の入院サービスを提供し,日本の一般病院全体よりもOECD諸国の一般病院に近い特徴を有するものの,外来患者の割合が高く,資本集約的で平均在院日数が長い。また,ケアミックス病院群は,亜急性期・療養・外来サービスを,療養型施設群は急性期病床においても療養サービスを,外来型施設群は多くの外来サービスを,提供していた。
結論 日本は,1980年代より,病院機能分化施策を進めてきたが,急性期病院以外の病院が多く,機能分化が進むべき余地がいまだに大きいと考えられる。地域医療構想における「地域完結型」の医療の実現には,2025年の将来推計における急性期と慢性期病床の過剰と回復期病床の不足の是正が必要である。日本の急性期病院群における急性期病床数はOECD平均なみであることから,急性期病床は,急性期病院群における削減よりも外来型施設群における削減(有床診療所への転換や回復期や慢性期のサービス提供への転換)が必要である。また,療養型施設群における療養病床の削減(介護施設への転換や回復期から慢性期のサービス強化)が必要である。
キーワード 医療施設調査・病院報告,OECD保健統計,一般病院,急性期病院,機能分化,地域医療構想
|
第68巻第4号 2021年4月 加熱式たばこに関する
仲下 祐美子(ナカシタ ユミコ) |
目的 近年わが国では,加熱式たばこが急速に流行している。本研究の目的は,国内のソーシャルメディアに投稿された加熱式たばこに関する質問の分析により,加熱式たばこや禁煙に対する疑問や懸念を明らかにし,加熱式たばこの流行に対応すべき公衆衛生上の課題を検討することである。
方法 データ収集のソーシャルメディアはYahoo!知恵袋を用い,キーワードは「加熱式たばこ」「新型たばこ」「無煙たばこ」などとした。質問投稿日は,わが国での加熱式たばこ販売開始直後の2014年1月1日から2019年12月31日の6年間とした。分析対象は751件とし,テキストマイニング法による分析を行った。
結果 質問投稿数は2016年以降に増加がみられ,質問投稿者は約4割が加熱式たばこを現在使用しており,約1割は家族や周囲の者が加熱式たばこを現在使用している者,1割弱は投稿者が加熱式たばこを使用希望していた。加熱式たばこ使用希望の中には,紙巻たばこの過去喫煙者や非喫煙者からの投稿もあった。質問文の頻出上位語は「アイコス」「吸う」「たばこ」であり,投稿者が加熱式たばこ使用群では「禁煙」「症状」「悪い」「喉」「体」などが頻出語であり,質問内容は加熱式たばこ使用による体調変化,加熱式たばこの健康影響,加熱式たばこ製品,禁煙に関することであった。家族や周囲の者が加熱式たばこ使用群では受動喫煙の害に関すること,加熱式たばこ使用希望群では加熱式たばこの健康影響に関する質問内容が多かった。「禁煙」に関連する特徴語分析では「アイコス」「思う」「喫煙」の語のほか,投稿者が加熱式たばこ使用群では「変える」「害」「健康」,家族や周囲の者が加熱式たばこ使用群では「悪い」「健康被害」「子ども」,加熱式たばこ使用希望群では「検査」「治療」「病院」などが関連語であった。
結論 分析の結果,加熱式たばこの健康被害や健康影響,受動喫煙の害に関する疑問や懸念が多く,健康影響が解明されるまでは,加熱式たばこが安全ではないことや受動喫煙により健康被害の可能性があることを情報提供する必要性が示された。一方,加熱式たばこ使用への関心は,紙巻たばこの過去喫煙者や非喫煙者にもみられたことから,禁煙者に再喫煙させない,非喫煙者には手を出させないようにする必要性が示唆された。禁煙に関しては,加熱式たばこをやめる方法や紙巻・加熱式たばこ併用者から禁煙方法について意見を求めているものがみられ,たばこの多様化が進む中で効果的な禁煙促進の検討が重要な課題である。
キーワード 加熱式たばこ,禁煙,ソーシャルメディア,内容分析,健康影響,情報提供
|
第68巻第4号 2021年4月 市町村保健師の平時における防災意識-災害時活動の経験との関連-川口 桂嗣(カワグチ ケイジ) 伊藤 俊弘(イトウ トシヒロ) |
目的 本研究は,市町村保健師の平時における防災意識を明らかにし,これらと災害時活動の経験との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 対象者の基本属性,災害時活動の経験の質問項目,災害対策に関する公共資料等を参考に「災害に対する考え」「災害対応力」「組織活動状況」「援助者としての知識経験」の各構成要素からなる「保健師の防災意識」に関する質問項目による調査票を作成し,北海道内の市町村保健師に配布・回収した。
結果 調査票を配布した1,343名のうち549名から回答が得られ(回収率40.9%),データに欠損のない495名(有効回答率36.9%)を対象に分析を行った。各構成要素に因子分析を行い,これらに信頼性・妥当性の分析を繰り返して因子を調整した結果,「災害に対する考え」8項目3因子,「災害対応力」7項目2因子,「組織活動状況」7項目2因子の各下位尺度が得られた。これらの因子に対する災害時活動の経験および災害による被害の影響を検討した結果,災害時活動の経験は7因子中6因子に関連を認めたが,災害による被害は1因子にのみ関連を示し,防災意識には災害時活動の経験が強く影響することが示された。
結論 北海道の市町村保健師の平時における防災意識は,災害時活動の経験との間に強い関連が示された。今後は,本質問項目をさらに検討し明らかにしていく必要はあるが,防災意識を明らかにすることによって保健師の災害教育等に活用され,保健師の災害に対する意識の向上に有用な指標となり得ることが期待される。
キーワード 市町村保健師,災害,防災意識,保健師教育
|
第68巻第4号 2021年4月 人口減少と高齢化が進む中山間地域在住高齢者における
李 錦純(リ クンスン) 山本 大祐(ヤマモト ダイスケ) 真鍋 雅史(マナベ マサシ) |
目的 人口減少と高齢化が進む中山間地域在住高齢者における訪問看護に対する認知度を把握し,関連する項目について明らかにすることで,在宅医療人材不足が深刻な地域における,訪問看護の適正利用の促進と在宅ケア体制の整備に向けて,訪問看護に対する住民ニーズを探索する上での基礎資料とすることを目的とした。
方法 中山間地域であるA県北部の二次医療圏B地域の5市町在住の65歳以上の元気~虚弱高齢者を対象に,無記名自記式質問紙調査を実施した。質問項目は,訪問看護の認知度に関する項目(名称・サービス内容・サービス内容別認知度),基本属性,介護保険サービス利用に関する項目,健康要因に関する項目,社会関係要因に関する項目とした。訪問看護のサービス内容認知度と各項目との単変量解析およびロジスティック回帰分析により関連する項目について分析した。
結果 578件の有効回答のうち(有効回答率60.0%),訪問看護の名称は526人(91.0%)が認知していたが,サービス内容については375名(64.9%)の認知度であった。内容別では,「療養上の世話」(73.0%),「病状の観察」(64.0%)の順に認知度が高い反面,「精神障がい者の看護」(19.9%)と「ターミナルケア」(27.2%)の認知度が低かった。訪問看護サービス内容認知度の有無を従属変数としたロジスティック回帰分析では,訪問リハビリテーションの認知度と,別居家族・親族とのソーシャルサポートが有意に影響していた。
結論 訪問看護サービスの内容別の認知度に差があり,認知度が低いながら社会的要請が高い精神障がい者やターミナルケアに対する訪問看護の意義と,地域住民へもたらす価値をいかに可視化し伝えていくかが課題として示された。訪問看護のサービス内容認知度には訪問リハビリテーションの認知度と別居家族・親族のソーシャルサポートが影響しており,背景として,訪問リハビリテーションを普及促進している地域医療体制の後押しによる住民ニーズの高まりと,地元を離れた別居家族の介護参加のあり方の一端がうかがえた。訪問看護サービスの具体的な内容の認知度向上により,地域住民の潜在ニーズの発掘と適正利用につながることから,リハビリテーション専門職とのさらなる連携強化と,別居家族・親族による介護体制の特徴を加味した情報発信上の工夫が必要である。
キーワード 中山間地域,過疎地域,高齢者,訪問看護,認知度,情報発信
|
第68巻第4号 2021年4月 非行領域における家族支援内容と連携の実態-連携対象・連携方法・評価方法・プログラムとの関連-大原 天青(オオハラ タカハル) 萩生田 伸子(ハギウダ ノブコ)笠松 将成(カサマツ マサナリ) 笠松 聡子(カサマツ サトコ) |
目的 重篤な非行や行動上の問題を示し家庭外に措置される子どもの多くは,養育者との葛藤や逆境的体験などがあり,子どもと家族の双方に働きかけることが重要であるとされる。本研究では児童自立支援施設に焦点をあて,次の3点を明らかにする。まず,非行領域における家族支援の内容について整理し,次にそれらの支援内容と連携対象,連携方法,家族支援の評価方法との関連を明らかにする。最後に既存のプログラムとの関連を示し,非行領域における家族支援の実態と今後必要とされることを考察した。
方法 全国の児童自立支援施設58施設に勤務する子どもや家族の支援を担う職員を対象に家族支援に関する調査への協力依頼を行った(2019年11月~2020年2月)。本研究の分析対象は,直接日常生活を支援する職員による回答436部とした。分析は,家族支援に関する支援内容30項目について因子分析を行い,次に抽出された因子と関連する要因を明らかにするため,連携対象,連携方法,家族支援の評価方法,プログラムとの相関分析を行った。
結果 非行領域における家族支援に関する支援内容の因子分析の結果,4因子が抽出された。第1因子は『子どもの状態像の共有』,第2因子は『家庭復帰までのプランニングと共有』,第3因子は『養育に関する振り返りと共有』,第4因子は『過去の出来事の整理と共有』と命名した。次にこれらの支援内容と連携対象との関連を分析したところ,母親,父親,児童福祉司,原籍校,進学・就職先,児童心理司,児童養護施設,心理士等との関連が明らかになった。また連携方法では,電話,個別協議,関係者会議が活用されていた。次に家族支援に関する評価方法では,面接による評価や振り返り,ワークシートが活用されていた。しかし,既存のプログラムとの関連は弱い相関であった。
結論 本研究によって,非行領域における家族支援の内容として4つの因子が抽出され,連携対象,連携方法,評価方法,プログラムとの関連が明らかになった。これらの結果から,非行領域における家族支援に必要とされる4つの働きかけを含む,家族支援プログラムの開発や活用,普及が必要であることを示唆した。
キーワード 非行少年,家族支援内容,連携,児童自立支援施設,家族合同ミーティング
|
第68巻第4号 2021年4月 健康保険組合における被扶養者向け特定保健指導事業の
|
目的 健康保険組合(以下,健保組合)では被扶養者における特定保健指導実施率向上が一つの事業課題となっている。本研究では保健事業のどのような実施方法・実施体制(以下,プロセス・ストラクチャー)が,特定保健指導実施率や指導による健康課題の解決に有意に関連しているのか,定量的に検証することを目的とした。
方法 「データヘルス・ポータルサイト」(以下,ポータルサイト)に蓄積された平成30年度の保健事業の実績データ(アウトプット指標・アウトカム指標の目標達成度)および保健事業のプロセス・ストラクチャーに関するデータを用いた。各プロセス・ストラクチャーの実施で,被扶養者向け特定保健指導のアウトプット指標・アウトカム指標の目標達成度が有意に異なるか検証した。
結果 被扶養者向け特定保健指導事業であり,かつアウトプット指標が「特定保健指導実施率(%)」に相当する内容で実施された事業は,計172事業(160組合で実施)であった。172事業のうち,プロセスでは「専門職による対面での健診結果の説明」,ストラクチャーでは「専門職と連携(産業医・産業保健師を除く)」の実施の有無によって,アウトプット指標・アウトカム指標の目標達成度が双方とも有意に異なっており(有意水準10%未満,ウィルコクソンの順位和検定で検証),各プロセス・ストラクチャーを実施している事業ではアウトプット指標・アウトカム指標の目標達成度が有意に高かった。また健保組合の属性(形態,扶養率,加入者数,被扶養者における特定健診実施率)も考慮してアウトプット指標の目標達成度に各プロセス・ストラクチャーが影響を及ぼしているか,重回帰分析によって検証した。健保組合の属性を考慮しても,「専門職による対面での健診結果の説明」を実施している事業のほうがアウトプット指標の目標達成度が有意に高かった(偏回帰係数=0.26,p値=0.05,自由度調整済み決定係数=0.01)。
結論 「専門職との連携」と「対面で本人の健診結果を説明する」という要素を組み合わせることで,被扶養者向け特定保健指導事業の効果的な実施につながる可能性が高い。今後もポータルサイトのようなシステムおよびそこに蓄積された大規模データを活用し,医療保険者の保健事業を効果的なものにするプロセス・ストラクチャーを定量的に検証していくことが必要である。
キーワード 被扶養者,特定保健指導,プロセス・ストラクチャー,専門職,データヘルス
|
第68巻第3号 2021年3月 高齢者の社会参加に関する研究
亀井 美登里(カメイ ミドリ) 本橋 千恵美(モトハシ チエミ) 太田 晶子(オオタ アキコ) |
目的 本研究は,高齢者を含む地域住民の社会参加の意欲や参加実態,住民の持つ専門資格,生活状況,地域への愛着等を把握・分析する。地域包括ケアシステムの構築を進めていく際の重要な社会関係資本としての地域住民の自助,互助,支え合いの可能性とそのあり方を検討する際の有効な基礎資料として役立てることを目的とする。
方法 A市と埼玉医科大学との協働で,A市B地区に在住する30歳以上の全住民1,419人(施設入所者等を除く)を対象とし,2019年11月に,郵送による自記式質問票調査を実施した。質問票の項目は,対象者の基本的属性,専門資格の保有状況,生活状況,地域支援活動の参加意向,地域への愛着等である。
結果 調査票送付数1,419人,回収数543人(回収率38.3%),除外例107人,有効回答数436人(30.7%)であった。地域における高齢者の支援に関する活動に参加意向のある者は全体で255人(58.5%)であった。地域支援活動への参加のきっかけは,男女ともに「知人・友人の誘い」「市などの講習・講座への参加」と答えた者が多く,男では「自治会等を通じての参加募集」が多かった。地域支援活動の参加に期待できることは,「地域や人の役に立つことができる」が最も多く,次いで「地域に知り合いや友達ができる」「自分の健康づくり・介護予防になる」をあげる者が多かった。
結論 A市B地区における地域支援活動参加意向の実態や参加を推進するための重要な因子が明らかになった。今後,地域包括ケアシステムの構築に向けて,地域の前期高齢者等が高齢者を支える地域の担い手として,また行政は地域の活動を促す互助の橋渡しをする立場として機能することで,地域の社会関係資本になり得ることが示唆された。A市の関係する行政計画等に反映されることで,地域包括ケアシステムを補完することが期待される。
キーワード 超高齢社会,地域包括ケアシステム,Social Capital(社会関係資本),地域支援活動,担い手,互助
|
第68巻第3号 2021年3月 地域在住高齢者に対する
飯坂 真司(イイザカ シンジ) 小板橋 恵美子(コイタバシ エミコ) 河村 秋(カワムラ アキ) |
目的 近年,日常の買い物が困難になる食料品アクセス低下が地域在住高齢者の社会問題となっている。この問題には,個人の身体要因,地理的環境,社会的要因が複合的に関与する。本研究の目的は,地域在住高齢者の食料品アクセスの状況を包括的に測定するための自記式尺度の開発と構成概念妥当性・基準関連妥当性の検証とした。
方法 文献レビューをもとに32項目4件法の尺度原案を作成した。首都圏の2政令市3地区の地域活動に参加する60歳以上の主に自立から要支援段階の住民を対象に,自記式質問紙による横断調査を実施した。探索的(最尤法,プロマックス回転)および確認的因子分析を用いて尺度の構成概念妥当性を検証した。また,基本属性,食・栄養関連指標,食料品店からの距離指標に対する基準関連妥当性を検証した。
結果 303名(平均年齢74.3歳,女性217名)を分析した。探索的因子分析の結果,固有値1以上の解釈可能な5因子構造とし,因子負荷量0.35以上の23項目を抽出した。5つの下位因子は「買い物自立度」6項目,「買い物しやすい環境」5項目,「食料品入手の社会的動機」6項目,「食生活面のサポート」3項目,「食生活の経済的余裕」3項目となった。内的整合性を示すCronbachのα係数は,第5因子0.57であったが,第1~4因子0.68~0.82であった。確認的因子分析による適合度は十分であった(GFI=0.902,AGFI=0.879,CFI=0.912,RMSEA=0.049)。基準関連妥当性では,「買い物自立度」は75歳以上,介護保険認定あり,運動器リスクのある者で低く,「食料品入手の社会的動機」は75歳未満,男性で低く,「食生活面のサポート」は独居世帯,介護保険認定ありの者で低く,「食生活の経済的余裕」は視覚障害ありの者で低かった(いずれもP<0.05)。また,「買い物しやすい環境」は,食料品店から500m圏にある居住地域の面積割合と有意な正の相関を示した(ρ=0.20,P=0.001)。
結論 地域在住高齢者に対して,「買い物自立度」「買い物しやすい環境」「食料品入手の社会的動機」「食生活面のサポート」「食生活の経済的余裕」の5因子23項目から構成される包括的食料品アクセス評価尺度を開発した。本尺度により,5つの視点から高齢者本人の食料品アクセスの状況を捉えることができ,個々人の適切な支援につながる。
キーワード 尺度開発,食料品アクセス,買い物,低栄養,介護予防,地域在住高齢者
|
第68巻第3号 2021年3月 地域在住高齢者における軽度尿失禁に関する相談意向小島 みさお(コジマ ミサオ) 東畠 弘子(ヒガシハタ ヒロコ) |
目的 本研究の目的は,不意に少量漏れてしまう軽度尿失禁を有する地域在住高齢者の実態,対応および相談意向について明らかにすることである。
方法 2018年6月~2019年3月に全国9都道府県33会場の健康づくりと排尿に関する地域の健康講座等に参加した地域在住高齢者のうち,要介護認定を受けていない60歳以上を対象とした。解析対象は482人(男性98人,女性384人)とした。調査方法は,自記式質問紙法により,基本属性,尿失禁経験の有無,現在の尿失禁の対応方法,今後の相談意向,尿失禁専用パッドの認知および使用経験,尿失禁用商品を販売するドラッグストアの利用頻度等について回答を得た。
結果 尿失禁経験率は全体で69.9%,男性58.3%,女性73.0%であった。尿失禁専用パッドの認知率は全体で87.4%,男性76.0%,女性90.3%で,尿失禁の対応は「特に何もしていない」が最多であった。男女で対応に差がみられ,男性は「特に何もしていない」割合が女性より多かった。女性は「尿失禁専用パッドを使用」「生理用ナプキンを使用」が男性よりも多かった。尿失禁についての相談意向ありは65.1%であった。尿失禁経験なしの者にも60.6%の相談意向がみられた。尿失禁経験者における尿失禁についての相談意向の影響要因についてロジスティック回帰分析を行った結果,性別に有意差は認めず,「ドラッグストア利用頻度」(オッズ比2.10,95%信頼区間:1.11-3.97)のみに有意差が認められた。
結論 地域在住高齢者自身が,状態像に合わせた尿失禁の具体的な対応方法や用品の選択と使用について知識を豊かにすることが必要であることが示唆された。地域生活の持続可能性を高めるために,尿失禁用商品を販売するドラッグストアも含め,地域で状態像に合わせた,個別の相談対応先の体制整備が重要である。併せて相談意向がない尿失禁経験者のスクリーニング体制の整備も重要と考える。
キーワード 尿失禁,地域在住高齢者,相談,意向,尿失禁専用パッド,個別支援
|
第68巻第3号 2021年3月 地域在宅居住高齢者における13年間生存日数を
星 旦二(ホシ タンジ) 栗盛 須雅子(クリモリ スガコ) 児玉 小百合(コダマ サユリ) |
目的 研究目的は,地域在宅居住高齢者における,夫婦年間収入額と生存日数との関連とともに一定の生存維持のための夫婦年間収入閾値額を明確にすることである。
方法 調査対象地域は九州中央に位置する自治体である。地域在宅居住高齢者を対象とし,1999年2月5日までの自記式質問紙を封書にて回収できた高齢者5,320人(回収率89.2%)が基盤調査である。転居者と65歳未満と85歳以上1,212人を除く,4,108人(男性1,806人,女性2,302人)を2011年8月31日まで最大4,670日間追跡し,その間の死亡日を自治体住民基本台帳で確認した。夫婦年間収入額別にみた生存日数との関連性と閾値を解析する方法では,一元配置分散分析を用いた。
結果 夫婦年間収入額が多くなる高齢者ほど生存日数が有意に維持される傾向が示された。一定の生存日数を維持するための夫婦年間収入閾値額は,性別を問わず年間200万円以上300万円未満であった。
結論 一定の生存日数を維持するための夫婦年間収入閾値額は,性別を問わず年間200万円以上300万円未満であった。詳細な収入状況を把握し,生存維持に関連する他の要因も含めて,他の地域と他の世代でも明確にするとともに,その因果構造を明確にすることが研究課題である。
キーワード 夫婦年間収入閾値額,生存日数,地域在宅居住高齢者,家庭間収入格差
|
第68巻第3号 2021年3月 地域密着型介護老人福祉施設における
山中 克夫(ヤマナカ カツオ) 小松崎 麻緒(コマツザキ ナオ) 登藤 直弥(トウドウ ナオヤ) |
目的 本研究は多くの地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)に設置されている地域交流スペースの活用の実態を明らかにすることを目的とした。
方法 関東内の全地域密着型特養312施設を対象に郵送法による質問紙調査(平成29年7月~9月)を行い,返送された157件のうち完全無回答を除く155件を分析対象とした(有効回答率49.7%)。
結果 地域交流スペースを設置している施設は全体の72.9%であったが,十分活用していると回答した施設は12.9%であった。また,活用施設の利用回数(年間換算)の中央値は48回であり,分布は少ない方に偏っていた。活用使途の第1位は「入居者の交流を中心とした活動」(72.0%)であり,第2位は「施設の職員が参加する研修会や会議」(69.0%)であった。利用回数を目的変数とした重回帰分析では,併設・隣接の施設の種類(特別養護老人ホーム他)と活用使途の種類(介護予防,自治会の活動,地域のサークル活動や地域交流,入居者の交流)がプラスに影響し,立地(市)と他事業総数がマイナスに影響していた。独自な取り組みに関する自由回答では,子ども食堂をはじめ多くの例が挙げられた。活用促進のための周知方法では,「自治会や民生委員を通じて」(43.0%)が最も多く,次いで「特に何もしていない」(33.0%)が多かった。活用に関する意見(自由回答)では,特に利用回数が多い施設から,管理・運営上の問題(費用など)が指摘された。また,「あまり活用していない」「活用していない」と回答した施設に理由を尋ねたところ,「利用してくれる人がいない」が最も多く(63.6%),次いで「普段の業務が忙しく余裕がない」(61.4%)が多かった。
結論 地域交流スペースは全体の約4分の3の施設に設置されていたが,全体的に利用回数が少なく,活用使途は施設内の活動が多く,地域に向けた活用が少ない実態が明らかにされた。活用していない理由からは,職員の忙しさ等から施設だけで活用を推進していくことには限界があり,また施設の立地や地域交流スペースの構造等を踏まえた活用が重要であると思われた。地域交流スペースは今後介護予防・生活支援の拠点他で活用が期待されるが,そのためには地域密着型サービス連絡会などを介して組織的に運営の指針を検討したり,実際の運営に関しても生活支援コーディネーターをはじめ外部連携が必要であると考えられた。
キーワード 地域密着型サービス,地域交流スペース,地域密着型介護老人福祉施設,地域支援事業,生活支援体制整備
|
第68巻第3号 2021年3月 地域在住高齢者における社会参加割合変化-JAGES6年間の繰り返し横断研究-渡邉 良太(ワタナベ リョウタ) 辻 大士(ツジ タイシ) 井手 一茂(イデ カズシゲ)林 尊弘(ハヤシ タカヒロ) 斎藤 民(サイトウ タミ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) |
目的 高齢者を対象に就労やグループ活動などの社会参加の推進が進められているが,社会参加割合の内訳を詳細に検討した研究は少ない。本研究の目的は性,年齢階層別に社会参加割合の変化を記述し,その特徴を明らかにすることである。
方法 日本老年学的評価研究(JAGES)の2010~11年度(以下,2010年)および2016年の2時点データを用いた繰り返し横断研究である。要介護認定を受けていない地域在住65歳以上高齢者を対象に郵送自記式質問紙調査を実施した。分析対象は2時点ともに悉皆調査を行った同一の10市町在住の日常生活動作が自立した男性9,567名,女性8,870名(2010年),男性10,038名,女性9,627名(2016年)とした。社会参加の定義は就労やグループ活動(ボランティアの会・スポーツの会・趣味の会)参加の有無とし,就労あり,またはグループ活動いずれか1つでも月1回以上参加で参加ありとした。2時点の参加割合を性・年齢階層別(5歳階層ごと)に記述し,χ2検定で2時点の割合を比較した。また,就労,グループ活動それぞれでも同様の分析を行った。
結果 2010年から2016年にかけて社会参加者割合は,男性で58.1%(5,557名)から61.5%(6,176名),女性で55.1%(4,891名)から62.1%(5,982名)といずれも増加を示した。年齢階層別でも全年齢階層で増加を示した(男性0.7~8.5ポイント,女性2.7~11.8ポイント増加)。内訳をみると就労割合は男女ともに65~69歳で特に増加を示した(6.6~9.0ポイント)。一方,グループ活動参加割合は約6年間で男性の65~74歳は2.1~9.0ポイント減少し,75歳以上で4.9~7.0ポイント増加,女性の65~69歳で1.3ポイント減少し,70歳以上で3.3~11.5ポイント増加していた。また,最もグループ活動参加している年齢階層は2010年で男性70~74歳,女性65~69歳に対し,2016年で男性75~79歳,女性70~74歳とより高年齢化していた。
結論 全国10市町の2010~16年の6年間における社会参加割合の変化を検討した。社会参加割合はすべての年齢階層で増加を示した。内訳をみると就労割合は65~79歳でより大きく増加し,グループ活動参加割合は後期高齢者でより大きく増加を示した。また,最もグループ活動参加している年齢階層が6年間で高年齢化していた。今後も高齢者の若返り,環境整備が進むことで就労割合は増加するとともに,グループ活動参加割合が高い年齢階層がより高年齢化する可能性がある。
キーワード ポピュレーションアプローチ,介護予防,就労,グループ活動,経年変化
|
第68巻第2号 2021年2月 医療系大学の双方向型授業における
山本 隆敏(ヤマモト タカトシ) 田邊 香野(タナベ カノ) 登尾 一平(ノボルオ イッペイ) |
目的 大学教育における実習や演習などの双方向型授業はインフルエンザ感染集団発生のリスクとなることが考えられるが,感染拡大防止を目的とした授業停止の有用性についてはあまり論じられていない。本研究では,季節性インフルエンザ発生増加に伴い双方向型授業のみを停止する機会を得たことから,その感染拡大防止への効果を検証した。
方法 医療系K大学A学科2年次113名を対象に,2018/2019年シーズンのインフルエンザ感染症による出席停止者数を双方向型授業停止前後で約2週間モニタリングした。さらに全員に対してインフルエンザ感染の有無,インフルエンザワクチン接種の有無,感染時の症状,インフルエンザ感染への意識の計4項目のアンケート調査を行った。また,双方向型授業停止の実施時期の妥当性を検証するために過去のデータから基準値を設定し,分析した。
結果 調査対象集団のインフルエンザ感染による出席停止者数は経時的に増加し,出席停止者の割合が15%を超えた時点(113名中18名)で,6日間の双方向型授業のみの停止を実施した(一方向型授業は継続)。その結果,双方向型授業停止解除後の観察期間中の出席停止者の割合は1.8%(113名中2名)まで減少し,対象集団内の流行は収束した。アンケートは111名から回答が得られ(回答率98.2%),すべて有効回答であった。対象集団全体のインフルエンザワクチンを接種した割合は94.6%(111名中105名)と極めて高く,感染した割合は19.0%(111名中21名)であった。インフルエンザ感染者に限っても90.5%(21名中19名)はワクチンを接種していた。感染者の症状では発熱が最も多く(21名中19名),36.9℃以下から40.0℃以上と最高体温は幅広く分布していた。次に,今回行った双方向型授業のみの停止時期が妥当であったか検証したところ,今回の授業停止開始時には既にこの基準値を超えていたことが判明した。
結論 学内でのインフルエンザ感染拡大防止には,双方向型授業のみを感染拡大早期に停止することが効果的であることが明らかとなった。また,ワクチンを接種した割合は極めて高いが,ワクチンの効果に対する知識が乏しいことが明らかとなった。今後は,ワクチン効果の限界について学生への啓発が重要であると考えられた。
キーワード インフルエンザ,ワクチン接種,一方向型授業,双方向型授業,感染拡大防止
|
第68巻第2号 2021年2月 高齢者における熱中症予防行動と
萱場(木村) 桃子(カヤバ モモコ) 近藤 正英(コンドウ マサヒデ) 本田 靖(ホンダ ヤスシ) |
目的 高齢者における熱中症予防行動の実態を明らかにし,さらにシール型温度計の配布が高齢者の熱中症予防における意識や行動を変容させるか評価することを目的とした。
方法 2013年7月に埼玉県A市の住民基本台帳から無作為抽出した65歳以上の高齢者2,124名に郵送で質問票を送付し,2012年夏季の熱中症予防行動について尋ねた。介入群(1,018名)にはシール型温度計を同封した。9月に同様の質問票を送付し,2012年と2013年の熱中症予防行動の比較,また,シール型温度計配布による介入効果を検討した。
結果 有効回答数は989名(有効回答率46.6%)であった。対象者は65-84歳(平均年齢72.5±4.9歳)の男性433名(43.8%),女性556名(56.2%)であった。2012年と2013年の行動を比較すると,エアコン使用時間,エアコン使用開始温度,エアコン設定温度,室温測定で差が認められた。飲水行動については,「喉が渇かなくても時々/定期的に水をよく飲むようにした」との回答が95%以上を占めており,2012年と2013年に差は認められなかった。シール型温度計を配布した介入群では対照群に比べ,2013年のエアコン使用開始室温「暑いと感じたら」,エアコン設定温度「一定の設定温度で決めていない」との回答が少なかった。また,対照群(62.1%)に比べ,介入群では2013年に温度計を「よく見る」と回答した人が75.1%と多かった。
結論 高齢者の熱中症予防行動の実態が明らかになった。シール型温度計配布による介入は高齢者の室温に対する意識を変化させる可能性が示唆された。安価で大量に作成および配布することが可能であるため,大規模集団における熱中症予防に向けた啓発に一定の効果はあると考えられるが,介入群の25%は温度計をあまり見ていなかったという結果を踏まえると,シール型温度計の配布だけでは高齢者の熱中症予防対策としては不十分である。今後,高齢者の熱中症予防行動の変容につながる効果的な介入方法について,さらなる検討が必要である。
キーワード 高齢者,熱中症,シール型温度計,エアコン使用
|
第68巻第2号 2021年2月 年齢層別住民ボランティアの地域活動への認識の特徴橋口 綾香(ハシグチ アヤカ) 池田 直隆(イケダ ナオタカ)岡本 双美子(オカモト フミコ) 河野 あゆみ(コウノ アユミ) |
目的 本研究では住民ボランティアの年齢層と地域活動への認識の関連を明らかにする。
方法 大阪府A市で地域活動を実施する住民ボランティア1,812名を調査対象者とし,無記名自記式質問紙調査を実施した。調査項目は,基本属性,地域活動への認識である。地域活動を見守り活動とし,地域活動への認識として地域コミットメント,地域高齢者見守り自己効力感を把握した。
結果 回収者数1,121名のうち分析対象者は764名であり,64歳以下が177名(23.2%),65~74歳が381名(49.9%),75歳以上が206名(27.0%)であった。対象者の基本属性では,住民ボランティアの年齢層が上がるにつれて女性の住民ボランティアの割合は低くなり(p<0.001),64歳以下が最も就業していた(p<0.001)。また,住民ボランティアの年齢層が上がるほど居住年数や地域活動の活動年数が長かった(p<0.001)。年齢層別にみた対象者の見守り活動および見守り関連活動への認識は,地域コミットメント得点では年齢層と統計学的な有意差はみられなかった。地域高齢者見守り自己効力感得点では,年齢層が高くなるほど見守り活動への自己効力感が高かった(p<0.001)。多重比較の結果,64歳以下と65~74歳(p<0.01),64歳以下と75歳以上(p<0.001),65~74歳と75歳以上(p<0.01)の群間で有意差がみられた。
結論 住民ボランティアの性別は,女性の住民ボランティアの割合が,男性ボランティアの割合より高かった。女性の就業率が上昇する現代日本においては,就業と地域活動によって女性の住民ボランティアの役割が過重になる可能性があり,今後活動内容を工夫する必要があると考えられる。また,地域活動への自己効力感は年齢層が上がるにつれて高くなることが示されたが,地域コミットメントは年齢層と関連がなかった。地域活動の内容は,前・後期高齢世代のニーズや興味に合わせたものである可能性が高いため,幅広い年代の住民ボランティアに調査を実施し,年代のニーズに応じた地域活動の内容へと工夫する必要がある。
キーワード 住民ボランティア,地域活動,地域コミットメント,地域高齢者見守り自己効力感
|
第68巻第2号 2021年2月 障害者手帳所持者数は,なぜ「推計」値か-障害者手帳の交付および所持に関する情報等の管理運用の現況-今橋 久美子(イマハシ クミコ) 北村 弥生(キタムラ ヤヨイ) 竹田 幹雄(タケダ ミキオ)竹島 正(タケシマ タダシ) 飛松 好子(トビマツ ヨシコ) 岩谷 力(イワヤ ツトム) |
目的 現在,身体・療育手帳の所持者数は,標本調査の結果から「推計」されている。平成28年の身体障害者手帳所持者数の推計値は436万人,交付台帳登載数(発行数)は515万人であり,後者が約80万人多い。交付台帳は発行者が管理しており,登載情報は死亡等により手帳が返還された場合に台帳から削除される。未返還により死亡が交付台帳に反映しきれないことが,所持者数の推計値と交付台帳登載数との乖離の原因となっている。もし動態情報を管理している市区町村において手帳交付情報との照合作業が行われていれば,推計に頼らずとも手帳所持数が得られることになる。そこで本研究では,将来的な障害保健福祉データベース構築のための基礎的な情報収集の一環として,手帳発行数と所持者数に違いが生じる背景要因を明らかにするために,市区町村における障害者手帳の交付および所持に関する情報等の管理運用に関する現況調査を行った。
方法 全国1,741市区町村の障害福祉担当部門に調査票を郵送配付した。質問内容は,①障害者手帳交付情報の主な管理方法,②死亡や転出等動態情報との照合状況,③他の制度とのデータ連携状況とした。
結果 1,445市区町村(83.0%)から有効回答を得た。管理方法は,①専用システムを導入し,住民基本台帳システムにおける死亡や転出の情報が自動的に反映される,②都道府県から紙媒体で市区町村に送られた決定内容や住民基本台帳システムの情報を手動で入力する,③動態を全く確認していない,の3つのパターンがあった。方法は一様ではないものの,有効回答のうち,98%は電子媒体で交付情報等を管理し,96%は動態情報と照合していた。動態把握は,手当等の適切な給付のためにも不可欠である旨が自由記述に記載されていた。なお3障害で管理方法や専用システム導入率に大きな差はなかった。
結論 本研究では,市区町村を対象に調査した。回答した市区町村の9割以上において交付情報と動態情報を照合していることから,管理運用上の課題を解決することにより,正確な所持者数の捕捉が可能であることが示唆された。一方で都道府県においては,返還届が進達されない限り,障害者手帳交付台帳に動態情報を反映することが制度上困難である。全国的には都道府県と市区町村との情報共有方法も一様でないことが推察されることから,都道府県における交付台帳の管理運用に関する調査も今後必要と考えられる。
キーワード 障害者手帳,障害者数,交付台帳,市区町村,人口動態,情報管理
|
第68巻第2号 2021年2月 横浜市産婦健康診査の産婦健診補助券からみた
杉原 麻理恵(スギハラ マリエ) 丹野 久美(タンノ クミ) 岩田 眞美(イワタ マミ) |
目的 近年,妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の必要性が重要視され,横浜市では産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図る観点から平成29年度より産婦健康診査事業を実施している。今回,横浜市産婦健診補助券に記載された内容を用いて,産婦健康診査の実施状況を分析し,さらに,エジンバラ産後うつ病質問票(以下,EPDS)の点数が産婦の支援にかかわる人に適切に解釈されるために,産婦の特性によるEPDSの推移の差に関する検討を行った。
方法 平成29年6月から平成30年3月までに横浜市産婦健診補助券を使用して産婦健康診査を受診した産婦15,605人の健診の実施内容・結果を分析した。さらに,2週間健診,1カ月健診の両方を受診し,両健診にてEPDSを使用した産婦8,880人を対象に,独立変数を健診時期(2週間と1カ月),産婦の特性(分娩歴,若年出産,高齢出産,多胎の有無),従属変数をEPDSの合計点数とし,反復測定二元配置分散分析を行い,産婦の特性の差によるEPDSの点数の推移について,有意な差異がみられるかを検討した。
結果 当該期間に2週間健診を受診した産婦は9,585人であった。2週間健診で「異常あり」とされた産婦は1,133人で,うち805人が9点以上であった。81人が区の福祉保健センターに報告され,7人が精神科に紹介された。2週間健診で9点以上だった産婦の32%が1カ月健診においても9点以上であったが,1カ月健診で9点以上であった産婦の約半数は2週間健診では低値であった。初産婦のEPDSの点数は2週間・1カ月健診共に経産婦に比べ有意に高く,高齢産婦の点数は,2週間健診では有意に低かったが,1カ月健診では有意差は認めなかった。いずれの要因でも,2週間健診のEPDSの点数が1カ月健診に比べて高値であった。2週間と1カ月健診の間での初産婦の点数の低下は顕著であり,他要因による交互作用が示唆された。分娩歴および高齢出産の有無による4層の層別解析では,2週間・1カ月健診ともに初産婦のほうが有意に高値であったが,高齢出産の有無による有意差は認めなかった。
結論 初産婦のEPDSの点数は経産婦と比較して一貫して高値であった。特に初産婦の産後2週間前後におけるメンタルヘルスの悪化は明確であるが,産後1カ月後には急速に回復する。EPDSの推移を参考にしながら,回復が遅れる初産婦の特性を把握し,早期介入に結び付けることが重要である。
キーワード 産婦健康診査,産後うつ,エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS),妊産婦のメンタルヘルス,産後の支援
|
第68巻第2号 2021年2月 東京都の医師の近隣県への派遣の状況に関する検討-2018年東京都が実施した調査に基づく分析-山内 和志(ヤマウチ カズシ) 田口 健(タグチ タケシ)森脇 睦子(モリワキ ムツコ) 河原 和夫(カワハラ カズオ) |
目的 東京都から近隣県への医師の派遣の状況を明らかにする。
方法 東京都が実施した専攻医プログラムの基幹施設である都内の医療機関および基幹施設となっていない大学病院,分院を対象とした医師派遣に関する調査の再分析を通じて,他の医療施設に派遣された医師数の詳細を分析し,さらに都外に派遣された医師数がその県内の医師数の占める割合を診療科別に推計した。
結果 派遣された東京都の医師のおよそ半数は都外の医療機関で診療に派遣されていた。女性医師は男性医師と比較して派遣地域が東京都や埼玉県である割合や,派遣期間が6カ月~1年未満である割合は高い傾向を示した。派遣された医師は,その県の医師数の10%を超え,また病院に従事する医師数の20%を超える診療科もあった。この場合,最低でもその県の診療科医師の4~5人に1人は東京都内の医療機関からの派遣医師であることを示しており,近隣県において,特に病院診療において医師確保が都内医療機関から移動する医師を供給源として一定の割合を占めている状況が明らかになった。
結論 東京都と近隣県の医師の供給については,一つの都県内だけでなく地域全体の現状を含めて考えていくことの重要性が示唆された。
キーワード 医師派遣,地域医療,医師確保,東京都
|
第68巻第1号 2021年1月 医療施設の曜日別診療状況と
三重野 牧子(ミエノ マキコ) 橋本 修二(ハシモト シュ二ウジ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) |
目的 患者調査の総患者数の推計方法は1990年頃の診療状況に基づくことから,見直しの必要性が指摘されている。最近の医療施設の曜日別診療状況を観察するとともに,推計方法の調整係数(平日の調査による再来外来患者数を1週間の平均再来外来患者数に調整する係数)について,1週間のうちで日曜が休診の想定による現行値(6/7),土曜の午後と日曜が休診の想定による代替値(5.5/7)の適切性を検討した。
方法 2005~2017年の患者調査と医療施設調査を利用した。患者調査による平日1日の再来外来患者数に対する,医療施設調査による1カ月間の平均再来外来患者数の比(調整係数の相当値と呼ぶ)を算定した。
結果 2017年の診療施設割合をみると,病院では午前・午後・18~19時ともに月~金曜でほぼ一定であり,土曜でそれより低かった。一般診療所と歯科診療所では午前・午後・18~19時ともに月・火・水・金曜でほぼ一定,木曜と土曜でそれより低かった。2005年と2017年の診療施設割合の差をみると,病院・一般診療所・歯科診療所,月~日曜と祝日の午前・午後・18~19時ともに-4~5%の範囲内であった。2005~2017年の調整係数の相当値は病院で平均6.2/7(範囲6.1/7~6.3/7),一般診療所で同5.8/7(5.7/7~6.0/7),歯科診療所で同4.7/7(4.4/7~5.0/7)であった。
結論 2005~2017年の曜日別診療施設割合は病院,一般診療所,歯科診療所の間に相違がみられたが,年次間ではほぼ一定傾向であった。調整係数としては,代替値への変更が支持されず,また,歯科疾患の推計に課題があるものの,現行値が比較的適切であると示唆された。
キーワード 医療施設調査,患者調査,総患者数,調整係数,保健統計
|
第68巻第1号 2021年1月 現代日本における格差と貧困の所在地平原 幸輝(ヒラハラ ユウキ) |
目的 地域福祉の地域アセスメントにおけるニーズ調査として,どの地域において経済的な格差が大きく,貧困に直面している人々が多いのかという点を明らかにする。
方法 2018年の『住宅・土地統計調査』データから算出される所得関連指標を,2015年の『国勢調査』データから算出される社会経済指標によって説明するモデルを,相関分析と重回帰分析を通じて導く。そこで導かれた回帰モデルに基づき,『住宅・土地統計調査』にデータのある自治体(または政令指定都市の区。以下同じ)は実測値,データのない自治体は推定値を用いることで,日本全国の市区町村における所得関連指標を網羅する。そして,得られた所得関連指標の値をZ得点化した上で,極めて深刻な格差や貧困の問題に直面している自治体を明らかにする。
結果 各自治体における社会経済指標が所得関連指標に影響を与えていることが示される中で,経済的な格差の大きさを示すジニ係数には単独世帯比率が,貧困層の多さを示す年間収入200万円未満世帯比率には老年人口比率が,最も強い正の影響を与えていた。また,格差や貧困の状況が空間分布として示され,極めて深刻な格差や貧困の問題に直面している自治体も示された。特に,格差への対策が求められる自治体には都市部,貧困への対策が求められる自治体には離島地域,格差や貧困への対策が求められる自治体には町や村といった郡部の自治体が,それぞれ多く含まれていた。
結論 本研究を通じ,日本全国の市区町村における所得関連指標を網羅することが可能になり,格差や貧困に対する取り組みが必要となる自治体が明らかになった。そして,このマクロ的な統計分析によって,現代日本における格差と貧困の現状を把握することが可能となり,格差と貧困に関する地域アセスメントにおけるニーズの把握が実現された。
キーワード 福祉,地域福祉,地域アセスメント,格差,貧困,ジニ係数
|
第68巻第1号 2021年1月 虚弱高齢者の自己決定を尊重した
笠原 幸子(カサハラ サチコ) 畑 智惠美(ハタ チエミ) |
目的 本研究では,超高齢社会を支えるために,専門職としての成熟が求められている介護福祉士が,虚弱高齢者の自己決定をどのように支援しているのか,介護福祉士の実践の構造を明らかにし,その実践に関連する要因を検討することを目的とする。
方法 A県介護福祉士会の会員を対象に自記式調査票を用い,2017年7月15~31日に郵送調査を実施した。分析は,第1に,虚弱高齢者の自己決定を尊重する介護福祉士の実践の構成因子を実証的に捉えるために,因子分析を行った。第2に,介護福祉士の実践の関連要因をとして有能感を取り上げ,その構成因子を実証的に捉えるために,因子分析を行った。第3に,介護福祉士の実践の構造に関連する要因を検討するために,従属変数には介護福祉士の実践の因子ごとの合計素得点を,独立変数は「職場外のスーパービジョン」「実践の振り返り」,介護福祉士の有能感の因子ごとの合計素得点等を投入し,強制投入法による重回帰分析を行った。
結果 第1の因子分析の結果,虚弱高齢者の自己決定を尊重する介護福祉士の実践は,「意向と主体性の把握」「主体的実行を引き出す支援」「関係づくり」の3因子が抽出された。第2の因子分析の結果,「業務の達成」「仕事上の予測と問題解決」「自己啓発と能力発揮」の3因子が抽出された.第3の重回帰分析の結果,「意向と主体性の把握」では,「仕事上の予測と問題解決」「実践の振り返り」「職場外のスーパービジョン」が正の有意な関連を示した。「主体的実行を引き出す支援」では,「自己啓発と能力発揮」「実践の振り返り」「介護福祉士としての経験年数」が正の有意な関連を示した。「関係づくり」では,「実践の振り返り」「自己啓発と能力発揮」が正の有意な関連を示した。
結論 虚弱高齢者の自己決定を尊重する介護福祉士の実践は,①「意向と主体性の把握」(虚弱高齢者の主体性を尊重しつつ意向を把握すること),②「主体的実行を引き出す支援」(選択肢の提示や待つこと等によって虚弱高齢者の主体的実行を引き出すこと),③「関係づくり」(自らの心を開いて接すること等によって虚弱高齢者との関係づくりをすること)の3領域が確認された。また,自らの実践を振り返っている,仕事上の予測と問題解決ができる,自己啓発と能力を発揮していると回答した介護福祉士ほど,虚弱高齢者の自己決定を尊重する実践ができていた。
キーワード 自己決定,介護福祉士,虚弱高齢者,量的研究,主体性,関係づくり
|
第68巻第1号 2021年1月 有料老人ホームにおける虐待予防策への取り組みの実態と課題-「介護付き」「住宅型」有料老人ホームと「特別養護老人ホーム」との比較をもとに-松本 望(マツモト ノゾミ) |
目的 本研究は,有料老人ホームのタイプ別に,虐待予防に向けた取り組みの実態と課題を明らかにすることを目的とした。
方法 調査は質問紙を用いて行い,A県にあるすべての有料老人ホーム,「特別養護老人ホーム」に書面にて調査への協力を依頼し,同意が得られた施設に勤務する全介護職員を調査対象として実施した。質問紙では,虐待予防策,基本属性について調査した。
結果 1,412名分の質問紙を回収し(回収率43.8%),そのうち「健康型」の有料老人ホームの3名分の回答と,欠損値のあった回答を除外した1,309名分を有効回答とした(有効回答率40.6%)。まず「虐待予防策」について探索的因子分析を行った結果,「職員の特性」「職場の人間関係」「上司の特性」「負担感のなさ」「職場の虐待への対策」の5因子が抽出された。次に,施設種別ごとに虐待予防策への取り組み状況を比較したところ,「職員の特性」「職場の人間関係」「職場の虐待への対策」の三つの因子に有意な差がみられた。まず「職員の特性」では,「住宅型」と「特別養護老人ホーム」(p<0.01),「介護付き」と「特別養護老人ホーム」(p<0.01)で有意な差がみられ,「住宅型」「介護付き」「特別養護老人ホーム」の順に得点が高かった。「職場の人間関係」では,「特別養護老人ホーム」と「介護付き」(p<0.05),「特別養護老人ホーム」と「住宅型」(p<0.05)で有意な差がみられ,「特別養護老人ホーム」「介護付き」「住宅型」の順に得点が高かった。最後に「職場の虐待への対策」では,「特別養護老人ホーム」と「住宅型」(p<0.01)で有意な差がみられ,「特別養護老人ホーム」「介護付き」「住宅型」の順で得点が高い傾向がみられた。
結論 「介護付き」「住宅型」の有料老人ホームにおいても実際に虐待が発生していることから,より質の高いケアを目指す必要がある。具体的な取り組みとしては,研修等により職員の知識や意識を維持・向上させるような取り組みや,職員同士が連携・協働できる体制づくり,施設全体で虐待の未然防止や相談・対応の体制整備に取り組むこと,そして経営層も含め施設全体の虐待に対する認識を高めていくことなどが求められる。
キーワード 介護付き有料老人ホーム,住宅型有料老人ホーム,特別養護老人ホーム,虐待予防策
|
第68巻第1号 2021年1月 改正健康増進法の必要性坂口 早苗(サカグチ サナエ) 坂口 武洋(サカグチ タケヒロ) |
目的 近年,喫煙防止教育や活動の成果によって,喫煙率は確実に低下しているが,喫煙者のマナーは向上しているとはいえない。大学生の喫煙および受動喫煙に関する調査を実施し,実際にどのような迷惑が生じているかについて把握し,併せて健康増進法の改正がいかに必要であったかを示すことを目的とした。
方法 調査対象者は関東地方にある女子大学の学生1,274人のうち,年齢および喫煙経験の記載があった1,214人であり,調査時期は2008~2019年の毎年秋に,協力の得られた約100人ずつに対し,その場で質問紙およびデータ用紙に記入を依頼し回収した。調査項目は,自記式の質問紙調査,呼気中のCO量および手先の皮膚温度の測定である。
結果 調査対象者の喫煙未経験率は,91.9%であった。呼気中のCO量の平均値は2.0±2.2(±標準偏差)ppm,COHbの平均値は0.8±0.6%,手先の皮膚温度の平均値は30.9±2.5℃であった。タバコの有害性に関する認知度は「身体への有害性」「肺がん」「胎児への影響」および「子どもへの影響」が90%以上であった。一方,「中年太り」「女性の禁煙しにくさ」および「女性の易依存性」については50%以下であった。喫煙未経験者1,024人の呼気中のCO量は,5~6ppmが7.4%,7ppm以上が2.0%であった。直近の暴露場所はアルバイト先が26.7%,居間が24.2%,居酒屋および歩きタバコがそれぞれ8.2,8.1%であった。2018~2019年の対象者126人に追加質問した結果,三次喫煙の認知度は38.9%,「喫煙30分後まで呼気中に有害物質が排出」されることを知っている者は63.5%であった。受動喫煙により迷惑と感じた経験については,喫煙後の人がタバコ臭いと感じた者は96.8%,タバコの煙で食事がまずくなった経験を有する者は78.6%,自分の髪の毛や洋服がタバコ臭いと感じた者は69.8%であった。
結論 最初の1本を口にしないための喫煙防止対策はかなり充実してきているが,タバコが身近にない環境(受動喫煙防止,防煙)対策はいまだ進んでいないこと,分煙では受動喫煙防止に効果がないことが明白となった。改正健康増進法の遵守と同時に,飲食店従業員の健康を護る対策が引き続き求められる。
キーワード 改正健康増進法,呼気中CO量,受動喫煙,三次喫煙,受動喫煙防止条例
|
第67巻第15号 2020年12月 奈良県における後期高齢者医療費と保険料水準の理論推計西岡 祐一(ニシオカ ユウイチ) 野田 龍也(ノダ タツヤ) 今村 知明(イマムラ トモアキ) |
目的 今後の日本の人口と医療費の推移のモデルとして,奈良県の後期高齢者医療制度の悉皆(全数)調査である国保データベース(以下,KDB)を用いて奈良県の後期高齢者医療費の推移について推計し,今後の医療費と後期高齢者医療保険料水準について考察する。
方法 奈良県人口調査年報および奈良県年齢別人口調査を用いて,男女別年齢別人口を1歳刻みで調査した。2018年10月1日現在の奈良県の年齢別人口から,①奈良県と奈良県外との間の男女別年齢別人口の流出入が同じである,②男女別年齢別死亡率は2018年簡易生命表のもので不変である,と仮定してその死亡率を基に2019年から2093年までの75歳以上の人口の推計を行った。医療費については奈良県KDBを用いて75歳以上の医療費合計を集計し,後期高齢者医療保険制度の75歳以上の被保険者1人当たりの医療費を年齢別に集計した。最後に人口1人当たりの医療費と75歳以上の人口推計を掛け合わせて,2019年度から2093年度までの75歳以上の医療費を推計し,これを基に後期高齢者医療保険の被保険者1人当たりの医療費を推計した。
結果 奈良県の75歳以上人口は,2017年の197,702人から2028年の261,400人まで増加し続け,それを境になだらかな減少ないし横ばいに転じる。その後2050年には227,899人となり,その後さらに減少し続けた。死亡率,現状の医療・介護体制がこのまま継続したとすると,2030年度以降は奈良県における後期高齢者医療費は,およそ1人当たり87,000~90,000点の間で推移した。特に今後10年間,後期高齢者人口は急激に増加し,総医療費も増加傾向を示す。一方,保険料水準と強く相関する後期高齢者1人当たりの医療費は,後期高齢者人口が急激に増えるタイミングで一旦減少傾向を示し,その後再び増加傾向に転じると推測された。
結論 本研究は,奈良県における75歳以上の後期高齢者の人口,医療費についての推計手法・推計結果を提供し,保険料水準の推移について考察した。0~74歳の人口は既に決まっており,死亡率,医療費のデータを用いることで,今後の医療費や保険料水準の推移を精緻に推計できることを示した。これらの推計は今後の社会保障制度を考えるうえで重要な基礎資料となる。
キーワード 後期高齢者,医療費,KDB,国保データベース,奈良県
|
第67巻第15号 2020年12月 ADL維持向上等体制加算における
松岡 森(マツオカ シン) 山田 修(ヤマダ オサム) 中上 和洋(ナカウエ カズヒロ) |
目的 消化器内科入院症例における入院日数が長期化する要因を明らかにし,ADL維持向上等体制加算におけるリハビリテーション(リハ)開始基準を検討した。
方法 対象は,2018年4月1日から9月30日の間に当院消化器内科に入院した396例を対象とした。今回の対象集団の入院期間の中央値である7日を基準とし,7日未満を短期入院群(S群),7日以上を長期入院群(L群)に分類し,患者因子(年齢・性別・入院方法:緊急/予定)・身体機能(入院時Barthel Index(BI)60点以上/未満・自立歩行可否)・社会的背景(独居有無・介護保険有無)・治療因子において比較・検討した。入院日数7日以上/未満により分類された2群を単変量解析し,単変量解析にて有意差を認めた項目を説明変数とした多重ロジスティック回帰分析にて入院日数との関連性を検討した。
結果 対象期間に消化器内科に入院した症例は,S群196例/L群200例であった。単変量解析では,年齢・緊急入院・入院時BI60点未満・自立歩行不可・介護保険有は,L群で有意に高値を示した。独居有無・治療因子は,有意差を認めなかった。多重ロジスティック回帰分析では,入院日数7日以上は緊急入院(オッズ比=0.47,95%信頼区間:0.29-0.77,p=0.003),入院時BI60点未満(オッズ比=0.34,95%信頼区間:0.14-0.80,p=0.013)と関連を示した。
結論 消化器内科入院患者において,緊急入院・入院時BI60点未満の症例は入院期間が長期化しやすく,ADL維持向上等体制加算による早期リハ介入の適応基準となる可能性が示唆された。
キーワード ADL維持向上等体制加算,リハビリテーション開始基準,消化器内科,入院日数
|
第67巻第15号 2020年12月 社会福祉施設における高齢者ボランティア受け入れの現状と課題-地域活動への展開を目指して-守本 友美(モリモト トモミ) |
目的 本研究では,まず,近年着目されている「地域共生社会」の担い手として期待されている高齢者の実践活動を進めるために,ボランティア活動が誘因となるという仮説を立てた。それを証明するための前段階となる基礎的資料を提示するとともに,高齢者ボランティアの意識および活動の展開・発展につながる福祉施設による支援方法を考察することを目的とした。
方法 A市所管の介護老人福祉施設への質問紙調査を実施した。調査期間は2019年6月20日から7月31日であった。A市所管の介護老人福祉施設数は151施設であり,調査票回収数は58件で,回収率は38.4%であった。調査項目は,運営主体,開設からの年数,入所定員,職員数,ボランティアの受け入れの有無,ボランティア受け入れの目的,65歳以上のボランティアの受け入れ状況と募集の方法,ボランティア活動の内容,ボランティアを受け入れる際の課題,ボランティア受け入れ担当者の有無,ボランティアコーディネーションの内容とした。
結果 介護老人福祉施設におけるボランティア受け入れの現状から,87.9%の施設がボランティアを受け入れており,そのうちの86.3%の施設で高齢者が活動していることから,高齢者のボランティアが高齢者福祉分野で活躍していることがわかった。ボランティア受け入れ担当者については,37施設,63.8%の施設が配置をしている。ただし,ボランティアを受け入れている施設は51施設,87.9%という調査結果からみると,ボランティアを受け入れていても,担当者が配置されていない施設があるということがわかる。また,受け入れに際しては,活動内容・範囲などの配慮を行っていることが明らかになった。
結論 社会福祉施設で活動するボランティアが地域活動にも活動範囲を拡大していくためには,ボランティアが施設で受け入れられ,安定して活動を継続することから生まれる自信が必要になると考えられる。したがって,受け入れ施設の支援としては,ボランティア受け入れの体制を整え,ボランティアコーディネーションの内容を充実させることが必要になる。また,その上で,地域活動への展開のためにも,コミュニティソーシャルワークの視点も求められる。
キーワード 高齢者ボランティア,社会福祉施設,ボランティア受け入れ,ボランティアコーディネーション
|
第67巻第15号 2020年12月 学童期におけるゲームに費やす時間と
射場 百花(イバ モモカ) 内藤 義彦(ナイトウ ヨシヒコ) |
目的 学童期は生活習慣の形成期であり,成人期の生活習慣に大きな影響を及ぼす大事な時期と考えられる。近年,ICTの生活全般への普及に伴い,学童期の日常生活におけるゲームに費やす時間(以下,ゲーム時間)の増加による様々な影響が危惧されており,望ましい生活習慣の形成を阻害するおそれがある。そこで,本研究では,一自治体の学童期の全員を調査対象として設定し,ゲーム時間と食生活および生活習慣との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 大阪府S市の全公立小学校に在籍しているすべての児童3,524人を対象とし,家庭における食生活と生活習慣に関する17項目からなる質問紙調査を実施した。このデータを用いて,ゲーム時間と児童の食生活・生活習慣との関連を,単変量および多変量ロジスティック回帰分析によりオッズ比と信頼区間を求め検討した。
結果 解析対象者は,年齢・性別等に記入漏れがなかった3,235人とした。解析対象者のうち,ゲーム時間が「2時間以上/日」の児童は,男子716人(44.1%),女子370人(23.0%)であり,女子より男子においてゲーム時間が長かった。食生活について,学年とは独立して男女ともに,朝食,野菜,間食,味が濃い料理の摂取頻度および食事の挨拶とゲーム時間との間に有意な関連を認めた。さらに男子では,共食,果物,カルシウムが多く含まれる食品,油の多い料理の摂取頻度でゲーム時間との間に有意な関連を認めた。他の生活習慣では,男女ともに身体活動,起床・就寝時刻との間に有意な関連を認めた。ゲーム時間が長いと就寝時刻が遅く,身体活動が少ない関連を認めた。
結論 ゲームに長時間費やしていることにより,就寝時刻が遅くなり,その結果,起床時刻も遅くなり,朝食の欠食,野菜の摂取頻度の低下や間食頻度の増加など食生活の乱れにつながることが示唆され,児童が健全な食生活および生活習慣を身につけるためには,ゲーム時間の制限が必要と考えられた。長時間ゲームに費やすことは,ゲーム依存という精神疾患に関係するという問題だけでなく,将来の生活習慣病のリスクを高めるおそれがあることにもっと注意をはらうべきである。なお,具体的対策としては,ゲーム時間の上限の設定および啓発が現実的であり,今後,上限の根拠の検討が必要になると考えられる。
キーワード 学童期,ゲーム,食生活,生活習慣,生活習慣病
|
第67巻第15号 2020年12月 貧困世帯の子ども・若者への支援-支援者ミーティングと支援記録の実践への活用に関連して-三沢 徳枝(ミサワ トクエ) |
目的 困難を有する子ども・若者を支援する民間団体(以下,法人)では,支援者ミーティングが実施されず支援記録をつけない状況がある。本研究では,貧困世帯の子ども・若者支援に注力する法人を対象とする調査データを用いて,支援者ミーティングと支援記録と関係機関との協力・連携や教育訓練における活用との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 「困難を有する子ども・若者の支援者調査,2011」(内閣府子ども若者・子育て施策総合推進室)から「ひきこもり」「発達障がい」等の支援を行う法人が回答したA調査票(447法人)を使用した。このうち貧困世帯の子ども・若者支援に注力する法人(122法人)の支援者ミーティングと支援記録の実施状況の二次分析でχ2検定あるいはFisher’s exact testを行った。
結果 貧困を経験した子ども・若者支援を行う法人の支援者ミーティングと支援記録の実施状況と協力・連携する機関や支援環境の整備,支援者の教育訓練の機会との関連が捉えられた。医療機関や特別支援学校,高等学校との協力・連携で,支援者ミーティングや支援記録が活用されている。地域活動へ参加する法人は,支援者ミーティングを支援者全員での実施が多く,ネットワークの構築をする法人はすべての対象者の支援記録をつける割合が多い。また教育訓練の機会について公的機関の研修・講演会への派遣を行う法人は,支援者ミーティングを全職員で行い,支援記録をすべての支援対象者につける割合が多いことがわかった。
結論 支援者ミーティングと支援記録は,貧困を経験した子ども・若者の支援をする法人が医療・福祉・教育機関と情報を共有し協力・連携するために,その活用について検討する必要がある。支援者ミーティングでは多様なメンバーを受け入れて,多様な地域の資源とつながることで,結果として子どもの社会に参画する力を育てることになる。また支援記録は支援の経緯を可視化して,多様な機関とのネットワークを構築するという点から,子ども・若者支援への介入に向けた活用方法を考える必要がある。支援者が公的機関の研修・講演会に参加して,子どもの多様なニーズに対応する知識とスキル,実践力を高め,様々な視点から実践の評価を可能にするために支援者ミーティングと支援記録が活用されると考えられた。
キーワード 子どもの貧困,ミーティング,支援記録,ネットワーク,情報共有
|
第67巻第13号 2020年11月 1期目の民生委員・児童委員の任期満了時点における
|
目的 1期目の民生委員・児童委員(以下,委員)の任期満了時点における2期目の活動継続意向と関連要因を明らかにすることとした。
方法 三重県内で活動する1期目委員全員を対象に,2016年8月~11月に4群34項目で構成する質問紙を用いた無記名自記式質問紙調査を行った。分析は継続・退任の意向で2群に分け,各項目について比較を行った。
結果 1,840名に調査票を配布し,1,566名から回答を得て,欠損値等のあるものを除外し,1,047名分(有効回答率:56.9%)を分析した。435名(41.5%)が1期目満了時点で退任する意向であった。継続・退任の2群間比較で有意差の認められた項目を説明変数とした二項ロジスティック回帰の結果,年齢(オッズ比(以下,OR):1.34,95%信頼区間(以下,CI):1.08-1.66,p=0.008),地域包括支援センターとの活動上の相談(OR:1.46,95%CI:1.10-1.94,p=0.009),民生委員同僚との活動上の相談(OR:1.43,95%CI:1.09-1.89,p=0.011),民生委員同僚との情報交換(OR:1.50,95%CI:1.14-1.96,p=0.003),活動に対する負担感(OR:1.68,95%CI:1.38-2.04,p<0.000)の5項目で継続・退任の意向と有意な関連が認められた。
結論 1期目の委員に対する支援として,地域包括支援センター等の関係機関側が活動について相談できる機会,委員が活動を振り返り,相互に情報交換できる機会,を設けていく必要性が示唆された。
キーワード 民生委員,児童委員,1期目,活動継続意向,連携,情報共有
|
第67巻第13号 2020年11月 回復期リハビリテーション病棟入院料と
奈良 浩之(ナラ ヒロユキ) 和泉 優子(イズミ ユウコ) |
目的 過疎地では,コメディカルをはじめとするスタッフに乏しく,回復期リハビリテーション病棟入院料の高い施設基準を満たせない可能性がある。そこで,二次医療圏における人口と届け出た回復期リハビリテーション病棟の最も高い入院料との関連を明らかにする。
方法 二次医療圏ごとの最も高い回復期リハビリテーション病棟入院料は,各地方厚生局のホームページから,二次医療圏の人口は2015年国勢調査から引用した。統計処理は,Mann-Whitney U検定を行い,Bonferroniの補正を行った。
結果 最も高い回復期リハビリテーション病棟入院料により二次医療圏を分類して居住人口の中央値を求めると,回復期リハビリテーション病棟入院料届け出医療機関のない場合では56,788人,入院料1では387,945人,入院料2では143,548人,入院料3では103,250人,入院料4では107,724人,入院料5では121,387人,入院料6では117,192人であった。施設基準(アウトカム評価)の最も高い入院料1の二次医療圏人口が,他の入院料の二次医療圏人口に比べ有意に多く,施設基準上の専門職の人員配置でほぼ類似する入院料1と2の二次医療圏人口においても,有意差を認めた(ともにBonferroniの補正後p<0.01)。
結論 良好な回復度を有し,高い施設基準を満たす入院料1の回復期リハビリテーション病棟は,人口規模の大きな二次医療圏に限られることが明らかになった。国民の間に健康格差があることは望ましくなく,リハビリテーションの質が都市部のみ高くなる診療報酬制度に課題があると思われる。さらに,地域の医療連携や病床機能分化により,回復期リハビリテーション病棟をより有効に機能させるべきである。また,専門職の人員不足や病床利用率低下,在宅復帰にも苦慮する過疎地においても達成可能なアウトカム評価を設定する必要性があろう。
キーワード 回復期リハビリテーション病棟入院料,アウトカム評価,二次医療圏人口,診療報酬,施設基準
|
第67巻第13号 2020年11月 若年成人女性の体成分と健康度・生活習慣の関連辛島 順子(カラシマ ジュンコ) 小林 理佐(コバヤシ リサ) |
目的 成人女性は,やせの者(BMI<18.5㎏/㎡)の割合が多いことが健康課題として挙げられる。一方で,BMIは正常でありながら体脂肪率が高い正常体重肥満者,いわゆる「隠れ肥満」の存在も注目されている。本研究の目的は,女子大学生を対象とした体成分測定と健康度・生活習慣診断検査を実施し,正常BMIかつ体脂肪率高値の者の体成分の特徴と健康度・生活習慣の関連から,次世代の健康を担う若年成人女性の生活習慣改善の方策を示すことである。
方法 2019年6月から7月に,A大学の女子大学生3・4年生80名を対象として,生体電気インピーダンス分析法(BIA法)の体成分測定と自記式質問紙調査を実施した。
結果 BMI18.5以上25.0未満の普通体重64名のうち,体脂肪率30%未満の者が49名(76.6%),30%以上の者が15名(23.4%)であった。体脂肪量,BMI,ウエストヒップ比は,体脂肪率30%以上の者が有意に高かった。筋肉バランスにおける体幹発達率,右足発達率,左足発達率は,体脂肪率30%未満の者が有意に高かった。部位別脂肪バランスにおける右手体脂肪量・体脂肪分布,左手体脂肪量・体脂肪分布,体幹体脂肪量・体脂肪分布,右足体脂肪量,左足体脂肪量は,体脂肪率30%以上の者が有意に高く,右足体脂肪分布,左足体脂肪分布は,体脂肪率30%未満の者が有意に高かった。精神的健康度は,体脂肪率30%以上の者が有意に高かった。また,健康度の総合得点は体脂肪率30%以上の者が高く,運動意識は体脂肪率30%未満の者が高い傾向がみられた。
結論 体脂肪率30%以上の者は内臓脂肪の蓄積と生活習慣病・骨粗しょう症のリスクが予測された。また,体脂肪率30%以上の者の方がグループ適応・対人関係が良好でイライラがなく,勉強や仕事がスムーズな傾向であると判定された。普通体重の若年成人女性は体脂肪率の違いにより,現時点で健康度や生活習慣に多くの差はみられていない。しかしながら,早い段階で体脂肪率の違いによる体成分や健康度,ならびにそれらに影響を及ぼすと考えられる生活習慣について自身が把握し,自分に合った適切な対処方法を学び,可能なことから実践することが望ましく,そのための環境整備も進める必要がある。
キーワード 若年成人女性,体成分,健康度,生活習慣,健康管理
|
第67巻第13号 2020年11月 都道府県別の女性未婚率の要因分析-自治体の少子化対策の観点から-田辺 和俊(タナベ カズトシ) 鈴木 孝弘(スズキ タカヒロ) |
目的 わが国の近年の出生数低下の最大原因は未婚化の進行にあるとされるが,未婚率には多数の要因が複雑に絡み合っている。そのため,要因解明を試みた研究は多数あるが,未婚要因はいまだに十分に解明されていない。本研究では自治体の少子化対策に有用な情報を得るために,都道府県別の女性の未婚率について非線形重回帰分析により多種多様な指標の中から要因を探索する分析を試みた。
方法 平成27年国勢調査からの47都道府県の女性の生涯未婚率(45歳~54歳)を目的変数とし,各種政府統計から得られる47種の指標を説明変数とし,非線形重回帰分析の一手法であるサポートベクターマシンを用いて,未婚率に対して統計的に有意な影響を及ぼす要因を探索し,さらに,感度分析法により,それらの要因の未婚率に及ぼす相対的影響度を評価した。
結果 都道府県別の女性未婚率に対して有意となる9種の要因を見いだし,そのうち,未婚率を下げる要因は親との同居率,持家率,製造業就業率,交際率,育児休業制度と介護休業制度利用率の6種,未婚率を上げる要因は所得,大学・大学院卒率,医療・福祉業就業率の3種であった。また,親との同居率が未婚率の低下に最大の影響を与える一方,高学歴かつ高所得女性の増加が未婚率の上昇に大きく寄与するという興味深い結果を得た。さらに,これまで未検証の製造業と医療・福祉業の就業率,交際率,育児休業制度と介護休業制度の利用率の5種の要因が有意となった。
結論 女性未婚率の要因として,親との同居率,所得,持家率,大学・大学院卒率などの他に,これまで未検証の要因を含む計9種を見いだし,本研究の解析方法の有効性を実証した。
キーワード 女性未婚率,要因分析,都道府県差,非線形重回帰
|
第67巻第13号 2020年11月 定年退職後の心のあり様尺度(PSAR)の開発谷口 千絵(タニグチ チエ) 小野 美月(オノ ミヅキ)北 素子(キタ モトコ) 久田 満(ヒサタ ミツル) |
目的 本研究の目的は,定年退職後の心のあり様尺度(以下,PSAR)を開発し,信頼性の検討および関連する要因を明らかにすることである。
方法 2017年12月時点でWeb調査会社に登録している人で,日本国内の企業に勤続し,定年退職を経験した60-74歳の男性308人を対象とした。PSARの暫定46項目について探索的因子分析を行った。抽出された各因子と退職後の人生設計,退職前から続けている趣味,現在のコミュニティへの関与度,現在の経済状況,現在の主観的身体的健康状態,基本属性について,対応のないt検定,一元配置分散分析を行い,有意な場合は多重比較を行った。さらに,各因子を従属変数とする重回帰分析を行った。
結果 3因子23項目が抽出された。第1因子10項目は〔定年後充実感〕,第2因子7項目は〔人生終わった感〕,第3因子6項目は〔現役への未練〕とした。Cronbachのα係数は,それぞれ0.84,0.83,0.73であった。〔定年後充実感〕は,趣味があり,同居人がいて,既婚者で,大学/大学院を卒業した群が高い得点であった。現在の経済状況を「苦しい」,健康状態を「不健康」,コミュニティへ「関わりはない」と回答した群の得点が低かった。〔人生終わった感〕は,定年退職前から続けている趣味がない群の得点が高かった。現在の経済状況が「苦しい」,健康状態を「不健康」,退職後の人生設計を,「考えていなかった/漠然と考えていた」と回答した群は高い得点であった。〔現役への未練〕は,現在パート・アルバイトに就いている群が高い得点で,コミュニティへ「関わりがない」,健康状態を「不健康」と回答した群の得点が低かった。重回帰分析の結果,〔定年後充実感〕は,定年退職前に考えていた人生設計があり,趣味があり,現在の経済状況に余裕があり,健康であると認識しているほど高かった。〔人生終わった感〕は,退職後の年数が浅く,定年退職前に考えていた人生設計がなく,現在の経済状況に余裕がないほど高かった。〔現役への未練〕は,現在のコミュニティへの関与度が高く,パート・アルバイトに就いており,経済状況に余裕がなく,退職後の年数が浅いほど高かった。
結論 定年退職後の男性を対象とし,定年退職後の人生や生活を営む過程における心の状態を客観的に把握するための心理尺度として〔定年後充実感〕〔人生終わった感〕〔現役への未練〕の3因子23項目が明らかになった。
キーワード 定年退職,心のあり様,男性,尺度の開発,退職移行期,人生設計
|
第67巻第13号 2020年11月 乳児を持つ父親が幼少期に受けた愛情の実感と
藤田 芙美子(フジタ フミコ) 吉田 和樹(ヨシダ カズキ) |
目的 乳児を持つ父親自身が幼少期に受けた愛情の実感と現在の精神的健康度との関連,さらには,育児状況との関連を調べることを目的とした。
方法 福島市で2017年10月から2018年3月に4カ月児健康診査を受診予定だった乳児945人の家庭に対して,通常の問診票に父親対象のアンケートを同封して郵送し,健康診査時に回答を回収した。加えて,健診票と問診票からもデータを転記した。アンケート回収率は54.8%であり,父親509人のデータを分析対象とした。父親の精神的健康度は「お父さんの気持ちの状態はいかがですか」と質問して,3件法で回答を求め,「よい」とそれ以外(「なんともいえない」「いいえ」)に2区分した。受けた愛情の実感は,「あなた自身は子どものころから愛情を受けて育ったという実感がありますか」と質問して,4件法で回答を求め,「ある」とそれ以外(「なんとなくある」「あまりない」「ない」)で2区分した。
結果 受けた愛情の実感が「ある」以外の父親は214人(42.1%),気持ちの状態が「よい」以外の父親は125人(24.6%)だった。父親の仕事の量的負担,母親の気持ちの状態,人間関係の問題,そして出生順位を調整した多変量解析の結果から,受けた愛情の実感が「ある」以外の場合,気持ちの状態が「よい」以外の調整オッズ比は1.99(95%信頼区間=1.30-3.06)であった。さらに,父親自身が受けた愛情の実感と父親の児に対する愛着に有意な関連が認められた(怒り:p=0.016,低い愛情:p=0.028)。
結論 父親自身の幼少期の親との関係と現在の精神的健康度が関連し,さらには現在の育児状況にまでも関連するという愛着の世代間伝達と育児への影響が示唆された。悪循環を断ち切るためには,父親に対する早期の育児支援が必要である。
キーワード 乳児健康診査,産後うつ,愛情,精神的健康度,父性行動
|
第67巻第12号 2020年10月 母子健康手帳に綴じ込まれた松井式便色カードの
顧 艶紅(コ エンコウ) 孔 元原(コウ ゲンゲン) 趙 金琦(チョウ キンキ) |
目的 2012年度から,デジタル印刷技術を利用した松井式便色カードが,改正された母子健康手帳に綴じ込まれて全国配布されるようになった。日本胆道閉鎖症研究会の報告では同便色カードの3番(陽性)と5番(陰性)の中間色である4番(陰性)が,約4割の胆道閉鎖症の患児で報告され,4番の新生児・乳児に対して,胆道閉鎖症の精査を行うかどうか議論されている。今回は北京市での追跡データを用いて,松井式便色カードの4番の回答頻度や転帰について解析し,生後4カ月までの便色の経時的変化,4番の便色と胆道閉鎖症の発症などの関係について明らかにすることを目的とした。
方法 2013年12月~2014年10月に北京市において,保護者が日本の母子健康手帳に綴じ込まれた松井式便色カードと同様のカード(中国語訳付き)を受け取った29,799人の出生児を研究対象とした。産科において訓練された産科のスタッフらが,保護者に家庭内で便色を観察し,1~3番の便色になったら,直ちに北京市新生児マススクリーニングセンターの外来へ受診をするように,また生後2週間,生後1カ月,生後1~4カ月の計3回記録するように説明した。記録情報は同センターの追跡システムや生後42日健診などを通して,フィードバックしてもらった。便色番号の報告頻度とその95%信頼区間を2項分布で計算し,検証した。
結果 有効回答数は27,561(92.5%)であった。生後2週間,生後1カ月,生後1~4カ月の3回の時点で最も報告の頻度の高かったのが5番で,次いで4番であった。4番と別の便色との組み合わせで出現する頻度が高い傾向にあった。しかし,4番と1番,2番,3番の組み合せと報告されたのはそれぞれ0人(0.0%),1人(0.02%),4人(0.07%)であった。4番便色と1~3番便色,5~7番便色と1~3番便色はそれぞれ交互に出現することもあったが,頻度は低く,両者の有意差はなかった。本研究で診断された2人の胆道閉鎖症患児では,3つの記録時点では,それぞれ4番→2番→(未観察),5~7番→5~7番→3番であった。
結論 健常児と胆道閉鎖症の患児において,生後4カ月まで,便色の経時的変化または複数の便色の組み合わせがみられた。4番の便色を示されてもすぐに精密検査をする必要はなく,引き続き観察し,1~3番に変化したら,すぐに受診するように勧める。胆道閉鎖症患児では必ずしも1番の「灰白色便」を呈するとは言い切れない。また,便色の変化を観察しながら,遅延性黄疸等のサインも見逃さないようにしてほしい。今後便色カードの異常便色のパネルを増やす選択肢を検討する必要がある。
キーワード 胆道閉鎖症,松井式便色カード,早期発見,陽性者,精密検査
|
第67巻第12号 2020年10月 運動実践者の体重減少に向けて食品カロリーの
松原 建史(マツバラ タケシ) 植木 真(ウエキ マコト) |
目的 運動実践者で腹囲がメタボリックシンドロームに該当する者は,食品カロリーの正しい知識が乏しいことが明らかにされている。そこで,食品カロリーの知識向上を図ることで,体重や腹囲の減少が期待できるため,この縦断的関係性について検討することを目的とした。
方法 対象を,公共運動施設を利用していて腹囲が85㎝以上だった女性74名とした(年齢:66±7歳,体重:58.1±7.0㎏,腹囲:90.5±6.4㎝)。対象者には平成28年2月と9月に,体重,腹囲,食品カロリーの知識調査を実施した。食品カロリーの知識調査は,ポスターに掲載した食品カロリーを伏せた寿司と焼鳥屋メニューそれぞれ数十種類の中から,一番カロリーが低いと思う組み合わせをクイズ形式で選択させ,そこから総合カロリー得点を算出して評価した。食品カロリーの正しい知識の浸透を図る支援として,2月と9月の食品カロリーの知識調査と同様の方法で,3月から8月まで食品カロリーを伏せた定食メニューやパン類など内容を変えながらクイズ式ポスターを掲示し,月末に答え合わせを行うことを繰り返した。その他の項目として,公共運動施設での自転車エルゴメータとトレッドミルの週当たり有酸素性運動時間を2月と9月それぞれで算出した。そして,2月から9月にかけて総合カロリー得点が全対象者の中で高水準を維持していた群,低水準から高水準に変化した群,低水準を維持していた群,高水準から低水準に変化した群の4群に分けた上で,年齢と週当たり有酸素性運動時間を調整因子にとった二元配置共分散分析を行った。
結果 全対象者では総合カロリー得点の向上傾向と体重の減少傾向を認めたが,変化量はそれぞれわずかであった。次に,4群の比較では,体重,腹囲とも有意な交互作用も群と時期の主効果を認めなかった。
結論 食品カロリーの正しい知識が向上しても体重や腹囲の減少にはつながらないことが明らかになった。知識の向上は全く必要ないということではなく,食行動の変容を図る支援を優先して実施し,その後に知識の向上を図っていくことで,より有効な支援になる可能性が高いと考えた。
キーワード メタボリックシンドローム,食行動,行動変容,縦断的研究
|
第67巻第12号 2020年10月 生活保護の厳格化は今も支持されているか?-時代効果,社会経済階層,利用するメディアとの関連-山田 壮志郎(ヤマダ ソウシロウ) 斉藤 雅茂(サイトウ マサシゲ) |
目的 生活保護の厳格化志向に関する先行研究では,包括的な従属変数を用いて,社会経済階層および利用するメディアとの関連が分析されてきたが,生活保護の厳格化をめぐる論点は多岐にわたるため,細分化された従属変数によって検討する必要がある。また,生活保護バッシング報道が沈静化する中,厳格化志向の時代的な変化を明らかにすることも重要である。そこで本研究では,生活保護の厳格化志向を細分化して捉えたうえで,それらが時代的にどう変化しているのか,また社会経済階層やメディア接触は厳格化志向にどう影響しているのかを分析することを目的とした。
方法 2014年と2018年に実施した生活保護に関するインターネット意識調査の結果を分析した。生活保護の厳格化に関する6つの側面(高生活保護費,不正受給厳罰化,扶養義務強化,外国人保護禁止,医療費一部負担,ギャンブル禁止)に対する態度を従属変数とした。第1に,2014年と2018年の態度の変化について記述統計量を確認した。第2に,厳格化志向に関連する要因を,時代効果,社会経済階層(職業,世帯税込年収),利用メディアを独立変数とする2項ロジスティック回帰分析により検討した。
結果 高生活保護費,不正受給厳罰化,扶養義務強化の3項目で時代効果が確認され,2014年より2018年の厳格化志向は弱まった。時代効果をコントロールした解析では,高生活保護費と医療費一部負担の2項目は,非正規社員や無職が厳格化志向をもちにくかった。また,不正受給厳罰化とギャンブル禁止の2項目は,年収が高いほど厳格化志向をもちやすかった。信頼できるメディアとしてインターネットを選択する人は,ほとんどの項目で厳格化志向をもちやすかった。特に,外国人保護禁止でその傾向が顕著だった。
結論 生活保護の厳格化志向のうち,高生活保護費,不正受給厳罰化,扶養義務強化は時代の影響が強く近年になって厳格化志向は弱まっている。また,不安定な就労状態にある人は,社会保障の抑制につながる厳格化に賛同しにくく,高収入層は生活保護受給者のモラルの観点から厳格化を求める傾向にある。
キーワード 生活保護,厳格化志向,時代効果,社会経済階層,利用メディア,インターネット調査
|
第67巻第12号 2020年10月 高校生ヤングケアラーの存在割合とケアの状況-埼玉県立高校の生徒を対象とした質問紙調査-濱島 淑恵(ハマシマ ヨシエ) 宮川 雅充(ミヤカワ マサミツ) 南 多恵子(ミナミ タエコ) |
目的 本研究は,2016年に実施した大阪府立高校10校の生徒を対象とした質問紙調査(以下,大阪府高校生調査)とほぼ同様の調査票を用い,子ども自身の認識に基づいたヤングケアラーの実態を把握することを目的として行った。
方法 2018年11月~2019年3月に,埼玉県の公立高校11校において,生徒を対象とした質問紙調査を実施した。調査対象の選定,調査票の配布・回収は高校に依頼した。11校の生徒4,550名が調査対象となった。
結果 4,260名に調査票を配布でき,4,252票の調査票が回収され,本研究の分析対象は3,917票となった。別居している家族も含め,家族にケアを必要としている人(以下,要ケア家族)がいるか否かを尋ねた結果,はいと回答した者が541名(13.8%)であり,そのうち241名(6.2%)は回答者自身がケアをしていると回答していた。障がいや疾病等はなく,幼いきょうだいがいるという理由のみでケアをしている者35名を除外し,残りの206名を対象とした。この206名がヤングケアラーと考えられ,存在割合は5.3%となった。また,負荷が大きいと考えられるヤングケアラーの存在割合は約1%となった。要ケア家族は祖母,母,祖父が多く,要ケア家族が祖母,祖父のみの場合,身体障がい・身体的機能の低下,認知症,病気が多く,母のみの場合,病気や精神疾患・精神障がい・精神的不安定が多かった。ケアの内容は,家事,感情面のサポート,力仕事が多かった。ケアの期間については中央値が3年11カ月であり,少なくとも半数が高校入学前からケアをしていた。ケアの頻度は毎日が最も多く,週4,5日と合わせて半数を超え,ケアの時間は学校がある日,学校がない日ともに1時間未満が最も多いが,2時間以上と回答した者が学校がある日では49名(23.8%),学校がない日では79名(38.3%)いた。ケアをしていることを家族以外の誰かに話したことがあるかを尋ねたところ,ないと回答した者が112名(54.4%)であった。話した相手は,友人が最も多く,次いで親戚,学校の先生であった。
結論 本研究では,高校におけるヤングケアラーの実態(ケアの状況,存在割合等)を示し,これらの結果は大阪府高校生調査と類似するものが多かった。ケアが長期化する者,負担が大きい者,孤立が懸念される者も確認され,教員,支援者による支援の必要性が示唆された。
キーワード ヤングケアラー,介護,手伝い,家族,高校生,質問紙調査
|
第67巻第12号 2020年10月 有職女性の周産期におけるケアニーズとケアの満足度木島 楓(キジマ カエデ) 浦中 桂一(ウラナカ ケイイチ) 朝澤 恭子(アサザワ キョウコ) |
目的 日本では女性就業者数が増加しているが,有職女性に焦点を当てた周産期のケアニーズに関する調査は見当たらない。本研究の目的は,育児中の有職女性における周産期ケアニーズと周産期ケアの満足度を明らかにすることである。
方法 量的横断的記述研究デザインを用いて,0~6歳の保育園に通園する子どもをもつ有職女性278人に無記名自記式質問紙でデータ収集した。首都圏にある7カ所の認可保育園に研究協力を得て,研究対象者に口頭と書面で研究の趣旨を説明した後に,無記名の自記式調査票を配布した。調査内容は属性,周産期ケアの実態,周産期ケアニーズ,周産期ケアの満足度であった。分析はマクネマー検定,マン・ホイットニーのU検定,フィッシャーの正確確率検定を用いた。
結果 調査票を認可保育園に子どもを預けている有職女性の278人に配布し,回収は194部(回収率69.8%)であり,有効回答149部(有効回答率53.6%)を用いてデータ分析を行った。周産期に看護職者に求めるケアニーズとして高かったものは,乳房マッサージが92.6%,産後の心身変化の説明が91.9%,乳房トラブル防止の情報提供が91.9%,ミルクの足し方の説明が89.3%であった。一方,ケアニーズのうち,保育園入園の情報提供が55.0%,育児時間の情報提供が55.0%,労働時間の情報提供が53.7%,職場復帰の情報提供が37.6%であった。周産期ケアの実態よりケアニーズの比率が高かった内容は,育児時間,保育園入園,労働時間の情報提供であった(p<0.001)。ケアの満足度は,看護職者・病院の総合的な対応が65.8%,職場復帰に関する情報提供が0.7%以下であった。
結論 有職女性への職場復帰の情報提供は,育児や母乳に関するケアよりニーズの比率が高く,職場復帰や保育園入園に関する情報提供の満足度が低かった。看護職者には育児や授乳に関するケアにプラスして職場復帰に関する情報提供が求められていることが示唆された。
キーワード 有職女性,助産ケア,量的横断的記述研究,職場復帰,情報提供,周産期
|
第67巻第12号 2020年10月 傾向スコア・マッチング法を用いた中・高年齢層の
|
目的 主観的健康感は,従来の罹患率や死亡率といった客観的健康指標を超えた生活の質をも含む指標として注目されている。主観的健康感とソーシャル・キャピタル(以下,SC)との関連についての既存の研究は一致していない。その理由の一部として不十分な交絡制御の可能性がある。そこで,観察研究での交絡因子の調整において有効な手法である傾向スコア・マッチング法により共変量を調整し,その関連性を解析した。
方法 平成27年度「滋賀の健康・栄養マップ調査」(以下,平27調査)参加者を対象に,40歳未満,または必要変数に欠損のある者を除外した男性1,245人(平均年齢62.9歳),女性1,470人(平均年齢63.2歳)を対象とした。平27調査項目である“地域の人々が互いに助け合っているか”および“あなたの現在の健康状態はいかがですか”の設問をもとにSCの『SCの自覚有り』『SCの自覚無し』および主観的健康感『良好』『良好でない』をそれぞれ定義した。傾向スコア算出モデルは,ロジスティック回帰分析にてAkaike’s Information Criterionを指標とした変数増減法により共変量を選択した。傾向スコアを用いてマッチングしたSCの『SCの自覚有り群』と『SCの自覚無し群』のペア間での主観的健康感良好群の割合を比較した。
結果 傾向スコア算出モデルに選択された共変量は「性別」「年齢」「世帯員数」「住んでいる市町名」「食事内容(野菜摂取量,果実類摂取量,食塩摂取量)」「1年以上の運動習慣」「徒歩10分の場所への移動手段」「高血圧および高脂血症の既往歴の有無」「過去1年間の健診受診有無」「喫煙の肺がんへの影響に関する知識」であった。マッチングにてSCの自覚有り・無し各群1,121人を選んだ。両群における各共変量に有意な差は認められず(p>0.10),また,Standardized Difference scoreの絶対値も0.1未満であった。主観的健康感『良好群』の割合は,SCの自覚有り群では49.3%,SCの自覚無し群では40.8%と有意な差があった(p<0.01)。
結論 傾向スコアを用いた交絡因子の調整を行った結果,SCが住民の主観的健康感と関連があることが示唆された。このことより,充実したSCの構築が健康や生活の質を高める可能性がある。
キーワード 傾向スコア・マッチング法,主観的健康感,ソーシャル・キャピタル
|
第67巻第11号 2020年9月 農村に住む高齢女性の食料品の調達方法と
野邊 政雄(ノベ マサオ) |
目的 多くの高齢者が地方の農山村に住み続けている。高齢者が農山村で暮らし続けるためには,食料品の調達および病院や診療所に通院する交通手段の確保が最低限必要である。本稿では,高齢女性がどのように食料品を調達したり,病院や診療所へ通院するための交通手段をどのように確保したりして,農村での暮らしを維持しているかを明らかにする。
方法 岡山県高梁市宇治町と松原町で2016-17年に高齢女性を対象に個別面接調査を実施した。65歳以上80歳未満の女性を全数調査した。有効票数は139票であった。食料品の調達および病院・診療所への通院の主要な方法を取った回答者の特徴をχ2検定もしくはフィッシャーの直接確率検定で明らかにした。
結果 ①食料品の調達方法について多かった調達方法は,「自分で自動車・バイクを運転して,買い物をした」(59.7%),「同居家族員が運転する自動車に乗って行った」(43.2%),「生協による自宅への配達」(36.7%)であった。②地域外の病院や診療所へ通院するための交通手段で多かったものは,「自分で自動車・バイクを運転して,通院した」(52.5%),「同居家族員が送迎」(39.6%),「バス・タクシーを利用」(19.4%)であった。③高齢女性が自分で自動車を運転できる場合,自ら自動車を運転して地域外で買い物をしていた。しかし,自分で自動車を運転できない場合,同居家族員がいれば,高齢女性は同居家族員に自動車を運転してもらって,地域外で買い物をしていた。移動販売や配達によって食料品を調達している高齢女性には,特定の特性が見られなかった。④高齢女性が自分で自動車を運転する場合,自ら自動車を運転して地域外の病院や診療所へ通院していた。しかし,自分で自動車を運転できない場合,同居家族員がいれば,同居家族員が高齢女性を送迎していた。自分で自動車を運転できず,同居家族員もいなければ,高齢女性はバスやタクシーを利用していた。
結論 ①半数以上の高齢女性は自分で自動車やバイクを運転して,買い物や通院をしていた。これは,68.3%の高齢女性が自動車やバイクを運転できたためである。多くの高齢女性が運転免許証を保有していたので,移動手段の確保は以前ほど深刻な問題ではなかった。②同居家族員は高齢女性の食料品調達や病院・診療所への通院で大きな役割を果たしていたのに対し,別居している近親者はあまり役立っていなかった。③近所の人が高齢女性の食料品の調達や病院・診療所への通院を支援することはあまりなかった。
キーワード 農村,高齢女性,食料品調達方法,通院方法,交通手段,相互扶助
|
第67巻第11号 2020年9月 労働者のインターネット依存と痩せおよび肥満との関連中村 優(ナカムラ ユウ) 榊原 文(サカキハラ アヤ) |
目的 近年,急速なインターネット(以下,ネット)の普及の一方で,ネットに過度に没入し,対人関係や日常生活への弊害が生じても,ネットに精神的に依存するネット依存が問題視されている。ネット依存の先行研究は思春期に焦点を当てたものが多く,壮年期のネット依存が健康や労働にどのような影響を及ぼしているのかは明らかにされていない。そこで本研究は,労働者を対象に,生活習慣病のリスクを高める痩せと肥満に焦点を当て,ネット依存との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 2019年8~9月,A製造業事業所の従業員530人を対象に,無記名自記式質問紙調査を行った。調査内容は,年齢,性別,身長,体重,ネット依存度,生活習慣である。ネット依存度は,Young’s Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction score(YDQ)を使用し,問題のあるネットユーザーとされるYDQ3点以上をネット依存と判定した。痩せ,肥満の評価は,BMI([体重(㎏)]÷[身長(m)2])を使用し,18.5未満を「痩せ」,25以上を「肥満」と判定した。男女別に痩せ・肥満を従属変数,ネット依存を独立変数として単変量ロジスティック回帰分析を行い,その後,睡眠時間,運動習慣,飲酒習慣等を共変量として投入し,多変量ロジスティック回帰分析を行った。
結果 調査票の回収数は384枚(回収率72.5%)であった。YDQ3点以上は全体で19.3%,男性19.8%,女性17.7%であった。痩せは,全体で5.5%,男性4.5%,女性8.3%であり,肥満は,全体で21.9%,男性25.3%,女性11.5%であった。痩せとネット依存の多変量ロジスティック回帰分析の結果,ネット依存の男性従業員がそうでない従業員と比較して痩せとなる調整オッズ比は,3.91(95%信頼区間[CI]:1.14-13.49)であったが,女性の痩せとネット依存に有意な関連は認められなかった(調整オッズ比=2.23(95%CI:0.29-17.19))。肥満とネット依存の多変量ロジスティック回帰分析では,男女ともに有意な関連は認められなかった(調整オッズ比=0.59(95%CI: 0.27-1.31),2.62(95%CI:0.47-14.52))。
結論 ネット依存の男性従業員はそうでない従業員と比較して約4倍痩せになることが示された。その理由として,ネットに夢中になるあまり食への関心が低下し,食欲減退により痩せになることが推察される。
キーワード インターネット依存,労働者,痩せ,肥満,BMI,生活習慣病
|
第67巻第11号 2020年9月 成人喫煙率の都道府県比較および経年変化-国民生活基礎調査の集計表より-冨岡 公子(トミオカ キミコ) |
目的 国民生活基礎調査の集計表を用いて,成人喫煙率の都道府県比較および経年変化を統計解析した。
方法 e-Statで提供されている2001年~2016年までの国民生活基礎調査の集計表を用いた。「昭和60年モデル人口」を基準集団とした年齢調整喫煙率(直接法)で都道府県比較を行った。年次推移に関する分析は,各調査年の年齢調整喫煙率と標準誤差を用いて,Joinpoint regressionで検定を行った。本研究において,喫煙状況不詳の者は解析対象外とし,男女別に分析した。2016年は震災の影響で熊本のデータが含まれていないため,都道府県比較は2013年を用いた。
結果 2016年の全国の粗喫煙率は男性31.7%,女性9.7%であった。2013年の年齢調整喫煙率(%)は,全国平均が男性37.3(95%信頼区間(CI)=36.9~37.8),女性12.9(12.6~13.1),都道府県別にみると,男性では青森45.4(40.9~49.8)が最も高く,奈良32.4(28.3~36.5)が最も低く,女性では北海道21.5(19.9~23.2)が最も高く,奈良8.5(6.2~10.7)が最も低かった。性別年齢調整喫煙率に関して,男女共に低いのは近畿地方,男女共に高いのは北海道および東北地方,女性のみ高いのは都市圏,男性のみ高いのは九州地方および中国地方に多い傾向がみられた。Joinpoint regressionの結果,2001年以降,年齢調整喫煙率は男女共に有意に減少していた[2001年~2016年平均年変化率(%):男性 -8.4(95%CI:-9.1,-7.7),女性 -7.3(95%CI:-9.7,-4.9)]。都道府県別にみると,男性では石川以外の都道府県では有意な減少傾向を認めたが,女性では47都道府県中15の自治体は有意な増減が確認できなかった。
結論 国民生活基礎調査の集計表を利用することで,高齢化の影響を調整した成人喫煙率を性別に都道府県比較したり,経年変化を検討することができた。一方,集計表では千人単位のため500人未満は「0」表記となっており,人口の少ない都道府県や女性の年齢階級別喫煙率の算出における限界が示唆された。今後,個票データを用いて,年齢以外の要因(学歴など)や個人レベルでの喫煙関連要因を検討する必要がある。
キーワード 国民生活基礎調査,e-Stat,公的統計,成人喫煙率,年齢調整,年次推移
|
第67巻第11号 2020年9月 在院日数の短縮に影響を及ぼす主要診断群分類と診療行為について中島 尚登(ナカジマ ヒサト) 矢野 耕也(ヤノ コウヤ) |
目的 Diagnosis Procedure Combination(DPC)制度では,在院日数の短縮が高く評価されるため,在院日数の短縮に影響する主要診断群分類(Major Diagnostic Category:MDC)と診療行為を検討した。
方法 2012-2017(以下,’12-’17)年のDPC対象病院(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ群)とDPC準備病院(以下,準備病院)のMDC比率,DPC算定病床数/準ずる病床数,手術数,化学療法数,放射線療法数,救急車搬送数,救急医療入院数,全身麻酔数および在院日数を用い,在院日数を目的変数として重回帰分析で検討した。
結果 ①Ⅰ群では’12年のMDC04(呼吸器系疾患),’15年のMDC06(消化器系疾患,肝臓・胆道・膵臓疾患),’16年のMDC15(小児疾患),Ⅱ群では’15-’16のMDC05(循環器系疾患),’16年のMDC02(眼科系疾患),Ⅲ群では’12-’17年のMDC02とMDC15,’12と’14-’17年のMDC03(耳鼻咽喉科系疾患),’12-’15と’17年のMDC12(女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩),’12-’14と’17年のMDC05,’12年のMDC14(新生児疾患,先天性奇形),’17年のMDC09(乳房の疾患),準備病院では’16-’17年のMDC02,’12-’13と’16-’17年のMDC03,’12-’13と’17年のMDC05,’13と’17年のMDC06,’17年のMDC07(筋骨格系疾患)とMDC11(腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患),’12-’13,’15と’17年のMDC14,これらが在院日数短縮に影響した。また’12-’17年を通じて,Ⅰ群ではMDC08(皮膚・皮下組織の疾患),Ⅱ群ではMDC01(神経系疾患),Ⅲ群ではMDC01とMDC04,MDC13(血液・造血器・免疫臓器の疾患),MDC16(外傷・熱傷・中毒),これらが在院日数延長に影響した。②Ⅰ群,Ⅱ群,準備病院ともに’13-’17年を通じて,手術件数は在院日数短縮に影響した。またⅠ群では’12-’14年と’16年の救急車搬送件数,Ⅱ群では’14年の放射線療法件数,’12年救急入院,準備病院では’16-’17年の化学療法件数,これらが在院日数短縮に影響した。
結論 在院日数の短縮に影響するMDC比率の調整が評価を高くする要因となる。
キーワード 在院日数,Diagnosis Procedure Combination(DPC)対象病院,主要診断群分類(Major Diagnostic Category:MDC),機能評価係数Ⅱ,効率性指数,重回帰分析
|
第67巻第11号 2020年9月 履歴書等データに基づく認知症対応型共同生活の
渡邊 裕文(ワタナベ ヒロフミ) |
目的 介護職の早期離職者数の削減を目的として,認知症対応型共同生活介護の施設への介護職としての入職希望者について,履歴書データを用いて,採用者・不採用者,早期離職者の特性を分析した。
方法 Aグループホームに開設当初より2018年3月までに残されていた介護職としての入職希望者の履歴書に書かれている内容を用いて分析を行った。本分析では,全履歴書データ(328通)のうち,開設当初で職員を多く採用していた3年間,性別,年齢に欠損のあるデータを除いた189名分の履歴書データを用いた。「採用・不採用」「勤続年数」を従属変数とし,履歴書に書かれている「性別」「年齢」「学歴」「転職回数」「福祉転職回数」「保有資格」の履歴書データを独立変数としてロジスティック回帰分析を行った。また,志望動機欄の記載内容について,テキストマイニングによる分析を合わせて行った。
結果 採用・不採用について分析の結果,年齢,保有資格について,採用・不採用との間に統計学的に有意な関連が認められた。他の独立変数の影響を除いて,30歳代に比べて20歳代以下,40歳代がそれぞれ5.52倍(95%CI:1.75-17.35),3.02倍(95%CI:1.04-8.72)採用されやすいことがわかった。統計学的に有意ではないが,50歳代以上は2.88倍(95%CI:0.93-8.92)採用されやすくなっている。テキストマイニングでは,「認知症」「高齢者」「家庭」など認知症対応型共同生活介護の本質に関するキーワードを記載している人が採用されていた。早期離職について分析の結果,保有資格との統計学的に有意な関係がみられ,ヘルパー等の資格を持つものは,6.93倍(95%CI:1.39-34.49)早期離職しやすいという結果が得られた。また,統計学的に有意ではないが,福祉関係の転職回数が2回以上の人は0.61倍,つまり福祉関係の転職経験が1回以下の人は1.64倍早期離職しやすくなっている。性別,年齢,学歴については,統計学的に有意な関係はみられなかった。テキストマイニングでは,「認知症」「人生」「関わる」「力づける」「施設見学」といった他者との関わりや理解,意欲に基づくと考えられる単語を記載している人が,早期離職していなかった。
結論 介護職の早期離職には,これまで施設の対応や施設内での人間関係が論じられてきた。今回の分析で,入職希望者の個人的特性や保有資格,転職経験との関連性が確認され,早期離職を減らすためには,介護職へ入職する前の段階での教育や体験の必要性が示唆された。
キーワード 認知症対応型共同生活介護,個人の特性,介護職,保有資格,転職回数,ロジスティック回帰分析
|
第67巻第11号 2020年9月 主観的経済状況と幼児の未処置う蝕の関連-仙台市認可保育所における横断研究-鎌田 由香(カマダ ユカ) |
目的 保護者の経済状況と幼児の未処置う蝕の関連とその要因について検討した。
方法 平成27年10月~12月に,仙台市内の保育所に通う4歳児の保護者を対象として,質問紙調査を実施した。経済的なゆとりを「ゆとりあり」「どちらともいえない」「あまりゆとりはない」「全くゆとりはない」に分類した。処置をしたう蝕のある者とう蝕のない者を「未処置う蝕なし」,未処置う蝕のある者を「未処置う蝕あり」とした。食物摂取頻度調査から主成分分析を行って,同定された食事パターンを使用した。経済状況を説明変数,未処置う蝕を従属変数とした多変量ロジスティック回帰分析を用い,オッズ比(95%信頼区間)を算出した。
結果 調査対象2,738人のうち解析対象は1,948人であった。経済状況は「ゆとりあり」30.6%,「どちらともいえない」32.1%,「あまりゆとりはない」28.9%,「全くゆとりはない」8.4%であった。「未処置う蝕あり」の幼児は309人で,経済的な「ゆとりあり」23.6%,「どちらともいえない」30.4%,「あまりゆとりはない」31.4%,「全くゆとりはない」14.6%であった(p<0.001)。多変量ロジスティック回帰分析の結果,「ゆとりあり」を基準としたオッズ比は「どちらともいえない」1.37(0.94-1.98),「あまりゆとりはない」1.35(0.92-1.97),「全くゆとりはない」2.17(1.32-3.58)であった(p=0.006)。未処置う蝕に影響を与える因子は,「遅い起床時間・遅い就寝時間」1.52(1.05-2.21),「幼児と保護者朝食欠食あり」1.79(1.22-2.64),「第2食事パターン(甘い食品や飲料,インスタント食品が多い)」1.24(1.10-1.41)であった。
結論 経済状況が厳しい保護者の子どもは,未処置う蝕の有症率が高かった。幼児の起床・就寝時間,朝食欠食やインスタント食品が多い食事などは,経済状況に関わらず未処置う蝕の有症率と関連していた。従って,幼児の未処置う蝕を減らしていくためには,経済状況の改善は重要であるが,それと同時に基本的な生活習慣の形成と,食事全体の質に着目した栄養の教育が重要であると考えられた。
キーワード 主観的経済状況,幼児,未処置う蝕,起床・就寝時間,朝食欠食,食事パターン
|
第67巻第8号 2020年8月 社会的養護における専門職の人材育成に関する実態と課題-職場研修のニーズを中心に-小林 理(コバヤシ オサム) 中原 慎二(ナカハラ シンジ) 新保 幸男(シンボ ユキオ) |
目的 本研究は,社会的養護分野における常勤専門職の「働く環境」などの自己評価を通じて,職場環境の実態を把握し,人材育成の課題を考察することを目的とした。
方法 調査対象は,全国の乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設の保育士・児童指導員などの常勤専門職の全員として,郵送法による無記名自記式調査を行った。調査項目は,「自らの専門性」「仕事への思い」「働く環境」など50項目を設定し,それぞれ1~10の数字(得点が高い方が高評価)で自己評価の回答を得た。調査期間は,2018年2月から3月であった。
結果 2018年3月末時点で回収された調査票のうち,期限を過ぎて返送された調査票を含み,すべての調査項目が有効回答であった調査票5,000通を対象として分析を行った。調査項目の50項目の平均得点は6.18点,標準偏差は2.32点であった。10点満点で8点以上と高い得点の項目は,「児童を理解しようとしている」(8.47点),「自らの専門性をより高めようと思っている」(8.35点)であった。一方,低い得点の項目は,「職場外でスーパービジョンを受ける機会が十分ある」(4.70点),「地域資源の活用に関して,自らの専門職としての能力は高い」(4.78点),「制度理解に関して,自らの専門職としての能力は高い」(4.81点),「自分の年収に満足している」(4.86点)であった。職場環境についての項目の合計点は,経験年数が低い群で低く,年数とともに得点が上がっていた。結果を年齢,経験年数の平均値を参考に,グループ化して分布をみた。「35歳以上45歳未満で経験5年未満」「45歳以上で経験5年未満」の者に,職場内外の研修や勉強会の機会が十分でない。職場内のスーパービジョン(SV)は,調査項目全体に相関があり,特に職場への誇り,専門性を高めやすいか,に相関があった。職場内SVは,年齢が低く経験が浅い群で課題がある。
結論 職場環境は,本来,新人にとって手厚くあるべきだが,本研究の結果から,年齢や経験年数が低い群に充実と捉えられていない傾向がみられた。これは,年齢が若く経験年数の少ない「新人組」の「仕事の継続」に壁となっていると考えられる。職場内外のSVの機会は,年齢は低いが経験年数が少なくない「若手組」と,年齢は低くないが経験年数が少ない「転職組」に十分ではない。特に,「転職組」は,内外の研修会や勉強会の課題を今後さらに調査していく必要が示唆された。
キーワード 社会的養護,常勤専門職,職場環境の実態,人材育成の課題,スーパービジョン(SV)の機会
|
第67巻第8号 2020年8月 農林業への関わりと助け合い活動への
服部 真治(ハットリ シンジ) 市田 行信(イチダ ユキノブ) |
目的 中山間地域等の農村部の特徴であり,人的ネットワークや自治活動に密接に関係している農林業の活動に着目し,農林業に関わる地域住民が,それに関わらない地域住民と比較して,どの程度生活支援の意識を持っているかを検証することを目的とした。
方法 鳥取県智頭町において2017年7月に行われた介護予防・日常生活圏域ニーズ調査をもとに,要介護状態でない高齢者2,452人に対し自記式調査票を用いて郵送調査を行った。このうち,年齢と性別に欠損値のない有効回答1,358票(55.4%)を対象として分析を行った。統計的分析は,目的変数を助け合い活動への参加意識,説明変数は農林業への関わりとし,年齢,性別,経済状況,認知機能,身体機能を調整変数としたロジスティック回帰分析を行った。また,助け合い活動への参加意識の有無と,地域活動への参加状況を分析した。
結果 年齢,性別,経済状況,身体機能,認知機能について調整した上で,助け合い活動(全体・無償)への参加意識と農林業への関わりとの関連を分析した結果,農林業への関わりがある人ほど,助け合い活動への参加意識があるという結果が得られた。また,地域活動のうち,「ボランティアのグループ」「スポーツ関係のグループやクラブ」「趣味関係のグループ」に関し,助け合い活動への参加意識がある群は,参加意識のない群に対し有意に参加者が多いという傾向がみられた。
結論 本研究で,農林業への関与は,助け合い活動への参加意識の高さに関連することが示された。
キーワード 高齢者,助け合い活動,中山間地域,農林業,生活支援,ボランティア
|
第67巻第8号 2020年8月 男女別にみた都市旧ニュータウンに居住する
相原 洋子(アイハラ ヨウコ) 前田 潔(マエダ キヨシ) |
目的 高齢化が進展する都市旧ニュータウンに居住する高齢者を対象に,認知症になったときの居場所,支援に対する希望について,男女別に実態を把握することを目的とした。
方法 1960年代に住宅地開発が行われた兵庫県内最古のニュータウンの明舞地区に居住する65歳以上の人全員を対象に,半構造化質問紙を用いた横断調査を2019年5~9月に実施した。認知症になったときに住みたい場所として,自宅での暮らし,施設への入居など5つの項目から選択してもらい,また認知症・軽度認知障害(MCI)になったときに必要と思う支援として,構造化した5つの支援項目について必要の度合いならびに自由記述による回答を得た。調査協力の得られた2,269人(回収率22.4%)のうち,性別の記載がある2,252人を分析対象とし,居場所と支援希望をアウトカムとして単変量解析ならびに内容分析の手法を用い,男女で比較を行った。
結果 認知症となったときの居場所は,男性は「今の家に住み続けたい」の回答が4割と最も多く,女性は「施設・サービス付き高齢者住宅に入居」「今の家に住み続けたい」を希望する人が35%とほぼ同数であった。居宅生活を希望する人は,男女ともに家庭内介護者がいること,男性のみに持ち家(戸建)に住んでいる,近所付き合いをしている人に多い傾向が示された。認知症・MCI診断時の支援として,定量分析の結果は「日常生活支援」を希望する人が最も多かった。定性分析の結果は,想像できない・わからないといった「不明」に関する記述が全体ならびに男性に最も多く,女性高齢者は施設入所,在宅生活の継続といった「居場所」に関する内容が多く記述されていた。
結論 認知症時の居場所の希望として,男性は自宅,女性は施設を希望する傾向がみられた。また希望する支援においても女性は「居場所」に関する記載が多く,介護環境の性差がこのような結果につながったと考える。一方の男性は,支援を不明とする回答が多かった。認知症時の住まいや住まい方を本人が選択していけるように,住宅や介護サービスの情報提供,相談場所や介入方法など,性差に着目した認知症施策や制度の設計が求められる。
キーワード エイジング・イン・プレイス,支援,性差,ニュータウン,認知症,高齢者
|
第67巻第8号 2020年8月 栃木県における画像検査の地域偏在岡野 員人(オカノ カズト) |
目的 本研究は,栃木県における診療放射線技師の地域偏在状況と画像検査で広く使われているCTおよびMRIの装置数や患者数を調査し画像検査の需給状況について調査することを目的とした。
方法 対象は,2017年の医療施設調査からCTおよびMRIの「装置数」および「患者数」,「診療放射線技師数」とした。また,比較対象として「医師数」を用いた。各データは栃木県の6つの二次医療圏ごとに集計を行い,地域偏在の指標の一つであるジニ係数と集中度を示すハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)を算出し比較した。
結果 人口10万対CT装置数の最少は県北9.2台,最多は宇都宮および県南11.7台であった。人口10万対MRI装置数の最少は県東2.7台,最多は県南6.8台であった。一方,人口10万対CT患者数の最少が県東1,261人,最多は県南2,710人であった。人口10万対MRI患者数の最少は県東468人,最多は宇都宮1,333人であった。人口10万対診療放射線技師数の最少は県東22.4人,最多が県南53.7人であった。装置数および患者数,診療放射線技師数のジニ係数は医師と比較して低値であり,医師よりも均一な分布を示した。特にCT装置数のジニ係数は0.038と高い均一を示した。一方で,各対象のHHIは人口と比較して高値を示しており,すべてにおいて特定の地域に集中している傾向にあった。
結論 栃木県における画像検査の需給状況について二次医療圏の人口や地理的要因により地域偏在状況や地域の特徴を捉えたが,画像検査の医療資源の適正な配置については他の都道府県との比較や継続的な調査が必要である。
キーワード 画像検査,医療資源,地域偏在,診療放射線技師,ジニ係数,ハーフィンダール・ハーシュマン指数
|
第67巻第8号 2020年8月 大阪府内市町村における大腸がん検診の個別受診勧奨の実態濱 秀聡(ハマ ヒトミ) 田淵 貴大(タブチ タカヒロ)中山 富雄(ナカヤマ トミオ) 宮代 勲(ミヤシロ イサオ) |
目的 大阪府のがん検診受診率は低い。受診率の向上を目的とした個別受診勧奨が推奨されているが,その実態はほとんどわかっていない。そこで,市町村が実施する大腸がん検診の個別受診勧奨の実態を把握し,勧奨方法とがん検診受診率との関連について検討した。
方法 大阪府が府内全43市町村に対して実施した2017年度の大腸がん検診における個別受診勧奨と検診受診率に関する調査データを分析した。各市町村の勧奨方法を対象年齢に応じて4群(40~69歳の年齢すべて・特定の年齢層・節目の年齢・その他)に分類し,個別受診勧奨の実態を把握した。さらに市町村における勧奨方法と受診率の関連について検討した。
結果 個別受診勧奨を実施していた市町村は39(90.7%)であった。そのうち「40~69歳の年齢すべて」に勧奨していた市町村数は4,「特定の年齢層」は7,「節目の年齢」は19,「その他」は9であり,節目の年齢に勧奨している市町村が多かった。個別受診勧奨実施の群では,受診率にバラツキがあるものの,未実施の群と比べて受診率は有意に高く,その差は8.0ポイントであった(p=0.017)。勧奨方法4群と未実施をあわせた5群間で受診率を比較した結果,40~69歳の年齢すべてに勧奨している群は,他の4群と比べて受診率が有意に高く,その差は10ポイント以上であった(特定の年齢層:p=0.028,節目の年齢:p=0.004,その他:p=0.032,未実施:p=0.001)。
結論 大阪府内の多くの市町村で,がん検診の個別受診勧奨が実施されていたが,対象者全員に対する勧奨は少なかった。対象者への勧奨ができるよう,国や都道府県による検診体制整備の支援が必要だと考えられた。
キーワード がん検診,個別受診勧奨,受診率,大腸がん,検診体制整備の支援
|
第67巻第8号 2020年8月 非喫煙者における家庭での受動喫煙と高血圧の関連-東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホート調査より-平田 匠(ヒラタ タクミ) 小暮 真奈(コグレ マナ) 成田 暁(ナリタ アキラ)土屋 菜歩(ツチヤ ナホ) 中村 智洋(ナカムラ トモヒロ) 目時 弘仁(メトキ ヒロヒト) 中谷 直樹(ナカヤ ナオキ) 丹野 高三(タンノ コウゾウ) 菅原 準一(スガワラ ジュンイチ) 栗山 進一(クリヤマ シンイチ) 辻 一郎(ツジ イチロウ) 呉 繁夫(クレ シゲオ) 寳澤 篤(ホウザワ アツシ) |
目的 近年,受動喫煙が高血圧と関連することを示す疫学研究が散見されるが,関連を示さない報告もあり,一定の結論は得られていない。また,受動喫煙に関して10年前と最近1年間の受動喫煙状況を反映した検討も行われていない。そこで,本研究では非喫煙者を対象とした家庭での10年前および最近1年間における受動喫煙の組み合わせと高血圧有病との関連につき,国内の大規模コホートデータを用いた検討を行った。
方法 本研究は東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホート調査のベースライン調査データ(2013年5月~2016年3月に実施)を用いた断面研究である。宮城県在住で同調査のベースライン調査を特定健診共同参加型で受けた非喫煙者を解析対象とし,全解析対象者を10年前と最近1年間の家庭における受動喫煙の有無の組み合わせにより4群に分類した。家庭における10年前・最近1年間の受動喫煙の組み合わせと高血圧有病との関連を多変量ロジスティック回帰分析により検討し,10年前・最近1年間ともに受動喫煙のない者を参照群とした他群の高血圧有病に対するオッズ比と95%信頼区間を算出した。
結果 本研究の解析対象者は15,381名(男性2,370名,女性13,011名)であり,高血圧の有病者は5,603名(36.4%)であった。最近1年間に家庭での受動喫煙を認めた者は1,961名(12.7%)であり,そのうち1,775名(90.5%)が10年前にも家庭での受動喫煙を認めた。多変量解析の結果,10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認める者では,10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認めない者と比較して,年齢・BMI・飲酒歴などの高血圧の危険因子と独立し,高血圧の有病と有意な正の関連を認めた(オッズ比1.15,95%信頼区間1.02-1.29)。男女別の解析では,10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認める女性が10年前・最近1年間ともに家庭での受動喫煙を認めない女性と比較し,高血圧の有病と有意な正の関連を認めた(オッズ比1.15,95%信頼区間1.02-1.30)。
結論 非喫煙者において家庭での長期間の受動喫煙があると年齢・BMIや飲酒歴などの古典的な高血圧の危険因子と独立して高血圧の有病リスクが有意に上昇した。公衆衛生上の観点からは家庭での受動喫煙の防止が肺がん・慢性閉塞性肺疾患や虚血性心疾患等の予防だけでなく血圧値の低下にも寄与する可能性が示唆された。
キーワード 受動喫煙,高血圧,疫学研究,非喫煙者,家庭
|
第67巻第7号 2020年7月 人生の終盤に向かう過程の事前準備支援に関する
島田 千穂(シマダ チホ) 伊東 美緒(イトウ ミオ) 児玉 寛子(コダマ ヒロコ) |
目的 人生の終盤を支えるエンドオブライフケアの質向上のためには,ケア利用者の意思に添ったケア計画が求められる。本研究は,利用者や家族との人生の終盤に向けた対話へのケアマネジャーの関与の実態とその程度に関連する要因を把握することを目的とした。
方法 居宅介護支援事業所5,612カ所に調査票を郵送し,管理者と最も多くの利用者を担当する所属ケアマネジャー最大3名を対象として自記式調査を実施した。返信用封筒を個別に添付し,回収した。調査内容は,人生の終盤に向けた対話への関与の程度,ケアマネジャーの属性,担当利用者属性(要介護度,独居,訪問診療利用者,認知症利用者など),ケアマネジャーの介護規範意識である。
結果 人生の終盤に向けた対話へのケアマネジャーの関与には個人差があり,担当する利用者の6割以上と対話経験があるケアマネジャーは,回答者3,320名のうち25.7%であった。一方,6割以上の利用者家族との対話は,36.2%が実施していた。ロジスティック回帰分析の結果,利用者本人との対話は,経験年数に加えてケアマネジャーの介護規範意識と有意に関連し,「家族が看取りにかかわるべき」と考える人ほど本人との対話は少なかった(p=0.038)が,利用者家族との対話と介護規範意識とは有意な関連が見られなかった。
結論 人生の終盤に向けた事前の対話は,本人より家族と実施しやすく,本人との対話はケアマネジャーの介護に対する規範意識と関連し,家族との対話はケアマネジメント業務上の必要性に基づく動機で開始されやすい可能性が考えられる。本人との事前対話の推進のためには,規範意識の変容をサポートする介入の必要性が示唆されたと考える。エンドオブライフケアを家族のみの責任としてとらえるのではなく,本人の意思に基づき社会で担うという考え方に基づくことで,事前準備のための対話への関与を高められる可能性があるだろう。本研究は,限られた地域のケアマネジャーを対象とした点で限界があるが,人生の終盤に向けた事前の対話に関与しているケアマネジャーの実態を示した初めてのデータとして価値があると考える。
キーワード エンドオブライフケア,アドバンスケアプランニング,ケアマネジメント,対話,ケアマネジャー,人生の終盤
|
第67巻第7号 2020年7月 健康寿命および平均寿命に関連する高齢者の生活要因の特徴細川 陸也(ホソカワ リクヤ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) 山口 知香枝(ヤマグチ チカエ)岡田 栄作(オカダ エイサク) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) |
目的 健康日本21(第二次)では,「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」が目標のひとつに掲げられている。効果的な取り組みを実施するためには,市区町単位の社会参加などのアプローチ可能な地域の特徴を明らかにしていく必要がある。そこで,本研究は,健康寿命および平均寿命に関連する高齢者の生活要因の特徴を地域レベルで検証することを目的とした。
方法 本研究は,JAGES(Japan Gerontological Evaluation Study,日本老年学的評価研究)の一環として,2013年の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に参加した全国85市区町を分析対象とした。地域レベルの指標として,高齢者の生活要因を社会参加,うつ傾向などの各割合とし,また,健康寿命・平均寿命を健康寿命の算定プログラムを用いた値とし,市区町単位で算出した。
結果 市区町を分析単位とし,健康寿命と平均寿命を従属変数,高齢者の生活要因を説明変数とし,種類ごとに個別に投入して重回帰分析を実施したところ,男性では,趣味の会への参加,スポーツの会への参加,ボランティアの会への参加,外出の機会,歯科医療機関への通院割合の高い市区町ほど健康寿命と平均寿命が長く,うつ傾向,喫煙の割合の高い地域ほど健康寿命と平均寿命が短い傾向がみられた。一方,女性に関しては,趣味の会への参加,スポーツの会への参加,ボランティアの会への参加,歯科医療機関への通院が有意な関連を示した。
結論 社会参加や歯科医療機関への通院など健康寿命と平均寿命に関連していた高齢者の生活の特徴にアプローチすることは,市区町などにおける健康寿命・平均寿命の延伸に寄与する可能性が示唆された。
キーワード 健康寿命,平均寿命,高齢者,生活要因,地域レベル
|
第67巻第7号 2020年7月 一人暮らし高齢者に対する
|
目的 本研究では,一人暮らし高齢者に対する支援において,介護支援専門員が感じている困難感についての実態を明らかにした。
方法 調査対象者は,一人暮らし高齢者を担当した経験のある介護支援専門員である。調査対象は大阪府下の居宅介護支援事業所と地域包括支援センターから2,500カ所を無作為に抽出し,1カ所につき1名の介護支援専門員とし,調査期間は平成31年1月30日~同年2月25日とした。質問紙調査は自記式質問紙を用いた郵送調査を行った。分析方法は,単純集計と記述統計量を用いた。
結果 回収された質問紙数は909票で,回収率は36.4%であった。介護支援専門員が感じる一人暮らし高齢者支援における困難感は,大きく2つに分けることができる。1つは,「対人支援を進めていく際の困難感」であり,もう1つは,「地域資源の不足による困難感」である。「対人支援を進めていく際の困難感」の代表的な困難感に,一人暮らし高齢者や別居家族の支援拒否に対する対応の困難感があげられ,「地域資源の不足による困難感」の代表的な困難感に,一人暮らし高齢者を支援していく際に重要となるキーパーソンの不在や地域住民に支援を求める際に生じる困難感があげられた。
結論 一人暮らし高齢者を支援していく際,介護支援専門員が感じる困難感を軽減していくための対応策では,一人暮らし高齢者事例に個別性が伴うため,容易な軽減策を見いだすことは難しいが,①地域包括支援センターの主任介護支援専門員によるスーパービジョンや後方支援,②地域ケア会議等の有効活用,③地域資源不足解消のための新たな制度設計や制度の見直し等を組み合わせることで適切な軽減策を見いだすことができると考える。
キーワード 介護支援専門員,支援困難感,一人暮らし高齢者,対人支援,地域資源,支援拒否
|
第67巻第7号 2020年7月 職員主体性の尊重とパーソンセンタードケア実践との関連-特別養護老人ホームと認知症型グループホームの介護職員に対する調査より-鄭 尚海(テイ ショウカイ) |
目的 本論文は,認知症ケアにおいて重要な役割を果たしている特別養護老人ホームと認知症型グループホームをフィールドにしながら,近年注目されているパーソンセンタードケア実践をよりよく行うための方策を提案することを目的とし,そこで働く職員の主体性の尊重とパーソンセンタードケア実践との関連を検討した。
方法 WAMNETに登録されている全国の特別養護老人ホームと認知症型グループホームのうち,それぞれ1,000カ所を無作為に抽出し,1施設につき1部,計2,000部の無記名の自記式調査票を各施設宛てに郵送した。回答者は,現在の施設において1年以上の認知症介護経験があり,現在も認知症介護に直接携わっている介護職員1名とし,その選出は各施設に一任することとした。分析は,単純集計と多重指標モデルを用いて,必要項目に欠損値のない556票を分析対象とした。
結果 単純集計において,職員主体性の尊重は,全体平均得点が3.50点(5点満点)であり,パーソンセンタードケアの実践は3.96点(5点満点)であった。また,パーソンセンタードケアの実践を従属変数,職員主体性の尊重を独立変数とした多重指標モデルは,いずれの指標においても統計学的な許容水準を満たしており,決定係数(説明率)が0.42と中程度であった。さらに,この多重指標モデルを用いて検証した結果,主体性が尊重されると感じる職員ほど,パーソンセンタードケア実践度が高かった。
結論 本研究の結果,パーソンセンタードケア実践をよりよく行うためには,職員主体性の尊重が重要であると示唆された。また,職員主体性の尊重を行う際に参考となる過程を提示し,重要となる中間管理職に対する研修の実施やスーパービジョン体制の構築を提言した。
キーワード 職員主体性の尊重,パーソンセンタードケア,職場環境,介護職員
|
第67巻第7号 2020年7月 高齢者の社会貢献活動の取り組みの現状と
|
目的 地域の生活課題の解決には高齢者の力がより活用されることが目指されているという背景から,本論文の目的は,高齢者の社会貢献活動の取り組みの状況,社会貢献活動に取り組めるきっかけや条件を性別および社会貢献活動(以下,活動への意向)への意向別に検討し,高齢者の社会貢献活動の取り組みが進展するための促進方法について考察することである。
方法 東京都A市にある集合住宅(分譲マンションと都営住宅)に居住する高齢者に,事前に自治会長に許可を得た上で無記名自記式質問紙調査を行った。調査期間は,2017年6月20日から10月15日である。分析対象者数は,性別の回答があった330人である。性別や活動への意向別の差の比較検討ではχ2検定を行った。
結果 本研究において,社会貢献活動をしたいと思っている高齢者は男女とも6割であったが,実際には7割の人が何らかの社会貢献活動を行っており,多くの高齢者において取り組まれていることが確認された。自治会活動が男女ともに最も多く取り組まれていた。シルバー人材センターを通した活動は男性で有意に多く行われていた。活動に取り組めるきっかけとして男性で一番多かったのは「行政や社協などによる募集」であり,女性で多かったのは「家族や他者からの勧め・誘い」であった。活動に取り組める条件では男女ともに「友人・知人と一緒にできること」と「自らの健康状態がよくなること」が多かったが,「通う手段が確保されること」は女性に有意に多かった。活動への意向別にみると,活動への意向がある人の方がそうでない人に比べ実際に活動に取り組んでいる傾向があった。活動への意向があまりない人においても,きっかけや条件によって取り組めると感じている人がいることが明らかになった。
結論 社会貢献活動に取り組む人を増やすための視点としては,活動への意向のある人を情報発信の強化や研修会の開催,活動への誘いを通してより実際の活動につなげていくこと,また活動への意向があまりない人に対しては,まずきっかけをつくり,活動に参加してもらうことで自らの役割を認識してもらうことや地域課題を学ぶ学習会などを通して活動に関心を持ってもらうことが有効である。社会貢献活動をする際に友人と一緒にできることや同世代と交流できることを取り組める条件としてあげている人が多かったことから,その点も考慮した活動の展開が求められる。また特に女性においては通う手段が確保されることも条件としてあげられており,活動に参加するための送迎も含めた支え合い活動も今後より重要である。
キーワード 社会貢献活動への意向,社会貢献活動に取り組めるきっかけ・条件,高齢者,地域の生活課題
|
第67巻第7号 2020年7月 高齢者のICT利用状況の変化要因について-縦断調査データを用いて-深谷 太郎(フカヤ タロウ) 小林 江里香(コバヤシ エリカ) |
目的 高齢者のインターネット利用率は年齢が高くなるにつれて低下するが,60代では7割を超えており,年々増加傾向にある。しかし,横断調査の繰り返しでは,高齢者集団の中で利用者が増えているのか,それとも利用率の高い年齢層が順次高齢者の仲間入りをしているのかは不明である。そこで,同一人物を対象とした縦断調査のデータを用いて,高齢者のICT(電子メール,インターネット)の利用状況の変化と,その要因を検討した。
方法 東京都健康長寿医療センター研究所,東京大学,ミシガン大学が共同で行っている全国の60歳以上を対象とした調査において,2012年に新規に調査対象者となり,かつ,2017年に行われた追跡調査にも回答があった865人を分析対象とした(平均年齢70.5歳)。電子メールとインターネットは,それぞれ利用頻度が週1回以上を「利用あり」として2時点の利用の有無の変化を調べた。また,2012年調査時点での利用者と非利用者に分け,2017年時点での利用の有無により,「利用開始」と「利用中止」のそれぞれを従属変数とするロジスティック回帰分析を実施した。独立変数は,2012年調査時点での性別,年齢,独居,居住地の都市規模,教育年数,暮らし向き(主観的な経済状態),就労状況,親しい友人・近隣数,手段的日常生活動作(IADL),抑うつ傾向,および2時点間での退職の有無とした。
結果 電子メール,インターネットとも,2回の調査間では,利用開始者と利用中止者の数はほぼ等しかった。さらに,両ICTともに,年齢の若い人や教育年数の長い人ほど利用を開始しやすく,電子メールは友人・近所とのつきあいがない人ほど開始しにくい傾向がみられた。利用中止の要因は電子メールとインターネットでは異なり,電子メールについては教育年数の短い人や経済状態が悪い人,就労していない人で中止しやすい傾向があった。
結論 既存の調査においてみられる高齢者のインターネットなどの利用率の上昇は,同一コホート内で実際に利用者が増えているのではなく,出生コホートの入れ替えに伴うものであり,短期的には高齢者のICT利用率は低いという前提で施策を立案すべきと思われる。また,利用開始と利用中止(利用継続)の関連要因は必ずしも同じではなく,ICT利用率の向上のためには,利用開始だけでなく利用中止の要因についても多面的に検討していく必要がある。
キーワード 高齢者,ICT利用,縦断研究,電子メール,インターネット
|
第67巻第6号 2020年6月 医師調査の届出率の推移-2002年から2016年の個票データを用いた推計-石川 雅俊(イシカワ マサトシ) |
目的 日本における医師調査は,厚生労働省によって二年に一回,すべての医師を対象として実施されているが,届け出を行わない医師が一定程度存在することが以前から指摘されてきた。先行研究によれば,届出率は約90%と推計されているが,近年の研究はない。本研究では,2002年から2016年の医師・歯科医師・薬剤師調査(以下,三師調査)の個票データを用いて生存率を補正した届出率を算出し,医師調査の届け出の現状について明らかにし,さらに,届出率を上げるための政策提言を行う。
方法 2002年から2016年の三師調査の個票を加工したデータを厚生労働省の許可を得て入手した。2002年から2016年までの医籍登録年ごとの届出数,医籍登録者数のデータを用いて,生存率を補正しない届出率の推移を推計した。さらに,2016年の生存率を補正した届出率を推計した。
結果 生存率を補正しない届出率は,2014年89.4%と上昇傾向にあった。医籍登録25年以上では,登録年数が長いほど,届出率は低くなる傾向にあり,医籍登録40~44年の届出率は80%を下回っていた。一方,医籍登録4年以下の医師の届出率は,2016年は95%を超える水準まで上昇傾向にあった。男女差をみると,医籍登録10年以上では女性医師の届出率が低くなっており,医籍登録15~19年で80%を下回っていた。生存率を補正した届出率は2016年で90.2%だった。
結論 女性医師は出産や育児の影響,高齢医師は退職や死亡の影響で,届出率が低下していると考えられる。届出率を向上させる施策として,医師データベースの構築,マスメディア等を活用した広報,未届けに対する罰則適用の厳格化等が考えられる。三師調査は,医療政策の適切な遂行のために重要な調査であり,届出率向上に向けた施策を検討し,適切に実施していく必要がある。
キーワード 届出率,医師調査,縦断研究,医籍登録,医療政策
|
第67巻第6号 2020年6月 患者調査データを用いた
奥井 佑(オクイ タスク) |
目的 患者調査のデータを用いて近年の循環器疾患の患者数と通院率の動向について年齢・時代・コホート分析(APC分析)を行った。
方法 1999年から2017年までの患者調査の循環器疾患患者の総患者数,人口動態調査の人口のデータを用いた。循環器疾患として,高血圧性疾患,心疾患(高血圧性を除く),虚血性心疾患,脳血管疾患の4疾患の動向を分析した。年齢区分は30-34歳から85-89歳まで5歳刻みで全12年齢階級とし,コホート情報として,1910-1914年生まれから1983-1987年生まれ世代まで1歳刻みでコホートを定義して用いた。分析手法として,ベイジアンAPCモデルを用い,男女別に通院率の変化を年齢効果,時代効果,コホート効果の3つに分離した。
結果 循環器疾患のうち,高血圧性疾患の患者数は男女とも増加傾向であるのに対して,虚血性心疾患や脳血管疾患は減少傾向であった。APC分析の結果,男女とも年齢効果が他の効果よりも相対的に変動が大きい場合が多く,通院率に対する年齢効果が高齢になるほど高まることが確認された。高血圧性疾患について,男女とも1948年生まれ近辺から通院率に対するコホート効果が世代を経るごとに減少していたが,男性の方が効果の減少度合いが緩やかであり,1976年生まれ近辺からは効果が上昇に転じていた。心疾患(高血圧性を除く)について,男性で1930年生まれ近辺から,女性では1920年代生まれ近辺からコホート効果の減少がみられたが,女性における効果の減少度合いがより顕著であり,男性では1965年生まれ近辺から効果が横ばいとなっていた。脳血管疾患については,男女ともコホート効果の減少が認められたが,男性においては1970年生まれ近辺から,女性においては1960年生まれ近辺からコホート効果が緩やかに上昇に転じていた。
結論 患者調査データを用いて循環器疾患通院率の動向をAPC分析した結果,疾患および性別により時代効果とコホート効果の動向が異なることが示され,男女で患者数の動向が類似する場合においても各効果の動向が異なる傾向が示された。
キーワード 循環器疾患,年齢・時代・コホート分析,患者調査,公的統計,ベイジアンAPCモデル