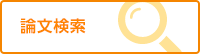論文記事
|
第62巻第5号 2015年5月 介護老人福祉施設職員の「介護実習指導を通じての学び」の
山本 綾美(ヤマモト アヤミ) |
目的 介護老人福祉施設の職員の「介護実習指導を通じての学び」の内容を明らかにし,実習に対する関心や,職員の自己成長を促す実習の体制を構築するための資料を得ようとした。
方法 首都圏の介護老人福祉施設250施設の職員(「窓口者」「フロア長」「一般職員」各施設1人ずつ)を対象に,郵送法による自記式質問紙調査を実施した。本研究では,「フロア長」を“学生が実習を行うフロアの長”,「一般職員」を“フロア長以外の実習を担当する介護職員”とした。
結果 有効回答は82施設の164人であった(有効回答率32.8%)。因子分析の結果,「介護実習指導を通じての学び」の内容として,“実践の振り返り”“施設の評価と職員教育”“利用者支援の新たな視点”“指導方法”“養成校とのパイプ”“仕事への愛着”の6因子が抽出された。相関分析の結果,実習指導継続希望は6因子すべてと正の相関がみられ,“仕事への愛着”とは中程度の相関がみられた。また,「フロア長」「一般職員」を独立変数にt検定を行った結果,6因子のいずれにおいても有意な差はみられなかった。
結論 施設職員の「介護実習指導を通じての学び」を促していくことで,実習指導継続の希望,実習に対する関心を高められる可能性があることが示唆された。実習指導に携わる職員の学びを促す実習体制の構築が今後の課題である。
キーワード 介護実習指導を通じての学び,実習指導者,介護職員,介護老人福祉施設
|
第62巻第5号 2015年5月 介護老人福祉施設における褥瘡対策に関する
三谷 佳子(ミタニ ヨシコ) 永野 みどり(ナガノ ミドリ) |
目的 介護老人福祉施設での褥瘡推定発生率は1.21%だが,半数は重度の褥瘡だと指摘されている。介護老人福祉施設は他の介護保険施設と比べ,介護に最も重点をおいた施設だが,介護職の褥瘡ケアに関する知識不足や,褥瘡処置技術に対する不安が報告されている。介護老人福祉施設における褥瘡対策状況を見直し,そこに勤める職員への教育について検討することは,介護老人福祉施設のケアの質や入所者のQOLの観点からも重要である。そこで本研究では,介護老人福祉施設における褥瘡ケアに関する職員教育の実態とその関連要因を検討することを目的とした。
方法 全国の特別養護老人ホーム5,800施設を対象に,郵送法にて質問紙調査を行った。回収数は2,731件で,そのうち褥瘡対策状況に関して回答のあった2,723件を有効回答とし分析を行った。
結果 回答者は看護職員が1,920人(70.5%),開設主体は社会福祉法人が2,309施設(90.3%)であり,褥瘡有病割合は3.0%であった。褥瘡対策チームのある施設は1,275施設(51.0%),褥瘡対策のための職員教育を実施している施設は1,283施設(49.1%)であった。職員教育で取り上げられているテーマは「褥瘡発生予防の勉強会」「褥瘡予防の用具等に関する事」「褥瘡処置・ケアの手順の実技」が多かった。職員教育の手法で最も多かったのは「講義」(31.3%)であった。職員教育の有無と,施設状況,加算算定状況,褥瘡対策状況,入所者の状況,職員状況との関連を検討した結果,職員教育あり群では「同一法人または関連法人が開設・運営する医療機関」を有する割合が有意に多かった(p=0.002)。職員教育の有無は,褥瘡対策チーム・褥瘡対策指針の有無と有意に関連していた(p<0.001)。また,職員教育あり群の方が円座の使用割合は有意に少なかった(p=0.01)。しかし,一方で職員教育あり群でも554施設(54.8%)では円座を使用していた。
結論 職員教育の実施には医療機関との連携体制が関わっており,他の医療機関のサポートが重要であると考えられる。また,褥瘡対策への取り組み状況に施設間で差があることが確認された。一方で,職員教育は褥瘡ケアの新しい知識の普及に有用だが,実際の褥瘡ケアに有用かつ新しく正しい情報が教育されていない,もしくは職員教育を実施しているにも関わらず実際の褥瘡ケアに教育内容が反映されていない施設が少なくないことも示唆された。
キーワード 褥瘡,職員教育,介護老人福祉施設,ケアの質
|
第62巻第5号 2015年5月 グループホーム入居者の退去先の決定要因岸田 研作(キシダ ケンサク) 谷垣 靜子(タニガキ シズコ) |
目的 グループホーム(以下,GH)入居者の退去先の決定要因を明らかにすることとした。
方法 全国のGHから無作為に抽出された6,064の事業所を対象に調査を行った。最終的に分析対象となったのは,1,415のGHの入居者および過去1年間の退去者(計11,787人)である。退去先の決定要因を多項ロジットモデルで分析した。
結果 看護師を配置しているGHでは,老人保健施設への退去が少なかった。看取りに取り組む意向があるGHでは,一般病院への退去が少なかった。母体法人が医療機関や介護施設を持つGHでは,医療機関や介護施設への退去が多かった。
結論 看護師の配置は,老人保健施設への退去確率を低下させるものの,療養病床や一般病院への退去確率に影響しなかったことから,医療依存度が高い者の入居継続を促進する効果は限定的であると考えられる。看取りに取り組む意向があるGHでは,医療依存度が高い入居者でも受け入れることにより,一般病院への退去が少ない。母体法人が医療機関や介護施設を持つGHでは,重度化した入居者を母体法人が有する医療機関や介護施設に入院・入所させている可能性がある。
キーワード グループホーム,退去者,看取り
|
第62巻第5号 2015年5月 小児科定点医療機関における内科標ぼうの有無による
船山 和志(フナヤマ カズシ) 田代 好子(タシロ ヨシコ)飛田 ゆう子(トビタ ユウコ) |
目的 感染症発生動向調査事業における小児科定点医療機関(以下,小児科定点)からの報告において,内科標ぼうの有無による患者の年齢構成の違いを検証した。
方法 横浜市における小児科定点から報告された感染性胃腸炎患者の年齢構成を,全小児科定点および小児科定点のうち,小児科を有する一般診療所(主たる診療科が小児科)において,内科標ぼうの有無でそれぞれ比較した。
結果 全小児科定点と小児科定点のうち,小児科を有する一般診療所(主たる診療科が小児科)のどちらにおいても,内科標ぼうの有無で年齢構成に有意な違いがみられた。
結論 地域によって内科標ぼうのある小児科定点の割合が異なる可能性が考えられることから,全国や地域間における患者の年齢構成の比較や,年齢ごとの罹患数を推計する際には,定点の内科標ぼうの有無についても考慮する必要があると考えられた。
キーワード 感染症発生動向調査,小児科定点医療機関,内科標ぼう,年齢構成
|
第62巻第5号 2015年5月 インフォームド・コンセントと
|
目的 患者調査から得られたデータを使用して,治療方法と薬の選択に関するインフォームド・コンセントとインフォームド・チョイスの理想と現実において,患者の属性が影響しているかを検証した。患者の属性として,性別,年齢,学歴を取り上げたが,性別のみに一貫した傾向がみられたので,患者の属性のうち,性別に限定した分析結果を報告する。
方法 2004年に関東,中部,近畿の各地方の患者を対象に実施された『患者さんの「医療への参加」に関する意識調査』のうち,治療方法と薬の選択に関するインフォームド・コンセントとインフォームド・チョイスの理想と現実に関する質問と患者の属性に関する質問から得られたデータを使用し,クロス集計表による分析およびMann-Whitney検定による分析を行った。
結果 治療方法と薬の選択に関するインフォームド・コンセントとインフォームド・チョイスにおいて,女性のほうが男性よりも患者の意向を重視した決定を望んでおり,現実においても女性のほうが男性より患者の意向を重視した決定がなされていると感じていることが示された。
結論 上記の結果が得られた理由として,女性は,防衛的で損失回避的な性質があることが考えられた。医師と対面する場合でも,損をしないように,危害を加えられないようにしたいため,より自分の意思を尊重してもらいたいという希望が強く,医師と対面する場面でも,男性は余計なコミュニケーションをしないが,女性は安心を得られるような丁寧なコミュニケーションを求めていると考えられる。そして,現実の場面でも,女性のほうが不安解消のために積極的にコミュニケーションをとるため,より患者の意思を尊重してもらう機会が増え,実際にもそうなっていると考えられる。
キーワード インフォームド・コンセント,インフォームド・チョイス,性差,治療方法,薬の選択
|
第62巻第5号 2015年5月 北海道における脳梗塞アルテプラーゼ静注療法拠点病院への
西條 泰明(サイジョウ ヤスアキ) 中木 良彦(ナカギ ヨシヒコ) 川西 康之(カワニシ ヤスユキ) |
目的 北海道内の居住地域から,脳梗塞アルテプラーゼ静注療法の実施できる脳卒中急性期医療拠点病院への自動車アクセス時間について地理情報システム(GIS)ソフトウエアを用いて推定し,またアクセス時間を短縮することで改善するための拠点病院配置案を示すことを目的とした。
方法 北海道医療計画に掲載されている61医療機関を脳卒中急性期医療拠点病院とし,平成22年国勢調査における町丁字別人口に1人以上の居住者が存在する地区ごとに,直近の拠点病院への自動車アクセス時間を推定した。二次医療圏・市町村ごとのアクセス時間は町丁字別人口居住者数の重み付けをした平均値として算出した。またアクセス時間を改善するための拠点病院配置案については,二次医療圏ごとにアクセス時間上位の二次医療圏へ,7医療機関を新たに割り当てたアクセス時間改善案の検討も行った。
結果 61拠点病院へのアクセス時間について,平均60分以上となる二次医療圏が6医療圏存在し,うち90分以上は5医療圏であった。アクセス時間を改善するための拠点病院追加案については,①二次医療圏でアクセス時間が平均60分以上であり,医療圏内に拠点病院が設定されていない6医療圏,②アクセス時間60分以上に該当する人数が,約7万4千人と医療圏では2番目に多い1医療圏に1拠点病院を追加したと仮定した。以上,計68拠点病院とした場合の二次医療圏ごとのアクセス時間を計算すると,平均60分以上は1医療圏のみとなった。
結論 本研究では,GISソフトウエアを用いて,特に二次医療圏ごとの拠点病院への平均アクセス時間を示した上で,北海道の現状を考えた脳卒中急性期医療拠点病院の例を示した。脳梗塞急性期治療については,二次医療圏や自治体ごとのアクセス状況を検討し,地域の現状を考えて改善案を考えていく必要があると考える。
キーワード 脳梗塞,遺伝子組み換え組織プラスミノゲンアクチベーター(rt-PA,アルテプラーゼ),拠点病院,地理情報システム(Geographic Information System:GIS),アクセス時間
|
第62巻第6号 2015年6月 施設入居後の高齢女性の主観的幸福感について-友人関係と高齢期の生き方を中心に-鈴木 依子(スズキ ヨリコ) |
目的 施設入居後の環境適応について,高齢期の望ましい生き方に対する志向の違いによって,友人関係の形成に差があるかどうかを検討した。また,主観的幸福感が,高齢期の望ましい生き方の認識や施設入居後の友人関係形成に関連があるかどうかを検討することを目的とし,今後,高齢期に住み替えを行う場合の基礎資料を得ることとした。
方法 対象者は東京都のケアハウスの居住者で,都内のケアハウスに調査協力を依頼し,生活相談員を通して調査趣旨に賛同の得られた居住者に対して,調査票を配布し無記名での回答を求め,郵送により回収した。有効回収数は428,有効回収割合は71%であった。施設職員による代理回答は求めなかった。このうち配偶者のいない女性278名のデータのみを用いた。調査内容は,基本属性,高齢期の生き方,友人関係,主観的幸福感とした。
結果 「変化・挑戦志向」的生き方をしている者は,主観的幸福感が高かった。提供サポートと受領サポートには主観的幸福感との関連が見られなかった。ただ,生き方が消極的な群で提供サポートに満足している場合に主観的幸福感が高かった。
結論 消極的な生き方の者が主観的幸福感を得ることができるように,彼らが施設内の友人に対して,サポートを提供できるような環境を整えることの重要性が示唆された。
キーワード ケアハウス入居者,高齢期の生き方,友人関係,主観的幸福感
|
第62巻第6号 2015年6月 柔道整復師が介入する被災地における訪問機能訓練事業の効果若井 晃(ワカイ アキラ) 豊嶋 良一(トヨシマ リョウイチ) 櫻田 裕(サクラダ ユタカ)松本 浩二(マツモト コウジ) 早坂 健(ハヤサカ タケシ) 中川 裕章(ナカガワ ヒロアキ) 三谷 誉(ミタニ ホマレ) 藤田 章一(フジタ ショウイチ) 星山 佳治(ホシヤマ ヨシハル) |
目的 東日本大震災後,被災地では環境の大きな変化から閉じこもり状態となる傾向にあるという。閉じこもりから生活不活発病につながり要介護状態へと移行するといわれ,最終的には死亡のリスクとなり得る。こうしたリスクを表面化する以前に食い止める方法が求められている。宮城県柔道整復師会では,柔道整復師が閉じこもり予防,支援の一つとしての訪問機能訓練を実施して,身体機能の向上,心理・社会的機能の向上を図り,活動意欲向上の実現を試みている。この試みが被災者の要介護・要支援への移行防止に役立つかどうかを検討することを目的とした。
方法 仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,および東松島市にて各地域包括支援センターから紹介された,もしくは接骨院に通院している者のうち,①被災した者,または被災した家族,②二次予防事業対象者に該当された者,または候補の者(自立判定を含む),③65歳以上で膝痛,腰痛の既往があり,生活不活発病に該当した者のいずれか1つに該当する者28名とした。柔道整復師による訪問機能訓練を実施して,心身機能および構造分野,健康に関する体力要素分野,ADL,IADL分野,QOL分野の4項目分野に改善がみられるかどうかを訓練前後で比較した。調査期間は,平成25年1月10日~3月17日とした。
結果 心身機能分野では,筋力,持久力,痛みについて有意に改善を認めた(p<0.05)。また健康に関する体力要素分野では,握力,開眼片脚起立時間,Timed Up&Go,5回椅子立ち上がりテスト,すべての項目において有意に改善を認めた(p<0.05)。ADL,IADL分野では,ADLに対する自己効力感の改善を認めた(p<0.05)。QOL分野では,一つずつの項目では有意差はみられなかったものの,QOLの項目合計を表す自己効力感に有意な改善を認めた(p<0.05)。
結論 柔道整復師が介入した訪問機能訓練によって,身体機能,健康に関する体力要素,日常生活や外出・参加に対する自信などの向上が図られたことから,これにより閉じこもりが解消され,対象者の望む生活を取り戻せる可能性が示唆された。
キーワード 被災地,柔道整復師,訪問機能訓練,閉じこもり状態,生活機能
|
第62巻第6号 2015年6月 孤独感による自殺死亡と同居人の有無の関連平光 良充(ヒラミツ ヨシミチ) |
目的 孤独感を原因・動機とする自殺死亡と同居人の有無の関連について,性・年齢別に明らかにすることを目的とした。
方法 自殺統計原票データを内閣府において特別集計した結果を分析に使用した。分析対象は,2009~2011年における自殺死亡者とし,自殺の原因・動機として「孤独感」が選択された者を孤独感による自殺死亡と定義した。自殺死亡率は,2009~2011年における自殺死亡数を2010年国勢調査人口の3倍で除して算出した。自殺死亡率比は,同居人の状況が「なし」の者(以下,独居群)の自殺死亡率を,「あり」の者(以下,同居群)の自殺死亡率で除した比として算出した。
結果 2009~2011年における自殺死亡数は男性65,879人,女性28,310人であり,そのうち孤独感による自殺死亡数は男性1,186人,女性627人であった。独居群では,男女とも,年齢が高くなるにつれて孤独感による自殺死亡率が上昇していた。一方,同居群では,孤独感による自殺死亡率は80歳未満では年齢による明らかな変化はみられなかったが,80歳以上では上昇していた。独居群,同居群ともすべての年齢において,男性の方が女性より孤独感による自殺死亡率が高かった。孤独感による自殺死亡率比は,男性では70~79歳,女性では60~69歳で最大であり,70歳以上では男性の方が女性より大きかった。
結論 独居は,性・年齢に関わらず孤独感による自殺死亡の危険因子であり,その影響は70歳以上では男性の方が女性より大きい可能性が示唆された。また,独居群,同居群ともに高齢者では孤独感による自殺死亡率が上昇していることから,同居人の有無に関わらず高齢者の孤独感の解消を行うことが自殺対策として必要になると考えられた。
キーワード 自殺死亡,孤独感,同居人,自殺統計原票
|
第62巻第6号 2015年6月 妊婦健康診査における公費負担と母子保健衛生に関する地域相関研究中野 玲羅(ナカノ レイラ) 佐藤 拓代(サトウ タクヨ) 磯 博泰(イソ ヒロヤス) |
目的 妊婦の経済的負担の軽減を図り,安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的として,平成21年より受診が望ましいとされる妊婦健康診査14回分の公費負担が行われている。しかしながら,都道府県ごとの公費負担額にはばらつきがあり,最大で3倍もの格差が生じている。また,近年,分娩が開始して初めて医療機関を受診する,あるいは救急隊要請を行う未受診妊婦あるいは飛び込み出産と呼ばれる事例が顕在している。未受診妊娠は流早産,低出生体重児,NICU入院も多く,母子ともに医学的にリスクの高い事例であるが、未受診の理由としては経済的問題が最も多く,約3割を占めている。このことから,妊婦健康診査における公費負担は,健診受診の促進につながり,ハイリスクな未受診妊娠を減少させる可能性があると考え,平成21年から23年までの都道府県ごとの公費負担額と母子保健衛生指標との関連を分析した。
方法 妊婦1人当たりの健診受診回数,満11週以内の妊娠届出割合,出生率,合計特殊出生率,低出生体重児割合,死産率,周産期死亡率,人工妊娠中絶実施率について,それぞれ全14回分の公費負担が開始された平成21~23年前後の値を用い,妊婦健診1人当たりの公費負担額との相関関係を調べた。さらに,妊娠届出週数に対する母の年齢の影響についても検討した。
結果 都道府県ごとの妊婦健診1人当たりの公費負担額は,満11週以内の妊娠届出割合との間に正の相関(r=0.15~0.31)を,人工妊娠中絶実施率とは負の相関(r=-0.19~-0.31)を示した。妊婦1人当たりの健診受診回数,出生率,合計特殊出生率,低出生体重児割合,死産率,周産期死亡率は公費負担額との間に明らかな相関はみられなかった。満11週以内の妊娠届出割合は出生時の母の平均年齢との間に正の相関(r=0.27~0.36)がみられた。
結論 妊婦健康診査における公費負担額の拡充は,妊娠早期の妊娠届出を促進し,人工妊娠中絶を抑制する可能性が示された。また,低年齢の妊婦に対する妊娠届出の重要性に関する啓発が必要と考えられた。
キーワード 母子保健,妊婦健康診査,公費負担,妊娠届出,人工妊娠中絶
|
第62巻第6号 2015年6月 在宅ケアにおける医療・介護職の多職種連携行動尺度の開発藤田 淳子(フジタ ジュンコ) 福井 小紀子(フクイ サキコ) 池崎 澄江(イケザキ スミエ) |
目的 本研究では,在宅ケアにおける医療職と介護職を含めた多職種による連携行動を評価できる尺度を開発し,その関連要因を検討することを目的とした。
方法 先行研究をレビューし,医療職や介護職との討議,さらにプレテストを経て作成した,多職種連携行動尺度について,3地域で在宅ケアを提供している医師,看護職,薬剤師,介護支援専門員,訪問介護従事者を対象とした質問紙調査を実施した。
結果 配布した1,526票中,665票の回収が得られ362票を分析に用いた。項目分析と因子分析(主因子法,プロマックス回転)の結果より項目の取捨選択を行い,最終的に“意思決定支援”,“予測的判断の共有”,“ケア方針の調整”,“チームの関係構築”,“24時間支援体制”の5因子構造の17項目からなる尺度を作成した。信頼性として,Cronbachのα係数は0.94,再テスト法による相関係数は0.91であり,内的一貫性および再現性が確認された。併存的妥当性として,地域の連携基盤やチームの連携達成度に関する自己評価とは,いずれも0.40以上の有意な相関を示した。また,関連要因として,多職種連携研修会や在宅終末期ケア研修受講がある場合,または過去1年間に終末期ケアを経験していた場合は,多職種連携行動の得点が有意に高かった。
結論 開発した尺度は,多職種連携行動を測定する尺度としての信頼性,妥当性を有すると考えられた。また,連携を高めるためには,実践的な知識や経験が必要であり,こうした機会を積極的に地域でつくりだす必要がある。今後は,本尺度を在宅ケアに従事する医療職と介護職の連携の評価とし,地域内での改善策を検討する際に活用することも可能と考える。
キーワード 多職種連携,在宅ケア,行動尺度,連携評価
|
第62巻第7号 2015年7月 市区町村単位の既存統計資料を活用した地域特性の把握-地域診断に備えて-安藤 実里(アンドウ ミノリ) 嶋田 雅子(シマダ マサコ) 若林 チヒロ(ワカバヤシ チヒロ)新村 洋未(シンムラ ヒロミ) 笹尾 久美子(ササオ クミコ) 加藤 朋子(カトウ トモコ) 島田 美喜(シマダ ミキ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) 柳川 洋(ヤナガワ ヒロシ) |
目的 政府が公表している市町村単位の統計資料を用いて,「健康日本21(第二次)」などの健康づくり計画の策定と実績を評価するための簡便なツールを作成し,地方自治体が実施する健康づくり政策策定のための基礎資料を効率的に収集し,活用することを目的とした。
方法 総務省統計局のe-Statや各府省のホームベージに掲載されている統計資料と一般財団法人厚生労働統計協会などの団体が刊行している統計資料のうち,市町村単位の集計成績が利用できるもののリストを作成する。さらに,このリストを用いて簡便に市町村の地域特性を把握するための評価シートを作成した。
結果 利用可能な市町村単位の統計資料のうち,健康づくり政策の策定に役立つものを選定し,①基礎データ項目(e-Statを含む),②人口動態・寿命に関するもの,③保健・医療・福祉に関するものの3つのカテゴリーに分けて,それらの名称,所在先(リンク先アドレス),収録資料の内容の総覧を作成した。その上で,選定した統計資料を用いて,対象とする自治体の値と全国,都道府県の平均値(標準値)とを比較するための簡便な評価シートを作成した。時系列データが利用できる資料については,標準値との比較の際に偶然のばらつきによる判断の誤りや年齢構成の影響を避けるために,可能な範囲で単年ではなく5年間の発生数の合計や標準化死亡比などを利用することとした。具体例として,1つの自治体(市レベル)を取り上げて,人口高齢化に関する項目を中心にして,評価シートにデータを入力し,作成した指標の妥当性を検証した。
結論 今回作成した市町村別統計資料リストと評価シートを用いることにより,基本的な地域特性を把握するための地域診断を,より効率的かつ簡便に行うことができると考える。しかし,政府が公表している市町村単位の統計資料には限りがあり,ここに示したリストとシートだけでは十分ではない。対象とする自治体および都道府県がもっている統計資料も有効活用することにより,地域診断の内容と精度を充実させたい。
キ-ワ-ド 既存統計資料,地域診断,健康日本21,e-Stat,地域特性評価シート,市町村別指標
|
第62巻第7号 2015年7月 介護サービス情報公表システムを用いた
小島 愛(コジマ メグミ) 大久保 豪(オオクボ スグル) |
目的 本研究の目的は介護サービス情報公表システムの運営状況チェック項目のうち,実施割合の低いものを明らかにすること,そして他者視点での評価(利用者アンケートや第三者評価)の実施状況を明らかにした上で,実施割合の低い項目との関連を明らかにすることとした。
方法 2014年4月から5月にかけて,介護サービス情報公表システムから岐阜県の高齢者入所施設の情報を収集した。調査対象の施設は介護老人福祉施設(以下,特養)114施設,介護老人保健施設(以下,老健)67施設の計181施設とした。調査対象の項目は,事業所の詳細および運営状況に掲載されているチェック項目とした。運営状況チェック項目について項目ごとの実施割合を計算し,50%未満であった項目を抽出した。ここで抽出した項目について,入所者アンケート実施の有無および第三者評価実施の有無とのクロス集計を行い,Fisherの直接確率検定を行った。
結果 入所者アンケートを行っていたのは84.5%,第三者評価を行っていたのは12.2%であった。運営状況チェック項目149項目のうち,102項目は実施割合が80%以上であった。実施割合が50%未満の項目は「成年後見制度又は日常生活自立支援事業を活用した記録がある」(入所者アンケートの有無による違いp=0.098;第三者評価の有無による違いp=0.005),「食事の開始時間を選択できることが確認できる」(0.665;0.096),「食事の場所を選択できることが確認できる文書がある」(1.000;0.008),「地域の研修会に対する講師派遣の記録がある」(0.071;0.133),「介護相談員又はオンブズマンとの相談,苦情等対応の記録がある」(0.013;0.171),「第三者委員との会議記録がある」(0.628;0.002),「地域の消防団,自治体等との防災協定書がある」(0.837;0.256),「自ら提供するサービスの質について,自己評価を行った記録がある」(0.536;0.037),「介護及び看護の記録について,利用者又はその家族等に対する報告又は開示を行った記録がある」(0.319;0.298),「精神的ケアに関する従業者研修の実施記録がある」(0.047;0.075),「在宅で療養している要介護者が緊急時に入所することについて記載があるマニュアル等がある」(0.259;0.356),「在宅で療養している要介護者が緊急時にショートステイを利用することを定めている文書がある」(0.281;0.318)であった。
結論 運営状況チェック項目のうち,実施割合が50%未満のものは12項目あり,一部の項目では入所者アンケートや第三者評価といった他者視点での評価を行っている施設で実施割合が高くなっていることも示唆された。
キーワード 介護の質,高齢者入所施設,質の向上,介護保険
|
第62巻第7号 2015年7月 低出生体重児出生率の地域差に関する検討芹澤 加奈(セリザワ カナ) 扇原 淳(オオギハラ アツシ) |
目的 低出生体重児は,生活習慣病等の発症リスクが高いことが知られているが,2000年代以降,わが国では,低出生体重児出生率が増加している。低出生体重児の出生に関連する要因の中でも,時間的空間的な特徴は明らかになっていない。そこで本研究では,都道府県レベルでみた低出生体重児出生率の年次推移について検討し,低出生体重児出生の時間的空間的な偏在とその特徴について明らかにすることを目的とした。
方法 厚生労働省,総務省統計局公表の都道府県別指標データから,1975年,1992年,2009年の2,500g未満出生率を抽出した。3つの年次の低出生体重児出生率を白地図上に色分けし,視覚化した。次に,抽出した年次データを用いて,都道府県別に低出生体重児出生率の増加率を算出した。
結果 1975年では,低出生体重児出生率の高かった上位5県は沖縄県,佐賀県,宮崎県,熊本県,高知県で,九州沖縄地方に集中していた。低い県上位5県は,青森県,宮城県,山形県,長野県,埼玉県で東北地方に多かった。1992年では,沖縄県,福岡県,静岡県,栃木県,佐賀県の順で高かった。2009年では,山梨県,沖縄県,島根県,鹿児島県,宮崎県の順で高かった。1975年を基準年とした2009年の低出生体重児の増加率は,山梨県(206.6%),長野県(193.9%),島根県(188.8%),青森県(187.2%),栃木県(183.1%)の順で高かった。
結論 わが国の低出生体重児出生率は周産期医療体制の整備とともに増加していった。都道府県別の低出生体重児出生率は,1975年には九州沖縄地方に多く,1992年には九州沖縄地方に加えて静岡,栃木といった本州の県で高い傾向がみられた。2009年には,再び九州沖縄地方で高い傾向がみられた。低出生体重児出生率の増加率(2009年/1975年)が高かった県は,周産期医療に関わる資源が高い可能性が考えられた。今後,低出生体重児出生率のリスク要因の分析に際しては,正・負双方の要因に注意した分析が求められる。
キーワード 低出生体重児,出生率,都道府県,年次推移
|
第62巻第7号 2015年7月 1歳半児の咀嚼力と養育者の児への食事提供の実態上野 祐可子(ウエノ ユカコ) 佐伯 和子(サエキ カズコ) 良村 貞子(ヨシムラ サダコ) |
目的 子どもの咀嚼力低下が問題視され,口腔発達に合わせた食事提供が重要視されるようになった。しかし,口腔発達に合った硬さの食事や大きめの物を食べていない状況があり,養育者の食事提供の視点から成長発達に合った食事支援について検討する必要がある。そこで本研究では,1歳半児の咀嚼力と養育者の食物の硬さと大きさに対する認識および児への食事時の声かけとの関連を明らかにすることを目的とした。
方法 2013年6~10月,北海道内の4市で行われた1歳6カ月児健康診査を受診した児の養育者を対象に,無記名自記式質問紙を配布し,郵送法で回収した。調査票は児の咀嚼力,養育者の児への食事の与え方で構成した。咀嚼力は「よく噛んでしっかり飲みこむ力」と定義した。分析には,児の咀嚼力との関連を検討するため,各変数のカテゴリーを2群に分け,χ2検定,Fisherの直接確率検定を行った。統計的有意水準はP<0.05とした。
結果 調査票配布は501部,うち有効回答者200人(有効回答率39.9%)であった。咀嚼力がある児は128人(64.0%)であった。養育者は,食物の硬さの目安として大人に近い硬さを29.2%が,大人と同じ硬さを11.2%が与えており,硬いものを入れる頻度は,「いつも入れる」「たまに入れる」を合わせて77.4%であった。普段から噛み切って1口サイズにする大きさの食物を提供している養育者は16.2%と少なく,普段から細かく数個をまとめて1口で食べる大きさを目安としている者は9.0%であった。声かけの頻度は,「いつもかける」「たまにかける」合わせて164人(82.0%)であった。養育者が硬いものを児の食事によく取り入れ(P=0.005),噛み切って1口サイズにするような大きなものを児の食事に取り入れている群(P=0.037)は有意に咀嚼力があった。また,硬いものや大きなものをあげた時に噛むよう声をかける群は有意に咀嚼力があった(P=0.002,P=0.014)。
結論 咀嚼力がある1歳半児は6割程度であった。養育者は,硬いものを与える意識が高いが,児の発達段階より硬すぎるものを目安として提供する傾向にあること,切歯で噛み切る必要のない大きさの食べ物を与える傾向にあることが示唆された。1歳半児には,発達に合わせた硬さ・前歯で噛む必要がある大きめな物を提供し,摂取時にしっかり噛むよう児へ声かけするよう提案する必要性が示唆された。
キーワード 咀嚼力,食物の硬さ,食物の大きさ,声かけ,1歳半児
|
第62巻第7号 2015年7月 大学生における早食いと肥満の関係山根 真由(ヤマネ マユ) 江國 大輔(エクニ ダイスケ) 森田 学(モリタ マナブ) |
目的 多くの横断研究では早食いと肥満との関連が示唆されているが,縦断研究で若年者を対象に早食いと肥満との関連を調べたものはあまりない。本研究の目的は,日本の大学生を対象に早食いと肥満との関連を縦断研究で調査することである。
方法 2010年4月に,岡山大学で行われた入学時の健康診断および3年後の健康診断を受診した1,396名のうち,BMIが25㎏/㎡未満の正常な体重の1,314名(男性676名,女性638名)を分析対象とした。早食いを含む生活習慣に関する自己記入式質問紙調査を行った。3年後の追跡調査時にBMIが25㎏/㎡以上だった者を「過体重/肥満群」,18.5㎏/㎡以上,25㎏/㎡未満だった者を「正常群」,18.5㎏/㎡未満だった者を「やせ群」と定義した。2群間(やせ群/正常群と過体重/肥満群)の食習慣の比較にχ2検定,「過体重/肥満群」の有無を従属変数,性別,早食い,油物をよく食べるを独立変数としてロジスティック回帰分析を行った。
結果 本研究では38名(2.9%)が3年後に過体重/肥満群となった。ロジスティック回帰分析では過体重/肥満群になるリスクは,男性でオッズ比2.77倍(95%信頼区間:1.33-5.79,P<0.01),早食いでオッズ比4.40倍(95%信頼区間:2.22-8.75,P<0.001)であった。
結論 日本の大学生において,早食いは肥満のリスクになることが示唆された。大学等で毎年実施されている健康診断の際に,BMIや食べる速さを調べること,および早食いの改善のために保健指導を取り入れることで,将来のBMI増加予防および生活習慣病予防に役立つことが期待される。
キーワード 早食い,大学生,肥満,縦断研究,BMI
|
第62巻第7号 2015年7月 地域の高齢者における友人の獲得とつながりの維持に関する縦断研究岡本 秀明(オカモト ヒデアキ) |
目的 地域の高齢者のつながりづくりやつながりの維持に関して友人に焦点をあて,縦断調査データを用いて,友人を獲得している者,友人と会う機会を維持している者,親しい友人・仲間をもち続けている者の特性の3点を明らかにすることを目的とした。
方法 千葉県都市部4市に在住する高齢者(65~79歳)2,000人を無作為抽出し,初回調査を2010年に,追跡調査を2013年に実施した。分析対象者数は,610人であった。分析には,二項ロジスティック回帰分析を用いた。従属変数は,友人を獲得している者の特性の検討では,初回調査時に友人の獲得がない者のみを抽出し,追跡調査時における友人の獲得の有無とし,友人と会う機会を維持している者の検討では,初回調査時に友人と会う機会がある者のみを抽出し,追跡調査時における友人と会う機会の有無とし,親しい友人・仲間をもち続けている者の検討では,初回調査時に親しい友人・仲間がいる者のみを抽出し,追跡調査時における親しい友人・仲間の有無とした。
結果 二項ロジスティック回帰分析の結果,友人を獲得している者の特性は,人間関係を広げる志向の得点が高い,趣味の会等仲間内の活動をしている,学習の場に参加している,であった。友人と会う機会を維持している者の特性は,人間関係を広げる志向の得点が高い,趣味の会等仲間内の活動をしている,老人クラブ活動をしている,であり,外出や活動参加に誘われるに有意傾向(p<0.1)がみられた。親しい友人・仲間をもち続けている者の特性は,人間関係を広げる志向の得点が高い,趣味の会等仲間内の活動をしている,学習の場に参加している,であり,女性に有意傾向がみられた。
結論 友人の獲得,友人と会う機会の維持,親しい友人・仲間の維持のそれぞれの関連要因が明らかになり,これらすべてに共通していた関連要因は,人間関係を広げる志向が強い,趣味の会等仲間内の活動をしていることであった。
キーワード 社会的ネットワーク,友人関係,友人の獲得,つながりの維持,高齢者,縦断研究
|
第62巻第8号 2015年8月 児童虐待問題を抱える家族の特徴に関する研究-児童相談所の虐待実態調査に関するクラスタ分析比較を通して-加藤 洋子(カトウ ヨウコ) |
目的 本研究は,児童相談所が対応している児童虐待事例に関する2つの実態調査の2次分析から虐待問題を抱える家族の特徴を明らかにし,虐待を深刻化させない対策を検討することを目的とした。
方法 「児童相談所が対応する虐待家族の特性分析」(2003年)と,全国児童相談所長会による「全国児童相談所における虐待の実態調査」(2008年)の2次分析(個別票データ)より,虐待が起こっている家族を類型化し比較を行った。2003年調査は,世帯別の416ケース(児童数501人)を分析対象とした(3都道府県内にある児童相談所に質問紙を送付・回収した。調査期間は2002年12月~2003年1月とし,2002年度中に一時保護し,一定の方針が立ったケースになる)。2008年調査は,全国の児童相談所(195/197カ所回収)が受理した虐待またはその疑いがあるケースを調査対象としている(2008年4月1日~6月30日までの期間に新規に受理したケース)。世帯別では7,256ケース(虐待相談として受理した児童数9,895人)になる。分析は多重コレスポンデンス分析の次元得点を利用したクラスタ分析を行った。
結果 類型は,「両親型」「ひとり親型」「祖父母同居型」「内縁型」に分かれ,どの家族形態(世帯)においても虐待が認められた。「ひとり親型」「祖父母同居型」の類型では,世帯の経済状況・就労状況の厳しさが明らかになり,「ひとり親型」では保護者が精神疾患に罹患しているケースが多いことがわかった。各類型とも身体的虐待,ネグレクトが大きな割合を占めており,次に心理的虐待の割合が高かった。2003年調査と2008年調査で経年の変化を確認したが,家族の特徴は大きく変化していなかった。
結論 本研究より「ひとり親型」「祖父母同居型」は経済的な状況が厳しい傾向が強く,経済的支援が欠かせないことが明らかになった。また「ひとり親型」では「ネグレクト」への配慮を十分に行うことが不可欠であり,保護者の精神疾患にも留意しなければならないことがわかった。それらを踏まえ,「ひとり親型」の家族には精神面と家事等における援助が必要であり,その施策の拡充がさらに求められるであろう。個々の家族を支援するソーシャルワークの必要性と,類型からみた家族の特徴をとらえた対応を同時に意識すること,またそれに合わせた施策の整備を行うことが現場では求められ,虐待死につながるような重篤な虐待を防ぐためには,これらの類型から導き出され重なり合っている注意すべき項目を見逃さず家族を支援しなければならない。
キーワード 児童虐待実態調査2次分析,虐待家族の特徴,クラスタ分析, 類型化の比較
|
第62巻第8号 2015年8月 認知症対応型生活介護(グループホーム)における看取りの実態と課題-運営法人別の特徴について-小長谷 陽子(コナガヤ ヨウコ) 鷲見 幸彦(ワシミ ユキヒコ) |
目的 認知症対応型共同生活介護(GH)は,介護保険法の施行後,施設数が増加し,GHにおける看取りも増えている。近年,増加が著しい営利法人運営のGHを含めた運営法人別の看取りの実態と課題を明らかにする。
方法 愛知・岐阜・三重3県のGH840カ所に調査票を郵送した。内容は,GHの運営主体,本体施設の有無とある場合の施設種類,ユニット数,利用者の診療体制,急変時や看取りに関するマニュアルの有無,急変時の医師への連絡体制,看取りへの協力の有無,過去の看取りの経験とその評価,今後の看取りに対する意見等である。調査期間は平成25年10月1日から11月末日までであった。
結果 522カ所のGHから有効回答を得た(回収割合:62.1%)。法人別で最も多かったのは株式会
社,次いで有限会社であった。これらとその他の会社法人を合わせて営利法人とした。解析は,営利法人,医療法人,社会福祉法人の3群で行った。単独型は全体で56.6%,社会福祉法人および医療法人では単独型はそれぞれ12.9%,11.8%であったが,営利法人では80.3%であった。併設型の場合の本体施設は,医療法人では病院と診療所,社会福祉法人では特別養護老人ホームが多かった。ユニット数は2ユニットが最も多く,次いで1ユニットであった。社会福祉法人では1ユニットが50.5%であり,医療法人と営利法人では2ユニットがそれぞれ62.3%,67.1%であった。本人や家族がGHでの看取りを希望した場合,「協力する」と答えたのは40.8%,「協力しない」は10.8%,「条件により協力する」は47.9%であった。社会福祉法人では「協力しない」が20.2%であったのに比べ,医療法人と営利法人ではそれぞれ9.3%,8.4%であった。GHでの看取りの経験は,59.0%のGHで「ある」と答えた。社会福祉法人では51.0%で経験がなかったが,医療法人と営利法人ではそれぞれ55.3%,63.0%の経験があり,3群間で有意な違いがみられた。看取りの回数は2~4回が最も多く,次いで1回であり,10回以上のGHもあった。医療法人と営利法人では5~9回がそれぞれ19.5%,19.1%であり,医療法人では10回以上が17.1%であったが社会福祉法人では2.2%であった。
結論 医療法人のGHは本体が医療施設であることから,医療との連携は十分であり,看取りの経験豊富な事業所が増えていた。一方,社会福祉法人では医療との連携はやや薄いながら,看取りに関する職員や家族の満足度が高く,質の良い看取りが行われていると考えられた。GHでの看取りの実態には,運営法人の背景に基づく特徴が反映されていた。
キーワード 認知症対応型共同生活介護(グループホーム),看取り,営利法人,医療法人,社会福祉法人
|
第62巻第8号 2015年8月 セーフコミュニティに向けた基礎的研究-都市在住高齢者における傷害予期不安と関連要因の検討-田髙 悦子(タダカ エツコ) 田口 理恵(タグチ リエ) 有本 梓(アリモト アズサ)臺 有桂(ダイ ユカ) 今松 友紀(イママツ ユキ) 鹿瀬島 岳彦(カセジマ タケヒコ) 塩田 藍(シオダ アイ) |
目的 都市在住高齢者における傷害予期不安の実態を把握するとともに関連要因を検討することにより,地域レベルで安心・安全の向上に取り組むセーフコミュニティ推進に向けた基礎資料を得ることとした。
方法 対象は,首都圏A市a行政区に在住する65歳以上の住民31,150名(全数)のうちから,1/50割合で無作為抽出された623名である。方法は無記名自記式質問紙調査(郵送法)である。調査内容は,基本属性,身体心理社会的特性,主観的健康感,外出頻度,抑うつ(K6尺度),ソーシャルネットワーク(Lubben Social Network Scale:LSNS),ならびに主要傷害(“自然災害”“交通事故”“犯罪”“転倒・転落”“外傷・脱水”“誤えん・窒息”)に対する今後5年間における予期不安の有無である。各傷害種別の予期不安を従属変数とし,各要因を独立変数とする重回帰分析を行った。
結果 回答者は381名(61.2%),有効回答者は359名(94.2%)であった。対象者の平均年齢は73.5(標準偏差=6.1)歳,うち男性が183名(51.0%),世帯状況は配偶者と同居している者が173名(48.6%)となっていた。予期不安を有する者の割合は,“自然災害”が66.9%と最も多く,次いで“犯罪”61.6%,“転倒・転落”が53.7%,“交通事故”49.0%,“誤えん・窒息”17.0%,“外傷・脱水”13.1%となっていた。また関連要因については,①すべての傷害に年齢および主観的健康感が有意に関連し,②“自然災害”“交通事故”“犯罪”については近所付き合いおよびソーシャルネットワーク,③“外傷・脱水”“誤えん・窒息”については当該傷害経験,抑うつ,外出頻度,④“転倒・転落”については当該傷害経験,抑うつ,外出頻度,近所付き合いおよびソーシャルネットワークが,おのおの有意に関連していた。
結論 都市在住高齢者における傷害予期不安は総じて高く,個人要因と環境要因が関連していたことから,今後,保健,医療,福祉はもとより,警察,消防,職域,教育,交通等における地域の諸領域のネットワークによりセーフコミュニティづくりを推進し,安心・安全を保障することが必要である。
キーワード 都市,傷害,高齢者,セーフコミュニティ,安心・安全,ネットワーク
|
第62巻第8号 2015年8月 医師の大幅な増員を仮定した場合の将来の医師数-女医の増加とその就業率に着目して-園田 智子(ソノダ トモコ) 森 満(モリ ミツル) |
目的 近年,医師不足が問題化してきたが,医師数が現状維持でも,長期的にみると医師不足は解消されるという報告がなされてきた。医学部新設などによって,今後恒常的に医師が増員された場合に,医師は供給過剰に陥ってしまうのか。そのかぎを握るのは女性医師の増加であると考えられる。そこで,男性医師と女性医師の年齢別死亡率と就業状況の違い,将来の人口の減少を考慮して,医師が大幅に増員された場合の将来の医師数を予測した。
方法 1980年から2060年までの10年ごとの男女別・年代別の医師数を求めた。国家試験合格者が,現状とほぼ同じく毎年9,070人の場合と,医学部新設または定員増により2030年以降,毎年最大10,000人の場合について,それぞれについて将来の医師数を予測した。国家試験合格者に占める女性の割合を35%と40%に設定した。さらに,年齢・性別の就業率の違いで修正した医師数も算出した。
結果 医師の増員がなければ,2060年の人口10万人当たり医師数は454.1~454.8人,全医師数に占める女性の割合は38.5~43.6%となる。2010年と比較して,男性医師数は変化なし,またはやや減少し,女性医師数は2.7~3.1倍となる。医師を増員して2030年以降に毎年10,000人の医師が誕生すると仮定すると,2060年の人口10万人当たり医師数は489.0~491.6人,全医師数に占める女性の割合は約38.0~43.4%となる。男性医師数は1.1倍に微増,または変化なし,女性医師数は2.9~3.3倍となる。医師の増員の有無に関わらず,60歳以上の女性医師は8~9倍に増加する。男女別・年代別の就業率の違いで医師数を修正すると,毎年10,000人の医師が誕生した場合でも2060年の医師数は2010年の1.4倍である。
結論 医師の増員の有無にかかわらず,①60歳以上の女性医師の増加が著しい,②男性医師数は横ばい,またはやや減少する,③人口10万人当たり医師数は日本の人口の減少によって2050年以降に増加率が増すが,受療率の高い高齢者の増加によって患者数は増えるため,患者当たりの医師数が増加するとは限らない。毎年10,000人の医師が誕生すると,④医師数はかなり増加するが,その主な増加分は女性である,⑤女性と高齢医師の就業率の低さのため,実際に就業する医師の増加は緩やかである。
キーワード 医師増員,医師数予測,女医,就業率
|
第62巻第8号 2015年8月 日豪の特別養護老人ホームにおける介護労働の比較研究-介護労働軽減プログラムと腰痛・筋骨格系の愁訴について-三宅 眞理(ミヤケ マリ) 上田 照子(ウエダ テルコ) Claire Emmanuel(クレア エマニエル)下埜 敬紀(シモノ タカキ) 神田 靖士(カンダ セイジ) 西山 利正(ニシヤマ トシマサ) |
目的 高齢化の進展から高齢者介護施設の需要も高まり,2025年には237~249万人の介護職員が必要とされている。本研究では,介護労働環境の異なる日本とオーストラリアの特別養護老人ホームの施設と職員に対し質問紙を用いて調査し,介護労働環境が介護職員に与える影響について検討した。
方法 対象は日本の近畿地方にある特別養護老人ホーム20施設(以下,JN)と,オーストラリアのビクトリア州にあるナーシングホーム7施設(以下,AN,日本の特別養護老人ホームにあたる施設)である。対象施設の代表者には調査票Ⅰを配布し,人員配置や給料,労働環境や労働安全教育などの基本情報を得た。調査票Ⅱは同施設の介護職員とし,JNの474人とANの324人を対象に,介護労働軽減プログラムとしての電動移乗介助機器(以下,リフト)の使用,排泄介助におけるベッドの高さの調整,スライディングシートの使用の3つの介助動作の状況や腰痛および筋骨格系の愁訴などについて,各々日本語版と英語版の調査票を用いて尋ねた。
結果 JNはANに比較して腰痛や筋骨格系の愁訴が高率であった。その背景として,入居者のADLが低いことや介護職員1人当たり入居者数が多いこと,また,移乗介助や排泄介助などにおける作業が,ANとは異なり1人での介助が主となっていることが考えられた。JNでは,リフトの使用状況,排泄介助におけるベッドの高さの調整,スライディングシートの使用が少なく,両群に有意な差が認められた。
結論 JNでは移乗介助や排泄介助において,ANとは異なり1人での介助が主となっていることや,介護労働負担軽減プログラムとしてのリフトの使用,排泄介助におけるベッドの高さの調整,スライディングシートの使用が少ないなど,介助における身体的負担が大きく,腰痛や筋骨格系の愁訴が高率となる要因として考えられた。ANでは,No Lift Policy「人力のみによって患者を移乗することを禁止した指針」を推進している。これにより移乗,排泄介助には必ず複数人での介助とリフト機械を利用することが義務づけられている。わが国の介護労働負担軽減のための介護労働環境の改善が必要であり,これらの見直しは喫緊の課題である。
キーワード 高齢者介護福祉施設,介護労働負担軽減,介護職員,腰痛,筋骨格系の愁訴,オーストラリア
|
第62巻第8号 2015年8月 地域別将来人口・患者数分析ツールの開発および医療計画策定への応用村松 圭司(ムラマツ ケイジ) 酒井 誉(サカイ ホマレ)久保 達彦(クボ タツヒコ) 藤野 善久(フジノ ヨシヒサ) 松田 晋哉(マツダ シンヤ) |
目的 人口構造の変化に伴い,各地域の医療需要が変化すると考えられる。限られた医療資源を有効に活用するためには,将来の医療需要を推計し適正に配置する必要がある。また,各地域で現状有する医療機能や隣接医療圏との関係など様々な事情が異なるため,画一的な将来患者推計結果の共有だけでなく,多様な切り口での分析を可能とする仕組みが必要である。今回著者らは既存のソフトウェアを用いて任意の地域および疾患の将来患者数推計を実現したので報告する。
方法 2011年患者調査の傷病分類別にみた都道府県別受療率および国立社会保障・人口問題研究所の人口推計を用いて,将来患者数を推計した。可視化にあたっては多くの自治体・医療機関で既に導入されているMicrosoft Excelのみを用いた。
結果 作成したツールを用いて北九州医療圏における将来人口・患者数推計の結果の可視化を行った。総人口は1990年から減少が続いており,2040年には約90万人となると推計されている。人口減少の主たる原因は高齢者の死亡によるもので,医療需要の増加が想定される。また,高齢者の人口が増加するため,医療の提供方式の見直しも必要と考えられる。将来患者数推計では入院・外来ともに2030年頃をピークに2010年のおよそ1.1~1.2倍に患者数が増加すると推計される。特に脳血管疾患,虚血性心疾患,肺炎,骨折の患者増が見込まれる。
結論 将来患者数推計の結果を活用することでより具体的な医療計画の策定が可能になることが示された。
キーワード 将来患者数推計,医療計画,地域医療構想
|
第62巻第11号 2015年9月 東日本大震災時に実施された避難所サーベイランスの評価と今後に向けた準備杉下 由行(スギシタ ヨシユキ) 菅原 民枝(スガワラ タミエ) 大日 康史(オオクサ ヤスシ)島谷 直孝(シマタニ ナオタカ) 高橋 琢理(タカハシ タクリ) 安井 良則(ヤスイ ヨシノリ) 中島 一敏(ナカシマ カズトシ) 砂川 富正(スナガワ トミマサ) 神谷 信行(カミヤ ノブユキ) 灘岡 陽子(ナダオカ ヨウコ) 谷口 清洲(タニグチ キヨス) 岡部 信彦(オカベ ノブヒコ) |
目的 2011年3月11日の東日本大震災後に避難所での感染症の流行を早期に把握するため,症候群を用いた避難所サーベイランスが導入された。本研究の目的はこの避難所サーベイランスの評価を行うことである。
方法 評価は,石巻市,東松島市,女川町を管轄する宮城県石巻保健所で実施した。避難所サーベイランスは2011年3月に国立感染症研究所が提案し,石巻保健所管内の避難所では,2011年5月からWebページ入力によるシステムを用いて開始された。2011年7月,保健所の避難所サーベイランス担当職員から実施状況を聞き取りし,「報告の過程」「避難所でサーベイランスに携わる者の症候群への理解」「迅速なシステム変更の可否」「専門職が報告を担当している避難所の割合」「避難所の参加率」「参加避難所からの自発的な報告率」「市町別の避難所参加率」「発症から報告までにかかる時間」「予定外のシステム機能停止の回数」「データ処理に要する時間」について評価を行った。
結果 避難所が保健所に報告し,保健所がデータ入力する運用であったため報告の過程は単純ではなかった。避難所でサーベイランスに携わる者の症候群への理解は十分であった。これまで稼動実績のある症候群サーベイランスシステムを導入しており新たな症候群の追加等には迅速に対応できる状態であった。保健師,看護師等の専門職が報告を担当している避難所の割合は約25%であった。避難所の参加率は41%,参加避難所からの自発的な報告率は20%であった。市町別の避難所参加率は,石巻市60%,東松島市2.5%,女川町46%であった。発症から報告までにかかる時間は1週間以内であった。予定外のシステム機能停止の回数は0回であり,データ処理は瞬時に行われた。
結論 将来の災害に備えるために,今後は避難所でサーベイランス情報を入力できる環境を作り上げ,教育や訓練を実施していくことが重要である。
キーワード 自然災害,サーベイランス,避難所,評価
|
第62巻第11号 2015年9月 ユニット型介護老人福祉施設における
石橋 洋次郎(イシバシ ヨウジロウ) 石井 敏(イシイ サトシ) 三浦 研(ミウラ ケン) |
目的 ユニット型の介護老人福祉施設(以下,ユニット型特養)における共同生活室の利用割合の関連要因を把握し,施設の設備等の状況と利用割合との関連性を明らかにするとともに,個別ケアがやりやすい環境について考察する。
方法 平成25年度に実施した「ユニット型施設の生活空間等の状況および運営等のコストに関する調査」の入居者単位のデータ(胃ろうの有無,QOL等)に,施設単位のデータ(設備等の状況)を結合したデータ13,167件を分析対象とした。最初に,χ2検定,t検定,Cochran-Armitage傾向検定による関連性の評価を行い,共同生活室の利用割合の関連要因を抽出した。次に,関連要因間の相関係数を算出して変数を整理して,説明変数を選定した。最後に,高頻度で共同生活室を利用しているか否かを被説明変数として,ロジスティック回帰分析を行った。
結果 ユニット型特養の入居者の87%が,食事の時に「毎日毎食」共同生活室を利用していた。胃ろうで栄養摂取している入居者に限れば,「毎日毎食」の利用は17%であった。検定の結果,胃ろう以外にも,QOLスコア,喀痰吸引等が関連していたが,性(男女)および年齢との関連は認められなかった。また,設備等に関する要因としては,『居室内にトイレが設置されている』等の4項目が関連していたが,他の10項目は関連していなかった。要因間の相関は,例えば『胃ろう・腸ろう等』と『喀痰吸引』との相関係数は0.76となり,強い相関関係がみられたので,利用割合との関連が強い『胃ろう・腸ろう等』で代表させた。ロジスティック回帰分析の結果,食事時の共同生活室の利用割合は,入居者の状態との関連が強く,胃ろうの有無が最も影響する要因であった。一方,利用割合との関連が認められた4つの設備等の状況の影響は相対的に小さく,いずれも利用割合を下げる要因となっていた。
結論 入居者の重度化あるいは医療必要度の増大は,共同生活室の利用を減らす要因であったが,要介護4の89%,要介護5の73%が実際に「毎日毎食」利用しており,重度者の多くが共同生活室を利用していることが確認できた。また,『入口に玄関があり,ユニット内外が明確になっている』等の4項目の設備等の状況下では,同程度の状態像の入居者に対して,食事の場所の選択がより個別的になされているものと考えられる。個別ケアがやりやすい環境を検討する際に考慮すべきである。
キーワード ユニット型,介護老人福祉施設,共同生活室,QOL,ロジスティック回帰,個別ケア
|
第62巻第11号 2015年9月 ホームヘルパーの楽観的態度に関連する要因の検討-構造方程式モデリングを用いて-広瀬 美千代(ヒロセ ミチヨ) |
目的 在宅介護においてホームヘルパーへのニーズは年々高まる一方であるが,その業務は個別性が高く,より複雑で柔軟な対応が求められる。本研究においては,このようなことをかんがみ,業務を楽観的に捉え,ストレスフルな状況をプラスに変えていけるような態度や価値観にはどのような要因が関連しているのかに関して検討することを目的とした。
方法 A県内の訪問介護事業所から無作為抽出した600人を対象とする自記式郵送調査を行った。有効回収数は149通,有効回収率は24.8%となった。質問項目はホームヘルパーの「介護業務において感じる困難性を肯定的,楽観的に解釈する態度,および人生における価値や学びを見いだす姿勢」を測定する尺度である「ヘルパー業務楽観的態度」15項目,性別,年齢,最終学歴,研修への自主的な参加の有無,ヘルパー業務継続に対する意識であった。統計分析においては「ヘルパー業務楽観的態度」について,「困難の楽観的解釈」「人生における利得感」「自己成長感」を潜在変数とする3因子2次因子モデルを設定し,確証的因子分析を行った。また,構造方程式モデルを用いて適合度と各変数間の関連性を確認した。
結果 欠損値のない131人のデータを用いて,「ヘルパー業務楽観的態度」に対して確証的因子分析を実施した結果,統計学的な水準を満たし,構成概念妥当性が支持された。また尺度のCronbachのα係数はすべての因子において0.855以上を示した。さらに「ヘルパー業務楽観的態度」と「最終学歴」「研修への自主的な参加の有無」「ヘルパー業務継続に対する意識」の間には,有意な関連が確認された。
結論 本尺度はホームヘルパーの利用者に対する支援や業務で起こりうる出来事に対して取り組む際の肯定的な見方や楽観的態度を測定する尺度として十分な妥当性と信頼性を有しているといえる。また,自発的に学ぶ姿勢があると研修参加によって獲得することが多く,そのような視点で業務を遂行することで困難状況にあっても楽観的なあるいは柔軟的な解釈や態度が身につくと予測される。さらに業務継続に対する強い意志があるとこのような楽観的態度が養われていくのではないかと考える。今後の課題としては因果関係の明瞭さを高めるため,質問項目を吟味し,調査を拡大して実施することが求められる。
キーワード ホームヘルパー,楽観的態度,肯定的側面,自己成長,研修参加,仕事継続意識
|
第62巻第11号 2015年9月 女子高校生の子宮頸がん予防ワクチン接種行動に関する心理社会的要因-修正版HBMに基づくパス解析による検討-小林 優子(コバヤシ ユウコ) 朝倉 隆司(アサクラ タカシ) |
目的 女子高校生の子宮頸がん予防接種行動を予測するHBM(Health Belief Model)の心理社会的な構成要因を測定する尺度開発を行い,その上でそれらを組み入れたHBMに基づいたパスモデルを用いて接種行動のメカニズムを明らかにすることを目的とした。
方法 神奈川県内の女子高校生1~3年生を対象に自記式質問紙調査を行った。因子分析の対象は項目に欠損値のない1~3年生2,463名であり,パス解析の対象は子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の対象学年であった1~2年生1,606名に限定した。子宮頸がん・予防接種に対する態度32項目に対し探索的因子分析を行い,8因子を抽出した。その後,確認的因子分析により8因子モデルの妥当性,各因子の構成概念妥当性を検討した。8因子および家族背景などの変数を用いて,まずHBMに基づくパスモデルを統計ソフトM-plusにより構築した。次いで思春期の保健行動を説明するためには,この時期に特徴的な要因である「調整力」が重要であると判断したため,「接種に向けた調整力」を加えてHBMに修正を加えたパスモデルを解析した。
結果 子宮頸がん・予防接種に対する態度としては,「家族の健康意識」「ワクチン接種の話題との接触」「接種に向けた調整力」「子宮頸がんの脅威」「ワクチン接種への肯定感と関心の高さ」「ワクチン接種への消極的態度・困難感」「ワクチンに対する不安」「ワクチン接種の時間と費用のバリア」の8因子が抽出された。HBMに基づく解析の結果,HBMの仮定どおりワクチン接種へのバリアが高いほどワクチン非接種の確率が高く,逆にワクチン接種への肯定感が高いほどワクチン接種の確率が高かった。そして,HBMの理論に反し「子宮頸がんの脅威」はワクチン接種を抑制していた。また,「ワクチンに対する不安」を説明する要因は特定できなかった。そこで,「接種に向けた調整力」を組み込んだ修正版HBMでは,HBMで特定されなかった「ワクチンに対する不安」の要因が明確になった。「子宮頸がんの脅威」は,直接的に接種行動を抑制する関連にあるが,「接種に向けた調整力」が媒介変数となり間接的に接種行動を促進するパスもあり,抑制と促進の両方の関連が明らかになった。なお,接種行動の説明率は25.2%から26.0%と「接種に向けた調整力」を加えたことによる大きな改善はみられなかった。
結論 オリジナルHBMに「接種に向けた調整力」を追加したことにより,女子高校生のワクチン接種行動をより明確に説明することができた。
キーワード 女子高校生,子宮頸がん予防ワクチン,接種行動,HBM,自律性
|
第62巻第11号 2015年9月 地域在住高齢者の歯の状態と
藤井 啓介(フジイ ケイスケ) 神藤 隆志(ジンドウ タカシ) 相馬 優樹(ソウマ ユウキ) |
目的 地域在住高齢者の歯の状態(残存歯数と義歯の使用の有無)と身体機能および転倒経験との関連性を明らかにすることを目的とした。
方法 2013年に茨城県笠間市で開催された健診事業に参加した地域在住高齢者205名(平均年齢74.1±4.5歳;男性49.8%)を対象とした。自記式質問紙により残存歯数と義歯(入れ歯やインプラント等)使用の有無を調査し,「残存歯数20本以上」「残存歯数19本以下かつ義歯有り」「残存歯数19本以下かつ義歯無し」の3群に分けた。握力,5回椅子立ち上がり時間,開眼片足立ち時間,Functional Reach,重心動揺軌跡長,Timed Up & Go,5m通常歩行時間により身体機能を評価した。また,過去1年間の転倒経験の有無を調査した。主たる統計解析には,従属変数に各身体機能評価項目または転倒経験の有無,独立変数に歯の状態を投入した共分散分析およびロジスティック回帰分析を用いた。各分析の共変量には年齢,性,教育年数,経済的な暮らし向き,Body Mass Indexを使用した。
結果 「残存歯数19本以下かつ義歯無し」群は「残存歯数20本以上」群に比べ重心動揺軌跡長が有意に長かった(p<0.05)。Timed Up&Goにおいては,「残存歯数19本以下かつ義歯無し」群は「残存歯数20本以上」群および「残存歯数19本以下かつ義歯有り」群に比べ有意に遅い値を示した(p<0.05)。「残存歯数19本以下かつ義歯無し」群は「残存歯数19本以下かつ義歯有り」群に比べ5m通常歩行時間が有意に遅い値を示した(p<0.05)。「残存歯数20本以上」群と比べ,「残存歯数19本以下かつ義歯が無し」群は,過去に転倒歴を有している割合が有意に高かった(オッズ比=5.80,95%信頼区間=1.74-19.37)。
結論 地域在住高齢者の身体機能は歯の状態によって異なり,さらに歯の状態と転倒経験に関連があることが示唆された。特に「残存歯数19本以下かつ義歯が無い」高齢者はバランス能力,歩行能力の低下が生じていることや,転倒リスクが高い可能性がある。
キーワード 地域在住高齢者,口腔機能,残存歯数,義歯,転倒,身体機能
|
第62巻第11号 2015年9月 労働者の収入とメンタルヘルス-職の不安定性による媒介効果に注目して-堤 明純(ツツミ アキズミ) 井上 彰臣(イノウエ アキオミ) 島津 明人(シマヅ アキヒト)高橋 正也(タカハシ マサヤ)川上 憲人(カワカミ ノリト) 栗岡 住子(クリオカ スミコ) 江口 尚(エグチ ヒサシ) 宮木 幸一(ミヤキ コウイチ) 遠田 和彦(エンタ カズヒコ) 小杉 由岐(コスギ ユキ) 戸津崎 貴文(トツザキ タカフミ) |
目的 収入の低い集団は高収入の集団に比してメンタルヘルス不調のリスクが高いとされるが,労働者における収入とメンタルヘルス不調の関係,およびその媒介要因を検証した研究はわが国では少ない。労働者の健康格差の実態とそのメカニズムを解明することを目的として行われているパネル研究のベースラインデータを用いて,労働者の収入とメンタルヘルスの関連,その媒介要因としての職の不安定性の影響を検討することを目的とした。
方法 労働者の健康格差のメカニズム解明を目的とした多目的パネルのベースライン調査参加者の男性7,645人,女性2,241人を対象とした。税込みの世帯収入を世帯員数で調整した世帯収入の下位3分位を低収入とした。将来の職の安定性,季節雇用,過去および将来の失業の可能性を尋ねる4項目の得点和の上位5分位以上を職の不安定とした。K6得点の13点以上をメンタルヘルス不調とした。男女別に,低収入群がメンタルヘルス不調に陥るリスクを,年齢,教育歴,職業,労働時間を調整したロジスティック回帰分析を用いて算出した調整後オッズ比,および95%信頼区間で推定した。低収入群とメンタルヘルス不調の関連を,職の不安定性がどの程度説明するかを,それぞれの変数を投入したオッズ比を求めて検討した。
結果 男女とも,低収入はメンタルヘルス不調と関連していた。低収入の男性労働者がメンタルヘルス不調に陥るリスク(属性・就業状況を調整したオッズ比)は1.26で,女性では1.62であった。職の不安定性を調整すると,メンタルヘルス不調に対する低収入のリスクは男女ともに約9%減弱し,男性において低収入とメンタルヘルス不調の関連は統計的有意ではなくなった。職の不安定性とメンタルヘルス不調の関連性の変化は,低収入を調整してもわずかであった。
結論 日本人労働者において,低収入は労働者のメンタルヘルス不調と関連することが観察された。低収入の労働者におけるメンタルヘルス不調のリスク増加の一部は職の不安定性によって説明され,職の安定の確保は,労働者のメンタルヘルスの所得格差を軽減する方策となる可能性が示された。
キーワード 収入,職の不安定性,メンタルヘルス,パネルデータ,労働者
|
第62巻第12号 2015年10月 過疎地域に居住する高齢者の介護サービス利用に関する分析杉井 たつ子(スギイ タツコ) |
目的 過疎地域と過疎地域以外における在宅高齢者の介護サービスの利用状況を把握し,生活環境と介護サービスの利用状況の関連を分析することをとおして在宅ケアの課題を明確にする。
方法 平成23年社会生活基本調査を利用した。回答者から65歳以上を抽出し,過疎地域と過疎地域以外に分別した。生活環境は,世帯・家族,住居の種類,自家用車の所有,世帯収入の4項目で比較した。介護サービスは,利用の有無と利用状況について比較した。さらに,介護の必要性が高いことが想定される後期高齢者と高齢者単独世帯の利用状況を比較した。
結果 96,141人(うち過疎地域13,814人,過疎地域以外82,327人)のデータを分析した。過疎地域は,後期高齢者が多く,女性が多い特徴があった。高齢者のみ世帯(単独・夫婦世帯)は,過疎地域以外に多かった。過疎地域では,子どもとの同居率が高く,子どもが同一市区町村内にいない割合も高かった。また,家や自家用車の所有率が過疎地域で高く,年間世帯収入100万円未満の割合が過疎地域で高かった。介護サービスの利用の有無には差がなかったが,過疎地域では,週に3日以下の介護サービスの利用が多く,週4日以上の利用が少ない状況にあった。後期高齢者では,過疎地域でサービス利用率が低く,週1日以上の日常的な利用においても少なかった。高齢者単独世帯では,サービス利用の有無で差は認められなかったが,過疎地域で週1日以下の介護サービスの利用が多かった。
結論 介護サービスの利用については,過疎地域において週1日未満の見守り的なサービスが多く,週4日以上の日常的な介護サービスを利用する高齢者が少なかった。全体的に,1人当たりの介護サービスの利用回数が低いことが明らかとなった。特に,後期高齢者や高齢者単独世帯の介護サービスの利用については,過疎地域で介護サービスの利用が低い状況にあった。この要因として,子どもとの同居率が高いことや世帯収入が低い世帯が多いことが考えられる。過疎地域では,子どもとの同居率が高い反面,子どもが近隣や同一市区町村内にいない割合が高く,日常的な支援が受けにくい高齢者が多い。過疎地域では,日常生活支援が必要な高齢者に適切な介護サービスが提供されているかを検証する必要がある。
キーワード 介護サービス,地域格差,地域ケア,過疎地域
|
第62巻第12号 2015年10月 NPO法人の活動分野における保健・医療・福祉の特性武村 真治(タケムラ シンジ) |
目的 ソーシャル・キャピタルの醸成において重要な役割を担う特定非営利活動法人(NPO法人)の活動分野の1つとしての「保健・医療・福祉」の特性を明らかにし,国民の健康・福祉の向上に資するNPO法人の活動を促進するための方策を検討した。
方法 内閣府が運営管理する「NPO法人ポータルサイト」において所轄庁(都道府県,政令指定都市)の認証を受けて登録されているNPO法人のうち,解散または認証取り消しがなされておらず,活動分野が明示されている49,319法人を対象として,活動分野(保健・医療・福祉,社会教育,まちづくり,観光,農山漁村・中山間地域,学術・文化・芸術・スポーツ,環境の保全,災害救援,地域安全,人権・平和,国際協力,男女共同参画社会,子どもの健全育成,情報化社会,科学技術の振興,経済活動の活性化,職業能力・雇用機会,消費者の保護,連絡・助言・援助,条例指定)などの登録データを分析した。
結果 保健・医療・福祉を活動分野とするNPO法人は約6割であった。保健・医療・福祉以外を活動分野とするNPO法人は他の複数の分野の活動を実施していたが,保健・医療・福祉を活動分野とするNPO法人は他の分野で活動していない傾向がみられ,保健・医療・福祉分野単独で活動している割合が大きかった。保健・医療・福祉を活動分野とするNPO法人は,職業能力・雇用機会,人権・平和,地域安全,男女共同参画社会,災害救援,消費者の保護,条例指定の分野で活動している傾向がみられたが,それ以外の分野の活動を実施していない傾向がみられた。活動分野の有無を変数とした因子分析の結果,保健・医療・福祉,人権・平和,男女共同参画社会に共通する因子が抽出された。
結論 NPO法人の活動分野の中で保健・医療・福祉は最も多く,今後もNPO法人が一定の役割を担っていくことが可能であると考えられるが,保健・医療・福祉は専門性が高いため,他の活動分野からの参入が阻害されている可能性がある。保健・医療・福祉の行政部門は,その連携体制を人権・平和,男女共同参画社会などに拡大し,保健・医療・福祉分野のNPO法人が関与する他の活動分野でも行政との協働が可能になるように支援する必要がある。
キーワード 特定非営利活動法人(NPO法人),ソーシャル・キャピタル,保健・医療・福祉,人権擁護
|
第62巻第12号 2015年10月 小児科標ぼう医不在町村における
|
目的 小児科標ぼう医不在町村における小児保健事業の実施方法については,十分な知見がない。これまで,筆者は北海道内の小児科標ぼう医不在53町村について調査を行った結果,多くの町村が乳幼児健診は集団健診,予防接種は個別接種として実施していることが明らかになった。今回の研究では,調査対象を全国の小児科標ぼう医不在町村に拡大し,乳幼児健診や予防接種の実施方法を明らかにする。さらに,これらの町村における乳幼児健診受診割合,健診における異常判定割合および予防接種割合を小児科標ぼう医がいる市町村と比較する。
方法 各市町村における小児科標ぼう医の有無は,平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査によった。小児科標ぼう医がいない町村における乳幼児健診および予防接種の実施方法,担当する医師の標ぼう診療科および医師の派遣元について,各町村の母子保健部局にアンケート調査を行った。また,乳幼児健診および予防接種の対象者数,受診・接種者数,ならびに乳幼児健診における異常判定割合は,平成23年度地域保健・健康増進事業報告から引用した。
結果 乳幼児健診は,ほとんどすべての町村が集団健診を実施しており,約7割の町村が外部の医療機関から小児科医(主たる小児科標ぼう医)の派遣を受けていた。一方,三種混合,ポリオおよび麻しん・風しんワクチンは,約8割の町村が個別接種を行っていた。しかし,担当する医師の診療科を小児科標ぼう医に限定する町村は集団接種・個別接種ともに約3割であった。各市町村の1歳6カ月児健診や3歳児健診の受診割合は,小児科標ぼう医の有無で大きな差異を認めなかったが,1歳6カ月児健診における異常判定割合は小児科標ぼう医不在町村でわずかに低かった。また,小児科標ぼう医不在町村の平成23年度における接種割合は,標ぼう医のいる市町村と比べて,三種混合ワクチン1期追加やポリオワクチン2回目では低く,麻しん・風しん2期ではわずかに高い傾向がみられた。
結論 小児科標ぼう医のいない町村の多くは,乳幼児健診については集団健診を実施し,小児科標ぼう医の派遣を他の市町村から受けていた。一方,予防接種では各医療機関に個別接種を委託し,担当医を小児科標ぼう医に限定している町村は少なかった。乳幼児健診の受診割合は標ぼう医がいる市町村と比べて大差がないが,予防接種割合については三種混合,ポリオワクチンでは低く,麻しん・風しんワクチンではわずかに高い傾向が認められた。
キーワード 小児科標ぼう医,乳幼児健診,予防接種,医師不足,小児保健事業
|
第62巻第12号 2015年10月 大都市圏の高齢単身世帯における
中島 民恵子(ナカシマ タエコ)中西 三春(ナカニシ ミハル) |
目的 本研究は,65歳以上の単身世帯(以下,高齢単身世帯)のうち,調査時点で在宅生活を継続している要介護高齢者と施設等へ移行した要介護高齢者の比較を通して,高齢者が在宅生活から施設等に移行する要因を明らかにすることを目的とした。
方法 大都市圏の6つの自治体の居宅介護支援専門員を対象に,担当している事例に関する質問紙調査を実施した。分析に使用する変数すべてに回答があった在宅継続224事例,施設等移行82事例を対象に,在宅継続か否かの種別を従属変数とするロジスティック回帰分析を行った。
結果 在宅継続の事例(以下,継続事例)の男性の割合は27.7%と施設等移行の事例(以下,移行事例)の35.4%に比べると低く,要介護高齢者本人のADLの自立度,認知症自立度については継続事例の方が良い状態であった。サービス利用に関しては,支給限度額割合は継続事例が74.1%と移行事例の66.8%と比べると高い一方,家族による身体介護の月間実施数は移行事例が6.7回と継続事例の3.8回に比べて高い状況であった。在宅継続意思は,本人の意思および家族の意思に関しては「あり」は継続事例が89.7%,51.8%と移行事例(65.9%,30.5%)よりも高かった。ロジスティック回帰分析の結果,要介護高齢者本人が男性であり,ADLの自立度が低く,認知症自立度が低く,本人および家族の在宅継続意思が低い方が施設等移行に該当しやすく,介護保険利用の支給限度額に対するサービス費用の比率が高い方が在宅継続に該当する傾向がみられた。
結論 本研究では,高齢単身世帯の要介護高齢者の施設等の移行の要因について,本人,家族,サービス(環境)の側面から明らかにした。さらに都市部において増加が見込まれる高齢単身世帯の自宅での生活支援のあり方に関する検討に貢献するものである。今後はパネル調査等を通して,在宅の継続のプロセスや規定要因等も詳しく検討していくことが望まれる。
キーワード 高齢単身世帯,要介護高齢者,在宅継続,施設・病院移行
|
第62巻第12号 2015年10月 都市部におけるセーフスクール推進に向けた
臺 有桂(ダイ ユカ) 田髙 悦子(タダカ エツコ)田口 理恵(タグチ リエ) |
目的 今日の都市部において,成長発達の過程にある学童の心身の健康や生活上の安心・安全を脅かす主要な事象として「傷害(injury)」があげられ,その発生は障害や死など重大な結果を招く恐れがある。そこで,本研究では,都市部在住の学童における,主要な傷害の実態およびリスク要因を把握・検討した。
方法 首都圏A市a行政区内4中学校に在籍する2年生全数459名に対して,無記名自記式アンケートを用いたクラス単位の集合調査法を実施した。 調査項目は①基本属性,傷害リスク要因として②環境要因,③個人要因(認知的ソーシャルキャピタル,ストレス対処能力,ライフスキル,生活習慣),④主要傷害である「スポーツ・運動中のけが」「転倒・転落」「溺水」「犯罪」「暴力・虐待」「交通事故」の過去1年間の受傷経験(ヒヤリハットを含む)の有無である。分析は,ロジスティック回帰分析を用いて,傷害とリスク要因の関連について検討した。
結果 対象者459名のうち有効回答450名(98.0%)であった。対象者は,男子232名(51.6%),女子218名(48.4%)であった。対象者における過去1年間の受傷経験では,「スポーツ・運動中のけが」263名(58.4%)が最も多く,次いで「転倒・転落」138名(30.7%),「犯罪」71名(15.8%)であった。傷害とリスク要因間では,スポーツ・運動中のけがで「性別」(オッズ比(OR)=2.07),溺水で「生活習慣:就寝時間」(オッズ比(OR)=2.77)「生活習慣:平均睡眠時間」(OR=2.48),犯罪で「地域環境の満足度」(OR=0.78),暴力・虐待で「性別」(OR=3.91)「認知的ソーシャルキャピタル(SC)」(OR=0.91)「ストレス対処能力(SOC)」(OR=0.95)が有意であった。
考察 傷害の受傷経験に「地域環境の満足度」「認知的SC」「SOC」の低さ,生活習慣の睡眠が関連していることが示唆された。学童を傷害から守るには,心身の健康の保持や危険を回避するスキル習得のための教育をはじめ,セーフスクールの理念に基づき,傷害の発生防止に向けた他分野と協働したコミュニティ・ネットワークの構築が必須であるといえる。
キーワード 傷害,リスク要因,セーフスクール,セーフコミュニティ,学校,学童
|
第62巻第12号 2015年10月 市町村単位の転倒者割合と歩行者割合に関する地域相関分析-JAGES2010-2013連続横断分析より-長嶺 由衣子(ナガミネ ユイコ) 辻 大士(ツジ タイシ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) |
目的 2015年4月からの第6期介護保険事業計画では,地域づくりによる介護予防に重点がおかれ,以前にも増して地域診断の重要性が高まっている。本研究では,市町村単位の地域診断の参考指標を探索するため,高齢者の1日平均30分以上などの歩行者割合(以下,歩行者割合)と転倒者割合の間に相関があるか,経年変化でも歩行者割合が増加した市町村ほど転倒者割合は減少したか,高齢者の歩行者割合と関連する地域要因は何かについて,地域相関研究を行った。
方法 本研究は2010年に全国31市町村,2013年に全国30市町村で実施された日本老年学的評価研究(JAGES)から,両時期に参加した23市町村を対象とした。前期高齢者・後期高齢者は層別化した。転倒者割合と歩行者割合についてスピアマンの順位相関分析にて相関係数を算出し,続いて歩行者割合が増加した市町村ほど転倒者割合は減少したかを明らかにするため,2010年から2013年への3年間の両変数の変化量間の相関係数を算出した。最後に,対象者の属性,環境等の変数の集計値と歩行者割合の相関係数を算出した。
結果 歩行者割合は2010→2013年で,前期高齢者70.9%→79.1%,後期高齢者59.8%→71.0%と増加していた。両年で前期高齢者・後期高齢者とも,歩行者割合と転倒者割合の間に負の相関が認められた(ρ=-0.18~-0.67)。3年間の両変数の変化量間の相関では,歩行者割合が増加した市町村ほど転倒者割合が減少していた(前期高齢者ρ=-0.53,後期高齢者ρ=-0.37)(ρ<0.05,ρ<0.1)。歩行者割合と繰り返し有意な相関を認めた要因は,前期高齢者でスポーツ組織参加,趣味の会参加,自宅から1㎞以内に運動・散歩に適した歩道あり,で正の相関,等価所得200万円未満で負の相関を認めた。後期高齢者では,自宅から1㎞以内に運動・散歩に適した歩道あり,で正の相関を認めた。
結論 歩行者割合が高い市町村では転倒者割合が低く,歩行者割合が増加すると転倒者割合は減少するという経時的変化も確認された。同時に,歩行者割合と関連するいくつかの地域要因も認めた。今後,市町村を単位として高齢者の転倒状況や歩行状況を把握し,さらにそれらの経年変化を評価することは,地域診断や市町村の転倒予防事業の評価を行う際に有益と思われた。
キーワード 地域診断,転倒,1日平均歩行時間,経年変化,社会参加,建造環境(built environment)
|
第62巻第13号 2015年11月 青森県民の食塩摂取量の推移に関する考察熊谷 貴子(クマガイ タカコ) 伊藤 治幸(イトウ ハルユキ) 真野 由紀子(マノ ユキコ) |
目的 青森県民の平均寿命は,男性の場合で30年以上前からわが国で最も短く,その原因としてがん,心疾患,脳血管疾患による高い死亡率が報告されている。これらの疾患の一因に食塩摂取量が関連することから,減塩対策が実施されている。今後,より一層の減塩活動を推進するうえで食塩摂取量の推移を検証することは重要である。そこで本研究では,青森県内において国ならびに県が実施した栄養調査,尿中塩分排泄量調査報告書のデータから食塩摂取量の推移を性・年齢階級別に検討し,その変化を考察することを目的とした。
方法 1980年から2010年に実施された国民栄養調査,国民健康・栄養調査,青森県県民健康・栄養調査報告書のうち,満1歳以上の食事調査結果を用いた。また,尿中塩分排泄量は,2001年と2005年の青森県県民健康・栄養調査から20歳以上の結果で検討した。性・年齢階級別の食塩摂取量の推移は,食事調査および尿中塩分排泄量の双方で青森県県民健康・栄養調査結果を用い,年齢区分が統一されている2001年,2005年,2010年の満1歳以上から検討した。
結果 食事調査による青森県の1日当たりの食塩摂取量の推移は,近年は減少傾向がみられ,2010年には10.2gと全国平均値と同値になった。性別にみると男性は12.4g(2001年)から11.0g(2010年)へ,女性は11.0g(2001年)から9.6g(2010年)へ減少し同時にエネルギー摂取量も減少していた。男性の15~19歳ではエネルギー摂取量が増加し続けており,食塩摂取量も増加傾向だった。女性の7~14歳ではエネルギー摂取量が減少しても食塩摂取量は増加していた。尿中塩分排泄量では,男性で14.3g(2001年)から14.2g(2005年),女性では13.1g(2001年)から12.7g(2005年)であった。
結論 食塩摂取量の推移は,食事調査では減少傾向にあり,現在は全国平均と同程度であるが,尿中塩分排泄量でみれば食事調査結果より多い可能性がある。性・年齢階級別では,食事調査および尿中塩分排泄量の双方で年齢により増減がみられた。食塩摂取量の把握においては,食事調査と尿中塩分排泄量を同時に調査し,性・年齢階級別に把握することが重要である。
キーワード 食塩摂取量,尿中塩分排泄量,エネルギー摂取量,県民栄養調査,青森県
|
第62巻第13号 2015年11月 中高年男性における禁煙後の体重変化が
道下 竜馬(ミチシタ リョウマ) 松田 拓朗(マツダ タクロウ) 清永 明(キヨナガ アキラ) |
目的 本研究では,中高年男性における禁煙後の体重変化がメタボリックシンドロームの危険因子に及ぼす影響について検討した。
方法 2008年に特定健康診査を受診し,喫煙習慣があり5年間追跡可能であった男性66名を対象とした。本研究では,2009年の特定健康診査において禁煙が達成でき,2013年まで禁煙を継続できた者のうち,2009年の体重が2008年の体重よりも増加した者を体重増加群(n=10,平均年齢55.9歳,体重66.5㎏),体重が維持・低下していた者を体重維持・低下群(n=12,平均年齢53.1歳,体重66.3㎏)とし,2008年から2013年まで喫煙を継続した者を喫煙継続群(n=44,平均年齢53.3歳,体重65.1㎏)とした。LDL-コレステロール,HDL-コレステロール,中性脂肪,空腹時血糖,ヘモグロビンA1c(HbA1c),身長,体重,腹囲,安静時血圧を測定し,3群間におけるベースライン時と1年後,5年後の各危険因子の変化について検討した。
結果 追跡1年後,いずれの群においても各危険因子の有意な変化は認められなかったが,体重増加群は体重維持・低下群,喫煙継続群に比べて体重,腹囲の変化量が有意に大きかった(p<0.05)。追跡5年後の結果,体重増加群,体重維持・低下群ともにベースライン時に比べて各危険因子の有意な差は認められなかったものの,喫煙継続群では収縮期血圧,HbA1cが有意に増加し(p<0.05),HDL-コレステロールが有意に低下した(p<0.05)。また,喫煙継続群は体重増加群,体重維持・低下群に比べて収縮期血圧,HbA1c,HDL-コレステロールの変化量が有意に大きかった(p<0.05)。各群における体重の変化量と各危険因子の変化量との関係について検討したところ,腹囲を除く危険因子との間には有意な相関関係は認められなかった。
結論 本研究の結果より,禁煙に伴い一時的に体重が増加することがあるが,長期的には禁煙することによってメタボリックシンドロームのリスクを軽減させることが可能であるため,禁煙が達成できるよう支援する必要があると考えられる。
キーワード 禁煙,体重変化,メタボリックシンドローム危険因子,特定健康診査
|
第62巻第13号 2015年11月 手術室看護師の特性的自己効力感,
平 尚美(タイラ ナオミ) 柏木 公一(カシワギ キミカズ) 小澤 三枝子(オザワ ミエコ) |
目的 自己効力感とは,ある結果を見いだすための行動を自分はどの程度うまく行うことができるかの確信である。高い自己効力感はストレスを緩衝し,看護師の職業継続意思に関連する。自己効力感には,特定の課題や場面に特異的に影響を及ぼす「領域固有の自己効力感(SSE)」と,具体的な状況に依存せず,より一般化した日常生活場面における行動に影響する「特性的自己効力感(GSE)」の2つがある。本研究の目的は,手術看護に関する領域固有の自己効力感を測定する尺度を開発することと,特性的自己効力感と領域固有の自己効力感が手術室勤務継続意思に及ぼす影響を明らかにすることである。
方法 特定機能病院31施設の手術室に勤務する看護師・准看護師1,206名を対象に無記名自記式質問紙調査を行った。調査内容は「特性的自己効力感」「領域固有の自己効力感」「手術室勤務継続意思」「自己効力感に関連する因子」などである。調査票の配布は看護部に依頼し,郵送で回収した。
結果 回収数628(回収率52.1%)のうち,有効回答618名(51.2%)を分析対象とした。手術看護に関する領域固有の自己効力感5項目のクロンバックのα係数は0.87で内的整合性を確認した。また特性的自己効力感6項目を合わせた11項目で因子分析を行った結果,2因子に分かれ弁別的妥当性を確認した。特性的自己効力感との相関係数は0.57で併存的妥当性を確認した。その後,特性的自己効力感・領域固有の自己効力感・手術室勤務継続意思の3つの関連について共分散構造分析(n=493)を行った結果,手術室勤務継続意思に影響するのは,領域固有の自己効力感であった。領域固有の自己効力感には,手術室内のソーシャルサポートや患者との関係,手術看護に関する教育などが関連していた。
結論 手術看護に関する領域固有の自己効力感は,本研究によって開発された5項目の尺度によって測定可能と考える。手術室看護師の勤務継続意思に影響するのは,特性的自己効力感より,手術看護に関する自己効力感であることが示唆された。手術室看護師が現在所属する手術室で勤務し続けようとする意思を保つには,領域固有の自己効力感を高めることが有効である可能性がある。
キーワード 手術室,看護師,特性的自己効力感(GSE),領域固有の自己効力感(SSE),勤務継続意思
|
第62巻第13号 2015年11月 日本人高齢者の孤食と食行動およびBody Mass Indexとの関連:
谷 有香子(タニ ユカコ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) 近藤 尚己(コンドウ ナオキ) |
目的 日本人高齢者の孤食と食行動およびBody Mass Indexとの関連を世帯状況ごとに検討することを目的とした。
方法 JAGES(日本老年学的評価研究)のデータのうち,食事状況の質問項目が含まれ,かつ除外基準に該当しない65歳以上の男性38,690人および女性43,674人を対象とした。食事状況,世帯状況,身長・体重等を自記式質問票で調査した。世帯状況は同居または独居,食事状況はひとりで食事をしている(孤食)または他者と食事をしている(共食)の2区分とした。ポアソン回帰分析を用い,食行動(欠食,野菜・果物の低摂取頻度)とBody Mass Index(BMI:肥満,過体重,低体重)について年齢,教育歴,等価所得,疾病の有無,残存歯数を調整したAdjusted-Prevalence Ratio(APR)および95%信頼区間を算出した。
結果 同居群では男性5.1%,女性7.9%が孤食であったのに対し,独居群では男性87.9%,女性81.7%が孤食であった。世帯状況で層化して解析した結果,孤食が食行動に与える影響は独居群よりも同居群において大きい傾向が認められた。世帯と食事状況で4群に分けて解析した結果,同居かつ共食群と比較すると,男性では独居かつ孤食群でのみ肥満(BMI>30.0㎏/(m)2以上)が有意に多いのに対し,女性では同居かつ孤食群で有意に多かった。一方,同居かつ共食群と比べると,男性のみ世帯に関わらず孤食と低体重(BMI<18.5㎏/(m)2)との有意な関連が認められた。
結論 男性では独居で孤食であること,女性では同居で孤食であることが不適切な食行動(欠食,野菜・果物の低摂取頻度),肥満,低体重のリスクが高い可能性が示唆された。高齢化に伴う世帯状況の変化に介入することは困難であるが,家族や友人,近隣の人をまきこんで共食を進めることが高齢者の食行動や体重管理に効果的かもしれない。
キーワード 孤食,欠食,野菜・果物摂取,肥満,低体重
|
第62巻第13号 2015年11月 産業保健の政策と学術の国際動向堀江 正知(ホリエ セイチ) |
目的 産業保健に関して,わが国では労働安全衛生法に基づき企業が労働者の健康管理を行う体制が確立されてきたが,国際的には新しい動きもある。そこで,産業保健の政策と学術に関する国際動向を調査してわが国の現状と比較することを目的とした。
方法 ILO,WHO,ISO,EU,アメリカ合衆国およびわが国が近年公表している産業保健に関する文書から政策動向をまとめ,産業医学に関係する学術誌に最近掲載された論文から学術動向をまとめ,これらの結果から課題を検討した。
結果 ILOは,国がすべての労働者を対象とした職場の産業安全,産業保健,職場環境で一貫した政策の策定,実施,評価を行い,労使と独立の立場から産業保健を供給し発展させること,また,企業が職場の有害要因による健康障害を予防することを求めている。WHOは,「ワーカーズ・ヘルス」という世界行動目標を提唱し,産業保健の知見を一般の疾病予防や健康増進活動に広げて「健康職場」を構築し,雇用,経済,貿易,環境保護の政策とも関連づけようとしている。ISOは,労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格化を検討している。EUは,「労働安全衛生分野の戦略的枠組」で2020年までに先端産業技術や高齢化への対策のほか各国における法制度の調整と簡素化等を推進している。アメリカ合衆国は,「ヘルシーピープル2020」の中で国家安全衛生研究計画(NORA)による成果の社会実装を推進している。わが国は,第12次労働災害防止計画や健康日本21(第二次)で長時間労働,メンタルヘルス,腰痛,熱中症等の対策を重点的に推進している。一方,最近1年間に産業医学関係の18誌に掲載された1,861論文は,職場・作業が労働者の健康,症状,疾病に与える影響を探究したものが大半で,物理化学的な要因に加えて心理的,社会経済的な要因も活発に研究されていた。
結論 産業保健は,労働政策と保健政策の重複領域として体系化されてきたが,両政策には視点や手法の相違がある中で,近年,産業保健の枠組みを活用した保健政策の推進が企図されている。産業医学の特徴である曝露の概念を家庭,学校,地域にも適用することによって保健政策を活性化できる可能性がある。また,わが国の法令には小規模事業場への適用やハイジニストの活用が不十分といった課題がある。欧米では,労働市場の国際化から,法令の簡素化,統一化とともに自律的なリスクアセスメントの推進による成果重視への政策転換が進んでおり,わが国の政策も国際標準との整合性を図る必要がある。
キーワード 産業保健,労働衛生,健康政策,ILO,WHO,ワーカーズ・ヘルス
|
第62巻第15号 2015年12月 医薬品と特定保険医療材料(医療機器)の
野田 龍也(ノダ タツヤ) 田倉 智之(タクラ トモユキ) 中村 哲也(ナカムラ テツヤ) |
目的 医薬品と特定保険医療材料(医療機器)の価格決定に関する定量的な手法を検討した。
方法 医療用医薬品の保険償還価格(薬価)における原価計算方式の「営業利益率」の補正率,および特定保険医療材料の支給に要する保険償還価格(基準材料価格)における類似機能区分比較方式の「画期性・有用性加算」と「改良加算」の加算率について,チェックリスト形式の定量化基準を作成した。作成にあたっては,過去の算定事例との整合性に留意しつつ,専門家による妥当性の検討を加えた。
結果 薬価の原価計算方式については,原価計算方式により薬価が算定された42品目について加算的または減算的補正の定量化基準を構築し,補正率は-50~100%の範囲となった。この補正率算出のルールに従って算出した補正率と,実際に適用された補正率の差はおおむね±10%の範囲内に収まった。基準材料価格の類似機能区分比較方式については,画期性加算および有用性加算,改良加算について加算要件の定量化基準を構築した。特定保険医療材料74件につき,本研究の方式による加算率と過去の実際の加算率を比較したところ,加算率の分布状況は5割以上が一致する傾向にあった。特定保険医療材料においては,製品の多様性や術者による効果の違い,長期的な耐久性など,医薬品にはない特性があり,これらの特性を定量化基準に盛り込むこととなった。
結論 本研究では,薬価および基準材料価格の算定ルールに基づき,個別の新製品が一定の加算または減算の対象に該当すると判断された場合に,その細分化した要件項目への該当/非該当をチェックシート形式により確認することで補正率(%)が一意に定まる定量化基準を提案した。これらの定量化基準を利用することで,薬価および基準材料価格について,予見性や透明性の高い補正ルールの運用が可能となると考えられる。
キーワード 薬価,基準材料価格,定量化基準,原価計算方式,類似機能区分比較方式
|
第62巻第15号 2015年12月 超高齢団地の居住者が抱える生活上の不安・困難と支援課題-全戸調査の自由記述回答分析-佐藤 惟(サトウ ユイ) 児玉 桂子(コダマ ケイコ)菱沼 幹男(ヒシヌマ ミキオ) 大島 千帆(オオシマ チホ) |
目的 全国平均を大幅に上回るスピードで高齢者世帯と単身世帯の増加する大規模団地において,居住者自身が感じている様々な生活ニーズを明らかにすることで,年齢・居住年数・経済階層など多様なバックグラウンドを持つ人々が,共に支え合い暮らしていくために必要な地域生活支援の手掛かりを得ることを目的とした。
方法 2013年12月1日から20日にかけて,団地の全居住者を対象に実施したアンケート調査の自由記述回答を分析した。はじめにKH Coderを用いた計量テキスト分析から頻度分析を行い,データの大まかな全体像を明らかにした上で,出現頻度の高い言葉を中心に,回答内容を精査した。さらに,性別,住居形態,居住年数,年齢などの外部変数に着目し,各属性別に言及率の高い言葉についても抽出を行った上で,自由記述回答の原文を参照しながら考察を行った。
結果 3,100世帯に調査票を配布し,白紙等を除き1,002件(32.3%)の回答を得た。分析の結果,「高齢」「一人」「不安」「エレベーター」「階段」等の言葉が,上位に抽出されていた。このほか,「団地内」「自治会」「活動」「参加」といった身近な地域のことに関する言葉は,居住年数が10年未満の比較的新しく入居してきた層や40代以下の若年世代,60代の定年を迎える世代で言及率が高く,「家賃」「年金」といった経済的内容は賃貸部分の居住者による記述が多い傾向にあった。階段昇降の負担やエレベーターの設置を訴える声では,買い物や荷物の運搬が困難であることへの言及が多かった。将来的な地域活動への参加意向や,地域レベルでの協力体制,近隣とのより密な交流を望む声が多数聞かれる一方,世代や居住年数による感覚の違いなどから,近所付き合いに難しさを感じる者も多い様子がうかがえた。
結論 一人暮らしの者が増え緊急時等への不安が増している一方,住民による支援意識も高まっている。特に比較的最近になって入居した者や,仕事を退職した者への呼びかけを強化することが,居住者の地域参加を促す上で有効な支援策となる可能性がある。また,分譲に比べ賃貸居住者では経済的な不安を述べている者が多く,地域住民との関係をとり結び,助け合い活動を喚起するためには,様々な所得階層の者が集う「ミクストコミュニティ」を目指す必要性が示唆された。
キーワード 団地,生活ニーズ,地域生活支援,自由記述,計量テキスト分析
|
第62巻第15号 2015年12月 わが国における専門医の地理的分布等に関する検討堀岡 伸彦(ホリオカ ノブヒコ) 堀口 逸子(ホリグチ イツコ) 坂上 裕樹(サカガミ ユウキ)丸井 英二(マルイ エイジ) 谷川 武(タニガワ タケシ) |
目的 わが国の専門医の地理的分布並びに標ぼうする診療科と専門医資格との関連を明らかにする。
方法 平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査に基づき,医師,専門医の地理的分布について分析を行った。専門医数と人口密度,医学部入学定員,臨床研修医在籍数との関連についてスピアマンの順位相関係数を求めた。さらに,人口密度ごとに標ぼうする医師数の増加率の低い診療科と高い診療科の専門医数の比を求めた。また,各診療科を標ぼうする専門医数を各診療科別医師数で除し,「専門医取得率」を計算した。
結果 都道府県別の人口10万人当たりの医師数と専門医数は,いずれも約2倍の偏在が認められた。二次医療圏別では,医師数で15倍,専門医数では67倍もの偏在が認められた。一方,人口密度ごとの医師数の増加率の低い診療科と高い診療科の専門医数の比は,人口密度との関連は認められなかった。また,都道府県別の専門医数は,臨床研修医在籍数と強い正の関連が認められた(p<0.001)。各診療科別の専門医取得率で最も高いのは脳神経外科の76.3%,低いのは内科の12.1%であった。外科は病院医師の方が診療所医師よりも高い専門医取得率を示していた。
結論 二次医療圏別の専門医は,医師よりも偏在が大きく,専門医の診察を受けることを希望する患者にとって公平性が保たれていないことが示された。医師よりも専門医の偏在が大きい原因として,標ぼうしている医師数が増加している診療科の専門医が人口密度の高い地域に集中している可能性を予想していたが,今回の分析結果からは否定された。一方,都道府県別の専門医と医師の偏在は同程度であり,都道府県単位では一定レベルで専門医へのアクセスが確保されていると考えられた。都道府県ごとの専門医数は,医学部入学定員よりも臨床研修医在籍数と関連が強く,専門医の地域偏在をさらに解消するためには,臨床研修医在籍数の増加を促進する取り組みが有効である可能性が示された。また,専門医取得率は多くの科で40%から60%程度であり,内科は12%と最も少なかった。今回の結果から,相当数の医師が専門医を取得せずに,その診療科を標ぼうしていることが示された。本研究は,専門医の地理的分布を全国的に分析した初めての研究である。各分野の専門医の適切な養成,配置は医療政策上重要な課題であり,今後も様々な観点から継続的に分析し,全国民が専門的な医療に公平にアクセスできるような施策を実施することが重要と考えられる。
キーワード 医師・歯科医師・薬剤師調査,専門医,総合診療医,医師数,地域偏在,研修医
|
第62巻第15号 2015年12月 介護支援専門員によるインフォーマル・サポート活用に影響を与えるケアマネジメント実践の検討橋本 力(ハシモト チカラ) 岡田 進一(オカダ シンイチ) 白澤 政和(シラサワ マサカズ) |
目的 本研究では,介護支援専門員によるインフォーマル・サポート活用に影響を与えるケアマネジメント実践について明らかにすることを目的とした。
方法 東京都,横浜市,名古屋市,大阪市,神戸市の居宅介護支援事業者のうち,800カ所を無作為に抽出し,各事業者につき1名,計800名の介護支援専門員を対象とした。調査方法は,自記式調査質問紙を用いた無記名の郵送調査を行った。調査票の回収数は379通,回収率は47.4%であった。分析方法として強制投入法による重回帰分析を用いた。この分析では,介護支援専門員によるインフォーマル・サポート活用を3つの合成変数として算出した「家族の活用」「近隣・友人の活用」「地域のインフォーマル団体等の活用」を従属変数とし,関連要因として想定した性別,年齢,経験年数,情報把握や情報収集に関わる合成変数を独立変数とした。
結果 「家族の活用」では,「家族に関する情報把握」(β=0.362)および「要援護者の支援時における多方面からの情報収集」(β=0.234)が,それぞれ0.1%水準で有意な関連を示した。「近隣・友人の活用」では,「近隣・友人に関する情報把握」(β=0.514)が,0.1%水準で有意な関連を示した。「地域のインフォーマル団体等の活用」では,「地域のインフォーマル団体等に関する情報把握」(β=0.363)および「地域のインフォーマル団体等との交流」(β=0.342)が,それぞれ0.1%水準で有意な関連を示した。
結論 インフォーマル・サポートの活用においては,アセスメントでのインフォーマル・サポートに関する情報把握が有効であることが明らかとなった。介護支援専門員は,アセスメントにおいてインフォーマル・サポートの情報を的確に把握することで,その活用につなげていくことが求められる。また,家族から支援の協力を得る際は,家族の情報把握に加え,多方面からの情報収集が有効であることが明らかとなった。介護支援専門員は,他職種のワーカーや以前のサービス記録,また家族本人など,多方面からの情報を収集することで,家族の状況を正確に理解し,その上で,支援の協力を求めていくことが必要である。さらに,地域のインフォーマル団体等に関しては,インフォーマル団体等との交流が,その活用に影響を与えていることが明らかとなった。介護支援専門員は,活用の可能性が期待できる地域のインフォーマル団体等に関しては定期的な交流を行っていくことが求められる。
キーワード 介護支援専門員,ケアマネジメント,インフォーマル・サポート活用,アセスメント
|
第62巻第15号 2015年12月 高齢者介護施設の介護職員の感染予防方法の実施状況と呼吸器感染症および感染性胃腸炎への罹患との関連佐々木 晶世(ササキ アキヨ) 佐久間 夕美子(サクマ ユミコ) 大竹 まり子(オオタケ マリコ)加藤 綾子(カトウ アヤコ) 叶谷 由佳(カノヤ ユカ) 佐藤 千史(サトウ チフミ) |
目的 高齢者介護施設での感染予防対策は重要であるが,介護職員の実際の感染予防方法の実施状況と介護職員自身の感染症罹患との関連についての報告はない。そこで,本研究は高齢者介護施設職員の感染予防方法(マスク・手洗い・うがい・エプロン)の実施状況と介護職員の呼吸器感染症および感染性胃腸炎への罹患との関連について調査することを目的とした。
方法 特別養護老人ホーム10施設に勤務する介護職員269名を対象とし,自記式質問紙調査を2012年6~7月に郵送法で実施した。調査項目は年齢,性別,経験年数,勤務しているフロア,インフルエンザワクチンの接種の有無と接種時期,通勤方法,定期的に立ち寄る場所,本人または家族のインフルエンザ罹患の有無と罹患した場合の対処方法,インフルエンザ以外に罹患した感染症(感染性胃腸炎や感冒等)の有無,手洗い・うがい・マスク着用を行う状況と方法,エプロンの使用頻度と洗濯回数とした。感染症罹患の有無と業務中の感染予防方法の実施状況との関連について,χ2検定および多重ロジスティック回帰分析で検討した。
結果 調査対象者269名中,217名から返送を得た(回収率80.7%)。感染症有の者の方が「下膳後」に手洗いをしていない者が多かった(p<0.05)。一方,うがいに関して,感染症有の者の方が「業務開始時」「フロア移動前」にうがいをしている者が多かった(p<0.05)。感染の有無でエプロン洗濯回数に有意差がみられ,感染症有の者はエプロンの洗濯回数が少なかった。感染症の罹患に関連する要因について,多重ロジスティック回帰分析を行った結果,「業務開始時のうがい」(OR[オッズ比]:4.13,95%CI〔95%信頼区間〕:1.07-15.95),「配膳時のマスク」(OR:12.11,95%CI:1.80-81.29)に有意差が認められた。
結論 高齢者介護施設の介護職員の感染症罹患に関連する要因として,業務開始時のうがいと配膳時のマスク着用が挙げられた。感染症罹患者の方が業務開始時のうがいと配膳時のマスク着用を行っていたことから,感染症罹患の経験により,業務開始時のうがいおよび配膳時のマスク着用といった感染予防方法につながった可能性が示唆された。
キーワード 高齢者介護施設,介護職員,感染,手洗い,うがい,マスク
|
第62巻第15号 2015年12月 喀痰吸引に関わる訪問介護員と訪問看護師の協働の実際橘 達枝(タチバナ ミチエ) 吉田 浩子(ヨシダ ヒロコ) |
目目的 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により,2012年4月から「介護職員等による喀痰吸引等実施のための制度」が施行され,地域包括ケアシステムに関わる介護職の医行為の実施には,訪問介護員と訪問看護師の連携の強化が必要とされるが,その実態は今だ不明である。そこで本研究は,介護職と看護職のより良い協働の在り方を検討するための新たな実証的知見を得ることを目的として,医行為を手がかりに都市部の在宅療養者の介護・看護を担う訪問介護員と訪問看護師の協働の実態を調査し,その結果からより効果的な協働の手法を検討した。
方法 2013年10月から12月に,首都圏A県の訪問介護員と訪問看護師各1,000人のうち,同意が得られた対象者に,無記名自記式質問紙調査を行った。対象の背景,改正法前後の喀痰吸引の状況,訪問介護員の喀痰吸引に対する意向,協働の経験・内容について,職種の関連を検討するため,χ2検定を用いて分析した。
結果 訪問介護員454人,訪問看護師361人(回収率:45.4%,36.1%)の回答から,誤記や無回答を除外し,訪問介護員194人,訪問看護師213人(有効回答率:19.4%,21.3%)の回答を分析対象とした。訪問介護員(n=194)において,喀痰吸引経験者の割合が同制度施行後に減少しており(同制度施行前9.3%,施行後は8.2%),訪問看護師(n=213)においても,訪問介護員の喀痰吸引を支援した経験がある者の割合が同制度施行後に減少した(施行前18.3%,施行後14.1%)。また,訪問介護員の喀痰吸引実施について肯定的な考え(やむを得ない・必要である)を表明した割合は,訪問介護員(56.2%)が訪問看護師(94.4%)に比べ有意に少なく,制度施行後の訪問介護員の喀痰吸引に対する姿勢は消極的であった。一方,両職種ともに約3割は,自分の家族の喀痰吸引の依頼先として,経験豊富あるいは認定を受けた訪問介護員を選択し,技術の習得により訪問介護員の医行為に対する抵抗感が緩和される可能性が示唆された。また,利用者宅で利用職種が偶然居合わせた場合は積極的に情報交換が行われていることがわかった。
結論 本調査結果から,訪問看護師が計画的に訪問介護員と利用者宅を同行訪問し,指導・支援することで訪問介護員の医行為の習得が可能になり,訪問介護員の医行為の実施促進につながる可能性が示唆された。実践の場で訪問看護師が訪問介護員の行う喀痰吸引等への教育・支援ができる協働の仕組み作りが現状の改善に有効である。
キーワード 訪問介護員,訪問看護師,医行為,協働,地域包括ケアシステム,都市部高齢化
|
第63巻第1号 2016年1月 国民生活基礎調査における
橋本 修二(ハシモト シュウジ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) |
目的 平成22年と25年の国民生活基礎調査における生活影響あり割合(健康日本21(第二次)の健康寿命の基礎資料)に対する生活影響の無回答の影響を評価した。
方法 同調査を統計法33条による調査票情報の提供を受けて利用した。自覚症状と通院の有無ごとに,生活影響ありと生活影響の回答なしの年齢調整割合を算定した。生活影響の無回答者における生活影響の有無を自覚症状と通院の回答状況から推計し,生活影響あり年齢調整割合について,調査対象者(生活影響の無回答者を含む)の推計値と生活影響の回答者の調査値を比較した。年齢調整の標準人口には平成25年の調査対象者を用いた。
結果 生活影響の回答なし割合は平成22年が13%で25年が2%であった。自覚症状または通院がありの場合は,なしの場合と比べて,生活影響あり年齢調整割合は著しく大きかったが,生活影響の回答なし年齢調整割合はほぼ一致した。生活影響あり年齢調整割合について,通院と自覚症状の回答状況による調査対象者の推計値は生活影響の回答者の調査値とほぼ一致し,平成22年では男性12.6~12.7%と女性15.2%,25年では男性12.1%と女性14.6%であり,推計値と調査値の比が1.002~1.005倍であった。
結論 平成22年と25年の生活影響あり割合に対して,生活影響の回答なしがほとんど影響しなかったと示唆された。
キーワード 健康寿命,健康日本21(第二次),日常生活に制限のある期間の平均,国民生活基礎調査,保健統計
|
第63巻第1号 2016年1月 熊本市およびその近郊における主介護者の抑うつ状態に影響を及ぼす要因研究-主介護者の性格特性を加味して-松村 香(マツムラ カオリ) 沼田 加代(ヌマタ カヨ) 畠山 玲子(ハタケヤマ レイコ)小林 きよみ(コバヤシ キヨミ) 工藤 明美(クドウ アケミ) 有田 明美(アリタ アケミ) |
目的 在宅で要介護高齢者を介護している介護者が,介護状況をどのように捉えるかは,その人の性格特性によって異なってくる。本研究は,要介護高齢者を介護する主介護者(以下,介護者)の抑うつ状態に影響を及ぼす要因について,介護者の性格特性と経済的側面を加味して検討を行うことを目的とした。また,本研究に先行して首都圏においても類似の調査を行っているが,地域を変えても同様のことがいえるのか,その結果の普遍性を探ることも目的とした。
方法 熊本市およびその近郊にある居宅介護支援事業所,訪問看護・介護ステーション,デイサービスの合計965カ所のうち,研究の協力が得られた14カ所の事業所を利用している要介護高齢者の介護者161名を対象として自己記入式質問票調査を実施した。
結果 回答が得られた136名(回収率84.5%)から,調査項目に欠損値を持たない121名を有効回答として解析対象とした(有効回答率89.0%)。解析にはt検定,一元配置分散分析,相関係数ならびに階層的重回帰分析を使用した。階層的重回帰分析の結果,介護者の抑うつ状態に影響を及ぼす要因として,介護者の「性別」「介護負担感」の高さ,介護者の性格特性のうち「神経質」の高さ,「調和性」の低さの4要因が関連していた。
結論 介護者の抑うつ状態に影響を及ぼす要因として,「介護負担感」の高さや介護者の「神経質」な性格特性の高さが,地域が違っても同様の結果が得られていることは,その結果に普遍性があると考える。介護者の抑うつ状態の予防には,「介護負担感」の軽減に加えて,介護者自身の「神経質」などの性格特性にも焦点を当て,対象者に合わせた介入や援助を展開することによって,抑うつ状態の予防につながる可能性があると考える。
キーワード 主介護者,抑うつ状態,要因,介護負担感,性格特性,神経質
|
第63巻第1号 2016年1月 A市地域子育て支援拠点事業の利用者評価-2012年度評価における満足度分析-小野セレスタ 摩耶(オノセレスタ マヤ) |
目的 地域子育て支援拠点事業(以下,拠点事業)を利用している保護者への利用者評価調査から,①利用者満足度を構成する要因を明らかにした上で,②利用者満足度を構成する要因と総合満足度との関連を明らかにする。
方法 調査対象者は,近畿地方A市(人口約20万人)の拠点事業(全8カ所)を調査時に利用している保護者である。調査実施方法は,利用者評価票を各事業実施場所に100枚ずつ留め置き記入を依頼し,回収箱に投函する形式をとった。調査期間は,2012年10月2~20日である。分析方法については,研究目的①では探索的因子分析を,研究目的②では,研究目的①より得られた領域別満足度がそれぞれどの程度総合満足度(紹介意向,継続利用意向,全体的満足)に影響するのかを明らかにするために,重回帰分析を行った。
結果 配布800件のうち有効回収数は381件(有効回答率47.6%)であった。研究目的①では,13項目3因子となり,それぞれ「スタッフの対応」(α=0.915),「交流・仲間づくりの機会」(α=0.925),「サービスの提供環境」(α=0.711)と名付けた。研究目的②では,いずれも1%水準で有意なモデルとなった。
結論 本研究では,満足度を構成する因子やそれら因子と紹介意向や継続利用意向,全体的満足との関係性を探索的に明らかにした。拠点事業の満足度を向上するためには,親子の交流や子育ての仲間ができたと感じられるような支援が必要である。そのためは,継続的な利用が必要であり,その際サービスの提供環境は重要な役割を果たすと考えられる。また,親子の交流や子育ての仲間づくりを推進して行くためには,スタッフの対応が重要な役割を果たすといえる。拠点事業に限らず,サービスや事業は利用者の満足度によってのみ評価されるべきものではなく,実施者視点(自己評価等)と利用者の評価が組み合わされ,客観的に評価され初めて説得力が出る。拠点事業は今後さらに保護者のニーズや地域特性に合った運営や支援方法が求められていく。その際,実施者・支援者の視点で運営や支援の在り方等の研究を積み上げていくとともに,利用者評価を取り入れながら方向性を検討することは,利用者視点の重視やサービスの質の向上に欠かせない。さらに多変量解析等詳細な分析を実施し,評価票の精緻化に取り組む必要がある。
キーワード 子ども・子育て支援,地域子育て支援拠点事業,利用者評価,利用者満足,利用者視点
|
第63巻第1号 2016年1月 健常者と認知症者における手指機能と認知機能の性・年齢別変化坪井 章雄(ツボイ アキオ) 林 隆司(ハヤシ タカシ)大橋 幸子(オオハシ サチコ) 目黒 篤(メグロ アツシ) |
目的 健常者の手指機能は,加齢に伴い低下することが知られている。健常者と認知症者の手指機能と認知機能に関する研究は少なく,手指機能と認知能力の関連は報告されているものの,年齢別の検討は不十分である。本研究では,健常者と認知症者の認知機能と手指機能の変化について性別,年齢群ごとに比較検討した。
方法 45歳以上の健常者と認知症者に対して,認知機能の指標として改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)を,手指機能の指標としてIPU巧緻動作検査(Ibaraki Prefectural University Finger Dexterity Test:IPUT)を用いた。
結果 45~94歳の健常者670名(男性242名,女性428名),および45~102歳の認知症者917名(男性206名,女性711名)について,HDS-RとIPUTを測定した。HDS-RおよびIPUTの年齢群別平均値は健常者・認知症者ともに50歳代より徐々に低下する傾向が示された。認知機能および手指機能ともに加齢によって低下していたが,認知症者においては年齢との関連が小さくなっていた。
結論 健常者および認知症者ともに,全体としては認知機能の指標としたHDS-Rと手指機能の指標としたIPUTで有意な負の相関が示された。しかし,認知症者では健常者に比べ弱い傾向が示された。このことは,認知症者では疾病の重症化によりHDS-Rの個人差が大きくなるため,HDS-RとIPUTの関連が小さくなったと考えられる。
キーワード 健常者,認知症者,認知機能,ペグボード,手指機能
|
第63巻第1号 2016年1月 人口の少ない地域における訪問看護ニーズの実態-訪問看護を利用できない地域に居住する要介護者の実態に焦点を当てて-田口 敦子(タグチ アツコ) 吉澤 彩(ヨシザワ アヤ) 岩﨑 昭子(イワサキ アキコ)鈴木 順一郎(スズキ ジュンイチロウ) 永田 智子(ナガタ サトコ) |
目的 本研究では,訪問看護の提供のない地域を含む人口の少ない高知県安芸保健医療圏を対象地域とし,在宅において,「訪問看護が必要であるが訪問看護を利用していない要介護者(以下,潜在ニーズ)」がどの程度いるか,訪問看護事業所のない地域に住む要介護者の特徴,および訪問看護の必要がある要介護者がどのような状況において訪問看護を必要としているのかを明らかにすることを目的とした。
方法 本研究は,質問紙調査(定量調査)とヒアリング調査(定性調査)とを組み合わせて行う定性・定量相互融合法を採用した。定量調査では,安芸保健医療圏の住民が利用する全居宅介護支援事業所32カ所の介護支援専門員を対象に,郵送自記式質問紙調査を実施した。調査項目は,訪問看護の利用および必要性,居住する市町村,性別,年齢,要介護度,介護保険によるサービス利用等であった。定性調査では,訪問看護事業所のない地域にある居宅介護支援事業所17カ所のうち,経験年数10年以上のベテラン介護支援専門員がいる2カ所(3人)を対象に,ヒアリング調査を実施した。介護支援専門員が担当する「訪問看護が必要であるが,事業所がないために利用していない要支援・要介護者」7人について,「訪問看護の必要性がある要介護者がどのような状況において訪問看護を必要としているのか」を尋ねた。調査期間は2013年1~3月であった。
結果 定量調査では,1,621人(有効回答率:76.5%)を分析対象とした。そのうち,訪問看護の利用者は28人(1.7%)であった。また,潜在ニーズは,187人(11.5%)であった。訪問看護事業所がある地域2市村とない地域7市町村を比較したところ,潜在ニーズ187人のうち,訪問看護事業所のない地域に住む者は128人であり,訪問看護事業所のある地域に住む者は59人であった。訪問看護が必要な者における潜在ニーズの割合は,訪問看護事業所のない地域(96.2%)の方が,訪問看護事業所のある地域(73.8%)より有意に高かった(p<0.001)。また,定性調査によると,訪問看護事業所のない地域では,「病状の悪化を防ぐための生活習慣を継続することが難しい」「受診ができず必要な医療処置を受けられない」「本人・介護者の医療処置の習得や病状への判断が難しい」「24時間,医療ニーズに対応する介護者の負担が大きい」「継続性の見込めないボランタリーな支援に支えられている」「介護支援専門員が医療面の調整を担うのに負担が大きい」ことについて,訪問看護を必要とする療養状況があることが明らかになった。
結論 訪問看護事業所のない地域にも訪問看護ニーズが存在し,それらの療養状況は,医療処置や介護力不足の状況において訪問看護を必要としていることが明らかになった。これらのニーズに継続的に対応できる訪問看護サービス提供の仕組みを構築していくことが必要であると考える。
キーワード 訪問看護事業所,人口過疎,潜在ニーズ,提供体制,訪問看護,二次保健医療圏
|
第63巻第1号 2016年1月 肺炎球菌ワクチン接種率の地域差と背景要因田代 敦志(タシロ アツシ) 菖蒲川 由郷(ショウブガワ ユウゴウ)齋藤 玲子(サイトウ レイコ) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) |
目的 高齢者における中学校区別の肺炎球菌ワクチン接種率に関する調査を行い,接種率の背景要因について個人要因と環境要因の双方から実態を明らかにし,定期接種化された後に接種率の向上に必要な取り組みについて検討した。
方法 N市在住の65歳以上の住民を対象として,要支援・要介護認定を受けていない8,000名の高齢者に郵送法で無記名自記式アンケート調査を実施した。57中学校区別に接種率を求め,住民構成を調整した後の地域差を分析した。接種の有無に関連する個人要因についてロジスティック回帰分析に加え,中学校区別の相関分析,個人と校区別集団の2つのレベルでマルチレベル相関分析を実施し,さらに,クラスタ標準誤差を使ったロジスティック回帰分析を行い,集団レベルの環境要因の影響も加味して接種率の地域差を評価した。
結果 肺炎球菌ワクチンの接種率は13.5%(男性14.5%,女性12.5%)で,男性の方が若干高い値であった。年代別では,男女とも前期高齢者では10%以下であり,80~84歳では20%を超えていた。中学校区別の接種率では,5%以下の地域が4カ所ある一方で20%を超える地域も2カ所存在し,性別と年齢を調整した後においても有意(P<0.01)な接種状況の地域差が認められた。ロジスティック回帰分析の結果,ワクチン接種を促進する要因として,高い年齢(P<0.01),低い主観的健康感(P<0.05),呼吸器疾患あり(P<0.01)が認められた。相関分析で中学校区別の接種率と関連する要因は認めず,マルチレベル相関分析において個人レベルでのみ,高い年齢,低い主観的健康感,呼吸器疾患あり,短い教育年数が接種ありと有意に相関した(P<0.01)。また,地域レベルの変数を説明変数に加えクラスタ標準誤差を使ったロジスティック回帰分析において,環境要因として中学校区別の教育年数や所得格差は有意ではなく,個人レベルの年齢,主観的健康感や呼吸器疾患の有無とは異なり,ワクチン接種に与える影響は認められなかった。
結論 高齢で主観的健康感が優れず呼吸器疾患を持った住民が多い地域において,肺炎球菌ワクチンの接種率が高く,調査した範囲で接種の有無に環境要因の影響は認められなかった。また,健康リテラシーが高いと推定される教育年数が長い集団ほど接種率は低い傾向が認められたことから,ワクチンの有用性について広く啓発活動を実施し,現在の健康状態に過信することなくワクチン接種を推奨する取り組みが求められている。
キーワード 肺炎球菌ワクチン,接種率,個人要因,環境要因,クラスタ標準誤差
|
第63巻第2号 2016年2月 市町村における外部委託事業のマネジメントの実態-特定保健指導を例に-鳩野 洋子(ハトノ ヨウコ) 森 晃爾(モリ コウジ) 曽根 智史(ソネ トモフミ) 永田 昌子(ナガタ マサコ)前野 有佳里(マエノ ユカリ) 柴田 善幸(シバタ ヨシユキ) 小橋 正樹(コハシ マサキ) |
目的 保健事業を外部委託する際のマネジメント項目を明らかにしたうえで,特定保健指導の外部委託を例に,外部委託事業のマネジメントの実態を把握することを目的とした。
方法 第一段階として6自治体の保健専門職にインタビューを行い,抽出した項目について,インタビュー対象者に妥当性を尋ね,意見に基づき修正してマネジメント項目を作成した。第二段階として,平成25年4月1日現在の全市町村1,738(災害避難対策区域の自治体を除く)の統括的立場の保健師あてに質問紙を送付し,担当者に配布してもらうよう依頼した。質問内容は,マネジメント項目の実施状況(5件法),外部委託の実施方法・種別,自治体の属性である。
結果 マネジメント項目は38項目に整理された。質問紙調査は,954件の回答が得られ,このうち特定保健指導の外部委託を実施していると回答した対象のうち,外部委託の実施方法および外部委託の種別の回答に欠損がない404件を分析対象とした。外部委託の実施方法は,「部分委託」が75.2%で,種別は「公募型以外の随意契約」が78.0%だった。マネジメントの実施状況では,外部委託の検討段階や外部委託を準備する段階においてはマネジメントを実施している割合が高いが,委託事業者により事業が提供されている段階,評価の段階と進むにつれて実施割合が低くなっていた。
結論 特定保健指導の外部委託事業のPDCAサイクルが十分に回っていない実態が明らかになった。マネジメント項目のさらなる洗練とともに,保健師の外部委託事業のマネジメントに対する意識の啓発と,評価のスキルの向上,委託先の資源が少ない地域でのマネジメントのあり方が課題である。
キーワード 保健事業, 外部委託,マネジメント,特定保健指導,保健師
|
第63巻第2号 2016年2月 地域在住高齢者の運動教室におけるスクエアステップの達成度が体力変化に与える影響
神藤 隆志(ジンドウ タカシ) 藤井 啓介(フジイ ケイスケ) 北濃 成樹(キタノ ナルキ) 角田 憲治(カクタ ケンジ) 大藏 倫博(オオクラ トモヒロ) |
目的 現在,地方自治体が主催する介護予防事業の一つとして運動器の機能向上プログラム(以下,運動教室)が全国各地で盛んに行われており,高齢者の体力の維持・向上に一定の成果をあげている。本研究では,介護予防運動としての有効性が報告され,運動教室の主運動課題として普及が進んでいるスクエアステップを取り上げ,参加者のスクエアステップのステップパターンの達成度が運動教室前後の体力変化に与える影響を検討した。
方法 対象は要支援・要介護認定を受けていない地域在住高齢者33名(69.7±3.6歳,男性4名)であった。スクエアステップを主運動課題とした週1回,1回90分,全11回の運動教室を行い,スクエアステップの達成度の評価として対象者が3カ月間で達成した総ステップパターン数を調査した。体力は平衡性(開眼片足立ち時間),筋力(5回椅子立ち上がり時間),起居移動能力(TUG;Timed Up and Go),歩行能力(5m通常歩行時間),反応性(全身選択反応時間)を評価した。認知機能の評価にはファイブ・コグ検査を用いた。達成度の最頻値を基準に対象者を3群に分け,3群間の体力変化の違いを2要因分散分析により検討した。なお,運動教室前の値に群間の有意差が認められた場合は,その値を共変量に投入した共分散分析を行った。
結果 3カ月間のスクエアステップ実践により達成されたステップパターン数は61.9±11.4パターンであり,達成度の上位群が中位群,下位群と比べて認知機能が有意に高かった(p<0.05)。3群間の体力変化の違いを比較したところ,開眼片足立ち時間において3群間に有意な交互作用が認められ(p<0.05),上位群においてのみ有意な向上が認められた。運動教室前の値で調整するとこの交互作用は消失し,3群における有意な時間の主効果のみ認められた(p<0.05)。この他に3群において有意な時間の主効果が認められた項目は,TUG,全身選択反応時間であった(p<0.05)。
結論 3カ月間の運動教室においてスクエアステップの達成度が高かった者は,運動教室前の認知機能が高かった。一方で,達成度にかかわらず平衡性,起居移動能力,反応性などの体力が向上したことから,スクエアステップは個人に合った難度のステップパターンに取り組むことで,体力への効果が見込める運動課題であることが示唆された。
キーワード 運動教室,Square-Stepping Exercise,身体機能,認知機能
|
第63巻第2号 2016年2月 職域男性の肥満・高血圧・脂質異常と食生活との関連-愛媛県愛南町地域診断モデル事業の取り組みから-
西岡 亜季(ニシオカ アキ) 植田 真知(ウエタ マチ) 松浦 仁美(マツウラ ヒトミ) 井上 和美(イノウエ カズミ) 加藤 泉(カトウ イズミ) 坂尾 良美(マツオ ヨシミ) 廣瀬 浩美(ヒロセ ヒロミ)上田 由喜子(ウエダ ユキコ)
|
目的 公衆衛生では,地域診断に基づいて保健事業を実施し,地域の環境を健康に向けて促進できるようアプローチすることが求められている。愛媛県宇和島圏域は,男女とも健康寿命が県平均より短く,かつ管轄の愛南町は65歳未満で死亡する割合が県下トップの状況にある。そこで,本研究では地域診断推進事業のモデル町である愛南町の20~40歳代の住民の食生活を調査し,40歳代男性が有所見となる要因について明らかにすることを目的とした。
方法 20~40歳代の職域男性231名を対象に,文書にて本研究への参加募集を行い,平成26年10~11月に食生活および食品摂取頻度に関する自記式質問紙調査,味覚感度調査を実施した。項目は,属性,過去1年間に行われた健康診断の結果,自記式質問紙は,田中らの先行研究を参考に普段(過去1カ月)の食生活に関する23項目と食品摂取頻度に関する23項目とした。味覚感度調査には,ソルセイブ(食塩味覚閾値判定ろ紙)を用い塩味を認識する閾値を調べた。食生活および食品摂取頻度については,2つのカテゴリーに再区分し,BMI,血圧,血中脂質との関連についてχ2検定およびロジスティック回帰分析を行い,食品摂取頻度については重回帰分析を行った。
結果 調査の回収率は94%であったが,記入漏れがあった者は除外したため有効回答数は117名(50.6%)となった。「食べるのが速い」男性は,「普通,遅い」男性よりも肥満/脂質異常になるオッズが約3.9倍/2.5倍,また「野菜たっぷりの料理はあまりない」男性は「1日1食以上」野菜を食べる男性よりも肥満/高血圧になるオッズが約3.0倍/3.5倍という結果が得られた。味覚感度と肥満・高血圧・脂質異常との間に関連は認められなかった。
結論 食生活の観点から有所見の要因を検討した結果,肥満が健康課題の1つの要因となっており,「食べるのが速い」「野菜の摂取量が少ない」「濃い味を好む」ことがわかり,「缶コーヒー」「乳酸菌飲料」「缶ジュース」の摂取頻度も影響していた。塩分や砂糖のとり過ぎを意識しない割合は,肥満者よりも肥満でない者の方が有意に高く,将来を見据えた生活習慣病予防の展開には,気づきや意識を高めるツールが必要であることが示唆された。
キーワード 職域男性,地域診断,生活習慣病,公衆衛生,協働,食生活
|
第63巻第2号 2016年2月 特定健診結果とレセプトデータを利用した腹囲と平均年間医療費の関係について
船山 和志(フナヤマ カズシ) 飛田 ゆう子(トビタ ユウコ) 東 健一(ヒガシ ケンイチ) |
目的 生活習慣病予防対策事業の経済効果を簡易に推測することを目的に,特別な検査器具を必要としない腹囲測定値を用い,医療費との関係について検討したので報告する。
方法 全国健康保険協会神奈川支部から提供された横浜市内に在住する被保険者本人のうち,平成24年度の特定健診を受診した88,556人の健診結果と医科レセプトデータをもとに分析を行った。低体重と高度肥満者に該当しないものを分析対象とし,年齢を調整した腹囲ごとの平均年間医療費を推計し,男女別に単回帰分析を行った。
結果 男性では,回帰式はy=2688.8x-79078(R2=0.960),女性では,回帰式はy=2453.3x-52037(R2=0.876)となり,どちらも回帰式と回帰係数は統計的に有意(p<0.01)であった。
結論 本研究の分析対象者においては,腹囲と年齢調整した平均年間医療費推計値は正の相関があり,腹囲1㎝減少につき,男性で2,700円,女性で約2,500円の平均年間医療費が減少していた。ただ,今回の結果は単年度の限られた集団から得られたものであり,対象者の社会状況,経済状況や治療状況等,医療費に大きく影響を与えていると考えられる様々な要因については検討していないため,解釈にはそれらのことを考慮する必要がある。ただ,特別な検査器具を用いずに測定できる,腹囲を用いた経済効果の推測は,市町村の健康づくり教室などの現場で有用と考えられた。
キーワード 特定健診,全国健康保険協会,レセプトデータ,腹囲,医療費
|
第63巻第2号 2016年2月 生活習慣病予防教室に参加した地域住民のQOLの向上とその効果の持続に関する研究
井倉 一政(イグラ カズマサ) 西田 友子(ニシダ トモコ) 榊原 久孝(サカキバラ ヒサタカ) |
目的 これまでのQOLに関する研究の多くは,疾患罹患の有無やQOLの高低によってどのような特徴があるかを考察したものであった。また,特定健康診査・特定保健指導では,運動の実践や食事指導の介入期間の終了後も継続して効果をあげることが期待されているにもかかわらず,散見される介入研究では,その多くが介入前後の比較であり,介入期間終了後もQOLの変化を継続して観察した研究はほとんどみられない。そこで本研究は,生活習慣病予防教室に参加した者と対照群を2年後まで継続して観察し,地域住民のQOLの向上とその持続について考察することを目的とした。
方法 住民健診の受診者(40~69歳の糖尿病,高脂血症の要注意者)に健康教室への参加を募り,無作為に介入群と対照群を100人ずつ選定し,最後まで参加した介入群84人,対照群77人を対象とした。介入群は集団健康教育(運動,栄養)と個別指導,日々の記録のやり取りなどを組み合わせて実施した。集団健康教育は,3カ月間は毎週実施し,3カ月後から1年後までは徐々に頻度を減らし,1年を過ぎてからは実施しなかった。対照群は,健診とその結果に基づく個別保健指導を実施した。両群の介入前,3カ月後,1年後,2年後のQOL(SF-36)の変化を観察した。
結果 身体的健康度である「体の痛み」「全体的健康感」の3カ月後の改善は,介入群の方が大きく,2年後でも同様であった。精神的健康度の「活力」「心の健康」の改善も3カ月後の介入群で向上し,1年後まで介入群で改善が認められたが,2年後では有意な差は認められなかった。
結論 健診結果に基づいて個別保健指導を行うだけでは,QOLの向上を図り,その効果を持続することは難しいと考えられた。特にQOLの精神的健康度の向上とその効果の持続のためには,集団指導の重要性が示唆された。
キーワード QOL,SF-36,効果の持続,生活習慣病予防教室,地域住民
|
第63巻第2号 2016年2月 高齢者向けの集団健診が余命および健康余命に及ぼす影響-草津町介護予防事業10年間の効果評価の試み-西 真理子(ニシ マリコ) 吉田 裕人(ヨシダ ヒロト) 藤原 佳典(フジワラ ヨシノリ) 深谷 太郎(フカヤ タロウ) 天野 秀紀(アマノ ヒデノリ) 熊谷 修(クマガイ シュウ) 渡辺 修一郎(ワタナベ シュウイチロウ) 村山 洋史(ムラヤマ ヒロシ) 谷口 優(タニグチ ユウ) 野藤 悠(ノフジ ユウ) 干川 なつみ(ホシカワ) 土屋 由美子(ツチヤ ユミコ) 新開 省二(シンカイ ショウジ) |
目的 群馬県草津町における介護予防事業の中核を成してきた健診が,余命および健康余命に及ぼす影響を明らかにし,高齢者向け健診の効果を検討することである。
方法 2001年に草津町の70歳以上の地域在宅高齢者を対象に実施した訪問面接調査の応答者のうち,健診会場への移動能力「あり」と判断された者800人について,その後2002年から2005年の4年間に実施した健診の受診回数を調べた(範囲:0-4回)。次いで,4回目の健診が終了した翌月時点で生存が確認された者を,さらに4年11カ月間追跡し,その間の死亡ならびに自立喪失の有無を調べ,4年間の健診受診状況とその後の死亡(余命)および自立喪失(健康余命)との関連を検討した。自立喪失は,新規の介護保険認定または認定なし死亡と定義し,介護保険認定を「要介護2以上」とした基準Aと「要支援以上(全認定)」とした基準Bの2つを設定した。分析では,健診の受診回数により対象者を3群に分類し(0回,1-2回,3-4回),追跡期間中の生存率および自立率の推移をKaplan-Meier法により比較した。その上で,健診の受診頻度の違いによる追跡期間中の死亡および自立喪失のリスクを,性,年齢,2001年時点での総合的移動能力,慢性疾患の既往,心理的変数などの交絡要因を調整変数としたCox比例ハザードモデルを用いて調べた。
結果 健診の受診頻度が高い群ほど,その後の生存率および自立率が良好であった。比例ハザード分析からは,重要な交絡要因を調整しても,健診非受診者に比べて3-4回受診者の死亡リスク(HR=0.57,95%CI=0.36-0.90)および自立喪失リスク(基準A:HR=0.55,95%CI=0.37-0.82)が統計的に有意に低いことが明らかとなった(基準Bでは低い傾向が示された:HR=0.72,95%CI=0.50-1.06)。健診未受診者に比べた1-2回受診者の死亡および自立喪失リスクの低さは有意ではなかった。
結語 草津町で実施した高齢者健診には,余命および健康余命を延伸する効果があり,この効果は継続的に健診を受診した場合に特に期待できるものであることが示された。
キーワード 高齢者健診,総合的機能評価,介護予防,余命,健康余命