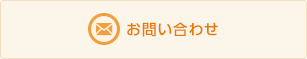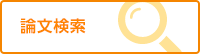論文記事
|
第63巻第4号 2016年4月 介護保険サービスの利用と家族介護者の抑うつ症状の推移-パネル調査データによる検討-菊澤 佐江子(キクザワ サエコ) |
目的 パネル調査データを用いて,高齢者を介護する家族介護者の抑うつ症状と介護保険サービスの利用状況の推移を把握するとともに,両者の関連について検討を行った。
方法 公益財団法人家計経済研究所が2011年10月と2012年7月に実施した「在宅介護のお金とくらしについての調査」データを用いた。分析対象は,2011年10月調査時点から2012年7月時点にかけて同居する要介護の親(または義理の親)を介護している主介護家族で,分析に用いた変数に欠損値がみられなかった207人(女性145人,男性62人)である。分析は,介護者の抑うつ症状(K6)の変化(良好/不良)を被説明変数とし,各介護保険サービスの利用状況の変化,被介護者の身体的障害,精神的障害(認知症)の程度,介護者の性別を説明変数とするロジスティック回帰分析を行った。
結果 介護者のうち,2時点間で,抑うつ症状が「良好」な推移をたどった者は35.8%,「不良」な推移をたどった者は64.3%であった。介護保険サービス利用については,2時点間でサービス利用に変化がないケース(「継続して利用がない」または「同程度の利用を継続」)が多いものの,サービス利用を増加・減少させているケースも各々8~17%程度みられた。ロジスティック回帰分析によって,介護者の抑うつ症状の変化(良好/不良)との関連を検討した結果,介護保険サービス利用については,2時点間で「同程度の通所介護利用を継続」「同程度の短期入所利用を継続」の回帰係数が,5%水準で正の方向に有意であった。このほか,性別ダミー(女性=1,男性=0)の回帰係数と,被介護者の精神的障害(認知症)の程度についての回帰係数が,それぞれ5%水準,1%水準で負の方向に有意であった。
結論 短期入所や通所介護を継続して同程度利用している場合には,利用していない場合に比べて,介護者の抑うつ症状が「良好」な推移をたどる確率が高いことが示されたが,こうしたサービスの利用による介護者の抑うつ症状軽減効果は弱いものにとどまっていることから,これらのサービスの供給体制をより充実させることが課題の1つと考えられた。また,被介護高齢者の精神的障害(認知症)の程度が重い場合,介護者の抑うつ症状が「良好」な推移をたどる確率が低いという傾向がみられたことから,認知症のある高齢者が利用できる介護保険サービスを広げることも重要な課題であると考えられた。
キーワード 介護保険サービス,家族介護,ストレス,抑うつ,パネル調査データ
|
第63巻第4号 2016年4月 臨死期におけるケアの場の移行を回避する看取りケア体制の関連要因島田 千穂(シマダ チホ) 石崎 達郎(イシザキ タツロウ) 高橋 龍太郎(タカハシ リュウタロウ) |
目的 特別養護老人ホームの看取りケアは定着しつつあるが,施設間格差は大きい。本研究では,死亡時の診断体制に着目し,看取りケア実施状況との関連分析から,医療との連携に基づく看取りケア体制構築の課題を検討した。
方法 関東地域の全特別養護老人ホーム1,777カ所を対象とし,郵送調査を行った。調査内容は,定員数,要介護度別入居者数,人工栄養実施人数,看取りケア方針の有無,平成25年1年間の退所者数とその内訳,死亡時の診断体制であった。看取りケア実施状況は,退所者数内訳から退所者数に占める看取りケア実施後の死亡者の割合から定義した。死亡時の診断体制は,①死亡時往診,②対応可能時往診,③病院搬送に分類した。
結果 有効回答数539(30.3%)を分析の対象とした。施設内死亡者数の退所者数に占める割合の平均値は39.2%,看取りケア実施者数の割合の平均値は29.9%であった。死亡時の診断体制は,死亡した時間帯に関わらず医師が診断する施設は27.6%,医師が対応できる時間帯に診断する施設が36.7%であった。看取りケア実施状況を「施設内死亡無」「施設内死亡有・看取り無」「看取り割合低」「看取り割合高」に分け,「施設内死亡有・看取り無」を基準カテゴリーの目的変数として多項ロジスティック回帰分析を行った。その結果,いずれのカテゴリーでも「死亡時の診断体制」が有意に関連していた。死亡診断を病院で行う体制の施設では,看取りケア実施施設が有意に少なく,死亡時往診と,対応可能時往診との間には,看取りケア実施状況において有意差はなかった。
結論 今後特別養護老人ホームで,臨死期の入院をできるだけ回避し,最期まで入居者へのケアを提供するためには,死亡時の診断体制整備に着目することが重要と考える。
キーワード 看取りケア,特別養護老人ホーム,死亡診断,医療との連携,ケアの質
|
第58巻第2号 2011年2月 要介護度の経年変化-同一集団における要介護度分布の9年間の変化-長田 斎(オサダ ヒトシ) 原田 洋一(ハラダ ヨウイチ) 畦元 智惠子(アゼモト チエコ)和久井 義久(ワクイ ヨシヒサ) |
目的 一自治体における一時点の要介護者集団について,要介護度の分布や生死等の中長期的な経年変化を明らかにすることを目的とした。
方法 東京都杉並区において,平成13年4月1日の時点で要介護認定を受けていた要支援・要介護者の全員を対象者として,6カ月ごとの要介護度,転出,死亡の情報を平成22年4月1日までの9年間分抽出し,要介護度等の分布の変化を観察した。また,Cutler-Ederer法により対象者全体および要介護度別に生存率を推計した。
結果 対象者全体では,観察期間の前半の4.5年経過後までにほぼ半数が死亡したが,9年後でも約25%は生存しており,死亡確率は観察期間の前半・後半ともおおむね同程度であった。要介護度別にみると,いずれの群でも当初の要介護度を維持している者は観察開始直後に急激に減少し,1年から2年の間に半減していた。またいずれの群も当初の要介護度から軽度に移行した者が認められたが,要介護2以上の群では観察開始6カ月後をピークにその後徐々に減少していた。平成18年4月の制度改正を契機に要支援が増加し要介護1が減少したが,同時に要介護2も増加していた。要支援・要介護1では,要介護2以上に比して,重度に移行した者の割合は少なかった。生存率曲線は,要介護度が重度な場合ほど下降する指数曲線状の形態となり,5年後に最大の差が認められた。
結論 本研究により,要介護者のnatural historyの基礎となるべき状態像の変化を示すことができた。また同一集団の要介護度の維持・改善率や生存率など,介護保険事業を比較的簡易かつ効果的に評価していくための示唆を得ることができた。
キーワード 要介護者,要介護度,経年変化,生存率
※論文中で言及されている参考表のデータはこちらからダウンロードして下さい。
|
第58巻第2号 2011年2月 組合管掌健康保険の保険料率と加入者の受診行動について佐川 和彦(サガワ カズヒコ) |
目的 組合管掌健康保険(以下,組合健保)の加入者は保険料率に対応して,合理性,損失回避の心理や権利意識,コスト意識にもとづいた受診行動をとると想定した3つの仮説(それぞれ,仮説A,仮説B,仮説C)を立てた。本稿では,これらの仮説の検証を行う。
方法 東京都の606の健康保険組合を対象にして,2004~2006年度(一部の変数については2003年度から使用)のパネルデータを使用することにより,受診率関数の推定を行った。年齢構成のデータが公表されていないため,特定の年齢層に限定した受診率(本稿では,3歳未満の被扶養者の受診率)を被説明変数として用いることにした。保護者の医療機関受診に対する考え方が乳幼児の受診率に反映するから,得られた検証結果の持つ意味は決して小さくはならないであろう。本稿の分析の特徴は,受診率関数の説明変数として保険料率の変化分を加えたことである。また,もとの保険料率が高い場合とそうでない場合に,保険料率の変更に対して反応が異なる可能性があることを考慮に入れて,係数ダミーを用いることにした。
結果 パネルデータの分析にあたって,モデル選択,系列相関,不均一分散に関する検定を行った。本稿では,これらの検定結果を受けて,必要と考えられる対策を講じながら,変量効果モデルと固定効果モデルの両方の推定を行った。入院外については,保険料率の変化分に対応するパラメータは統計的に有意ではなかったが,これに係数ダミーをかけたものに対応するパラメータの符号はマイナスであり,5%の有意水準で有意であった。
結論 入院外について,前年度の保険料率が高い水準に達していなければ,組合健保の加入者は保険料率の変更に対して合理的に対応する。しかし,前年度の保険料率が高くなると,もともと有していたコスト意識のほうが強くなり,仮説Cで想定されるような受診行動をとるようになる。すなわち,保険料率が高いとき,コスト節約のために入院外の受診をなるべく控えようとするのである。
キーワード 組合管掌健康保険,保険料率,合理性,損失回避の心理,コスト意識,パネルデータ
|
第58巻第2号 2011年2月 在宅療養支援診療所による看取り数に
岸田 研作(キシダ ケンサク) 谷垣 靜子(タニガキ シズコ) |
目的 在宅療養支援診療所(以下,在支診)による在宅での看取り数に影響する地域特性を明らかにすることを目的とした。
方法 データはすべて厚生労働省による都道府県単位の二次データである。65歳以上の死亡者数に占める在支診による在宅での看取り数が占める割合(以下,在宅看取り割合)を被説明事象とするロジット分析を行った。独立変数は,高齢者当たり在支診数,人口密度,高齢者当たり療養型医療機関の病床数,高齢者当たり訪問看護ステーション数,同居割合,1人当たり住宅床面積である。
結果 死亡者1万人当たりで評価した在宅看取り割合の平均は260人であった。在宅見取り割合が一番高い東京都(594人)と一番低い高知県(39人)を比較すると15倍もの差があった。高齢者当たり在支診が多いこと,人口密度が高いことは,在宅看取り割合が高いことと関連していた。高齢者当たり療養病床数が多いことは,在宅看取り割合が低いことと関連していた。
結論 人口密度が高いことは,在宅看取り割合が高いことと関連していた。このことは,在支診と患者宅の距離が近いほど往診が効率的に行えるため,在宅死が行いやすいことを示していると考えられる。高齢者当たり療養病床数が多いことは,在宅看取り割合が低いことと関連していた。このことは,療養病床が少ない地域では在支診がその受け皿の役割を果たし,在宅での看取りが多くなる可能性を示唆していると考えられる。ただし,受け皿となる在支診の整備や家族介護の支援体制がないまま病床数を削減すると,いわゆる介護難民が発生するだけでなく,適切な終末期医療を受けることができない可能性があることには充分注意を払う必要がある。
キーワード 在宅療養支援診療所,在宅での看取り,療養型医療機関
|
第58巻第2号 2011年2月 子ども医療センター開設から約1年半における
渡邉 英明(ワタナベ ヒデアキ) 堀口 逸子(ホリグチ イツコ) 吉川 一郎(キッカワ イチロウ) |
目的 医療法が定める三次保健医療圏を担う役割をもつ子ども医療センター(以下,センター)開設当初からの小児整形外科外来新患患者の状況を分析し,医療供給体制の問題点や小児整形外科患者の特徴を把握することである。
方法 2006年10月より2008年3月までに,センター小児整形外科を受診した外来新患患者474人を対象とした。診療録にある住所,初診年月日,来院経路,外来患者の年齢,性別,疾患について分析した。
結果 年齢は平均5.8±0.3歳で0から23歳までであり,年齢別でみると0歳(24.3%)が最も多かった。1日当たりの平均初診患者数は26.3人であり,月別にみると,開院より2007年2月までは月15人以下であったが,3月より徐々に増え始め,2007年6月以降は,しばしば月約40人の初診患者数となった。居住地を地域別にみると,センターのあるT県は373人で全体の78.7%であった。T県の二次保健医療圏内でみると,センターがあるA医療圏が最も多く196人(52.5%),次いで隣接する県庁所在地のあるE医療圏103人(27.6%)であった。来院経路は,院外より紹介38.4%,院内より紹介28.3%,紹介なしが33.3%であった。1年を4期に分けて紹介率をみると,62.5%(2007年7~9月)から78.2%(2006年10~12月)の範囲であった。診療科別でみると,整形外科が125人(39.6%)と最も多く,続いて小児科が123人(38.9%)で,これら2科で全体の約80%であった。ICD-10大項目分類による分類をみると,最も多い疾患はQ6(先天奇形,変形及び染色体異常;筋骨格系の先天奇形及び変形:股関節,足,多指<趾>)で118人(24.9%)であった。
考察 今回の分析によって,センター小児整形外科は,疾患の特徴から三次保健医療機関として特に小児科への啓発と,小児整形外科医療をより効果・効率的に提供するにあたり,季節性を考慮した医師の配置および疾患の特徴からみた専門性が必要であることが明らかになった。
キーワード 子ども医療センター,小児整形外科,外来患者,新患患者動向
|
第58巻第2号 2011年2月 乳がん検診に対する態度の測定関 愛子(セキ アイコ) 平井 啓(ヒライ ケイ) 長塚 美和(ナガツカ ミワ)原田 和弘(ハラダ カズヒロ) 荒井 弘和(アライ ヒロカズ) 狭間 礼子(ハザマ アヤコ) 石川 善樹(イシカワ ヨシキ) 濱島 ちさと(ハマシマ チサト) 斎藤 博(サイトウ ヒロシ) 渋谷 大助(シブヤ ダイスケ) |
目的 日本人の乳がん検診に対する態度を測定する尺度を作成し,対象者の心理的特性と受診行動の関連を明らかにすることを目的とした。
方法 40代~50代女性331名を対象にインターネットによる質問紙調査を行い,有効回答の得られた310名(平均年齢48.68±5.82歳,40代155名,50代155名)を対象に分析を行った。
結果 乳がん検診に対する態度を測定する尺度として4因子を抽出し,十分な妥当性および信頼性が確認された。Trans-theoretical Modelに基づく行動変容ステージと本尺度の因子得点の関連を調べた結果,検診を定期的に受診している人ほど「受診前の障害」「重要性の低さ」「受診時の障害」の得点が低く,「主観的規範」の得点が高いことが明らかになった。また,乳がんに対する不安や心配が強い人は受診ステージが高く,乳がん検診の重要性を高く評価していることが示された。
結論 本研究により,40~50代女性の乳がん検診受診行動の実態が一部把握された。本研究で作成した尺度は,受診率向上を目的とした今後の介入研究に向けて,対象者の心理特性を測定するために有用であると考えられる。
キーワード 乳がん検診,Trans-theoretical Model,受診率,マンモグラフィ,行動変容,不安
|
第58巻第2号 2011年2月 体力水準の異なる高齢者に対する,
|
目的 市町村レベルで行う短期間の介護予防教室では,会場確保の困難さや自治体の負担の大きさを考えると週1回以下の介入頻度による教室運営が現実的であると考えられる。短期間かつ週1回の介入頻度による運動介入では効果が得られないとする報告は多いが,介入効果の判定に影響すると予想される介入前の体力水準について十分な検討はなされていない。本研究では,体力水準の異なる高齢者間で,短期間,週1回の運動介入の効果検証を行い,短期間かつ週1回の介入頻度で効果の得られる体力水準について検討した。
方法 要支援・要介護認定を受けていない女性の在宅高齢者62名(71.8±5.1歳)を対象に,主成分分析によって算出された身体機能総合得点を用いて3分位を行い,体力水準別に3群を作成した。すべての対象にSquare-Stepping Exerciseを中心とした週1回,11週間の運動介入を行い,体力水準別に介入効果の違いを比較した。
結果 5回椅子立ち上がり時間,ペグ移動,全身選択反応時間,身体機能総合得点で運動介入による主効果が認められた。年齢調整後も交互作用が認められた身体機能評価項目は,Timed up and go,身体機能総合得点の2項目であり,身体機能総合得点において下位群のみに有意な向上効果が認められた。
結論 短期間かつ週1回の運動介入でも,低体力な高齢者に関しては運動効果が期待できる。中~高体力水準にある高齢者において,短期間の運動介入で向上効果を得るには,従来の報告のように介入頻度を週あたり複数回に増加させたり,運動強度を上げる必要がある。
キーワード 高齢者,体力水準,運動介入,低頻度,Square-Stepping Exercise
|
第58巻第2号 2011年2月 小規模多機能型居宅介護事業所の有効性に関する研究-全国における事業所の現状調査-野田 毅(ノダ タカシ) 糟谷 昌志(カスヤ マサシ) |
目的 地域の拠点として,在宅介護を支援することが期待されている小規模多機能型居宅介護事業所について,在宅認知症高齢者の在宅介護支援機能ならびに在宅介護支援を行う地域の拠点施設機能の現状を明らかにする。
方法 WAM-NETに登録されている介護保険の指定小規模多機能型居宅介護事業所全数の中から,ランダムサンプリングで500カ所を選び,2008年7~8月に調査票を郵送にて配布した。そのうち186カ所から回答を得て,回収率は37.2%であった。分析方法は,SPSSを用いての単純集計分析にて行った。
結果 小規模多機能型居宅介護事業所における認知症高齢者の受け入れは,約5割の事業所が積極的に受け入れると回答しており,在宅で認知症高齢者を支えるためのサービスとして機能しているといえる。さらに認知症高齢者の行動的心理的徴候(behavioral and psychological symptoms of dementia:以下,BPSD)の種類別の受け入れについて,一部暴力や攻撃性など,他の利用者に対して直接的な影響を与える場合には受け入れについて検討するという結果であったが,BPSDの種類別の受け入れ方に大きな違いは認められなかった。また,かかりつけ医の把握や友人関係など,利用者本人がこれまで築いてきた地域の社会資源を把握しており,他の福祉事業所よりも医療機関との連携が取れていた。
結論 小規模多機能型居宅介護事業所は,在宅認知症高齢者を支える役割を果たしており,近隣地域の住民や関係機関・団体との連携も取れていた。特に医療機関との連携が強く取れており,このことは,利用者の状態が急変した際の対応として,日頃からの関係が必要であるという認識の現れであるといえる。
キーワード 小規模多機能型居宅介護事業所,認知症,地域
|
第58巻第3号 2011年3月 日本の医療費対GDP比率についての認識とその対策-大阪府医師会調査から-島田 永和(シマダ ナガカズ) 安田 光隆(ヤスダ ミツタカ) 鈴木 隆一郎(スズキ タカイチロウ)中村 正廣(ナカムラ マサヒロ) 武田 温裕(タケダ アツヒロ) 澤村 昭彦(サワムラ アキヒコ) 酒井 英雄(サカイ ヒデオ) 酒井 國男(サカイ クニオ) |
目的 日本の医療は,GDPに占める医療費の割合が諸外国と比較して低く,安い費用で高い成果を得ていると総括されている。この効率の良さには医療従事者の献身的な勤務が大きく関与していると推測されるが,1980年代から政府が進めた社会保障費抑制により,その体制も限界に達し,地域医療の現場にて綻びが散見され,放置できない状況となっている。改革に当たっては,国民が現状を認識することが前提となり,より一層の広報や啓発活動が求められる。その資料となるようアンケート調査から現状の認知度についてまとめた。
方法 大阪府医師会は,平成7年より府民調査,昭和46年より医師会員調査を隔年実施している。府民調査は,エリアサンプリング(調査会社の調査員が訪問し記入を依頼(1,320名))および地区医師会配布(地区医師会の医師会員が配付し記入を依頼(1,311名))の2通りで実施した。医師会員調査は,大阪府医師会の会員約2万人を診療所長,病院長,勤務医に区分し,3,017人に調査票を配付した。有効回収率は65.2%であった。
結果 わが国のGDPに占める総医療費の割合が低いことを認識している府民は少なく,窓口での支払いは「高い」と感じている。国の医療費抑制政策についても反対意見が多いが,「わからない」との回答率も高い。一方,医師会員調査では,日本のGDPに占める総医療費の割合が低いことの認識が顕著に高く,低医療費政策が医療現場に与えている影響の大きさを伺わせる結果となった。
結論 国民の医療に対する期待は高く,これらのニーズに対応した質の高い医療を提供し続けるには医療費の増大は避けられない。また,医師が過重労働による「医療ミス」の可能性に不安を感じている事実は,医療を受ける側にも直結する問題であり,早急な改善が不可欠である。まずは,総医療費が低いという理解を浸透させるため,広報・啓発活動の充実・工夫が望まれる。
キーワード アンケート調査,医療の質,国民医療費,国際比較,地域医療体制
|
第58巻第3号 2011年3月 救急搬送を伴った高齢者の転倒の実態調査-人口規模別の検討-吉本 好延(ヨシモト ヨシノブ) 三木 章江(ミキ フミエ) 浜岡 克伺(ハマオカ カツミ)大山 幸綱(オオヤマ ユキツナ) 佐藤 厚(サトウ アツシ) |
目的 本研究の目的は,全国各地の消防本部の救急搬送記録を用いて,救急搬送を伴った高齢者の転倒状況を人口規模別に検討することであった。
方法 調査期間は平成19年の1年間であった。対象は,全国の消防本部50機関(6.2%)において救急隊員により搬送が行われた高齢者(65歳以上)の中等症以上の転倒(死亡または入院加療を必要とするもの)延べ13,372件(男性4,078件,女性9,294件)とした。調査項目は,受傷者の性別,年齢,転倒の発生場所,発生季節の計4項目とした。対象機関は,人口20万人以上の市町村を含む12機関(大都市),人口20万人未満の市町村で構成されている38機関(小都市)に分類した。人口規模別の転倒搬送件数は,住民基本台帳人口要覧を用いて,人口10万人当たりの搬送件数を各消防本部で男女それぞれ算出し,大都市と小都市の間で比較した。人口規模別の転倒の発生場所および発生季節は,転倒搬送の割合をそれぞれ算出し,大都市と小都市の間で比較した。
結果 人口10万人当たりの女性の転倒搬送件数は,小都市より大都市で有意に多かった。住宅での転倒の割合は,大都市と小都市で有意差はなかったが,大都市・小都市ともに男性より女性に高い傾向を示した。屋外での転倒の割合は,大都市と小都市で有意差はなかったが,大都市・小都市ともに女性より男性に多かった。転倒の発生季節は,大都市と小都市で有意差はなかったが,秋季・冬季の割合が全体的に高い傾向にあり,特に小都市における女性の冬季の割合は29.0%と最も高かった。
結論 女性高齢者の転倒搬送件数は小都市より大都市で多いことが明らかになったが,転倒の発生場所と発生季節は大都市と小都市で差はなく,人口規模別に特徴的な発生状況を明らかにすることはできなかった。今後は,分析的研究を用いた仮説の検証が必要である。
キーワード 救急搬送,高齢者,転倒,人口規模
|
第58巻第3号 2011年3月 回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者の
|
目的 本研究の目的は,回復期リハビリ病棟に入院した脳卒中患者の入院から2週目までのADL得点の変化と,入院から10週間後の歩行状態の回復との関連を明らかにすることである。
方法 2施設の入院患者のうち入院時に歩行できなかった脳卒中患者136人を対象とし,入院から2週間後のFIM(Functional Independence Measure)得点の変化と,入院から10週間後の歩行状態の判定を行った。入院時FIM得点,年齢,下肢BRS得点,発症から回復期リハビリ病棟入院までの期間の4因子を制御した多重ロジスティック回帰分析を行った。
結果 入院から2週間の更衣上半身FIM得点変化(OR:2.810,95%CI:1.242-7.448),入院時FIM得点(OR:1.085,95%CI:1.051-1.129),下肢BRS得点(OR:2.791,95%CI:1.661-5.140)が10週間後の歩行状態の回復に有意な因子であった。
結論 上半身の更衣に関するADL回復への看護介入が,入院10週間後の歩行状態の回復に有用である可能性が示唆された。
キーワード リハビリテーション看護,脳血管障害,歩行状態,FIM(Functional Independence Measure),BRS(Brunnstrom Recovery Stage),回復期リハビリテーション病棟
|
第58巻第3号 2011年3月 都道府県別の肥満者割合と社会経済格差について長谷川 卓志(ハセガワ タカシ) |
目的 肥満者の割合はわが国のみならず世界各国でも上昇を続けており,健康問題としてその実態解明と対策には多くの研究と実践が進んでいる。肥満は,生物学的にはカロリーの過剰摂取,運動量の低下などがその要因に挙げられており,多くの研究ではそれらの対策に焦点が当てられてきた。しかしながら,疾病を取り巻く各種の社会経済状態,特に格差について,海外では研究テーマとして盛んに取り上げられているものの,わが国における研究,報告は少ない。本研究では47都道府県の資料をもとに,地域の肥満者割合が,社会経済状態を示す各指標によりいかに説明されるものか検討したものである。
方法 都道府県の肥満者の割合を従属変数,ジニ係数,高等学校卒業者の大学等進学率,1人当たり県民所得,老年人口割合,65歳平均余命,完全失業率,1日の歩数,保有自家用車数を独立変数として分析,重回帰分析(変数増減法)を行った。
結果 重回帰分析の結果,男性では完全失業率(β,0.561,p<0.001),保有自家用車数(β,0.350,p<0.001),女性では大学等進学率(β,-0.507,p<0.001),ジニ係数(β,0.310,p<0.01),保有自家用車数(β,0.243,p<0.05)などが有意な関連を認めた。
結論 都道府県の肥満者割合とその地域差を規定する因子として経済格差,学歴格差が重要な役割を演じている可能性を示唆する結果であった。肥満を格差とその社会環境からとらえることが,予防対策を推進させるにあたりますます重要となるであろう。
キーワード 体格指数,肥満者割合,経済格差,学歴格差,ジニ係数
|
第58巻第3号 2011年3月 都道府県別合計特殊出生率の実態について石井 憲雄(イシイ ノリオ) |
目的 厚生労働省「人口動態統計」で公表されている都道府県別合計特殊出生率(Total Fertility Rate,以下,TFR)の算出方法の問題点を洗い出し,近年における都道府県別TFRの動向の実態を把握することである。
方法 山形県を例にとり,「人口動態統計」の都道府県別TFRの算出方法が国勢調査年と非国勢調査年で異なることが,TFRにどのような影響を及ぼしているか分析した。次に,「2005年人口動態統計」の「概数」と「確定数」の乖離を基に,非国勢調査年の各都道府県のTFRがもつ誤差の測定を行った。さらに,2000年から2009年までの非国勢調査年について,分母に用いる年齢階級別女子人口の定義を国勢調査年と統一するなどして改善した補正TFRの推計を試みた。
結果 「人口動態統計」の非国勢調査年の都道府県別TFRは,分母に用いる女子人口に外国人人口が含まれる影響や,推計人口の推計誤差の影響により,全都道府県で国勢調査年に比べ相当低い水準となっていることが判明した。そこで,補正TFRを推計した結果,大部分の都道府県において,2005年のTFRが2000年から2009年における最低値となっており,2006年以降回復基調にあることが示された。
結論 時系列でみると,「人口動態統計」の都道府県別TFRの動向は,その分母に用いる女子人口の問題から,その分子である出生数の動向との関係に一部整合性がみられない。したがって,都道府県別TFRの動向を正確に把握する必要がある地方自治体や,研究者においては,非国勢調査年の値については,本研究で示した手法を利用するなどして,独自に推計することが推奨される。
キーワード 合計特殊出生率,TFR,人口動態統計,推計人口,都道府県,国勢調査
|
第58巻第3号 2011年3月 共働き世帯の父親の育児参加と
桐野 匡史(キリノ マサフミ) 朴 志先(パク ジソン) 近藤 理恵(コンドウ リエ) |
目的 本研究は,就学前の児を養育している若い共働き世帯を対象に,父親の育児参加が母親の心理的well-beingに及ぼす影響について明らかにすることを目的とした。
方法 K県C市とO県K市内の保育所を管轄している市の担当課等を通して協力が得られた保育所15カ所を利用している1,000世帯(C市:6保育所500世帯,K市:9保育所500世帯)の両親を対象に「ワーク・ライフ・バランスに関する調査」を実施した。本研究では,前記調査のうち,統計解析に必要なデータとして,父親の回答からは年齢,収入(月収),就業形態,父親の育児参加を抜粋し,また母親の回答からは年齢,子どもの数,末子の年齢,就業形態,父親の情緒的育児サポートに関する母親の認知,夫婦関係満足感,精神的健康,健康関連QOLを抜粋した。統計解析には,回答が得られた共働き世帯である334世帯のうち,分析に必要なすべての変数に欠損値を有さない278世帯のデータを用いた。なお,本研究では,「父親の育児参加は,父親の情緒的育児サポートに関する母親の認知を通して母親の心理的well-being,すなわち夫婦関係満足感と精神的健康(抑うつ傾向)に影響し,夫婦関係満足感は,直接的に,または精神的健康を通して間接的に,健康関連QOLに影響する」とした因果関係モデルを仮定し,そのモデルのデータに対する適合度と変数間の関連性を構造方程式モデリングにより検討した。
結果 因果関係モデルのデータに対する適合度は,CFIが0.983,RMSEAが0.052と統計学的な許容水準を満たす結果であった。また,分析の結果,父親の育児参加は,父親の情緒的育児サポートに関する母親の認知を通じて間接的に夫婦関係満足感に影響し,夫婦関係満足感は,直接的に,または精神的健康を通して間接的に,健康関連QOLに影響していた。
結論 本研究の結果,早急に父親の育児参加に関連した仮説を取り込んだ新たな理論の検証を総合的に行っていく必要性が示唆された。また,未就学児を育児している共働き家庭にあっては,質の高いワーク・ライフ・バランスが維持できる家族形成支援を,根本的には,いかにして父親の育児参加を促すかといった問題に立ち戻って解決されるべきであることが推察された。
キーワード 父親,母親,育児サポート,夫婦関係満足感,ワーク・ライフ・バランス
|
第58巻第4号 2011年4月 今後の国民生活基礎調査の
橋本 英樹(ハシモト ヒデキ) |
目的 国民生活基礎調査の現行のサンプリングデザイン・実施体制について,回収率向上や匿名化データセット作成の観点から問題点を整理した。
方法 国民生活基礎調査室の担当数理官へのインタビューを行い,サンプリングならびに比推定の手法について質疑応答を通じて取材した。また実施の状況について,某都道府県担当部局を通じて,調査実施担当者数名からのグループインタビューを実施させていただいた。匿名化データセットの作成に関する問題点については,平成21年度厚生統計協会研究委託「国民生活基礎調査の匿名データ化に関する研究会」に筆者が参加した際の議論も一部踏まえつつ,問題点を整理した。
結果 大調査年では都道府県別表章の誤差範囲を均一化すること,実施体制・コストの制限から地点抽出・地点内悉皆調査により比推定に基づく母数推計が行われている。全国値の算出にあたって分散の違いが考慮されておらず,確率抽出を採用している小調査年統計値との整合性を再検討する余地がある。また比推定は回収率低下によるバイアスの影響を受けやすいことから,実施体制の見直し,特に実施系統の一本化・調査員の教育・情報普及など検討すべきである。匿名化データ作成にあたっては現行のサンプリングデザインに制限を考慮すれば,世帯員レベルでのリサンプリングが匿名性を保ちつつ地域情報を含めるうえでは自由度が高いと思われた。
結論 国民生活基礎調査は,世帯面の基幹統計として,変化する調査環境・ユーザーとそのニーズの多様化に対応するには,統計の継続性を確保しつつも,常にその内容や実施方法について大胆な変革を見通した議論を継続していく必要がある。対象者である国民に対して「国民の共有財産としての統計」としての正当性を明確に説明できることが求められる。
キーワード 国民生活基礎調査,サンプリングデザイン,調査実施手法,回収率向上,匿名化データセット
|
第58巻第4号 2011年4月 勤労者における抑うつ状態と体力との関連の縦断的研究久保田 晃生(クボタ アキオ) 竹内 亮(タケウチ リョウ) 原田 和弘(ハラダ カズヒロ)笹井 浩行(ササイ ヒロユキ) 甲斐 裕子(カイ ユウコ) 高見 京太(タカミ キョウタ) |
目的 勤労者を対象に抑うつ状態と体力との関連を縦断的調査結果から検討し,職域のメンタルヘルスケアの向上を効果的に推進する基礎的資料を得ることである。
方法 静岡県内のN社K製造所に勤務し,ベースライン調査および1年後の追跡調査に協力の得られた男性277人を分析対象者とした。ベースライン調査では,握力,長座体前屈,上体起こし,反復横とび,立ち幅とびの測定と,質問紙で推定最大酸素摂取量,抑うつ状態(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(CES-D)日本語版),身体活動量のほか,年齢,配偶者,学歴,睡眠時間,夜勤,喫煙習慣,飲酒習慣,現病歴の状況を把握した。また,同時期の健診結果からBMIを把握した。追跡調査では抑うつ状態を把握した。「うつ病の治療中」「解析項目に1つ以上の欠損値」「体力項目のいずれかが平均値+標準偏差×3以上の値」「CES-Dで逆転項目の回答が不十分」である69人を除いた208人を最終解析対象者とした。解析は,CES-D得点の変化から4群に分け体力および交絡因子を比較した。次に抑うつ状態への変化と体力との関連を検討した。さらに,ベースライン調査が非抑うつ状態で追跡調査が抑うつ状態であった群と,両調査時点が非抑うつ状態であった群の2群を目的変数,ベースライン調査の各体力項目を説明変数,ベースライン調査の年齢,配偶者,学歴,睡眠時間,夜勤,喫煙習慣,飲酒習慣,現病歴,BMIを調整変数としたロジスティック回帰分析(強制投入法)を施した。各体力測定値は関連の強さを比較検討するため,それぞれ標準偏差で除し解析に用いた。
結果 解析対象者(208人)のCES-D得点の平均値は,ベースライン調査で14.5±7.7点,追跡調査で13.4±7.8点であった。ベースライン調査が非抑うつ状態で追跡調査が抑うつ状態であった群は17人(8%),両調査時点が非抑うつ状態であった群は112人(54%)であった。抑うつ状態への変化と体力との関連を検討するために行ったロジスティック回帰分析の結果,目的変数と有意な関連が認められた項目は,立ち幅とび(オッズ比0.48)のみであった。
結論 抑うつ状態と関連が認められた項目は立ち幅とびであった。立ち幅とびのような複合的な体力を向上させるためには,体力全般の向上を図ることが重要かもしれない。しかし,本研究は課題も多く,今後も研究を蓄積することが必要である。
キーワード 抑うつ状態,CES-D,体力,身体活動量
|
第58巻第4号 2011年4月 保健予防対策の重点支援地域の発見-ベイズ推計による補正を施した受診指数と死亡率データの活用-古城 隆雄(コジョウ タカオ) 黒島 テレサ(クロシマ テレサ) 印南 一路(インナミ イチロ) |
目的 本研究の目的は,第一に脳血管疾患患者と脳血管疾患の危険因子である高血圧患者を対象に,複数の指標を用いて国や都道府県が重点的に支援するべき市町村(重点支援地域)を対策度別に明らかにすることである。第二に,階層ベイズ法を用いて市町村レベルの受診指数を推定し,SAEの問題に対する階層ベイズ法の有用性を確認することである。
方法 脳血管疾患SMR,脳血管疾患受診指数,高血圧受診指数の3指標を用いて,医療費が低い3県(山形県,長野県,静岡県)と医療費が高い3府県(大阪府,広島県,高知県)の市町村を,脳血管疾患の重度化と発症予防の観点から要対策度別に5段階に分類した。脳血管疾患受診指数,高血圧受診指数を作成する際には,SAEの問題を回避するため,階層ベイズ法(ポアソン対数正規モデル)による指数の推定を行い,指数の推定精度を高めた。
結果 まず,高血圧と脳血管疾患の受診指数を,階層ベイズ法による補正前と補正後で比較してみると,補正後の値が基準値1に集約される形で安定化した。特に,受診件数が少ない脳血管疾患,そして小規模自治体の受診指数が強く補正されていた。次に,保健予防上の要対策度別に6府県の市町村を分類し,6府県の特徴を明らかにした。山形県と高知県は,脳血管疾患SMRと脳血管疾患受診指数が共に高い要対策度5の市町村が59%を占める。長野県は,脳血管疾患SMRが高く,脳血管疾患受診指数が低い要対策度4の市町村が75%に達する。広島県は,脳血管疾患SMRの値は低いが,脳血管疾患の受診指数は高い要対策度3に67%の市町村が該当する。大阪府は,83%の市町村が,脳血管疾患SMR,脳血管疾患の受診指数が低い要対策度2と1に分類された。静岡県は,要対策度2~5に分類される市町村がそれぞれ一定程度存在する混在型であった。
結論 疾患がまれな疾病で受診率が低い場合や小規模自治体で指数を算出する際には,ベイズ統計による指数の補正を行うことが必要であろう。医療費の水準が低いことや平均在院日数が低いことから長野県を目指すべきモデルとして扱う傾向があるが,長野県は脳血管疾患SMRの値が高く,要対策度4の市町村が75%を占めており,決してモデル地域とはいえない。保健予防対策を考える際には,医療費の高低だけでなく,死亡率や医療機関への受診状況など複数の指標を考慮し,支援するべき市町村の包括的な優先順位を付すべきである。
キーワード 重点支援地域,SMR,受診指数,階層ベイズ,ベイズ統計
|
第58巻第4号 2011年4月 老衰死はどのように変化してきているのか-人口動態統計を利用した記述疫学的検討-今永 光彦(イマナガ テルヒコ) 丸井 英二(マルイ エイジ) |
目的 「老衰死」に関して,人口動態統計を利用して戦後から現在までの記述疫学的な検討を行い,過去から現在にかけてどのように「老衰死」が変化してきているのかを考察するとともに,今後の老衰死亡者数の推計を試みた。
方法 基礎資料として,昭和25年(1950年)から平成20年(2008年)までの人口動態統計と2005年人口動態特殊報告・都道府県別年齢調整死亡率,平成18年12月推計日本の将来推計人口を用いた。老衰死亡率(人口10万対死亡率,性別年齢調整死亡率)の推移,年齢別にみた老衰死亡者数の推移,性別にみた老衰死亡者数の推移,老衰死亡者の死亡場所の変化についてそれぞれ検討を行った。1975年と2005年における老衰の性・都道府県別年齢調整死亡率を用いて,各都道府県の性別年齢調整死亡率の全国値に対する比を算出し,地域差があるかどうかの検討と各都道府県の変化を比較した。老衰の年齢階級別死亡率が2008年と同率で推移すると仮定して,2015年と2025年の老衰死亡者数の推計を試みた。
結果 戦後から減少傾向にあった老衰死亡率は,近年,人口10万対死亡率は増加しているが,年齢調整死亡率は横ばいである。性別ではどの年代でも女性の死亡者数が多い。老衰死の年齢構造や亡くなる場所の変化をみると,過去は現在よりも若年で老衰死と診断され,自宅で亡くなっている方が多い。近年は病院や施設など亡くなる場所が多様化している。各都道府県別の比較では,1975年・2005年ともに地域差を認めており,男女とも,中部地方で増加,近畿地方で減少している。県別では沖縄県が著明に減少している。老衰死亡者数の推計では,2008年と比較して,2015年で約1.5倍,2025年で約2.6倍になると推計された。
結論 今後,老衰死亡者数が増加することが予測され,死亡場所に関しても,自宅に限らず病院・施設と多様化していることを考えると,臨床医が「老衰死」に遭遇する機会は増えることが考えられる。
キーワード 老衰,老衰死,高齢者医療,超高齢者,人口動態統計,記述疫学
|
第58巻第5号 2011年5月 社会福祉施設におけるボランティア受け入れの現状と課題守本 友美(モリモト トモミ) |
目的 本研究は,開かれた施設づくりの一側面としてのボランティアの受け入れに関する実態を把握し,ボランティアの主体性を支援し,ボランティア活動を通して施設と地域社会をつなぐ役割を担うボランティアコーディネーター(ボランティア受け入れ担当者)の必要性を明らかにすることを目的とした。
方法 三重県社会福祉施設名簿に掲載されている社会福祉施設のうち,保育所,助産施設,在宅介護支援センター,訪問看護ステーションを除いた施設937施設に対して自計式調査票を用いた郵送調査を実施した。調査時期は2009年9月1日から10月15日である。回収数は390件で,回収割合は41.6%であった。本研究では,「施設の概要」「ボランティア受け入れの状況」「ボランティアコーディネーターの配置状況」「ボランティアコーディネーションの内容」に焦点を絞って調査項目を作成した。
結果 290施設(74.4%)がボランティアを受け入れているが,そのボランティアを支援し,施設と地域社会とを結び相互の関係を築いていくための役割を担う専門職であるボランティアコーディネーターの配置がされているのは,26.7%にすぎなかった。そして,ボランティアコーディネーターが配置されていないことから,ボランティアを受け入れ,支援していくために必要な内容の実施割合が低いことも明らかになった。「ボランティア受け入れのためのマニュアルを作成している」「ボランティアのための部屋を用意している」などの物的環境整備については,そのなかでも比較的実施割合が高い内容であったが,ボランティアへの直接的支援については,実施割合の高いものと低いものとの差が見られた。特に,ボランティアコーディネーターの重要な役割となる「ボランティアへのスーパービジョン(相談)を行っている」の実施割合が10%にも満たないことは,ボランティアへの支援が十分には行われていないことを示している。
結論 施設は施設利用者にサービスを提供することのみにとどまらず,地域からのボランティアを受け入れ,住民の自発的な福祉活動を支援することなどを通して地域福祉推進の機能も期待されている。この機能を果たしていくためには,施設におけるボランティアコーディネートの手法の導入と組織体制の整備が急務であり,ボランティアの受け入れに対する考え方を明確に打ち出し,コーディネーターの役割を担う担当者を養成し配置する必要がある。
キーワード 社会福祉施設,ボランティアコーディネーター,ボランティア受け入れ,ボランティア活動
|
第58巻第5号 2011年5月 大都市圏住民のメンタルヘルス,生活ストレスと自殺関連体験-大阪市「市政モニター質問書」調査結果を中心に-高梨 薫(タカナシ カオル) 吉原 千賀(ヨシハラ チカ) 清水 新二(シミズ シンジ) |
目的 自殺対策基本法成立によって自殺対策は総合的な対策,取り組みへ軸足を移しつつある。しかし自殺対策はその中核にこころの問題がとらえられており,うつ病の早期発見という具体的,対症療法的施策もこれまでどおり重要である。そこで自殺者実数が最も多い大阪市調査データを使用し,自殺関連体験とメンタルヘルス状況,およびメンタルヘルス関連要因を検討した。
方法 大阪市市政モニター600人を対象に平成20年9月,市政モニター調査を自記式郵送法で実施し,558の調査票を回収,回収割合は93.0%であった。自殺関連体験は過去1年間の自殺念慮および自殺企図を尋ね,メンタルヘルスはCES-D(Center for Epidemiologic Studies Depression)スケールを使用した。メンタルヘルス関連要因としては暮らし向き,地域の人との交流とソーシャルサポートを尋ねた。この他,悩み・ストレスの相談について尋ねた。これらを集計検討したうえで,CES-Dを従属変数とした重回帰分析を欠損値のあるものを除いた432人(男子238人,女子194人)を対象に行った。
結果 過去1年間に自殺念慮をもった回答者は男子8.8%,女子12.8%,全体10.8%と,市民10人に1人が何らかの程度で自殺念慮を体験し,同様に過去1年間に実際に自殺を試みた体験を持つ者は男女とも1.8%,およそ市民50人に1人の割合であった。またCES-Dは平均13.9,標準偏差9.0で,男子13.5±9.4,女子14.4±8.5となっていた。年代別では20歳代が最も高かった(15.7±10.0)。CES-Dを従属変数とした重回帰分析では性別で関連要因が異なり,男子では暮らし向き,地域の人との交流,職場関係サポートが,女子では暮らし向き,地域の人との交流,家族サポートが有意となった。おのおの暮らし向き「ゆとりがある」,地域の人との交流「よくある」方,職場関係,家族サポートの多い方でCES-D点数は低くなっていた。
結論 自殺念慮,企図体験者の割合は厚生労働省調査と比較し著しく高かった。また市民のメンタルヘルスには暮らし向きが大きな影を落としているものの,地域の人との交流,家族(女子において)や職場(男子において)のサポート効果が示唆された。地域,職場のサポートや,悩み・ストレスの相談のしやすさなどについての改善工夫,これまでのうつ病対策とともに総合的なメンタルヘルス対策と生活支援の取り組みが望まれる。
キーワード 自殺対策基本法,自殺念慮,自殺企図,メンタルヘルス,社会関係資本
|
第58巻第5号 2011年5月 高齢者の要介護認定有無別医療費の比較分析安西 将也(アンザイ マサヤ) 延原 弘章(ノブハラ ヒロアキ) |
目的 近年,医療・介護保険者にとって,医療・介護の制度における給付の状況を把握し,介護予防や疾病予防のための方策の在り方を中心とした健康づくり事業の支援に向けた取り組みが重要となっている。そこで,本研究では,滋賀県国民健康保険団体連合会の電算データから,国保高齢者の医療給付状況(介護給付状況を含む)を把握し,要介護認定の有無別に比較分析した。
方法 滋賀県下26市町の国民健康保険および長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者のうち,平成20年8月31日現在65歳以上で,平成20年6~8月に医科レセプトが1件以上ある者213,346人を対象とし,平成20年6~8月の医療給付費および介護給付の状況について分析を行った。
結果 滋賀県の65歳以上すべての被保険者241,170人のうち,医療を受けた割合をみると,全体で88.5%であった。また,滋賀県すべての要介護認定者44,728人のうち,医療を受けたものは,全体で83.6%であった。介護給付の有無別にみたところ,介護給付ありが81.1%,介護給付なしが18.9%であった。要介護認定を受けていながら介護サービスを受けていない者が2割近くいることがわかった。要介護認定あり(介護給付なし)の1人当たり金額は要介護認定のない者よりも調剤,外来・調剤,入院において有意に高かったこと,また,要介護認定あり(介護給付あり)は要介護認定のない者よりも調剤および外来・調剤において有意に高いことが明らかとなった。傷病別にみたところ,要介護認定あり・なしにかかわらず,生活習慣病の件数が多いことがわかった。
結論 種々の結果から,要介護認定者は介護依存が高いだけでなく,要介護認定のない高齢者よりも医療依存が強いことから,医療機関と連携したケアプランの作成などの工夫が必要であること,また,医療費適正化の観点から,一般高齢者だけでなく,要介護高齢者に対しても生活習慣病予防・介護予防や健康維持・向上の支援の必要性を示唆していた。
キーワード 医療保険制度,医療費,介護保険,要介護認定,入院外来,傷病
|
第58巻第5号 2011年5月 日本の禁煙強化政策に対する喫煙者の反応依田 高典(イダ タカノリ) 高橋 裕子(タカハシ ユウコ) 後藤 励(ゴトウ レイ) |
目的 近年の禁煙強化政策にどのように反応しているか,喫煙者の禁煙意思の詳細な分析を行うために,価格や健康リスクといった情報に対する喫煙者の反応について定量的に分析し,それらの反応がニコチン依存度によって異なるかどうかを検討する。
方法 対象は,モニター調査会社に登録している現在喫煙者と現在非喫煙者である。さらに,FTNDテスト(Fagerstrom Test for Nicotine Dependence)により高度喫煙者,中度喫煙者,低度喫煙者に分類された600名の喫煙者に対して,コンジョイント分析を実施した。
結果 第1に,最近の禁煙強化政策に関して,予想通り,喫煙者は反対し,非喫煙者は賛成している。第2に,たばこ事業法の変更に関して,喫煙者は慎重であり,非喫煙者は前向きである。第3に,2006年調査と同じ設定でたばこ価格値上げに対する喫煙継続確率に対するコンジョイント分析を実施したところ,高度喫煙者の禁煙意思は大幅に増加している一方で,低度喫煙者の禁煙意思は低下している。
結論 禁煙成功割合が現行の仮定である50%程度にとどまり,たばこ価格が欧米価格以下にとどまる限り,たばこ税の安定的税収確保というたばこ事業法の目的は達せられるが,禁煙成功割合が大幅に改善したり,たばこ価格が欧米価格以上に引き上げられたりする場合,たばこ税収は減少に転じることもあり得る。
キーワード 禁煙行動,コンジョイント分析,健康リスク,たばこ価格,FTND
|
第58巻第5号 2011年5月 「食生活改善行動の採用」尺度と行動変容モデルの予測深澤 友恵(フカザワ トモエ) 清原 昭子(キヨハラ アキコ) 北風 真衣(キタカゼ マイ)福井 充(フクイ ミツル) 上田 由喜子(ウエダ ユキコ) |
目的 本研究では,個人の食物選択が社会に影響を及ぼすことの理解は,食に対する意識や行動に影響を与えると考え,「食生活改善行動の採用」を評価する尺度の開発と行動変容へと導くモデルを提案することを目的とする。
方法 対象は40歳から62歳の被雇用労働者の男性200名とし,調査は平成21年9月に行った。データ収集方法は,インターネットを利用した間接的な自記式質問紙調査とした。質問紙の信頼性については,反応分布の検討,次にG-P分析を行い,各項目得点の高群と低群で平均値の差が顕著でない(p≦0.05)項目は除外した。さらに,I-T相関分析を行い,項目と全体得点の相関が低い(<0.25)項目は除外した。最後に因子分析(主成分分析)を繰り返し,因子を抽出した。質問紙の妥当性および「食生活改善行動の採用」モデルの予測については,特定保健指導に参加した成人男女82名を対象に,同年12月に調査を行った。仮定した因子構造モデルのデータへの適合度は,パス解析を用いて検討した。
結果 44項目の反応分布から27項目5因子が残り,これを「食生活改善行動の採用」測定尺度とした。Cronbachのα係数は全体としての尺度が0.908,下位尺度では0.628から0.830を示し,内的整合性が確認された。外的基準である新しい食物選択動機調査票の下位尺度やecSatter調査票の一部の項目との関連により,一定の収束的妥当性も認められた。また,「個人の食物選択が社会に影響を及ぼす」と理解することから,食に関する意識や行動への影響については,「食事バランスへの意識」が0.676(p<0.001),「食生活変化の受容態度」は0.664(p<0.001),「食物選択動機の合理性」には0.913(p<0.001)の因果関係がみられ,モデルの適合度もそれぞれ受容可能な値が示された。
結論 栄養教育において食物選択と社会へのつながりを理解させることは,彼らの食意識に影響を与え,改善行動の採用に導くための有効なアプローチとして成り立つと考えられる。
キーワード 尺度,妥当性,行動変容,食環境
|
第58巻第6号 2011年6月 地域における健康危機管理コンピテンシーの
|
目的 地域における健康危機管理を担うすべての公衆衛生従事者に求められる健康危機管理コンピテンシーの習得レベルを,実務者のコンセンサスを得つつ,職種別・職位別に明らかにする。
方法 デルファイ法による。調査対象は,すべての保健所・地域保健担当部局・地方衛生研究所の管理者および層別抽出職種の職員(744カ所,合計1,899人)。第2回調査集計結果に対してデルファイメンバー16名によるラウンドテーブルディスカッションを行い,最終意見集約を行った。
結果 質問紙調査回答は第1回1,016件(53.5%),第2回756件(対象992件中76.2%)。回答の中央値・最頻値は多くの項目で一致した。両者不一致の習得レベルは,歯科医師・歯科衛生士6項目,薬剤師2項目,管理的立場の事務職2項目,非管理的立場の事務職2項目などにみられた。中央値・最頻値が不一致の項目および事前調査で賛意50%未満の項目を中心とする検討により,すべての職種・職位に対して求められる健康危機管理コンピテンシーの習得すべきレベルが意見集約された。
結論 習得すべき健康危機管理コンピテンシーのレベルは,職種・職位により特徴を有する分布パターンであった。医師の回答には職位「管理的立場の専門職」がバイアス因子となっている可能性が考えられた。本研究の調査結果は,すべての地域における健康危機管理を担う公衆衛生従事者に対して,求められる「健康危機管理コンピテンシーの『習得しておくべきレベル』についてコンセンサスを得つつ意見集約した結果となっている。今後,地域における健康危機管理体制の整備に必要な「人材育成」を,地域の実情に応じて企画・立案・実施・評価していく際に,本研究成果を活用すべきであると思われた。
キーワード 公衆衛生行政職員,健康危機管理コンピテンシー,習得レベル,デルファイ調査,ラウンドテーブルディスカッション,職種
|
第58巻第6号 2011年6月 診療報酬明細書における性感染症の記載状況に関する検討谷原 真一(タニハラ シンイチ) 岡本 悦司(オカモト エツジ) 今任 拓也(イマトウ タクヤ)百瀬 義人(モモセ ヨシト) 宮崎 元伸(ミヤザキ モトノブ) 畝 博(ウネ ヒロシ) |
目的 感染症サーベイランスシステムから得られる情報が実態をどの程度反映しているかを定期的に評価することは現実に即した感染症対策を実施する上での基本である。本研究は医療機関からの届け出割合の影響を受けない情報源の一つである診療報酬明細書(以下,レセプト)による情報を用いて性感染症サーベイランスの評価を行う上での課題を明らかにすることを目的とした。
方法 複数の健康保険組合における被保険者本人および被扶養者で2006年5月に入院外診療を受けた126,433人(男65,434人(51.8%),女60,999人(48.2%))の入院外レセプト169,622件に記載された傷病名の総数442,010件の中から,社会保険表章用疾病分類表(厚生労働省保険局)の中分類の「性的伝播様式をとる感染症」に該当する傷病名を抽出した。その後,各傷病名を国際疾病分類第10版の2003年改訂版(以後,ICD-10)により再分類し,各傷病名ごとの主傷病と副傷病の割合および疑い病名が占める割合を比較した。
結果 レセプトに記載された傷病名442,010件のうち,性的伝播様式をとる感染症に該当するものは820件(0.2%)であった。そのうち,主傷病は153件(18.7%),副傷病は667件(81.3%)であった。疑い病名は331件(40.4%)であった。主傷病のうち26件(17.0%),副傷病のうち305件(45.7%)が疑い病名であり,統計学的に有意(p<0.001)に副傷病に占める疑い病名の割合は主傷病よりも高くなっていた。傷病名別の検討ではクラミジア(ICD-10:A56),淋菌(同:A54),梅毒(同:A51,A52,A53)では統計学的に有意(p<0.05)に副傷病の疑い病名の割合は主傷病より高くなっていた。しかし,性器ヘルペス(ICD-10:A60)およびその他の性的伝播をとる感染症(同:A58,A63,A64)では副傷病と主傷病の間の疑い病名の割合に統計学的有意差は認められなかった。
結論 レセプトに記載された情報は保険診療である限り,医師の届け出に左右されないという特徴を持つために,性感染症サーベイランスシステムから得られる結果の評価や改善に有益である。傷病名をICD-10によって詳細に分類することと主傷病および副傷病の区分並びに疑い病名に関する検討を行うことは,現在のレセプト分析では十分実施されておらず,レセプトに記載された情報を性感染症サーベイランスの評価や改善に用いる上での課題である。
キーワード 診療報酬明細書(レセプト),サーベイランス,性感染症,主傷病,副傷病,疑い病名
|
第58巻第6号 2011年6月 情報サービス産業で働く日本人システムエンジニアの
丹羽 俊子(ニワ トシコ) 呉 珠響(オウ チュヒャン) 斉藤 恵美子(サイトウ エミコ) |
目的 本研究は,情報サービス産業で働く開発技術者の蓄積疲労の実態を把握し,労働環境との関連を明らかにすることを目的とする。
方法 東京都内の情報サービス産業で働く開発技術者160人を対象として質問紙調査を行った。調査項目は,基本的属性,職場・労働環境,蓄積疲労度とした。分析は,疲労蓄積度高群と低群の比較として各変数間でχ2検定を行った。
結果 分析対象とした120人中,蓄積疲労度が高い人の割合は55.9%であった。また,1カ月の平均残業時間が45時間超の割合は22.5%であり,負担と感じる割合が高かった項目は,仕事内容のあいまいさ,仕事の難しさ,納期の時間的切迫などであった。疲労蓄積度高群と低群を比較して,高群が有意に高かった項目は,通勤時間60分以上,勤務場所が出向先,平均残業時間45時間超,長時間労働,仕事量の多さ,仕事の難しさ,納期の時間的切迫,納品後のトラブル,コミュニケーションの少なさ,室内(気温・湿度)の不快,仕事中の休憩頻度の不足,眼の痛み・疲れ,首・肩のこり・痛みであった。
結論 本調査の結果,仕事による負担度が高いと回答した人は約6割であった。蓄積疲労度と労働環境の負担感の関連では,蓄積疲労度が高い群の方が,労働環境で負担と感じる10項目について有意に割合が高かった。産業看護職は開発技術者の労働環境の特性に応じて,主観的な負担度などを考慮した助言・指導が必要であることが示唆された。
キーワード 開発技術者,情報サービス,労働環境,ストレス,蓄積疲労
|
第58巻第6号 2011年6月 ケアマネジメント業務自己評価尺度の開発-介護支援専門員が業務遂行のために必要とする技能修得度の測定-西村 昌記(ニシムラ マサノリ) 小原 眞知子(オハラ マチコ) 大和 三重(オオワ ミエ)小西 加保留(コニシ カホル) 村社 卓(ムラコソ タカシ) |
目的 介護支援専門員が業務遂行のために必要とする技能の修得度を簡便に自己評価するための尺度として「ケアマネジメント業務自己評価尺度」を開発し,その構成概念妥当性(因子的妥当性),基準関連妥当性(判別的妥当性),および信頼性の検証を行った。
方法 兵庫県社会福祉協議会主催の専門研修に参加した介護支援専門員600名と主任介護支援専門員研修に参加した主任介護支援専門員492名を対象に集合調査を行い,それぞれ538名,389名から回答を得た(回収率は各89.7%,79.1%)。分析対象は実務経験2年未満の者と分析に関連する質問項目に欠損値のあった者を除く769名とした。探索的因子分析より析出した共通因子を第1次因子,総合的評価にあたる第2次因子を仮定した2段階の因子構造よりなる分析モデルを設定し,構造方程式モデリングにより解析を行った。尺度の信頼性の検討には,信頼性係数αを算出した。判別的妥当性の検証には,経験年数を外的基準として,尺度得点の比較を行った。
結果 探索的因子分析の結果,「制度理解」「ニーズ尊重」「利用者主体」「情報活用」「環境開拓」の5因子が析出された。15項目の観測変数と5つの第1次因子,1つの第2次因子よりなる高次因子分析モデルを構築し,構造方程式モデリングを行った結果,モデルの適合度は受容基準を満たしていることが明らかになった。また,15項目を単純加算した総合的評価および5つの下位尺度の信頼性係数αは,いずれも受容基準を満たしていた。経験年数を外的基準とした判別的妥当性の検証においては,総合的評価といずれの下位尺度とも,経験年数の長い層の方が平均得点が有意に高いことが明らかになった。
結論 本研究で開発された「ケアマネジメント業務自己評価尺度」は,構成概念妥当性,基準関連妥当性,および信頼性を有する尺度であることが示された。
キーワード 介護支援専門員,ケアマネジメント,自己評価,技能修得度,尺度開発
|
第58巻第6号 2011年6月 補完代替医療の利用における心理社会的要因の影響三澤 仁平(ミサワ ジンペイ) |
目的 補完代替医療(以下,CAM)の利用について調査し,心理社会的要因を考慮に入れて,CAMの利用における関連要因のメカニズムを明らかにすることを目的に検討した。
方法 無作為抽出された仙台市に居住する20歳から69歳までの男女1,500名を対象に郵送調査を行った「健康と暮らしに関する意識調査」データを用いた(調査期間:2009年5月~7月)。過去1カ月間のCAM利用の有無を応答変数として,個人属性や健康関連QOL(SF-8),心理社会的要因(健康不安,将来における経済不安)を投入して,一般化線形モデルを用いて解析した。
結果 CAMを利用したことのある対象者は,全体の60.9%であった。個人属性のみを投入したモデルでは,性別(女性)(オッズ比=1.50[95%信頼区間:1.06-2.13]),年齢(40歳代)(OR=1.76[95%CI:1.02-3.05])が,CAM利用と有意に関連した。つぎに,健康関連QOL(SF-8)を追加したモデルでは,世帯収入(中位)(OR=1.54[95%CI:1.03-2.31])に有意なCAM利用との関連が認められた。SF-8の日常役割機能(RP)(OR=2.07[95%CI:1.31-3.31]),体の痛み(BP)(OR=1.46[95%CI:1.06-2.02])が有意な正の関連,身体機能(PF)(OR=0.62[95%CI:0.39-0.97])が有意な負の関連を示した。心理社会的要因を投入したモデルでは,健康不安(OR=1.66[95%CI:1.19-2.32])が有意にCAMの利用と関連していたが,将来における経済不安(OR=0.85[95%CI:0.55-1.29])は関連が認められなかった。また,年齢(40歳代)の関連が消失した。
結論 CAM利用の予測因子として性別は大きな要素であると考えられる。身体に関する軽度な健康問題を抱えていることはCAMの利用に関連するものの,あまりに健康状態がよくない場合にはCAMの利用へはつながらないと思われる。年齢(40歳代)は,健康不安を介して,CAM利用の有無に関連していると考えられる。このことは,年齢が中年期であることがCAMの利用につながるという直接的な関係があるのではなく,中年期の人は健康に関する不安を覚えやすく,そのことによってCAMを利用するという間接的な心理社会的なメカニズムが働いているのではないかと思われる。健康社会を目指すほど,健康不安が増長される可能性が指摘されているため,現代社会の健康づくりのあり方を検討することや,CAMに関するエビデンスを構築し,適切に報じることが求められる。
キーワード 補完代替医療,CAM,心理社会的要因,健康不安,将来における経済不安,SF-8
|
第58巻第7号 2011年7月 高齢者支援に向けたコミュニティ・エンパワメント
|
目的 本研究は,住民と保健福祉専門職に対するフォーカス・グループインタビューを実施し,高齢者支援に向けたコミュニティ・エンパワメント展開のための当事者のニーズを抽出することを目的とした。
方法 大都市近郊農村自治体住民と保健福祉専門職4グループに対するフォーカス・グループインタビューを実施した。対象の内訳は男性22名,女性20名,合計42名で,年齢は30~70歳代であった。各グループのインタビューから得られた結果をシステム理論に基づきカテゴリー化し,コミュニティ・エンパワメントに関するニーズを抽出した。
結果 『個・相互・地域システム』のシステム構造に基づいて高齢者支援に向けたコミュニティ・エンパワメント展開のための当事者のニーズを抽出した結果,次のニーズが明らかになった。まず『個』の領域においては,「生きがい,楽しみ」「健康な生活への主体的な取り組み」「保健福祉サービスの活用」が,次に『相互』の領域においては,「交流の必要性」「相互支援体制の整備」が,また『地域システム』の領域においては,「地域の魅力化」「安心・安全な地域システムづくり」「地域で支え合う人材育成」「健康に関する支援の充実」のニーズである。
結論 健康は,単にヘルスサービス供給にとどまらず,保健活動に関する意思決定における住民参加の原則に基づいて増進される。今回得られた住民の「なまの声」をもとに,当事者のニーズを活かした保健福祉活動の今後の発展が求められる。
キーワード コミュニティ・エンパワメント,フォーカス・グループインタビュー,質的研究
|
第58巻第7号 2011年7月 初期の体重減少は保健指導効果の予測因子となる渡邉 美穂(ワタナベ ミホ) 市川 太祐(イチカワ ダイスケ) 大橋 健(オオハシ ケン)倉橋 一成(クラハシ イッセイ) 古井 祐司(フルイ ユウジ) |
緒言 特定保健指導実施者は,対象者の体重変化等をモニタリングし,必要があれば支援計画を見直す必要がある。本研究では,初回面接時に得られた情報と,保健指導開始後1カ月の体重から,保健指導を開始して3カ月の体重変化を予測できるかを検証し,効果的な保健指導の検討に資することを目的とした。
方法 解析対象は,2008年度に特定保健指導の積極的支援を受けた,9健康保険組合の男性の被保険者とした。解析方法は,初回面接から90日前後1週間の体重変化比を目的変数とし,「年齢」「減量等の経験」「ストレスの有無」「生活習慣改善が重要だと思うか」「行動変容ステージ」「初回面接時BMI」と初回面接から30日前後1週間の体重変化比を説明変数として,重回帰分析を行った。
結果 解析対象者は199名であり,平均年齢は50.1±6.3歳,平均初回面接時BMIは26.0±2.4であった。30日体重変化比の平均は0.98±0.02,90日体重変化比の平均は0.97±0.03だった。「年齢」「減量等の経験」「ストレスの有無」「生活習慣改善が重要だと思うか」「行動変容ステージ」「初回面接時BMI」は,除外され,「30日体重変化比」のみが説明変数として選ばれた。
結論 年齢や,取り組み前の体格,態度に関わらず,取り組みを始めて初期の段階で効果が出た方が,その後の効果も期待できると考えられる。
キーワード 特定保健指導,減量,初期の体重減少,支援
|
第58巻第7号 2011年7月 介護支援専門員の基礎資格は主治医との連携に影響を及ぼす鳴釜 千津子(ナルカマ チヅコ) 陳 君(チン クン) 吉井 初美(ヨシイ ハツミ)庄司 和義(ショウジ カズヨシ) 佐藤 キヨ子(サトウ キヨコ) 森田 定一(モリタ サダイチ) 菅村 佳美(スガムラ ヨシミ) 赤澤 宏平(アカザワ コウヘイ) 田城 孝雄(タシロ タカオ) |
目的 本研究では,介護支援専門員の基礎資格を看護系と介護系に分けて,主治医とのコミュニケーションのとり方に違いがあるかどうかを,アンケート調査に基づき統計学的に分析した。
方法 アンケートの調査時期は2006年11月であり,対象地域は1県4市の合計5カ所である。対象者は居宅介護支援事業所の介護支援専門員であり,その基礎資格を看護系と介護系の2種に大別した。群間における主治医との連携の違いを調べるために,アンケート調査票の中で「主治医との連携」に関連のある4項目を選び比較検討を行った。
結果 ケアマネジメント業務での相談相手としては,看護系,介護系ともに「サービス事業者」と「職場の上司・同僚」が高率であった。「主治医」との相談は看護系で有意に高かった。サービス担当者会議に関しては,その開催にあたり「参加を呼びかけた人」は,両群ともに「サービス事業者」「家族」「利用者」が高率であった。また,看護系において有意に高かった項目は,「主治医」であった。さらに,開催にあたり困難を感じる理由としては,両群ともに「サービス事業者との日程調整」の割合が高かった。「主治医が出席できない」を理由として挙げた人の割合は介護系で有意に高かった。介護系の介護支援専門員が考える,医師がサービス担当者会議に参加しない理由としては,「介護支援専門員自身が主治医に出席を呼びかけていない」「介護支援専門員と主治医との信頼関係が確立されていない」「主治医と連絡がつかない」の3項目であった。
結論 看護系と介護系の2群間で主治医との連携には大きな違いがあることがわかった。両群ともに,医療との連携が十分とはいえないが,看護系は介護系に比べ主治医との連携が良好であった。このことは,各介護支援専門員の基礎資格,すなわち,それぞれの異なる教育課程や経験に起因するものと考えられる。看護系の介護支援専門員が減少し,介護系の介護支援専門員が増加している現状を踏まえ,基礎資格別の教育システムの導入が必要と考える。同時に医療関係者の介護保険制度に対する認識を深める施策も重要である。
キーワード 介護保険制度,介護支援専門員,主治医,基礎資格,サービス担当者会議,ケアマネジメント
|
第58巻第7号 2011年7月 クルマ依存脱却に向けた公共交通・自転車利用の阻害要因-地方中枢都市の住民を対象として-難波 秀行(ナンバ ヒデユキ) 山口 幸生(ヤマグチ ユキオ) 武田 典子(タケダ ノリコ) |
目的 日常生活の移動手段において,クルマから電車やバスなどの公共交通や自転車の利用にシフトすることは身体活動の増加につながる。近年,クルマ依存社会からの脱却は,モビリティ・マネジメント(以下,MM)の取り組みとして注目されている。しかしながら,MMによる身体活動促進の可能性については明らかになっていない。本研究では,クルマの代わりに公共交通・自転車を利用することの阻害要因を明らかにし,啓発冊子により運動習慣者のない者に対する身体活動促進の可能性を検討することを目的とした。
方法 調査地域選定の条件は,地方中核都市の都心部から約5㎞離れ,自動車所有率の高い一戸建住宅の集中地区とした。さらに,地下鉄沿線の特定駅から半径500m以内に限定して,住宅地図から対象世帯を事前に抽出し,留置法により質問紙調査を実施した。分析対象は,男性176名(平均58.3±標準偏差13.5歳),女性211名(54.5±13.8歳),計387名(56.2±13.8歳)であった。
結果 クルマの代わりに公共交通・自転車を利用することの阻害要因として,荷物が多いことが120名(31.0%)と最も多く,時間がかかることが107名(27.6%)と続いた。「荷物が多いこと」の阻害要因では女性(37.4%)が男性(23.3%)よりこの割合が有意(p<0.05)に高かった。「時間がかかること」の阻害要因では,通勤者(34.7%)が非通勤者(20.4%)よりこの割合が有意(p<0.05)に高かった。さらに,通勤手段をクルマに依存しているものは,クルマ以外の交通手段で通勤している者に比べ,徒歩を苦痛に感じている割合が有意(p<0.05)に高かった。運動習慣がない156名において公共交通を利用したいと「とても思う」「思う」と回答した者が合わせて75名(48%)であり,MMによる身体活動促進の可能性が示された。
結論 本研究により公共交通利用の阻害要因が明らかとなり,対象者の基本属性により阻害要因の割合が異なることが明らかとなった。さらに運動習慣がないものに対しても,公共交通利用の啓発冊子により身体活動を促進できる可能性が考えられた。
キーワード 公共交通,モビリティ・マネジメント,阻害要因,ウォーキング,自転車,身体活動量
|
第58巻第7号 2011年7月 特定高齢者における介護予防サービスへのアクセスの阻害要因杉澤 秀博(スギサワ ヒデヒロ) 杉原 陽子(スギハラ ヨウコ) |
目的 特定高齢者の候補者を対象に,介護予防サービスへのアクセスの阻害要因について,通所型と訪問型のサービスニーズの重複およびサービスの利用意向の乏しさの2側面から検討する。
方法 対象は,東京都下の市に在住の65歳以上の高齢者を対象とした郵送調査の回答者の中から,厚生労働省が作成した生活機能の基本チェックリストに基づき特定高齢者の候補者として選定された900人であった。分析は以下2つの視点から行った。第1の視点は,通所型と訪問型のサービスニーズの重複割合を分析することであった。通所型サービスニーズのある人とは,運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上であり,訪問型サービスニーズのある人とは,うつの予防・支援,閉じこもりの予防・支援,認知症の予防・支援のいずれかに該当するものとした。第2の視点は,介護予防サービスの利用意向の乏しさを分析することであり,介護予防サービスの中心となっている各通所型サービスについて,ニーズがある人を対象に利用意向のない人の割合と利用意向に影響する要因を分析した。要因の候補には健康度,介護予防の認知度,社会的ネットワーク,医療機関への通院を位置づけた。
結果 通所型サービスニーズは99%の人がもっていたが,通所型と訪問型のサービスニーズが重複している人は特定高齢者の候補者全体の71%にみられた。利用意向については,3種類の通所型サービスのいずれも,ニーズがあるにもかかわらず利用意向がない人が約80%いた。利用意向の要因をニーズの多かった運動器の機能向上と口腔機能の向上について分析したが,いずれのサービスとも地域組織への参加頻度が低い人で利用意向のない人の割合が有意に高かった。
結論 介護予防サービスに対する特定高齢者のアクセスを阻害する要因の一つとして,訪問型と通所型のサービスニーズの重複が考えられた。アクセスを向上させるには訪問型サービスの拡充を図ることが重要であることが示唆された。さらに,通所型サービスについては,利用意向が低いこともサービスへのアクセスを阻害する要因の一つであった。利用意向を高めるためには,地域組織への参加など特定高齢者の社会的ネットワークの拡充を図ることが重要であることが示唆された。
キーワード 特定高齢者,サービスへのアクセスの阻害要因,通所型サービス,訪問型サービス,サービスの利用意向
|
第58巻第7号 2011年7月 北海道の周産期医療における病院アクセスと周産期アウトカム西條 泰明(サイジョウ ヤスアキ) 中木 良彦(ナカギ ヨシヒコ) 伊藤 俊弘(イトウ トシヒロ)杉岡 良彦(スギオカ ヨシヒコ) 吉田 貴彦(ヨシダ タカヒコ) |
目的 北海道内の各市町村から産婦人科・小児科救急拠点病院へのアクセス時間について地理情報システム(Geographic Information System,以下,GIS)ソフトウエアを用いて推定し,それらの周産期アウトカムの影響を検討することを目的としている。
方法 市町村ごとの平成15~19年の乳児死亡数,新生児死亡数,周産期死亡数から,5年間平均の乳児死亡率,新生児死亡率(出生千対),周産期死亡率(出産千対)を計算した。産婦人科医と小児科医の常勤医がそれぞれ2名以上勤務する28施設を今回の産婦人科・小児科拠点病院とした。各市町村から28産婦人科・小児科拠点病院のうち直近の施設への乗用車でのアクセス時間を推定するためArcGIS9.3(ESRI,NYC)のNetwork analyst解析を用いた。各市町村からのアクセス時間を説明変数として乳児死亡率の第4四分位,新生児死亡率の第3三分位,周産期死亡率の第4四分位となるオッズ比についてロジスティック回帰分析を用いて算出した(新生児死亡率のみ分布が低値に偏っているため四分位に適さず,三分位とした)。
結果 対象医療機関への到達時間の中央値は48.4分,平均値57.3分(標準偏差39.0),最小値,0.3分,最大値は181.0分で,90分以上の市町村は40(22.7%)に認め,そのうち13市町村(7.4%)が120分以上となっていた。ロジスティック回帰分析では,乳児死亡率ではアクセス時間による有意な差を認めなかった。新生児死亡率については,アクセス時間が60分以上90分未満の群が30分未満の群に比べて有意に減少していた(オッズ比(OR)=0.22,95%信頼区間(CI):0.07-0.73,P=0.013)。また,90分以上の群では上昇する傾向を認めた(OR=4.33,95%CI:0.17-1.09,P=0.076)。また,周産期死亡率はアクセス時間が30分以上60分未満の群において有意の上昇を認めた(OR=2.61,95%CI:1.04-6.58,P=0.041)。
結論 新生児死亡率では60分以上90分未満で有意にオッズ比の低下を認めたが,90分以上でオッズ比の上昇傾向を認めた。しかし,周産期死亡率では,30分以上60分未満でオッズ比の上昇を認めた。都市部の未受診妊婦の増加などの影響も考えられ,アクセス時間は単純にはアウトカムに関係しなかったと考えられるが,90分以上のアクセス時間は問題である可能性もあり,今後も検討を重ね,道路やドクターヘリの整備,医療機関の効率的な配置などを考えていく必要がある。
キーワード 乳児死亡率,新生児死亡率,周産期死亡率,拠点病院,地理情報システム(Geographic Information System:GIS),到達時間
|
第58巻第8号 2011年8月 特定健診未受診者へのアンケート調査からみた
後藤 めぐみ(ゴトウ メグミ) 武田 政義(タケダ マサヨシ) 開沼 洋一(カイヌマ ヨウイチ) |
目的 平成20年4月から医療保険者に実施が義務づけられた特定健診の未受診者を対象に未受診の要因を調査し,健診受診率向上のための方策について検討することを目的とした。
方法 山形県尾花沢市において,平成17年度から市の健診を一度も受診していない国保被保険者1,492人に対し,アンケートにて性,年齢,居住地区,職業の有無,主観的な健康状態,通院の有無と疾患名,健康づくりへの取り組みの有無とその内容,前年度の健診受診状況,特定健診未受診の理由,特定健診への希望を調査した。調査票回収後,数年または今まで基本健診や特定健診を受診しておらず定期通院もしていないと回答した者に対して電話や訪問で受診勧奨を行った。
結果 アンケート回答者は1,214人で回答割合は81.4%であった。健診未受診の理由は「定期的に通院中」が回答者の半数を超え,年齢別にみた場合,49歳以下では「仕事や家事が忙しい」が最も多かったが,50歳以上では「通院中」が多くなっていた。健診への希望は44~64歳では「健診を受けられる期間を長くする」「夜間や土日も受けられる」といった実施期間や時間設定への希望割合が高く,65歳以上では「市保健センター以外でも受けられる」や「送迎あり」といった会場の利便性や出向く手段への希望が多かった。受診勧奨では,電話より訪問の方が健診受診に結びつく割合が高かった。
結論 年齢により特定健診未受診の理由に違いがみられたことから,受診率向上には年齢別,未受診理由別の対応が有効と考えられた。また,未受診理由として「通院中」が多くあげられたことから,治療中の者が特定健診を受診することの有効性を検討する必要があると考えられた。
キーワード 特定健診,受診率,未受診者,受診勧奨,国民健康保険
|
第58巻第8号 2011年8月 騒音職場勤労者の喫煙習慣と聴力高田 康光(タカタ ヤスミツ) 内田 智子(ウチダ トモコ) 祝迫 麻衣(イワイサコ マイ)谷口 友理(タニグチ ユリ) |
目的 喫煙習慣は聴力障害の危険因子であるとともに騒音性の聴力障害を増悪させる因子として疑われている。騒音障害が管理されている騒音職場の勤労者の聴力に喫煙習慣がどのような影響を及ぼしているかを検討した。
方法 勤労者の騒音健康診断と定期健康診断結果を用いて年齢,性別,聴力閾値レベル,職場騒音暴露年数,余暇での騒音暴露の有無,BMI,喫煙習慣,飲酒習慣を調査した。
結果 平均年齢42歳の男性304名,38歳の女性51名の対象でそれぞれ,平均18年間と16年間の騒音職場勤務歴を認めた。男性では1000Hz,4000Hz,6000Hz,女性では6000Hzの聴力の悪化と年齢に有意な関連を認めたが喫煙習慣とは有意な関連を認めなかった。一方,男性勤労者で余暇にパチンコをする習慣がある群は,ない群に比べ4000Hzの聴力が有意に悪化し,また,喫煙習慣をもつ者が多かった。
結論 保護具による暴露予防と衛生教育が継続されていた騒音職場では,男女の勤労者の聴力は年齢とは関連していたが,喫煙習慣の有無では差を認めなかった。しかし,聴力障害の予防には職場外の生活環境での騒音暴露を減らすことがさらに必要であり,その暴露には喫煙習慣が関連している可能性を認めた。
キーワード 聴力障害,騒音,喫煙
|
第58巻第8号 2011年8月 定期健康診断有所見率の上昇と労働者の高齢化との関連牧野 茂徳(マキノ シゲノリ) |
目的 わが国の定期健康診断有所見率は上昇している。有所見率の上昇の一因として健康診断を受診する労働者の高齢化も関与している。そこで,定期健康診断有所見率の上昇と労働者の高齢化との関連について検討した。
方法 基準となる有所見率は都産健協が2007年に実施した性,年齢別有所見率調査結果を利用した。1990年から2008年までの性,年齢別就業者数は総務省統計局が実施した労働力調査の資料を用いた。基準となる有所見率と各年次の性,年齢別就業者数から性,年齢別の有所見者数を計算し,さらに合計の有所見者数を計算した。そして,合計の有所見者数と合計の就業者数を用いて,1990年から2008年の有所見率を計算した。
結果 1990年から2008年の就業者の平均年齢は男性が42.8歳から45.3歳に上昇した。女性は42.0歳から44.1歳に上昇した。55歳以上の就業者の割合は,男女とも増加している。1990年から2008年の間に所見のあった者の割合は2.4ポイント上昇した。聴力検査(4,000Hz)が2.0ポイント,血圧測定が1.8ポイント,血中脂質検査が1.2ポイント,胸部X線検査が1.1ポイント上昇した。
結論 胸部X線検査,心電図検査,血圧測定の有所見率の上昇は高齢化の影響を受けている。所見のあった者の割合の上昇は高齢化の影響は大きくない。
キーワード 有所見率,定期健康診断,労働者の高齢化
|
第58巻第8号 2011年8月 水痘ワクチンの定期接種化に関する医療経済分析須賀 万智(スカ マチ) 赤沢 学(アカザワ マナブ) 池田 俊也(イケダ シュンヤ)五十嵐 中(イガラシ アタル) 小林 美亜(コバヤシ ミア) 佐藤 敏彦(サトウ トシヒコ) 白岩 健(シロイワ タケル) 杉森 裕樹(スギモリ ヒロキ) 田倉 智之(タクラ トモユキ) 種市 摂子(タネイチ セツコ) 平尾 智広(ヒラオ トモヒロ) 和田 耕治 耕治(ワダ コウジ) |
目的 水痘ワクチンの定期接種化を医療経済学的に評価するため,水痘ワクチンの1歳時皆接種を導入したときに期待される費用対効果と,導入後10年間の医療経済への影響を,日本の既存の疫学データを用いて推計した。
方法 費用対効果の推計:出生コホート110.1万人において,水痘ワクチンの1歳時皆接種を導入する前(任意接種)と導入した後(定期接種)で,14歳までに生じる,水痘によるDALY(障害調整生存年),水痘関連医療費,予防接種費を推計した。費用と効果はいずれも割引率3%にて現在価値に割り引き,費用対効果の指標として罹患接種費用比と1DALY回避費用を求めた。導入後10年間の医療経済への影響の推計:水痘罹患リスクがある1~14歳人口1607.5万人において,水痘ワクチンの1歳時皆接種を導入した翌年から10年後まで,各年の水痘関連医療費と予防接種費の推移を推計した。医療経済への影響の指標として増分費用を求めた。
結果 費用対効果の推計:皆接種導入前,出生コホートの95.3%(104万9565人)が水痘に罹患し,水痘によるDALYは4,238,水痘関連医療費は123億235万円にのぼると推計された。皆接種導入後,予防接種費は51億7789万円に増加するが,その効果として,罹患数,入院数,死亡数は大幅に減少し,水痘によるDALYは1,438(66%減),水痘関連医療費は41億9313万円(66%減)になると推計された。罹患接種費用比は2.15であり,水痘関連医療費の減少額が予防接種費の増加額を上回った。1DALY回避費用は134.8万円であった。導入後10年間の医療経済への影響の推計:皆接種導入前,水痘によるDALYは4,407,水痘関連医療費は121億4915万円であったが,10年後に罹患数は71%減少し,その結果,水痘によるDALYは1,191,水痘関連医療費は34億6825万円に減少すると推計された。増分費用は,接種単価5,000円とした場合,4年後にマイナスに転じて,10年後にはマイナス17億3154万円(水痘関連医療費の減少額>予防接種費の増加額)に達したが,接種単価7,500円とした場合,10年後にもプラス8億3106万円(水痘関連医療費の減少額<予防接種費の増加額)にとどまった。
結論 水痘ワクチンの定期接種化は医療経済的観点から導入の根拠があると考えられた。
キーワード 水痘,予防接種,医療経済分析,費用対効果
|
第58巻第8号 2011年8月 スクエアステップが高齢者の運動継続に及ぼす効果北角 俊(キタズミ スグル) 重松 良祐(シゲマツ リョウスケ) |
目的 日本の高齢化率が20%を超える一方で,生活習慣病や寝たきりになる人も増加している。それらの予防には運動する必要があるが,プログラムの種類が少なく,各自にあったプログラムを選択できないために運動に結びつかないことが多いとされている。そこで本研究では,新しく考案されたスクエアステップというプログラムが高齢者の運動行動の変容を促す因子(運動媒介変数)に及ぼす影響と,その後の運動習慣について検討することとする。
方法 65~74歳の男女68名を,実験群としてのスクエアステップ群(SSE群32名,うち女性18名,平均年齢68.6±2.4歳)と,対照群としてのウォーキング群(W群36名,うち女性25名,平均年齢69.3±3.1歳)に無作為に割り付けた。両群とも1回70分のプログラムを3カ月間にわたって,SSE群は週に2回,W群は週に1回それぞれ集まって運動した。スクエアステップは,薄いマット(100㎝×250㎝)を線で40個の正方形に区切り,その上をステップしながら進んでいく運動である。W群には日常生活における歩数を増やすように指示した。3カ月間の介入前後に,4種類の運動媒介変数を質問紙にて調査した。また,介入が終了してから約17カ月後に電話にて運動実施状況を調査した。
結果 媒介変数である運動セルフエフィカシー,運動ソーシャルサポート,行動的スキル,意志決定バランスのいずれの項目も,3カ月間の介入によって有意に改善した。行動的スキルでは有意な交互作用が認められ,W群で顕著に改善していることが示された。介入期間中の歩数に有意差はみられなかった。介入終了17カ月後に電話で調査した結果,運動習慣を有している者はSSE群93.3%,W群83.3%であり,有意ではないもののSSE群の方が多く運動習慣を有していた。
結論 SSEを用いた3カ月間の介入によって,運動媒介変数を有意に改善させることができた。また,その改善度は行動スキル以外でW群と同程度であった。介入終了後における運動継続は両群で違いがなかった。以上のことから,SSEを用いた介入は高齢者の運動継続に有効であることが明らかとなった。
キーワード 行動変容,運動継続,運動プログラム
|
第58巻第8号 2011年8月 女性医師割合の高い診療科(眼科・皮膚科・麻酔科)に
児玉 知子(コダマ トモコ) 小池 創一(コイケ ソウイチ) 松本 伸哉(マツモト シンヤ) |
目的 本研究では,医師・歯科医師・薬剤師調査(以下,三師調査)コホートデータを用いて比較的女性医師割合の高い眼科,皮膚科,麻酔科における女性医師のキャリアパスを検討し,医籍登録後(以下,登録後)の就業における動態を把握する。
方法 1984年,1994年,2004年の三師調査において診療科の女性医師割合を年齢階級別に比較した。さらに,医籍登録番号で統合されたコホートデータを作成し,女性医師割合の高い眼科,皮膚科,麻酔科について,1984年医籍登録者と1994年医籍登録者における女性医師の就労継続,復職,休職,診療科の届け出変更について分析した。
結果 2004年調査における女性医師割合は,眼科36.8%,皮膚科38.0%,麻酔科29.1%と高率であった。1984,1994,2004年時の女性医師割合を年齢階級別に比較したところ,すべての年齢階級において眼科には有意差がなく,皮膚科,麻酔科では有意な女性医師割合の増加がみられた。特に29歳以下の若年齢層においては眼科51.5%,皮膚科68.4%,麻酔科46.8%と高率であった。1984年医籍登録者と1994年医籍登録者の登録後10年時における在職率の比較では,眼科において1994年登録者で有意に高かった。1984年登録者の20年後の在職率は,眼科で95%,皮膚科で107%(中途参入含む),麻酔科で55%であった。麻酔科では登録後4~6年時で診療科の変更が多く,眼科から他科への変更は1%未満と低率であった。隔年調査での平均復職率は,眼科12%,皮膚科18%,麻酔科10%であり,麻酔科で休職率が復職率を上回っていた。
結論 眼科,皮膚科,麻酔科においては女性医師の割合が高く,特に眼科,皮膚科では登録後20年時の在職率が非常に高いことが明らかとなった。離職のピークは眼科,皮膚科においては登録後8~10年であり,麻酔科においては明らかなピークは認めなかった。女性医師の継続就労,休職,復職パターンは診療科によって異なる可能性があることが示唆された。
キーワード 女性医師,キャリアパス,医師・歯科医師・薬剤師調査,眼科,皮膚科,麻酔科
|
第58巻第11号 2011年9月 訪問看護利用者数および訪問看護師必要数の推計中島 民恵子(ナカシマ タエコ) 八巻 心太郎(ヤマキ シンタロウ) 吉池 由美子(ヨシイケ ユミコ)井ノ口 珠喜(イノクチ タマキ) 福田 敬(フクダ タカシ) 新野 由子(ニイノ ヨシコ) |
目的 本研究では,2020年までの訪問看護サービス利用者数の推計を行うことで,今後必要とされる訪問看護師数を把握することを目的とする。
方法 本研究では,訪問看護利用者数および訪問看護師必要数の推計を行うための枠組み構築を行うとともに,必要なデータを収集し,推計を行った。訪問看護利用者数については,2つのシナリオを設定して推計を行った。また,訪問看護師必要数については,処遇改善等の要件を変化させた場合の訪問看護師必要数の推計を行った。
結果 現状の要介護認定率と訪問看護利用率をベースとし,訪問看護利用者数を推計したところ,訪問看護利用者数は2009年時点の340.4千人(うち介護保険277.8千人,医療保険62.6千人)から,2020年には少なくとも489.5千人(うち介護保険414.7千人,医療保険74.7千人)まで伸びることとなり,全体として149.1千人分の利用ニーズが増加することとなった。施設サービス利用率を下げたシナリオで訪問看護利用者数を推計したところ,443.9千人(介護保険のみ)の利用ニーズが見込まれた。一方,医療保険の訪問看護については,2020年までの現状ベースでの伸び(1.19倍)を1.5倍または2.0倍と仮定して推計を行ったところ,1.5倍の場合は93.9千人,2.0倍の場合は125.2千人の利用ニーズが生じた。これらの訪問看護利用者数に対する訪問看護師必要数については,2009年時点の36,687人から,現状の労働時間の場合は2020年に52,756人,労働時間を1,800時間に改善した場合は63,158人が必要となった。
結論 2020年の訪問看護利用者数は増加が見込まれ,それらに対応するための訪問看護師は,2009年の時点と比較すると,2020年の時点では,約16,000人(処遇改善した場合は約26,500人)の訪問看護師が不足することがわかった。今後,増加する訪問看護の利用ニーズを満たすために必要な訪問看護師の確保は,喫緊の課題である。
キーワード 訪問看護利用者数,訪問看護師の確保,推計,利用ニーズ
|
第58巻第11号 2011年9月 地域高齢者における3年間にわたる閉じこもりの変化と
森 裕子(モリ ヒロコ) 佐藤 ゆかり(サトウ ユカリ) 齋藤 圭介(サイトウ ケイスケ) |
目的 介護予防の観点から近年注目されている閉じこもりは,要介護状態や活動能力の低下をもたらすことが報告されている。しかし,閉じこもりは改善することもあり,その変化と身体機能や活動能力の推移との関連は明らかにされていない。本研究では,地域高齢者を対象とした追跡期間3年・3時点の調査をもとに閉じこもりの変化について類型化し,移動能力・日常生活活動・活動能力の推移との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 A県B町の65歳以上の高齢者全員2,274名を対象に2002年12月に初回調査を実施し,次いで入院入所者,調査拒否・不能者を除く1,901名に対し,2004年6月と2005年12月に追跡調査を実施した。集計対象は,地域生活が自立している高齢者を対象とするため,要介護1~5の者,歩行不可能な者,初回調査時点より閉じこもりの者,追跡不能者を除外した699名とした。3時点の変化から,閉じこもりの観点より「脱却群」「継続群」「発生群」「非閉じこもり維持群」の4群に類型化し,移動能力(Rivermead Mobility Index)・日常生活活動(Katz Index)・活動能力(老研式活動能力指標)の継時的な変動の有無を二元配置分散分析により確認した上で,各群における得点推移の特徴について検討を行った。
結果 集計対象699名の閉じこもり類型の内訳は,脱却群が11名(1.6%),継続群が7名(1.0%),閉じこもり発生群が39名(5.6%),非閉じこもり維持群が642名(91.8%)であった。これら4群における移動能力・日常生活活動・活動能力の得点推移について検討した結果,いずれも統計的に有意に変動することが示され(p<0.01),非閉じこもりから閉じこもりになると各得点は低下し,閉じこもりを脱却すると各得点は改善する特徴が示された。
結論 地域高齢者を対象に閉じこもりの観点から3年間の継時的な推移の関連を検討した結果,閉じこもり脱却群,継続群,発生群,非閉じこもり維持群の4群が同時に存在することが確認された。そして,非閉じこもり状態を維持すると移動能力・日常生活活動・活動能力は維持されるのに対し,閉じこもり状態になるといずれも低下,閉じこもり状態を脱却するといずれも向上していた。以上の知見は,閉じこもりに関する変化と移動能力・日常生活活動・活動能力との密接な関連を示唆するものである。
キーワード 地域高齢者,閉じこもり,移動能力,日常生活活動(ADL),活動能力,類型化
|
第58巻第11号 2011年9月 在宅要介護高齢者の介護者における介護負担感とその関連要因-日本と韓国の比較を通じて-金 東善(キム ドンソン) |
目的 在宅要介護高齢者の介護者における介護負担感に影響する要因について日本と韓国を比較し,それぞれの国の事情を勘案して在宅介護者の介護負担の軽減について考察をする。
方法 在宅で65歳以上の高齢者を主に介護している者とした。日本では2009年5月12日~6月6日まで168部の質問紙を配布し,各自返送する方法で回収した。韓国では2009年11月1日~30日まで329部の質問紙を配布し,各自返送する方法で回収した。介護者の基本属性,要介護高齢者の基本属性,介護者の介護時の悩み,介護負担感の項目などを設定した。介護負担感については,日本語版Zarit介護負担感尺度を用いて,妥当性と信頼性を検証した。
結果 日本では63.1%が回収され,韓国では62.0%が回収された。日本と韓国の介護者の悩みについて主成分分析(バリマックス回転)を行った結果,「家事援助に関する悩み」と「身体的援助に関する悩み」の2因子が抽出された。介護者と要介護者の基本属性,介護者の悩みの2因子を独立変数とし,介護負担感を従属変数とした重回帰分析の結果,日本では介護者の健康状態が良い,要介護者に認知症がある,家事援助に悩みがあることが,介護負担感を増加させているという結果がみられた。一方,韓国では介護者の健康状態が悪い,介護者の1日の介護時間が長い,要介護者が女性,要介護者に認知症がある,家事援助に悩みがあることが,介護負担感を増加させているという結果がみられた。
結論 両国の介護者は,要介護者が認知症を抱えていることで介護負担感への影響は大きいことが共通していた。日本と韓国ともに身体的援助に関する悩みより家事援助に関する悩みの方が介護負担感への影響は大きかった。特に,家事援助に関する悩みの介護負担感への影響は,日本より韓国の方が高かった。介護者は介護をもっと頑張らないといけないという思いから献身的になってしまい,介護も家事も長く一人で抱え込んでしまった結果,介護負担感は高くなっている。介護負担軽減のためには,介護サービスなどの社会資源を利用するとともに,介護者の崩れている日常生活を取り戻せることが大事であると考えられる。
キーワード 在宅要介護高齢者,介護者,介護家族,介護負担感
|
第58巻第11号 2011年9月 自殺死亡に対する職業および配偶関係の相乗的関連山内 貴史(ヤマウチ タカシ) 藤田 利治(フジタ トシハル) 立森 久照(タチモリ ヒサテル)竹島 正(タケシマ タダシ) 稲垣 正俊(イナガキ マサトシ) |
目的 本研究は,配偶関係と職業の有無を組み合わせた各カテゴリーについて年齢の影響を調整した自殺死亡の相対リスクを算出することにより,自殺死亡に対する配偶関係および職業の関連を明らかにすることを目的とした。
方法 1995年度,2000年度および2005年度の人口動態調査死亡票および国勢調査を用いて分析を実施した。年度別・性別に配偶関係・職業の有無別の自殺死亡数および死亡率を算出した。また,年度別・性別にポアソン回帰モデルにより,配偶関係と職業を組み合わせた各カテゴリーの相対リスクを求めた。
結果 1995年度から2000年度にかけて,自殺死亡数では有職・無職を問わず有配偶者での増加が大きかったが,増加率では離別と無職が重なった男性で2倍超の上昇と顕著であった。また,男女ともに,いずれの年度も離別と無職が重なった者の自殺死亡率が極めて高くなっていた。ポアソン回帰モデルにより,有配偶の有職者を基準とし,年齢の影響を調整した自殺死亡の相対リスクを算出したところ,調査年度間で各カテゴリーの相対リスクに大きな相違はみられず,男女ともに離別と無職が重なった者の相対リスクが一貫して極めて高いこと,および女性では未婚と無職が重なった者の相対リスクも一貫して高いことが確認された。
結論 配偶関係と職業の有無を組み合わせた各カテゴリーについて年齢の影響を調整した自殺死亡の相対リスクを算出したところ,調査年度を問わず男女ともに離別および無職は一貫して自殺のリスクを高めうること,とりわけ離別と無職が重なった状態は極めてハイリスクであることが示唆された。
キーワード 自殺,リスク因子,配偶関係,職業,相対リスク,人口動態調査
|
第58巻第11号 2011年9月 大規模住民調査による生活機能評価未受診者の特性の解析大渕 修一(オオブチ シュウイチ) 河合 恒(カワイ ヒサシ) 小島 成実(コジマ ナルミ)小島 基永(コジマ モトナガ) |
目的 本研究では,大規模住民調査により,生活機能評価(以下,健診)未受診者の特性を明らかにすることを目的とした。
方法 東京都A区において,要介護認定者を含む高齢者の約10%にあたる3,500名を,性,居住地区別に層化のうえ無作為に抽出し,これらの対象の,①健診受診の有無,②要介護度,③基本チェックリスト,④介護予防の認知,⑤体や頭の衰えを予防できる自信,⑥主観的健康感,⑦移動能力,⑧外出頻度,⑨孤立感などについて,調査用紙を郵送して回答を求めた。回収割合は60.3%,有効回答割合は52.2%であった。これらのデータを,受診者と未受診者の2群に分け,クロス集計にて未受診者の特性を分析した。さらに,健診受診有無を従属変数,健診受診有無と統計学的に有意な関連が認められた指標を独立変数とした多重ロジスティック解析を行い,それぞれのオッズ比を検討した。
結果 未受診者は受診者と比較して,介護予防の認知,体や頭の衰えを予防できる自信,主観的健康感が低く,孤立感を感じている者が多かった。移動能力や外出頻度も未受診者において低かったが,交通手段によってひとりで外出できる者は79.0%,家庭内や隣近所ではほぼ不自由なく動き活動できるが,ひとりで遠出はできないと回答した者が9.7%と高い割合を占めていた。多重ロジスティック解析の結果,介護予防の認知(「よく知っていた」者に対して「全く知らなかった」者では1.6倍(95%信頼区間(CI):1.1-2.3),主観的健康感(「とても健康だ」と回答した者に対して「健康ではない」と回答した者では2.9倍(95%CI:1.7-5.0)),移動能力(「交通手段によってひとりで外出できる」者に対して「起きてはいるが,あまり動けない」者では3.9倍(95%CI:1.7-9.3))が未受診に関連する独立した要因であった。
結論 未受診に関わる要因として,移動能力の低下,主観的健康感の低下,介護予防の知識の不足が挙げられた。従って,健診受診者の拡大には,送迎サービスや出張サービス等の健診受診のための手段的な支援や,在宅で知識を向上させるための取り組みが必要と考えられた。
キーワード 地域住民調査,生活機能評価,介護予防
|
第58巻第12号 2011年10月 平均割引期間や平均年齢の分析手法を
|
目的 「平均割引期間(Average Discounted Terms)」の概念を用いれば,賦課方式を基本としつつ,積立金を保有し運用する年金制度において,金利の高低による効率性の分岐点を表現することができる。これを拡張して,この概念や人口の平均年齢などの分析手法が基本形となり,医療費などの社会保障に係る費用を定量的に分析する際に,同様の手法が適用されることを解説していきたい。
方法 各種の分析手法(平均割引期間の分析手法,人口(安定人口,現実人口)の平均年齢の分析手法,年金平均年齢の分析手法,世代間移転の分析手法)を検証し,これらには同様の手法が適用され,いずれも共通の計算式構造で表現できることを確認する。さらには,その他の分野へ拡張される可能性を検討する。
結果 医療費平均年齢および負債的な概念の医療費への拡張を試みた。具体的には,年金平均年齢の議論における年金受給者の年金額ベースの平均年齢の代わりに,医療費ベース(年齢階級別1人当たり医療費のカーブを用いる)の平均年齢を用いると,年金と同様の平均年齢が計算できる。さらに,「将来の医療費の一時金換算合計-将来の医療費負担の一時金換算合計」は,「負担重心(負担者の平均年齢)と給付重心(受給者の平均年齢)との差としての平均回収期間に,年間保険料収入を乗じたもの」で表現できる。
結論 分析を通じてわかったことは,例えば,第1に安定状態の下での,将来の費用等の一時金換算合計は,「現在の費用等×平均年齢」で表現が可能,第2に上記の年齢軸で見た平均年齢は,時間軸で見た平均割引期間(デュレーション)と同様の機能をもち,人口増加力や利力を介在させることにより,その感応度分析が可能,第3に「①:現在の給付×給付の平均年齢」と「②:現在の負担×負担の平均年齢」の大小関係で給付と負担の大局的構造の観測が可能などである。いずれの分野における議論においても共通構造があり,このためさらに統一的な表現ができる可能性も秘められている。
キーワード 平均割引期間,負債のデュレーション,感応度分析,安定人口,平均年齢,年金平均年齢
|
第58巻第12号 2011年10月 地域生活移行による居住環境の変化に伴う
森地 徹(モリチ トオル) 村岡 美幸(ムラオカ ミユキ) 水嶌 友昭(ミズシマ トモアキ) |
目的 昨今の日本の障害者政策において,その政策課題に掲げられている障害者入所施設からの地域生活移行のうち,知的障害者入所施設からの地域生活移行において,地域生活移行が移行者の生活満足度に及ぼす影響を検証することを本研究の目的とする。
方法 Healらによって作成された生活満足度尺度であるLifestyle Satisfaction Scale(LSS)の28項目を用いて,同一施設の入所者で地域住居に移った群(以下,地域群)と入所施設に残った群(以下,施設群)の生活満足度の比較を横断調査により行った。調査は倫理的配慮を行ったうえで実施し,地域群24名と施設群36名から回答を得た。また,分析においては,t検定と数量化Ⅲ類を用いた。
結果 地域群でも施設群でも住居,食事,外出,仕事に対して高い満足度が感じられる様子が認められた。また,地域群では個別での生活が志向される傾向があり,入所施設には戻りたくないと考える傾向があった。
結論 知的障害者入所施設からの地域生活移行に伴い,個別での生活が保障されることで,移行者の生活満足度が高まる可能性がある。そして,個別での生活が保障されることによって移行者の生活満足度が高まり,施設に戻りたくないと考える傾向があった。これらのことから,地域生活移行に際して個別での生活を保障することが移行者の高い生活満足度につながり,そのための取り組みを行うことが必要になると考えられる。
キーワード 地域生活移行,生活満足度,比較研究,ノーマライゼーション理念,個別性
|
第58巻第12号 2011年10月 都市在住高齢者における
鳩野 洋子(ハトノ ヨウコ) 前野 有佳里(マエノ ユカリ) |
目的 都市在住高齢者における郵送調査未回答者の健康状態や生活状態を記述することを目的とした。
方法 A市の2地区の65歳以上の全住民4,968名に郵送法による質問紙調査を行い,調査期限内に回答しなかった対象に対して保健師が訪問を行い,質問紙への回答を依頼した。調査内容は,属性,特定高齢者への該当状況(運動機能,口腔機能,認知機能),身体・精神状況,社会的状況,健康づくりに関する状況である。調査期間は,郵送調査は平成21年8月12日~31日,訪問は同年9月28日~12月10日の間に実施した。得られた回答から,回答の欠損の多い者,在宅以外の者,要介護認定を受けている者(申請中の者も含む)を除外し,回答期限内に回答した者(期間内回答群)と,そうでない者(期間外回答群)の回答割合を比較した。比較にはχ2検定を用い,有意水準5%で差がみられた場合を有意差ありとした。
結果 4,641名から回答が得られ,最終的に期間内回答群3,207名,期間外回答群438名を分析対象とした。2群に差がみられた項目は,「年齢」(期間外回答群が若い),「家族形態」(期間外回答群が独居・高齢世帯が少ない),「治療中の病気」「既往歴」(期間外回答群のほうが「有り」の割合が少ない),「地域活動への参加」「近所との交流」(期間外回答群のほうが実施していない),「閉じこもりと寝たきりの関係の知識」(期間外回答群のほうが保有割合が少ない)であった。特定高齢者への該当状況の割合に差はみられなかった。
結論 期間内回答群と期間外回答群は保有している健康上のリスクの質に違いがみられた。期間外回答群は,身体的な健康状態は期間内回答群に比較して保たれているが,社会的な面から,将来的な健康上のリスクを有している集団と考えられた。質問紙調査の結果を解釈する際には,両群の違いを考慮することの必要性が示唆された。
キーワード 質問紙調査,高齢者,未返送者,健康状態,生活状態
|
第58巻第12号 2011年10月 インターネットにおける
|
目的 わが国におけるインフルエンザに関する検索およびインフルエンザの流行に関する指標を用いて,インフルエンザの流行とインターネット上の検索行動との関連の追試を実施するとともに,検索行動がインフルエンザ流行の先行指標として機能するかを調査する。この際,インフルエンザに関する検索行動をいくつかのクラスタに分割した上で検討する。
方法 インフルエンザに関する検索状況に関するデータは,Google Insights for Searchを利用して収集した。インフルエンザの流行の指標としては,国立感染症研究所感染症情報センターのインフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数など)を利用した。インフルエンザに関する検索語をクラスタ分析を利用して分類した上で,インフルエンザの流行の指標との相互相関を検討した。
結果 インフルエンザに関する日本語の検索語は大きく「予防」と「対処」の2つに分類されること,「対処」に関する検索がインフルエンザの流行と強い相関(r>0.80)を持つことが示唆された。また,検索を先行させた際の相関(相互相関)は,中程度から強い相関を示していた(0.34<r<0.85)。
結論 海外のデータで指摘されていたインフルエンザの流行と検索エンジン利用との関連についてわが国のデータを用いて追試を行った結果,先行研究の内容は支持された。「対処」に関する検索の増加は,その後の流行の増加と関連することが示唆されたが,「対処」に関する検索とインフルエンザの流行は同期的に変化していると考えられた。
キーワード インフルエンザ,インターネット,情報疫学,検索エンジン,相互相関
|
第58巻第12号 2011年10月 栃木県における自殺の動向-警察データからみた原因・動機の経時的変化-坪井 聡(ツボイ サトシ) 千原 泉(チハラ イズミ) 工藤 由佳(クドウ ユカ)定金 敦子(サダカネ アツコ) Tsogzolbaatar Enkh-Oyun 阿江 竜介(アエ リュウスケ) 小谷 和彦(コタニ カズヒコ) 青山 泰子(アオヤマ ヤスコ ) 上原 里程( ウエハラ リテイ) 中村 好一(ナカムラ ヨシカズ) |
目的 栃木県における自殺の動向や自殺の原因,動機の推移を明らかにし,栃木県の自殺対策について検討する。
方法 2007年から2009年の間に栃木県内で発生したすべての自殺者を対象とした。栃木県警察が保有する,県内で発生した自殺に関する小票を分析資料として用いた。また,警察庁が公表している自殺統計から得られる全国の値を比較対象として用いた。分析に用いた項目は,自殺者の性,年齢,自殺した年,職業,同居人の有無,自殺未遂歴の有無,自殺の原因・動機,自殺の原因・動機の判断資料である。自殺の原因・動機には,家庭問題(親子関係の不和,夫婦関係の不和など),健康問題(身体の病気,うつ病など),経済・生活問題(倒産,多重債務など),勤務問題(職場の人間関係,仕事疲れなど),男女問題(結婚をめぐる悩み,失恋など),学校問題(学業不振,いじめなど),その他(犯罪発覚時,孤独感など),不詳が含まれていた。また,人口10万人当たりの自殺死亡者数を自殺率とした。
結果 観察した3年間の総自殺死亡者数は,栃木県で1,796人,全国で98,187人であった。総死亡者数に占める男女の割合,自殺者の年齢分布,就業状況は,栃木県と全国との間で大きな違いはみられなかった。全国では,男女とも自殺率に大きな変化はみられなかったが,栃木県の自殺率はいずれの年も男女ともに全国より高く,また,2007年以降で増加していた。栃木県の自殺の原因・動機について,男では健康問題の割合が最も大きく,経済・生活問題,家庭問題と続いた。女では,健康問題の割合が最も大きく,家庭問題,経済・生活問題と続いた。これらの内,2007年以降で増加していたのは男女ともに経済・生活問題だけであった。経済・生活問題の中の多重債務による自殺は,栃木県の男では中高年に多くみられ,2007年から2008年にかけては60歳代,2008年から2009年にかけては50歳代で特に増加していた。一方,女では,2007年には40歳代と50歳代に限られていたが2008年以降は幅広い年代にみられた。
結論 本研究によって,多重債務を中心とした経済・生活問題が栃木県の自殺率を増加させている可能性が示唆された。栃木県では,既に整備されている多重債務等の問題に関する相談窓口の利用を促進するための調査や働きかけを行い,自殺の推移を今後も注意深く観察していく必要がある。
キーワード 自殺,警察データ,栃木県,記述疫学,経済・生活問題,多重債務
|
第58巻第13号 2011年11月 一般事業所における障害者の雇用実態-三原市の調査から-三原 博光(ミハラ ヒロミツ) 松本 耕二(マツモト コウジ) |
目的 障害者雇用促進法や障害者自立支援法などにより,現在,障害者の就労が重視されてきている。そこで,一般事業所の障害者の雇用実態を調べることを本研究の目的として質問紙調査を実施した。
方法 三原市内の50人以上の従業員の一般事業所に対して,障害者の雇用状況に関する質問紙用紙を郵送した。
結果 三原市内の110事業所に質問紙用紙を郵送し,59事業所から回答を得た。その結果,30事業所が現在,障害者を雇用していた。雇用されている障害者の半数は身体障害者であり,障害の程度は軽度であった。雇用形態は,半数は「常用雇用」であった。雇用の方法は,6割強が障害者雇用促進法によるものではなく,一般事業所の業務の必要性から雇用されていた。雇用されている障害者やその保護者は雇用されている事に満足をしていた。そして,現在,障害者を雇用している一般事業所の4割は希望があれば,さらに障害者を雇用しても良いと回答していた。一方,20事業所は,現在,障害者を雇用していないと回答し,その理由として「障害者に適した職業がない」「障害者を雇用する環境が整備されていない」をあげていた。そして,将来の障害者の雇用の可能性については,半数の事業所は「困難である」と回答していた。
結論 障害者を雇用している事業所では,障害者やその保護者は雇用されていることに満足し,事業所も障害者の雇用について積極的に考えていた。一方,障害者を雇用していない事業所は,将来においても,障害者の雇用には消極的であった。今後,障害者の雇用に消極的な事業所に対して,行政や福祉関係者などから,障害者の雇用に関して,積極的な働きかけの必要性が課題として示された。
キーワード 一般事業所,障害者,雇用,就労
|
第58巻第13号 2011年11月 三重県の高齢者入所施設における
豊島 泰子(トヨシマ ヤスコ) 鷲尾 昌一(ワシオ マサカズ) 高橋 裕明(タカハシ ヒロアキ) |
目的 高齢者入所施設にインフルエンザウイルスが持ち込まれるとインフルエンザの集団発生に結びつく。本研究では2009/2010シーズンの新型インフルエンザの流行時における高齢者施設の入所者および看護・介護職員を対象として,季節性・新型インフルエンザの罹患状況とインフルエンザワクチン接種の現状を調査した。
方法 三重県内の全高齢者入所施設(224施設)のインフルエンザワクチン担当者を対象に,2009/2010シーズン終了後の2010年4月に郵送で,入所者および看護・介護職員の季節性・新型インフルエンザ罹患とインフルエンザワクチン接種に関する無記名のアンケート調査を行った。
結果 224施設中155施設から回答が得られた(回収率69.2%)。入所者にインフルエンザの罹患を認めた施設は季節性5.2%,新型3.2%,不明1.9%であった。看護・介護職員にインフルエンザの罹患を認めた施設は季節性20.6%,新型54.8%,不明10.3%であった。入所者のインフルエンザワクチン接種が70%以上の施設は季節性90.3%,新型72.9%であり,看護・介護職員のインフルエンザワクチン接種が70%以上の施設は季節性91.0%,新型61.9%であった。季節性インフルエンザワクチン接種割合が70%以上の施設は,入所者と看護・介護職員ともに,新型インフルエンザワクチン接種割合が70%以上の施設に比べて有意に多かった(p<0.01)。新型インフルエンザワクチン接種割合は,入所者が看護・介護職員に比べて有意に高かった(p<0.01)。看護・介護職員のインフルエンザワクチン接種に対する費用負担は,季節性では全額施設負担が58.1%,一部施設負担が32.3%,全額自己負担が9.7%であった。一方,新型では全額施設負担が45.2%,一部施設負担が29.7%,全額自己負担が23.2%であった。
結論 看護・介護職員の季節性インフルエンザワクチン接種率は入所者とほぼ同様であったが,新型インフルエンザワクチンの接種率は有意に低く,看護・介護職員の新型インフルエンザの罹患者が多く,外部からの持ち込みの防止には看護・介護職員の新型インフルエンザワクチン接種率の向上が必要であった。また面会の家族や出入りの業者に対するインフルエンザワクチン接種の勧奨の取り組みが少なく,インフルエンザの感染予防対策の見地からも改善の必要があると考えられた。
キーワード 看護・介護職員,高齢者入所施設,ワクチン,季節性インフルエンザ,新型インフルエンザ
|
第58巻第13号 2011年11月 基本健診の血圧からみた脳卒中発症に対する集団寄与危険割合中川 愛理(ナカガワ エリ) 朝倉 幸代(アサクラ ユキヨ) 佐野 文恵(サノ フミエ)遊道 啓子(ユウドウ ケイコ) 島崎 忠美(シマザキ マミ) 飯野 三惠子(イイノ ミエコ) 瀧波 賢治(タキナミ ケンジ) 高橋 洋一(タカハシ ヒロカズ) 成瀬 優知(ナルセ ユウチ) |
目的 市全体の脳卒中発症に血圧がどの程度寄与しているのかを把握するために,性・年齢階級別の集団寄与危険割合を算出した。また,この分析で示された結果がこれまで市で実施してきた保健事業の内容と整合しているかを検討し,今後の脳卒中対策事業の基礎情報とすることを目的とした。
方法 平成12年度健診受診者のうち40~84歳の38,112人(男性11,357人,女性26,755人)を対象とした。この中から収縮期および拡張期血圧の結果を有し,平成12年4月1日~平成17年3月末日までに脳卒中を発症していた494人(男性248人,女性246人)を抽出した。発症状況は富山県脳卒中情報システムデータから把握した。なお,富山県脳卒中情報システム事業の情報利用については,富山県厚生部の承認を得た。血圧は区分値を設定し5カテゴリーに分けた。脳卒中発症に関わるリスク比は,年齢4群と血圧カテゴリー5群との計20群で男女別にCoxの比例ハザードモデルにてハザード比を算出した。健診受診者の性,年齢階級別の各カテゴリー別構成割合をもとに,平成19年9月末日の富山市の40~84歳における男女別の推計人数を算出した。次に,この推計人数に脳卒中発症のハザード比を乗じ,年齢階級ごとのカテゴリー別に推計脳卒中発症数を算出し,年齢階級別集団寄与危険割合を算出し,かつ各カテゴリー別にその構成値を示した。
結果 ハザード比はおおむね年齢が上がるとともに上昇する傾向がみられた。年齢階級別にみると,血圧のハザード比の上昇レベルは一様ではなかった。集団寄与危険割合は男性において65~74歳が最も高く55.4%であり,総数では44.0%であった。75~84歳以外の年齢階級において「軽症高血圧」で最も高い値を示した。女性において40~54歳が最も高く68.1%であり,年齢階級が上がるごとに集団寄与危険割合が下がる傾向がみられ,総数では46.3%であった。ほとんどの年齢階級において「軽症高血圧」で最も高い値を示した。
結論 市全体の脳卒中発症を減らすという視点で保健対策について検討した結果,男女ともに前期高齢者以下の年齢への高血圧対策,特に軽症高血圧対策が今後も必要であることが示された。今後も長期的に情報を集約・分析し,市民の健康状態を把握するとともに保健施策の成果を適切に評価し,効果的な保健事業の実施へつなげていくことが重要であると考えられる。
キーワード 脳卒中,血圧,集団寄与危険割合,保健対策
|
第58巻第13号 2011年11月 日本成人男性におけるHIVおよびAIDS感染拡大の状況-MSM(Men who have sex with men)とMSM以外の男性との比較-塩野 徳史(シオノ サトシ) 金子 典代(カネコ ノリヨ) 市川 誠一(イチカワ セイイチ) |
目的 わが国におけるMSM(Men who have sex with men,これまでに同性間性的接触を有する男性)人口を推定し,さらに感染経路別にHIV感染者とAIDS患者の有病率,罹患率の推計に資するデータを得ることによって,日本成人男性におけるHIVおよびAIDS感染拡大の状況の一端を明らかにする。
方法 東北,関東,東海,近畿,九州の5地域に在住する20~59歳の日本成人男性を対象として,郵送法による質問紙調査を実施しMSMの割合を算出した。得られたMSMの割合と国勢調査人口を用いてMSMの人口を推定した。そしてエイズ動向委員会による報告を基に,日本国籍MSMとMSM以外の男性(日本国籍の男性からMSM人口を除いた男性全体)におけるHIV感染とAIDSの有病率と罹患率をそれぞれ推計し比較した。
結果 質問紙調査の有効回答者は1,659人(回収率:44.8%)であり,MSMの割合は全体で2.0%(95%信頼区間:1.32-2.66%)であった。MSM割合について居住地域間での統計学的な有意差はみられなかった(p=0.170)。質問紙調査により得たMSMの割合2.0%を日本成人男性のMSM割合と仮定して有病率と罹患率をそれぞれ算出したところ,MSM以外の男性に比べてMSMは,HIV有病率では96倍,AIDS有病率では33倍の高さであった。罹患率については,MSM以外の男性では2001~2008年度の間にHIV罹患率は0.5~0.7,AIDS罹患率は0.3~0.5と大きな変化はみられなかった。一方,MSMでは,HIV罹患率は42.6(2001年)から103.7(2008年)と8年間で2.4倍,AIDS罹患率は11.6(2001年)から23.9(2008年)と8年間で2.1倍に拡大していた。
結論 20歳から59歳における日本成人男性のMSM割合の推定と,推定MSM人口を母集団としたHIVおよびAIDSの有病率と罹患率を算出した。日本人男性の中ではMSM集団において,HIV感染が拡大し,AIDS患者が増加していることが示された。わが国においてはMSM集団を対象としたHIVおよびAIDS対策を早急に実施していくことが重要である。
キーワード HIV感染症,AIDS,有病率,罹患率,MSM,MSM割合
|
第58巻第13号 2011年11月 朝の排便時間帯別にみた保育園5・6歳児の生活実態泉 秀生(イズミ シュウ) 前橋 明(マエハシ アキラ) 町田 和彦(マチダ カズヒコ) |
目的 本研究では,2009年度に行った「幼児の生活実態調査」結果をもとに,保育園児の普段の生活実態の中から,定時に排便している幼児を抽出し,排便の時間帯と生活状況との関連を分析した。そして,子どもたちが,健康で生き生きと生活するための知見を得ることを目的とした。
方法 幼児の生活実態調査を1都9県の保育園5・6歳児2,072名(男児1,069名・女児1,003名)の保護者を対象に実施した。調査の内容は,普段の平日の生活実態を聞くものであった。そして,排便を「定時にする」と答えた幼児のみを抽出し,その中から,午前9時前に排便する幼児「登園前排便児」と,午後4時以降に排便する幼児「降園後排便児」の2群に分けて,それぞれの生活時間やその実態を比較・分析した。
結果 朝の排便を,「定時にする」子どもは,男児で1,069名中333名(31.2%),女児で1,003名中232名(23.1%)であり,その中でも,朝9時までにする「登園前排便児」は男児で266名(24.9%),女児で178名(17.7%)確認され,午後4時以降の「降園後排便児」は,男児で65名(6.1%),女児で54名(5.4%)となった。男児において,「登園前排便児」の方が「降園後排便児」よりも,生活時間が有意に早く(p<0.01),睡眠時間が有意に長い(p<0.01)ことや,1日のテレビ・ビデオ視聴時間が有意に短く(p<0.01),起床時の機嫌が「いつも良い・良いときの方が多い」子どもの割合が有意に多い(p<0.01)ことを確認した。また,「登園前排便児」の方が,夕食後のおやつを「食べない時の方が多い・食べない」割合が有意に多く,「降園後排便児」では「食べる・食べる時の方が多い」割合が有意に多かった(p<0.01)。男児において,「登園前排便児」では,朝食時のテレビ・ビデオを「見ない時の方が多い・見ない」子どもが多く,「降園後排便児」では「見る・見る時の方が多い」子どもが多くなった(p<0.01)。
結語 「登園前排便児」は,「降園後排便児」に比べて,生活時間が全体的に早いことを確認した。とくに,男児において,「登園前排便児」の朝の機嫌が良いこと,朝食時にテレビを見る子どもや夕食後のおやつを食べる子どもが少ないことが確認された。幼児期の子どもでは,毎日排便をすることに加えて,登園前に排便をしていることが,規則正しい生活をおくっている証となり,ひいては,生き生きとした健やかな暮らしを育む可能性が推察された。
キーワード 保育園児,排便状況,起床時刻,登園時刻,朝食開始時刻
|
第58巻第13号 2011年11月 気象条件・死亡場所が死亡原因に与える影響羽山 広文(ハヤマ ヒロフミ) 釜澤 由紀(カマザワ ユキ) 松村 亮典(マツムラ リョウスケ)菊田 弘輝(キクタ コウキ) |
目的 目的外使用により入手した人口動態調査死亡票および気象庁のアメダスデータを用い,地域,季節,外気温度,死亡場所による死亡率の関係について検討した。
方法 人口動態統計死亡票は平成15~18年の4年間分を使用した。ICD-10に準拠したCode. 9200-9208を「心疾患」,同9300-9304を「脳血管疾患」に分類した。人口データは平成17年国勢調査人口を用いた。外気温度などの条件による死亡率を評価するため,外気温度の発生頻度を考慮した死亡率を用いた。
結果 ①自宅において心疾患,新生物,脳血管疾患の順に多く,自宅での心疾患は他の死因と比較し比率が高い。②心疾患に関し,急性心筋梗塞,その他の虚血性心疾患,不整脈・伝導障害,心不全について,病院に対する自宅での死亡率のオッズ比を求めた結果,その他の虚血性心疾患,急性心筋梗塞が他の心疾患と比較し顕著であった。③脳血管疾患に関し,くも膜下出血,脳内出血,脳梗塞について,病院に対する自宅での死亡率のオッズ比を求めた結果,脳内出血が他の脳血管疾患と比較し顕著であった。④各疾患に関し,月別死亡数比を病院と自宅で比較した結果,その他の虚血性心疾患,急性心筋梗塞,脳内出血で顕著な差異が見られた。⑤心疾患および脳血管疾患の外気温別オッズ比は,病院では外気温度の影響が少なく自宅ではいずれの地域でも外気温の低下とともに顕著に増加する。地域別にみると,温暖な地域はその傾向が顕著であった。
考察 死因における心疾患と脳血管疾患に関し,同類の疾患の中でも自宅での死亡率が病院と比較し顕著に高くなる疾患は,その他の虚血性心疾患,急性心筋梗塞,脳内出血であった。いずれの疾患も危険因子として高血圧が挙げられる。自宅では温暖な地域ほど外気温が低くなった場合,リスクの増加が顕著であることから,温暖な地域でも自宅の断熱性能向上の必要性が裏付けられた。
キーワード 人口動態統計,気象データ,死亡場所,外気温度,死亡率,オッズ比
|
第58巻第15号 2011年12月 日本の社会的養護施設入所児童における被虐待経験の実態筒井 孝子(ツツイ タカコ) |
目的 国内の先行研究において,これまで社会的養護関連施設別や,個々の児童の基本属性別にみた被虐待経験割合,あるいは複数の被虐待経験の組み合わせについての詳細は,全国レベルではほとんど明らかにされてこなかった。そこで本研究では,2009年に実施された全国の社会的養護関連施設の全入所児童のデータを用いて,第1に,わが国の全社会的養護関連施設の全入所児童における被虐待経験の割合を明らかにすること,第2に,被虐待経験の組み合わせを類型化し,その発生割合を明らかにすること,第3に,児童の被虐待経験と基本属性との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 2009年度に社会的養護関連施設を対象とした調査で収集された全入所児童36,234名のデータを用いて,児童の年齢,性別等の基本属性,被虐待経験の有無と虐待の種類(身体的虐待,性的虐待,ネグレクト,心理的虐待,その他)について分析した。
結果 日本の社会的養護施設入所児童における被虐待経験ありの割合は,55.5%であった。男女別にみると男女ともに約6割と過半数を超え,年齢階級別では,虐待経験ありの割合が過半数だったのは,7歳以上16歳未満,16歳以上であった。また被虐待経験ありの割合は,施設種別によって大きく異なっており,情緒障害児短期治療施設が最も高く78.1%,児童自立支援施設が66.2%,児童養護施設では59.2%,母子生活支援施設が43.7%,乳児院34.4%であった。この結果からは,社会的養護入所施設のうち,乳児院と母子生活支援施設を除けば,被虐待経験を持つ児童は半数を超えており,社会的養護入所施設は,単に養育に欠ける児童へのケアだけでなく,被虐待児童に対して,治療的なケアも担うべき存在となっているものと考えられた。
結論 本研究では,施設種別ごとの被虐待経験の分析結果より,入所児童の属性が大きく異なっていることが示されたと同時に,被虐待児童への治療的ケアを含めた適切に提供できることが求められていることが明らかにされた。今後は,臨床現場で実施されている被虐待経験に対応するためのケアを明確にし,これを標準化していくことが課題である。
キーワード 社会的養護,被虐待経験,施設養護,要保護児童
|
第58巻第15号 2011年12月 高齢者ショートステイにおける生活相談員業務の実態調査-業務の「実施状況」と「必要性認識」に着目して-口村 淳(クチムラ アツシ) |
目的 短期入所生活介護(以下,ショートステイ)における生活相談員(以下,相談員)業務の「実施状況」ならびに「必要性認識」を明らかにし,その特徴について検討することを目的とする。
方法 無作為抽出(系統抽出法)した短期入所生活介護500施設に所属する相談員(1施設1人)を対象に,郵送調査を実施した。調査時期は,2010年10月(1カ月間),回収割合は50.8%である。28項目の業務内容を,「実施状況」ならびに「必要性認識」の視点から,それぞれ4件法で尋ねた。また,「実施状況」と「必要性認識」の差については,両項目の平均値の差を検定(t検定)した。
結果 ショートステイにおける相談員業務の傾向として,連絡調整,相談,入退所に関する業務が,「実施状況」「必要性認識」ともに高い割合がみられた一方で,介護関連の割合は両項目ともに低かった。また,スタッフ教育,経営管理,人間関係調整に関する業務も,相談員中心の業務という意味では,両項目とも5割程度にとどまった。さらに,「実施状況」と「必要性認識」の平均値の差を検討したところ,「利用者の送迎」「入所判定」「利用者・家族の入所前相談面接」をはじめとする7項目で,「実施状況」が「必要性認識」を有意に上回った。
結論 本調査の結果,ショートステイの相談員業務における「実施状況」と「必要性認識」は,おおむね一致していることが明らかになった。しかし,一部の業務では,「実施状況」が「必要性認識」を上回っていた。これは,本来,他職種が中心または他職種と協働で実施する業務であるにもかかわらず,相談員が担うことになっている可能性を示している。そのためにも,施設内の他職種との業務調整,業務分掌による系統的な体制整備の必要性等が示唆された。
キーワード ショートステイ,生活相談員,業務の実施状況,業務の必要性認識
|
第58巻第15号 2011年12月 水中運動指導者の皮膚状態田名部 佳子(タナベ ヨシコ) 辻本 朋美(ツジモト トモミ) 根来 佐由美(ネゴロ サユミ)井上 智子(イノウエ トモコ) |
目的 水中運動がより安全な健康づくりとして普及するために,プール水が水中運動指導に従事する運動指導士と健康運動実践指導者(以下,水中運動指導者)の皮膚に及ぼす影響を把握することを目的とした。
方法 2009年11月中旬から12月下旬にかけて,大阪府内の運動施設に勤務する水中運動指導者7名を対象に,アンケートを用いた皮膚状態や生活習慣の調査,ならびに1人当たり4~5回の両前腕内側中央部および両下腿膝蓋骨内側顆下部の角層水分量と皮膚pHの測定を行った。経時的変化を観察するため,水中運動指導前と指導直後から15分間隔に指導60分後まで測定した。
結果 水中運動指導者の1回指導時間は1.4±0.7時間であり,1週間当たり5.9±1.0時間であった。水中運動指導前の角層水分量は前腕10.6±3.8μS,膝下9.2±3.0μSと低く乾燥状態であり,指導直後に有意に上昇した(ダネット法,p<0.05)が60分後には指導前同様の低値になった。皮膚pHは指導前に前腕pH5.5±0.5,膝下pH5.2±0.6と正常であったものが指導後に上昇し,指導後60分が経過しても指導前の皮膚pHより高く,有意な差があった(ダネット法,p<0.05)。さらに,水中運動指導者は皮膚の乾燥を招きやすい生活習慣をもっており,皮膚の乾燥や痛み,髪の傷みなど,スキントラブルを実感していた。
結論 水中運動指導者の皮膚は乾燥しており,プール水の影響や生活習慣の関与が示唆された。また,プール水の影響により指導後60分が経過しても皮膚のバリア機能が低下していた。
キーワード 水中運動,運動指導士,健康運動実践指導者,スキントラブル
|
第58巻第15号 2011年12月 全国保健所の精神障害者デイケアサービスの
佐伯 圭吾(サエキ ケイゴ) 山田 全啓(ヤマダ マサヒロ) 山下 典子(ヤマシタ ノリコ) |
目的 わが国の保健所は精神障害者デイケア提供に先駆的かつ重要な役割を担ってきたが,1999年の精神保健福祉法改正,2005年の障害者自立支援法施行によって,障害者福祉を主に担当する行政機関は都道府県から市町村に移行された。これらの法整備は保健所デイケアのあり様に影響を及ぼしていると考えられるが,その状況は明らかでない。そこで,精神障害者を対象とした保健所デイケアの実施状況の推移と,調査時現在のデイケア実施の有無にかかわる要因の検討を目的として本研究を実施した。
方法 全国517保健所(調査時現在)の精神保健福祉担当者宛てに,自記式調査票を2008年10月から2009年1月にかけて郵送にて配布し,回収した。調査票では,管内人口,保健所デイケアの過去からの実施状況,デイケアを終了した保健所にはその理由,管内の精神科医療機関数や精神保健福祉施設数などについての回答を求めた。
結果 411保健所(79.5%)から回答が得られた。県型保健所でのデイケアの実施割合は1975年から増加し,1997年と1998年にピーク(91.5%)を形成した後,2002年以降は急速に減少し,調査時(2008年)には23.7%にまで低下していた。これに対し,市区型保健所の減少はなだらかで,その結果,調査時現在のデイケア実施割合は県型保健所が,政令指定都市型の50.0%,中核市型の71.4%,特別区保健所の81.3%に比べ有意に低率であった(P<0.01)。調査時現在のデイケア実施の有無を目的変数,保健所区分,管内の精神科医療機関数,精神福祉施設数,デイケア実施施設数などを説明変数とした多重ロジスティック回帰分析では,保健所区分のみが有意な関連を示した。また,県型保健所のうちデイケアを「実施している」保健所と「実施していない」保健所との比較では,前者に比べて後者の管内人口10万人当たりの精神福祉施設数が有意に多かった(P<0.01)。
結論 県型保健所における精神障害者のためのデイケアサービスの実施割合は大きく減少し,その減少には,精神保健福祉法改正や障害者自立支援法施行により精神障害者福祉の窓口となる行政機関が保健所から市町村へ変化したことや,地域の精神福祉資源数が関与していたことが示唆された。
キーワード 保健所,精神障害者デイケア,精神保健福祉法,障害者自立支援法
|
第58巻第15号 2011年12月 小学生・中学生・高校生の朝食欠食と学習時間の関係野田 龍也(ノダ タツヤ) 徳本 史郎(トクモト シロウ) 村田 千代栄(ムラタ チヨエ)早坂 信哉(ハヤサカ シンヤ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) |
目的 わが国における児童・生徒の朝食摂取と学習時間との関係を大規模調査を用いて明らかにすることを目的とした。
方法 2001年の社会生活基本調査の個票を用い,小学生(10歳以上),中学生および高校生を対象に,朝食欠食の有無と1日の合計学習時間・学校内外での学習時間との関連を学校種別および通学日・休日の別に検討した。さらに,朝食欠食の有無と他の生活行動時間との関連をみるため,児童・生徒の1日の生活行動時間の分布を,通学日・休日別,学校種別,朝食欠食の有無別に示した。
結果 対象者は通学日7,308名,休日11,265名であった。小学生,中学生,高校生について,朝食欠食率は2.8,5.9,13.4%(通学日),5.9,10.5,21.0%(休日)であり,平均学習時間は373.9,420.8,401.1(通学日),154.5,203.2,212.7分(休日)であった。朝食欠食の有無と学習時間の関係では,小学生と中学生の通学日については朝食群と朝食欠食群とで有意な差を認めなかったが,小学生の休日(両群の差:43.9分)と中学生の休日(同61.0分),さらに高校生の通学日(同51.3分)と休日(同93.7分)では朝食群の学習時間が有意に長かった。1日の生活行動時間の分布を朝食群と朝食欠食群で比較したところ,通学日では,小学生で朝食群の通学時間が有意に長かった。高校生では,朝食群で学習,スポーツに費やす時間が有意に長く,通学等,睡眠,趣味・娯楽,休養,その他の行動は有意に短かった。休日では,すべての学校種別において,朝食群の方が学習,通学等,食事,スポーツに有意に多くの時間を費やしており,睡眠とテレビ・雑誌等の時間が有意に短かった。また,中学生と高校生では,朝食群で身の回りの用事に費やす時間が有意に長く,高校生では朝食欠食群で交際・つきあいに有意に多くの時間を費やしていた。
結論 小中学生の学習時間は,通学日では朝食摂取とさほど関連しないが,休日では大きく関連していた。高校生においては,通学日,休日のいずれでも朝食摂取者の学習時間が顕著に長く,1日の生活行動時間パターンでも朝食群と欠食群で行動の分布が大きく異なることが明らかとなった。
キーワード 朝食欠食,学習時間,小学生,中学生,高校生,社会生活基本調査
|
第59巻第1号 2012年1月 ICDを中心としたWHO-FIC(WHO国際分類)に
瀧村 佳代(タキムラ カヨ) 及川 恵美子(オイカワ エミコ) 鐘ヶ江 葉子(カネガエ ヨウコ) |
1 WHO-FICとは
WHO国際分類ファミリー(WHO Family of International Classification. 以下,WHO-FIC)とは,
WHOが作成した国際分類を中心とする,健康に関する情報を国際的に比較するための分類群である。
WHO-FICは,以下の3種類の分類で構成されている(図1)。ファミリーを構成することによって,
分類間の矛盾を可能な限り減少させ,健康関連分類の管理者機能をもつことができる。
(1) 中心分類(reference classification)
中心分類は,死亡,疾患,生活機能,障害等,健康・保健医療福祉システムに関する主な変数
(パラメータ)を包含している分類である。現在,ICD(International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems.疾病及び関連保健問題の国際統計分類)およびICF
(International Classification of Functioning,Disability and Health.国際生活機能分類)がこ
れに該当する。 なお,ICHI(lnternational Classification of Health Intervention.国際医療
行為分類)は,現在もなお作成検討中である。
1)ICDについて
ICDは,疾病名および関連用語をコード化した分類であり,WHOがWHO憲章に基づいて
作成し,加盟国に対して死亡統計等に使用するよう勧告している。ICDを導入することにより,
異なる国や地域から,異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録,分析,解
釈および比較を行うことが可能となる。
最新の分類は,1990年の第43回世界保健総会において採択されたICD第10回改訂版であり,
ICD-10と呼ばれている。
現在,わが国では,ICD-10を一部改正したICD-10(2003)に準拠した「疾病,傷害及び
死因分類」を作成し,統計法に基づく統計調査に使用されるほか,医学的分類として医療機関
における診療録の管理等に活用されている。
統計法に基づく統計調査のうち人口動態統計における死亡統計では,明治32年(1899)年か
らICDを活用している。死亡原因は国民の健康に直結する極めて重要な問題であることから,
死亡診断書(死体検案書)の記載内容からWHOより勧告された死因選択ルールに基づい
て「原死因」を確定し,ICDを用いて死因別に表示している。
|
第59巻第1号 2012年1月 都道府県別乳がん死亡率と教育系ファシリティとの関連-ソーシャル・キャピタルの視点から-片山 佳代子(カタヤマ カヨコ) 助友 裕子(スケトモ ヒロコ) 黒沢 美智子(クロサワ ミチコ)横山 和仁(ヨコヤマ カズヒト) 岡本 直幸(オカモト ナオユキ) 稲葉 裕(イナバ ユタカ) |
目的 都道府県別乳がん死亡率と教育系ファシリティは,どのような関連性を示すのか,喫煙率,乳がん検診受診率,ボランティア活動行動者率をもとにソーシャル・キャピタルを視野に入れ検討した。
方法 政府統計資料の中から,乳がん検診受診率と,成人女性喫煙率(2001年),各種ボランティア活動行動者率(2001年),各種教育系ファシリティ数(2002~2003年)を収集し,すべて都道府県別に順位データに変換し分析に使用した。乳がん死亡率は55歳前後で死亡率を算出し使用した。各種教育系ファシリティに関しては,少子化の影響と喫煙開始年齢を考慮し,都道府県別20歳以上女性人口(2001年)1人当たり数に換算して使用し,その後クラスター分析(Ward法)により分類した。各種ボランティア活動行動者率は,主成分分析より算出した値をソーシャル・キャピタル指数総合ボランティア活動率として使用した。各変数間の相関分析を通して,共分散構造分析を探索的に行いモデル化した。また教育系ファシリティ19施設の集積性を確認するために,格差係数であるジニ係数をファシリティ指標ごとに算出した。
結果 各種教育系ファシリティは「社会教育系」「限定教育系」「地域公立系」「大学系」「その他教育系」の5種に分類された。55歳以上乳がん死亡率は,東京・神奈川と関東域が高く,総合ボランティア活動率,「大学系」を除く教育系ファシリティと負の相関がみられた。共分散構造分析結果から,55歳以上乳がん死亡率には,喫煙が大きく関係しており,採用した教育ファシリティは,喫煙率を介して,乳がん死亡率に間接的に負の影響を及ぼす方向と,ソーシャル・キャピタル指標として作成した総合ボランティア活動を介して,検診受診率と喫煙率に負の影響を及ぼし,間接的に乳がん死亡率に影響を与える因果構造モデルが得られた。
結論 都道府県単位の分析ではあるが,乳がん死亡率に,公立小中高校等の地域公立系ファシリティと,幼稚園,保育所,公民館等の社会教育系ファシリティが喫煙率や,総合ボランティア活動に影響を及ぼす可能性が示唆された。今後は,地域の教育系ファシリティをどのように活用していくのか,健康教育プログラム開発,がん教育,たばこ教育プログラム等その地域特性を生かした取り組みがなされることが期待される。
キーワード 都道府県単位,乳がん死亡率,教育,ファシリティ,ソーシャル・キャピタル,地域格差
|
第59巻第1号 2012年1月 子どものすこやかな発達と子育て支援への
安梅 勅江(アンメ トキエ) 冨崎 悦子(トミサキ エツコ) 望月 由妃子(モチヅキ ユキコ) |
目的 「木育(もくいく)」とは,すべての人が木とふれあい,木に学び,木と生きる取り組みであり,人と木や森とのかかわりを主体的に考える豊かな心を育むことを目標としている。本研究は「木育の効果」の評価を目的とし,子どものすこやかな発達と子育て支援への一助とすることを意図した。
方法 M市の保育園児とその養育者168名に対し,約2時間の木育プログラムを実施した。木育の前後で子どもの社会性と主体性,養育者のかかわりの変化を,「かかわり指標(Interaction Rating Scale, IRS)」および「描画」を用いて評価した。分析は,「かかわり指標」については全体得点と領域得点を算出し,木育前後での子どもと養育者の得点の変化を検討した。また「描画」については,色の数,描画の大きさ,アイテム数について数値で評価した。
結果 「かかわり指標」を用いた分析では,子どもの微笑みや養育者へのアイコンタクト,発話が増え,子どもの主体性,共感性,運動制御得点が有意に高くなるなど,木育を通じて子どもから養育者へのかかわりが活発になる傾向がみられた。養育者の子どもへの対応は,木育の前後で子どもに向ける視線や声かけが増えるとともに,子どもの主体性発達への配慮,応答性への配慮が有意に高くなるなど,養育者の子どもへの配慮が高まる傾向がみられた。描画について,木育前は単純な木の絵を描く傾向が多くみられたが,木育後はプログラムに関連した「遊ぶ様子」や「さまざまな想像力」にあふれた絵が多くみられた。色数が多彩になり,大きさが拡大し,力強く描く者が増加した。
結論 「木育」を通じて子どもからのかかわり,養育者からのかかわりがともに増え,子どもと養育者が調和のとれた関係性を築いている様子がうかがわれた。子どもと養育者ともに,木育の前後で描画が大きく変化した。木育後は「勢い」「開放性」「躍動感」のある描画が多くみられた。ともに木育を十分に楽しむ様子が観察された。「木育」の積極的な活用が,子どものすこやかな発達,養育者の子育て支援への一助となる可能性がある。
キーワード 木育,評価,かかわり,描画,社会性発達,子育て支援
|
第59巻第1号 2012年1月 特別養護老人ホームにおける
池崎 澄江(イケザキ スミエ) 池上 直己(イケガミ ナオキ) |
目的 特別養護老人ホーム(以下,特養)における死亡について推移を把握し,特養内死亡の関連要因を明らかにする。
方法 最初に,人口動態統計と介護サービス施設・事業所調査を用い,1999年から2009年までの特養における死亡数と定員に占める割合を算出した。次に,2009年10月に無作為に抽出した全国653カ所の特養に郵送およびFAXにて調査票を配布した。内容は,施設概要,終末期ケアに関する方針,医師・看護師等の職員体制,および2008年10月から2009年9月までの1年間における退所者の内訳を尋ねた。最後に,特養における看取りに関連する要因をみるために,100床当たりに換算した特養内死亡数を算出し,ノンパラメトリック検定を行った。なお,終末期ケアに関する方針は,2002年の医療経済研究機構の調査項目と同じものを用い,同調査と比較した。
結果 1999~2009年までの間で特養における死亡数は1.7万人から3.6万に約2.2倍増加していた。この間の定員は29万人から42万へ約1.5倍増で,定員に占める死亡割合は5.8%から8.5%へ約1.5倍増であり,両者の増加が同程度に寄与していた。看取り介護加算が創設された2006年以後の定員に占める死亡割合は,より高い増加傾向を示した。2009年の郵送調査の回答数は,郵送・FAXあわせて371施設(回答割合56.8%)であった。特養内死亡が多い施設は,施設内で看取る方針を持ち,嘱託医に在宅療養支援診療所の医師がおり,終末期ケアの希望の確認を文書で行っていた。終末期ケアの施設方針を2002年の医療経済研究機構の調査と比較すると,「速やかに病院等へ移す」方針の施設が58.5%から35.6%に減少し,「施設内で看取る」方針の施設が20.7%から29.9%に増加していた。
結論 特養における死亡は看取り介護加算創設後により高い増加傾向にあり,国による看取り介護の推進は一定の効果を発揮していた。今後,さらに多くの特養が看取り介護の方針を持てるよう支援すること,および在宅療養支援診療所との連携を強化することで,特養内死亡が増加する可能性が示唆された。
キーワード 特別養護老人ホーム,看取り介護加算,在宅療養支援診療所,特養内死亡,人口動態統計
|
第59巻第1号 2012年1月 医療計画における基準病床数の算定式と
小松 俊平(コマツ シュンペイ) 渡邉 政則(ワタナベ マサノリ) 亀田 信介(カメダ シンスケ) |
目的 医療計画における基準病床数の算定式と,都道府県別将来推計人口を用いて,都道府県別に入院需要の推移を予測し,さらに,これと供給を対比することで,高齢社会における医療提供体制の確保に関する議論の基礎となるデータを提供する。
方法 医療計画における基準病床数の算定式を,都道府県別に入院需要の推移を予測し,その傾向を比較するという目的にかなうよう改変し,参考基準一般病床数,参考基準療養病床数を定義した。これらと,最新の既知の値である2009年の医療・介護サービスの供給量の実績値を対比するため,一般病床需給比率,療養病床需給比率を定義した。
結果 全国の参考基準一般病床数は,2030年まで増加して減少に転じた。全国の参考基準一般病床数は,2010年と比較して2030年には86,723床増加したが,このうち41,984床,率にして48%が,埼玉・千葉・東京・神奈川における増加分だった。全国の参考基準療養病床数は,2035年まで増加し続けた。全国の参考基準療養病床数は,2010年と比較して2030年には847,822床増加したが,このうち288,059床,率にして34%が,埼玉・千葉・東京・神奈川における増加分だった。一般病床需給比率は,2030年までに埼玉・千葉・神奈川・愛知のみで100を上回った。療養病床需給比率は,2030年までにすべての都道府県で100を大幅に上回った。埼玉・千葉・東京・神奈川では,2030年には療養病床需給比率が250を超えた。
考察 人口構造の高齢化により,首都圏を中心とした都市部で,医療・介護需要が爆発的に増加すること,このまま供給を増やさなければ,首都圏を中心として,必要な医療・介護を受けられない者が大量に出現することが示唆された。首都圏での壊滅的な供給不足を防ぐためには,あらゆる方策を駆使する必要があると考えられた。
キーワード 入院需要,高齢化,医療提供体制,医療計画,基準病床数,将来推計人口
|
第59巻第1号 2012年1月 心理社会的要因は,仕事に支障をきたす慢性腰痛への
松平 浩(マツダイラ コウ) 磯村 達也(イソムラ タツヤ) 犬塚 恭子(イヌヅカ キョウコ) |
目的 西欧では,腰痛の慢性化への移行には心理社会的要因が強く関与するとのエビデンスがある。本研究の目的は,わが国の勤労者における仕事に支障をきたす慢性腰痛への移行に関わる危険因子を,前向き研究により探索することである。
方法 腰痛およびそれに関連しうる多要因(多くの個人的要因,人間工学的要因,心理社会的要因等)を網羅した自己記入式調査票を首都圏多業種16事業所の勤労者6,140人に依頼した。ベースラインでは5,310人から,翌1年の腰痛状況等を追跡調査では3,811人から回答を得た(追跡率72%)。そのうちベースライン調査時から過去1年において腰痛はあったものの仕事に支障はなかった1,675人を抽出し,翌1年に仕事に支障をきたす非特異的腰痛が3カ月以上あったこと(従属変数)の危険因子をベースラインデータの変数から探索した。
結果 ベースライン調査時から翌1年の間,非特異的腰痛で3カ月以上仕事に支障をきたした人が2.6%(43人)発生した。ロジスティック回帰分析(性・年齢を含む多変量解析)の結果,重量物取り扱いに従事していること,働きがいが低いこと,ストレスによって起こりうる身体愁訴が多いこと(身体化傾向が強いこと),そして,家族に生活や仕事に支障をきたした腰痛の既往があることが,有意な因子であった。
結論 わが国の産業現場でも,仕事に支障をきたす慢性腰痛への移行には,腰への身体的な負荷要因のみならず心理社会的要因が強く影響することが示唆された。よって非特異的腰痛の難治・慢性化の予防と治療には,腰へかかる負担に関わる問題と心理社会的な問題へのアプローチを車の両輪とした包括的な対策が必要であると思われた。
キーワード 腰痛,慢性非特異的腰痛,危険因子,心理社会的要因,勤労者
|
第59巻第2号 2012年2月 在日コリアンの人口高齢化と死亡の動向-死亡・死因統計に関する日本人との比較分析-李 錦純(リ クンスン) 李 節子(リ セツコ) 中村 安秀(ナカムラ ヤスヒデ) |
目的 旧植民地時代に日本に渡航した在日コリアンは,長期在住により高齢化し,65歳以上の高齢者人口は10万人を超えた。日本社会の高齢化と同時期に高齢化した在日コリアンの健康水準を把握することは,顕在化している保健医療福祉問題を明確化する上で重要である。本研究は,在日コリアンの高齢化の推移と人口学的特徴を明らかにするとともに,健康水準を評価する指標として,死亡・死因統計について,日本人との比較分析により検討した。
方法 厚生労働省の人口動態統計(1955~2008年)および法務省の在留外国人統計(1959~2009年)を用いて,高齢者人口の推移と死亡数,死亡率,主要死因別死亡数,日本人を基準人口とした標準化死亡比を算出し,その推移を観察した。
結果 在日コリアンの高齢化率は2009年には17.8%,後期高齢者数は一貫して女性が多かった。死亡率は,日本人より低値で経過しているが,日本の社会情勢や高齢化に同調して,類似したパターンで推移していた。総死亡数に占める65歳以上の死亡数の割合は,1955年の10.5%から2005年には総死亡数4,660人に対し3,332人と,71.5%を占めるようになった。標準化死亡比(SMR)において有意に高い値を示したのは,男性の全年齢では「悪性新生物」「脳血管疾患」「不慮の事故」「自殺」,65歳以上では「悪性新生物」「自殺」であり,「自殺」は2.60と顕著であった。女性の全年齢では「心疾患」が一貫して高かったが,65歳以上において2009年には有意差は認められず,日本人と同水準を示すに至った。
結論 近年における在日コリアン人口の著しい高齢化が認められた。人口高齢化を反映し,高齢者人口の死亡数の経年的増加が認められ,今後も在日コリアン高齢者の保健医療ニーズは高まるものと推察される。SMRにおいても性差が表れており,女性高齢者は日本人と類似した傾向だが,男性高齢者は,悪性新生物と自殺において日本人以上に高値を示した。男性高齢者における悪性新生物の部位別死亡率の検討や社会環境要因の明確化とともに,日本人に対する自殺対策だけでなく,在日コリアンをも含めた自殺の原因究明など,実態に即した自殺防止対策を早急に推進していくことが求められる。
キーワード 在日コリアン,高齢者,死亡率,死因統計,標準化死亡比
|
第59巻第2号 2012年2月 名古屋市における共食・孤食と食生活に関する調査平光 良充(ヒラミツ ヨシミチ) |
目的 名古屋市における孤食の実態を把握するとともに,家族との食事形態と食に関する知識や食生活との関係を明らかにすることを目的に調査を行った。
方法 名古屋市に居住する16歳以上の男女のうち,無作為に抽出された3,000人に調査票を配布した。回答が得られた人のうち,同居する家族がいる1,514人を対象に分析を行った。家族と一緒に食事をする機会が週3日以上の人を「共食群」,週2日以下の人を「孤食群」として分析を行った。
結果 回答者の内訳は,共食群88.0%,孤食群12.0%であった。孤食群の割合は,性別にみた場合は男性で,また年齢階級別にみた場合は20~29歳で多かった。性,年齢階級を調整したオッズ比を算出したところ,孤食群は共食群と比較して食に関する知識に乏しく,好ましい食生活を送っていなかった。孤食群が好ましい食生活を送らない理由は,忙しいからが最も多かった。
結論 孤食群に対しては,共食を勧めるとともに,食に関する正しい知識を提供し,多忙な生活スタイルの中であっても正しい食生活を実践できるように保健指導を行う工夫が必要であると考えられた。
キーワード 共食,孤食,食生活,BMI,食育
|
第59巻第2号 2012年2月 30歳未満女性の子宮頸がんに対する意識と
梅澤 敬(ウメザワ タカシ) 星山 佳治(ホシヤマ ヨシハル) 落合 和徳(オチアイ カズノリ) |
目的 わが国における子宮頸がんのハイリスク者は20~30歳代であるが,30歳未満女性を対象とした,子宮頸がんに関連する実態調査や子宮頸がん検診の受診要因の分析研究は乏しい。本研究は30歳未満女性を対象に疫学調査を実施し,子宮頸がんに関連する認知状況と子宮頸がん検診の受診要因について明らかにすることを目的とした。
方法 対象は承諾が得られた都内の保健医療系女子学生である。方法は無記名自記式質問紙法による「子宮頸がんに関する意識調査」で,調査期間は2010年5~8月である。分析は30歳未満の18~19歳と20~29歳の2群間比較,および子宮頸がん検診受診歴の有無と各要因との関連を分析した(χ2検定,有意水準5%)。
結果 調査用紙は対象者全員の596人に配布し,485通回収できた(回収率81.4%)。解析対象者の平均年齢は20.4歳で,18~19歳は246人(53.1%),20~29歳は217人(46.8%)であった。本研究対象の子宮頸がん検診受診率は5.0%(18~19歳:1.6%,20~29歳:8.8%),受診理由の1位は検診無料クーポン券利用が35.3%であった。HPV-DNA検査を受けたことがあると回答したのは全体の1.9%であった。子宮頸がんに関連する認知状況は,子宮頸がんの病気を知っているのは35.1%,罹患率は20~30歳代に最も多いことを知っているのは51.8%,子宮頸がんの原因はHPVであることを知っているのは47.7%,検診の受け方を知っているのは12.3%,受診要件(20歳から2年に1回)を知っているのは20.7%,細胞診スクリーニング検査を知っているのは13.2%であった。子宮頸がんに関連する2群間比較の分析の結果,未成年者は20~29歳の検診対象群に比べ低い認知状況であった(p<0.001)。30歳未満の子宮頸がん検診受診者の特性は,婦人科の既往歴(不正性器出血,月経困難,腹痛,性感染症)があり,子宮頸がん検診の受診方法,受診要件,細胞診スクリーニング検査,の検診内容について知っている人であった(p<0.001)。
結論 子宮頸がんのハイリスク者である30歳未満での子宮頸がん検診の受診率向上には,検診に関連する詳細な情報提供が寄与する。
キーワード 子宮頸がん検診,HPV,母性保護,細胞診スクリーニング検査
|
第59巻第2号 2012年2月 推奨運動量レベルの運動習慣と入院外医療費との関連-藤沢市における検討-齋藤 義信(サイトウ ヨシノブ) 小熊 祐子(オグマ ユウコ) 鈴木 清美(スズキ キヨミ)相馬 純子(ソウマ ジュンコ) 田中 あゆみ(タナカ アユミ) 吉田 幸平(ヨシダ コウヘイ) 小堀 悦孝(コボリ ヨシタカ) |
目的 本研究は藤沢市国民健康保険被保険者を対象とした国保ヘルスアップモデル事業で得られたデータを用い,「健康づくりのための運動基準2006」で示された日本における推奨運動量(週4METs・時)レベルの運動習慣の継続・増加・減少という変化と医療費との関連について検討することを目的とした。
方法 対象は藤沢市国民健康保険被保険者1,343名(年齢63.3±5.1歳:Mean±SD)であった。医療費の分析は2002年度と2004年度の年間入院外医療費を用いた。運動習慣は質問紙により,1週間に1回30分以上の運動やスポーツを行う頻度について,事業開始時(2002年)と2年後(2004年)の追跡調査により評価した。その結果から,「運動習慣が週2回未満のまま推奨値を満たさなかった群(非推奨群)」,「週2回以上の推奨値から週2回未満に減少した群(減少群)」,「週2回未満から週2回以上に増加した群(増加群)」および「週2回以上継続し,推奨値を満たした群(推奨群)」の4群に分類した。運動習慣の変化と医療費との関連の検討には,始めに事業開始年度における医療費の群間比較を行った。その後,事業開始年度と事業最終年度の医療費の差(変化)の群間比較を多重比較検定にて行った。また重回帰分析を用いて,医療費の変化に関連する要因の検討を行った。
結果 事業開始年度の医療費は,運動習慣4群間で差はみられなかった。事業開始年度と事業最終年度の医療費の差の比較では,非推奨群と推奨群との間に有意差が認められた。事業開始年度と事業最終年度の医療費の差の平均値は,非推奨群では13,700円の増加,減少群では16,416円の増加,増加群では6,710円の増加,推奨群は94円の減少であった。重回帰分析を用いて医療費の変化に関連する要因を検討した結果,運動習慣において非推奨群に対し推奨群であることで有意に入院外医療費の増加が少なかった。一方,事業開始時の主観的健康感が低い,年齢が高い,糖尿病を治療中であることが増加に関連する要因であった。
結論 運動習慣は入院外医療費の増加に関連する要因であると考えられ,推奨運動量レベル以上の運動を継続することにより,入院外医療費の増加を抑制する傾向が示唆された。
キーワード 推奨運動量,運動習慣,生活習慣病,入院外医療費
|
第59巻第2号 2012年2月 小学高学年の生活実態および意識と将来への期待について尾木 まり(オギ マリ) 柏女 霊峰(カシワメ レイホウ) 斉藤 進(サイトウ ススム)八重樫 牧子(ヤエガシ マキコ) 三輪 律江(ミワ ノリエ) |
目的 小学高学年児童の生活実態並びに意識を把握することにより,家庭生活,学校生活,交友関係,将来の職業意識などを把握し,この時期の児童の生活に保障すべき生活環境について検討するための基礎資料を得ることを目的とした。また,「21世紀出生児縦断調査」における児童本人への調査手法等の検討に資することを目的とした。
方法 全国5都市12小学校の小学5・6年生の親子2,685組を対象に,平成22年9~10月に質問紙調査を実施した(小学校で配布・回収)。回収された2,140件(回収率79.7%)のうち,有効回答2,110件(有効回答率98.6%)について,都市別,学年別,性別等により分析した。また,親子に対して共通に尋ねた質問への回答の一致度を検証した。
結果 地域別には祖父母との同居,居住形態,保護者の働き方や帰宅時間に違いがみられた。学校生活では,9割の子どもが友だちと会うことを楽しみとし,昼休みも放課後も友だちと過ごすが,その過ごし方には男女差がみられた。また,放課後過ごす場所は,首都圏都市では他の都市よりも「習い事」「公園」をあげる割合が高かった。「保護者の子どもとの接し方」を尋ねた結果では,子どもの方が保護者よりも「とてもそう思う」と感じる割合が高く,保護者の接し方を肯定的にとらえていた。自分自身への意識では,自己肯定感や幸福感を含み,全体的に肯定的なとらえ方がされており,中でも「とてもそう思う」の割合は「自分には夢中になれるものがある」(74%),「自分には将来の夢がある」(67%),「自分にはなりたい職業がある」(60%)で高かった。保護者の回答と子どもの回答の一致度は客観的事実である時間でさえも一致度は低く,子どもの意識については約4割方の一致度しかみられなかった。
結論 都市部や郡部で生活の実態に違いがみられるものの,多くの小学高学年生はその生活の中で幸せを感じ,比較的高い自己肯定感を抱きつつ生活していると考えられた。また,親が思っているよりも子どもは,親に対してよい関係を抱いており,子どもは子どもで様々な生活環境の影響を受けながらもたくましく生きているという実態が浮かび上がってきた。親子調査の手法を検討するために,親子に対していくつかの共通の設問をし,その回答を比較したところ,一致度は決して高くなく,小学高学年の保護者を通じて,子どもの生活実態や意識を把握することが適切ではないことが明らかとなった。
キーワード 小学高学年,生活実態,自己肯定感,幸福感,職業意識,親子調査
|
第59巻第3号 2012年3月 福島市の戸建住宅における
田中 正敏(タナカ マサトシ) |
目的 準寒冷地域である東北地方の住宅,居住環境と健康状態との関係を明らかにすることを目的とした。
方法 準寒冷地域で盆地にあり,夏は高温多湿,冬は盆地特有の底冷えのする気象の福島市の戸建住宅を対象として居住環境,人々の健康状態などに関するアンケート調査を行った。
結果 有効回答数は428通(47%)であった。家の構造については,木造・木質系が82%であった。1~2人の家族構成である場合が25%であり,家族数が少ないなかで,部屋数が5部屋以上である場合が多くを占めていた。住居内の状況については,「結露が発生している」が51%,結露の発生場所は「窓のみ」が91%と多かった。カビについては,「発生している」が45%で,発生場所として,「風呂場のみ」が74%と最も多かった。室内の換気方法は,窓の開閉による場合が多く,「全室に換気装置がある」は31%であった。換気装置の使用状況については,「部屋の使用時は常時使用」が40%と最も多く,「ほとんど使用しない」が15%にみられた。「家族のなかで頭痛など何らかの症状,湿疹やアレルギーなどのある人」が「いる」場合は,80戸(18.7%)の住居であった。症状のなかで多かった項目は,「鼻づまり」などの鼻の症状,湿疹,「皮膚がかゆい」などであった。アレルギー性疾患では,アレルギー性鼻炎の罹患が最も多かった。室内環境要因と健康状態との関係で有意であったのは,「タオルの乾きにくさ(風呂場)」「結露の発生」「カビの発生」などで,湿気に関係する項目が多かった。
結論 寒冷地である東北地方の建物は,本州にみられる一般的な住宅の場合と同様に,窓などの開口部はサッシにより気密性は高いが,壁や屋根などで断熱性の低い住宅が多く,室内の換気が等閑にされると空気汚染が生じやすい。福島市のような盆地で多湿の気候条件は,室内の結露,ダニや真菌のなどの微生物の増殖を招きやすく,室内環境においてアルデヒド類,揮発性有機化合物などの化学的要因とともに生物学的要因に注意が必要である。
キーワード 気密居住環境,換気,シックハウス,アレルギー性疾患,アンケート調査
|
第59巻第3号 2012年3月 定時制高校生における大麻など違法薬物に関する意識調査磯村 毅(イソムラ タケシ) |
目的 違法薬物乱用防止のためには,青年期の若者における違法薬物への意識や違法薬物との接点について理解することが大切である。大麻はタバコと同様に煙の吸引により使用するため,喫煙の常習化からの進展しやすさが想定できる。そこで若年者における喫煙経験と大麻との関連について検討した。
方法 愛知県内の定時制高校の生徒90名に,喫煙行動および大麻など違法薬物に関する意識調査を実施し,40歳以上の4名と喫煙行動が無回答の15名を除いた71名を対象として解析した。
結果 喫煙行動別に人数,平均年齢は,現喫煙群(11名,18.1歳),前喫煙群(8名,17.1歳),試し喫煙群(10名,17.6歳),非喫煙群(42名,17.4歳)であった。「周囲に大麻などを所持または使用した人がいる」と回答した人は,試し喫煙群+非喫煙群の52名中1名(2%)に比べ,現喫煙群+前喫煙群では回答者17名中6名(35%)と多かった(p<0.001)。大麻などを手に入れるのは,「簡単だと思う」または,「何とか手に入ると思う」と回答した人は,試し喫煙群+非喫煙群で52名中25名(48%)に対し,現喫煙群+前喫煙群では18名中16名(89%)に達した(p<0.01)。大麻の有害性の認識は,「大麻には中毒になる危険がないと思う」と答えた生徒は69名中22名(32%),「大麻には犯罪に巻き込まれる危険がないと思う」と答えた生徒は70名中24名(34%)であった。これらの回答は,非喫煙群において順に42名中18名(43%),19名(45%)であり,いずれも現喫煙群+前喫煙群+試し喫煙群と比較して有意に高かった(p<0.05)。これらの回答は,非喫煙群で大麻などを「入手不可能」と回答した24名では順に15名(63%),16名(67%)で,「入手可能」と回答した非喫煙群に比べ多かった(p<0.01)。
結論 喫煙が違法薬物のゲートウェイとなっている可能性が示唆された。また,有害性の認識が非喫煙群の大麻などを「入手不可能」と回答した生徒において低かったことから,非喫煙のごく一般の若者において,大麻などに対する警戒感が緩んでいることが危惧された。
キーワード 喫煙,大麻,違法薬物,ゲートウェイドラッグ,定時制高校
|
第59巻第3号 2012年3月 国民健康保険加入の特定健康診査未受診者の
渡辺 美鈴(ワタナベ ミスズ) 臼田 寛(ウスダ カン) 谷本 芳美(タニモト ヨシミ) |
目的 特定健康診査の実施率の向上を目的に,年齢別にみた未受診者の特徴を明らかにし,その対応を検討する。
方法 対象者は40~74歳の国民健康保険加入者で平成21年度の特定健康診査未受診者を層化無作為抽出した2,000人である。方法は,平成22年6月1日~30日の間に,郵送法によるアンケート調査を実施した。回収数は1,212(回収割合;60.6%)であった。性,年齢,職業を回答した1,182人を解析対象者とした。未受診に関連する項目を年齢別に分析した。
結果 対象者の63.1%は無職であった。65.3%はかかりつけ医がおり,45.9%は2週間に1回以上通院していた。未受診理由は,「忘れていた」「健康である・メタボでない」「通院中」「市からの情報不足」「受ける時間・暇がなかった」と続いていた。40歳代,50歳代,60歳代は「忘れていた」,70歳代は「通院中」が多かった。
結論 本調査結果から,対象者には「かかりつけ医がある」や「通院中」が多いことが明らかになった。受診率の向上には,かかりつけ医に受診勧奨や個別健診の実施を依頼することが必要である。年齢別では40歳代,50歳代,60歳代の「忘れていた」の理由に対して,忘れることがないよう複数の手段を用いて受診勧奨を促す。70歳以上では「通院中」を重視し,個別健診の受診を働きかけることが受診率向上につながると思われる。
キーワード 特定健康診査,国民健康保険,受診率,未受診理由
|
第59巻第3号 2012年3月 介護保険サービスの必要量利用の可否が
上田 照子(ウエダ テルコ) 三宅 眞里(ミヤケ マリ) 荒井 由美子(アライ ユミコ) |
目的 介護保険サービスを介護者が必要と思われる量を利用できているか否かと,介護者の介護負担や介護疲労との関連について検討する。
方法 高齢者の主介護家族を対象とし,質問紙法を用い無記名で行った。質問紙の内容は,高齢者の属性,介護サービスの利用状況,介護者の属性,介護負担,身体的・精神的疲労,健康状態,経済事情等である。質問紙の配布は,介護支援専門員が利用者宅への訪問時に配布し,回収は郵送にて行った。276人の回答を得た(回収割合70.6%)。回答の不備等の10ケースを除外し,266人の調査票を分析した。調査時期は2009年3~5月である。
結果 介護保険サービスが「必要と思われる量を利用できている」と回答した者は61.3%,「できていない」者が30.8%であった。できていない理由の内訳は,「自己負担金が高くつくから」が40.2%,「高齢者が嫌がるから」が50.0%,「役に立たない」が4.9%などであった。介護者の経済事情として,「介護の費用が高齢者の収入で賄えるかどうか」「一部自己負担金の経済的負担」「経済状況」について,サービスが必要量利用できているか否かとの関連を検討した結果,各々において有意な関連がみられ,介護者の経済的事情がサービスの必要量利用の可否に影響を与えている可能性が示唆された。サービス必要量利用の可否と介護状況,介護負担,健康状態等の項目との関連を検討した結果,介護時間,介護による拘束時間,Zarit介護負担感得点,困りごとの数,身体疲労,精神疲労,健康状態において,サービス必要量利用の可否との間に有意な関連が認められた。また,これらについてサービスが必要量利用できていない理由別に検討した結果,理由が「自己負担金がかさむ」群では,Zarit介護負担感得点,困りごとの数,身体疲労,精神疲労において有意な関連を示した。
結論 介護保険サービスは,介護家族の経済事情によって利用が制限されていることが認められた。また,サービスが必要量利用できていない場合には,介護者の介護負担や介護疲労の増大を招いている可能性が示唆され,これらを予防するためにはサービス利用のための経済的な支援が必要と考えられた。
キーワード 介護保険サービス,介護サービスの必要量利用の可否,一部自己負担金,介護負担,介護疲労
|
第59巻第3号 2012年3月 高齢者における短縮版Generativity尺度の作成と
田渕 恵(タブチ メグミ) 中川 威(ナカガワ タケシ) 権藤 恭之(ゴンドウ ヤスユキ) |
目的 中年期の発達課題であるGenerativityを高齢者において測定するため,McAdamsらが開発した「Loyola Generativity Scale(LGS)」の日本語訳を用いたGenrativity尺度およびその短縮版を作成し,妥当性および信頼性について検討することを目的とした。
方法 調査1では近畿圏内の生涯学習団体に所属する高齢者556名を,調査2では兵庫県但馬圏域に住む中高年者798名を分析対象とした。LGSを翻訳した20項目の確認的因子分析結果より,5つの因子から1項目ずつ選択した5項目からなる短縮版を作成した。
結果 20項目版と短縮版の相関は0.85であり,また両者共に年齢,Generativity行動,感情的Well-being,人生満足度との有意な関連性が認められた。信頼性係数の推定値としてのα係数は,調査1では0.66,調査2では0.68であった。
結論 本研究で作成された短縮版Generativity尺度は,LGSの概念構造となる5側面を含み,かつ信頼性・妥当性の示された尺度であることが確認された。
キーワード Generativity,高齢者,Loyola Generativity Scale,信頼性,妥当性,短縮版
|
第59巻第4号 2012年4月 第13回OECDヘルスアカウント専門家会合の報告-A System of Health Accounts 2011 EDITION-満武 巨裕(ミツタケ ナオヒロ) |
OECD(経済協力開発機構),EUROSTAT(欧州委員会統計局)そしてWHO(World Health Organization)が共同で4年間にわたって行ってきたSHA(A System of Health Accounts)の改訂作業が2011年6月に終了し,10月にSHA2011としてOECDから公表された1)。
本誌において,著者はOECDヘルスアカウント専門家会合およびSHAの改訂作業について報告してきた2)-4)。今回は,2011年に開催された第13回OECDヘルスアカウント専門家会議について報告する。また,SHA2011は,公表直前にOECD事務局側の独自修正によって,以前本誌で紹介した内容と異なる部分が存在する。そこで,この修正部分についても併せて報告する。
Ⅰ は じ め に
2000年に発表されたヘルスアカウントの推計手法であるSHA1.0を改訂する作業は,当初の計画から約1年遅れて完成した。公表の直前にOECD事務局側が内容の一部に変更を加えた部分もあったが,2011年10月に正式名称SHA 2011として公表された(改訂作業中は,SHA 2.0と呼ばれていた)。
ヘルスケア支出の国際比較が可能となるSHAマニュアルが改訂されたことの意義およびその影響力は大きい。SHAは,国際比較する際のグローバルスタンダード(国際標準)になっており,今後はOECD加盟国のみならず発展途上国も含めた多くの国で,SHA2011に準拠した推計方法が開発されていくことになるからである。また,日本は,これまで諸外国と比べて比較的少ない医療費で,質の高い医療を提供しているといわれてきた。例えば,SHA1.0での総医療保健支出は42.9兆円(2008年度),対GDP比8.5%でありOECD加盟国34のうち20位となるため,「日本は比較的少ない」,との根拠になっている。しかし,SHA2011に伴って推計値にも変化が生じると,この順位が変わる可能性もある。
Ⅱ 第13回ヘルスアカウント専門家会合の議題
会合では,毎年,OECD事務局の各担当者から各議題について説明を行い,ヘルスアカウント専門家とOECD事務局の検討を経て,今後の方針が決められていく。
第13回会合は,SHA2011が3カ月前に完成していたこともあり,議題が例年よりも少なく(第12回会合の議題数15に対して,議題数9),開催期間も1日のみであった(第12回会合は2日間)(表1)。
|
第59巻第4号 2012年4月 OECDヘルスデータ担当者会合(2011)の報告中山 佳保里(ナカヤマ カオリ) |
Ⅰ は じ め に
OECD(経済協力開発機構)では,34の加盟国から保健医療および保健医療制度に関するデータを収集し,ウェブ上のデータベース「OECDヘルスデータ」として,毎年公表している。データベースの改善のため,加盟国(保健担当省,統計担当機関等)や関係機関(WHO,Eurostat等)が出席するOECDヘルスデータ担当者会合(以下,会合)が,年1回開催されており,データ範囲の拡大や比較可能性の向上について議論している。本稿では,近年の会合における議論の動向を含め2011年10月3,4日に開催された会合(於パリ,参加者数約95名)の議論について報告する。
Ⅱ OECDヘルスデータを巡る近年の動向
はじめに,議論の背景として,ヘルスデータに関する近年の大きな動きを把握しておきたい。第1に,節目となる2010年10月のOECD保健大臣会合(約5年に1回開催)では,コミュニケにおいて「データの違いを説明する要因をより注意深く検証すること等により,データ・情報の比較可能性を高めるべきである」とされた1)。これにより,今年の会合でも,各国から提出された数値を並べるだけでなく,それがどのようなデータであるかの検討に力が入れられ,その分析を受けてデータ区分の改善が進められている。第2に,ヘルスデータ2010から,WHO欧州地域事務局およびEurostatとの合同質問票によるデータ収集が医療支出以外の指標に拡大されたことも,大きな動きの1つである。主に事務局間の調整により,欧州域内の国際比較指標との整理が進められ,新規指標が増えるとともに,既存の指標の定義や区分も見直されている。第3に,これは個々の指標に影響を与えるものではないが,OECDヘルスデータ2011から,公表のプラットフォーム(基盤)が,有料の個別データベースから,OECDの総合統計データベース(保健分野に限らない)であるOECD.Statへ移行することとなった。データベースの70%がID・パスワード不要の無料で提供されるため,データ利用の増大が期待されている2)。
Ⅲ 指標開発に係る議論
OECDヘルスデータに含まれる指標一覧は,ウェブ上で参照可能である2)3)。そのうち,最近の会合の検討対象となった主な指標については表1を参照いただきたい。慢性疾患の増加や医師不足など加盟国における政策課題を反映したものや合同質問票の導入に係る指標が取り上げられ,比較可能性向上のために区分を細分する傾向が見受けられる。以下では,2011年の会合において議論された3点について紹介する4)。
(1) 医療従事者(医師・看護師)の概念に関する議論
現在,医療従事者については,①臨床,②専門活動中,③登録(Practicing, Professionally active, Licensed)の3つの概念についてデータ収集されている。一般的に国際比較で用いられるのは,患者に直接医療サービスを提供する①臨床数であるが,研究者や行政機関で働く者を含む②,あるいは③のみしか提出できない国もある。こうしたデータギャップを埋めるため,今回の担当者会合では,②に関する新たなデータソースとして,労働力調査(Labour Force Survey)の活用について検討された。アイルランド,オランダ,Eurostatにおいて,それぞれ既存の従事者調査あるいは単発で実施した調査と労働力調査をベースとした推計値の比較が行われた。その結果,アイルランドにおいては比較的良い結果が得られたものの,オランダ,Eurostatでは,残念ながら両者の差が非常に大きく,さらには,労働力調査は住民を対象としており,国境を越えた労働力を把握できないとの問題点も指摘され,労働力調査は医療従事者数のデータソースとしては,他にソースがない場合の最後の手段(last resort)とすべきであるとの結論になった。
(2) 医師の種類に関する議論
医師の種類は,従来のデータ収集では,「一般診療」「専門医」「その他」(General practice, Specialist, Others)の3区分に分かれ,専門医については,小児科医,産婦人科医,精神科医等に細分されていた。しかしOECD事務局が2010年に収集されたデータを分析した結果,インターンやレジデントの扱い(訓練中として「その他」と判断する国と実際に診療に携わるため「一般診療」または「専門」とする国),また,専門医ではない医師を「一般診療」「その他」のどちらに振り分けるかにより,データに大きな影響が出ていることが判明した。そのため,OECDヘルスデータ2012からは,一般診療を「家庭医・GP(General Practitioner)」と「その他の一般(インターン等を含む)」に分け,さらに専門の種類にも「その他の専門」の区分を設けることとなった。なお,この論点は,他にも難しい課題が多く,会合でも例えば,GPは専門の一種とすべきであるという見解や口腔科の医師については,歯科医(Dentist)という医師とは別の指標とされているが,医師の専門の1つとすべきであるとの見解等が示されたが,こうした点についてOECDは,国際標準職業分類(ISCO-08)に従っており,現在の分類を維持するとしている。
(3) 手術分類別の手術数に関する議論
手術数については,1人の患者について一連の手術が行われた際,どのように数えるかが1つの論点となる。昨年の議論により,2重計上を避けるためすべての手術・処置ではなく,また過小評価を避けるため主な手術のみの数ではなく,1人の患者の1つの手術分類につき1つのコードまたは患者数(準全数(“Quasi-all”procedures))について報告することとなった。今年はその結果が示され,スペインやイタリアなど報告態様を変更したいくつかの国については,手術数が大幅に減少する例もあったことが紹介された。また,昨年のデータ収集では試験的に日帰り手術の実施場所について,「病院」と「病院以外」の別を設けたところ,病院以外の医療センター等で多くの手術が実施されている国もあることが判明した。一方で病院における手術数しか報告できない国もあり,ひとまずこの区分を維持することが決定された。
Ⅳ データと政策分析プロジェクト
OECDでは,先進国からデータ・情報を入手できる強みを活かし,政策分析のプロジェクトも実施しており,会合でもそうした取り組みの一端が紹介された。現在は,医療サービスの利用のおける格差,メンタルヘルス,介護の質に関する作業等が進んでおり,介護については,2011年5月に増大する需要に対する介護労働力と介護財政に着目した報告書11)が刊行され,今後は,そのフォローアップとして,介護の質に焦点を当てた分析を進めるとのことであった。
Ⅴ お わ り に
OECDヘルスデータは,先進国の保健医療に関する最も包括的なデータソースであり,こうしたOECDによる政策分析での利用に止まらず,各国の政策立案や国際比較研究の基礎資料として頻繁に参照されている。しかし,こうした比較的信頼性が高いといわれるデータベースでも,上述のように,各国が必ずしも同じ中味のデータを提出できているとは限らず,単にデータを並べて,順位を付けるだけでは,現状を正しく理解できないこともある。国際比較データは怪しいという認識を有している人は多いと思うが,実際にデータの中味に踏み込んで検証するのは,かなり手間のかかる作業であり,国際機関でこうした地道な作業が実施されることは歓迎できる。会合でも,山積する課題のほんの一部とはいえ,データの違いによる影響が明確に示され,改めて国際比較データを利用するにあたっての注意喚起となるとともに,有用なデータベースの構築へ向けた重要な取り組みがなされているといえる。
文 献
1)OECD保健大臣会合コミュニケ(http://www.oecd.org/dataoecd/4/55/46163626.pdf)
2)OECD.Stat(Health)(http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT)
3)OECDヘルスデータの指標一覧(和英対照表を含む)(http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_37407_2085193_1_1_1_37407,00.html)
4)OECDヘルスデータ担当者会合2011プレゼン資料(http://www.oecd.org/health/presentations)
5)山﨑亜弥.OECDヘルスデータ担当者会合(2010)の報告,厚生の指標2011;58(4):23-6.
6)山﨑亜弥.OECDヘルスデータ担当者会合(2009)の報告,厚生の指標2010;57(3):1-4.
7)山﨑亜弥.OECDヘルスデータ担当者会合の報告,厚生の指標2009;56(4):1-4.
8)OECD保健医療関係ワーキングペーパー一覧(http://www.oecd.org/els/health/workingpapers)
9)鐘ヶ江洋子訳,OECD編著図表でみる世界の保健医療 OECDインディケータ(2009年版)2010.
10)OECD,“Health at a Glance 2011”,2011.
11)OECD,“Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care”,2011.
|
第59巻第4号 2012年4月 都市部在住高齢者における社会活動参加者の特性-介護予防の推進に向けた基礎資料-佐藤 むつみ(サトウ ムツミ) 大渕 修一(オオブチ シュウイチ) 河合 恒(カワイ ヒサシ)新井 武志(アライ タケシ) 小島 成実(コジマ ナルミ) |
目的 本研究では,高齢者の社会活動参加者に対して介護予防を推進するための基礎資料を得ることを目的として,都市部在住高齢者における社会活動参加者の活動の種類別特性を検討した。
方法 東京都A区において,65歳以上の高齢者の約10%にあたる3,500名を,性,居住地区別に層化のうえ無作為に抽出し,社会活動参加の状況,基本属性,介護予防に関する知識,健康に対する意識,心身の健康状態などについて,調査用紙を郵送して回答を求めた。有効回答票1,886件(53.9%)のうち,要支援・要介護者を除く1,485件(有効回答票の78.7%)を分析対象とした。社会活動参加の状況は,①町内会,自治会,②老人会,老人クラブ,③趣味・スポーツ・学習サークル,自主グループなどの参加の有無を尋ねた。①と②を地域社会活動,③を個人社会活動とし,それぞれの参加群と不参加群の特性をクロス集計にて検討した。さらに,参加の有無を従属変数,クロス集計にて統計学的に有意な関連が認められた項目を独立変数とした多重ロジスティック解析を行い,オッズ比を検討した。
結果 地域社会活動参加群は99名,個人社会活動参加群は459名であった。地域社会活動参加群は不参加群と比較して,男性,高卒以下,高齢者のみ世帯ではない,地域包括支援センターを知っているなどの割合が高かった。個人社会活動参加群では,女性,専門・短大・大卒以上,高齢者のみ世帯,暮らし向きがふつう・余裕がある,介護予防を知っている,二次予防事業対象非該当,体の衰えを予防できる自信がある,主観的健康感が健康,移動能力が高い,外出頻度が高い,孤立感がないなどの割合が高かった。多重ロジスティック解析の結果,地域社会活動の参加と独立した関連が認められた要因は,男性,高卒以下,高齢者のみ世帯ではない,地域包括支援センターを知っている,の4項目であった。一方,個人社会活動の参加では,女性,専門学校・短大・大卒以上,高齢者のみ世帯,暮らし向きがふつう・余裕がある,主観的健康感が健康,移動能力が高い,外出頻度が高い,の7項目であった。
結論 地域社会活動と個人社会活動では参加者の特性が全く違うことがわかった。介護予防の推進のためには,社会活動の種類に応じた介入方法を検討していく必要があることが示唆された。
キーワード 地域住民調査,社会活動,介護予防,地域高齢者,都市部
|
第59巻第4号 2012年4月 訪問看護の潜在ニーズを含めたニーズの推計田口 敦子(タグチ アツコ) 永田 智子(ナガタ サトコ) 成瀬 昂(ナルセ タカシ)桒原 雄樹(クワハラ ユウキ) 福田 敬(フクダ タカシ) 山田 雅子(ヤマダ マサコ) 吉池 由美子(ヨシイケ ユミコ) 八巻 心太郎(ヤマキ シンタロウ) 中尾 杏子(ナカオ キョウコ) 田上 豊(タガミ ユタカ) 村嶋 幸代(ムラシマ サチヨ) |
目的 本研究では,訪問看護を必要とする患者数・要介護者数の潜在ニーズまで含めた推計を行い,その活用可能性を提示することを目的とした。
方法 ニーズ推計では,今後各自治体が自身で定期的に推計できるようになることに留意し,いずれの都道府県や自治体でも入手しやすい既存の統計データを用いるように努めた。既存の統計から得られないデータについては,質問紙調査から得た。顕在ニーズと潜在ニーズのいずれも,介護保険と医療保険を分けて推計し,その後合算した。可能な限り2008年の統計データを用いたが,2008年のデータがないものについては推計値や直近のデータを用いた。
結果 調査票を発送した施設・事業所3,740カ所のうち,1,241カ所から回答があった(回収率33.2%)。施設・事業所から得た利用者データの回収数は43,018人で,有効回答数は42,636人であった。2008年の全訪問看護利用者数,すなわち,顕在ニーズは317.9千人(内訳:介護保険256.5千人,医療保険61.4千人)であった。潜在ニーズの小計は262.2千人(内訳:居宅および介護施設で213.0千人,医療療養病床および一般病床で36.6千人,精神病床で12.6千人)であった。2008年度における顕在ニーズと潜在ニーズを合算した訪問看護ニーズの総数は580.1千人であった。
結論 潜在ニーズを含めた訪問看護ニーズは,現在の顕在ニーズの1.8倍であることが明らかとなった。今回開発した方式および調査結果として算出した数値割合は,各都道府県や自治体にある既存統計を活用することによって訪問看護ニーズが算出可能なこと,人口や要介護度の増減を調整できるため,地域の実情に応じてシミュレーションが可能であることから,有用性が高い。都道府県や自治体が医療計画や介護保険事業計画等の立案時に,潜在ニーズも含めた訪問看護ニーズを把握し,供給体制を整備していく上で役立つことが期待される。
キーワード 訪問看護,推計,顕在ニーズ,潜在ニーズ,利用者数
|
第59巻第4号 2012年4月 国民健康・栄養調査の協力率とその関連要因西 信雄(ニシ ノブオ) 中出 麻紀子(ナカデ マキコ) 猿倉 薫子(サルクラ ノブコ)野末 みほ(ノズエ ミホ) 坪田 恵(ツボタ メグミ) 三好 美紀(ミヨシ ミキ) 卓 興鋼(タク キョウコウ) 由田 克士(ヨシタ カツシ) 吉池 信男(ヨシイケ ノブオ) |
目的 国民健康・栄養調査のデータは健康日本21の最終評価等に活用され,健康増進施策の推進,評価のために貴重な資料となっている。本研究は,国民健康・栄養調査の調査地区が国民生活基礎調査の調査地区から抽出されることを利用して,世帯および個人単位で国民健康・栄養調査の協力率とそれに関連する要因を検討することにより,統計学的な代表性を評価することを目的とした。
方法 平成15年から19年の国民健康・栄養調査の調査地区について,国民生活基礎調査と国民健康・栄養調査のレコードリンケージを行った。世帯単位の協力率については,世帯単位でレコードリンケージを行い,国民健康・栄養調査の協力率および協力率に関連する要因を検討した。個人単位の協力率については,国民生活基礎調査に協力した世帯の20歳以上の世帯員を対象に個人単位でレコードリンケージを行い,国民健康・栄養調査の協力率を身体状況調査およびその一部の血液検査と,栄養摂取状況調査,生活習慣調査の各々について検討した。
結果 世帯単位の協力率は平成15年から19年の平均で66.4%であり,世帯人員が1人の世帯,特に男性の単独世帯で低かった。個人単位の協力率は身体状況調査が53.2%,血液検査が34.4%,栄養摂取状況調査が61.3%,生活習慣調査が63.1%であり,身体状況調査,特に血液検査で低かった。性別にみると,いずれの調査も男性より女性の協力率が高く,特に身体状況調査と血液検査で男女の差が大きかった。年齢階級別にみると,いずれの調査も20歳代が最も低く,男性では60歳代と70歳以上が,女性では60歳代が高かった。配偶者の有無別にみると,男女のいずれの年齢階級でも配偶者なし(未婚・死別・離別)の者に比べて配偶者ありの者の協力率が高かった。
結論 世帯や個人の特性により国民健康・栄養調査の協力率に差がみられたことは,統計学的な代表性が損なわれてきている可能性を示唆している。また,調査の種類によっても協力率に大きな差がみられた。今後,国民健康・栄養調査の協力率を向上させるためには,調査の種類ごとに対象者の特性に応じた方法を検討する必要があると考えられる。
キーワード 国民健康・栄養調査,国民生活基礎調査,レコードリンケージ,協力率,単独世帯,配偶者の有無
|
第59巻第4号 2012年4月 日本における「自殺希少地域」の地勢に関する考察-1973年~2002年の全国市区町村自殺統計より標準化死亡比を用いて-岡 檀(オカ マユミ) 藤田 利治(フジタ トシハル) 山内 慶太(ヤマウチ ケイタ) |
目的 本研究の目的は,「自殺希少地域」の地理的特性を把握し,それら特性の自殺率に与える影響を考察することにある。
方法 1973年~2002年の全国3,318市区町村自殺統計のデータから標準化死亡比を算出し,本分析における自殺率の指標,「自殺SMR」とした。さらに自殺SMRの信頼区間を求め,その結果から自殺率が有意に低い市区町村-「自殺希少地域」を分類した。地理的変数については既存のデータと,既存のデータを加工したものを併用した。ヒストグラムを描いて全国市区町村の自殺SMRの分布を確認し,記述統計量によって「自殺希少地域」とその他地域の地勢の傾向を概観した。クロス集計およびχ2検定を行い,「自殺希少地域」の地理的特徴を確認した。また,相関分析,重回帰分析重み付け最小2乗法を行って,地勢が自殺SMRに与える正負の影響とその強さを確認した。追加的分析として,全国市区町村から自殺SMRの下位1%を抽出し,それら市区町村の地勢の傾向を確認した。
結果 「自殺希少地域」は山間部よりも海岸部の低地に属し,可住地人口密度の高い市区町村に多いという傾向が示された。海岸部属性を有する市区町村のうち,「自殺希少地域」は他の地域に比較して,島属性および単一島属性を有する市区町村が多かった。また,「自殺希少地域」の市区町村が面する海域は,他の地域に比較して太平洋と瀬戸内海に多かった。
結論 「自殺希少地域」の地勢は,自殺危険因子のひとつである医療や社会福祉サービスへのアクセシビリティや,コミュニティにおける社会的支援の質とも関係がある可能性が示唆された。人が自殺へと至る機序は複雑であり,地勢との関係からのみ論じるには限界があるが,本分析結果は自殺対策を検討する際の参考資料となりうるであろう。
キーワード 自殺希少地域,地勢,コミュニティ,標準化死亡比,全国市区町村
|
第59巻第5号 2012年5月 わが国におけるスズメバチ等による死亡の疫学西 基(ニシ モトイ) |
目的 スズメバチ等に刺されたことによる死亡の状況について,人口動態統計の資料を使用して,都道府県別の標準化死亡比(SMR)などの指標を算出し,気温との関連も検討する。
方法 人口動態統計の資料で,ICD10コードX23(スズメバチ,ジガバチ及びミツバチとの接触)による,2000年から2009年までの,都道府県別・男女別の死亡数および全国における5歳階級別・男女別の死亡数を求めた。国勢調査の資料で,2000年および2005年の都道府県別・男女別・5歳階級別の人口を求めた。これらの資料から,各年の全国における死亡数,各年齢階級における死亡数,各県・各地方におけるSMRを算出した。気温との関係を検討するため,気象庁がホームページで提供している主要都市の月平均気温の資料を使用した。
結果 2000年から2009年までの死亡数は男性が178例,女性が40例であった。男性では25歳未満の,女性では45歳未満の死亡は,それぞれみられず,大部分が50歳以上であった。男女合計で,最多が福島県で12例,次が岩手県で11例であった。東北各県のSMRは宮城県を除いて200~400前後,東北地方としては237.4で,突出して高かった。東京都の死亡数は0で,関東地方のSMRは44.4と低かった。月別の気温との関係をみたところ,夏の気温と当該年における死亡数との間には関係は認められず,春先の平均気温との間に負の相関がみられた。
結論 関東地方のSMRが低く,東北地方が高かったのは,山野に出かける頻度の相違や,ショックに対応できる救急医療施設の密度・アクセスのしやすさなども関係すると考えられた。死亡例に若年者が全くみられなかったのは,刺された累積回数が少ないとアナフィラキシーに至りにくいことが1つの理由と推測された。「夏の気温が高いと,スズメバチの活動が活発になり,刺される例が増える」という通説を裏付けることはできなかった。春先の気温との負の相関については,今後生態学的に検証する価値があると考えられた。
キーワード スズメバチ,標準化死亡比,都道府県,地方
|
第59巻第5号 2012年5月 高校生の喫煙実態調査について-10年前の調査結果との比較-光井 朱美(ミツイ アケミ) 金辻 治美(カナツジ ハルミ) 大槻 眞美子(オオツキ マミコ)西田 秀樹(ニシダ ヒデキ) 繁田 正子(シゲタ マサコ) 青木 篤子(アオキ アツコ) |
目的 喫煙による健康被害は,喫煙開始年齢が低いほど大きくなるため,未成年者の喫煙防止対策は重要な課題であり,平成12年度に実施した調査を元に,10年を経過した現在の未成年の喫煙実態を把握することで,これまで取り組んできた未成年者に対する喫煙防止対策の検証と,さらなる対策の推進を図る基礎資料とすることを目的とした。
方法 管内にある3つの高等学校の生徒を対象に自記式無記名のアンケート調査を実施し,合計2,464人(回答率92.4%)から回答を得た。調査内容は,平成12年度の調査内容を基本とし,22年度は一部変更し,分析については平成12年度の調査結果と比較検討した。
結果 平成22年度調査は10年前と比較して,高校生全体の非喫煙者が,51.2%から81.9%に増加し,喫煙者が著しく減少した。
結論 喫煙者の著しい減少には,社会的な関心の高まりや公共施設等の禁煙化だけでなく,学校教育を中心とした未成年者喫煙防止対策等も影響している1つとして考えられた。
キーワード アンケート調査,高校生,防煙教育,未成年の喫煙実態
|
第59巻第5号 2012年5月 家族構成の変動と家族関係が子ども虐待へ与える影響-母親の家族内における立場に注目して-中澤 香織(ナカザワ カオリ) |
目的 子どもの虐待は,経済的困窮をはじめ親や子どもの障害や疾病,家族の関係など様々な困難が複合的に重なり合う問題であり,介入と防止の取り組みには家族の状況と背景にある社会を捉える視点が必要である。本研究は,家族構成の変動と家族構成員間の関係が子ども虐待へ与える影響を考察するため,家族類型による虐待の様相を捉えることを目的とする。
方法 調査は平成15年度に北海道内すべての児童相談所において受理された虐待相談件数のうち,5歳,10歳,14・15歳の129例を対象とし,各児童相談所を訪問した研究班メンバーが児童票から必要事項を転記するという方法で行い,個人情報保護が可能な形に整理できた119例を分析した。
結果 家族類型による虐待種別・虐待者の違いに家族の関係が表れていた。ステップファミリーでは継父による身体的虐待(45.8%)と性的虐待(20.8%)が多かった。実父母家族では実父による身体的虐待(21.2%)と実母によるネグレクト(33.3%)が多かった。母子家族では実母によるネグレクト(59.2%)が多かった。家族類型ごとの虐待の特徴には,母親の家族内における立場の違い,継父母と継子の関係形成の困難さ,夫婦関係における不均衡な力関係などの影響がみられた。
結論 虐待など家族内で生起する問題に関して家族の機能の低下が指摘されるが,家族構成員相互の関係に注目する必要がある。虐待がそれぞれの家族にある不均衡な力関係の下に起きていることを捉えていくことが介入と支援に不可欠である。
キーワード 子ども虐待,家族構成員の力関係,母親,社会経済的問題
|
第59巻第5号 2012年5月 高齢者のボランティア活動および
岡本 秀明(オカモト ヒデアキ) |
目的 元気な高齢者には,地域において支える側としての活躍や地域の絆の再生に寄与してもらうことが期待されている。本研究では,高齢者のボランティア活動と友人・近隣援助活動それぞれに関連する要因を明らかにすることを目的とした。ボランティア活動の関連要因の検討については,2006年に報告した大阪調査の追試を兼ねた。
方法 千葉県市川市の高齢者(65~84歳)1,400人を無作為抽出し,自記式調査票を用いた郵送調査を実施した。有効回答数755人のうち,主要項目に欠損値のない711人を分析対象とした。分析は,ボランティア活動,友人・近隣援助活動それぞれを従属変数とした2項ロジスティック回帰分析を行った。独立変数は,「家族・経済・他」「健康」「暮らし方の志向性」「技術や経験」「社会・環境的状況」の5領域を構成する計17変数,統制変数は,年齢と性別とした。
結果 ボランティア活動をしている高齢者は,IADLの得点が高い(p<0.05),地域に貢献する活動をしたい(p<0.001),中年期にボランティア経験がある(p<0.001),親しい友人や仲間の数が多い(p<0.05),ボランティア活動情報の認知の程度が高い(p<0.001)という特性であった。友人・近隣援助活動をしている高齢者は,地域に貢献する活動をしたい(p<0.01),若い世代と交流したい(p<0.01),親しい友人や仲間の数が多い(p<0.05)という特性を有していた。
結論 都市部における高齢者のボランティア活動の促進要因として重要なものは,本研究と大阪調査の結果で一致して示された,健康の良好さ,地域に貢献する活動をしたい志向性がある,中年期のボランティア経験がある,親しい友人や仲間の数が多い,ボランティア活動情報の認知の程度が高いことであることが明らかになった。地域に貢献する活動をしたい志向性がある,親しい友人や仲間の数が多いことは,友人・近隣援助活動の促進要因でもあった。元気な高齢者が,貢献活動により地域で支える側として活躍が活発になるには,示されたこれらの促進要因をより効果的に支える取り組みをしていくことが求められる。
キーワード 高齢者,ボランティア活動,貢献活動,社会活動,プロダクティブ・エイジング
|
第59巻第5号 2012年5月 高校福祉科進学動機と介護・援助に関する意識調査佐藤 大輔(サトウ ダイスケ) |
目的 介護福祉士養成を行う高校福祉科の生徒と,対照群として総合高校の生徒の高校入学以前における介護経験や環境を比較し,介護や援助に対する意識の違いを検討し,高校福祉科の生徒が,高校から介護の道を志した関連要因を明らかにする。
方法 高校福祉科(福祉科群,n=136)と総合高校(対照群,n=260)において,2008年12月~2009年2月に質問紙調査を行った(有効回答割合:福祉科群,97.1%:対照群,95.0%)。質問紙の項目は,基本属性として,学年,性別,同居している家族構成のほか,高校入学以前の介護福祉施設訪問経験と介護実施経験,家族や親族内の医療・介護従事者の有無を尋ねた。さらに,介護のやりがいについては4件法で,既存の援助規範意識尺度は5件法で回答を求めた。福祉科群と対照群の比較は,基本属性をχ2検定,介護のやりがいの得点と援助規範意識尺度得点の比較をt検定とU検定を用いて行い,有意水準を5%とした。
結果 福祉科群では,対照群と比較して,祖父(20.5%),または祖母(34.1%)と同居している者が有意に多く,高校入学以前の介護福祉施設訪問経験がある者(70.5%)が有意に多かった。また,福祉科群では家族や親族に医療・介護従事者のいる者(50.8%)が有意に多かった。介護のやりがいを尋ねた質問の平均得点では,福祉科群(3.62±0.60,n=130)が,対照群(3.26±0.76,n=232)よりも有意に高かった。また,属性別に群間比較を行った結果,男女では違いがみられた。援助規範意識の両群間の平均得点の比較では,自己犠牲規範意識において,福祉科群(3.53±0.49,n=122)が,対照群(3.31±0.48,n=240)よりも有意に高く,弱者救済規範意識でも,福祉科群(3.58±0.42,n=127)が,対照群(3.45±0.47,n=239)よりも有意に高かった。
結論 高校福祉科生徒の特徴から,環境を整えれば若者の介護に対する意識が高まる可能性がある。また,高校福祉科の女子においては,高校入学以前の経験や環境にかかわらず,自己犠牲規範意識が高い傾向があり,介護福祉関連職への適性の高さがうかがえた。
キーワード 高校福祉科,介護のやりがい,援助規範意識
|
第59巻第5号 2012年5月 介護分野におけるインシデント・アクシデント・
柿沼 倫弘(カキヌマ トモヒロ) 関田 康慶(セキタ ヤスヨシ) 柿沼 利弘(カキヌマ トシヒロ) |
目的 介護分野の安全管理の基本情報となるインシデント・アクシデントの定義の現状を明らかにするとともに,インシデント・アクシデント・レベル概念を定義し,その妥当性を検証する。
方法 介護分野,医療分野の関連文献等のインシデント・アクシデントに関する定義やレベルを参考に,筆者らの議論に基づいたレベル概念を設計した。その妥当性を検証するために,北海道・東北地方の介護老人福祉施設906施設と介護老人保健施設537施設を対象にWEBアンケート調査(筆者らの研究グループが開発)を実施した。本調査では,筆者らが提示したインシデント・アクシデント・レベル概念の妥当性を検証した。施設長が想定しているレベルとの類似性を妥当性の指標とした。また,報告事例を用いたレベルと報告内容のあり方等について検証した。具体的な事例を3つ挙げ,レベル概念の設計指針充足度に応じてレベルの分類を求めた。事例1と事例2は,筆者らの作成したレベルの設計指針を満たし,事例3は十分に満たさないものとした。レベル分類比較では,両施設が同じ分類を行っているか否かについて5%の有意水準でχ2検定を試みた。
結果 WEBアンケート調査回収率は,11.2%(162施設)であった。インシデント・アクシデント・レベルを設定する施設のうち,約9割の施設が筆者らの提示したレベル概念と類似していることが判明した。レベル分類では,事例1で約8割,事例2で約9割とほぼ想定どおりの分類がみられたが,事例3では分類の判断が大幅に分かれた。施設間のレベル分類比較でのχ2検定の結果,経過観察が必要になった場合に介護老人福祉施設のほうが有意に介護老人保健施設より重症に捉える傾向がみられた。
結論 介護分野のインシデント・アクシデントの定義は数多くあるが,統一された定義のないことが判明した。筆者らの提示したレベル概念の定義は,多くの施設と類似していたので,受け入れられる可能性が高い。レベル概念の定義には,利用者の状態や経過事実等を含め,報告内容と対応していることが重要である。レベルの分類では,経過観察を行った場合のレベル分類に有意な差がみられたので,施設種別ごとにレベルの分類が異なる場合があることに注意する必要がある。しかし,インシデント・アクシデント・レベルは,報告内容を対応させることで全体的に高い分類力がみられるので,ある程度標準化できる可能性が示唆された。
キーワード インシデント・アクシデント・レベル,レベル分類,標準化,情報共有,予防
|
第59巻第6号 2012年6月 生活機能評価未受診である特定高齢者候補者の特徴と
南部 泰士(ナンブ ヒロヒト) 越後谷 綾子(エチゴヤ アヤコ) 柿崎 明子(カキザキ アキコ) |
目的 本研究は,医療機関で生活機能評価を行い,特定高齢者候補者とされた人の生活状態,介護予防に対する認識を明らかにし,二次予防事業,対象者把握事業における課題を考察することを目的とした。
方法 秋田県A市で,医療機関方式により,特定高齢者候補者とされた87人の,①基本チェックリスト,②家族・地域との関わりに関する項目(世帯構成,家族との関係,近所の人と関わる場所,外出時の移動手段),③介護予防に関する項目(介護について相談する人,介護について相談する公的機関,介護予防教室の認識,介護予防教室に参加したいと思わない理由),④健康のために行っていること,⑤かかりつけ医に関する項目(かかりつけ医の主たる診療科)について,面接で調査し,特定高齢者候補者の特徴を分析した。
結果 医療機関方式により特定高齢者候補者とされた人は,健診と同時に行われる生活機能評価の受診者に比べ,男女共に平均年齢が高かった。家族・地域との関わりに関する項目で,「近所の人との関わりがない」と回答した人は31.0%,介護予防に関する項目で,「介護予防教室が行われていることを知らない」と回答した人は64.4%,「介護予防教室に参加したいと思わない」と回答した人は81.6%であり,高い割合を占めていた。かかりつけ医を有している人は87.4%であった。
結論 特定高齢者候補者の介護予防に対する考え方は多様であった。特定高齢者候補者を早期に介護予防事業に促すためには,家族との関係性や生活背景等の社会的状態,身体の状態,趣味等を総合的に評価し,二次予防事業を提供する必要がある。地域の民生委員,地域支援病院や診療所等の医療機関,地域包括支援センターの関係職種がより連携を強め,特定高齢者を早期に,より多く発見できるような,地域ケアシステムの検討が急務であると考えられた。
キーワード 介護予防,二次予防事業,対象者把握事業,生活機能評価
|
第59巻第6号 2012年6月 全国の地域包括支援センターにおける
田原 美香(タハラ ミカ) 北川 慶子(キタガワ ケイコ) 外尾 一則(ホカオ カズノリ) |
目的 本報告は,地域包括支援センターに対する防災と災害時要援護者の支援に関する全国調査から,自然災害時の地域包括支援センターにおける災害時要援護者に対する支援機能の現状把握を目的とした。
方法 全国4,209地域包括支援センターに対し,被災と防災・減災に関する質問紙調査を実施し,1,338件の有効回答(回収率31.8%)を得た。調査票は郵送し,調査期間は2010年12月1日から2011年2月28日まで3カ月間の留め置き法とした。
結果 地域包括支援センター職員の防災意識は「やや低い(50.3%)」が最も多く,次いで「やや高い(26.5%)」となり「高い(6.2%)」が最も少なかった。被災経験のある地域包括支援センターが災害復旧時に行った対応は「被災者の避難先の確認(81.7%)」「被災者の体調把握(74.4%)」「被災者の自宅訪問(64.6%)」の順に多く,「ボランティア等への被災高齢者のニーズ情報提供(23.2%)」が最も少なかった。また,災害時要援護者への支援準備ができているのは,「職員の情報連絡体制の整備(87.5%)」「災害時の組織体制の確立(51.9%)」の順に多く,「災害時記録表の作成(11.0%)」「関係機関等の災害時連絡先名簿の作成(21.6%)」の順に少なかった。防災意識と災害時要援護者への支援準備との関連をみると,すべての項目で準備をしていると回答したセンターの方が防災意識の平均スコアが有意に高かった。
結論 地域包括支援センターの災害時支援は,被災高齢者への直接的支援が実施された割合が高く,地域包括支援センター内部の連絡体制も整備されていた。他方,地域の要介護高齢者情報の把握や消防,医療・保健・福祉等関連諸施設・機関との連携等,地域包括支援センターに最も期待し求められている被災者と支援をつなぐ差配(マネジメント)機関としての準備不足が明らかになった。背景には,地域包括支援センター職員の防災意識が低いという状況があり,防災意識の低さが被災者支援の準備不足の一因となっていることが示唆される。
キーワード 自然災害,地域包括支援センター,災害時要援護者,高齢者の避難支援機能
|
第59巻第6号 2012年6月 検疫所職員の職業性ストレスおよび
中村 奈緒美(ナカムラ ナオミ) 菅原 琢磨(スガハラ タクマ) 大山 卓昭(オオヤマ タカアキ) |
目的 国内外の社会状況や世界の感染症流行が年々大きく変化する中,検疫所業務はその変化への迅速な対応が求められる。また,業務には法律や医学など専門的な知識も必要であり,職員への負担はますます多様化していくと考えられる。本研究では検疫所職員が通常の職場生活で感じている職業性ストレスの要因や,そのストレスによって起こりうる精神的,身体的反応について調査し,検疫所職員の職業性ストレス対策を考察することを目的とした。
方法 わが国の全検疫所職員(約860人)を対象に自記式アンケートによる悉皆調査を行った。調査票1では「個人属性」「家族構成」「主に関わっている部門」「勤務年数」「現在所属する職場の環境」に関して質問した。調査票2では労働者のストレス測定のために労働省委託研究のストレス測定研究班により開発された「職業性ストレス簡易調査票」を用いた。これは,ストレスの原因となる因子やストレスによって起こる心身の反応,ストレスへの修飾要因などを評価することができる。調査結果の解析にはMann-Whitney U(MWU)検定,Kruskal Wallis(KW)検定,共分散構造分析(Multiple Indicator Multiple Cause Model:MIMICモデル)を用いた。
結果 回答率は約7割(608人)であり,回答者の属性や職場環境,勤務条件は大きく異なっていた。ストレス状態には「職場の対人関係」をはじめ,「仕事の量的負担」「仕事の質的負担」「仕事のコントロール度の低さ」「仕事の適性度の低さ」のいずれも有意に関連していた。また職場の上司,同僚,配偶者,家族,友人などからのサポートがストレス軽減に関連することが示唆された。
結論 検疫所職員においても職業性ストレスには職場の対人関係などが影響する一方で,職場のみならず家族や友人などのサポートがストレス軽減につながることが明らかになった。検疫所職員のストレス軽減の取り組みとして,職場内での良好な人間関係を構築することが重要であると考えられた。
キーワード 職業性ストレス,ストレッサー,ストレス反応,検疫所職員,職業性ストレス簡易調査票
|
第59巻第6号 2012年6月 日韓中における就学前児の父親の
朴 志先(パク ジソン) 小山 嘉紀(コヤマ ヨシノリ) 近藤 理恵(コンドウ リエ) |
目的 本研究は,Hillsonらのマルトリートメントの発生プロセスモデルに基づき,日韓中における就学前児の父親を対象に,育児関連Daily Hassles(DH)の経験頻度および育児ストレス強度とマルトリートメントとの関係を明らかにすることを目的とした。
方法 本研究の対象は,日本,韓国,中国の保育所を利用している世帯の父親とした(日本:K県の保育所2カ所500人,韓国:S市,C市,Y市内の保育所15カ所1,250人,中国:J省,Z省の保育所8カ所1,500人)。本研究では,「育児関連DHの経験頻度(潜在的ストレッサー)が,それらの経験に対する一次評価(ストレス強度)を介して,子どもに対するマルトリートメントの実施頻度に影響を与える」といった因果関係モデルを仮定し,構造方程式モデリングにより,前記モデルのデータへの適合性を検討した。
結果 因果関係モデルは3カ国いずれもデータに適合していた。具体的には,3カ国において「対応が求められる児の行動(頻度)」は「対応が求められる児の行動(強度)」を介して「心理的虐待」の実施頻度に影響しており,また「育児タスク(強度)」は,韓国では,「身体的虐待」に,中国では「ネグレクト」に有意な影響を与えていたが,日本ではマルトリートメントに有意な関連性がみられないという知見を得た。
結論 本研究では,Hillsonらが提起しているマルトリートメントの発生プロセスモデルが支持された。特に3カ国の共通点として,対応が求められる児の行動に対する否定的評価が心理的虐待を促進する傾向にあり,子どもの発達や行動特性に関する父親の無理解と適切な養育方法の情報欠如が関係していることが推察された。また,相違点として,父親が育児タスクについて否定的に評価した場合,韓国では対応が求められる児に対する身体的虐待を,中国ではネグレクトを促進する傾向にあったが,日本ではマルトリートメントの関連性は見いだせなかった。韓国の場合,家父長的家族制度による子どもの訓育のひとつとして暴力的な行動に表出され,さらに日本と韓国に比べ父親の育児参加頻度が高い中国では,育児から離れ,自身のネガティブな感情を軽減しようとしている結果ではないかと推察された。なお日本では,父親の育児参加への期待は高まっていても,長時間労働により子どもと積極的に関わる時間が減少し,ふたつの変数間の関連性がみられなかったのではないかと推察された。こうした知見を総合すると,子どもに対する父親のマルトリートメント防止に向けてより効果的な対策を開発していくには,マルトリートメントの発生の背景を考慮すべきものといえよう。
キーワード 父親,マルトリートメント,育児ストレス,東アジア
|
第59巻第6号 2012年6月 3歳児の睡眠時間がその後の肥満に与える影響の縦断的検討高橋 彩紗(タカハシ アヤサ) 鈴木 孝太(スズキ コウタ) 佐藤 美理(サトウ ミリ)山縣 然太朗(ヤマガタ ゼンタロウ) |
目的 近年,日本において肥満傾向児の割合は高く,そのリスクファクターとして食事や運動,睡眠時間などの生活習慣が注目されている。このうち睡眠時間に関しては,多くの先行研究において横断的に検討されているが,縦断的な研究は少ない。本研究では,幼児期の睡眠時間が学童期における肥満に与える影響を明らかにすることを目的とし,縦断データを用いて3歳時の睡眠時間が9~10歳時の肥満に与える影響を検討した。
方法 1991年4月1日から2000年3月31日までに山梨県甲州市(旧塩山市)で出生した児のうち3歳児健診時に肥満ではなく,その後,甲州市内の小学校において小学校4年生(9~10歳)のときに身体測定を受けた者を解析対象者とした。睡眠時間は,3歳児健診時に母親が記入した調査票における児の就寝時刻と起床時刻から算出した。肥満の指標には,3歳児健診および小学校4年生の身体測定データから算出したBody Mass Index(BMI)を用いて,成人の肥満(BMI≧25)に相当する国際的な小児肥満の基準によって判定した。3歳時の睡眠時間と9~10歳時の肥満との関係について,χ2検定および多重ロジスティックモデルによる多変量解析を行った。
結果 期間内に出生した児は2,083人であり,このうち肥満でなかった児は1,960人(94.1%)であった。その児のうち,9~10歳時の身体測定データが存在した児は1,541人(追跡率74.0%)であった。性別,3歳児健診時アンケート調査における食事回数,テレビ視聴時間で調整した結果,3歳時の睡眠時間が9時間の児に比べて,睡眠時間が11時間以上の児は肥満になるリスクが1.69倍(95%信頼区間1.13-2.54)と有意に高かった。一方,3歳時の睡眠時間が9時間未満の児は,肥満になりやすい傾向を認めた(オッズ比1.74(95%信頼区間0.87-3.46))。
結論 本研究では幼児期(3歳時)の睡眠がその後の肥満に及ぼす影響を縦断的に検討し,長い睡眠時間はその後の肥満のリスクとなることが示された。幼児期の睡眠習慣を含む生活習慣が,その後の肥満に対して与える影響に関しては,今後もさらなる検討が必要である。
キーワード 3歳児,9~10歳児,睡眠時間,肥満,過体重,コホート研究
|
第59巻第6号 2012年6月 小学校高学年児童の
朴峠 周子(ホウトウゲ シュウコ) 武田 文(タケダ フミ) 坂野 純子(サカノ ジュンコ) |
目的 精神健康の維持・増進にはストレス対処力(Sense of Coherence:SOC)が関与するが,精神健康問題が多発する小学校高学年期におけるSOCの動静については,これまでほとんど明らかにされていない。そこで本研究では,小学校高学年児童の個人レベルでのSOCについて,1年間の学期ごとの変動パターンを明らかにする。
方法 神奈川県内の近郊にある公立A小学校に通う4~6年生全児童403名を対象とし,属性,SOCに関する無記名自記式の調査票を用いて,1年間の縦断調査を実施した。各学期(全3回)の調査への回答が完全であった303名について,各学期のSOC得点を高群と低群に2群化し,1学期時点をベースラインとして,1・2・3学期の高低2群を掛けあわせた8つのSOCレベル変動パターンを作成した。そして,変動パターンと属性との関連を検討し,各変動パターンにおける学期ごとのSOC得点を比較した。
結果 8つのSOCレベル変動パターンに該当する児童数の内訳は,ベースライン高群4パターンについては,[高-高-高]群96名,[高-低-高]群22名,[高-高-低]群21名,[高-低-低]群23名,ベースライン低群4パターンについては,[低-高-高]群16名,[低-低-高]群18名,[低-高-低]群20名,[低-低-低]群87名であり,これらの変動と学年・性別との関連はみられなかった。各変動パターンのSOC得点は,[高-高-高]群では3学期が1学期よりも有意に高かったが(p<0.05),[低-低-低]群では学期間の有意差がなかった。その他6パターンではいずれも,高群に該当する学期が低群に該当する学期よりも有意に高かった(p<0.001)。
結論 小学校4~6年生児童303名の1・2・3学期におけるストレス対処力の変動について検討したところ,6割の児童はSOCレベルが1学期から3学期を通して安定していた。高レベルを維持している児童,低レベルを維持している児童が各3割あり,前者では1学期に比べて3学期のレベルがさらに上昇していた。残る4割の児童は2学期・3学期のどこかでSOCレベルが変動する6パターンのいずれかに該当し,その内訳はほぼ同割合であった。このようなストレス対処力の変動は,学年と性別にかかわらず小学校高学年児童全般に認められるものであった。
キーワード ストレス対処力(Sense of Coherence:SOC),児童用SOCスケール日本語版,小学校高学年児童,縦断調査
|
第59巻第7号 2012年7月 自殺率とインターネットにおける検索エンジン利用の関連-医療・社会・経済・家族関連語を利用した検討-末木 新(スエキ ハジメ) |
目的 わが国における自殺のリスク・ファクターに関する検索データ(医療・社会・経済・家族等含む)および自殺率を用いて,自殺率の先行指標として機能可能な検索語を明らかにする。
方法 自殺のリスク・ファクターに関する検索データは,Google Insights for Searchを利用して収集した。自殺率には,厚生労働省の人口動態統計を利用した。調査対象となった46の検索語の検索ボリュームについて,それぞれ自殺率との相互相関を算出し,時系列的関連を検討した。
結果 検索を先行させた場合(-3カ月<ラグ<-1カ月)においては,「酒」「失業」「社会福祉」「アレルギー」の4語が弱~中程度の正の相関を示しており(0.25<r<0.47),「うつ病」「ストレス」「不眠」「睡眠薬」「抗うつ薬」「精神科」「喘息」「頭痛」「結婚」「完全自殺マニュアル」の10語が弱~中程度の負の相関を示していた(-0.53<r<-0.25)。
結論 社会・経済関連語を中心に,いくつかの検索語の検索ボリュームが自殺率の先行指標となることが示唆された。しかし,算出された結果の中には,海外において実施された先行研究の知見と相反する関連を示しているもの,結果の解釈が難しいものも含まれていた。分析データの年数を長くしてより一般化可能性の高い結果を得ること,検索行動の文化普遍性と日本語における固有性に焦点を当てた検討が必要になると考えられた。
キーワード 自殺予防,インターネット,情報疫学,検索エンジン,相互相関
|
第59巻第7号 2012年7月 精神保健福祉業務担当の保健所保健師の
|
目的 精神保健福祉業務を担当する保健所保健師における,担当業務としての認識と,それらの業務に対する遂行能力の自己評価について基礎的なデータを得る。
方法 全国の都道府県立保健所とその支所418カ所の精神保健福祉業務を主に担当する保健師442人に無記名の自記式質問紙調査票を配布した。142人から回答があり(回収率32.1%),140人を分析対象とした。精神保健福祉10業務48項目に対する担当業務としての認識を「全くそう思わない」~「とてもそう思う」の4段階で,遂行能力の自己評価は「全くできない」~「できると思う」の4段階で調査し,精神保健福祉業務担当年数10年以下,11~20年,21年以上の3群に分類して集計した。
結果 担当業務として「とてもそう思う」の回答割合が高かった上位2項目は,10年以下の群では,問題が複雑で処遇困難なケースの相談と医師や社会福祉関係等の行政機関,医療機関等の関係機関との連携,11~20年の群では,問題が複雑で処遇困難なケースの相談と管内の精神保健福祉の実態把握,21年以上の群は,精神障害に対する正しい知識の普及と記録業務だった。「とてもそう思う」の回答割合が低かった下位2項目には,3群に共通してボランティア団体の組織育成があった。担当年数10年以下の群は,精神保健福祉10業務48項目のうち45項目で「できると思う」の回答割合が50%未満で,11~20年の群,21年以上の群に比べ遂行能力の自己評価が低い項目が多かった。問題が複雑で処遇困難なケースの相談は,11~20年の群と21年以上の群では,「できると思う」が50%以上あったが,10年以下の群は22.3%だった。
結論 保健師の担当業務としての認識は,個別事例の相談から管内の実態把握,普及活動や管理を含めた精神保健福祉活動へと拡大していくと考えられる。また,担当年数10年以下の群では,他の2群に比べ精神保健福祉業務に対する能力の自己評価が低く,業務を遂行する上で困難な者が多いと考えられ,専門的能力向上が重要である。
キーワード 保健所保健師,精神保健福祉業務,担当業務の認識,遂行能力の自己評価
|
第59巻第7号 2012年7月 個別化助言を自動化した
足達 淑子(アダチ ヨシコ) 田中 みのり(タナカ ミノリ) 石野 祐三子(イシノ ユミコ) |
目的 多数の指導者が大規模母集団に介入する特定保健指導においては,補助手段として標準化された行動変容ツールを活用すると効率的であると考えられる。その観点から,個別化助言を自動化した非対面行動変容プログラムによる保健指導の効果を検討した。
方法 某企業で特定保健指導の継続支援に該当した男性を健診時期により群別し,2008年5~10月受診者176名は個別化助言を提供するコンピュータシステム「健康達人Pro」を用いて指導したKTPP群とし,2008年1~4月受診者から年齢マッチングにより選んだ152名を対照群として,1年後の健診値を比較した。両群とも健診の1~2カ月後に健診結果,助言および一般情報を提供し,約5カ月後に個別面接を行った。その後,KTPP群は2回の測定会と6回の個別化助言を,対照群は通信指導と個別面接を各1回ずつ受けた。
結果 ベースライン時(2008年度)において,KTPP群と対照群の年齢,就労部門,支援レベル,喫煙状況の比率に有意差は認めず,健診値も総コレステロール値を除き有意差はなかった。KTPP群は健診から面接までに,1㎏体重が増加した。1年後,体重,BMI,中性脂肪,LDLコレステロールとALTの5項目で交互作用があり,KTPP群が対照群より大きく低下し,初期体重の3%および4%の減量達成率はKTPP群が高率傾向にあった。群内比較では,KTPP群で体重,BMI,ウエスト周囲長,TG,HDLコレステロール,LDL-C,TC,ALT,γGTPが有意に低下したが,対照群では変化を認めなかった。支援レベルは両群とも改善し,群間の有意差はなかった。
考察 体重と血中脂質,肝機能の改善においてKTPP群の優位性が示唆された。健診から面接までの結果から,健診値のフィードバックと一般情報提供のみの効果は乏しいと思われた。行動変容に必要な個別対応指導を効率よく実施するために,個別化助言を自動化したシステムを活用することは有望である。
キーワード 特定保健指導,個別化助言,情報技術,非対面プログラム,行動変容支援