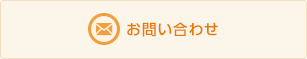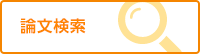論文記事
|
第52巻第11号 2005年10月 スクールソーシャルワーク実践モデルの構築に関する研究-「学級崩壊」を経験した保護者への仲介モデルの検証-大塚 美和子(オオツカ ミワコ) |
目的 「学級崩壊」を経験した保護者への援助実践モデル(仲介モデル)の構築とその検証を行い,スクールソーシャルワークの実践モデルの作成を試みた。
方法 先行研究や「学級崩壊」経験者に対するインタビュー調査の結果,また,それに基づく予調査の結果を参考に,学校と家庭の関係,両者の仲介役,「学級崩壊」に関する自己記入式質紙を作成し,京阪神地区在住の小中学生の保護者660 人を対象として郵送によるアンケート調査を実施した。有効回答数(率)は241(37%)で,今回は,そのうち「学級崩壊」経験者63人のデータを分析対 象とした。因子分析により抽出された「学校への危機意識」「教師への信頼度」「親の教育参加」「親の学校協力」「親の無力感」「仲介」の6因子を採用して 親と学校間の仲介モデル(仮説モデル)を構築し,共分散構造分析を用いてそのモデルの検証を行った。
結果 本モデル全体については,χ􌛌値は88.037(自由度82),適合度指標のCFIは0.986,RMSEAは0.034であり,仲介モデルとデータはほぼ適合しており,妥当性が確認された。モデル内の潜在変数間に有意な関連がみられたのは,「教師への信頼度」から「学校への危機意識」,「学校への危機意識」から「親の無力感」,「仲介」から「親の教育参加」であった。
結論 1)本モデルは当事者の視点とニーズを取り入れた実践モデルであることが検証された。2)本モデルは,親と学校の葛藤の解決方法として,仲介のタイミングとその役割を明示した。3)本モデルは,学校関係者や援助者に対して親の学校離れのプロセスを示唆した。
キーワード スクールソーシャルワーク,仲介モデル,学級崩壊,親の無力
|
第52巻第8号 2005年8月 家族介護者の介護に対する肯定的評価に関連する要因広瀬 美千代(ヒロセ ミチヨ) 岡田 進一(オカダ シンイチ) 白澤 政和(シラサワ マサカズ) |
目的 本研究の目的は,要介護高齢者を在宅で介護する家族が感じる介護に対する肯定的評価に関連する要因を,家族介護者が受けるサポートの頻度やサポートに対する満足度という視点から明らかにすることである。
方法 調査対象者は,大阪府内の介護家族の会連絡会や老人介護者家族の会会員440人であり,調査方法は,自記式質問紙を用いた郵送調査である。調査期間は2003年7月30日~8月31日であり,有効回収率は55.2%であった。研究目的を達成するための分析方法は,“介護充足感”や“肯定的感情”を従属変数とする重回帰分析である。“介護充足感”を従属変数とする重回帰モデルにおいては,「ホームヘルプサービス利用頻度」「訪問看護利用頻度」「家族会参加頻度」「家族会満足度」が独立変数として選択され,“肯定的感情”を従属変数とする重回帰モデルにおいては,「ホームヘルプサービス利用頻度」「訪問看護利用頻度」「ショートステイ利用頻度」「インフォーマルサポート満足度」が独立変数として選択された。なお,独立変数の選択は相関分析に基づいて行われた。
結果 ⑴“介護充足感”を従属変数とした重回帰分析においては,介護者年齢,訪問看護利用頻度,家族会満足度とに有意な正の関連がみられた。⑵“肯定的感情”を従属変数とした重回帰分析においては,インフォーマルサポート満足度のみに有意な正の関連がみられた。
結論 家族会に対する満足度が高く,また,訪問看護を利用する介護者ほど,介護に対する“介護充足感”が高くなる傾向があることが示された。また,家族や近隣などからのインフォーマルサポートに高い満足度を感じている介護者ほど,“肯定的感情”が高くなる傾向があることが示された。以上のことから,家族会から受ける満足度の高いサポートや看護師の訪問によるサポートは,家族介護者の介護に対する受容を表す“介護充足感”を高めるのに役立ち,家族や近隣などから得る介護者の満足度の高い情緒的および手段的サポートは,要介護高齢者に対する好意的な感情を表す“肯定的感情”を高めるのに有効であることが示唆された。
キーワード 家族介護者,介護に対する肯定的評価,要介護高齢者,家族会
|
第52巻第13号 2005年11月 埼玉県川口保健所管内における自殺死亡の現状山田 ひろみ(ヤマダ) 木野田 昌彦(キノダ マサヒコ) |
目的 川口保健所管内の自殺の現状を明らかにするとともに,2003年の自殺死亡の増加の要因を検討し,地域の自殺予防対策の基礎資料とする。
方法 人口動態統計を用い,自殺死亡数・死亡率の年次推移について回帰分析を行った。2001~2003年の3年次における埼玉県川口保健所管内(川口管内)の人口動態調査死亡小票のうち,死因が自殺による349人分について,年齢階級別死亡率,月別死亡数,手段別死亡数および配偶関係別死亡数について検討した。
結果 川口管内の2003年の自殺死亡数は過去最高の140人であり,男の死亡率は全国と埼玉県の値を上回っていた。1991年以降,川口管内,埼玉県および全国の自殺死亡数・死亡率は直線的増加傾向が認められ,回帰分析の結果,2013年には川口管内で180人以上,全国で44,000人以上の死亡数が予測された。年齢階級別死亡率の年次推移では,3年次とも55~64歳の年齢階級で最も高く,2003年では,35~44歳,45~54歳の年齢階級で前年の2倍に増加したことが認められた。2003年の月別死亡数では,2~6月で平均死亡数の1.6倍に増加し,手段別死亡数の割合ではガスが増加したことが認められた。ガスは,2001年,2002年には皆無であった練炭等によるものが6%,従来の排ガス等によるものが5%であった。
結論 長期的には自殺死亡の直線的増加傾向が認められた。2003年の急増については,月別死亡数,手段別死亡数の検討から,練炭等を使用した自殺の報道が手段の模倣にとどまらず自殺死亡を引き上げたのではないかと示唆された。地域の自殺の現状を把握し,自殺予防対策を推進する必要があろう。
キーワード 自殺,人口動態統計,手段別死亡数,練炭
|
第52巻第13号 2005年11月 2004/05年シーズンにおける
延原 弘章(ノブハラ ヒロアキ) 渡辺 由美(ワタナベ ユミ) 三浦 宜彦(ミウラ ヨシヒコ) |
目的 インフルエンザワクチンの計画的な供給に資することを目的として,2004/05年シーズンのインフルエンザワクチンの需要予測を行った。
方法 インフルエンザワクチン供給に実績のある医療機関など 5,158施設を対象として,2003/04年シーズンのインフルエンザワクチンの購入本数,使用本数,接種状況および2004/05年シーズンの接種見込人数について調査を行い,2004/05年シーズンのインフルエンザワクチン需要見込本数の推計を行った。
結果 2004/05年シーズンのインフルエンザワクチン需要は,約1817万本から約1898万本と推計された。
結論 2004/05年シーズンのワクチンメーカーの製造予定数は2061万本であり,需要に見合う量の供給が行われるものと推測された。
キーワード インフルエンザワクチン,需要予測
|
第52巻第13号 2005年11月 わが国における認知症患者数の推計
三浦 大(ミウラ ダイ) 旭 伸一(アサヒ シンイチ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) |
目的 現在,わが国は高齢化が急速に進んでおり,認知症の高齢者も増加している。認知症は入院や介護負担を要することが多く,重要な社会問題を引き起こす原因の1つとなっていることから,全国規模および都道府県別で認知症患者数を推計し,受診している入院および外来患者受診医療機関の特性を明らかにすることを目的とした。
方法 平成8年の患者調査と医療施設静態調査をデータ結合し,解析した。その際,認知症患者は主傷病名が認知症であるものに限定した。入院認知症患者数,外来認知症患者数をそれぞれ年齢階級別に推計し,入院または外来受診医療機関の病床数階級別に検討を加え,全国および都道府県間で比較した。また,受診医療機関の精神科を有する割合も検討した。
結果 全国の入院認知症患者数,外来認知症患者数はそれぞれ43.3千人,10.5千人であった。病院に入院している認知症患者のうち65.2%にあたる28.0千人が精神病床に入院していた。入院認知症患者の入院医療機関および外来認知症患者の外来受診医療機関は,年齢が高くなるほど病床数や精神科を有する割合が低くなる傾向にあった。各都道府県の入院,外来認知症患者数は,各都道府県の人口10万人当たりの精神病床数,精神科を有する施設数とそれぞれ相関関係がみられた。
結論 入院認知症患者,外来認知症患者の入院または外来受診施設は患者の年齢によって異なる傾向があり,患者が高齢なほど医療施設規模は小さくなり,精神科を有する割合も低下した。
キーワード 認知症,アルツハイマー病,血管性認知症,患者調査,医療施設静態調査,精神病床
|
第52巻第13号 2005年11月 地域保健行政活動の評価について糸数 公(イトカズ トオル) 福永 一郎(フクナガ イチロウ) |
目的 地域で行われている保健行政活動をその業務量を用いて分析し,保健衛生活動の指標の標準化を行い,市町村活動の強化と健康政策事業の拠点としての保健所機能強化に資する。
方法 平成13年度地域保健事業・老人保健事業報告に計上されている保健衛生活動の業務量を統計学的に分析した。母子保健,精神保健福祉,老人保健など保健衛生活動の領域別の業務量を,保健所においては設置主体別に,市町村においては保健所設置の有無,設置主体別,保健所非設置市町村については人口規模別に算出し,その特性や差異について分析を行い,さらに領域別の業務量について,その分野を代表しうる指標を用いて設置主体別,市町村別の比較を試みた。
結果 市町村業務量については,保健所を設置している指定都市,中核市,政令市,特別区で,企画調整機能と精神保健福祉や難病対策の業務量が高く,保健所を設置していない市町村では,人口規模が小さいほど業務量が高い結果であった。保健所業務量については,健診や保健指導などの一次的直接業務は,都道府県型を除く保健所で広く行われていた。都道府県型は,難病などの専門的直接業務は比較的優位で,企画調整的機能も業務量が高い結果であった。その他の設置主体では,一次的直接業務は高いが,企画調整的機能において実績の低いところも一部みられた。
結論 市町村規模別,保健所の有無別,各領域の事業や総業務量に関して,各々の活動の特性や自治体間の格差が明らかになった。
キーワード 地域保健・老人保健事業報告,業務量分析,保健衛生活動指標
|
第52巻第13号 2005年11月 ホームヘルパーの業務専門性とサービス評価に関する韓日比較張 允楨(チャン ユジョン) |
目的 ホームヘルプサービスに求められる専門的力量を業務専門性という概念でとらえ,業務専門性とサービス評価との関連を明らかにしたうえで,その結果について韓日比較を行い,業務専門性の重要性を実証的に検証することを目的とした。さらに,業務専門性に関連する要因の分析を行い,今後,ホームヘルプサービスの質の確保と向上を図るための条件を検討した。
方法 2003年7月から10月の間に,韓国210人,日本303人のホームヘルパーを対象とし,郵送法による自記式質問紙調査を行った。調査内容は,業務専門性の領域(知識・技術,利用者の情報把握),サービス評価の領域,その他の領域(対象者の基本属性,雇用・労働の実態,仕事上のトレーニング・業務管理)によって構成した。
結果 ①日本のホームヘルパーは韓国のホームヘルパーより知識・技術,利用者の情報把握,サービス評価においてより高いレベルにあった。②韓国日本両国において,知識・技術および利用者の情報把握とサービス評価には統計学的に有意な関連が認められた。③知識・技術に関して,韓国は個人レベルにかかわること(年齢,私的介護の経験)が,日本は制度的システムの中で行われていること(主な援助内容,資格,研修会の参加,援助内容の記録,マニュアルの確認)が関連する要因として見いだされた。また,利用者の情報把握には,両国とも仕事上のトレーニング・業務管理が統計学的に有意に関連していた。
結論 韓国と日本のホームヘルプサービスにおける制度的背景の違いは,両国におけるホームヘルパーの業務専門性とサービス評価の差をもたらした要因とみられた。また,業務専門性の向上には,研修会や事業所単位で行われる仕事上のトレーニング・業務管理が重要であることが示唆された。
キーワード ホームヘルパー,業務専門性,サービス評価,韓日比較
|
第52巻第15号 2005年12月 上手な老いかたと生活状況の関連谷垣 靜子(タニガキ シズコ) 黒沢 洋一(クロサワ ヨウイチ)細田 武伸(ホソダ タケノブ) 仁科 祐子(ニシノ ユウコ) |
目的 地域高齢者を対象に,上手に老いる(サクセスフル・エイジング)と生活状況との関連を明らかにすることである。
方法 鳥取県N町の60 歳以上の全住民3,021人を対象に記名自記式調査票により質問紙調査を実施した。調査内容は基本的属性,健康状態,生活に関する満足度,サクセスフルエ イジングを実感しているかどうか等である。サクセスフル・エイジングは「加齢とともに,上手に年をとったと思われますか」という問いに対して,4つの回答 肢から1つを選択させた。これを本研究での目的変数とした。説明変数は,既往歴,健康状態,健康のために心がけていること,食生活,生活の満足度,生活の はり,心の健康状態などである。サクセスフル・エイジングに関連する因子を明らかにする目的で,単変量解析で有意な変数すべてを説明変数にして強制投入す る多変量ロジスティック回帰分析を行った。
結果 有効回答数(率) は2,219人(73.5%)であった。男性886人,女性1,314人,不明19人を分析対象とした。平均年齢は72.6±6.7(中央値72.0)歳 であった。年齢階級は60~64歳が282人(12.7%),65~69歳が483人(21.8%),70~74歳が594人(26.8%),75~79 歳が482人(21.7%),80~84歳が257人(11.6%),85歳以上が121人(5.5%)であった。解析対象者2,219人のうち,上手に 年をとったと思われますかという質問に「非常にそう思う」と回答した者が67人(3.0%),「まあそう思う」と回答した者が1,291人 (58.2%),「あまりそう思わない」と回答した者が612人(27.6%),「思わない」と回答した者が159人(7.2%),無回答あるいは回答不 明が90人(4.1%)であった。以下の解析は回答が得られた2,219人から「上手に年をとったと思われますか」という質問に有効な回答が得られなかっ た90人を除いた2,129人で行った。多変量ロジスティック回帰分析の結果,サクセスフル・エイジングに関連した項目は,生活のはりがある,生活の満足 感,健康である,ひとりで楽しく生きていく自信がある,家族関係の満足感,運動・スポーツをする,非常に人から頼られている,これからもすばらしいことが ある,であった。
結論 健康感を持ちながら,生活のはりがあり,生活にも満足していることがサクセスフル・エイジングに有意に関連した。本研究では,60歳以上の全住民を対象としたが,入院・入所している人が除外されている可能性があり,研究結果をそのまま地域高齢者一般に当てはめるには限界がある。
キーワード サクセスフル・エイジング,生活状況
|
第52巻第15号 2005年12月 働き盛り世代における脳卒中発症の
巴山 玉蓮(トモヤマ ギョクレン) 藤田 幸司(フジタ コウジ) 五十嵐 久人(イガラシ ヒサト) |
目的 長野市における働き盛り世代の脳卒中発症の生活背景要因を明らかにする。
方法 脳卒中発症の対象年齢を働き盛り世代(40 歳以上65歳未満)とした。40~64歳で脳卒中を発症し,脳卒中情報システムおよび保健師が把握している現在74歳以下の者250人をケース(脳卒中発 症群)とし,現在40~64歳でこれまで脳卒中を発症していない長野市在住の約1,200人(対象人口の1%)をコントロール(健常群)としてケース・コ ントロール研究を行った。脳卒中発症群については,保健師が個別面接により本人から聴取し,健常群については郵送法によりアンケート調査を実施した。
結果 脳 卒中発症群と健常群との比較において有意な差がみられた因子について,独立した影響力を明らかにするために,多重ロジスティック回帰分析を行い,オッズ比 を算出した。脳卒中の発症に独立して寄与することが明らかとなったリスクファクターとそのオッズ比は,①高血圧である(12.6),② 喫煙している(8.8),③揚げ物・炒め物など油を使う料理をほぼ毎日食べている(8.3),④味付けの濃い物をほぼ毎日食べている(5.7),⑤自分の 判断で仕事の量や期限を調整できない状況にある(5.3),⑥卵・卵料理をほぼ毎日食べている(5.3),⑦年齢が高い(3.8),⑧近親者に脳卒中を発 症した人がいる(3.0)であった。地域的な特色と考えられた川魚,イナゴなどの食習慣については,脳卒中との関連が認められなかった。
結論 今 回の調査によって,働き盛り世代にある人の脳卒中の発症に独立して寄与する要因が明らかとなった。加齢や,近親者に脳卒中を発症した人がいるという遺伝的 要因は個人で制御できるものではないが,①高血圧を上手にコントロールすること,②喫煙をしないこと,③食生活では,揚げ物や油や卵料理をとりすぎないよ うにし,薄い味付けを心がけること,④生活面では,仕事の量や期限を調整しながら,過労やストレスを制御し,楽しく継続的に運動することは,個人・企業・ 地域レベルの取り組みや専門家の支援によって制御可能と考えられる。これらの科学的なエビデンスを児童生徒や学生を含めた市民に還元し,働き盛り世代にお ける脳卒中をこれまで以上に減少させ,その発症を遅らせることが大切であることが示唆された。
キーワード 脳卒中,働き盛り,ケース・コントロール研究,リスクファクター,多重ロジスティック分析
|
第52巻第15号 2005年12月 社会福祉士養成教育の専門性と現場実習の効果の分析-国家試験合否との関連から-清重 哲男(キヨシゲ テツオ) |
目的 社会福祉士一般養成課程について,入学時の属性,成績評価を要因とし,国家試験合否との関連性から養成教育の専門性と現場実習の水準を明らかにし,今後の養成教育の方向性を示すことを目的とした。
方法 研究対象は,平成13年,14年に入学した460人中,規定年限2年で修了し国家試験を受験した学生321人とした。国家試験合否を従属変数とし,学生の性別,年代,職業,履修20科目評価,現場実習評価を独立変数とする二項ロジスティック回帰分析を行った。
結果 20 科目評価と年代は,国家試験合否に強い有意の相関が認められ,大きな影響を及ぼすことが明らかとなった。また20科目評価と実習評価の間に見かけの正の有 意な関係が確認された。実習免除者は,実習履修者より20科目評価が低く,国家試験合格率も低かった。入学時の職業が直接福祉業務に関与しない福祉系以 外,無職・学生,およびその他福祉系の者は成績評価,国家試験合格率が優れていた。
結論 1年次,2年次の各科目を優秀な成績で履修することは,養成教育の基本であり最も重要なことである。実習免除者の実務経験が科目成績と国家試験の合格にマイナス要因となり,今後の養成教育の重要な課題となった。一方,30歳代の成績評価と合格率が最も低い理由は,今後の研究課題としたい。
キーワード 社会福祉士,社会福祉士養成,国家資格,現場実習,ソーシャルワーク
|
第52巻第15号 2005年12月 国民生活基礎調査における所得分布の精度について石井 太(イシイ フトシ) 古屋 裕文(フルヤ ヒロフミ) |
目的 国民生活基礎調査の実施により得られる所得分布に関する情報提供の充実に資する観点から,同調査の所得分布に関する精度について検討を行う。
方法 国民生活基礎調査における所得分布に関する誤差情報について,ブートストラップ法などを用い,所得分位値,所得階級別構成割合,ジニ係数の各標準誤差(率)に関する評価を行った。
結果 中央値の標準誤差率は大規模年では1.3%, 中間年では2.4%となっており,他の分位値とともに,概して平均値よりも誤差率が高かった。所得階級(100万円階級)別構成割合については,1%の幅 を許容すれば95%の確率で利用できるものと考えられた。ジニ係数の標準誤差は,平成16年調査では0.0027ポイント,平成15年調査では 0.0050ポイントであった。
結論 従来,評価が困難であった分位値などに関する精度の定量的評価がブートストラップ法を用いることにより可能となり,対前年比較や結果の信頼性など,所得分布に関する各種指標や統計表の見方に関する豊富な情報を提供することができる。
キーワード 所得分布,分位値,標準誤差,ブートストラップ法,ジニ係数
|
第52巻第15号 2005年12月 介護保険施設における介護報酬改定に対する
藤林 慶子(フジバヤシ ケイコ) 小山 秀夫(コヤマ ヒデオ) |
目的 介護保険施設における平成15年4月の介護報酬改定への意見や経営意識などを分析し,介護報酬改定後の施設の状況と経営意識に関する今後の課題を明らかにすることを目的とした。
方法 埼玉県下の介護保険施設300 施設(介護老人福祉施設169施設,介護老人保健施設89施設,介護療養型医療施設42施設)に対して,郵送記入方式の調査を実施した。調査期間は,平成 15年3月初旬から中旬の2週間程度であった。有効回答数(率)は,全体で99施設(33.0%),その60%以上が介護老人福祉施設であった。
結果 平成15 年の介護報酬改定によって経営に影響が生じるとする意見は項目によって差違があり,介護老人保健施設の「リハビリテーション機能の強化加算」では「大変影 響がある」70.0%であった。介護報酬改定への対応については,「現状で対応が可能」とする回答が「全施設共通:退所(退院)前連携加算の新設」で 44.4%,「介護老人保健施設,介護療養型医療施設:退所(退院)時情報加算の新設」で62.5%であった。「介護老人福祉施設:小規模生活単位介護福 祉施設サービス(ユニットケア)の新設」については,「対応するつもりはない」が61.8%であった。介護報酬改定後の経営方針では,全体として「具体的 な対応策あり」が90%を超えており,「高要介護者の入院・入所」の項目においては,「大変そのように考えている」「ややそのように考えている」をあわせ て67.0%であった。居宅介護支援報酬改定への意見としては,「要介護度別単位廃止による一律給付」は賛成が94.8%,「4種類以上の居宅サービスを 定めたケアプラン作成加算」「居宅介護支援に対する諸条件設定による減算」は,賛成と反対がほぼ同数であった。経営管理状況については,各項目について 「実施している」とする回答が多かった。
結論 介 護報酬改定後の施設の状況については,介護保険施設として経営的に厳しいととらえた意見もあり,何らかの対応が必要であると考えていることが明らかになっ た。今後の課題としては,一般企業と保健医療福祉分野の経営マネジメントがどのような点で異なり,どのような点で類似しているかなどを明確にすることが必 要である。そして経営マネジメント概念を取り入れることは,介護保険施設の経営管理だけではなく,高齢者保健・医療・福祉施策の再構築のためにも重要であ ると考える。
キーワード 介護報酬改定,介護保険施設,経営意識,マネジメント
|
第53巻第1号 2006年1月 要援護高齢者の主介護者における精神的健康東野 定律(ヒガシノ サダノリ) 筒井 澄栄(ツツイ スミエイ) 矢嶋 裕樹(ヤジマ ユウキ)桐野 匡史(キリノ マサフミ) 筒井 孝子(ツツイ タカコ) 中嶋 和夫(ナカジマ カズオ) |
目的 在宅で要援護高齢者を介護している主介護者の精神的健康をGHQ-12で測定し,GHQ-12の構成概念妥当性を因子モデルおよび基本属性との関連性で明らかにすることを目的とした。
方法 調査対象はS県A市に在住し,平成14年4月1日現在,要介護認定を受けた第1号被保険者5,189人の要援護高齢者のうち,協力が得られたその主介護者1,143人であった。調査員は介護支援専門員とした。調査内容は,要援護高齢者の性,年齢,主介護者の性,年齢,介護期間,続柄,精神的健康で構成した。精神的健康はGHQ-12で測定した。統計解析では,GHQ-12の因子モデルは1因子モデルとして設定し,さらにその精神的健康に対する主介護者の性,年齢,介護期間がGHQ-12の調査項目に与える影響をMultiple Indicators Multiple Causes(モデリング)で検討した。
結果 想定した英国版GHQ-12の1因子モデルのデータへの適合度は,統計学的な許容水準をほぼ満たしていた。また,その信頼性は,KR-20係数で0.85であった。さらに,MIMICモデリングで検討した主介護者の性,年齢,介護期間と精神的健康との関連性については,主介護者の精神的健康には性別が関連し,女性が男性に比べて精神的健康度が劣悪な状態であった。
結論 英国版GHQ-12は下位概念(因子)を想定せず,そのまま観測変数の合計点をもって,精神的健康度の程度とみなせることを支持する結果と解釈できた。また,女性が男性に比べて精神的健康度が劣悪な状態にあるという結果は性的役割社会化仮説を支持する知見と推察された。
キーワード 高齢者,家族介護者,負担感,精神的健康
|
第53巻第1号 2006年1月 一般高齢者と入院高齢患者における
松井 美帆(マツイ ミホ) |
目的 一般高齢者と入院高齢患者の終末期ケアに関する意向について比較検討することを目的とした。
方法 広島市,宇部市における65歳以上の老人クラブ会員である一般高齢者313名と大学病院内科病棟入院患者52名を対象とし,終末期の療養場所の希望,延命治療の意向,リビング・ウイル(書面による生前の意思表示)の支持に関する自記式質問紙調査を行った。
結果 対象者の平均年齢は,一般高齢者75.4±5.4歳,入院患者72.7±4.7歳で一般高齢者が有意に高く,性別は共に男性が55%であった。終末期ケアの意向に関して両群の意向を比較検討した結果,終末期の療養場所の希望については,一般高齢者では自宅が44.6%と最も多かったのに対して,入院高齢患者では今まで治療を受けた病院が52.1%と高い割合を示した。延命治療の意向に関して,回復の見込みが難しい状況における心肺蘇生法,人工呼吸器,人工栄養について,一般高齢者では「医師の判断に任す」が44.3~45.9%と最も多かったのに対して,入院高齢患者では「希望しない」とした回答が49.0~53.0%と,人工呼吸器,人工栄養では有意な差を認めた。さらに,リビング・ウイルの支持については,一般高齢者で賛同するものが72.8%であったのに対して,入院高齢患者では55.8%と有意に低かった。
結論 終末期ケアに関する意向について一般高齢者と入院患者では相違を認めた。入院患者では話し合いが難しくなることも予測されるため,健康な時から自らの意向を考え,家族やかかりつけ医などと話し合っておくことが重要と考えられる。
キーワード 終末期ケア,高齢者,延命治療,リビング・ウイル
|
第53巻第1号 2006年1月 介護サービスの質の確保策に影響を与える要因の検討-自治体の質問紙調査データを用いて-金 貞任(キム ションニム) 平岡 公一(ヒラオカ コウイチ) 山井 理恵(ヤマノイ リエ) |
目的 介護保険制度実施後の初期段階における自治体による介護サービスの質の確保策について,その取り組み状況に影響を及ぼす要因を分析し,介護サービスの質の確保策に関する課題を抽出する。
対象と方法 2000年12月から2001年1月に全国の市区町村介護保険担当課に対して実施した質問紙調査により得られたデータを用いた。有効回収数(率)は,1,361(41.9%)であり,それらを分析対象として,自治体の介護サービスの質の確保策に関する5指標を従属変数とし,自治体人口などに関する8つの変数を説明変数とするロジスティック回帰分析を行った。
結果 1)人口は「独自のサービス評価システム」「アンケート調査の実施」の指標に関して有意となった。2)財政力指数は,「苦情情報の活用と公開」「ケアプランの内容把握」「ケアプランの改善対策」「独自のサービス評価システム」「アンケート調査の実施」に関して有意であった。3)ケアマネジメントに関する問題の認知度は,「ケアプランの内容把握」「ケアプランの改善対策」のみで有意であった。
結論 人口,財政力,ケアマネジメントに関する問題の認知度といった要因が,自治体によるサービスの質の確保策に関する複数の指標に有意な影響を及ぼしていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ,各自治体の取り組み事例の収集と分析なども行い,サービスの質の確保策への取り組み状況を総合的に把握できる枠組みを構築する必要がある。
キーワード 介護保険,サービスの質,地方自治体,ケアマネジメント
|
第53巻第1号 2006年1月 わが国における過去の大規模健康被害に関する主要事例分析今村 知明(イマムラ トモアキ) 下田 智久(シモダ トモヒサ) |
目的 過去の大規模健康被害事例の分析に基づき,わが国における健康危機管理の制度・体制に係る課題を整理する。
方法 わが国における過去50年の大規模健康被害の主な事例17件から被害の拡大要因と国民の不安の拡大要因を抽出し,分析した。
結果 大規模健康被害の経緯として,原因判明あるいは初動対策実施までの時間,被害者あるいは患者数,課題,原因,初動,具体的対策を整理した。またこれらの調査から,被害の拡大要因として,原因究明の長期化や短期間での被害の拡大,原因究明後の対策不足が抽出された。健康被害に係る国民の不安の拡大要因として,企業倫理の低下,将来の予期できぬ危険性への不安,風評被害が抽出された。
結論 被害の未然防止の観点から,健康危機管理情報等の収集・分析・提供の体制の整備が必要である。特に,被害の拡大防止の観点から,あいまい情報の積極的な収集・分析とこれを初動対応につなげる体制・制度の整備とともに,風評被害等への対策の確立が必要である。
キーワード 大規模健康被害,健康危機管理,過去の健康被害
|
第53巻第1号 2006年1月 新障害者プラン遂行業務に携わる市町村障害福祉
橋本 卓也 (ハシモト タクヤ) 岡田 進一(オカダ シンイチ) 橋本 力(ハシモト チカラ) |
目的 新障害者プラン遂行業務に携わる市町村障害福祉担当職員の障害者の自立(自律)支援に対する意識を把握し,その意識に影響を与えている要因を明らかにすることを目的とした。
方法 調査対象者は,近畿2府4県342市町村の新障害者プラン遂行業務に携わる障害福祉担当職員であり,調査方法は自記式質問紙を用いた郵送調査である。調査期間は2003年12月2日から12月25日であり,有効回答率は43.9%であった。調査項目は,基本属性と「自立および自立支援」に関連する項目とし,そのうち担当職員の意識を測定する尺度として17項目を設定した。分析は,まず,バリマックス回転を伴う因子分析(主因子法)を行い,そこから得られた4つの因子ごとに単純集計を行った。次に,担当職員の意識に影響を与える要因を明らかにするため,「資格の有無」「福祉職歴の有無」を独立変数とし,各因子の項目の合計得点を従属変数とするt検定を行った。「現在の職場経験年数」「医療・福祉業務等における経験年数」と各因子との相関については,ピアソンの相関分析を用いて分析を行った。
結果 「資格の有無」や「福祉業務に関する職歴経験」等が,障害福祉担当者の意識に影響を与えていることが明らかになった。t検定および相関分析の結果,資格を有している職員,および福祉業務に関する職歴経験のある職員は,自己決定・自己選択等を自立の概念としてとらえる自立観や,インクルーシィヴな教育環境に関する意識が高いことが明らかになった。また,医療・保健・福祉に関する業務年数が長い職員は,上記以外に「障害者の性」に関して意識が高いことが明らかになった。
結論 新障害者プランの基本理念を施策に反映させていくためには,障害者の自立観や教育環境,および性と結婚などに対する市町村障害福祉担当職員の意識変革が重要な課題になる。そのためには,業務経験年数や職員の意識レベルに応じた研修体制の確立,フィールドワークの導入などを含めた研修方法の見直し,および各職員の意識向上・変革において欠かすことのできないスーパーバイザーの育成が求められる。また,有資格者や福祉関連職歴を有している職員,および業務経験年数の長い職員と新人職員とのバランスを考慮した職員配置を行うなど,受けてきた専門教育や研修などが十分に生かされ有資格者や業務経験年数の長い職員の意見が反映されるような職場環境や人員配置が望ましいと考えられる。
キーワード 新障害者プラン,市町村障害福祉担当職員の意識,自立観,障害児(者)の教育環境,障害者の性,エンパワメント
|
第53巻第2号 2006年2月 基本健康診査受診者のがん罹患と生命予後に関する研究後藤 順子(ゴトウ ジュンコ) 沼沢 さとみ(ヌマザワ サトミ) |
目的 老人保健法による基本健康診査受診者のデータを用いて,死亡やがんの罹患の関連要因を検討し,高齢化社会に対応した保健指導を考えることを目的とした。
方法 対象は山形県内の2町の住民で,1993年度から2001年度の9年間に老人保健法に基づく基本健康診査を受診した実人員6,466人とし,データは,検査結果として8項目(BMI,赤血球数,血色素,総コレステロール,中性脂肪,尿酸,空腹時血糖,動脈硬化指数),問診項目として4項目(喫煙習慣,飲酒習慣,既往歴(心臓病,眼底出血,高血圧,脳卒中,がん,腎臓病,肝臓病,貧血,高脂血症,糖尿病の有無),家族歴(がん,脳卒中,高血圧,心臓病,糖尿病の有無))とした。これらの初回受診時のデータをベースラインデータとし,この受診者コホートを2002年11月30日現在の全死因死亡と2000年1月1日現在のがん罹患との発生について追跡した。この受診者をがん罹患と全死因死亡をエンドポイントとして追跡し,各要因との関連を検討した。
結果 男性では,BMIが18.5未満,空腹時血糖が126(mg/dl)以上であることが死亡のリスクを有意に高めていたが,中性脂肪150(mg/dl)以上では死亡のリスクを有意に低下させていた。女性では,有意な項目はなかった。既往歴と全死亡との関連では,男女とも高血圧治療中が死亡のリスクを有意に高めていた。がん罹患との関連では,男性は血色素18(g/dl)を超える,中性脂肪150(mg/dl)以上,心臓病の治療中が大腸がん罹患のリスクを有意に高め,女性では赤血球数450(10 /mm )を超える,総コレステロール220(mg/dl)以上,中性脂肪150(mg/dl) 以上,動脈硬化指数4.5以上が大腸がん罹患のリスクを有意に高めていた。
結論 基本健康診査の検査結果,問診項目とがん罹患および総死亡との関連を検討した結果,総死亡は高血圧の治療などとの関連があり,がん罹患は部位によってリスクファクターが違い,これらを予防していくためには,各要因の複合的な関連を示すmetabolic syndrome(代謝症候群)への指導の必要性が示唆された。今後,若年世代からの生活習慣病予防教育の展開,産業保健との連携による壮年期全体の指導体制の確立,高齢者を対象とした健診や指導の検討が課題である。
キーワード 基本健康診査,metabolic syndrome,生活習慣,累積死亡率,累積がん罹患率
|
第53巻第2号 2006年2月 介護認定と入院を考慮した新しい健康余命とその特徴京田 薫(キョウタ カオル) 丸谷 祐子(マルタニ ユウコ)伊藤 美樹子(イトウ ミキコ) 早川 和生(ハヤカワ カズオ) |
目的 入手可能な既存データを用いて算定が簡便な新たな地域指標を提案することを目的とし,介護認定の有無と入院受療の有無を用いた健康余命DFLE(Osaka University DFLE:OUDFLE)をSullivan法によって都道府県別に推定し,既存の健康余命との比較からその特性を検討した。
方法 健康の定義を「介護認定または入院受療の有無」と規定し,直接法によって標準化した上で,Sullivan法に基づくOU-DFLEを,性,65歳,75歳,85歳の年齢階級,都道府県別に算定した。OU-DFLEと既存の4つの健康余命との比較には,性・年齢別にKruskal-Wallisの検定を行い,ボンフェローニの不等式を用いて多重比較を行った。さらに,都道府県単位ごとに求めたOU-DFLEと4つの比較対照の健康余命を用いて,健康余命を従属変数とし平均余命で回帰させ,決定係数(R )を検討した。最後に,すべての健康余命をOU-DFLEを基準にして都道府県順位に並び替えて観察し,それぞれの健康余命の質の特性を検討した。
結果 OU-DFLEの健康余命/平均余命比は,65歳時,男性87.87%,女性89.23%,75歳時,同80.15%,84.34%,85歳時,同68.56%,80.91%と,性別では女性が大きく,男性では75歳から85歳の間で著しく低下した。また,OU-DFLEは75歳男性を除く各年齢階級において男女ともすべての既存値と有意差が認められた。次に,健康余命を従属変数とし平均余命で回帰させた結果,OU-DFLEの決定係数(R )は,4つの比較対照の健康余命と比べて男性では0.33,女性では0.42と低かった。
結論 4つの比較対照の健康余命には,相互に類似性が認められたのに対し,OU-DFLEには,女性の健康余命/平均余命比が大きく,平均余命との弁別性が高いという特徴が明らかになった。データ入手が容易で,地域の実情を反映しやすいOU-DFLEは,市町村や二次医療圏といった小規模な地域の指標として用いるのには適していると言える。
キーワード DFLE,高齢者,Sullivan法,介護保険認定,入院受療,地域指標
|
第53巻第2号 2006年2月 福岡県における長期入院高齢者の介護保険法施行後の動向馬場 みちえ(ババ ミチエ) 今任 拓也(イマトウ タクヤ ) 馬場園 明(ババゾノ アキラ )谷原 真一(タニハラ シンイチ) 宮崎 元伸 (ミヤザキ モトノブ) 西岡 和男 (ニシオカ カズオ) 畝 博(ウネ ヒロシ) |
目的 介護保険法施行により,高齢者の長期入院者および長期入院の医療費がどの程度低下したかを明らかにするとともに,1999年度に300日以上長期入院した者(長期入院者)の介護保険法施行後の動向について調査し,そのまま入院を継続した者と長期入院から介護施設に移動・移行した者の死亡リスクについて検討した。
方法 資料として1999~2003年度の診療報酬明細書と2000~2003年度の介護給付費請求明細書を用い,長期入院者数とその診療費を計算した。生命予後については,介護保険法施行後に介護施設に移動・移行した者,そのまま長期入院を継続した者,および対照群として特別養護老人ホーム入所者の標準化死亡比を算出し比較した。標準化死亡比は,福岡県における2001年の性別年齢階級別死亡率を基準として計算した。また,介護保険法施行後に介護施設に移動・移行した者と対照群に関しては,Coxの比例ハザードモデルを用いて,その死亡リスクについて比較した。
結果 300日以上の長期入院者は介護保険法施行後約半分に,また,全体の入院診療費に占める長期入院者の診療費は約2/3に低下した。1999年度長期入院者のうち,介護保険法施行後の2000年度には約1/3がそのまま長期入院を継続し,約1/3が介護施設に移動・移行して300日以上の長期入所者となった。1999年度長期入院者の大部分は2003年度までの5年間,病院に入院あるいは介護施設に入所し続けており,家庭復帰する者はほとんどいなかった。介護保険法施行後に介護施設に移動・移行した者の死亡リスクは対照群とほとんど変わらなかった。しかし,介護保険法施行後も長期入院を継続した者の標準化死亡比は対照群より高かった。
結論 介護保険法施行により,1999年度長期入院者のうち,約1/3の者が介護施設に移動・移行し,長期入院者は約半分に,また長期入院診療費の割合は約2/3にまで低下した。2000年度から2003年度の4年間の累積死亡率は男で61.1%,女で47.3%であった。長期入院から介護施設に移動・移行した者の死亡リスクは,当初から特別養護老人ホーム(介護施設)に入所していた者とほとんど変わらなかった。これらのことから,長期入院者の多くは,治療より生活を快適に過ごすための介護サービスが与えられるべき人たちだったと考えられる。介護保険は,こうした治療より介護が必要な長期入院者に本来必要としている介護サービスが受けられることを制度として可能にした点で評価できるのではないかと考えられた。
キーワード 高齢者,介護保険,長期入院,長期入所,死亡リスク
|
第53巻第2号 2006年2月 出生日を用いた標本抽出法についての一考察髙田 崇司(タカダ タカシ) 石井 太(イシイ フトシ) |
はじめに
厚生労働省では,医療施設や社会福祉施設など厚生労働行政に関係する様々な施設に対する統計調査を行っている。施設の基本的な情報については全数調査が行われることが多いが,施設の利用者などについては,全数調査ではなく,対象から一定の大きさの標本を抽出して行う標本調査が多い。この標本抽出に当たっては,まず(一定数の)施設を標本抽出した後,客体となった施設における利用者などからさらに標本抽出して調査を行う,二段抽出法がよく用いられる。このとき,施設の標本抽出は全数調査により作成された名簿があるため,これを用いて厚生労働省側で標本抽出を行うことが可能であるが,一般的に施設の利用者などは調査時点での対象者が事前に把握できないため,各施設において標本抽出を行う必要が生じる。これを行うためには,最も簡易な系統抽出法の場合でも,利用者等の名簿を整備して一定間隔で客体を抽出するなどの手間が必要になるとともに,実務的に複雑な作業を行うことから生じるミスなどによる標本の無作為性のクオリティ低下が起きる危険性がないとはいえない。
そこで,厚生労働省が実施する標本調査では,施設において利用者などを標本抽出する際,「出生日が奇数の利用者のみを客体とする」など出生日の特性を利用して標本抽出を行うという標本抽出法が採られているものがいくつかある(患者調査,社会福祉施設等調査,介護サービス施設・事業所調査,地域児童福祉事業等調査など)。このような方法を採ることにより,施設などの現場でも比較的容易に標本抽出を行うことが可能になるとともに,(後述するように,一定の条件の下で)標本の無作為性についても一定のクオリティが担保されることとなる。
ところで,標本調査には抽出された標本が全体とは異なることから生じる標本誤差があり,この標本誤差を一定の精度に管理する標本設計が必須のものとなる 。「統計行政の新たな展開方向」(平成15年6月各府省統計主管部局長等会議申合せ) の中でも,指定統計については達成誤差などの誤差情報を提供していくこととされたほか,既に情報提供している統計調査についても「その内容の充実を図ることとし,承認統計や届出統計についても指定統計に準じて情報提供を図ること」とされており,すべての官庁統計について,標本調査における誤差情報提供の一層の充実は,まさに必須の重要課題である。さて,出生日を利用した標本抽出法の理論的整理を試みようとすると次のような問題があることに気がつく。すなわち,ある調査日における利用者の出生日は,母集団において既に確定しているのであるから,施設を抽出すると同時に客体となる利用者も決定しており,利用者を標本抽出することによる確率的な変動はない。したがって,通常,誤差情報として提供を行っているsampling designによる標本誤差は,二段目の標本抽出については考えられないのではないかという問題である。この点については,平成17年患者調査(指定統計第66号)計画案の審議の場においても,「標本設計の面で,最初から生年月日の末尾でもって配り分けられるべき調査票というのが分かれてしまっているという形になっています。だから,ランダムな過程が入っていないので,(中略)たとえ全数調査をしたとしても,簡単な調査票を配った方の人については詳しい情報はわからないという形になっているわけです。(中略)ただ,恐らく調査されている項目と生年月日との間にはあまり関係はないであろうという大きな前提条件があって,その条件の下では,このように調査したとしても標本誤差の評価というのが可能になって,多分,そういう整理になると思われます」との問題提起がされている 。このように,出生日を利用した標本抽出は,通常の標本抽出とは理論的に異なった側面をもっていると考えられるが,この場合の推定量やその精度に関し,標本調査論における理論的な位置づけと,これら厚生労働省の実際の調査を直接的に関連づけて整理を行った論文はあまり多くない。本稿は,厚生労働省で実際に行われている調査に近い例を用いて,出生日を利用した標本抽出法の理論的な位置づけの整理を試みるとともに,具体的な数値シミュレーションによる評価を行ったものである。
|
第53巻第3号 2006年3月 基本健康診査未受診の高齢者における
中野 匡子(ナカノ キョウコ) 矢部 順子(ヤベ ジュンコ) 安村 誠司(ヤスムラ セイジ) |
目的 老人保健法の基本健康診査未受診の高齢者の生命予後と関連する要因を明らかにし,未受診群への健康教育の重点項目を示すことを目的とした。
方法福島県須賀川市の満70歳以上の在住者から3分の1抽出した2,718人を対象とし,ベースライン調査として自記式調査票を用いた郵送アンケート調査を実施した。質問項目は,身長,体重,疾病の有無,健康度自己評価,閉じこもりの有無,Breslowの7つの健康習慣(BMI,睡眠,喫煙,飲酒,朝食,運動,間食)とした。HPI(健康習慣保有数)として,睡眠,BMI,運動,喫煙,飲酒の5習慣の得点を合計した。有効回答者2,019人(74.3%)の平成12年度の基本健診受診の有無を確認し,住民基本台帳に基づき3年4カ月間の死亡・転出状況を調査した。受診の有無とアンケート項目のクロス集計,Kaplan-Meier法による累積生存率の算出,コックスの比例ハザードモデルによる多変量解析を行った。
結果 .ベースライン調査:基本健診未受診群は,疾病がある,健康度自己評価が悪い,閉じこもり,喫煙する,運動が週1回以下の者の割合が有意に高かった。.死亡状況:累積生存率は,受診群が未受診群に対し有意に高かった。コックスの比例ハザードモデルによる解析では,受診の有無を共変量とすると,未受診群の死亡のリスクが高く,性,年齢,健康度自己評価,閉じこもりの有無,HPIに死亡と有意な関連がみられた。受診群と未受診群に分けて,年齢,性,健康度自己評価,閉じこもりの有無,疾病の有無,HPIを共変量とすると,受診群では,性,健康度自己評価が死亡と有意な関連がみられた。これに対し,未受診群では,高年齢,男性,閉じこもり,HPIが低い者が死亡のリスクが有意に高かった。HPIに代えて7つの健康習慣の各々を共変量とすると,受診群では性のみが,未受診群では,年齢,性,閉じこもりの有無,BMI,運動が有意に死亡と関連していた。受診群,未受診群ともに疾病の有無は死亡と有意な関連がなかった。
結論 .高齢者での基本健診未受診群は,受診群に比べ,生命予後,生活習慣,健康度自己評価が悪い。.未受診群の男性高齢者は,疾患があっても「良い生活習慣の複数維持,運動奨励,BMI適正化,閉じこもり予防」で死亡のリスクを減らしうる可能性があり,これらの項目について重点的な支援が必要である。
キーワード 高齢者,基本健康診査,未受診者,運動,閉じこもり,コホート研究
|
第53巻第3号 2006年3月 北海道における他殺の疫学西 基(ニシ モトイ) 三宅 浩次(ミヤケ ヒロツグ) |
目的 北海道において1979年から2002年までの24年間に人口動態統計で「他殺」に分類された死亡につき,疫学的に検討する。
方法 北海道保健統計年報の資料から,1979年から2002年までに北海道において他殺(ICD-9基本分類E960-E969,ICD-10同X85-Y09)に分類された死亡を対象とし,解析を行った。
結果 24年間の通算で北海道の他殺による死亡は970例(人口10万対0.71),全国を標準集団とした標準化死亡比は男性96.9%,女性101.2%とほぼ全国の平均であった。殺害手段は男性が被害者の場合,刃物(男性全体の37.9%)が絞首(20.2%)の約2倍だったが,女性の場合は逆に絞首(女性全体の41.6%)が刃物(25.2%)の1.5倍以上を占めた。また,被害者の年齢が15歳未満または65歳以上では,男女とも刃物の頻度が低下し,絞首の頻度が上昇した。年齢層別では,0歳児の他殺死亡率(出生10万対7.88)は全国(4.51)より有意に高く,かつ他殺全体の11.3%(総計110人)を占め,これは全国の6.7%をはるかに上回った。他殺0歳児の56.4%は出生当日か翌日に殺害されていた。0歳児の他殺死亡率を地域別に検討したところ,札幌市で出生10万対8.88と,札幌市以外の地域(7.44)と比較して高かった。遺棄により殺害された割合が札幌市で有意に高く(42.1%対23.6%),これが同市の0歳児他殺死亡率を押し上げる要因となっていた。0歳児他殺は3月中旬・4月下旬・8月上旬に多かった。
結論 性と年齢による殺害手段の相違は,抵抗力の強弱が凶器を用いるか否かに結びついた結果と考えられた。寒冷な自然条件と大都会での人間関係の希薄さが,児が死んでいく様子を見ずに済む方法である遺棄による殺害を決意させる要因となっている可能性も考えられた。0歳児殺害は卒業・大型連休・お盆などで祖父母などに会う時期の直前に多いと言え,不本意な妊娠の処理手段として児殺害が選択されている場合が多いと推測された。
キーワード 他殺,疫学,嬰児殺害,手段
|
第53巻第3号 2006年3月 Zarit介護負担尺度日本語版の短縮版
上村 奈美(ウエムラ ナミ) 新田 静江(ニッタ シズエ) 飯島 純夫(イイジマ スミオ) |
目的 在宅介護の実践で,家族介護者の負担感を的確に把握するために活用しうる妥当な質問項目を提言していくために,Zarit介護負担尺度日本語版の短縮版の妥当性と信頼性の追試を行うことである。
方法 居宅サービス利用高齢者と同居し,家族介護者と自己認識している222名を対象とし,調査票を用いた個別面接にてデータを収集した。分析には,最尤法Varimax回転にて因子分析を行い,選択した項目の妥当性(構成概念妥当性・併存的妥当性)と信頼性(内的整合性)を確認し,確証的因子分析(因子的妥当性)のために共分散構造分析を行った。
結果 因子分析にて抽出された第1因子(role strain)から5項目と第2因子(personal strain)から3項目の計8項目を選択し,短縮版(J-ZBI-8Y)とした。妥当性は,構成概念妥当性として,家族介護者が健康であると認識しているほど負担感得点は低く,J-ZBI,J-ZBI-8Yのいずれでも有意差がみられた。また,就業している場合の負担感得点は高くJ-ZBIとJ-ZBI-8Yで有意差がみられたが,その他の概要(高齢者の性別・年齢・介護区分,家族介護者の性別・続柄・副介護者の有無)には有意差はみられなかった。併存的妥当性を示すJ-ZBIとJ-ZBIの項目22とJ-ZBI-8Y間の相関は0.90,0.63であった。J-ZBI-8Yの共分散構造分析の結果,モデルの適合度は十分であり(CFI=0.99),信頼性を示すα係数は,0.84であった。
結論 J-ZBI-8Yは,構成概念妥当性,併存的妥当性,確証的因子分析による因子的妥当性と信頼性が確認され,既存の短縮版(J-ZBI 8)と同様に短縮版として有用であると考える。J-ZBI-8YとJ-ZBI 8において一致して抽出された項目は,personal strainで3項目とrole strainで2項目の合計5項目であり,これらは負担感を測定するJ-ZBIの短縮版作成には,不可欠な項目と推察される。今後は,J-ZBI-8Yで抽出された項目とJ-ZBI 8で抽出された項目との相違の検証が課題である。
キーワード 要介護高齢者,介護負担尺度,家族介護者,因子分析,妥当性,信頼性
|
第53巻第3号 2006年3月 富山県における花粉症発症に関連する
内田 満夫(ウチダ ミツオ) 寺西 秀豊(テラニシ ヒデトヨ) 加藤 輝隆(カトウ テルタカ) |
目的 富山県において,花粉症に影響すると予想される生活習慣と環境因子について横断的に調査し,統計学的に検討して発症予防につなげる。
方法 平成16年の8月から12月,富山県の市町村保健センター25カ所の協力を得て,センター職員と来所者を対象に自己記入式アンケートを実施した。質問内容は,住所,回答者を含む家族全員の性別,年齢,職業,花粉症の診断歴,毎年の花粉症発症月,現喫煙習慣,回答者本人のストレス度,運動習慣,ペットの所持,自宅の気密性と道路までの距離,食習慣としてインスタント食品,コンビニエンスストアの弁当,スナック菓子,肉類,魚介類,野菜類,卵大豆類,乳製品などの摂取頻度とした。また環境因子として平成16年の空中花粉飛散数,気温,風速,日照時間,降水量,森林面積,大気汚染データ,居住地の海岸線からの距離について検討した。
結果 アンケート回答者は1,341人,家族を含めた全対象者は4,468人であった。花粉症有病者は,回答者では212人(15.8%),全対象者では532人(11.9%)であった。月別空中花粉飛散数と月別発症数の間に有意な相関を認めた(r=0.884,P<0.005)。花粉症有病者については性差がなかったが,年齢差(P<0.0001),職業差(P<0.0001)が認められた。生活習慣では,ストレス度(P<0.01),ペットの所持(P<0.05),インスタント食品(P<0.005)において有意な差を認めた。環境因子では,居住地の海岸線からの距離において有意な差を認めた(P<0.001)。
結論 ストレスの増加,ペットの所持,インスタント食品の摂取,居住地の海岸線からの距離の項目に花粉症有病率と有意な関係を確認した。これらの生活習慣や環境因子をコントロールすることが花粉症予防につながると期待される。
キーワード 花粉症,生活習慣,環境,横断調査
|
第53巻第3号 2006年3月 サテライトケアが要介護高齢者の精神機能に及ぼす影響池田 志保子(イケダ シホコ) |
目的 認知症高齢者の施設ケアでは,より在宅生活に近い居住環境を整えた「ユニットケア」に代表される,個別ケアが重視されているものの,こうした小規模集団ケアと従来の大規模集団ケアの比較先行研究は少ない。筆者らは,本体施設から離れた場所にある民家をサテライトケア拠点(「海の家」)と位置づけ,個別性を重視したケアを実施している。この「海の家」は,施設入所者が施設外のケア施設に通う点からみて「逆デイサービス」ともいえる。この「海の家」によるケア提供が精神機能へ与える影響を検討することにより,小規模集団ケアの有効性を考察する。
方法 特別養護老人ホーム(特養)7名,老人保健施設(老健)10名,グループホーム(GH)7名の合計24名に対し,月に1~2回(計8回程度),「海の家」において昼食作りや趣味活動など,個別性の高いケアを実施した。介入前後の精神機能の評価は精神機能障害評価票(MENFIS)によって行った。
結果 全体では動機づけ機能において有意な改善を認めたが,認知機能には改善は認められなかった。施設間の比較では,老健と特養において全機能合計得点に改善傾向がうかがわれるものの,GHではむしろ増悪傾向がみられた。
結論 「海の家」での個別性を重視したケアによって,MENFISにおける動機づけ機能が改善し,小規模集団によるケアにおける意欲賦活効果が示唆された。なお,GH群においてMENFISの増悪がみられた理由としては,居住するGHと「海の家」が環境として類似しており,GHと「海の家」を行き来することから生じる,地誌的要因によって混乱をきたしたと考えられた。しかしながら,「海の家」が他施設群にとっては良好な影響を与えることからみると,逆説的には,GHにはすでに認知症高齢者の生活環境として良好な条件が備えられているとも考えられる。これは,小規模集団によるケア提供の有効性の傍証になるものと思われた。
キーワード サテライトケア,逆デイサービス,小規模ケア,認知症,MENFIS,精神機能
|
第53巻第4号 2006年4月 介護予防施策における対象者抽出の課題佐川 和彦(サガワ カズヒコ) |
目的 小児科を取り巻く環境の変化がかなり大きくない限り,病院はその廃止や開設については二の足を踏み,現状維持のままを選ぶであろう。しかし,それが一定の限度を超えた場合には,廃止あるいは開設に踏み切ると想定できる。本稿では,このような行動パターンが実際に存在するかどうかを検証する。
方法 都道府県単位で集計した小児科を標榜する一般病院数を分析の対象とし,1990年以降の期間を3年ごとに区切って,それぞれの期間中の各都道府県における変化率を調べた。環境の変化に対して,病院が滑らかに行動を変化させているのではなく,摩擦(フリクション)が生じて実際の行動の変化がおこりにくくなっていることを説明するために,フリクションモデルを応用した。
結果 各都道府県で小児科を標榜する一般病院数を変動させるような環境の変化がおこったとしても,1990~1993年についてはその変動の大きさが±1.34%の範囲内であるならばフリクションが生じ,実際には小児科を標榜する一般病院数は変動しなかった。この範囲を超えたところから実際の変動が始まった。1993~1996年についてはこのような範囲が±0.767%に狭まったが,これ以降の期間はその範囲が拡大し,変動がおこりにくくなった。
結論 病院が小児科の廃止や開設を検討するような事態に至ったときに,フリクションモデルが想定するような行動パターンをとっている可能性は高い。
キーワード 少子化,小児科を標榜する一般病院,フリクションモデル
|
第53巻第4号 2006年4月 日本における死因構造の推移(1950~2000)-平均寿命の性差への寄与-吉永 一彦(ヨシナガ カズヒコ) 畝 博(ウネ ヒロシ) |
目的 戦後,日本の平均寿命の伸長は目覚しく,これに伴いその性差も拡大し,1950年で3.50年,1970年では5.35年,1980年で5.41年,2000年では6.88年といずれも女性の方が長い。その性差の推移について年齢分布と主要な死因構造の差異から観察する。
方法 年次ごとにJ.H.Pollard法により,平均寿命の性差の年数を年齢階級および各主要死因による寄与年数に分割する。
結果 平均寿命の性差への寄与年数は,1950年では結核0.54年,脳血管疾患0.38年,不慮の事故0.76年であり,1970年では結核0.24年,悪性新生物0.83年,脳血管疾患1.30年,不慮の事故1.15年となり結核の寄与が減少し,悪性新生物と脳血管疾患は増大した。1980年では悪性新生物がさらに増大し1.31年,脳血管疾患0.86年,不慮の事故0.69年である。2000年では悪性新生物が大きく突出して2.24年,虚血性心疾患0.51年,脳血管疾患0.62年,肺炎0.65年,不慮の事故0.57年,自殺0.51年でほぼ同程度である。年齢層では65~74歳をピークとした55歳以降の中高齢層での格差が大きく,年次とともにそれらはより顕著になり,また高齢へとシフトしている。また,20歳前後の寄与もやや大きい。
結論 平均寿命の性差の背景として,1950~1970年では結核,不慮の事故および脳血管疾患による寄与が大きく,その後,特に1980年以降では悪性新生物による寄与が急激に増大し,今後の性差の推移に大きな影響を与えると思われる。また,年齢層では20歳前後の不慮の事故と特に55歳以降の中高齢層での格差が拡大し,さらに高齢へとシフトしている。しかしながら,1999年以降,格差の伸びが急速に減衰している。その推移についてはまだ資料不足のため今後の課題とするが,この現象は今後の男女の寿命および性差の予測を困難にしている。
キーワード 平均寿命,性差,寄与年数,主要死因別死亡率
|
第53巻第4号 2006年4月 歯科医療関係者の法に基づいて
|
目的 医師・歯科医師・薬剤師調査における歯科医師の届出率は,若年齢の者において低いと報告されている。また,この届出は多くが医療施設を介して行われているが,その実態は明らかでないことから,若年齢の歯科医師が多く勤務する大学附属病院での届出に関する実態,その問題点を明らかにする。
方法 2005年2月に歯科・医科大学附属病院92施設を対象として,著者らが作成した調査票を郵送法で送付し,届出票の入手ルート,病院内での回収方法,保健所への提出率などについて調査を行った。
結果 調査票の回答施設数(率)は74(80%)であった。届出票はそのほとんどを保健所から入手しているが,必要枚数を入手できたのは半数ほどの施設であった。歯科医療関係者から届出票を回収する際には81%の病院が「催促して」提出率向上に努めている。100%提出している病院は,歯科医師分80%,臨床研修歯科医師分91%,歯科衛生士分88%,歯科技工士分92%であり,「催促している」病院で多い。
結論 歯科医療関係者の届出票はその入手から提出まで保健所と病院との協力関係で行われており,病院に多くの人手をわずらわせている。保健所への提出率を高めるには,保健所から病院に必要枚数を送付し,病院は催促して届出票を回収する手間が必要である。また,歯科医師臨床研修が必修化する際には,臨床研修歯科医師に対する教育での徹底も重要である。
キーワード 医師・歯科医師・薬剤師調査,届出票
|
第53巻第4号 2006年4月 老人保健福祉計画で用いられる健康指標の活用と
|
目的 近年,保健所や地方衛生研究所が中心となって,地域保健情報システムが構築されつつある。本研究では,老人保健福祉計画(介護保険事業計画を含む)で用いられる健康指標の活用について,市町村,保健所,地方衛生研究所の間で,情報の提供と分析に関する支援関係は確立されているのかについて調査した。
方法 2002年9月,東京都と神奈川県の90区市町村の老人保健福祉計画担当者,73保健所の保健情報担当者を対象として郵送法でアンケート調査を行った。区市町村には,計画作成過程における健康指標の使用状況と今後の意向を聞き,保健所には,重要な死亡指標の算出や,高齢者に関する調査の実施状況などを聞いた。また,両都県における人口動態統計表の還元方法や,地方衛生研究所の機能についてヒアリング調査を行った。
結果 アンケートの回収率は区市町61.1%,保健所67.1%であった。区市町が健康指標を使用した割合は,介護保険や社会参加など(50%以上),老人医療費やがん検診の有所見割合など(25~50%),医療施設数や老人の死亡統計(25%未満)で,保健所が扱う健康指標の使用割合が最も小さかった。しかし,使用する健康指標を拡充する必要があるとする区市町は80.0%であった。健康指標の分析で県型保健所の支援を受けた例は1件だけであったが,保健所の支援を今後は希望するという回答は60.0%であった。保健所が行った分析は,老人保健事業に関するものが最も多く(58.3%),管内の年齢調整死亡率などの算出は半数以下(43.8%)であった。これらの分析実施は,管内自治体からの問い合わせの有無と関連していた。これらの分析で,地方衛生研究所と協力した例はなかった。人口動態統計の死亡データは,都県レベルでは,性・年齢階級・死因別の死亡数が公表されていた。区市町村レベルでは,東京都は,性・年齢階級・主要死因別の死亡数を公表していた。神奈川県はそれを公表しておらず,各保健所が指定統計の目的外使用の手続きをする必要があった。
結論 市町村は,老人保健福祉計画で種々の健康指標を活用することに積極的であり,その過半数が保健所の支援を望んでいた。保健所が管内高齢者の死亡統計を活用するためには,区市町村の死亡データを経年的・電子的に維持・管理する方法を確立する必要がある。そのためには市町村,保健所,地方衛生研究所それぞれの役割と機能を明確にした地域保健情報システムを確立し,制度面からそれを支援する必要があると考えられる。
キーワード 老人保健福祉計画,健康指標,市町村支援,保健所,地方衛生研究所
|
第53巻第4号 2006年4月 日本人高齢者における身体機能の
|
目的 同一の地域に在住する高齢者(65歳以上)に対する長期縦断研究から,特に身体機能について1992年,1998年,2002年のコホートのデータを用い,1)1992年の高齢者コホートにおける10年間の加齢変化,2)1992年と1998年の高齢者コホートにおける4年間の加齢変化の比較,3)1992年と2002年の高齢者コホートにおける横断的比較,4)2002年の高齢者コホートは1992年コホートのいずれの年齢階層と相同の分布を示すか,の4点について検証を行う。
方法 東京都老人総合研究所が1991年から継続して行っている「中年からの老化予防総合的長期追跡研究」(TMIG-LISA)のフィールドのひとつである秋田県南外村(現:大仙市南外地区)における65歳以上の地域在宅高齢者を研究対象者とした。1992年の初回調査時における対象者は748名(男性300名,女性448名)であり,2002年の調査時には1,327名(男性549名,女性778名)である。TMIG-LISA<4SP>は会場に招待しての医学調査と面接調査からなっているが,今回の分析では,高齢者の生活機能を規定する重要な要因のひとつである身体的運動能力(握力,開眼片脚起立時間,通常歩行速度,最大歩行速度)と栄養学的指標(BMI,血清アルブミン,血清総コレステロール)の7項目について分析した。
結果 1)1992年の高齢者コホートにおける10年間の加齢変化については,男女とも前期および後期高齢者での変化のパターンはほぼ同じ状態を示していたが,後期高齢者での低下がより明瞭であった。2)1992年と1998年の高齢者コホートにおける4年間の加齢変化の比較については,(血清アルブミンと血清総コレステロールを除き)両群ともほぼ等しい変化パターンを示し,4年間で有意な低下を示す項目が多かった。3)1992年と2002年の高齢者コホートの横断的比較では,男女とも2002年コホートで有意に高値を示す項目が多く,運動機能,栄養指標ともに2002年コホートで著しく向上していることが明らかとなった。4)2002年の高齢者コホートは1992年コホートのいずれの年齢階層と相同の分布を示すかを分散と平均値から検証した場合,1992年コホートに相等する分布を示すのは,測定項目により異なるが男性で(最小)69歳以上から(最大)76歳以上となり,女性では(最小)68歳以上から(最大)76歳以上となっていた。
結論 地域在宅高齢者における最近10カ年の身体機能の加齢変化を示した。一般に前期高齢者に比べ,後期高齢者での機能の減衰がより大きいことが示された。また1992年の高齢者コホートと2002年の高齢者コホートを比較した場合,後者では最小で3歳から最大で11歳の分布のズレが認められ,いわば相当の若返りが認められた。少なくともわが国の高齢者は平均寿命の延伸とともに,身体機能は改善・向上していることが示唆された。
キーワード 地域高齢者,縦断研究,横断的比較,若返り
|
第53巻第5号 2006年5月 住民参加型の保健福祉活動の推進に向けた
杉澤 悠圭(スギサワ ユウカ) 篠原 亮次(シノハラ リョウジ) 安梅 勅江(アンメ トキエ) |
目的 住民と保健福祉専門職に対するフォーカス・グループインタビュー(グループインタビュー)を実施し,コミュニティ・エンパワメントに関するニーズを質的に把握し,住民参加型の保健福祉活動の推進への一助とすることを目的とした。
方法 大都市近郊農村T自治体住民と保健福祉専門職4グループに対するグループインタビューを実施した。対象の内訳は男性14名,女性15名,合計29名で,年齢は30~70歳代,内容はコミュニティ・エンパワメントのニーズであった。各グループのインタビューから得られた結果をカテゴリー化し,その共通点,相違点,背景要因に注目してコミュニティ・エンパワメントのニーズを抽出し,特性を分析した。
結果 地域エンパワメントの条件は「個の領域」「相互の領域」「地域システムの領域」の3つに分類された。主要な要件は「地域の魅力化」「安心・安全なシステムづくり」「地域で支え合う人材育成」「情報支援の充実」の4点であった。
結論 コミュニティ・エンパワメントに関する住民と専門職の生の声を質的に分析した結果,今後さらに住民と専門職が協働してサービス企画や運営に関わる体制作りの重要性が示された。そのためには,住民リーダーの育成や専門職のコミュニティ・エンパワメント技術,コーディネート技術の向上に向けた教育システムの構築が期待される。
キーワード コミュニティ・エンパワメント,フォーカス・グループインタビュー,ニーズ,健康長寿,住民参加
|
第53巻第5号 2006年5月 福岡県の一般診療所・歯科診療所の
山本 武志(ヤマモト タケシ) |
目的 医師の地理的分布の地域格差については,諸外国においても医療政策上重要な課題とされており,分布の平等性に関する多くの研究がみられる。わが国では一般診療所・歯科診療所は年々増加の傾向にあるが,診療所数の増加は地域格差を逆に拡大させる可能性もある。本研究では診療所の地理的分布の平等性について,福岡県の15年間の推移について検証した。
方法 一般診療所数・歯科診療所数は,医療施設調査(厚生労働省)から福岡県内の全市区町村の1985年,1990年,1995年,2000年の15年間,4時点のデータを用い,人口10万人対診療所数の変動係数およびジニ係数を算出し,ローレンツ曲線を描いた。また,市区町村の人口規模別に人口10万人対診療所数の推移を分析した。
結果 人口10万人対診療所数のジニ係数の値は,一般診療所が0.211(1985年)から0.212(2000年)へと横ばいだったが,歯科診療所は0.271(1985年)から0.209(2000年)へと減少しており,市区町村間格差が縮小していた。自治体規模による比較では都鄙(とひ,都会と田舎)間の格差が縮小する傾向がみられ,一般診療所では,人口規模が小さい市区町村において30%を超える増加が認められ,歯科診療所では,人口規模の大きい市区町村において伸びが小さかった。ただし,人口規模が小さい自治体では人口減の影響が大きいと推測された。
結論 福岡県の診療所の地理的分布はおおむね平等な状態が保たれており,歯科診療所については15年間で地理的分布の格差が縮小していた。一般診療所については,市区町村間での格差の変動はみられなかったが,小規模自治体ではとくに人口10万人対診療所数が増加していた。ただし,人口減による影響が認められるため,長期的な観点から診療所医療の需給の動向を見守る必要性がある。
キーワード 一般診療所,歯科診療所,地理的分布,ジニ係数
|
第53巻第5号 2006年5月 生活保護現業員の困難経験とその改善に関する研究-負担感・自立支援の自己評価を中心に-森川 美絵(モリカワ ミエ) 増田 雅暢(マスダ マサノブ) 栗田 仁子(クリタ ジンコ)原田 啓一郎(ハラダ ケイイチロウ) 谷川 ひとみ(タニガワ ヒトミ) |
目的 本稿の目的は,生活保護制度における援助業務の困難状況を,生活保護担当の現業員の意識の面から,業務の実施体制と関連づけて計量的に把握するとともに,業務の実施体制という位相における困難改善のあり方を検討することにある。
方法 国内の全福祉事務所(平成15年12月1日時点,1,240カ所)につき1名の生活保護担当現業員を対象に,「業務全般への負担感」と「自立助長の援助に対する自己評価」からなる概括的な業務困難意識と,意識の下位側面(業務量,ケース特性,現業員特性,組織的支援)の構成を尋ねた(自記式郵送調査,有効回答率57.5%)。負担感と自己評価の構成要素のうち,実施体制にかかわる要素である業務量,専門性について,対応する客観的変数(1人当たり担当ケース数,経験年数,所持資格)と,負担感および自立助長援助の自己評価との関連を,クロス集計により分析した。
結果 負担感が高い場合は,業務量過多という認識が強く,専門性不足という認識は弱かったのに対し,負担感が低い場合は,業務量過多の認識は低く,専門性不足の認識が強かった。「非常に負担」の割合は,担当ケース数別では,91以上で46.1%,50以下で24.7%であり,経験年数別では,5年以上10年未満で40.3%,2年未満では34.7%であった。自立助長の援助が「不十分」な理由は,主に,担当ケースが多く十分なかかわりがもてないことや,相談援助の専門性が不足していることであった。担当ケース数が91以上の場合,援助「不十分」の割合は77.7%,「不十分」な理由として「援助方針が不明確」に同意した者が44.3%に達した。また,社会福祉士資格を持つ者は,援助の自己評価が低かった。
結論 1人当たりの担当ケース数が90を超える場合,援助を振り返る余裕もなく,援助関係作りや援助方針の設定も困難になっていた。また,新任職員のみならず中堅層職員が多様な負担要素を抱えている可能性,社会福祉士が低い自己評価にさいなまれる可能性が示唆された。実施体制という側面から現業員の困難状況を改善するためには,現業員が援助について振り返るゆとりの確保,業務量軽減への本格的対応,中堅層を含めた支援の整備,援助実践の評価基準の共有化,という視点が重要である。
キーワード 生活保護,福祉事務所,現業員(ケースワーカー),負担感,自立助長,評価
|
第53巻第5号 2006年5月 高齢化社会時代の死亡率の年次変化に関する考察牧野 国義(マキノ クニヨシ) |
目的 高齢化社会が高齢社会へと進行する中で,高齢者への健康対策が重視されている。その指標の一つである死亡率について,通常,経年変化による増減が判断材料とされてきた。しかし,本来,死亡率の年次変化の検討は同一集団で行う必要があるが,現実には異なってくる。そこで,基準年を設定し,その死亡傾向が継続するとしたとき,実際の死亡傾向とどのように異なるかを検討し,高齢者への健康対策の評価に資することを目的とした。
方法 わが国の年齢調整死亡率の基礎となる昭和60年(1985年)を基準年として,以降もこの年における年齢階級別死亡率を一定とした人口集団を考えた。5歳ごとの年齢階級では,1990年,1995年,2000年の年齢階級では1つずつ上の階級へ移行する。もし,上記年齢階級別死亡率が一定であると,その後の人口集団は実際とは異なった集団となる。このときに,その主要死因における死亡率(仮定死亡率)を実際の死亡率と比較し,その相違について検討した。
結果 1985~2000年における5年ごとの50歳以上の人口変化は,男女とも全年齢階級が増加傾向で,年齢階級別の死亡数分布は高齢者ほど近年に増加した。人口変化を仮定人口と比較すると,仮定人口でも増加傾向にはあるが,85歳以上の高齢者人口の増加が著しかった。主要死因別にみると,悪性新生物では,粗死亡率は実際の死亡率の方が男女とも上昇傾向が著しかったが,女子の年齢調整死亡率については,実際の死亡率の方が仮定死亡率より低く,上昇傾向にもなかった。心疾患や脳血管疾患について,仮定死亡率は粗死亡率,年齢調整死亡率の男女とも上昇傾向,実際の死亡率は年齢調整死亡率が男女とも低下傾向であった。肺炎について,粗死亡率では男女とも実際の死亡率の方が上昇が著しかった。一方,年齢調整死亡率では1990年には両死亡率に差がなかったが,2000年には実際の死亡率が仮定の死亡率よりも低下した。肝疾患については,男女の粗死亡率,年齢調整死亡率とも,仮定死亡率は上昇傾向,実際の死亡率は低下傾向を示した。不慮の事故,自殺については,いずれも顕著な傾向がなく,実際と仮定の両死亡率間でも明確な相違は認められなかった。
結論 女子の悪性新生物や男女の心疾患,脳血管疾患,肝疾患の死亡については,1985年の時点に比べてわが国の健康対策に効果のあったことが推察された。肺炎については効果は1995年以降に認められた。一方,不慮の事故,自殺においては1985年の時点と変化の傾向が明確でないために効果が明らかでなく,死因により効果の違いが推察された。
キーワード 高齢者,死亡率,経年変化,人口変化
|
第53巻第5号 2006年5月 受療状況が要介護認定率の地域差に及ぼす影響中村 秀恒(ナカムラ ヒデチカ) |
目的 介護給付費と強い相関のある要介護認定率には都道府県格差があり,特に軽度要介護認定率において地域格差が大きいが,生活習慣病は高齢期以前にも発症し後遺症を残すなど,後の高齢期における要介護状態のリスクとなると考えられ,要介護認定率の地域格差に影響を及ぼしている可能性が考えられることから,生活習慣病の患者の多さを表す指標の1つである高齢期前の受療率や要介護認定率に影響を与えると考えられるその他の要因について,要介護認定率との相関を調べ,地域格差の要因について明らかにすることを目的とした。
方法 要介護認定率の地域格差に影響を及ぼすと考えられる要因として,病床数,介護保険3施設数・定員数,居宅介護サービス登録数,高齢単身者割合,2次判定変更率について,都道府県別の軽度・重度要介護認定率との相関を検討した。次に,厚生労働省「患者調査」から,要介護状態に結びつく可能性の高い傷病大分類(新生物,精神障害,循環器系の疾患,高血圧性疾患,虚血性心疾患,脳血管疾患,筋骨格系疾患,糖尿病,骨折)について,調査7回分平均の受療率(65歳未満)と都道府県別の軽度・重度認定率との相関を検討した。
結果 軽度要介護認定率については,施設関連の指標,居宅介護サービス登録数の一部,高齢者単身者割合,2次判定軽度変更率,外来受療率(総数,新生物,糖尿病),入院受療率(高血圧性疾患,糖尿病)と正の相関が,2次判定重度変更率と負の相関がみられた。重度要介護認定率については,外来受療率(新生物,精神障害,循環器系の疾患,高血圧性疾患,脳血管疾患),入院受療率(総数,新生物,循環器系の疾患,高血圧性疾患,脳血管疾患,筋骨格系疾患,糖尿病)と正の相関が,居宅介護サービス登録数のうちでショートステイ(医療)のみと負の相関がみられた。重度要介護認定率と入院受療率(循環器系の疾患,脳血管疾患)でやや強い相関関係がみられた。
結論 要介護認定率の地域差について,軽度要介護認定率についてはサービス供給状況,申請率,審査判定,単身,受療率などの人為的因子や社会背景などの違いが要因の可能性として考えられたが,重度要介護認定率については違う要因が考えられ,高齢期以前の循環器系の疾患や脳血管疾患などの生活習慣病の発生・悪化によって影響を受ける可能性があると考えられた。また,要介護者の増加や重度化を防ぐためには,高齢者に対する介護予防事業のほかに,高齢期以前の生活習慣病の発症予防や重症化予防のための対策の有効性が示唆された。
キーワード 要介護認定率,受療率,地域格差,介護保険,生活習慣病,介護予防
|
第53巻第6号 2006年6月 高次脳機能障害と社会福祉施設の利用に関する研究進士 恵実(シンジ メグミ) 中村 考一(ナカムラ コウイチ) 寺島 彰(テラシマ アキラ) |
目的 高次脳機能障害とは,頭部外傷や脳血管障害などによる脳の損傷の後遺症として記憶障害や遂行機能障害などが起きることである。本研究では,全国の社会福祉施設を利用している高次脳機能障害者の現状や具体的な支援の内容を検討した。
方法 一次調査では,全国の身体障害または精神障害施設(計428施設)に対して高次脳機能障害者の有無と人数,施設概要などに関する調査票を郵送した。次に,一次調査において高次脳機能障害のある人がいると答えた施設に対する二次調査として,その高次脳機能障害者1人1人に関する属性や支援内容などに関する調査票を郵送した。
結果 一次調査では294施設から調査票を回収した(回収率69%)。高次脳機能障害者がいると答えた施設は218施設,いないと答えた施設は76施設であった。高次脳機能障害者がいると答えた218施設中,20人未満の施設が139施設であった。入所と通所の合計利用人数に占める高次脳機能障害者の割合が0~19%の施設は82施設(38%),20~39%の施設は66施設(30%)であった。二次調査では,一次調査において高次脳機能障害者がいると答えた施設の対象者(2,553名)中,1,235名から回答が得られた。施設で実施されている様々な支援に関して,支援の必要な人の割合を施設別に検討したところ,更生施設では「金銭管理」「服薬」「訓練・作業に関する動機付け」において割合が高かった。授産施設のうち,身体障害者通所授産施設と重度身体障害者授産施設では「訓練・作業に関する動機付け」に関する支援が多く必要とされ,重度身体障害者授産施設と身体障害者授産施設では「服薬」などの健康管理に関する項目と「金銭管理」に関して支援が多く必要とされていた。身体障害者療護施設では,身体介助や生活援助や健康管理の多くの項目で支援を必要としている人が多かった。
結論 わが国において高次脳機能障害のある人が既に様々な施設で支援を受けている状況が明らかになった。また,当事者のコミュニケーションスキルや発動性を高めるための支援や服薬管理を中心とする健康管理が必要とされていることが明らかになった。
キーワード 高次脳機能障害,社会福祉施設,支援内容
|
第53巻第6号 2006年6月 保育園を利用する2歳児の発達・社会適応・
|
目的 保育園を利用する2歳児の発達・社会適応・問題行動・健康状態について,母親のストレスに焦点をあてて,保育サービスの特性,育児環境,インフォーマルサポート,保護者の特性,子どもの特性の複合的な関連を明らかにする。
方法 全国の認可保育園87カ所において,保護者と園児の担当保育専門職に質問紙調査を実施し,両者のデータが揃った2歳児394名を分析対象とした。
結果 (1)母親のストレスと有意な関連が認められた項目は,育児環境の「本を読み聞かせる機会」「子どもをたたく頻度」「知人との交流の機会」,インフォーマルサポートの「育児相談者の有無」「配偶者と子どもの話をする機会」,保護者の特性の「育児に対する自信」,子どもの特性の「きょうだいの有無」であり,ストレス高群に育児環境,インフォーマルサポート,育児に対する自信におけるリスクの割合が多かった。きょうだいにおいては,ストレス非高群に一人っ子が多かった。(2)性別調整後の関連要因は,「保育時間」が11時間以上の場合に「理解」のリスクが0.3倍,「入園年齢」が1歳未満の場合に「対人技術」のリスクが0.4倍,「コミュニケ-ション」のリスクが0.2倍,「理解」のリスクが0.4倍,「一緒に遊ぶ機会」がめったにない場合に「粗大運動」のリスクが39.7倍,「一緒に歌う機会」がめったにない場合に「生活リズムの乱れ」のリスクが15.5倍,「配偶者の育児協力」がめったにない場合に「対人技術」のリスクが3.7倍,「微細運動」のリスクが4.3倍,「育児相談者」がいない場合に「対人技術」のリスクが10.2倍,「育児支援者」がいない場合に「対人技術」のリスクが2.9倍,有意に高くなる関連を示した。(3)多重ロジスティック回帰分析では,1歳以上の入園を1とした場合,1歳未満の入園では「生活技術」のリスクは0.1倍,「対人技術」のリスクは0.3倍,「コミュニケーション」のリスクは0.2倍,「理解」のリスクは0.4倍であった。きょうだいがいる場合を1とした場合,一人っ子では「対人技術」のリスクは0.4倍,育児相談者がいる場合を1とすると,いない場合は「対人技術」のリスクは12.4倍であった。また,子どもと一緒に歌を歌う機会がある場合を1とすると,めったにない場合では「生活リズムの乱れ」のリスクは13.6倍であった。
結論 母親のストレスには,育児環境やインフォーマルサポート,育児に対する自信,子どものきょうだいの有無と強い関連がみられた。複合分析では,保育の特性の入園年齢や子どもの特性のきょうだいの有無,インフォーマルサポート,育児環境の人的かかわりが,子どもの発達や健康状態に強く関連していたことから,子育て支援においては,相談機能の充実に加え,バラエティに富むかかわりが持てるような育児環境の整備や育児に対する自信が持てるよう,母親のストレス軽減に向けた援助が必要である。
キーワード 子どもの発達,母親のストレス,育児環境,育児に対する自信,保育サービス
|
第53巻第6号 2006年6月 2005/06年シーズンにおける
延原 弘章(ノブハラ ヒロアキ) 渡辺 由美(ワタナベ ユミ) |
目的 インフルエンザワクチンの計画的な供給に資することを目的として,2005/06年シーズンのインフルエンザワクチンの需要予測を行った。
方法 インフルエンザワクチン供給に実績のある医療機関など5,083施設を対象として,2004/05年シーズンのインフルエンザワクチンの購入本数,使用本数,接種状況および2005/06年シーズンの接種見込人数について調査を行い,2005/06年シーズンのインフルエンザワクチン需要見込本数の推計を行った。
結果 2005/06年シーズンのインフルエンザワクチン需要は,約2087万本から約2155万本と推計された。
結論 2005/06年シーズンのワクチンメーカーの製造予定数は最大で2150万本であり,ほぼ需要に見合う量の供給が行われるものと推測された。
キーワード インフルエンザワクチン,需要予測
|
第53巻第6号 2006年6月 介護職員に起因するストレスが施設高齢者の
桐野 匡史(キリノ マサフミ) 柳 漢守(ユ ハンス) 濵口 晋(ハマグチ ススム) |
目的 施設高齢者に対する精神保健的なアプローチの確立に向けた基礎的資料を得ることをねらいに,介護職員に起因するストレスが施設高齢者の精神的健康に与える影響を検討する。
方法 調査対象は,S県内の介護老人保健施設51カ所と介護老人福祉施設13カ所に入居している高齢者のうち,施設職員によって自記式質問紙に回答できると判断された296人であった。調査内容は,施設高齢者の性,年齢,施設利用年数,介護職員に起因するストレス,精神的健康で構成した。介護職員に起因するストレスは,著者らが独自に作成した15項目で測定した。精神的健康の測定には,抑うつ性尺度であるZung's Self-Rating Depression Scale(SDS)を使用した。統計解析は,介護職員に起因するストレスを独立変数,精神的健康(抑うつ性)を従属変数とする因果関係モデルを構築し,構造方程式モデリングにより検討した。
結果 介護職員に起因するストレスは,施設高齢者の抑うつ性と強く関連することが明らかになった。また,施設高齢者の性,年齢,施設利用年数,介護職員に起因するストレスの抑うつ性に対する説明率は56.7%であった。
結論 介護職員によるストレスの軽減,すなわち施設高齢者に対する精神保健上の配慮が介護職員においてより強く望まれることが示唆された。施設高齢者の人権保障や生活の質の向上を図るうえで,利用者の精神保健上の配慮を強調した総合的な施設環境整備を推進していくことが必要である。
キーワード 施設高齢者,対人ストレス,精神的健康,介護職員
|
第53巻第6号 2006年6月 脳卒中データバンク(JSSRS)による
汐月 博之(シオツキ ヒロユキ) 大櫛 陽一(オオグシ ヨウイチ) 伏見 清秀(フシミ キヨヒデ) |
目的 脳卒中発症患者におけるアルコール摂取量と重症度の関係についての報告はほとんど見かけないことから,全国規模の脳卒中患者データベース(JSSRS)による患者データを用いて,脳梗塞発症患者の過去の飲酒量と入院時重症度,退院時重症度,そして退院時の認知症との関連を調べることを目的とした。
方法 JSSRSの登録患者データ中,脳梗塞発症患者9,991例を対象として,過去のアルコール摂取量を,「0:ほとんど飲まない,1:機会飲酒,2:毎日1~2合,3:毎日2~3合,4:毎日3合以上,5:大酒家」と順序データ化し,アルコール摂取量と入院時重症度,退院時重症度,退院時の認知症発症の関係について,統計的手法により有意なアルコール摂取量を特定した。その際,多重比較の欠点を補うため,p<0.001を真の有意差とした。
結果 (1)入院時重症度は,アルコール摂取量が「ほとんど飲まない,大酒家>機会飲酒,毎日3合以上>毎日1~2合,毎日2~3合」の順で良くない傾向があった(p<0.05)。(2)退院時重症度は,アルコール摂取量が「ほとんど飲まない,大酒家>機会飲酒,毎日3合以上>毎日1~2合,毎日2~3合」の順で良くなかった(p<0.001)。(3)退院時の認知症発症は,アルコール摂取量が「ほとんど飲まない,大酒家>機会飲酒,毎日3合以上>毎日1~2合,毎日2~3合」の順で高かった(p<0.001)。
結論 アルコール摂取量と入院時重症度の明確な関連はみられなかったが,退院時重症度と退院時の認知症の存在はアルコール摂取量との間にJカーブ(Uカーブ)現象を示し,適度な飲酒(毎日1~3合まで)をしていた者は退院時の重症度や認知症への影響が有意に低かった。また,これらの者は在院日数も有意に短かった。
キーワード 脳梗塞,アルコール,予後,重症度,Jカーブ,リスク
|
第53巻第7号 2006年7月 救急救命士の疲労とストレスに関する基礎調査細田 武伸(ホソダ タケノブ) 谷垣 靜子(タニガキ シズコ) 原口 由紀子(ハラグチ ユキコ)仁科 祐子(ニシナ ユウコ) 宮階 ひとみ(ミヤガイ ヒトミ) 渡辺 勝也(ワタナベ カツヤ) 橋本 健治(ハシモト ケンジ) 武本 和之(タケモト カズユキ) 細田 多紀子(ホソダ タキコ) 穆 浩正(ムー コウセイ) 小谷 和彦(コタニ カズヒコ) 黒沢 洋一(クロザワ ヨウイチ) 能勢 隆之(ノセ タカユキ) |
目的 近年の救急出場件数の増加により,救急隊員という職域集団の身体的・精神的疲労やストレスの増大が問題となっている。このため,鳥取県西部広域行政管理組合消防局の救急救命士(救急専従職員)を対象として健康状態,疲労,ストレスと救急出場件数および夜間出場件数との関連を調査することを目的とした。
方法 ストレス尺度と質問項目を選ぶため,平成16年7月に調査対象者(救急救命士)の中から年齢,勤続年数,前年度出場件数等が平均的である5名に半構造化面接による事前調査を行った。その結果をもとに「NIOSH職業性ストレス調査票」から14の尺度と88の質問項目を抽出した。次に疲労とストレスを調査するため,平成16年9~10月に消防署および出張所において,勤務前後に健康調査,アンケート調査「自覚症調べ」「CFSI(疲労徴候インデックス)」「NIOSH職業性ストレス調査票(事前調査で抽出した項目)」,フリッカーテストおよび血圧測定を行った。救急出場件数は,後日,救急活動報告書から調べた。
結果 救急出場件数が増加すると休憩・仮眠時間も少なくなり,勤務明けに一般的な疲労を訴えていた。また日常的に一般的な疲労と身体不調を訴えており精神的に不安兆候にある者が多かった。反面,慢性疲労の訴えは少なく労働意欲の低下を訴える者も少なかった。対象者は,勤務期間が最低でも15年の既婚者の男性集団であり,上司,同僚,家族・友人からのサポートが良好であり,かつ職場満足度も高いことから,現状の健康を維持していることが推測された。今後は,さらなる救急業務の増加と隊員の高齢化に備える必要があると思われた。
結論 現状では,すぐに入院加療を要するほどの者はいなかった。しかし,今後,職員の高齢化や業務の多忙さにより,疲労とストレスの程度は増加することが予想され,実態の把握を続けるとともに,消防職員委員会を活用して現場の実態を上層部に届けやすくするなど,業務および勤務状態の改善を図っていく必要があると思われた。
キーワード 救急救命士,疲労,ストレス
|
第53巻第7号 2006年7月 介護保険3施設における施設内医療処置の状況-公表統計データを用いた検討-竹迫 弥生(タケザコ ヤヨイ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) 梶井 英治(カジイ エイジ) |
目的 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設の介護保険3施設内で医療処置を受けている者の在所者全体に対する割合を医療処置の種類別に明らかにする。
方法 厚生労働省が2001年に行った全国調査の公表データをもとに,施設種別ごと,要介護度別に,介護保険3施設内で行われた医療処置の状況について比較検討した。
結果 医療処置を受けている者の在所者全体に対する割合は,介護老人福祉施設と介護老人保健施設で約2割,介護療養型医療施設で約4割であった。3施設ともに,要介護1~4の在所者では,医療処置を受ける者の割合は全体の3割以下であり,処置の内容としては,疼痛管理,モニター測定,点滴,膀胱カテーテルなどが高かった。一方,要介護5の在所者では,介護老人福祉施設と介護老人保健施設で3割,介護療養型医療施設で6割の者が医療処置を受けており,処置の内容としては,経管栄養と喀痰吸引の割合が高かった。また,経管栄養と喀痰吸引の処置を受けている者の割合は,在所者全体でも,要介護5の在所者のみでも,介護老人保健施設より介護老人福祉施設の方が高かった。
結論 施設内で何らかの医療処置を受けている在所者の割合は,介護療養型医療施設が介護老人福祉施設および介護老人保健施設の約2倍であった。しかし,経管栄養と喀痰吸引の処置を受けている在所者の割合は,医療職員の少ない介護老人福祉施設の方が介護老人保健施設より高く,今後の課題と考えられた。
キーワード 介護保険施設,ナーシングホーム,医療処置,経管栄養,疼痛,褥瘡
|
第53巻第7号 2006年7月 地域がん登録事業におけるがん患者の
田中 英夫(タナカ ヒデオ) |
目的 個人情報保護法制定に伴い,保健,衛生分野における個人情報の第三者提供のあり方に対する関心が高まっている。地域がん登録事業におけるがん患者の登録拒否に関し,法的,実務的,倫理的側面から検討する。
方法 個人情報保護法の内容を医療・介護関係事業者用のルールとしてまとめられた「医療・介護ガイドライン」を法的検討の対象とする。次に,地域がん登録事業にかかわる当事者間で扱う個人情報の流れを踏まえ,もし同事業に患者の登録拒否の意思表明を反映させる(オプトアウト)とすると,実務面でどのような状況が起きるかについて検討した。また,登録拒否という行為を,複数の倫理的価値の対立面から考察した。
結果 「医療・介護ガイドライン」が示す個人情報の第三者提供に際しての本人同意原則の除外事例(地域がん登録でのがん患者,がん検診の精度管理での要精検者,児童虐待での親,医療事故調査での被害患者)は,いずれも共通してオプトアウトの容認と事業目的の遂行が両立し難い性質のものであると考えられることから,ガイドラインの意図に沿えば,同意認定手段としてのがん患者の拒否の有無の確認の効力は発生していないと考えられた。オプトアウトを地域がん登録事業に導入すると,その実効性の確保のためには拒否者の個人識別情報を登録する必要が生じ,また拒否の内容,範囲によって,情報の取り扱いに関する相当の負担を医療現場に強いることが予測された。倫理的価値の対立としては,①オプトアウトの権利を行使した患者の自律性と,事業成果の減損およびオプトアウト制度の維持にかかるコストの負担とのバランス,②オプトアウトの権利を行使する患者と行使しない患者の間に生じる受益と負担のバランスの不平等が考えられた。
結論 地域がん登録事業におけるオプトアウトの容認は,現行法の枠内では予定されない考えであると思われた。また,もし実行に移した場合,実務面での障害が相当程度生じることが予測されるとともに新たな倫理的価値の対立を生むことが予想された。
キーワード 地域がん登録事業,個人情報保護法,第三者提供,オプトアウト,本人同意原則,倫理
|
第53巻第7号 2006年7月 食事の多様性と生活習慣,食品・栄養素摂取量との関連-厚生労働省研究班による多目的コホート研究-小林 実夏(コバヤシ ミナツ) 津金 昌一郎(ツガネ ショウイチロウ) |
目的 住民ベースの大規模コホート研究(JPHC Study)5年後調査の断面データを用いて,多様な食品を摂取することと生活習慣,食品・栄養素摂取量との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 対象者は1995年から1999年の間に44~76歳であった全国11保健所管内に居住する42,227名の男性と51,345名の女性である。自記式質問票により,既往歴,飲酒,喫煙状況,運動習慣,食習慣,食品摂取量などの情報を収集した。質問票に掲載されている133食品項目について,1日に何食品を摂取しているか算出した。1日に摂取する食品の種類を5分位に分類し,群ごとの生活習慣,食品・栄養素摂取量を比較した。
結果 摂取食品数が多くなるほど,肥満ややせが少ない,喫煙率が低い,飲酒量が少ない,朝食の欠食率が少ない,習慣的な運動習慣があるなど,健康的な生活習慣との関連が明らかになった。また,摂取食品数が多くなるほど,一人暮らしの割合が少ない,生活を楽しいと感じている人が多いなどの特徴が明らかになった。一方,多様な食品を摂取する群ほどエネルギー摂取量は多く,栄養素・食品群摂取量も多く摂取しているものが多かったが、炭水化物,穀類,砂糖類の摂取は低く,アルコールや嗜好飲料の摂取も低かった。
結論 1日に摂取する食品に多様性があることは,健康的な生活習慣と関連があることが明らかになった。また,多様な食品を摂取することと食物・栄養素摂取状況との関連も明らかになった。
キーワード 食事の多様性,生活習慣,食品・栄養素摂取,コホート
|
第53巻第7号 2006年7月 特別養護老人ホームの待機者の
岸田 研作(キシダ ケンサク) 谷垣 靜子(タニガキ シズコ) |
目的 特別養護老人ホーム(以下,特養)の待機者の入所希望時期に影響する要因を明らかにすること。
方法 対象は,中国地方のA市に在住する無作為に抽出された500の特養待機者世帯である。調査時期は2004年10月で,調査方法は郵送自記式である。分析は,入所希望時期を被説明事象,世帯属性を独立変数とする順序ロジスティック回帰分析で行った。
結果 解析の対象となったのは,必要な変数に欠損値がない199世帯である(有効回収率39.8%)。在宅の待機者は,27.6%であった。入所希望時期の内訳は,「すぐにでも入所したい」(30.2%),「できるだけ早く入所したい」(23.1%),「しばらくは待つことができる」(17.6%),「将来,必要になったときに入所したい」(29.1%)であった。早期の入所希望と関連していたのは,待機場所が老人保健施設または一般の病院であること,要介護度が3以上であることであった。待機者本人の性別,年齢,世帯形態,待機期間,調査票記入者の属性と入所希望時期との関連はみられなかった。
考察 「将来,必要になったときに入所したい」と答えた者は,入所の順番が現時点でまわってきてもすぐには入所しないと考えられる。したがって,入所希望時期を尋ねることで予約的な入所申請者を把握することは,計画的な施設整備を行う上で有益である。老人保健施設や一般の病院での待機者世帯が早期の入所を希望する理由として,病院・施設から退所勧告を受けている可能性が考えられる。また,要介護度が高い場合に早期の入所を希望した。これは,在宅待機者の場合,家族の介護負担が大きいことを反映し,在宅外待機者の場合,要介護度が高い者の家族がすでに在宅介護を断念していることを反映していると考えられる。
キーワード 特別養護老人ホーム,待機者,入所希望時期,順序ロジスティック回帰分析
|
第53巻第8号 2006年8月 家族の介護意識と要介護者の自己決定阻害の関係に関する研究-高齢者虐待の予防に向けて-安梅 勅江(アンメ トキエ) 鈴木 英子(スズキ エイコ) |
目的 高齢者虐待の予防のため,要介護者の自己決定阻害に焦点をあて,住民の介護意識,要介護者の自己決定阻害に関する意識および両者の関連を明らかにすることを目的とした。
方法 平成12年に中部地方の大都市近郊の農村Sに在住する20歳以上の全住民を対象に質問紙調査を実施し,2,998名(有効回答率84.7%)から回答を得た。調査内容は,要介護者の自己決定の阻害に関連する意識と考えられる3項目(要介護者は「家族の意見に従うべき」「我慢すべき」「自己主張すべきでない」),介護意識4項目(「介護受容」「家族介護負担感」「世間体意識」「家族優先意識」),属性,介護の要不要,家族内の要介護者の有無,身体症状,入院・通院歴,日常生活動作能力,社会関連性,体力イメージ,サービス満足度,過去1年間のライフイベントであった。
結果 1)年齢・性別,要介護者の有無別,介護状態別に分析した結果,自己決定の阻害に関連する意識の割合は高年齢世代,介護経験あり,世間体を気にする場合に多くなっていた。2)自己決定の阻害に関連する意識を目的変数とし,多重ロジスティック回帰分析を行った結果,いずれも「介護受容」「世間体意識」「家族介護負担感」「家族優先意識」のある場合に,ない場合に比較して要介護者は「家族の意見に従うべき」「我慢すべき」「自己主張すべきでない」とするオッズ比が高くなっていた。
結論 すべての地域住民を対象とした要介護者の自己決定を尊重するための啓発や,介護負担を軽減するためのサポート,介護の理解を深めるための情報提供や教育などが,地域における虐待リスクの軽減に有効である可能性が示唆された。
キーワード 高齢者虐待,自己決定,家族介護,予防
|
第53巻第8号 2006年8月 パンデミック時の抗ウイルス剤およびワクチンの
大日 康史(オオクサ ヤスシ) 菅原 民枝(スガワラ タミエ) 谷口 清州(タニグチ キヨス) |
目的 新型インフルエンザのパンデミック時には,抗インフルエンザウイルス薬や新型インフルエンザ用のワクチンが不足することが予想され,そのために治療あるいは予防のための薬剤の使用に関する優先順位付けを事前に行っておくことが重要となることから,現状での国民の意思を把握するために,一般住民調査を通じて優先順位について検討した。
対象と方法 2005年4月上旬に全国において実施された調査における回答を分析した。調査内容は,12種類の人ロ集団に対して,優先順位付けを1位から12位まで行うことを求めた。分析は優先順位について各順位での支配的な人口集団の分析と,代表的な人ロ集団である「高齢者」「妊婦,乳児の母親」「乳幼児・小学生」の最優先人口集団の選択に関する分析を行った。
結果 調査票は880世帯に送付し,772世帯の20歳以上の成人1,220人から回収を得た。優先順位付けに関しては,賛成,反対,わからないがほぼ同数であった。1つ目の分析である優先順位は,第1位「乳幼児・小学生」,第2位「妊婦」,第3位「乳児の母親」,第4位「医療従事者」,第5位「60歳未満の慢性肺疾患患者,心疾患患者,腎疾患患者,代謝異常患者,免疫不全状態の患者」,第6位「特別養護老人ホーム・老人保健施設などの従業員」,第7位「健康な高齢者(65歳以上)」,第8位「警察・消防関係者」,第9位「通信・交通・電力・エネルギー業界関係者」,第10位「行政担当者」,第11位「他の項目に当てはまる人を除く健康な13歳以上65歳未満の人」,第12位「60歳以上の慢性肺疾患患者,心疾患患者,腎疾患患者,代謝異常患者,免疫不全状態の患者」,の順で選択されていた。また,医療従事者と60歳未満の慢性肺疾患患者,心疾患患者,腎疾患患者,代謝異常患者,免疫不全状態の患者,特別養護老人ホーム・老人保健施設などの従業員と健康な高齢者(65歳以上),警察・消防関係者と通信・交通・電力・エネルギー業界関係者の間には有意な差はないので同じ順位であった。また,この順位は抗インフルエンザウイルス剤,ワクチン接種の場合で共通であった。2つ目の分析である代表的な人口集団における最優先人口集団に関する推定結果は,抗インフルエンザウイルス剤とワクチン接種において,優先順位で「幼児・小学生」を最優先とする確率は,幼児・小学生の同居家族はそうでない場合よりも,抗インフルエンザウイルス剤では9.7ポイント,ワクチン接種では8.0ポイント高かった。逆に,「高齢者」を最優先とする確率は,高齢者はそうでない者よりも抗インフルエンザウイルス剤では4.7ポイント,ワクチン接種では4.8ポイント高かった。
結論 調査結果は,オランダでの優先順位に関する研究とは整合的であるが,新型インフルエンザ対策に関する検討小委員会報告での提言内容とは必ずしも整合的ではなかった。
キーワード パンデミックインフルエンザ,抗ウイルス剤,ワクチン,使用優先順位,パンデミックプラン
|
第53巻第8号 2006年8月 介護保険制度を利用した埼玉県の健康寿命の算出池田 祐子(イケダ ユウコ) 生嶋 昌子(イクシマ マサコ) 長谷川 紀美子(ハセガワ キミコ)徳留 明美(トクトメ アケ ミ) 高野 眞理子(タカノ マリコ) 峰岸 文江(ミネギシ フミエ) 丹野 瑳喜子(タンノ サキコ) 三浦 宜彦(ミウラ ヨシヒコ) |
目的 埼玉県では,新たな健康づくり行動計画「すこやか彩の国21プラン」を策定し,平成22年度を目標年とした健康づくり運動を推進中であり,このプランの達成度や効果が把握できる健康の総合指標として「埼玉県の健康寿命」を算出し,また同指標の算出が簡単に行えるソフトの作成を目的とする。
方法 生命表の作成にはChiangの方法を用い,「障害発生時点」を「介護保険制度における要介護等認定を受けた時点」としてとらえ,「要介護等認定を受けないで生活できる期間」を「健康寿命」とした。また,平均余命に対する健康寿命の割合を健康割合とし,埼玉県全体と県内医療圏(13)別に分析した。健康寿命算出ソフトの作成は,エクセルVBAマクロと関数を利用して行った。
結果 埼玉県の健康寿命は,65歳男性で14.73年,75歳で7.78年,65歳女性で16.35年,75歳で8.13年であった。65歳,75歳では女性の方が健康寿命が長いが,85歳になると,男性3.09年,女性2.43年と逆転した。健康割合は,65歳男性で84.5%,75歳で73.1%であるが,女性はそれぞれ73.4%,57.4%で,65歳,75歳ともに女性の方が低かった。医療圏別では,65歳健康寿命は男性が14.16~15.05年,女性が16.01~16.94年で,男女とも県南・県南東部で低かった。65歳健康割合は,男性が83.4~86.2%,女性が71.1~76.7%で,男女とも県北部で高かった。作成した健康寿命算出ソフトは,「埼玉県の健康寿命」をはじめ,平均寿命(余命)や健康割合などが医療圏別,市町村別に算出可能であり,最新データを追加することによって,今後も継続して活用することが可能である。
結論 介護保険制度を基に算出する健康寿命は,1)既存の統計資料の活用が可能であるため,継続的に算出可能で,経年評価ができる,2)全国的に統一された手順と基準に沿って要介護度の認定作業が行われていることから,自治体間の比較が可能である,3)健康づくり事業の達成度や効果が把握できる,などの特徴をもつ指標である。また,作成した健康寿命算出ソフトは,エクセル上で稼働し,低コスト,簡単操作であり,集団の健康指標算出ツールとして利便性が高いものと言える。
キーワード 介護保険制度,健康寿命,健康割合,健康寿命算出ソフト
|
第53巻第8号 2006年8月 家庭における乳幼児のタバコ曝露の実態-尿中ニコチン代謝物測定による検討-矢野 公一(ヤノ コウイチ) 花井 潤師(ハナイ ジュンシ) 福士 勝(フクシ マサル)菅原 有希(スガワラ ユキ) 毛利 優子(モウリ ユウコ) 高本 厚子(タカモト アツコ) 伊澤 栄子(イザワ エイコ) 藤田 晃三(フジタ コウゾウ) |
目的 家庭における乳幼児のタバコ曝露の実態を,尿中ニコチン代謝物の測定によって明らかにすることを目的とした。
方法 2004年9~11月,札幌市南保健センターでの乳幼児健診児を対象に,36家族(38児)の母と児の尿中ニコチン代謝物(コチニン)を測定した。
結果 喫煙する27家族中6家族の児がコチニン陽性であった。陽性児の母はすべて喫煙者で,コチニン陽性であった。母がコチニン陽性の児は20人で,このうち母乳栄養の9児中5児がコチニン陽性であった。一方,非母乳栄養の11児では1児のみがコチニン陽性であった。さらに,生尿と濾紙抽出液中の尿中コチニン濃度は良好な相関を示した。
結論 ①尿中ニコチン代謝物測定によって,乳幼児のタバコ曝露が明らかとなった。②ニコチンあるいはコチニンが母乳を介して児に移行することが示唆された。③濾紙尿を用いて乳幼児の尿中コチニンを測定することが可能となった。
キーワード 乳幼児,タバコ曝露,尿中コチニン,母乳栄養
|
第53巻第8号 2006年8月 施設入所高齢者におけるインフルエンザワクチンの
井手 三郎(イデ サブロウ) 児玉 寛子(コダマ ヒロコ) 高山 直子(タカヤマ ナオコ) |
目的 インフルエンザワクチンの臨床的効果のみならず,個人レベルで実際の費用と効果に関するデータを積み上げて,ワクチン接種の医療費削減効果を検討する。
方法 福岡県久留米市内の同一医療機関が設置する介護老人保健施設の入所者(2002/03シーズン)および医療型療養病棟の入院患者(2003/04シーズン)を対象として,インフルエンザ様疾患に対するワクチン接種の効果を生存時間解析により検討するとともに,罹患後の医療費削減効果を検討した。介護老人保健施設では89人(接種75,非接種14)を2003年1~3月の間,医療型療養病棟では92人(接種12,非接種80)を2003年12月~2004年3月の間,追跡観察した。
結果 1) 2002/03シーズンの介護老人保健施設では,インフルエンザ様疾患に対するワクチンの有効性は境界域の有意性を示した(ハザード比=0.41,95%信頼区間0.14-1.17,p=0.095)。医療行為の実施率や超過医療費は,接種群において低い傾向を示したが,有意差を検出するには至らなかった。2) 2003/04シーズンの医療型療養病棟では,ワクチン接種によりインフルエンザ様疾患の罹患率の低下傾向を観察したが,有意差を認めるには至らなかった(ハザード比=0.59,95%信頼区間0.07-4.73,p=0.619)。また超過医療費の削減傾向も観察された。3) 両シーズンの観察結果をプールした解析において,インフルエンザ様疾患に対するワクチンの有効性は境界域の有意性を示した(ハザード比=0.44,95%信頼区間0.17-1.12,p=0.084)。またワクチン接種は,インフルエンザ様疾患に関連する超過医療費を削減する傾向も観察された。その他,ハイリスク者においては超過医療費が増大することが観察された。
結論 例数は不十分であるものの,インフルエンザワクチンは施設入所高齢者のインフルエンザ様疾患罹患防止に約40~60%の有効率であることが示唆された。また,インフルエンザ様疾患に関連する医療費の削減が期待される。
キーワード インフルエンザワクチン,有効性,費用対効果,医療費削減効果,後ろ向きコーホート研究,疫学
|
第53巻第10号 2006年9月 要介護認定者の日常生活自立度と生命予後との関連寺西 敬子(テラニシ ケイコ) 下田 裕子(シモダ ユウコ) 新鞍 眞理子(ニイクラ マリコ)山田 雅奈恵(ヤマダ カナエ) 田村 一美(タムラ ヒトミ) 廣田 和美(ヒロタ カズミ) 神谷 貞子(カミヤ サダコ) 岩本 寛美(イワモト ヒロミ) 上坂 かず子(コウサカ カズコ) 成瀬 優知(ナルセ ユウチ) |
目的 要支援を含む新規要介護認定者において,性・年齢階級別に日常生活自立度と生命予後との関連を明らかにすることを目的とした。
方法 富山県のN郡3町村に居住し,2001 年4月から2004年12月に新規に要支援または要介護認定を受けた65歳以上の住民1,700人(男性616人,女性1,084人)を対象とした。介護 保険認定審査会資料より初回認定時の情報として性,年齢,障害老人の日常生活自立度(ランクJ,A,B,C),主治医意見書に記載された診断名,2005 年3月現在の転帰(生存,転出,死亡)を把握した。初回認定時の日常生活自立度別の累積生存率を,性・年齢階級別(65~74歳,75~84歳,85歳以 上)にKaplan-Meier法を用いて算出した。生存曲線の有意性の検定にはlog-rank検定を行った。また,性・年齢階級別に診断名と初回認定 時の年齢を共変量としたCoxの比例ハザードモデルを用いて,ランクJを基準とした日常生活自立度の死亡に対するハザード比を求めた。
結果 男性の65~74 歳,75~84歳,85歳以上の各年齢階級において日常生活自立度の違いによって累積生存率は有意に異なっていた。同様に女性の各年齢階級においても有意 に異なっていた。性・年齢階級別にそれぞれのランクJを基準として各日常生活自立度の死亡ハザード比を求めると,男女共に85歳以上以外の年齢階級で,ラ ンクCが最も高い死亡ハザード比を有意に示すことが共通して明らかとなった。一方で,日常生活自立度の程度の低下による死亡ハザード比の上昇は性・年齢階 級別に異なる特徴を示し,年齢階級が上がると日常生活自立度の低さによる死亡ハザード比の上昇の程度が小さくなる傾向が,女性は男性よりも日常生活自立度 の違いによる死亡ハザード比の格差が小さい傾向が明らかとなった。
結論 要支援を含む要介護認定者の初回認定時の日常生活自立度の程度は,性・年齢階級別に解析し,診断名を調整しても生命予後と関連していることが明らかとなった。また,その関連は性・年齢階級別に異なっていた。
キーワード 要介護認定,日常生活自立度,生命予後
|
第53巻第10号 2006年9月 グループホームにおける“家庭的”
前田 享史(マエダ タカフミ) 金子 信也(カネコ シンヤ) 永幡 幸司(ナガハタ コウジ) |
目的 グループホームの施設職員が認識する“家庭的”な生活・環境を構成する 要素を,“家庭”を構成する要素と比較検討することによって,どのような生活・環境要素がグループホームにとって必要なのか,また,それらの要素間でどの ような関係性があるのかを明らかにすることを目的とした。
方法 宮城県グループホーム協議会に所属するグループホームの管理者および主任介護員5名を対象とし,ブレインストーミングを用いて,“家庭”と“家庭的”に関する要素(ことば・単語・行為・環境など)の抽出を行い,分類整理した。
結果 “家庭”と“家庭的”の要素は,食,入浴・トイレ,睡眠,生活様式,外出,買い物,場,趣味・嗜好,物,交流,関係性,絆などに分類され,さらに自由,役割・義務,愛着対象,人間関係,その他の5つに大きく分類された。自由は,“家庭”で16 要素,“家庭的”で38要素が抽出された。「外食ができる」は,“家庭”のみでみられた。役割・義務は,“家庭”で10要素,“家庭的”で6要素,愛着対 象は,“家庭”で18要素,“家庭的”で9要素,人間関係は,“家庭”で51要素,“家庭的”で20要素であった。“家庭”では,家族や家族との交流や絆 を表す要素が多く抽出された。一方,“家庭的”では「一緒に~する」という行為を表す要素が多く抽出された。また,“家庭”では笑いや未来のことを表す言 葉が挙げられていた。心配してくれる人の存在を表す要素は,“家庭”と同様“家庭的”でも抽出された。その他では,“家庭”では家族旅行などの非日常的な 事柄が抽出されたが,“家庭的”では逆に「大規模な行事をあまりしない」が抽出された。また,“家庭”では「ストレス解消できる」という意見が抽出され た。
結論 “家庭的”では,「自由」を連想させる要素が多く含まれたのに対し, “家庭”では,「家族」「人間関係」「交流」を連想させる要素が多く含まれた。グループホームの環境づくりにおいて,施設管理者などの自由に対する認識の 高さを反映していると考えられた。また,外食も含めた近所や周辺地域との積極的な交流や入所者である認知症高齢者のストレスマネジメントの必要性が考えら れた。
キーワード 認知症高齢者,ホームライク,QOL,ブレインストーミング,KJ法
|
第53巻第10号 2006年9月 老人医療費と介護費の類似した
堀 真奈美(ホリ マナミ) 印南 一路(インナミ イチロ) 古城 隆雄(コジョウ タカオ) |
目的 肥満は生活習慣病の原因として重要であり,生命予後を含めた健康の悪化要因とされる。この肥満および体重変化が10年後の健康に及ぼす影響を,職域の定期健診結果と5年間の終末期を除く医療費を指標として検討した。
方法 対象は1992年度に定期健康診断を受けた40~59歳の男性で,2004年度末にも健在で健保に加入していた6,867名と,この間に死亡を理由に健保を脱退した182名である。医療費は終末期の高額医療費を除くために1999~2003年度の5年間の診療報酬明細書から医科と調剤を用いて算出した。
結果 1992~1994年度の3年間の平均体重で求めたBMIを5分位で検討すると,医療費はBMIが大きいほど高額であった。年齢調整累積死亡率が最も低かったのはBMI20.9~22.3の群であった。2001~2003年度までの10年間の体重変化を5分位で検討すると,体重減少が最も大きい群で医療費は高額であった。観察開始時のBMIで3群に分けて体重変化と医療費の関係をみても,体重の大きな減少は高額医療費と関連していた。最も医療費が少ないのは,観察開始時BMIが小さい群では約3㎏増加,大きい群では約1㎏低下する群であった。糖尿病では,観察開始時の肥満度に関係なく体重増加は高額医療費と関連した。高額医療費を示す主な保険主傷病名は,虚血性心疾患,脳血管疾患,悪性新生物,高血圧などであり,糖尿病では体重増加にしたがってこれらの疾患頻度は増加傾向にあった。喫煙に関しては,10年間の観察期間中の新たな禁煙群が最も医療費は大きかったが,この群で多くみられる体重増加は医療費に関係しなかった。
結論 肥満は10年後の終末期を除く医療費を高額とした。死亡率が低かったのはBMI21~22の群であった。10年間の体重の減少は医療費を高額とした。体重低下と高額の医療費は重大な疾患に罹患したための二次的なものと考えるのが妥当である。禁煙による体重増加は医療費を増加させなかった。これらから男性では,「中年までの肥満の予防が重要であること」「BMI22~23を目標とした体重管理が好ましいこと」「糖尿病では体重の増加は高額の医療費をもたらすこと」「意図した体重の管理が重要であること」などが示唆される。今後,意図した体重減少が長期的な健康に好ましいことを証明する研究が必要である。
キーワード 肥満,体重変化,定期健診,診療報酬明細書(レセプト),医療費,喫煙
|
第53巻第10号 2006年9月 地域在住高齢者における車両スピード認知
内田 勇人(ウチダ ハヤト) 朝居 由香里(アサイ ユカリ) 藤原 佳典(フジワラ ヨシノリ) |
目的 近年,公衆衛生領域では周産期の母親へのメンタルヘルス支援を行い,効果を挙げているが,ドメスティックバイオレンス(以下,DV)など多くの困難な出来事にさらされることによるメンタルヘルスの影響や,その援助への検討はいまだに取り組まれていない。そのため様々な困難を抱えているであろう母子生活支援施設入所者を対象として,どのような支援が有効であるのかを明らかにすることを目的に調査を行った。
方法 東京都内母子生活支援施設(以下,支援施設)に入所中で調査協力の得られた母親を対象とし,自記式アンケート調査(匿名郵送回収)を行った。調査項目は,基本的属性,ソーシャルサポート,メンタルヘルス(うつ評価尺度・解離性体験尺度),母親の子どもへの愛着(愛着形成障害評価尺度),子どもへの不適切な育児,実家との関係,パートナーとの関係など多面的な項目を設定した。解析方法は抑うつの有無を独立変数に,従属変数として量的変数にはt検定,質的変数にはχ2検定(Exact-Test)を用いた。抑うつの要因については抑うつ傾向得点との関連が有意であった変数を独立変数,不適切な育児得点を従属変数として,強制投入法による重回帰分析を行った。
結果 143名から回答を得た。調査結果から対象者の半数(49%)に抑うつ傾向がみられた。また入所者の67.4%がパートナーからの被暴力経験を持ち,95%がパートナーとの関係に葛藤性を抱えていた。抑うつ傾向と各項目間では,ソーシャルサポート(がない),実家との関係(被虐待経験),解離傾向の有無,愛着障害得点,不適切な育児得点とに関連がみられた。抑うつ傾向は子どもへの愛着障害にも影響し,さらに子どもへの攻撃性や放置などの育児行為にも影響していた。
結論 支援施設入所者の就労割合は78.9%と高く,その約半数が抑うつ傾向を持ちつつ就労しており,生活・育児面にかなりの困難さを有しているであろうことが推測されたが,調査結果からも子どもへの愛着や不適切な育児への影響が確認された。DVなどをはじめ,様々な困難を抱える母親には,子どもへの影響および世代間連鎖を阻止する視点からも,メンタルケアを含め経済・生活面への総合的支援が必要であることが示された。
キーワード 母子生活支援施設,抑うつ,ソーシャルサポート,愛着障害,不適切な育児,メンタルケア
|
第53巻第11号 2006年10月 一保健所管内の小・中学生を対象とした喫煙行動と関連要因に関する大規模調査研究(第2報)-小・中学生を対象とする禁煙外来のあり方について-藤田 信(フジタ マコト) |
目的 喫煙する小・中学生の禁煙外来に対する考えを明らかにして,禁煙外来受診を促進し,小・中学生の喫煙の解消に資することを目的とする。
方法 静岡県A保健所管内の小学校35校,2,428名,中学校17校,2,316名に対して,無記名自記式の調査票によるアンケート調査を実施した。
結果 過去に禁煙を試みた者は,小・中学生ともに約8割で,そのうち小学生で95%,中学生で78%の者が禁煙を達成していた。過去に禁煙を試みたとき,誰にも相談しなかった者は小学生の男子女子ともに69%,中学生男子で71%,女子で75%であった。現在の禁煙を試みる意思は,「今すぐ」「1カ月以内に」「3カ月以内に」やめたいとする者が,合わせて小学生の男子で69%,女子で57%,中学生の男子で43%,女子で38%であった。禁煙外来受診時に希望する付き添いは,「父母」が小学生男子で34%,女子で27%,中学生男子で14%,女子で20%,「行きたくない」が同様に23%,23%,13%,11% であった。禁煙外来に希望する担当医は,小学生では「学校医」と「顔見知りの医師」が比較的多く,中学生では「顔見知りの医師」と「顔見知りでない医師」 とでほぼ二分された。禁煙外来受診の希望日時は,概して日曜日・祝日や夏休みなどの長期休業期間が多かった。禁煙外来を安心して受診できる条件は,「学校 や氏名が分からないように」が小学生男子で44%,女子で46%,中学生男子で76%,女子で60%,「診察室は別で話が他に聞こえない」が同様に29%,36%,30%,34%であった。保護者への喫煙と禁煙の告知について,「できない」が小学生男子で6%,女子で5%,中学生男子で20%,女子で11%,「話すつもりはない」が同様に9%,なし,27%,18%であった。
結論 小・中学生を対象とする禁煙外来は,匿名とし診察室を別にして話が他に聞こえない必要があり,診療日は日曜日・祝日または長期休業期間が望ましく,担当する医師は小学生では顔見知りの医師とすることが望ましい。
キーワード 禁煙外来,小・中学生,保健所,質問紙調査,喫煙の習慣性
|
第53巻第10号 2006年9月 主観的健康感と職業性ストレスとの関連について-MYヘルスアップ研究から-豊川 智之(トヨカワ サトシ) 三好 裕司(ミヨシ ユウジ) 宮野 幸恵(ミヤノ ユキエ)鈴木 寿子(スズキ トシコ) 須山 靖男(スヤマ ヤスオ) 井上 まり子(イノウエ マリコ) 井上 和男(イノウエ カズオ) 小林 廉毅(コバヤシ ヤスキ) |
目的 金融保険系企業の従業員を対象としたMYヘルスアップ研究における調査により,労働者の主観的健康感(Self-Rated Health: SRH)と職業性ストレス,特に仕事の要求度とコントロールとの関連について検討した。
方法 職業性のストレス要因を,「高ストレイン」「パッシブ」「アクティブ」「低ストレイン」の4つに分け,これらを独立変数,SRH を従属変数とするロジスティック回帰分析モデルにより分析した。共変量として年齢,職区分,婚姻状態,喫煙習慣,飲酒習慣,運動習慣,睡眠時間,現在治療 中の病気の有無,過去に治療した病気の有無を含め,「基本モデル」とした。次に,周囲からの支援による,ストレスとSRHとの関連の変化を示すため,上 司,同僚,家族・友人からの支援を共変量としてモデルに入れ「支援ありモデル」とした。
結果 回帰モデル(支援ありモデル)によるオッズ比(OR) では,職業性ストレスについて,高ストレイン(男性OR;1.88,女性OR;1.70),パッシブ(男性OR;1.23,女性OR;1.40),アク ティブ(男性OR;1.28,女性OR;1.20)は,低ストレインと比較してSRHが低いことが示された。女性では営業職が事務職に比べSRHが低いこ とが示された(OR;1.85)。男性では家族・友人からの支援(OR; 1.80)がない場合,女性では上司(OR;1.37)からの支援がない場合にSRHが低かった。
結論 仕事の要求度とコントロールによるストレスの違いに焦点を当てて分析を行った結果,高ストレインの労働者のSRH が低いことが明らかになった。ストレスに関与する要因の中で,男性では家族・友人からの支援を得られない場合に,女性では上司や同僚からの支援を得られな い場合にSRHが低いことが示された。男性では単身赴任していること,女性では独身でいることが低SRHと関連することが示され,これらの社会的関係性が SRHと結びついていることが示された。
キーワード 主観的健康感,職業性ストレス,カラセックモデル,社会的関係性
|
第53巻第11号 2006年10月 家族介護者の介護負担感と関連する因子の研究(第1報)-基本属性と介入困難な因子の検討-平松 誠(ヒラマツ マコト) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) 梅原 健一(ウメハラ ケンイチ)久世 淳子(クゼ ジュンコ) 樋口 京子(ヒグチ キョウコ) |
目的 介護負担感の関連因子を探る基礎作業として,年齢や性別などの介護者の基本属性,介護期間などの介入困難な因子について検討した。
方法 対象は,A県下の7保険者において,介護保険の在宅サービスを利用していたすべての要介護者の介護者(7,278人)である。回収数(率)3,610(49.6%)のうち,主介護者によって回答された3,149人を分析対象とした。主観的介護負担感(8点から32点で,得点が高いほど介護負担感が高い)と主介護者の基本属性(性別,年齢,続柄),および介入困難な因子(要介護者の障害老人の日常生活自立度,認知症老人の日常生活自立度,要介護度,1日の平均介護時間,目の離せない時間,介護期間)の9因子との関連を検討した。
結果 介護負担感は,介護者が女性で,高齢,続柄が妻の場合に,有意に高かった。しかし,例えば,男性の介護負担感の平均値は26.3±5.3,女性は27.2±5.4で,その差は0.9点 と小さかった。また,どの年齢・性別においても,障害が重く,介護時間が長くなるに伴い,介護負担感が有意に高くなる傾向がみられた。ただし,その結果 は,介護負担感スケールで何点以上を「高い」とするのか,平均値でみるのかという変数の扱い方によっても変動した。介護期間については,長いほど介護負担 感が高い傾向を示したが,統計学的な有意差は65歳未満の女性でのみみられた。
結論 介護負 担感は,介護者が女性で,高齢,続柄は妻で有意に高く,障害の重症度が重い群,もしくは介護時間が長い群で,介護負担感が高くなるという傾向が確認され た。今後の介護負担感研究においては,介護負担感との間に統計学的に有意な関連が認められた(介護期間を除く)8つの交絡因子を考慮して分析を行うことが 望ましいと考えられた。
キーワード 要介護高齢者,家族介護,介護負担感,日常生活自立度,性差
|
第53巻第11号 2006年10月 藤沢市における個別健康支援プログラムの有効性の検討鈴木 清美(スズキ キヨミ) 小堀 悦孝(コボリ ヨシタカ) 相馬 純子(ソウマ ジュンコ)小野田 愛(オノダ アイ) 齋藤 義信(サイトウ ヨシノブ) 尾形 珠恵(オガタ タマエ) 李 廷秀(リ チョンスウ) 森 克美(モリ カツミ) 川久保 清(カワクボ キヨシ) |
目的 藤沢市が厚生労働省から委託を受けて実施した「国保ヘルスアップモデル事業」(平成14~16年度)は,対象とする生活習慣病とその予備群を選定の上,健康度という概念と指標を設定し,個別健康支援プログラムの開発・実施と事業効果の分析・評価を行うものである。本研究は,開発した藤沢市個別健康支援プログラムの有効性を検討することを目的とした。
方法 プログ ラムの有効性を検討するため,年1回の健康診断と健康相談を受けるコース1,コース1の内容に加えて半年後の効果測定と食生活相談を受けるコース2,コー ス2の内容に加えて週1回の運動トレーニングを行い,総合的に健康づくりを行うコース3の3種類のコースを設定した。各コースについて,健診結果と生活習 慣調査結果のデータにより,正味2年間の介入前後の比較,事業に参加した介入群(979人)と対照群(4,570人)の変化量の比較を行った。
結果 介入群における介入前後の比較で数値データの変化をみると,コース2,3とも,体重,BMI,血清HDLコレステロール値が改善した。またコース2では中性脂肪値が改善し,コース3では血圧値が改善した。対照群との比較では,コース2,3とも,体重,BMI,収縮期血圧,血清総コレステロール値の変化が有意であった。またコース2では中性脂肪値に,コース3では収縮期血圧,拡張期血圧,血清LDLコレステロール値に有意差があった。生活習慣についてはコース1,2,3とも介入前後の比較で改善を示し,コース2,3は対照群との比較でも有意差があった。
結論 藤沢市 個別健康支援プログラムは,生活習慣の改善,身体状況の改善の両者において有効であることが実証された。特にコース2参加者は中性脂肪値の改善が有意であ り,コース3参加者は血圧値の改善が有意であることが明らかになったことから,今後,この結果を踏まえた食生活および運動習慣を配慮した総合的健康づくり システムを構築していく方向性が示された。
キーワード 国保へルスアップモデル事業,個別健康支援プログラム,生活習慣病
|
第53巻第11号 2006年10月 地域福祉活動の住民満足度分析に関する研究-地域福祉活動計画への活用-増子 正(マスコ タダシ) |
目的 地域福 祉は,住民の生活の満足度を向上させるという目標を有している。本研究では,市町村社会福祉協議会が実施している地域福祉事業への住民満足度に影響を与え ている要因を分析して,地域福祉計画,地域福祉活動計画策定に反映させることで,住民ニーズに立脚した計画の策定とアカウンタビリティ(説明責任)確保の 遂行に寄与することを目的としている。
方法 著者が日本学術振興会の科学研究費補助を受けて開発した「ベンチマーク方式による社会福祉協議会の事業評価」の手法を活用して,秋田県A町在住の18歳以上の男女1,197名を対象に,同町社会福祉協議会が実施している地域福祉事業に対する住民意識調査の結果からデータベースを構築し,地域福祉活動や事業に対する住民の満足度に影響を及ぼしている要因を分析した。
結果 事業に対する満足度と,周知度,居住地,居住年数,年齢との関係を分析した結果,活動や事業に対する住民の周知度の違いが,それぞれの事業への期待度と満足度に大きく影響を及ぼしていて,事業に対する周知度が低い集団で満足度のスコアが極端に低いことがわかった。
結論 地域福祉計画,地域福祉活動計画の策定段階で,住民満足度を的確に分析し,ニーズ把握に活用することは,計画のアカウンタビリティ確保に有用であり,事業に対する住民の周知度を高めることが住民の生活の満足度の向上に寄与することが検証された。
計画策定の目標のなかに,地域福祉活動や事業に対する住民の認識度を向上させるための情報提供システムを再構築することの重要性が示唆された。
キーワード 地域福祉活動,住民満足度,地域福祉計画,地域福祉活動計画,事業評価
|
第53巻第11号 2006年10月 がん終末期患者の在宅医療・療養移行の課題-病状説明,告知の現状-沼田 久美子(ヌマタ クミコ) 清水 悟(シミズ サトル) 東間 紘(トウマ ヒロシ) |
目的 終末期がん患者が在宅での医療・療養継続を希望した場合に,急性期病院(以下「急性期」)医師と地域での医療を担う(以下「地域」)医師の連携に重要となる課題およびそれぞれの役割を明らかにする。
方法 第7回日本在宅医学会大会に参加した医師を対象に調査用紙を配布・回収した。医師は,急性期医師と地域医師の2群とし,それぞれ自記式での回答を求めた。
結果 調査対象医師数は185人で,回答者数123人(急性期医師35人,地域医師88人),回収率66.5%であった。急性期医師は年齢45.7±9.2歳,医師経験18.7±9.0年,在宅移行経験88.6%,訪問診療経験77.1%,地域医師は年齢47.2±8.9歳,医師経験20.9±9.2年,訪問診療経験93.2%,在宅看取り経験93.2%であった。急性期医師の告知に関する回答は「病名はするが余命告知はしない」25.7%,「病名・余命の告知をする」28.6%,「家族の希望に沿う」が42.9%であり,特に,訪問診療経験のない急性期医師は経験のある医師と比較して,余命告知をする割合が低かった(p<0.05)。また,「余命の告知をしないことで患者への対応に困難を感じた」との回答は急性期医師71.4%,地域医師77.3%とそれぞれ高率であった。病状理解について,「退院時に患者・家族は病状理解ができている」と回答した急性期医師は85.7%,地域医師では58.0%と認識に差がみられたが,患者・家族の病状理解が不十分な時には急性期医師の80.0%,地域医師では83.0%が対応困難と感じていた。また,「急性期医師よりの病状申し送り内容と患者の病状理解が一致していない」と地域医師の51.2%が回答し,その医師は全員,対応困難を感じていた。地域医師の回答で,退院時に「患者・家族が不安に思っていること」は「夜間の医療対応」71.6%,「緊急時の病院対応」68.2%,「介護への不安」46.6%,「病状」が27.3%であった。
結論 急性期医師の1/4 は「余命告知をしない」と回答し,特に,訪問診療経験のない急性期医師は告知をしない割合が高いことから在宅療養における告知の重要性の認識が薄いと考え られた。多くの地域医師は,患者が余命告知をされていないことや病状理解が不十分なために対応困難を抱えており,患者・家族も退院に当たって病状について 大きな不安を抱いている。急性期医師は在宅での医療・療養の特性を理解した上で,対応困難が生じると思われる事項を患者の入院中に改善し,患者・家族の置 かれている状況や療養上必要な情報を地域医師へ的確に引き継ぐことが重要である。その上で,患者・家族の不安を地域医師と共有し,それぞれの役割を生かし た連携を行うことが望まれる。
キーワード 在宅医療,がん終末期患者,アンケート調査,在宅移行連携,医師の認識
|
第53巻第13号 2006年11月 昭和ヒトケタ男性の寿命-世代生命表による生存分析-岡本 悦司(オカモト エツジ) 久保 喜子(クボ ヨシコ) |
目的 1980年代に社会的関心を集めた「昭和ヒトケタ短命説」について,その寿命への影響を世代生命表を用いて30歳以降の生存率により定量的に検証した。
方法 1920~1949年出生の男性コホートについて,戦争などの影響を受けていない30~55歳の年齢別死亡率から生存率を算出し推移を観察した。さらに,戦争などの影響を受けなかったと仮定した場合の生存率の改善を傾向線で表現し,昭和ヒトケタを中心とした世代の観察された生存率と傾向線との差から,戦争などによるコホート効果を65歳までの生存率で定量的に推計した。
結果 1926~1938年に出生した男性において,30歳以降の生存率の停滞が明瞭に観察され,その相対的低下は1932年生まれにおいて最も顕著であった。この年に出生した男性の30歳のうち65歳まで生存した者の割合は,戦争などの影響がなかったとしたら辿ったであろう生存率と比較して1.87%低かった。この世代の30歳時人口が約82万人であったことから,65歳まで到達できた者が約1.5万人,あるべき数より少なかったことを意味する。1926~1938年間全体では30歳男性1037万人に対して65歳到達者は,あるべき数より11.7万人少なかった(1.1%)。また,30歳以降の生存率は,世代を追うごとに改善されてきたが,1929年出生者については,わずかながら前世代を下回る現象が確認され,さらに終戦時に乳幼児だった1942~1944年出生世代でも,30歳以降の生存率にわずかながら停滞現象が観察された。
結論 発育期を戦争中に過ごしたという「負い目」は30歳から65歳までの生存率を1%以上低下させる影響をもたらした。戦後生まれ世代との格差は彼らが老齢に入るにつれてますます拡大している。彼らがまだ中年だった頃に初めて発見された現象は一時的なものではなく,人生最後までつきまとう「この時期に生まれたるの不幸」であった。
キーワード 世代生命表,コホート効果,生存率,中高年死亡
|
第53巻第13号 2006年11月 訪問介護サービスを利用している独居高齢者の主観的健康感に
中尾 寛子(ナカオ ヒロコ) 平松 正臣(ヒラマツ マサオミ) |
目的 独居で介護保険の訪問介護サービスを利用している要援護高齢者の主観的健康感に影響する社会関係要因を明らかにし,さらに独居年数によってどのように異なるのかを検証する。
方法 対象は,中国地方のA県B市内4カ所のホームヘルプステーション(訪問介護事業所)で介護保険の訪問介護サービスを利用している独居高齢者51人である。対象者の自宅を調査員が訪問介護員に同行訪問して,調査票を用いた個別の面接聞き取り調査を行い,年齢,婚姻歴,子どもの有無,要介護度,独居年数などの属性と主観的健康感,QOL(生活満足度尺度K)および社会関係についての情報を得た。独居年数が明らかでなかった2人を除く対象者を独居年数が10年未満(短期)群(n=20)と10年以上(長期)群(n=29) の2群に分けて,グループごとに主観的健康感に関連する要因を社会関係の中から探り,その結果を2群間で比較した。単変量解析とカテゴリカル回帰分析を実 施し,カテゴリカル回帰分析の従属変数は主観的健康感(よい[1]~よくない[4]),説明変数は年齢,性,要介護度,社会関係指標とした。
結果 カテゴリカル回帰分析から,両群ともに有意な関連が認められた。独居年数10年未満群では「男性」「デイサービス・デイケアを利用」「近所づきあいに満足」「閉じこもり傾向なし」が,独居年数10年以上群では,「女性」「近所づきあいに満足」が主観的健康感を有意に高める傾向にあることを示した。また,両群ともに「年齢」「要介護度」と主観的健康感との間に有意な関連はなかった。主観的健康感に最も有意な関連性をもつのは「近所づきあいの満足度」であった。
結論 独居期間が短い要援護高齢者の心身の健康にとっては,「デイサービス・ デイケアの利用」や「閉じこもり予防事業への参加」がより高い効果を発揮する可能性が示された。また,独居年数にかかわらず,独居要援護状態の高齢者の主 観的健康感には,離れて住む子どもや友人よりもむしろ「近隣住民との関係性」のほうが強い影響を及ぼすことが明らかになった。これらのことから,デイサー ビス・デイケアや閉じこもり予防事業などの地域福祉サービスを独居開始の早い時点つまり「適切な時期」に利用につなげる援助と,本人自身が近隣住民と満足 できる関係性を築くことへの援助の両方が,要援護高齢者にとって高い健康感をもちながらひとり暮らしを続けるためには特に重要であると考えられた。
キーワード 独居要援護高齢者,主観的健康感,社会関係,独居年数,近所づきあいの満足度
|
第53巻第13号 2006年11月 島嶼地域住民の主観的健康感の関連要因に関する研究志水 幸(シミズ コウ) 小関 久恵(コセキ ヒサエ) 嘉村 藍(カムラ アイ) |
目的 サクセスフル・エイジングに資するべく,日常生活行動の典型例の抽出が可能な島嶼(しょ)地域住民を対象に,ライフスタイルを構成する多元的要素を包括する視点から主観的健康感に関連する要因を明らかにする。
方法 山形県酒田市飛島に居住する満40歳以上の住民208人を対象に,訪問面接調査法(一部,配票留置法)による悉皆調査を実施した。調査項目は,基本属性,社会関連性指標,老研式活動能力指標,ソーシャルサポート,生活満足度,健康生活習慣に関する85項目を設定した。解析方法として,単変量解析では,質的変数の検定にχ2検定を,量的変数の検定にはt検定を適用した。さらに,多変量解析では,主観的健康感を目的変数とし,単変量解析で有意差が認められた項目を説明変数とするロジスティックモデルを構築し,強制投入法により変数の独立性について検討した。
結果 調査対象者のうち,192人(回収率92.3%)から回答を得た。壮年期ではISI(社会関連性指標)の「便利な道具の利用」の「実施群」が,高齢期ではISIの「訪問機会」「積極性」の「実施群」,LSI-Kの「去年と同じように元気である」の「肯定的回答群」が,壮年期・高齢期の両群ではLSI-Kの「物事を深刻に考える」の「肯定的回答群」において,主観的健康感が高いことが明らかになった。
結論 主観的健康感は加齢に伴い,身体的要因よりも精神的・社会的要因の影響を強く受けることが示唆された。
キーワード 主観的健康感,サクセスフル・エイジング,ライフスタイル,島嶼地域
|
第53巻第13号 2006年11月 家族介護者の介護負担感と関連する因子の研究(第2報)-マッチドペア法による介入可能な因子の探索-平松 誠(ヒラマツ マコト) 近藤 克則(コンドウ カツノリ) 梅原 健一(ウメハラ ケンイチ)久世 淳子(クゼ ジュンコ) 樋口 京子(ヒグチ キョウコ) |
目的 介護負担感を軽減する支援策を探るために,交絡因子の条件を同一にするマッチドペア法を用いて,介護負担感と関連する介入可能な因子を検討した。
方法 対象は,A県下の7保険者の地域代表サンプルの介護者(7,278人)である。回収数(率)3,610(49.6%)のうち,主介護者によって回答された3,149人を分析対象とした。今回,検討を行った介入可能な因子は,ソーシャルサポート,副介護者の有無,十分な介護情報の有無,趣味や気晴らし,介護者のGDS(Geriatric Depressive Scale-short form)-15項目短縮版,ストレス対処能力(SOC; Sense of Coherence)である。また,第1報での検討をふまえ,8つの交絡因子をマッチさせたマッチドペア法を用いて,介護負担感が高い群(20以上)と,低い群(19以下)の2群間で差がみられる因子を検討した。マッチさせた条件は,介護者の年齢,性別,続柄,障害老人の日常生活自立度,認知症老人の日常生活自立度,要介護度,1日の平均介護時間,目の離せない時間の8因子である。
結果 介護負担感が低い群には,情緒的サポートがあり,手段的サポートがあり,介護情報があり,趣味や気晴らし活動をしており,ストレス対処能力(SOC)が高く,GDSが低いものが,有意に多かった。介護負担感との関連性の大きさ(γ係数)をみると,ストレス対処能力(-0.61),GDS(0.57)や情緒的サポート(-0.45)などの介護者の認知や主観を反映する因子で高く,一方,十分な介護の情報(0.26),副介護者の有無(0.08),趣味や気晴らし(0.33)などの因子で低い傾向が示された。
結論 従来検討されてきたソーシャルサポートなどの客観的な側面の因子と介護負担感の関係よりも,むしろストレス対処能力やGDSなどの介護者の主観的な側面を反映する因子で関連性が大きかった。このことは介護負担感の軽減にむけての支援策として客観的状況を変える支援だけではなく,認知や主観への介入も今後は検討すべきことを示唆していると思われる。
キーワード 要介護高齢者,介護負担感,心理,介護者支援,ストレス対処能力,うつ
|
第53巻第13号 2006年11月 幼稚園児の母親を対象とした育児不安の研究本村 汎(モトムラ ヒロシ) 上原 あゆみ(ウエハラ アユミ) |
目的 本研究では,「インフォーマルな支援」としての「夫からの協力」「夫とのコミュニケーション」「友人からの支援」,母親の「性役割分業意識」が,母親の育児不安にどのような影響を与えているかを明らかにし,その影響のメカニズムを検討することを目的とした。
方法 調査対象はA県H市の私立幼稚園に通園している幼児の母親から無作為に抽出された300名(有効回収率74.3%)であり,調査方法は自計式質問紙法で,調査時期は平成15年10月末~11月末とした。測定尺度としては9項目から構成された「育児不安」尺度と,支援測定尺度の副尺度である夫からの協力尺度(5項目),夫とのコミュニケーション尺度(5項目),友人からの支援尺度(3項目)を用い,そのいずれも4件法で測定した。尺度の信頼係数(cronbachのα係数)は国際基準0.70以上に達している。母親のパーソナリティの測定尺度としては,標準化されているPOMS(Psychiatric Outpatient Mood Scale)を用いた。
結果 1)一元配置分散分析によれば,インフォーマルな支援が増大すると,そ れに対応する形で母親の「育児不安」は減少していた。2)一元配置分散分析のレベルでは,母親の「性役割分業意識」は育児不安になんらの影響も与えていな かったが,夫婦関係のありかた如何によっては,影響があることを示していた。3)母親のパーソナリティとの関連では,いずれの「心理因子」も母親の育児不 安に影響を与え,「活力因子」以外の因子は,いずれも母親の育児不安に「負」の効果をもたらしていた。4)重回帰分析は,「友人からの支援」と母親のパー ソナリティの「活力因子」が「育児不安」の減少に貢献していた。
結論 支援効果をあげていくためには支援の量を増大するだけでなく,母親のパーソナリティ特性に注目し,母親のネガティブな心理因子の「負」の効果を減少させるために,「活力因子」の強化に焦点をあてた支援の必要性が示された。
キーワード 育児不安,パーソナリティ構造,インフォーマルな支援,一元配置分散分析,重回帰分析
|
第53巻第15号 2006年12月 一般世帯および食物アレルギー患者世帯における食品表示などの利用状況-妊産婦教室および乳幼児教室の参加者を対象として-野村 真利香(ノムラ マリカ) 堀口 逸子(ホリグチ イツコ) 丸井 英二(マルイ エイジ) |
目的 厚生労働省によって新たに提示された介護予防施策では,「一般高齢者」「特定高齢者」「要支援高齢者」「要介護高齢者」の4つの階層を用意し,対象と給付の関係を明確化した。しかし対象者の選定には『基本チェックリスト』と『要介護認定方式』が並行的に運用され,そこから抽出される「特定高齢者」と「要支援高齢者」の境界や階層性の関係は,いまだに明らかにされていない。本研究では,「要支援高齢者」の候補者である旧要支援,旧要介護1の認定者に対して,『基本チェックリスト』により試行的に判定し,「特定高齢者」と「要支援高齢者」との間の階層的な関係について検証を行った。
方法 対象は,東京都A市において旧要支援,旧要介護1の認定を受けた者のうち,介護保険以外の生活支援型サービスを利用している在宅高齢者767名である。調査は,2006年2月に自記式の郵送調査によって実施し,回収率は92.3%であった。調査内容は,厚生労働省の『基本チェックリスト』およびIADL(手段的日常生活動作)5項目の遂行能力を問う項目を用いた。本研究では,すべての調査項目に回答した456名(旧要支援:107名,旧要介護1:349名)を分析対象とした。
結果 旧要支援,旧要介護1の認定者に『基本チェックリスト』による判定を試行した結果,特定高齢者に選定されたのは,旧要支援では33.6%,旧要介護1では57.8%となり,「要支援高齢者」であるにもかかわらず「特定高齢者」には選定されないケース,つまり施策の想定とは逆の階層関係となるケースが,約半数に出現することが明らかとなった。次にIADL5項目による自立者の割合を確認した結果,旧要支援,旧要介護1認定者の54.8%がすべてのIADL項目が自立していた。これに対して,IADLが非自立であった者の4分の1に当たる25.7%が特定高齢者に選定されなかった。
結論 2つの異なる基準から抽出された特定高齢者と要支援高齢者の間には,階層関係が逆転しているケースが約半数にみられ,両者を階層的に位置づけるのは困難であることが明らかとなった。その要因の1つは,新たに開発された基本チェックリストが,要介護認定との階層的な関係を十分に考慮せずに作成されたことにある。もう1つは,要介護認定方式が,IADLの能力を適切にスクリーニングできず,自立(非該当)との境界が曖昧になっている点が示唆された。今後,介護予防施策を一貫したシステムとして構築するためには,介護予防施策の対象者の統合も含めて,基本チェックリストと要介護認定方式の抜本的な見直しが不可欠である。
キーワード 介護予防,要介護認定方式,基本チェックリスト,給付区分,特定高齢者
|
第53巻第15号 2006年12月 介護保険施設におけるケアマネジメント実践の検証真辺 一範(マナベ カズノリ) |
目的 介護保険施設におけるケアマネジメントの実践内容を概念的モデルとの比較から検証し,施設ケアマネジメントのあり方を模索した。
方法 先行研究に基づきケアマネジメント実践の程度を測るための項目を用い,兵庫県内の介護保険施設491カ所に所属する施設ケアマネジャーを対象として,郵送によるアンケート調査を実施した。質問紙の作成に際しては,回答者が理解しやすいように各質問項目を介護保険施設の現状に合うよう適切な表現に変更し,その実践度合いを5段階のリッカートスケールでたずねた。有効回答数(率)は,330名(67.2%)であった。調査結果の分析は,施設ケアマネジメントの実践プロセスの枠組みを明らかにするためにそれぞれ因子分析(主因子法・バリマックス回転)を行った。さらに実際の援助プロセスごとに回答者の属性による違いを明らかにするため,その因子分析で抽出されたそれぞれの因子を従属変数とし,属性を独立変数としたt検定,一元配置分散分析(F検定)および下位検定の多重比較(Tukey法)を行った。また,因子分析の結果と概念的モデルを比較し,ケアマネジメント実践プロセスに関する分析を行った。
結果 因子分析により抽出された因子は「アセスメント」「モニタリング」「ケース発見」であった。「アセスメント」に関しては,性別,年齢,基礎資格,基礎資格経験年数(基礎年数),ケアマネ人数,所属施設,勤務形態(専任兼任),事例検討形式の研修受講有無(事例研修)によって有意差がみられた。特に所属施設においては「老人保健施設(以下,老健)」が「特別養護老人ホーム(以下,特養)」より有意に高かった。また,「モニタリング」に関しては,担当ケース数,担当者会議の有無,着任経緯によって有意差がみられ,特に担当ケース数では「40~59件」が「0~39件」より有意に高かった。「ケース発見」に関しては性別,演習形式の研修受講有無,事例検討形式の研修受講有無によって有意な差がみられた。なお,相談相手の有無や講義形式の研修受講有無ではすべてのプロセスにおいて有意な差はみられなかった。
結論 1)施設ケアマネジメントの特徴は,「アセスメント」とその後に続く「目標設定とケア計画」「ケア計画実施(リンキング)」のプロセスが一体的に連動して実施されており,実践プロセスではその部分が明確に区別されていない。2)「評価」については,具体的で実効性のある手法を開発し,実践レベルに導入できる取り組みが早急に必要である。
キーワード 施設ケアマネジメント,介護支援専門員の専門性,介護保険制度,施設ケアマネジメント実践の定義,研修システム
|
第53巻第15号 2006年12月 介護保険施設における施設ソーシャルワークの構造と規定要因-介護老人福祉施設と介護老人保健施設の相談員業務の比較分析を通して-和気 純子(ワケ ジュンコ) |
目的 介護老人福祉施設と介護老人保健施設における相談員業務の比較分析を通して,介護保険施設における施設ソーシャルワークのあり方を検討するための基礎データを作成することを目的とする。
方法 無作為抽出(系統抽出法)した介護老人福祉施設500カ所および介護老人保健施設500カ所の生活相談員・支援相談員のうち,当該施設で最も経験年数の長い相談員を対象に郵送調査を実施した。調査時期は,2004年11~12月,回収率は48.4%である。30項目の業務内容の頻度を5段階で尋ね,一元配置分散分析によって各業務頻度の比較を行った後,探索的因子分析によって因子構造を把握した。その上で,各因子得点を従属変数とし,施設特性および相談員特性を独立変数とする重回帰分析を行い,相談員業務を規定する要因の異同について考察した。
結果 介護老人保健施設の相談員は,入退所をめぐる相談・調整業務に多くの時間を費やしているのに対し,介護老人福祉施設の相談員は利用者の日常生活支援や地域社会と関わる幅広い業務により頻繁に従事している。業務の因子構造では類似点もみられるが,抽出された因子数や因子寄与率に差異が認められた。各業務因子に影響を与える要因では,介護老人福祉施設の場合は施設特性の影響力が強く,介護老人保健施設では相談員特性のみが規定要因となっていることが判明した。
結論 施設としての役割や機能を異にする介護老人福祉施設と介護老人保健施設であるが,入所者の権利を擁護し,その生活の質を高めるために,いずれの施設にあっても施設ソーシャルワークを担う相談員が果たす役割はますます重要になっていくものと考えられる。介護保険施設として,利用者のニーズに最も的確に応える相談員業務の設定と必要な専門性の確保が求められる。
キーワード 介護保険施設,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,ソーシャルワーク,相談員
|
第53巻第15号 2006年12月 身体障害者福祉施設の施設職員が認識する
仁坂 元子(ニサカ モトコ) 岡田 進一(オカダ シンイチ) 髙橋 美樹(タカハシ ミキ) |
目的 本研究は,身体障害者福祉施設の施設職員(施設長を含む)が認識する自立の構造を明らかにすることが目的である。
方法 調査対象者は,近畿2府4県の身体障害者福祉施設150カ所の職員,施設長各1名ずつの計300名であり,調査方法は無記名の自記式郵送調査である。調査期間は2005年2月14日から3月11日で,有効回答率は66.0%であった。調査項目は,基本属性,先行研究から抽出された自立に関連する項目を設定した。施設職員が認識する自立概念を明らかにするため,分析方法にはバリマックス回転を伴う因子分析(主因子法)を用いた。
結果 本研究の分析から,施設職員が認識する自立概念は,「生活主体者という立場からの自己実現志向」「一個人として尊重されていることへの気づき」「社会制度の選択・開発過程への積極的関与」「身辺および経済面における自助志向」「他者との非依存的な人間関係の構築」の5因子からなることが明らかとなった。
結論 本研究は,自立を「身体的」や「経済的」側面から捉えていくことの限界を示唆した先行研究を支持する結果となった。そして,施設職員は,自助志向の従来の自立観と自己実現などをキーワードとする新しい自立観という2つの立場を内包していることが明らかとなった。今後,施設職員は,障害者に対する適切な自立支援を行っていくためにも,何を自立と考えるのかを明確にし,具体的な自立支援の方法を考えていくことが必要となる。また,従来の自助志向の自立観も否定されるものではないが,その考え方が障害者から必ずしも支持されてきた自立観ではないことから,今日の自立支援の方向性として,個人として尊重されることや社会制度との関わりを意識した支援が求められる。そして,社会制度の利用を自立と捉えることは,障害者自立支援法に基づいた支援を行っていくにあたり,非常に重要なことであり,障害者に対する「権利擁護」の考え方にもつながるものであると考えられる。
キーワード 身体障害者,施設職員,施設長,自立
|
第53巻第15号 2006年12月 高齢者のボランティア活動に関連する要因岡本 秀明(オカモト ヒデアキ) |
目的 人口高齢化の進行の中にあって元気な高齢者数も増加しているわが国では,高齢者は社会や地域に貢献する資源であるという観点を持ち,高齢社会を構築していくことが求められる。本研究では,高齢者のボランティア活動に関連する要因を明らかにすることを目的とした。
方法 大阪市24区のうち8区から無作為抽出し,65~84歳の高齢者1,500人を対象に自記式質問票を用いた郵送調査を実施した。有効回収数771人のうち,特定項目に欠損値のない671人を分析対象とした。分析は,ボランティア活動の有無を従属変数としたロジスティック回帰分析を行った。独立変数は,「家族・経済・他(4変数)」「健康(2変数)」「暮らし方の志向性(7変数)」「技術や経験(2変数)」「社会・環境的状況(2変数)」という5領域の計17変数とし,統制変数は,年齢と性別を投入した。領域ごとに分析し,次に,統計学的な有意が認められた変数をすべて投入して分析を行った。
結果 ボランティア活動をしている者は24.0%であり,年1~2回活動している者が最も多かった。ボランティア活動への関心がある者は58.8%,活動への参加意向がある者は48.9%であった。ロジスティック回帰分析を行った結果,ボランティア活動をしている者の特性として,「中年期にボランティア経験がある」「地域に貢献する活動をしたい」「ボランティア活動情報の認知の程度が高い」(p<0.001),「技術・知識・資格がある」「親しい友人や仲間の数が多い」(p<0.01),「主観的健康感が高い」(p<0.05)ということが明らかになった。
結論 ボランティア活動への関心のある者は6割弱,参加意向のある者は5割弱であるのに対し,実際に活動している者は2割強にとどまっていた。活動への関心や参加意向のある者を実際の活動に結びつけやすいよう環境を整備していくことにより,ボランティア活動に参加する高齢者が増加することが期待できる。高齢期以前にボランティア経験を持てるような場の設定や啓発,活動への参加の機会に関する情報を多くの高齢者に認知してもらえる環境を整えていくことなどが求められる。
キーワード 高齢者,ボランティア,社会活動,社会参加
|
第54巻第1号 2007年1月 子どもの発達の全国調査にもとづく園児用
安梅 勅江(アンメ トキエ) 篠原 亮次(シノハラ リョウジ) 杉澤 悠圭(スギサワ ユウカ) |
目的 全国の保育園児の発達状態について実態を調査し,それに基づいた園児用発達チェックリストを開発することを目的とした。
方法 対象は,長時間保育を含む全国98カ所の認可保育所を利用する22,819名の子どもである。担当保育士が各々の子どもの発達状態について,園児用発達チェックリスト試案を用いて運動発達(粗大運動,微細運動),社会性発達(生活技術,対人技術),言語発達(表現,理解)の6領域,各領域32項目,全192項目について評価した。すべての項目について,10%の子どもが実施可能となる月齢(10パーセンタイル値),50%の子どもが可能となる月齢(50パーセンタイル値),90%の子どもが可能となる月齢(90パーセンタイル値)を算出した。
結果 すべての項目について,10パーセンタイル値,50パーセンタイル値,90パーセンタイル値が試案の序列に添った形で抽出され,また基準月齢が10~90パーセンタイル値の範囲内にあることが確認された。信頼性は各領域で82.5~97.9%であった。
結論 この園児用発達チェックリストが,現在の日本における園児の発達を評価する指標として妥当であることが示された。
キーワード 子どもの発達,保育,評価,園児,全国
|
第54巻第1号 2007年1月 高齢者を対象とした地域における運動教室の医療経済効果神山 吉輝(カミヤマ ヨシキ) 白澤 貴子(シラサワ タカコ) 小出 昭太郎(コイデ ショウタロウ)高橋 英孝(タカハシ エイコウ) 川口 毅(カワグチ タケシ) 久野 譜也(クノ シンヤ) |
目的 地域における高齢者を対象にした運動教室について,開始前1年間と開始後の2年間以上のデータを用い,3年間以上の年間医療費の推移を示した形で,医療経済評価を行うことを目的とした。
方法 新潟県M市,富山県S市,埼玉県K市,愛媛県W町の健康運動教室参加者のうちの国民健康保険の被保険者(以下,国保加入者)を運動群とするとともに,国保加入者の中から運動教室に参加していない約3倍の人数を対照群として抽出し,両群の年間の医療費の推移を比較した。医療費の増減の総和を明らかにするために,各年の1人当たり医療費をみるだけではなく,教室開始前の医療費に教室開始後の年間医療費を次々に加えていく累積医療費を算出し,運動群と対照群とで比較を行った。
結果 4市町において,運動群は対照群に比較して,運動教室の開始前から医療費が低いものの,累積医療費でみると,教室開始1年目,2年目とその差が広がっていくことが示された。
結論 教室開始前と開始後2年間以上の国民健康保険の医療費データを用い,運動群と対照群を比較することで,地域における高齢者を対象とした運動教室による医療経済効果の可能性が示唆された。
キーワード 高齢者,運動教室,筋力トレーニング,医療経済
|
第54巻第1号 2007年1月 地域福祉に対するコミュニティワーカーの意識構造谷川 和昭(タニカワ カズアキ) |
目的 地域福祉が学問として生誕したのは1970年代のことであるが,地域福祉の推進を専門とするコミュニティワーカーの意識構造を手がかりとして,未だ定かとなっていない地域福祉とは何かを明らかにすることが本研究の目的である。そのため地域福祉の構成要件を提起し,その体系化の可能性について検討した。
方法 市区町村社会福祉協議会のコミュニティワーカーへの郵送調査(2003年2~3月)を行い,分析項目のすべてに欠測のない222票のデータを用いた。探索的因子分析の手法を用いて,最初に地域福祉に関わる因子の抽出と解釈を行い,続いて地域福祉計画に関わる因子の抽出と解釈を行った。また,両者間の関連の有無を相関分析によって確認した。その後,地域福祉に関する質問33項目と地域福祉計画に関する質問32項目を合成した地域福祉概念に関する65項目の質問項目を用いて一次因子分析を行い検討した。次に,この一次因子分析で析出された因子構造についてさらなる知見を得るため,二次因子分析を行い,因子の抽出と解釈を試みた。また,一次因子分析による構成因子の特徴について考察するためクラスター分析を行った。
結果 地域福祉に関わる因子,地域福祉計画に関わる因子のいずれも抽出とその解釈が可能であった。また地域福祉と地域福祉計画との関連が認められた(r=0.834,p<0.001)。合成した地域福祉概念についての一次因子分析の結果,10個の因子が抽出され,その解釈は可能であった。これら10個の因子による二次因子分析の結果も解釈が可能であった。クラスター分析の結果,関係性が見いだせそうな組合せや独立した因子が明らかになった。
結論 分析結果から,「地域福祉の原理・原則」「新旧社会政策との調整」「予防的社会福祉の増進」「地域社会サービスの整備」「地域のコミュニケーション」「福祉のネットワーキング」「地域福祉圏域の設定」「福祉サービス利用への支援」「社会福祉の空間づくり」「地域における福祉の方向性」が地域福祉の構成要件として示された。また,これらは「制度・政策・施策」「実践・方法・理念」の2つに集約された。さらに,以上の要件のうち,「地域における福祉の方向性」が地域福祉の推進にとって重要と考えられた。
キーワード 地域福祉,地域福祉計画,地域福祉の構成要件,コミュニティワーカー,意識構造
|
第54巻第1号 2007年1月 東北地方の在宅高齢者における
高橋 和子(タカハシ カズコ) 安村 誠司(ヤスムラ セイジ) 矢部 順子(ヤベ ジュンコ) |
目的 「虚弱高齢者」から「極めて元気な高齢者」まで,その体力レベルに応じた役割の創造と開発を目的に,東北地方における在宅高齢者の地域・家庭での役割の実態把握を行い,現状での役割にはどのような要因が影響しているのかを明らかにすることで,高齢者の役割の創造・開発における課題を検討する。
方法 福島県S市A地区の高齢者から無作為抽出した693人を対象に,郵送法による質問紙調査を行った。高齢者の役割については,収入の伴う仕事の有無,シルバー人材センター・高齢者事業団の仕事の経験の有無,家の中での役割,地域の団体・組織・会とのかかわり,現在または最近行ったボランティア活動を把握した。分析方法は,各質問の回答を2項目に分類して行った。最初に各変数についてFisherの直接法を用いて性差を確認した。次に役割の有無による属性の比較を行い,p値が0.05未満となったものを投入し,変数減少法による多重ロジスティック回帰分析を行った。
結果 高齢者の役割のうち,収入の伴う仕事は女性よりも男性で有している割合が有意に高かった。家の中での役割は,男性は「大工仕事や家の修繕」,女性は家事全般において実施している割合が高く,男女で有意差が認められた。地域の団体・組織・会とのかかわりは,男女とも「町内会・自治会」「老人会・高齢者団体」に入っている割合が高かった。ボランティア活動は,男女とも「美化・環境整備の活動」「農作業に関する活動」の実施割合が高かった。高齢者の属性による役割の有無の比較では,収入の伴う仕事,家の中での役割,地域の団体・組織・会とのかかわり,ボランティア活動ともに,日常生活自立度のレベルにより役割の有無に差が認められ,自立者で割合が高かった。また,役割を目的変数とした多重ロジスティック回帰分析の結果においても,現在の役割の有無には日常生活自立度が大きく影響していた。
結論 現在,高齢者が担っている家の中や地域での役割は,性や日常生活自立度で違いがあり,日常生活で介助を要する者は役割を持たない者が多いことがうかがわれた。新たな役割の創造・開発を行う上で,性・年齢とともに高齢者の活動レベルに応じた役割を検討することの重要性が確認された。
キーワード 社会参加,社会活動,役割,在宅高齢者
|
第54巻第1号 2007年1月 高齢者福祉活動の必要性に関する地域住民の意識渡辺 裕一(ワタナベ ユウイチ) |
目的 近年,地域の高齢者福祉問題の解決に向けた地域住民の参加への期待は高まっている。しかし,多くの地域住民の力は潜在化し,その期待にこたえられる状況にあるとは言えない。地域住民が主体的にこれらの問題を共有し,解決に向けて働きかけることが求められており,その導入に高齢者福祉活動の必要性意識を持つという過程があると考えられる。そこで,本研究では高齢者福祉活動の必要性に関する地域住民の意識の現状を把握し,その意識に影響を与えている要因を探索的に明らかにすることを目的とした。
方法 1つの中学校区を対象として社会調査からデータを収集し,χ2検定などを行った。従属変数として,①介護の方法や知識について勉強する機会(学習機会),②介護が必要になることを予防するための活動(介護予防),③高齢者が交流するサロンや趣味,サークル活動(高齢者交流),④介護をしている人が交流する機会(介護者交流)に関してそれぞれ必要と思うかを質問した。独立変数には,「性別」「年齢」「家族構成」「配偶者」「学歴」「永住希望」「広報紙(市・区・自治会レベル)」「地域の集まり」「住居」「仕事の有無」「65歳以上の方と同居しているか」「介護の必要な方と同居しているか」を用いた。
結果 「介護予防」との間に有意な関連が認められた独立変数は,「学歴」「年齢」「地域の集まり」「配偶者」「住居」「仕事の有無」「広報紙(市・区・自治会レベル)」であった。「高齢者交流」と各独立変数との間には有意な関連は認められず,「介護者交流」は,「年齢」「家族構成」「地域の集まり」「65歳以上の方と同居しているか」との間に有意な関連が認められた。「学習機会」は「地域の集まり」「広報紙(市・区レベル)」との間に有意な関連が認められた。
結論 高齢者福祉活動の必要性意識に影響を与えている要因は,内的要因(年齢,性別,その他)と外的要因(広報紙,地域の集まり,その他)の2つに分類することができる。内的要因に外的要因を重ねていく働きかけによって,地域住民の高齢者福祉活動に関する必要性意識を高めていくことができる可能性が示唆されたと言える。
キーワード 高齢者福祉活動,必要性意識,共有,地域住民,参加,エンパワメント
|
第54巻第2号 2007年2月 胃がんと肺がんにおける死亡年齢と罹患年齢の年次推移高橋 菜穂(タカハシ ナホ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) 亀井 哲也(カメイ テツヤ)谷脇 弘茂(タニワキ ヒロシゲ) 栗田 秀樹(クリタ ヒデキ) 橋本 修二(ハシモト シュウジ) |
目的 胃がんと肺がんにおいて,人口構成の変化を調整した上で,死亡率と罹患率とともに,死亡年齢と罹患年齢の年次推移を検討した。
方法 1975~1999年の性・年齢階級別の死亡数と罹患数から,年齢調整死亡率,年齢調整罹患率,調整平均死亡年齢と調整平均罹患年齢を算出した。
結果 胃がんにおいて,1999年の平均死亡年齢は男で70.9歳と女で73.0歳,平均罹患年齢は男で67.7歳と女で69.7歳であった。年齢調整死亡率と年齢調整罹患率は年次とともに低下傾向,調整平均死亡年齢と調整平均罹患年齢は上昇傾向であった。肺がんにおいて,1999年の平均死亡年齢は男で72.4歳と女で73.8歳,平均罹患年齢は男で71.1歳と女で71.6歳であった。年齢調整死亡率と年齢調整罹患率は上昇傾向であったが,1990年ごろから上昇の鈍化傾向あるいは横ばい傾向がみられた。調整平均死亡年齢と調整平均罹患年齢は上昇傾向であったが,1990年ごろから男で上昇の鈍化傾向,女で横ばい傾向がみられた。
結論 胃がんと肺がんにおいて,死亡年齢と罹患年齢が年次とともに大きく変化していることを示した。
キーワード 胃がん,肺がん,死亡年齢,罹患年齢,年次推移
|
第54巻第2号 2007年2月 地区単位のソーシャル・キャピタルが主観的健康感に及ぼす影響藤澤 由和(フジサワ ヨシカズ) 濱野 強(ハマノ ツヨシ) 小藪 明生(コヤブ アキオ) |
目的 地区を単位としたソーシャル・キャピタル変数が全体的健康感に対してどの程度,影響を及ぼしているかに関して明らかにすることを目的とした。
方法 日本国内に居住する満20歳以上75歳未満の男女3,000人を調査対象者とし,抽出方法は層化二段無作為抽出法を用いた。2004年2月に調査員による面接調査を実施し,1,910人(男性870人,女性1,040人)から回答を得た(回収率63.7%)。分析方法は,相関分析および性別,年齢,慢性疾患の有無,暮らし向き,ソーシャル・キャピタル(6項目)を独立変数,全体的健康感を従属変数とする重回帰分析を行った。なお,分析においては,分析単位を地区としていることから,各変数について平均値および割合を用いて地区単位への集約を行った。
結果 全体的健康感と相関が示されたソーシャル・キャピタルは5項目であり,さらに重回帰分析を行った結果,「私の住んでいるこの地区はとても安全である」「私の近所の誰かが助けを必要としたときに,近所の人たちは手をさしのべることをいとわない」「急病の時など,すぐにかかれる医療機関があって安心できる地域である」「私の地域では,お互いに気軽に挨拶を交し合う」において統計的に有意な関連が示された(p<0.05)。なお,慢性疾患率および暮らし向きについても有意な関連が示された(p<0.05)。
結論 本結果から,地区単位のソーシャル・キャピタルは,他の変数とともに全体的健康感に一定の影響を与えていることが明らかとなった。慢性疾患率や暮らし向きなどの変数が全体的健康感に影響を与えているのは非常に理解しやすいものであるが,これらの変数と同様に複数のソーシャル・キャピタル変数が全体的健康感に同程度の影響を与えていた点が注目に値する。今後は,ソーシャル・キャピタル概念の理論的検討,その健康への影響プロセス,そして規定要因としての分析上の問題を克服する必要があると考えられる。
キーワード ソーシャル・キャピタル,主観的健康感
|
第54巻第2号 2007年2月 都道府県における母子保健統計情報の収集・利活用状況に関する研究鈴木 孝太(スズキ コウタ) 薬袋 淳子(ミナイ ジュンコ) 成 順月(チェン シュンユエ)田中 太一郎(タナカ タイチロウ) 山縣 然太朗(ヤマガタ ゼンタロウ) |
目的 現在わが国において,市町村から都道府県,国へと伝達されている母子保健統計情報は,人口動態調査,地域保健・老人保健事業報告のみである。しかしながら今後,「健やか親子21」で提示している母子保健の取り組みなどについて目標値の設定・評価などを行う際には,それら以外の母子保健統計情報が必要である。そこで本研究では,都道府県における母子保健統計・情報の集計実態について調査し,その現状を把握することを目的とした。
方法 都道府県の母子保健担当者の連絡先(E-mailアドレス)を,都道府県ホームページなどから検索した。E-mailを用いて,担当者に母子保健統計情報の収集・利活用状況に関する調査票を送付し,回答をE-mailまたはFAXで回収した。具体的な調査内容は,市町村における母子保健統計情報を都道府県が把握・集計するシステムの有無,その情報の内容,乳幼児健診の形態(集団・個別),情報公開の有無などである。
結果 回答は全都道府県から得られ,45都道府県(95.7%)において市町村で集計したデータをまとめていた。しかし,情報内容については,乳幼児健診の受診率(100%)およびその内容・結果(77.8%)をほとんどの都道府県で集計している一方,妊婦の喫煙(6.7%)や小児の事故(15.6%)についてはあまり集計されていなかった。このように集計している情報の内容は都道府県によりかなりばらつきがあり,また政令市については政令市以外の市町村と一括して集計していない道府県が大半であった。
結論 国としてまとめている人口動態調査,地域保健・老人保健事業報告以外の母子保健統計情報について,45都道府県において市町村が集計した情報をまとめていたが,その内容にはばらつきがあるため,調査内容について今後より精査する必要がある。また今回の研究結果は,様々な母子保健の指標を評価するのに必要な,情報の標準化・規格化を目指すうえでの基礎資料となりうる。
キーワード 母子保健,乳幼児健診,健やか親子21,統計情報,情報公開
|
第54巻第2号 2007年2月 少子化の人口学的要因と社会経済的要因の解析小島 里織(コジマ サオリ) 上木 隆人(ウエキ タカト) 柳川 洋(ヤナガワ ヒロシ) |
目的 わが国の2000年出生率は1970年の約半分までに低下し,出生率低下の主な原因として晩婚化・晩産化が指摘される。代表的な社会経済指標を取り上げ,出生率などとの相関を検討して,出生率低下に影響を及ぼす社会経済的要因を明らかにする。
方法 1970年から2000年までの人口動態統計と国勢調査のデータをもとにして,わが国の出生率などの年次推移を1970年を1とした比で算出した。次に,25~29歳と35~39歳の有配偶率と有配偶出生率について,社会経済指標である第三次産業就業人口割合,15~44歳女子労働力,1人当たり県民所得との相関を,また20~24歳の有配偶率と有配偶出生率について進学率との相関を求めた。
結果 (1)2000年の出生率は1970年と比べて,20~24歳と25~29歳では半減し,30~34歳と35~39歳では低下の後で上昇した。有配偶率は全体に低下傾向で,20~24歳と25~29歳で半減した。有配偶出生率は20~24歳と25~29歳で横ばい,30~34歳と35~39歳で低下の後に上昇した。(2)有配偶率や有配偶出生率と社会経済指標との相関は,25~29歳有配偶率は第三次産業就業人口割合と,25~29歳有配偶出生率は女子労働力や1人当たり県民所得と,35~39歳の有配偶率と有配偶出生率は第三次産業就業人口割合と相関がみられた。20~24歳の有配偶率と有配偶出生率は進学率と負の相関を示した。(3)社会経済指標間の相関は,女子労働力は第三次産業就業人口割合や進学率と負の相関,1人当たり県民所得は進学率と正の相関を示した。
結論 女子労働力,第三次産業就業人口割合,1人当たり県民所得,進学率などの指標に現れる社会経済的要因が相互に関係しつつ,晩婚化,晩産化をもたらしたと考えられる。出生率低下への対応は,女子労働の問題や,出産・育児や子どもの教育に関連する経済的負担,住宅事情に関連する問題などを年代ごとにとらえる必要があろう。
キーワード 出生率,有配偶率,有配偶出生率,第三次産業就業人口割合,女子労働力,進学率
|
第54巻第5号 2007年5月 都道府県別たばこ消費本数と主要死因別標準化死亡比との関連竹森 幸一(タケモリコウイチ) |
目的 都道府県別たばこ消費本数と主要死因別標準化死亡比(以下SMR)との関連を検討することにより,都道府県における喫煙の健康影響について探求することを目的とした。
方法 各都道府県の2002年,2003年,2004年のたばこ売渡本数から返還本数と課税免除本数を差し引いた値を同年の各都道府県男女別15歳以上人口で除して,男女別15歳以上1人当たりたばこ消費本数を求めた。都道府県の男15歳以上1人当たりたばこ消費本数の年次間の相関と平均値の差をみた。都道府県別15歳以上1人当たりたばこ消費本数と全死因,悪性新生物(総数,胃,大腸,肝及び肝内胆管,気管・気管支及び肺),心疾患(総数,急性心筋梗塞)および脳血管疾患の各SMRとの相関係数を男女別に求めた。
結果 男15歳以上1人当たりたばこ消費本数は年次間に高い相関がみられ,2002年から2004年にかけて有意に低下していた。15歳以上1人当たりたばこ消費本数との間に,男の2002年で全死因,気管・気管支及び肺の各SMR,2003年で全死因,悪性新生物総数,気管・気管支及び肺の各SMR,2004年で気管・気管支及び肺のSMRに有意な正相関がみられた。女では2003年で悪性新生物総数のSMRに有意な正相関がみられた。15歳以上1人当たりたばこ消費本数と基本健康診査喫煙率,国民生活基礎調査喫煙率および国民栄養調査から計算した喫煙者指数との間に有意の正相関がみられた。
結論 都道府県別たばこ消費本数と主要死因別SMRとの相関関係から,気管・気管支及び肺などの主要死因で喫煙の影響を否定しえない結果が得られた。
キーワード たばこ消費本数,都道府県別標準化死亡比,悪性新生物,全死因
|
第54巻第2号 2007年2月 中都市在住高齢者の手段的ソーシャルサポート選好度とその構造-大都市在住高齢者との比較の視点に基づいた考察-権 泫珠(コン ヒョンジュ) |
目的 中都市在住高齢者が自分自身に手段的ソーシャルサポートが必要になったとき,誰に対して,どの程度の支援を求めたいと考えているのかといった手段的ソーシャルサポート選好度およびその構造を明らかにすることを目的とした。また,大都市在住高齢者を対象とした同様の先行研究の結果と比較し,高齢者の選好度の特徴を考察する。
方法 愛知県A市に在住する65歳以上の高齢者のうち,900人を無作為抽出し,自記式質問紙を用いた郵送調査を行った。調査期間は,2004年11月1~15日であり,有効回収率は51.6%(464票)であった。分析方法は,手段的ソーシャルサポート選好度の構造を把握するために因子分析を行った。また,因子ごとの平均値からそれぞれのサポート源に対する選好の程度を把握した。その結果を大都市高齢者対象の先行研究と比較した。
結果 手段的サポートに対する選好度は,家事や介護サポートを家族に求めたいという選好度が最も高く,次いで,介護や経済サポートを行政や福祉機関に求めたいという選好度が高かった。また,因子構造は,「フォーマルサポート源への選好」「家族以外のインフォーマルサポート源への選好」「家族への選好」「経済サポート/フォーマル機関への選好」の4因子となった。因子ごとの平均値は,「家族への選好」が最も高く,次いで「経済サポート/フォーマル機関への選好」「フォーマルサポート源への選好」「家族以外のインフォーマルサポート源への選好」の順であった。
結論 研究結果は大都市高齢者を対象とした先行研究とも一致するものであり,高齢者の手段的ソーシャルサポート選好度の構造および選好順位は地域間での違いはみられず,一般化できる可能性が示唆された。一方,「家族への選好」因子の平均値は,中都市高齢者の方で高く,地域差がみられた。
キーワード 中都市在住高齢者,ソーシャルサポート選好度,手段的ソーシャルサポート,大都市在住高齢者,地域差
|
第54巻第3号 2007年3月 静岡県における自殺死亡の地域格差および社会生活指標との関連久保田 晃生(クボタ アキオ) 永田 順子(ナガタ ジュンコ)杉山 眞澄(スギヤマ マスミ) 藤田 信(フジタ マコト) |
目的 本研究の目的は,自殺死亡の低率県である静岡県内の自殺死亡の地域格差について確認するとともに,自殺死亡に関連する社会生活指標を検討し,今後の静岡県における自殺予防施策の基礎資料を得ることとした。
方法 静岡県内における男女別の自殺死亡標準化死亡比(SMR)(1999~2003年)をマップ化して,地域格差を確認した。また,地域の社会生活指標を収集し,自殺死亡SMRとの関連について,主成分分析および重回帰分析を行い検討した。
結果 静岡県内の自殺死亡SMRは,男女とも同様の分布を示し,市よりも町の方が高い値を示した。また,女性では自殺死亡SMRが200を超える地域が3町あり,男性より地域間の格差が認められた。本研究の社会生活指標を主成分分析した結果,第1主成分は都市化の程度を分ける指標,第2主成分はサービス産業と生活の豊かさを分ける指標として解釈された。さらに,自殺死亡SMRを加えた分析においても,因子構造は同様であった。自殺死亡SMRを目的変数に,社会生活指標を説明変数に用いた重回帰分析を行った結果,男性では「小売店数(人口千対)」,女性では「離婚率(人口千対)」「第二次産業就業者比率(%)」「健康相談延べ人数(人口千対)」が選択された。このうち,自殺死亡SMRとの単相関では,男性の「小売店数(人口千対)」のみ,有意な正の相関を認めた。
結論 静岡県の自殺死亡SMRは,男女とも都市化の程度が影響することが示唆された。この状況は,秋田県,岐阜県との報告と同様であり,自殺予防には過疎地域への働きかけが重要であると考えられた。
キーワード 自殺,標準化死亡比,社会生活指標,地域格差
|
第54巻第3号 2007年3月 青森県および長野県の市町村別たばこ売渡本数と
竹森 幸一(タケモリ コウイチ) |
目的 青森県および長野県の市町村別たばこ売渡本数と主要死因別標準化死亡比(以下SMR)との関連を検討することにより, 市町村における喫煙の健康影響について探求することを目的とした。
方法 各市町村の2002年,2003年,2004年のたばこ売渡本数を同年の男女別15歳以上人口で除して,男女別15歳以上1人当たりたばこ売渡本数を求めた。青森県および長野県の男15歳以上1人当たりたばこ売渡本数の年次間の相関と平均値の差をみた。また各年の青森県と長野県の男15歳以上1人当たりたばこ売渡本数の県間の差をみた。15歳以上1人当たりたばこ売渡本数と全死因,悪性新生物(総数,胃,大腸,肝及び肝内胆管,気管・気管支及び肺),心疾患(総数,急性心筋梗塞),脳血管疾患のSMRとの相関係数を青森県と長野県について男女別に求めた。
結果 男15歳以上1人当たりたばこ売渡本数は両県とも年次間に高い相関がみられ,2002年から2004年にかけて有意に低下し,2002年,2003年,2004年ともに青森県が長野県より有意に高かった。15歳以上1人当たりたばこ売渡本数との間に,青森県の場合,男の2002年で悪性新生物総数,大腸,2003年で悪性新生物総数,胃,大腸,脳血管疾患,2004年で全死因,悪性新生物総数,胃,大腸,脳血管疾患に有意な正相関がみられた。女では関連がみられなかった。長野県の場合,男の2002年で胃,大腸,2003年で胃,大腸,2004年で大腸に有意な正相関がみられ,女の2002年で悪性新生物総数,大腸,2003年で悪性新生物総数,大腸,2004年で悪性新生物総数,大腸に有意な正相関がみられた。
結論 市町村別たばこ売渡本数と主要死因別SMRとの相関関係から,多くの主要死因で喫煙の影響を否定しえない結果が得られた。
キーワード たばこ売渡本数,市町村別標準化死亡比,悪性新生物,心疾患,脳血管疾患
|
第54巻第3号 2007年3月 医療費からみた国保ヘルスアップモデル事業の評価-福島県二本松市における個別健康支援プログラムの検討-小川 裕(オガワ ユタカ) 安村 誠司(ヤスムラ セイジ) |
目的 生活習慣病の一次予防を目的とした個別健康支援プログラムに基づいて実施されたヘルスアップモデル事業を2年間の追跡により医療費の面から評価する。
方法 福島県二本松市における基本健康診査または国保人間ドック受診者のうち,脂質,血糖,血圧,BMIのいずれかで「要指導」または「要医療」であった者をモデル事業の対象者として介入群と対照群を設定し,介入年1年間とその後2年間の追跡が可能であった40~69歳のそれぞれ119人についてレセプト情報に基づき医療費に関する分析を行った。
結果 受療状況では,有意ではなかったが「レセプトが認められなかった」者が介入群では経時的に増え,介入後2年には対照群より多かったこと,「入院レセプトが認められた」者がいずれの年にも対照群に多く,その差が介入年より介入後に大きかったことが介入効果を示唆する結果であった。また,レセプト件数,点数,日数の検討では,入院外のレセプト点数が対照群のみで有意な増加を示し,入院外と入院を合計した件数,点数,日数のいずれも介入2年後の増加率が対照群で高かった。このうち点数の年齢別検討では,60歳以上で介入効果が大きいことが示唆された。さらに介入年に入院外レセプトのみ認められた者について個人ごとにレセプト件数,点数,日数の変化を比較したところ,いずれも介入後に減少した者の割合は介入群で高く,60歳以上ではレセプト件数,点数,日数における減少者の割合が介入後2年でも維持される傾向がみられた。介入年における入院外点数の「高」・「低」別に比較した検討では,「高」点数群において介入効果が高く,効果が持続される可能性が示唆された。
結論 実施した個別健康支援プログラムが,医療費関連指標を低下させること,とくに60歳代で入院外レセプト点数の比較的高い群で介入効果が大きくなる可能性が示唆された。
キーワード 生活習慣病,一次予防,個別健康支援プログラム,医療費,ヘルスアップモデル事業
|
第54巻第3号 2007年3月 国民栄養調査の解析による「健康日本21」目標達成の予測-肥満を中心に-若林 チヒロ(ワカバヤ シチヒロ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) 萱場 一則(カヤバ カズノリ)三浦 宜彦(ミウラ ヨシヒコ) 柳川 洋(ヤナガワ ヒロシ) |
目的 「健康日本21」で挙げた項目は現状のまま推移して2010年までに目標を達成するか否かを性年齢階級別の人口集団ごとに検討した。特に肥満者割合とそれに関連する栄養・食生活,身体活動・運動の項目を中心に,今後強化すべき対策について検討した。
方法 国民栄養調査で,肥満者割合(BMI≧25.0),脂肪エネルギー比,日常生活における運動習慣のある者の割合,日常生活における歩数について性年齢階級別に1995年から2003年までの値で回帰分析を行い,2010年における予測値を算出して,「健康日本21」目標達成の可否を検討した。
結果 肥満者割合について2010年までに目標を達成できるのは女性の40歳代以下のみで,男性のすべての年齢階級と女性の50歳代以上では目標を達成することができないと予測された。特に30歳代以上の男性の肥満者割合は増加傾向が強く,2010年には40%近い値になると予測された。脂肪エネルギー比では40歳代以上,運動習慣者割合では男女共60歳代のみ,日常生活における歩数では20歳代男性と40歳代女性のみが目標を達成できると予測され,他の性年齢階級では目標達成は困難と予測された。肥満者割合で目標達成できないと予測された人口集団のうち,脂肪エネルギー比では男性30歳代以下,運動習慣者割合では男性50歳代以下と女性50歳代,日常生活における歩数では男性30歳代以上と女性50歳代以上では目標達成できないと予測され,これら人口集団に対して対策を強化する必要があると考えられた。
結論 「健康日本21」で肥満者割合について挙げた目標の達成は大部分の性年齢階級で困難と予測された。肥満に関連する栄養・食生活や身体活動・運動に関する項目でも目標達成困難な集団が多く,今後集団ごとにきめ細かな対策をとりいれる必要がある。
キーワード 健康日本21,国民栄養調査,肥満,健康政策,栄養・食生活,身体活動・運動
|
第54巻第3号 2007年3月 吹田市基本健診での生活習慣とメタボリックシンドロームに関する研究奈倉 淳子(ナグラ ジュンコ) 小久保 喜弘(コクボ ヨシヒロ) 川西 克幸(カワニシ カツユキ)小谷 泰(コタニ ヤスシ) 伊達ちぐさ 岡山(ダテ チグサ) 明 友池(オカヤマ アキラ) |
目的 都市住民のメタボリックシンドローム(Mets)有病率とMets定義病態に関連する生活習慣の特徴を性・年齢ごとに評価した。
方法 平成16年度吹田市基本健康診査受診者のうち問診票で有効回答が得られた30~89歳の26,522人の男女を対象とした。MetsはUS National Cholesterol Education Program: Adult Treatment Panel Ⅲの基準を改変して診断した。Mets有病率,Mets有病者での構成因子の有病率を求め,さらにMetsと関連する生活習慣の検討を行った。
結果 30~89歳でのMetsの有病率は,男性19.4%,女性10.7%であった。Mets有病者のうち,若年群では肥満の有病率が高く(30歳代:男性82%,女性90%),高齢群では血圧高値の有病率が高い傾向にあった(80歳代:男性99%,女性98%)。生活習慣では,「他の人より食べる量が多い」「早食いである」「睡眠が不規則である」「立位・歩行時間が1時間未満である」は,男女ともすべての年代でMetsと関連していた。4項目のいずれにも該当しない対象者と1項目該当の対象者のMetsの多変量調整オッズ比は1.29~2.17の値をとり,2個では1.66~4.60,3個では3.13~5.09で,4個すべてに該当する対象者では5.36であった。
結論 Metsの構成因子は年齢により異なっていたが,過食・早食い・不規則な睡眠・運動不足はすべての年代でMetsとの関連がみられ,これらを多く満たす人ほどMetsのリスクが高かったことから,これら4つの項目はMetsの予防・改善の保健指導の項目となりうる生活習慣と考えられた。
キーワード メタボリックシンドローム,有病率,生活習慣
|
第54巻第4号 2007年4月 生活習慣病予防事業による医療費への影響亀 千保子(カメ チホコ) 馬場園 明(ババゾノ アキラ) 石原 礼子(イシハラ レイコ) |
目的 現在,多くの自治体で生活習慣病予防事業が行われているが,無作為比較対照研究による介入前後での医療費抑制効果の報告はされていない。そこで,本研究では,無作為比較対照研究による予防事業の介入前,介入中,介入後での医療費とその変化を比較し,介入による医療費への影響を明らかにすることを目的とした。
方法 対象者を目標達成型プログラム介入A群,従来型プログラム介入B群の2群に無作為抽出法により割付け,2群間および両群合わせた全体で,介入前々年,前年,介入年の介入前中後の3期間における平均入院外医療費(歯科は除く)についてウィルコクソン符号付順位検定により比較を行った。なお,医療費は年齢に比例して高くなるため,医療費変化を介入前中後で比較し,増加抑制効果をみることで年齢による影響を考慮した。群間差の比較は,ウィルコクソン順位和検定を行った。介入中期間においては,傷病マグニチュード按分法(PDM法)ver.3を用いて,傷病別にも同様の解析を行った。さらに,複数・多・重複受診件数およびこれら受診件数の変化についても同様の解析を行った。
結果 介入中期間の平均入院外医療費は,両群および全体において平成14年度と比べて15年度には有意に増加,平成15年度と比べて16年度には,有意差はないが減少傾向がみられた。医療費変化では,介入中期間の全体においてのみ有意な増加抑制が認められた。有意な増加抑制は他の期間ではどの群においても認められなかった。介入中期間における傷病別分析では,両群および全体で有意な入院外医療費減少と増加抑制が認められた傷病に重症な傷病は含まれていなかった。
結論 両群および全体において重症でない疾患の有意な平均入院外医療費減少と増加抑制につながり,複数受診件数も介入A群と全体において有意な増加抑制が認められた。しかしながら,4カ月間の介入では,有意差をもって平均入院外医療費減少は示せず,介入中期間では全体における増加抑制効果は有意差をもって示せたもののプログラムA,B間の差を有意に示すに至らなかった。生活習慣病におけるこれらの効果を明らかにするためには,無作為比較対照試験での長期間の追跡が必要であると考えられる。
キーワード 生活習慣病予防事業,保健事業,医療費,レセプト,複数受診,無作為比較対照試験
|
第54巻第4号 2007年4月 認知症高齢者を居宅で介護する家族介護者の主観的QOLに関する研究-“介護に関する話し合いや勉強会”への参加経験や参加に対する意思との関連性について-朴 偉廷(パク ウィジョン) 遠藤 忠(エンドウ タダシ) 佐々木 心彩(ササキ シンサイ)時田 学(トキタ ガク) 長嶋 紀一(ナガシマ キイチ) |
目的 認知症高齢者を居宅で介護する家族介護者の“介護に関する話し合いや勉強会”の参加状況および参加に対する意思について把握すること,家族介護者の主観的QOL(現在の満足感,生活のハリ,心理的安定感)を測定すること,両者の関連性について検討し,家族介護者支援を考案するための基礎資料を得ることを目的とした。
方法 調査対象者は,A県で要介護高齢者を居宅で介護する家族介護者2,262名であった。そして「介護に関する話し合いや勉強会」9項目(栄養,介護の仕方,介護保険,認知症の方との関わり方,認知症の知識,介護サービス,医療サービス,身体的な健康管理,介護予防教室のような集まり)の参加の有無(経験群,未経験群),未経験群の参加への意思(経験希望群,無関心群),家族介護者の主観的QOL尺度,要介護高齢者の認知障害の程度を把握するための日本語版SMQ等を調査した。
結果 1,462名の調査票が回収され(回収率64.6%),調査項目に未回答のあった671名と日本語版SMQにおいて非認知症と評価された55名を除いた736名の認知症高齢者の家族介護者を分析対象とした。介護に関する話し合いや勉強会の参加状況は,経験群で10.7~23.9%,未経験群のうち無関心群は40.4~54.4%,経験希望群は31.1~45.5%と参加経験者の割合が低かった。介護に関する話し合いや勉強会9項目の参加状況および参加に対する意思を独立変数,主観的QOL尺度総得点を従属変数,主観的QOLと相関係数において有意であった家族介護者の年齢,家族介護者の健康状態,日本語版SMQを統制変数として共分散分析を行った結果,全項目において有意差が認められ,多重比較の結果から,特に認知症の方との関わり方,認知症の知識,介護の仕方の項目において,無関心群は経験群に比べて主観的QOLが低いことが示唆された。
結論 特に無関心群の家族介護者が,認知症高齢者の介護をひとりで抱え込まず,認知症の疾患や関わり方の知識を得る場,家族介護者同士の交流の場など介護に関する話し合いや勉強会に参加意欲や意思をもち,積極的に参加していくとともに,主観的QOLを高めていくこと,そのための効果的な開催方法を考案することが課題として考えられた。
キーワード 認知症高齢者,介護に関する話し合いや勉強会,家族介護者,主観的QOL
|
第54巻第4号 2007年4月 母親の育児関連Daily Hasslesと児に対するマルトリートメントの関連唐 軼斐(ト ウジヒ) 矢嶋 裕樹(ヤジマ ユウキ) 中嶋 和夫(ナカジマ カズオ) |
目的 母親の育児に関連したDaily Hassles(DH)の経験頻度およびストレス強度を明らかにし,Hillsonらのモデルに基づき,育児関連DHの経験頻度およびストレス強度と,虐待やネグレクトといったマルトリートメント(不適切な関わり)との関連を検討することを目的とした。
方法 2004年11月現在,S県S市内の協力の得られた保育所16カ所を利用していたすべての母親1,700人を対象に,無記名自記式による質問紙調査を実施した。育児関連DHの測定には,Parenting Daily Hassles Scale(PDH)を日本語訳して使用した。母親の児に対するマルトリートメントは,母親の子どもに対するマルトリートメント傾向指標を用いて測定した。統計解析には構造方程式モデリング(Structural Equation Modeling: SEM)を使用し,育児関連DHの経験頻度が,それら育児関連DHのストレス強度を介して,児に対するマルトリートメントの実施頻度に影響を与えるといったモデルを構築し,そのモデルのデータに対する適合度と各変数間の関連を検討した。
結果 育児関連DHの経験率をみると,ほとんどの項目において8割以上の母親が経験していた。また,育児関連DHに対するストレス強度得点も,米国の母親を対象とした先行研究とおおむね一致していた。SEMの結果,育児関連DHの下位領域「育児タスク」の経験頻度が高い者ほど,ストレスを強く感じ,心理的虐待およびネグレクトの発生頻度が高かった。また,育児関連DHの下位領域「挑戦すべき児の行動」の経験頻度が高い者ほど,ストレスを強く感じ,身体的虐待と心理的虐待の発生頻度が高かったことが明らかとなった。
考察 育児タスクが心理的虐待やネグレクトを促進していたことから,育児ストレス軽減のために,育児の代行機能を有する託児サービスの重要性が示唆された。また,児の挑戦すべき行動が身体的虐待と心理的虐待と関連していたことから,母親が児の挑戦すべき行動に適切に対応できるように,地域育児教室や両親教室等の機会を利用して,児の発育や発達に関する情報提供や児の挑戦的な行動に対する母親の受容的な態度の養成を促す必要性が示唆された。
キーワード 児童虐待,ストレス,母親,育児
|
第54巻第4号 2007年4月 脳卒中患者における自宅退院の時代変遷に関する研究-富山県脳卒中情報システム事業より-須永 恭子(スナガ キョウコ) 成瀬 優知(ナルセ ユウチ) 遠藤 俊朗(エンドウ シュンロウ)野村 忠雄(ノムラ タダオ) 野原 哲夫(ノハラ テツオ) 福田 孜(フクダ ツトム) 垣内 孝子(カキウチ タカコ) 木谷 隆一(キタニ リュウイチ) 飯田 博行(イイダ ヒロユキ) 瀬尾 迪夫(セオ ミチオ) |
目的 入院患者数増と高齢化が進む脳卒中患者の自宅退院には,社会的支援が必要な場合が多く,在宅療養サービス利用の増加が予測される。そこで,富山県脳卒中ケアシステム事業登録者の自宅退院割合と富山県の在宅療養支援サービスの充足・利用状況を把握し,社会的支援の影響下,脳卒中患者の自宅退院の動向を考察した。
方法 富山県脳卒中情報システム事業の登録者のうち,発症年が平成3年7月から平成15年12月で,退院時死亡と退院先未定を除いた14,952名を抽出した。そのうち,30歳以上の14,040名と55歳以上の12,160名を分析の対象とした。分析には,登録情報のうち,「退院先・年齢・発症年・自力による行動範囲・認知症状の有無」を使用した。自宅退院の概況として30歳以上の性別・年齢別・発症年次(時代)別の各々について自宅退院割合を,自宅退院の時代変遷として,1991~1993年を基準に年齢調整自宅退院比と時代以外の影響を調整した自宅退院のオッズ比を求めた。
結果 退院先の割合は,自宅退院が最も高く69.9%で,次いで転院,その他の順だった。年齢別,時代別の動向では,男女ともに高齢と時代推移に伴い自宅退院割合はおおむね減少していた。1991~1993年を基準とした時代別年齢調整自宅退院比では,男性の1994~1995年のみ1を越え,それ以外では男女ともに1未満であった。自宅退院のオッズ比について,1991~1993年に対する各時代群の結果は,すべて1以下で,時代推移に伴い低下していたが,介護保険開始年の2000~2001年では,その低下の傾きがやや緩やかになっていた。医療・福祉制度改正を考慮し,介護保険開始以降,各施設数・利用者数の推移を社会的支援の時代変遷として確認した。富山県の療養型病床群の病床数・新患者数は経年的に増加し,平成12~15年の病床利用率は90%台であった。また,介護老人福祉施設,介護老人保健施設の利用者数増加率は全国より高く,介護老人福祉施設の方が高かった。
結論 自宅退院割合の時代推移に伴う低下が明らかになった。この低下を介護保険開始以降の在宅療養サービスにおける各施設数・利用状況から検討した結果,介護老人福祉施設・療養型病床群の施設充実とその利用が進む中,脳卒中患者は退院先の幅を広げ,自宅退院以外を選択していることが考えられた。
キーワード 脳卒中,自宅退院,脳卒中情報システム事業,介護保険
|
第54巻第5号 2007年5月 健診実施の適正間隔に関する検討須賀 万智(スカマチ) 吉田 勝美(ヨシダカツミ) |
目的 定期健診を効率的かつ効果的なものにするために,健診の内容(項目)を見直す動きがあるが,健診実施の適正間隔に関する検討もまた必要である。本研究では,健診実施の適正間隔について,某事務系事業所の定期健診データベースを用いて,異常所見のない状態が連続している者における健診実施の省略の可否を検討した。
方法 某事務系事業所の定期健診データベースから,BMI,血圧,空腹時血糖,総コレステロール,中性脂肪,尿酸の6項目を①連続4年分得られた30~59歳の男性12,045名,女性1,708名,②連続5年分得られた30~59歳の男性10,959名,女性1,496名を対象とした。①の連続4年分のデータでは2年連続異常所見のない者,②の連続5年分のデータでは3年連続異常所見のない者を項目ごとに抽出して,(A)「1年後の検査から検出された異常所見の割合(1年後有所見率)」と「1年後と2年後の検査から検出された異常所見の割合(2年間累積有所見率)」,(B)「1年後と2年後の検査から検出された異常所見の割合(2年間累積有所見率)」と「2年後の検査から検出された異常所見の割合(2年後有所見率)」について,性別,年齢別,BMI別に,二項分布のZ値による率の差の検定を実施した。
結果 (A)の1年後有所見率と2年間累積有所見率の比較について,男性は5項目すべてで有意差を認めた。女性は高血糖について3年連続異常所見のない45~59歳群と2年連続異常所見のない肥満なし群,高中性脂肪について2年連続異常所見のない45~59歳群と3年連続異常所見のない肥満あり群,高尿酸について2年連続異常所見のない者のすべての群で有意差を認めず,それ以外については有意差を認めた。(B)の2年間累積有所見率と2年後有所見率の比較について,男性は5項目すべてで有意差を認めた。女性は高血糖について2年連続異常所見のない者の30~44歳群を除いたすべての群と3年連続異常所見のない者のすべての群,高コレステロールと高中性脂肪について3年連続異常所見のない45~59歳群,高尿酸について2年連続異常所見のない者および3年連続異常所見のない者のすべての群で有意差を認めず,それ以外については有意差を認めた。
結論 血圧,空腹時血糖,総コレステロール,中性脂肪,尿酸の5項目のうち,尿酸は2年連続異常所見がない女性において翌年の検査を省略しうるが,それ以外は少なくとも年1回検査することを原則にすべきと考えられた。
キーワード 定期健診,検査間隔,生活習慣病予防
|
第54巻第5号 2007年5月 介護予防施策における対象者抽出の課題-特定高齢者と要支援高齢者の階層的な関係の検証-石橋 智昭(イシバシトモアキ) 池上 直己(イケガミナオキ) |
目的 厚生労働省によって新たに提示された介護予防施策では,「一般高齢者」「特定高齢者」「要支援高齢者」「要介護高齢者」の4つの階層を用意し,対象と給付の関係を明確化した。しかし対象者の選定には『基本チェックリスト』と『要介護認定方式』が並行的に運用され,そこから抽出される「特定高齢者」と「要支援高齢者」の境界や階層性の関係は,いまだに明らかにされていない。本研究では,「要支援高齢者」の候補者である旧要支援,旧要介護1の認定者に対して,『基本チェックリスト』により試行的に判定し,「特定高齢者」と「要支援高齢者」との間の階層的な関係について検証を行った。
方法 対象は,東京都A市において旧要支援,旧要介護1の認定を受けた者のうち,介護保険以外の生活支援型サービスを利用している在宅高齢者767名である。調査は,2006年2月に自記式の郵送調査によって実施し,回収率は92.3%であった。調査内容は,厚生労働省の『基本チェックリスト』およびIADL(手段的日常生活動作)5項目の遂行能力を問う項目を用いた。本研究では,すべての調査項目に回答した456名(旧要支援:107名,旧要介護1:349名)を分析対象とした。
結果 旧要支援,旧要介護1の認定者に『基本チェックリスト』による判定を試行した結果,特定高齢者に選定されたのは,旧要支援では33.6%,旧要介護1では57.8%となり,「要支援高齢者」であるにもかかわらず「特定高齢者」には選定されないケース,つまり施策の想定とは逆の階層関係となるケースが,約半数に出現することが明らかとなった。次にIADL5項目による自立者の割合を確認した結果,旧要支援,旧要介護1認定者の54.8%がすべてのIADL項目が自立していた。これに対して,IADLが非自立であった者の4分の1に当たる25.7%が特定高齢者に選定されなかった。
結論 2つの異なる基準から抽出された特定高齢者と要支援高齢者の間には,階層関係が逆転しているケースが約半数にみられ,両者を階層的に位置づけるのは困難であることが明らかとなった。その要因の1つは,新たに開発された基本チェックリストが,要介護認定との階層的な関係を十分に考慮せずに作成されたことにある。もう1つは,要介護認定方式が,IADLの能力を適切にスクリーニングできず,自立(非該当)との境界が曖昧になっている点が示唆された。今後,介護予防施策を一貫したシステムとして構築するためには,介護予防施策の対象者の統合も含めて,基本チェックリストと要介護認定方式の抜本的な見直しが不可欠である。
キーワード 介護予防,要介護認定方式,基本チェックリスト,給付区分,特定高齢者
|
第54巻第5号 2007年5月 がん検診受診行動に関する市民意識調査川上 ちひろ(カワカミ) 岡本 直幸(オカモトナオユキ) 大重 賢治(オオシゲケンジ)杤久保 修(トチクボオサム) |
目的 日本が世界一の長寿国であることはすでに周知の事実であるが,この長寿による人口の高齢化に伴い死亡原因も大きく変化し,昭和56年以降,死因の第1位はがんである。がん対策は高齢化社会での重要な保健政策課題であり,なかでも,がん検診の受診率を向上させることは早期発見・早期治療を行う上で非常に重要になってきている。本研究では,がん検診の受診行動に影響を与える要因について質問票による調査を実施し分析を行った。
方法 横浜市在住の40~69歳の男女3,000人を対象に無記名自記式による質問票調査を行った。調査実施期間は平成18年2~3月であり,この間に調査票の配布,回収を行った。本研究では40歳代の回答率が30%に届かなかったため,50・60歳代の回答について分析を行った。50・60歳代への質問票送付は2,000通で,21通があて先不明等にて返送,611人より回答を得た(回答率30.9%)。主な調査項目は,1)がん検診の受診経験,2)病気の予防に対する責任,3)病気の予防に支払える金額,4)がん検診を受診する際の受診行動に影響を与える因子(コンジョイント分析)である。本調査では,検診場所,自己負担額,検診の所要時間,検診の信頼性を受診行動に影響を与える因子として設定し分析した。
結果 1)がん検診の受診経験は,年1回受診(35.8%),数年に1回受診(30.3%),受診経験なし(33.2%)であった。2)病気の予防に対する責任について,責任者を個人・行政(市町村)・国の3者に分け,全体で100%になるように回答を求めた。個人の責任が50%と回答した人が24.5%と最も多く,次いで60~70%と回答した人が21.3%だった。3)世帯全体で1年間に病気の予防に支払える金額を尋ねた結果,1万円以上5万円未満との回答が,最も多く43.7%であった。4)仮想状況でのがん検診受診希望を質問した結果,がん検診の受診行動に影響を与える因子は検診にかかる時間と費用であった。
結論 病気の予防は個人の責任で行うべきとの回答者が多い反面,がん検診に費用や時間をかけることができないという回答が多かった。このことを踏まえ,住民にとって受診行動を起こしやすくなるような検診システムを構築し受診率を向上させることが,早期発見・早期治療のための課題のひとつであると考えられる。
キーワード がん検診,受診率,質問票調査,受診行動,コンジョイント分析
|
第54巻第5号 2007年5月 保健医療福祉分野における地方自治体の施策の目標と指標橋本 修二(ハシモトシュウジ) 逢見 憲一(オオミケンイチ) 曽根 智史(ソネトモフミ)遠藤 弘良(エンドウヒロヨシ) 浅沼 一成(アサヌマカズナリ) 中嶋 潤(ナカジマジュン) 浜田 淳(ハマダジュン) 三觜 文雄(ミツハシフミオ) 藤崎 清道(フジサキキヨミチ) |
目的 保健医療福祉分野において地方自治体の施策の推進上,その目指す目標と実施状況について,複数の地方自治体を広域的な視点から比較することが重要と考えられる。ここでは,地方自治体の施策が目指す目標およびその実施状況を表す指標について,選定の基本的考え方を定めるとともに,具体案の作成を試みた。
方法 複数の専門家が議論を重ね,全員の合意によって選定の基本的考え方を定めた。その基本的考え方に従って,保健医療福祉のあるべき姿や地域差の状況などを考慮しつつ,同様の進め方により具体案を作成した。
結果 基本的考え方において,選定のねらいは保健医療福祉分野における地方自治体による施策の実施状況を把握し,今後の施策の推進に資することと定めた。目標の選定では地域住民の視点に基づくこと,基本的目標,目標,具体的目標の層的構造とした。指標の選定では具体的目標に対応すること,結果指標,中間指標,取り組み指標の層的構造とした。結果指標は具体的目標の達成状況を,取り組み指標は施策の投入した量と質を,中間指標はその中間段階の進捗状況を表すものとした。具体案において,基本的目標は「健康で安心して暮らせる地域社会」「生きがいと尊厳をもって暮らせる地域社会」「安心して子育てできる地域社会」の3つとした。基本的目標ごとに3つの目標,目標ごとに1~4の具体的目標とした。具体的目標ごとに,1~4の結果指標,0~5の中間指標,1~5の取り組み指標を定めるとともに,評価・留意点を示した。
結論 目標と指標の選定の基本的考え方と具体案を提示した。今後,実際の使用に向けて様々な面から検討を重ねることが重要であろう。
キーワード 指標,施策,保健医療福祉,地方自治体
|
第54巻第5号 2007年5月 質問紙健康調査票THIに対する新総合尺度の特性と有効性浅野 弘明(アサノヒロアキ) 竹内 一夫(タケウチカズオ) 笹澤 吉明(ササザワヨシアキ)大谷 哲也(オオタニテツヤ) 小山 洋(コヤマヒロシ) 鈴木 庄亮(スズキショウスケ) |
目的 質問紙健康調査票THI(Total Health Index)は,妥当性や信頼性の検討が数多くなされ,様々な疫学調査で応用されるとともに,職場・地域・学校における健康増進活動にも利用されてきた。THI調査に対するパソコン支援システムの開発を契機に,基準集団を見直し新基準集団を設定するとともに,従来の尺度に主成分分析を適用し構築した新総合尺度の利用を開始した。その後の調査で新総合尺度の有効性が確認できたので,死亡傾向との関連性も含め報告する。
方法 2003年に設定した新基準集団のデータを用い,「多愁訴,呼吸器,目と皮膚,口と肛門,消化器,直情径行,虚構性,情緒不安定,抑うつ,攻撃性,神経質,生活不規則」の12尺度に対し主成分分析を適用し,T1,T2の2主成分を導出した。必要な統計処理を行い,特徴を抽出するとともにその有効性を検証した。また,7年後の死亡・転出データに対しCoxの比例ハザードモデルを適用し,T1,T2と死亡傾向の関連性についても検討した。
結果 第1主成分T1は,全尺度の変動をよく吸収していた。特に,T1が5ptl(パーセンタイル値)未満あるいは95ptl以上の場合,12尺度の個人変動はほぼ平均的パターンに限定され,健康状態を総合的に判定する指標として好ましい性質を持つことが確認された。さらに,死亡傾向とも統計的に有意な関連性が認められ,T1が中央値から95ptlまで上昇する(健康状態が悪くなる)と死亡リスクが1.4倍になることが判明した。これに対してT2は,1尺度並の情報しか有しておらず,さらに,死亡との関連も明確ではなかったが,心と体の健康バランスを示しており,T1を補足する指標として活用できることが示唆された。
考察・まとめ パソコンを利用した支援システム「THIプラス」の開発を契機に,アドバイスシートの返却を開始した。その過程で,12尺度+3傾向値を要約する総合尺度が必要となった。今回構築したT1は,総合尺度としてふさわしい性質を持つばかりでなく,身体表現性障害とも密接に関連しており,意義深い尺度になっていることが確認された。また,T2は従来の尺度・傾向値にはない特徴を有しており,これらと併用できることが示唆された。今回の知見を活用し,個人の心の健康対策や生活習慣病の予防に役立つ,より有効なアドバイスシステムを構築していきたいと考えている。
キーワード THI,質問紙健康調査票,総合尺度,死亡リスク
|
第54巻第4号 2007年4月 基準病床数制度による病床数への影響に関する研究-入院需要量の変化に対する病床数の変化について-溝口 達弘(ミゾグチ タツヒロ) 堀口 逸子(ホリグチ イツコ) 丸井 英二(マルイ エイジ) |
目的 基準病床数制度が,病床数の増減に与えた影響を明らかにし,また,もし仮に,現状で基準病床数制度を廃止した場合に,どの程度病床が増床するのか検討することを目的とした。
方法 対象は,病床の種別にかかわらず病院における全病床および全入院患者とした。病床供給の検討は,入院需要量の変化を考慮した上で行うこととし,入院需要量の変化として,予想される入院患者数の年次推移を推計し用いることとした。推計は昭和59年,昭和62年,平成2年,平成5年,平成8年の5つの時点を基準として行った。推計された5つの入院患者数の年次推移を,それぞれ基準とした時点のモデルと呼ぶこととし,各モデルの比較検討,実際の人口との関連および実際の病床数との比較,基準病床数制度導入前のモデルから求めた平成16年の病床数と実際の病床数との比較を行った。
結果 5つのモデルは,いずれも年々増加する結果となった。平成16年時点において比較すると,多い方から,昭和62年モデル,平成2年モデル,昭和59年モデル,平成5年モデル,平成8年モデルの順であった。いずれのモデルにおいても,総人口との相関が強く,それ以上に65歳以上人口との相関が強かった。65歳未満人口とは負の相関が強かった。基準病床数制度導入前のモデルから算出された病床数と実際の平成16年の病床数との差は,53~62万床であった。
結論 必要病床数制度が制定されて以降現在に至るまで,入院需要は高齢化による影響で常に増加傾向にあり,介入等何らかの要因がない限り,病床数も増加しようとする傾向があったと考えられた。必要病床数制度導入以降,予想される入院需要の増加を上回る病床数の増加が一時的にあったものの,平成5年以降は,入院需要の増加に対して病床数は減少し,昭和59年時点と比べて限定された入院需要にしか対応できていないことが示唆された。また,基準病床数制度を撤廃すると,平成16年現在で,約50万床以上増床する可能性があることが示唆された。
キーワード 医療計画,病床規制,基準病床数,必要病床数,入院需要
|
第54巻第6号 2007年6月 健康危機管理事件発生時のリスクコミュニケーションにおける
今村 知明(イマムラ トモアキ) 下田 智久(シモダ トモヒサ) 小田 清一(オダ セイイチ) |
目的 過去の食品災禍事件における公的情報提供(文字情報)と報道内容の間に発生した情報格差を把握するとともに,その発生原因を分析することで,良好なリスクコミュニケーションの実施に資する。
方法 O157事件,BSE事件において,関係行政機関が提供した文字情報と国内主要紙の報道内容を比較し,格差の有無の確認,発生状況を把握・分析し,この原因について考察した。
結果 O157事件では,厚生省(当時)が中間報告したO157の感染源に関する調査結果について報告書の中で感染源の特定を否定したが,報道の中には「感染源が特定した」との印象を与えるものもあった。BSE事件では,スクリーニング検査陽性(確定検査では陰性)の検体の発生に関する情報提供について,「偽陽性」と「疑陽性」を混同した報道も散見された。
結論 公的情報提供と報道内容の格差は,「事実の捉え方の相違」や「報道機関の表現方法の選択」により発生するものと推測される。これらに起因する情報格差の発生を抑止するためには,関係行政機関が報道関係者と日頃からコミュニケーションを図るとともに,正確な情報伝達や発信情報の一元化を行うための体制の確立が必要である。
キーワード 大規模健康被害,健康危機管理,リスクコミュニケーション,報道