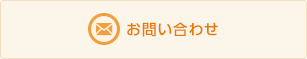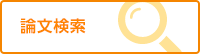論文記事
|
第56巻第8号 2009年8月 保健・衛生行政業務報告に基づく特定疾患医療受給者数および
石島 英樹(イシジマ ヒデキ) 永井 正規(ナガイ マサキ) |
目的 特定疾患の2001~2005年度の受給者数,2003~2005年度の登録者数,受給者から登録者への変更数,登録者から受給者への変更数を観察し,登録者証交付制度(以下,登録者制度)が受給者数の変化に及ぼした影響を考察する。
方法 2001~2003年度地域保健・老人保健事業報告と2004,2005年度保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)を用いて,各年度末現在の受給者数,登録者数,受給者から登録者への年間変更数,登録者から受給者への年間変更数を,疾患別に集計した。
結果 登録者制度対象19疾患,同制度対象外26疾患の両者において,受給者数は2001~2005年度にかけて増加傾向であったが,両者ともに2003年度に受給者数の減少もしくは増加傾向の停滞がみられた。登録者制度対象19疾患では,同制度対象外26疾患より2003年度の受給者数減少の程度が大きかったが,その後は登録者制度導入前と同程度の増加傾向を示した。登録者制度が受給者数に与える影響の大きさは,疾患によって異なっていた。登録者制度対象19疾患のうち,2003年度の受給者数減少が大きいのは,再生不良性貧血,サルコイドーシス,特発性血小板減少性紫斑病であり,登録者の対受給者数比も大きかった。再生不良性貧血では10~20歳代で,サルコイドーシスでは10~30歳代で,特発性血小板減少性紫斑病では20歳未満で,受給者の減少が大きく,これらの年齢層で登録者の対受給者数比が大きかった。
結論 2003年度に受給者数増加傾向が鈍化した。この原因の1つは2003年9月に全受給者に更新手続きを求めたことであり,もう1つは登録者制度が導入されたことである。2003年度の登録者制度の導入は同制度対象疾患の受給者数減少に寄与した。登録者制度の影響の大きさは,疾患によって異なり,再生不良性貧血,サルコイドーシス,特発性血小板減少性紫斑病など,軽症者が多い,あるいは治癒・寛解しやすいといった特徴のある疾患で大きかった。登録者制度が受給者数増加を抑制する効果は一時的なものであると考えられた。
キーワード 特定疾患医療受給者,登録者,保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)
|
第56巻第8号 2009年8月 生命行政の検証-岩手県旧沢内村(現西和賀町)の老人医療費無料化が村におよぼした影響-鈴木 るり子(スズキ ルリコ) |
目的 岩手県旧沢内村(現西和賀町),(以下,「沢内村」)の生命行政,特に老人医療費無料化が村におよぼした影響について検証する。
方法 聞き取り並びに文献による。
結果および考察 岩手県沢内村の生命行政は,沢内村出身の深沢晟雄によって実践された。深澤晟雄は,昭和29年教育長,昭和31年助役,昭和32年村長に就任し,豪雪・貧困・多病と闘い,昭和35年12月から65歳以上,翌年4月から60歳以上と乳児の医療費無料化を全国で初めて実施した。また,沢内村の豪雪に対しては,ブルドーザーでの除雪で人々の諦め意識の改革,高い生活保護率に対しては,貧困と疾病の悪循環を断ち切るため保健師を採用し,本格的な保健活動を展開した。昭和37年には日本で初めて乳児死亡ゼロを達成し,昭和38年に保健文化賞を授与されている。深澤村長は,さらに健康管理課を設置した。課長は医師とし,保健・医療の沢内方式の予防活動を展開し,地域包括医療のシステ化を図った。老人医療費無料化が村に与えた影響は①長寿村の達成-昭和55年には,近隣のどの町村よりも長寿の村となった。②国民健康保険の医療費の減少-被保険者1人当たりの医療費は,昭和43年には県平均を下回った。③健康な村づくりに発展-60歳以上の医療費無料化が果たした役割について,元沢内村病院長増田進は,「村が明るくなった。老人の自殺が減少した。嫁の受診が増え,家族の健康に気配りができるようになった」と述べている。このように沢内村が行った老人医療費の無料化は,高齢者を明るく元気にし,全村民の健康づくりに波及した生命行政であった。健康が保障されれば,住民の関心とエネルギーは次の段階へ向けられる。村の高齢者達が生き生きと活動する姿はいかに生命や健康の基盤を支えることが重要かを示唆している。
キーワード 生命行政,老人・乳児医療費無料化,沢内方式,地域包括医療
|
第56巻第8号 2009年8月 精神障害者の社会適応訓練から一般就労への有効な支援大野 順子(オオノ ジュンコ) |
目的 社会適応訓練利用後,労働関係機関との連携・協働により一般就労に至った3事例を通し,保健師の精神障害者に対する就労支援のあり方を考える。
対象と結果 社会適応訓練事業を利用した精神障害者への一般就労の支援経過の検討を行った。西多摩保健所では,平成18年10月から19年3月まで,都内で働く保健師1,260人を対象に「就労支援において保健師が大切と考えている支援の視点」についてアンケート調査を行った。その結果,保健師は保護的就労(福祉的就労)とされる通所授産施設,共同作業所,社会適応訓練事業利用については,保健師の視点や支援方法で有意に影響する項目があったが,一般就労では有意に影響する項目は明らかにならなかった。社会適応訓練中から一般就労への動機づけを行い,障害をオープンにした就労活動で障害者本人の希望に添える一般就労支援ができた。
結論 精神障害者の一般就労には保健師の支援だけでは困難であり,労働関係機関等との連携・協働が不可欠と考えられた。精神障害者は仕事や人間関係という訓練の環境を変えずに一般就労したいという希望が強い。保健師は働いて報酬を得ることが生活の安定だけでなく,本人達の自尊心につながることを重視し援助した。障害者の病状,能力,意欲,体力をアセスメントし,障害をオープンにして労働機関関係者との連携,制度を活用することが一般就労には有効と考えられる。
キーワード 精神障害者,社会適応訓練事業,保護的就労(福祉的就労),一般就労
|
第56巻第10号 2009年9月 グループ回想法の介入効果-特別養護老人ホーム入所者の生きがい感-津田 理恵子(ツダ リエコ) |
目的 先行研究において,回想法介入による効果の確認を,生きがい感スケールを用い,長期的にその効果を検証している研究は見当たらなかった。そこで,特別養護老人ホームでクローズド・グループによる回想法の介入を試み,生きがい感スケールを用いて,多層ベースラインで調査を実施し回想法の介入効果を確認することを目的とした。
方法 特別養護老人ホームに入所している高齢者13名を,A組・B組・C組の3グループに分け,1グループにつき5週間ずつ,介入時期を2カ月間ずらしてグループ回想法を実践し,生きがい感スケールを用いて2カ月ごとに5回(10カ月間)測定した(多層ベースライン)。
結果 生きがい感スケールの得点と生きがい感スケールの下位項目の得点について,3(グループ;A組,B組,C組)×5(時期;1回目,2回目,3回目,4回目,5回目)の分散分析を行った。その結果,交互作用に有意な傾向が認められた(p<0.06)。多重比較を行った結果,A組では1回目と2回目の間(p<0.03),B組は2回目と3回目の間(p<0.03),C組では3回目と4回目の間(p<0.04)に有意な改善が確認できた。有意な差がみられた時点は,それぞれ回想法の介入直後であった。さらに,生きがい感スケールの下位項目では,「私には施設内・外で役割がある」「世の中がどうなっていくのかもっと見ていきたいと思う」「私は家族や他人から期待され頼りにされている」の3項目に有意な改善が示された。
結論 回想法の介入によって,特別養護老人ホーム入所者の生きがい感の向上に効果があることが確認できた。日々の生活における余暇時間における活動として,回想法は,個人の懐かしい記憶に働きかける個別性が尊重された支援であると示した。
キーワード グループ回想法,特別養護老人ホーム,生きがい感,多層ベースライン
|
第56巻第10号 2009年9月 青年勤労者における抑うつ状態と体力との関連久保田 晃生(クボタ アキオ) 原田 和弘(ハラダ カズヒロ) 笹井 浩行(ササイ ヒロユキ)甲斐 裕子(カイ ユウコ) 高見 京太(タカミ キョウタ) |
目的 本研究は職域の青年期を対象に抑うつ状態と体力との関連を検討し,職域におけるメンタルヘルスの向上を効果的に推進するための基礎的資料を得ることを目的とする。
方法 静岡県内のN社K製造所で,本研究に協力の得られた20歳代,30歳代の男性288人を対象とした。この内,「解析項目に1つでも欠損値がある」「体力項目のいずれかに平均値+標準偏差×3以上の値がある」「CES-Dで逆転項目の回答が不十分である」75人を除いた213人を解析対象者とした。体力は握力と長座体前屈,反復横とび,上体起こし,立ち幅とびを測定した。質問紙調査では,自記式の推定最大酸素摂取量,Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(CES-D)日本語版,International Physical Activity Questionnaire(IPAQ)日本語版Short Versionのほか,年齢,配偶者,学歴,睡眠時間,夜勤,喫煙習慣,飲酒習慣,現病歴の状況を把握した。また,同時期の健診結果からBMIを把握した。解析は,CES-D得点から2群(16点以上の抑うつ群と16点未満の非抑うつ群)に分け,体力測定,質問紙調査の結果をMann-Whitney U検定,χ2検定で比較した。抑うつの有無(抑うつ群=1,非抑うつ群=0)を目的変数,各体力項目を説明変数,各交絡因子を調整変数としたロジスティック回帰分析を施し,抑うつ状態と体力との関連を検討した。
結果 全体のCES-D得点は15.3±8.1点(平均値±標準偏差)で,抑うつ群は88人(41.3%)であった。抑うつ群と非抑うつ群の比較では,年齢,配偶者,夜勤,BMI,立ち幅とび,上体起こしで有意差が認められた(p<0.05)。立ち幅とび,上体起こし以外の体力項目は,有意差は認められなかったが,抑うつ群の方が非抑うつ群よりも低い値を示した。ロジスティック回帰分析では,立ち幅とび(1標準偏差上昇に対するオッズ比0.57,95%信頼区間0.41-0.80),推定最大酸素摂取量(0.58,0.39-0.86),上体起こし(0.72,0.53-0.97),握力(0.73,0.54-0.99)が有意な関連を示した(p<0.05)。
結論 本研究の結果,抑うつ状態と体力を構成する要素である筋力(握力)と筋持久力(上体起こし),筋パワー(立ち幅とび),持久力(推定最大酸素摂取量)が関連し,体力を向上させることが,抑うつ予防につながる可能性が考えられた。しかし,本研究は横断的研究であり,抑うつ状態と体力との因果関係は断言できない。今後,縦断的研究が望まれる。
キーワード 抑うつ状態,CES-D,体力,身体活動量,青年期,勤労者
|
第56巻第10号 2009年9月 在宅要支援・要介護1認定者における
松本 たか子(マツモト タカコ) 猫田 泰敏(ネコダ ヤストシ) |
目的 本研究は,高齢者の自立支援を基本理念とする介護保険制度で軽度認定を受けた在宅高齢者の第1回更新月1カ月分の介護保険サービス利用による,第1回更新時から第2回更新時までの介護度の悪化防止への効果について分析した。
方法 調査対象地域は,65歳以上の人口割合が全国値に近似し,介護保険法に基づく介護保険サービスの全種類の利用可能な東京都B区を選定した。自治体の既存の介護保険データを用い,2003年度に新規申請を行い,初回認定時および第1回更新時に要支援・要介護1の認定を受けた第1号被保険者456人を調査対象とした。調査項目は,性別,第1回更新申請時の年齢,新規時および第1回・第2回更新時の介護度,第1回・第2回更新年月日,第1回更新月1カ月分のすべての介護保険サービスの利用状況とした。第1回更新時から第2回更新時までの介護度の変化と調査対象の特性,サービス利用状況との関連について分析した。
結果 第1回更新時から第2回更新時までに介護度が悪化した者は61名(13.4%)であった。調査対象の特性と介護度の変化の間には有意な関連は認められなかった。個別の介護保険サービスの利用状況と介護度の変化の分析の結果,訪問介護の利用者において月6回以上の利用者のオッズ比が0.37(0.17~0.84)と悪化防止への影響が認められた。また,通所介護では月1~5回の利用者でオッズ比が2.74(1.15~6.53)と逆に悪化することが示された。多重ロジスティック分析の結果も同様であった。
結論 自立可能性が高い軽度認定者に対する在宅高齢者の介護保険サービスのうち,訪問介護の提供が有効であることが示された。このことから,対象者の生活や疾病などの個別性を踏まえたサービスの提供が必要であることが重要と考えられた。通所介護については,現在の実施のあり方に検討すべき点があることを示唆するものと考えられた。
キーワード 介護保険制度,在宅高齢者,要支援・要介護1,介護度の変化,介護保険サービス
|
第56巻第10号 2009年9月 家族介護者の抑うつ傾向に影響を及ぼす介護保険サービスの検討坪井 章雄(ツボイ アキ オ) |
目的 在宅介護家族の介護ストレスによる介護破綻を予防するために,抑うつ傾向の軽減のための有用な在宅サービスの可能性を探る目的で調査を行った。
方法 対象は,茨城県内のすべての在宅介護家族を母集団として層化二段無作為抽出法により標本抽出した。在宅介護家族支援と介入を行っている居宅療養管理指導事業所(以下,事業所)の利用者を対象とし,標本抽出台帳から153施設を無作為抽出し,調査の依頼を行った。介護ストレスの軽減に有用なサービスや問題解決の内容・方法を抽出するために,Ⅰ:介護者・被介護者属性,Ⅱ:利用サービス内容,Ⅲ:問題解決の方法,について調査票を作成し,調査票との関連を検討するために,介護者の測定には標準的うつ評価スケールとして国際的に受け入れられているGDS-15を調査に用いた。
結果 サービス利用者と非利用者間におけるGDS-15の差の検定では,障害の予後や改善の説明やスロープの設置でサービス利用者が非利用者より有意にGDS-15平均点が低かった。問題解決実施者と非実施者間におけるGDS-15の差の検定では,相談者がいる介護者,援助者がいる介護者,趣味がある介護者,および家族に相談している介護者,医師や看護師,PT・OTなどの医療職に相談している介護者,インターネットを用いている介護者では,非実施者より有意にGDS-15平均点が低かった。一方,何もしない介護者は有意にGDS-15平均点が高かった。
結論 抑うつ傾向軽減のためには,被介護者の将来の状況に対する不安が軽減するサービスが有効と考えられた。また,家族が相談者や支援者とすることで抑うつ傾向が軽減することが示されており,主たる介護者と共にそれ以外の家族に対して,在宅介護に対する理解と協力を得る事を目的とした介入の必要性が考えられる。
キーワード 介護家族GDS-15,抑うつ,介護保険サービス,介護破綻
|
第56巻第10号 2009年9月 児童養護問題の階層性-児童養護施設6カ所の実態調査から-堀場 純矢(ホリバ ジュンヤ) |
目的 児童養護施設(以下,施設)で暮らす子どもと親の生活問題に関する研究は,1990年代以降,ほとんどみうけられない。そこで筆者は,子どもと親(家族)の背負う労働問題を生活問題と不可分のものとして捉え,東海地区の施設6カ所で暮らす子どもと親の生活問題に関する調査を行った。本稿の目的は,この調査結果をもとに,児童養護問題の階層性を統計的に浮き彫りにすることである。
対象・方法 調査対象は,東海地区の施設6カ所の父母352名(父179名,母173名)とした。A園(2000年3月),B園(2003年4月),C園(2006年8月),D園(2006年10月),E園(2006年3月),F園(2008年8月),すべてその月現在の各施設に在籍している子どもと親の生活歴についてケース記録より情報抽出を行った。また,施設職員にケースごとに情報が不足する項目について聞き取りを行った。調査期間は,2000年8月,2003年5月~2004年8月,2006年1月~2008年8月である。調査項目は,学歴,就労・所得,社会保険,居住場所,近所づきあいの程度,健康状態の6項目とした。
結果 施設で暮らす子どもの親は,親の親(祖父母)の代からの貧困を背景として,「学歴」が低く,そのことが「不安定就労」「無職」「生活保護」につながっていた。その結果,住居も相対的に狭小な民間アパート・寮・公営住宅で暮らさざるをえず,自己負担の割合が高く給付が不十分な「国保」「無保険」につながっていた。さらに,雇用・労働条件が不安定で重労働のため,「近所づきあい」をするゆとりもなく社会的に孤立し結果として心身の健康問題が深刻化していた。
結論 施設で暮らす子どもと親のほとんどが不安定低所得階層であること,母親に不安定就労や無職が多く,生活問題が深刻であること,父母ともに厳しい労働・生活実態を反映して,心身の健康問題が深刻であること,児童養護問題の背景には親の労働・生活問題があること,以上の4点が明らかとなった。
キーワード 児童養護施設,階層性,健康・生活問題
|
第56巻第10号 2009年9月 若年女性の健康を考える子宮頸がん予防ワクチン接種の意義と課題荒川 一郎(アラカワ イチロウ) 新野 由子(ニイノ ヨシコ) |
目的 子宮頸がんの発生は,発がん性のHPV(Human Papillomavirus)の感染が主要因である。HPVは性交渉によって子宮頸部粘膜へ経路する。近年,若年女性の性交渉率と性感染症の増加が問題となっている。また,子宮がん検診の受診率は欧米に比べて日本では24%程度と極端に低く,さらに20~30代の若年女性で子宮頸がんの発生が増えている。今回著者らはその要因について考察し,子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の意義,そして包括的なリプロダクティブ・ヘルスへの対策について検討した。
方法 マルコフモデルを用いて,がん検診率50%によるアウトカムの計量化を予備的に試みた(費用効用分析,社会全体の立場)。そして,20~30代女性の立場からHPVワクチンの臨床的,経済的アウトカムへの影響について検討を行った。分析手法は,費用便益分析を用い,観察期間を10歳からの30年間とし,年率3%で割引いた。いずれの検討も,モデル計算に必要な変数は,国内外の公表文献や国内の統計データより得た。
結果 定期検診率向上に関する予備検討の結果,生涯における子宮頸がんの発生率や死亡率は13~14%減少することが示唆されたが,増分費用効果比が約1兆700億円/QALY(quality-adjusted life year)と非効率的であった。12歳児のコホート(n1=589,000)へのワクチン接種(接種率100%)は,非接種(n2=589,000)と比較して,20~30代における子宮頸がんの発生や子宮頸がんによる死亡を減少させることができ,そして約12億円の純便益が得られると推計された。
結論 今回の検討結果から,検診率の向上だけでは子宮頸がんの発生を抑えるには十分ではなく,非効率的であるため,若年女性の立場からHPVワクチン接種の意義が示唆された。しかし,わが国の若者の多様な性行動に対する対策を検討する必要性が考えられ,子宮がん検診の向上とHPVワクチンの集団接種の導入に加え,諸外国の対策を参考として性の健康に関する正しい知識を提供する性教育の浸透という多角的な対策が,現実的に今回推計した便益の獲得につながると期待する。リプロダクティブ・ヘルス,生涯を通じた女性の健康への対策として,社会全体で子宮頸がん撲滅ための取り組みが今求められているのではないだろうか。
キーワード 子宮頸がん,HPV,ワクチン,疾病負担,性感染症,性教育
|
第56巻第11号 2009年10月 感染性胃腸炎対策研修プログラムにおける
堀口 逸子(ホリグチ イツコ) 黒瀬 琢也(クロセ タクヤ) |
目的 感染性胃腸炎集団感染予防対策を学ぶための教材を,ゲーミングシミュレーションを用いて開発した。これを利用した参加型研修プログラムについて評価し,その有用性について検討した。
対象と方法 研修プログラムは,①開始前のルールの自学学習,②ノロウイルスに関する講話,③ゲーミングシミュレーションの実施,④感染拡大防止に関する講話,⑤質疑応答,⑥質問紙記入,の約1時間20分である。教材はノロウイルスの感染拡大をイメージできるボードゲームである。評価は,フェイスシート(年齢,勤務年数,集団感染経験,研修受講経験,勤務先での立場),研修会評価(構成,所要時間,資料),教材評価(楽しさ,ルール,感染拡大,対策および連携の重要性,再度の実施可能性)の全15問からなる質問紙によった。平成20年にM市保健所管内の保健福祉施設勤務者を対象として実施した研修にて,プログラムを実行した。質問紙は受付にて配布し当日回収した。
結果 参加者(評価対象者)139名は,50歳台が最も多く全体の3割を超え,次いで40歳台が全体の1/4を占めていた。勤務年数は,多い順に10年以上,5年以上であった。集団感染が起きた場合に指揮をとる立場のものは全体の約半数であった。研修会評価は,すべての項目でよかったとされた。教材評価では,とても楽しく感じ,感染拡大の様子が実感でき,連携や対策の重要性を認識していることがわかった。そして,再度の実施を希望していた。両評価とも,集団感染経験,研修の受講経験,年齢,勤続年数において有意な差はみられなかった。
結論 講義形式の研修は,学問レベルは高いが内容の現実性や体験との関連性,理解度,問題解決の場としては劣るなどの問題点が指摘されている。今回の教材は質問紙調査の結果からは,経験の有無などに関わらず学習効果が得られることが示唆された。また,研修会の評価も高かった。今後,ゲーミングシミュレーションを利用した教材によって効果的な研修会ができることが示唆された。
キーワード ゲーミングシミュレーション,参加型研修プログラム,感染性胃腸炎
|
第56巻第11号 2009年10月 年齢・職業不詳の自殺者が都道府県別自殺率に及ぼす影響赤澤 正人(アカザワ マサト) 松本 俊彦(マツモト トシヒコ) 川野 健治(カワノ ケンジ)稲垣 正俊(イナガキ マサトシ) 竹島 正(タケシマ タダシ) |
目的 警察庁発表の自殺の概要資料と厚生労働省の人口動態統計では,毎年自殺者数,自殺率に差が確認される。集計方法の違いが要因のひとつと考えられるが,自殺の概要資料には発見された年以前の自殺がその年の自殺として計上されうる。本研究では,発見された年以前の自殺者であると推測される自殺者を,「年齢不詳」かつ「職業不詳」の自殺者として捉え,年齢・職業不詳の自殺者が都道府県の自殺率に及ぼす影響を検討する。
方法 警察庁から自殺予防総合対策センターに提供を受けた,平成16年から18年の自殺についての自殺統計原票に基づく集計データから,都道府県別に年齢・職業不詳の自殺者数を集計した。そして発見地による自殺者数から年齢・職業不詳の自殺者数を除いた自殺率を求め,発見地による自殺率と比較検討した。
結果 3年間に全国で779人の年齢・職業不詳の自殺者が確認された。年齢・職業不詳の自殺者が多い都道府県は,東京都,山梨県,福岡県,神奈川県,愛知県等であった。山梨県は他県と比較して,発見地による自殺率(41.9,41.8,42.7)と,年齢・職業不詳の自殺者数を除いた自殺率(38.3,36.0,36.4)との間に差があることが分かった。
結論 山梨県では,年齢・職業不詳の自殺者数が自殺の概要資料における自殺率を高めている可能性が示唆された。自殺の実態把握にはデータの特徴や限界を認識しておくことが重要である。
キーワード 自殺,自殺率,自殺の概要資料,人口動態統計,年齢・職業不詳の自殺者
|
第56巻第11号 2009年10月 二次医療圏別平均寿命による健康指標の開発若林 チヒロ(ワカバヤシ チヒロ) 新村 洋未(シンムラ ヒロミ) 加藤 朋子(カトウ トモコ)川島 美知子(カワシマ ミチコ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) 柳川 洋(ヤナガワ ヒロシ) |
目的 平均寿命は,地域の健康水準とそれに影響を及ぼす保健医療福祉政策を評価する最も適切な指標であり,都道府県単位と市区町村単位で公表されている。しかし,保健医療福祉政策の効果を評価するには,都道府県単位では広域すぎて地域ごとの評価指標としては適切ではないし,市区町村単位では単位ごとの人口規模が数百から数十万の範囲にまたがるためにばらつきが大きく信頼度に問題がある。医療サービスは二次医療圏単位で供給されており,保健医療福祉政策を評価するためには,二次医療圏単位の平均寿命による評価が必要である。そこで本研究では,市区町村単位で公表されている平均寿命を基にして,二次医療圏単位の平均寿命を計算し,その分布を観察する。さらに,二次医療圏別平均寿命を用いた解析の例として,性別に老年人口割合との関連を検討した。
方法 2005年性別市区町村別平均寿命(2006年12月31日現在の市区町村区分)と2005年国勢調査人口(2005年10月1日現在の市区町村区分)から,市町村合併前後の対応表を用いて,2006年12月31日現在の市町村区分に統一したデータベースを作成する。二次医療圏の分類は「医療施設調査」(2006年10月1日の分類)より引用し,2006年10月1日と12月31日の市町村区分の相違を確認したうえで,2006年12月31日現在の二次医療圏分類を作成した。これらを元に,人口規模を考慮した二次医療圏別平均寿命を性別に算出した。二次医療圏別平均寿命について分布の特性を観察し,地域の基本的な背景として老年人口割合との相関を観察した。
結果 二次医療圏別平均寿命は,男性78.50±0.92歳,女性85.75±0.59歳で,男女の相関はr=0.677であった。二次医療圏単位の平均寿命は,老年人口割合との間には,男性は負の相関(r=-0.440)があったが,女性は相関がなかった(r=-0.037)。
結論 市区町村別平均寿命を元に二次医療圏別平均寿命を算出し,分布と老年人口割合との関係を観察したところ,男性の方が二次医療圏別の差異が大きく,男性では都市化との関連がみられたが,女性では関連がみられず,就労形態,居住地,職業選択や保健医療福祉サービスとの関連が伺われた。二次医療圏別平均寿命は,他の社会経済指標および医療供給指標との関連を観察することで,幅広い公衆衛生活動の評価指標として利用できる。市区町村別平均寿命は5年ごとに公表されるので,5年後の指標も作成し,地域における健康水準の推移を観察する予定である。
キーワード 平均寿命,二次医療圏,健康指標,保健医療福祉政策,地域格差
|
第56巻第11号 2009年10月 住民がかかりつけ医を持っていない割合とその特性-「食生活改善行動の採用」尺度と行動変容モデルの予測-松嶋 大(マツシマ ダイ) 岡山 雅信(オカヤマ マサノブ) 松嶋 恵理子(マツシマ エ リ コ)藤原 真治(フジワラ シンジ) 小松 憲一(コマツ ケンイチ) 梶井 英治(カジイ エイジ) |
目的 地域住民がかかりつけ医を持っていない割合と,その特性を明らかにする。
方法 対象は,下野市,小山市,真岡市,上三川町,二宮町,筑西市,結城市の2007年住民健診(2007年9~11月)の受診者である。調査方法は自記式質問紙調査で,調査項目は対象者情報(年齢,性別,学歴,就労,自宅周囲の医療機関)とかかりつけ医の有無である。かかりつけ医は「普段定期的に受診している医師」もしくは「自分の健康や病気のことを気軽に相談できる医師」と定義した。回収した質問紙のうち年齢,性別,かかりつけ医の有無のすべてに回答があるものを有効回答とした。対象者を「かかりつけ医あり(あり)」と「かかりつけ医なし(なし)」の2群に分類し比較した。
結果 対象者は2,397名で2,376名(99.1%)から回収した。有効回答は2,228名(92.9%,対象者数に対する割合)で,「あり」1,507名(67.6%),「なし」721名(32.4%)であった。かかりつけ医の有無の比較では,平均年齢,最終学歴,就労で有意差を認めた。平均年齢は,「あり」の61.5歳に対し,「なし」は52.8歳で有意に若かった。最終学歴は,専門学校卒業以上が「あり」25.8%に対し「なし」では37%であり,「なし」が有意に多かった。就労は,有職者が「あり」37.7%に対し「なし」では52.1%であり,「なし」が有意に多かった。かかりつけ医なしの対象者特性について,多重ロジスティック回帰分析にて20~64歳(若年から中年層),専門学校卒業以上(高学歴者),有職者で有意差を認めた。年齢は65歳以上と比べて,20~39歳,40~64歳のオッズ比がそれぞれ8.17,2.47で,若年から中年層はかかりつけ医を持っていない傾向にあった。最終学歴は,専門学校卒業以上について高校卒業以下と比較すると,オッズ比1.28と,専門学校卒業以上がかかりつけ医を持っていない傾向にあった。就労は有職を無職と比較すると,オッズ比1.29と,有職者はかかりつけ医を持っていない傾向にあった。
結論 住民の3割がかかりつけ医を持っていないこと,および若年から中年層,高学歴者,有職者はかかりつけ医を持っていない傾向があることが示された。
キーワード かかりつけ医,地域住民
|
第56巻第11号 2009年10月 精神障害者の就労支援におけるQOLの変化-SF_36v2日本語版を用いて-立石 宏昭(タテイシ ヒロアキ) |
目的 「個別職業紹介とサポートによる援助付き雇用プログラム(Individual Placement Support Program:IPS)」の考え方を取り入れた訪問型個別就労支援の実践を通して,就労支援とQOLの関係を明らかにすることである。
方法 精神障害者地域活動支援センターの利用者73人に対して,S1(就労準備),S2(求職活動),S3(フォローアップ),S4(保留・終了)という就労支援のターニングポイントを設け,「SF-36v2日本語版(振り返り期間が1カ月間)」によるQOLの変化を測定した。調査期間は,2006年4月から2008年3月までの2年間である。分析は,SF-36v2の36項目の設問に0~100点をスコアリングし,「国民標準値(Norm Based Scoring: NBS)」と比較した。また,SF-36v2の下位尺度に重みづけをしたあと,「身体的健康度をあらわすサマリースコア(Physical Component Summary: PCS)」と「精神的健康をあらわすサマリースコア(Mental Component Summary:MCS)」の変化を探った。さらに,各ステージの特性値に対する因子の影響を知るため,反復測定による一元配置分散分析および多重比較を行った。
結果 S1(就労準備)のPCS(-3.6),MCS(-4.0)は,ともにNBSを下回り,就労を目指す段階ではQOLは低下していた。しかし,S2(求職活動)では,S1を上回り,S3(フォローアップ)になると,PCS(0.8),MCS(3.5)はNBSを上回るほど高い数値を示していた。さらに,S3(3カ月)では,PCS(4.3)はNBSを大きく上回り,身体的健康度が高くなっていた。しかし,S3(6カ月)を過ぎるころから,PCS(3.7),MCS(2.3)の低下が始まり,S3(18カ月)になると,PCS(-1.3),MCS(-0.1)はNBSを下回っていた。つまり,各ステージにより利用者のQOLに変化が見られた。また,反復測定による一元配置分散分析および多重比較を行ったところ,①S1とS3,②S1とS3(3カ月),③S1とS3(6カ月),④S2とS3,⑤S2とS3(6カ月)の群間で有意差を確認することができた(F値6.425,p<0.000)。
結論 就労支援を始めて18カ月当たりに就労継続を図るためのターニングポイントがあった。
キーワード 精神障害者,就労支援,SF-36v2,QOL,地域活動支援センター
|
第56巻第11号 2009年10月 回復期リハビリテーション病棟における
|
目的 これまで急性期病院から,回復期リハ病棟に転院してきた患者がどのような状態で,入院し,退院するかについては,十分にデータが示されてこなかった。そこで本研究では,「重症度・看護必要度」および「重症度」基準の調査項目を用い,回復期病棟の患者の入院時および退院時の状態を急性期病院の患者タイプとの比較から明らかにし,さらに,その一入院の変化について分析することを目的とした。
方法 回復期リハビリテーション病棟連絡協議会の会員施設のうち看護師配置の高い21病院51病棟の患者の「重症度・看護必要度」および「重症度」基準の評価項目によるAおよびB得点を収集した。分析は,得点の平均値および標準偏差を示し,また入院時と退院時の得点等の分析に関しては,3段階以上のカテゴリー評価については,Wilcoxonの符号付き順位検定,2段階評価は,McNemar検定を行い,一入院における得点の変化を明らかにした。
結果 回復期リハ病棟の患者は,医療処置はほとんどなかったが,7対1や10対1の急性期病棟より,療養上の看護に手間がかかる患者タイプ4と5の割合が高く,全体の41.4%と示された。また,同一患者における入院時と退院時の一入院の変化については,退院時では入院時より平均得点が2.5点低下しており,患者の7割以上に得点低下がみられた。
結論 本研究結果から,回復期リハ病棟の患者は,医療的な処置がなくなった時点で急性期病棟から転院し,全患者の7割程度が改善して退院していることがわかった。今後は,新たに収集されることになった日常生活機能評価による得点データを用いて,急性期から回復期までの一入院のデータ,さらには,在宅における状態の変動を継続的に調査し,地域におけるリハビリテーションサービスやケア提供の在り方を検討することが課題である。
キーワード 回復期リハビリテーション病棟,看護必要度(nursing care intensity),重症度・看護必要度,日常生活機能評価
|
第56巻第11号 2009年10月 アフガニスタンにおける
|
目的 アフガニスタンにおけるポリオ根絶プログラムの成果を評価し,今後の地域における予防接種の一層の普及のために,経口ポリオウイルスワクチン(OPV)接種率の地理的分布を分析し,実際に世帯訪問調査を行い,予防接種の促進要因を明らかにする。
方法 アフガニスタン公衆衛生省EPI事務所,WHO,UNICEFの調査による予防接種記録,2002年国勢調査結果,および地理情報データベースに基づき331地区の保健医療地理情報データベースを構築し,OPV3回接種について分析した。また急性弛緩性麻痺サーベイランスデータより,ポリオ診断確定数の変化を分析した。カブール県において,1,400世帯を対象とした世帯訪問調査を2006年に行い,ポリオ予防接種歴と,健康状態,社会経済要因,生活環境要因,ならびに保健医療サービスへのアクセスなどについてデータベースを作成し,予防接種の促進要因を分析した。
結果 アフガニスタンにおけるOPV3回接種率は向上しており,地理的分布も広がっている。また,ポリオ確定診断ケースも激減しており,地域的に限局化している。また,カブール世帯訪問調査結果から,OPV3回以上接種率は,年齢に従って増加し,それぞれ,44.8%(1歳未満),62.7%(1歳),60.4%(2歳),64.1%(3歳),68.8%(4歳)であった。また,統計的に有意な予防接種の促進要因は,アウトリーチ活動チームによる家庭訪問,予防接種の健康教育,医療施設分娩,妊婦健診,医療施設までの地理的利便性であることが示された。なお背景として,社会経済要因の影響も統計的に有意であった。
結語 アフガニスタンのポリオワクチン接種率は,目標接種率には到達していないが,近年急速に向上している。目標接種率に到達するためには,地域格差,特に,低接種率地区における予防接種活動の課題への対応が不可欠となる。ポリオの根絶に向けて,地域の安定を含む社会経済条件の向上を図る様々な支援プログラムとの連携をはかり,アウトリーチ型の活動の一層の展開,健康教育の拡充,医療施設分娩の機会拡大,妊婦検診の普及などを包括的に推進することにより,一層の予防接種の普及が図られるものと考えられる。
キーワード アフガニスタン,ポリオ,予防接種,EPI,地域保健
|
第56巻第15号 2009年11月 消費者が必要な食の安全に関する知識-食品衛生監視員対象の質的調査から-中垣 俊郎(ナカガキ トシロウ) 堀口 逸子(ホリグチ イツコ) 馮 巧蓮(ヒョウ コウレン) 赤松 利恵(アカマツ リエ) 田中 久子(タナカ ヒサコ) 丸井 英二(マルイ エイジ) |
目的 消費者が食品のリスク情報を解釈するために必要な知識は何であるのかを明らかにすることを目的とした。
方法 地域的偏りがないよう全国から選出された検疫所を除く行政機関に勤務する食品衛生監視員27名を対象とし,質的調査(デルファイ法)を実施した。第1回調査では「一般消費者が必要とする食の安全の知識としてどのような内容が考えられるか」の質問に対して,7項目挙げ,その選出理由を記載してもらった。第2,3回調査では,第1回調査で選出された項目から優先度が高いと考える項目7つを選択してもらい,第1位を7点,第2位を6点,第3位を5点と7位1点まで順次得点化し,項目別の合計得点を算出した。選出理由はKJ法2)を用いて分析した。調査期間は,平成19年12月から20年2月であった。
結果 回収率は85%以上であった。第1回調査で56項目が選出され,最終的に35項目に1点以上の得点が与えられた。第1位より「生食の危険性」「食中毒防止」「食品表示」と続き,上位10項目中4項目はリスク分析に関する項目であった。上位10項目の選出理由では「消費者と食品と健康被害の関係」に対して「社会の抱える課題」と「リスクコミュニケーション」がそれぞれ関連し,「消費者自身」は「知識不足」「不十分な理解」「反応」「間違った理解」「態度」「能力」といった内面が「喫食行動」と関連していた。また,「食品」は,「リスク」そのものだけでなく「流通」「管理」があがった。
結論 消費者が必要な知識として認識されている項目は,リスク評価,リスク分析の考え方の視点からだけでなく,そのときどきのメディアの影響の可能性も示唆された。
キーワード 食の安全,知識,デルファイ法,食品衛生監視員
|
第56巻第15号 2009年11月 精神に病を持つ人の居場所感尺度の検討國方 弘子(クニカタ ヒロコ) 茅原 路代(カヤハラ ミチヨ) 土岐 弘美(トキ ヒロミ) |
目的 精神に病を持つ人が地域で充実感がある生活を送るためには,居場所のあることが重要な要素の1つである。本研究は,居場所感を「自分がそこにいてもいい場であり,自分らしくいられる場であり,自分がありのままにそこにいてもいいと認知し得る感覚」と定義し,精神に病を持つ人の居場所感尺度を作成し,その信頼性と妥当性を検証することを目的とした。
方法 分析対象は,地域で生活しデイケアに通所する統合失調症者83名とした。初回調査は平成19年1~2月に行い,追跡調査は尺度の信頼性と妥当性を評価するために同一対象に,6カ月後に実施した。測定用具は,71項目からなる居場所感尺度原案,疎外感尺度(併存的妥当性の確認),WHOQOL-26尺度(予測的妥当性の確認),属性で構成した。分析は,探索的因子分析,確証的因子分析,シンクロナウス・イフェクツ・モデルを用いて妥当性を検討した。信頼性は,内的整合性と安定性の評価で検討した。
結果 探索的因子分析の結果,3因子が抽出された。3因子を一次因子,精神に病を持つ人の居場所感を二次因子とする高次因子モデルを構築しデータへの適合度を検討した結果,モデルは受容できた(χ2/df比=1.409,GFI=0.930,AGFI=0.851,CFI=0.980,RMSEA=0.071)。初回調査と追跡調査の精神に病を持つ人の居場所感は正の相関(γ=0.631,p<0.01),初回調査における精神に病を持つ人の居場所感と疎外感尺度は負の相関(γ=-0.548,p<0.01)があった。精神に病を持つ人の居場所感とWHOQOL-26の因果関係を分析した結果,初回調査における精神に病を持つ人の居場所感は,追跡調査の同一変数を0.545の標準偏回帰係数(p<0.001)で予測し,追跡調査における精神に病を持つ人の居場所感は追跡調査のWHOQOL-26を0.364の標準偏回帰係数(p<0.05)で予測した。α係数は0.893であった。
結論 結果より,本尺度の信頼性と妥当性は支持された。しかし,用いたデータが少ないために今後,大量のサンプルで調査を行うことが必要である。また,交差妥当性の検討も必要である。
キーワード 精神に病を持つ人,居場所感,尺度の開発,信頼性と妥当性
|
第56巻第15号 2009年11月 利用者主体の福祉サービスの実践条件に対する職員と利用者の認識渡邉 修宏(ワタナベ ノブヒロ) 森山 哲美(モリヤマ テツミ) |
目的 本研究の目的は,福祉サービスの実践条件に対する職員と利用者双方の認識を比較し,利用者主体の福祉サービスの実践に必要な条件を明らかにすることである。
方法 調査対象はA県内の障害者支援施設14カ所(身体障害者療護施設)の職員451名(回収率74.1%)と利用者228名(回収率67.1%)であり,留置法か直接聞き取りのどちらかによる悉皆調査を2005年6月から同年9月までの期間に実施した。利用者主体の福祉サービスの実践条件に対する職員と利用者の認識を把握するため,「より良い福祉サービスが実践されるために何が重視されるべきか」「職員と利用者のかかわりをよくするために何が重視されるべきか」「職員と利用者のかかわりがよいほど福祉サービスはよくなるか」「現在,利用している施設の職員と利用者のかかわりはよいか」という質問を用いて回答を求めた。
結果 利用者主体の福祉サービスに対する職員と利用者の認識の間でいくつかの違いがみられたが,本質的に異なるものではなかった。違いは,利用者主体の福祉サービスを実践するための両者の視点の方向性の違いであった。すなわち,職員は福祉サービスを実践するための外的要因を重視したが,利用者は自分に向けられる福祉サービスの内容そのものを重視した。職員と利用者の認識を比較して明らかになった利用者主体の福祉サービスに必要な条件は,①ケアにかかわる人々の関係を良好にするための知識と技術を職員が習得すること,②利用者へのサービス量を拡充するための施設内設備の充実や外部関係機関との連携が強化されること,③利用者の要求に見合った,施設と家族の連携,施設と地域社会の交流が促進されること,④職員と利用者が,互いに話し合うことができ,相手を理解して共感的に対応できるような環境が設定されること,⑤利用者の話に耳を傾け,利用者のニーズを理解して共感的に対応できるケアの技術を職員が習得することの5つであった。
結論 本研究で明らかになった5つの条件を満たす福祉サービスが実践される必要がある。そのために,利用者と職員がかかわる場面と,そのときの彼らの行動の関係を調べ,どのような行動上の問題があるのか具体的に調べる必要がある。そして,その問題が解決されるなら,真の意味での利用者主体の福祉サービスの実践は可能となるだろう。
キーワード 利用者主体の福祉サービス,実践条件,職員と利用者の認識
|
第56巻第15号 2009年11月 日本人渡航者における黄熱予防対策の状況小池 絵梨香(コイケ エリカ) 西川 幸位(ニシカワ ユイ) 久保 瑠華(クボ ルカ)福岡 賢治(フクオカ ケンジ) 森岡 郁晴 (モリオカ イクハル) |
目的 本研究では,日本人渡航者が,黄熱の予防接種時に黄熱に対する基本的知識,渡航先の流行の有無,帰国後に黄熱の発症を疑うときの対処法などについての情報収集ができているかを明らかにし,日本人渡航者の感染症対策について検討することを目的とした。
方法 対象者は,2008年6月~9月に,黄熱の予防接種を受けるため関西国際空港検疫所に来所した日本人渡航者とした。自記式質問票の調査内容は,渡航先,渡航目的,滞在期間,予防接種の必要性を知りえた情報源,黄熱に対する基本的な知識(症状,感染経路,対処法,予防策),渡航先での流行状況の把握の有無とその情報源,渡航先で受診できる病院の知識の有無とその情報源,帰国後疑わしい症状が出現した際の対処法の知識の有無とその情報源など計15項目とした。
結果 対象者数115名のうち,有効回答数は112名であった(有効回答率97.4%)。黄熱について「調べている」と回答した者の割合は52.7%であった。そのうち,黄熱の主な症状についての正答率は半数以上であり,感染経路の正答率は89.8%であった。さらに,対処法,予防策の正答率も高かった。黄熱に関する全体的な知識を渡航経験の有無別に各個人の正答数と誤答数でみると,正答数はある者4.3個,ない者6.8個であり,ある者の方が有意に少なかった。誤答数はある者3.8個,ない者2.2個と,ある者の方が有意に多かった。渡航先での黄熱の流行状況を51.8%の者が「把握している」と回答した。渡航先で病気・けがをした場合に受診できる病院を「調べている」と回答した者が13.4%であった。また,帰国後に感染症が疑われる症状が続く場合の対処法を「把握している」と回答した者は36.6%であった。これらのことから黄熱の対処方法の情報収集は十分ではなかった。
結論 日本人渡航者は,渡航経験の有無を問わず黄熱の症状や感染経路などの基本的な知識はある程度持っているが,感染症対策について十分に対応できていないことが明らかになった。したがって,医療に携る者は,渡航者に対し,自分の身は自分で守るという意識改善を訴えていかなければならない。
キーワード 渡航者,黄熱,予防対策
|
第56巻第15号 2009年11月 米国におけるブタ(swine)インフルエンザ集団発生(1976年)から全国予防接種キャンペーン開始までの経緯武知 茉莉亜(タケチ マリア) 小林 真之(コバヤシ マサユキ) 近藤 亨子(コンドウ キョウコ)大藤 さとこ(オオフジ サトコ) 福島 若葉(フクシマ ) 前田 章子(ワカバ マエダ) 廣田 良夫(アキコ ヒロタ) |
目的 1976年2月にFort Dix米陸軍基地で認められたブタ(swine)インフルエンザの集団発生から,同年10月の全国インフルエンザ予防接種キャンペーン(National Influenza Immunization Program: NIIP)開始までの一連の流れを要約し,新型インフルエンザ対策の参考に資する。
方法 Fort Dixにおけるswineインフルエンザの集団発生,NIIP決定までの経緯,およびワクチンのfield trialに関する文献から得た情報を時系列に記す。
結果 Fort Dixのswineインフルエンザ集団発生以後,米国の内外で新たな集団事例が確認されなかったにもかかわらず,swineインフルエンザの流行が起こるという前提のもと,NIIPの実施が決定された。計画当初では,接種対象の優先順位は決められておらず,全国民に対して1回の予防接種が妥当であるという予測のもと,2億人分のワクチンを製造することが決定された。また,採択されたNIIPの計画案では,swineインフルエンザ流行が再来しない,という場合については想定されていなかった。NIIPで使用する予定のワクチンに関してfield trialが行われ,様々な年齢層を対象に,2社のsplitワクチンおよび他2社のwholeワクチンが抗原量別に評価された。その結果を踏まえ,免疫原性と安全性が確認されたワクチンにつき,用量・接種回数を規定したうえで接種が勧告された。しかし,NIIP開始までにすべてのfield trialは完了せず,開始前の接種勧告発表に至らなかった年齢層もみられた。また,全国民に予防接種を行うことを予定していたにもかかわらず,ワクチンの必要供給量は確保できていなかった。ワクチン接種開始後,接種者におけるギラン・バレ-症候群の発生が報告され,NIIPは中止となった。
結論 1976年のswineインフルエンザ事例から,流行の可能性はもとよりワクチン製造といった人為的なことを含め,あらゆる点において予測は覆されうるという前提に立って対策を検討する必要性が示唆された。予防接種キャンペーンを計画する際は,そのような前提を考慮したうえで,計画の社会的意義を国民に周知させることが重要と考えられる。
キーワード swineインフルエンザ,予防接種計画,ワクチン製造
|
第56巻第15号 2009年11月 保健所の権限および組織からみた健康危機管理にふさわしい組織のあり方に関する研究藤本 眞一(フジモト シンイチ) 石川 貴美子(イシカワ キミコ) |
目的 「保健所」の様々な役割のうち,健康危機管理機能に着目して,地方自治体により福祉事務所との統合組織を構築されたことによる様々な形態となっている組織と,地方自治体の首長から委任されている権限を分析した。都道府県立保健所については,筆者らの先行研究があるので,今回は市・特別区立保健所について分析を行った。
方法 保健所設置市区の保健所を含む統合組織の実態と,健康危機管理を含む保健所等に委任された権限を平成18年11月現在で調査・分析した。統合組織の分析は各自治体のホーム・ページおよび全国所長会の名簿等を参考とした。また保健所に委任される権限は,衛生・環境に関係する法令について,保健所,あるいは保健所を含んだ統合組織,保健所を含まないその他の組織への委任に分けて分析を行った。
結果 保健所組織については市区が設置するものは140カ所であったが,政令指定都市以外の設置する市区保健所は全て統合化されておらず,また全体としても単独設置が大半であった。また権限委任については,82市区中3市は委任が皆無であり,1市はほとんど委任されていなかった。他の78市区において,健康危機管理に関する権限の委任割合は都道府県よりも少なかった。委任の内容は自治体により様々であった。
結論 保健所組織,権限とも様々な形態が観察された。地方分権としての首長の自由裁量と,保健所の本来果たすべき役割の法的位置づけを,さらに整理して,法定化していく必要がある。
キーワード 保健所,健康危機管理,地方分権,統合組織,権限
|
第56巻第15号 2009年11月 介護老人福祉施設におけるケアの質の確保と施設の組織・管理石黒 文子(イシグロ アヤコ) |
目的 高齢者に対するケアの質は,提供する介護職員の質に依存することが多く,一人の利用者に対して多くの介護職員が関わる施設介護の現場において,質の高いケアを提供していくためには,組織的な取り組みが必要である。そこで,介護職員と組織との良好な関係が,結果的にケアの質の維持・向上につながるものと仮定し,介護職員の仕事と組織・管理に関する認識の現状を探索的に分析し,施設において優先的に取り組むべき組織の課題を明らかにすることを目的とした。
方法 2007年9月に,ケアの質の向上に組織的に取り組む3カ所の介護老人福祉施設の介護職員を対象とした留め置きによる自記式回答法調査を実施した。調査項目は,基本属性のほかに,組織コミットメント,仕事や職場の組織・管理の現状,職務満足度を中心に構成した。
結果 組織コミットメントを因子分析した結果抽出された第1因子「残留・意欲」および第2因子「情緒的コミットメント」の因子得点と,個人属性,仕事や職場の現状に対する認識,職務満足度との関連について,相関係数の算出,一元配置分散分析,重回帰分析を行った結果,職務や教育体制の現状に対して肯定的に捉えている職員,賃金に対して満足している職員ほど「残留・意欲」と「情緒的コミットメント」がともに高かった。また,上司・リーダーや同僚との関係の現状に対して肯定的に捉えている職員ほど「情緒的コミットメント」が高い傾向にあった。さらに,組織コミットメントについて,離職率の高い施設と低い施設の介護職員に差がみられた。
結論 結果から,ケアの質の向上のために優先的に取り組むべき組織的な課題として,3点があげられる。第1に,仕事に対して達成感が感じられる仕組みや自分の能力を活かすことができる体制を構築していくこと,第2に,労働に見合った賃金のあり方を検討し,施設に見合った人事評価制度のあり方を確立していくこと,第3には,職員の意見を反映した教育・研修を行っていくことである。また,離職が介護施設を揺るがす大きな課題となっている中で,離職率による差がみられた組織コミットメントは,組織を管理していく上での有効な1つの指標となる可能性が示唆された。
キーワード ケアの質,介護職員,組織コミットメント,離職
|
第56巻第15号 2009年12月 健康危機関連事件における本来のリスクを上回ると思われる
今村 知明(イマムラ トモアキ) 尾花 尚弥(オバナ ナオヤ) 山口 健太郎(ヤマグチ ケンタロウ) |
目的 食品健康被害事件の際におこる報道機関や消費者における不明確なリスクや不可視なリスクに対する過剰な反応の発生メカニズムを把握する。
方法 近年発生した食品由来の健康危機について,新聞記事を収集し,定量分析を行った。また,収集した新聞記事の中で,BSE事件(2001年)については,この事件が原因と推定した自殺者の数もカウントした。
結果 食品由来の健康危機事件の中で,BSE事件では,記事数・文字数ともに大きく減少することなく報道が継続された。事件が社会問題化したことにより,関連産業の売上減少等が発生し,複数名の関係者が自殺する事態に至った。鳥インフルエンザ(山口県)においても,毎日の報道記事数が数十件に達するなど,報道の持続性がみられた。一方で,消費者の本来のリスクを上回るような反応が懸念されたが,顕在化しなかった6事例では,リスクを報道する記事が毎日掲載されることはなく,1日平均記事件数も数件程度に止まった。また,これらの事例の新聞記事の掲載頻度は,日数を経るごとに件数・文字数ともに減少し,BSE事件等で観察された「報道の持続性」を確認できなかった。鳥インフルエンザは,2004年以降,毎年大規模な感染が発生したが,2004年の事件では,多数の記事が毎日掲載された。他方,翌年以降の事例では,発生後約1週間を境に新聞記事数が漸減した。
結論 食品由来の健康危機に直面した消費者,報道機関において,本来のリスクを上回る反応が発生している状況が確認できた。筆者らは,このような一般消費者の,客観的なリスク水準(被害の発生確率)に拠らない過剰な反応を「ゴースト効果」と名付けた。消費者は,平常時であれば,健康危機の不安を報じる記事に接触しても冷静に対応できるものの,危機発生時には「幽霊」が発生し,消費行動を変える可能性が高まる。したがって,危機発生時には,不安報道が増えないことが望まれるが,このためには,食品リスクについて,「原因が未解明である」「新規性が高い」など報道機関のリスクを上回る反応を誘発するリスク特性への適合状況を確認し,「幽霊」の発生可能性の高さを早期に見極め,対策を検討する必要がある。
キーワード 健康危機,リスクコミュニケーション,報道情報,リスク分析
|
第56巻第15号 2009年12月 要支援ならびに要介護高齢者を居宅で介護している
|
目的 要支援ならびに要介護高齢者(以下,要介護高齢者)の家族介護者の介護負担と主観的QOLを測定し,要介護高齢者の要介護度ならびに認知症の有無との関連性を明らかにし,家族介護者支援を考慮するための基礎資料を得ることを目的とした。
方法 2007年8月時点において,要介護高齢者を居宅において介護する家族介護者1,657名を調査対象とした。家族介護者と要介護高齢者の基本属性に加えて,要介護高齢者の要介護度,認知症の有無や家族介護者の介護負担尺度(J-ZBI_8)と主観的QOL尺度等について調査した。
結果 771票が回収され(回収率46.5%),主要な分析項目において欠損のなかった579票(有効回答率34.9%)を分析対象とした。要介護高齢者の要介護度は,要介護2(21.6%)同3(20.0%)同1(18.7%)の順で多かった。また要介護高齢者の約半数が認知症を有していた(認知症群47.1%)。家族介護者のJ-ZBI_8の平均得点は12.5点(得点範囲0~32点),主観的QOL尺度の平均得点は24.0点(得点範囲12~36点)であった。そしてJ-ZBI_8得点と主観的QOL尺度総得点の相関係数はr=-0.588で有意であった(p<0.001)。「家族介護者の介護サービス利用満足感」と「介護期間」を統制変数とし,要介護高齢者の要介護度と認知症の有無を独立変数,J-ZBI_8得点と主観的QOL総得点をそれぞれ従属変数とする2要因共分散分析を行った。その結果,J-ZBI_8得点では交互作用が有意(p<0.05)であり,単純主効果の分析の結果,要支援から要介護3までは,認知症の有無の単純主効果が有意に認められ,認知症群は非認知症群に比べて介護負担が有意に高かった。また非認知症群において要介護度の単純主効果が有意に認められ,多重比較(Bonferroni法)の結果,要介護4は要支援,要介護1,同3に比べて介護負担が有意に高かった。特に要介護度が低い場合,認知症高齢者の家族介護者は非認知症高齢者の場合に比べて介護負担が高く,介護ニーズの程度が高い状態である可能性が示唆された。また主観的QOL総得点では,認知症の有無の主効果が有意(p<0.01)であり,認知症群は非認知症群に比べて主観的QOLが有意に低かった。家族介護者の主観的QOLの低下を防ぐこと,さらに介護負担が増悪しないためにも,早期介入による支援は有効であると考えられる。
結論 要介護度別と認知症の有無において,家族介護者の介護負担と主観的QOLの状況が異なることが示唆された。このことから,家族介護者の介護負担と日常の介護生活における主観的QOLを併せて測定し,要介護度と認知症の有無において,両変数の状況を明確にし,基礎資料とする取り組みは,家族介護者支援を考慮するための端緒として重要であることが考えられた。
キーワード 家族介護者,要支援ならびに要介護高齢者,認知症,介護負担,主観的Qualify of Life(QOL)
|
第56巻第15号 2009年12月 食生活改善推進員の健康習慣と役割意識に関する調査鈴木 みちえ(スズキ ミチエ) 中野 照代(ナカノ テルヨ) |
目的 健康づくりのための地区組織として活動の歴史が長い食生活改善推進員活動の有用性検討の基礎資料を得ることを目的に,推進員自身の健康習慣と役割意識との関連について検討した。
方法 平成19年5月に開催されたS県健康づくり食生活推進協議会総会に参加した推進員を対象に属性および背景,健康習慣,推進員としての役割意識に関する自記式質問紙調査を実施した。有効回答が得られた223名を分析対象とし基本統計量の算定,健康習慣と役割意識との関連性について検討した。
結果 推進員の年代は50代,60代が85.6%を占め,経験年数は1年未満~32年とその幅が広く,10年~20年未満の長期に渡る者が32.7%あった。推進員以外の社会活動への参加経験を96.4%が有し,「非常に健康・健康なほうである」の両者で91.5%であった。好ましい健康習慣保有者は喫煙しない99.1%が最も多く,続いて毎日朝食96.4%,適正飲酒78.5%,定期健診73.1%,適正体重,適正睡眠,休養は50%以下,間食注意35.0%,定期的な運動は32.7%と最も少なかった。さらに,有職者の方が適正飲酒の割合が少なく(p<0.01),適正睡眠,定期的な運動,休養,定期健診の4項目で少ない傾向にあった(p<0.1)。役割意識は因子分析の結果「組織の活動目標の自覚」「推進員に求められる姿勢の自覚」「組織の社会的役割の自覚」「家庭内役割の自覚」の4つに分類され,因子別平均値は好ましい健康習慣保有者の方がそうでない者より高値であった(p<0.01またはp<0.05)。
結論 一般人より健康意識の高いと推測される集団であっても,間食注意,定期的な運動等,習慣化しにくい保健行動があり,健康づくりリーダーとしての個々の力量を高めるためには,集団としての推進員への働きかけと併せて,個別の健康支援の必要性が示唆された。役割意識と好ましい健康習慣との関連が認められ,役割の自覚が自身の健康管理意識を高めることになるという活動の有用性の示唆を得た。
キーワード 地区組織活動,食生活改善推進員,健康習慣,役割意識
|
第56巻第15号 2009年12月 就学前児社会スキル尺度と広汎性発達障害(PDD)との関連篠原 亮次(シノハラ リョウジ) 星野 崇宏(ホシノ タカヒロ) 杉澤 悠圭(スギサワ ユウカ)童 連(トン レン) 田中 笑子(タナカ エミコ) 渡辺 多恵子(ワタナベ タエコ) 恩田 陽子(オンダ ヨウコ) 安梅 勅江(アンメ トキエ) |
目的 本研究は,発達障害のなかでも特に社会性の障害をその特徴とする広汎性発達障害(PDD)に焦点を当て,就学前児用社会スキル尺度(第1因子:協調,第2因子:自己制御,第3因子:自己表現)の下位尺度得点との関連およびその予測妥当性を検討することで,社会スキル発達リスク該当児の早期発見,早期支援への一助とすることを目的とした。
方法 対象は,2000年から2006年にかけて,全国夜間保育園連盟に加入している21都道府県98カ所の認可保育園に在籍している2歳から6歳までの園児である。方法は,各保育園の担当保育士が,年1回,就学前児用社会スキル尺度を用いて各園児の社会スキルを評価した。また,発達障害に関しては,2006年および2007年に各園で「気になる子ども」としてあげられた園児の中から,医療機関の診断,所見で発達障害(PDD,ADHD(注意欠陥多動性障害),MR(精神遅滞))の確定もしくは疑いの診断をうけている園児のデータを訪問調査の協力を得た各保育園から収集した。分析は,発達障害の確定もしくは疑い該当児を除く園児を「非該当」,PDD該当児を「PDD該当」と2群に分類し,年齢ごとに就学前児用社会スキル尺度の各下位尺度得点に関して2群間の平均値の差の検定を実施した。つづいて,PDD(該当,非該当)を目的変数,就学前児用社会スキル尺度の各下位尺度得点を説明変数としたロジスティック回帰分析を年齢ごとに実施した。
結果 各下位尺度得点に関して,「PDD該当」児と「非該当」児それぞれの平均値は,年齢経過にしたがって平均値の推移に大きな差がみられた。「非該当」児では,年齢の経過とともに各下位尺度得点の平均値が上昇していく傾向があるが,「PDD該当」児では推移の変化に乏しい。特に4歳以降では「非該当」児と「PDD該当」児のすべての下位尺度得点平均値が有意な差を示しており,「PDD該当」児の社会スキルは「非該当」児に比較して低いことが示された。一方,ロジスティック回帰分析結果では,2歳,3歳において第3因子(協調)でのみ,また4歳,5歳,6歳ではすべての因子で有意な関連がみられた。
結論 就学前児用社会スキル尺度は,4歳以降では「PDD該当」リスクが社会スキル尺度の全因子で,また医療機関の診断が確定しにくい2歳,3歳では,第3因子(自己表現)の下位尺度得点で,「PDD該当」への移行を把握可能であることが示唆された。本尺度が,子育て支援専門職にとってPDD児の早期発見,早期支援のための評価手法の一助となることが期待される。
キーワード 社会スキル,就学前児,広汎性発達障害,コホート調査
|
第56巻第15号 2009年12月 がん専門病院における禁煙支援クリニカルパスの実施田中 政宏(タナカ マサヒロ) 田中 英夫(タナカ ヒデオ) 谷内 佳代(タニウチ カヨ)泉本 美佳(イズモト ミカ) 赤木 弘子(アカギ ヒロコ) 大西 聖子(オオニシ セイコ) 松尾 茂子(マツオ シゲコ) 道平 恵子(ミチヒラ ケイコ) 若林 榮子(ワカバヤシ エイコ) |
目的 都道府県がん診療連携拠点病院である大阪府立成人病センターにおける,入院喫煙患者を対象とした禁煙支援クリニカルパス(以下,パス)の実施について報告する。
方法 初回入院の喫煙患者(禁煙開始後1カ月以内を含む)に対して以下のような禁煙支援介入を実施した。同意を得ることのできた喫煙患者に対して,入院予約日にパスを発行して外来看護師による禁煙指導と情報提供を行い,入院日に病棟看護師による禁煙指導と情報提供を行った。また,退院日には病棟看護師による入院中の禁煙状況の確認,禁煙継続の勧奨と情報提供を行い,さらに退院後1カ月,6カ月時点での調査票の送付による禁煙状況の確認(自己申告によるフォローアップ)を行った。実施方法を標準化するために,それぞれの介入はいずれもパスと禁煙情報提供用のリーフレットに基づいて行われ,実施時間は原則として数分間の簡単なものとした。
結果 2005年5月~2009年3月までに1,789人(年齢中央値59歳)に対してパスを発行した。うち,2009年3月末までに退院した1,585人(以下,パス発行者)の77%が入院予約日時点で喫煙中であり,20%が禁煙開始後1カ月以内であった。パス発行者の入院予約から入院までの日数の中央値は18日であり,入院までの喫煙状況は,対象者の52%が入院前日まで喫煙し,13%が入院前2~7日以内の間に喫煙していた。入院時介入はパス発行者の82%に行われており,入院中に喫煙した者は21%であった。退院時介入は対象者の67%で実施されており,そのうちの81%がフォローアップに同意していた。同意者のうち,退院後1カ月時点,6カ月時点での禁煙継続割合(未返答者は喫煙者とみなす)はそれぞれ48%,42%であった。
結論 パス実施上の課題としては以下が考えられた。①入院時・退院時ともに介入を実施できた患者の割合は対象患者全体の7割程度であり,退院時が特に低く,ともにパス制度の導入時から漸減傾向にあったこと。その理由としては,職員の入れ替わりと,パスの必要性の認知が他のクリニカルパスよりも低い可能性などが考えられた。②パスの対象者が比較的禁煙困難な者であり,かつ介入がごく簡単なものであることから考えると,退院後6カ月時点での禁煙継続割合が4割という値は予想以上に高い印象をうけること。この理由としては,入院・手術という環境介入効果が大きいこと,また自己申告の不正確さの可能性等が考えられた。③退院後の禁煙継続のためには,禁煙指導のフォローアップ体制の強化が必要であり,患者に影響力の高い主治医の外来での協力を得る方策の検討が望まれること。他に,入院前後の禁煙治療とパスの連携の強化が望まれる。
キーワード 禁煙,クリニカルパス,入院,治療効果,がん,循環器
|
第56巻第15号 2009年12月 夜間対応型訪問介護の最重要課題-関係機関への追跡実態調査を踏まえて-田中 孝明(タナカ タカアキ) 脇野 幸太郎(ワキノ コウタロウ) |
目的 在宅での生活を希望する要介護者にとって,夜間帯での緊急時のニーズに対応するのが夜間対応型訪問介護である。平成17('05)年の介護保険法改正によって地域密着型サービスのひとつとして創設され,市町村の指定・監督権限のもと実施されている。本研究では,この事業の実態について把握することを目的とし,そこから明らかになる問題点について若干の検討を行ってみたい。
方法 本調査は,平成20('08)年4月から平成21('09)年4月までの厚生労働省「介護給付費実態調査月報」を参考とするほか,平成21('09)年7月1日から31日に実施した追跡アンケート調査をもとにまとめた。具体的には,全国の夜間対応型訪問介護の事業所に対するアンケート調査から実態を分析する。
結果 事業所数の推移は,全国的な傾向として減少傾向にある。開設主体では営利法人が最も多く,これに社会福祉法人が続いている。利用者数に関して,全国的には増加傾向にある。利用者の属性として,介護度が軽・中度の利用者が大半を占めている。家族構成は,高齢者単身世帯が半数以上である。訪問理由について,「排泄」が最も多く,次いで「転落・転倒」であった。自治体による緊急通報サービスとの兼務に関しては,29事業所のうち6事業所が自治体から委託されていた。
結論 この事業の利用状況は低調であり,利用率を伸ばすためには潜在的なニーズの掘り起こしが必要である。そのためには,広報の充実が求められるとともに,安定的な運営体制の確保のために人材の確保が急務である。また,この事業拡大のために,類似したサービスである緊急通報サービスとの機能を整理したうえで,有機的な活用方法が望まれる。
キーワード 夜間対応型訪問介護,介護報酬改定,利用限度額,緊急通報サービス
|
第57巻第1号 2010年1月 大学生を対象とした,食の安全教育に用いる教材
|
目的 現代の消費者は,安全性からみた食の選択能力を身につける必要がある。著者らは,専門家が考える,一般消費者が必要とする知識をもとに,カードゲーム「カルテット-食の安全編-」を開発した。本研究は,「カルテット-食の安全編-」の利用可能性を評価することを目的とした。
方法 対象者は,都内の女子大学1校に在学中の,食物栄養学を学ぶ学部3年生34人とした。調査は2009年1月,構内の教室にて実施し,ランダム化比較試験を用いた。介入群(以下,ゲーム群)ではカルテットを用いたゲームを行い,コントロール群(以下,講義群)では講義を行った。
結果 介入による知識の変化は,時間による主効果はみられたが(F(1,30)=83.33,p<0.001),群による主効果と交互作用はみられなかった(群による主効果:F(1,30)=0.49,p=0.488;交互作用:F(1,30)=3.33,p=0.078)。また「面白さ」において,有意差はみられなかったが,「とても面白かった/まあまあ面白かった」と回答した割合は,ゲーム群(17人,100%)のほうが講義群(15人,88%)よりも多かった。
結論 ゲームと講義で習得した知識に差はなかった。しかし,有意差はないものの「面白さ」と「新しく得たもの」はゲーム群で多く,ゲームで遊ぶメリットが得られた。今後は大学生以外の一般消費者に対しても,「カルテット-食の安全編-」を実施し,利用可能性および教育効果を測定する必要がある。
キーワード 大学生,食の安全教育,ゲーム,ランダム化比較試験,利用可能性,知識
|
第57巻第1号 2010年1月 大阪府におけるがん患者受療動態および地域別生存率の検討志岐 直美(シキ ナオミ) 大野 ゆう子(オオノ ユウコ)伊藤 ゆり(イトウ ユリ) 津熊 秀明(ツクマ ヒデアキ) |
目的 大阪府を対象にがん患者の治療時における受療動態および地域別生存率を検討した。
方法 対象は1993年から2002年の間にがんと診断され,大阪府がん登録に登録された患者のうち,主要5部位(胃,大腸,肝臓,肺,乳房)のがん患者を対象とした。がん診断年を前期(1993~1997年)と後期(1998~2002年)に分け,それぞれについて各2次医療圏間の患者移動状況を整理し,2次医療圏を単位とした患者の流出割合を部位ごとに算出した。特に,がん診断時の患者居住地と,治療を受けた医療機関の所在地(施設所在地)が同一の患者の割合を完結割合として算出した。さらに前期に診断された患者については,進行度,年齢構成の影響を調整した5年生存率を施設所在地別,患者居住地別に算出し,地域間の生存率格差について検討した。
結果 完結割合は地域によって異なり,前期では87.8%(大阪市)から40.3%(中河内),後期では90.2%(大阪市)から38.2%(中河内)の違いがあった(5部位計)。同一地域でも部位によって完結割合は異なり,特に肝がん,肺がんで低い傾向がみられた。前期から後期にかけて,大腸がんや乳がんでは完結割合が増加する地域がみられた。各地域に居住する患者の主な流出先は大阪市など治療において拠点となるような医療機関が集中する医療圏であり,当該地域の医療提供体制が患者受療動態に影響していると考えられた。施設所在地別の生存率では,年齢,進行度を調整した後も地域間格差がみられ,特に肝がんで11.0%,肺がんで13.4%と大きかった。一方,患者居住地別では生存率の地域間格差はどの部位においても3~5%前後と小さくなっていた。患者の医療圏間の移動によって,生存率の地域間格差が小さくなっている可能性が示唆された。
結論 現在,2次医療圏ごとに医療提供体制が整備されてはいるが,医療圏によって治療成績は異なり,また,部位によって受療動態は異なっていた。医療圏間の施設連携など,患者受療動態を踏まえた医療提供体制整備が望まれる。
キーワード がん患者,受療動態,地域別生存率,大阪府がん登録(856words)
|
第57巻第1号 2010年1月 中高年を対象とした健康不安感尺度作成と信頼性・妥当性の検討鈴木 宏和(スズキ ヒロカズ) 長塚 美和(ナガツカ ミワ)荒井 弘和(アライ ヒロカズ) 平井 啓(ヒライ ケイ) |
目的 薬局を訪れた中高年を対象としたアンケート調査により,健康不安感尺度を作成して,健康不安と性別,年齢,健康関連QOLとの関連を検討した。
方法 「医療とライフスタイルに関するアンケート調査」として,全国15地域の調剤薬局に訪れた人の中から30歳以上の男女を対象にして無記名の郵送法による横断的質問紙調査を行った。健康不安感尺度に関して最尤法プロマックス回転による探索的因子分析を行った。その後,因子妥当性を確認するため確認的因子分析を行った。また,作成した健康不安尺度を基に,健康不安と性別,年齢,健康関連QOLとの関連を,t検定と相関分析を用いて検討した。
結果 健康不安感尺度について,「身体的健康に対する心配」「重篤な病に対する否定的認知」「健康に対する心気傾向」の3つの因子からなる尺度が作成された。そして,これらの因子は互いに関連しあっていた。また,尺度の因子全体の適合度についてみるとGFI=0.94,CFI=0.93,RMSEA=0.06という結果が得られ,因子妥当性,内的整合性ともに十分な結果を得た。また,健康不安尺度は年齢と正の相関があった。性差は認められなかった。さらに,この健康不安感尺度は健康関連QOLと負の相関があることが確認された。
結論 本研究により,健康不安を多面的に捉えることのできる尺度が開発され,わが国の一般成人の健康不安についての基礎データが得られた。今後,高齢化が進む中で心気症的愁訴を持つ患者は増えるものと予想されるなか,心気症か否かで患者に対する対応を考えるのではなく,健康に対して大きな不安を持った人々に対してどのようにサポートしていくかが今後の課題となる。そのサポートを明らかにしてゆくときに,本研究で開発された尺度は健康不安を多面的に測定する尺度として使用されることが期待できる。
キーワード 健康不安,心気症,主観的健康,中高年
|
第57巻第1号 2010年1月 点字ブロックが車いす使用者,高齢者,幼児の移動に
水野 智美(ミズノ トモミ) 徳田 克己(トクダ カツミ) |
目的 車いす使用者,歩行補助車(シルバーカーを含む)を使用する高齢者,ベビーカー使用者,幼児が点字ブロックをどの程度,歩行上のバリアに感じているかを明らかにする。
方法 車いす使用者193名,ベビーカー使用者441名,幼児をもつ保護者433名に対する質問紙調査,歩行補助車を使用する高齢者206名に対する個別ヒアリング調査を実施した。
結果 車いす使用者のうちで点字ブロックを不便に感じたことがないと答えた者はわずか5%に過ぎず,多くの者が点字ブロックをバリアに感じていた。バリアに感じる理由として「点字ブロックの凹凸によってキャスターの向きが変わるため進行方向が定まらない(55%)」「振動のために体位が安定しない(43%)」等が挙げられた(複数回答)。また,歩行補助車を使用する高齢者のうちの55%(112名)が点字ブロック上は歩きにくいと感じていた。その理由として「車輪が引っかかる」「凹凸の上を歩くと足が痛い」等が挙げられた。さらに,ベビーカー使用者のうちの82%(362名)が点字ブロックにベビーカーの車輪がひっかかって困ると回答し,幼児の50%(218名)が点字ブロックにつまずいたことがあると答えた。
結論 本研究の結果から,車いす使用者,高齢者,幼児は点字ブロックをバリアとして感じている傾向が強いことが確認できた。今後,様々な人が共生する社会を実現するため,これらの人々のバリアにならないための点字ブロックの設置方法について具体的に検討していく必要がある。
キーワード 点字ブロック,共生,バリアフリー
|
第57巻第1号 2010年1月 タイムスタディで捉えるレジデンシャル・
|
目的 転換期にある施設福祉サービスマネジメントに注目して,そのソーシャルワークの標準化と専門性を明らかにすることを目的に,時間と回数という量的測度から,介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における生活相談員(以下,相談員)の業務と計画担当介護支援専門員(以下,施設ケアマネ)のソーシャルワーク業務の実態を調査した。
方法 調査は2009年4月から5月に介護老人福祉施設15施設の相談員16人を対象とし,比較対照として施設ケアマネ21人を加え,1分間タイムスタディ調査(自計式)を実施した。そのソーシャルワーク業務分類を,16項目の大分類,106項目の中分類,285項目の小分類のコードに設定できた。今回の調査分析には,大分類と中分類における各業務の「1日当たりの平均累積時間」「1日当たりの平均発生回数」「1回当たりの平均発生時間」を検証した。統計分析は,SPSS 17.0 J for Windowsのソフトを用いて,Spearman順位相関とMann-Whitney順位検定で分析した。
結果 相談員における大分類の1日当たりの平均累積時間では,1位「ケアワーク」169.61±103.88分は全体平均総和の百分率30.5%で最も多く,続いて2位「間接業務」109.00±77.77分(19.6%),3位「チームマネジメント」72.69±68.97分(13.1%)の順であった。相談員の1回当たりの平均発生時間では,1位「アセスメント」59.25±37.45分は全体の平均総和13.6%が最も多く,続いて2位「職員研修」49.38±29.17分(11.4%),3位「契約」31.67±14.04分(7.3%)の順であった。相談員と施設ケアマネの1日当たりの平均累積時間と平均発生回数の有意差の検定をした結果,相談員には,「施設運営管理等(p<0.01)」「地域との連携(p<0.01)」「ニーズの把握(p<0.01)」「スーパービジョン(p<0.01)」「チームマネジメント(p<0.05)」「権利擁護(p<0.05)」に統計的有意差が認められ,施設ケアマネは「ケアワーク(p<0.01)」のみに統計的有意差を認めた。
結論 ソーシャルワークにおける1日当たりの平均累積時間は,業務時間の標準化となるが,その専門性は評価が困難であった。1回当たりの平均発生時間が,1日当たりの平均累積時間より長い業務は,ソーシャルワークの専門性を評価するものと考える。施設内ソーシャルワークとケアマネジメント業務に有意差がみられた業務は,分業による特異性が高いと考える。
キーワード 介護老人福祉施設,1分間タイムスタディ,レジデンシャル・ソーシャルワーク(RSW),RSWコード
|
第57巻第1号 2010年1月 医学的研究およびICD改正に対応した索引データの整備に関する検討藤原 研司(フジワラ ケンジ) |
目的 ICD(通称:国際疾病分類)は,現在ICD-10までの改訂が行われており,さらにICD-11に向けて国際的に検討が進められている。WHOのICD改正・改訂作業に,より迅速に対応するため,英語と日本語を関連づけした電子化索引データを整備する。
方法 索引データの整備は,①WHOの英語版(ICD-10第2版)と日本語版(ICD-10(2003年版準拠))の索引の統合,②英語版にのみ記載された項目,日本語版にのみ記載された項目の特定,③階層構造をもつデータの同時検索システムの構築,④WHOのICD-10第2版以後の一部改正を作成したデータに追加の内容で行ない,英訳,和訳が統一的に行われているか等を検証した。
結果 索引データ(約63,000行)について,和訳,英訳が統一的に記載されたものとするとともに,
階層構造のデータを一度に検索可能なデータとした。これにより,全体の約1割弱については,日本で独自に索引に追加したものであること,同一の英語であっても1次索引項目に続く項目によっては和訳が異なること等が判明した。
結論 今回整備されたデータは,ICDの分類としての基本構造を検討する際の基本的データとして利用可能であり,今後,ICD-11の分類構造について検討を行う際の問題点抽出等に大きな役割を果たすことできると考えられる。
キーワード ICD改正,電子化索引データ,索引データの整備
|
第57巻第2号 2010年2月 居宅要支援高齢者の健康状態と健康管理の特徴-前期・後期高齢者別の検討-長谷川 直人(ハセガワ ナオト) 佐藤 和佳子(サトウ ワカコ) 佐藤 冨美子(サトウ フミコ)舟山 恵美(フナヤマ エミ) 大島 扶美(オオシマ フミ) 今野 日出子(コンノ ヒデコ) 佐藤 千鶴(サトウ チヅル) 山形市健康福祉部介護福祉課 |
目的 要支援および軽度要介護高齢者は急増しており,第3期介護保険改正(平成18年)において要支援高齢者の介護予防を目的に新予防給付が創設された。本研究では,介護度の中重度化予防に資するべく,居宅要支援高齢者の健康状態および健康管理の実態を示すとともに,前期・後期高齢者別の特徴を明らかにすることを目的とする。
方法 山形市に登録されている要介護状態区分が,要支援1・2および経過的要介護である1,732名に対し,郵送法によるアンケート調査を実施した。調査項目は,基本属性(性別,年齢,家族構成,経済状況に対する認識,要介護状態区分,障害高齢者および認知症高齢者の日常生活自立度),健康状態(現病歴,自覚している身体機能の低下と症状,身長,体重,受療頻度,睡眠の満足感,抑うつ症状,主観的健康感),健康管理(食事,水分摂取,運動,眠剤・安定剤の使用,自立への意欲)である。解析では,対象を前期群(75歳未満),後期群(75歳以上)の2群に分類し,各項目についてχ2検定を実施した。
結果 アンケート票1,085通(63.1%)が回収され,1,059通(有効回答率97.6%)を解析対象とした。居宅要支援高齢者は,ほぼ全員が何らかの病気で治療を受けており,身体機能の低下や症状を自覚していた。また,約7割がうつ予防の支援が必要と推測され,自分自身を「健康ではない」と捉えていた。一方,約8割が食事や水分摂取に配慮しており,約7割が週に2回以上の運動を実施していた。前期・後期別の比較では,前期群は脳卒中の既往を有する者,手足の不自由さやしゃべりにくさを自覚している者,および肥満の該当者が多く,主観的健康感が低い対象全体の中でもさらに低かった。後期群は,認知症高齢者の日常生活自立度が低く,眼病・心臓病・呼吸器病を有する者,足腰や関節の痛み,もの忘れ,失禁および聞こえにくさを自覚している者が多かった。
結論 居宅要支援高齢者の健康状態を適切にアセスメントし,病気の管理と生活習慣の改善を支援することでより効果的な介護予防につながる可能性が示唆された。特に前期高齢者は生活習慣病予防,後期高齢者は廃用症候群および認知症予防により特化して支援することが必要と考えられる。
キーワード 高齢者,要支援,健康状態,健康管理,介護予防
|
第57巻第2号 2010年2月 介護保険に基づく平均自立期間の算定方法の適切性に関する調査世古 留美(セコ ルミ) 川戸 美由紀(カワド ミユキ) 橋本 修二(ハシモト シュウジ)林 正幸(ハヤシ マサユキ) 加藤 昌弘(カトウ マサヒロ) 渡辺 晃紀(ワタナベ テルキ) 野田 龍也(ノダ タツヤ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) 辻 一郎(ツジ イチロウ) |
目的 介護保険に基づく平均自立期間の算定方法(厚生労働科学研究費補助金による「健康寿命の地域指標算定の標準化に関する研究班」が提案)に関して調査を行い,その適切性などを検討した。
方法 都道府県,特別区と指定都市(以下,都道府県等)の健康福祉担当部局主管課長87人と保健所長517人に対して,調査票を配布・回収した。調査内容は指標の名称と要介護の定義(提案方法では介護保険の要介護2~5)の適切性などとし,回答は「適切」「どちらかといえば適切」「どちらかといえば適切でない」「適切でない」などの4肢択一形式とした。
結果 都道府県等は69人(79%),保健所は388人(75%)から調査票が回収された。平均自立期間という名称の適切性に対して「適切」または「どちらかといえば適切」の回答割合は90%であった。要介護2~5以外の介護保険の要介護度で,あるいは介護保険以外で,要介護の適切な定義に対して「ある」または「どちらかといえばある」の回答割合は10%以下であった。平均自立期間の意味に対して,地域保健担当者による理解が「容易」または「どちらかといえば容易」の回答割合は92%,一般住民でのそれは61%であった。市区町村の算定に対して「重要」または「どちらかといえば重要」の回答割合は81%であった。都道府県健康増進計画以外への活用に対して「可能」または「どちらかといえば可能」の回答割合は68%であった。いずれの回答割合ともに都道府県等と保健所に大きな差がなかった。
結論 提案された平均自立期間の算定方法は都道府県等からおおよそ支持されたと考えられる。今後,市区町村の算定と都道府県健康増進計画以外への活用を検討することが重要であろう。
キーワード 平均自立期間,健康寿命,介護保険,都道府県健康増進計画
|
第57巻第2号 2010年2月 北海道内の産婦人科および小児科医師数の減少が死亡率に及ぼす影響中木 良彦(ナカギ ヨシヒコ) 西條 泰明(サイジョウ ヤスアキ) 伊藤 俊弘(イトウ トシヒロ)杉岡 良彦(スギオカ ヨシヒコ) 遠藤 整(エンドウ ヒトシ) 千石 一雄(センゴク カズオ) 今井 博久(イマイ ヒロヒサ) 吉田 貴彦(ヨシダ タカヒコ) |
目的 本研究では,個人の食物選択が社会に影響を及ぼすことの理解は,食に対する意識や行動に影響を与えると考え,「食生活改善行動の採用」を評価する尺度の開発と行動変容へと導くモデルを提案することを目的とする。
方法 対象は40歳から62歳の被雇用労働者の男性200名とし,調査は平成21年9月に行った。データ収集方法は,インターネットを利用した間接的な自記式質問紙調査とした。質問紙の信頼性については,反応分布の検討,次にG-P分析を行い,各項目得点の高群と低群で平均値の差が顕著でない(p≦0.05)項目は除外した。さらに,I-T相関分析を行い,項目と全体得点の相関が低い(<0.25)項目は除外した。最後に因子分析(主成分分析)を繰り返し,因子を抽出した。質問紙の妥当性および「食生活改善行動の採用」モデルの予測については,特定保健指導に参加した成人男女82名を対象に,同年12月に調査を行った。仮定した因子構造モデルのデータへの適合度は,パス解析を用いて検討した。
結果 44項目の反応分布から27項目5因子が残り,これを「食生活改善行動の採用」測定尺度とした。Cronbachのα係数は全体としての尺度が0.908,下位尺度では0.628から0.830を示し,内的整合性が確認された。外的基準である新しい食物選択動機調査票の下位尺度やecSatter調査票の一部の項目との関連により,一定の収束的妥当性も認められた。また,「個人の食物選択が社会に影響を及ぼす」と理解することから,食に関する意識や行動への影響については,「食事バランスへの意識」が0.676(p<0.001),「食生活変化の受容態度」は0.664(p<0.001),「食物選択動機の合理性」には0.913(p<0.001)の因果関係がみられ,モデルの適合度もそれぞれ受容可能な値が示された。
結論 栄養教育において食物選択と社会へのつながりを理解させることは,彼らの食意識に影響を与え,改善行動の採用に導くための有効なアプローチとして成り立つと考えられる。
キーワード 尺度,妥当性,行動変容,食環境
|
第57巻第2号 2010年2月 介護保険制度下における在宅療養者の生命予後に関連する要因倉澤 高志(クラサワ タカシ) |
目的 介護保険制度が定着した現在の状況における,在宅療養患者の生命予後に影響する要因を検討し,改善するための課題を明らかにすることとした。
方法 大阪府保険医協会の内科系会員を対象に,2007年3月末日時点で継続的に訪問診療を行っている患者に対し1年間の追跡調査の説明を行い同意を得た349名(男性35.5%)につき死亡を主転帰指標として1年間追跡した。ベースラインでの患者情報の中で自立度,認知度,栄養状態については介護保険主治医の意見書に準拠して評価した。生死を従属変数,性別と年齢に加えて自立度,認知度,栄養状態,自己負担金の有無,点滴管理,介護保険サービスの利用有無を独立変数としたコックス回帰分析を行った。
結果 疾患別の生命予後の検討では悪性腫瘍のある者が有意に予後不良であることは明らかであった(p=0.017)。そこで,悪性腫瘍のある者を除外してコックス回帰分析を行った。生命予後に影響する要因として単変量解析では栄養状態不良に加えて自立度や年齢も有意な要因であったが,多変量解析では栄養状態不良のみが有意(p<0.01)な要因として抽出された。そのハザード比は6.89(95%信頼区間2.27-20.92)であった。次に介護認定を受けている者に限定して,栄養状態に影響する介護保険サービスの種類を検討した。訪問診療,訪問看護,通所サービス(通所介護,通所リハビリ)についてはサービス利用の有無と栄養状態不良者の割合とで関連はなかったが,訪問介護についてはサービスを利用者で栄養状態不良者の割合が有意に低かった(女性のみ,p<0.05)。
結語 医療介護全般を考慮した解析では,在宅療養中の患者の生命予後に最も影響するのは栄養状態であった。栄養状態を維持するためには訪問介護の利用が必要であるが,自己負担金のために利用率が下がっている事については何らかの救済策が必要である。
キーワード 在宅療養,生命予後,コックス回帰分析,栄養状態,訪問介護
|
第57巻第2号 2010年2月 介護保険施設の介護職員における介護時間の評価-介護支給時間から介護労働時間と非特定介護時間の比較-國定 美香(クニサダ ミカ) |
目的 介護保険施設の介護職員に対して,タイムスタディ調査を実施し,介護時間および介護内容の実態把握を行う。その結果から,介護保険施設の介護職員における介護サービスの評価を介護時間により検討することを目的とする。
方法 介護保険施設の介護職員による自計式タイムスタディ調査を実施した。調査対象は,介護保険施設7施設の介護職員172人および入所者470人である。研究方法は,介護職員が特定された入所者に対して個別に提供した介護時間と定義した「介護支給時間」と,介護職員が介護サービスに従事した介護時間と定義した「介護労働時間」について,介護内容ごとにWilcoxonの符号付き順位検定で統計分析する。さらにそれらの2つの差である個人を特定できない介護時間を「非特定介護時間」として,その介護内容を検討する。
結果 「介護支給時間」と「介護労働時間」の2つについて,Wilcoxonの符号付き順位検定の結果,ケアコード大分類の10項目中における①入浴清潔保持整容更衣,②移動移乗体位変換,③食事,④排泄,⑤生活自立支援,⑥医療,⑦対象者に直接関わらない業務,⑧機能訓練,⑨社会生活支援で平均介護時間に有意な差が認められた。「非特定介護時間」の介護内容については,小分類ごとの平均値が多いケア内容の結果から,「非特定間接業務」と「非特定直接業務」の2つで主に構成されていることが明らかとなった。
結論 本研究では,以下の3つのことが明らかになった。1つ目として,「介護支給時間」と「介護労働時間」には,大分類10項目の内9項目の平均介護時間に有意な差が認められた。2つ目として,「非特定介護時間」は,「非特定間接業務」や「非特定直接業務」の2つで主に構成されていた。3つ目として,介護保険施設の介護職員における介護サービスの評価として「介護支給時間」だけでなく,「介護労働時間」と「非特定介護時間」も評価する必要性が求められる。
キーワード 介護時間評価,タイムスタディ調査,介護労働時間,介護支給時間,非特定介護時間
|
第57巻第3号 2010年3月 飲食店の分煙状況および関連要因に関する研究長山 有香理(ナガヤマ ユカリ) 桑原 徹人(クワハラ テツヒト) 木下 幸子(キノシタ サチコ)早坂 信哉(ハヤサカ シンヤ) 村田 千代栄(ムラタ チヨエ) 野田 龍也(ノダ タツヤ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) |
目的 浜松市内の飲食店における受動喫煙対策の状況およびその関連要因を明らかにする。
方法 NTT西日本発行,職業別デイリータウンページ静岡県浜松版(2008.2~2009.1)のグルメの項目に掲載されている飲食店(居酒屋,飲食店,うどん・そば店など)から1/10の系統抽出をした356件を調査対象とし電話調査を実施した。質問内容は,禁煙席と喫煙席の区別の有無,常時喫煙以外の場合に分煙や常時禁煙にしようと考えた理由,常時禁煙以外の場合に分煙や常時禁煙にできない理由,全面禁煙・分煙・全面喫煙可能の場合でどの状況が一番客の入りがよいと考えるか,健康増進法による飲食店の受動喫煙防止義務についての認知等である。
結果 有効回答数は345件(96.9%)であった。受動喫煙対策を実施している店は全体で97件(28.1%)あり,そのうちわけは常時禁煙43件(12.5%),常時分煙38件(11.0%),時間・曜日によって異なる16件(4.6%)であった。業種別には,居酒屋で4件(7.3%),居酒屋以外で93件(32.1%)であった。受動喫煙対策を実施した理由は,「客の要望・苦情」と「経営方針」が39件(41.5%)ずつであった。対策が実施できない理由として,居酒屋では「スペース確保が困難」の22件(43.1%),居酒屋以外では「顧客を失うことが心配」の91件(40.1%)が最も多かった。最も来客が多くなると責任者が予想した受動喫煙対策状況は,居酒屋が「全面喫煙可能」の30件(58.8%),居酒屋以外では「分からない」の89件(33.3%)との回答が多かった。対策を実施した方が来客が多いと予想している店で,受動喫煙対策実施割合が高かった。健康増進法による飲食店の受動喫煙防止義務については,「具体的には知らない」を含めると,240件(75.5%)の責任者が「知らない」と答えた。また,責任者が喫煙者の場合や,健康増進法の規定を知らない場合に,受動喫煙防止対策を実施している割合が低い結果であった。
結論 分煙や禁煙など何らかの受動喫煙対策を実施していた店舗は全体の97件(28.1%)であった。健康増進法第25条の規定を知らない,もしくは具体的に知らない責任者は全体の240件(75.5%)であった。責任者が健康増進法の規定を知っていると,受動喫煙対策を実施している割合が高かった。
キーワード 受動喫煙,飲食店,健康増進法,分煙,静岡県浜松市
|
第57巻第3号 2010年3月 都道府県別合計特殊出生率,ボランティア活動行動者率,
|
目的 都道府県別合計特殊出生率,ボランティア活動行動者率,各種ファシリティ数の関連性を検討し,少子化対策に配慮したまちづくりのあり方を検討した。
方法 政府統計資料の中から,合計特殊出生率(2006年),ボランティア活動行動者率(2006年),各種ファシリティ(1999~2001年)の計28指標を収集した。ファシリティ指標はすべて都道府県別15~49歳女性人口(2000年)1人当たり数に換算した値を使用した。ファシリティ指標を順位データに変換し,クラスター分析(Ward法)を行い共分散構造分析に用いる潜在変数を検討した。その後,相関分析,共分散構造分析により探索的にモデル化を行った。地域特性の違いの程度を確認するためにそれぞれのファシリティ指標のジニ係数を求めた。
結果 クラスター分析により,ファシリティを「公園」「商業」「医療」「生活」「衛生」「教養娯楽」の6種に分類した。共分散構造分析により,合計特殊出生率にはボランティア活動行動者率,「衛生」「生活」の3変数が正の影響を及ぼし,「教養娯楽」はボランティア活動行動者率を介し,「医療」は「衛生」を介し間接的に合計特殊出生率に影響を及ぼすという因果構造モデルが得られた。
結論 いくつかのファシリティが合計特殊出生率とボランティア活動行動者率に影響を与えている可能性が示された。本研究では,合計特殊出生率を高めるための都市計画や都市開発を視野に入れた健康なまちづくりを意識し,その一助となり得るモデルが得られたと考えている。衛生従事者の活動を通じて,「教養娯楽」「衛生」「生活」「医療」の各種ファシリティ関係者や都市計画関係者との連携を想定した少子化対策が行われることに今後期待したい。
キーワード 都道府県別,合計特殊出生率,ボランティア活動行動者率,ファシリティ,地域格差,まちづくり
|
第57巻第3号 2010年3月 在宅医療に必要な通信機能のついた医療機器に関するインターネット調査川上 ちひろ(カワカミ チヒロ) 市川 靖史(イチカワ ヤスシ) |
目的 高齢化が進んでいるわが国では,今後死亡者数が増加することが予想されている。このため,在宅医療の需要も高まると考えられるが,在宅医療は24時間対応や緊急時の往診など医療者側の負担も大きく人材確保が課題である。通信機能のついた医療機器等(デバイス)を有効に利用することで在宅医療での医師の負担軽減につながるのではないかと考え,そのために必要なデバイスとは何かを検討するために,アンケート調査を実施した。
方法 2009年1月にインターネットを通じ,医師の基本属性やIT化への取り組み,在宅医療に有効と思われる27項目のデバイスに対する評価などを調査した。
結果 305名の医師から回答を得た。回答者の平均年齢は49.5±8.2歳であり,性別では281名(92%)が男性であった。IT化を行っていると回答したのは16名(5%)だったが,電子カルテの導入がほとんどであった。IT化の費用負担は公的負担が必要であるとの意見が多かった。血圧,体温,血液内酸素濃度,意識レベルの確認などが在宅医療に有効なデバイスとしてあげられたが,IT化は患者管理には有効でも医師の負担軽減にはつながらないという意見が多かった。
結論 バイタルサインとしてのデバイスのみでなく,Quality of Lifeにかかわるデバイスも在宅医療には重要であり,これらの装置の開発も行っていく必要がある。また,IT化することで医師の負担が軽減されるような通信用デバイスとは何かを検討する必要がある。 地域医療の連携やセキュリティーなども重要な課題である。
キーワード インターネット調査,在宅医療,通信機能付き医療機器
|
第57巻第3号 2010年3月 保健所保健師に求められる筋萎縮性側索硬化症患者への
|
目的 わが国の難病対策において,保健所は在宅で療養する難病患者の医療の確保や療養支援等を行っている。その中でも,筋萎縮性側索硬化症(以下,ALS)患者への支援の充実が求められていることから,保健師によるALS患者への支援の現状を明らかにし,今後の支援のあり方を検討した。
方法 近畿,中国,四国地方の保健所280施設に勤務する難病事業主担当保健師280人を対象に郵送による自記式アンケート調査を実施し,回答が有効であった123人(有効回答率43.9%)を分析対象とした。調査項目は,保健所の背景,保健師の特性,ALS患者のQOLを高める保健師の支援内容,支援困難なALS患者の状況等の6項目である。概念枠組みから,患者のQOLを高める支援を,精神的な支援,コミュニケーション手段の確保,同疾患患者との出会いの場の提供,外出の機会の確保への支援とし,それらの支援の実施と,保健師の経験年数,在宅療養中のALS患者支援数との関連について統計的検討を加えた。
結果 保健所の難病事業主担当保健師は,保健師としての経験年数の長短に関わらず,気管切開による人工呼吸器を装着しているALS患者の支援経験が少なかった。保健師が支援困難と感じているALS患者と初めて関わった時期は,確定診断後1カ月以内が最も多く,介護者の休息を目的としたレスパイト入院病床の確保や専門医の確保等が困難と感じていた。QOLを高める支援のうち,精神的な支援,コミュニケーション手段の確保,外出の機会の確保は,在宅療養中のALS患者支援数の多い保健師の方が少ない保健師よりも有意に多く行っており,また,保健師の経験年数に対して在宅療養中のALS患者支援数の多い保健師は,少ない保健師よりも有意に多くQOLを高める支援を実施していた。
結論 保健師はALS患者の発病初期から療養生活支援に関わっており,患者・家族の疾病受容や円滑なサービス導入のための支援に大きな役割を果たすことが示唆された。また,ALS患者のQOLを高める支援をより多く行うためには,保健師の経験だけではなく,実際にALS患者を支援する経験を積み重ねる必要があることが明らかになった。しかし,実際にはALS患者の支援経験が少ないため,今後はALS患者の支援経験を保健師が積み重ねることのできる体制の構築が必要である。
キーワード 保健所保健師,難病対策,患者支援,在宅療養,QOL
|
第57巻第4号 2010年4月 日本の出生体重低下に関する統計的研究-世界58カ国における日本の状況-阿部 範子(アベ ノリコ) 孫 超(ソン チョウ) 島田 友子(シマダ トモコ)緒方 昭(オガタ アキラ) |
目的 日本の出生体重平均値は,1975年以降低下を続け,低出生体重児割合は増加しつつある。 その原因を探るに当たって,この様な現象が,日本のみに観察されるものか否かを明らかにする事を目的とした。
方法 世界人口年鑑1986,1999年版(国際連合発行)を資料として,1998年前後における出生体重平均値と低出生体重児割合が算出可能な58カ国を観察対象国とし,出生体重平均値,低出生体重児割合,妊娠期間平均値,母の年齢平均値,複産率,出生性比を検討指標とした。観察対象国の最近年値について,平均値,%,比を算出し,それぞれの度数分布を作成し,分布内における日本の位置をz値(標準評価値)で示す。次いで1977年から1998年に至る間の資料より,各検討指標の年間変動量を求め,その分布内における日本の位置をz値で評価する。
結果 各検討指標の最近年値の分布における日本の位置:出生体重平均値はz=-1.56と分布の低位置にあるが,低出生体重児割合並びに他の検討指標は,分布の平均値付近に位置する。年間変動量分布における日本の位置:出生体重平均値はz=-1.80と低位置を占め,低出生体重児割合はz=+1.27と高位置に存在するが, 他の検討指標は分布の平均値付近に位置する。
結論 1998年における日本の出生体重平均値は観察対象国中低位置にあり,タイ,フィリピン,スロバキアと共に低出生体重児割合が多い。しかし,出生体重の分布範囲(標準偏差)が他国より狭いために,上記3カ国より低出生体重児割合は少ない。また,年間変動量の観察から,日本の出生体重平均値の低下速度,および低出生体重児割合の増加速度は,観察対象国中速い。なお,出生体重への影響要因と考えられる妊娠期間,母の年齢,複産割合,出生性比は,観察対象国の中で平均的な推移を示している。日本の出生体重平均値の低下,低出生体重割合の上昇の状況は特異的で,しかも,妊娠期間,母の年齢,複産割合,出生性比は,その変動要因とは考えられず,日本のみに存在する特有の要因によるものと推測する。
キーワード 出生体重,低出生体重児割合,複産児割合,世界人口年鑑
|
第57巻第4号 2010年4月 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からみた
菅村 佳美(スガムラ ヨシミ) 鳴釜 千津子(ナルカマ チヅコ) 庄司 和義(ショウジ カズヨシ) |
目的 本研究では,地域包括支援センターの役割とサービス担当者会議の運営方法について,居宅介護支援事業所を対象としたアンケート調査に基づき,問題点と解決策を検討した。
方法 アンケートの実施時期は2006年11月9日~11月30日,対象地域は1県4市の合計5カ所である。また,対象者は居宅介護支援事業所の介護支援専門員である。1,487人の回答に基づき,「主任介護支援専門員の業務達成度」「ケアマネジメント業務上での相談相手」「サービス担当者会議に参加すべき人とその開催に関わるべき団体」「サービス担当者会議開催時の地域包括支援センターのサポート体制」および「地域包括支援センターへの期待・要望」について,集計・分析を行った。
結果 介護支援専門員による,地域包括支援センターの主任介護支援専門員の役割に対する評価において,多職種協働・連携による長期継続ケアマネジメントの支援については評価が低かった。ケアマネジメント業務を進める上の相談相手としては,職場の上司・同僚(78.5%)サービス事業者(77.1%),についで,地域包括支援センターの職員(47.9%)であった。サービス担当者会議の運営に関しては,地域包括支援センター職員の会議への毎回参加は期待されていない。その一方で,会議開催の旗振り役への期待が57.2%と高率であった。また,サービス担当者会議開催への地域包括支援センターのサポートに,満足している人の割合は,22.4%にとどまった。「大変満足している」人43名と,「まったく満足していない」人182名を対象に,フリーコメントを集計したところ,「地域包括支援センターの職員の経験,専門性,資質の不足」「介護予防ケアプラン作成などの業務量が多く多忙」「居宅介護支援事業所と地域包括支援センターとの連携上の問題」などが挙げられた。
結論 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からみた地域包括支援センターには,解決すべきいくつかの課題が残されていることがわかった。特に,主任介護支援専門員は指導,助言,相談の役割を求められているが,それらについての介護支援専門員による評価は必ずしも高くはない。また,サービス担当者会議の運営に関して,地域包括支援センターの間接的なサポートの方法にも課題が残されている。これらの解決方法として,地域包括支援センターの組織の改変や職員のキャリアアップ体制の整備が必要と考える。
キーワード 地域包括支援センター,介護保険法,介護支援専門員,主任介護支援専門員,サービス担当者会議,ケアマネジメント支援
|
第57巻第4号 2010年4月 在宅外傷性脳損傷患者の
鈴木 雄介(スズキ ユウスケ) 種村 留美(タネムラ ルミ) 元村 直靖(モトムラ ナオヤス) |
目的 在宅外傷性脳損傷患者および介護者の特性,介護者の精神的健康度などを明らかにし,介護者の精神的健康度を維持,増進していくための支援のあり方を検討することを目的とする。
方法 近畿圏を中心とする脳損傷患者家族会に所属する介護者に自記式調査票を郵送した。調査項目は患者に関しては特性,日常生活動作能力,高次脳機能障害の症状,介護者に関しては特性,精神的健康度とした。分析は外傷性脳損傷患者と介護者に関する調査項目の各状態が,介護者の精神的健康度に与えている影響についての解析を行った。調査期間は2008年1月13日~2月29日で62名を対象とした。
結果 患者は男49名,女13名,平均年齢は37.3±11.9歳であった。介護者は男3名,女59名,続柄は母親が43名で最も多かった。GHQ-30平均は14.8±7.6点で,精神的不健康とされる介護者は47名(75.8%)であった。介護者の精神的健康度に与えている影響について解析を行った結果,介護期間と介護者の睡眠時間が短いほど介護者の精神的健康度が悪化することが明らかとなった。患者の日常生活動作能力との関連では,整容と更衣に介助を要するほど精神的健康度が悪化していた。また,患者の高次脳機能障害の症状との関連では,遂行機能障害と社会的行動障害の症状を有するほど精神的健康度が悪化していた。
結論 外傷性脳損傷患者の介護者の精神的健康度に影響を与える要因を明らかにした。介護者に必要な支援は,外傷性脳損傷患者と介護者のコミュニケーションの特徴を捉え,双方にとってストレスを引き起こさないための関係の再構築,身だしなみやTPOに合わせ適切な衣服を着るなど,他者との関わりに影響を及ぼす日常生活動作の介助方法の指導,介護生活を維持していくための体調管理への支援である。また,これらの援助は患者が高次脳機能障害を呈し,介護生活が始まる初期段階からの援助が重要であることが示唆された。
キーワード 外傷性脳損傷,高次脳機能障害,介護者,精神的健康度
|
第57巻第4号 2010年4月 要介護認定者数に基づく平均自立期間の小地域への適用加藤 昌弘(カトウ マサヒロ) 世古 留美(セコ ) 川戸 美由紀(ルミ カワド)橋本 修二(ミユキ ハシモト) 林 正幸(シュウジ ハヤシ) 渡辺 晃紀(マサユキ ワタナベ) 野田 龍也(テルキ ノダ) 尾島 俊之(タツヤ オジマ) 辻 一郎(トシユキ ツジ) |
目的 健康増進計画の目標評価項目の1つに挙げられている65歳平均自立期間について,愛知県の国民健康保険各保険者において算定を行い,そのばらつきと人口規模との関係,利用する死亡資料の期間の違いについて検討を行った。
方法 愛知県の国民健康保険団体連合会を構成する58保険者(32市,25町村および1事務組合)を対象として,対象地域の人口,死亡者数および介護保険法に基づく要介護度Ⅱ~Ⅴの認定者数を用いて,2005年の保険者別,男女別の65歳平均自立期間とその95%信頼区間を算定した。ただし,算定にあたっては,人口および死亡者数を2005年の1年間(以下,1年間)利用したものと2004~2006年の3年間(以下,3年間)利用の2通り行った。
結果 資料を1年間利用した場合の2005年の65歳平均自立期間推定値の平均値は,男16.91±1.08年,女20.03±1.02年であり,男女とも対象の人口規模に応じかなりのばらつきが認められた。1年間利用と3年間利用した場合の比較では,男女とも各推定値のばらつきは3年間利用の方が小さかった。また,1年間利用と3年間利用した場合の各推計値は,男女とも正の相関を示し,相関係数は男が0.78,女が0.84であった。死亡資料を1年間利用した場合における平均自立期間の各推定値の95%信頼区間の幅は,一定条件下で1年間の死亡資料に基づき人口規模に応じて試算をした95%信頼区間の幅に,男女ともほぼ一致をした。このことから,平均自立期間の推定値のばらつきの大よその大きさは,全国資料に基づく試算値で見積もることが可能であることが示唆された。
結論 要介護認定者数に基づく平均自立期間は,人口規模の小さい地域での適用が可能であり有用であると考えられた。ただし,人口規模が小さい地域においては,3年間の人口および死亡者数を利用することや,平均自立期間の推定値に併せて,その95%信頼区間を明示することが望ましいと考えられた。
キーワード 健康寿命,平均自立期間,介護保険,要介護,保健指標
|
第57巻第4号 2010年4月 睡眠医療専門機関受診者における
櫻井 進(サクライ ススム) 大平 哲也(オオヒラ テツヤ) 前田 均(マエダ ヒトシ) |
目的 睡眠呼吸障害(SDB)は循環器系疾患の危険因子であるばかりでなく,睡眠の量・質の低下による日中の眠気・集中力低下,それに起因すると考えられる高い自動車事故率,労働災害率が示されており,職業運転者の居眠り運転を含め社会的な問題になりつつある。本研究では,主に運転業務中の居眠りおよび交通事故等の頻度を調べ,体格指数(BMI),SDBの程度等との関連を検討した。
方法 睡眠医療専門機関にSDBを主訴に受診した者を対象とし,文書によるインフォームドコンセントのもとに質問紙調査を行い,398名を最終対象者とした。Epworth Sleepiness Scale(ESS),および終夜睡眠ポリソムノグラフィ検査を実施し,覚醒指数(ARI),および無呼吸低呼吸指数(AHI)を算出した。一部の対象者には,持続陽圧換気療法(CPAP)による症状の改善状況を調査した。さらに,重大事故群,重大事故予備群,居眠り群,眠気群,眠気なし群に分類し各医療機関別の頻度,職種,および業務と眠気・事故の頻度との関連を検討した。
結果 対象者の半数以上で,業務中に「頻繁に」または「ときどき」眠気を感じていた。運転中に居眠りをした人は約35%,居眠りによる事故経験者は約15%であった。運送業務・営業職において運転中の事故率が高い傾向がみられた。交代制勤務者で業務中に眠気を頻繁に感じる者は通常勤務者の約2倍であった。AHI値で3区分した場合,交代制勤務者はどの区分においても通常勤務者より,頻繁な眠気を訴える割合が多かった。通常勤務者ではAHIが高くなるにしたがって,業務中の眠気を訴える頻度が多くなったが,交代制勤務者では業務中,運転中にかかわらずAHIと眠気との関連はみられなかった。肥満,重度無呼吸および日中の眠気が強い,をすべて満足する群とひとつもあてはまらない群を比較したところ,重大事故発生比は11.4倍であった。運転業務従事者の中では,BMI値が大きいほど,また,ESSスコアが高いほど重大事故を起こす危険性が高くなっていた。CPAP治療実施中で回答があった方の約6割は治療の効果を実感していた。
結論 SDBを主訴に受診した対象者の多くが業務中の眠気を感じ居眠り事故率も高く対策が求められる。肥満防止・睡眠呼吸障害治療が重大交通事故発生減少に効果があることが示唆された。
キーワード 睡眠時無呼吸症候群,睡眠呼吸障害,パルスオキシメトリ法,スクリーニング検査,交通事故,産業災害
|
第57巻第4号 2010年4月 利用者のQOLの変化からみたケアマネジメントの効果林 暁淵(イム ヒョヨン) 綾部 貴子(アヤベ タカコ) 岡本 秀明(オカモト ヒデアキ)所 道彦(トコロ ミチヒコ) 白澤 政和(シラサワ マサカズ) |
目的 介護保険サービスの新規利用者の生活の質(QOL)が,介護支援専門員によるケアマネジメント実施前と比較して,実施6カ月後にどのように変化しているのかを調査し,ケアマネジメント実施の効果を明らかにすることを目的とする。
方法 近畿地方の4府県の介護支援専門員協会・協議会の会員で,かつ居宅介護支援事業者にて従事する介護支援専門員が担当することになった新規の利用者本人を対象とし,介護支援専門員が利用者本人に尋ねて記入するという他記式調査を行った。調査期間は,初回調査が平成16年8~10月,2回目調査が平成17年2~4月であり,それぞれの対象者が初回調査に回答した日から6カ月後に2回目調査を設定した。有効回収数は,初回調査が158人,2回目調査が120人であり,分析対象者は双方の調査において要介護度の記載も含めて回答があり,かつ自分自身のことについて意思表現に困難のない利用者91人とした。利用者のQOLをみるために,主観的健康度,睡眠,食事,家事,経済的安定感,対人関係,住環境,抑うつ,自己決定,生きがい感,生活満足度という11のQOL領域,計23の調査項目を用意した。
結果 利用者のQOL各領域の得点の6カ月後における変化を対応のあるt検定により検討した結果,初回調査時の各領域の得点の平均値を基準とした「低位群」の場合は,ほとんどの領域において肯定的な変化がみられた。一方で,初回調査時の各領域の得点の平均値を基準とした「高位群」の場合は,肯定的な変化はみられず,ほとんどの領域において低下していた。
結論 ケアマネジメントの目的である生活の質の向上に関して,ケアマネジメントによる効果は,当初のQOL領域の得点が低いレベルの場合にはその効果が比較的高いが,当初のQOL領域の得点が高い場合においては,生活の質の向上や維持に不十分であることが考えられた。ケアマネジメントを実施する介護支援専門員は,特に新規利用者のうち身体機能面・社会環境面,精神心理面の生活の質が比較的良好な利用者に対し,これらの状態が低下しないように努めることや,生活の質が部分的に低下しないように利用者の生活の質を総合的に注視することが求められる。
キーワード ケアマネジメント,介護支援専門員(ケアマネジャー),高齢者,生活の質
|
第57巻第5号 2010年5月 首都圏内在住中年成人における腹囲測定に基づく
古畑 公(フルハタ タダシ) 橋詰 直孝(ハシヅメ ナオタカ) 高橋 佳子(タカハシ ヨシコ) |
目的 内臓脂肪型肥満は,うつをはじめとした心理学的・精神医学的状態と関連があると言われている。両者はともに現代社会の象徴する健康問題であり,その関連について評価する意義は高い。本研究では首都圏内の一般成人を対象とした健診データを用いて,腹囲測定に基づいた内臓脂肪型肥満と軽症うつとの関連について検討した。
方法 首都圏内のI市における成人病基本健康診査受診者のうち,40歳から59歳までの4,039名を対象にアンケートを送付した。軽症うつについては,潜在性微量栄養素欠乏発見システムに含まれる体調・不定愁訴問診表セットを用いた。男性は腹囲85㎝以上,女性は腹囲90㎝以上を内臓脂肪型肥満ありとした。
結果 返答されたアンケート(2,164枚)のうち分析項目においてデータに欠損のある者を除いた1,831名(男性388名,女性1,443名)を分析対象とした。女性の内臓脂肪型肥満に軽症うつが有意に多くみられた(オッズ比3.4,P<0.05)。食事非適量を調整したオッズ比は1.6と減少し,統計学的有意性も消失していた。多重ロジスティック回帰モデルでは,男女とも内臓脂肪型肥満は有意な関連を示さなかった。
結論 女性の内臓脂肪型肥満により軽症うつが高い関連が2変数間ではみられたが,食生活,特に食事非適量による交絡が示唆された。食事を適量に保つことを中心とした食生活指導により,腹囲とうつ症状が改善する可能性について,今後も検討を重ねる意義が示された。
キーワード メタボリックシンドローム,腹囲,軽症うつ,中年成人
|
第57巻第5号 2010年5月 愛知県における若年認知症の就業,日常生活動作および介護保険利用状況小長谷 陽子(コナガヤ ヨウコ) 渡邉 智之(ワタナベ トモユキ) |
目的 若年認知症の生活の実態を明らかにするため,愛知県において,医療機関,介護福祉施設,行政関係機関を網羅した調査を行った。
方法 愛知県内の医療機関,介護福祉施設,行政関係機関等に対し,2段階によるアンケート調査を行った。1次調査で若年認知症ありとした施設や機関に,本人の属性,認知症の原因疾患,合併症,家族歴,既往歴,認知症の程度,就労状況,日常生活動作(ADL)能力,認知症の行動と心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: BPSD)の有無と内容,介護認定状況,サービス利用状況,障害者手帳・年金受給状況および現在の問題点などからなる調査票を送り回収した。
結果 調査時点で65歳以上の人を含めて,2次調査で重複を調整した後の総数は1,092人で,男性569人(52.1%),女性520人(47.6%),性別無回答3人であった。ADLのうち歩行と食事に関しては,それぞれ全体の42.9%,46.2%と約半数が自立していた。しかし,排泄(30.6%),入浴(20.2%),着脱衣(24.2%)の自立度はこれより低く,日常生活に何らかの介助が必要な人が多かった。就労や社会福祉制度の利用率は必ずしも高くなかった。
結論 若年認知症者の生活は,ADLや介護福祉サービスの利用状況などからは生活が厳しい現状であることが明らかとなった。介護保険の認定は40歳以上の約80%が受けているが,サービスは十分には利用されていない。社会福祉制度の周知や利用の促進を含め,若年認知症に対応する医療・介護福祉関係者や行政担当者の理解が不可欠である。
キーワード 若年認知症,生活実態調査,愛知県,就労状況,ADL,介護保険サービス
|
第57巻第5号 2010年5月 マネジメントサイクルに基づく
近藤 今子(コンドウ イマコ) 酒井 映子(サカイ エイコ) 尾島 俊之(オジマ トシユキ) |
目的 今日,重要性が一層高まっている市町村公衆栄養活動がマネジメントサイクルに基づき実施されるために,先行調査で鍵を握ることが示唆された目標設定の状況および関連要因を明らかにし,目標設定の方法を検討することを目的とした。
方法 愛知,岡山,静岡県の政令市を除く市町村の行政栄養士147人に対し平成19年11,12月に郵送により自記式無記名でアンケート調査を行い,113人(回収率76.9%)から得た回答を分析した。調査内容は目標設定の状況,目標設定への指示,実態把握,相談機関,研修,評価に関する項目である。項目間の検討にはピアソンのχ2検定,さらに有意の項目にスピアマンの順位相関を用いた。p<0.05を有意とした。
結果 目標設定の状況は,3県間に差はなく,「ほとんど設定」と「設定のほうが多い」で46.4%,設定の必要性は75.7%が有るとしていた。評価は「ほとんど実施」と「実施のほうが多い」で53.2%であった。目標の設定と評価の実施は有意に関係していた。実態把握に関して,情報の活用は市町村独自で実施する調査等の労力を要するもので低く,プリシード・プロシードモデルに対応する各項目の把握は行動とライフスタイル,環境,準備・強化・実現因子で低かった。いずれも,目標設定をしているほうが良好であった。目標設定は,良い経験の有無,組織内の目標設定の指示の有無,指示がある場合の目標設定の意識,評価の実施,目標設定の必要性の意識,研修の活用,目標の設定方法が分からないとの間に有意な関連を認めた。また,指示がある場合の目標設定の意識は,良い経験の有無,評価の実施,目標設定の必要性の意識,組織内の目標設定の指示の有無との間に,さらに,目標設定の必要性の意識は,良い経験の有無,困った経験の有無,研修の受講との間に有意な関連を認めた。目標設定に関する研修は49.6%が受け,研修を活用できたとする約6割の目標設定は良好であった。
結論 目標設定の関連要因は,「組織の指示と指示への対応」「目標設定にかかる経験」「専門能力」「資質向上のための支援」に大別できた。指示は目標設定を促し,目標設定による良い経験が,より積極的な目標設定につながると推察される。さらに,目標設定に必要なスキルを確保できる研修や支援が目標設定の実現には必要である。
キーワード マネジメントサイクル,市町村公衆栄養活動,目標設定,評価,指示,専門能力
|
第57巻第5号 2010年5月 介護労働者の介護態度自己評価に関連する要因谷垣 靜子(タニガキ シズコ) 岸田 研作(キシダ ケンサク) |
目的 介護労働現場における介護態度に注目をし,介護労働者の介護態度自己評価に関連する要因を明らかにすることである。
対象と方法 対象は,A団体に加盟する66の特別養護老人ホームに勤務する正規職員または非常勤フルタイムの介護職員1,570名である。調査は,職員を対象とした郵送自記式で実施した。介護態度自己評価を従属変数とし,年齢,性別,雇用形態,資格,勤務時間,施設管理者のリーダーシップ,職場の人間関係,性格等を独立変数とする重回帰分析を行った。
結果 分析対象者の平均年齢±標準偏差は,35.9±11.9歳であった。性別では,対象者の77.1%が女性であった。正規職員は,75.4%であった。介護態度の自己評価得点の平均値±標準偏差は,17.9±3.0点であった。施設管理者のリーダーシップ得点の平均値±標準偏差は,22.6±5.5であった。属性等による介護態度評価得点の比較では,「雇用形態」「シフト希望」「相談者の有無」「性格」で平均値の差があり,「仕事満足度」「利用者の立場にたつ」「職場の人間関係」「仕事継続意思」で傾向性の検定における順位相関が有意であった。重回帰分析の結果では,介護態度評価得点に影響する要因は,「年齢」「利用者の立場にたつ」「穏やかな性格」「仕事継続意思」「仕事満足度」であった。
結論 今回の調査によって,介護労働者の自己介護態度評価は,介護労働の環境よりも,介護の仕事に対する姿勢や介護に対する肯定観などが関連した。こうした影響要因が,質の高い介護実践に結びついたものであるかどうか,今後検討を要するところである。
キーワード 介護労働者,介護態度,評価,特別養護老人ホーム
|
第57巻第5号 2010年5月 基本健診項目からみた死亡に対する集団寄与危険割合
朝倉 幸代(アサクラ ユキヨ) 島崎 忠美(シマザキ マミ) 柳瀬 香織(ヤナセ カオリ) |
目的 富山市全体の健康状況の把握を健康指標である死亡から捉えることとし,市全体の死亡に影響する要因を明らかにするため,性・年齢階級別集団寄与危険割合を算出した。また,この分析で示された結果とこれまで市で実施してきた保健事業の内容と整合しているかどうかを確認し,今後も同様に保健対策を継続していくことが必要かどうか脳卒中対策事業の基礎情報として検討した。
方法 平成12年度健診受診者のうち40~84歳までの38,112人(男性11,357人,女性26,755人)を対象とした。この中から健診結果を有し,平成12年4月1日~平成17年11月末日までに発生した病死2,164人(男性1,276人,女性888人),生存35,882人(男性10,041人,女性25,841人)を分析対象とした。血圧は区分値を設定し5カテゴリーに分けた。HbA1cは5%ごとに5カテゴリー,HDLコレステロール(以下,HDL)は10㎎/dlごとに5カテゴリーに分けた。各健診項目の死亡に関わるリスク比は,それぞれ年齢4群で性別にCoxの比例ハザードモデルにてハザード比を算出した。各健診項目における性別,年齢階級別の各カテゴリー別構成割合を平成19年9月末日の富山市の40~84歳の人口での推計人口を算出した。次に,この推計人口に死亡のリスク比を乗じ,年齢階級ごとのカテゴリー別に推計死亡数を算出し,年齢階級別集団寄与危険割合を算出し,かつ各カテゴリー別にその構成値を示した。
結果 血圧では,男性の40~54歳,55~64歳の壮年期で集団寄与危険割合はそれぞれ6.5%,13.5%,女性の壮年期,前期高齢者では4.1%,9.9%,11.9%と高値を示した。HbA1cでは,男性の55~64歳を除くすべての性・年齢階級で高い集団寄与危険割合を示し,その値は10~16%であった。しかし(4.9%以下)の構成値も計で男性4.3%,女性5.5%と正の値を示した。HDLでは,男性の64歳以下を除くすべての性・年齢階級で高い集団寄与危険割合を示し,その値は7~39%であった。
結論 市全体の死亡を減らすという新たな視点で保健対策について検討した結果,男性の壮年期,女性の壮年期および前期高齢者の高血圧対策,HbA1c高値,HDLコレステロール低値への対策が有効であることが示された。今後も長期的に情報を集約,分析し,市民の健康状態を把握するとともに保健施策の成果を適切に評価し,効果的な保健事業の実施へつなげていくことが重要であると考えられる。
キーワード 健康指標,集団寄与危険割合,保健対策
|
第57巻第7号 2010年7月 定年退職を控えた地方公務員における職業性ストレス,
宇佐見 和哉(ウサミ カズヤ) 笹原 信一朗(ササハラ シンイチロウ) 吉野 聡(ヨシノ サトシ) |
目的 平成19年以降いわゆる団塊世代が大量に定年退職を迎えるなど社会的にも注目されている。定年退職は老年期における重要なライフイベントとして以前から知られるが,この時期の労働者の職業性ストレスを検討した研究はほとんど認められない。今回,定年退職を直前に控える地方公務員の職業性ストレスとストレス対処能力の特性と精神的健康度との関連について検証し,定年退職を直前に控える労働者の職業性ストレスモデルを明らかにし,職場におけるメンタルへルス対策に資することを本研究の目的とした。
方法 某地方自治体に勤務する公務員のうち,平成21年3月に定年退職する者に対し実施された,定年退職者セミナーに参加した職員1,351名を対象とした。調査方法は,平成20年10月に実施された定年退職者セミナー内において,研究実施担当者が本調査に関する趣旨説明を行った後,記名自記式質問紙を配布,後日郵送にて回収した。調査項目には年齢,性別などの基本属性のほか,職業性ストレスの指標として職業性ストレス簡易調査票(BSJS: Brief Scales for Job Stress),ストレス対処能力の指標として首尾一貫感覚(SOC: Sense of Coherence)29項目版,そして精神的健康度の指標としてSDS(Self-Rating Depression Scale)をそれぞれ用いた。
結果 回収数は713名(回収率52.8%)で,質問項目に欠損値のない552名を解析対象とした。性別は男性447名(81.0%),女性105名(19.0%)であった。SOC平均得点は132.8±18.8点で,SDS平均得点は29.3±7.2点であった。SDS得点を目的変数,SOC得点およびBSJS下位項目得点を独立変数とした重回帰分析を行ったところSDS得点にはSOCが非常に強い影響を与え,また職業性ストレスのうち「質的負荷」が強く影響していることが明らかになった。
結論 定年退職を控える労働者においては,ストレス対処能力は高く,職業性ストレスは軽度であり精神的健康が良好に保たれていることがわかった。また職業性ストレスのうち,「質的負荷」の急激な増大が精神的健康度の悪化に影響する可能性が示唆された。
キーワード 定年退職,首尾一貫感覚(SOC),ストレス対処能力,精神的健康度,職業性ストレス
|
第57巻第7号 2010年7月 日本の高齢女性における死因構造の推移(1955~2005年)-前期高齢者と後期高齢者の死亡率・死亡割合の推移-吉永 一彦(ヨシナガ カズヒコ) 畝 博(ウネ ヒロシ) |
目的 近年,日本人の死亡率は,生活環境の改善,医薬品・医療技術の開発,生活水準の向上などを背景に著しく低下し,高齢者についても同様であるが,75歳を境とする前期高齢者と後期高齢者においては,その死因構造と推移に相違がうかがえ,50歳以上の高齢者について1955年以降の主要死因の経年推移を分析する。
方法 1955~2005年における50~99歳の主要死因の死亡率と死亡割合について経年推移を観察する。
結果 全死因の死亡率の著しい低下現象が,1955年以降60歳辺りから80歳辺りへ経年的に推移していた。死因別死亡率では胃腸炎,結核,高血圧性疾患,脳血管疾患が全高齢者で低下したが,悪性新生物と肺炎は前期高齢者では低下していたが,後期高齢者は逆に上昇していた。このうち前期高齢者での悪性新生物の低下はわずかであったが,肺炎の低下は大きい。また,自殺は65歳以下で女はほとんど変わらないが男は上昇していた。後期高齢者では男女ともに低下していた。死亡割合では胃腸炎,結核,高血圧性疾患が著しく減少し,1%にも満たなくなった。脳血管疾患は1955年では65~69歳をピークとし35%ほどを占めていたが前期高齢者で著しく減少し,10%程度となった。悪性新生物は全年齢で凸状に増大し,2005年ではピークは女で50~54歳で56%,男は65~69歳で46%を占めていた。肺炎は後期高齢者での上昇が大きく,95~99歳では20%と大きな割合を占めていた。全体的に,死亡割合では悪性新生物が全年齢で増加し,脳血管疾患は1975年までは大きな割合を占めていたがその後高齢へ移行しながら減少した。また心疾患,肺炎も後期高齢者で大きな割合を占めていた。
結論 高齢者の死亡率は経年とともに著しく低下しているが,その中でも前期高齢者における結核,脳血管疾患の低下が大きく,75歳付近における死亡率の変曲現象への影響が大きいと思われた。死因の年齢分布では前期高齢者と後期高齢者とがおおむね大別されるように思われる。すなわち,前期高齢者から後期高齢者の前半にかけては悪性新生物が大きな死亡割合を占め,後期高齢者では悪性新生物,心疾患,脳血管疾患,肺炎の死亡割合が大きく,その内,悪性新生物は前半で大きく,加齢とともに減少し,心疾患,脳血管疾患は近年では減少しつつもまだ大きな割合を占め,肺炎は経年的にも増加していた。
キーワード 死亡率曲線,変曲現象,死因構造,前期高齢者,後期高齢者
|
第57巻第7号 2010年7月 都市在宅高齢者に対する
星 旦二(ホシ タンジ) 栗盛 須雅子(クリモリ スガコ) 中山 直子(ナカヤマ ナオコ) |
方法 分析対象者は,都市郊外A市に居住する高齢者を調査対象にして2001年に自記式質問紙調査に回答した13,066人である。調査内容は,受療状況,社会ネットワーク,生活習慣,生活活動能力である。回答割合の関連要因と選択バイアスを分析する方法は,住民基本台帳人口と自治体報告要介護者数を基準とし,質問紙調査結果でみた性別年齢階級別回答者数と介護度別要介護者数とを比較して求めた。
結果 本調査結果により,回答割合を低下させる関連要因は,80歳以上であることと要介護度低下であり,要介護者をより少なく推定するという選択バイアスが存在する可能性が示された。
キーワード 自記式質問紙調査,回答割合,都市在宅高齢者,選択バイアス
|
第57巻第7号 2010年7月 特定健診データと医療費データからみる
満武 巨裕(ミツタケ ナオヒロ) 福田 敬(フクダ タカシ) 古井 祐司(フルイ ユウジ) |
目的 本研究は,2008年4月から医療保険者に実施が義務化された特定健診データと医療費(レセプト)データを用いて,特定保健指導対象者の実態を把握し,今後の医療保険者における対象者選定および予防施策のあり方の検討に資する情報を提示することが目的である。
方法 6つの保険者(健康保険組合および市町村の国民健康保険)から特定健診データ,医療費データを入手し,「標準的な健診・保健指導プログラム」に基づき階層化(「情報提供群」「動機付け支援群」「積極的支援群」)を行うことで特定保健指導対象者のステップごとの人数の推移を観察すると同時に,突合分析を行うことで医療費との関係を検討する。
結果 階層化の結果,特定保健指導の対象となる「積極的支援群」の割合は,健康保険組合の17.2%に対して国民健康保険では3.7%と少ない。医療費は,特定保健指導の対象外となっている「情報提供群」が大きな割合を占め,健康保険組合では約7割,国民健康保険では約9割であった。「情報提供群」の中でも「服薬中の者」の医療費が全保険者で共通して最も大きな割合を占めた。突合分析による1人当たり医療費および重回帰分析からも,「服薬中の者」の医療費が一番高額であった。
結論 服薬者の除外規定により,特に,国民健康保険では特定保健指導の対象者が大きく減少する。服薬により生活習慣病の悪化防止が期待できるが,必ずしも継続的な受診や自己管理が十分ではない患者が少なくないことが想定されることから,今後,服薬者でリスクを有したままの群がこれ以上重症化しないための予防プログラムの必要性が示唆された。
キーワード 特定健診,特定保健指導,突合分析,医療費,標準的な健診・保健指導プログラム
|
第57巻第5号 2010年5月 今後の国民生活基礎調査の在り方についての一考察(第2報)-「食生活改善行動の採用」尺度と行動変容モデルの予測-橋本 英樹(ハシモト ヒデキ) |
目的 国民生活基礎調査に平成19年調査より採用された心の健康指標(K6)の表章のあり方について検討を行う。また,自覚的健康状態の報告バイアスについて検証する。
方法 旧統計法のもとで平成19年国民生活基礎調査の世帯票・健康票・介護票・所得票・貯蓄票について,目的外利用申請を行いデータを入手した。K6については,先行研究にならいスコア化したうえで5点をカットオフとして心理的ストレスの有所見割合を年齢・性・各票項目とクロスさせて推計した。自覚的健康状態(5件法)を年齢・性・罹患疾患・日常生活影響・心理的ストレス有無・10地域ダミーでordered probit modelで回帰したのち,推計値を求めなおし,これを自覚的健康状態の回答結果と対比してバイアスの有無を検証した。
結果 心理的ストレスの有所見割合は,身体的健康や世帯構成,就労や所得・資産の保有状況など,個人を取り巻く様々な世帯面要因と関連が認められた。また,年齢層や性別によって,世帯面要因との関連は異なることが観察された。自覚的健康状態と推計された標準化健康指標との間には性差・地域差によるずれはみられなかったが,高年齢ほど推計値よりも低い健康状態を報告する傾向が明瞭にみられた。これは疾病や日常生活動作の障害などで表現される以外の,生理的加齢による影響を反映している可能性が考えられた。
結論 心理的ストレスは,ジェンダー役割やライフステージによってストレッサーが異なり,それに応じた評価分析や対応が必要であることが示唆された。そのためには年齢・性別に加えて,世帯票・介護票・所得票各票の項目とのクロス集計が必要であると考えられた。自覚的健康状態は,健康状態の客観的指標として年齢層ごとに地域比較や属性比較を行うには,十分機能していることが確認された。年齢による影響についてはさらなる検討が必要である。
キーワード 国民生活基礎調査,K6,表章のあり方,自覚的健康状態,報告バイアス
|
第57巻第6号 2010年6月 特別養護老人ホームを対象とした質問紙調査における依頼と回答の実態-アンケートがもたらす業務への支障-大西 次郎(オオニシ ジロウ) |
目的 質問紙調査(アンケート)は発信側にとって取り組みやすく,低コストで広範にデータを収集できる反面,十分に吟味されない調査が少なからず実施されることで,受信側にとって回答の作成・返送が重荷となる危険性をはらむ。他方,介護施設は高齢者の生活の場であるとともに,福祉の実践,社会保障政策の反映の場でもあり,複数の学術領域から関心を持たれている。とくに,最大数の定員を擁する特別養護老人ホーム(以下,特養)への調査は,その規模からアンケートの形をとりやすい。そこで特養を対象にしたアンケートの実態と,業務に与える影響を検証するため,あえて一片の質問紙調査を行った。
方法 兵庫県下の全特養(251施設)へ無記名,自記式の調査票を郵送し,記載を依頼した。休止1と移転1を除く249施設のうち,総回収数(率)は183施設(73.5%)であった。調査へ協力しない,ないし協力するが公表に同意しない意思を表明した23施設を除く160施設(64.3%)を総分析対象とした。調査期間は2008年10月から同年12月までである。
結果 2007年11月から2008年10月までの1年間で,中央値11~15件(最頻値6~10件)のアンケートの依頼があり,109施設でその半数以上へ返送(回答)を行っていた。ほとんど返送できないとした施設の数は7にとどまった。一方,154施設で返送に負担を感じており,123施設は業務に支障をきたす可能性があるとした。しかし,今後の対応は110施設において従来と同様か,それ以上に返送を続けると判断していた。
結論 アンケートに対する回答は,多くの特養において重荷となっている可能性がある。その上での返送には,施設の経営や職場環境の改善へ向けた願いがあり,発信側には質問量と内容を厳選し,かつ同種調査の重複を避けるといった受信側への配慮とともに,調査の社会的価値を高めていく努力が求められる。
キーワード 質問紙調査,アンケート,特別養護老人ホーム,介護福祉施設,調査技術
|
第57巻第6号 2010年6月 要介護認定を受けた認知症高齢者の日常生活自立度の変化と
鳶野 沙織(トビノ サオリ) 新鞍 真理子(ニイクラ マリコ) 下田 裕子(シモダ ユウコ) |
目的 認知症高齢者の日常生活自立度(以下,認知症自立度)の変化を明らかにすることを目的とした。さらに中核症状や周辺症状といった認知症関連症状項目についてもその変化を明らかにし,これらの症状と認知症高齢者が要介護認定を受けた場所や歩行能力との関連を検討した。
方法 T県X地区において2001年4月1日~2007年6月30日の期間に新規に要介護認定を受けた第1号被保険者のうち,認知症自立度ランクⅠ-Ⅲと判定された1,717人を対象とした。そして,要介護認定2回目更新時の認知症自立度が改善した者,維持した者,悪化した者の割合を算出した。次にランクⅠ-Ⅲ別の改善群・維持群・悪化群に分け,認知症関連症状項目ごとに初回と2回目更新時の有所見者の割合を算出し,その割合の差が大きかった関連症状項目を抽出した。さらに割合の差が大きかった関連症状項目のうち,初回認定調査実施場所が「自宅であった者における有所見者の割合」と「自宅外であった者における有所見者の割合」および「歩行可能であった者における有所見者の割合」と「歩行不可能であった者における有所見者の割合」を算出し,それぞれにおいてその割合の差を求めた。
結果 対象の60.7%が認知症自立度を維持し,12.0%が認知症自立度を改善させていた。中核症状やひどい物忘れの有所見者の割合は高く,また2回目更新時の改善や悪化における変化も大きかった。中核症状やひどい物忘れは,必ずしも認定調査実施場所が自宅や歩行可能な場合に有所見者割合が低いという事はなく,場所や歩行能力によって特定の方向性を示す事はなかった。
結論 認知症の中心となる中核症状であっても,大きく症状が改善したり悪化したりする可能性が示唆された。
キーワード 介護保険制度,認知症高齢者の日常生活自立度,認知症の症状
|
第57巻第6号 2010年6月 首都圏A市在宅高齢者の知的能動性と
|
目的 地域在宅高齢者の基礎調査時の知的能動性と5.9年間追跡した生存・死亡状況との関連から,認知症見逃し割合を明らかにすることとした。
方法 2001年9月に実施した65歳以上在宅高齢者全数対象の生活実態調査(回収割合80.2%)に基づき,13,058人を分析対象とし,家族が代理回答で「理解力なし(認知症あり)」を選択した場合を,家族が同居高齢者の認知症を認識している群(以下,家族認識認知症群),それ以外の群を「家族認識以外群」とした。2004年と2007年に生存死亡状況を調査し,12,143人について5.9年間追跡した。知的能動性活動として「預貯金の出し入れ・年金等の書類記入・新聞書物を読む」を用いて得点化し,ROC曲線(受診者動作特性曲線)により低得点群と高得点群に分割した。家族認識以外群をさらに低得点・高得点群に分け,家族認識認知症群と家族認識以外2群の死亡割合の関連から認知症見逃し割合を検討した。
結果 家族認識認知症群の低得点群は男性95.1%,女性96.2%,家族認識以外群の低得点群は男性6.3%,女性9.3%であった。5.9年間の累積死亡割合は,家族認識認知症群が56.7%(男性63.5%,女性54.0%),家族認識以外低得点群は49.4%(男性55.6%,女性45.6%),家族認識以外高得点群が11.6%(男性15.3%,女性8.1%)であった。5.9年間の死亡者の死亡時平均年齢は,家族認識認知症群が男性85.6歳,女性90.1歳,家族認識以外低得点群は男性84.8歳,女性90.2歳,家族認識以外高得点群では男性79.6歳,女性80.2歳であった。
結論 家族認識以外低得点群である男性6.3%,女性9.3%は,先行研究の結果と同様に,死亡割合が高く,死亡時平均年齢が家族認識認知症群とほぼ等しいことによって,認知機能低下があるにもかかわらずその症状が見過ごされている認知症見逃し割合に等しいことが示唆された。さらに,家族も本人も認知症と認識していない場合であっても,知的能動性を測定して低得点者を識別する意義が大きい可能性が示された。
キーワード 家族認識認知症群,知的能動性,家族認識以外低得点群,認知症見逃し割合,累積死亡割合,死亡時平均年齢
|
第57巻第6号 2010年6月 小規模地方自治体における医療費関連指標に関する地域診断と相関分析-総務省類型による町村Ⅰ-1を対象として-上岡 洋晴(カミオカ ヒロハル) 岡田 真平(オカダ シンペイ) 武藤 芳照(ムトウ ヨシテル)本多 卓也(ホンダ タクヤ) 森山 翔子(モリヤマ ショウコ) |
目的 本研究は,総務省が平成19(2007)年度に分類した小規模自治体を対象として,老人医療費,地域差指数,介護費,介護認定率,平均寿命についての地域診断を実施すること,介護費および老人医療費に関連する因子との相関を明らかにすることを目的とした。
方法 総務省はすべての地方自治体を人口と産業構造によって35分類しているが,このうち農山村が主に含まれる「町村Ⅰ-1(人口5,000人未満で,第2,3次産業従事者が80%以上,第3次産業従事者55%未満)」を対象とした。最新の平成19年度の分類では,32町村が該当した。医療関連,介護関連,健康関連の指標は,平成17(2005)年度分公開統計を利用した。具体的には,国民健康保険(国保)における老人(65歳以上)1人当たり医療費と地域差指数,65歳以上1人当たり介護費,人口(人口,世帯数),高齢化状況(高齢化率,高齢者に占める後期高齢者割合,生産人口比率,高齢単身・夫婦・同居の各世帯割合),産業構造(第1次・2次・3次の各産業従事者割合,人口に占める就業者割合,飲食店数),医療福祉サービス供給(人口対医療福祉業従事者数),介護依存実態(要介護認定率,介護費用に占める居宅介護費用割合),健康関連指標(平均寿命),人口対病院数・診療所数,人口対常勤保健師数であった。地域診断では,各町村における老人医療費,地域差指数,介護費,介護認定率,平均寿命の5項目を全国平均と比較してレーダーチャートで示した。その上で,老人医療費と介護費を目的変数とした重回帰分析を行った。
結果 地域診断では,神恵内村は介護費が安価だが老人医療費が高価な型であった。若桜町と球磨村は,介護費が高価だが老人医療費が安価な型であった。その他の町村は,5項目が安定あるいは良好な型であった。老人医療費と介護費の単相関係数は,r=-0.13で有意ではなかった。重回帰分析の結果,老人医療費との標準回帰係数の大きい順に相関の高かった因子は,1人当たり入院費,1人当たり入院外費であった。介護費では,世帯数,第2次産業比率であった。
結論 総務省類型の小規模自治体(町村I-1)においては,老人医療費と介護費との相関係数は低く,類似・相互補完関係など多様であった。小規模町村の評価には,保健・福祉事業の詳細を把握するような質的分析の必要性が示唆された。
キーワード 地方自治体,老人医療費,介護費,過疎,高齢化
|
第57巻第7号 2010年7月 市町村合併が保健(師)活動に及ぼした影響-人口規模別の比較検討-都筑 千景(ツヅキ チカゲ) 桝本 妙子(マスモト タエコ) 生田 惠子(イクタ ケイコ)平野 かよ子(ヒラノ カヨコ) 石川 貴美子(イシカワ キミコ) 烏帽子田 彰(エボシダ アキラ) |
目的 2006年11月,全自治体1,840市町村(特別区を除く)を対象に行った質問紙調査をもとに,合併を行った自治体について,合併が保健(師)活動に与えた影響を人口規模別に比較検討した。
方法 事前に電話で協力を依頼し,了解が得られた974市町村の保健活動の責任者(保健師)に,郵送で調査票を配布し,記名により郵送で回収した(回収率52.9%)。このうち平成元年以降に合併を実施した329市町村(調査時点での全国合併市町村の58.4%)を分析した。使用した項目は,市町村の概況,保健部門の組織基盤,保健師配置と確保状況,保健事業および保健師活動に関する項目である。
結果 合併後の旧保健センターの機能位置づけは,どの人口規模も「変化なし・対等」が一番多かった。「本所と分所」は人口規模が大きいほど多く,「1カ所に集約」は人口規模が小さいところが多かった。保健事業に関する権限は,どの人口規模も「所管課に集中化」「ほぼ集中」が多数で約80%を占めた。旧市町村の保健師配置は,3万人以上の市町村では「支所に配置」が62.8~78.4%,3万人未満では半数程度であった。旧市町村で展開していた質の高い事業は,1万人未満で「当該地域で継続」が一番多く,「全市町に拡大して実施」は1~3万人未満が50%と一番高かった。合併後の保健師の業務形態は,「地区分担制」5%,「業務分担制」9.5%,「地区分担・業務分担の併用」82.3%であり,1万人未満の市町村で「業務分担制」が23.1%と一番多かった。保健師の担当分野が「合併後に専門分化された」のは3~5万人未満で一番多く,「専門分化ではなく他領域を対象とする傾向」が1万人未満で一番多かった。
結論 多くの新市町で保健事業に関する権限は支所になく,保健師の配置も十分でない状況が明らかになり,広範囲の地域を対象とした住民ニーズの把握方法や関係機関との連携・協働のあり方を検討していくことが必要であると考えられた。新市町において,保健師は地域診断を行って地域特性や課題を把握し,課題解決に向けて実現可能な活動について職場で共有し,質の高い活動を展開していくことが必要であり,そのための手法の確立が今後の課題であると考えられた。
キーワード 市町村合併,保健(師)活動,人口規模,保健事業
|
第57巻第8号 2010年8月 転倒・転落死亡率の統計的分析(1950~2006年)-「食生活改善行動の採用」尺度と行動変容モデルの予測-今泉 洋子(イマイズミ ヨウコ) 屋久 真寛(ヤヒサ マサヒロ) 鐘ヶ江 葉子(カネガエ ヨウコ) |
目的 転倒・転落死亡率の長期変動を調べると共に,これらの死亡率に影響を及ぼした要因について分析を行い,転倒・転落死の実態を明らかにすることである。
方法 1950~2006年の人口動態統計資料を用い,転落・転倒死亡率の統計的分析である。
結果 転倒・転落死の男子年齢調整死亡率は1970年から2006年までに半減,女子の値は1966年から2006年までに1/3近くまで減少した。死亡率の男女格差は1958~2006年まで3倍前後で推移していたが,0~4歳と70歳以上の死亡率は男女とも同程度,特に男女格差が大きいのは30~39歳で10倍以上と高いが,1995年以降は4倍前後と男女格差は縮小している。主要3死因の中で特に男女の「階段及びステップからの転落及びその上での転倒(W10)」と男子の「建物又は建造物からの転落(W13)」の年齢調整死亡率の減少率は大きい。W10とW13の傷害発生場所が家庭内の割合は男子では年次と共に上昇,女子W10の家庭内割合は70%以上,W13の値は50~70%と横ばいで推移している。一方「スリップ,つまずき及びよろめきによる同一平面上での転倒(W01)」の男子の死亡率は1950年から2006年にわたり年次変動はあるが上昇傾向がみられた。女子のW01死亡率は1974年まで上昇,翌年から1990年まで減少後は横ばい傾向にある。なお,男女共にW01年齢調整死亡率の減少率が低いのは高齢化率の上昇と関係していた。
結論 W01年齢調整死亡率の減少が始まった年次は男女で異なるが,1966~1979年まで男女の死亡率は同程度であり1990年まで減少している。1990年までの死亡率の減少はバリアフリーの整備や医療水準の向上によるが,1991年以降の男子死亡率の上昇や女子の横ばい傾向は,わが国の高齢化率の上昇と関係しているので,高齢者向けの居住環境の整備が必要であろう。男子W13死亡率の減少は工業用地域での従業中の死亡率の低下によるものである。この減少は環境整備や医療水準の向上によるものと思われる。なお,男子W13死亡率の急速な減少が転倒・転落死の男女格差の縮小をもたらしている。男子のW10とW13死亡率の家庭内割合が上昇したのは,高層住宅の普及と関係があると思われる。
キーワード 転倒・転落死亡率,人口動態統計,長期変動,傷害発生場所,男女格差
|
第57巻第8号 2010年8月 学生の介護職のイメージ-介護福祉実習体験の違いによる意識の比較-津田 理恵子(ツダ リエコ) |
目的 介護に対する社会的イメージが悪い中で,介護福祉士養成施設における学生の定員割れは深刻な課題となっている。そこで,介護福祉士養成施設で学ぶ学生に,介護職のイメージなどについてアンケート調査を実施し,介護福祉実習経験を重ねることでその意識に差があるのか比較検討し,その結果をもとに,介護現場が抱える課題を整理することで,介護福祉士養成施設における学生への価値教育に役立てたいと考えた。
方法 調査対象は4年制大学介護福祉コースの学生81名で,2009年4月4日~4月15日の期間に,介護職のイメージや働きがい,介護福祉実習体験による介護職のイメージの変化,将来の就職希望職種などの質問紙を作成し,学年ごとに一斉に配布し自己記入方式,無記名で回答を得た。介護福祉実習経験を重ねた者による意識を比較するためにSPSS15.0を使用し,学年ごとの回答を記述統計処理し,自由記述回答は,回答内容をカテゴリー化して整理した。
結果 介護職は働きがいがあると感じているにも関わらず,介護に対するイメージは良いとはいえず,「介護の質」「人材不足」「給料面」での課題を感じていることが明確になった。介護福祉実習を重ねることで,介護現場の課題を認識したうえで,現場の表面的な大変さだけでなく,介護者としての喜びを実感し介護職を希望する学生が増える傾向があることが明確になった。
結論 専門職者として理論と実践の統合を目指した介護福祉実習では,学生が利用者との関わりから,生活支援を通して働きがいがある職種としてその喜びが実感できるよう,学生自身の成功体験を導く教授内容を展開する必要である。そして,社会における介護職のイメージ回復に向けた取り組みにより,介護のイメージの負のスパイラルは断ち切れると示した。
キーワード 介護職のイメージ,学生,介護福祉実習,実践現場の課題,養成教育
|
第57巻第8号 2010年8月 行政事業協力型保健ボランティア活動における
奥野 ひろみ(オクノ ヒロミ) |
目的 行政事業協力型保健ボランティア活動における協働のためのファシリテーション技術と,それを促進する担当者の要因を明らかにする。
方法 調査は,全国市町村保健センター要覧より系統抽出を実施した1,175区市町村保健センターに対し,自記式質問紙の郵送法により行った。調査項目は,ファシリテーション技術,担当者の保健ボランティア活動への積極性,ヘルスプロモーション活動に関する意識,住民参加の認識,自己研鑽,担当者の属性,ボランティアの選出方法である。分析は,ファシリテーション技術の尺度点を用いて因子分析を行い,ボランティアの選出方法間でファシリテーション因子得点の差異を確認した。ファシリテーション技術を促進する担当者の要因は,ファシリテーション技術高群と低群の2群間で確認した。
結果 対象1,175区市町村保健センターのうち,606区市町村から回答が得られた(51.6%)。そのうち保健ボランティア活動を実施し有効回答の得られた478市町村(40.7%)で分析を行った。ファシリテーション技術は,「円滑なコミュニケーション」「メンバーの自己決定への配慮」「住民とのパートナーシップ」「成果の公表」「メンバーの確保」の5因子が抽出された。自薦のボランティアグループは,ファシリテーション技術の「メンバーの自己決定への配慮」「住民とのパートナーシップ」「成果の公表」「メンバーの確保」で因子得点が高値であった。ファシリテーション技術高群は低群に比して,活動への積極性,ヘルスプロモーション活動に対する意識の高さがみられた。
考察 ファシリテーション技術は,事前準備,グループ・プロセスのサポート,継続に向けての意欲の向上という一連の流れの中での技術と捉えることができる。また,これらを促進するためには担当者のヘルスプロモーション意識の向上が重要であることが示唆された。
キーワード 保健ボランティア活動,ファシリテーション技術,ヘルスプロモーション
|
第57巻第8号 2010年8月 がんと精神科医療-DPCデータに基づく検討結果から-松田 晋哉(マツダ シンヤ) 藤森 研司(フジモリ ケンジ) 桑原 一彰(クワバラ カズアキ)石川 ベンジャミン光一(イシカワ ベンジャミンコウイチ) 堀口 裕正(ホリグチ ヒロマサ) |
目的 がん医療においては抑うつや不安などに対する精神科的ケアの重要性が高い。しかしながら,がん診療の入口となる急性期入院医療の現場で精神科的ケアがどの程度行われているのかは明らかでない。そこで,現在急性期病院を対象に行われているDPC調査で収集されているデータをもとに,がん医療における精神科医療の状況を分析し,今後の在り方を考究することを試みた。
方法 平成20年度に厚生労働科学研究費研究事業「包括払い方式が医療経済及び医療提供体制に及ぼす影響に関する研究」に参加した855病院から収集したDPCデータから乳房の悪性腫瘍(090010)で,分析に必要な必須項目の入力に問題のない36,047例(女性症例のみ)を抽出し,併存症・続発症としてのうつ関連疾患(ICD-10でF3$,F4$)の発生状況を分析した。
結果 F3$,F4$の記載割合はともに1.8%で,年齢階級別では30~39歳で最も高かった(F3$:3.1%,F4$:2.6%)。手術と化学療法の組合せ別にF3$とF4$の出現割合をみると,手術なし群では化学療法「なし群」で「あり群」より有意にF3$の出現割合が高く(3.6%と1.7%;p<0.001),手術あり群では化学療法「あり群」が「なし群」より有意にF3$の出現割合が高く(3.1%と1.4%;p<0.001),またF4$の出現割合も有意に高かった(2.6%と1.2%;p<0.001)。精神科的治療の内容の分析結果では,F3$の記載のある症例の19.6%で抗うつ剤による治療,9.8%で精神科専門療法,0.9%で緩和ケアが行われていた。
考察 本研究の結果は,わが国の急性期入院医療においては,がん患者のうつに対して十分な精神科的対応が行われていないことを示唆しており,今後の急性期病院における精神科の在り方について検討が必要であると考えられた。
キーワード DPC,乳がん,うつ,がん医療,精神科医療
|
第57巻第8号 2010年8月 権利擁護としての日常生活自立支援事業の現状と課題-専門員・生活支援員の支援活動と地域連携を中心に-濱島 淑恵(ハマシマ ヨシエ) 加藤 薗子(カトウ ソノコ) 谷口 真由美(タニグチ マユミ) |
目的 日常生活自立支援事業は,利用制度をベースとした現在の社会福祉制度下において,判断能力が不十分な者の権利擁護を行う極めて重要な事業である。本研究では,日常生活自立支援事業の担い手である専門員および生活支援員の支援活動の実態および地域の社会資源との連携の現状を明らかにし,権利擁護としての当事業の課題を検討することを目的としている。
方法 2008年6月から7月,近畿・東海圏の3府県下の社会福祉協議会を通して,日常生活自立支援事業を担当している専門員および生活支援員に対し,調査票を配布した。回答は無記名で行い,回収は郵送法で行った。調査票の配布数は専門員56名,生活支援員673名とし,回収数は専門員40名(回収率71.4%),生活支援員387名(回収率57.5%)であった。なお,対象者には調査目的や個人情報が特定できないことを文書で示し,質問紙の回収をもって調査への同意を得たものとみなした。
結果 専門員は国家資格保持者や年齢層の比較的若い世代が多く,生活支援員は国家資格保持者が極めて少なく,年齢層が高い者が多かった。また専門員は正規雇用の者が非常に多く,生活支援員は非正規非常勤で低報酬の者が多かった。次に支援活動の状況では,新規ケースが非常に少ないこと,専門員は他の業務と兼務している者が多いことが示された。さらに支援の内容では,事業が規定している範囲外の支援を行っている者が専門員,生活支援員ともに多くみられ,また両者の支援内容には重複があることが示された。地域連携の状況については,専門員と生活支援員間の連携はよく行われていたが,その他の地域の社会資源との連携については,インフォーマルとの連携が手薄であり,縦割りの連携を行う傾向がみられた。
結論 日常生活自立支援事業の周知,利用の促進,専門性を発揮する重要な役割を担うことが期待される専門員の人員配置の充実,事業の支援内容の範囲とその柔軟性,分業体制のあり方についての再検討,地域連携に向けた総合的な取り組みの必要性を今後の課題として挙げた。
キーワード 日常生活自立支援事業,地域福祉権利擁護事業,専門員,生活支援員,権利擁護
|
第57巻第8号 2010年8月 岩手県花巻市における特定健診未受診者の未受診理由と健康意識久保田 和子(クボタ カズコ) 大久保 孝義(オオクボ タカヨシ) 佐藤 陽子(サトウ ヨウコ)廣瀬 卓男(ヒロセ タクオ) 今井 潤(イマイ ユタカ) |
目的 基本健康診査の地域における受診率は40%程度に過ぎなかった。特定健診受診率の最終目標は市町村国保で65%とされており,今までよりかなり高い数値を求められている。本研究では市町村国保加入者における特定健診未受診者を対象に,未受診理由と健康意識についての調査を行った。
方法 岩手県花巻市における平成20年度の特定健診対象国保加入者20,519人のうち,10,043人が特定健診を受診した(受診率49%)。末受診者のうち施設入所者・人間ドック受診者等397名を除いた10,079人を対象に,平成21年1月に郵送で未受診理由・健康意識等に関するアンケート調査を実施した。
結果 特定健診未受診者10,079人のうち,4,840人より回答が得られた(回収率48%)。健診未受診の理由としては,他機関での受診や医療機関での受療などを除くと,「自分は健康だから」「時間の都合がつかない」と回答した者が多かった。また健診所要時間に対する許容範囲は非常に短く,「待ち時間を含めて1時間未満」と答えた者が7割に達していた。メタボリックシンドロームについての認知度はかなり高く,名前だけ知っている人まで勘案するとほぼ90%が「知っている」と回答していた。しかし「内容も知っている」と答えた人は3分の2程度であった。回答者の5割強程度が保健指導への参加を希望していた。しかし希望者においても費用負担をする概念はほとんどなく,5割は「無料」を希望し,「有料でも参加」と回答した場合であっても,その希望単価の平均は男性で1,700円,女性では1,200円程度であった。
考察 特定健診未受診理由としては「自分は健康だから」および「時間の都合がつかない」と回答した者が多かった。それぞれ地域啓発と柔軟性の高い受診機会の提供が主な対策となる。未受診者の健診所要時間への要望は現実とはかけ離れており,健診の効率化など行政側の工夫と住民の意識啓発が重要であると考えられた。
キーワード 特定健診受診率,健診未受診理由,医療機関受療,健康意識,メタボリックシンドローム認知度
|
第57巻第10号 2010年9月 茨城県全市町村の加重障害保有割合(WDP)と
栗盛 須雅子(クリモリ スガコ) 福田 吉治(フクダ ヨシハル) 大高 恵美子(オオタカ エミコ) |
目的 茨城県の介護予防施策と健康づくり施策の立案と評価のための基礎資料を得ることを目的に,茨城県全44市町村の2006年,2007年,2008年の65歳以上の介護保険統計を用いた加重障害保有割合と障害調整健康余命を算出し,地域間比較を行った。WDPは障害の程度によって重みづけをした障害者の割合,DALEは平均余命(生命表)とWDPを使って算出される健康寿命のひとつである。
方法 性・年齢階級別WDPは,性・年齢階級別・介護度別の認定者数,性・年齢階級別人口,および介護度別の効用値(要支援1=0.80,要支援2=0.72,要介護1=0.71,要介護2=0.61,要介護3=0.46,要介護4=0.30,要介護5=0.20)を用いて算出した。性・年齢階級別DALEは性・年齢階級別WDPと生命表を用いてSullivan法で算出した。地域間比較は,地理情報分析支援システムMANDARAを用いて分布図を作成し,行政区分(県北,鹿行,県南,県西,県央)で行った。
結果 茨城県全体では,年齢調整WDPは男女とも年々高くなり,65~69歳のDALEは男女とも年々短くなっていた。WDPの地域間比較は,65~69歳の男性は鹿行が3年とも高い傾向にあり,女性は県南が高くなる経年的傾向を示した。DALEの地域間比較は,65~69歳の男性は県北が3年とも長い傾向にあり,男女とも鹿行が短い傾向にあった。また,女性は県央が長い傾向にあった。
結論 WDPを低下させ,健康余命を延ばす取り組みを行う場合は,画一的ではなく,それぞれの地域特性に合った取り組みを行う必要がある。そのためには,WDP,DALEの背景にある地域の健康要因(例えば,3大死因,その他の疾病の死亡率),社会経済要因(医療環境,就業率,所得),人口学的要因(独居高齢者,生活保護世帯)などについて分析し,課題を抽出した上で,施策を策定することが望ましいと考えられた。
キーワード 加重障害保有割合,障害調整健康余命,地域間比較,地域特性
|
第57巻第10号 2010年9月 児童養護施設の施設形態に関する実証的分析大原 天青(オオハラ タカハル) |
目的 今日,児童虐待相談対応件数は年々増加の一途をたどり,それとともに社会的養護を必要とする子どもの数が増加してきた。そうした中で,児童養護施設に入所する子どものニーズに適した施設形態の議論が行われている。ところが,児童養護施設の施設形態に関する実証的分析は非常に少ない。そこで本研究は,児童養護施設に入所する子どもの基本属性を示したうえで,施設形態ごとの子どもの特徴を統計的に示すことを目的とする。
方法 調査対象は,A県管轄のすべての児童養護施設25カ所に調査依頼を行い,承諾の得られた10施設に入所する児童128人である。各児童を担当する直接支援職員に,Child Behavior Checklist/4-18(子どもの行動チェックリスト,以下,CBCL)の9尺度(「引きこもり」「身体的訴え」「不安・抑うつ」「社会性の問題」「思考の問題」「注意の問題」「非行的行動」「攻撃的行動」「その他の問題」)の中から各6項目程度を選択した合計54項目と,児童の性別・入所期間・虐待の有無等の質問票に回答してもらった。調査期間は,2008年8月~9月である。
結果 本研究では,A県という限られた地域を対象としたが,全国児童養護施設入所児童調査と比較して性別や年齢でほぼ一致した結果が得られた。3つの施設形態(小舎制・中舎制・大舎制)ごとのCBCL得点は,「身体的訴え」「不安・抑うつ」内向尺度で中舎制より小舎制が高かった。さらに,「非行的行動」「攻撃的行動」外向尺度で大舎制よりも小舎制が高得点を示した。
結論 施設形態によるCBCL得点の違いについて,措置の判断や職員の精神的負担感,集団力動による表出の違いが関係していることを考察した。また,職員の自己覚知の必要性や精神的負担感の軽減,職員の配置基準の問題を解決していく必要性が示唆された。
キーワード 児童養護施設,CBCL,施設形態,小舎制,情緒と行動,直接支援職員
|
第57巻第10号 2010年9月 世帯分類別の異状死基本統計-東京都区部における孤独死の実態調査-金涌 佳雅(カナワク ヨシマサ) 森 晋二郎(モリ シンジロウ) 阿部 伸幸(アベ ノブユキ)谷藤 隆信(タニフジ タカノブ) 重田 聡男(シゲタ アキオ) 福永 龍繁(フクナガ タツシゲ) 舟山 眞人(フナヤマ マサト) 金武 潤(カネタケ ジュン) 鈴木 恵子(スズキ ケイコ) |
目的 福祉保健上の問題である孤独死について,行政上対策に資することのできる基本統計を提供することを目的に,東京都区部における単身および複数世帯別の異状死の調査を行った。
方法 昭和62年から平成18年までに東京都監察医務院で取り扱った自宅死亡の異状死のうち,特別区居住者を単身世帯,複数世帯に区分した。調査項目としては,世帯・性別死亡数,世帯・性・年齢階級別死亡数と死亡率,年齢調整死亡率,世帯・性別平均死後経過時間,世帯・性・死後経過時間別死亡数構成比とした。
結果 調査対象例は77,938例であった。世帯・性別死亡数は,各群で死亡数は年々増加していたが,男性単身群は平成9~11年にかけて急激な増加があった。世帯・性・年齢階級別死亡数は,男性単身の40~69歳群で死亡数が突出する傾向が,経年的に顕著であった。世帯・性・年齢階級別死亡率は,いずれの群でも年齢と共に死亡率の上昇が認められたが,特に男性単身群では40歳以降に死亡率の上昇が特徴的であった。年齢調整死亡率は,男性単身群,女性単身群,男性複数群,女性複数群の順で,これに経年変動はなかった。平均死後経過時間は,複数群は各年で変動はなく,単身世帯者は経年増加する傾向があった。世帯・性・死後経過時間別の死亡数構成比は,死後経過時間の進行と共に急激に減少しており,3日以内の死後経過は,単身群で5~7割,複数群で9割以上であった。
結論 本調査において,死亡数・死亡率ともに40歳代以降の男性で深刻な状況であることが示された。孤独死対策では,男性の高齢者のみならず40歳代以降の中年層に対する対策が必要であると示唆される。年齢調整死亡率で著明な経年変動はなかったが,高齢化社会の進行から,孤独死の数は今後増加することは確実であろう。そのために,行政上の対策が求められるが,本調査研究からは,孤独死の予防可能性の行政上の対策に資する基本統計の提供が可能と考えられる。
キーワード 孤独死,孤立死,監察医,行政解剖,死体検案
|
第57巻第10号 2010年9月 地域高齢者における死亡予測因子の検討-高齢者健診と基本健康診査から-金子 知香子(カネコ チカコ) 中野 匡子(ナカノ キョウコ) 安村 誠司(ヤスムラ セイジ) |
目的 老人保健事業の見直しに伴い,高齢者を対象に実施する健康診査の項目について,どのような健診項目が適切であるかの検討は重要である。今回著者らは,死亡の発生を評価指標としてアンケート調査,体力測定,従来の基本健康診査項目を評価することを目的とした。
方法 福島県大玉村在住者で満70歳以上に達する者のうち,介護保険認定者(要介護2以上)および入院中の者を除いた1,347人を対象とし,平成16年7月の基本健康診査実施時に高齢者健診(アンケート調査・体力測定)を実施した。高齢者健診の非受診者の訪問によるアンケート調査・体力測定を行った。会場受診群443人,訪問受診群395人について3年間の死亡・転出状況を観察した。
結果 会場受診群と比較し訪問受診群は年齢が高く,日常生活自立度が低い,歩行・入浴が要介護の状態である,老研式活動能力指標得点が低い,健康度自己評価で健康でない,生活体力Motor fitness scale(MFS)の得点が低い,脳卒中の既往がある,栄養摂取頻度が低い,うつ傾向がある,外出頻度が週1回未満,長座位立ち上がり時間が長い者の割合が高いといった特徴を認め,3年間での死亡者の割合が高かった。転帰は会場受診群は生存421人,死亡21人,転出1人であった。訪問受診群は生存351人,死亡42人,転出2人であった。死亡と有意に関連がみられた項目は,①会場受診群では尿糖陽性,総コレステロール低値,②訪問受診群では高齢,男性である,脳卒中の既往がある,MFSの得点低値であった。③受診者全体では高齢,男性である,脳卒中の既往がある,MFSの得点低値,高齢者健診の未受診群であった。
結論 受診者全体,訪問受診群でMFSが死亡に有意に関連していたことから,MFSが高齢者健診の項目として有効な可能性がある。また,会場受診群では従来からの基本健康診査項目のうち尿糖,総コレステロールの有効性が認められ,疾病対策の重要性が示された。地域在住高齢者の死亡発生は会場受診群で低く,会場受診群と訪問受診群では危険因子が異なることが示された。行政の側から健診未受診者の把握は容易である。健診未受診群が全体の死亡の危険因子であることから未受診者対策が高齢者において重要であり,一層の対策が望まれる。
キーワード 死亡予測因子,地域在住高齢者,生活体力(Motor fitness scale),基本健康診査
|
第57巻第10号 2010年9月 児童虐待と親のメンタルヘルス問題-児童福祉施設への量的調査にみるその実態と支援課題-松宮 透髙(マツミヤ ユキタカ) 井上 信次(イノウエ シンジ) |
目的 本研究は,児童福祉施設入所児童におけるメンタルヘルス問題のある親による児童虐待の実態を把握するとともに,そのソーシャルワーク支援のニーズおよび支援体制構築に向けた課題を明確化することを目的とする。
方法 児童福祉施設(児童養護施設,乳児院,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設)の全数を対象に,家庭支援専門相談員等への郵送による質問紙調査を行った。質問紙は施設入所児童数等に関するデータ,回答者の属性,その意識に関する5件法の設問とで構成した。
結果 児童福祉施設に入所する児童の49.1%は被虐待児童であり,被虐待児童の46.1%はメンタルヘルス問題のある親による虐待を受けていた。虐待した親のメンタルヘルス問題としては感情障害,虐待種別としてはネグレクトの割合が最も大きかった。当該事例への支援において回答者は困難やストレスを感じている一方,ソーシャルワーカーとしての国家資格所持者は回答者の19.1%,メンタルヘルス問題に関する十分な研修受講者も16.6%にとどまっていた。さらに,精神科医療機関や精神保健福祉士との連携体制は不十分であり,当該問題へのソーシャルワーク支援機能を果たすには体制上の課題があることも明らかになった。
結論 児童福祉施設における精神保健福祉ニーズは非常に高い半面,施設機能および機関連携上その支援体制は不十分である。児童福祉施設と精神保健福祉機関・専門職との連携体制の構築や支援方策・社会資源の開発などが緊急の課題であると言える。
キーワード 児童福祉施設,児童虐待,メンタルヘルス,ソーシャルワーク,家庭支援専門相談員(FSW)
|
第57巻第10号 2010年9月 認知症早期発見を目的とした集団検診の継続意義と
杉山 智子(スギヤマ トモコ) 丸井 英二(マルイ エイジ) 松村 康弘(マツムラ ヤスヒロ) |
目的 認知症の早期発見は,認知症の重症化や進行予防,介護予防の方策を考える上で重要な課題になりつつある。今回,各自治体で実施されている高齢者健康診査に物忘れ関連項目を加えた簡易な検診システムを考案追加し,2002年度から追跡調査を行った。しかし,この検診事業の中で年ごとに検診に来なくなる高齢者が次第に増加することが観察された。そのため,この群の中に高い割合で認知症や障害の発症があるのではないかとの仮定から集団検診脱落群に焦点をあてて検診未受診者の追跡調査をすることとした。
方法 対象は,都内A病院に区委託の高齢者検診を目的として来院し,本研究の趣旨の説明を受け,同意したものとした。調査内容は,認知機能をMMSEで測定したほか,頭部X線CT,生活習慣調査を行った。また,2008年度に行われた検診に未受診であった者で,本人または家族の連絡で未受診の理由が把握できた以外の者に対し,2008年ならびに2009年2月に電話調査を行い,検診未受診の理由を尋ねた。分析対象は,2003年度の検診事業へ参加した者とした。このうち,2008年度に受診したものを継続群,2008年度を含む3年間連続で未受診であった者を脱落群とし,MMSE得点の比較と脱落群の検診未受診となった理由をその内容に応じて分類し,集計を行った。
結果 2003年度において検診を受診した者は409名であった。対象者の属性は,2003年当時の平均年齢75.8歳,性別は女性の方が多く,256名(62.6%)であった。対象のうち,継続群は289名(70.7%),脱落群は120名(29.3%)であった。2003年度調査時のMMSE得点は,継続群28.1±2.9点,脱落群26.3±5.3点であり,脱落群は継続群よりMMSE得点が有意に低かった(t=3.61,p<0.05)。また,年齢においても脱落群の方が高く,受診年齢で差が認められた。脱落群の未受診理由で最も多かったのは,記載されていた電話番号が使われていない「不通」が23名(21.3%)であり,身体的理由は42名(38.9%)であった。検診未受診理由別のMMSE得点において,身体的な理由(24.2±7.7点)は,元気であると回答した者(28.6±1.4点)よりも得点が有意に低かった(t=-3.54,p<0.05)。
結論 脱落群への追跡調査や脱落をエンドポイントとして検討することの重要性が示唆され,この種のコホート研究にエンドポイントとして何かしらの理由による脱落を設定しておくことは変化の解釈に有効であると考えられた。
キーワード 認知症,早期発見,脱落群,集団検診,MMSE,検診未受診理由
|
第57巻第12号 2010年10月 国民年金と生活保護に関する実質的受給額の比較-高齢者単身世帯および高齢者2人世帯を例にして-和田 一郎(ワダ イチロウ) 高橋 秀人(タカハシ ヒデト) 大久保 一郎(オオクボ イチロウ) |
目的 国民年金を納付しなかった(できなかった)人が,老後に生活保護受給者になった場合,その受給額が国民年金(老齢基礎年金)受給額より厚いのではないかといわれている。しかし受給額を計量的に比較した研究はほとんどない。本研究は,生活保護の高齢者モデルケースをもとに,平成18年度のデータを用いて,そのケースが生活保護を受給せずに国民年金のみ受給している場合の額と被保護者として支給される受給額を,住宅や医療,介護の支出を考慮した実質的受給額として単純比較することを目的とする。
方法 モデルケースである(A)高齢者単身世帯(68歳女),(B)高齢者2人世帯(68歳男,65歳女)を用いた。国民年金受給額(満額,平均額)には医療費・介護費の自己負担額がない高齢者「元気な高齢者」とその自己負担額を考慮する高齢者「一般的な高齢者」,生活保護受給額には生活扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助を考慮してそれぞれの月額の実質的受給額を比較した。
結果 (A)高齢単身世帯:「元気な高齢者」では,国民年金の実質的受給額は満額(平均額)61,856円(43,435円)であった。これに対して生活保護受給額は最低級地(最高級地)で80,568円(98,458円)であり,国民年金受給額の満額は18,712円(36,602円),平均額は37,133円(55,023円)下回っていた。(B)高齢者2人世帯:「元気な高齢者」では,国民年金の実質的受給額は満額(平均額)123,712円(86,870円)であった。生活保護受給額は最低級地(最高級地)で131,066円(158,126円)であり,国民年金受給額の満額は7,354円(34,414円),平均額は44,196円(71,256円)下回っていた。「一般的な高齢者」では医療費自己負担額11,455円(( )内は高齢者2人世帯の額:22,910円),介護費自己負担額1,829円(3,658円)の合計13,284円(26,568円)または介護費自己負担額を0円とした合計額が,それぞれの国民年金の実質的受給額からさらに減じられる形になる。
結論 比較したすべてのパターンで,実質的な国民年金受給額は生活保護受給額より低額であり,福祉における再分配はゆがんでいる可能性がある。この問題への対応や今後の福祉政策立案・施行は,科学的に裏打ちされた根拠に基づいて行う必要がある(根拠に基づいた福祉:Evidence-Based Welfare,EBW)。
キーワード 国民年金,生活保護,比較,不公平感,根拠に基づいた福祉(Evidence-Based Welfare,EBW)
|
第57巻第12号 2010年10月 被虐待児の育児環境の特徴と支援に関する研究望月 由妃子(モチヅキ ユキコ) 篠原 亮次(シノハラ リョウジ) 杉澤 悠圭(スギサワ ユウカ)童 連(トン レン) 平野 真紀(ヒラノ マキ) 冨崎 悦子(トミサキ エツコ) 田中 笑子(タナカ エミコ) 渡辺 多恵子(ワタナベ タエコ) 恩田 陽子(オンダ ヨウコ) 川島 悠里(カワシマ ユリ) 安梅 勅江(アンメ トキエ) |
目的 本研究は,虐待に関連する養育者側および子ども側要因を経年的な分析により明らかにし,虐待の早期発見・早期支援に向けた支援への一助とすることを目的とした。
方法 全国の認可夜間および併設昼間保育園(18園)に在籍する2~6歳の子どもと保護者2,050名が対象であり,担当保育専門職より「気になる子ども」と評価された40名の園児のうち,2006年度における虐待の聞き取り調査で「虐待」の「確定」「疑い」と評価された6名を対象とし,基準年(2005年)と1年後(2006年)のデータ双方から育児環境と発達状況を分析した。担当保育専門職には「子どもの気になる行動」「園児用発達チェックリスト」の記入とともに,「虐待やネグレクトの有無」について聞き取り調査を行った。
結果 虐待の聞き取り内容では,「疑い」5名,「確定」1名であった。子どもの発達は1年後に「リスクあり」が増加しており,子どもの発達リスクと虐待との関係が示された。その中で1名は1年後に発達が好転しており,背景に保護者の昼間勤務への転職による生活の改善があった。乳幼児の発達に「規則正しい生活リズム」と「情緒的安定」が重要であることが示された。育児環境では「父・母の協力が乏しい」「子どもを持つ友人との交流が乏しい」が基準年および1年後ともに高い割合であり,保護者は配偶者や友人のサポートが得られず孤立した中で子育てをしていた。子どもの失敗への対応に「たたく」と答えた2名は,「精神的に不安定な母親」と「しつけに厳しい父親」であった。また「先週子どもをたたいた回数」は「1~2回以上」が半数以上おり,虐待のグレーゾーンを示していた。「たたいた」と基準年および1年後に回答した保護者のうち3名は同じ人で,子どもの失敗に対し「たたく」と答えた2名と「母子家庭で高校生の姉が面倒を見ているケース」であった。保護者特性では,「育児の自信がない」と半数が基準年および1年後に回答しており,保護者の背景要因に即した適切な支援が求められている。「保育園に行くのを楽しみにしている」は基準年および1年後ともに全数であり,保育園は家庭でのかかわりを日常的に補完する役割を担っていた。
結論 児童虐待の早期発見・早期支援のために,保育園等乳幼児期の子どもの支援機関で活用可能な根拠のある支援技術の普及と地域や家庭における子育て支援システムの構築が期待される。
キーワード 児童虐待,子どもの発達,早期発見・早期支援,子育て支援
|
第57巻第12号 2010年10月 介護保険を利用する長期療養者におけるADLの経時的変化-要介護認定調査の中間評価項目第2群(移動)の慢性透析群と非透析群における比較-清水 詩子(シミズ ウタコ) |
目的 わが国では慢性透析の長期化と透析者の高齢化が顕著になりつつあり,透析者の日常生活動作(ADL)の把握が急務である。目的は,要介護認定調査のうち中間評価項目得点を用いて,透析者の移動に関するADLの経時的変化の特徴を透析群と非透析群との比較によって明らかにし,透析者に必要なサービス検討のための基礎資料とすることである。
方法 調査対象は,2009年3月末時点で新潟市に在住する要介護(要支援)認定者のうち,過去14日間に受けた医療で「透析あり」に該当する者すべてと,対照群として「透析なし」の者,合計1,000名の,2003年4月から2009年3月までのデータである。分析対象は,透析群・非透析群とも,4年以上の認定調査結果がある「介護保険を利用する長期療養者」を男女別,年齢区分別(69歳以下と70歳代)に分けた。そして,直近の認定調査結果を4回目とし,1年遡るごとに3回目,2回目,1回目とし,各回の中間評価項目第2群(移動)の平均得点を算出した。
結果 2009年3月31日現在,新潟市において「透析あり」(透析群)は234名(男性113名,女性121名)であり,うち,4年以上の調査結果がある者は,69歳以下の男性10名,女性9名,70歳代の男性15名,女性13名であった。一方,非透析群で4年以上の調査結果があり,かつ過去14日以内に受療しなかった者は,69歳以下の男性9名,女性6名,70歳代の男性38名,女性36名であった。中間評価項目第2群の平均得点の経時的変化は,69歳以下の男女で認定調査回数4回とも透析群が非透析群を下回り,70歳代女性で認定調査回数4回とも透析群が非透析群を上回った。また,透析群の69歳以下男性の中間評価項目第2群の平均得点は,認定調査回数の4回すべてで最も低値であった。
結論 透析者では,69歳以下の比較的若年であっても,移動に関するADLの低下がみられた。透析者は透析合併症によりADLが低下する可能性を考慮し,透析年数別にADLの経時的変化を調査する必要がある。
キーワード 介護保険制度,中間評価項目,日常生活動作(ADL),慢性透析者
|
第57巻第12号 2010年10月 仙台市泉区内における妊婦を対象とした意識調査鈴木 修治(スズキ シュウジ) 庄子 俊江(ショウジ トシエ) 田崎 香菜子(タザキ カナコ) |
目的 住宅団地の多い仙台市泉区内における妊娠・出産の状況と妊婦の子育てへの意識や夫婦の役割に関する考え方等を調べた。そこから仙台市のような大都市に共通する核家族化と少子化指向社会の中で,子育てにおける夫婦の役割や行政の支援のあり方を明らかにする事を目的とした。
方法 母子健康手帳の交付を受けに泉区保健福祉センター(保健所)に来所した妊婦に調査の趣旨を口頭で説明し協力依頼した。調査への協力の有無で本人には不利益がないことを付言した。同意を得た人に質問票をわたし,退所時に本人が記入した質問票を539人から回収した。無記名方式による調査である。
結果 調査時点では妊婦が理想とする子ども数が実際の出生児数より若干多く今後妊娠・出産適齢層が子どもを持つ可能性は残った。心配な事柄では母子の健康(56.6%)や出産時の費用(36.2%)が多かった。夫やパートナーには育児の分担(77.6%)と家事の分担(69.6%)を多く期待していた。出産予定は近隣の医療機関(52.7%)や里帰りと思われる場合(36.6%)が多かった。
結論 核家族化が進む大都市での育児環境の変化から生じる不安の軽減や少子化対策には,夫婦が協力し育児の出来る環境整備と育児負担の軽減を図る行政の支援が必要である。安心して妊娠・出産に臨むには近隣の医療機関の確保も必要となる。
キ-ワード 妊娠・出産,妊婦の負担感,育児環境と費用,夫婦の育児協力
|
第57巻第12号 2010年10月 人間ドック受検者の飲酒量が検査値に及ぼす影響と介入効果石川 信仁(イシカワ ノブヒト) 山門 桂(ヤマカド カツラ) 繁田 正子(シゲタ マサコ) |
目的 生活習慣病の進展や関与を指摘されながら,支援や指導への情報が少ない飲酒の問題について,飲酒量による検査値への影響とドックでの介入効果を明らかにする。
方法 対象は2005年に当院ドックを受検した男性5,403名のうち,2007年に再受診した男性3,633名(明らかなアルコール依存症や誤記を除く)とした。問診票より1日当たりの飲酒量に1週間当たりの飲酒日数を掛け,7で割ったものを1回の飲酒量とし,非飲酒群(以下,ND)959名,少量飲酒群(LD:1.0単位/日以下)1,574名,中等量飲酒群(MD:1.1~3.0単位/日以下)943名,多量飲酒群(HD:3.1単位/日以上)157名の4群に分け,検査値との関連を分散分析により検討した。人間ドック当日にCAGE法と久里浜スケールを組み合わせたアルコールアンケートを行い,医師と看護職・栄養士が連携して様々な介入を行い,2年後の飲酒量や検査値の推移を分析した。
結果 各群のγ-GTP(IU/ℓ)の平均値および標準偏差は,ND:34.9±1.2,LD:44.5±1.2,MD:66.7±5.4,HD:96.0±5.8となり,すべての群間で有意差を認めた。その他,中性脂肪,収縮期血圧,BMIが飲酒量に相関して高値であった。適量を超える飲酒量のMDとHDを合せた1,100名において,2年後のγ-GTP,HbA1c,1日当たりの飲酒量,1週間当たりの飲酒日数が有意に低下していた。
結論 健康な成人が受検する人間ドックでさえ,3割の男性は適量超える飲酒,1割は多量飲酒していた。適量を超える飲酒は肝機能や代謝に明らかに悪影響を及ぼしているが,支援や指導により継続受検者では飲酒量の減少が認められ,介入の有効性が示唆された。
キーワード 保健指導,人間ドック,γ-GTP,血圧,中性脂肪,飲酒習慣
|
第57巻第12号 2010年10月 首都圏の大規模集合住宅における
|
目的 高度経済成長期に多く建設された大規模集合住宅において,住民の高齢化および単身化を背景に孤独死の増加が指摘されている。本研究では,大規模集合住宅に居住する単身高齢者の生活の現状を明らかにし,また同じ大規模集合住宅内における賃貸・分譲ごとの住宅形態別による比較検討を通して,孤独死予防のための環境整備や生活支援について考察した。
方法 対象者は,東京都新宿区A集合住宅B地区に居住する単身高齢者である。調査は無記名自記式質問紙法であり,各世帯への質問紙の配布と回収は各棟の自治会役員が行った。質問紙の配布は単身高齢者を含めた全世帯を対象に行い,質問紙配布数610,回収数186(回収率30.5%)であった。そのうち分析対象者である単身高齢者は58人(男性6人,女性52人)であった。調査時期は平成20年5月下旬から6月下旬である。調査項目は,基本的属性の他にエレベーターの有無,要介護認定調査,主観的健康度,外出頻度,親族や友人・知人と会うまたは電話する頻度,緊急連絡先の有無とその内訳,親しくしている親族,親しい友人・知人の有無,楽しみや気晴らしにしていること,団地の生活で困っていること,地域活動の活動状況や参加意向,利用しているサービス等である。住宅形態の比較としての「分譲住宅」に居住する人と「都営住宅」に居住する人の2群の差の検討では,年齢についてはT検定,入居年数についてはマンホイットニー検定を行い,その他の項目についてはχ2検定を行った。
結果 高齢者のいる世帯における単身高齢者世帯の割合は42.6%であった。平均年齢は76.49歳であり,住宅形態は「都営住宅」が65.5%,「公社分譲住宅」が34.5%であった。要介護認定調査を受けている人の割合は「都営住宅」の方が「分譲住宅」に比べて有意に高く,自分が健康であると考えている人の割合は「分譲住宅」の方が有意に高かった。また,「親しい親族」において「子ども」をあげた人の割合が「分譲住宅」で有意に高かった。
結論 きっかけがあれば地域活動を行う意向のある高齢者が団地内に多く居住しており,孤独死予防策として,自立した高齢者が身体機能の低下した高齢者の支え手として機能する可能性が十分にあること,また「都営住宅」に居住する単身高齢者において,「分譲住宅」に居住する人に比べ健康状態や子どもとの関係において課題があると考えられたことから,より多様な人材,サービスによる重層的な生活支援の充実が求められると考えられた。
キーワード 単身高齢者,大規模集合住宅,住宅形態,賃貸・分譲,生活支援,孤独死予防
|
第57巻第13号 2010年11月 障害児を養育する家族のエンパワメント測定尺度
涌水 理恵(ワキミズ リエ) 藤岡 寛(フジオカ ヒロシ) 古谷 佳由理(フルヤ カユリ) |
目的 情緒障害を抱えた子どもを地域で養育する家族のエンパワメントを測定する尺度であるFamily Empowerment Scale(以下,FES)日本語版を作成し,その信頼性と妥当性の検証を行うことである。
方法 都市部と郊外の施設(計3施設)に外来通院中である5~18歳の情緒・発達障害児を養育している保護者を対象に自記式質問紙調査を実施した。回答結果から,FES日本語版の内的一貫性・再テスト信頼性・収束妥当性・弁別妥当性・因子妥当性・自己効力感尺度および自尊感情尺度との併存的妥当性・社会参加活動状況の異なる2群での既知集団妥当性について統計学的に検証した。
結果 十分な内的一貫性(Cronbach’s α:0.81-0.87)と再テスト信頼性(級内相関係数:0.79-0.82)が示され,尺度の信頼性が確認された。また収束妥当性,弁別妥当性の検討では,尺度化成功率は90%以上であった。併存的妥当性の検討では自己効力感尺度および自尊感情尺度との有意な正の相関がみられ,既知集団妥当性の検討ではFES全下位尺度得点において社会参加活動「あり」の群が「なし」の群を上回った(p<0.0001)。
結論 本研究より,FES日本語版の高い信頼性と妥当性が示され,わが国における情緒障害児の養育者を対象とした調査や研究,あるいは看護介入や長期フォローアップの評価指標として使用可能であることが示唆された。
キーワード 障害児,家族,エンパワメント,尺度,信頼性,妥当性
|
第57巻第13号 2010年11月 居宅介護支援事業所における診療情報の入手の実態と影響要因五十嵐 歩(イガラシ アユミ) 山下 悦子(ヤマシタ エツコ) 山田 ゆかり(ヤマダ ユカリ) |
目的 ケアマネジメントにおいて利用者の診療情報を得ることは重要であるが,現状では医療機関と居宅介護支援事業所間の情報共有が円滑に行われていない実態がある。本研究では,利用者の入退院時における居宅介護支援事業所による診療情報の入手の現状と情報入手に対する影響要因を明らかにし,医療機関・居宅介護支援事業所間の情報共有を促進する方策を検討した。
方法 WAM NETより無作為抽出した全国150居宅介護支援事業所を対象に,自記式質問紙による郵送調査を実施した。調査項目は,事業所特性(法人種別・併設事業・利用者数・過去1年間の入院利用者数・実働介護支援専門員(以下,ケアマネ)数),ケアマネの基礎資格,診療情報入手の必要性,診療情報入手の程度,診療情報の入手方法とした。
結果 90事業所(回収率60%)のケアマネ226人より返送を得た。医療系ケアマネは100人(44%),福祉系ケアマネは126人(56%)だった。ほぼすべてのケアマネが利用者が入退院した際の診療情報を必要と考えているにも関わらず,実際に診療情報を「十分得られる」「得られる」と回答した者は合わせて54%であった。入手方法は,「利用者・家族に聞く」(94%),「入院先に直接出向く」(68%)が多かった。診療情報の入手の程度を従属変数とし,事業所特性および各入手方法の有無を独立変数とするロジスティック回帰分析の結果,医療系ケアマネでは診療情報の入手への有意な関連要因はなかったが,福祉系ケアマネでは医療系事業所に所属していること(p=0.003)と入院先に直接出向くこと(p=0.015)が,情報入手に有効であった。
結論 医療機関・居宅介護支援事業所間の診療情報の共有には,ケアマネの医療機関へのアクセスを促進させる施策を充実させるとともに,利用者を介した情報伝達の体制づくりも有効であると考えられる。
キーワード 医療と介護の連携,介護支援専門員,居宅介護支援事業所,医療機関,診療情報の共有
|
第57巻第13号 2010年11月 歯科医療費からみた事業所における歯科検診の有効性馬場 みちえ(ババ ミチエ) 畝 博(ウネ ヒロシ) 谷原 真一(タニハラ シンイチ)今任 拓也(イマトウ タクヤ) 吉永 一彦(ヨシナガ カズヒコ) |
目的 事業所における歯科検診が歯科医療費の抑制に有効であるかどうかを明らかにすることである。
方法 対象はA企業のB事業所に所属している22~59歳の従業員1,636人である。2003年から2006年までに行われた歯科検診を4回連続して受けた4回受診者419人,1~3回受診者765人,非受診者452人の3群に分けて,2003年~2006年の診療報酬明細書を用いて,歯科診療費(調剤費を除いた歯科医療費)について比較検討した。
結果 対象者100人当たりの年間歯科受診率では,最も多いのが1~3回受診者で120.0,次が4回受診者で116.4,最も少なかったのが非受診者で110.3であった。レセプト1件当たりの平均受診日数は,非受診者が2.98日,1~3回受診者が2.82日,4回受診者が2.61日で,歯科検診受診回数が少ない群ほど有意に多く,また,1日当たりの平均歯科診療費は,非受診者が6,443円,1~3回受診者が5,822円,4回受診者が5,368円で,歯科検診受診回数が少ない群ほど有意に高かった。対象者1人当たりの年間歯科診療費は,非受診者が18,333円,1~3回受診者が18,353円で,両者の間にはほとんど差がなかったが,4回受診者では15,355円と,非受診者や1~3回受診者より約3千円安かった。
結論 対象者100人当たりの年間歯科受診率,レセプト1件当たりの受診日数,1日当たりの歯科診療費の結果から,歯科検診を受けることにより,歯科診療所への受診回数は多くなるが,異常が早期に発見され,早期に治療されるために,1回当たりの治療期間は短く,かつ1回当たりにかかる歯科医療費は安くなると考えられた。また,1人当たりの年間歯科診療費も,毎年受診した4回受診者では非受診者や1~3回受診者より安く,歯科検診を毎年受診することにより,歯科医療費が抑制されることが示唆された。
キーワード 費用対効果,歯科医療費,歯科検診,産業歯科保健
|
第57巻第13号 2010年11月 わが国における受動喫煙起因死亡数の推計片野田 耕太(カタノダ コウタ) 望月 友美子(モチヅキ ユミコ) 雑賀 公美子(サイカ クミコ)祖父江 友孝(ソブエ トモチカ) |
目的 受動喫煙は,肺がんや虚血性心疾患への因果関係が科学的に認められている。諸外国では受動喫煙起因死亡数の推計が行われているが,わが国では報告がない。本研究は,わが国における受動喫煙の人口寄与危険割合および受動喫煙起因死亡数を推計することを目的とした。
方法 先行研究から,能動喫煙と受動喫煙の曝露割合と相対リスクを抽出した。能動喫煙の曝露割合および相対リスクに基づいて,集団全体の死亡者に占める非喫煙者の割合を求め,さらに受動喫煙の曝露割合および相対リスクから受動喫煙の人口寄与危険割合を求めた。受動喫煙起因死亡数は,人口寄与危険割合を,平成20年(2008年)人口動態統計死亡数に乗じて求めた。対象疾患は肺がん,虚血性心疾患,および乳幼児突然死症候群(SIDS)とし,対象集団は,肺がんおよび虚血性心疾患については日本人女性,SIDSについては日本人全体とした。
結果 わが国の女性における家庭での受動喫煙の人口寄与危険割合は,肺がんおよび虚血性心疾患でそれぞれ6.2%および4.8%,肺腺がんで20.8%であった。女性における職場での受動喫煙の人口寄与危険割合は,肺がんおよび虚血性心疾患でそれぞれ1.9%,4.3%であった。SIDSにおける親の喫煙の人口寄与危険割合は,父親で36.3%,母親で14.0%であった。これらの人口寄与危険割合に基づくと,わが国の女性における受動喫煙起因年間死亡数は,家庭での受動喫煙については,肺がん1,131人,肺腺がん2,554人,および虚血性心疾患1,640人,職場での受動喫煙については,肺がん340人および虚血性心疾患1,471人と推計された。受動喫煙起因年間SIDS死亡数は,男女計で,父親の喫煙起因が61人,母親の喫煙起因が24人と推計された。
結論 わが国における受動喫煙起因死亡数は多く,女性肺がん死亡数に占める割合では米国の約4倍に相当する。米国などの喫煙対策先進国と同様に,公共の場所および職場での禁煙法制化,家庭での屋内喫煙防止対策など,受動喫煙を防ぐ総合的な対策を進める必要がある。
キーワード 受動喫煙,人口寄与危険割合,肺がん,虚血性心疾患,乳幼児突然死症候群
|
第57巻第13号 2010年11月 知的障害者のグループホームにおける職員の業務に関する考察中野 加奈子(ナカノ カナコ) 田中 智子(タナカ トモコ) |
目的 障害者自立支援法が制定以後,従来の障害者福祉施策は新たな事業体系へ大きく変化した。その中で,障害者の生活の職住分離を目指し,日中活動の場,生活の場という考えが示され,生活の場としてグループホーム・ケアホーム(以下,GHCH)への期待は高まっている。大規模施設での生活から小集団の家庭的な生活,施設内で完結する生活から地域の中に溶け込んだ生活へと移行することによる豊かな「暮らし」の実現がGHCHによって可能になると考えられているのである。しかし,障害者の地域生活を支えるGHCHの運営や支援の実際は,いまだ十分には把握されていない。本稿では,各GHCHに委ねられているのが現状であり,利用者の障害程度,年齢,職員の配置状況,支援の方法などは多様化している。
方法 調査は「タイムスタディ調査」と「生活支援業務調査」の2種類を実施した。調査対象は,グループホーム・ケアホーム(以下,GHCH)を運営する76カ所,およびその他近畿圏内の協力事業所6カ所,合計82事業所へ調査依頼を行い,各事業所のホーム数合計99カ所を調査対象とした。回収数は2008年8月18日現在,75事業所,ホーム数合計77カ所で,回答職員数は171人であった。
結果 本調査では,利用者の平均障害程度区分は約4で比較的障害が重度の利用者が多くみられたこと,加齢への対応も必要となってきているホームがあった。またGHCHの職員は非正規の者が多く,また労働時間も長時間化している傾向が伺えた。各GHCHにおいて各種マニュアルが整備されているものの,マニュアルに沿った対応が必ずしも実行できる状況とはいえないことや,個別支援計画の職員間の共有が困難な状態であること等が明らかになった。
結論 現在のGHCHでは利用者像は多様化しており,かつ個別性・専門性の高い支援が必要な者が多く利用しているにも関わらず,学生のアルバイトやフリーター層,主婦層による短期間の労働サイクルによって支援が担われていることが推測され,専門性の追求につながりにくい条件を持つ者が中心となっていた。また,GHCHでは夜間を中心とした支援体制が取られ,職員の労働時間の長時間化していた。また,夜間支援体制は必要に応じた加算方式であり,報酬単価は認知症GHと比較すると低い設定であった。
キーワード 知的障害,グループホーム・ケアホーム,職員配置,報酬単価
|
第57巻第13号 2010年11月 女性労働者の子宮がん検診受診行動に関わる要因-MYヘルスアップ研究から-兼任 千恵(カネトウ チエ) 豊川 智之(トヨカワ サトシ) 三好 裕司(ミヨシ ユウジ)鈴木 寿子(スズキ トシコ) 須山 靖男(スヤマ ヤスオ) 小林 廉毅(コバヤシ ヤスキ) |
目的 金融保険系企業職員を対象としたMYヘルスアップ研究における調査結果をもとに,女性労働者の子宮がん検診受診行動に関連する要因を明らかにすることを目的とした。
方法 2004年10月に実施したアンケート調査と同年の定期健康診断問診票のデータを用いて,子宮がん検診の定期的受診(1~2年ごと)の有無に関連する可能性のある要因を多変量ロジスティック回帰分析により検討した。分析項目は,年齢,職種,月経の状況,肥満度,生活習慣(飲酒,喫煙,運動,健康行動,朝食欠食),主観的健康感,仕事のストレス,現病歴(婦人科疾患,がん),既往歴(婦人科疾患,がん),家族歴(がん),家族形態(配偶者・子どもの有無,親との同居)とし,分析対象は20~59歳の女性職員とした。
結果 1~2年ごとに子宮がん検診を受診していると回答した者の割合は25.8%(6,227/24,150)であった。多変量ロジスティック回帰分析の結果,年齢が高い者,運動習慣・健康行動がある者や禁煙した者,婦人科疾患やがんの現病歴・既往歴のある者,がんの家族歴のある者,配偶者や子どものある者などは,定期的に子宮がん検診を受診していることが示された。一方,やせや肥満,現在の喫煙,朝食欠食などがある場合は,子宮がん検診を定期的に受けない傾向があった。また,年齢を調整すると,閉経前の者と比較して閉経後の者は検診を受診しない傾向にあった。
結論 年齢や生活習慣,本人および家族の病歴,家族形態,閉経などが,子宮がん検診の受診行動に関連していることが示唆された。
キーワード 子宮がん,がん検診,受診行動,受診率,女性
|
第57巻第15号 2010年12月 北海道鹿追町における歯科保健施策と医療費増加抑制西 基(ニシ モトイ) 三宅 浩次(ミヤケ ヒロツグ) 袰岩 由美子(ホロイワ ユミコ)菅原 裕美(スガワラ ヒロミ) 荻野 弘子(オギノ ヒロコ) |
目的 北海道鹿追町において実施された歯科保健施策と同町民の歯科保健関係の指標の好転,およびそれに付随して認められた国民健康保険医療費増加の抑制について記述疫学的報告を行う。
方法 鹿追町における2001年からの保健施策の最重要課題として,歯科保健を取り上げ,町民への歯磨きの励行や歯科検診受診等の勧奨を行った。2001,2004,2007年に,それぞれ町民の約1割を層化無作為抽出し,歯科関係の指標を含む諸項目につき,自記式アンケートによる調査を実施した。同町の国民健康保険医療費の資料は,同町の資料によった。また,この調査の参加者を歯科検診毎年受診者とそれ以外に分け,国保医療費を比較した。
結果 歯磨きを行う者の割合等の歯科保健関係の指標は,年を追うごとに改善された。医療費は,2003年から,全国の変化を元に算出した期待値より低くなり,かつ絶対額も2002年には低下した。1999年には,実際の医療費は期待額より4700万円余り高かったが,2005年には1億9300万円余り低くなった。歯科検診毎年受診者の医療費は,それ以外の者より低かった。
結論 鹿追町の歯科保健を最優先とした保健施策が,同町の医療費逓減に対し一定の寄与をしたと思われる。今後,わが国の医療費抑制に対して,歯科保健は1つのカギになりうると思われ,また目下実施中の特定健診には歯科検診が含まれいていないため,今後,取り入れることを積極的に検討すべきと思われた。
キーワード 鹿追町,歯科保健,医療費,衛生行政
|
第57巻第15号 2010年12月 地区単位のソーシャル・キャピタルの測定尺度の妥当性に関する検討-エコメトリックな視点による「近隣効果尺度」の日本語版の開発-大賀 英史(オオガ ヒデフミ) 大森 豊緑(オオモリ トヨノリ) 近藤 高明(コンドウ タカアキ)小山 修(オヤマ オサム) |
目的 ソーシャル・キャピタルと地域住民の健康度との関連を評価する指標として,「近隣効果」が注目されている。この近隣効果を生活する環境の視点から測定するスケール(近隣効果尺度)が米国で考案されており,その妥当性について検証するとともに,わが国の地方自治体レベルでの活用の有用性について検討した。
方法 近隣効果尺度(美観,歩行環境,健康的な食品の入手,安全,暴力,社会的密着性,近隣づきあいの7尺度)の日本語版,自覚的健康度,健康不安,K6(うつ・不安のスケール)などを含む調査票を作成し,平成19年9月に,東京都内近郊都市で活動するまちづくりの市民団体が,住みよいまちづくりの資料とする目的を地域住民に説明し,同意が得られた住民から回答を得た。生活環境をとらえる指標として産業施設数,人口密度,緑地・公園数,無人野菜販売所などの値と,調査で得られた市民250人分の個人別データから居住地区別(23地区)の平均値との相関分析を行った(両側検定,p<0.05)。また,7尺度の地区別平均値をマップ化し,都市計画図や地域別犯罪マップ(警視庁作成)などとの照合により,質的な検討を行った。
結果 7尺度の値と地区の事業所数との有意な関連は,「歩行環境」尺度の値が低い地区は卸売・小売業が多く,「暴力」尺度の値が低い(暴力が多い)地区は飲食・宿泊業が多く,また人口密度が低く,「近隣づきあい」尺度の値が高い地区は,教育・学習支援業が少なく,人口密度が高かった。都市計画図との照合では,「美観」尺度の値が高い地区は区画整備された地域と緑地保全緑地がある地区であり,準工業地域が多い地区,ゴミ焼却用を有する地区は得点が低かった。「歩行環境」尺度の値が高い地区は緑地保全地域やウォーキングコースが整備された河川を有する地区であった。「暴力」尺度の値が低い(暴力が多い)地区は駅周辺の鉄道沿線であり,地域別犯罪マップの「粗暴犯」の多い地区と地理的な分布に関連があった。「安全」「社会的密着性」「近隣づきあい」の各尺度の値が高いほど健康不安が高く,「近隣づきあい」尺度の値が高い地区ほど,うつ・不安を示すK6の値が低かった(いずれもp<0.05)。
結論 米国で考案された近隣効果尺度は,地区単位の平均値という簡便な方法であっても,わが国の地方自治体における各地区の特徴をとらえ得ることが確認できた。
キーワード ソーシャル・キャピタル,エコメトリック,近隣効果尺度,地区単位
|
第57巻第15号 2010年12月 居住系施設における医療のあり方と看取りに関する研究金子 さゆり(カネコ サユリ) 濃沼 信夫(コイヌマ ノブオ) 伊藤 道哉(イトウ ミチヤ)尾形 倫明(オガタ トモアキ) 三澤 仁平(ミサワ ジンペイ) 千葉 宏毅(チバ ヒロキ) 森谷 就慶(モリヤ ユキノリ) |
目的 グループホームなど居住系施設における療養について,看取りに関する情報提供がどのように行われているか,その実態を明らかにし,利用者の安心や信頼を確保するための居住系施設における医療のあり方とその普及・促進の方策について検討する。
方法 全国の在宅療養支援診療所の中から年間看取り数が10件以上の実績がある178診療所を抽出し,電話にて調査協力の同意が得られた126診療所を対象に,居住系施設における訪問診療・往診の現状について調査した。調査にて44診療所の医師より回答が得られ,この時点で訪問診療・往診を受けている居住系施設127施設とその利用者629人と家族629人を対象にアンケート調査を実施した。
結果 居住系施設の調査は109施設(85.8%)から回答が得られ,うち看取り体制・方針を定めている施設は55.9%であった。1施設当たり定員数は28.5人,訪問診療・往診の利用者数は10.4人であり,1施設当たり年間死亡数3.8人のうち,施設看取り数は2.5人であった。また,訪問診療・往診を受けている居住系施設の利用者356人(56.6%),家族344人(54.7%)の回答が得られた。利用者の平均年齢は84.5歳,女性が76.0%を占め,利用者の90.2%に認知障害がみられた。施設からの説明について,急変時の対応に関して利用者本人は「説明を受けた」36.0%,「説明を受けたが理解できなかった」24.5%であり,家族は「説明を受けた」85.8%であった。看取りに関して利用者本人は「説明を受けた」23.2%,「説明を受けたが理解できなかった」20.6%であり,家族は「説明を受けた」67.0%であった。
結論 現状は施設看取りが定着しつつあると考えられる。しかし,看取りに関する説明を受けた割合は,家族は73.5%,利用者は43.8%,そのうち利用者の約半数が説明を受けたが理解できなかったと回答していることから,利用者や家族の意向を尊重した施設看取りを実現するためには,家族だけでなく,利用者へ対してわかりやすい説明と工夫が求められる。また,看取りについて十分な説明を受けた場合は,そうでない場合に比べて,最期を迎える場所として医療機関を選択する割合が減ることが示唆された。
キーワード 居住系施設,看取り,救急搬送,情報提供
|
第57巻第15号 2010年12月 早期乳幼児期の麻疹ワクチン接種率に関連する因子-埼玉県70市町村の分析から-相崎 扶友美(アイザキ フユミ) 田宮 菜奈子(タミヤ ナナコ) 岸本 剛(キシモト ツヨシ)古島 大資(フルシマ ダイスケ) 田中 政宏(タナカ マサヒロ) 柏木 聖代(カシワギ マサヨ) 金子 道夫(カネコ ミチオ) |
目的 2012年麻疹排除達成に向け,乳幼児の麻疹ワクチン接種率が低い集団における接種率向上が課題である。そこで,埼玉県内全70市町村におけるワクチン接種率データを用い,早期乳幼児期の麻疹ワクチン接種率の関連要因を明らかにする。
方法 埼玉県予防接種事業実施状況調査を基に,2006年度,2007年度,2006年度から2カ年の,早期乳幼児期の麻疹ワクチン1期接種率を算出した。また,2006年から2カ年の,市町村の麻疹ワクチン1期接種率を従属変数とし,国内の公表統計データより得た市町村特性を独立変数として,市町村を単位とした単回帰分析を行った。
結果 2006年度および2007年度における,市町村の麻疹ワクチン1期接種率の平均は,88.9%および91.8%であった。また,2006年度から2カ年の間の麻疹ワクチン1期接種率の平均値±SD,中央値(レンジ)は,90.3±5.0,90.5(74.3-99.2)(%)であった。単回帰分析では,世帯当たりの平均課税対象所得(万円/年)は回帰係数(β)=0.035,p=0.052であった。また,この他に,関連を示す傾向を認めた独立変数は,5歳未満人口割合(%)(β=1.006,p=0.192)と65歳以上人口割合(%)(β=-0.282,p=0.140)であった。
結論 2006年度と2007年度の接種率分布からは,日本全体の接種率の推移と同様に埼玉県においても,麻疹ワクチン1期接種率が年々上昇したが,一方で,市町村間で接種率に差が存在していた。市町村の麻疹ワクチン1期接種率と市町村特性の単変量の関係をみた限りでは,統計学的有意性に至った特定項目はなかったが,「低所得世帯の乳幼児」と「乳幼児が少なく,高齢者の多い地域に住む乳幼児」が麻疹ワクチン低接種率のハイリスク群である可能性が示唆された。今後は,さらに他の関連要因の影響も考慮し,ハイリスク群を明らかにする必要がある。また,予防接種事業に関する実証研究が乏しいわが国においては,接種率関連要因を明らかにするとともに,接種率向上の具体的な取り組みを検証し,さらにその結果を自治体間と共有することで,実証に基づく麻疹予防接種政策を実施することが望まれる。
キーワード 麻疹ワクチン,乳幼児,市町村,所得,接種率,乳幼児・高齢者人口割合
|
第57巻第15号 2010年12月 東北4県における地域福祉課題の動向について-平成17・20年の東北の民生委員調査結果から-都築 光一(ツヅキ コウイチ) 細田 重憲(ホソダ シゲノリ) 杉岡 直人(スギオカ ナオト)吉田 渡(ヨシダ ワタル) 李 忻(リ シン) |
目的 少子高齢化が著しい東北の4県(青森・秋田・岩手・山形)において,平成17年と平成20年に民生委員を対象として実施した調査結果に基づき,入所施設の必要性,高齢期になって必要な小売店,障害者との交流意識を中心に,地域福祉課題の動向を明らかにする。
方法 調査は,平成17・20年ともに質問紙による配票留置法にて各県の民生委員協議会を通じ,各県の民生委員全員を対象に配布し回収した。また同時に,4カ所の地方公共団体にてインタビュー等の関連調査を実施した。
結果 回収率は平成17年が88.5%,平成20年が84.6%であった。調査結果を比較すると,入所施設の必要性と介護者支援の必要性が高くなってきていた。これについては,インタビュー等関連調査結果により,高齢者の単独世帯や高齢者夫婦世帯で,要支援要介護状態になる高齢者が増加していることや,居宅サービスと施設サービスの総合化等,施設を望む声が高いことが確認された。また,高齢期になって生活に必要な物資の調達のために,コンビニエンスストアの必要性が高まっている。この理由は,高齢者になって移動が困難になったり,自動車免許証を返還した後の移動手段が失われていることが理由として考えられた。さらに,障害者の地域移行が進んでいると考えられたが,むしろ地域においては,障害者との活動面で,交流意識に躊躇傾向がみられた。
結論 今後,若年世帯との世帯分離が一層進むことが予想されることから,高齢者世帯の増加に伴い,ますます入所施設の必要性が高くなることが懸念され,これに対する対応のあり方が課題と思われた。次に高齢者世帯の家族人員の減少により,家事負担が大きくなってきているところから,衣食住を含めた総合的な生活支援のあり方が課題と思われた。さらに,障害者の地域移行の達成のために,地域に密着した活動プログラムのあり方が課題と思われた。これらを踏まえ,新たな地域の運営システムをデザインする必要があると考えられた。
キーワード 地域福祉課題,パネルデータ,民生委員,東北4県
|
第57巻第15号 2010年12月 児童生徒と両親の生活習慣病危険因子の相関に関する研究藤井 千惠(フジイ チエ) 榊原 久孝(サカキバラ ヒサタカ) |
目的 教育委員会および学校との連携により,親子を対象に健康調査を実施してその関連について明らかにし,学校における生活習慣病予防教育のあり方について検討した。
方法 平成18年に長野県のある町の子どもの健康調査を受診した小学校第5学年(小学生)と中学校第2学年(中学生)計340人のうち,家族の健康調査への参加を保護者が同意した小学生117人,中学生99人計216人とその父親197人,母親213人を対象とした。親子相関の解析には,小中学生は子どもの健康調査結果を利用し,両親は職場や地域における健康診断結果と生活習慣についての自記式質問紙調査を実施してその結果を用いた。さらに,子どもの健康調査結果に対する保護者の意識について質問紙調査を実施した。
結果 体格では両親と小中学生のBMIで有意な正の相関がみられ,血圧では父親と小学生の収縮期血圧で有意な関連がみられた。血液検査結果では両親と小中学生のHDLコレステロールで有意な関連がみられ,さらにLDLコレステロールなどの血清脂質や母子間ではヘモグロビンA1cなどとの有意な関連もみられた。遺伝的な背景を踏まえた上で生活習慣の積み重ねによる影響を考える必要がある。就寝・起床時刻,睡眠時間では,母親と小中学生で有意な正の相関がみられたが,父親とは生活時間が異なるために有意な関連はみられなかった。運動頻度では,父親と小学生で有意な関連がみられた。食習慣では両親と小中学生の朝食,野菜,インスタント食品,清涼飲料水の摂取頻度で有意な正の相関がみられた。さらに,母子間では間食・夜食,スナック菓子の摂取頻度で有意な関連がみられ,小学生の方が母親の食習慣が大きく影響していた。満腹まで食べる傾向では両親と小中学生で有意な関連がみられ,食事の内容とともに食べ方についても親子で注意する必要がある。子どもの健康調査結果に対して保護者は関心を示し,ほぼ全員が家族全員で生活習慣を見直すことが大切であると回答した。
結論 児童生徒とその両親では,体格,血圧・血液検査結果,生活習慣で有意な正の相関が認められ,児童生徒の健康状態には遺伝的な背景とともに生活習慣の積み重ねによる影響が示唆され,さらに子どもの生活習慣には親の生活習慣が大きく影響を与えていることが明らかになった。健康調査結果を見ることは家族の生活習慣を見直す機会につながることが示され,子どもと保護者を主体とする家族の生活習慣病予防教育を家庭・学校・地域連携により協働で実践する必要性が示唆された。
キーワード 生活習慣病危険因子,親子相関,児童生徒,予防教育,家庭・学校・地域連携
|
第63巻第4号 2016年4月 協会けんぽのレセプトデータを用いた期間統計の方法による
|
Ⅰ は じ め に
「電子レセプトによる保健・医療統計の改善に向けて-「電子レセプトを用いたレセプト統計の改善に関する研究」の概要(その1)-」(本誌28年3月号)1)(以下,前稿)では,電子レセプト統計について,社会医療診療行為別調査の向上のため,新たな期間統計の方法による診療エピソード統計を提言している。そして,その統計の概念規定や計算方法の詳細,さらには全国健康保険協会のデータを用いた統計作成のデモンストレーションは別稿で紹介するとしており,本稿はその別稿にあたる。本稿では,
・これまでのレセプト統計の考え方・分析方法と患者単位,患者の動向分析のための統計としてみた時の課題
・期間統計の方法による診療エピソード統計の考え方・分析手法の概要
・全国健康保険協会のデータを用いた統計作成のデモンストレーションの方法と結果
を述べる。
現在,医療提供体制の分野では地域医療構想とそれを含む医療計画が,また,医療保険分野では医療費適正化計画があり,その医療費適正化対策の一つとして保健分野の特定健康診査・特定保健指導が実施されている。さらに,各医療保険者はデータヘルス計画を策定し実施することとされている。これらの施策にレセプトデータを活用するとされているところであるが,期間統計の方法による診療エピソード統計は,従来のレセプト統計と異なり,患者単位で,患者の発生・受診の継続・受診の終了といった患者の受診動向を把握できるため,医療提供体制・医療費・保健の各分野との関連づけが容易であり,これらの政策立案・実施状況把握・評価にも有用と考えられる。
Ⅱ これまでのレセプト統計の考え方・分析手法と課題
電子レセプト導入以前のレセプト統計は,大量の紙レセプトを処理するという制約と審査支払優先のため,毎月得られるデータはレセプト件数,診療実日数,点数(医療費)に限られ,それらを用いた統計であり,以下の2つの考え方により構築されている。その1番目の考え方は,
・1枚のレセプトは,医療機関が暦月1カ月中に対応した患者ごとの入院,入院外,歯科別の調査票であり,記載されている診療実日数と点数は調査票の調査項目と考えることであり,レセプトを調査の調査票と考えるものである。
具体的には,この調査では,レセプト件数は標本数(調査票枚数に相当),診療実日数・点数(医療費)は調査項目であり,1件当たり日数・1件当たり点数は,診療実日数・点数を件数で割った標本平均である。
|
第63巻第4号 2016年4月 重回帰分析を用いたDPC対象病院の
中島 尚登(ナカジマ ヒサト) 矢野 耕也(ヤノ コウヤ) 長澤 薫子(ナガサワ カオコ) |
目的 機能評価係数Ⅱと構成する6指数に対してDiagnosis Procedure Combination(DPC)データがどのように影響しているか重回帰分析し,さらに機能評価係数Ⅱの予測式を作成して検討した。
方法 対象はⅠ群80,Ⅱ群90,Ⅲ群1,326病院であり,平成24年DPCデータのうち,多重共線性を避けるため強い相関を示す項目を除外して手術有,化学療法有,放射線療法有,救急車搬送有,在院日数平均値を選び重回帰分析の説明変数とした。また平成25年機能評価係数Ⅱと構成する6指数のうち,χ2適合度検定による正規性の判定よりⅠ,Ⅱ群の効率性指数,複雑性指数,カバー率指数,救急医療指数,およびⅠ,Ⅱ,Ⅲ群の機能評価係数Ⅱは正規分布であった。よってこれらの指数を重回帰分析の目的変数とした。そして重回帰分析を行い,目的変数の予測に有用な説明変数を選択し,さらに回帰係数より機能評価係数Ⅱの予測式を作成した。
結果 目的変数である機能評価係数Ⅱに対し,選択された説明変数は,Ⅰ群では救急車搬送有,放射線療法有,手術有,在院日数平均値,Ⅱ群では救急車搬送有,放射線療法有,在院日数平均値,Ⅲ群では救急車搬送有,在院日数平均値,放射線療法有,手術有,化学療法有であり,それぞれ在院日数平均値と手術有の回帰係数が負の値を示した。また次の予測式を作成した。
Ⅰ群:機能評価係数Ⅱ=3×10-6×救急車搬送件数+1×10-5×放射線療法件数−1×10-6×手術件数−5.22×10-4×在院日数平均値+0.027
Ⅱ群:機能評価係数Ⅱ=3×10-6×救急車搬送件数+8×10-6×放射線療法件数−5.29×10-4×在院日数平均値+0.024
Ⅲ群:機能評価係数Ⅱ=5×10-6×救急車搬送件数−2.96×10-4×在院日数平均値+3×10-6×放射線療法件数−1×10-6×手術件数+1×10-6×化学療法件数+0.022
次に予測式と機能評価係数Ⅱとの相関をSpearman順位相関係数検定で検討した。その結果,Ⅰ群r=0.527,Ⅱ群r=0.614,Ⅲ群r=0.610,と有意に正の相関を示した。
結論 重回帰分析で病院群別に機能評価係数Ⅱの予測式を作成した。その結果,予測値は実測値と相関し,機能評価係数Ⅱの評価に有用であった。
キーワード DPC,機能評価係数Ⅱ,重回帰分析
|
第63巻第4号 2016年4月 在宅重症心身障がい児家族の支援ニードと
|
目的 在宅で生活する重症心身障がい児家族(以下,在宅重症児家族)の支援ニードを明らかにし,彼らと日常的に関わる看護職および行政職の支援ニードに対する重要度の認識および実践の現状を明らかにし,今後取り組むべき課題を同定することである。
方法 首都圏近郊の在宅重症児家族にインタビュー調査を行い,質的内容分析法により支援ニード項目を作成した。またデルファイ法により,看護職および行政職に2度のアンケート調査を実施し,各立場からの重要度および実践度について,項目ごとの中央値・四分位範囲(IQR)・IQR%を算出した。
結果 在宅重症児家族25組計56名へのインタビューより支援ニード41項目を作成した。デルファイ1次調査対象者は看護職29名,行政職97名で行い,2次調査対象者は看護職19名,行政職52名であった。重要度の特に高かった項目は,看護職で23項目,行政職では18項目であり,看護職・行政職ともに重要度が高いと見なした項目は「医療者は家族に在宅療養においてできることを的確に伝えてほしい」「将来を見据えたケアや療育アドバイスがほしい」などの6項目であった。実践度の高かった項目は,看護職で15項目中3項目,行政職で13項目中3項目であった。実践度と重要度に乖離があった項目は看護職が「サービスの利用方法がわからないときに相談に乗ってほしい」などの5項目,行政職が「災害時に迅速に対応できるようにしてほしい」「家族だけで頑張りすぎないでいいことを伝えてほしい」の2項目であった。
結論 看護職および行政職ともに,家族の支援ニードを支持する姿勢を有しており,重症心身障がい児の成長に合わせて家族の将来の見通しが立てられるよう,サービス利用情報や療育アドバイスを充実していくことの重要性を認識していた。重要度および実践度に乖離がみられた項目への対策として,看護職では在宅重症児家族に必要なサービス利用や家族会等の情報を部局内で周知・共有すること,他職種と協働して各家族や児の個別性をアセスメントしつつ在宅療養への助言,将来を見据えた助言,家族へのサポートを行う組織としての体制や機会を作ること,行政職では地域の状況を考慮した災害への具体的な備えの検討,家族との対話とねぎらいを行うことが取り組むべき課題として提示された。
キーワード 重症心身障がい児家族,在宅生活,支援ニード,デルファイ法,看護職,行政職
|
第63巻第4号 2016年4月 特別養護老人ホームにおける
|
的 ユニットケアを導入する特別養護老人ホームは増加しているがユニットケアが定着するための効果的な研修方法は未だ確立されていない。本研究では,新規に開設するユニット型特養を対象に「教育的介入」を試み,その有用性を検証することを目的とした。
方法 教育的介入群の2特養に対して,厚生労働省が定めるユニットリーダー研修のプログラムと同一の内容である「ユニットケア定着研修」を開設前に実施した。また,開設から半年後に各特養の管理職を対象とした「コーディネーター養成研修」を行った。これらの研修の実施を本研究における「教育的介入」とした。ユニットケアの定着を測定するために,介入群2特養と非介入群の5特養に対して厚生労働省が定める調査票を用いた現地調査,その後,介入群に対する同様の再現地調査,再々現地調査の結果により,教育的介入の効果を検証した。なお,非介入群は,開設1年以上3年未満の特養が2施設,開設3年以上の特養が3施設とした。
結果 介入群の現地調査の結果は平均53.0点であった。非介入群の現地調査結果は,開設1年以上3年未満の特養で平均37.0点,開設3年以上の特養で平均49.0点であった。介入群の2施設ともに現地調査から再現地調査で大きく得点が上昇した(+18.5点,+20.0点)。1年後の再々現地調査においても点数が維持されていた。
結論 これらの結果から,ユニットケア定着研修およびコーディネーター養成研修を行う教育的介入の有用性が示唆された。今回対象となった介入群のように,ユニットケアに新規に取り組む特養の多くの職員がユニットケア定着研修を受講し,コーディネーター養成研修を受講したコーディネーターが,ユニットケアの推進役を果たすことで,短期間であってもユニットケアが定着する可能性が示唆された。
キーワード ユニットケア,ユニットケア定着研修,コーディネーター養成研修,特別養護老人ホーム