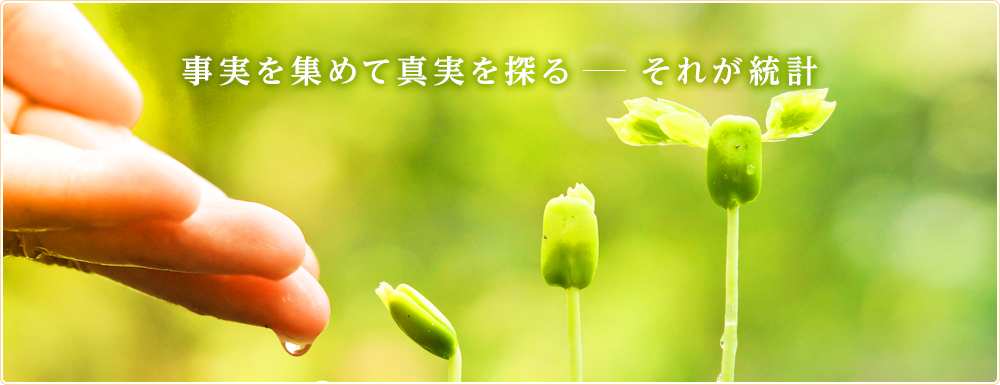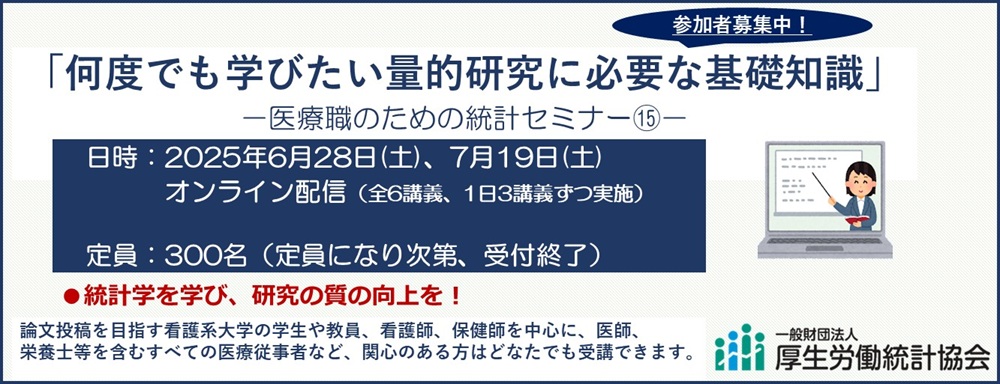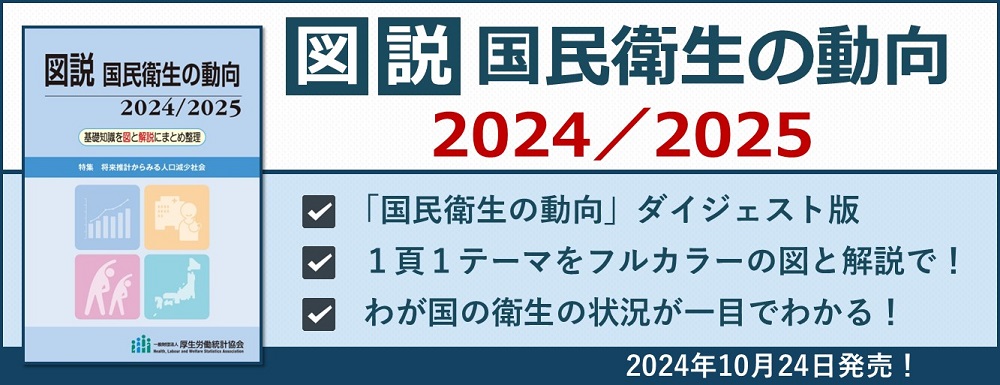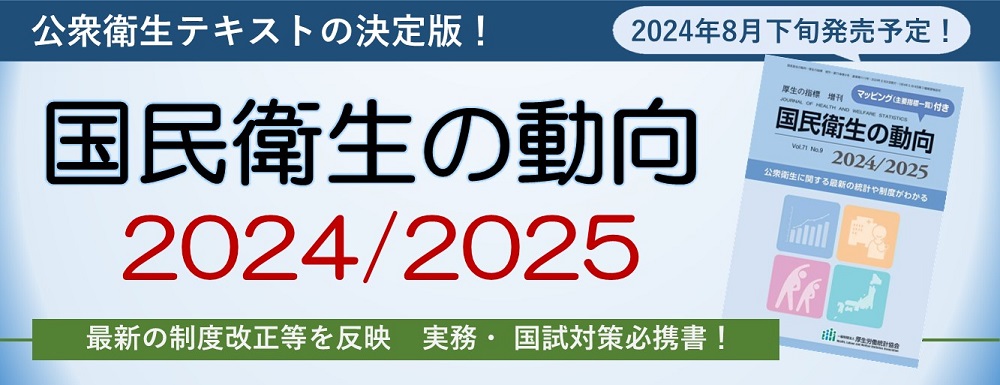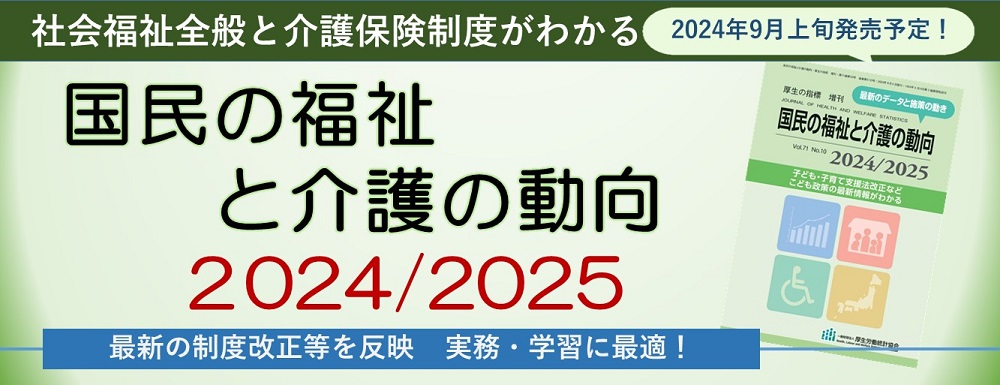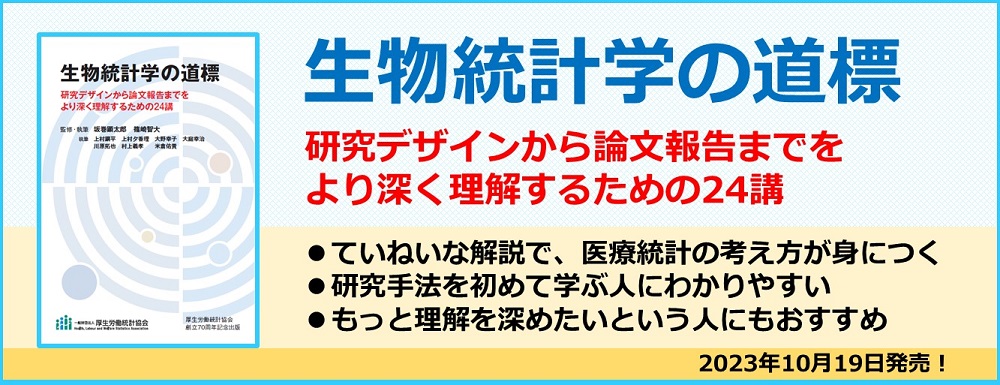令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第112回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午後 必修問題
▶午後1改題
令和4年(2022年)の0歳男児の平均余命はどれか。
- 78.1年
- 81.1年
- 84.1年
- 87.1年
▶午後2改題
健康日本21(第三次)における1日の塩分摂取量の目標値で正しいのはどれか。
- 5.0g
- 7.0g
- 9.0g
- 11.0g
▶午後3
循環式浴槽の水質汚染で発症するのはどれか。
- コレラ
- A型肝炎
- レジオネラ肺炎
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
▶午後4
国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。
- 1割
- 2割
- 3割
- 4割
▶午後5
看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
▶午後6
大泉門が閉鎖する時期に最も近いのはどれか。
- 6か月
- 1歳6か月
- 2歳6か月
- 3歳6か月
▶午後7
正期産の新生児が生理的体重減少によって最低体重になるのはどれか。
- 生後3〜5日
- 生後8〜10日
- 生後13〜15日
- 生後18〜20日
▶午後8
エリクソンが提唱する発達理論において、学童期に達成すべき心理社会的課題はどれか。
- 親密 対 孤立
- 自律性 対 恥・疑惑
- 勤勉性 対 劣等感
- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立 対 自我同一性〈アイデンティティ〉の拡散
▶午後9
家族成員の最少人数はどれか。
- 4人
- 3人
- 2人
- 1人
▶午後10
地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。
- 病気の治療
- 住民の健康診査
- 看護師免許申請の受理
- 専門的で広域的な健康課題への対応
▶午後11
副交感神経の作用で正しいのはどれか。
- 瞳孔散大
- 気管支拡張
- 心拍数の増加
- 消化液分泌の促進
▶午後12
心臓の刺激伝導系で最初の興奮部位はどれか。
- 洞房結節
- 房室結節
- His〈ヒス〉束
- Purkinje〈プルキンエ〉線維
▶午後13
成人の正常な赤血球の説明で正しいのはどれか。
- 球状の細胞である。
- 腎臓で破壊される。
- 寿命は約60日である。
- 酸素の輸送を担っている。
▶午後14
チアノーゼとは( )の絶対量が増加して5g/dL以上になり、皮膚や粘膜が紫から青紫色を示す状態のことをいう。
( )に入るのはどれか。
- ビリルビン
- ヘモグロビン
- ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉
- 脱酸素化ヘモグロビン〈還元ヘモグロビン〉
▶午後15
飛沫感染するのはどれか。
- 疥癬
- 破傷風
- デング熱
- インフルエンザ
▶午後16
モルヒネの副作用(有害事象)はどれか。
- 出血
- 難聴
- 便秘
- 骨髄抑制
▶午後17
上腕動脈で行う聴診法による血圧測定で適切なのはどれか。
- 成人では9〜10cm幅のマンシェットを用いる。
- マンシェットの下端と肘窩が重なるように巻く。
- マンシェットの装着部位と心臓が同じ高さになるようにする。
- マンシェットと腕の間に指が3、4本入る程度の強さで巻く。
▶午後18
グリセリン浣腸を準備する際の浣腸液の温度で適切なのはどれか。
- 20℃
- 30℃
- 40℃
- 50℃
▶午後19
不活動状態が持続することで生じるのはどれか。
- 廃用症候群
- 緊張病症候群
- 慢性疲労症候群
- シックハウス症候群
▶午後20
入浴の援助で正しいのはどれか。
- 入浴前後は水分制限をする。
- 入浴時の湯温は45℃とする。
- 脱衣室と浴室の温度差を小さくする。
- 浴室に入り、始めに浴槽に浸かるように促す。
▶午後21
成人の気道の異物除去を目的とするのはどれか。
- 胸骨圧迫
- 人工呼吸
- 頭部後屈顎先挙上法
- 腹部圧迫法〈Heimlich〈ハイムリック〉法〉
▶午後22
看護師が行う処置で滅菌手袋を使用すべきなのはどれか。
- 筋肉内注射
- 口腔内吸引
- ストーマパウチの交換
- 尿道カテーテルの挿入
▶午後23
静脈血採血の穿刺時の皮膚に対する針の適切な刺入角度はどれか。
- 15〜20度
- 35〜40度
- 55〜60度
- 75〜80度
▶午後24
成人の一次救命処置〈BLS〉における胸骨圧迫の速さ(回数)で正しいのはどれか。
- 40〜60回/分
- 70〜90回/分
- 100〜120回/分
- 130〜150回/分
▶午後25
腹部前面を図に示す。
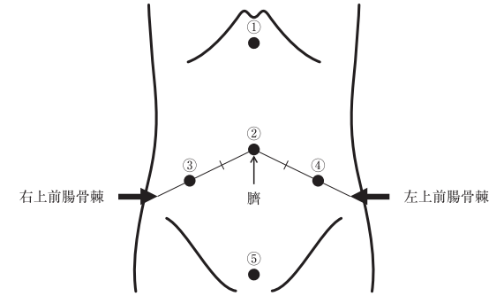
McBurney〈マックバーニー〉圧痛点はどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第112回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午前問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」と合わせてご活用ください。
▼第112回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午前 状況設定問題
▶次の文を読み91〜93の問いに答えよ。
Aさん(47歳、男性、会社員)は妻と2人暮らしで、自宅の室内で犬を飼っている。15年前に慢性糸球体腎炎と診断され、徐々に腎機能低下が認められたので、2年前から慢性腎不全のため血液透析療法を週3回受けている。今回、弟から腎臓の提供の申し出があり、生体腎移植の目的で入院した。入院3日、Aさんの生体腎移植手術は予定通り終了した。
▶午前91
Aさんの手術直後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。
- 尿量
- 血糖値
- 白血球数
- シャント音
▶午前92
Aさんは術前からタクロリムスなど複数の免疫抑制薬を服用している。Aさんは「移植したら免疫抑制薬を飲む必要があることは分かっているのですが、退院後は何に気を付ければよいですか」と看護師に質問した。
Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「犬は今まで通り室内で飼育できます」
- 「グレープフルーツは摂取しないでください」
- 「感染予防のため風疹のワクチン接種をしてください」
- 「薬を飲み忘れたときは2回分をまとめて服用してください」
▶午前93
Aさんは順調に回復し、移植後の拒絶反応もなく退院することになった。Aさんは「腎臓が悪くなってから気を付けないといけないことが多かったのですが、移植してこれまでの制約がなくなりますね」と話した。
Aさんの退院後の生活で継続が必要なのはどれか。
- 蛋白質の摂取制限
- 週3回の通院
- 水分の制限
- 体重の管理
▶次の文を読み94〜96の問いに答えよ。
Aさん(28歳、女性、美容師)はゴルフが趣味である。同居しているパートナーと1週前にゴルフに行った後から、顔面の紅斑、微熱、全身倦怠感および手指の関節痛が現れた。病院を受診したところ、全身性エリテマトーデス〈SLE〉と診断され入院した。Aさんは看護師に「これまで病気をしたことがなかったので、驚いています」と話した。
バイタルサイン:体温37.4℃、呼吸数18/分、脈拍64/分、整、血圧110/60mmHg。
血液所見:赤血球260万/μL、Hb9.0g/dL、白血球7,600/μL、血小板18万/μL、尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.8mg/dL、CRP0.7mg/dL、直接Coombs〈クームス〉試験陽性。
尿所見:尿蛋白(-)、尿潜血(-)。
神経学的検査:異常所見なし。
12誘導心電図:異常所見なし。
胸部エックス線写真:異常所見なし。
▶午前94
Aさんに生じている可能性が高いのはどれか。
- 心膜炎
- 溶血性貧血
- ループス腎炎
- 中枢神経ループス
▶午前95
Aさんはステロイドパルス療法の後、副腎皮質ステロイド薬の内服治療が開始された。入院3週ころから満月様顔貌がみられたため、外見の変化に気持ちが落ち込むようになった。
Aさんへの対応で適切なのはどれか。
- 気にする必要はないと励ます。
- パートナーの面会を制限する。
- 外見よりも病気の治療を優先すると説明する。
- 薬の量が減れば満月様顔貌は軽減すると説明する。
▶午前96
Aさんは外来で副腎皮質ステロイド薬の内服治療を継続することになった。Aさんは「病気を悪化させないために退院後はどのような生活がよいでしょうか」と看護師に質問した。
Aさんへの退院指導で適切なのはどれか。
- 「すぐに復職できます」
- 「避妊は必要ありません」
- 「身体を冷やさないでください」
- 「くもりなら屋外でゴルフができます」
▶次の文を読み97〜99の問いに答えよ。
Aさん(81歳、女性)は夫(86歳)と2人で暮らしている。高血圧症で内服治療をしているが、血圧のコントロールはできている。両眼に老人性白内障があり、老人性難聴のために補聴器を使用している。認知機能は問題なく、日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立している。1年前から両眼の羞明、霧視が強くなり、視力が低下して趣味の編み物ができなくなってきた。また、家の中を移動するときに小さな段差につまずいたりドアにぶつかるなど、歩行時の転倒の危険性が増えた。Aさんは自宅での生活を安全に送りたい、趣味を続けたいという希望があり、10日間程度の入院で両眼の超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術を行うことになった。
▶午前97
入院当日、病棟の看護師がAさんに対してパンフレットを用いて手術前オリエンテーションを行うことになった。
Aさんへのオリエンテーションの方法で適切なのはどれか。
- 耳元で大きな声で説明する。
- Aさんの身体に触れてから話しかける。
- 窓際の明るい場所でパンフレットを見せる。
- 手術後の注意点はパンフレットに赤色の太い文字で書く。
▶午前98
Aさんの手術は局所麻酔下で行われ、10分程度で終了した。手術中および手術直後のバイタルサインに問題はなく、病室に戻ってきた。Aさんは眼痛や頭痛、気分不快などの症状はなく、「無事に終わって良かった」と話している。
手術後のAさんへの説明で適切なのはどれか。
- 手術直後から点眼する。
- 洗顔は手術の翌日から行う。
- 手術後24時間はベッド上で安静にする。
- 医師の許可があるまでは頭を振る動作をしない。
▶午前99
手術後2日、Aさんは日中はベッドに横になって過ごしている時間が多い。夜間にAさんから看護師に「手術後はゆっくり眠れていません。どうしたらよいでしょうか」という訴えがあった。
Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 寝る前に温かい緑茶を飲むことを勧める。
- 日中はベッドから離れて過ごすことを促す。
- 眠れなくてもベッドに横になっていることを勧める。
- 夜はよく眠っているので様子をみましょうと伝える。
▶次の文を読み100〜102の問いに答えよ。
Aさん(75歳、男性)は妻(75歳)と2人暮らしで、15年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断された。7年前よりレボドパ〈L-dopa〉を1日3回内服している。Hoehn&Yahr〈ホーエン・ヤール〉重症度分類のステージⅣで、要介護2である。妻は腰痛のため毎日リハビリテーション目的で通院中である。妻の介護負担を軽減するため、Aさんは毎月10日間、介護老人保健施設の短期入所〈ショートステイ〉を利用している。今回は妻の腰痛が増強したため、Aさんは予定を早めて入所した。Aさんは握力が低下しているが、スプーンを使用し自力で食事を摂取している。食事中に姿勢が崩れることが多く、むせや食べこぼしがある。
▶午前100
看護師のAさんへの食事援助で正しいのはどれか。
- 頸部を後屈した体位にする。
- 座位時の体幹を安定させる。
- 食後に嚥下体操を実施する。
- こぼさずに摂取できるよう全介助する。
▶午前101
Aさんは社交的で短期入所中はいつも介護老人保健施設の利用者や職員と笑顔で会話していたが、今回は、会話中に急に表情がなくなり声が聞きとれないほど小さくなったり、手足の震えが出現することがあった。食後に薬を内服すると症状は改善するが、内服して2時間後には同じような症状が現れることがあった。
Aさんの症状はどれか。
- オンオフ現象
- ジスキネジア
- アナフィラキシー反応
- ウェアリングオフ現象
▶午前102
妻の腰痛が改善したため、Aさんは自宅に戻ることになった。Aさんは「妻に負担をかけないように自分で動けるようになりたい。自宅でできる運動や注意することを教えてください」と看護師に話した。
Aさんへの指導で適切なのはどれか。
- 「毎日30分間の階段昇降を行いましょう」
- 「歩行時に腕を大きく振りましょう」
- 「小刻みに歩くようにしましょう」
- 「毎日1km歩きましょう」
▶次の文を読み103〜105の問いに答えよ。
Aちゃん(2歳、男児)は両親、兄(5歳)の4人家族である。3日前から発熱が続くため、母親と一緒に外来を受診した。診察の結果、川崎病と診断され、個室に入院となり左手背に点滴静脈内留置針が挿入された。入院中は母親が希望し、Aちゃんに付き添っている。Aちゃんにγ-グロブリン療法とアスピリンの内服が開始されることになった。看護師がγ-グロブリン療法の開始のために訪室すると、Aちゃんは不機嫌にぐずって泣いている。
▶午前103
γ-グロブリン療法の開始に伴う看護師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。
- γ-グロブリン製剤の投与中もAちゃんと売店に行けると母親に伝える。
- 留置針の自己抜去防止のために右肘関節に抑制帯を使用する。
- 心負荷の軽減のためにAちゃんの経口水分摂取を制限する。
- 心電図モニターの装着を確認する。
- 留置針の刺入部を観察する。
▶午前104
Aちゃんの入院中、母親は一度も自宅に帰らずに付き添いを続けている。入院3日の朝に看護師が訪室したところ、母親が「夫から電話があって、Aの入院後、兄がほとんど寝ずに大泣きしているらしく、私は心配です」と話している。
母親への看護師の対応で適切なのはどれか。
- 病室内でAちゃんと兄を面会させてよいと伝える。
- Aちゃんのことに集中するべきであると伝える。
- 兄と関わる時間を持てるよう母親に帰宅を促す。
- 退院の可否を医師と相談すると伝える。
▶午前105
入院4日、Aちゃんは解熱し活気が出てきた。翌日、看護師がAちゃんを観察すると、手指の先端から皮膚が膜のように薄くむけていた。
この所見に対する看護師のアセスメントで適切なのはどれか。
- γ-グロブリン療法の副作用〈有害事象〉である。
- 皮膚のツルゴールが低下している。
- 川崎病の回復期の症状である。
- 皮膚科の受診が必要である。
▶次の文を読み106〜108の問いに答えよ。
Aさん(33歳、初産婦、会社員)は夫と2人で暮らしている。妊娠28週5日、夕方から下腹部に生理痛のような痛みを感じ、少量の性器出血があったため来院した。来院時、子宮口2cm開大、未破水、8分おきに20秒持続する子宮収縮があり、切迫早産と診断された。子宮収縮抑制薬(リトドリン塩酸塩)の点滴静脈内注射と安静による治療が開始された。
▶午前106
点滴を開始して30分後に看護師が訪室すると、AさんはFowler〈ファウラー〉位で休んでいた。
このときのAさんの状態で看護師が注意して観察すべき項目はどれか。
- 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉
- 血圧
- 呼吸数
- 脈拍
▶午前107
切迫早産の症状がなくなり、Aさんは妊娠35週0日で退院した。妊娠36週0日に妊婦健康診査のために来院した。ノンストレステスト〈NST〉を実施中に、「気分が悪い」とナースコールがあり看護師が訪れると、Aさんは仰臥位になっていた。
Aさんへの対応で看護師が最初に行うのはどれか。
- 医師に報告する。
- 血圧測定を行う。
- 左側臥位にする。
- 酸素吸入を行う。
▶午前108
Aさんは妊娠36週5日、8時に分娩が開始した。16時30分に子宮口全開大、16時35分に自然破水、18時30分に男児を出産した。分娩時出血量は350mL、児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後8点、5分後9点であった。
Aさんの分娩のアセスメントで適切なのはどれか。
- 早期産である。
- 異常出血である。
- 前期破水である。
- 新生児仮死である。
▶次の文を読み109〜111の問いに答えよ。
Aさん(34歳、初産婦)は妊娠39週6日に3,000gの女児を出産した。分娩後の母児の経過は順調である。
出生後12時間、看護師がAさんの児の観察を行った。児は活気がありバイタルサインは安定しており、排便が認められた。直接授乳を開始している。出生後の排尿回数は4回、排便回数は3回である。
▶午前109
便の写真を別に示す。
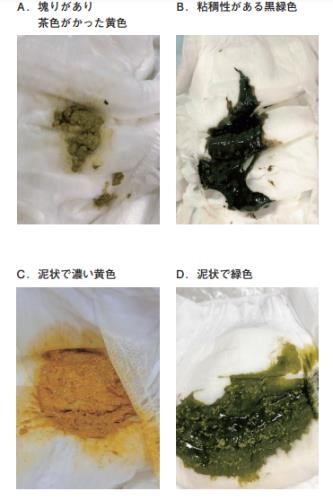
このときのAさんの児の便はどれか。
- A
- B
- C
- D
▶午前110
日齢2。Aさんの児の胎外生活への適応は順調に経過している。哺乳回数は1日8回。Aさんは母乳育児を希望しているが、児に乳頭を吸われると痛いと話しており、左右の乳頭に軽度の発赤が認められる。
このとき看護師が観察する項目で優先度が高いのはどれか。
- 児の体重減少率
- 乳汁の分泌状態
- 乳房の緊満状態
- ラッチオンの状態
▶午前111
日齢4。看護師がAさんの児を観察したところ、バイタルサインは、体温(直腸温)37.3℃、呼吸数55/分、心拍数134/分。経皮ビリルビン20.0mg/dLであった。
Aさんの児の状態で医師に報告が必要なのはどれか。
- 経皮ビリルビン値
- 呼吸数
- 心拍数
- 体温
▶次の文を読み112〜114の問いに答えよ。
Aさん(20歳、女性)は境界性人格〈パーソナリティ〉障害の診断を受け、精神科外来に通院中である。ある日、人間関係のトラブルから処方されていた睡眠薬を過量服薬して自殺企図をしたところを家族に発見され、救命救急センターに搬送された。
▶午前112
Aさんは救急外来で治療を受け会話ができるまでに回復した。
Aさんへの看護師の最初の対応で適切なのはどれか。
- 過量服薬した場面の振り返りを促す。
- 現在の希死念慮の有無について確認する。
- 大量の睡眠薬を飲まずに残していた理由を追及する。
- Aさんと看護師の間で二度と過量服薬しないと約束する。
▶午前113
Aさんは身体的な治療を受けた後、精神科病棟に入院することになった。入院3日の22時、Aさんがハサミを貸してほしいとナースステーションに来た。日勤の看護師がいる時間帯のみ付き添いでハサミの貸出が可能という主治医からの指示を伝えると「看護師Bは貸してくれたのに。こんなひどい対応をする看護師はあなただけだ」と話し、その場を動かない。
このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。
- ハサミの使用目的を聞く。
- 看護師付き添いのもとハサミを貸し出す。
- 看護師Bが誤った対応をしたと説明する。
- Aさんの行動が心配なので貸し出せないと伝える。
▶午前114
入院1週、Aさんは看護師ごとに言動や態度を変えることが多く、病棟ではAさんに対して共感を示す看護師と、拒否的な態度を示す看護師に分かれてしまった。そのため、病棟の看護師はチームでの対応についてカンファレンスを行った。
Aさんへの看護師のチームとしての対応で適切なのはどれか。
- Aさんと看護師が関わる頻度を減らす。
- Aさんに共感を示す看護師に担当を固定する。
- Aさんに対する感情を看護師同士で表出しないように統一する。
- Aさんの行動が患者―看護師関係にもたらす影響について評価する。
▶次の文を読み115〜117の問いに答えよ。
Aちゃん(6歳、男児)は父親(50歳、会社員)、母親(48歳)、姉(11歳)と4人で暮らしている。Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで身体障害者手帳(肢体不自由1級)が交付されている。喀痰吸引、胃瘻による経管栄養が必要で、訪問看護を週に2回利用している。まばたきの回数で「はい」と「いいえ」の意思表示はできるが、視線や上肢の動きには誤動作もあり、構音障害もあるため家族以外では意思の判断が難しい。また、手指での細かい操作はできない。Aちゃんは次年度から姉と同じ小学校の特別支援学級に通い、通常の学級の児童と交流の予定がある。
▶午前115
入学時に担任がAちゃんの意思を確認する方法で最も適切なのはどれか。
- 五十音の文字盤を用いてAちゃんが指でさした文字を文字ずつ読み取る。
- 視線で入力できる意思伝達装置を用いてAちゃんに文字を入力してもらう。
- 閉じた質問〈closed question〉をしてAちゃんのまばたきの回数を確認する。
- 感情を絵で表現したカードを見せてAちゃんが指でさしたカードを確認する。
▶午前116
Aちゃんが小学校に入学して6か月が経過した。小学校への送迎は母親が行っており、学内での喀痰吸引や経管栄養の注入は小学校に配置されている看護師が行っている。Aちゃんは体調も安定しており、小学校での生活にも慣れてきた。Aちゃんの母親は「夫は朝早く出勤し、長女もまだ小さく、Aを小学校に連れて行くまで忙しくて大変です」と訪問看護師に話した。訪問看護師は保健所の保健師に相談し、Aちゃん宅で家族も含めてAちゃんが利用できる支援サービスを検討することにした。
Aちゃんと家族に利用を勧める支援サービスで適切なのはどれか。
- 児童発達支援
- 重度訪問介護
- 放課後等デイサービス
- 短期入所〈ショートステイ〉
▶午前117
Aちゃんは入学して1度も入院することなく2年生になった。Aちゃんの母親はケアに必要な物品を学校の看護師に渡す際に「Aは学校に通うようになり、お友達が増えて本当によかったと思います。それに比べて私は仕事をしていないし、Aに友達ができた喜びや日々の苦労を理解してもらえる友達がいません。Aの同級生の親には年齢が近くて話しやすい人がいません」と話した。
Aちゃんの母親への提案で最も適切なのはどれか。
- 「学校の行事に参加してみませんか」
- 「短時間でも仕事を始めてはいかがですか」
- 「お姉ちゃんのお友達の親に話しかけてみませんか」
- 「障害のある子どもを持つ家族の会に参加してみませんか」
▶次の文を読み118〜120の問いに答えよ。
Aさん(57歳、男性、無職)は妻(55歳、会社員)と2人で暮らしている。Aさんは、飲酒が原因で仕事での遅刻や無断欠勤が続いたため1年前に職場を解雇された。その後も朝から自宅で飲酒する生活が続き、体調が悪化したため受診し、アルコール性肝硬変とアルコール依存症と診断された。医師から断酒を指導されていたが実行できず通院していなかった。
Aさんは最近、倦怠感が強く食欲がなく、1週前から飲酒もできなくなった。妻に付き添われて受診した際、外来のトイレで吐血し倒れ食道静脈瘤破裂と診断され入院した。
身体所見:呼びかけに応じるが反応が遅い。腹水や浮腫はない。手指の振戦はない。体温37.0℃、呼吸数22/分、脈拍98/分、整、血圧92/50mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。
▶午前118
入院時、Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 上半身を挙上する。
- 身体を側臥位にする。
- 頭部の冷罨法を行う。
- 酸素療法の準備をする。
▶午前119
入院当日、Aさんは緊急に内視鏡的治療を受けた。入院7日、Aさんは食道静脈瘤の治療のため、食道静脈瘤硬化療法を受けることになった。治療前のバイタルサインは、体温36.7℃、呼吸数16/分、脈拍72/分、整、血圧126/70mmHgである。検査所見は、血小板15万/μL、プロトロンビン時間〈PT〉10秒85%である。入院後は吐血していない。
Aさんが食道静脈瘤硬化療法を受けた直後に注意すべき症状はどれか。
- 下血
- 胸部痛
- 皮下出血
- 手指の振戦
▶午前120
Aさんは食道静脈瘤硬化療法を終えて、アルコール依存症の治療を受けるために精神科病院に転院した。
転院して2か月、病棟ではAさんの退院に向けた話し合いが進められている。Aさんは「退院した後にお酒をやめられるか自信がない。体力が落ちており、何もしていないとお酒を飲んでしまいそうです」と悩みを打ち明けた。
Aさんへの看護師の声かけで適切なのはどれか。
- 「断酒をする意思を強く持ちましょう」
- 「肝硬変があるので、今は安静が必要です」
- 「入院中も飲酒をやめられているので大丈夫です」
- 「アルコールの問題で悩んでいる人たちとの話し合いに参加してみましょう」
資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第112回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
「国民衛生の動向」は、毎年わが国の衛生の状況や保健行政の動向を解説したものとして、昭和24年の創刊以来、公衆衛生テキストの決定版として長年ご愛用いただいています。とくに本誌では、最新の衛生を取り巻く制度の解説や人口・健康状況などの統計が網羅されており、医療関係者の国家試験対策のテキストとしても広く活用されているところです。
当ページでは、医療職の国家試験の中でもご利用者の多い看護師国家試験の受験者向けに、最新の「国民衛生の動向2024/2025」(2024年8月27日発売)がカバーする看護師国家試験の過去問をピックアップし、本誌の該当箇所を示します。問題を解きながら不明な部分を本誌で確認し、学習効率の向上にご活用下さい。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
看護師国家試験について
最新の試験日程や手続き等の情報は、看護師国家試験の施行(厚生労働省)をご確認下さい。
看護師国家試験は昭和25年(1950年)から開始し、最新では令和7年(2025年)2月に114回目の試験が実施されました。
過去10年間の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりです。
|
|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 114回(2025年) | 63,131人 | 56,906人 | 90.1% |
| 113回(2024年) | 63,301人 | 55,557人 | 87.8% |
| 112回(2023年) | 64,051人 | 58,152人 | 90.8% |
| 111回(2022年) | 65,025人 | 59,344人 | 91.3% |
| 110回(2021年) | 66,124人 | 59,769人 | 90.4% |
| 109回(2020年) | 65,568人 | 58,513人 | 89.2% |
| 108回(2019年) | 63,603人 | 56,767人 | 89.3% |
| 107回(2018年) | 64,488人 | 58,682人 | 91.0% |
| 106回(2017年) | 62,534人 | 55,367人 | 88.5% |
| 105回(2016年) | 62,154人 | 55,585人 | 89.4% |
合格率は9割前後と国家試験としては高いですが、必修問題50点中40点以上、一般問題・状況設定問題250点中約160点(毎年変動)以上という明確な合格基準があり、対策をせずに臨んで合格することは難しいものとなっています。
看護師国家試験の出題基準は、平成12年の公表以来、保健師助産師看護師国家試験出題基準改定部会で検討を行い、改定を重ねてきており、令和5年実施の試験からは、「保健師助産師看護師国家試験出題基準 令和5年版」が適用されています。出題基準では、①必修問題、②人体の構造と機能、③疾病の成り立ちと回復の促進、④健康支援と社会保障制度、⑤基礎看護学、⑥成人看護学、⑦老年看護学、⑧小児看護学、⑨母性看護学、⑩精神看護学、⑪在宅看護論/地域・在宅看護論、⑫看護の統合と実践の12の領域が設けられ、それぞれ幅広い出題範囲が設定されています。
当サイトを活用した勉強方法
「看護師国家試験に出る国民衛生の動向」では、最新の第113回試験から第102回試験までの12年分の過去問題をすべて解説付きで掲載していているほか、統計、法律、感染症、介護などテーマ別に整理したまとめページも掲載しています。
扱っている問題数は1000問を超えており、やみくもに手を付けてしまうとしっかり理解できないまま学習が行き詰まってしまうおそれがあります。以下に効率的な学習モデルとして一例を示します。
① 必修問題をマスターする
看護師国家試験は、重要な基本的事項を問う必修問題(50問50点)と、一般問題(130問130点)・状況設定問題(60問120点)に分かれます。
必修問題は、基本的に50問中40問以上(80%以上)正答しなければ不合格となる絶対的な合格基準が設定されており、必修問題の点数が足りずに不合格になる、いわゆる「必修落ち」だけは避けなければなりません。
必修問題として用いられる問題の範囲は限られており、過去10年程度の出題と同一または類似の問題が約半数を占めているので、まず過去に出題された必修問題をマスターすることが最も重要となります。
当サイトでは保健師助産師看護師国家試験出題基準に対応して、過去12年の必修問題を以下の16ページに網羅しています。
- 健康の定義と理解
- 健康に影響する要因
- 看護で活用する社会保障
- 看護における倫理
- 看護に関わる基本的法律
- 人間の特性
- 人間のライフサイクル各期の特徴と生活
- 看護の対象としての患者と家族
- 主な看護活動の場と看護の機能
- 人体の構造と機能
- 徴候と疾患
- 薬物の作用とその管理
- 看護における基本技術
- 日常生活援助技術
- 患者の安全・安楽を守る看護技術
- 診療に伴う看護技術
いずれも、まずポイントを解説した後、関連する過去問題を掲載しており、初学者でもインプットとアウトプットを繰り返しながら、十分に理解と実践が図れるように構成しています。
これを短期間で少なくとも2~3週し、不安があればさらに回数を重ねて過去の必修問題はすべて解けるという自信を身に付けて下さい。
② 頻出分野を理解する
看護師国家試験で最も出題されるテーマの一つが「健康支援と社会保障制度」です。
これは人口や世帯、健康状態、医療費などの各種統計や、保健・福祉・介護など社会保障を支える法律などが含まれており、暗記量も多く受験生の苦手とする分野です。
さらに、最近の統計資料や制度改正なども踏まえた上で出題されるため、知識をアップデートしなければ誤答となることも少なくありません。
当サイトでは、「国民衛生の動向」がカバーする頻出分野ごとに、以下の4ページを掲載しています。
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の感染症問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめ
いずれも最新の知識が必要であり、一通り確認することをおすすめします。
特に統計問題は一回で数値等を覚えることは難しいので、複数回繰り返して着実に定着させて下さい。
③ 実践形式で問題を解く
必修問題や頻出分野を理解した後は、実践形式で過去問題を数多く解いて、解説を読みながらさらに知識量を増やしていく必要があります。
当サイトでは、最新の第113回試験(2024年2月)までの12年分の全問題と解説を掲載しています。少なくとも5年分、できれば10年分以上挑戦してください。
第113回(2024年)
第112回(2023年)
第111回(2022年)
第110回(2021年)
第109回(2020年)
第108回(2019年)
第107回(2018年)
第106回(2017年)
第105回(2016年)
第104回(2015年)
第103回(2014年)
第102回(2013年)
④ 参考書等で周辺知識を広げる
看護師国家試験では過去問対策が最重要ですが、当然過去に出題されていない統計数値、新規法律、医学用語なども多く出題されます。
そのため、講義・演習で使った「国民衛生の動向」等の教科書・参考書や資料・ノート、「レビューブック」「クエスチョン・バンク」(メディックメディア)などの国家試験対策書、「看護roo!国試」などスマートフォン向け学習アプリ、YouTube等の学習チャンネルなど様々な媒体を活用して周辺知識を確実に定着させ、点数の上乗せを図り、合格へさらに近づくことが大切です。
看護師国家試験過去問題PDF
厚生労働省が公表している過去10年間の問題、正答のPDFの一覧です。
|
第113回 (2024年) |
午前問題別冊 | 正答 | |
|
第112回 (2023年) |
午前問題別冊 | 正答 | |
|
第111回 (2022年) |
午前問題別冊 | 正答 | |
|
第110回 (2021年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第109回 (2020年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第108回 (2019年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第107回 (2018年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第106回 (2017年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第105回 (2016年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第104回 (2015年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
医療職国家試験に出る国民衛生の動向
看護師資格と合わせて取得を目指す方も多い保健師国家試験や助産師国家試験のほか、医師、薬剤師国家試験の統計問題など「国民衛生の動向」が対応する問題とポイントを掲載しています。
内容も重なる部分が多く、知識の定着や予想問題として活用することをおすすめします。
図説 国民衛生の動向
 |
『図説 国民衛生の動向』は、「国民衛生の動向」の図説ダイジェスト版です。「国民衛生の動向」の内容に沿って、1ページ1テーマで、フルカラーの図表とともに要点を絞って解説しています。
看護師国家試験の内容も広くカバーしていますので、記述量の多い「国民衛生の動向」の手軽な副読本としても活用できます。
医療職のための統計セミナー
厚生労働統計協会では、看護師等の医療職の皆様のキャリアアップのために、研究発表や論文作成に必要な統計知識を実践的に学んでいただくオンラインセミナーを、毎年数回開催しています。
詳細はこちらをご確認下さい。
「国民衛生の動向」は公衆衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。保健師国家試験では様々な統計調査を基にした、最新の数値を問う問題が毎年必ず出題されるので、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。
このページでは、第110回(2024年)から第101回(2015年)までの10年間の保健師国家試験に出題された統計問題をピックアップし、最新の数値とともに「国民衛生の動向」の参照箇所を示します。これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる力を身に付けていただければ幸いです。
なお、問題と回答については、最新の統計の数値に合わせて改題を行っています。数値は2025年2月に実施される第111回試験に沿った「国民衛生の動向2023/2024」内に掲載している年次のものになります。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
統計別問題目次
第1編:社会保障の動向と衛生行政の体系
- 社会保障費用統計
- 地域保健・健康増進事業報告
- 保健師活動領域調査
第2編:衛生の主要指標
- 国勢調査・人口推計
- 国民生活基礎調査
- 将来推計人口
- 労働力人口
- 人口動態統計
- 患者調査
- 生命表
第3編:保健と医療の動向
- 国民健康・栄養調査
- 歯科疾患実態調査
第4編:医療提供体制と医療保険
- 医療従事者・医療施設数
- 国民医療費
第5編:保健医療を取り巻く社会保障
- 福祉行政報告例(児童虐待)
- 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査
第7~10編:生活環境・労働衛生・学校保健
- 食中毒統計調査
- 労働災害・業務上疾病
- 労働安全衛生調査(実態調査)
- 学校保健統計調査
- 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
社会保障費用統計
第1編1章 1.5〕社会保障の状況 p16~17
社会保障給付費〈令和2年度〉
- 令和2年度(2020年度)の社会保障給付費は132.2兆円と毎年増加を続けており、国民1人当たりでみると104.8万円となっている。
- 社会保障給付費を部門別にみると、年金が55.6兆円(42.1%)と最も多く、次いで医療が42.7兆円(32.3%)、福祉その他が33.9兆円(25.6%)となっている。
▶106回午後34改題
令和2年度(2020年度)の社会保障給付費で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 医療給付費が最も多くを占める。
- 雇用保険の失業給付が含まれる。
- 給付総額は年間300兆円を超える。
- 給付総額は前年度よりも減少している。
- 国民1人あたりの給付費は約100万円である。
地域保健・健康増進事業報告
第1編2章 3.一般衛生行政の活動 p24~25
調査項目
地域保健・健康増進事業報告は、全国の保健所・市区町村を対象に、地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする調査である。
【地域保健事業】
①母子保健、②健康増進、③歯科保健、④精神保健福祉、⑤エイズ、⑥予防接種、⑦職員の配置状況
【健康増進事業】
①健康診査、②歯周疾患検診・骨粗鬆症検診、③健康教育、④健康相談、⑤訪問指導、⑥がん検診、⑦肝炎ウイルス検診
▶110回午後26
厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。
- 介護保険施設
- 企業および事業所
- がん診療連携拠点病院
- 保健所および市区町村
- 病院、療養病床を有する診療所
▶105回午前39
地域保健・健康増進事業報告で把握されるのはどれか。2つ選べ。
- 糖尿病の総患者数
- エイズに関する相談件数
- 退院患者の平均在院日数
- 乳児の健康診査の受診率
- 脳血管疾患の年齢調整死亡率
保健師活動領域調査
第1編2章 5.保健師の活動 p25~27
保健師の活動状況
令和4年(2022年)の常勤保健師を就業場所別にみると以下のとおりである。
- 都道府県:5,675人(14.9%)
- 保健所設置市:9,808人(25.8%)
- 特別区:1,563人(4.1%)
- 市町村:20,957人(55.1%)
また、活動項目別に保健師一人当たりの平均活動時間数の割合をみると、都道府県では「健康危機管理」が最も高く、保健所設置市・特別区、市町村では「直接対人支援」が最も高い。
▶108回午前2改題
令和4年度(2022年度)の保健師活動領域調査で正しいのはどれか。
- 保健師の就業場所で最も多いのは市町村である。
- 保健所設置市で働く常勤保健師は地方自治体における保健師全体の3割を超えている。
- 都道府県保健所に所属する保健師の活動項目別の活動時間割合は「直接対人支援」が最も多い。
- 市町村保健師の活動項目別の保健師1人当たりの平均時間数は「施策管理・業務及び組織マネジメント」が最も長い。
国勢調査・人口推計
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
人口静態統計
- 人口静態はある時点における人口や世帯、年齢別状況などの静止した姿を指す。
- 総務省統計局が実施する国勢調査はその主要統計で、5年に1回実施される全数調査(悉皆調査)である。
▶110回午後35
国勢調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 3年ごとに実施する。
- 人口静態を把握する。
- 厚生労働省が実施する。
- 調査区を無作為抽出する。
- 世帯員と世帯について調査を実施する。
総人口・年齢3区分別人口〈令和4年〉
- 総人口は1億2495万人(男6076万人・女6419万人)で、2010年ころから減少傾向にある。
- 年齢3区分別に人口構成割合をみると、年少人口(0~14歳)割合が11.6%、生産年齢人口(15~64歳)割合が59.4%、老年人口(65歳以上)割合が29.0%となっている。少子高齢化により、年少人口割合と生産年齢人口割合は減少傾向、老年人口割合は増加傾向にある。
▶101回午後2改題
日本の令和4年(2022年)の人口について正しいのはどれか。
- 総人口は前年より増加している。
- 出生数は70万人を超えている。
- 年少人口の割合は10%以下である。
- 世界で人口の多い国上位5位以内である。
人口指数〈令和4年〉
●年少人口指数=19.5(低下傾向)
:年少人口÷生産年齢人口×100
●老年人口指数=48.8(上昇傾向)
:老年人口÷生産年齢人口×100
●従属人口指数=68.4(上昇傾向)
:(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100
●老年化指数=249.9(上昇傾向)
:老年人口÷年少人口×100
▶107回午後28
従属人口指数はどれか。
- 老年人口÷総人口×100
- 老年人口÷生産年齢人口×100
- (年少人口+老年人口)÷総人口×100
- (年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100
- 老年人口÷(年少人口+生産年齢人口)×100
▶102回午前19
老年化指数はどれか。
- (老年人口÷総人口)×100
- (老年人口÷年少人口)×100
- (老年人口÷生産年齢人口)×100
- {(老年人口÷年少人口)÷生産年齢人口}×100
▶105回午前38
日本の人口に関する指標のうち、平成23年(2011年)以降、増加傾向にあるのはどれか。2つ選べ。
- 総人口
- 老年化指数
- 従属人口指数
- 年少人口割合
- 生産年齢人口割合
国民生活基礎調査
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
調査の概要
▶106回午前30
全国から無作為抽出された世帯及び世帯員を対象として行われる調査はどれか。
- 患者調査
- 人口動態調査
- 食中毒統計調査
- 学校保健統計調査
- 国民生活基礎調査
世帯の状況
令和3年(2021年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に以下のとおりである。
①単独世帯:29.5%
②夫婦と未婚の子のみの世帯:27.5%
③夫婦のみの世帯:24.5%
④ひとり親と未婚の子のみの世帯:7.1%
⑤三世代世帯:4.9%
▶107回午後1改題
A市の世帯構造別にみた世帯の割合を図に示す。

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査に基づく全国の割合と比較して、A市が高いのはどれか。2つ選べ。
- 単独世帯
- 夫婦のみの世帯
- 夫婦と未婚の子のみの世帯
- ひとり親と未婚の子のみの世帯
- 三世代世帯
世帯数の推移
- 近年の世帯割合の推移をみると、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」が増加傾向、「夫婦と未婚の子のみの世帯」と「三世代世帯」が減少傾向にある。
- こうした世帯構造の変化を受けて、令和3年(2021年)の平均世帯人員は2.37人と減少が続いている。
▶104回午後28改題
平成22年(2010年)から令和3年(2021年)における日本の社会情勢の変化で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 完全失業率の増加
- 老年化指数の低下
- 平均世帯人員の減少
- 社会保障給付費の減少
- 65歳以上の雇用者数の増加
将来推計人口
第2編1章 1.4〕将来推計人口 p42~43
人口・世帯の将来推計
- 日本の将来推計人口(平成29年推計)によると、総人口は令和35年(2053年)には1億人を割り、令和47年(2065年)には8808万人になると推計されている。
- 65歳以上の老年人口割合の推計では、令和7年(2025年)には30.0%を超え、令和22年(2040年)には35.3%になると推計されている。
▶102回午前30改題
日本の令和22年(2040年)の推計について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 総人口が1億人を下回る。
- 75歳以上の高齢者が2,000万人を超える。
- 総人口のおよそ3人に1人が65歳以上になる。
- 世帯主が65歳以上の世帯における単独世帯の割合が50%を超える。
労働力調査
第2編1章 3.労働力人口 p48~49
労働力人口(令和4年)
- 労働力人口とは15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計で、令和4年(2022年)平均で6,902万人である。性別にみると、男性は3,805万人(55.1%)、女性は3,096万人(44.9%)で、男性は前年から減少したが、女性は増加が続いている。
- 女性の年齢階級別労働力率をみると、その特徴として子育て期に当たる30歳代に労働力率が低下し、20歳代と40歳代をピークとするM字カーブが挙げられる(近年は緩和傾向)。
▶104回午前4改題
令和4年(2022年)の労働力調査について正しいのはどれか。
- 女性の労働力人口は前年に比べ減少した。
- 女性の雇用形態は正規の雇用が約6割である。
- 労働力人口の総数に占める女性の割合は約45%である。
- 女性雇用者数に占める割合で最も多い産業は製造業である。
▶109回午前3改題
令和4年(2022年)の労働力調査における日本の女性の労働で正しいのはどれか。
- 就業者は前年に比べ減少している。
- 労働力人口の総数の約6割を占めている。
- 年齢階級別労働力率では40~44歳が最も高い。
- 非正規の雇用形態はパート・アルバイトが最も多い。
▶105回午前11改題
令和4年(2022年)の女性の労働に関する説明で正しいのはどれか。
- 育児休業取得率は90%を超えている。
- 労働力人口比率は60%を超えている。
- 30歳代の就業率は40歳代よりも低い。
- 平均勤続年数は20年前よりも短くなっている。
その他雇用の状況
- 完全失業者・完全失業率は、平成22年(2010年)の334万人・5.1%から低下傾向にあり、令和4年(2022年)は179万人・2.6%となっている。
- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は、平成2年(1990年)には19.1%であったが上昇を続け、令和4年(2022年)には36.9%となっている。
▶103回午前3改題
日本の社会格差を示す指標の過去20年間の推移について正しいのはどれか。
- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は減少している。
- 相対的貧困率は低下している。
- 完全失業率は低下している。
- ジニ係数は低下している。
人口動態統計
第2編2章 人口動態 p51~69
調査の概要
▶102回午後34
人口動態統計に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 出生
- 婚姻
- 妊娠
- 転出
- 入院
▶105回午後32
人口動態統計の情報を用いて算出を行う指標はどれか。2つ選べ。
- 受療率
- 婚姻率
- 生活影響率
- 年少人口指数
- 合計特殊出生率
出生に関する統計
- 令和4年(2022年)の出生数は77.1万人、人口千対の出生率は6.3と減少が続いている。
- 15~49歳の女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は1.26で、過去最低であった平成17年(2005年)と並んでいる。
- 母の年齢階級別に出生率をみると30~34歳が最も高い。
- 母の年齢別出生率を女児だけについて合計した総再生産率は0.64、さらに女児の死亡を見込んだ純再生産率は0.63となっている(令和3年)。
▶106回午前29
人口動態統計で、人口1,000対で表すのはどれか。
- 出生率
- 純再生産率
- 総再生産率
- 周産期死亡率
- 合計特殊出生率
▶110回午前19
合計特殊出生率の算出方法で正しいのはどれか。
- 出生数を人口で除し、1,000を乗ずる。
- ある年齢の母の出生数を同年齢の女性人口で除し、1,000を乗ずる。
- 母の年齢別出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。
- 母の年齢別女児出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。
▶107回午前33改題
令和4年(2022年)の日本における出生の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 出生順位別構成割合は第1子が50%を上回っている。
- 母の年齢別にみた出生率は30~34歳が最も高い。
- 都道府県別合計特殊出生率は沖縄県が最も低い。
- 出生率は8.0(人口千対)を下回っている。
- 純再生産率は1を超えている。
死因統計の分類
- 人口動態調査における死因統計の分類は、世界保健機関(WHO)が作成する国際疾病分類(ICD)に基づいている。
- ICDは医学の進歩等に応えて一定期間を置いて修正が行われ、近年では平成7年(1995年)からICD-9に代わりICD-10が、平成18年(2006年)からICD-10(2003年版)が、平成28年(2016年)からICD-10(2013年版)準拠が適用されている。
▶105回午後21
国際疾病分類〈ICD〉に基づいた統計が含まれるのはどれか。
- 国勢調査
- 人口動態調査
- 医療施設動態調査
- 国民生活基礎調査
- 国民健康・栄養調査
▶102回午後22・107回午前17類問
国際疾病分類〈ICD〉について正しいのはどれか。
- 日本の死因統計では平成7年(1995年)にICD-10が採用された。
- 患者調査での疾病分類には用いられない。
- 各種疾病の治療指針が示されている。
- 国際疫学会が改訂を行っている。
主な死因別の死亡率(令和4年)
▶108回午前29改題・101回午後26類問
日本の主な死因別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移を図に示す。

心疾患はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
▶102回午後20改題
脳血管疾患について正しいのはどれか。
- 年齢調整死亡率は増加している。
- 脳出血の最大の危険因子は糖尿病である。
- 脳梗塞よりくも膜下出血による死亡数が多い。
- 令和4年(2022年)の死因順位は第4位である。
▶104回午前32改題
日本の死因別死亡率の年次推移を図に示す。

説明として正しいのはどれか。
- 縦軸の死亡率は年齢を調整した値である。
- 死因Aが上昇傾向にある主な理由は野菜摂取量の減少である。
- 死因Bの平成7年の急激な低下は国際生活機能分類(ICF)改訂の影響である。
- 死因Cが低下傾向にある主な理由は血圧の管理である。
- 死因Dが低下傾向にある主な理由は食生活の見直しである。
年齢階級別にみた死因第1位(令和4年)
▶110回午後25改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位はどれか。
- 自殺
- 肺炎
- 心疾患
- 悪性新生物
- 先天奇形、変形及び染色体異常
▶109回午前4改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における年齢階級とその死因第1位の組合せで正しいのはどれか。
- 1~4歳――インフルエンザ
- 5~9歳――悪性新生物〈腫瘍〉
- 10~14歳――不慮の事故
- 15~19歳――心疾患
▶103回午後25改題
令和4年(2022年)の日本における各年代と年代別死因第1位の組合せで正しいのはどれか。
- 20歳代―自殺
- 30歳代―悪性新生物〈腫瘍〉
- 40歳代―心疾患
- 50歳代―脳血管疾患
- 60歳代―肺炎
▶107回午前30改題
令和4年(2022年)の人口動態統計月報年計における性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合を示す。

自殺はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
▶109回午後27改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における20歳以上の年齢別死亡原因を以下に示す。

不慮の事故はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
悪性新生物〈腫瘍〉による死亡(性・部位別)〈令和4年〉
- 令和4年(2022年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.6万(男22.3万人・女16.3万人)である。
- 部位別にみると、総数および男では気管、気管支及び肺が、女では大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。
▶107回午前24
成人男性の部位別にみた悪性新生物の年齢調整死亡率の推移のグラフを示す。

Aの一次予防として正しいのはどれか。
- 肥満予防
- 減塩の推奨
- 野菜の摂取
- 受動喫煙防止
- 節度ある飲酒
自殺の状況(令和4年)
- 自殺による死亡数は2.1万人(男1.4万人・女0.7万人)で、上記のとおり10~39歳の各階級で死因の第1位となっている。自殺対策基本法などの取り組みにより、平成22年以降は自殺者数・率ともに減少傾向を示している。
- 性・年齢階級別に自殺死亡数をみると、男女ともに5歳階級別では「50~54歳」、10歳階級別では「50~59歳」が最も多い。
- 自殺者の特定された原因・動機をみると(複数回答)、健康問題が12,774人と最も多く、家庭問題(4,775人)、経済・生活問題(4,697人)と続く(警察庁)。
▶106回午後29改題
令和4年(2022年)の日本の人口動態統計における自殺死亡で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 男性の死亡率は女性よりも高い。
- 20〜24歳の死因の第1位である。
- 死因順位別死亡数は第5位である。
- 自殺死亡率は10年前よりも増加している。
- 男性の死亡率が最も高い年齢階級は40〜44歳である。
不慮の事故
令和3年(2021年)の年齢階級別にみた子どもの不慮の事故の原因の第1位は以下のとおりである。
0歳:窒息
1~4歳:溺死及び溺水
5~9歳:交通事故
10~14歳:交通事故
▶110回午前24改題
令和3年(2021年)の人口動態統計で、子どもの不慮の事故による年齢別死因の割合についてのグラフを以下に示す。

窒息はどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
妊産婦死亡
- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。
- 妊産婦死亡率(出産(出生+死産)10万対)について、戦後は諸外国と比べて著しく高く、昭和35年(1960年)には117.5であったが、昭和40年(1965年)には80.4、昭和45年(1970年)には48.7、昭和50年(1975年)には27.3と急激に低下していき、令和3年(2021年)には2.5と、諸外国に比べて極めて低率となっている。
▶110回午前30
先進諸国(アメリカ合衆国、イギリス、スウェーデン、フランス、日本)における妊産婦死亡率の推移のグラフを別に示す。
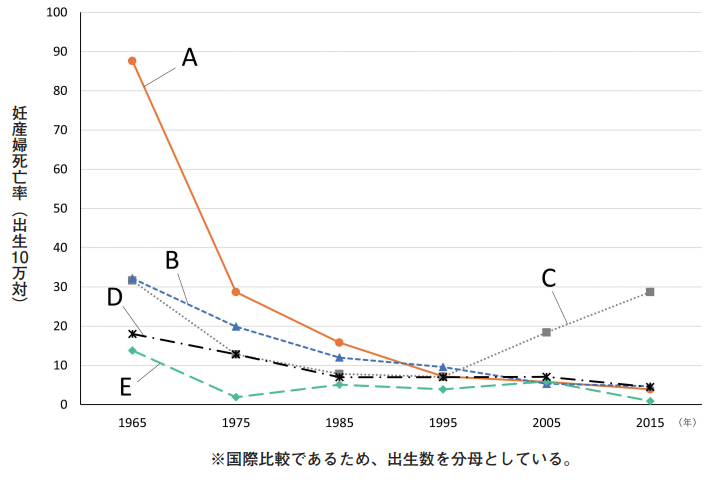
日本はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
患者調査
第2編4章 2.受療状況 p76~79
調査の概要
- 患者調査は、全国の医療施設(病院、一般診療所、歯科診療所)を利用する患者の傷病などの状況を把握するため、3年に1度実施されている。
- 把握する内容は、調査日に全国の医療施設で受療した推計患者数や、人口10万人に対する推計患者数である受療率、退院患者の平均在院日数、継続的に医療を受けている患者を含めた傷病別の総患者数などである。
▶103回午後26
患者調査で把握できるのはどれか。
- 有訴者率
- 死亡率
- 致命率
- 有病率
- 受療率
▶107回午前16
患者調査で正しいのはどれか。
- 5年に1回実施される。
- 推計患者数には調査日に受療した患者数が含まれる。
- 調査日に入院している患者の平均在院日数が把握される。
- 総患者数には医療を受けたことのない有病者数も含まれる。
推計患者数・受療率(令和2年)
- 推計患者数は、入院では121.1万人、外来では713.8万人となっている。それぞれ65歳以上の高齢者が占める割合をみると、65歳以上の入院患者は74.7%、外来患者は50.7%と多くを占めている。
- 受療率は、入院では960、外来では5,658となっている。それぞれ年齢階級別にみると、入院患者では男女とも90歳以上が最も高く、外来患者では男80~84歳、女75~79歳が最も高い。
▶105回午前22改題
令和2年(2020年)に実施された患者調査のうち高齢者の調査結果で正しいのはどれか。
- 入院患者では65歳以上が約7割を占めている。
- 外来患者では65歳以上が約8割を占めている。
- 年齢階級別外来受療率(人口10万対)では90歳以上が最も高い。
- 年齢階級別入院受療率(人口10万対)では75~79歳が最も高い。
傷病分類別受療率(令和2年)
▶108回午後28改題
令和2年(2020年)患者調査の疾病分類別の結果を表に示す。

Cに当てはまる疾患はどれか。
- 結核
- 消化器系の疾患
- 循環器系の疾患
- 悪性新生物〈腫瘍〉
- 精神および行動の障害
精神及び行動の障害の状況(令和2年)
- 上記のとおり、精神及び行動の障害の外来受療率は211、入院受療率は188、退院患者の平均在院日数は294.2日となっている。また、総患者数は502.5万人で増加傾向にあり、傷病分類別にみると「気分[感情]障害(躁うつ病含む)」が172.1万人で最も多い。(患者調査)
- 病院の平均在院日数をみると、精神病床は277.0日と諸外国と比べて非常に高くなっている。また、精神病床に入院している患者27.4万人を傷病分類別にみると、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が14.1万人と半分以上を占めている。(病院報告)
▶102回午前10改題
令和2年(2020年)の患者調査における精神及び行動の障害に関する動向について正しいのはどれか。
- 外来受療率は入院受療率より高い。
- 精神病床の平均在院日数は約100日である。
- 年齢階級別外来受療率は年齢とともに上昇する。
- 血管性及び詳細不明の認知症の総患者数は減少している。
▶109回午後30改題
平成23年(2011年)から令和2年(2020年)までの日本の精神疾患患者の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 総患者数は減少傾向にある。
- 気分障害の患者数が最も多い。
- 入院患者数は増加傾向に転じている。
- 外来患者数では75歳以上の患者が減少傾向にある。
- Alzheimer〈アルツハイマー〉病の患者数は増加傾向である。
入院形態別精神疾患患者の状況(精神保健福祉資料)
- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。
- 任意入院が行われる状態にないと判定された者については、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に医療保護入院が行える。
- 2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には措置入院を行うことができる。
- 令和3年(2021年)の入院形態別入院患者割合は、医療保護入院が49.8%と最も高く、任意入院が49.1%、措置入院が0.6%となっている。
▶104回午後24改題
令和3年(2021年)6月末における精神疾患を有する者の入院者数が最も多い入院形態はどれか。
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
▶107回午後34改題
令和2年(2020年)における精神疾患の患者に関する動向について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 入院患者は外来患者より少ない。
- 措置入院患者は、入院患者の0.6%である。
- 精神病床における平均在院日数は300日以上である。
- 平成23年(2011年)と比較して患者数は減少している。
- 入院患者の5割以上がAlzheimer〈アルツハイマー〉病である。
生命表
第2編3章 生命表 p70~73
平均寿命と健康寿命(令和元年)
- 平均寿命とは0歳の平均余命をいい、男性が81.56年、女性が87.71年と延びている。
- 健康寿命とは日常生活に制限のない期間の平均であり、男性が72.68年、女性が75.38年と延びている。
- 平均寿命と健康寿命の差は日常生活に制限のある期間ということになり、上記の差をみると、男性が8.73年、女性が12.07年となる。個人の生活の質の向上、社会保障負担の軽減のため、この差を短縮することも重要となる。
▶104回午前33改題
健康日本21(第二次)における健康寿命について正しいのはどれか。
- 患者調査の結果を計算に用いる。
- 年齢別死亡率は計算に不要である。
- 日常生活に制限のない者の平均年齢である。
- 健康寿命の増加分を上回る平均寿命の増加を目標とする。
- 令和元年(2019年)の健康寿命と平均寿命の差は男性より女性が大きい。
国民健康・栄養調査
第3編1章 2.健康増進対策 p84~94
主な調査項目
- 肥満・やせ(BMI、腹囲等)、糖尿病、血圧、血中コレステロール
- 食塩・野菜摂取量
- 運動習慣者、歩数、睡眠の状況
- 飲酒・喫煙
▶103回午後32
国民健康・栄養調査で把握できるのはどれか。2つ選べ。
- 健康寿命
- BMIの平均値
- 蛋白質の必要量
- 喫煙習慣者の割合
- 支出に占める食料費の割合
▶107回午後20
国民健康・栄養調査について正しいのはどれか。
- 血圧値は調査項目である。
- 3日間の食事調査が行われる。
- 調査日の食費は調査項目である。
- 栄養素等摂取量が市区町村別に比較される。
糖尿病の状況(令和元年)
- 糖尿病が強く疑われる者は1000万人、糖尿病の可能性を否定できない者も1000万人となっている。(平成28年)
- 男女ともに年齢が高くなるほど糖尿病が強く疑われる者の割合が増え、70歳以上では男が26.4%、女が19.6%となっている。
- 糖尿病が強く疑われる者の割合を男女別にみると、40~49歳、50~59歳、60~69歳、70歳以上のいずれの階級でも、女性より男性が高い。
- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者は74.8%と多くを占めている。
▶106回午後17改題
令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査の糖尿病に関する統計で正しいのはどれか。
- 平成28年(2016年)の糖尿病が強く疑われる者は約1,000万人である。
- 40歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、男性よりも女性が高い。
- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者の割合は40%以下である。
- 30歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、女性では年齢に関係なく一定である。
肥満者/やせの者の割合(令和元年)
- 成人の肥満度を求める指標としてBMI(体格指数)が用いられる。計算式は、体重(kg)÷(身長(m))2で、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせと判定される。
- 肥満者の割合は男性33.0%・女性22.3%、やせの者の割合は男性3.9%・女性11.5%となっている。
▶109回午前1
令和元年(2019年)の生活習慣病の動向で正しいのはどれか。
- 肥満者の割合は男性より女性の方が多い。
- 脳血管疾患の死亡率は脳内出血より脳梗塞が高い。
- 悪性新生物の年齢調整死亡率で男性の部位別の第1位は大腸である。
- 糖尿病を強く疑われる者のうち現在治療を受けている者の割合は、男女ともに50%以下である。
運動習慣者、歩数の状況(令和元年)
- 20歳以上の運動習慣のある者の割合は男性33.4%・女性25.1%で、男女ともに70歳以上が最も高く(男性42.7%・女性35.9%)、次いで60~69歳となっている。
- 20歳以上の1日当たりの歩数の平均値は6,278歩で、男性6,793歩・女性5,832歩となっている。
▶109回午後19
令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査における身体活動・運動で正しいのはどれか。
- 20~49歳で運動習慣のある者の割合が最も高い。
- 20歳以上の歩数の平均値は1日8,000歩を下回る。
- 男性より女性の方が運動習慣のある者の割合が高い。
- 歩数の平均値は平成22年(2010年)の約2倍である。
喫煙習慣者の割合(令和元年)
▶108回午後25改題
令和元年(2019年)国民健康・栄養調査における20歳以上の男女別の「現在習慣的に喫煙している者の割合」で正しいのはどれか。
- 男性37.1% 女性27.6%
- 男性37.1% 女性17.6%
- 男性27.1% 女性17.6%
- 男性27.1% 女性7.6%
- 男性17.1% 女性7.6%
歯科疾患実態調査
第3編2章 5.歯科保健医療 p118~120
8020運動
▶107回午後24改題
令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査の結果をグラフに示す。

このグラフが表しているのはどれか。
- う歯を持つ者の割合
- 顎関節の異常がある者の割合
- 20歯以上の歯を有する者の割合
- 4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合
▶105回午後17改題
令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査において80歳で20本以上の自分の歯を有する者の割合に最も近いのはどれか。
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
医療従事者・医療施設数
第4編1章 4.医療関係者 5.医療施設 p184~204
医療従事者の就業者数・就業先(令和2年末)
- 就業している看護職員の総数は166.0万人で、保健師が5.6万人、助産師が3.8万人、看護師が128.1万人、准看護師が28.5万人となっている。
- 保健師の就業先をみると、市区町村が54.8%と最も多く、次いで保健所が15.3%、事業所が6.8%、病院が6.4%などとなっている。
▶101回午後1改題
令和2年(2020年)の衛生行政報告例における保健師の就業場所の構成割合で、市区町村、保健所の次に多いのはどれか。
- 病院
- 事業所
- 社会福祉施設
- 訪問看護ステーション
医療施設数(令和2年10月1日)
- 病院数は平成2年(1990年)ころをピークに減少傾向で、令和2年(2020年)は8,238施設となっている。
- 診療所は長期的に増加傾向で、令和2年(2020年)の一般診療所は102,612施設、歯科診療所は67,874施設となっている。
▶108回午前35改題
令和2年(2020年)の日本の医療施設数または医療従事者数で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 病院数は約6千施設である。
- 一般診療所数は約5万施設である。
- 就業保健師数は約5万6千人である。
- 歯科診療所数は約6万8千施設である。
- 就業看護師数は約100万5千人である。
国民医療費
第4編2章 6.国民医療費 p216~219
国民医療費の概要・状況
- 国民医療費は、医療機関などにおける傷病の治療に要する費用を推計したものである。正常な妊娠や分娩などに要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用、平成12年度から開始した介護保険制度の給付費は含まない。
- 令和2年(2020年)度の国民医療費は43.0兆円(国民総生産に対する比率は8.02%)で、人口1人当たり34.1万円である。人口1人当たりの国民医療費を年齢階級別にみると、65歳未満が18.4万円に対し、65歳以上は73.4万円(約4倍)、75歳以上は90.2万円(約5倍)となっている。
▶108回午後27改題
令和2年度(2020年度)の国民医療費について正しいのはどれか。
- 介護保険給付費を含む。
- 総額は40兆円を超える。
- 正常な妊娠・分娩の費用を含む。
- 国民総生産に対する比率は20%を超える。
- 健康の維持・増進を目的とした健康診断の費用を含む。
制度区分別・診療区分別国民医療費、傷病分類別医科診療医療費(令和2年度)
- 制度区分別に国民医療費をみると、医療保険等給付分が45.1%で最も多く、次いで後期高齢者医療給付分が35.6%、患者等負担分が12.1%、公費負担医療給付分が7.3%などとなっている。
- 診療区分別に国民医療費をみると、医科診療が71.6%で最も多く、次いで薬局調剤17.8%、歯科診療7.0%、入院時食事・生活1.7%、訪問看護0.8%などとなっている。
- 傷病分類別医科診療医療費をみると、循環器系の疾患が6.0兆円(19.5%)で最も多く、次いで新生物〈腫瘍〉が4.7兆円(15.2%)となっている。
▶108回午後21改題・107回午前31類問
令和2年度(2020年度)の傷病分類別医科診療医療費で、医療費が最も多いのはどれか。
- 精神および行動の障害
- 呼吸器系の疾患
- 循環器系の疾患
- 消化器系の疾患
- 新生物〈腫瘍〉
▶103回午前18改題
令和2年度(2020年度)の国民医療費について正しいのはどれか。
- 制度区分別国民医療費では公費負担医療給付分が最も多くを占める。
- 傷病分類別の医科診療医療費では悪性新生物〈腫瘍〉が最も多くを占める。
- 65歳以上の人口一人当たり国民医療費は65歳未満の約4倍である。
- 訪問看護医療費は全体の5%を上回る。
福祉行政報告例(児童虐待)
第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p237~238
児童虐待対応件数等〈令和3年度〉
- 児童虐待対応件数(20.7万件)のうち、虐待の種別にみると、心理的虐待が60.1%で最も多く、次いで身体的虐待が23.7%、ネグレクトが15.1%、性的虐待が1.1%となっている。虐待対応件数は、総数・種別ともに増加傾向にある。
- 主たる虐待者をみると、実母が9.9万件(47.5%)で最も多く、次いで実父が8.6万件(41.5%)となっているが、実父の構成割合は年々上昇している。
▶102回午前14改題
令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待相談対応件数について正しいのはどれか。
- 児童相談所の対応件数は前年度に比べ横ばいである。
- 実父による虐待は前年度に比べ増加傾向である。
- 実母による虐待は全体の4割以下である。
- 身体的虐待は心理的虐待より多い。
高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査
第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242
養護者による高齢者虐待と認められた件数等〈令和3年度〉
- 養護者による高齢者虐待のうち、虐待を行った養護者の続柄は、息子が38.9%で最も多く、次いで夫が22.8%となっている。
- 被虐待高齢者の性別は女性が75.6%と最も多く、年齢階級別にみると80~84歳が24.6%で最も高い。
- 高齢者虐待の種別にみると、身体的虐待が67.3%で最も多く、次いで心理的虐待が39.5%などとなっている。また、虐待の種別・要介護度別にみると、身体的虐待や心理的虐待は要介護度が重い方の割合が低く、介護等放棄では逆の傾向がみられる。
▶103回午前21改題
令和3年度(2021年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」における養護者による高齢者虐待に関する説明として適切なのはどれか。
- 経済的虐待が全体の6割を占めている。
- 虐待者の続柄は息子の割合が最も高い。
- 虐待の種別にかかわらず、要介護度が高いほど虐待の発生割合が高い。
- 被虐待者の9割が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅡ以上である。
食中毒統計調査
第7編2章 10.食中毒対策 p285~288
食中毒の発生状況(令和4年)
- 令和4年(2022年)の食中毒の事件数は962件、患者数は6,856人、死者は5人となっている。
- 特定された原因食品をみると、件数では魚介類に起因するものが53.7%と最も多い。
- 判明した病因物質をみると、患者数ではノロウイルスが32.2%と最も多く、件数ではアニサキスが59.4%と最も多い。
▶101回午前39改題
令和4年(2022年)の厚生労働省による食中毒統計調査について正しいのはどれか。
- 患者数は年間100万人以上である。
- 死亡者数は年間1,000人以上である。
- ノロウイルスによる患者が最も多い。
- 原因食品で最も多いのは肉類およびその加工品である。
労働災害・業務上疾病
第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308
業務上疾病の発生状況(令和3年)
▶110回午前27改題
令和3年度(2021年度)の業務上疾病発生状況等調査における疾病分類別業務上疾病発生者数をグラフに示す。
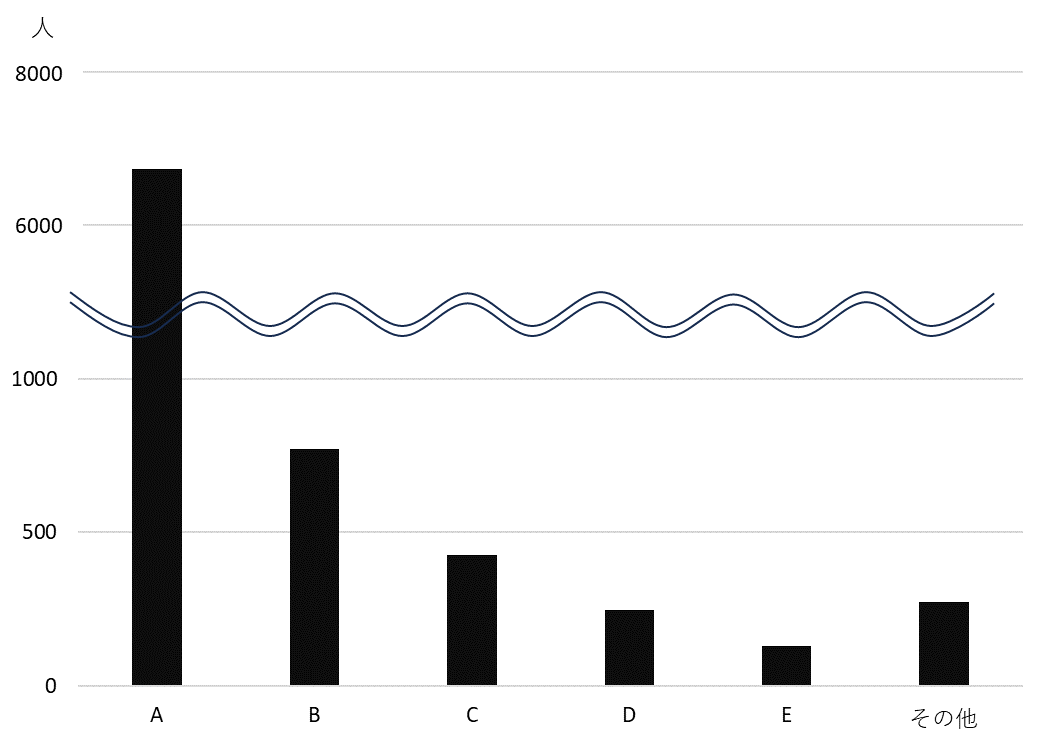
Aに該当するのはどれか。
なお、「新型コロナウイルスり患によるもの」を含む「病原体による疾病」はグラフから除いている。
- 化学物質による疾病
- 負傷に起因する疾病
- 物理的因子による疾病
- 作業態様に起因する疾病
- じん肺及びじん肺合併症
労働災害の発生状況(令和3年)
- 労働災害の発生状況をみると、死亡者数は774人で減少傾向、休業4日以上の死傷者数は13.2万人と増加傾向にある。
- 過労死等に関連する労災認定数をみると、脳・心臓疾患は172人で減少傾向、精神障害等は629人で増加傾向にある。
▶108回午後33改題・101回午後13類問
令和3年(2021年)の労働災害と業務上疾病の発生状況について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 労働災害による死亡者数は2,000人以上である。
- 労働災害による死亡者数は平成27年(2015年)に比べ減少している。
- 労働災害の認定数は脳・心臓疾患よりも精神障害によるものが多い。
- 業務上疾病(休業4日以上)発生数は平成27年(2015年)に比べ減少している。
- 業務上疾病(休業4日以上)発生数の内訳では「作業様態に起因する疾病」が最も多い。
石綿による肺がん・中皮腫の労災保険支給決定件数
▶104回午前19改題
石綿による疾病に関する労災保険給付の支給決定件数で正しいのはどれか。
- 平成18年度(2006年度)がピークである。
- 平成22年度(2010年度)から令和3年度(2021年度)まで連続して増加している。
- 令和3年度(2021年度)では中皮腫より肺がんの方が多い。
- 令和3年度(2021年度)の肺がんに対する支給は1,000件を超えている。
労働安全衛生調査(実態調査)
仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項(令和3年)
▶108回午前26改題
令和3年(2021年)の労働安全衛生調査(実態調査)で、労働者の仕事や職業生活における強い不安、悩み、ストレスの内容に関して最も割合が高いのはどれか。
- 仕事の質
- 対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)
- 仕事の失敗、責任の発生等
- 会社の将来性
- 仕事の量
学校保健統計調査
第10編 4.学齢期の健康状況 p347~349
学校保健統計調査の概要
▶102回午前24
学校保健統計調査から得られるのはどれか。
- ぜん息の被患率
- 自殺した児童生徒数
- 救急車による搬送件数
- 不登校の状態にある児童生徒数
- 学校の管理下における突然死の件数
▶109回午前11
文部科学省が実施する学校保健統計調査で正しいのはどれか。
- 悉皆調査である。
- 毎年10月に行われる。
- 学校で実施する健康診断の結果に基づいている。
- 学校管理下で死亡した児童生徒数が集計されている。
児童・生徒の異常被患率(令和3年)
【幼稚園】
①むし歯(う歯)26.5%
②裸眼視力1.0未満の者24.8%
【小学校】
①むし歯(う歯)39.0%
②裸眼視力1.0未満の者36.9%
【中学校】
①裸眼視力1.0未満の者60.7%
②むし歯(う歯)30.4%
【高等学校】
①裸眼視力1.0未満の者70.8%
②むし歯(う歯)39.8%
- むし歯(う歯)の者の割合は全学校段階で減少傾向にあるが、裸眼視力1.0未満の者の割合は増加傾向にある。
▶110回午後22改題
令和3年(2021年)の学校保健統計調査における学校種別の主な疾病・異常被患率を以下に示す。
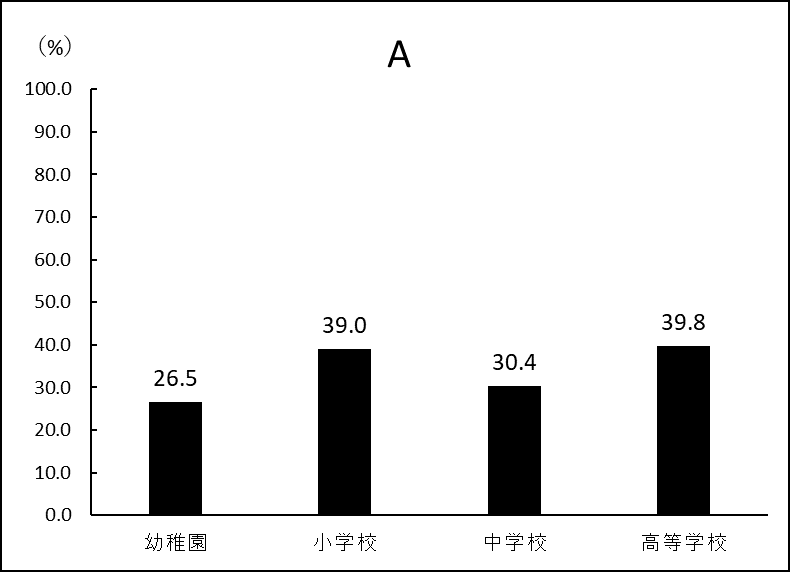

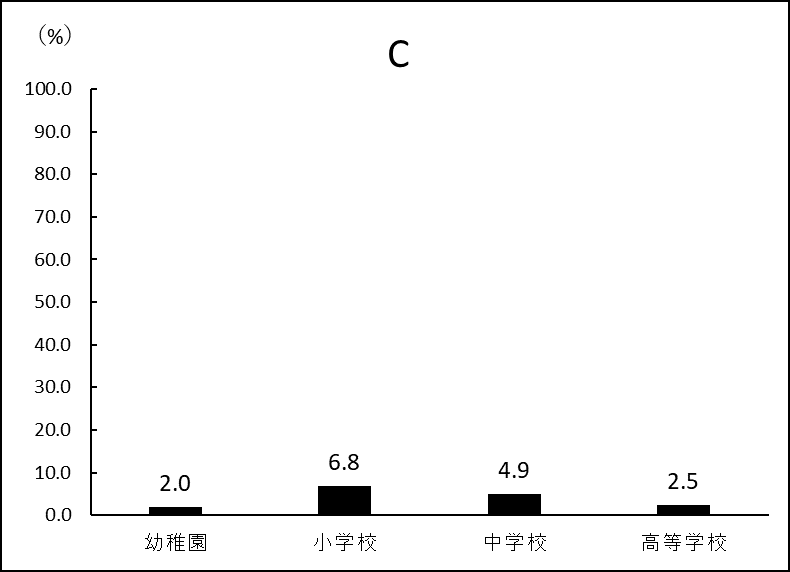
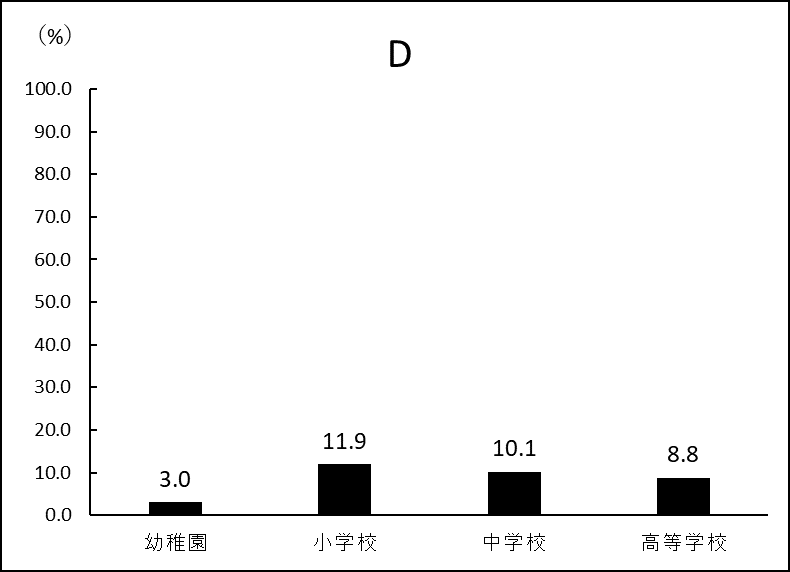
裸眼視力1.0未満の者を示したグラフはどれか。
- A
- B
- C
- D
▶108回午後29改題
令和3年度(2021年度)の学校保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 幼稚園児のむし歯(う歯)の保有率は15%程度である。
- 裸眼視力1.0未満の小学生は37%程度である。
- むし歯(う歯)を保有する小学生は前年度に比べて減少している。
- 中学生のむし歯(う歯)の保有率は45%程度である。
- 裸眼視力1.0未満の高校生は50%程度である。
▶105回午後31改題
令和3年度(2021年度)学校保健統計調査における主な疾病・異常等で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 肥満傾向児の出現率は、平成23年度(2011年度)以降男女ともに増加を続けている。
- 小学校における疾病・異常の被患率は、裸眼視力1.0未満の者が最も高い。
- むし歯(う歯)の者の割合は、全ての学校段階で前年度より減少している。
- ぜん息の者の年齢別の割合は、小学校で高い傾向がみられる。
- 心電図異常の割合は、高等学校より小学校の方が多い。
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
小学校・中学校におけるいじめ・不登校の状況(令和3年)
- いじめの認知件数をみると、小学校で50.1万件、中学校で9.8万件となっている。いじめの発見のきっかけは、小・中学校ともに「アンケート調査など学校の取組により発見」が最も高く、それぞれ57.8%、36.4%となっている。その内容は、小・中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が最も高く、それぞれ57.0%、62.2%となっている。
- 小・中学校の長期欠席のうち不登校の児童生徒数をみると、小学校で8.1万人(1.3%)、中学校で16.3万人(5.0%)となっている。不登校の主たる要因は、小・中学校ともに「無気力・不安」が最も高く、いずれも49.7%となっている。
▶108回午前16改題
令和3年度(2021年度)児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査で正しいのはどれか。
- 小学校における不登校児童数は約10万人である。
- いじめの発見のきっかけの第1位は「本人からの訴え」である。
- 中学校における不登校の主たる要因の第1位は「無気力・不安」である。
- 小学校におけるいじめの内容の第1位は「仲間はずれ、集団による無視をされる」である。
特別支援教育の状況
第10編 5.特別支援教育 p349~351
特別支援教育の状況(令和3年)
▶108回午前14改題
令和3年(2021年)の特別支援教育の状況で正しいのはどれか。
- 訪問教育を受けている児童生徒は小学生が最も多い。
- 特別支援学級の児童生徒の障害は知的障害が最も多い。
- 義務教育段階の児童生徒のうち特別支援学校に在籍している割合は全児童生徒の3%である。
- 特別支援教育が開始された平成19年(2007年)に比べて対象となる児童生徒数は減少している。
保健統計調査(複合問題)
▶104回午後34
保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国勢調査は5年に1度実施される。
- 患者調査から死因別死亡率が得られる。
- 人口動態調査は2年に1度集計される。
- 国民生活基礎調査は2年に1度実施される。
- 国民健康・栄養調査の調査項目に腹囲がある。
▶109回午前38
調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 患者調査は毎年実施される。
- 国勢調査で出生率が把握される。
- 社会生活基本調査は総務省が実施する。
- 人口動態調査は無作為抽出による標本調査である。
- 国民健康・栄養調査は健康増進法に基づいて実施される。
「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。
看護師国家試験では、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が毎年問われています。専門的な内容も多く、受験者の苦手とする分野でもありますが、覚えれば必ず解答できる部分でもあり、重要な得点源になります。
このページでは、看護師試験に頻出する法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、113回(2024年)から104回(2015年)までの10年分の試験の中から対応する法律問題をピックアップしています。
出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
法律別問題目次
第1編:衛生行政活動
- 地域保健法
- 災害対策基本法
第3編:保健対策・疾病対策
- 健康増進法
- 母子保健法
- 母体保護法
- 障害者総合支援法
- 精神保健福祉法
- 発達障害者支援法
- 自殺対策基本法
- がん対策基本法
- 難病法
- 臓器移植法
第4編:医療提供体制・医療保険制度
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 医療保険各法
第5編:社会保険・社会福祉
- 国民年金法等
- 生活保護法
- 社会福祉法
- 児童福祉法
- 児童虐待防止法
- DV防止法
- 男女雇用機会均等法
- 労働基準法
- 育児・介護休業法
- 老人福祉法
- 高齢者虐待防止法
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第6編:薬事
- 医薬品医療機器等法
- 麻薬及び向精神薬取締法
第7編~10編:食品・労働・環境・学校
- 食品衛生法・食品安全基本法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 環境基本法
- 学校保健安全法
地域保健法
第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24
保健所
地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
- 診療所
- 保健所
- 地域包括支援センター
- 訪問看護ステーション
保健所の設置主体で正しいのはどれか。
- 国
- 都道府県
- 社会福祉法人
- 独立行政法人
市町村保健センター
地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。
- 病気の治療
- 住民の健康診査
- 看護師免許申請の受理
- 専門的で広域的な健康課題への対応
災害対策基本法
第5編2章 6.2〕災害時の支援体制 p244
主な規定
災害対策基本法は災害対策の最も基本となる法律で、以下のような防災体制の整備が規定されている。
- 地域防災計画(都道府県・市町村)の作成
- 物資の備蓄
- 防災訓練義務
災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。
- 物資の備蓄
- 避難所の設置
- 災害障害見舞金の支給
- 救護班による医療の提供
健康増進法
第3編1章 2.1〕(5)健康増進法 p86~87
主な規定
- 国民健康・栄養調査
- 保健指導等
- 特定給食施設
- 受動喫煙防止
健康増進法に基づき実施されるのはどれか。
- 受療行動調査
- 特定保健指導
- アレルギー疾患対策
- 受動喫煙の防止対策
母子保健法
第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99
主な規定
母子保健法では以下の事項などを規定している。
- 妊産婦・乳幼児の健康診査
- 市町村への妊娠の届出
- 母子健康手帳の交付
- 未熟児に対する養育医療の給付
- 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置
養育医療が定められている法律はどれか。
- 児童福祉法
- 母子保健法
- 発達障害者支援法
- 児童虐待の防止等に関する法律
母子保健法に基づく届出はどれか。
- 婚姻届
- 死産届
- 死亡届
- 出生届
- 妊娠届
乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。
- 母子保健法
- 児童福祉法
- 次世代育成支援対策推進法
- 児童虐待の防止等に関する法律
産科外来を初めて受診した妊婦。夫婦ともに外国籍で、日本の在留資格を取得している。
この妊婦への説明で正しいのはどれか。
- 「母子健康手帳は有料で入手できます」
- 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」
- 「出生届は外務省に提出します」
- 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」
母子保健法に規定されているのはどれか。
- 母子健康包括支援センター
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 助産施設
- 特定妊婦
母体保護法
第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103
主な規定
母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に以下の事項を規定している。
- 不妊手術
- 人工妊娠中絶
- 受胎調節の実地指導
母体保護法で規定されているのはどれか。
- 育児時間
- 生理休暇
- 受胎調節の実地指導
- 育児中の深夜業の制限
人工妊娠中絶
母体保護法に定める人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を保続することのできない時期(通常妊娠満22週未満)に、人工的に母体外に排出することをいい、以下の者の実施が可能であるとしている。
- 妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者
- 暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した者
母体保護法で規定されているのはどれか。
- 産後の休業
- 妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限
- 妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止
- 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶
日本の人工妊娠中絶で正しいのはどれか。
- 配偶者の同意が必須である。
- 妊娠10週以降は死産の届出が必要である。
- 実施が可能なのは妊娠22週未満の場合である。
- 実施率は母の年齢が20~24歳よりも20歳未満の方が高い。
出生前診断について正しいのはどれか。
- 遺伝相談は勧めない。
- 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。
- 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。
- 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。
障害者総合支援法
第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111
地域移行支援
Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。
Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。
- 療養介護
- 施設入所支援
- 地域移行支援
- 自立訓練としての機能訓練
就労移行支援
- 障害者総合支援法では就労移行支援事業が設けられ、就労を希望し、一般雇用が可能な障害者に対して、一定期間就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行っている。
- 一般雇用が困難である者には、雇用契約に基づく就労継続支援A型、雇用契約に基づかない就労継続支援B型による支援が行われている。
一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。
- 就労移行支援
- 自立生活援助
- ピアサポート
- 就労継続支援A型
Aさん(40歳、男性)は、5年前に勤めていた会社が倒産し再就職ができず、うつ病になった。その後、治療を受けて回復してきたため、一般企業への再就職を希望している。
Aさんが就労を目指して利用できる社会資源はどれか。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 自立訓練〈生活訓練〉
共同生活援助〈グループホーム〉
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。
- 育成医療
- 居宅療養管理指導
- 共同生活援助〈グループホーム〉
- 介護予防通所リハビリテーション
自立支援医療
- 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度である。
- 身体障害者には更生医療、身体障害児には育成医療、精神障害者には精神通院医療がなされている。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。
- 障害基礎年金
- 一定割合の雇用義務
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療〈精神通院医療〉
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
第3編2章 4.精神保健 p111~118
精神保健指定医
精神保健指定医を指定するのはどれか。
- 保健所長
- 都道府県知事
- 厚生労働大臣
- 精神保健福祉センター長
精神保健指定医について正しいのはどれか。
- 医療法で規定されている。
- 都道府県知事が指定する。
- 障害年金の支給判定を行う。
- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
精神障害者の入院形態
- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。
- 任意入院が行われる状態にない者については、その家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に医療保護入院が行える。また、急速を要し、家族等の同意が得られない場合には、72時間以内の応急入院を行うことができる。
- 2人以上の指定医の診察を要件に、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者については措置入院を行うことができる。また、急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが72時間以内の緊急措置入院を行うことができる。
Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。
Aさんの入院形態はどれか。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
医療保護入院で正しいのはどれか。
- 入院の期間は72時間に限られる。
- 患者の家族等の同意で入院させることができる。
- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 応急入院は72時間以内に限られている。
- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
精神医療審査会
精神医療審査会で審査を行うのはどれか。
- 精神保健指定医の認定
- 入院患者からの退院請求
- 退院後生活環境相談員の選任
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否
精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。
- 保健所
- 地方裁判所
- 精神医療審査会
- 地方精神保健福祉審議会
精神科入院患者の制限事項
精神科入院患者で隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、以下の事項については制限できない。
- 信書(手紙)の発受
- 行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会
- 患者からの退院請求、処遇改善請求
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
- 警察官
- 検察官
- 患者本人
- 精神保健福祉士
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。
- 家族との面会
- 患者からの信書の発信
- 患者からの退院の請求
- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
信書の発受に関する例外
精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。
当日の看護師の対応で適切なのはどれか。
- 患者に渡さず破棄する。
- 患者による開封に立ち会う。
- 開封せず患者の家族に転送する。
- 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。
- 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。
隔離時の遵守事項
精神保健指定医が必要と判断した12時間以上の患者の隔離を行うに当たっては以下のような遵守事項が定められている。
- 隔離室には患者一人のみ入室させること。
- 隔離を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載すること。
- 隔離期間中は注意深い臨床的観察や適切な治療を確保し、部屋の衛生の確保に配慮すること。
- 医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うこと。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。
- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。
- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。
- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。
- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。
精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 行動制限の理由を患者に説明する。
- 原則として2名以上のスタッフで対応する。
- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
- 精神保健指定医による診察は週1回とする。
- 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。
身体拘束時の遵守事項
- 身体的拘束は制限の程度が強く、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない。
- 実施する際は、患者に身体的拘束を行う理由を知らせるよう努めること、身体的拘束が漫然と行われることがないよう医師は頻回に診察を行うことなどに特に留意する。
精神科病棟における身体拘束時の看護で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1時間ごとに訪室する。
- 拘束の理由を説明する。
- 水分摂取は最小限にする。
- 患者の手紙の受け取りを制限する。
- 早期の解除を目指すための看護計画を立てる。
精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付される。
- 手帳の交付により所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引などが受けられる。
精神障害者保健福祉手帳の交付によって精神障害者に適用されるのはどれか。
- 行動援護の介護給付
- 所得税の障害者控除
- 自立支援医療(精神通院医療)
- グループホームで必要な日常生活上の援助
精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。
- 知的障害も交付対象である。
- 取得すると住民税の控除対象となる。
- 交付によって生活保護費の支給が開始される。
- 疾病によって障害が永続する人が対象である。
精神保健福祉センター
- 精神保健福祉センターは、地域精神保健業務を技術面から指導・援助する機関で、都道府県・指定都市に設置される。
- 同センターには精神保健福祉相談員を配置することとされ、精神障害者やその家族の相談に応じ、必要な指導・援助を行っている。
都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。
- ゲートキーパー
- ピアサポーター
- 精神保健福祉相談員
- 退院後生活環境相談員
現在の日本の精神医療で正しいのはどれか。
- 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。
- 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。
- 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。
- 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。
精神保健福祉士
Aさん(60歳、女性)は、統合失調症で10年間入院していた。来月退院予定となったため、Aさん、医師、看護師でチームを作り、退院支援計画を立てることになった。Aさんは「両親も亡くなってしまい、これからの生活費や住む場所がとても心配だ」と訴えてきた。
退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。
- 薬剤師
- 精神保健福祉士
- ピアサポーター
- 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師等)
精神保健福祉法改正の主な経緯・内容
近年の精神保健福祉法の改正内容は以下のとおりである。
●平成7年(1995年)
精神保健法から名称変更。精神障害者保健福祉手帳の創設。
●平成17年(2005年)
通院医療公費負担制度(1965年導入)を障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の成立に伴い新設された自立支援医療に一元化。
●平成25年(2013年)
障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていた保護者制度の廃止。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。
- 保護者制度の廃止
- 自立支援医療の新設
- 精神保健指定医制度の導入
- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更
精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律への改正で行われたのはどれか。
- 私宅監置の廃止
- 任意入院の新設
- 通院医療公費負担制度の導入
- 精神障害者保健福祉手帳制度の創設
発達障害者支援法
第3編2章 4.6〕(4)発達障害者支援 p115~116
発達障害の定義
発達障害者支援法で発達障害と定義されているのはどれか。
- 学習障害
- 記憶障害
- 適応障害
- 摂食障害
自殺対策基本法
第3編2章 6.自殺対策 p121~122
責務
- 自殺対策基本法に基づき、政府には自殺総合対策大綱の策定を、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。
- 国民に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるため、自殺予防週間(9月10日~16日)、自殺対策強化月間(3月)を設けている。
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
- 自殺総合対策推進センターの設置
- 自殺総合対策大綱の策定
- ゲートキーパーの養成
- 自殺対策計画の策定
自殺対策基本法について正しいのはどれか。
- 自殺対策強化月間を設けることを定めている。
- 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
- 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
- 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。
がん対策基本法
第3編4章 1.がん対策 p149~152
責務
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 受動喫煙のない職場を実現する。
- がんによる死亡者の減少を目標とする。
- 都道府県がん対策推進計画を策定する。
- がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
基本的施策
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
- 受動喫煙のない職場環境を整備する。
- 学校等でのがんに関する教育を推進する。
- がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
第3編4章 2.難病対策 p153~157
難病にかかる医療費の助成
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。
- 中皮腫
- C型肝炎
- 慢性腎不全
- 再生不良性貧血
責務
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
- 申請に基づく特定医療費の支給
- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
臓器の移植に関する法律
第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162
脳死判定
脳死とは脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、以下の5項目で判定される。
①深い昏睡
②瞳孔の散大と固定
③脳幹反射の消失
④平坦な脳波
⑤自発呼吸の停止
臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。
- 低体温
- 心停止
- 平坦脳波
- 下顎呼吸
臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。
- 瞳孔径は左右とも3mm以上
- 脳波上徐波の出現
- 微弱な自発呼吸
- 脳幹反射の消失
- 浅昏睡
脳死の状態はどれか。
- 縮瞳がある。
- 脳波で徐波がみられる。
- 自発呼吸は停止している。
- 痛み刺激で逃避反応がある。
脳死臓器提供可能年齢
平成22年の改正臓器移植法施行により、本人の意思が不明な場合(拒否の意思がない場合)でも、家族(遺族)の書面による承諾により脳死判定および臓器摘出が可能となったことにより、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が認められることとなった。
臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。
- 1歳
- 6歳
- 15歳
- 20歳
- 年齢制限なし
医療法
第4編1章 1.医療法 p166
第4編1章 2.医療計画 p166~169
概要
医療法はわが国の医療提供体制の基本となる法律として以下の事項を定めている。
- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項
- 医療の安全を確保するために必要な事項
- 病院・診療所・助産所の開設と管理に関し必要な事項
- これらの施設の整備と医療提供施設相互間の機能の分担・業務の連携を推進するために必要な事項
医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。
- 医療法
- 医師法
- 健康保険法
- 保健師助産師看護師法
医療に関する選択の支援等
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。
- 医療法
- 健康保険法
- 地域保健法
- 個人情報の保護に関する法律
医療の安全の確保
病院等の管理者は医療に係る安全管理のため、以下の体制整備を実施する。
- 医療安全管理者や医薬品安全管理責任者の配置
- 指針の整備
- 医療安全委員会の設置
- 職員研修(年2回程度)の実施
医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
医療安全支援センター/医療事故調査・支援センター
- 医療安全支援センターは、医療の安全の確保のために都道府県・保健所設置市・特別区が設置するもので、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。
- 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査の支援、整理分析、普及啓発、研修事業などを実施するもので、医療事故等が発生した場合、病院等の管理者は遅滞なく同センターに報告することとなっている。
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- 医療安全支援センターを設置する。
- 医療安全管理者養成研修を実施する。
- 医療の安全を確保するための指針を策定する。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。
- 医療安全管理者の配置
- 厚生労働省へのインシデント報告
- 患者・家族への医療安全指導の実施
- 医療安全支援センターへの医療事故報告
病院・診療所
- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
- 診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)をいう。
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
- 9
- 19
- 29
- 39
特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院
- 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。
- 地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。
- 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
- 診療所
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
- 臨床研究中核病院
医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。
- 助産所
- 診療所
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 保健所
- 特定機能病院
- 地方衛生研究所
- 市町村保健センター
- 医療安全支援センター
病床種別
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
病床種別ごとの人員配置基準
看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
- 医療法
- 労働基準法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。
【 】に入るのはどれか。
- 2
- 3
- 4
- 6
病床種別ごとの構造設備基準
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。
- 3.4m2以上
- 4.4m2以上
- 5.4m2以上
- 6.4m2以上
5疾病6事業
医療法に定める医療計画には、医療提供体制の整備に重要な5疾病6事業が掲げられている。
●5疾病
「がん」「脳卒中」「心血管疾患」「糖尿病」「精神疾患」
●6事業
「救急医療」「災害医療」「新興感染症等の感染拡大時における医療(令和6年度から追加)」「へき地医療」「周産期医療」「小児医療」
令和3年(2021年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。
①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。
①――②
- 4――4
- 4――5
- 5――5
- 5――6
- 6――6
災害医療について正しいのはどれか。
- 災害拠点病院は市町村が指定する。
- 医療計画の中に災害医療が含まれる。
- 防災訓練は災害救助法に規定されている。
- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。
医療計画
- 医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。
- 記載事項として、5疾病6事業のほか、在宅医療、地域医療構想に基づく病床の整備(基準病床数)、二次医療圏・三次医療圏の設定事項などが含まれる。
医療法における医療計画で正しいのはどれか。
- 国が策定する。
- 在宅医療が含まれる。
- 3年ごとに見直される。
- 病床の整備は含まれない。
医療計画について正しいのはどれか。
- 基準病床数を定める。
- 5年ごとに見直しを行う。
- 特定機能病院の基準を定める。
- 一次、二次および三次医療圏を設定する。
地域医療構想
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。
- 子育て世代包括支援センター
- 地域包括ケアシステム
- 子どもの医療費の助成
- 地域生活支援事業
- 地域医療構想
保健師助産師看護師法
第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197
看護師免許の付与
看護師免許を付与するのはどれか。
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 文部科学大臣
業務に従事する看護師の届出
業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。
( )に入る数字はどれか。
- 1
- 2
- 3
- 4
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 都道府県ナースセンターの長
看護師免許付与における相対的欠格事由
保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者
- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者
- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者
看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
- 20歳未満の者
- 海外に居住している者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 伝染性の疾病にかかっている者
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
看護師の守秘義務
保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。
- 研究をする。
- 看護記録を保存する。
- 看護師自身の健康の保持増進を図る。
- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。
看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師の業務
- 看護師は傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする(保健師助産師看護師法5条)。
- 診療の補助の範囲は厚生労働省通知により解釈がなされ、静脈内注射などは医師の指示の下に行うことができる。
看護師の業務で正しいのはどれか。
- グリセリン浣腸液の処方
- 褥婦への療養上の世話
- 酸素吸入の流量の決定
- 血液検査の実施の決定
医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。
- 静脈内注射
- 診断書の交付
- 末梢静脈路の確保
- 人工呼吸器の設定の変更
看護師の特定行為
- 保健師助産師看護師法に定める特定行為は、看護師が医師または歯科医師の作成する手順書により行う診療の補助で、38行為が規定されている。
- 平成27年(2015年)から特定行為に係る看護師の研修制度が開始し、厚生労働大臣が特定行為研修を行う研修機関を指定している。
看護師の特定行為で正しいのはどれか。
- 診療の補助である。
- 医師法に基づいている。
- 手順書は看護師が作成する。
- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。
特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。
- 特定行為は診療の補助行為である。
- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。
- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197
看護師等の確保のための関係者の責務
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
- 医療法
- 労働契約法
- 教育基本法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
- 人員配置基準に基づき看護師を配置する。
- 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
- 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
- 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
都道府県ナースセンターの実施事業
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
- 訪問看護業務
- 看護師免許証の交付
- 訪問入浴サービスの提供
- 看護師等への無料の職業紹介
看護師の復職支援
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。
- 看護師等免許保持者の届出
- 特定行為に係る研修
- 教育訓練給付金
- 業務従事者届
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
- 届出は義務である。
- 届出先は保健所である。
- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
医療保険各法
第4編2章 1.医療保険制度 p208~209
国民皆保険
わが国はすべての国民が、①被用者保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度のいずれかの医療保険に加入することとしている(国民皆保険制度)。
日本において国民皆保険制度となっているのはどれか。
- 医療保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
医療給付内容
- 医療の給付は保健医療機関(病院、診療所等)が行い、医療保険の種類に関わらず医療給付の内容は同じである。
- その内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。
健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
- 手術
- 健康診査
- 予防接種
- 人間ドック
被用者保険(職域保険)
- 被用者保険の被保険者は、会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の者である。
- 保険者により全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険(組合健保)、船員保険、共済組合(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員)がある。
日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 年金保険
- 雇用保険
- 船員保険
- 組合管掌健康保険
- 労働者災害補償保険
国民健康保険
- 国民健康保険の被保険者は被用者保険の加入者(被保険者とその家族)でも後期高齢者医療の被保険者(原則75歳以上の者)でもない者である。
- 保険者は都道府県・市町村・国民健康保険組合である。
国民健康保険の保険者はどれか。2つ選べ。
- 国
- 都道府県
- 市町村
- 健康保険組合
国民健康保険で正しいのはどれか。
- 被用者保険である。
- 保険者は国である。
- 高額療養費制度がある。
- 保険料は加入者の年齢で算出する。
後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度(2008年度)に開始した。
- 被保険者は原則75歳以上の後期高齢者である。
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- 介護保険法
- 老人福祉法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉
後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
( )に入るのはどれか。
- 70
- 75
- 80
- 85
医療費の自己負担
国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。
- 1割
- 2割
- 3割
- 4割
高齢者の医療の確保に関する法律の内容で正しいのはどれか。
- 医療の給付は市町村が行う。
- 高齢者は一律3割の医療費を自己負担する。
- 40歳以上の被保険者と被扶養者にがん検診を行う。
- 後期高齢者の医療給付の内容は国民健康保険と同じである。
医療保険について正しいのはどれか。
- 医療給付には一部負担がある。
- 高額療養費の受給には年齢制限がある。
- 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。
- 後期高齢者医療における公費負担は8割である。
日本の医療保険制度について正しいのはどれか。
- 健康診断は医療保険が適用される。
- 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。
- 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。
- 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。
国民年金法・厚生年金保険法
第5編2章 1.公的年金 p234~235
公的年金の特徴
わが国の公的年金の特徴として、以下のような特徴が挙げられる。
- 加入者が保険料を拠出し、年金給付を受ける社会保険方式。
- 20歳以上60歳未満の国民すべてが国民年金に加入する国民皆年金。
- 現在の現役世代が負担した保険料を原資に、現在の高齢世代が年金給付を受ける賦課方式。
公的年金制度について正しいのはどれか。
- 学生は申請によって納付が免除される。
- 生活保護を受けると支給が停止される。
- 保険料が主要財源である。
- 任意加入である。
- 積立方式である。
生活保護法
第5編2章 2.生活保護 p235
生活保護法による8扶助
生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。
( )に入る数字はどれか。
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
- 医療扶助――医療にかかる費用
- 教育扶助――高等学校以上の教育にかかる費用
- 住宅扶助――住宅の購入にかかる費用
- 出産扶助――新生児の育児用品にかかる費用
生活保護の決定
生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。
- 保健センター
- 福祉事務所
- 保健所
- 病院
社会福祉法
第5編2章 6.地域福祉 p243~245
社会福祉協議会
社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。
- がん対策
- 男女共同参画
- 就労の支援活動
- ボランティア活動
児童福祉法
第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239
児童相談所
- 児童相談所は各都道府県・指定都市に設置が義務づけられており、児童福祉司などの専門職員を配置し、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行う。
- 調査等に基づいて、児童相談所長または都道府県知事の決定に基づく児童の一時保護などの措置を行っている。
ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。
- 家庭裁判所長
- 児童相談所長
- 保健所長
- 警察署長
- 市町村長
児童相談所について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国が設置する。
- 児童福祉司が配置されている。
- 母親を一時保護する機能を持つ。
- 知的障害に関する相談を受ける。
- 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。
児童相談所の業務はどれか。2つ選べ。
- 児童の一時保護
- 自立支援給付の決定
- 不登校に関する相談
- 身体障害者手帳の交付
- 放課後児童健全育成事業の実施
小児慢性特定疾病医療費の支給
小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。
- 対象は5疾患群である。
- 対象年齢は20歳未満である。
- 医療費の自己負担分の一部を助成する。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。
養育支援訪問事業
母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。
- 育成医療――結核児童
- 養育医療――学齢児童
- 健全母性育成事業――高齢妊婦
- 養育支援訪問事業――特定妊婦
児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉
第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p237~238
概要
- 児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、福祉事務所もしくは児童相談所への通告義務を課している。
- 児童虐待は、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待と定義されている。このうち最も相談件数の多い心理的虐待については、児童に対する著しい暴言や拒絶的な対応のほか、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力など、児童に著しい心理的外傷を与える言動と定義している。
児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づいて行う通告で正しいのはどれか。
- 警察に通告する。
- 守秘義務の遵守が優先される。
- 通告にあたっては児童自身の意思を尊重することが規定されている。
- 児童が同居している家庭における配偶者に対する暴力は通告の対象となる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
第5編2章 3.5〕配偶者からの暴力の防止対策 p238
配偶者暴力相談支援センターと裁判所の役割
- DV防止法に基づき、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない。
- 通報を受けた配偶者暴力相談支援センターは、婦人相談員による相談や自立支援、一時保護などを行う。加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令は裁判所が行う。
配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。
- 一時保護
- 就労の仲介
- 外傷の治療
- 生活資金の給付
Aさん(38歳、女性、パート勤務)は、腹痛のため、姉に付き添われて救急外来を受診した。診察時、身体には殴られてできたとみられる複数の打撲痕が確認された。腹痛の原因は夫から蹴られたことであった。Aさんは「家に帰るのが怖い。姉には夫の暴力について話したくない」と泣いている。
外来での看護師の対応で適切なのはどれか。
- 打撲痕を姉に見てもらう。
- 配偶者暴力相談支援センターに通報する。
- 暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。
- Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。
- 離婚調停の支援
- 成年後見制度の利用
- 保健所による自立支援
- 婦人相談員による相談
- 裁判所による接近禁止命令
配偶者・暴力の定義
- DV防止法に規定する配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。
- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。
- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。
- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。
- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。
- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉で正しいのはどれか。
- 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。
- 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。
- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
- 母子健康センターは被害者の保護をする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239
妊婦健康診査を受診する時間の確保
- 男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。
- その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。
妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
- 母子保健法
- 労働基準法
- 育児介護休業法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
正常に経過している妊娠26週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。
- 4週後
- 3週後
- 2週後
- 1週後
正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。
- 4週後
- 3週後
- 2週後
- 1週後
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。
- 生理日の就業制限
- 産後6週間の就業禁止
- 妊産婦の時間外労働の禁止
- 妊婦健康診査の受診時間の確保
労働基準法
第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239
妊産婦等の就業に関する規定
- 労働基準法の規定により、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間(産後6週間経過後の女性の請求による就業は可)を経過しない女性を就業させてはならない(産前産後休業)。
- 妊産婦等の危険有害業務の就業禁止のほか、女性の請求による妊産婦等の軽易業務転換、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、育児時間なども規定している。
労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- 妊娠の届出
- 妊婦の保健指導
- 産前産後の休業
- 配偶者の育児休業
- 妊産婦の時間外労働の制限
就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。
- 時差出勤――母子保健法
- 産前産後の休業――児童福祉法
- 軽易業務への転換――母体保護法
- 危険有害業務の制限――労働基準法
育児時間
法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。
- 請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。
- 父親と母親の両方が取得できる。
- 1日に2回請求できる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239
育児に関する規定
育児・介護休業法には育児に関して以下のような規定がある。
- 子どもが1歳になるまでの育児休業。
- 3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮。
- 小学校就学前までの子を養育する労働者の請求による看護休暇の取得や時間外労働の制限。
Aさん(28歳、女性)は、2歳の子どもを養育しながら働いている。
Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。
- 児童福祉法
- 労働基準法
- 男女共同参画社会基本法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。
- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限
老人福祉法
第5編2章 5.高齢者福祉等 p241~243
老人福祉計画
老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。
- 国
- 市町村
- 都道府県
- 福祉事務所
- 後期高齢者医療広域連合
老人デイサービスセンター
老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。
- 介護医療院
- 介護老人保健施設
- 老人福祉センター
- 老人デイサービスセンター
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉
第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242
概要
- 高齢者虐待に関する防止、保護、支援については、市町村(特別区を含む)が第一義的に責任を持つ。
- 高齢者を保護・分離する手段として、居宅サービスの措置、養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置などを講じることが規定されている。
養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉に基づき通報する先として正しいのはどれか。
- 市町村
- 警察署
- 消防署
- 訪問看護事業所
高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
- 有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 高齢者生活福祉センター
- サービス付き高齢者向け住宅
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第5編2章 5.4〕高齢者の就労支援 p242
シルバー人材センター事業
退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。
- シルバー人材センター
- 老人福祉センター
- 老人クラブ
- 自治会
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉
第6編1章 4.医薬品等の承認・許可制度 p249~250
毒薬・劇薬
毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
- 薬剤師法
- 毒物及び劇物取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉
毒薬の表示
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。
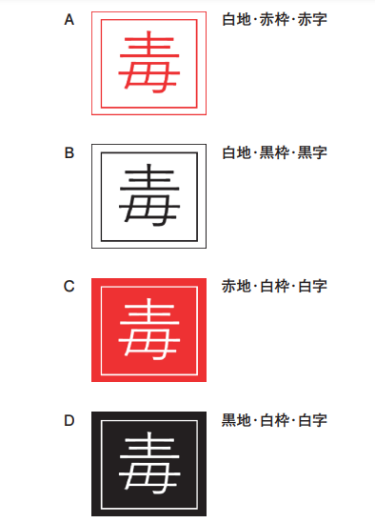
正しいのはどれか。
- A
- B
- C
- D
劇薬の表示
医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
麻薬及び向精神薬取締法
第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p269~271
麻薬の保管等の規定
他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。
- ヘパリン
- インスリン
- リドカイン
- フェンタニル
麻薬を扱う者
麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。
- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。
- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。
- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。
- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。
食品衛生法・食品安全基本法
第7編2章 1.食品安全行政の概要 p278~279
概要
- 食品衛生法は、食品等の事業者の責務や規格・基準、監視指導などを規定している。
- 食品安全基本法は、リスク分析(評価・管理・コミュニケーション)により食品安全の確保を図るもので、リスク評価は内閣府に設置された食品安全委員会が担当する。
食品衛生法に定められていないのはどれか。
- 残留農薬の規制
- 食品添加物の規制
- 食品安全委員会の設置
- ポジティブリスト制度の導入
労働基準法
第8編 9.1〕過重労働による健康障害防止対策 p308
労働時間
休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。
- 30時間
- 35時間
- 40時間
- 45時間
労働安全衛生法
第8編 3.労働衛生管理の基本 p300~301
労働衛生の3管理
- 労働安全衛生法では、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理の労働衛生の3管理を整備している。
- 健康管理については健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導を規定している。
職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。
- 労働組合法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働関係調整法
労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。
( )に入るのはどれか。
- 健康管理
- 総括管理
- 労務管理
- 出退勤管理
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 失業手当の給付
- 労働者に対する健康診断の実施
- 労働者に対する労働条件の明示
- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
ストレスチェック制度
職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。
- 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。
- 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。
- 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。
- 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。
労働者災害補償保険法
第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308
概要
- 労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。
- 保険者は政府(国)であり、事業に要する費用は原則として事業主が負担する保険料で賄われる。
労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 通勤災害時の療養給付
- 失業時の教育訓練給付金
- 災害発生時の超過勤務手当
- 有害業務従事者の健康診断
- 業務上の事故による介護補償給付
労働者災害補償保険法に規定されている保険者はどれか。
- 国
- 事業主
- 市町村
- 都道府県
- 健康保険組合
雇用保険法
第8編 9.9〕雇用保険制度 p310
雇用保険制度
- 雇用保険制度は政府が管掌する労働保険で、失業等給付や育児休業給付の支給などを行う。
- 労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、保険料は労働者と事業主双方が負担する。
雇用保険法について正しいのはどれか。
- 育児休業給付がある。
- 雇用保険は任意加入である。
- 雇用保険の保険者は市町村である。
- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。
環境基本法
第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p320~324
第9編2章 3.騒音・振動・悪臭対策の動向 p327~329
大気汚染に係る環境基準
- 環境基本法に基づき、大気汚染物質に対して大気汚染に係る環境基準が設定されている。
- そのうち、微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも特に粒径が小さい有害大気汚染物質で、呼吸器や循環器への影響が懸念される。
大気汚染物質はどれか。
- フロン
- カドミウム
- メチル水銀
- 微小粒子状物質(PM2.5)
騒音についての環境基準
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。
- 20dB以下
- 50dB以下
- 80dB以下
- 110dB以下
学校保健安全法
第10編 1.学校保健行政の動向 p341~344
主な規定
- 設置が義務づけられている学校医は、健康相談や保健指導、健康診断、疾病・感染症・食中毒予防処置などに従事する。
- 就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。
- 校長は感染症にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を停止させることができる。
学校保健について正しいのはどれか。
- 学校医は健康相談を実施する。
- 校長は学校医を置くことができる。
- 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。
- 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。
複合法律問題
公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。
- 未熟児の養育医療――医療法
- 結核児童の療養給付――児童福祉法
- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。
- 児童福祉法――受胎調節の実地指導
- 地域保健法――市町村保健センターの設置
- 健康増進法――医療安全支援センターの設置
- 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理
出産や育児に関する社会資源と法律の組合せで正しいのはどれか。
- 入院助産――児童福祉法
- 出産扶助――母体保護法
- 出産手当金――母子保健法
- 養育医療――児童手当法
精神保健医療福祉に関する法律について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。
- 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。
- 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。
- 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。
- 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。
健康に影響を及ぼす生活環境とそれを規定している法律の組合せで正しいのはどれか。
- 上水道水質――汚濁防止法
- 飲食店――食品衛生法
- 家庭ごみ――悪臭防止法
- 学校環境――教育基本法
- 住宅用の建築材料――環境基本法
社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。
- 医療保険――健康保険法
- 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉
- 雇用保険――社会福祉法
- 年金保険――生活困窮者自立支援法
次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。
- 未成年者喫煙禁止法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- アルコール健康障害対策基本法
- ギャンブル等依存症対策基本法
施行日が最も新しい法律はどれか。
- 高齢社会対策基本法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉
子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。
- 児童憲章の宣言
- 児童福祉法の公布
- 母子保健法の公布
- 児童の権利に関する条約の日本の批准
近年成立の法律・制度
法律や制度は社会情勢の変化に合わせて成立、改正、廃止が行われるため、看護師国家試験においては、過去問題だけを解いていても対応できない新規の内容の問題が出てくることは頻繁にあります。
「国民衛生の動向」では毎年、最新の制度改正を反映した情報に更新しているため、法律・制度の総チェックが可能です。
以下に看護師国家試験で頻出テーマであり、近年法改正等がなされた事項について列記します。詳しくは「国民衛生の動向」を確認しながら、過去問題と合わせて予想問題対策としてお使いください。
令和6年(2024年)
4月
- 「21世紀における第三次国民健康づくり運動」〈健康日本21(第三次)〉が開始(令和17年度まで)。「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の4つを基本的方向として掲げる。
- 医療計画の5疾病5事業に6事業目として「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加。
- 医療法等の改正による医師の働き方改革の適用開始。時間外労働の上限規制を定め、医師の健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限等)や医師の労働時間短縮計画の作成などの措置を講じる。また、業務の移管や共同化(タスク・シフティング/タスク・シェアリング)を推進する。
令和5年(2023年)
5月
- 新型コロナウイルス感染症を感染症法の5類感染症に位置づけ変更。また、学校において予防すべき感染症として第二種に位置づけ。
4月
- 9価HPVワクチンによる定期接種の開始。
令和4年(2022年)
12月
- 地域保健法改正により地方衛生研究所等の体制整備が法定化された。地方衛生研究所は、公衆衛生の向上と増進を図るための科学的・技術的中核として都道府県・指定都市が設置するもので、これまで地方衛生研究所設置要綱等に基づいて設置されている。
- 障害者総合支援法の一部改正。①就労アセスメントの手法を活用した「就労選択支援」の創設、②基幹相談支援センターおよび地域生活支援拠点等の整備を市町村に努力義務化など。
- 精神保健福祉法改正。①医療保護入院の見直し(家族等の同意・不同意の意思表示を行わない場合にも市町村長の同意により行うことを可能とすること、入院期間を設定して一定期間ごとに入院の要否を確認すること)、②入院者訪問支援事業の創設(入院訪問支援者が患者本人の希望により精神科病院を訪問してサポートを行うもの)など。
- 難病法改正。難病患者に対する医療費助成の開始時期を、申請日から重症化したと診断された日に前倒しするなど。
11月
- 健康日本21(第二次)最終評価報告書公表。目標値に達した項目は健康寿命や血糖コントロール不良者の減少など、悪化していると評価された項目はメタボリックシンドローム該当者・予備軍の数や適正体重の子どもの増加など。
10月
- 自殺総合対策大綱の閣議決定。「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」「女性に対する支援の強化」「地域自殺対策の取組強化」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など」を追加。
- 後期高齢者医療制度における窓口負担割合について、原則1割、現役並み所得者3割に加えて、一定以上の所得がある者を2割とする。
- 「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得。
4月
- 不妊治療の保険適用化。一般不妊治療における「人工授精」、生殖補助医療における「体外受精」「顕微授精」など保険適用。
令和3年(2021年)
6月
- 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」成立。医療的ケア児とは日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童をいう。
4月
- 改正母子保健法の施行により、市町村に産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子と乳児に対する産後ケア事業の実施を努力義務化。
- 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。
2月
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正。「まん延防止等重点措置」が創設され、従来の「緊急事態宣言」と合わせ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い順次適用された。
令和2年(2020年)
10月
- ロタウイルス感染症の予防接種の定期接種化。
4月
- 改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙。
- 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」使用開始。成人のナトリウム(食塩相当量)の目標量引き下げ(男7.5g/日未満・女6.5g/日未満)など。
令和元年(2019年)
12月
- 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(循環器病対策基本法)施行。政府は循環器病対策基本計画を策定し、循環器病対策を推進する。
- 「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)施行。政府は基本的な方針を策定し、関連施策を推進する。
「国民衛生の動向」は、昭和24年の創刊以来、時代の変化に合わせて、わが国の衛生を取り巻く最新の状況を網羅する本として幅広く利用されています。
かつては、結核をはじめとした感染症対策がその記述の中心でしたが、近年では感染症を軸とした対策から、生活習慣の改善による発症予防(一次予防)を推進する生活習慣病対策に重点が置かれてきていました。
しかし、2020年以降、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、医療機関や保健所だけでなく、介護施設や飲食店、学校、家庭などでも感染症対策の重要性が再認識されたところです。こうした中で、看護師国家試験では、これまで同様、もしくはこれまで以上に感染症を問う問題が出題されると考えられます。
当ページでは、113回(2024年)から104回(2015年)の10年分の試験問題の中から感染症に関わる問題をピックアップし、簡易的な説明とともに示します。問題を解きながら、「国民衛生の動向」第3編3章の感染症対策の記述を参考に、感染症法の規定、各感染症の特徴、医療機関における予防策など、総合的に把握することが大切です。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
感染症問題目次
- 結核
- ウイルス性肝炎
- マラリア
- エイズ/HIV
- 風疹・麻疹
- 性感染症
- その他の感染症
- 院内感染対策
- 身体の免疫機能
- 世界保健機関(WHO)
- 学校における感染症予防
感染症法
感染症法による分類
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉では、対象とする感染症の感染力や罹患した場合の症状の重篤性などに基づいて以下のように分類している。
【対象感染症の一例】
- 1類感染症:エボラ出血熱、ペスト
- 2類感染症:結核、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉
- 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症
- 4類感染症:A型肝炎、E型肝炎、マラリア
- 5類感染症:後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、麻疹、風疹、細菌性髄膜炎、水痘
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。
- 一類
- 二類
- 三類
- 四類
- 五類
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。
- 一類感染症
- 二類感染症
- 三類感染症
- 四類感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく五類感染症はどれか。2つ選べ。
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
- 腸管出血性大腸菌感染症
- つつが虫病
- 日本脳炎
- 梅毒
感染症法に基づく届出基準
- 1~4類感染症と、5類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風疹および麻疹)、新型インフルエンザ等感染症を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
- 5類感染症のうち麻疹等を除く全数把握対象疾患については7日以内に届け出なければならない。
感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。
- 結核――診断後7日以内
- 梅毒――診断後直ちに
- E型肝炎――診断後直ちに
- 腸管出血性大腸菌感染症――診断後7日以内
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉――診断後直ちに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
- インフルエンザ
- 細菌性髄膜炎
- 水痘
- 梅毒
結核
結核
- 結核(2類感染症)は、結核菌によって空気感染し、主に肺結核を引き起こすわが国の主要な感染症の一つで、咳、痰、呼吸困難などの症状を呈する。
- 結核菌に感染後、すぐに発病する一次結核と、長期にわたり体内に潜伏したのち再び活動を開始して発症する二次結核がある。
- 結核菌の消毒にはエタノールが有効である。
感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。
- インフルエンザ
- 結核
- ノロウイルス性胃腸炎
- 流行性耳下腺炎
肺結核について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 結核の10%程度である。
- 感染経路は接触感染である。
- 肺アスペルギルス症と同じ原因菌である。
- 二次性の発症は過去の感染の再活性化による。
- DOTS〈Directly Observed Treatment, Short-course〉が推奨される。
結核患者・死亡数の推移
令和4年(2022年)の日本の結核対策で増加が問題とされているのはどれか。
- 新登録結核患者数
- 菌喀痰塗抹陽性の肺結核患者数
- 外国生まれの新登録結核患者の割合
- 結核による死亡数
BCGワクチン
- BCGは結核を予防するワクチンで、予防接種法に基づき生後1歳に至るまで(標準的な接種は生後5~8か月)の間に定期接種を行う。
- 接種後5~6週間頃に針の痕に一致して発赤や膿がみられることがあるが、正常な反応とされる。ただし、接種から約10日以内にこうした反応が生じた場合は、すでに結核菌に感染しているおそれもあり、速やかに医療機関に相談・受診する必要がある。
発育と発達に遅れのない生後6か月の男児。BCG接種の翌日に接種部位が赤く腫れ次第に増悪して膿がみられたため、母親は接種後4日目に医療機関に電話で相談し、看護師が対応した。児に発熱はなく、哺乳や機嫌は良好である。
このときの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「通常の反応です」
- 「速やかに来院してください」
- 「1週間後にまた電話をください」
- 「患部をアルコール消毒してください」
ウイルス性肝炎
A型肝炎
- A型肝炎(4類感染症)は、A型肝炎ウイルス(HAV)の感染による肝疾患で、主な感染経路は汚染された食品や水などを介した経口感染である。
- 感染後まれに劇症化することがあり、B型肝炎やC型肝炎とは異なり慢性化することはない。
経口感染するウイルス性肝炎はどれか。
- A型肝炎
- B型肝炎
- C型肝炎
- D型肝炎
Aさん(42歳、女性)は、3日前から微熱と強い全身倦怠感を自覚したため病院を受診したところ、肝機能障害が認められ、急性肝炎の診断で入院した。1か月前に生の牡蠣を摂取している。Aさんはこれまで肝臓に異常を指摘されたことはなく、家族で肝臓疾患を罹患した者はいない。
Aさんが罹患した肝炎について正しいのはどれか。
- 細菌感染である。
- 劇症化する危険性がある。
- 慢性肝炎に移行しやすい。
- インターフェロン療法を行う。
B型肝炎
- B型肝炎(5類感染症)は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染による肝疾患である。HBVはDNAウイルスで、RNAウイルスである他の肝炎ウイルスとは異なる。
- 主な感染経路として血液感染(医療現場での針刺し事故等)、母子感染(垂直感染)、性行為感染がある。
- B型肝炎に対するワクチンがあり、定期予防接種の対象となっている。
ウイルス性肝炎の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。
- A型肝炎ウイルス
- B型肝炎ウイルス
- C型肝炎ウイルス
- E型肝炎ウイルス
針刺し事故によって感染するのはどれか。
- RSウイルス
- B型肝炎ウイルス
- ヘルペスウイルス
- サイトメガロウイルス
C型肝炎
- C型肝炎(5類感染症)は、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染による肝疾患で、主な感染経路は血液感染である。
- 感染後、多くは自覚症状が現れず慢性化し、肝硬変や肝がんに進行する場合がある。
- 治療としては主にインターフェロン治療がとられる。
C型慢性肝炎に使用するのはどれか。
- ドパミン
- インスリン
- リドカイン
- インターフェロン
マラリア
マラリア
- マラリア(4類感染症)は熱帯・亜熱帯地域に広く分布する感染症で、ハマダラカ(蚊)によって媒介される。最も多い症状は発熱と悪寒で、熱発は間隔をあけて発熱期と無熱期を繰り返す。
- その感染力や対策費用の負担の大きさから、「HIV/エイズ」「結核」と並び三大感染症ともいわれる。
令和4年(2022年)時点での世界の三大感染症に入るのはどれか。
- ポリオ〈急性灰白髄炎〉
- マラリア
- 天然痘
- 麻疹
Aさん(28歳、男性)。海外出張で訪れたアフリカ地域から帰国後1週に39℃の発熱と解熱を繰り返すため外来を受診した。腹部症状は特にない。
予測される感染症はどれか。
- マラリア
- コレラ
- 赤痢
- 破傷風
エイズ/HIV
エイズ/HIV
- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉は、免疫システムである白血球中のヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球に感染し、増殖、破壊することで、免疫不全状態を引き起こす。
- HIV感染後、多くは無症候性キャリアの状態で10年程度経過した後に症状が現れ、ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)などの指標疾患を発症するとエイズ(5類感染症)と診断される。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染している患者で、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の状態にあると判断できる疾患はどれか。
- 季節性インフルエンザ
- ニューモシスチス肺炎
- ノロウイルス性腸炎
- 単純性膀胱炎
HIVの感染経路
- HIVの主な感染経路は、①HIV感染者との性行為、②血液または血液製剤の輸注、③母子感染(垂直感染)の3つである。
- 性行為による感染対策としてはコンドームの使用、母子感染対策としては妊婦の感染の早期発見と抗HIV薬等による適切な対策が効果的である。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉の感染経路で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 感染者の嘔吐物との接触
- 感染者の咳による曝露
- 感染者の糞便との接触
- 感染者からの輸血
- 感染者との性行為
母体から胎児への感染はどれか。
- 水平感染
- 垂直感染
- 接触感染
- 飛沫感染
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。
- 空気感染する。
- 無症候期がある。
- DNAウイルスによる。
- 血液中のBリンパ球に感染する。
血液曝露事故によるHIV感染率
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に汚染された注射針による針刺し事故の感染率で正しいのはどれか。
- 40%
- 10%
- 2%
- 0.3%
HIVの感染者への指導
学習支援として、集団指導よりも個別指導が望ましいのはどれか。
- 小学生へのインフルエンザ予防の指導
- 塩分摂取量が多い地域住民への食事指導
- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導
- 3〜4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導
HIV感染者の動向
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 本人より先に家族に病名を告知する。
- 国内では異性間性的接触による感染が最も多い。
- 適切な対応によって母子感染率を下げることができる。
- 性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。
- HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について正しいのはどれか。
- 令和4年(2022年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。
- 日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。
- 早期に発見して治療を開始すれば完治する。
- 保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。
世界の地域別HIV感染者数
令和4年(2022年)の国連エイズ合同計画〈UNAIDS〉の報告において、ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉陽性者が最も多い地域はどれか。
- 東欧・中央アジア
- 西欧・中欧・北アメリカ
- アジア太平洋
- 東部・南部アフリカ
風疹・麻疹
風疹
- 風疹(5類感染症)は、発熱や発疹、リンパ節腫脹を特徴とする感染性疾患で、風疹ウイルスの飛沫感染により生じる。
- 妊婦が妊娠20週ごろまでに感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。
風疹の疑いがある入院患者の隔離予防策で適切なのはどれか。
- 標準予防策
- 標準予防策と接触感染予防策
- 標準予防策と飛沫感染予防策
- 標準予防策と空気感染予防策
妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。
- 水痘
- 風疹
- 麻疹
- 流行性耳下腺炎
妊娠中の母体の要因が胎児に及ぼす影響について正しいのはどれか。
- 飲酒の習慣による巨大児
- 喫煙による神経管形成障害
- 妊娠初期の風疹の罹患による先天性心疾患
- ビタミンAの過剰摂取による低出生体重児
妊婦の感染症と児への影響の組合せで正しいのはどれか。
- 風疹――白内障
- 性器ヘルペス――聴力障害
- トキソプラズマ症――先天性心疾患
- 性器クラミジア感染症――小頭症
麻疹
- 麻疹(5類感染症)は高熱や頬粘膜に生じるコプリック斑、下半身に広がる赤い発疹を特徴とする感染性疾患で、麻疹ウイルスの空気感染により生じる。
- 一次予防として、麻疹ワクチンの定期予防接種(二期)が行われている。ただし、麻疹に対しては特異的な治療法はなく、症状を和らげる対症療法が行われる。
感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。
- 結核――接触感染
- 麻疹――空気感染
- マラリア――飛沫感染
- インフルエンザ――経口感染
入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。
- 麻疹
- 風疹
- 手足口病
- 流行性耳下腺炎
麻疹に関して正しいのはどれか。2つ選べ。
- 合併症として脳炎がある。
- 感染力は発疹期が最も強い。
- 効果的な抗ウイルス薬がある。
- 2回のワクチン定期接種が行われている。
- エンテロウイルスの感染によって発症する。
性感染症
性感染症報告数と予防
- 性感染症とは、性行為によって伝播する5疾患(梅毒・性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・淋菌感染症・尖圭コンジローマ)で、令和4年(2022年)の報告数では、性器クラミジア感染症が30,136人と最も多い。
- 性感染症の予防にはコンドームの使用が効果的で、感染、または感染疑いのある場合、本人だけでなくパートナー等も含めた検査・治療を行うことが重要である。
令和4年(2022年)の感染症発生動向調査による年間の性感染症〈STD〉報告数で最も多いのはどれか。
- 性器クラミジア感染症
- 尖圭コンジローマ
- 性器ヘルペス
- 淋菌感染症
梅毒
- 梅毒は性行為による接触で伝播する性感染症で、梅毒トレポネーマ(細菌)の感染によって生じる。
- 早期の抗菌薬による薬物治療で完治が可能だが、検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすことがある。
梅毒について正しいのはどれか。
- ウイルス感染症である。
- 感染経路は空気感染である。
- 治療の第一選択薬はステロイド外用薬である。
- 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。
その他の感染症
細菌性髄膜炎
細菌性髄膜炎の症状はどれか。
- 羞明
- 羽ばたき振戦
- Raynaud(レイノー)現象
- Blumberg(ブルンベルグ)徴候
水痘
- 水痘(5類感染症)は水痘帯状疱疹ウイルスにより引き起こされる感染症で、典型的な症例では、皮膚の表面が赤くなる紅斑から発疹が始まり、水疱、膿疱を経て痂皮(かさぶた)化して治癒する。
- 定期予防接種として、生後12月から生後36月までの幼児(2回接種)を対象としている。
水痘の症状はどれか。
- 耳下腺の腫脹
- 両頰部のびまん性紅斑
- 水疱へと進行する紅斑
- 解熱前後の斑状丘疹性発疹
幼児を対象とする定期予防接種はどれか。
- DTワクチン(二種混合)
- ロタウイルスワクチン
- BCGワクチン
- 水痘ワクチン
流行性角結膜炎
流行性角結膜炎の原因はどれか。
- 淋菌
- 緑膿菌
- クラミジア
- アデノウイルス
- ヘルペスウイルス
レジオネラ症
- レジオネラ症(4類感染症)は自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息しているレジオネラ属菌の感染により発症し、主な病型として重症の肺炎を引き起こすレジオネラ肺炎がある。
- 浴槽の湯を濾過器を通して循環させる循環式浴槽では、換水や消毒、清掃を怠ることでレジオネラ属菌が繁殖する危険性が高まる。
循環式浴槽の水質汚染で発症するのはどれか。
- コレラ
- A型肝炎
- レジオネラ肺炎
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
インフルエンザ(季節性)
飛沫感染するのはどれか。
- 疥癬
- コレラ
- A型肝炎
- インフルエンザ
ノロウイルス感染症
- ノロウイルスは冬季に多く発生する食中毒で、物品や居室の消毒には次亜塩素酸ナトリウムを用いる。
- 乾燥すると空中に漂いやすく、これが口に入って感染することがあるため、嘔吐物は乾燥する前に速やかに処理する必要がある。
ノロウイルス感染症に罹患した患者の嘔吐物が床に飛び散っている。
この処理に使用する消毒薬で適切なのはどれか。
- 70%エタノール
- ポビドンヨード
- 塩化ベンザルコニウム
- 次亜塩素酸ナトリウム
人類共通感染症
人獣共通感染症で蚊が媒介するのはどれか。
- Q熱
- 黄熱
- 狂犬病
- オウム病
- 重症熱性血小板減少症候群〈SFTS〉
予防接種
予防接種の役割
感染症の成立過程において、予防接種が影響を与える要素はどれか。
- 病原体
- 感染源
- 感染経路
- 宿主の感受性
定期予防接種の対象(令和3年4月現在)
- 定期予防接種のうち、毒性を弱めた生ワクチンが使用される対象は、結核(BCG)、麻疹、風疹、水痘、ロタウイルスなどとなっている。
- 定期予防接種のうち、感染力を失わせた不活化ワクチン・トキソイドが使用される対象は、ポリオ、百日せき、ジフテリア、破傷風、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(Hib)、ヒトパピローマウイルス(HPV)などとなっている。
▶105回午後77
乳児の髄膜炎などを抑制するため、平成25年(2013年)に定期接種に導入されたのはどれか。
- 日本脳炎ワクチン
- ロタウイルスワクチン
- インフルエンザワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
- Hibワクチン
予防接種に生ワクチンが使用される疾患はどれか。2つ選べ。
- ジフテリア
- 日本脳炎
- 破傷風
- 結核
- 麻疹
定期予防接種について正しいのはどれか。
- BCG接種前にツベルクリン反応を実施する。
- ロタウイルスワクチンは不活化ワクチンである。
- ポリオウイルスワクチンの定期接種は廃止された。
- 麻疹ウイルスワクチンは就学までに4回接種する。
- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンは筋肉内注射する。
院内感染対策
標準予防策(スタンダードプリコーション)
標準予防策(スタンダードプリコーション)で感染源として取り扱うのはどれか。
- 汗
- 爪
- 唾液
- 頭髪
標準予防策(スタンダードプリコーション)において、創傷や感染のない患者への援助で使い捨て手袋が必要なのはどれか。
- 手浴
- 洗髪
- 口腔ケア
- 寝衣交換
手指衛生(手洗い)
感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。
- 石けんは十分に泡立てる。
- 洗面器に溜めた水で洗う。
- 水分を拭きとるタオルを共用にする。
- 塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。
感染経路別予防策(空気感染)
空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。
- 手袋
- N95マスク
- シューズカバー
- フェイスシールド
感染性廃棄物
廃棄する物とその区分との組合せで正しいのはどれか。
- 滅菌パックの袋――産業廃棄物
- エックス線フィルム――一般廃棄物
- 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物
- pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物
バイオハザードマーク
感染性廃棄物を収納した容器には、関係者が識別できるように下記のバイオハザードマークを付けることが推奨されている。

廃棄物の種類が識別できるように、性状に応じてマークの色を、①液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、②固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、③鋭利なもの(注射針等)は黄色と分けることが望ましい。
使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。
- 赤
- 黄
- 黒
- 橙
医療機関の廃棄物とバイオハザードマークの色の組合せで正しいのはどれか。
- 固体状の放射性廃棄物――黒色
- 注射針などの鋭利な廃棄物――赤色
- 血液などの液状、泥状の廃棄物――黄色
- 血液の付着したガーゼの廃棄物――橙色
消毒・滅菌
オートクレーブによる滅菌法はどれか。
- 乾熱滅菌
- プラズマ滅菌
- 高圧蒸気滅菌
- 酸化エチレンガス滅菌
医療器材と消毒・滅菌の組合せで正しいのはどれか。
- 手術用持針器――第4級アンモニウム塩
- ステンレス製便器――熱水消毒
- 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌
- ベッド柵――グルタラール
感染制御チーム
病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。
- 医師で構成される。
- 各病棟に配置される。
- アウトブレイク時に結成される。
- 感染症に関するサーベイランスを行う。
薬剤耐性菌対策
院内感染の観点から、多剤耐性に注意すべきなのはどれか。
- ジフテリア菌
- 破傷風菌
- 百日咳菌
- コレラ菌
- 緑膿菌
身体の免疫機能
白血球(好中球)
- 白血球は体内に侵入した細菌、ウイルスなどを排除する免疫機能を持つ。
- 白血球の多くを占める好中球は、細菌感染から体を守る主要な生体防御機構(免疫)である。
免疫機能に関与する細胞はどれか。
- 血小板
- 白血球
- 網赤血球
- 成熟赤血球
細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。
- 単球
- 好酸球
- 好中球
- 好塩基球
- リンパ球
敗血症性ショック
- 敗血症は、細菌が産生するエンドトキシン等に起因して重度の全身性の炎症反応や臓器障害を起こしている病態をいう。
- 蘇生処置にも関わらず低血圧が持続し、ショック状態に陥った状態を敗血症性ショックといい、急性多臓器不全などにより死亡リスクが非常に高い。
細菌感染で起こるショックはどれか。
- 心原性ショック
- 敗血症性ショック
- アナフィラキシーショック
- 循環血液量減少性ショック
敗血症性ショックについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- 血圧は上昇する。
- 血中の乳酸濃度は低下する。
- エンドトキシンが原因である。
- 最重症の臨床像は多臓器不全である。
- コールドショックからウォームショックに移行する。
世界保健機関(WHO)
WHOの役割
国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。
- 国連難民高等弁務官事務所〈UNHCR〉――有償資金協力
- 国連教育科学文化機関〈UNESCO〉――児童の健康改善
- 世界保健機関〈WHO〉――感染症対策
- 国際労働機関〈ILO〉――平和維持活動
学校における感染症予防
学校において予防すべき感染症
- 学校保健安全法では、学校において予防すべき感染症として、感染力に応じて第一種から第三種に分類され、出席停止の期間の基準が定められている。
- 分類の考え方として、感染症法の1類感染症と2類感染症(結核除く)は第一種、それ以外の空気感染または飛沫感染により流行を広げる可能性が高い感染症は第二種、そのほかの感染症は第三種とされる。
学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。
- インフルエンザ
- 細菌性赤痢
- ジフテリア
- 腸チフス
- 流行性角結膜炎
介護保険制度は、少子高齢化の進む中で、社会全体で高齢者介護を支えるため、平成12年度(2000年度)の介護保険法の施行に伴い開始し、20年以上が経過しました。
制度開始当初の平成12年度(2000年度)と令和3年度(2021年度)を比べると、サービス受給者数は184万人から589万人、給付費は3.2兆円から10.4兆円と3倍以上伸びており(介護保険事業状況報告)、広く国民に身近な制度となっています。
介護保険制度は医療との連携の観点からも重要で、看護師国家試験において頻出テーマの一つとなっており、制度の概要や法改正に伴うサービスの追加・変更、介護者の現状など、幅広い最新の知識をしっかりと押さえておく必要があります。
このページでは、第113回(2024年)から第104回(2015年)までの過去10年の看護師国家試験問題の中から介護保険制度に関する問題をピックアップし、解説とともに示します。これまでの介護制度問題の出題傾向を把握し、最新の制度や詳細な統計を「国民衛生の動向」第5編で確認することで、介護制度に関する理解を一層深めていただければ幸いです。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
介護保険制度問題目次
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
- 地域支援事業
- 地域包括支援センター
- 介護人材
- 介護者の支援
介護保険制度の対象・手続き
保険者
▶108回午前4
介護保険制度における保険者はどれか。
- 市町村及び特別区
- 都道府県
- 保健所
- 国
被保険者
▶106回午前4
介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
- 45歳以上
- 55歳以上
- 65歳以上
- 75歳以上
▶109回午前3
介護保険の第2号被保険者は、( )歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
( )に入る数字はどれか。
- 30
- 40
- 50
- 60
介護保険料・利用者負担
▶108回午後29
介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。
- 介護保険料は全国同額である。
- 介護保険被保険者証が交付される。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 介護保険給付の利用者負担は一律3割である。
要介護認定
- 市町村は、被保険者からの要介護認定の申請を受けて調査を行う。
- 市町村に設置された介護認定審査会は、被保険者の程度に応じて要介護状態の区分(要支援1・2、要介護1~5の7区分)の審査・判定を行う。
▶110回午前4
要介護認定の申請先はどれか。
- 市町村
- 診療所
- 都道府県
- 介護保険審査会
▶104回午後4
要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。
- 介護認定審査会
- 介護保険審査会
- 社会福祉協議会
- 社会保障審議会
▶112回午前5
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
- 4
- 5
- 6
- 7
介護給付・予防給付
- 要介護状態の者には介護給付が支給され、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを内容とする。
- 要支援状態の者には予防給付が支給され、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを内容とする。
▶105回午前4
介護保険の給付はどれか。
- 年金給付
- 予防給付
- 求職者給付
- 教育訓練給付
▶111回午後4
介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。
- 医療給付
- 介護給付
- 年金給付
- 予防給付
居宅サービス
訪問入浴介護
- 訪問入浴介護は、自宅の浴槽での入浴が困難な要介護者に対して、浴槽を居宅に持ち込み、入浴の介護を行う居宅サービスである。
- ほぼ寝たきりの状態にある要介護5の利用者の割合が46.9%(令和3年)と半分近くを占めている。
▶113回午後68
介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。
- 訪問入浴介護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶109回午前72改題
令和3年(2021年)の介護サービス施設・事業所調査における要介護度別利用者数の構成割合で、要介護5の利用者が最も多いのはどれか。
- 訪問介護
- 訪問看護ステーション
- 居宅介護支援
- 訪問入浴介護
福祉用具貸与
- 福祉用具貸与は介護保険制度における居宅サービスであり、利用者負担の上で福祉用具の貸与を受ける。
- 要支援及び要介護1の者は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)のみ貸与を受けられる。
▶108回午前58
Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。
Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。
- 車椅子
- 歩行器
- 電動ベッド
- 入浴用椅子
特定福祉用具販売
▶112回午後81
介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。
- 簡易浴槽
- 特殊寝台
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 取り付け工事を伴わないスロープ
施設サービス
施設サービスの類型
▶106回午後9
介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。
- 介護保険法
- 健康保険法
- 地域保健法
- 老人福祉法
▶111回午前53
介護保険制度における施設サービスはどれか。
- 介護医療院サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
介護老人福祉施設
▶106回午前59
介護保険法で「入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 介護療養型医療施設
- 介護療養型老人保健施設
介護老人保健施設
▶108回午後10・104回午前8類問
要介護者に対し、看護・医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行うのはどれか。
- 介護老人保健施設
- 短期入所生活介護
- 保健センター
- 有料老人ホーム
▶113回午後41
介護老人保健施設について適切なのはどれか。
- 常勤医師の配置は義務ではない。
- 老人福祉法に基づき設置される。
- 要介護者に対して自宅での生活に向けた支援を行う。
- 従事者の配置基準は看護職員と介護職員が同数である。
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
▶110回午後68
介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。
- 重度訪問介護
- 地域活動支援事業
- 小規模多機能型居宅介護
- 特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
▶108回午後51
介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 通所リハビリテーション
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
▶105回午前74
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)で正しいのはどれか。
- 光熱費は自己負担である。
- 12人を1つのユニットとしている。
- 看護師の配置が義務付けられている。
- 介護保険制度の施設サービスである。
- 臨死期は提携している病院に入院する。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶105回午後89
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 介護予防サービスである。
- 24時間を通じて行われる。
- 地域密着型サービスである。
- 重症心身障害児を対象とする。
- 施設サービス計画の作成を行う。
サービスの指定・監督
▶112回午前70
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
- 福祉用具貸与
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉
地域支援事業
概要
- 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するため、市町村は65歳以上のすべての高齢者を対象として、地域支援事業を実施している。
- 地域支援事業の総合事業として、外出や調理が困難な者に対する配食サービス(介護予防・生活支援サービス事業)や、介護予防教室(一般介護予防事業)を行っている。
▶113回午前4
介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。
- 保険給付である。
- 都道府県の事業である。
- 介護保険施設で実施される。
- 配食サービスは生活支援サービスの1つである。
▶112回午前55
65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。
- 介護予防教室
- 介護老人保健施設
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護〈デイサービス〉
地域包括ケアシステム
地域包括支援センター
▶111回午後86
地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
- 介護保険法
- 健康増進法
- 社会福祉法
- 地域保健法
- 老人福祉法
▶108回午前11・107回午前4類問
平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。
- 保健所
- 市町村保健センター
- 地域包括支援センター
- 訪問看護ステーション
地域包括支援センターの業務
地域包括支援センターが行う地域支援事業として以下の業務を実施する。
- 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
- 総合相談支援業務
- 権利擁護業務(虐待の防止、早期発見)
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
▶108回午後68
家族からネグレクトを受けている高齢者について、地域包括支援センターに通報があった。
この通報を受けた地域包括支援センターが行う業務はどれか。
- 権利擁護
- 総合相談支援
- 介護予防ケアマネジメント
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援
地域包括ケアシステム
▶106回午後58
地域包括ケアシステムについて正しいのはどれか。
- 都道府県を単位として構築することが想定されている。
- 75歳以上の人口が急増する地域に重点が置かれている。
- 本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている。
- 地域特性にかかわらず同じサービスが受けられることを目指している。
地域包括ケアシステムにおける支援のあり方
地域包括ケアシステムにおける支援は、以下のとおり分類される。
- 生活保護など税による公の負担により支える公助
- 介護保険など負担と受給による支え合い(社会保険方式)である共助
- 費用負担が制度的に裏付けされていないボランティアなどの助け合いである互助(インフォーマルサポート)
- 自発的な体重測定など自ら行う自助
▶108回午前74
地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。
- 高齢者が生活保護を受けること
- 住民が定期的に体重測定すること
- 要介護者が介護保険サービスを利用すること
- 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと
▶107回午後31
インフォーマルサポートはどれか。
- 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成
- 医師による居宅療養管理指導
- 近隣住民による家事援助
- 民生委員による相談支援
介護人材
介護支援専門員(ケアマネジメント)
- 介護支援専門員等によるケアマネジメントでは、利用者の身体状態や家族の介護能力などを踏まえた解決すべき課題を把握(アセスメント)し、解決のための介護サービス計画を作成する。
- 介護サービス計画に基づき実施されたサービスについては、要介護者等の心身や生活の状況の変化を継続的に把握・評価(モニタリング)し、それに応じて介護サービス計画の修正を行う。
- 介護サービス計画は利用者自ら作成し、居宅サービスを受けることも可能である。
▶105回午後9
介護支援専門員が行うのはどれか。
- 通所介護の提供
- 福祉用具の貸与
- 短期入所生活介護の提供
- 居宅サービス計画の立案
▶110回午前67
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
- 家族の介護能力はアセスメントに含めない。
- 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。
- 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。
- モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。
▶104回午前82
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
- スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。
- アセスメントで利用者の疾患を診断する。
- 利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。
- ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。
- ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。
介護福祉士
▶107回午後81・112回午後34類問
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。
- 摘便
- 創処置
- 血糖測定
- 喀痰吸引
- インスリン注射
介護者の支援
レスパイトケア
▶109回午前8
レスパイトケアの目的はどれか。
- 介護者の休息
- 介護者同士の交流
- 介護者への療養指導
- 療養者の自己決定支援
▶105回午後62
レスパイトケアの主な目的について適切なのはどれか。
- 高度な治療を集中的に行う。
- 家族へ介護方法の指導を行う。
- 居宅サービス料金を補助する。
- 介護を行う家族のリフレッシュを図る。
▶111回午前68・106回午後45類問
Aさん(80歳、女性)は1人暮らし。要介護2の認定を受け、長男(50歳、会社員)、長男妻(45歳、会社員)、孫(大学生、男性)と同居することになった。長男の家の間取りは、洋室5部屋、リビング、台所である。Aさんは同居後に訪問看護を利用する予定である。訪問看護を利用するにあたりAさんの家族から「在宅介護は初めての経験なのでどうすればよいですか」と訪問看護師に相談があった。
訪問看護師の説明で最も適切なのはどれか。
- 「Aさんの介護用ベッドはリビングに置きましょう」
- 「Aさんの介護に家族の生活リズムを合わせましょう」
- 「活用できる在宅サービスをできる限り多く利用しましょう」
- 「特定の同居家族に介護負担が集中しないように家族で話し合いましょう」
育児・介護休業法における介護関連規定
- 育児・介護休業法における介護休業では、要介護状態にある対象家族1人につき3回まで、連続したひとまとまりの期間の休業(合計93日まで)を取得できる。
- 対象家族は配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が該当する。
▶111回午前30
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
- 介護休業は分割して取得することはできない。
- 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
- 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
- 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
訪問看護
訪問看護を行う職種
▶104回午後9
介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。
- 医師
- 薬剤師
- 理学療法士
- 介護福祉士
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、訪問看護サービスを提供する事業所として都道府県知事から指定を受けて開設されるもので、以下の人員基準等が定められている。
- 看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)と、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数置くこと。
- 管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師とすること。
- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設置すること。
▶111回午後10
指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。
( )に入るのはどれか。
- 1.0
- 1.5
- 2.0
- 2.5
▶107回午後9
訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。
- 医師
- 看護師
- 介護福祉士
- 理学療法士
▶109回午後71
訪問看護事業所で正しいのはどれか。
- 24時間対応が義務付けられている。
- 自宅以外への訪問看護は認められない。
- 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。
- 従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。
▶105回午前63
訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。
- 事務所を設置する必要はない。
- 訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。
- 利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。
- 利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。
▶112回午後67
指定訪問看護ステーションについて正しいのはどれか。
- 看護職員以外は配置できない。
- 緊急時用の薬剤の保管が義務付けられている。
- 訪問看護指示書に基づいて療養者のケアを行う。
- 従事する看護職員は5年以上の臨床経験が必要である。
訪問看護の対象者
要介護者等には介護保険から、それ以外の者には医療保険から訪問看護の給付が行われる。ただし、要介護者等であっても、以下に該当する者は医療保険の給付による。
- 末期の悪性新生物や人工呼吸器を使用している状態など厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
- 主治医による特別訪問看護指示書(14日間有効、一部2回交付可)の交付を受けた者
- 認知症以外の精神障害を有する者
また、これらに該当する者は、週3日を超えてのサービス提供が可能となっている。
▶105回午前62
介護保険被保険者で介護保険による訪問看護が提供されるのはどれか。
- 脳血管疾患
- 末期の結腸癌
- 脊髄小脳変性症
- 進行性筋ジストロフィー
▶109回午前69
Aさん(68歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。
Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。
- 医療保険から給付される。
- 特別訪問看護指示書を受けて実施される。
- 複数の訪問看護事業所の利用はできない。
- 理学療法士による訪問は給付が認められない。
▶107回午後62
健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。
- サービス対象は75歳以上である。
- 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。
- 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。
- 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。
▶105回午後63
訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。
- 主治医の意見書が必要である。
- 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
- サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
- 主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
▶107回午前62
特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。
- 提供できる頻度は週に3回までである。
- 提供できる期間は最大6か月である。
- 対象に指定難病は含まない。
- 医療保険が適用される。
▶108回午後65
訪問看護制度で正しいのはどれか。
- 管理栄養士による訪問は保険請求できる。
- 精神科訪問看護は医療保険から給付される。
- 医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。
- 訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。
訪問看護の利用者の状況
- 介護保険法の利用者が74.4万人、健康保険法等の利用者が48.4万人となっている。(令和5年)
- 年齢階級別にみると、80~89歳が38.0万人と最も多い。(令和4年)
- 要介護度別にみると、要介護2が15.9万人と最も多く、それを境に要介護(要支援)度が上がる・下がるにつれて減少する。(令和4年)
- 傷病分類別にみると、循環器系の疾患が26.9万人(うち、脳血管疾患12.4万人)と最も多い。(令和4年)
▶113回午前68改題
令和4年(2022年)の介護サービス施設・事業所調査において、介護保険制度による訪問看護の利用者の特徴で正しいのはどれか。
- 要介護5の利用者が最も多い。
- 傷病別では悪性新生物が最も多い。
- 医療保険制度による利用者よりも多い。
- 要支援1、2の利用者は全体の利用者の4割を占める。
令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第112回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 必修問題
▶午前1改題
令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。
- 19.7歳
- 24.7歳
- 29.7歳
- 34.7歳
▶午前2改題
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。
- 頭痛
- 腰痛
- 体がだるい
- 目のかすみ
▶午前3
喫煙指数(Brinkman〈ブリンクマン〉指数)を算出するために、喫煙年数のほかに必要なのはどれか。
- 喫煙開始年齢
- 受動喫煙年数
- 家庭内の喫煙者数
- 1日の平均喫煙本数
▶午前4
休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。
- 30時間
- 35時間
- 40時間
- 45時間
▶午前5
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
- 4
- 5
- 6
- 7
▶午前6
緩和ケアの目標で正しいのはどれか。
- 疾病の治癒
- 余命の延長
- QOLの向上
- 在院日数の短縮
▶午前7
運動機能の発達で3歳以降に獲得するのはどれか。
- 階段を昇る。
- ひとりで立つ。
- ボールを蹴る。
- けんけん〈片足跳び〉をする。
▶午前8
ハヴィガースト, R. J.が提唱する成人期の発達課題はどれか。
- 経済的に自立する。
- 身体的衰退を自覚する。
- 正、不正の区別がつく。
- 読み、書き、計算ができる。
▶午前9改題
令和4年(2022年)の衛生行政報告例における看護師の就業場所で、医療機関(病院、診療所)の次に多いのはどれか。
- 事業所
- 市町村
- 保健所
- 訪問看護ステーション
▶午前10
体性感覚はどれか。
- 視覚
- 触覚
- 聴覚
- 平衡覚
▶午前11
健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。
- 単球
- 好酸球
- 好中球
- リンパ球
▶午前12
体温変化をとらえ、体温調節の指令を出すのはどれか。
- 橋
- 小脳
- 視床下部
- 大脳皮質
▶午前13
下血がみられる疾患はどれか。
- 肝囊胞
- 大腸癌
- 子宮体癌
- 腎細胞癌
▶午前14
糖尿病の急性合併症はどれか。
- 足壊疽
- 脳血管疾患
- 糖尿病網膜症
- ケトアシドーシス昏睡
▶午前15
メタボリックシンドロームの診断基準において男性の腹囲〈ウエスト周囲径〉で正しいのはどれか。
- 80cm以上
- 85cm以上
- 90cm以上
- 95cm以上
▶午前16
炎症マーカーはどれか。
- CA19-9
- 抗核抗体
- C反応性蛋白質〈CRP〉
- リウマトイド因子〈RF〉
▶午前17
薬物動態で肝臓が関与するのはどれか。
- 吸収
- 分布
- 代謝
- 蓄積
▶午前18
胃から食道への逆流を防ぐために、成人が食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。
- 座位
- 仰臥位
- 右側臥位
- 半側臥位
▶午前19
全身清拭時に皮膚に触れるタオルの温度で適切なのはどれか。
- 20〜22℃
- 30〜32℃
- 40〜42℃
- 50〜52℃
▶午前20
個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。
- 手袋
- ガウン
- サージカルマスク
- フェイスシールド
▶午前21
オートクレーブによる滅菌法はどれか。
- 酸化エチレンガス滅菌
- 高圧蒸気滅菌
- 放射線滅菌
- 乾熱滅菌
▶午前22
薬物の吸収速度が最も速いのはどれか。
- 経口投与
- 筋肉内注射
- 静脈内注射
- 直腸内投与
▶午前23
室内空気下での呼吸で、成人の一般的な酸素療法の適応の基準はどれか。
- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr以上
- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr未満
- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr以上
- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr未満
▶午前24
CO2ナルコーシスの症状で正しいのはどれか。
- 咳嗽
- 徐脈
- 浮腫
- 意識障害
▶午前25
母乳栄養の児に不足しやすいのはどれか。
- ビタミンA
- ビタミンB
- ビタミンC
- ビタミンE
- ビタミンK
資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第112回看護師国家試験
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 必修問題
▶午前1改題
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。
- 1.25人
- 2.25人
- 3.25人
- 4.25人
▶午前2改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのはどれか。
- 自宅
- 病院
- 老人ホーム
- 介護医療院・介護老人保健施設
▶午前3
食品を扱う人の化膿した創が汚染源となる食中毒の原因菌はどれか。
- 腸炎ビブリオ
- ボツリヌス菌
- 黄色ブドウ球菌
- サルモネラ属菌
▶午前4
介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。
- 保険給付である。
- 都道府県の事業である。
- 介護保険施設で実施される。
- 配食サービスは生活支援サービスの1つである。
▶午前6改題
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査で20歳以上の男性における喫煙習慣者の割合に最も近いのはどれか。
- 6%
- 16%
- 26%
- 36%
▶午前7
学童期中学年から高学年にみられる、親から離れて仲の良い仲間同士で集団行動をとる特徴はどれか。
- 心理的離乳
- 自我の芽生え
- ギャングエイジ
- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立
▶午前8
壮年期の男性で減少するのはどれか。
- エストロゲン
- プロラクチン
- アルドステロン
- テストステロン
▶午前9
核家族はどれか。
- 兄弟姉妹のみ
- 夫婦と子ども夫婦
- 夫婦と未婚の子ども
- 夫婦とその親と夫婦の子ども
▶午前10
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
- 17
- 18
- 19
- 20
▶午前11
肘関節を伸展させる筋肉はどれか。
- 三角筋
- 大胸筋
- 上腕三頭筋
- 上腕二頭筋
▶午前12
脳幹に含まれる部位はどれか。
- 延髄
- 小脳
- 下垂体
- 松果体
▶午前13
免疫機能に関与する細胞はどれか。
- 血小板
- 白血球
- 網赤血球
- 成熟赤血球
▶午前14
脳死の状態はどれか。
- 縮瞳がある。
- 脳波で徐波がみられる。
- 自発呼吸は停止している。
- 痛み刺激で逃避反応がある。
▶午前15
経口感染するウイルス性肝炎はどれか。
- A型肝炎
- B型肝炎
- C型肝炎
- D型肝炎
▶午前16
抗菌薬について正しいのはどれか。
- ウイルスに有効である。
- 経口投与では効果がない。
- 耐性菌の出現が問題である。
- 正常の細菌叢には影響を与えない。
▶午前17
インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。
- 痛風
- 咽頭炎
- 消化性潰瘍
- 関節リウマチ
▶午前18
異常な呼吸音のうち低調性連続性副雑音はどれか。
- 笛のような音〈笛音〉
- いびきのような音〈類鼾音〉
- 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉
- ストローで水中に空気を吹き込むような音〈水泡音〉
▶午前19
膝蓋腱反射の低下で疑われる病態はどれか。
- 脚気
- 壊血病
- くる病
- 夜盲症
▶午前20
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。
- 3.4m2以上
- 4.4m2以上
- 5.4m2以上
- 6.4m2以上
▶午前21
無菌操作が必要なのはどれか。
- 浣腸
- 気管内吸引
- 口腔内吸引
- 経鼻胃管挿入
▶午前22
成人への坐薬の挿入方法で正しいのはどれか。
- 息を止めるよう説明する。
- 右側臥位になるよう説明する。
- 挿入後1、2分肛門を押さえる。
- 肛門から2cmの位置に挿入する。
▶午前24
直流除細動器の使用目的はどれか。
- 血圧の上昇
- 呼吸の促進
- 体温の上昇
- 洞調律の回復
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午前問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」と合わせてご活用ください。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午前 状況設定問題
次の文を読み91~93の問いに答えよ。
Aさん(49歳、女性)は、これまで在宅勤務でほとんど外出することがなく、BMI33であった。Aさんは久しぶりの出勤の際に転倒し、右大腿骨頸部骨折と診断され、右人工股関節置換術を受けることになった。
▶午前91
Aさんの術後に最も注意すべき所見はどれか。
- Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候
- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候
- Homans〈ホーマンズ〉徴候
- Romberg〈ロンベルグ〉徴候
▶午前92
術後1日、Aさんは39.1℃の発熱がみられた。
バイタルサイン:呼吸数18/分、脈拍117/分、整、血圧132/82mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)。
身体所見:呼吸音は異常なし、腰背部痛なし、術創部の腫脹、発赤、熱感はない。左手の末梢血管内カテーテル刺入部に発赤、熱感がある。
血液検査所見:赤血球344万/μL、Hb12.1g/dL、白血球11,900/μL、血小板18万/μL。
血液生化学所見:尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.8mg/dL、CRP11.4mg/dL。
尿所見:沈査に白血球を認めない。
胸部エックス線写真:異常所見なし。
Aさんの発熱の原因で考えられるのはどれか。2つ選べ。
- 肺炎
- 腎盂腎炎
- 術創部感染
- 術後の吸収熱
- カテーテル関連血流感染症
▶午前93
術後3日、Aさんの全身状態は改善し、読書をして過ごしている。
Aさんの術後の合併症を予防する適切な肢位はどれか。
- 外旋
- 外転
- 内旋
- 内転
次の文を読み94~96の問いに答えよ。
Aさん(57歳、男性)は、妻(50歳)と2人で暮らしている。21歳から喫煙習慣があり、5年前に風邪で受診した際に肺気腫と診断された。最近は坂道や階段を昇ると息切れを自覚するようになってきた。
▶午前94
Aさんの呼吸機能に関する数値で増加を示すのはどれか。
- 1秒率
- 残気量
- 1回換気量
- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉(room air)
▶午前95
Aさんは発熱、咳嗽、粘稠痰、呼吸困難を認めたため受診し、肺炎を伴う慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉の急性増悪と診断されて入院した。入院後、薬物療法によって病状は改善し退院が決定した。看護師がAさんに退院後の生活について尋ねると、今回の入院をきっかけにAさんは退職し、家事に専念すると答えた。
Aさんの呼吸機能に対する負荷が最も小さい動作はどれか。
- 食べる直前に調理する。
- 部屋全体に掃除機をかける。
- 頭より高い位置に洗濯物を干す。
- 買い物した荷物をカートで運ぶ。
▶午前96
5年後、Aさんは急性増悪による入退院を繰り返していた。今回の入院では呼吸機能の低下がみられたため、退院後に在宅酸素療法〈HOT〉を導入することになった。Aさんは「家での生活で気をつけることは何ですか」と看護師に質問した。
Aさんへの指導内容で適切なのはどれか。
- 「寒いときは電気毛布を使ってください」
- 「入浴時は酸素チューブを外してください」
- 「ガス調理器を電磁調理器に変更してください」
- 「呼吸が苦しいときは楽になるまで酸素流量を上げてください」
次の文を読み97~99の問いに答えよ。
Aさん(72歳、女性)は、1人で暮らしている。小学校の教員を定年退職後、書道教室に月2回、体操教室に月1回通っている。20年前に高血圧症と診断され、月に1回かかりつけの病院を受診し、内服治療をしている。6か月前から、Aさんは病院の受診日を間違えたり、書道教室の日時を忘れることがあり、かかりつけの医師に相談した。Aさんは認知症専門医を紹介され、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点で、軽度のAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症と診断された。
▶午前97
Aさんに出現している認知機能障害はどれか。
- 脱抑制
- 近時記憶障害
- 実行機能障害
- 物盗られ妄想
▶午前98
診断から2か月後、かかりつけの病院の看護師にAさんは「50年以上住んでいるこの土地で、できるだけ他人の迷惑にならず生活を続けたいと思って貯金もしてきました。私は軽い認知症だと言われたのですが、これからも自分でお金の管理ができるか心配です。どうしたらよいのでしょうか。私が使えるサービスがあれば知りたいです」と話した。
Aさんが利用できるのはどれか。
- 生活保護制度
- 地域生活支援事業
- 後期高齢者医療制度
- 日常生活自立支援事業
▶午前99
診断から半年後、Aさんは、かかりつけの病院の看護師に「書道教室や体操教室は、部屋のカレンダーに書いて参加しています。ただ、最近、病院に行くときに薬が残っています。大切な薬だと先生から言われていますし、忘れずに飲みたいのですが、どうしたらよいでしょうか」と相談した。
看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 「お薬手帳を毎朝見るようにしましょう」
- 「薬のことは主治医に相談してください」
- 「薬を飲んだらカレンダーに丸を付けてみませんか」
- 「この病気の方は、薬を飲み忘れることがあります」
次の文を読み100~102の問いに答えよ。
Aさん(70歳、女性)は夫(68歳)と2人で暮らしている。BMI26で左股関節の変形性関節症のため関節可動域の制限と疼痛があり、外出時はT字杖を使用している。症状が強いときに消炎鎮痛薬を服用しているが、日常生活動作は自立している。Aさんは過去に転倒したことはないが、左右の下肢の差が3cmあり、立ち上がるときにふらつくことがある。自宅で座って過ごす時間が長い。Aさんは定期受診のため夫に付き添われて外来を受診した。
▶午前100
Aさんの症状の悪化を予防するための説明で適切なのはどれか。
- 運動はしない。
- 減塩食をとる。
- 体重を減らす。
- 家事は夫に任せる。
▶午前101
外来で、診察終了後にAさんから「少し話がある」と言われた女性のB看護師は、空いている診察室で面談した。Aさんから「男性の医師には聞けなかったのですが、性交はやめておいた方がよいでしょうか。股関節の痛みが強くなることはないのですが、夫も心配していました」と相談があった。
このときのB看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。
- 「同年代の変形性関節症の方に聞いてみてはいかがですか」
- 「股関節に負担がない体位について説明します」
- 「性交時は潤滑剤を使いましょう」
- 「性交は避けた方がよいでしょう」
▶午前102
B看護師は、Aさんが処置室前の待合室でT字杖を持ち、椅子から立ち上がろうとしているのを見かけた。B看護師が声をかけると、Aさんは「夫が会計をしていますが、急にトイレに行きたくなって」と慌てていた。夫はAさんから2mほど離れた所で会計をしているため、Aさんの様子に気がついていない。待合室は患者や家族で混雑しており、外来にある車椅子は別の患者が使用中だった。
AさんへのB看護師の声かけで適切なのはどれか。
- 「車椅子を探してきます」
- 「ご主人をお呼びしましょう」
- 「トイレまで一緒に行きましょう」
- 「転ばないように気を付けて行ってくださいね」
次の文を読み103~105の問いに答えよ。
Aちゃんは出生前診断で羊水過多があり先天性食道閉鎖症の疑いを指摘されていた。在胎37週5日に帝王切開で出生、出生体重2,780g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点である。出生後、Aちゃんは先天性食道閉鎖症と診断された。
▶午前103
出生直後のAちゃんにみられるのはどれか。
- 腹部エックス線写真の鏡面像
- 口腔内の泡沫状唾液の流出
- 胆汁性の嘔吐
- 噴水状の嘔吐
▶午前104
Aちゃんは、出生当日に胃瘻造設、気管食道瘻切断と食道端々吻合術を受け、無事に終了した。術後2日、人工呼吸器管理下で胸腔ドレーンが挿入されている。
このときの看護で適切なのはどれか。
- 頸部を伸展させた体位を保持する。
- 摂食嚥下機能の獲得のため支援を開始する。
- 親がAちゃんを自由に抱っこするのを見守る。
- 唾液の吸引時には吸引チューブの挿入を吻合部の手前までにする。
▶午前105
Aちゃんは3歳6か月になった。現在は胃瘻を閉鎖し経口摂取をしているが、吻合部の狭窄による嚥下困難が生じ、これまでに食道バルーン拡張術を2回行った。現在も症状が残っていて、固形物の通過障害が軽度ある。身長92.5cm(25パーセンタイル)、体重11.5kg(3パーセンタイル)で、半年後に保育所へ入園する。両親が「Aはあまり体重が増えません。保育所ではみんなより食事に時間がかかるのではないかと心配です」と外来看護師に話したため、今後の対応について両親、看護師および医師で話し合った。
Aちゃんの摂食に関する対応で適切なのはどれか。
- 再度、胃瘻を造設する。
- 食事を保育士に介助してもらう。
- 昼前に保育所から帰宅し、家で昼食を摂る。
- 同じクラスの子ども達と同量を食べられるよう訓練する。
- Aちゃんに適した食事形態の提供が可能か保育所に確認する。
次の文を読み106~108の問いに答えよ。
Aさん(28歳、会社員)は、夫(30歳、会社員)と2人で暮らしている。2023年2月5日からの月経を最後に無月経となり、妊娠の可能性を考えて受診した。医師の診察の結果、妊娠と診断された。
▶午前106
Naegele〈ネーゲレ〉概算法を用いてAさんの分娩予定日を求めよ。
2023年【①】【②】月【③】【④】日
▶午前107
診察後、Aさんから看護師に妊娠中の生活や体重の管理について質問があった。Aさんは「缶ビール2本を週に1回、コーヒーを1日に6杯以上飲んでいます。友人に勧められて半年前から1日240μgの葉酸のサプリメントを飲んでいます」と話す。Aさんは身長160cm、非妊時体重62kgである。
看護師のAさんへの説明で適切なのはどれか。
- 「飲酒は中止しましょう」
- 「妊娠中の体重増加は7kg未満にしましょう」
- 「コーヒーは今までどおりに飲んでも大丈夫です」
- 「葉酸は妊娠前と同じ量を摂るようにしましょう」
▶午前108
妊娠30週2日。Aさんは妊婦健康診査を受け、妊娠経過に異常はなく児の発育も順調と診断された。診察後、Aさんから看護師に「最近、腰が痛くなることがあります。腰痛への対処法はありますか」と質問があった。
看護師のAさんへの説明内容で適切なのはどれか。
- 安静にする。
- 椅子に浅く座る。
- Sims〈シムス〉位で休む。
- 柔らかいマットレスや布団で寝る。
次の文を読み109~111の問いに答えよ。
Aさん(32歳、初産婦)は妊娠39週4日で男児を正常分娩した。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水を拭き取り、インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。その後、温めておいた衣服を着せてコットに寝かせ、コットを空調の風が当たらない場所に配置した。
▶午前109
看護師の行為で対流による児の熱喪失を予防したのはどれか。
- 羊水を拭き取った。
- インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。
- 温めておいた衣服を着せた。
- コットを空調の風が当たらない場所に配置した。
▶午前110
産褥3日。Aさんは児の啼泣に合わせて横抱きで母乳を与えている。Aさんの乳房の型はⅢ型、熱感が出てきている。乳管は左右とも4本開通している。「抱き方は色々あると聞きました。今の方法以外の授乳の仕方はありますか」と相談を受けた。
授乳の仕方を図に示す。
Aさんに適した授乳の仕方はどれか。

▶午前111
日齢4。体重2,760g。児のバイタルサインは正常である。経皮ビリルビン10mg/dL。前日の排尿は1日4回、排便1日1回。母乳のみを哺乳している。1回の授乳に30分以上かかり、授乳後も児は啼泣している。児は音に反応して抱きつくような動きをする。
新生児のアセスメントで適切なのはどれか。
- 異常な反射を認める。
- 母乳不足が疑われる。
- 黄疸が生理的範囲を超えている。
- 体重減少が生理的範囲を超えている。
次の文を読み112~114の問いに答えよ。
Aさん(22歳、男性)は、高校卒業後に就職したが、同僚との関係がうまく築けず、転職を繰り返している。「他の人と自分はどこか違う。自分の将来が不安だ」と感じたAさんは精神科クリニックを受診し、自閉症スペクトラム障害と診断された。
Aさんは小学生のころから他人の気持ちが理解できないときがあり、対人関係を築くことが苦手で、学校で孤立していた。また、偏食が強く、るいそうがみられたために、同級生から容姿のことでいじめられたことがあった。中学校や高校では忘れ物が多く、集団生活になじめなかった。
▶午前112
Aさんに認められるのはどれか。
- 被害妄想
- 予期不安
- ボディイメージの障害
- コミュニケーションの障害
▶午前113
クリニックに通院し半年が経過した。現在、Aさんは無職である。Aさんは仕事が長続きしないことで将来への不安が強く、自身の適性にあった職場を探したいと希望している。外来看護師は主治医とも相談し、Aさんに就労移行支援のサービスについて伝えることにした。
Aさんへの説明で適切なのはどれか。
- 「仕事が見つかるまで期限なく通所できます」
- 「同じ障害を持つ仲間との共同生活が原則です」
- 「一般就労に向けて知識や能力の向上を目指します」
- 「生活リズムを整え、集団に慣れていくことが目的です」
▶午前114
就労移行支援を利用し、Aさんは仕事を始めたが、苦手な仕事内容が多く、失敗が続いているため同僚から注意を受け続けている。外来看護師は、Aさんから「毎日が憂うつでつらい。ストレスが溜まるのでどうしたらよいか」と相談を受けた。
Aさんへの対応で適切なのはどれか。
- 仕事に慣れるまで待つように説明する。
- 憂うつな気分について詳しく話してもらう。
- 職場の同僚とうまく付き合う方法を考えてもらう。
- 外来看護師が行っているストレス発散方法を指導する。
次の文を読み115~117の問いに答えよ。
Aさん(87歳、女性、要介護1)は1人暮らしで、長女(52歳、会社員)が同じマンションの隣の部屋に住んでいる。5年前に乳癌のため左乳房切除術を受けた。1年前に肺への転移が確認され、胸水の貯留への対症療法のため入退院を繰り返していた。退院後は、状態観察と体調管理のため大学病院の外来を月に2回受診し、訪問介護と訪問看護を週に1回ずつ利用して在宅療養を続け「これ以上の積極的な治療はせずに自宅で最期まで過ごしたい」と話している。 ある日、長女から「最近、母は通院がつらそうで、先月は1回しか受診していません。医師の診察は大事だと思うので、受診を続けるために主治医に何を相談すればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。
▶午前115
長女への助言で適切なのはどれか。
- 緩和ケア病棟への入院
- 在宅療養支援診療所の利用
- 医師の診察を月1回に減らすこと
- 通所リハビリテーションを利用すること
▶午前116
3か月後、Aさんは呼吸状態の悪化のため在宅酸素療法〈HOT〉(3L/分、24時間)を受けることになった。要介護3に変更され訪問看護を週に3回利用することになった。毎日午前は訪問介護、午後は長女が介護休業制度の短時間勤務等の措置を利用して介護することになった。訪問介護員から「Aさんの食事を作り、食べた後の片付けをしているのですが、Aさんが食事の後に少し息が苦しいと言うことがあります。どうすればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。
訪問介護員への助言で適切なのはどれか。
- 「食事を介助しましょう」
- 「食事の後に短速呼吸を促しましょう」
- 「食事以外の時間は安静に過ごしてもらいましょう」
- 「Aさんの1回分の食事量を減らし回数を増やしましょう」
▶午前117
6か月後、Aさんは長女に見守られ自宅で最期を迎えた。2週後、長女から「私なりに頑張りましたが、十分に介護してあげられなかった。もっとできることがあったのではと考えてしまいます」と訪問看護師に連絡があった。
訪問看護師の長女への対応で適切なのはどれか。
- 「もう少し仕事を休んで傍にいられたらよかったですね」
- 「何をすればよかったのか一緒に考えましょう」
- 「最期までよく介護していたと思いますよ」
- 「仕事に集中してみましょう」
次の文を読み118~120の問いに答えよ。
Aさん(44歳、男性)は、午前9時に発生した震度5強の地震で自宅の2階から慌てて逃げる際に階段から転落した。午前9時30分、Aさんは殿部に激しい痛みが出現し動けなくなったため、救急車で搬送され入院した。
身体所見:体温36.8℃、呼吸数22/分、脈拍100/分、血圧76/38mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)。
検査所見:赤血球300万/μL、Hb9.0g/dL、CRP0.3mg/dL、Na140mEq/L、K4.0mEq/L、濃縮尿、尿比重1.020、尿潜血(+)。
▶午前118
Aさんの状態で考えられるのはどれか。
- 敗血症
- 骨盤骨折
- 硬膜下血腫
- 腰部脊柱管狭窄症
▶午前119
午前11時、Aさんの母親Bさん(80歳)は、余震が続くため避難する途中で転倒し、歩行が困難となった。Bさんは、孫のCさん(14歳、女子)に付き添われて救急車で病院に搬送された。Bさんは、意識は清明で、腰痛を訴えている。バイタルサインは、呼吸数16/分、脈拍90/分、血圧135/80mmHgで、排尿によって着衣が濡れている。
外来で診察を待っている間に、Bさんの隣にいるCさんがうずくまっているのを看護師が発見した。Cさんのバイタルサインは、呼吸数36/分、脈拍110/分、血圧94/40mmHgで、手のしびれ、動悸を訴えている。
看護師の初期対応で優先度が高いのはどれか。
- Bさんの着衣の交換
- Bさんの既往歴の確認
- Cさんの四肢の保温
- Cさんの経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の測定
▶午前120
Bさんは、歩行が困難であったため入院したが、検査の結果、腰部の打撲のみで他に身体的な問題を認めなかった。日中は眠っていることが多く、夕方になると落ち着かなくなり、大声で家族を呼んだり、家に帰ろうとすることがあった。入院4日後、Bさんは少しずつ歩けるようになり、退院が決まった。自宅が半壊状況のため、福祉避難所に行くことになった。一緒に福祉避難所に行くAさんの妻(42歳)は看護師に「義母は、入院前は大声を出すことはありませんでした。避難所で人に迷惑をかけるのではないかと心配です」と相談した。
看護師のBさんに関する助言内容で適切なのはどれか。
- 福祉避難所では昼間の覚醒を促す。
- 福祉避難所では人との交流を少なくする。
- Bさんの退院を延期できるか医師に相談する。
- 福祉避難所に行ったらすぐに精神科を受診する。
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午後問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」と合わせてご活用ください。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午後 状況設定問題
次の文を読み91~93の問いに答えよ。
Aさん(58歳、男性、会社員)は、身長175cm、体重73kgである。Aさんは、健康診断の胸部エックス線撮影で異常陰影を指摘され、3週前に胸部造影CT検査を受けた。左肺下葉に約8mmの病変が見つかり、精密検査の結果、肺癌(T1N0M0)と診断され、本日、手術目的で入院した。咳嗽、息苦しさ、喀痰はない。喫煙歴があり、20年間20本/日、禁煙後18年である。
バイタルサイン:体温36.9℃、呼吸数14/分、脈拍72/分、整、血圧136/76mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)。
検査所見:赤血球510万/μL、Hb15.6g/dL、Ht47%、白血球6,200/μL、血小板32万/μL、総蛋白7.7g/dL、アルブミン4.2g/dL、空腹時血糖102mg/dL。
呼吸機能所見:%VC76%、FEV1%73%。
▶午後91
入院時の所見で正しいのはどれか。
- 頸部リンパ節の腫脹
- 拘束性換気障害
- 低栄養
- 貧血
▶午後92
Aさんは、入院2日目に胸腔鏡下左下葉切除術を受ける予定である。Aさんは看護師に「全身麻酔で手術を受けるのは初めてです。医師から手術の説明はあったけれど、合併症についてもう一度教えてもらえますか」と質問した。
Aさんに生じる可能性が高い合併症はどれか。
- 気胸
- 反回神経麻痺
- Horner〈ホルネル〉症候群
- Pancoast〈パンコースト〉症候群
▶午後93
Aさんの手術は予定通りの術式で行われ、肺癌は術前診断通りの病期であった。Aさんの術後経過は良好であり、退院日が決定した。Aさんのバイタルサインは、体温36.3℃、呼吸数18/分、脈拍66/分、整、血圧134/76mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)であった。
退院後の生活指導で正しいのはどれか。
- 「インフルエンザワクチンは接種できません」
- 「左手で重い荷物を持たないでください」
- 「少しずつ活動量を増やしてください」
- 「自宅で酸素吸入を行ってください」
次の文を読み94~96の問いに答えよ。
Aさん(43歳、男性、会社員)は、1か月前に右頸部の腫瘤を自覚した。大学病院で非Hodgkin〈ホジキン〉リンパ腫と診断され化学療法導入目的で入院した。
バイタルサイン:体温37.1℃、呼吸数16/分、脈拍84/分、整。
身体所見:顔面に浮腫を認める。
検査所見:Hb12.8g/dL、白血球6,400/μL、総蛋白7.6g/dL、アルブミン4.1g/dL。
胸部造影CT:縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫を認める。
▶午後94
Aさんの顔面の浮腫の原因で考えられるのはどれか。
- 発熱
- 貧血
- 低蛋白血症
- 上大静脈の圧迫
▶午後95
AさんはR-CHOP療法(リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)を受けた。
AさんのR-CHOP療法の初日に生じる可能性がある合併症はどれか。
- 脱毛
- 口内炎
- 低血糖
- 好中球減少症
- 腫瘍崩壊症候群
▶午後96
AさんはR-CHOP療法終了後も嘔気・嘔吐が続き、制吐薬の追加投与を受けた。治療後3日、「やっと楽になって食事が摂れるようになったけど、やっぱりつらかった。思い出すだけでも気持ち悪くなります」と話している。
Aさんの次回のR-CHOP療法において、嘔気・嘔吐への対応で適切なのはどれか。
- 1日1,000mLの水分摂取
- 治療前日の夕食の中止
- 治療前の制吐薬の投与
- 抗癌薬の減量
次の文を読み97~99の問いに答えよ。
Aさん(71歳、女性)は夫と10年前に死別し、1人で暮らしている。息子は結婚して他県に住んでいる。Aさんは、3か月前に脳梗塞を発症して要介護1となり、介護老人保健施設に入所した。 Aさんは老人性白内障があるがADLに支障はなく、認知機能やコミュニケーションに問題はない。食事は自力で摂取できる。紅茶が好きで、毎日カップ2、3杯は飲んでいる。我慢できない強い尿意があり尿が漏れてしまうため、下着に尿取りパッドを付けている。トイレには自力で移動でき、下着やズボンの上げ下ろしは自立している。排便は2日に1回である。
▶午後97
Aさんの尿失禁の種類で考えられるのはどれか。
- 溢流性尿失禁
- 機能性尿失禁
- 切迫性尿失禁
- 腹圧性尿失禁
▶午後98
4、5日前からAさんは倦怠感を訴え、ベッドで寝ていることが多くなった。食欲が落ちてきて、1日の水分摂取量も減少した。トイレでの排尿が間に合わないことが多くなり、頻回に尿失禁するようになった。看護師がAさんの尿取りパッドの交換を介助すると尿臭が強く、色も茶褐色であった。Aさんが「おしっこをするとお腹の下の方が痛い。体がだるい」と看護師に訴えたため、体温を測定すると37.5℃であった。看護師がAさんの状況を施設の医師に報告すると、抗菌薬を内服するように指示が出された。
Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 日中に飲水を勧める。
- 下腹部をマッサージする。
- 抗菌薬は自分で管理してもらう。
- 昼間は離床して過ごすように促す。
▶午後99
5日後、Aさんは解熱し、少しずつ食欲が出てきた。下腹部痛は消失し、尿失禁の回数も少なくなった。
症状の再燃を防止するためのAさんへの対応で適切なのはどれか。
- 2時間ごとに排尿誘導する。
- 用手圧迫排尿の方法を指導する。
- 排尿の度に陰部を洗浄するように促す。
- 尿取りパッドの交換回数を増やすように指導する。
次の文を読み100~102の問いに答えよ。
Aちゃん(7歳、女児)は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に来院した。1か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、Aちゃんは体温36.6℃、呼吸数20/分、心拍数84/分、血圧130/80mmHgで、床上安静の指示が出された。
▶午後100
Aちゃんの入院時の看護計画で適切なのはどれか。
- 水分摂取を促す。
- 1日3回の血圧測定を行う。
- 食事の持ち込みを許可する。
- 腰部に消炎鎮痛薬を貼用する。
▶午後101
入院3日。両眼瞼の浮腫と肉眼的血尿は続いていた。看護師がAちゃんのベッドサイドを訪れると、Aちゃんは「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えた。Aちゃんは体温36.6℃、呼吸数20/分、心拍数92/分、血圧148/88mmHgであった。
この状況からAちゃんに起こりうる症状はどれか。
- 眼のかゆみ
- 意識障害
- 耳漏
- 鼻閉
▶午後102
入院して1週が経過した。症状は軽快傾向にあるが床上安静は続いている。仲が良かった同じ病室の児が退院して、Aちゃんはイライラしている。Aちゃんの母親は、毎日昼食後から夕食まで面会をしている。
Aちゃんのストレスに対する看護師の発言で適切なのはどれか。
- 「すぐに退院できるから頑張ろう」
- 「好きなだけテレビや動画を観ていいよ」
- 「ベッドに寝たままプレイルームに行こう」
- 「夕食後もお母さんに付き添ってもらおう」
次の文を読み103~105の問いに答えよ。
A君(5歳、男児)は共働きの両親と3人で暮らしている。2歳6か月で自閉スペクトラム症と診断され、保育所と療育センターに通っている。保育所の健康診断で低身長を指摘され、受診を勧められて両親と来院した。A君は待合室を走ったり診察室の扉を開けたりしていた。診察室に入ると「頑張ろう」と泣きながら叫び、恐怖心を抑えている様子だった。母親は「Aは病院が苦手で、予防接種はAの手足と体を看護師さん3人で抑えて行ってきましたが、繰り返し説明することで、抑えなくても注射ができるようになりました」と話した。
診察の結果、1週後に成長ホルモン分泌刺激試験を行うことになった。母親から「Aが血液検査でパニックを起こすのではないかと心配です」と発言があった。
▶午後103
母親への声かけで適切なのはどれか。
- 「検査があることは当日に説明しましょう」
- 「予防接種ができるのであれば心配ありません」
- 「家でA君に説明できる絵カードをお渡しします」
- 「看護師3人でA君をしっかりと抑えて採血します」
▶午後104
成長ホルモン分泌刺激試験の結果、母親が自宅で毎晩A君に成長ホルモン製剤を注射することになった。外来で母親は注射の手技を習得し、A君も注射に慣れた。
自宅での注射に向けて、母親に確認する事項で優先度が高いのはどれか。
- 保育所でのA君の様子
- A君と家族の日課
- 家族の経済状況
- 祖父母の居住地
▶午後105
3か月後、自宅でのA君への成長ホルモン製剤の注射は順調に実施されている。外来受診時に母親から看護師に「Aが通っている療育センターにも相談しましたが、Aは自閉スペクトラム症であるだけでなく、注射もしているので就学のことを考えると心配です。通常の学級に通わせたいと考えているのですが、通常の学級への就学について教えてください」と相談があった。
看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「お母さんが学校で待機する必要があります」
- 「就学する学級は受入れ先の校長が決定します」
- 「通常の学級に籍を置くと通級指導は受けられません」
- 「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」
次の文を読み106~108の問いに答えよ。
Aさん(32歳、初産婦)は、夫と2人で暮らしている。骨盤位のために妊娠38週0日に予定帝王切開術で午前11時に男児を出産した。分娩時出血量は480mLであった。出生後、手術室で男児と面会をして「無事に生まれてきてくれてありがとう」と話した。帰室後、子宮底は臍高、硬度良好、悪露は赤色で20gであった。後陣痛と創部痛があり夜間に鎮痛薬を使用した。
▶午後106
帝王切開術後1日、午前9時、子宮底は臍下1横指、硬度良好、バイタルサインは体温36.9℃、呼吸数18/分、脈拍72/分、整、血圧110/70mmHgであった。夜間に排ガスを認めた。Aさんは「痛み止めを使用した後は眠れましたが、また痛みが出てきました。こんな状態で動けるか心配です。この後の予定を知りたいです」と話した。
このときのAさんへの説明で適切なのはどれか。
- 「入院中は毎日、タオルで身体を拭きます」
- 「膀胱に入れている管は明日抜きます」
- 「今日から歩行を開始します」
- 「食事は明日からです」
▶午後107
帝王切開術後3日、子宮底は臍下3横指、悪露は褐色であった。乳房に熱感があり、乳管は左右とも3本開通しており、移行乳の分泌を認める。看護師が訪室するとAさんは「まだ、お腹の創が痛くて、動くのはつらいです」と話す。慣れない手付きで児に授乳をしながら「上手にできなくてごめんね」と児の顔を見て語りかけている。Aさんと児の目と目が合う様子がみられる。
アセスメントで適切なのはどれか。
- 子宮復古が遅れている。
- 乳汁分泌が遅れている。
- 母子相互作用がみられる。
- マタニティブルーズである。
▶午後108
帝王切開術後5日、診察の結果、明日退院することになった。Aさんの乳房は緊満しており、乳管は左右とも5、6本開通している。母児同室を行い、児の哺乳の欲求に合わせて1日10回の授乳を行っている。「母乳で育てたいと思っています。でもおっぱいが張ってつらいです。この子も上手に吸ってくれません」と看護師に話した。
このときの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「授乳の回数を減らしましょう」
- 「授乳前に乳輪を柔らかくしましょう」
- 「授乳と授乳の間は乳房を温めましょう」
- 「乳房の緊満が強くなるのはこれからです」
次の文を読み109~111の問いに答えよ。
Aさん(65歳、男性)は、妻と自営業を営んでおり、2人で暮らしている。2か月前に仕事で大きな失敗をし、謝罪と対応に追われ、あまり夜に眠れなくなり、食欲不振が続いている。1か月前から気分が落ち込み、仕事で妻から間違いを指摘されたことで自信をなくしていた。Aさんは死んでしまいたいと思い、夜に自宅でロープを使って自殺を図ろうとしたところを妻に見つけられた。妻に付き添われ、精神科病院を受診し、うつ病と診断された。受診当日に入院し、抗うつ薬の内服が開始された。Aさんは「生きていても仕方がない。どうせ誰も分かってくれない」と看護師に話した。
▶午後109
このときの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 「生きていれば良いことがありますよ」
- 「薬を飲むと数日で効いて楽になります」
- 「悲しいことが続くときは誰にでもあります」
- 「Aさんがつらい状況にあることを私は心配しています」
▶午後110
Aさんはその後しばらく会話をしたり、食事も少し食べられたりしていたが、入院3日から、臥床したままで1日中全く動かず、昏迷状態になった。検査の結果、軽度の脱水以外の異常はなかった。治療として修正型電気けいれん療法が開始されることになり、実施後20分でAさんは覚醒し、その後の観察中にけいれん発作は認めなかった。実施後30分、Aさんは突然起き上がり興奮し、大きな声で「仕事に行く」と言って病室から出ていこうとした。看護師が制止し、一緒に座って話を聞いたところ、見当識障害、記憶障害、注意障害が認められた。
Aさんの状態で正しいのはどれか。
- せん妄
- 躁状態
- 不安発作
- 前向性健忘
▶午後111
入院1か月が経過し、Aさんは夜間の睡眠がとれるようになり、食事は全量摂取している。妻から間違いを指摘されたことを思い出し、「何をやってもきっと失敗するだけだ。今度はもっと大きな失敗をして仕事を辞めることになる。だから自分はだめな人間だ。努力しても意味がない」と看護師に言った。
Aさんへの治療法で最も適切なのはどれか。
- 森田療法
- 集団精神療法
- 認知行動療法
- 社会生活技能訓練〈SST〉
次の文を読み112~114の問いに答えよ。
Aさん(24歳、女性)は大学卒業後、一般企業に就職したが、何度も自宅の鍵を閉めたかどうかを確認するため、遅刻を繰り返した。連絡せずに複数回の遅刻があったことを上司のBさんから強く注意され、うつ状態となったため精神科外来を受診したところ、強迫性障害と診断され、選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉が処方された。
▶午後112
内服を始めて1週後、Aさんは看護師に「鍵を閉めたかどうかの確認が増え、睡眠時間が減ってつらい」と訴えている。
看護師の声かけで適切なのはどれか。
- 「主治医に薬の変更を相談しましょう」
- 「睡眠状況を具体的に教えてください」
- 「Bさんに別の部署に異動したいと伝えてみましょう」
- 「鍵を閉めたかどうか気になるときは別のことを考えましょう」
▶午後113
受診に同行していた母親からは「Aから『私の代わりに鍵が閉まっているか見てきてほしい』といった要望が多い。それに従わないと『どうして私のつらさを分かってくれないの』と大きな声を出す。どのように関わればよいか分からない」と看護師に相談があった。
母親への看護師の対応で適切なのはどれか。
- 要望に応じ続ける方がよいと助言する。
- 治療の効果が得られるまで待つように伝える。
- 母親が疾患をどのように理解しているか確認する。
- Aさんが大きな声を出しても反応しないように助言する。
▶午後114
選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉の内服を始めてから2か月が経過し、Aさんは外出中に鍵を閉め忘れたかもしれないという考えが強くなり、外出から予定より早く帰宅することがある。Aさんは「鍵を閉め忘れていないかの確認を減らしたい」と看護師に相談した。
Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 外出を控えるよう助言する。
- 外出するときは誰かに付き添ってもらうよう提案する。
- 鍵の閉め忘れが気になる理由を考えてみるよう伝える。
- 鍵の閉め忘れが特に気になるときの前後の状況を振り返るよう促す。
次の文を読み115~117の問いに答えよ。
Aさん(14歳、男子、特別支援学校の中学生)はDuchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで両親、弟(7歳)と2階建ての家に4人で暮らしている。呼吸障害が進行したため非侵襲的陽圧換気療法を導入する目的で入院した。Aさんの呼吸状態は安定し、両親に対するバッグバルブマスクによる用手換気の指導が終了したため、自宅に退院し訪問看護を毎日利用して療養生活を続けることになった。両親は「日常の呼吸管理について退院後に対応できるか心配です」と病棟の看護師に話した。
▶午後115
Aさんの両親に対する看護師の指導で適切なのはどれか。
- 息苦しいときは非侵襲的陽圧換気の吸気圧を上げる。
- 人工呼吸器が動かないときはすぐに救急車を要請する。
- 人工呼吸器が過剰送気を示すときは回路が外れていないか確認する。
- マスクの周囲から空気が漏れるときはマスクのベルトをきつく締める。
▶午後116
退院後1週。Aさんの父親から「最近、大雨や落雷、地震による被災の報道が多くて、Aは人工呼吸器を付けているし、弟もまだ小さいので不安です。災害に備え何をすればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。
訪問看護師がAさんの父親に説明する内容で優先度が高いのはどれか。
- 非常用電源の選び方
- 福祉避難所への移動手段
- 足踏み式吸引器の使用方法
- ハザードマップの確認方法
▶午後117
退院後6か月。Aさんは人工呼吸器を装着して特別支援学校に通学することにも慣れてきた。Aさんの母親から「弟がインフルエンザと診断された。弟は2階の子ども部屋、Aは1階のリビングで過ごしている。家族全員がインフルエンザの予防接種を受けた。Aにインフルエンザがうつらないか心配」と訪問看護師に連絡があった。
訪問看護師の対応で適切なのはどれか。
- Aさんが特別支援学校を2週間休むことを勧める。
- Aさんが感染予防の目的で入院することを医師に相談する。
- Aさんは予防接種を受けているのでうつらないと説明する。
- ケアを父母で分担し、弟の担当は弟以外と接触しないことを提案する。
次の文を読み118~120の問いに答えよ。
Aさん(72歳、男性)は、妻と2人暮らしで子どもはいない。定年後は2人で旅行するのが趣味であった。Aさんは、1か月前から残尿感や夜間頻尿が気になり病院を受診した結果、前立腺癌と診断され根治的前立腺摘出手術を受けた。退院後は、手術後の補助療法として、外来で放射線の外照射療法を行うことになっている。
▶午後118
放射線外来の看護師が行うAさんへの説明で正しいのはどれか。
- 「入浴直後に照射部位の観察をしましょう」
- 「照射後は照射部位に冷湿布を貼りましょう」
- 「照射部位の皮膚は乾燥させておきましょう」
- 「照射部位は強くこすらないようにしましょう」
▶午後119
Aさんの放射線療法が開始され初回の照射を終えた。放射線外来の看護師は、終了後にAさんへ声をかけた。Aさんは「ベッドは硬いし、最後まで同じ姿勢でいることがとても苦痛です。大きな音がするので恐怖も感じます」と訴えた。
このときの看護師の説明で正しいのはどれか。
- 「次回から照射中は傍に付き添います」
- 「治療体位をとるための固定具を工夫してみます」
- 「照射時間を短くできるよう主治医に相談してみます」
- 「照射中に体位変換ができるよう放射線技師に相談します」
▶午後120
Aさんが放射線治療を終了して半年後、腰部と右大腿部の痛みが出現した。倦怠感と食欲不振が続いたため病院を受診し精密検査を受けた。骨転移していることが分かり、Aさんと妻に主治医から余命と治療方針の説明があった。Aさんはその場で「痛みを取り除いてほしい。つらい治療は受けたくない」と訴え、3日後に緩和ケア病棟に入院した。
入院翌日、受け持ちの看護師Bが、プリセプターである看護師に「今朝、奥さんの顔色が悪くふらついていたので声をかけると『夫の最期を受け入れられない気がして不安です』と打ち明けられました。昨夜も眠らずにAさんに付き添っていたようでした。奥さんにどう対応したらよいのでしょうか」と相談した。
プリセプターである看護師が看護師Bに助言する内容で適切なのはどれか。
- 妻がAさんの死を受け入れられるよう妻を励ますこと
- 妻がAさんへの思いを看護師Bに語る時間をつくること
- Aさんの予後について再度主治医から妻へ説明するよう調整すること
- 妻がAさんの死を受け入れられるまで夜も付き添うよう妻に伝えること
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午後 必修問題
▶午後1改題
令和4年(2022年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。
- 77年
- 82年
- 87年
- 92年
▶午後3
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 失業手当の給付
- 年少者の労働条件
- 過労死に関する調査研究
- 労働者に対する健康診断
▶午後4
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
- L字バーを設置する。
- 離床センサーを設置する。
- 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
- ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
▶午後5
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 都道府県ナースセンターの長
▶午後6
成長・発達における順序性で正しいのはどれか。
- 頭部から脚部へ
- 微細から粗大へ
- 複雑から単純へ
- 末梢から中心へ
▶午後7
第二次性徴が発現し始めた思春期に関心が向くのはどれか。
- 善悪の区別
- 仕事と家庭の両立
- 自己の身体の変化
- 経済力の確保と維持
▶午後8
老化に伴う視覚の変化で正しいのはどれか。
- 視野が狭くなる。
- 近くが見やすくなる。
- 色の識別がしやすくなる。
- 明暗順応の時間が短縮する。
▶午後9
人口統計資料集2020年版における生涯未婚率(50歳時の未婚割合)で、平成22年(2010年)から令和2年(2020年)の推移で適切なのはどれか。
- 変化はない。
- 下降し続けている。
- 上昇し続けている。
- 上昇と下降を繰り返している。
▶午後10改題
令和5年(2023年)の人口動態統計における合計特殊出生率に最も近いのはどれか。
- 0.7
- 1.2
- 1.7
- 2.2
▶午後12
膵管と合流して大十二指腸乳頭(Vater〈ファーター〉乳頭)に開口するのはどれか。
- 肝管
- 総肝管
- 総胆管
- 胆嚢管
▶午後13
正期産となる出産時期はどれか。
- 妊娠35週0日から39週6日
- 妊娠36週0日から40週6日
- 妊娠37週0日から41週6日
- 妊娠38週0日から42週6日
▶午後14
器質的変化で嚥下障害が出現する疾患はどれか。
- 食道癌
- 脳血管疾患
- 筋強直性ジストロフィー
- Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群
▶午後15
高血圧が原因で起こりやすいのはどれか。
- 脳出血
- 脳塞栓症
- 脳動静脈奇形
- 急性硬膜下血腫
▶午後16
手術予定の患者が服用している場合、安全のために術前の休薬を検討するのはどれか。
- 鉄剤
- 抗血小板薬
- 冠血管拡張薬
- プロトンポンプ阻害薬
▶午後17
看護過程における客観的情報はどれか。
- 家族の意見
- 患者の表情
- 患者の痛みの訴え
- 患者の病気に対する思い
▶午後18
フィジカルアセスメントで問診の次に行うのはどれか。
- 視診
- 触診
- 打診
- 聴診
▶午後19
男性の導尿でカテーテルを挿入するとき、体幹に対する頭部側からの挿入角度はどれか。
- 0~10度
- 40~50度
- 80~90度
- 120~130度
▶午後20
床上で排便しやすい体位はどれか。
- 仰臥位
- 側臥位
- Sims〈シムス〉位
- Fowler〈ファウラー〉位
▶午後22
成人の静脈血採血の穿刺部位で適切なのはどれか。
- 腋窩静脈
- 上腕静脈
- 腕頭静脈
- 肘正中皮静脈
▶午後23
自動体外式除細動器〈AED〉を使用するときに、胸骨圧迫を中断するのはどれか。
- 電源を入れるとき
- 電極パッドを貼るとき
- 心電図の解析中
- 電気ショックの直後
▶午後24
側臥位における褥瘡の好発部位はどれか。
- 後頭部
- 耳介部
- 仙骨部
- 肩甲骨部
▶午後25
緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。
- コデイン
- アスピリン
- アトロピン
- ジゴキシン
- フェニトイン
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
看護師国家試験の問題は、大きく必修問題と一般問題・状況設定問題の二つに分けられます。
合格のためには、①必修問題(1問1点)で50点中40点以上(80%以上)、②一般問題(1問1点)・状況設定問題(1問2点)で250点中約160点(毎年変動)以上の二つの基準を満たす必要があります。つまり、一般問題・状況設定問題で合格基準を突破しても、必修問題で39問以下の正解しかできなければ不合格となります(不適切問題として除外等されない場合)。
問題数に対して必修問題の合格ラインが高く、看護師試験の学習としては、まず基礎的な土台を固めて必修問題を落とさないことが最重要であり、その後、より応用的な知識を身に付けて一般問題・状況設定問題で点数を積み上げていく方針が定番となっています。
必修問題は重要な基本的事項を問うものとされ、問題内容から午前と午後のそれぞれ最初の25問、合計50問が該当すると一般的に考えられます(必修問題の箇所は公表されていないので不確定)。
その範囲・難易度は看護師国家試験出題基準に沿って限られ、過去の問題と同内容・傾向の問題がたびたび出題されるため、過去問の対策がとくに重要です。
例えば、第111回(2022年)看護師国家試験の必修問題が、110回から101回までの10年間の必修問題部分で何問出題されたかをみると、必修問題として不適当とされた2問を除いた48問のうち、10年間の必修問題で類似内容の問題は28問(58.3%)出題されています。
つまり、111回試験では、過去10年間の必修問題を解き、周辺知識を含めてしっかりと理解すれば、必修問題の半分以上が確実に正答できたということであり、過去問対策の重要性がわかります。
当サイトでは最新の看護師国家試験出題基準に沿って、113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験に出題された必修問題を網羅・解説しています。
衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。
▼看護師国家試験必修問題まとめ
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
【必修】大項目1「健康の定義と理解」
| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |
| A.健康の定義 |
世界保健機関〈WHO〉の定義 ウェルネスの概念 |
| B.健康に関する指標 | 総人口 年齢別人口 労働人口 将来推計人口 世帯数 婚姻、家族形態 出生と死亡の動向 死因の概要 平均余命、平均寿命、健康寿命 |
| C.受療状況 | 有訴者の状況 有病率、罹患率、受療率 外来受診の状況 入院期間 |
A.健康の定義
世界保健機関〈WHO〉の定義
第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39
世界保健機関〈WHO〉が定義する健康について正しいのはどれか。
- 単に病気や虚弱のない状態である。
- 国家に頼らず個人の努力で獲得するものである。
- 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。
- 経済的もしくは社会的な条件で差別が生じるものである。
一次予防・二次予防・三次予防
第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p80
生活習慣病の一次予防はどれか。
- 早期治療
- 検診の受診
- 適切な食生活
- 社会復帰を目指したリハビリテーション
疾病や障害に対する二次予防はどれか。
- 早期治療
- 予防接種
- 生活習慣の改善
- リハビリテーション
生活習慣病の三次予防はどれか。
- 健康診断
- 早期治療
- 体力づくり
- 社会復帰のためのリハビリテーション
B.健康に関する指標
総人口
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
令和5年(2023年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。
- 1億人
- 1億400万人
- 1億2,400万人
- 1億4,400万人
年齢別人口
令和5年(2023年)10月1日現在の年齢3区分別人口構成割合は、
- 年少人口(0~14歳):11.4%
- 生産年齢人口(15~64歳):59.5%
- 老年人口(65歳以上):29.1%
で、少子高齢化により年少人口と生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
人口年齢区分における15歳から64歳までの年齢区分はどれか。
- 従属人口
- 年少人口
- 老年人口
- 生産年齢人口
日本の令和5年(2023年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
日本における令和5年(2023年)の総人口に占める老年人口の割合で最も近いのはどれか。
- 19%
- 29%
- 39%
- 49%
令和5年(2023年)の日本の人口推計で10年前より増加しているのはどれか。
- 総人口
- 年少人口
- 老年人口
- 生産年齢人口
将来推計人口
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
令和5年(2023年)推計による日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の将来推計人口に最も近いのはどれか。
- 6,700万人
- 8,700万人
- 1億700万人
- 1億2,700万人
日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の65歳以上人口が総人口に占める割合に最も近いのはどれか。
- 24%
- 39%
- 54%
- 69%
世帯数
令和4年(2022年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に、
①単独世帯:32.9%
②夫婦と未婚の子のみの世帯:25.8%
③夫婦のみの世帯:24.5%
④ひとり親と未婚の子のみの世帯:6.8%
⑤三世代世帯:3.8%
となっている。なお、②~④を合わせた核家族世帯は57.1%となっている。
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、単独世帯の占める割合はどれか。
- 12.9%
- 32.9%
- 52.9%
- 72.9%
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で次の世帯構造のうち最も少ないのはどれか。
- 単独世帯
- 三世代世帯
- 夫婦のみの世帯
- 夫婦と未婚の子のみの世帯
▶113回午前9
核家族はどれか。
- 兄弟姉妹のみ
- 夫婦と子ども夫婦
- 夫婦と未婚の子ども
- 夫婦とその親と夫婦の子ども
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。
- 30%
- 45%
- 60%
- 75%
平均世帯人員
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。
- 1.25
- 2.25
- 3.25
- 4.25
65歳以上の者のいる世帯の割合
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。
- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
平均初婚年齢
第2編2章 8.婚姻 p68~69
令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。
- 19.7歳
- 24.7歳
- 29.7歳
- 34.7歳
生涯未婚率
第2編2章 8.婚姻 p68~69
人口統計資料集2020年版における生涯未婚率(50歳時の未婚割合)で、平成22年(2010年)から令和2年(2020年)の推移で適切なのはどれか。
- 変化はない。
- 下降し続けている。
- 上昇し続けている。
- 上昇と下降を繰り返している。
出生数
第2編2章 2.出生 p51~55
令和5年(2023年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。
- 40万人
- 70万人
- 100万人
- 130万人
合計特殊出生率
第2編2章 2.出生 p51~55
日本の令和5年(2023年)における合計特殊出生率はどれか。
- 0.70
- 1.20
- 1.70
- 2.20
母の年齢階級別出生率
第2編2章 2.出生 p51~55
日本の令和5年(2023年)における母の年齢階級別出生率が最も高いのはどれか。
- 20~24歳
- 25~29歳
- 30~34歳
- 35~39歳
- 40~44歳
死亡数
第2編2章 3.死亡 p55~64
日本の令和5年(2023年)の死亡数に近いのはどれか。
- 118万人
- 138万人
- 158万人
- 178万人
死因順位
令和5年(2023年)の主要死因別にみた死亡順位は以下のとおりである。
第1位:悪性新生物〈腫瘍〉
第2位:心疾患
第3位:老衰
第4位:脳血管疾患
第5位:肺炎
第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58
日本の令和5年(2023年)における主要死因別にみた死亡率が最も高いのはどれか。
- 肺炎
- 心疾患
- 悪性新生物〈腫瘍〉
- 脳血管疾患
令和5年(2023年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患の順位はどれか。
- 1位
- 2位
- 3位
- 4位
小児の死因順位
令和5年(2023年)の年齢階級別にみた小児の死因の第1位は以下のとおりである。
0歳:先天奇形、変形及び染色体異常
1~4歳:先天奇形、変形及び染色体異常
5~9歳:悪性新生物〈腫瘍〉
10~14歳:自殺
第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58
日本における令和5年(2023年)の5~9歳の子どもの死因で最も多いのはどれか。
- 肺炎
- 心疾患
- 不慮の事故
- 悪性新生物〈腫瘍〉
悪性新生物〈腫瘍〉
第2編2章 3.3〕死因―悪性新生物〈腫瘍〉 p58~59
日本における令和5年(2023年)の部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。
- 胃
- 肝及び肝内胆管
- 気管、気管支及び肺
- 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸
自殺の動機
第2編2章 3.7〕(2)自殺 p61~63
警察庁の「令和5年(2023年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。
- 学校問題
- 家庭問題
- 勤務問題
- 健康問題
死亡場所
- 令和4年(2022年)の死亡場所は、病院が64.5%と最も多く、次いで自宅が17.4%となっている。
- なお、過去の意識調査では、人生の最後をむかえるときに生活したい場所として自宅が最も高く、在宅医療の充実が図られている。
第4編1章 3.1〕在宅医療 p170
令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのはどれか。
- 自宅
- 病院
- 老人ホーム
- 介護医療院・介護老人保健施設
平均寿命
第2編3章 生命表 p70~73
平均寿命で正しいのはどれか。
- 0歳の平均余命である。
- 20歳の平均余命である。
- 60歳の平均余命である。
- 死亡者の平均年齢である。
令和4年(2022年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。
- 77年
- 82年
- 87年
- 92年
日本の令和4年(2022年)における男性の平均寿命はどれか。
- 71.05年
- 76.05年
- 81.05年
- 86.05年
健康寿命
第3編1章 2.1〕(6)健康寿命の延伸 p87~88
世界保健機関〈WHO〉が平成12年(2000年)に提唱した「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」はどれか。
- 健康寿命
- 健康余命
- 平均寿命
- 平均余命
C.受療状況
有訴者
第2編4章 1.1〕有訴者の状況 p74
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)で正しいのはどれか。
- 6.5
- 76.5
- 276.5
- 476.5
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。
- 腰痛
- もの忘れ
- 体がだるい
- 目のかすみ
- 手足の関節が痛む
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。
- 頭痛
- 腰痛
- 体がだるい
- 目のかすみ
通院者
第2編4章 1.2〕通院者の状況 p74~75
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における通院者率が男女ともに最も高いのはどれか。
- 糖尿病
- 腰痛症
- 高血圧症
- 眼の病気
受療率
第2編4章 2.2〕受療率 p77~78
令和2年(2020年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。
- 新生物〈腫瘍〉
- 呼吸器系の疾患
- 消化器系の疾患
- 内分泌、栄養及び代謝疾患
▼看護師国家試験必修問題まとめ