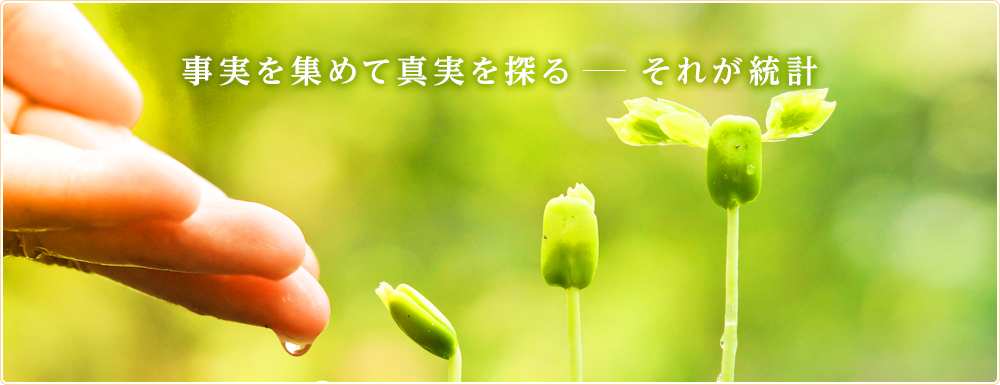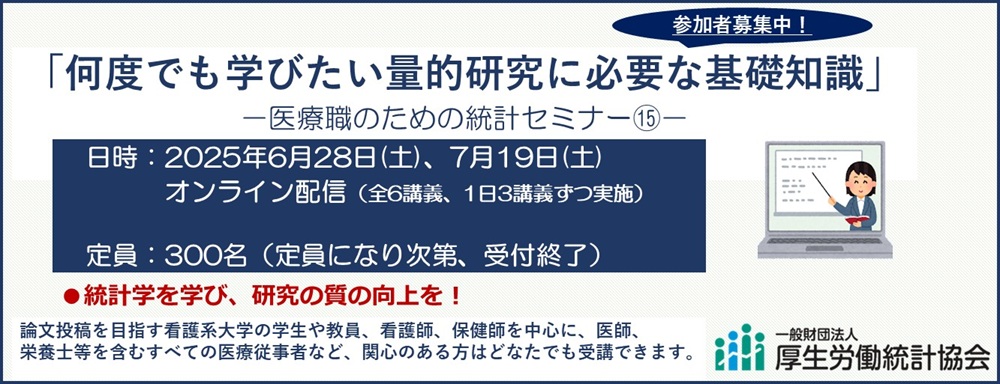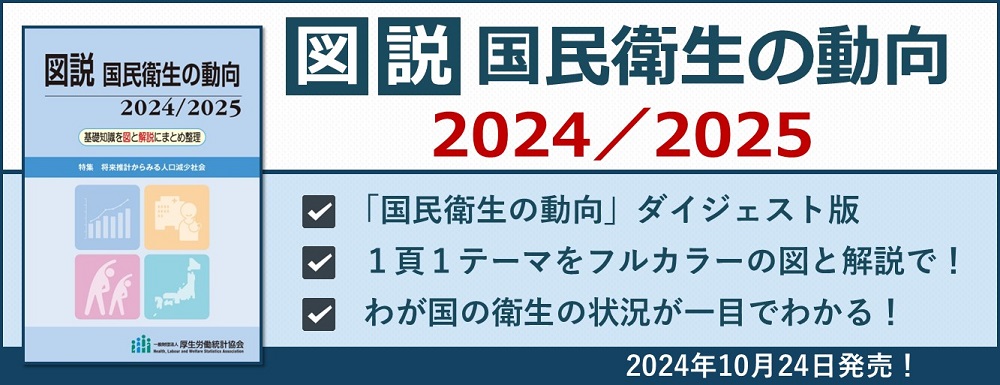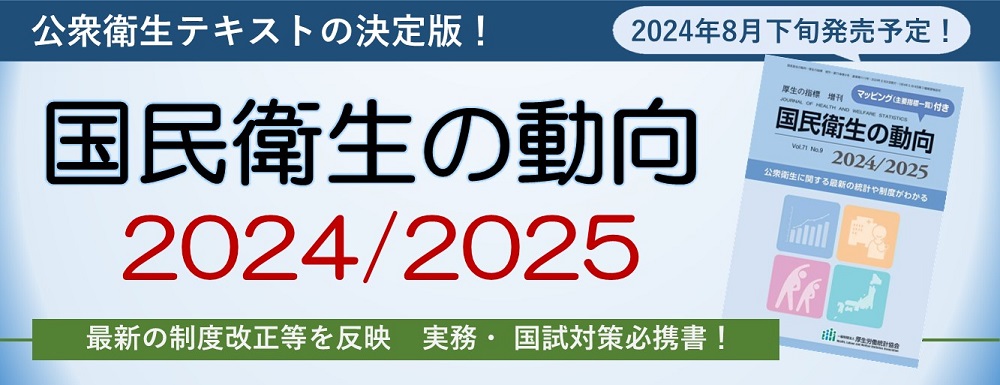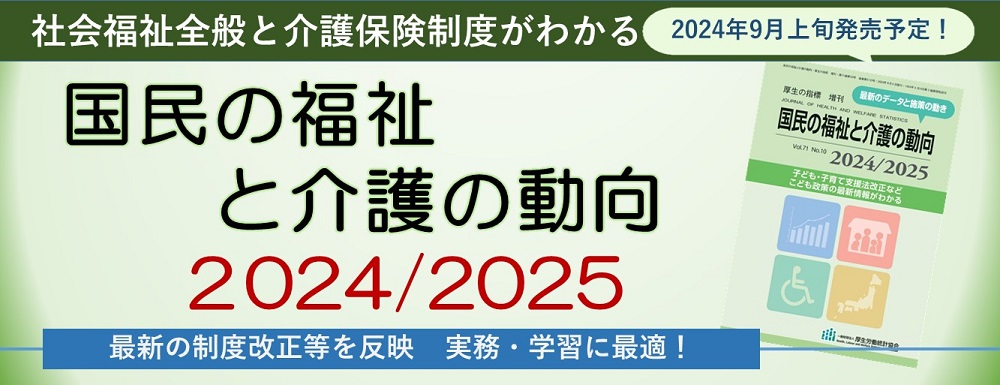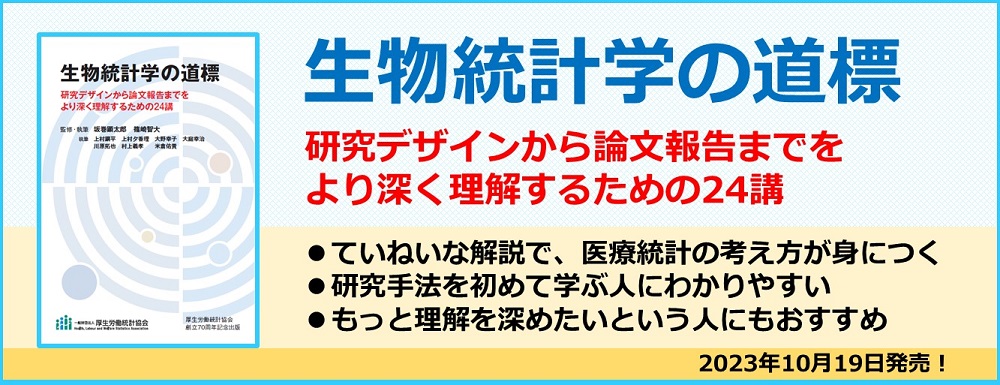「国民衛生の動向」は、毎年わが国の衛生の状況や保健行政の動向を解説したものとして、昭和24年の創刊以来、公衆衛生テキストの決定版として長年ご愛用いただいています。とくに本誌では、最新の衛生を取り巻く制度の解説や人口・健康状況などの統計が網羅されており、医療関係者の国家試験対策のテキストとしても広く活用されているところです。
当ページでは、医療職の国家試験の中でもご利用者の多い看護師国家試験の受験者向けに、最新の「国民衛生の動向2024/2025」(2024年8月27日発売)がカバーする看護師国家試験の過去問をピックアップし、本誌の該当箇所を示します。問題を解きながら不明な部分を本誌で確認し、学習効率の向上にご活用下さい。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
看護師国家試験について
最新の試験日程や手続き等の情報は、看護師国家試験の施行(厚生労働省)をご確認下さい。
看護師国家試験は昭和25年(1950年)から開始し、最新では令和7年(2025年)2月に114回目の試験が実施されました。
過去10年間の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりです。
|
|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 114回(2025年) | 63,131人 | 56,906人 | 90.1% |
| 113回(2024年) | 63,301人 | 55,557人 | 87.8% |
| 112回(2023年) | 64,051人 | 58,152人 | 90.8% |
| 111回(2022年) | 65,025人 | 59,344人 | 91.3% |
| 110回(2021年) | 66,124人 | 59,769人 | 90.4% |
| 109回(2020年) | 65,568人 | 58,513人 | 89.2% |
| 108回(2019年) | 63,603人 | 56,767人 | 89.3% |
| 107回(2018年) | 64,488人 | 58,682人 | 91.0% |
| 106回(2017年) | 62,534人 | 55,367人 | 88.5% |
| 105回(2016年) | 62,154人 | 55,585人 | 89.4% |
合格率は9割前後と国家試験としては高いですが、必修問題50点中40点以上、一般問題・状況設定問題250点中約160点(毎年変動)以上という明確な合格基準があり、対策をせずに臨んで合格することは難しいものとなっています。
看護師国家試験の出題基準は、平成12年の公表以来、保健師助産師看護師国家試験出題基準改定部会で検討を行い、改定を重ねてきており、令和5年実施の試験からは、「保健師助産師看護師国家試験出題基準 令和5年版」が適用されています。出題基準では、①必修問題、②人体の構造と機能、③疾病の成り立ちと回復の促進、④健康支援と社会保障制度、⑤基礎看護学、⑥成人看護学、⑦老年看護学、⑧小児看護学、⑨母性看護学、⑩精神看護学、⑪在宅看護論/地域・在宅看護論、⑫看護の統合と実践の12の領域が設けられ、それぞれ幅広い出題範囲が設定されています。
当サイトを活用した勉強方法
「看護師国家試験に出る国民衛生の動向」では、最新の第113回試験から第102回試験までの12年分の過去問題をすべて解説付きで掲載していているほか、統計、法律、感染症、介護などテーマ別に整理したまとめページも掲載しています。
扱っている問題数は1000問を超えており、やみくもに手を付けてしまうとしっかり理解できないまま学習が行き詰まってしまうおそれがあります。以下に効率的な学習モデルとして一例を示します。
① 必修問題をマスターする
看護師国家試験は、重要な基本的事項を問う必修問題(50問50点)と、一般問題(130問130点)・状況設定問題(60問120点)に分かれます。
必修問題は、基本的に50問中40問以上(80%以上)正答しなければ不合格となる絶対的な合格基準が設定されており、必修問題の点数が足りずに不合格になる、いわゆる「必修落ち」だけは避けなければなりません。
必修問題として用いられる問題の範囲は限られており、過去10年程度の出題と同一または類似の問題が約半数を占めているので、まず過去に出題された必修問題をマスターすることが最も重要となります。
当サイトでは保健師助産師看護師国家試験出題基準に対応して、過去12年の必修問題を以下の16ページに網羅しています。
- 健康の定義と理解
- 健康に影響する要因
- 看護で活用する社会保障
- 看護における倫理
- 看護に関わる基本的法律
- 人間の特性
- 人間のライフサイクル各期の特徴と生活
- 看護の対象としての患者と家族
- 主な看護活動の場と看護の機能
- 人体の構造と機能
- 徴候と疾患
- 薬物の作用とその管理
- 看護における基本技術
- 日常生活援助技術
- 患者の安全・安楽を守る看護技術
- 診療に伴う看護技術
いずれも、まずポイントを解説した後、関連する過去問題を掲載しており、初学者でもインプットとアウトプットを繰り返しながら、十分に理解と実践が図れるように構成しています。
これを短期間で少なくとも2~3週し、不安があればさらに回数を重ねて過去の必修問題はすべて解けるという自信を身に付けて下さい。
② 頻出分野を理解する
看護師国家試験で最も出題されるテーマの一つが「健康支援と社会保障制度」です。
これは人口や世帯、健康状態、医療費などの各種統計や、保健・福祉・介護など社会保障を支える法律などが含まれており、暗記量も多く受験生の苦手とする分野です。
さらに、最近の統計資料や制度改正なども踏まえた上で出題されるため、知識をアップデートしなければ誤答となることも少なくありません。
当サイトでは、「国民衛生の動向」がカバーする頻出分野ごとに、以下の4ページを掲載しています。
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の感染症問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめ
いずれも最新の知識が必要であり、一通り確認することをおすすめします。
特に統計問題は一回で数値等を覚えることは難しいので、複数回繰り返して着実に定着させて下さい。
③ 実践形式で問題を解く
必修問題や頻出分野を理解した後は、実践形式で過去問題を数多く解いて、解説を読みながらさらに知識量を増やしていく必要があります。
当サイトでは、最新の第113回試験(2024年2月)までの12年分の全問題と解説を掲載しています。少なくとも5年分、できれば10年分以上挑戦してください。
第113回(2024年)
第112回(2023年)
第111回(2022年)
第110回(2021年)
第109回(2020年)
第108回(2019年)
第107回(2018年)
第106回(2017年)
第105回(2016年)
第104回(2015年)
第103回(2014年)
第102回(2013年)
④ 参考書等で周辺知識を広げる
看護師国家試験では過去問対策が最重要ですが、当然過去に出題されていない統計数値、新規法律、医学用語なども多く出題されます。
そのため、講義・演習で使った「国民衛生の動向」等の教科書・参考書や資料・ノート、「レビューブック」「クエスチョン・バンク」(メディックメディア)などの国家試験対策書、「看護roo!国試」などスマートフォン向け学習アプリ、YouTube等の学習チャンネルなど様々な媒体を活用して周辺知識を確実に定着させ、点数の上乗せを図り、合格へさらに近づくことが大切です。
看護師国家試験過去問題PDF
厚生労働省が公表している過去10年間の問題、正答のPDFの一覧です。
|
第113回 (2024年) |
午前問題別冊 | 正答 | |
|
第112回 (2023年) |
午前問題別冊 | 正答 | |
|
第111回 (2022年) |
午前問題別冊 | 正答 | |
|
第110回 (2021年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第109回 (2020年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第108回 (2019年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第107回 (2018年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第106回 (2017年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第105回 (2016年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
|
第104回 (2015年) |
午前問題 | 午前問題別冊 | 正答 |
医療職国家試験に出る国民衛生の動向
看護師資格と合わせて取得を目指す方も多い保健師国家試験や助産師国家試験のほか、医師、薬剤師国家試験の統計問題など「国民衛生の動向」が対応する問題とポイントを掲載しています。
内容も重なる部分が多く、知識の定着や予想問題として活用することをおすすめします。
図説 国民衛生の動向
 |
『図説 国民衛生の動向』は、「国民衛生の動向」の図説ダイジェスト版です。「国民衛生の動向」の内容に沿って、1ページ1テーマで、フルカラーの図表とともに要点を絞って解説しています。
看護師国家試験の内容も広くカバーしていますので、記述量の多い「国民衛生の動向」の手軽な副読本としても活用できます。
医療職のための統計セミナー
厚生労働統計協会では、看護師等の医療職の皆様のキャリアアップのために、研究発表や論文作成に必要な統計知識を実践的に学んでいただくオンラインセミナーを、毎年数回開催しています。
詳細はこちらをご確認下さい。
「国民衛生の動向」は公衆衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。保健師国家試験では様々な統計調査を基にした、最新の数値を問う問題が毎年必ず出題されるので、「国民衛生の動向」などで最新の統計をまとめて押さえることが必須となります。
このページでは、第110回(2024年)から第101回(2015年)までの10年間の保健師国家試験に出題された統計問題をピックアップし、最新の数値とともに「国民衛生の動向」の参照箇所を示します。これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる力を身に付けていただければ幸いです。
なお、問題と回答については、最新の統計の数値に合わせて改題を行っています。数値は2025年2月に実施される第111回試験に沿った「国民衛生の動向2023/2024」内に掲載している年次のものになります。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
統計別問題目次
第1編:社会保障の動向と衛生行政の体系
- 社会保障費用統計
- 地域保健・健康増進事業報告
- 保健師活動領域調査
第2編:衛生の主要指標
- 国勢調査・人口推計
- 国民生活基礎調査
- 将来推計人口
- 労働力人口
- 人口動態統計
- 患者調査
- 生命表
第3編:保健と医療の動向
- 国民健康・栄養調査
- 歯科疾患実態調査
第4編:医療提供体制と医療保険
- 医療従事者・医療施設数
- 国民医療費
第5編:保健医療を取り巻く社会保障
- 福祉行政報告例(児童虐待)
- 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査
第7~10編:生活環境・労働衛生・学校保健
- 食中毒統計調査
- 労働災害・業務上疾病
- 労働安全衛生調査(実態調査)
- 学校保健統計調査
- 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
社会保障費用統計
第1編1章 1.5〕社会保障の状況 p16~17
社会保障給付費〈令和2年度〉
- 令和2年度(2020年度)の社会保障給付費は132.2兆円と毎年増加を続けており、国民1人当たりでみると104.8万円となっている。
- 社会保障給付費を部門別にみると、年金が55.6兆円(42.1%)と最も多く、次いで医療が42.7兆円(32.3%)、福祉その他が33.9兆円(25.6%)となっている。
▶106回午後34改題
令和2年度(2020年度)の社会保障給付費で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 医療給付費が最も多くを占める。
- 雇用保険の失業給付が含まれる。
- 給付総額は年間300兆円を超える。
- 給付総額は前年度よりも減少している。
- 国民1人あたりの給付費は約100万円である。
地域保健・健康増進事業報告
第1編2章 3.一般衛生行政の活動 p24~25
調査項目
地域保健・健康増進事業報告は、全国の保健所・市区町村を対象に、地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得ることを目的とする調査である。
【地域保健事業】
①母子保健、②健康増進、③歯科保健、④精神保健福祉、⑤エイズ、⑥予防接種、⑦職員の配置状況
【健康増進事業】
①健康診査、②歯周疾患検診・骨粗鬆症検診、③健康教育、④健康相談、⑤訪問指導、⑥がん検診、⑦肝炎ウイルス検診
▶110回午後26
厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。
- 介護保険施設
- 企業および事業所
- がん診療連携拠点病院
- 保健所および市区町村
- 病院、療養病床を有する診療所
▶105回午前39
地域保健・健康増進事業報告で把握されるのはどれか。2つ選べ。
- 糖尿病の総患者数
- エイズに関する相談件数
- 退院患者の平均在院日数
- 乳児の健康診査の受診率
- 脳血管疾患の年齢調整死亡率
保健師活動領域調査
第1編2章 5.保健師の活動 p25~27
保健師の活動状況
令和4年(2022年)の常勤保健師を就業場所別にみると以下のとおりである。
- 都道府県:5,675人(14.9%)
- 保健所設置市:9,808人(25.8%)
- 特別区:1,563人(4.1%)
- 市町村:20,957人(55.1%)
また、活動項目別に保健師一人当たりの平均活動時間数の割合をみると、都道府県では「健康危機管理」が最も高く、保健所設置市・特別区、市町村では「直接対人支援」が最も高い。
▶108回午前2改題
令和4年度(2022年度)の保健師活動領域調査で正しいのはどれか。
- 保健師の就業場所で最も多いのは市町村である。
- 保健所設置市で働く常勤保健師は地方自治体における保健師全体の3割を超えている。
- 都道府県保健所に所属する保健師の活動項目別の活動時間割合は「直接対人支援」が最も多い。
- 市町村保健師の活動項目別の保健師1人当たりの平均時間数は「施策管理・業務及び組織マネジメント」が最も長い。
国勢調査・人口推計
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
人口静態統計
- 人口静態はある時点における人口や世帯、年齢別状況などの静止した姿を指す。
- 総務省統計局が実施する国勢調査はその主要統計で、5年に1回実施される全数調査(悉皆調査)である。
▶110回午後35
国勢調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 3年ごとに実施する。
- 人口静態を把握する。
- 厚生労働省が実施する。
- 調査区を無作為抽出する。
- 世帯員と世帯について調査を実施する。
総人口・年齢3区分別人口〈令和4年〉
- 総人口は1億2495万人(男6076万人・女6419万人)で、2010年ころから減少傾向にある。
- 年齢3区分別に人口構成割合をみると、年少人口(0~14歳)割合が11.6%、生産年齢人口(15~64歳)割合が59.4%、老年人口(65歳以上)割合が29.0%となっている。少子高齢化により、年少人口割合と生産年齢人口割合は減少傾向、老年人口割合は増加傾向にある。
▶101回午後2改題
日本の令和4年(2022年)の人口について正しいのはどれか。
- 総人口は前年より増加している。
- 出生数は70万人を超えている。
- 年少人口の割合は10%以下である。
- 世界で人口の多い国上位5位以内である。
人口指数〈令和4年〉
●年少人口指数=19.5(低下傾向)
:年少人口÷生産年齢人口×100
●老年人口指数=48.8(上昇傾向)
:老年人口÷生産年齢人口×100
●従属人口指数=68.4(上昇傾向)
:(年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100
●老年化指数=249.9(上昇傾向)
:老年人口÷年少人口×100
▶107回午後28
従属人口指数はどれか。
- 老年人口÷総人口×100
- 老年人口÷生産年齢人口×100
- (年少人口+老年人口)÷総人口×100
- (年少人口+老年人口)÷生産年齢人口×100
- 老年人口÷(年少人口+生産年齢人口)×100
▶102回午前19
老年化指数はどれか。
- (老年人口÷総人口)×100
- (老年人口÷年少人口)×100
- (老年人口÷生産年齢人口)×100
- {(老年人口÷年少人口)÷生産年齢人口}×100
▶105回午前38
日本の人口に関する指標のうち、平成23年(2011年)以降、増加傾向にあるのはどれか。2つ選べ。
- 総人口
- 老年化指数
- 従属人口指数
- 年少人口割合
- 生産年齢人口割合
国民生活基礎調査
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
調査の概要
▶106回午前30
全国から無作為抽出された世帯及び世帯員を対象として行われる調査はどれか。
- 患者調査
- 人口動態調査
- 食中毒統計調査
- 学校保健統計調査
- 国民生活基礎調査
世帯の状況
令和3年(2021年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に以下のとおりである。
①単独世帯:29.5%
②夫婦と未婚の子のみの世帯:27.5%
③夫婦のみの世帯:24.5%
④ひとり親と未婚の子のみの世帯:7.1%
⑤三世代世帯:4.9%
▶107回午後1改題
A市の世帯構造別にみた世帯の割合を図に示す。

令和3年(2021年)の国民生活基礎調査に基づく全国の割合と比較して、A市が高いのはどれか。2つ選べ。
- 単独世帯
- 夫婦のみの世帯
- 夫婦と未婚の子のみの世帯
- ひとり親と未婚の子のみの世帯
- 三世代世帯
世帯数の推移
- 近年の世帯割合の推移をみると、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」が増加傾向、「夫婦と未婚の子のみの世帯」と「三世代世帯」が減少傾向にある。
- こうした世帯構造の変化を受けて、令和3年(2021年)の平均世帯人員は2.37人と減少が続いている。
▶104回午後28改題
平成22年(2010年)から令和3年(2021年)における日本の社会情勢の変化で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 完全失業率の増加
- 老年化指数の低下
- 平均世帯人員の減少
- 社会保障給付費の減少
- 65歳以上の雇用者数の増加
将来推計人口
第2編1章 1.4〕将来推計人口 p42~43
人口・世帯の将来推計
- 日本の将来推計人口(平成29年推計)によると、総人口は令和35年(2053年)には1億人を割り、令和47年(2065年)には8808万人になると推計されている。
- 65歳以上の老年人口割合の推計では、令和7年(2025年)には30.0%を超え、令和22年(2040年)には35.3%になると推計されている。
▶102回午前30改題
日本の令和22年(2040年)の推計について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 総人口が1億人を下回る。
- 75歳以上の高齢者が2,000万人を超える。
- 総人口のおよそ3人に1人が65歳以上になる。
- 世帯主が65歳以上の世帯における単独世帯の割合が50%を超える。
労働力調査
第2編1章 3.労働力人口 p48~49
労働力人口(令和4年)
- 労働力人口とは15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計で、令和4年(2022年)平均で6,902万人である。性別にみると、男性は3,805万人(55.1%)、女性は3,096万人(44.9%)で、男性は前年から減少したが、女性は増加が続いている。
- 女性の年齢階級別労働力率をみると、その特徴として子育て期に当たる30歳代に労働力率が低下し、20歳代と40歳代をピークとするM字カーブが挙げられる(近年は緩和傾向)。
▶104回午前4改題
令和4年(2022年)の労働力調査について正しいのはどれか。
- 女性の労働力人口は前年に比べ減少した。
- 女性の雇用形態は正規の雇用が約6割である。
- 労働力人口の総数に占める女性の割合は約45%である。
- 女性雇用者数に占める割合で最も多い産業は製造業である。
▶109回午前3改題
令和4年(2022年)の労働力調査における日本の女性の労働で正しいのはどれか。
- 就業者は前年に比べ減少している。
- 労働力人口の総数の約6割を占めている。
- 年齢階級別労働力率では40~44歳が最も高い。
- 非正規の雇用形態はパート・アルバイトが最も多い。
▶105回午前11改題
令和4年(2022年)の女性の労働に関する説明で正しいのはどれか。
- 育児休業取得率は90%を超えている。
- 労働力人口比率は60%を超えている。
- 30歳代の就業率は40歳代よりも低い。
- 平均勤続年数は20年前よりも短くなっている。
その他雇用の状況
- 完全失業者・完全失業率は、平成22年(2010年)の334万人・5.1%から低下傾向にあり、令和4年(2022年)は179万人・2.6%となっている。
- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は、平成2年(1990年)には19.1%であったが上昇を続け、令和4年(2022年)には36.9%となっている。
▶103回午前3改題
日本の社会格差を示す指標の過去20年間の推移について正しいのはどれか。
- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は減少している。
- 相対的貧困率は低下している。
- 完全失業率は低下している。
- ジニ係数は低下している。
人口動態統計
第2編2章 人口動態 p51~69
調査の概要
▶102回午後34
人口動態統計に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 出生
- 婚姻
- 妊娠
- 転出
- 入院
▶105回午後32
人口動態統計の情報を用いて算出を行う指標はどれか。2つ選べ。
- 受療率
- 婚姻率
- 生活影響率
- 年少人口指数
- 合計特殊出生率
出生に関する統計
- 令和4年(2022年)の出生数は77.1万人、人口千対の出生率は6.3と減少が続いている。
- 15~49歳の女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は1.26で、過去最低であった平成17年(2005年)と並んでいる。
- 母の年齢階級別に出生率をみると30~34歳が最も高い。
- 母の年齢別出生率を女児だけについて合計した総再生産率は0.64、さらに女児の死亡を見込んだ純再生産率は0.63となっている(令和3年)。
▶106回午前29
人口動態統計で、人口1,000対で表すのはどれか。
- 出生率
- 純再生産率
- 総再生産率
- 周産期死亡率
- 合計特殊出生率
▶110回午前19
合計特殊出生率の算出方法で正しいのはどれか。
- 出生数を人口で除し、1,000を乗ずる。
- ある年齢の母の出生数を同年齢の女性人口で除し、1,000を乗ずる。
- 母の年齢別出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。
- 母の年齢別女児出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。
▶107回午前33改題
令和4年(2022年)の日本における出生の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 出生順位別構成割合は第1子が50%を上回っている。
- 母の年齢別にみた出生率は30~34歳が最も高い。
- 都道府県別合計特殊出生率は沖縄県が最も低い。
- 出生率は8.0(人口千対)を下回っている。
- 純再生産率は1を超えている。
死因統計の分類
- 人口動態調査における死因統計の分類は、世界保健機関(WHO)が作成する国際疾病分類(ICD)に基づいている。
- ICDは医学の進歩等に応えて一定期間を置いて修正が行われ、近年では平成7年(1995年)からICD-9に代わりICD-10が、平成18年(2006年)からICD-10(2003年版)が、平成28年(2016年)からICD-10(2013年版)準拠が適用されている。
▶105回午後21
国際疾病分類〈ICD〉に基づいた統計が含まれるのはどれか。
- 国勢調査
- 人口動態調査
- 医療施設動態調査
- 国民生活基礎調査
- 国民健康・栄養調査
▶102回午後22・107回午前17類問
国際疾病分類〈ICD〉について正しいのはどれか。
- 日本の死因統計では平成7年(1995年)にICD-10が採用された。
- 患者調査での疾病分類には用いられない。
- 各種疾病の治療指針が示されている。
- 国際疫学会が改訂を行っている。
主な死因別の死亡率(令和4年)
▶108回午前29改題・101回午後26類問
日本の主な死因別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移を図に示す。

心疾患はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
▶102回午後20改題
脳血管疾患について正しいのはどれか。
- 年齢調整死亡率は増加している。
- 脳出血の最大の危険因子は糖尿病である。
- 脳梗塞よりくも膜下出血による死亡数が多い。
- 令和4年(2022年)の死因順位は第4位である。
▶104回午前32改題
日本の死因別死亡率の年次推移を図に示す。

説明として正しいのはどれか。
- 縦軸の死亡率は年齢を調整した値である。
- 死因Aが上昇傾向にある主な理由は野菜摂取量の減少である。
- 死因Bの平成7年の急激な低下は国際生活機能分類(ICF)改訂の影響である。
- 死因Cが低下傾向にある主な理由は血圧の管理である。
- 死因Dが低下傾向にある主な理由は食生活の見直しである。
年齢階級別にみた死因第1位(令和4年)
▶110回午後25改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位はどれか。
- 自殺
- 肺炎
- 心疾患
- 悪性新生物
- 先天奇形、変形及び染色体異常
▶109回午前4改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における年齢階級とその死因第1位の組合せで正しいのはどれか。
- 1~4歳――インフルエンザ
- 5~9歳――悪性新生物〈腫瘍〉
- 10~14歳――不慮の事故
- 15~19歳――心疾患
▶103回午後25改題
令和4年(2022年)の日本における各年代と年代別死因第1位の組合せで正しいのはどれか。
- 20歳代―自殺
- 30歳代―悪性新生物〈腫瘍〉
- 40歳代―心疾患
- 50歳代―脳血管疾患
- 60歳代―肺炎
▶107回午前30改題
令和4年(2022年)の人口動態統計月報年計における性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合を示す。

自殺はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
▶109回午後27改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における20歳以上の年齢別死亡原因を以下に示す。

不慮の事故はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
悪性新生物〈腫瘍〉による死亡(性・部位別)〈令和4年〉
- 令和4年(2022年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.6万(男22.3万人・女16.3万人)である。
- 部位別にみると、総数および男では気管、気管支及び肺が、女では大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。
▶107回午前24
成人男性の部位別にみた悪性新生物の年齢調整死亡率の推移のグラフを示す。

Aの一次予防として正しいのはどれか。
- 肥満予防
- 減塩の推奨
- 野菜の摂取
- 受動喫煙防止
- 節度ある飲酒
自殺の状況(令和4年)
- 自殺による死亡数は2.1万人(男1.4万人・女0.7万人)で、上記のとおり10~39歳の各階級で死因の第1位となっている。自殺対策基本法などの取り組みにより、平成22年以降は自殺者数・率ともに減少傾向を示している。
- 性・年齢階級別に自殺死亡数をみると、男女ともに5歳階級別では「50~54歳」、10歳階級別では「50~59歳」が最も多い。
- 自殺者の特定された原因・動機をみると(複数回答)、健康問題が12,774人と最も多く、家庭問題(4,775人)、経済・生活問題(4,697人)と続く(警察庁)。
▶106回午後29改題
令和4年(2022年)の日本の人口動態統計における自殺死亡で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 男性の死亡率は女性よりも高い。
- 20〜24歳の死因の第1位である。
- 死因順位別死亡数は第5位である。
- 自殺死亡率は10年前よりも増加している。
- 男性の死亡率が最も高い年齢階級は40〜44歳である。
不慮の事故
令和3年(2021年)の年齢階級別にみた子どもの不慮の事故の原因の第1位は以下のとおりである。
0歳:窒息
1~4歳:溺死及び溺水
5~9歳:交通事故
10~14歳:交通事故
▶110回午前24改題
令和3年(2021年)の人口動態統計で、子どもの不慮の事故による年齢別死因の割合についてのグラフを以下に示す。

窒息はどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
妊産婦死亡
- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。
- 妊産婦死亡率(出産(出生+死産)10万対)について、戦後は諸外国と比べて著しく高く、昭和35年(1960年)には117.5であったが、昭和40年(1965年)には80.4、昭和45年(1970年)には48.7、昭和50年(1975年)には27.3と急激に低下していき、令和3年(2021年)には2.5と、諸外国に比べて極めて低率となっている。
▶110回午前30
先進諸国(アメリカ合衆国、イギリス、スウェーデン、フランス、日本)における妊産婦死亡率の推移のグラフを別に示す。
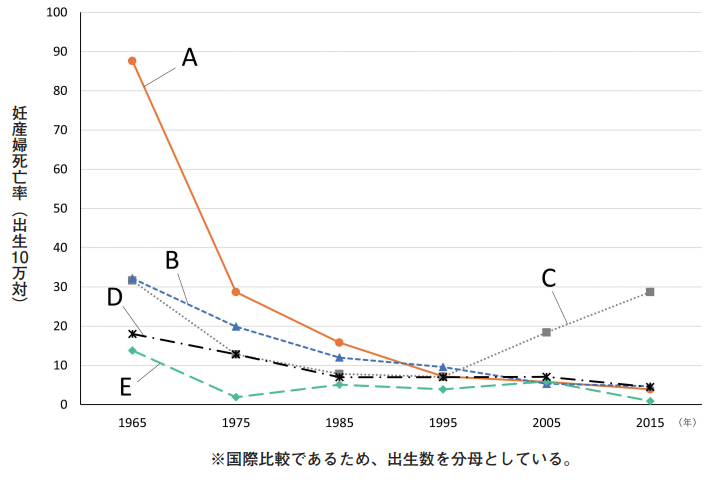
日本はどれか。
- A
- B
- C
- D
- E
患者調査
第2編4章 2.受療状況 p76~79
調査の概要
- 患者調査は、全国の医療施設(病院、一般診療所、歯科診療所)を利用する患者の傷病などの状況を把握するため、3年に1度実施されている。
- 把握する内容は、調査日に全国の医療施設で受療した推計患者数や、人口10万人に対する推計患者数である受療率、退院患者の平均在院日数、継続的に医療を受けている患者を含めた傷病別の総患者数などである。
▶103回午後26
患者調査で把握できるのはどれか。
- 有訴者率
- 死亡率
- 致命率
- 有病率
- 受療率
▶107回午前16
患者調査で正しいのはどれか。
- 5年に1回実施される。
- 推計患者数には調査日に受療した患者数が含まれる。
- 調査日に入院している患者の平均在院日数が把握される。
- 総患者数には医療を受けたことのない有病者数も含まれる。
推計患者数・受療率(令和2年)
- 推計患者数は、入院では121.1万人、外来では713.8万人となっている。それぞれ65歳以上の高齢者が占める割合をみると、65歳以上の入院患者は74.7%、外来患者は50.7%と多くを占めている。
- 受療率は、入院では960、外来では5,658となっている。それぞれ年齢階級別にみると、入院患者では男女とも90歳以上が最も高く、外来患者では男80~84歳、女75~79歳が最も高い。
▶105回午前22改題
令和2年(2020年)に実施された患者調査のうち高齢者の調査結果で正しいのはどれか。
- 入院患者では65歳以上が約7割を占めている。
- 外来患者では65歳以上が約8割を占めている。
- 年齢階級別外来受療率(人口10万対)では90歳以上が最も高い。
- 年齢階級別入院受療率(人口10万対)では75~79歳が最も高い。
傷病分類別受療率(令和2年)
▶108回午後28改題
令和2年(2020年)患者調査の疾病分類別の結果を表に示す。

Cに当てはまる疾患はどれか。
- 結核
- 消化器系の疾患
- 循環器系の疾患
- 悪性新生物〈腫瘍〉
- 精神および行動の障害
精神及び行動の障害の状況(令和2年)
- 上記のとおり、精神及び行動の障害の外来受療率は211、入院受療率は188、退院患者の平均在院日数は294.2日となっている。また、総患者数は502.5万人で増加傾向にあり、傷病分類別にみると「気分[感情]障害(躁うつ病含む)」が172.1万人で最も多い。(患者調査)
- 病院の平均在院日数をみると、精神病床は277.0日と諸外国と比べて非常に高くなっている。また、精神病床に入院している患者27.4万人を傷病分類別にみると、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が14.1万人と半分以上を占めている。(病院報告)
▶102回午前10改題
令和2年(2020年)の患者調査における精神及び行動の障害に関する動向について正しいのはどれか。
- 外来受療率は入院受療率より高い。
- 精神病床の平均在院日数は約100日である。
- 年齢階級別外来受療率は年齢とともに上昇する。
- 血管性及び詳細不明の認知症の総患者数は減少している。
▶109回午後30改題
平成23年(2011年)から令和2年(2020年)までの日本の精神疾患患者の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 総患者数は減少傾向にある。
- 気分障害の患者数が最も多い。
- 入院患者数は増加傾向に転じている。
- 外来患者数では75歳以上の患者が減少傾向にある。
- Alzheimer〈アルツハイマー〉病の患者数は増加傾向である。
入院形態別精神疾患患者の状況(精神保健福祉資料)
- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。
- 任意入院が行われる状態にないと判定された者については、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に医療保護入院が行える。
- 2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には措置入院を行うことができる。
- 令和3年(2021年)の入院形態別入院患者割合は、医療保護入院が49.8%と最も高く、任意入院が49.1%、措置入院が0.6%となっている。
▶104回午後24改題
令和3年(2021年)6月末における精神疾患を有する者の入院者数が最も多い入院形態はどれか。
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
▶107回午後34改題
令和2年(2020年)における精神疾患の患者に関する動向について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 入院患者は外来患者より少ない。
- 措置入院患者は、入院患者の0.6%である。
- 精神病床における平均在院日数は300日以上である。
- 平成23年(2011年)と比較して患者数は減少している。
- 入院患者の5割以上がAlzheimer〈アルツハイマー〉病である。
生命表
第2編3章 生命表 p70~73
平均寿命と健康寿命(令和元年)
- 平均寿命とは0歳の平均余命をいい、男性が81.56年、女性が87.71年と延びている。
- 健康寿命とは日常生活に制限のない期間の平均であり、男性が72.68年、女性が75.38年と延びている。
- 平均寿命と健康寿命の差は日常生活に制限のある期間ということになり、上記の差をみると、男性が8.73年、女性が12.07年となる。個人の生活の質の向上、社会保障負担の軽減のため、この差を短縮することも重要となる。
▶104回午前33改題
健康日本21(第二次)における健康寿命について正しいのはどれか。
- 患者調査の結果を計算に用いる。
- 年齢別死亡率は計算に不要である。
- 日常生活に制限のない者の平均年齢である。
- 健康寿命の増加分を上回る平均寿命の増加を目標とする。
- 令和元年(2019年)の健康寿命と平均寿命の差は男性より女性が大きい。
国民健康・栄養調査
第3編1章 2.健康増進対策 p84~94
主な調査項目
- 肥満・やせ(BMI、腹囲等)、糖尿病、血圧、血中コレステロール
- 食塩・野菜摂取量
- 運動習慣者、歩数、睡眠の状況
- 飲酒・喫煙
▶103回午後32
国民健康・栄養調査で把握できるのはどれか。2つ選べ。
- 健康寿命
- BMIの平均値
- 蛋白質の必要量
- 喫煙習慣者の割合
- 支出に占める食料費の割合
▶107回午後20
国民健康・栄養調査について正しいのはどれか。
- 血圧値は調査項目である。
- 3日間の食事調査が行われる。
- 調査日の食費は調査項目である。
- 栄養素等摂取量が市区町村別に比較される。
糖尿病の状況(令和元年)
- 糖尿病が強く疑われる者は1000万人、糖尿病の可能性を否定できない者も1000万人となっている。(平成28年)
- 男女ともに年齢が高くなるほど糖尿病が強く疑われる者の割合が増え、70歳以上では男が26.4%、女が19.6%となっている。
- 糖尿病が強く疑われる者の割合を男女別にみると、40~49歳、50~59歳、60~69歳、70歳以上のいずれの階級でも、女性より男性が高い。
- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者は74.8%と多くを占めている。
▶106回午後17改題
令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査の糖尿病に関する統計で正しいのはどれか。
- 平成28年(2016年)の糖尿病が強く疑われる者は約1,000万人である。
- 40歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、男性よりも女性が高い。
- 糖尿病が強く疑われる者のうち、糖尿病治療を受けている者の割合は40%以下である。
- 30歳以上で糖尿病が強く疑われる者の割合は、女性では年齢に関係なく一定である。
肥満者/やせの者の割合(令和元年)
- 成人の肥満度を求める指標としてBMI(体格指数)が用いられる。計算式は、体重(kg)÷(身長(m))2で、BMIが25以上で肥満、18.5未満でやせと判定される。
- 肥満者の割合は男性33.0%・女性22.3%、やせの者の割合は男性3.9%・女性11.5%となっている。
▶109回午前1
令和元年(2019年)の生活習慣病の動向で正しいのはどれか。
- 肥満者の割合は男性より女性の方が多い。
- 脳血管疾患の死亡率は脳内出血より脳梗塞が高い。
- 悪性新生物の年齢調整死亡率で男性の部位別の第1位は大腸である。
- 糖尿病を強く疑われる者のうち現在治療を受けている者の割合は、男女ともに50%以下である。
運動習慣者、歩数の状況(令和元年)
- 20歳以上の運動習慣のある者の割合は男性33.4%・女性25.1%で、男女ともに70歳以上が最も高く(男性42.7%・女性35.9%)、次いで60~69歳となっている。
- 20歳以上の1日当たりの歩数の平均値は6,278歩で、男性6,793歩・女性5,832歩となっている。
▶109回午後19
令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査における身体活動・運動で正しいのはどれか。
- 20~49歳で運動習慣のある者の割合が最も高い。
- 20歳以上の歩数の平均値は1日8,000歩を下回る。
- 男性より女性の方が運動習慣のある者の割合が高い。
- 歩数の平均値は平成22年(2010年)の約2倍である。
喫煙習慣者の割合(令和元年)
▶108回午後25改題
令和元年(2019年)国民健康・栄養調査における20歳以上の男女別の「現在習慣的に喫煙している者の割合」で正しいのはどれか。
- 男性37.1% 女性27.6%
- 男性37.1% 女性17.6%
- 男性27.1% 女性17.6%
- 男性27.1% 女性7.6%
- 男性17.1% 女性7.6%
歯科疾患実態調査
第3編2章 5.歯科保健医療 p118~120
8020運動
▶107回午後24改題
令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査の結果をグラフに示す。

このグラフが表しているのはどれか。
- う歯を持つ者の割合
- 顎関節の異常がある者の割合
- 20歯以上の歯を有する者の割合
- 4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合
▶105回午後17改題
令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査において80歳で20本以上の自分の歯を有する者の割合に最も近いのはどれか。
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
医療従事者・医療施設数
第4編1章 4.医療関係者 5.医療施設 p184~204
医療従事者の就業者数・就業先(令和2年末)
- 就業している看護職員の総数は166.0万人で、保健師が5.6万人、助産師が3.8万人、看護師が128.1万人、准看護師が28.5万人となっている。
- 保健師の就業先をみると、市区町村が54.8%と最も多く、次いで保健所が15.3%、事業所が6.8%、病院が6.4%などとなっている。
▶101回午後1改題
令和2年(2020年)の衛生行政報告例における保健師の就業場所の構成割合で、市区町村、保健所の次に多いのはどれか。
- 病院
- 事業所
- 社会福祉施設
- 訪問看護ステーション
医療施設数(令和2年10月1日)
- 病院数は平成2年(1990年)ころをピークに減少傾向で、令和2年(2020年)は8,238施設となっている。
- 診療所は長期的に増加傾向で、令和2年(2020年)の一般診療所は102,612施設、歯科診療所は67,874施設となっている。
▶108回午前35改題
令和2年(2020年)の日本の医療施設数または医療従事者数で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 病院数は約6千施設である。
- 一般診療所数は約5万施設である。
- 就業保健師数は約5万6千人である。
- 歯科診療所数は約6万8千施設である。
- 就業看護師数は約100万5千人である。
国民医療費
第4編2章 6.国民医療費 p216~219
国民医療費の概要・状況
- 国民医療費は、医療機関などにおける傷病の治療に要する費用を推計したものである。正常な妊娠や分娩などに要する費用、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用、固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢などの費用、平成12年度から開始した介護保険制度の給付費は含まない。
- 令和2年(2020年)度の国民医療費は43.0兆円(国民総生産に対する比率は8.02%)で、人口1人当たり34.1万円である。人口1人当たりの国民医療費を年齢階級別にみると、65歳未満が18.4万円に対し、65歳以上は73.4万円(約4倍)、75歳以上は90.2万円(約5倍)となっている。
▶108回午後27改題
令和2年度(2020年度)の国民医療費について正しいのはどれか。
- 介護保険給付費を含む。
- 総額は40兆円を超える。
- 正常な妊娠・分娩の費用を含む。
- 国民総生産に対する比率は20%を超える。
- 健康の維持・増進を目的とした健康診断の費用を含む。
制度区分別・診療区分別国民医療費、傷病分類別医科診療医療費(令和2年度)
- 制度区分別に国民医療費をみると、医療保険等給付分が45.1%で最も多く、次いで後期高齢者医療給付分が35.6%、患者等負担分が12.1%、公費負担医療給付分が7.3%などとなっている。
- 診療区分別に国民医療費をみると、医科診療が71.6%で最も多く、次いで薬局調剤17.8%、歯科診療7.0%、入院時食事・生活1.7%、訪問看護0.8%などとなっている。
- 傷病分類別医科診療医療費をみると、循環器系の疾患が6.0兆円(19.5%)で最も多く、次いで新生物〈腫瘍〉が4.7兆円(15.2%)となっている。
▶108回午後21改題・107回午前31類問
令和2年度(2020年度)の傷病分類別医科診療医療費で、医療費が最も多いのはどれか。
- 精神および行動の障害
- 呼吸器系の疾患
- 循環器系の疾患
- 消化器系の疾患
- 新生物〈腫瘍〉
▶103回午前18改題
令和2年度(2020年度)の国民医療費について正しいのはどれか。
- 制度区分別国民医療費では公費負担医療給付分が最も多くを占める。
- 傷病分類別の医科診療医療費では悪性新生物〈腫瘍〉が最も多くを占める。
- 65歳以上の人口一人当たり国民医療費は65歳未満の約4倍である。
- 訪問看護医療費は全体の5%を上回る。
福祉行政報告例(児童虐待)
第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p237~238
児童虐待対応件数等〈令和3年度〉
- 児童虐待対応件数(20.7万件)のうち、虐待の種別にみると、心理的虐待が60.1%で最も多く、次いで身体的虐待が23.7%、ネグレクトが15.1%、性的虐待が1.1%となっている。虐待対応件数は、総数・種別ともに増加傾向にある。
- 主たる虐待者をみると、実母が9.9万件(47.5%)で最も多く、次いで実父が8.6万件(41.5%)となっているが、実父の構成割合は年々上昇している。
▶102回午前14改題
令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待相談対応件数について正しいのはどれか。
- 児童相談所の対応件数は前年度に比べ横ばいである。
- 実父による虐待は前年度に比べ増加傾向である。
- 実母による虐待は全体の4割以下である。
- 身体的虐待は心理的虐待より多い。
高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査
第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242
養護者による高齢者虐待と認められた件数等〈令和3年度〉
- 養護者による高齢者虐待のうち、虐待を行った養護者の続柄は、息子が38.9%で最も多く、次いで夫が22.8%となっている。
- 被虐待高齢者の性別は女性が75.6%と最も多く、年齢階級別にみると80~84歳が24.6%で最も高い。
- 高齢者虐待の種別にみると、身体的虐待が67.3%で最も多く、次いで心理的虐待が39.5%などとなっている。また、虐待の種別・要介護度別にみると、身体的虐待や心理的虐待は要介護度が重い方の割合が低く、介護等放棄では逆の傾向がみられる。
▶103回午前21改題
令和3年度(2021年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」における養護者による高齢者虐待に関する説明として適切なのはどれか。
- 経済的虐待が全体の6割を占めている。
- 虐待者の続柄は息子の割合が最も高い。
- 虐待の種別にかかわらず、要介護度が高いほど虐待の発生割合が高い。
- 被虐待者の9割が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅡ以上である。
食中毒統計調査
第7編2章 10.食中毒対策 p285~288
食中毒の発生状況(令和4年)
- 令和4年(2022年)の食中毒の事件数は962件、患者数は6,856人、死者は5人となっている。
- 特定された原因食品をみると、件数では魚介類に起因するものが53.7%と最も多い。
- 判明した病因物質をみると、患者数ではノロウイルスが32.2%と最も多く、件数ではアニサキスが59.4%と最も多い。
▶101回午前39改題
令和4年(2022年)の厚生労働省による食中毒統計調査について正しいのはどれか。
- 患者数は年間100万人以上である。
- 死亡者数は年間1,000人以上である。
- ノロウイルスによる患者が最も多い。
- 原因食品で最も多いのは肉類およびその加工品である。
労働災害・業務上疾病
第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308
業務上疾病の発生状況(令和3年)
▶110回午前27改題
令和3年度(2021年度)の業務上疾病発生状況等調査における疾病分類別業務上疾病発生者数をグラフに示す。
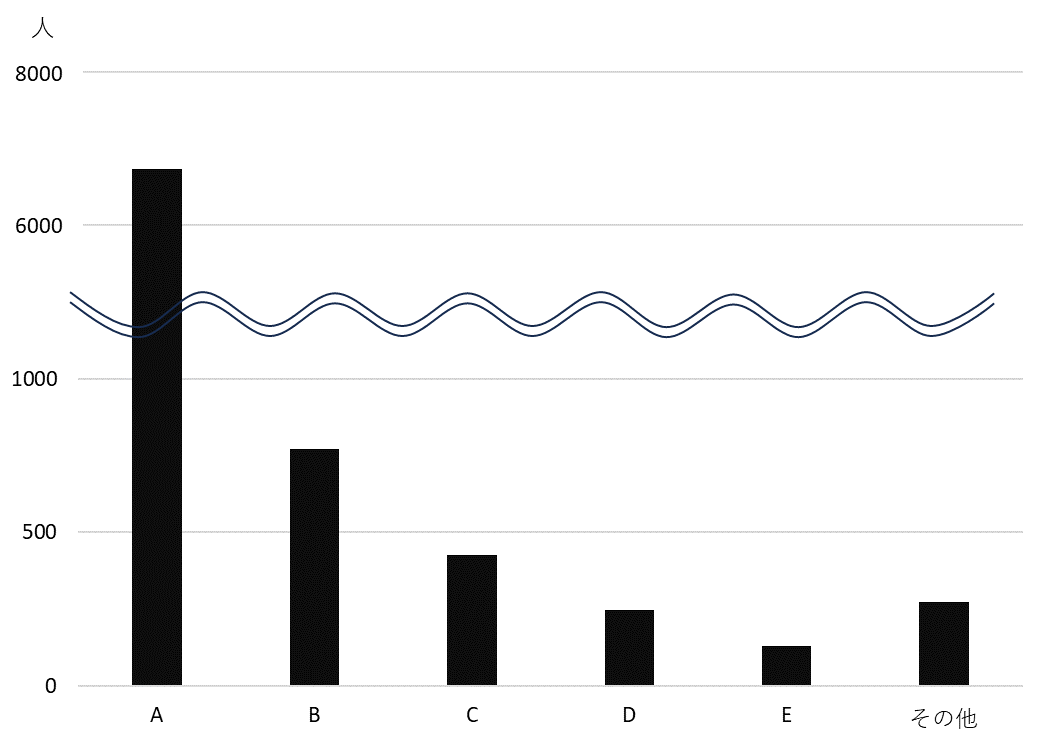
Aに該当するのはどれか。
なお、「新型コロナウイルスり患によるもの」を含む「病原体による疾病」はグラフから除いている。
- 化学物質による疾病
- 負傷に起因する疾病
- 物理的因子による疾病
- 作業態様に起因する疾病
- じん肺及びじん肺合併症
労働災害の発生状況(令和3年)
- 労働災害の発生状況をみると、死亡者数は774人で減少傾向、休業4日以上の死傷者数は13.2万人と増加傾向にある。
- 過労死等に関連する労災認定数をみると、脳・心臓疾患は172人で減少傾向、精神障害等は629人で増加傾向にある。
▶108回午後33改題・101回午後13類問
令和3年(2021年)の労働災害と業務上疾病の発生状況について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 労働災害による死亡者数は2,000人以上である。
- 労働災害による死亡者数は平成27年(2015年)に比べ減少している。
- 労働災害の認定数は脳・心臓疾患よりも精神障害によるものが多い。
- 業務上疾病(休業4日以上)発生数は平成27年(2015年)に比べ減少している。
- 業務上疾病(休業4日以上)発生数の内訳では「作業様態に起因する疾病」が最も多い。
石綿による肺がん・中皮腫の労災保険支給決定件数
▶104回午前19改題
石綿による疾病に関する労災保険給付の支給決定件数で正しいのはどれか。
- 平成18年度(2006年度)がピークである。
- 平成22年度(2010年度)から令和3年度(2021年度)まで連続して増加している。
- 令和3年度(2021年度)では中皮腫より肺がんの方が多い。
- 令和3年度(2021年度)の肺がんに対する支給は1,000件を超えている。
労働安全衛生調査(実態調査)
仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項(令和3年)
▶108回午前26改題
令和3年(2021年)の労働安全衛生調査(実態調査)で、労働者の仕事や職業生活における強い不安、悩み、ストレスの内容に関して最も割合が高いのはどれか。
- 仕事の質
- 対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)
- 仕事の失敗、責任の発生等
- 会社の将来性
- 仕事の量
学校保健統計調査
第10編 4.学齢期の健康状況 p347~349
学校保健統計調査の概要
▶102回午前24
学校保健統計調査から得られるのはどれか。
- ぜん息の被患率
- 自殺した児童生徒数
- 救急車による搬送件数
- 不登校の状態にある児童生徒数
- 学校の管理下における突然死の件数
▶109回午前11
文部科学省が実施する学校保健統計調査で正しいのはどれか。
- 悉皆調査である。
- 毎年10月に行われる。
- 学校で実施する健康診断の結果に基づいている。
- 学校管理下で死亡した児童生徒数が集計されている。
児童・生徒の異常被患率(令和3年)
【幼稚園】
①むし歯(う歯)26.5%
②裸眼視力1.0未満の者24.8%
【小学校】
①むし歯(う歯)39.0%
②裸眼視力1.0未満の者36.9%
【中学校】
①裸眼視力1.0未満の者60.7%
②むし歯(う歯)30.4%
【高等学校】
①裸眼視力1.0未満の者70.8%
②むし歯(う歯)39.8%
- むし歯(う歯)の者の割合は全学校段階で減少傾向にあるが、裸眼視力1.0未満の者の割合は増加傾向にある。
▶110回午後22改題
令和3年(2021年)の学校保健統計調査における学校種別の主な疾病・異常被患率を以下に示す。
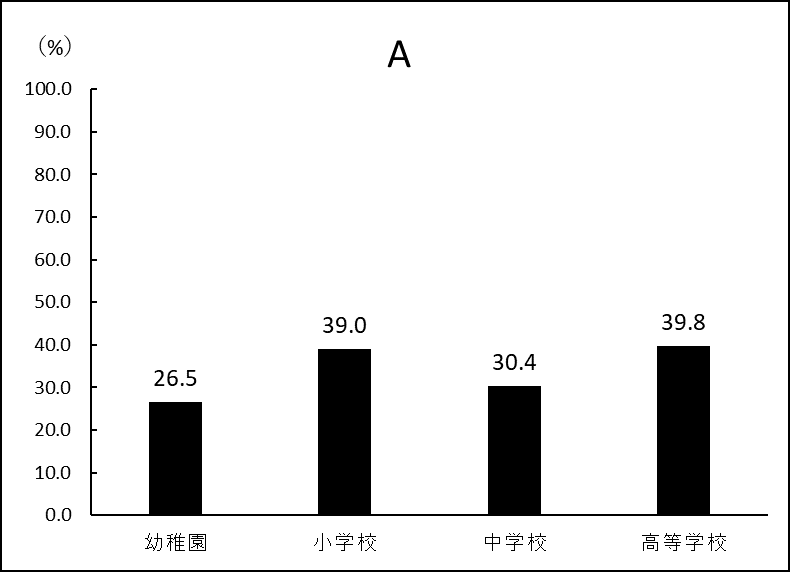

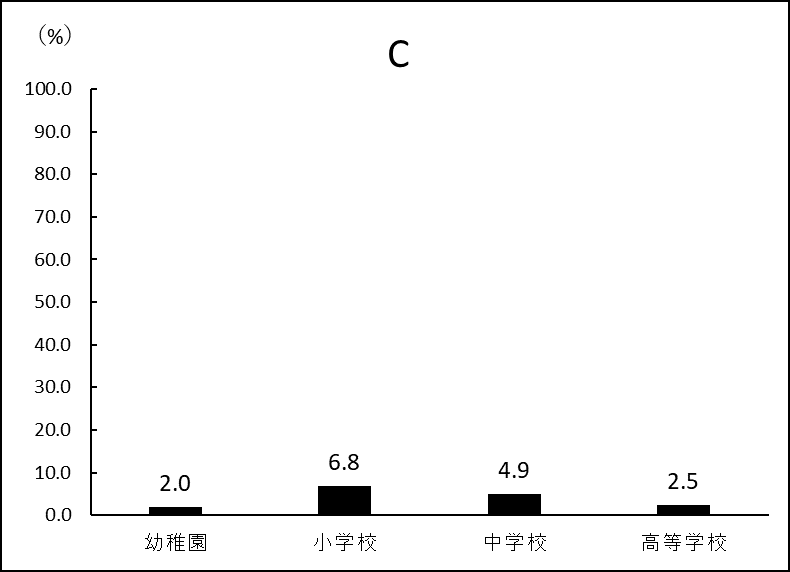
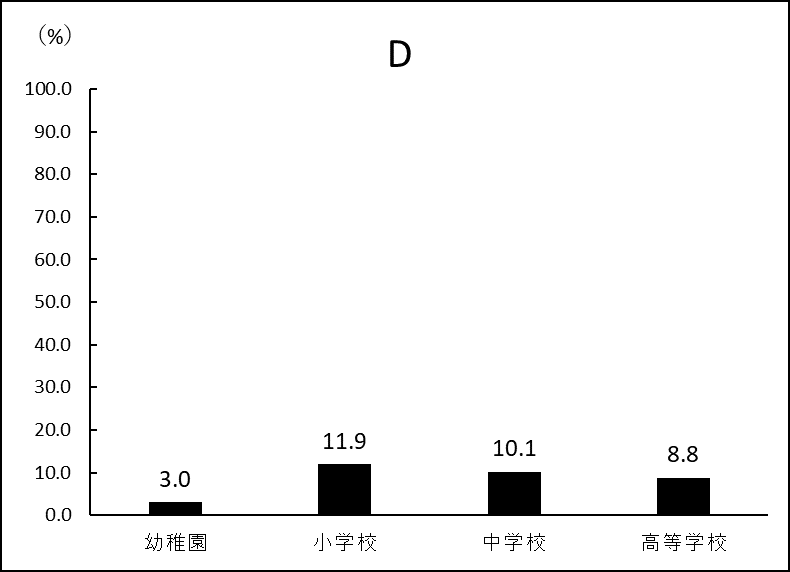
裸眼視力1.0未満の者を示したグラフはどれか。
- A
- B
- C
- D
▶108回午後29改題
令和3年度(2021年度)の学校保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 幼稚園児のむし歯(う歯)の保有率は15%程度である。
- 裸眼視力1.0未満の小学生は37%程度である。
- むし歯(う歯)を保有する小学生は前年度に比べて減少している。
- 中学生のむし歯(う歯)の保有率は45%程度である。
- 裸眼視力1.0未満の高校生は50%程度である。
▶105回午後31改題
令和3年度(2021年度)学校保健統計調査における主な疾病・異常等で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 肥満傾向児の出現率は、平成23年度(2011年度)以降男女ともに増加を続けている。
- 小学校における疾病・異常の被患率は、裸眼視力1.0未満の者が最も高い。
- むし歯(う歯)の者の割合は、全ての学校段階で前年度より減少している。
- ぜん息の者の年齢別の割合は、小学校で高い傾向がみられる。
- 心電図異常の割合は、高等学校より小学校の方が多い。
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
小学校・中学校におけるいじめ・不登校の状況(令和3年)
- いじめの認知件数をみると、小学校で50.1万件、中学校で9.8万件となっている。いじめの発見のきっかけは、小・中学校ともに「アンケート調査など学校の取組により発見」が最も高く、それぞれ57.8%、36.4%となっている。その内容は、小・中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が最も高く、それぞれ57.0%、62.2%となっている。
- 小・中学校の長期欠席のうち不登校の児童生徒数をみると、小学校で8.1万人(1.3%)、中学校で16.3万人(5.0%)となっている。不登校の主たる要因は、小・中学校ともに「無気力・不安」が最も高く、いずれも49.7%となっている。
▶108回午前16改題
令和3年度(2021年度)児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査で正しいのはどれか。
- 小学校における不登校児童数は約10万人である。
- いじめの発見のきっかけの第1位は「本人からの訴え」である。
- 中学校における不登校の主たる要因の第1位は「無気力・不安」である。
- 小学校におけるいじめの内容の第1位は「仲間はずれ、集団による無視をされる」である。
特別支援教育の状況
第10編 5.特別支援教育 p349~351
特別支援教育の状況(令和3年)
▶108回午前14改題
令和3年(2021年)の特別支援教育の状況で正しいのはどれか。
- 訪問教育を受けている児童生徒は小学生が最も多い。
- 特別支援学級の児童生徒の障害は知的障害が最も多い。
- 義務教育段階の児童生徒のうち特別支援学校に在籍している割合は全児童生徒の3%である。
- 特別支援教育が開始された平成19年(2007年)に比べて対象となる児童生徒数は減少している。
保健統計調査(複合問題)
▶104回午後34
保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国勢調査は5年に1度実施される。
- 患者調査から死因別死亡率が得られる。
- 人口動態調査は2年に1度集計される。
- 国民生活基礎調査は2年に1度実施される。
- 国民健康・栄養調査の調査項目に腹囲がある。
▶109回午前38
調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 患者調査は毎年実施される。
- 国勢調査で出生率が把握される。
- 社会生活基本調査は総務省が実施する。
- 人口動態調査は無作為抽出による標本調査である。
- 国民健康・栄養調査は健康増進法に基づいて実施される。
「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。
看護師国家試験では、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が毎年問われています。専門的な内容も多く、受験者の苦手とする分野でもありますが、覚えれば必ず解答できる部分でもあり、重要な得点源になります。
このページでは、看護師試験に頻出する法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、113回(2024年)から104回(2015年)までの10年分の試験の中から対応する法律問題をピックアップしています。
出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
法律別問題目次
第1編:衛生行政活動
- 地域保健法
- 災害対策基本法
第3編:保健対策・疾病対策
- 健康増進法
- 母子保健法
- 母体保護法
- 障害者総合支援法
- 精神保健福祉法
- 発達障害者支援法
- 自殺対策基本法
- がん対策基本法
- 難病法
- 臓器移植法
第4編:医療提供体制・医療保険制度
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 医療保険各法
第5編:社会保険・社会福祉
- 国民年金法等
- 生活保護法
- 社会福祉法
- 児童福祉法
- 児童虐待防止法
- DV防止法
- 男女雇用機会均等法
- 労働基準法
- 育児・介護休業法
- 老人福祉法
- 高齢者虐待防止法
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第6編:薬事
- 医薬品医療機器等法
- 麻薬及び向精神薬取締法
第7編~10編:食品・労働・環境・学校
- 食品衛生法・食品安全基本法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 環境基本法
- 学校保健安全法
地域保健法
第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24
保健所
地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
- 診療所
- 保健所
- 地域包括支援センター
- 訪問看護ステーション
保健所の設置主体で正しいのはどれか。
- 国
- 都道府県
- 社会福祉法人
- 独立行政法人
市町村保健センター
地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。
- 病気の治療
- 住民の健康診査
- 看護師免許申請の受理
- 専門的で広域的な健康課題への対応
災害対策基本法
第5編2章 6.2〕災害時の支援体制 p244
主な規定
災害対策基本法は災害対策の最も基本となる法律で、以下のような防災体制の整備が規定されている。
- 地域防災計画(都道府県・市町村)の作成
- 物資の備蓄
- 防災訓練義務
災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。
- 物資の備蓄
- 避難所の設置
- 災害障害見舞金の支給
- 救護班による医療の提供
健康増進法
第3編1章 2.1〕(5)健康増進法 p86~87
主な規定
- 国民健康・栄養調査
- 保健指導等
- 特定給食施設
- 受動喫煙防止
健康増進法に基づき実施されるのはどれか。
- 受療行動調査
- 特定保健指導
- アレルギー疾患対策
- 受動喫煙の防止対策
母子保健法
第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99
主な規定
母子保健法では以下の事項などを規定している。
- 妊産婦・乳幼児の健康診査
- 市町村への妊娠の届出
- 母子健康手帳の交付
- 未熟児に対する養育医療の給付
- 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置
養育医療が定められている法律はどれか。
- 児童福祉法
- 母子保健法
- 発達障害者支援法
- 児童虐待の防止等に関する法律
母子保健法に基づく届出はどれか。
- 婚姻届
- 死産届
- 死亡届
- 出生届
- 妊娠届
乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。
- 母子保健法
- 児童福祉法
- 次世代育成支援対策推進法
- 児童虐待の防止等に関する法律
産科外来を初めて受診した妊婦。夫婦ともに外国籍で、日本の在留資格を取得している。
この妊婦への説明で正しいのはどれか。
- 「母子健康手帳は有料で入手できます」
- 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」
- 「出生届は外務省に提出します」
- 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」
母子保健法に規定されているのはどれか。
- 母子健康包括支援センター
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 助産施設
- 特定妊婦
母体保護法
第3編2章 1.8〕(4)家族計画 p103
主な規定
母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に以下の事項を規定している。
- 不妊手術
- 人工妊娠中絶
- 受胎調節の実地指導
母体保護法で規定されているのはどれか。
- 育児時間
- 生理休暇
- 受胎調節の実地指導
- 育児中の深夜業の制限
人工妊娠中絶
母体保護法に定める人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を保続することのできない時期(通常妊娠満22週未満)に、人工的に母体外に排出することをいい、以下の者の実施が可能であるとしている。
- 妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者
- 暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した者
母体保護法で規定されているのはどれか。
- 産後の休業
- 妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限
- 妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止
- 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶
日本の人工妊娠中絶で正しいのはどれか。
- 配偶者の同意が必須である。
- 妊娠10週以降は死産の届出が必要である。
- 実施が可能なのは妊娠22週未満の場合である。
- 実施率は母の年齢が20~24歳よりも20歳未満の方が高い。
出生前診断について正しいのはどれか。
- 遺伝相談は勧めない。
- 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。
- 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。
- 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。
障害者総合支援法
第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111
地域移行支援
Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。
Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。
- 療養介護
- 施設入所支援
- 地域移行支援
- 自立訓練としての機能訓練
就労移行支援
- 障害者総合支援法では就労移行支援事業が設けられ、就労を希望し、一般雇用が可能な障害者に対して、一定期間就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行っている。
- 一般雇用が困難である者には、雇用契約に基づく就労継続支援A型、雇用契約に基づかない就労継続支援B型による支援が行われている。
一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。
- 就労移行支援
- 自立生活援助
- ピアサポート
- 就労継続支援A型
Aさん(40歳、男性)は、5年前に勤めていた会社が倒産し再就職ができず、うつ病になった。その後、治療を受けて回復してきたため、一般企業への再就職を希望している。
Aさんが就労を目指して利用できる社会資源はどれか。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 自立訓練〈生活訓練〉
共同生活援助〈グループホーム〉
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づいて、障害者が利用できるサービスはどれか。
- 育成医療
- 居宅療養管理指導
- 共同生活援助〈グループホーム〉
- 介護予防通所リハビリテーション
自立支援医療
- 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度である。
- 身体障害者には更生医療、身体障害児には育成医療、精神障害者には精神通院医療がなされている。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、精神障害者に適用されるのはどれか。
- 障害基礎年金
- 一定割合の雇用義務
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療〈精神通院医療〉
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
第3編2章 4.精神保健 p111~118
精神保健指定医
精神保健指定医を指定するのはどれか。
- 保健所長
- 都道府県知事
- 厚生労働大臣
- 精神保健福祉センター長
精神保健指定医について正しいのはどれか。
- 医療法で規定されている。
- 都道府県知事が指定する。
- 障害年金の支給判定を行う。
- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
精神障害者の入院形態
- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。
- 任意入院が行われる状態にない者については、その家族等の同意がある場合に、精神保健指定医1名の診察を要件に医療保護入院が行える。また、急速を要し、家族等の同意が得られない場合には、72時間以内の応急入院を行うことができる。
- 2人以上の指定医の診察を要件に、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者については措置入院を行うことができる。また、急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが72時間以内の緊急措置入院を行うことができる。
Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。
Aさんの入院形態はどれか。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
医療保護入院で正しいのはどれか。
- 入院の期間は72時間に限られる。
- 患者の家族等の同意で入院させることができる。
- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 応急入院は72時間以内に限られている。
- 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
- 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
- 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
- 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
精神医療審査会
精神医療審査会で審査を行うのはどれか。
- 精神保健指定医の認定
- 入院患者からの退院請求
- 退院後生活環境相談員の選任
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否
精神科病院に医療保護入院をしている患者から退院請求があった。入院継続の適否について判定するのはどれか。
- 保健所
- 地方裁判所
- 精神医療審査会
- 地方精神保健福祉審議会
精神科入院患者の制限事項
精神科入院患者で隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、以下の事項については制限できない。
- 信書(手紙)の発受
- 行政機関の職員や代理人である弁護士との電話・面会
- 患者からの退院請求、処遇改善請求
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
- 警察官
- 検察官
- 患者本人
- 精神保健福祉士
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。
- 家族との面会
- 患者からの信書の発信
- 患者からの退院の請求
- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
信書の発受に関する例外
精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。
当日の看護師の対応で適切なのはどれか。
- 患者に渡さず破棄する。
- 患者による開封に立ち会う。
- 開封せず患者の家族に転送する。
- 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。
- 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。
隔離時の遵守事項
精神保健指定医が必要と判断した12時間以上の患者の隔離を行うに当たっては以下のような遵守事項が定められている。
- 隔離室には患者一人のみ入室させること。
- 隔離を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載すること。
- 隔離期間中は注意深い臨床的観察や適切な治療を確保し、部屋の衛生の確保に配慮すること。
- 医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うこと。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。
- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。
- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。
- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。
- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。
精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 行動制限の理由を患者に説明する。
- 原則として2名以上のスタッフで対応する。
- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
- 精神保健指定医による診察は週1回とする。
- 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。
身体拘束時の遵守事項
- 身体的拘束は制限の程度が強く、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない。
- 実施する際は、患者に身体的拘束を行う理由を知らせるよう努めること、身体的拘束が漫然と行われることがないよう医師は頻回に診察を行うことなどに特に留意する。
精神科病棟における身体拘束時の看護で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1時間ごとに訪室する。
- 拘束の理由を説明する。
- 水分摂取は最小限にする。
- 患者の手紙の受け取りを制限する。
- 早期の解除を目指すための看護計画を立てる。
精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付される。
- 手帳の交付により所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引などが受けられる。
精神障害者保健福祉手帳の交付によって精神障害者に適用されるのはどれか。
- 行動援護の介護給付
- 所得税の障害者控除
- 自立支援医療(精神通院医療)
- グループホームで必要な日常生活上の援助
精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。
- 知的障害も交付対象である。
- 取得すると住民税の控除対象となる。
- 交付によって生活保護費の支給が開始される。
- 疾病によって障害が永続する人が対象である。
精神保健福祉センター
- 精神保健福祉センターは、地域精神保健業務を技術面から指導・援助する機関で、都道府県・指定都市に設置される。
- 同センターには精神保健福祉相談員を配置することとされ、精神障害者やその家族の相談に応じ、必要な指導・援助を行っている。
都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。
- ゲートキーパー
- ピアサポーター
- 精神保健福祉相談員
- 退院後生活環境相談員
現在の日本の精神医療で正しいのはどれか。
- 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。
- 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。
- 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。
- 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。
精神保健福祉士
Aさん(60歳、女性)は、統合失調症で10年間入院していた。来月退院予定となったため、Aさん、医師、看護師でチームを作り、退院支援計画を立てることになった。Aさんは「両親も亡くなってしまい、これからの生活費や住む場所がとても心配だ」と訴えてきた。
退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。
- 薬剤師
- 精神保健福祉士
- ピアサポーター
- 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師等)
精神保健福祉法改正の主な経緯・内容
近年の精神保健福祉法の改正内容は以下のとおりである。
●平成7年(1995年)
精神保健法から名称変更。精神障害者保健福祉手帳の創設。
●平成17年(2005年)
通院医療公費負担制度(1965年導入)を障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の成立に伴い新設された自立支援医療に一元化。
●平成25年(2013年)
障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていた保護者制度の廃止。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。
- 保護者制度の廃止
- 自立支援医療の新設
- 精神保健指定医制度の導入
- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更
精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律への改正で行われたのはどれか。
- 私宅監置の廃止
- 任意入院の新設
- 通院医療公費負担制度の導入
- 精神障害者保健福祉手帳制度の創設
発達障害者支援法
第3編2章 4.6〕(4)発達障害者支援 p115~116
発達障害の定義
発達障害者支援法で発達障害と定義されているのはどれか。
- 学習障害
- 記憶障害
- 適応障害
- 摂食障害
自殺対策基本法
第3編2章 6.自殺対策 p121~122
責務
- 自殺対策基本法に基づき、政府には自殺総合対策大綱の策定を、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。
- 国民に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるため、自殺予防週間(9月10日~16日)、自殺対策強化月間(3月)を設けている。
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
- 自殺総合対策推進センターの設置
- 自殺総合対策大綱の策定
- ゲートキーパーの養成
- 自殺対策計画の策定
自殺対策基本法について正しいのはどれか。
- 自殺対策強化月間を設けることを定めている。
- 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
- 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
- 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。
がん対策基本法
第3編4章 1.がん対策 p149~152
責務
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 受動喫煙のない職場を実現する。
- がんによる死亡者の減少を目標とする。
- 都道府県がん対策推進計画を策定する。
- がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
基本的施策
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
- 受動喫煙のない職場環境を整備する。
- 学校等でのがんに関する教育を推進する。
- がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
第3編4章 2.難病対策 p153~157
難病にかかる医療費の助成
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。
- 中皮腫
- C型肝炎
- 慢性腎不全
- 再生不良性貧血
責務
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
- 申請に基づく特定医療費の支給
- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
臓器の移植に関する法律
第3編4章 6.臓器移植・組織移植 p161~162
脳死判定
脳死とは脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、以下の5項目で判定される。
①深い昏睡
②瞳孔の散大と固定
③脳幹反射の消失
④平坦な脳波
⑤自発呼吸の停止
臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準に含まれるのはどれか。
- 低体温
- 心停止
- 平坦脳波
- 下顎呼吸
臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。
- 瞳孔径は左右とも3mm以上
- 脳波上徐波の出現
- 微弱な自発呼吸
- 脳幹反射の消失
- 浅昏睡
脳死の状態はどれか。
- 縮瞳がある。
- 脳波で徐波がみられる。
- 自発呼吸は停止している。
- 痛み刺激で逃避反応がある。
脳死臓器提供可能年齢
平成22年の改正臓器移植法施行により、本人の意思が不明な場合(拒否の意思がない場合)でも、家族(遺族)の書面による承諾により脳死判定および臓器摘出が可能となったことにより、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が認められることとなった。
臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。
- 1歳
- 6歳
- 15歳
- 20歳
- 年齢制限なし
医療法
第4編1章 1.医療法 p166
第4編1章 2.医療計画 p166~169
概要
医療法はわが国の医療提供体制の基本となる法律として以下の事項を定めている。
- 医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項
- 医療の安全を確保するために必要な事項
- 病院・診療所・助産所の開設と管理に関し必要な事項
- これらの施設の整備と医療提供施設相互間の機能の分担・業務の連携を推進するために必要な事項
医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。
- 医療法
- 医師法
- 健康保険法
- 保健師助産師看護師法
医療に関する選択の支援等
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。
- 医療法
- 健康保険法
- 地域保健法
- 個人情報の保護に関する法律
医療の安全の確保
病院等の管理者は医療に係る安全管理のため、以下の体制整備を実施する。
- 医療安全管理者や医薬品安全管理責任者の配置
- 指針の整備
- 医療安全委員会の設置
- 職員研修(年2回程度)の実施
医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
医療安全支援センター/医療事故調査・支援センター
- 医療安全支援センターは、医療の安全の確保のために都道府県・保健所設置市・特別区が設置するもので、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。
- 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査の支援、整理分析、普及啓発、研修事業などを実施するもので、医療事故等が発生した場合、病院等の管理者は遅滞なく同センターに報告することとなっている。
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- 医療安全支援センターを設置する。
- 医療安全管理者養成研修を実施する。
- 医療の安全を確保するための指針を策定する。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。
- 医療安全管理者の配置
- 厚生労働省へのインシデント報告
- 患者・家族への医療安全指導の実施
- 医療安全支援センターへの医療事故報告
病院・診療所
- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
- 診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)をいう。
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
- 9
- 19
- 29
- 39
特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院
- 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。
- 地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が承認する。
- 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
- 診療所
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
- 臨床研究中核病院
医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。
- 助産所
- 診療所
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 保健所
- 特定機能病院
- 地方衛生研究所
- 市町村保健センター
- 医療安全支援センター
病床種別
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
病床種別ごとの人員配置基準
看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
- 医療法
- 労働基準法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。
【 】に入るのはどれか。
- 2
- 3
- 4
- 6
病床種別ごとの構造設備基準
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。
- 3.4m2以上
- 4.4m2以上
- 5.4m2以上
- 6.4m2以上
5疾病6事業
医療法に定める医療計画には、医療提供体制の整備に重要な5疾病6事業が掲げられている。
●5疾病
「がん」「脳卒中」「心血管疾患」「糖尿病」「精神疾患」
●6事業
「救急医療」「災害医療」「新興感染症等の感染拡大時における医療(令和6年度から追加)」「へき地医療」「周産期医療」「小児医療」
令和3年(2021年)の医療法の改正によって、医療計画には①疾病・②事業及び在宅医療の医療体制に関する事項を定めることとされている。
①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。
①――②
- 4――4
- 4――5
- 5――5
- 5――6
- 6――6
災害医療について正しいのはどれか。
- 災害拠点病院は市町村が指定する。
- 医療計画の中に災害医療が含まれる。
- 防災訓練は災害救助法に規定されている。
- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。
医療計画
- 医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。
- 記載事項として、5疾病6事業のほか、在宅医療、地域医療構想に基づく病床の整備(基準病床数)、二次医療圏・三次医療圏の設定事項などが含まれる。
医療法における医療計画で正しいのはどれか。
- 国が策定する。
- 在宅医療が含まれる。
- 3年ごとに見直される。
- 病床の整備は含まれない。
医療計画について正しいのはどれか。
- 基準病床数を定める。
- 5年ごとに見直しを行う。
- 特定機能病院の基準を定める。
- 一次、二次および三次医療圏を設定する。
地域医療構想
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。
- 子育て世代包括支援センター
- 地域包括ケアシステム
- 子どもの医療費の助成
- 地域生活支援事業
- 地域医療構想
保健師助産師看護師法
第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197
看護師免許の付与
看護師免許を付与するのはどれか。
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 文部科学大臣
業務に従事する看護師の届出
業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。
( )に入る数字はどれか。
- 1
- 2
- 3
- 4
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 都道府県ナースセンターの長
看護師免許付与における相対的欠格事由
保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として以下を定め、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがあり、看護師が該当した場合は厚生労働大臣が免許の取消し等の処分をすることができる。
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 医事に関し犯罪または不正の行為のあった者
- 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者
- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者
看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
- 20歳未満の者
- 海外に居住している者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 伝染性の疾病にかかっている者
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
看護師の守秘義務
保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。
- 研究をする。
- 看護記録を保存する。
- 看護師自身の健康の保持増進を図る。
- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。
看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師の業務
- 看護師は傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする(保健師助産師看護師法5条)。
- 診療の補助の範囲は厚生労働省通知により解釈がなされ、静脈内注射などは医師の指示の下に行うことができる。
看護師の業務で正しいのはどれか。
- グリセリン浣腸液の処方
- 褥婦への療養上の世話
- 酸素吸入の流量の決定
- 血液検査の実施の決定
医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。
- 静脈内注射
- 診断書の交付
- 末梢静脈路の確保
- 人工呼吸器の設定の変更
看護師の特定行為
- 保健師助産師看護師法に定める特定行為は、看護師が医師または歯科医師の作成する手順書により行う診療の補助で、38行為が規定されている。
- 平成27年(2015年)から特定行為に係る看護師の研修制度が開始し、厚生労働大臣が特定行為研修を行う研修機関を指定している。
看護師の特定行為で正しいのはどれか。
- 診療の補助である。
- 医師法に基づいている。
- 手順書は看護師が作成する。
- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。
特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。
- 特定行為は診療の補助行為である。
- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。
- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197
看護師等の確保のための関係者の責務
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
- 医療法
- 労働契約法
- 教育基本法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
- 人員配置基準に基づき看護師を配置する。
- 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
- 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
- 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
都道府県ナースセンターの実施事業
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
- 訪問看護業務
- 看護師免許証の交付
- 訪問入浴サービスの提供
- 看護師等への無料の職業紹介
看護師の復職支援
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。
- 看護師等免許保持者の届出
- 特定行為に係る研修
- 教育訓練給付金
- 業務従事者届
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
- 届出は義務である。
- 届出先は保健所である。
- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
医療保険各法
第4編2章 1.医療保険制度 p208~209
国民皆保険
わが国はすべての国民が、①被用者保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度のいずれかの医療保険に加入することとしている(国民皆保険制度)。
日本において国民皆保険制度となっているのはどれか。
- 医療保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
医療給付内容
- 医療の給付は保健医療機関(病院、診療所等)が行い、医療保険の種類に関わらず医療給付の内容は同じである。
- その内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。
健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
- 手術
- 健康診査
- 予防接種
- 人間ドック
被用者保険(職域保険)
- 被用者保険の被保険者は、会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の者である。
- 保険者により全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険(組合健保)、船員保険、共済組合(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員)がある。
日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 年金保険
- 雇用保険
- 船員保険
- 組合管掌健康保険
- 労働者災害補償保険
国民健康保険
- 国民健康保険の被保険者は被用者保険の加入者(被保険者とその家族)でも後期高齢者医療の被保険者(原則75歳以上の者)でもない者である。
- 保険者は都道府県・市町村・国民健康保険組合である。
国民健康保険の保険者はどれか。2つ選べ。
- 国
- 都道府県
- 市町村
- 健康保険組合
国民健康保険で正しいのはどれか。
- 被用者保険である。
- 保険者は国である。
- 高額療養費制度がある。
- 保険料は加入者の年齢で算出する。
後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度(2008年度)に開始した。
- 被保険者は原則75歳以上の後期高齢者である。
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- 介護保険法
- 老人福祉法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉
後期高齢者医療制度の被保険者は、区域内に住居を有する( )歳以上の者、および65歳以上( )歳未満であって、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
( )に入るのはどれか。
- 70
- 75
- 80
- 85
医療費の自己負担
国民健康保険に加入している自営業者(40歳)の医療費の一部負担金の割合はどれか。
- 1割
- 2割
- 3割
- 4割
高齢者の医療の確保に関する法律の内容で正しいのはどれか。
- 医療の給付は市町村が行う。
- 高齢者は一律3割の医療費を自己負担する。
- 40歳以上の被保険者と被扶養者にがん検診を行う。
- 後期高齢者の医療給付の内容は国民健康保険と同じである。
医療保険について正しいのはどれか。
- 医療給付には一部負担がある。
- 高額療養費の受給には年齢制限がある。
- 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。
- 後期高齢者医療における公費負担は8割である。
日本の医療保険制度について正しいのはどれか。
- 健康診断は医療保険が適用される。
- 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。
- 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。
- 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。
国民年金法・厚生年金保険法
第5編2章 1.公的年金 p234~235
公的年金の特徴
わが国の公的年金の特徴として、以下のような特徴が挙げられる。
- 加入者が保険料を拠出し、年金給付を受ける社会保険方式。
- 20歳以上60歳未満の国民すべてが国民年金に加入する国民皆年金。
- 現在の現役世代が負担した保険料を原資に、現在の高齢世代が年金給付を受ける賦課方式。
公的年金制度について正しいのはどれか。
- 学生は申請によって納付が免除される。
- 生活保護を受けると支給が停止される。
- 保険料が主要財源である。
- 任意加入である。
- 積立方式である。
生活保護法
第5編2章 2.生活保護 p235
生活保護法による8扶助
生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。
( )に入る数字はどれか。
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
- 医療扶助――医療にかかる費用
- 教育扶助――高等学校以上の教育にかかる費用
- 住宅扶助――住宅の購入にかかる費用
- 出産扶助――新生児の育児用品にかかる費用
生活保護の決定
生活保護法に基づき保護を決定するのはどれか。
- 保健センター
- 福祉事務所
- 保健所
- 病院
社会福祉法
第5編2章 6.地域福祉 p243~245
社会福祉協議会
社会福祉法に基づき社会福祉協議会が推進するのはどれか。
- がん対策
- 男女共同参画
- 就労の支援活動
- ボランティア活動
児童福祉法
第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239
児童相談所
- 児童相談所は各都道府県・指定都市に設置が義務づけられており、児童福祉司などの専門職員を配置し、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行う。
- 調査等に基づいて、児童相談所長または都道府県知事の決定に基づく児童の一時保護などの措置を行っている。
ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。
- 家庭裁判所長
- 児童相談所長
- 保健所長
- 警察署長
- 市町村長
児童相談所について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国が設置する。
- 児童福祉司が配置されている。
- 母親を一時保護する機能を持つ。
- 知的障害に関する相談を受ける。
- 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。
児童相談所の業務はどれか。2つ選べ。
- 児童の一時保護
- 自立支援給付の決定
- 不登校に関する相談
- 身体障害者手帳の交付
- 放課後児童健全育成事業の実施
小児慢性特定疾病医療費の支給
小児慢性特定疾病対策における医療費助成で正しいのはどれか。
- 対象は5疾患群である。
- 対象年齢は20歳未満である。
- 医療費の自己負担分の一部を助成する。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。
養育支援訪問事業
母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。
- 育成医療――結核児童
- 養育医療――学齢児童
- 健全母性育成事業――高齢妊婦
- 養育支援訪問事業――特定妊婦
児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉
第5編2章 3.4〕児童虐待防止対策 p237~238
概要
- 児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、福祉事務所もしくは児童相談所への通告義務を課している。
- 児童虐待は、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待と定義されている。このうち最も相談件数の多い心理的虐待については、児童に対する著しい暴言や拒絶的な対応のほか、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力など、児童に著しい心理的外傷を与える言動と定義している。
児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づいて行う通告で正しいのはどれか。
- 警察に通告する。
- 守秘義務の遵守が優先される。
- 通告にあたっては児童自身の意思を尊重することが規定されている。
- 児童が同居している家庭における配偶者に対する暴力は通告の対象となる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
第5編2章 3.5〕配偶者からの暴力の防止対策 p238
配偶者暴力相談支援センターと裁判所の役割
- DV防止法に基づき、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない。
- 通報を受けた配偶者暴力相談支援センターは、婦人相談員による相談や自立支援、一時保護などを行う。加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令は裁判所が行う。
配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。
- 一時保護
- 就労の仲介
- 外傷の治療
- 生活資金の給付
Aさん(38歳、女性、パート勤務)は、腹痛のため、姉に付き添われて救急外来を受診した。診察時、身体には殴られてできたとみられる複数の打撲痕が確認された。腹痛の原因は夫から蹴られたことであった。Aさんは「家に帰るのが怖い。姉には夫の暴力について話したくない」と泣いている。
外来での看護師の対応で適切なのはどれか。
- 打撲痕を姉に見てもらう。
- 配偶者暴力相談支援センターに通報する。
- 暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。
- Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。
- 離婚調停の支援
- 成年後見制度の利用
- 保健所による自立支援
- 婦人相談員による相談
- 裁判所による接近禁止命令
配偶者・暴力の定義
- DV防止法に規定する配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。
- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について正しいのはどれか。
- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。
- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。
- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。
- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉で正しいのはどれか。
- 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。
- 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。
- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
- 母子健康センターは被害者の保護をする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239
妊婦健康診査を受診する時間の確保
- 男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。
- その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。
妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
- 母子保健法
- 労働基準法
- 育児介護休業法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
正常に経過している妊娠26週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。
- 4週後
- 3週後
- 2週後
- 1週後
正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。
- 4週後
- 3週後
- 2週後
- 1週後
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。
- 生理日の就業制限
- 産後6週間の就業禁止
- 妊産婦の時間外労働の禁止
- 妊婦健康診査の受診時間の確保
労働基準法
第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239
妊産婦等の就業に関する規定
- 労働基準法の規定により、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間(産後6週間経過後の女性の請求による就業は可)を経過しない女性を就業させてはならない(産前産後休業)。
- 妊産婦等の危険有害業務の就業禁止のほか、女性の請求による妊産婦等の軽易業務転換、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、育児時間なども規定している。
労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- 妊娠の届出
- 妊婦の保健指導
- 産前産後の休業
- 配偶者の育児休業
- 妊産婦の時間外労働の制限
就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。
- 時差出勤――母子保健法
- 産前産後の休業――児童福祉法
- 軽易業務への転換――母体保護法
- 危険有害業務の制限――労働基準法
育児時間
法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。
- 請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。
- 父親と母親の両方が取得できる。
- 1日に2回請求できる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
第5編2章 3.6〕妊産婦等の就業 p238~239
育児に関する規定
育児・介護休業法には育児に関して以下のような規定がある。
- 子どもが1歳になるまでの育児休業。
- 3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮。
- 小学校就学前までの子を養育する労働者の請求による看護休暇の取得や時間外労働の制限。
Aさん(28歳、女性)は、2歳の子どもを養育しながら働いている。
Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。
- 児童福祉法
- 労働基準法
- 男女共同参画社会基本法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。
- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限
老人福祉法
第5編2章 5.高齢者福祉等 p241~243
老人福祉計画
老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。
- 国
- 市町村
- 都道府県
- 福祉事務所
- 後期高齢者医療広域連合
老人デイサービスセンター
老人福祉法と介護保険法のいずれにも位置付けられている施設はどれか。
- 介護医療院
- 介護老人保健施設
- 老人福祉センター
- 老人デイサービスセンター
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉
第5編2章 5.2〕高齢者虐待防止対策 p241~242
概要
- 高齢者虐待に関する防止、保護、支援については、市町村(特別区を含む)が第一義的に責任を持つ。
- 高齢者を保護・分離する手段として、居宅サービスの措置、養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置などを講じることが規定されている。
養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉に基づき通報する先として正しいのはどれか。
- 市町村
- 警察署
- 消防署
- 訪問看護事業所
高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
- 有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 高齢者生活福祉センター
- サービス付き高齢者向け住宅
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第5編2章 5.4〕高齢者の就労支援 p242
シルバー人材センター事業
退職した高齢者に就労機会を提供するのはどれか。
- シルバー人材センター
- 老人福祉センター
- 老人クラブ
- 自治会
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉
第6編1章 4.医薬品等の承認・許可制度 p249~250
毒薬・劇薬
毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
- 薬剤師法
- 毒物及び劇物取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉
毒薬の表示
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。
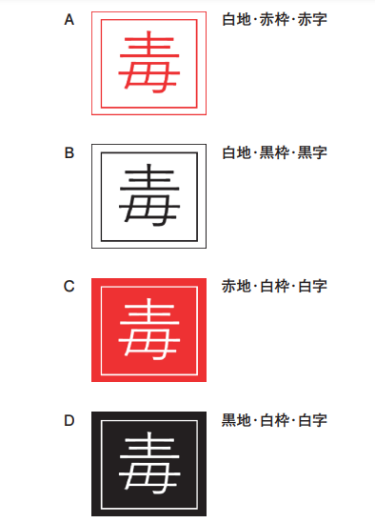
正しいのはどれか。
- A
- B
- C
- D
劇薬の表示
医薬品表示を別に示す。

劇薬の表示で正しいのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
麻薬及び向精神薬取締法
第6編3章 2.麻薬・覚醒剤等 p269~271
麻薬の保管等の規定
他の医薬品と区別して貯蔵し、鍵をかけた堅固な設備内に保管することが法律で定められているのはどれか。
- ヘパリン
- インスリン
- リドカイン
- フェンタニル
麻薬を扱う者
麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。
- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。
- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。
- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。
- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。
食品衛生法・食品安全基本法
第7編2章 1.食品安全行政の概要 p278~279
概要
- 食品衛生法は、食品等の事業者の責務や規格・基準、監視指導などを規定している。
- 食品安全基本法は、リスク分析(評価・管理・コミュニケーション)により食品安全の確保を図るもので、リスク評価は内閣府に設置された食品安全委員会が担当する。
食品衛生法に定められていないのはどれか。
- 残留農薬の規制
- 食品添加物の規制
- 食品安全委員会の設置
- ポジティブリスト制度の導入
労働基準法
第8編 9.1〕過重労働による健康障害防止対策 p308
労働時間
休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。
- 30時間
- 35時間
- 40時間
- 45時間
労働安全衛生法
第8編 3.労働衛生管理の基本 p300~301
労働衛生の3管理
- 労働安全衛生法では、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理の労働衛生の3管理を整備している。
- 健康管理については健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導を規定している。
職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。
- 労働組合法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働関係調整法
労働衛生の「3管理」とは、作業環境管理と作業管理と( )である。
( )に入るのはどれか。
- 健康管理
- 総括管理
- 労務管理
- 出退勤管理
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 失業手当の給付
- 労働者に対する健康診断の実施
- 労働者に対する労働条件の明示
- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
ストレスチェック制度
職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。
- 1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。
- 8時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。
- 生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。
- 妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。
労働者災害補償保険法
第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308
概要
- 労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。
- 保険者は政府(国)であり、事業に要する費用は原則として事業主が負担する保険料で賄われる。
労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 通勤災害時の療養給付
- 失業時の教育訓練給付金
- 災害発生時の超過勤務手当
- 有害業務従事者の健康診断
- 業務上の事故による介護補償給付
労働者災害補償保険法に規定されている保険者はどれか。
- 国
- 事業主
- 市町村
- 都道府県
- 健康保険組合
雇用保険法
第8編 9.9〕雇用保険制度 p310
雇用保険制度
- 雇用保険制度は政府が管掌する労働保険で、失業等給付や育児休業給付の支給などを行う。
- 労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、保険料は労働者と事業主双方が負担する。
雇用保険法について正しいのはどれか。
- 育児休業給付がある。
- 雇用保険は任意加入である。
- 雇用保険の保険者は市町村である。
- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。
環境基本法
第9編2章 1.大気汚染対策の動向 p320~324
第9編2章 3.騒音・振動・悪臭対策の動向 p327~329
大気汚染に係る環境基準
- 環境基本法に基づき、大気汚染物質に対して大気汚染に係る環境基準が設定されている。
- そのうち、微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも特に粒径が小さい有害大気汚染物質で、呼吸器や循環器への影響が懸念される。
大気汚染物質はどれか。
- フロン
- カドミウム
- メチル水銀
- 微小粒子状物質(PM2.5)
騒音についての環境基準
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。
- 20dB以下
- 50dB以下
- 80dB以下
- 110dB以下
学校保健安全法
第10編 1.学校保健行政の動向 p341~344
主な規定
- 設置が義務づけられている学校医は、健康相談や保健指導、健康診断、疾病・感染症・食中毒予防処置などに従事する。
- 就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。
- 校長は感染症にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を停止させることができる。
学校保健について正しいのはどれか。
- 学校医は健康相談を実施する。
- 校長は学校医を置くことができる。
- 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。
- 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。
複合法律問題
公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。
- 未熟児の養育医療――医療法
- 結核児童の療養給付――児童福祉法
- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。
- 児童福祉法――受胎調節の実地指導
- 地域保健法――市町村保健センターの設置
- 健康増進法――医療安全支援センターの設置
- 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理
出産や育児に関する社会資源と法律の組合せで正しいのはどれか。
- 入院助産――児童福祉法
- 出産扶助――母体保護法
- 出産手当金――母子保健法
- 養育医療――児童手当法
精神保健医療福祉に関する法律について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。
- 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。
- 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。
- 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。
- 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。
健康に影響を及ぼす生活環境とそれを規定している法律の組合せで正しいのはどれか。
- 上水道水質――汚濁防止法
- 飲食店――食品衛生法
- 家庭ごみ――悪臭防止法
- 学校環境――教育基本法
- 住宅用の建築材料――環境基本法
社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。
- 医療保険――健康保険法
- 介護保険――高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉
- 雇用保険――社会福祉法
- 年金保険――生活困窮者自立支援法
次の法律のうち最も新しく制定されたのはどれか。
- 未成年者喫煙禁止法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- アルコール健康障害対策基本法
- ギャンブル等依存症対策基本法
施行日が最も新しい法律はどれか。
- 高齢社会対策基本法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉
子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。
- 児童憲章の宣言
- 児童福祉法の公布
- 母子保健法の公布
- 児童の権利に関する条約の日本の批准
近年成立の法律・制度
法律や制度は社会情勢の変化に合わせて成立、改正、廃止が行われるため、看護師国家試験においては、過去問題だけを解いていても対応できない新規の内容の問題が出てくることは頻繁にあります。
「国民衛生の動向」では毎年、最新の制度改正を反映した情報に更新しているため、法律・制度の総チェックが可能です。
以下に看護師国家試験で頻出テーマであり、近年法改正等がなされた事項について列記します。詳しくは「国民衛生の動向」を確認しながら、過去問題と合わせて予想問題対策としてお使いください。
令和6年(2024年)
4月
- 「21世紀における第三次国民健康づくり運動」〈健康日本21(第三次)〉が開始(令和17年度まで)。「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の4つを基本的方向として掲げる。
- 医療計画の5疾病5事業に6事業目として「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加。
- 医療法等の改正による医師の働き方改革の適用開始。時間外労働の上限規制を定め、医師の健康確保措置(面接指導、連続勤務時間制限等)や医師の労働時間短縮計画の作成などの措置を講じる。また、業務の移管や共同化(タスク・シフティング/タスク・シェアリング)を推進する。
令和5年(2023年)
5月
- 新型コロナウイルス感染症を感染症法の5類感染症に位置づけ変更。また、学校において予防すべき感染症として第二種に位置づけ。
4月
- 9価HPVワクチンによる定期接種の開始。
令和4年(2022年)
12月
- 地域保健法改正により地方衛生研究所等の体制整備が法定化された。地方衛生研究所は、公衆衛生の向上と増進を図るための科学的・技術的中核として都道府県・指定都市が設置するもので、これまで地方衛生研究所設置要綱等に基づいて設置されている。
- 障害者総合支援法の一部改正。①就労アセスメントの手法を活用した「就労選択支援」の創設、②基幹相談支援センターおよび地域生活支援拠点等の整備を市町村に努力義務化など。
- 精神保健福祉法改正。①医療保護入院の見直し(家族等の同意・不同意の意思表示を行わない場合にも市町村長の同意により行うことを可能とすること、入院期間を設定して一定期間ごとに入院の要否を確認すること)、②入院者訪問支援事業の創設(入院訪問支援者が患者本人の希望により精神科病院を訪問してサポートを行うもの)など。
- 難病法改正。難病患者に対する医療費助成の開始時期を、申請日から重症化したと診断された日に前倒しするなど。
11月
- 健康日本21(第二次)最終評価報告書公表。目標値に達した項目は健康寿命や血糖コントロール不良者の減少など、悪化していると評価された項目はメタボリックシンドローム該当者・予備軍の数や適正体重の子どもの増加など。
10月
- 自殺総合対策大綱の閣議決定。「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」「女性に対する支援の強化」「地域自殺対策の取組強化」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など」を追加。
- 後期高齢者医療制度における窓口負担割合について、原則1割、現役並み所得者3割に加えて、一定以上の所得がある者を2割とする。
- 「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得。
4月
- 不妊治療の保険適用化。一般不妊治療における「人工授精」、生殖補助医療における「体外受精」「顕微授精」など保険適用。
令和3年(2021年)
6月
- 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」成立。医療的ケア児とは日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童をいう。
4月
- 改正母子保健法の施行により、市町村に産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子と乳児に対する産後ケア事業の実施を努力義務化。
- 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。
2月
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正。「まん延防止等重点措置」が創設され、従来の「緊急事態宣言」と合わせ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い順次適用された。
令和2年(2020年)
10月
- ロタウイルス感染症の予防接種の定期接種化。
4月
- 改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙。
- 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」使用開始。成人のナトリウム(食塩相当量)の目標量引き下げ(男7.5g/日未満・女6.5g/日未満)など。
令和元年(2019年)
12月
- 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(循環器病対策基本法)施行。政府は循環器病対策基本計画を策定し、循環器病対策を推進する。
- 「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)施行。政府は基本的な方針を策定し、関連施策を推進する。
「国民衛生の動向」は、昭和24年の創刊以来、時代の変化に合わせて、わが国の衛生を取り巻く最新の状況を網羅する本として幅広く利用されています。
かつては、結核をはじめとした感染症対策がその記述の中心でしたが、近年では感染症を軸とした対策から、生活習慣の改善による発症予防(一次予防)を推進する生活習慣病対策に重点が置かれてきていました。
しかし、2020年以降、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、医療機関や保健所だけでなく、介護施設や飲食店、学校、家庭などでも感染症対策の重要性が再認識されたところです。こうした中で、看護師国家試験では、これまで同様、もしくはこれまで以上に感染症を問う問題が出題されると考えられます。
当ページでは、113回(2024年)から104回(2015年)の10年分の試験問題の中から感染症に関わる問題をピックアップし、簡易的な説明とともに示します。問題を解きながら、「国民衛生の動向」第3編3章の感染症対策の記述を参考に、感染症法の規定、各感染症の特徴、医療機関における予防策など、総合的に把握することが大切です。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
感染症問題目次
- 結核
- ウイルス性肝炎
- マラリア
- エイズ/HIV
- 風疹・麻疹
- 性感染症
- その他の感染症
- 院内感染対策
- 身体の免疫機能
- 世界保健機関(WHO)
- 学校における感染症予防
感染症法
感染症法による分類
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉では、対象とする感染症の感染力や罹患した場合の症状の重篤性などに基づいて以下のように分類している。
【対象感染症の一例】
- 1類感染症:エボラ出血熱、ペスト
- 2類感染症:結核、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉
- 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症
- 4類感染症:A型肝炎、E型肝炎、マラリア
- 5類感染症:後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、麻疹、風疹、細菌性髄膜炎、水痘
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。
- 一類
- 二類
- 三類
- 四類
- 五類
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。
- 一類感染症
- 二類感染症
- 三類感染症
- 四類感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく五類感染症はどれか。2つ選べ。
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
- 腸管出血性大腸菌感染症
- つつが虫病
- 日本脳炎
- 梅毒
感染症法に基づく届出基準
- 1~4類感染症と、5類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風疹および麻疹)、新型インフルエンザ等感染症を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
- 5類感染症のうち麻疹等を除く全数把握対象疾患については7日以内に届け出なければならない。
感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。
- 結核――診断後7日以内
- 梅毒――診断後直ちに
- E型肝炎――診断後直ちに
- 腸管出血性大腸菌感染症――診断後7日以内
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉――診断後直ちに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
- インフルエンザ
- 細菌性髄膜炎
- 水痘
- 梅毒
結核
結核
- 結核(2類感染症)は、結核菌によって空気感染し、主に肺結核を引き起こすわが国の主要な感染症の一つで、咳、痰、呼吸困難などの症状を呈する。
- 結核菌に感染後、すぐに発病する一次結核と、長期にわたり体内に潜伏したのち再び活動を開始して発症する二次結核がある。
- 結核菌の消毒にはエタノールが有効である。
感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。
- インフルエンザ
- 結核
- ノロウイルス性胃腸炎
- 流行性耳下腺炎
肺結核について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 結核の10%程度である。
- 感染経路は接触感染である。
- 肺アスペルギルス症と同じ原因菌である。
- 二次性の発症は過去の感染の再活性化による。
- DOTS〈Directly Observed Treatment, Short-course〉が推奨される。
結核患者・死亡数の推移
令和4年(2022年)の日本の結核対策で増加が問題とされているのはどれか。
- 新登録結核患者数
- 菌喀痰塗抹陽性の肺結核患者数
- 外国生まれの新登録結核患者の割合
- 結核による死亡数
BCGワクチン
- BCGは結核を予防するワクチンで、予防接種法に基づき生後1歳に至るまで(標準的な接種は生後5~8か月)の間に定期接種を行う。
- 接種後5~6週間頃に針の痕に一致して発赤や膿がみられることがあるが、正常な反応とされる。ただし、接種から約10日以内にこうした反応が生じた場合は、すでに結核菌に感染しているおそれもあり、速やかに医療機関に相談・受診する必要がある。
発育と発達に遅れのない生後6か月の男児。BCG接種の翌日に接種部位が赤く腫れ次第に増悪して膿がみられたため、母親は接種後4日目に医療機関に電話で相談し、看護師が対応した。児に発熱はなく、哺乳や機嫌は良好である。
このときの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「通常の反応です」
- 「速やかに来院してください」
- 「1週間後にまた電話をください」
- 「患部をアルコール消毒してください」
ウイルス性肝炎
A型肝炎
- A型肝炎(4類感染症)は、A型肝炎ウイルス(HAV)の感染による肝疾患で、主な感染経路は汚染された食品や水などを介した経口感染である。
- 感染後まれに劇症化することがあり、B型肝炎やC型肝炎とは異なり慢性化することはない。
経口感染するウイルス性肝炎はどれか。
- A型肝炎
- B型肝炎
- C型肝炎
- D型肝炎
Aさん(42歳、女性)は、3日前から微熱と強い全身倦怠感を自覚したため病院を受診したところ、肝機能障害が認められ、急性肝炎の診断で入院した。1か月前に生の牡蠣を摂取している。Aさんはこれまで肝臓に異常を指摘されたことはなく、家族で肝臓疾患を罹患した者はいない。
Aさんが罹患した肝炎について正しいのはどれか。
- 細菌感染である。
- 劇症化する危険性がある。
- 慢性肝炎に移行しやすい。
- インターフェロン療法を行う。
B型肝炎
- B型肝炎(5類感染症)は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染による肝疾患である。HBVはDNAウイルスで、RNAウイルスである他の肝炎ウイルスとは異なる。
- 主な感染経路として血液感染(医療現場での針刺し事故等)、母子感染(垂直感染)、性行為感染がある。
- B型肝炎に対するワクチンがあり、定期予防接種の対象となっている。
ウイルス性肝炎の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。
- A型肝炎ウイルス
- B型肝炎ウイルス
- C型肝炎ウイルス
- E型肝炎ウイルス
針刺し事故によって感染するのはどれか。
- RSウイルス
- B型肝炎ウイルス
- ヘルペスウイルス
- サイトメガロウイルス
C型肝炎
- C型肝炎(5類感染症)は、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染による肝疾患で、主な感染経路は血液感染である。
- 感染後、多くは自覚症状が現れず慢性化し、肝硬変や肝がんに進行する場合がある。
- 治療としては主にインターフェロン治療がとられる。
C型慢性肝炎に使用するのはどれか。
- ドパミン
- インスリン
- リドカイン
- インターフェロン
マラリア
マラリア
- マラリア(4類感染症)は熱帯・亜熱帯地域に広く分布する感染症で、ハマダラカ(蚊)によって媒介される。最も多い症状は発熱と悪寒で、熱発は間隔をあけて発熱期と無熱期を繰り返す。
- その感染力や対策費用の負担の大きさから、「HIV/エイズ」「結核」と並び三大感染症ともいわれる。
令和4年(2022年)時点での世界の三大感染症に入るのはどれか。
- ポリオ〈急性灰白髄炎〉
- マラリア
- 天然痘
- 麻疹
Aさん(28歳、男性)。海外出張で訪れたアフリカ地域から帰国後1週に39℃の発熱と解熱を繰り返すため外来を受診した。腹部症状は特にない。
予測される感染症はどれか。
- マラリア
- コレラ
- 赤痢
- 破傷風
エイズ/HIV
エイズ/HIV
- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉は、免疫システムである白血球中のヘルパー〈CD4陽性〉Tリンパ球に感染し、増殖、破壊することで、免疫不全状態を引き起こす。
- HIV感染後、多くは無症候性キャリアの状態で10年程度経過した後に症状が現れ、ニューモシスチス肺炎(カリニ肺炎)などの指標疾患を発症するとエイズ(5類感染症)と診断される。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染している患者で、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の状態にあると判断できる疾患はどれか。
- 季節性インフルエンザ
- ニューモシスチス肺炎
- ノロウイルス性腸炎
- 単純性膀胱炎
HIVの感染経路
- HIVの主な感染経路は、①HIV感染者との性行為、②血液または血液製剤の輸注、③母子感染(垂直感染)の3つである。
- 性行為による感染対策としてはコンドームの使用、母子感染対策としては妊婦の感染の早期発見と抗HIV薬等による適切な対策が効果的である。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉の感染経路で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 感染者の嘔吐物との接触
- 感染者の咳による曝露
- 感染者の糞便との接触
- 感染者からの輸血
- 感染者との性行為
母体から胎児への感染はどれか。
- 水平感染
- 垂直感染
- 接触感染
- 飛沫感染
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症で正しいのはどれか。
- 空気感染する。
- 無症候期がある。
- DNAウイルスによる。
- 血液中のBリンパ球に感染する。
血液曝露事故によるHIV感染率
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に汚染された注射針による針刺し事故の感染率で正しいのはどれか。
- 40%
- 10%
- 2%
- 0.3%
HIVの感染者への指導
学習支援として、集団指導よりも個別指導が望ましいのはどれか。
- 小学生へのインフルエンザ予防の指導
- 塩分摂取量が多い地域住民への食事指導
- ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染者への生活指導
- 3〜4か月児健康診査に来た保護者への離乳食の指導
HIV感染者の動向
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 本人より先に家族に病名を告知する。
- 国内では異性間性的接触による感染が最も多い。
- 適切な対応によって母子感染率を下げることができる。
- 性行為の際には必ずコンドームを使用するよう指導する。
- HIVに感染していれば後天性免疫不全症候群〈AIDS〉と診断できる。
ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症について正しいのはどれか。
- 令和4年(2022年)の新規感染者数は10年前に比べ増加している。
- 日本では異性間の性的接触による感染が最も多い。
- 早期に発見して治療を開始すれば完治する。
- 保健所でのHIV検査は匿名で受けられる。
世界の地域別HIV感染者数
令和4年(2022年)の国連エイズ合同計画〈UNAIDS〉の報告において、ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉陽性者が最も多い地域はどれか。
- 東欧・中央アジア
- 西欧・中欧・北アメリカ
- アジア太平洋
- 東部・南部アフリカ
風疹・麻疹
風疹
- 風疹(5類感染症)は、発熱や発疹、リンパ節腫脹を特徴とする感染性疾患で、風疹ウイルスの飛沫感染により生じる。
- 妊婦が妊娠20週ごろまでに感染すると、白内障や先天性心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の児が生まれる可能性がある。
風疹の疑いがある入院患者の隔離予防策で適切なのはどれか。
- 標準予防策
- 標準予防策と接触感染予防策
- 標準予防策と飛沫感染予防策
- 標準予防策と空気感染予防策
妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。
- 水痘
- 風疹
- 麻疹
- 流行性耳下腺炎
妊娠中の母体の要因が胎児に及ぼす影響について正しいのはどれか。
- 飲酒の習慣による巨大児
- 喫煙による神経管形成障害
- 妊娠初期の風疹の罹患による先天性心疾患
- ビタミンAの過剰摂取による低出生体重児
妊婦の感染症と児への影響の組合せで正しいのはどれか。
- 風疹――白内障
- 性器ヘルペス――聴力障害
- トキソプラズマ症――先天性心疾患
- 性器クラミジア感染症――小頭症
麻疹
- 麻疹(5類感染症)は高熱や頬粘膜に生じるコプリック斑、下半身に広がる赤い発疹を特徴とする感染性疾患で、麻疹ウイルスの空気感染により生じる。
- 一次予防として、麻疹ワクチンの定期予防接種(二期)が行われている。ただし、麻疹に対しては特異的な治療法はなく、症状を和らげる対症療法が行われる。
感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。
- 結核――接触感染
- 麻疹――空気感染
- マラリア――飛沫感染
- インフルエンザ――経口感染
入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。
- 麻疹
- 風疹
- 手足口病
- 流行性耳下腺炎
麻疹に関して正しいのはどれか。2つ選べ。
- 合併症として脳炎がある。
- 感染力は発疹期が最も強い。
- 効果的な抗ウイルス薬がある。
- 2回のワクチン定期接種が行われている。
- エンテロウイルスの感染によって発症する。
性感染症
性感染症報告数と予防
- 性感染症とは、性行為によって伝播する5疾患(梅毒・性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・淋菌感染症・尖圭コンジローマ)で、令和4年(2022年)の報告数では、性器クラミジア感染症が30,136人と最も多い。
- 性感染症の予防にはコンドームの使用が効果的で、感染、または感染疑いのある場合、本人だけでなくパートナー等も含めた検査・治療を行うことが重要である。
令和4年(2022年)の感染症発生動向調査による年間の性感染症〈STD〉報告数で最も多いのはどれか。
- 性器クラミジア感染症
- 尖圭コンジローマ
- 性器ヘルペス
- 淋菌感染症
梅毒
- 梅毒は性行為による接触で伝播する性感染症で、梅毒トレポネーマ(細菌)の感染によって生じる。
- 早期の抗菌薬による薬物治療で完治が可能だが、検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすことがある。
梅毒について正しいのはどれか。
- ウイルス感染症である。
- 感染経路は空気感染である。
- 治療の第一選択薬はステロイド外用薬である。
- 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。
その他の感染症
細菌性髄膜炎
細菌性髄膜炎の症状はどれか。
- 羞明
- 羽ばたき振戦
- Raynaud(レイノー)現象
- Blumberg(ブルンベルグ)徴候
水痘
- 水痘(5類感染症)は水痘帯状疱疹ウイルスにより引き起こされる感染症で、典型的な症例では、皮膚の表面が赤くなる紅斑から発疹が始まり、水疱、膿疱を経て痂皮(かさぶた)化して治癒する。
- 定期予防接種として、生後12月から生後36月までの幼児(2回接種)を対象としている。
水痘の症状はどれか。
- 耳下腺の腫脹
- 両頰部のびまん性紅斑
- 水疱へと進行する紅斑
- 解熱前後の斑状丘疹性発疹
幼児を対象とする定期予防接種はどれか。
- DTワクチン(二種混合)
- ロタウイルスワクチン
- BCGワクチン
- 水痘ワクチン
流行性角結膜炎
流行性角結膜炎の原因はどれか。
- 淋菌
- 緑膿菌
- クラミジア
- アデノウイルス
- ヘルペスウイルス
レジオネラ症
- レジオネラ症(4類感染症)は自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息しているレジオネラ属菌の感染により発症し、主な病型として重症の肺炎を引き起こすレジオネラ肺炎がある。
- 浴槽の湯を濾過器を通して循環させる循環式浴槽では、換水や消毒、清掃を怠ることでレジオネラ属菌が繁殖する危険性が高まる。
循環式浴槽の水質汚染で発症するのはどれか。
- コレラ
- A型肝炎
- レジオネラ肺炎
- 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
インフルエンザ(季節性)
飛沫感染するのはどれか。
- 疥癬
- コレラ
- A型肝炎
- インフルエンザ
ノロウイルス感染症
- ノロウイルスは冬季に多く発生する食中毒で、物品や居室の消毒には次亜塩素酸ナトリウムを用いる。
- 乾燥すると空中に漂いやすく、これが口に入って感染することがあるため、嘔吐物は乾燥する前に速やかに処理する必要がある。
ノロウイルス感染症に罹患した患者の嘔吐物が床に飛び散っている。
この処理に使用する消毒薬で適切なのはどれか。
- 70%エタノール
- ポビドンヨード
- 塩化ベンザルコニウム
- 次亜塩素酸ナトリウム
人類共通感染症
人獣共通感染症で蚊が媒介するのはどれか。
- Q熱
- 黄熱
- 狂犬病
- オウム病
- 重症熱性血小板減少症候群〈SFTS〉
予防接種
予防接種の役割
感染症の成立過程において、予防接種が影響を与える要素はどれか。
- 病原体
- 感染源
- 感染経路
- 宿主の感受性
定期予防接種の対象(令和3年4月現在)
- 定期予防接種のうち、毒性を弱めた生ワクチンが使用される対象は、結核(BCG)、麻疹、風疹、水痘、ロタウイルスなどとなっている。
- 定期予防接種のうち、感染力を失わせた不活化ワクチン・トキソイドが使用される対象は、ポリオ、百日せき、ジフテリア、破傷風、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(Hib)、ヒトパピローマウイルス(HPV)などとなっている。
▶105回午後77
乳児の髄膜炎などを抑制するため、平成25年(2013年)に定期接種に導入されたのはどれか。
- 日本脳炎ワクチン
- ロタウイルスワクチン
- インフルエンザワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
- Hibワクチン
予防接種に生ワクチンが使用される疾患はどれか。2つ選べ。
- ジフテリア
- 日本脳炎
- 破傷風
- 結核
- 麻疹
定期予防接種について正しいのはどれか。
- BCG接種前にツベルクリン反応を実施する。
- ロタウイルスワクチンは不活化ワクチンである。
- ポリオウイルスワクチンの定期接種は廃止された。
- 麻疹ウイルスワクチンは就学までに4回接種する。
- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンは筋肉内注射する。
院内感染対策
標準予防策(スタンダードプリコーション)
標準予防策(スタンダードプリコーション)で感染源として取り扱うのはどれか。
- 汗
- 爪
- 唾液
- 頭髪
標準予防策(スタンダードプリコーション)において、創傷や感染のない患者への援助で使い捨て手袋が必要なのはどれか。
- 手浴
- 洗髪
- 口腔ケア
- 寝衣交換
手指衛生(手洗い)
感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。
- 石けんは十分に泡立てる。
- 洗面器に溜めた水で洗う。
- 水分を拭きとるタオルを共用にする。
- 塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。
感染経路別予防策(空気感染)
空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。
- 手袋
- N95マスク
- シューズカバー
- フェイスシールド
感染性廃棄物
廃棄する物とその区分との組合せで正しいのはどれか。
- 滅菌パックの袋――産業廃棄物
- エックス線フィルム――一般廃棄物
- 血液の付着したメスの刃――感染性産業廃棄物
- pH12.5以上のアルカリ性の廃液――感染性一般廃棄物
バイオハザードマーク
感染性廃棄物を収納した容器には、関係者が識別できるように下記のバイオハザードマークを付けることが推奨されている。

廃棄物の種類が識別できるように、性状に応じてマークの色を、①液状又は泥状のもの(血液等)は赤色、②固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)は橙色、③鋭利なもの(注射針等)は黄色と分けることが望ましい。
使用後の注射針を廃棄する容器のバイオハザードマークの色はどれか。
- 赤
- 黄
- 黒
- 橙
医療機関の廃棄物とバイオハザードマークの色の組合せで正しいのはどれか。
- 固体状の放射性廃棄物――黒色
- 注射針などの鋭利な廃棄物――赤色
- 血液などの液状、泥状の廃棄物――黄色
- 血液の付着したガーゼの廃棄物――橙色
消毒・滅菌
オートクレーブによる滅菌法はどれか。
- 乾熱滅菌
- プラズマ滅菌
- 高圧蒸気滅菌
- 酸化エチレンガス滅菌
医療器材と消毒・滅菌の組合せで正しいのはどれか。
- 手術用持針器――第4級アンモニウム塩
- ステンレス製便器――熱水消毒
- 軟性内視鏡――高圧蒸気滅菌
- ベッド柵――グルタラール
感染制御チーム
病床数300床以上の医療機関で活動する感染制御チームで適切なのはどれか。
- 医師で構成される。
- 各病棟に配置される。
- アウトブレイク時に結成される。
- 感染症に関するサーベイランスを行う。
薬剤耐性菌対策
院内感染の観点から、多剤耐性に注意すべきなのはどれか。
- ジフテリア菌
- 破傷風菌
- 百日咳菌
- コレラ菌
- 緑膿菌
身体の免疫機能
白血球(好中球)
- 白血球は体内に侵入した細菌、ウイルスなどを排除する免疫機能を持つ。
- 白血球の多くを占める好中球は、細菌感染から体を守る主要な生体防御機構(免疫)である。
免疫機能に関与する細胞はどれか。
- 血小板
- 白血球
- 網赤血球
- 成熟赤血球
細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。
- 単球
- 好酸球
- 好中球
- 好塩基球
- リンパ球
敗血症性ショック
- 敗血症は、細菌が産生するエンドトキシン等に起因して重度の全身性の炎症反応や臓器障害を起こしている病態をいう。
- 蘇生処置にも関わらず低血圧が持続し、ショック状態に陥った状態を敗血症性ショックといい、急性多臓器不全などにより死亡リスクが非常に高い。
細菌感染で起こるショックはどれか。
- 心原性ショック
- 敗血症性ショック
- アナフィラキシーショック
- 循環血液量減少性ショック
敗血症性ショックについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- 血圧は上昇する。
- 血中の乳酸濃度は低下する。
- エンドトキシンが原因である。
- 最重症の臨床像は多臓器不全である。
- コールドショックからウォームショックに移行する。
世界保健機関(WHO)
WHOの役割
国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。
- 国連難民高等弁務官事務所〈UNHCR〉――有償資金協力
- 国連教育科学文化機関〈UNESCO〉――児童の健康改善
- 世界保健機関〈WHO〉――感染症対策
- 国際労働機関〈ILO〉――平和維持活動
学校における感染症予防
学校において予防すべき感染症
- 学校保健安全法では、学校において予防すべき感染症として、感染力に応じて第一種から第三種に分類され、出席停止の期間の基準が定められている。
- 分類の考え方として、感染症法の1類感染症と2類感染症(結核除く)は第一種、それ以外の空気感染または飛沫感染により流行を広げる可能性が高い感染症は第二種、そのほかの感染症は第三種とされる。
学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。
- インフルエンザ
- 細菌性赤痢
- ジフテリア
- 腸チフス
- 流行性角結膜炎
介護保険制度は、少子高齢化の進む中で、社会全体で高齢者介護を支えるため、平成12年度(2000年度)の介護保険法の施行に伴い開始し、20年以上が経過しました。
制度開始当初の平成12年度(2000年度)と令和3年度(2021年度)を比べると、サービス受給者数は184万人から589万人、給付費は3.2兆円から10.4兆円と3倍以上伸びており(介護保険事業状況報告)、広く国民に身近な制度となっています。
介護保険制度は医療との連携の観点からも重要で、看護師国家試験において頻出テーマの一つとなっており、制度の概要や法改正に伴うサービスの追加・変更、介護者の現状など、幅広い最新の知識をしっかりと押さえておく必要があります。
このページでは、第113回(2024年)から第104回(2015年)までの過去10年の看護師国家試験問題の中から介護保険制度に関する問題をピックアップし、解説とともに示します。これまでの介護制度問題の出題傾向を把握し、最新の制度や詳細な統計を「国民衛生の動向」第5編で確認することで、介護制度に関する理解を一層深めていただければ幸いです。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
介護保険制度問題目次
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
- 地域支援事業
- 地域包括支援センター
- 介護人材
- 介護者の支援
介護保険制度の対象・手続き
保険者
▶108回午前4
介護保険制度における保険者はどれか。
- 市町村及び特別区
- 都道府県
- 保健所
- 国
被保険者
▶106回午前4
介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
- 45歳以上
- 55歳以上
- 65歳以上
- 75歳以上
▶109回午前3
介護保険の第2号被保険者は、( )歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
( )に入る数字はどれか。
- 30
- 40
- 50
- 60
介護保険料・利用者負担
▶108回午後29
介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。
- 介護保険料は全国同額である。
- 介護保険被保険者証が交付される。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 介護保険給付の利用者負担は一律3割である。
要介護認定
- 市町村は、被保険者からの要介護認定の申請を受けて調査を行う。
- 市町村に設置された介護認定審査会は、被保険者の程度に応じて要介護状態の区分(要支援1・2、要介護1~5の7区分)の審査・判定を行う。
▶110回午前4
要介護認定の申請先はどれか。
- 市町村
- 診療所
- 都道府県
- 介護保険審査会
▶104回午後4
要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。
- 介護認定審査会
- 介護保険審査会
- 社会福祉協議会
- 社会保障審議会
▶112回午前5
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
- 4
- 5
- 6
- 7
介護給付・予防給付
- 要介護状態の者には介護給付が支給され、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを内容とする。
- 要支援状態の者には予防給付が支給され、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを内容とする。
▶105回午前4
介護保険の給付はどれか。
- 年金給付
- 予防給付
- 求職者給付
- 教育訓練給付
▶111回午後4
介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか。
- 医療給付
- 介護給付
- 年金給付
- 予防給付
居宅サービス
訪問入浴介護
- 訪問入浴介護は、自宅の浴槽での入浴が困難な要介護者に対して、浴槽を居宅に持ち込み、入浴の介護を行う居宅サービスである。
- ほぼ寝たきりの状態にある要介護5の利用者の割合が46.9%(令和3年)と半分近くを占めている。
▶113回午後68
介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。
- 訪問入浴介護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶109回午前72改題
令和3年(2021年)の介護サービス施設・事業所調査における要介護度別利用者数の構成割合で、要介護5の利用者が最も多いのはどれか。
- 訪問介護
- 訪問看護ステーション
- 居宅介護支援
- 訪問入浴介護
福祉用具貸与
- 福祉用具貸与は介護保険制度における居宅サービスであり、利用者負担の上で福祉用具の貸与を受ける。
- 要支援及び要介護1の者は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)のみ貸与を受けられる。
▶108回午前58
Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。
Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。
- 車椅子
- 歩行器
- 電動ベッド
- 入浴用椅子
特定福祉用具販売
▶112回午後81
介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。
- 簡易浴槽
- 特殊寝台
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 取り付け工事を伴わないスロープ
施設サービス
施設サービスの類型
▶106回午後9
介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。
- 介護保険法
- 健康保険法
- 地域保健法
- 老人福祉法
▶111回午前53
介護保険制度における施設サービスはどれか。
- 介護医療院サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
介護老人福祉施設
▶106回午前59
介護保険法で「入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と規定されているのはどれか。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 介護療養型医療施設
- 介護療養型老人保健施設
介護老人保健施設
▶108回午後10・104回午前8類問
要介護者に対し、看護・医学的管理の下で必要な医療や日常生活上の世話を行うのはどれか。
- 介護老人保健施設
- 短期入所生活介護
- 保健センター
- 有料老人ホーム
▶113回午後41
介護老人保健施設について適切なのはどれか。
- 常勤医師の配置は義務ではない。
- 老人福祉法に基づき設置される。
- 要介護者に対して自宅での生活に向けた支援を行う。
- 従事者の配置基準は看護職員と介護職員が同数である。
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
▶110回午後68
介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。
- 重度訪問介護
- 地域活動支援事業
- 小規模多機能型居宅介護
- 特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
▶108回午後51
介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- 通所リハビリテーション
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
▶105回午前74
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)で正しいのはどれか。
- 光熱費は自己負担である。
- 12人を1つのユニットとしている。
- 看護師の配置が義務付けられている。
- 介護保険制度の施設サービスである。
- 臨死期は提携している病院に入院する。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶105回午後89
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 介護予防サービスである。
- 24時間を通じて行われる。
- 地域密着型サービスである。
- 重症心身障害児を対象とする。
- 施設サービス計画の作成を行う。
サービスの指定・監督
▶112回午前70
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
- 福祉用具貸与
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉
地域支援事業
概要
- 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するため、市町村は65歳以上のすべての高齢者を対象として、地域支援事業を実施している。
- 地域支援事業の総合事業として、外出や調理が困難な者に対する配食サービス(介護予防・生活支援サービス事業)や、介護予防教室(一般介護予防事業)を行っている。
▶113回午前4
介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。
- 保険給付である。
- 都道府県の事業である。
- 介護保険施設で実施される。
- 配食サービスは生活支援サービスの1つである。
▶112回午前55
65歳以上の高齢者が要介護認定の有無に関わらず利用できるのはどれか。
- 介護予防教室
- 介護老人保健施設
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護〈デイサービス〉
地域包括ケアシステム
地域包括支援センター
▶111回午後86
地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
- 介護保険法
- 健康増進法
- 社会福祉法
- 地域保健法
- 老人福祉法
▶108回午前11・107回午前4類問
平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。
- 保健所
- 市町村保健センター
- 地域包括支援センター
- 訪問看護ステーション
地域包括支援センターの業務
地域包括支援センターが行う地域支援事業として以下の業務を実施する。
- 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
- 総合相談支援業務
- 権利擁護業務(虐待の防止、早期発見)
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
▶108回午後68
家族からネグレクトを受けている高齢者について、地域包括支援センターに通報があった。
この通報を受けた地域包括支援センターが行う業務はどれか。
- 権利擁護
- 総合相談支援
- 介護予防ケアマネジメント
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援
地域包括ケアシステム
▶106回午後58
地域包括ケアシステムについて正しいのはどれか。
- 都道府県を単位として構築することが想定されている。
- 75歳以上の人口が急増する地域に重点が置かれている。
- 本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている。
- 地域特性にかかわらず同じサービスが受けられることを目指している。
地域包括ケアシステムにおける支援のあり方
地域包括ケアシステムにおける支援は、以下のとおり分類される。
- 生活保護など税による公の負担により支える公助
- 介護保険など負担と受給による支え合い(社会保険方式)である共助
- 費用負担が制度的に裏付けされていないボランティアなどの助け合いである互助(インフォーマルサポート)
- 自発的な体重測定など自ら行う自助
▶108回午前74
地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。
- 高齢者が生活保護を受けること
- 住民が定期的に体重測定すること
- 要介護者が介護保険サービスを利用すること
- 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと
▶107回午後31
インフォーマルサポートはどれか。
- 介護支援専門員による居宅サービス計画の作成
- 医師による居宅療養管理指導
- 近隣住民による家事援助
- 民生委員による相談支援
介護人材
介護支援専門員(ケアマネジメント)
- 介護支援専門員等によるケアマネジメントでは、利用者の身体状態や家族の介護能力などを踏まえた解決すべき課題を把握(アセスメント)し、解決のための介護サービス計画を作成する。
- 介護サービス計画に基づき実施されたサービスについては、要介護者等の心身や生活の状況の変化を継続的に把握・評価(モニタリング)し、それに応じて介護サービス計画の修正を行う。
- 介護サービス計画は利用者自ら作成し、居宅サービスを受けることも可能である。
▶105回午後9
介護支援専門員が行うのはどれか。
- 通所介護の提供
- 福祉用具の貸与
- 短期入所生活介護の提供
- 居宅サービス計画の立案
▶110回午前67
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
- 家族の介護能力はアセスメントに含めない。
- 介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。
- 利用者が介護サービス計画を作成することはできない。
- モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。
▶104回午前82
介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。
- スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。
- アセスメントで利用者の疾患を診断する。
- 利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。
- ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。
- ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。
介護福祉士
▶107回午後81・112回午後34類問
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。
- 摘便
- 創処置
- 血糖測定
- 喀痰吸引
- インスリン注射
介護者の支援
レスパイトケア
▶109回午前8
レスパイトケアの目的はどれか。
- 介護者の休息
- 介護者同士の交流
- 介護者への療養指導
- 療養者の自己決定支援
▶105回午後62
レスパイトケアの主な目的について適切なのはどれか。
- 高度な治療を集中的に行う。
- 家族へ介護方法の指導を行う。
- 居宅サービス料金を補助する。
- 介護を行う家族のリフレッシュを図る。
▶111回午前68・106回午後45類問
Aさん(80歳、女性)は1人暮らし。要介護2の認定を受け、長男(50歳、会社員)、長男妻(45歳、会社員)、孫(大学生、男性)と同居することになった。長男の家の間取りは、洋室5部屋、リビング、台所である。Aさんは同居後に訪問看護を利用する予定である。訪問看護を利用するにあたりAさんの家族から「在宅介護は初めての経験なのでどうすればよいですか」と訪問看護師に相談があった。
訪問看護師の説明で最も適切なのはどれか。
- 「Aさんの介護用ベッドはリビングに置きましょう」
- 「Aさんの介護に家族の生活リズムを合わせましょう」
- 「活用できる在宅サービスをできる限り多く利用しましょう」
- 「特定の同居家族に介護負担が集中しないように家族で話し合いましょう」
育児・介護休業法における介護関連規定
- 育児・介護休業法における介護休業では、要介護状態にある対象家族1人につき3回まで、連続したひとまとまりの期間の休業(合計93日まで)を取得できる。
- 対象家族は配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が該当する。
▶111回午前30
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
- 介護休業は分割して取得することはできない。
- 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
- 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
- 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
訪問看護
訪問看護を行う職種
▶104回午後9
介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。
- 医師
- 薬剤師
- 理学療法士
- 介護福祉士
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、訪問看護サービスを提供する事業所として都道府県知事から指定を受けて開設されるもので、以下の人員基準等が定められている。
- 看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)と、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数置くこと。
- 管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師とすること。
- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設置すること。
▶111回午後10
指定訪問看護ステーションには常勤換算で( )人以上の看護職員を配置することが定められている。
( )に入るのはどれか。
- 1.0
- 1.5
- 2.0
- 2.5
▶107回午後9
訪問看護ステーションの管理者になることができる職種はどれか。
- 医師
- 看護師
- 介護福祉士
- 理学療法士
▶109回午後71
訪問看護事業所で正しいのはどれか。
- 24時間対応が義務付けられている。
- 自宅以外への訪問看護は認められない。
- 特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。
- 従事する看護師は臨床経験3年以上と定められている。
▶105回午前63
訪問看護ステーションの管理・運営について正しいのはどれか。
- 事務所を設置する必要はない。
- 訪問看護の利用回数の調整は市町村が行う。
- 利用者が希望すれば訪問看護の記録を開示する。
- 利用者とのサービス契約後に重要事項を説明する。
▶112回午後67
指定訪問看護ステーションについて正しいのはどれか。
- 看護職員以外は配置できない。
- 緊急時用の薬剤の保管が義務付けられている。
- 訪問看護指示書に基づいて療養者のケアを行う。
- 従事する看護職員は5年以上の臨床経験が必要である。
訪問看護の対象者
要介護者等には介護保険から、それ以外の者には医療保険から訪問看護の給付が行われる。ただし、要介護者等であっても、以下に該当する者は医療保険の給付による。
- 末期の悪性新生物や人工呼吸器を使用している状態など厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
- 主治医による特別訪問看護指示書(14日間有効、一部2回交付可)の交付を受けた者
- 認知症以外の精神障害を有する者
また、これらに該当する者は、週3日を超えてのサービス提供が可能となっている。
▶105回午前62
介護保険被保険者で介護保険による訪問看護が提供されるのはどれか。
- 脳血管疾患
- 末期の結腸癌
- 脊髄小脳変性症
- 進行性筋ジストロフィー
▶109回午前69
Aさん(68歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。
Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。
- 医療保険から給付される。
- 特別訪問看護指示書を受けて実施される。
- 複数の訪問看護事業所の利用はできない。
- 理学療法士による訪問は給付が認められない。
▶107回午後62
健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。
- サービス対象は75歳以上である。
- 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。
- 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。
- 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。
▶105回午後63
訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。
- 主治医の意見書が必要である。
- 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
- サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
- 主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
▶107回午前62
特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。
- 提供できる頻度は週に3回までである。
- 提供できる期間は最大6か月である。
- 対象に指定難病は含まない。
- 医療保険が適用される。
▶108回午後65
訪問看護制度で正しいのはどれか。
- 管理栄養士による訪問は保険請求できる。
- 精神科訪問看護は医療保険から給付される。
- 医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。
- 訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。
訪問看護の利用者の状況
- 介護保険法の利用者が74.4万人、健康保険法等の利用者が48.4万人となっている。(令和5年)
- 年齢階級別にみると、80~89歳が38.0万人と最も多い。(令和4年)
- 要介護度別にみると、要介護2が15.9万人と最も多く、それを境に要介護(要支援)度が上がる・下がるにつれて減少する。(令和4年)
- 傷病分類別にみると、循環器系の疾患が26.9万人(うち、脳血管疾患12.4万人)と最も多い。(令和4年)
▶113回午前68改題
令和4年(2022年)の介護サービス施設・事業所調査において、介護保険制度による訪問看護の利用者の特徴で正しいのはどれか。
- 要介護5の利用者が最も多い。
- 傷病別では悪性新生物が最も多い。
- 医療保険制度による利用者よりも多い。
- 要支援1、2の利用者は全体の利用者の4割を占める。
令和5年2月12日(日)に実施された第112回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第112回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 必修問題
▶午前1改題
令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。
- 19.7歳
- 24.7歳
- 29.7歳
- 34.7歳
▶午前2改題
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。
- 頭痛
- 腰痛
- 体がだるい
- 目のかすみ
▶午前3
喫煙指数(Brinkman〈ブリンクマン〉指数)を算出するために、喫煙年数のほかに必要なのはどれか。
- 喫煙開始年齢
- 受動喫煙年数
- 家庭内の喫煙者数
- 1日の平均喫煙本数
▶午前4
休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。
- 30時間
- 35時間
- 40時間
- 45時間
▶午前5
介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
- 4
- 5
- 6
- 7
▶午前6
緩和ケアの目標で正しいのはどれか。
- 疾病の治癒
- 余命の延長
- QOLの向上
- 在院日数の短縮
▶午前7
運動機能の発達で3歳以降に獲得するのはどれか。
- 階段を昇る。
- ひとりで立つ。
- ボールを蹴る。
- けんけん〈片足跳び〉をする。
▶午前8
ハヴィガースト, R. J.が提唱する成人期の発達課題はどれか。
- 経済的に自立する。
- 身体的衰退を自覚する。
- 正、不正の区別がつく。
- 読み、書き、計算ができる。
▶午前9改題
令和4年(2022年)の衛生行政報告例における看護師の就業場所で、医療機関(病院、診療所)の次に多いのはどれか。
- 事業所
- 市町村
- 保健所
- 訪問看護ステーション
▶午前10
体性感覚はどれか。
- 視覚
- 触覚
- 聴覚
- 平衡覚
▶午前11
健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。
- 単球
- 好酸球
- 好中球
- リンパ球
▶午前12
体温変化をとらえ、体温調節の指令を出すのはどれか。
- 橋
- 小脳
- 視床下部
- 大脳皮質
▶午前13
下血がみられる疾患はどれか。
- 肝囊胞
- 大腸癌
- 子宮体癌
- 腎細胞癌
▶午前14
糖尿病の急性合併症はどれか。
- 足壊疽
- 脳血管疾患
- 糖尿病網膜症
- ケトアシドーシス昏睡
▶午前15
メタボリックシンドロームの診断基準において男性の腹囲〈ウエスト周囲径〉で正しいのはどれか。
- 80cm以上
- 85cm以上
- 90cm以上
- 95cm以上
▶午前16
炎症マーカーはどれか。
- CA19-9
- 抗核抗体
- C反応性蛋白質〈CRP〉
- リウマトイド因子〈RF〉
▶午前17
薬物動態で肝臓が関与するのはどれか。
- 吸収
- 分布
- 代謝
- 蓄積
▶午前18
胃から食道への逆流を防ぐために、成人が食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。
- 座位
- 仰臥位
- 右側臥位
- 半側臥位
▶午前19
全身清拭時に皮膚に触れるタオルの温度で適切なのはどれか。
- 20〜22℃
- 30〜32℃
- 40〜42℃
- 50〜52℃
▶午前20
個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。
- 手袋
- ガウン
- サージカルマスク
- フェイスシールド
▶午前21
オートクレーブによる滅菌法はどれか。
- 酸化エチレンガス滅菌
- 高圧蒸気滅菌
- 放射線滅菌
- 乾熱滅菌
▶午前22
薬物の吸収速度が最も速いのはどれか。
- 経口投与
- 筋肉内注射
- 静脈内注射
- 直腸内投与
▶午前23
室内空気下での呼吸で、成人の一般的な酸素療法の適応の基準はどれか。
- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr以上
- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉 60Torr未満
- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr以上
- 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉 60Torr未満
▶午前24
CO2ナルコーシスの症状で正しいのはどれか。
- 咳嗽
- 徐脈
- 浮腫
- 意識障害
▶午前25
母乳栄養の児に不足しやすいのはどれか。
- ビタミンA
- ビタミンB
- ビタミンC
- ビタミンE
- ビタミンK
資料 厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験、第112回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第112回看護師国家試験
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午前問題のうち必修問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
午前 必修問題
▶午前1改題
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。
- 1.25人
- 2.25人
- 3.25人
- 4.25人
▶午前2改題
令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのはどれか。
- 自宅
- 病院
- 老人ホーム
- 介護医療院・介護老人保健施設
▶午前3
食品を扱う人の化膿した創が汚染源となる食中毒の原因菌はどれか。
- 腸炎ビブリオ
- ボツリヌス菌
- 黄色ブドウ球菌
- サルモネラ属菌
▶午前4
介護保険法の地域支援事業で正しいのはどれか。
- 保険給付である。
- 都道府県の事業である。
- 介護保険施設で実施される。
- 配食サービスは生活支援サービスの1つである。
▶午前6改題
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査で20歳以上の男性における喫煙習慣者の割合に最も近いのはどれか。
- 6%
- 16%
- 26%
- 36%
▶午前7
学童期中学年から高学年にみられる、親から離れて仲の良い仲間同士で集団行動をとる特徴はどれか。
- 心理的離乳
- 自我の芽生え
- ギャングエイジ
- 自我同一性〈アイデンティティ〉の確立
▶午前8
壮年期の男性で減少するのはどれか。
- エストロゲン
- プロラクチン
- アルドステロン
- テストステロン
▶午前9
核家族はどれか。
- 兄弟姉妹のみ
- 夫婦と子ども夫婦
- 夫婦と未婚の子ども
- 夫婦とその親と夫婦の子ども
▶午前10
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
- 17
- 18
- 19
- 20
▶午前11
肘関節を伸展させる筋肉はどれか。
- 三角筋
- 大胸筋
- 上腕三頭筋
- 上腕二頭筋
▶午前12
脳幹に含まれる部位はどれか。
- 延髄
- 小脳
- 下垂体
- 松果体
▶午前13
免疫機能に関与する細胞はどれか。
- 血小板
- 白血球
- 網赤血球
- 成熟赤血球
▶午前14
脳死の状態はどれか。
- 縮瞳がある。
- 脳波で徐波がみられる。
- 自発呼吸は停止している。
- 痛み刺激で逃避反応がある。
▶午前15
経口感染するウイルス性肝炎はどれか。
- A型肝炎
- B型肝炎
- C型肝炎
- D型肝炎
▶午前16
抗菌薬について正しいのはどれか。
- ウイルスに有効である。
- 経口投与では効果がない。
- 耐性菌の出現が問題である。
- 正常の細菌叢には影響を与えない。
▶午前17
インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。
- 痛風
- 咽頭炎
- 消化性潰瘍
- 関節リウマチ
▶午前18
異常な呼吸音のうち低調性連続性副雑音はどれか。
- 笛のような音〈笛音〉
- いびきのような音〈類鼾音〉
- 耳元で髪をねじるような音〈捻髪音〉
- ストローで水中に空気を吹き込むような音〈水泡音〉
▶午前19
膝蓋腱反射の低下で疑われる病態はどれか。
- 脚気
- 壊血病
- くる病
- 夜盲症
▶午前20
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。
- 3.4m2以上
- 4.4m2以上
- 5.4m2以上
- 6.4m2以上
▶午前21
無菌操作が必要なのはどれか。
- 浣腸
- 気管内吸引
- 口腔内吸引
- 経鼻胃管挿入
▶午前22
成人への坐薬の挿入方法で正しいのはどれか。
- 息を止めるよう説明する。
- 右側臥位になるよう説明する。
- 挿入後1、2分肛門を押さえる。
- 肛門から2cmの位置に挿入する。
▶午前24
直流除細動器の使用目的はどれか。
- 血圧の上昇
- 呼吸の促進
- 体温の上昇
- 洞調律の回復
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午前問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」と合わせてご活用ください。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午前 状況設定問題
次の文を読み91~93の問いに答えよ。
Aさん(49歳、女性)は、これまで在宅勤務でほとんど外出することがなく、BMI33であった。Aさんは久しぶりの出勤の際に転倒し、右大腿骨頸部骨折と診断され、右人工股関節置換術を受けることになった。
▶午前91
Aさんの術後に最も注意すべき所見はどれか。
- Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候
- Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候
- Homans〈ホーマンズ〉徴候
- Romberg〈ロンベルグ〉徴候
▶午前92
術後1日、Aさんは39.1℃の発熱がみられた。
バイタルサイン:呼吸数18/分、脈拍117/分、整、血圧132/82mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)。
身体所見:呼吸音は異常なし、腰背部痛なし、術創部の腫脹、発赤、熱感はない。左手の末梢血管内カテーテル刺入部に発赤、熱感がある。
血液検査所見:赤血球344万/μL、Hb12.1g/dL、白血球11,900/μL、血小板18万/μL。
血液生化学所見:尿素窒素16mg/dL、クレアチニン0.8mg/dL、CRP11.4mg/dL。
尿所見:沈査に白血球を認めない。
胸部エックス線写真:異常所見なし。
Aさんの発熱の原因で考えられるのはどれか。2つ選べ。
- 肺炎
- 腎盂腎炎
- 術創部感染
- 術後の吸収熱
- カテーテル関連血流感染症
▶午前93
術後3日、Aさんの全身状態は改善し、読書をして過ごしている。
Aさんの術後の合併症を予防する適切な肢位はどれか。
- 外旋
- 外転
- 内旋
- 内転
次の文を読み94~96の問いに答えよ。
Aさん(57歳、男性)は、妻(50歳)と2人で暮らしている。21歳から喫煙習慣があり、5年前に風邪で受診した際に肺気腫と診断された。最近は坂道や階段を昇ると息切れを自覚するようになってきた。
▶午前94
Aさんの呼吸機能に関する数値で増加を示すのはどれか。
- 1秒率
- 残気量
- 1回換気量
- 動脈血酸素分圧〈PaO2〉(room air)
▶午前95
Aさんは発熱、咳嗽、粘稠痰、呼吸困難を認めたため受診し、肺炎を伴う慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉の急性増悪と診断されて入院した。入院後、薬物療法によって病状は改善し退院が決定した。看護師がAさんに退院後の生活について尋ねると、今回の入院をきっかけにAさんは退職し、家事に専念すると答えた。
Aさんの呼吸機能に対する負荷が最も小さい動作はどれか。
- 食べる直前に調理する。
- 部屋全体に掃除機をかける。
- 頭より高い位置に洗濯物を干す。
- 買い物した荷物をカートで運ぶ。
▶午前96
5年後、Aさんは急性増悪による入退院を繰り返していた。今回の入院では呼吸機能の低下がみられたため、退院後に在宅酸素療法〈HOT〉を導入することになった。Aさんは「家での生活で気をつけることは何ですか」と看護師に質問した。
Aさんへの指導内容で適切なのはどれか。
- 「寒いときは電気毛布を使ってください」
- 「入浴時は酸素チューブを外してください」
- 「ガス調理器を電磁調理器に変更してください」
- 「呼吸が苦しいときは楽になるまで酸素流量を上げてください」
次の文を読み97~99の問いに答えよ。
Aさん(72歳、女性)は、1人で暮らしている。小学校の教員を定年退職後、書道教室に月2回、体操教室に月1回通っている。20年前に高血圧症と診断され、月に1回かかりつけの病院を受診し、内服治療をしている。6か月前から、Aさんは病院の受診日を間違えたり、書道教室の日時を忘れることがあり、かかりつけの医師に相談した。Aさんは認知症専門医を紹介され、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉18点で、軽度のAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症と診断された。
▶午前97
Aさんに出現している認知機能障害はどれか。
- 脱抑制
- 近時記憶障害
- 実行機能障害
- 物盗られ妄想
▶午前98
診断から2か月後、かかりつけの病院の看護師にAさんは「50年以上住んでいるこの土地で、できるだけ他人の迷惑にならず生活を続けたいと思って貯金もしてきました。私は軽い認知症だと言われたのですが、これからも自分でお金の管理ができるか心配です。どうしたらよいのでしょうか。私が使えるサービスがあれば知りたいです」と話した。
Aさんが利用できるのはどれか。
- 生活保護制度
- 地域生活支援事業
- 後期高齢者医療制度
- 日常生活自立支援事業
▶午前99
診断から半年後、Aさんは、かかりつけの病院の看護師に「書道教室や体操教室は、部屋のカレンダーに書いて参加しています。ただ、最近、病院に行くときに薬が残っています。大切な薬だと先生から言われていますし、忘れずに飲みたいのですが、どうしたらよいでしょうか」と相談した。
看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 「お薬手帳を毎朝見るようにしましょう」
- 「薬のことは主治医に相談してください」
- 「薬を飲んだらカレンダーに丸を付けてみませんか」
- 「この病気の方は、薬を飲み忘れることがあります」
次の文を読み100~102の問いに答えよ。
Aさん(70歳、女性)は夫(68歳)と2人で暮らしている。BMI26で左股関節の変形性関節症のため関節可動域の制限と疼痛があり、外出時はT字杖を使用している。症状が強いときに消炎鎮痛薬を服用しているが、日常生活動作は自立している。Aさんは過去に転倒したことはないが、左右の下肢の差が3cmあり、立ち上がるときにふらつくことがある。自宅で座って過ごす時間が長い。Aさんは定期受診のため夫に付き添われて外来を受診した。
▶午前100
Aさんの症状の悪化を予防するための説明で適切なのはどれか。
- 運動はしない。
- 減塩食をとる。
- 体重を減らす。
- 家事は夫に任せる。
▶午前101
外来で、診察終了後にAさんから「少し話がある」と言われた女性のB看護師は、空いている診察室で面談した。Aさんから「男性の医師には聞けなかったのですが、性交はやめておいた方がよいでしょうか。股関節の痛みが強くなることはないのですが、夫も心配していました」と相談があった。
このときのB看護師のAさんへの対応で適切なのはどれか。
- 「同年代の変形性関節症の方に聞いてみてはいかがですか」
- 「股関節に負担がない体位について説明します」
- 「性交時は潤滑剤を使いましょう」
- 「性交は避けた方がよいでしょう」
▶午前102
B看護師は、Aさんが処置室前の待合室でT字杖を持ち、椅子から立ち上がろうとしているのを見かけた。B看護師が声をかけると、Aさんは「夫が会計をしていますが、急にトイレに行きたくなって」と慌てていた。夫はAさんから2mほど離れた所で会計をしているため、Aさんの様子に気がついていない。待合室は患者や家族で混雑しており、外来にある車椅子は別の患者が使用中だった。
AさんへのB看護師の声かけで適切なのはどれか。
- 「車椅子を探してきます」
- 「ご主人をお呼びしましょう」
- 「トイレまで一緒に行きましょう」
- 「転ばないように気を付けて行ってくださいね」
次の文を読み103~105の問いに答えよ。
Aちゃんは出生前診断で羊水過多があり先天性食道閉鎖症の疑いを指摘されていた。在胎37週5日に帝王切開で出生、出生体重2,780g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点である。出生後、Aちゃんは先天性食道閉鎖症と診断された。
▶午前103
出生直後のAちゃんにみられるのはどれか。
- 腹部エックス線写真の鏡面像
- 口腔内の泡沫状唾液の流出
- 胆汁性の嘔吐
- 噴水状の嘔吐
▶午前104
Aちゃんは、出生当日に胃瘻造設、気管食道瘻切断と食道端々吻合術を受け、無事に終了した。術後2日、人工呼吸器管理下で胸腔ドレーンが挿入されている。
このときの看護で適切なのはどれか。
- 頸部を伸展させた体位を保持する。
- 摂食嚥下機能の獲得のため支援を開始する。
- 親がAちゃんを自由に抱っこするのを見守る。
- 唾液の吸引時には吸引チューブの挿入を吻合部の手前までにする。
▶午前105
Aちゃんは3歳6か月になった。現在は胃瘻を閉鎖し経口摂取をしているが、吻合部の狭窄による嚥下困難が生じ、これまでに食道バルーン拡張術を2回行った。現在も症状が残っていて、固形物の通過障害が軽度ある。身長92.5cm(25パーセンタイル)、体重11.5kg(3パーセンタイル)で、半年後に保育所へ入園する。両親が「Aはあまり体重が増えません。保育所ではみんなより食事に時間がかかるのではないかと心配です」と外来看護師に話したため、今後の対応について両親、看護師および医師で話し合った。
Aちゃんの摂食に関する対応で適切なのはどれか。
- 再度、胃瘻を造設する。
- 食事を保育士に介助してもらう。
- 昼前に保育所から帰宅し、家で昼食を摂る。
- 同じクラスの子ども達と同量を食べられるよう訓練する。
- Aちゃんに適した食事形態の提供が可能か保育所に確認する。
次の文を読み106~108の問いに答えよ。
Aさん(28歳、会社員)は、夫(30歳、会社員)と2人で暮らしている。2023年2月5日からの月経を最後に無月経となり、妊娠の可能性を考えて受診した。医師の診察の結果、妊娠と診断された。
▶午前106
Naegele〈ネーゲレ〉概算法を用いてAさんの分娩予定日を求めよ。
2023年【①】【②】月【③】【④】日
▶午前107
診察後、Aさんから看護師に妊娠中の生活や体重の管理について質問があった。Aさんは「缶ビール2本を週に1回、コーヒーを1日に6杯以上飲んでいます。友人に勧められて半年前から1日240μgの葉酸のサプリメントを飲んでいます」と話す。Aさんは身長160cm、非妊時体重62kgである。
看護師のAさんへの説明で適切なのはどれか。
- 「飲酒は中止しましょう」
- 「妊娠中の体重増加は7kg未満にしましょう」
- 「コーヒーは今までどおりに飲んでも大丈夫です」
- 「葉酸は妊娠前と同じ量を摂るようにしましょう」
▶午前108
妊娠30週2日。Aさんは妊婦健康診査を受け、妊娠経過に異常はなく児の発育も順調と診断された。診察後、Aさんから看護師に「最近、腰が痛くなることがあります。腰痛への対処法はありますか」と質問があった。
看護師のAさんへの説明内容で適切なのはどれか。
- 安静にする。
- 椅子に浅く座る。
- Sims〈シムス〉位で休む。
- 柔らかいマットレスや布団で寝る。
次の文を読み109~111の問いに答えよ。
Aさん(32歳、初産婦)は妊娠39週4日で男児を正常分娩した。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水を拭き取り、インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。その後、温めておいた衣服を着せてコットに寝かせ、コットを空調の風が当たらない場所に配置した。
▶午前109
看護師の行為で対流による児の熱喪失を予防したのはどれか。
- 羊水を拭き取った。
- インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。
- 温めておいた衣服を着せた。
- コットを空調の風が当たらない場所に配置した。
▶午前110
産褥3日。Aさんは児の啼泣に合わせて横抱きで母乳を与えている。Aさんの乳房の型はⅢ型、熱感が出てきている。乳管は左右とも4本開通している。「抱き方は色々あると聞きました。今の方法以外の授乳の仕方はありますか」と相談を受けた。
授乳の仕方を図に示す。
Aさんに適した授乳の仕方はどれか。

▶午前111
日齢4。体重2,760g。児のバイタルサインは正常である。経皮ビリルビン10mg/dL。前日の排尿は1日4回、排便1日1回。母乳のみを哺乳している。1回の授乳に30分以上かかり、授乳後も児は啼泣している。児は音に反応して抱きつくような動きをする。
新生児のアセスメントで適切なのはどれか。
- 異常な反射を認める。
- 母乳不足が疑われる。
- 黄疸が生理的範囲を超えている。
- 体重減少が生理的範囲を超えている。
次の文を読み112~114の問いに答えよ。
Aさん(22歳、男性)は、高校卒業後に就職したが、同僚との関係がうまく築けず、転職を繰り返している。「他の人と自分はどこか違う。自分の将来が不安だ」と感じたAさんは精神科クリニックを受診し、自閉症スペクトラム障害と診断された。
Aさんは小学生のころから他人の気持ちが理解できないときがあり、対人関係を築くことが苦手で、学校で孤立していた。また、偏食が強く、るいそうがみられたために、同級生から容姿のことでいじめられたことがあった。中学校や高校では忘れ物が多く、集団生活になじめなかった。
▶午前112
Aさんに認められるのはどれか。
- 被害妄想
- 予期不安
- ボディイメージの障害
- コミュニケーションの障害
▶午前113
クリニックに通院し半年が経過した。現在、Aさんは無職である。Aさんは仕事が長続きしないことで将来への不安が強く、自身の適性にあった職場を探したいと希望している。外来看護師は主治医とも相談し、Aさんに就労移行支援のサービスについて伝えることにした。
Aさんへの説明で適切なのはどれか。
- 「仕事が見つかるまで期限なく通所できます」
- 「同じ障害を持つ仲間との共同生活が原則です」
- 「一般就労に向けて知識や能力の向上を目指します」
- 「生活リズムを整え、集団に慣れていくことが目的です」
▶午前114
就労移行支援を利用し、Aさんは仕事を始めたが、苦手な仕事内容が多く、失敗が続いているため同僚から注意を受け続けている。外来看護師は、Aさんから「毎日が憂うつでつらい。ストレスが溜まるのでどうしたらよいか」と相談を受けた。
Aさんへの対応で適切なのはどれか。
- 仕事に慣れるまで待つように説明する。
- 憂うつな気分について詳しく話してもらう。
- 職場の同僚とうまく付き合う方法を考えてもらう。
- 外来看護師が行っているストレス発散方法を指導する。
次の文を読み115~117の問いに答えよ。
Aさん(87歳、女性、要介護1)は1人暮らしで、長女(52歳、会社員)が同じマンションの隣の部屋に住んでいる。5年前に乳癌のため左乳房切除術を受けた。1年前に肺への転移が確認され、胸水の貯留への対症療法のため入退院を繰り返していた。退院後は、状態観察と体調管理のため大学病院の外来を月に2回受診し、訪問介護と訪問看護を週に1回ずつ利用して在宅療養を続け「これ以上の積極的な治療はせずに自宅で最期まで過ごしたい」と話している。 ある日、長女から「最近、母は通院がつらそうで、先月は1回しか受診していません。医師の診察は大事だと思うので、受診を続けるために主治医に何を相談すればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。
▶午前115
長女への助言で適切なのはどれか。
- 緩和ケア病棟への入院
- 在宅療養支援診療所の利用
- 医師の診察を月1回に減らすこと
- 通所リハビリテーションを利用すること
▶午前116
3か月後、Aさんは呼吸状態の悪化のため在宅酸素療法〈HOT〉(3L/分、24時間)を受けることになった。要介護3に変更され訪問看護を週に3回利用することになった。毎日午前は訪問介護、午後は長女が介護休業制度の短時間勤務等の措置を利用して介護することになった。訪問介護員から「Aさんの食事を作り、食べた後の片付けをしているのですが、Aさんが食事の後に少し息が苦しいと言うことがあります。どうすればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。
訪問介護員への助言で適切なのはどれか。
- 「食事を介助しましょう」
- 「食事の後に短速呼吸を促しましょう」
- 「食事以外の時間は安静に過ごしてもらいましょう」
- 「Aさんの1回分の食事量を減らし回数を増やしましょう」
▶午前117
6か月後、Aさんは長女に見守られ自宅で最期を迎えた。2週後、長女から「私なりに頑張りましたが、十分に介護してあげられなかった。もっとできることがあったのではと考えてしまいます」と訪問看護師に連絡があった。
訪問看護師の長女への対応で適切なのはどれか。
- 「もう少し仕事を休んで傍にいられたらよかったですね」
- 「何をすればよかったのか一緒に考えましょう」
- 「最期までよく介護していたと思いますよ」
- 「仕事に集中してみましょう」
次の文を読み118~120の問いに答えよ。
Aさん(44歳、男性)は、午前9時に発生した震度5強の地震で自宅の2階から慌てて逃げる際に階段から転落した。午前9時30分、Aさんは殿部に激しい痛みが出現し動けなくなったため、救急車で搬送され入院した。
身体所見:体温36.8℃、呼吸数22/分、脈拍100/分、血圧76/38mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)。
検査所見:赤血球300万/μL、Hb9.0g/dL、CRP0.3mg/dL、Na140mEq/L、K4.0mEq/L、濃縮尿、尿比重1.020、尿潜血(+)。
▶午前118
Aさんの状態で考えられるのはどれか。
- 敗血症
- 骨盤骨折
- 硬膜下血腫
- 腰部脊柱管狭窄症
▶午前119
午前11時、Aさんの母親Bさん(80歳)は、余震が続くため避難する途中で転倒し、歩行が困難となった。Bさんは、孫のCさん(14歳、女子)に付き添われて救急車で病院に搬送された。Bさんは、意識は清明で、腰痛を訴えている。バイタルサインは、呼吸数16/分、脈拍90/分、血圧135/80mmHgで、排尿によって着衣が濡れている。
外来で診察を待っている間に、Bさんの隣にいるCさんがうずくまっているのを看護師が発見した。Cさんのバイタルサインは、呼吸数36/分、脈拍110/分、血圧94/40mmHgで、手のしびれ、動悸を訴えている。
看護師の初期対応で優先度が高いのはどれか。
- Bさんの着衣の交換
- Bさんの既往歴の確認
- Cさんの四肢の保温
- Cさんの経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉の測定
▶午前120
Bさんは、歩行が困難であったため入院したが、検査の結果、腰部の打撲のみで他に身体的な問題を認めなかった。日中は眠っていることが多く、夕方になると落ち着かなくなり、大声で家族を呼んだり、家に帰ろうとすることがあった。入院4日後、Bさんは少しずつ歩けるようになり、退院が決まった。自宅が半壊状況のため、福祉避難所に行くことになった。一緒に福祉避難所に行くAさんの妻(42歳)は看護師に「義母は、入院前は大声を出すことはありませんでした。避難所で人に迷惑をかけるのではないかと心配です」と相談した。
看護師のBさんに関する助言内容で適切なのはどれか。
- 福祉避難所では昼間の覚醒を促す。
- 福祉避難所では人との交流を少なくする。
- Bさんの退院を延期できるか医師に相談する。
- 福祉避難所に行ったらすぐに精神科を受診する。
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午後問題のうち状況設定問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」と合わせてご活用ください。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午後 状況設定問題
次の文を読み91~93の問いに答えよ。
Aさん(58歳、男性、会社員)は、身長175cm、体重73kgである。Aさんは、健康診断の胸部エックス線撮影で異常陰影を指摘され、3週前に胸部造影CT検査を受けた。左肺下葉に約8mmの病変が見つかり、精密検査の結果、肺癌(T1N0M0)と診断され、本日、手術目的で入院した。咳嗽、息苦しさ、喀痰はない。喫煙歴があり、20年間20本/日、禁煙後18年である。
バイタルサイン:体温36.9℃、呼吸数14/分、脈拍72/分、整、血圧136/76mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)。
検査所見:赤血球510万/μL、Hb15.6g/dL、Ht47%、白血球6,200/μL、血小板32万/μL、総蛋白7.7g/dL、アルブミン4.2g/dL、空腹時血糖102mg/dL。
呼吸機能所見:%VC76%、FEV1%73%。
▶午後91
入院時の所見で正しいのはどれか。
- 頸部リンパ節の腫脹
- 拘束性換気障害
- 低栄養
- 貧血
▶午後92
Aさんは、入院2日目に胸腔鏡下左下葉切除術を受ける予定である。Aさんは看護師に「全身麻酔で手術を受けるのは初めてです。医師から手術の説明はあったけれど、合併症についてもう一度教えてもらえますか」と質問した。
Aさんに生じる可能性が高い合併症はどれか。
- 気胸
- 反回神経麻痺
- Horner〈ホルネル〉症候群
- Pancoast〈パンコースト〉症候群
▶午後93
Aさんの手術は予定通りの術式で行われ、肺癌は術前診断通りの病期であった。Aさんの術後経過は良好であり、退院日が決定した。Aさんのバイタルサインは、体温36.3℃、呼吸数18/分、脈拍66/分、整、血圧134/76mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)であった。
退院後の生活指導で正しいのはどれか。
- 「インフルエンザワクチンは接種できません」
- 「左手で重い荷物を持たないでください」
- 「少しずつ活動量を増やしてください」
- 「自宅で酸素吸入を行ってください」
次の文を読み94~96の問いに答えよ。
Aさん(43歳、男性、会社員)は、1か月前に右頸部の腫瘤を自覚した。大学病院で非Hodgkin〈ホジキン〉リンパ腫と診断され化学療法導入目的で入院した。
バイタルサイン:体温37.1℃、呼吸数16/分、脈拍84/分、整。
身体所見:顔面に浮腫を認める。
検査所見:Hb12.8g/dL、白血球6,400/μL、総蛋白7.6g/dL、アルブミン4.1g/dL。
胸部造影CT:縦隔リンパ節腫大による上大静脈の圧迫を認める。
▶午後94
Aさんの顔面の浮腫の原因で考えられるのはどれか。
- 発熱
- 貧血
- 低蛋白血症
- 上大静脈の圧迫
▶午後95
AさんはR-CHOP療法(リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)を受けた。
AさんのR-CHOP療法の初日に生じる可能性がある合併症はどれか。
- 脱毛
- 口内炎
- 低血糖
- 好中球減少症
- 腫瘍崩壊症候群
▶午後96
AさんはR-CHOP療法終了後も嘔気・嘔吐が続き、制吐薬の追加投与を受けた。治療後3日、「やっと楽になって食事が摂れるようになったけど、やっぱりつらかった。思い出すだけでも気持ち悪くなります」と話している。
Aさんの次回のR-CHOP療法において、嘔気・嘔吐への対応で適切なのはどれか。
- 1日1,000mLの水分摂取
- 治療前日の夕食の中止
- 治療前の制吐薬の投与
- 抗癌薬の減量
次の文を読み97~99の問いに答えよ。
Aさん(71歳、女性)は夫と10年前に死別し、1人で暮らしている。息子は結婚して他県に住んでいる。Aさんは、3か月前に脳梗塞を発症して要介護1となり、介護老人保健施設に入所した。 Aさんは老人性白内障があるがADLに支障はなく、認知機能やコミュニケーションに問題はない。食事は自力で摂取できる。紅茶が好きで、毎日カップ2、3杯は飲んでいる。我慢できない強い尿意があり尿が漏れてしまうため、下着に尿取りパッドを付けている。トイレには自力で移動でき、下着やズボンの上げ下ろしは自立している。排便は2日に1回である。
▶午後97
Aさんの尿失禁の種類で考えられるのはどれか。
- 溢流性尿失禁
- 機能性尿失禁
- 切迫性尿失禁
- 腹圧性尿失禁
▶午後98
4、5日前からAさんは倦怠感を訴え、ベッドで寝ていることが多くなった。食欲が落ちてきて、1日の水分摂取量も減少した。トイレでの排尿が間に合わないことが多くなり、頻回に尿失禁するようになった。看護師がAさんの尿取りパッドの交換を介助すると尿臭が強く、色も茶褐色であった。Aさんが「おしっこをするとお腹の下の方が痛い。体がだるい」と看護師に訴えたため、体温を測定すると37.5℃であった。看護師がAさんの状況を施設の医師に報告すると、抗菌薬を内服するように指示が出された。
Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 日中に飲水を勧める。
- 下腹部をマッサージする。
- 抗菌薬は自分で管理してもらう。
- 昼間は離床して過ごすように促す。
▶午後99
5日後、Aさんは解熱し、少しずつ食欲が出てきた。下腹部痛は消失し、尿失禁の回数も少なくなった。
症状の再燃を防止するためのAさんへの対応で適切なのはどれか。
- 2時間ごとに排尿誘導する。
- 用手圧迫排尿の方法を指導する。
- 排尿の度に陰部を洗浄するように促す。
- 尿取りパッドの交換回数を増やすように指導する。
次の文を読み100~102の問いに答えよ。
Aちゃん(7歳、女児)は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に来院した。1か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、Aちゃんは体温36.6℃、呼吸数20/分、心拍数84/分、血圧130/80mmHgで、床上安静の指示が出された。
▶午後100
Aちゃんの入院時の看護計画で適切なのはどれか。
- 水分摂取を促す。
- 1日3回の血圧測定を行う。
- 食事の持ち込みを許可する。
- 腰部に消炎鎮痛薬を貼用する。
▶午後101
入院3日。両眼瞼の浮腫と肉眼的血尿は続いていた。看護師がAちゃんのベッドサイドを訪れると、Aちゃんは「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えた。Aちゃんは体温36.6℃、呼吸数20/分、心拍数92/分、血圧148/88mmHgであった。
この状況からAちゃんに起こりうる症状はどれか。
- 眼のかゆみ
- 意識障害
- 耳漏
- 鼻閉
▶午後102
入院して1週が経過した。症状は軽快傾向にあるが床上安静は続いている。仲が良かった同じ病室の児が退院して、Aちゃんはイライラしている。Aちゃんの母親は、毎日昼食後から夕食まで面会をしている。
Aちゃんのストレスに対する看護師の発言で適切なのはどれか。
- 「すぐに退院できるから頑張ろう」
- 「好きなだけテレビや動画を観ていいよ」
- 「ベッドに寝たままプレイルームに行こう」
- 「夕食後もお母さんに付き添ってもらおう」
次の文を読み103~105の問いに答えよ。
A君(5歳、男児)は共働きの両親と3人で暮らしている。2歳6か月で自閉スペクトラム症と診断され、保育所と療育センターに通っている。保育所の健康診断で低身長を指摘され、受診を勧められて両親と来院した。A君は待合室を走ったり診察室の扉を開けたりしていた。診察室に入ると「頑張ろう」と泣きながら叫び、恐怖心を抑えている様子だった。母親は「Aは病院が苦手で、予防接種はAの手足と体を看護師さん3人で抑えて行ってきましたが、繰り返し説明することで、抑えなくても注射ができるようになりました」と話した。
診察の結果、1週後に成長ホルモン分泌刺激試験を行うことになった。母親から「Aが血液検査でパニックを起こすのではないかと心配です」と発言があった。
▶午後103
母親への声かけで適切なのはどれか。
- 「検査があることは当日に説明しましょう」
- 「予防接種ができるのであれば心配ありません」
- 「家でA君に説明できる絵カードをお渡しします」
- 「看護師3人でA君をしっかりと抑えて採血します」
▶午後104
成長ホルモン分泌刺激試験の結果、母親が自宅で毎晩A君に成長ホルモン製剤を注射することになった。外来で母親は注射の手技を習得し、A君も注射に慣れた。
自宅での注射に向けて、母親に確認する事項で優先度が高いのはどれか。
- 保育所でのA君の様子
- A君と家族の日課
- 家族の経済状況
- 祖父母の居住地
▶午後105
3か月後、自宅でのA君への成長ホルモン製剤の注射は順調に実施されている。外来受診時に母親から看護師に「Aが通っている療育センターにも相談しましたが、Aは自閉スペクトラム症であるだけでなく、注射もしているので就学のことを考えると心配です。通常の学級に通わせたいと考えているのですが、通常の学級への就学について教えてください」と相談があった。
看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「お母さんが学校で待機する必要があります」
- 「就学する学級は受入れ先の校長が決定します」
- 「通常の学級に籍を置くと通級指導は受けられません」
- 「A君の特性に合わせた配慮を学校に求めることができます」
次の文を読み106~108の問いに答えよ。
Aさん(32歳、初産婦)は、夫と2人で暮らしている。骨盤位のために妊娠38週0日に予定帝王切開術で午前11時に男児を出産した。分娩時出血量は480mLであった。出生後、手術室で男児と面会をして「無事に生まれてきてくれてありがとう」と話した。帰室後、子宮底は臍高、硬度良好、悪露は赤色で20gであった。後陣痛と創部痛があり夜間に鎮痛薬を使用した。
▶午後106
帝王切開術後1日、午前9時、子宮底は臍下1横指、硬度良好、バイタルサインは体温36.9℃、呼吸数18/分、脈拍72/分、整、血圧110/70mmHgであった。夜間に排ガスを認めた。Aさんは「痛み止めを使用した後は眠れましたが、また痛みが出てきました。こんな状態で動けるか心配です。この後の予定を知りたいです」と話した。
このときのAさんへの説明で適切なのはどれか。
- 「入院中は毎日、タオルで身体を拭きます」
- 「膀胱に入れている管は明日抜きます」
- 「今日から歩行を開始します」
- 「食事は明日からです」
▶午後107
帝王切開術後3日、子宮底は臍下3横指、悪露は褐色であった。乳房に熱感があり、乳管は左右とも3本開通しており、移行乳の分泌を認める。看護師が訪室するとAさんは「まだ、お腹の創が痛くて、動くのはつらいです」と話す。慣れない手付きで児に授乳をしながら「上手にできなくてごめんね」と児の顔を見て語りかけている。Aさんと児の目と目が合う様子がみられる。
アセスメントで適切なのはどれか。
- 子宮復古が遅れている。
- 乳汁分泌が遅れている。
- 母子相互作用がみられる。
- マタニティブルーズである。
▶午後108
帝王切開術後5日、診察の結果、明日退院することになった。Aさんの乳房は緊満しており、乳管は左右とも5、6本開通している。母児同室を行い、児の哺乳の欲求に合わせて1日10回の授乳を行っている。「母乳で育てたいと思っています。でもおっぱいが張ってつらいです。この子も上手に吸ってくれません」と看護師に話した。
このときの看護師の説明で適切なのはどれか。
- 「授乳の回数を減らしましょう」
- 「授乳前に乳輪を柔らかくしましょう」
- 「授乳と授乳の間は乳房を温めましょう」
- 「乳房の緊満が強くなるのはこれからです」
次の文を読み109~111の問いに答えよ。
Aさん(65歳、男性)は、妻と自営業を営んでおり、2人で暮らしている。2か月前に仕事で大きな失敗をし、謝罪と対応に追われ、あまり夜に眠れなくなり、食欲不振が続いている。1か月前から気分が落ち込み、仕事で妻から間違いを指摘されたことで自信をなくしていた。Aさんは死んでしまいたいと思い、夜に自宅でロープを使って自殺を図ろうとしたところを妻に見つけられた。妻に付き添われ、精神科病院を受診し、うつ病と診断された。受診当日に入院し、抗うつ薬の内服が開始された。Aさんは「生きていても仕方がない。どうせ誰も分かってくれない」と看護師に話した。
▶午後109
このときの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 「生きていれば良いことがありますよ」
- 「薬を飲むと数日で効いて楽になります」
- 「悲しいことが続くときは誰にでもあります」
- 「Aさんがつらい状況にあることを私は心配しています」
▶午後110
Aさんはその後しばらく会話をしたり、食事も少し食べられたりしていたが、入院3日から、臥床したままで1日中全く動かず、昏迷状態になった。検査の結果、軽度の脱水以外の異常はなかった。治療として修正型電気けいれん療法が開始されることになり、実施後20分でAさんは覚醒し、その後の観察中にけいれん発作は認めなかった。実施後30分、Aさんは突然起き上がり興奮し、大きな声で「仕事に行く」と言って病室から出ていこうとした。看護師が制止し、一緒に座って話を聞いたところ、見当識障害、記憶障害、注意障害が認められた。
Aさんの状態で正しいのはどれか。
- せん妄
- 躁状態
- 不安発作
- 前向性健忘
▶午後111
入院1か月が経過し、Aさんは夜間の睡眠がとれるようになり、食事は全量摂取している。妻から間違いを指摘されたことを思い出し、「何をやってもきっと失敗するだけだ。今度はもっと大きな失敗をして仕事を辞めることになる。だから自分はだめな人間だ。努力しても意味がない」と看護師に言った。
Aさんへの治療法で最も適切なのはどれか。
- 森田療法
- 集団精神療法
- 認知行動療法
- 社会生活技能訓練〈SST〉
次の文を読み112~114の問いに答えよ。
Aさん(24歳、女性)は大学卒業後、一般企業に就職したが、何度も自宅の鍵を閉めたかどうかを確認するため、遅刻を繰り返した。連絡せずに複数回の遅刻があったことを上司のBさんから強く注意され、うつ状態となったため精神科外来を受診したところ、強迫性障害と診断され、選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉が処方された。
▶午後112
内服を始めて1週後、Aさんは看護師に「鍵を閉めたかどうかの確認が増え、睡眠時間が減ってつらい」と訴えている。
看護師の声かけで適切なのはどれか。
- 「主治医に薬の変更を相談しましょう」
- 「睡眠状況を具体的に教えてください」
- 「Bさんに別の部署に異動したいと伝えてみましょう」
- 「鍵を閉めたかどうか気になるときは別のことを考えましょう」
▶午後113
受診に同行していた母親からは「Aから『私の代わりに鍵が閉まっているか見てきてほしい』といった要望が多い。それに従わないと『どうして私のつらさを分かってくれないの』と大きな声を出す。どのように関わればよいか分からない」と看護師に相談があった。
母親への看護師の対応で適切なのはどれか。
- 要望に応じ続ける方がよいと助言する。
- 治療の効果が得られるまで待つように伝える。
- 母親が疾患をどのように理解しているか確認する。
- Aさんが大きな声を出しても反応しないように助言する。
▶午後114
選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉の内服を始めてから2か月が経過し、Aさんは外出中に鍵を閉め忘れたかもしれないという考えが強くなり、外出から予定より早く帰宅することがある。Aさんは「鍵を閉め忘れていないかの確認を減らしたい」と看護師に相談した。
Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。
- 外出を控えるよう助言する。
- 外出するときは誰かに付き添ってもらうよう提案する。
- 鍵の閉め忘れが気になる理由を考えてみるよう伝える。
- 鍵の閉め忘れが特に気になるときの前後の状況を振り返るよう促す。
次の文を読み115~117の問いに答えよ。
Aさん(14歳、男子、特別支援学校の中学生)はDuchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで両親、弟(7歳)と2階建ての家に4人で暮らしている。呼吸障害が進行したため非侵襲的陽圧換気療法を導入する目的で入院した。Aさんの呼吸状態は安定し、両親に対するバッグバルブマスクによる用手換気の指導が終了したため、自宅に退院し訪問看護を毎日利用して療養生活を続けることになった。両親は「日常の呼吸管理について退院後に対応できるか心配です」と病棟の看護師に話した。
▶午後115
Aさんの両親に対する看護師の指導で適切なのはどれか。
- 息苦しいときは非侵襲的陽圧換気の吸気圧を上げる。
- 人工呼吸器が動かないときはすぐに救急車を要請する。
- 人工呼吸器が過剰送気を示すときは回路が外れていないか確認する。
- マスクの周囲から空気が漏れるときはマスクのベルトをきつく締める。
▶午後116
退院後1週。Aさんの父親から「最近、大雨や落雷、地震による被災の報道が多くて、Aは人工呼吸器を付けているし、弟もまだ小さいので不安です。災害に備え何をすればよいでしょうか」と訪問看護師に相談があった。
訪問看護師がAさんの父親に説明する内容で優先度が高いのはどれか。
- 非常用電源の選び方
- 福祉避難所への移動手段
- 足踏み式吸引器の使用方法
- ハザードマップの確認方法
▶午後117
退院後6か月。Aさんは人工呼吸器を装着して特別支援学校に通学することにも慣れてきた。Aさんの母親から「弟がインフルエンザと診断された。弟は2階の子ども部屋、Aは1階のリビングで過ごしている。家族全員がインフルエンザの予防接種を受けた。Aにインフルエンザがうつらないか心配」と訪問看護師に連絡があった。
訪問看護師の対応で適切なのはどれか。
- Aさんが特別支援学校を2週間休むことを勧める。
- Aさんが感染予防の目的で入院することを医師に相談する。
- Aさんは予防接種を受けているのでうつらないと説明する。
- ケアを父母で分担し、弟の担当は弟以外と接触しないことを提案する。
次の文を読み118~120の問いに答えよ。
Aさん(72歳、男性)は、妻と2人暮らしで子どもはいない。定年後は2人で旅行するのが趣味であった。Aさんは、1か月前から残尿感や夜間頻尿が気になり病院を受診した結果、前立腺癌と診断され根治的前立腺摘出手術を受けた。退院後は、手術後の補助療法として、外来で放射線の外照射療法を行うことになっている。
▶午後118
放射線外来の看護師が行うAさんへの説明で正しいのはどれか。
- 「入浴直後に照射部位の観察をしましょう」
- 「照射後は照射部位に冷湿布を貼りましょう」
- 「照射部位の皮膚は乾燥させておきましょう」
- 「照射部位は強くこすらないようにしましょう」
▶午後119
Aさんの放射線療法が開始され初回の照射を終えた。放射線外来の看護師は、終了後にAさんへ声をかけた。Aさんは「ベッドは硬いし、最後まで同じ姿勢でいることがとても苦痛です。大きな音がするので恐怖も感じます」と訴えた。
このときの看護師の説明で正しいのはどれか。
- 「次回から照射中は傍に付き添います」
- 「治療体位をとるための固定具を工夫してみます」
- 「照射時間を短くできるよう主治医に相談してみます」
- 「照射中に体位変換ができるよう放射線技師に相談します」
▶午後120
Aさんが放射線治療を終了して半年後、腰部と右大腿部の痛みが出現した。倦怠感と食欲不振が続いたため病院を受診し精密検査を受けた。骨転移していることが分かり、Aさんと妻に主治医から余命と治療方針の説明があった。Aさんはその場で「痛みを取り除いてほしい。つらい治療は受けたくない」と訴え、3日後に緩和ケア病棟に入院した。
入院翌日、受け持ちの看護師Bが、プリセプターである看護師に「今朝、奥さんの顔色が悪くふらついていたので声をかけると『夫の最期を受け入れられない気がして不安です』と打ち明けられました。昨夜も眠らずにAさんに付き添っていたようでした。奥さんにどう対応したらよいのでしょうか」と相談した。
プリセプターである看護師が看護師Bに助言する内容で適切なのはどれか。
- 妻がAさんの死を受け入れられるよう妻を励ますこと
- 妻がAさんへの思いを看護師Bに語る時間をつくること
- Aさんの予後について再度主治医から妻へ説明するよう調整すること
- 妻がAさんの死を受け入れられるまで夜も付き添うよう妻に伝えること
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
令和6年2月11日(日)に実施された第113回看護師国家試験について、午後問題のうち必修問題の正答と解説を示します。
「国民衛生の動向2024/2025」で内容を解説している問題に関しては、その参照章・ページを示しているので、同書を併用しながらの利用をおすすめします。
▼第113回看護師国家試験
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
午後 必修問題
▶午後1改題
令和4年(2022年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。
- 77年
- 82年
- 87年
- 92年
▶午後3
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 失業手当の給付
- 年少者の労働条件
- 過労死に関する調査研究
- 労働者に対する健康診断
▶午後4
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
- L字バーを設置する。
- 離床センサーを設置する。
- 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
- ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
▶午後5
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 都道府県ナースセンターの長
▶午後6
成長・発達における順序性で正しいのはどれか。
- 頭部から脚部へ
- 微細から粗大へ
- 複雑から単純へ
- 末梢から中心へ
▶午後7
第二次性徴が発現し始めた思春期に関心が向くのはどれか。
- 善悪の区別
- 仕事と家庭の両立
- 自己の身体の変化
- 経済力の確保と維持
▶午後8
老化に伴う視覚の変化で正しいのはどれか。
- 視野が狭くなる。
- 近くが見やすくなる。
- 色の識別がしやすくなる。
- 明暗順応の時間が短縮する。
▶午後9
人口統計資料集2020年版における生涯未婚率(50歳時の未婚割合)で、平成22年(2010年)から令和2年(2020年)の推移で適切なのはどれか。
- 変化はない。
- 下降し続けている。
- 上昇し続けている。
- 上昇と下降を繰り返している。
▶午後10改題
令和5年(2023年)の人口動態統計における合計特殊出生率に最も近いのはどれか。
- 0.7
- 1.2
- 1.7
- 2.2
▶午後12
膵管と合流して大十二指腸乳頭(Vater〈ファーター〉乳頭)に開口するのはどれか。
- 肝管
- 総肝管
- 総胆管
- 胆嚢管
▶午後13
正期産となる出産時期はどれか。
- 妊娠35週0日から39週6日
- 妊娠36週0日から40週6日
- 妊娠37週0日から41週6日
- 妊娠38週0日から42週6日
▶午後14
器質的変化で嚥下障害が出現する疾患はどれか。
- 食道癌
- 脳血管疾患
- 筋強直性ジストロフィー
- Guillain-Barré〈ギラン・バレー〉症候群
▶午後15
高血圧が原因で起こりやすいのはどれか。
- 脳出血
- 脳塞栓症
- 脳動静脈奇形
- 急性硬膜下血腫
▶午後16
手術予定の患者が服用している場合、安全のために術前の休薬を検討するのはどれか。
- 鉄剤
- 抗血小板薬
- 冠血管拡張薬
- プロトンポンプ阻害薬
▶午後17
看護過程における客観的情報はどれか。
- 家族の意見
- 患者の表情
- 患者の痛みの訴え
- 患者の病気に対する思い
▶午後18
フィジカルアセスメントで問診の次に行うのはどれか。
- 視診
- 触診
- 打診
- 聴診
▶午後19
男性の導尿でカテーテルを挿入するとき、体幹に対する頭部側からの挿入角度はどれか。
- 0~10度
- 40~50度
- 80~90度
- 120~130度
▶午後20
床上で排便しやすい体位はどれか。
- 仰臥位
- 側臥位
- Sims〈シムス〉位
- Fowler〈ファウラー〉位
▶午後22
成人の静脈血採血の穿刺部位で適切なのはどれか。
- 腋窩静脈
- 上腕静脈
- 腕頭静脈
- 肘正中皮静脈
▶午後23
自動体外式除細動器〈AED〉を使用するときに、胸骨圧迫を中断するのはどれか。
- 電源を入れるとき
- 電極パッドを貼るとき
- 心電図の解析中
- 電気ショックの直後
▶午後24
側臥位における褥瘡の好発部位はどれか。
- 後頭部
- 耳介部
- 仙骨部
- 肩甲骨部
▶午後25
緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。
- コデイン
- アスピリン
- アトロピン
- ジゴキシン
- フェニトイン
資料 厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験、第113回看護師国家試験の問題および正答について」
注 当ページに掲載する解説は、看護師国家試験を解く上での理解しやすさを重視しているため、本来はより専門的・学術的な説明や議論がある部分を一部省略しています。正確な情報を掲載するように努めていますが、特に医療・看護行為や疾病、薬剤等の説明において、その正確性を保証するものではありませんので、学習以外での使用はお控え下さい。
▼第113回看護師国家試験
テーマ別
必修問題まとめ
①国民衛生の動向対応/②看護の倫理・対象/③人体の構造と機能・健康障害・薬物/④看護技術
年次別
第113回/第112回/第111回/第110回/第109回/第108回/第107回/第106回/第105回/第104回/第103回/第102回
看護師国家試験の問題は、大きく必修問題と一般問題・状況設定問題の二つに分けられます。
合格のためには、①必修問題(1問1点)で50点中40点以上(80%以上)、②一般問題(1問1点)・状況設定問題(1問2点)で250点中約160点(毎年変動)以上の二つの基準を満たす必要があります。つまり、一般問題・状況設定問題で合格基準を突破しても、必修問題で39問以下の正解しかできなければ不合格となります(不適切問題として除外等されない場合)。
問題数に対して必修問題の合格ラインが高く、看護師試験の学習としては、まず基礎的な土台を固めて必修問題を落とさないことが最重要であり、その後、より応用的な知識を身に付けて一般問題・状況設定問題で点数を積み上げていく方針が定番となっています。
必修問題は重要な基本的事項を問うものとされ、問題内容から午前と午後のそれぞれ最初の25問、合計50問が該当すると一般的に考えられます(必修問題の箇所は公表されていないので不確定)。
その範囲・難易度は看護師国家試験出題基準に沿って限られ、過去の問題と同内容・傾向の問題がたびたび出題されるため、過去問の対策がとくに重要です。
例えば、第111回(2022年)看護師国家試験の必修問題が、110回から101回までの10年間の必修問題部分で何問出題されたかをみると、必修問題として不適当とされた2問を除いた48問のうち、10年間の必修問題で類似内容の問題は28問(58.3%)出題されています。
つまり、111回試験では、過去10年間の必修問題を解き、周辺知識を含めてしっかりと理解すれば、必修問題の半分以上が確実に正答できたということであり、過去問対策の重要性がわかります。
当サイトでは最新の看護師国家試験出題基準に沿って、113回(2024年)から102回(2013年)までの12年分の看護師国家試験に出題された必修問題を網羅・解説しています。
衛生テキスト「国民衛生の動向」と合わせてご活用ください。
▼看護師国家試験必修問題まとめ
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
【必修】大項目1「健康の定義と理解」
| 中項目(出題範囲) | 小項目(キーワード) |
| A.健康の定義 |
世界保健機関〈WHO〉の定義 ウェルネスの概念 |
| B.健康に関する指標 | 総人口 年齢別人口 労働人口 将来推計人口 世帯数 婚姻、家族形態 出生と死亡の動向 死因の概要 平均余命、平均寿命、健康寿命 |
| C.受療状況 | 有訴者の状況 有病率、罹患率、受療率 外来受診の状況 入院期間 |
A.健康の定義
世界保健機関〈WHO〉の定義
第1編2章 12.世界保健機関〈WHO〉 p36~39
世界保健機関〈WHO〉が定義する健康について正しいのはどれか。
- 単に病気や虚弱のない状態である。
- 国家に頼らず個人の努力で獲得するものである。
- 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。
- 経済的もしくは社会的な条件で差別が生じるものである。
一次予防・二次予防・三次予防
第3編1章 1.1〕生活習慣病の概念 p80
生活習慣病の一次予防はどれか。
- 早期治療
- 検診の受診
- 適切な食生活
- 社会復帰を目指したリハビリテーション
疾病や障害に対する二次予防はどれか。
- 早期治療
- 予防接種
- 生活習慣の改善
- リハビリテーション
生活習慣病の三次予防はどれか。
- 健康診断
- 早期治療
- 体力づくり
- 社会復帰のためのリハビリテーション
B.健康に関する指標
総人口
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
令和5年(2023年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。
- 1億人
- 1億400万人
- 1億2,400万人
- 1億4,400万人
年齢別人口
令和5年(2023年)10月1日現在の年齢3区分別人口構成割合は、
- 年少人口(0~14歳):11.4%
- 生産年齢人口(15~64歳):59.5%
- 老年人口(65歳以上):29.1%
で、少子高齢化により年少人口と生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
人口年齢区分における15歳から64歳までの年齢区分はどれか。
- 従属人口
- 年少人口
- 老年人口
- 生産年齢人口
日本の令和5年(2023年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
日本における令和5年(2023年)の総人口に占める老年人口の割合で最も近いのはどれか。
- 19%
- 29%
- 39%
- 49%
令和5年(2023年)の日本の人口推計で10年前より増加しているのはどれか。
- 総人口
- 年少人口
- 老年人口
- 生産年齢人口
将来推計人口
第2編1章 1.人口の動向 p41~44
令和5年(2023年)推計による日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の将来推計人口に最も近いのはどれか。
- 6,700万人
- 8,700万人
- 1億700万人
- 1億2,700万人
日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の65歳以上人口が総人口に占める割合に最も近いのはどれか。
- 24%
- 39%
- 54%
- 69%
世帯数
令和4年(2022年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に、
①単独世帯:32.9%
②夫婦と未婚の子のみの世帯:25.8%
③夫婦のみの世帯:24.5%
④ひとり親と未婚の子のみの世帯:6.8%
⑤三世代世帯:3.8%
となっている。なお、②~④を合わせた核家族世帯は57.1%となっている。
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、単独世帯の占める割合はどれか。
- 12.9%
- 32.9%
- 52.9%
- 72.9%
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で次の世帯構造のうち最も少ないのはどれか。
- 単独世帯
- 三世代世帯
- 夫婦のみの世帯
- 夫婦と未婚の子のみの世帯
▶113回午前9
核家族はどれか。
- 兄弟姉妹のみ
- 夫婦と子ども夫婦
- 夫婦と未婚の子ども
- 夫婦とその親と夫婦の子ども
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。
- 30%
- 45%
- 60%
- 75%
平均世帯人員
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。
- 1.25
- 2.25
- 3.25
- 4.25
65歳以上の者のいる世帯の割合
第2編1章 2.世帯の動向 p44~48
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。
- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
平均初婚年齢
第2編2章 8.婚姻 p68~69
令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。
- 19.7歳
- 24.7歳
- 29.7歳
- 34.7歳
生涯未婚率
第2編2章 8.婚姻 p68~69
人口統計資料集2020年版における生涯未婚率(50歳時の未婚割合)で、平成22年(2010年)から令和2年(2020年)の推移で適切なのはどれか。
- 変化はない。
- 下降し続けている。
- 上昇し続けている。
- 上昇と下降を繰り返している。
出生数
第2編2章 2.出生 p51~55
令和5年(2023年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。
- 40万人
- 70万人
- 100万人
- 130万人
合計特殊出生率
第2編2章 2.出生 p51~55
日本の令和5年(2023年)における合計特殊出生率はどれか。
- 0.70
- 1.20
- 1.70
- 2.20
母の年齢階級別出生率
第2編2章 2.出生 p51~55
日本の令和5年(2023年)における母の年齢階級別出生率が最も高いのはどれか。
- 20~24歳
- 25~29歳
- 30~34歳
- 35~39歳
- 40~44歳
死亡数
第2編2章 3.死亡 p55~64
日本の令和5年(2023年)の死亡数に近いのはどれか。
- 118万人
- 138万人
- 158万人
- 178万人
死因順位
令和5年(2023年)の主要死因別にみた死亡順位は以下のとおりである。
第1位:悪性新生物〈腫瘍〉
第2位:心疾患
第3位:老衰
第4位:脳血管疾患
第5位:肺炎
第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58
日本の令和5年(2023年)における主要死因別にみた死亡率が最も高いのはどれか。
- 肺炎
- 心疾患
- 悪性新生物〈腫瘍〉
- 脳血管疾患
令和5年(2023年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患の順位はどれか。
- 1位
- 2位
- 3位
- 4位
小児の死因順位
令和5年(2023年)の年齢階級別にみた小児の死因の第1位は以下のとおりである。
0歳:先天奇形、変形及び染色体異常
1~4歳:先天奇形、変形及び染色体異常
5~9歳:悪性新生物〈腫瘍〉
10~14歳:自殺
第2編2章 3.2〕死因の概要 p56~58
日本における令和5年(2023年)の5~9歳の子どもの死因で最も多いのはどれか。
- 肺炎
- 心疾患
- 不慮の事故
- 悪性新生物〈腫瘍〉
悪性新生物〈腫瘍〉
第2編2章 3.3〕死因―悪性新生物〈腫瘍〉 p58~59
日本における令和5年(2023年)の部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。
- 胃
- 肝及び肝内胆管
- 気管、気管支及び肺
- 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸
自殺の動機
第2編2章 3.7〕(2)自殺 p61~63
警察庁の「令和5年(2023年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。
- 学校問題
- 家庭問題
- 勤務問題
- 健康問題
死亡場所
- 令和4年(2022年)の死亡場所は、病院が64.5%と最も多く、次いで自宅が17.4%となっている。
- なお、過去の意識調査では、人生の最後をむかえるときに生活したい場所として自宅が最も高く、在宅医療の充実が図られている。
第4編1章 3.1〕在宅医療 p170
令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのはどれか。
- 自宅
- 病院
- 老人ホーム
- 介護医療院・介護老人保健施設
平均寿命
第2編3章 生命表 p70~73
平均寿命で正しいのはどれか。
- 0歳の平均余命である。
- 20歳の平均余命である。
- 60歳の平均余命である。
- 死亡者の平均年齢である。
令和4年(2022年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。
- 77年
- 82年
- 87年
- 92年
日本の令和4年(2022年)における男性の平均寿命はどれか。
- 71.05年
- 76.05年
- 81.05年
- 86.05年
健康寿命
第3編1章 2.1〕(6)健康寿命の延伸 p87~88
世界保健機関〈WHO〉が平成12年(2000年)に提唱した「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」はどれか。
- 健康寿命
- 健康余命
- 平均寿命
- 平均余命
C.受療状況
有訴者
第2編4章 1.1〕有訴者の状況 p74
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)で正しいのはどれか。
- 6.5
- 76.5
- 276.5
- 476.5
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。
- 腰痛
- もの忘れ
- 体がだるい
- 目のかすみ
- 手足の関節が痛む
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。
- 頭痛
- 腰痛
- 体がだるい
- 目のかすみ
通院者
第2編4章 1.2〕通院者の状況 p74~75
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における通院者率が男女ともに最も高いのはどれか。
- 糖尿病
- 腰痛症
- 高血圧症
- 眼の病気
受療率
第2編4章 2.2〕受療率 p77~78
令和2年(2020年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。
- 新生物〈腫瘍〉
- 呼吸器系の疾患
- 消化器系の疾患
- 内分泌、栄養及び代謝疾患
▼看護師国家試験必修問題まとめ
「国民衛生の動向」は衛生の状況に関わる統計を網羅し、毎年直近の数値に更新した最新版を刊行しています。
看護師国家試験では、人口や世帯、健康状況などの統計数値を問う問題が毎年必ず出題されます。とくに、80%以上の正答率が求められる必修問題にも多く出題されており、受験者にとって決して落とせない部分になっています。
このページでは、看護師試験に頻出するテーマごとに、113回(2024年)から104回(2015年)の10年分の問題の中から「国民衛生の動向」がカバーする統計問題をほぼすべてピックアップし、115回試験に合わせた数値(「国民衛生の動向2024/2025」準拠)とともに示します。
これまで出題された統計問題の傾向を把握し、「国民衛生の動向」を参照して、より詳細なデータや推移、その対策や制度などを関連付けて確認することで、様々な問題に対応できる基礎力を身に付けていただければ幸いです。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
いつの統計が出題されるか
看護師国家試験に使用される統計調査は毎年実施されるものが多く、古い数値が掲載された参考書や問題集で学習していると間違える可能性があります。特に必修問題として人口や世帯数などが多く問われ、そこで落とすことは避けなければなりません。
ただし、看護師国家試験では試験日時点で最新の統計が出題されることはほぼありません。以下に参考として、2020年2月に実施された第109回試験の問題に使われた統計と、その公表日を示します。
| 問題に使われた統計 | 統計公表日 | |
| 2017年 | 人口推計 | 2018年4月 |
| 2017年 | 国民生活基礎調査(世帯) | 2018年7月 |
| 2017年 | 人口動態統計 | 2018年6月(概数) 2018年9月(確定数) |
| 2017年 | 簡易生命表 | 2018年7月 |
| 2017年 | 国民健康・栄養調査 | 2018年9月 |
多くの統計が、看護師国家試験が実施される時点から1年以上前に公表されていることがわかります。
「国民衛生の動向」では毎年8月に最新の数値に更新した最新版を発行していますが、看護師国家試験に用いられる数値はその前年版のものが中心となるため、例えば2026年に実施される115回試験では、2024年8月発売の「2024/2025」版から出題されると考えられます。
ただし、これまでの試験内容をみると、1年古いデータや新しいデータを覚えていたとしても正答に影響するという問題はごく小数であり、十分に配慮がなされていると思われるため、過度に統計の時期や細かい数値を気にする必要はなく、近年の動向や数値を直近の「国民衛生の動向」等の参考書でしっかり押さえることがまず重要となります。
統計別問題目次
人口静態
第2編1章 人口静態 p41~50
人口静態統計
- 人口静態はある時点における人口や年齢別などの静止した姿を指す。
- 総務省統計局が実施する国勢調査はその主要統計で、5年に1回実施され、その中間年は人口推計が公表される。
日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。
- 患者調査
- 国勢調査
- 国民生活基礎調査
- 国民健康・栄養調査
総人口
令和5年(2023年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。
- 1億人
- 1億400万人
- 1億2,400万人
- 1億4,400万人
労働力人口
- 労働力人口とは15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計で、令和5年(2023年)平均で6925万人(男3801万人・女3124万人)である。
- 平成22年(2010年)には6632万人(男性3850万・女性2783万人)であり、男性が微減しているのに対し、女性は300万人程度増加している。
▶111回午前1改題
労働力調査による労働力人口の令和5年(2023年)平均に最も近いのはどれか。
- 4,900万人
- 5,900万人
- 6,900万人
- 7,900万人
▶113回午前28改題
労働力調査における平成22年(2010年)と令和5年(2023年)の男性と女性の労働力人口の比較で正しいのはどれか。
- 男性、女性とも減少している。
- 男性、女性とも増加している。
- 男性は減少し、女性は増加している。
- 男性は増加し、女性は減少している。
総人口に占める年齢3区分別人口割合
令和5年(2023年)10月1日現在の年齢3区分別人口構成割合は、
- 年少人口(0~14歳):11.4%
- 生産年齢人口(15~64歳):59.5%
- 老年人口(65歳以上):29.1%
で、少子高齢化により年少人口と生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。
▶104回午後7
人口年齢区分における15歳から64歳までの年齢区分はどれか。
- 従属人口
- 年少人口
- 老年人口
- 生産年齢人口
日本の令和5年(2023年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
日本における令和5年(2023年)の総人口に占める老年人口の割合で最も近いのはどれか。
- 19%
- 29%
- 39%
- 49%
令和5年(2023年)の日本の人口推計で10年前より増加しているのはどれか。
- 総人口
- 年少人口
- 老年人口
- 生産年齢人口
将来推計人口
令和5年(2023年)推計による日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の将来推計人口に最も近いのはどれか。
- 6,700万人
- 8,700万人
- 1億700万人
- 1億2,700万人
日本の将来推計人口で令和52年(2070年)の65歳以上人口が総人口に占める割合に最も近いのはどれか。
- 24%
- 39%
- 54%
- 69%
世帯構造別割合
令和4年(2022年)の世帯構造別にみた世帯割合は多い順に、
①単独世帯:32.9%
②夫婦と未婚の子のみの世帯:25.8%
③夫婦のみの世帯:24.5%
④ひとり親と未婚の子のみの世帯:6.8%
⑤三世代世帯:3.8%
となっている。なお、②~④を合わせた核家族世帯は57.1%となっている。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で次の世帯構造のうち最も少ないのはどれか。
- 単独世帯
- 三世代世帯
- 夫婦のみの世帯
- 夫婦と未婚の子のみの世帯
核家族はどれか。
- 兄弟姉妹のみ
- 夫婦と子ども夫婦
- 夫婦と未婚の子ども
- 夫婦とその親と夫婦の子ども
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。
- 30%
- 45%
- 60%
- 75%
世帯割合・平均世帯数の推移
- 近年の世帯割合の推移をみると、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」が増加傾向、「夫婦と未婚の子のみの世帯」と「三世代世帯」が減少傾向にある。
- こうした世帯構造の変化を受けて、令和4年(2022年)の平均世帯人員は2.25人と減少が続いている。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。
- 1.25
- 2.25
- 3.25
- 4.25
日本の世帯構造の平成4年(1992年)から30年間の変化で正しいのはどれか。
- 単独世帯数は増加している。
- 平均世帯人数は増加している。
- ひとり親と未婚の子のみの世帯数は3倍になっている。
- 65歳以上の者のいる夫婦のみの世帯数は2倍になっている。
日本の最近10年の成人を取り巻く社会状況で正しいのはどれか。
- 生産年齢人口の占める割合の増加
- 単独世帯の占める割合の増加
- 非正規雇用者の比率の低下
- 平均初婚年齢の低下
65歳以上の者のいる世帯の世帯割合
令和4年(2022年)の65歳以上の者のいる世帯は2747万世帯で、総世帯数の50.6%と半数近くを占めている。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。
- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
65歳以上の者のいる世帯の世帯構造別割合
令和4年(2022年)の65歳以上の者のいる世帯の構造別割合は多い順に、
①夫婦のみの世帯:32.1%
②単独世帯:31.8%
③親と未婚の子のみの世帯:20.1%
④三世代世帯:7.1%
で、①~③は増加傾向、④三世代世帯は大幅に減少傾向にある。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における65歳以上の高齢者がいる世帯について正しいのはどれか。
- 単独世帯は1割である。
- 三世代世帯は3割である。
- 夫婦のみの世帯は4割である。
- 親と未婚の子のみの世帯は2割である。
人口動態
第2編2章 人口動態 p51~69
出生数
令和5年(2023年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。
- 40万人
- 70万人
- 100万人
- 130万人
合計特殊出生率
日本の令和5年(2023年)における合計特殊出生率はどれか。
- 0.70
- 1.20
- 1.70
- 2.20
母の年齢階級別出生率
▶108回午前64改題
日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。
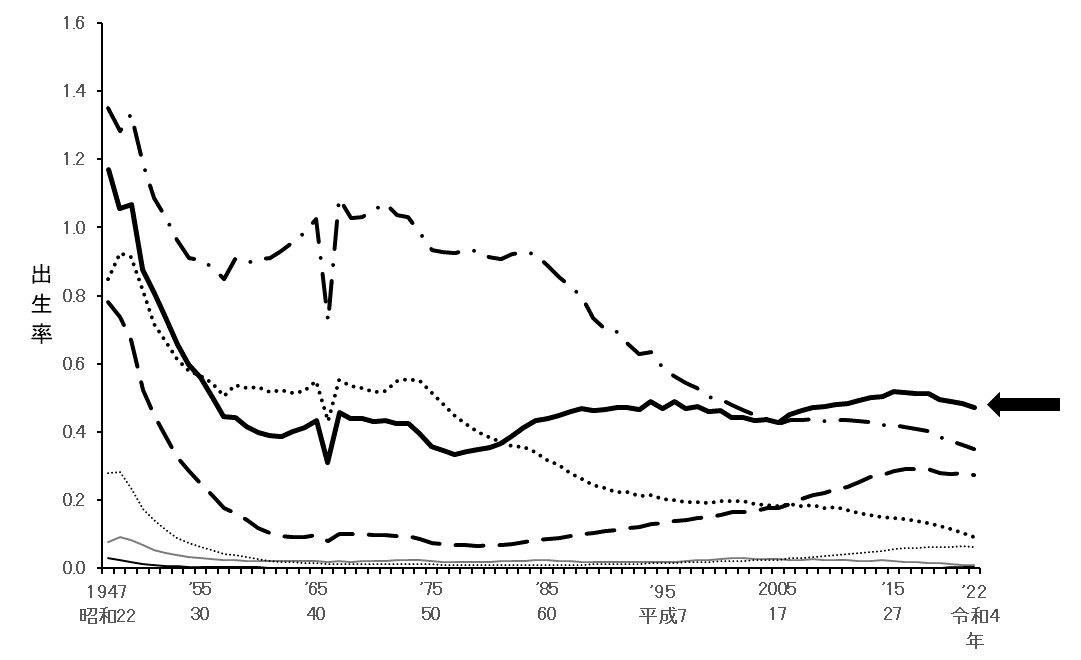
図の矢印で示してある年齢階級はどれか。
- 20~24歳
- 25~29歳
- 30~34歳
- 35~39歳
第一子出生時の母親の平均年齢
令和5年(2023年)の人口動態統計における日本の出生で正しいのはどれか。
- 出生数は過去10年で最低である。
- 出生数は80万人を上回っている。
- 合計特殊出生率は1.10を下回っている。
- 第1子出生時の母の平均年齢は30歳未満である。
死亡数・率
日本の令和5年(2023年)の死亡数に近いのはどれか。
- 118万人
- 138万人
- 158万人
- 178万人
主要死因別死亡順位
令和5年(2023年)の主要死因別にみた死亡順位は以下のとおりである。
第1位:悪性新生物〈腫瘍〉
第2位:心疾患
第3位:老衰
第4位:脳血管疾患
第5位:肺炎
令和5年(2023年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患の順位はどれか。
- 1位
- 2位
- 3位
- 4位
小児の死因第1位
令和5年(2023年)の年齢階級別にみた小児の死因の第1位は以下のとおりである。
0歳:先天奇形、変形及び染色体異常
1~4歳:先天奇形、変形及び染色体異常
5~9歳:悪性新生物〈腫瘍〉
10~14歳:自殺
令和5年(2023年)の人口動態統計において、1~4歳の死因で最も多いのはどれか。
- 肺炎
- 心疾患
- 悪性新生物〈腫瘍〉
- 不慮の事故
- 先天奇形、変形及び染色体異常
令和5年度(2023年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。
- 0歳
- 1~4歳
- 5~9歳
- 10~14歳
小児の不慮の事故の原因第1位
令和4年(2022年)の年齢階級別にみた小児の不慮の事故の原因の第1位は以下のとおりである。
0歳:窒息
1~4歳:窒息
5~9歳:溺死及び溺水
10~14歳:溺死及び溺水
令和4年(2022年)の人口動態調査で、5~9歳の死因における不慮の事故の原因で最も多いのはどれか。
- 窒息
- 交通事故
- 転倒・転落
- 溺死および溺水
悪性新生物〈腫瘍〉による死亡状況
- 令和5年(2023年)の悪性新生物〈腫瘍〉による死亡数は38.2万(男性22.1万人・女性16.1万人)で、主要死因の第1位である。
- 部位別にみると、総数および男性では「気管、気管支及び肺」が、女性では「大腸」(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)が最も多い。
日本における令和5年(2023年)の部位別にみた悪性新生物〈腫瘍〉の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。
- 胃
- 肝及び肝内胆管
- 気管、気管支及び肺
- 結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸
自殺者の原因・動機
警察庁の「令和5年(2023年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。
- 学校問題
- 家庭問題
- 勤務問題
- 健康問題
死亡場所
- 令和4年(2022年)の死亡場所は、病院が64.5%と最も多く、次いで自宅が17.4%となっている。
- なお、過去の意識調査では、人生の最後をむかえるときに生活したい場所として自宅が最も高く、在宅医療の充実が図られている。
令和4年(2022年)の人口動態統計における死亡場所で最も多いのはどれか。
- 自宅
- 病院
- 老人ホーム
- 介護医療院・介護老人保健施設
妊産婦死亡
- 妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいう。
- 妊産婦死亡率は、出産(出生+死産)10万対で示し、令和4年(2022年)は4.2と国際的にみても低率である。
日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。
- 出生10万対で示す。
- 出産後1年までの女性の死亡をいう。
- 令和4年(2022年)の妊産婦死亡率は、10.1である。
- 間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。
周産期死亡
- 周産期死亡は、妊娠満22週以後の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをいう。
- 令和5年(2023年)の周産期死亡数は2,403(胎・人)、周産期死亡率(出産千対)は3.3となっている。
日本の令和5年(2023年)における周産期死亡率(出産千対)について正しいのはどれか。
- 1.3
- 3.3
- 5.3
- 7.3
死産
- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。
- 死産のうち、人工死産は胎児の母体内生存が確実なときに人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産であり、令和5年(2023年)の自然死産数は7,150胎、人工死産数は8,382胎で、死産率(出産千対)は自然死産が9.4、人工死産が9.9となっている。
日本の周産期の死亡に関する記述で正しいのはどれか。
- 新生児死亡は生後1週未満の死亡をいう。
- 死産は妊娠満12週以後の死児の出産をいう。
- 妊産婦死亡は妊娠中又は妊娠終了後満28日未満の女性の死亡をいう。
- 令和5年(2023年)の人口動態統計では自然死産数が人工死産数よりも多い。
母子保健統計の算出方法で出生数を分母としているのはどれか。
- 妊娠満22週以後の死産率
- 周産期死亡率
- 乳児死亡率
- 死産率
平均初婚年齢
令和5年(2023年)の人口動態統計における妻の平均初婚年齢はどれか。
- 23.7歳
- 25.7歳
- 27.7歳
- 29.7歳
- 31.7歳
生涯未婚率
人口統計資料集2020年版における生涯未婚率(50歳時の未婚割合)で、平成22年(2010年)から令和2年(2020年)の推移で適切なのはどれか。
- 変化はない。
- 下降し続けている。
- 上昇し続けている。
- 上昇と下降を繰り返している。
平均寿命・健康状態・受療状況
第2編3章 生命表 p70~73
第2編4章 健康状態と受療状況 p74~79
平均寿命
平均寿命で正しいのはどれか。
- 0歳の平均余命である。
- 20歳の平均余命である。
- 40歳の平均余命である。
- 死亡者の平均年齢である。
令和4年(2022年)の日本における簡易生命表で女性の平均寿命に最も近いのはどれか。
- 77年
- 82年
- 87年
- 92年
日本の令和4年(2022年)における男性の平均寿命はどれか。
- 71.05年
- 76.05年
- 81.05年
- 86.05年
日本の令和4年(2022年)の健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。
- 女性の死因の第2位は老衰である。
- 男性の死因の第2位は肺炎である。
- 女性の平均寿命は89年を超えている。
- 男性の平均寿命は83年を超えている。
有訴者率
- 令和4年(2022年)の病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)は、人口千人当たり276.5(男性246.7・女性304.2)である。
- 症状別にみると、男女ともに腰痛が最も高い(男性91.6・女性111.9)。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。
- 腰痛
- もの忘れ
- 体がだるい
- 目のかすみ
- 手足の関節が痛む
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。
- 頭痛
- 腰痛
- 体がだるい
- 目のかすみ
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査による有訴者率(人口千対)で正しいのはどれか。
- 6.5
- 76.5
- 276.5
- 476.5
通院者率
- 令和4年(2022年)の傷病で通院している者(通院者)は、人口千人当たり417.3(男性401.9・女性431.6)である。
- 傷病別にみると、男女ともに高血圧症が最も高い(男性146.7・女性135.7)。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における通院者率が男女ともに最も高いのはどれか。
- 糖尿病
- 腰痛症
- 高血圧症
- 眼の病気
高齢者の有訴者・通院者
- 令和4年(2022年)の有訴者率(人口千対)をみると、65歳以上で418.2(男397.6・女435.2)、75歳以上で474.6(男462.4・女483.7)となっており、傷病別では腰痛が最も高い。
- 令和4年(2022年)の通院者率(人口千対)をみると、65歳以上で696.4(男700.8・女692.7)、75歳以上で729.2(男739.2・女721.9)となっており、症状別では高血圧症が最も高い。
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における高齢者の健康状態で正しいのはどれか。
- 75歳以上の通院率は約9割である。
- 65歳以上の半数以上が有訴者である。
- 65歳以上の外来受療率は年齢が上がるほど高くなる。
- 65歳以上の自覚症状で男女とも最も多いのは腰痛である。
患者調査
保健統計調査と調査項目の組合せで正しいのはどれか。
- 患者調査――受療の状況
- 人口動態調査――転出入
- 国民生活基礎調査――生活習慣
- 国民健康・栄養調査――健康診断の受診状況
受療率
- 受療率とは、人口10万人に対する推計患者数(調査日当日に病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数)をいう。
- 令和2年(2020年)の受療率を傷病分類別にみると、入院では「精神及び行動の障害」(188)が、外来では「消化器系の疾患」(1007)が最も多い。
健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。
- 罹患率が高い疾患は有病率が高くなる。
- 推計患者数には助産所を利用した者を含む。
- 受療率は人口10万人に対する推計患者数である。
- 平均在院日数は調査時点で入院している者の在院日数の平均である。
令和2年(2020年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。
- 新生物〈腫瘍〉
- 呼吸器系の疾患
- 消化器系の疾患
- 内分泌、栄養及び代謝疾患
総患者数
令和2年(2020年)の患者調査において医療機関を受診している総患者数が最も多いのはどれか。
- 喘息
- 糖尿病
- 脳血管疾患
- 高血圧性疾患
生活習慣状況
第3編1章 生活習慣病と健康増進対策 p80~94
健康寿命
健康寿命の説明で適切なのはどれか。
- 生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。
- 2019年の健康寿命は2016年よりも短い。
- 2019年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。
- 平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。
運動習慣のある者
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。
- 20~29歳
- 40~49歳
- 60~69歳
- 70歳以上
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査において、運動習慣のある女性の割合が最も高い年齢階級はどれか。
- 30~39歳
- 40~49歳
- 50~59歳
- 60~69歳
- 70歳以上
高齢者の社会活動
令和3年(2021年)の高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査で、高齢者が過去1年間に参加した社会活動のうち割合が最も多いのはどれか。
- 教育・文化
- 子育て支援
- 生産・就業
- 健康・スポーツ
BMI(体格指数)
身長170cm、体重70kgの成人の体格指数(BMI)を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②
肥満者・やせの者の割合
- 令和5年(2023年)の肥満者の割合は、男性では60歳代(35.0%)が最も多く、次いで50歳代(34.8%)、40歳代(34.3%)となっている。
- 令和5年(2023年)のやせの者の割合は、女性では20歳代(24.4%)が最も高く、次いで30歳代(17.9%)となっている。
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査の結果で、該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。
- 20~29歳
- 40~49歳
- 60~69歳
- 70歳以上
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査による40歳代男性の肥満者の割合に最も近いのはどれか。
- 15%
- 35%
- 55%
- 75%
喫煙習慣者の割合
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査で20歳以上の男性における喫煙習慣者の割合に最も近いのはどれか。
- 6%
- 16%
- 26%
- 36%
令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査における成人の生活習慣の特徴で正しいのはどれか。
- 朝食の欠食率は40歳代が最も多い。
- 運動習慣のある人の割合は30歳代が最も多い。
- 1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多い。
- 習慣的に喫煙している人の割合は10年前に比べて増加している。
医療提供体制・国民医療費
第4編1章 医療提供体制 p166~206
第4編2章 医療保険制度 p208~219
看護師の就業場所
- 令和4年(2022年)末に就業している看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の総数は約166万人(うち看護師131万人)である。
- 令和4年(2022年)の看護師の就業場所をみると、多い順に以下のとおりである。
①病院:67.8%
②診療所:13.2%
③介護保険施設等:7.7%
④訪問看護ステーション:5.4%
⑤社会福祉施設:1.7%
令和4年(2022年)の衛生行政報告例における看護師の就業場所で、医療機関(病院、診療所)の次に多いのはどれか。
- 事業所
- 市町村
- 保健所
- 訪問看護ステーション
平均在院日数
令和4年(2022年)の病院報告による一般病床の平均在院日数はどれか。
- 6.2日
- 16.2日
- 26.2日
- 36.2日
病院数
日本の医療提供施設について正しいのはどれか。
- 病院数は1995年から増加傾向である。
- 2019年の人口対病床数は先進国の中で最も多い。
- 介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。
- 精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。
国民医療費の状況
- 国民医療費は、医療機関などにおける傷病の治療に要する費用を推計したものである。
- 令和3年(2021年)度の国民医療費総額は45兆359億円である。
- 人口1人当たりでは35.9万円で、年齢階級別にみると65歳未満が19.9万円に対し、65歳以上は75.4万円(約4倍)、75歳以上は92.3万円(約5倍)となっている。
令和3年(2021年)の国民医療費はどれか。
- 約450億円
- 約4,500億円
- 約4兆5000億円
- 約45兆円
令和3年(2021年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。
- 16万円
- 26万円
- 36万円
- 46万円
日本の令和3年度(2021年度)の国民医療費について正しいのはどれか。
- 総額は約25兆円である。
- 財源の約半分は保険料である。
- 国民総生産に対する比率は5%台である。
- 人口1人当たりでは65歳以上が65歳未満の約2倍である。
介護状況
第5編1章 介護保険 p220~233
主な介護者の続柄
▶109回午後54改題
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合のうち、「同居の家族」が占める割合に最も近いのはどれか。
- 6%
- 26%
- 46%
- 66%
▶107回午後8改題
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査で、要介護者からみた主な介護者の続柄で割合が最も多いのはどれか。
- 同居の父母
- 別居の家族
- 同居の配偶者
- 同居の子の配偶者
同居している主な介護者の状況
▶108回午前70改題・113回午後65類問
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。
- 性別は女性が多い。
- 続柄は子が最も多い。
- 年齢は50~59歳が最も多い。
- 介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。
社会保障・社会保険・社会福祉
第1編1章 1.5〕社会保障の状況 p16~17
第5編2章 社会保険と社会福祉 p234~245
社会保障給付費の状況
令和3年度(2021年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に並んでいるのはどれか。
- 年金>医療>福祉その他
- 年金>福祉その他>医療
- 医療>年金>福祉その他
- 医療>福祉その他>年金
高齢者世帯の所得
令和4年(2022年)の国民生活基礎調査における高齢者世帯の所得のうち62.8%を占めるものは何か。
- 稼働所得
- 財産所得
- 公的年金・恩給
- 年金以外の社会保障給付金
育児休業取得状況
令和4年度(2022年度)の家族に関する調査で正しいのはどれか。
- 人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。
- 労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。
- 人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。
- 雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が17.13%である。
児童虐待の状況
- 令和3年度(2021年度)の児童虐待対応件数(20.8万件)のうち、主たる虐待者は実母が9.9万件(47.5%)で最も多く、次いで実父が8.6万件(41.5%)となっている。
- 虐待の種別にみると、「心理的虐待」が60.1%で最も多く、次いで「身体的虐待」が23.7%、「ネグレクト」が15.1%、「性的虐待」が1.1%となっている。虐待対応件数は、総数でみても種別でみても増加傾向にある。
令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待で正しいのはどれか。
- 主たる虐待者は実父が最も多い。
- 性的虐待件数は身体的虐待件数より多い。
- 児童虐待相談件数は5年間横ばいである。
- 心理的虐待件数は5年前に比べて増加している。
養護者による高齢者虐待の状況
- 令和4年度(2022年度)の養護者による高齢者虐待(1.7万件)のうち、虐待を行った養護者の続柄は、息子が39.0%で最も多く、次いで夫が22.7%となっている。
- 被虐待高齢者の性別は女性が75.8%と多く、年齢階級別にみると80~84歳が25.3%で最も高い。
- 虐待の種別にみると、身体的虐待が65.3%と半分以上を占めている。
日本の令和4年(2022年)の養護者による高齢者虐待の種類で最も多いのはどれか。
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- 介護等放棄
- 性的虐待
令和4年度(2022年度)「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果において、養護者による高齢者虐待に関する説明で正しいのはどれか。
- 夫による虐待が最も多い。
- 被虐待者の9割が女性である。
- 心理的虐待が全体の6割を占めている。
- 被虐待者の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はランクⅡが最も多い。
労働衛生・学校保健
第8編 労働衛生 p299~310
第10編 学校保健 p341~351
業務上疾病発生状況
日本の令和4年(2022年)における業務上疾病で、新型コロナウイルスり患によるものを除いた場合、発生件数が最も多いのはどれか。
- 振動障害
- 騒音による耳の疾患
- 負傷に起因する疾病
- じん肺症及びじん肺合併症
学童期の異常被患率
令和4年(2022年)の学校保健統計調査における学童期の異常被患率で最も高いのはどれか。
- 高血圧
- 摂食障害
- 心電図異常
- 裸眼視力1.0未満の者
「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。
保健師国家試験では、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が毎年問われています。その多くは市町村や都道府県、保健所などが関与しており、合格のためだけの知識ではなく、今後保健師として従事していく上でも大切な知識となっています。
このページでは、保健師国家試験に出題された法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、110回(2024年)から101回試験(2015年)までの過去12年の出題の中から対応する法律問題をピックアップしています。「国民衛生の動向」と併用してご活用下さい。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
法律別問題目次
第1編:社会保障の動向と衛生行政の体系
- 地域保健法
- 災害対策基本法
- 災害救助法
第3編:保健と医療の動向
- 健康増進法
- 母子保健法
- 障害者総合支援法
- 精神保健福祉法
- 発達障害者支援法
- 歯科口腔保険の推進に関する法律
- 自殺対策基本法
- がん対策基本法
- がん登録推進法
- 難病法
第4編:医療提供体制と医療保険
- 医療法
- 医療介護総合確保推進法
- 訪問看護制度
- 保健師助産師看護師法
- 医療保険各法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
第5編:保健医療を取り巻く社会保障
- 介護保険法
- 国民年金法・厚生年金保険法
- 生活保護法
- 生活困窮者自立支援法
- 子ども・子育て支援法
- 児童福祉法
- 障害者基本法
- 障害者虐待防止法
第7~10編:生活環境・労働衛生・学校保健
- 食品表示法
- 労働安全衛生法
- 労働基準法
- 労働者災害補償保険法
- 学校教育法
- 学校保健安全法
- 学校給食法
地域保健法
第1編2章 2.衛生行政の組織 p22~24
第1編2章 5.保健師の活動 p25~27
保健所
- 保健所は地域における公衆衛生の向上と増進を図るために、地域保健法に基づいて都道府県、政令指定都市、中核市、施行令で規定された市、特別区が設置する(令和5年4月1日現在468カ所)。
- 保健所長は原則として医師であって要件に該当する者を当てる。ただし、平成16年の施行令改正により、医師でなくとも医師と同等以上の公衆衛生行政に必要な専門的知識を有すると認めた者などの要件を満たした職員を、2年以内の期間を限り保健所長とすることができることとなった。
- 保健所では、次に掲げる事項についての指導やこれに必要な事業を行う。(地域保健法6条)
- 地域保健に関する思想の普及と向上
- 人口動態統計その他地域保健に係る統計
- 栄養の改善と食品衛生
- 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生
- 医事と薬事
- 保健師
- 公共医療事業の向上と増進
- 母性、乳幼児、老人の保健
- 歯科保健
- 精神保健
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健
- エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防
- 衛生上の試験と検査
- その他地域住民の健康の保持と増進
▶110回午前3
保健所の説明で正しいのはどれか。
- 平成30年(2018年)から令和4年(2022年)の5年間の推移で中核市の保健所は減少傾向にある。
- 地域保健に関する思想の普及が業務の1つである。
- 健康増進法に基づき設置されている。
- 介護認定審査会を開催する。
市町村保健センター
▶109回午前19
地域保健法に規定されている内容で正しいのはどれか。
- 市町村健康増進計画の策定を義務づけている。
- 市町村保健センター業務の1つに調査研究がある。
- 市町村保健センターの整備について規定している。
- 都道府県保健所の業務の1つに予防接種事業がある。
▶101回午後27
地域保健法で規定されている市町村保健センターの役割で正しいのはどれか。
- 健康診査
- 結核の予防
- 衛生上の検査
- 人口動態統計調査
- 医療従事者届の受付
▶102回午前25改題
市町村保健センターで正しいのはどれか。
- 市町村に設置義務がある。
- センター長は原則として医師である。
- 地域保健法に設置が定められている。
- 診療放射線技師の配置が定められている。
- 令和5年4月時点のセンター数は1,500か所である。
▶104回午前26
地域保健法に規定されている内容はどれか。
- 市町村保健センターの所長は原則として医師である。
- 市町村に対する必要な財政的援助は都道府県の責務である。
- 保健所には所管区域内の市町村職員の研修の実施が義務付けられている。
- 保健所が行う事業に母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項がある。
地域保健対策の推進に関する基本的な指針
▶109回午前25・103回午前15類問
健康危機管理について、地域保健法で厚生労働大臣が定めることが規定されているのはどれか。
- 地域防災計画
- 厚生労働省健康危機管理基本指針
- 医療提供体制の確保に関する基本方針
- 地域保健対策の推進に関する基本的な指針
- 地域における保健師の保健活動に関する指針
▶102回午前28
地域保健対策の推進に関する基本的な指針について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 健康危機管理体制の管理責任者は保健所長が望ましい。
- 科学的根拠に基づく地域保健対策の計画を策定する。
- 自助の推進から公助の積極的な活用への移行を図る。
- 専門家とのリスクコミュニケーションに努める。
- 災害対策基本法に基づいて定められている。
地域における保健師の保健活動に関する指針
平成25年(2013年)に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」では、以下の基本的な方向性の10項目が示されている。
- 地域診断に基づくPDCAサイクルの実施
- 個別課題から地域課題への視点・活動の展開
- 予防的介入の重視
- 地区活動に立脚した活動の強化
- 地区担当制の推進
- 地域特性に応じた健康なまちづくりの推進
- 部署横断的な保健活動の連携・協働
- 地域のケアシステムの構築
- 各種保健医療福祉計画の策定・実施
- 人材育成
▶107回午後17
「地域における保健師の保健活動に関する指針」に基づく保健師の保健活動の基本的な方向性の10項目に該当するのはどれか。
- 業務分担制の推進
- 予算の適切な執行管理
- 顕在化している課題への介入重視
- 部署横断的な保健活動の連携・協働
▶102回午前26
平成25年(2013年)の地域における保健師の保健活動に関する基本的な指針における記載事項でないのはどれか。
- 人材育成
- 地区担当制の推進
- 予防的介入の重視
- 個別課題の視点の重視
- 地区診断に基づくPDCAサイクルの実施
都道府県保健所等に所属する保健師の活動
「地域における保健師の保健活動に関する指針」では、都道府県保健所等に所属する保健師の活動として以下などが掲げられている。
- 広域的・専門的な保健サービス等の提供
- 災害等の健康危機に対応できる体制づくり
- 新たな健康課題に対する先駆的な保健活動の実施
- 生活衛生・食品衛生対策
- 医療施設等に対する指導
- 地域の健康情報の収集・分析・提供と調査研究
- 管内市町村との重層的な連携体制の構築
▶106回午前31
平成25年(2013年)に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に示された都道府県保健所等に所属する保健師の活動はどれか。2つ選べ。
- 広域的・専門的な保健サービスの提供
- 住民の主体的な健康づくり支援
- ボランティア組織の育成支援
- 市町村保健師の業務の補助
- 健康危機への体制づくり
市町村に所属する保健師の活動
「地域における保健師の保健活動に関する指針」では、市町村に所属する保健師の活動として以下などが掲げられている。
- 住民の身近な保健サービス等の企画・立案・提供・評価
- 地区担当制の推進
- 市町村が保険者として実施する特定健康診査・特定保健指導
- 介護保険事業等への取り組み
- 地域特性を反映した各種保健医療福祉計画、防災計画、障害者プラン、まちづくり計画等の策定
▶108回午前1
平成25年(2013年)に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に示された市町村に所属する保健師の活動はどれか。
- 医療施設等に対する指導
- 防災計画の策定への参画
- 健康危機管理の体制づくり
- 広域的、専門的な保健サービスの提供
▶105回午前17
都道府県や市区町村において統括的な役割を担う保健師の活動で最も適切なのはどれか。
- 住民への総合相談を実施する。
- 組織横断的な総合調整及び推進を行う。
- 地区担当制による地区活動を実施する。
- 広域的かつ専門的な保健サービスを行う。
災害対策基本法・災害救助法
第5編2章 6.2〕災害時の支援体制 p244
災害対策基本法
災害対策基本法は統一的かつ計画的な防災体制の整備を図る、災害対策の最も基本となる法律で、地域防災計画(都道府県・市町村)の作成や物資の備蓄、防災訓練義務といった平時における予防等の責務など幅広く規定している。
▶105回午後30
災害対策基本法に示されている住民の責務はどれか。2つ選べ。
- 過去の災害から得られた教訓の伝承
- 避難行動要支援者名簿の作成
- 生活必需物資の備蓄
- 防災組織の充実
- 防災活動の促進
災害対策基本法に基づき都道府県が行う災害対策はどれか。2つ選べ。
- 防災のための調査研究
- 指定緊急避難場所の指定
- 都道府県地域防災計画の作成
- 避難行動要支援者名簿の作成
- 住民の自発的な防災活動の促進
災害救助法
▶107回午後25
災害救助法で定められているのはどれか。
- 自主防災組織の促進
- 地域防災計画の作成
- 避難所及び応急仮設住宅の供与
- 広域災害救急医療情報システム〈EMIS〉の運用
- 災害時健康危機管理支援チーム〈DHEAT〉の派遣
▶102回午前37
災害救助法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- 防災計画の作成
- 職員の派遣義務
- 被災した住宅の応急修理
- 避難所及び応急仮設住宅の供与
- 地方公共団体とボランティアとの連携
▶110回午前28
災害対策基本法に規定されているのはどれか。
- 救護所における医療
- 自主防災組織の育成
- 被災世帯の住宅再建支援
- 被災者への生活再建支援金給付
- 被災世帯への災害援護資金の貸し付け
健康増進法
第3編1章 2.1〕(5)健康増進法 p86~87
市町村の役割
- 健康増進法に基づき、厚生労働大臣は国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定め、基本方針に基づき都道府県は健康増進計画を定めるものとされる。市町村については、それらを勘案して健康増進計画を定めるように努める。
- 市町村は、住民の健康の増進を図るため、住民からの生活習慣の改善に関する相談や必要な栄養指導などの保健指導を行う。また、市町村による健康増進事業として、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する)の交付などの実施に努める。
▶108回午前38
健康増進法に基づく市町村の役割はどれか。2つ選べ。
- 特定保健指導
- がん検診の実施
- 健康増進計画の策定
- 特定給食施設に対する指導
- 飲食店における受動喫煙の防止に関する指導
▶103回午前7
健康増進法に基づく市町村の役割はどれか。
- 生活習慣相談の実施
- 特定給食施設の指導
- 飲食店における利用者の受動喫煙の防止
- 健康増進の総合的な推進のための基本方針の策定
▶105回午前40
健康増進法に基づき市町村が実施するのはどれか。2つ選べ。
- 栄養指導員の任命
- 健康手帳の交付
- 骨粗鬆症検診
- 特定健康診査
- 妊婦健康診査
▶104回午後14
健康増進法に基づく健康増進事業による肝炎ウイルス検診について正しいのはどれか。
- 実施主体は都道府県である。
- 対象は満40歳以上の者である。
- 60歳から無料で検診が受けられる。
- 特定健康診査の検査項目に定められている。
母子保健法
第3編2章 1.1〕母子保健法に基づく施策 p96~99
主な母子保健施策のあゆみ
- 昭和17年(1942年):妊産婦手帳制度
- 昭和23年(1948年):妊産婦・乳幼児の保健指導
- 昭和29年(1954年):育成医療
- 昭和33年(1958年):未熟児養育医療
- 昭和36年(1961年):3歳児健康診査、新生児訪問指導
- 昭和40年(1965年):母子保健法、母子健康手帳
- 昭和44年(1969年):妊産婦健康診査の公費負担制度
- 昭和49年(1974年):小児慢性特定疾患治療研究事業
- 昭和52年(1977年):1歳6か月児健康診査、先天性代謝異常のマススクリーニング
- 平成9年(1997年):母子保健法改正(保健指導、新生児・妊産婦の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳など市町村に権限委譲)
- 平成12年(2000年):健やか親子21
- 平成15年(2003年):少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策推進法
- 平成17年(2005年):小児慢性特定疾患治療研究事業を児童福祉法に位置づけ
- 平成18年(2006年):マタニティマーク
- 平成23年(2011年):タンデムマス法を用いた新生児スクリーニング検査の導入
- 平成25年(2013年):未熟児養育医療・未熟児訪問指導を市町村に権限委譲
- 平成26年(2014年):健やか親子21(第2次)
- 平成28年(2016年):子育て世代包括支援センター
- 平成30年(2018年):成育基本法
▶105回午前10
年代と母子保健施策の組合せで正しいのはどれか。
- 昭和17年(1942年)――母子健康手帳の制度化
- 昭和36年(1961年)――1歳6か月児健康診査開始
- 昭和52年(1977年)――3歳児健康診査開始
- 平成9年(1997年)――新生児訪問が市町村へ移管
▶101回午前10
母子保健施策のうち最も新しいのはどれか。
- 母子健康手帳の交付
- マタニティマークの配布
- 妊婦健康診査の公費負担
- 新生児マススクリーニング検査におけるタンデムマス法の導入
妊娠届
▶102回午後10
妊娠届について正しいのはどれか。
- 都道府県知事に提出する。
- 医師の診断書が必要である。
- 届出の事項は定められていない。
- 届出をした者に対し母子健康手帳を交付する。
子育て世代包括支援センター
▶107回午後29
子育て世代包括支援センターで正しいのはどれか。
- 要保護児童対策地域協議会を設置する。
- 母子保健推進員の配置が定められている。
- 児童福祉法において設置が定められている。
- 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う。
- 市町村は子育て世代包括支援センターを設置しなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
第3編2章 3.障害児・者施策 p107~111
概要
- 障害者総合支援法は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、難病等の種別にかかわらず、障害のある人々が必要な医療・福祉サービスを利用できるように総合的に支援を行うものである。
- 同法に基づく制度の給付申請の窓口は市町村で、実施主体は都道府県・指定都市とされる。利用者の負担額は所得に応じて負担上限月額が設けられている(応能負担)。
▶101回午後22
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービスについて正しいのはどれか。
- 申請窓口は都道府県である。
- 発達障害者は対象である。
- 利用者負担は定額である。
- 措置制度である。
自立支援医療
▶105回午後11
県の保健所に住民から「うつ病で通院中なので、医療費を公費で負担してくれる制度の内容や手続きについて知りたい」という電話相談があった。
保健所保健師の説明で適切なのはどれか。
- 「県の保健所が申請窓口です」
- 「精神保健福祉法に基づく制度です」
- 「世帯の所得に応じて負担上限額があります」
- 「お住まいの市が医療費受給の判定を行います」
障害者総合支援法のあゆみ
●平成18年(2006年)
障害者自立支援法施行。支援の対象は身体障害、知的障害、精神障害とされた(平成22年の一部改正で精神障害として発達障害が対象となることを明確化)。
●平成24年(2012年)
名称を障害者総合支援法と改め、①障害者の範囲として難病等の追加、②創設された障害支援区分に基づくサービスの提供、③障害者に対する理解を深めるための研修・啓発などの地域生活支援事業の追加といった改正がなされた。
●平成28年(2016年)
障害者の望む地域生活の支援として、自立生活援助、就労定着支援などのサービスが新設された。
▶101回午後31
障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律への改正時に、変更された内容はどれか。2つ選べ。
- 難病は支援の対象から除外された。
- 障害程度区分を障害支援区分とした。
- 支援の対象者に精神障害者を追加した。
- 利用者の負担額は利用した障害福祉サービスの額の3割とした。
- 地域生活支援事業として障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業を追加した。
▶108回午前33
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 療育手帳の根拠法令である。
- 障害支援区分に基づきサービスが利用できる。
- 自立支援医療の自己負担額は原則2割である。
- サービスを利用する場合は都道府県の窓口に申請する。
- 平成28年(2016年)の改正によって就労定着支援が新設された。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
第3編2章 4.精神保健 p111~118
精神障害者の入院形態
- 任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。
- 任意入院が行われる状態にないと判定された者については、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に医療保護入院が行える。しかし、急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内の応急入院を行うことができる。
- 2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には指定病院等への措置入院を行うことができる。措置入院の対象であるが急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが入院期間は72時間以内に制限される緊急措置入院を行うことができる。
▶108回午後31
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定されている内容で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 市町村の役割に普及啓発がある。
- 精神通院医療費は公費で負担される。
- 医療保護入院は患者本人の同意が必要である。
- 緊急措置入院は精神保健指定医1人の診察が必要である。
- 発達障害者支援センターの設置について規定されている。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉に関して、知識の普及・調査研究、複雑または困難な相談・指導などを行うものとして都道府県・指定都市に設置され、精神科医や精神保健福祉士、精神保健福祉相談員などの職員を配置する。
▶106回午前20
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく精神保健福祉センターで正しいのはどれか。
- 設置主体は市町村である。
- 地域生活支援事業を実施する。
- 社会復帰の促進のための啓発活動を行う。
- 自立支援医療(精神通院医療)の申請窓口である。
▶103回午前20
精神保健福祉センターの業務で正しいのはどれか。
- 措置入院の決定
- 精神保健福祉相談員の任命
- 精神障害者保健福祉手帳の交付
- 精神障害者の福祉に関する困難な相談
▶109回午前35
精神保健福祉センターの業務で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 精神保健に関する普及啓発
- 地域自立支援協議会の運営
- 薬物の不正取引の取り締まり
- 自殺総合対策推進センターの運営
- 保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導・援助
精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されるもので、交付により所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引などが受けられる。
- 手帳の申請は市町村の担当窓口を経由して都道府県知事に行い、都道府県知事は審査・交付を行う。交付された者は障害の程度に応じて1~3級に等級が区分され、有効期限は公布日から2年で、更新が必要となる。
▶102回午前36
精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 市町村長が交付する。
- 高次脳機能障害は対象となる。
- 税制上の優遇措置が受けられる。
- 1~4級の等級に区分されている。
- 1年ごとに認定の更新が必要である。
精神保健福祉法改正の主な経緯・内容
精神病院設置義務、私宅監置の廃止
●昭和40年(1965年)改正
保健所を精神保健行政の第一線機関として位置づけ、通院医療公費負担制度の創設
●昭和62年(1987年)改正
精神保健法に名称変更、任意入院、応急入院、精神保健指定医、精神医療審査会の導入
●平成5年(1993年)改正
社会復帰の促進、グループホームの法定化
●平成7年(1995年)改正
精神保健福祉法に名称変更、精神障害者保健福祉手帳の創設、市町村の役割の明示
●平成11年(1999年)改正
医療保護入院の移送制度の創設
●平成17年(2005年)改正
障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の成立に伴い通院医療公費負担制度を自立支援医療に一元化
●平成25年(2013年)改正
障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていた保護者制度の廃止
▶101回午前11
精神保健対策の変遷で最も新しいのはどれか。
- 市町村の役割が明示された。
- 医療保護入院のための移送が規定された。
- 精神障害者保健福祉手帳制度が創設された。
- 保健所が精神保健行政を担うこととされた。
発達障害者支援法
第3編2章 4.6〕(4)発達障害者支援 p115~116
発達障害の定義・発達障害者支援センター
- 発達障害者支援法では、発達障害を広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢で発症する脳機能の障害と定義している。
- 発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見や支援、情報提供などの業務を実施するもので、都道府県知事が指定することができる。
▶101回午前25
発達障害者支援法について正しいのはどれか。
- 学習障害は対象に含まれる。
- 発達障害者に療育手帳を交付する。
- 支援の対象は18歳未満の障害者と定めている。
- 市町村長は発達障害者支援センターを設置しなければならない。
▶105回午後35
発達障害で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 発達障害者は障害者総合支援法のサービスを利用することができる。
- 発達障害者は精神障害者保健福祉手帳を申請することはできない。
- 発達障害の定義は発達障害者支援法に規定されている。
- 発達障害者に二次障害が出現することはない。
- 発達障害者支援センターは市町村が設置する。
歯科口腔保健の推進に関する法律
第3編2章 5.歯科保健医療 p118~120
歯科保健施策のあゆみ
●平成元年(1989年)
成人歯科保健対策検討会提言。以降、80歳になっても20本以上の歯を保つことを目的とする8020運動が推進されている。
●平成7年度(1995年度)
老人保健事業として歯周疾患検診が導入。対象年齢を拡大しながら、平成20年度(2008年度)からは健康増進法に基づく健康増進事業として市町村が実施に努めている。
●平成23年(2011年)
歯科口腔保健の推進に関する法律が成立。総合的な歯科保健施策の方針、目標、計画を示した歯科口腔保健の推進に関する基本的事項が翌年策定され、各ライフステージおける取り組みが示された。
●平成25年度(2013年度)
第4次国民健康づくり対策である健康日本21(第二次)開始。歯・口腔の健康に関する目標が示され、8020運動の目標数値を設定した(平成28年実績値51.2%)。
▶104回午後30・110回午後30類問
歯科保健施策について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 歯科疾患実態調査は3年ごとに実施されている。
- 健康増進法によって歯周疾患検診が義務化された。
- 平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。
- 第一次国民健康づくり対策の課題の1つとして歯の健康が取り上げられた。
- 食育の推進の一助として噛ミング30〈カミングサンマル〉運動が行われている。
▶103回午前13
8020運動について正しいのはどれか。
- う蝕予防に重点を置く運動である。
- 健康日本21(第二次)に目標値が設定されている。
- 日本医師会と日本歯科医師会とが推進を提言した。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づいて運動を開始した。
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の目標
●歯科疾患の予防における目標
乳幼児期では健全な歯・口腔の育成を、学齢期では口腔状態の向上を、成人期では健全な口腔状態の維持を、高齢期では歯の喪失防止を掲げている。
●生活の質の向上に向けた目標
乳幼児期と学齢期では口腔機能の獲得を、成人期と高齢期では口腔機能の維持・向上を掲げている。
▶106回午後11
歯科口腔保健の推進に関する法律に基づく基本的事項の目標とライフステージの組合せで正しいのはどれか。
- 口腔状態の向上――乳幼児期
- 歯の喪失防止――学童期
- 健全な歯・口腔の育成――成人期
- 口腔機能の維持・向上――高齢期
自殺対策基本法
第3編2章 6.自殺対策 p121~122
自殺対策基本法(平成18年成立、平成28年改正)の概要
- 自殺対策基本法は、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止とあわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
- 政府には推進すべき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱の策定が義務づけられている。また、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。
▶105回午前21
現行の自殺対策基本法で正しいのはどれか。
- 自殺者の親族等に対する支援が目的に含まれる。
- 事業主の責務に長時間労働の禁止を規定している。
- 保健所に自殺総合対策会議の実施を義務付けている。
- 市町村に自殺予防総合相談窓口の設置を義務付けている。
▶101回午後35
自殺対策基本法について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 事業主に長時間労働の禁止を規定している。
- 自殺総合対策大綱で自殺対策の指針が策定された。
- 自殺者の親族に対する適切な支援が目的に含まれる。
- 保健所を自殺予防総合対策センターに位置付けている。
- 自殺予防総合相談窓口の設置を市町村に義務付けている。
▶110回午前21
日本の自殺対策で正しいのはどれか。
- 高齢者の自殺対策を重点施策に位置付けている。
- 市町村に自殺対策計画の立案を義務付けている。
- 事業主にメンタルヘルス対策推進を義務付けている。
- 令和8年までに自殺死亡率を平成27年と比べて10%減少することを目標としている。
がん対策基本法
第3編4章 1.がん対策 p149~152
がん登録
- がん対策基本法により、国はがん対策推進基本計画の策定、都道府県は都道府県がん対策推進計画の策定が定められている。
- 令和5年(2023年)に閣議決定された第4期がん対策推進基本計画では、がん予防を図るため、指針に基づく全てのがん検診において、がん検診受診率60%を目指すことを掲げている。
▶110回午後19
第3期がん対策推進基本計画の目標項目で正しいのはどれか。
- がん有病率
- がん検診受診率
- 緩和ケア病棟数
- がん患者の支援団体数
がん登録等の推進に関する法律〈がん登録推進法〉
第3編4章 1.がん対策 p149~152
がん登録
- がんと診断されたすべての人について、全病院には都道府県への罹患情報の届け出義務が課され、国(国立がん研究センター)がデータベース化を行い、がん罹患率などを正確に把握し、がん対策に活用している(全国がん登録)。
- 情報は一般には公開されていないが、研究者や国、都道府県の関係者などに限った提供が行われている。
▶104回午後27
法律に基づく全国の疾病登録があるのはどれか。
- がん
- 糖尿病
- 脳卒中
- 慢性腎臓病
- マイコプラズマ感染症
▶106回午前40
がん登録等の推進に関する法律〈がん登録推進法〉で正しいのはどれか。2つ選べ。
- がん診療連携拠点病院を2次医療圏に整備する。
- がん登録届出の際は患者の同意が必要である。
- がんの罹患に関する情報のデータベース化は国が行う。
- 全国がん登録データベースは一般に公開されている。
- 病院には罹患情報の届出義務がある。
▶110回午後24
全国がん登録制度について正しいのはどれか。
- 罹患率を計測する。
- 健康増進法に基づいている。
- 診断後7日以内に届け出る。
- がん罹患者の同意が必要である。
- 指定届出機関による定点把握である。
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
第3編4章 2.難病対策 p153~157
難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針
難病法では国の責務として基本方針を策定することとされ、以下の9項目が告示されている。
- 医療等の推進の基本的な方向
- 医療提供体制の確保
- 医療に関する人材の養成
- 調査研究
- 医薬品・医療機器に関する研究開発の推進
- 患者の療養生活の環境整備
- 医療等と福祉サービスに関する施策や就労の支援に関する施策等との連携
- その他医療等の推進に関する重要事項
- 医療費助成制度に関する事項
▶107回午前35
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針で定める内容はどれか。2つ選べ。
- 発症の予防
- 就労の支援
- 医療費の適正化
- 対象疾患の拡充
- 療養生活の環境整備
難病・指定難病
- 難病とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。
- 医療費助成の対象となる指定難病は、難病のうち当該難病の患者数が本邦において千分の一(0.1%)程度に相当する数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることなど厚生労働省令で定める要件等を満たし、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもので、令和3年11月現在338疾病が指定されている。
▶106回午前12
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病で正しいのはどれか。
- 治療方法が確立している。
- 発病の機構が明らかである。
- 客観的な指標による一定の診断基準が定まっている。
- 患者数が日本の人口のおおむね百分の一程度に相当する。
医療費助成の概要
- 医療費助成を申請する者は、難病指定医等の記載した臨床調査個人票をもって、都道府県・指定都市に申請し、支給認定を受ける必要がある。また、助成を受ける際には、都道府県・指定都市が指定した医療機関のうち、原則として患者が事前に登録した医療機関に限っている。
- 医療費助成は都道府県・指定都市が実施主体となり、国がその2分の1を義務的に負担する。患者負担については2割とし、所得や治療の内容に応じた負担限度額が設定されている。また、一定の重症度以上の者を医療費助成の対象としているが、軽症者であっても高額な医療を継続することが必要な者についても対象としている。
▶109回午前21改題
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病の医療費助成制度で正しいのはどれか。
- 患者の自己負担割合は3割である。
- 令和3年(2021年)時点で指定難病は110疾患である。
- 国が指定した医療機関で受診した医療費が助成対象である。
- 新規に医療費助成を受けるには難病指定医による診断書が必要である。
▶105回午後28
難病対策で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 医療費助成の患者負担割合は1割である。
- 都道府県は療養生活環境整備事業を実施できる。
- 居住地の都道府県内の医療機関は全て医療費助成の対象である。
- 軽症者でも高額な医療を継続する者は医療費助成の対象となる。
- 都道府県は難病相談支援センターの設置が義務付けられている。
難病相談支援センター
▶107回午後11
難病相談・支援センターの説明で正しいのはどれか。
- 設置主体は市町村である。
- 難病医療提供体制の整備を図る。
- 難病患者の交流活動を支援する。
- 難病医療費助成制度の申請窓口である。
難病対策地域協議会
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は難病の患者への支援の体制の整備を図るため難病対策地域協議会を置くように努める(法32条)。
- 難病対策地域協議会の構成員としては、保健所を中心に医療、福祉、保健関連の機関や職種をはじめ、当事者である患者や家族なども含まれる。
▶106回午後10
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に定める難病対策地域協議会で正しいのはどれか。
- 構成員に患者の家族が含まれる。
- 医療費助成の支給認定を行っている。
- 患者や家族への医療情報の提供を目的とする。
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区に設置の義務がある。
▶108回午後8
難病対策で正しいのはどれか。
- 市町村は難病対策地域協議会の設置に努める。
- 診断基準が未確立である疾病が医療費助成の対象となる。
- 日常生活用具の給付には身体障害者手帳の取得が必要である。
- 指定医療機関による訪問看護の費用は医療費助成の対象となる。
▶101回午前12
難病対策で正しいのはどれか。
- スモンの研究体制の整備から始まった。
- 難病対策要綱は昭和36年に定められた。
- 一律の自己負担限度額が設定されている。
- 各都道府県に難病情報センターが設置されている。
医療法
第4編1章 1.医療法 2.医療計画 3.各医療対策の動向 p166~184
第4編1章 5.医療施設 p199~204
医療計画
- 医療法に定める医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。
- 記載事項として、重点的に対策を推進する5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)と5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)のほか、居宅等における医療(在宅医療)の確保、医療従事者の確保、医療の安全の確保、二次医療圏・三次医療圏の設定と医療圏ごとの基準病床数などが含まれる。
- なお、令和6年度(2024年度)の医療計画から、6事業目として「新興感染症等の感染拡大時における医療」が追加される。
▶106回午後35
医療法に基づき都道府県が定める医療計画における5疾病に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- がん
- 結核
- 脳卒中
- 慢性肝炎
- 気管支喘息
▶105回午後34
医療法において医療計画に定めるものとされているのはどれか。2つ選べ。
- 緩和医療
- 救急医療
- 歯科医療
- 先進医療
- 災害時における医療
▶108回午前24
医療計画において定めることとされている事項はどれか。
- 診療報酬の点数
- 市町村の介護医療院の設置数
- 居宅等における医療の確保に関する事項
- 市町村の地域支援事業利用者数の見込み
▶104回午後13
精神保健医療福祉施策について正しいのはどれか。
- 精神通院医療は障害者基本法に規定されている。
- 市町村には基幹相談支援センターの設置義務がある。
- 精神障害者の在宅福祉サービスの実施主体は都道府県である。
- 精神疾患は医療計画で重点的に対策を推進する疾病に位置付けられている。
医療の安全の確保
- 病院等(病院・診療所・助産所)の管理者は、提供した医療に起因した、または疑われる死亡・死産であって管理者が予期しなかった医療事故等が発生した場合、厚生労働大臣が指定した医療事故調査・支援センターに遅滞なく報告し、遺族への説明、原因究明のための調査を行わなければならない。
- 医療の安全の確保のため、都道府県・保健所設置市・特別区は医療安全支援センターを設置するように努めなければならない。同センターは、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。
▶108回午後17
医療安全支援センターの説明で正しいのはどれか。
- 医療に関する苦情に対応する。
- 地域の中核病院内に設置されている。
- 医療に起因する予期しない死亡事例の報告を受ける。
- 厚生労働省から医療事故情報収集等事業を委託されている。
▶105回午前20
医療安全対策で正しいのはどれか。
- 産科医療補償制度は医療法に基づき実施されている。
- 医療事故調査は病院の管理者に義務付けられている。
- 都道府県に医療安全支援センターの設置が義務付けられている。
- 都道府県知事は医療事故調査・支援センターを指定することができる。
医療法に定める医療施設
- 病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
- 診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
- 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。
- 地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が個別に承認する。
- 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。
▶104回午後35
医療提供体制について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 医療法において病床の種別は3つに分類されている。
- 医療計画には医療従事者の確保に関する事項を記載する。
- 日本の医療施設の病床数は過去10年間は増加傾向にある。
- 特定機能病院を称するには厚生労働大臣の承認が必要である。
- 診療所は20人以下の患者を入院させるための施設を有すると規定されている。
医療介護総合確保推進法
第4編1章 2.医療計画 p166~169
概要
- 平成26年(2014年)に成立した医療介護総合確保推進法では、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(地域包括ケアシステムの構築)のため、医療法や介護保険法などの関係法律を一体的に整備している。
- 医療法の見直しでは、都道府県は医療計画の一部として地域医療構想を策定することとし、病床機能報告制度によって、二次医療圏を原則とした構想区域ごと、病床機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)ごとに、令和7年(2025年)の医療需要、病床の必要量などを推計している。
▶107回午後21
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で規定されたのはどれか。
- 病床機能報告制度
- 医療安全支援センターの設置義務
- 医療計画への在宅医療の達成目標の記載
- 重症心身障害児(者)への日中の活動の場の確保
▶110回午前38
平成26年(2014年)に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で示された地域医療構想について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 構想区域は現行の三次医療圏を原則としている。
- 地域包括ケアシステムの進捗と密接に関係する。
- 都道府県は地域医療構想の調整会議を設けて必要な協議を行う。
- 令和2年度(2020年度)末までに約9割の都道府県で策定を終えた。
- 令和22年(2040年)の医療需要と医療従事者の必要量を推計して定める。
訪問看護制度
第4編1章 3.2〕訪問看護 p170~172
訪問看護の対象者
- 訪問看護の給付を受ける際は、要介護者等には介護保険による給付が行われ、それ以外の者には医療保険による給付が行われる。
- 介護保険の給付は医療保険の給付に優先するが、要介護者等であっても、①末期の悪性新生物や人工呼吸器を使用している状態など厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や、②主治医による特別訪問看護指示書の交付を受けた者、③認知症以外の精神障害を有する者には、医療保険の給付による訪問看護が行われる。これらに該当する者は、週3日を超えての提供が可能となっている。
▶104回午前28
がん患者の在宅療養支援における医療保険および介護保険の活用について正しいのはどれか。
- 同日に医療保険と介護保険の利用はできない。
- 居宅療養管理指導は医療保険による診療報酬の対象である。
- 訪問看護の利用にあたっては医療保険と介護保険のいずれかを利用者が選択できる。
- 40歳から65歳未満のがん患者は介護保険法で定める特定疾病の状態のときに介護保険が利用できる。
保健師助産師看護師法
第4編1章 4.4〕看護職員等 p193~197
保健師の届出義務
▶107回午前1
保健師の業務従事者届について正しいのはどれか。
- 医療法で規定されている。
- 届出の間隔は一年ごとである。
- 居住地の都道府県知事に届け出る。
- 届出は業務に従事する保健師の義務である。
守秘義務
▶107回午前39・105回午前1類問・101回午後29類問
市町村保健師が実施する保健サービスで保健師が知り得た秘密を漏らしてはならないことについて規定している法律はどれか。2つ選べ。
- 母子保健法
- 地域保健法
- 地方公務員法
- 保健師助産師看護師法
- 次世代育成支援対策推進法
▶108回午後13
自治体で働く保健師の活動に関して守秘義務規定がある法律はどれか。
- 刑法
- 医療法
- 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
医療保険各法
第4編2章 1.医療保険制度 p208~209
医療保険制度
▶101回午前34
医療保険でないのはどれか。
- 介護保険
- 国民健康保険
- 組合管掌健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 全国健康保険協会管掌健康保険
高齢者の医療の確保に関する法律
第4編2章 3.3〕後期高齢者医療制度 p211~212
後期高齢者医療制度の概要
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年度(2008年度)から後期高齢者医療制度が開始した。被保険者は原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は原則1割(所得により2割または3割)である。
- 後期高齢者医療制度の医療給付の財源は、後期高齢者の保険料負担が1割、74歳以下からの後期高齢者支援金が4割、公費負担が5割となっている。
▶105回午前18
現行の後期高齢者医療制度の運営における医療給付の財源負担で正しいのはどれか。
- 後期高齢者支援金は45歳以上75歳未満の者の医療保険料から拠出される。
- 国、都道府県および市町村による公費が全体の約5割を占めている。
- 高齢者が医療機関を受診した時の自己負担額は無料である。
- 後期高齢者による保険料は全体の約2割を占めている。
特定健康診査・特定保健指導
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上への健康診査のほか、40~74歳の被保険者・被扶養者に対する特定健康診査・特定保健指導が、市町村を含む医療保険者に義務づけられている。特定健康診査の結果から、生活習慣病のリスクの高さ順に、積極的支援レベル、動機づけ支援レベル、情報提供レベルにグループ分けされ、特定保健指導が実施される。
- なお、歯周疾患検診や骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診などは健康増進法に基づき市町村が実施する。
▶106回午後23
高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて市町村が行う事業はどれか。
- がん検診
- 歯周疾患検診
- 特定健康診査
- 就労者の定期健康診査
- 生活保護受給者の検診
▶102回午後11
特定健康診査・特定保健指導について適切なのはどれか。
- 実施義務者は医療保険者である。
- 対象年齢は60~74歳と定められている。
- 服薬治療中の者は特定健康診査の対象でない。
- 動機付け支援対象者と積極的支援対象者に対して一緒にグループ面接を行う。
特定健康診査の基本的な実施項目
- 質問票(服薬・喫煙歴等)
- 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)
- 血圧測定
- 理学的検査(身体検査)
- 検尿(尿糖、尿蛋白)
- 血液検査(脂質検査・血糖検査・肝機能検査)
このうち、腹囲とBMIによって生活習慣病のリスクを判定し、腹囲が男≧85cm・女≧90cmの場合、または腹囲はそれ未満であるがBMI25以上である場合、特定保健指導における支援の対象となる。
▶110回午前23
特定健康診査の基本的な項目はどれか。
- 眼底検査
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 心電図検査
- 血清クレアチニン検査
介護保険法
第5編1章 介護保険 p220~233
要介護認定
- 市町村は介護保険被保険者からの要介護認定の申請を受けて、主治医の意見(主治医意見書)の聴取や心身の状況などの調査を行い、一次判定を行う。その結果等に基づき、市町村に設置された介護認定審査会は要介護状態の区分の審査・判定を行う(二次判定)。
- 介護サービス利用者は原則1割を費用負担して居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなどの介護サービスを受ける。ただし、居宅や施設のサービスを受ける際に介護支援専門員等が作成するサービス計画の費用については、介護保険から10割給付される(自己負担なし)。
▶104回午前18
介護保険制度について正しいのはどれか。
- 利用者は居宅介護サービス計画を作成するための費用の1割を負担する。
- 介護保険認定の申請手続きの代行は被保険者の家族以外はできない。
- 利用者の日常生活能力の自己申告に基づき要介護認定が行われる。
- 利用者の選択によってサービスを決定することが基本である。
被保険者・給付内容
- 介護保険の被保険者(給付を受けられる者)は、65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の医療保険加入者である第2号被保険者である。
- 第2号被保険者は、脳血管疾患などの老化に起因する特定疾病に罹患して要介護等の認定をされた場合に、介護保険からの給付が受けられる。
- 要介護認定で要介護状態に該当する者には介護給付が、要支援状態に該当する者には予防給付が支給される。
▶110回午前34
介護保険について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 被保険者は40歳以上の者である。
- 財源は保険料と公費が50%ずつである。
- 特定疾病には交通事故による外傷が含まれる。
- 要介護者のケアプランは地域包括支援センターが作成する。
- 要介護認定で非該当になったものは予防給付の対象となる。
地域包括ケアシステム
- 地域包括ケアシステムは、高齢者の日常生活圏域で、医療、介護、予防、住まい、生活支援の5つの視点での取り組みを包括的・継続的に行う地域の体制で、市町村等が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて構築することとされる。政府は団塊の世代が75歳以上となる令和7年(2025年)の実現を目途に構築を進めている。
- 単位となる日常生活圏域は、市町村介護保険計画において地理的条件、人口、交通事情などを勘案して市町村が設定するもので、概ね30分以内に必要なサービスが提供される範囲とされる(具体的には中学校区)。
▶108回午前8
地域包括ケアシステム構築のために行われる活動について正しいのはどれか。
- 地域の特性に応じて国が作り上げる。
- 既存のケアシステムの実態把握を行う。
- 入院を主体とするサービス体制を中心に整備する。
- 保健医療福祉部門ごとの体制に合わせて構築する。
▶104回午前12・110回午前7統合
介護保険法で規定される市町村介護保険事業計画の日常生活圏域について正しいのはどれか。
- 市町村が範囲を設定する。
- 高齢者の人口で数を決める。
- 二次医療圏と同規模である。
- 介護保険法制定時に定められた。
- おおむね小学校区である。
地域包括ケアシステム等における相互援助
- 支援には、生活保護など税による公の負担により支える公助、介護保険など負担と受給による支え合い(社会保険方式)である共助、費用負担が制度的に裏付けされていないボランティアなどの助け合いである互助(インフォーマルサポート)、民間サービスの利用や自発的な体重測定など自ら行う自助がある。
- 地域包括ケアシステムにおいては、自助と互助の果たす役割が大きくなるとされる。
▶103回午前10改題
地域包括ケアシステムの推進に関する説明で正しいのはどれか。
- 公助が優先される。
- 実施主体は保健所である。
- 令和2年(2020年)に向けた対応策である。
- 高齢者のニーズに応じた住まいの整備が含まれる。
▶107回午前2
地域包括ケアシステムにおける相互援助の概念と具体的な取り組みとの組合せで適切なのはどれか。
- 自助――民間サービスの購入
- 互助――医療保険
- 共助――生活保護
- 公助――ボランティア
地域包括支援センター
- 介護保険法に定められる地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。
- 地域包括支援センターが行う地域支援事業では、要支援者や虚弱高齢者に対する介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業を行う介護予防・日常生活支援総合事業のほか、包括的支援事業として、①介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)、②総合相談支援業務、③権利擁護業務(虐待の防止、早期発見)、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(介護支援専門員への助言、ネットワークづくり)などがある。
▶106回午前23
介護保険法に基づく地域包括支援センターの基本機能で正しいのはどれか。
- 介護予防ケアマネジメント
- 高齢者の住まいの整備
- 要介護認定の実施
- 福祉用具の貸与
▶102回午後25
介護保険法における権利擁護事業を担当するのはどれか。
- 社会福祉協議会
- 地域福祉センター
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
▶104回午前27
介護保険法に基づく地域支援事業について正しいのはどれか。
- 実施主体は保健所である。
- 包括的支援事業が含まれる。
- 家族介護を支援する事業はない。
- 地域支援事業に係る費用は介護報酬から支払われる。
▶110回午後31
地域支援事業のうち包括的支援事業はどれか。2つ選べ。
- 総合相談支援
- 通所型サービス
- 家族介護支援事業
- 介護予防ケアマネジメント
- 地域リハビリテーション活動支援事業
▶102回午前22
地域包括支援センターについて正しいのはどれか。
- 概ね1万人ごとに設置する。
- 要介護状態区分の決定を行う。
- 地域密着型介護予防サービスの提供を行う。
- 介護支援専門員の地域ネットワークを構築する。
▶102回午後13
介護予防・日常生活支援総合事業で正しいのはどれか。
- 地域生活支援事業である。
- 平成17年(2005年)に創設された。
- 要支援認定を受けている者も対象である。
- 一般介護予防事業の対象は第2号被保険者である。
介護保険法改正の主なあゆみ
●平成17年(2005年)改正
予防給付の創設、地域支援事業の創設、地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの創設など
●平成23年(2011年)改正
地域包括ケアシステムの推進、介護保険事業計画の策定、定期巡回・臨時対応サービスや複合型サービスの創設など
●平成26年(2014年)改正
医療介護総合確保推進法に基づく在宅医療・介護の連携や地域ケア会議の推進、予防給付のうち訪問介護・通所介護の地域支援事業への移行、一定以上所得者の利用者負担の見直し(2割)など
●平成29年(2017年)改正
介護医療院(施設サービス)の創設、介護納付金への総報酬割の導入、利用者負担2割のうち特に所得の高い者を3割に引き上げなど
▶101回午前35
平成23年(2011年)の介護保険法改正によって創設されたのはどれか。2つ選べ。
- 予防給付
- 複合型サービス
- 居宅療養管理指導
- 地域包括支援センター
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶104回午後23
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉による介護保険法の見直し事項はどれか。
- 地域ケア会議の推進
- 地域密着型サービスの創設
- 介護予防訪問看護の地域支援事業への移行
- 市町村単位での医療機能の分化および連携の推進
▶107回午前8
平成29年(2017年)の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律で改正されたのはどれか。
- 介護医療院の創設
- 地域ケア会議の推進
- 全国一律の予防給付の地域支援事業への移行
- 一定以上所得のある者のサービス費の利用者負担2割
国民年金法・厚生年金保険法
第5編2章 1.公的年金 p234~235
公的年金の特徴
- 公的年金制度は、20歳以上の全国民が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2階建ての体系となっている。
- 公的年金の被保険者には、高齢になれば老齢年金が、障害の状態になれば障害年金が、死亡した場合は遺族年金が支給される。
- 被保険者は、自営業者などの第1号被保険者、厚生年金に加入する会社員や公務員などの第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者となっている。
▶109回午後21
公的年金制度について正しいのはどれか。
- 20歳以上の学生は国民年金に任意加入である。
- 20歳未満の傷病による障害者にも障害基礎年金が支給される。
- 国民年金から支給される年金給付の1つは老齢厚生年金である。
- 被用者に扶養される配偶者は国民年金の第2号被保険者である。
生活保護法
第5編2章 2.生活保護 p235
概要
- 生活保護制度は、憲法25条(生存権)の保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できない、生活に困窮する国民に対し、国が必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である。その基本原理として、①国家責任、②無差別平等、③最低生活保障、④補足性の4つが掲げられている(法1~4条)。
- 生活保護は世帯単位で行い、要保護者の生活需要の性質等に応じて、①生活、②教育、③住宅、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の8種類の扶助が設けられている。
▶104回午前39
生活保護制度について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 扶助の種類は7種類である。
- 保護施設に更生施設がある。
- 日本国憲法第14条の理念に基づいている。
- 保護は世帯を単位とすることを原則とする。
- 介護扶助によって介護保険料が現金給付される。
▶106回午前39改題
生活保護制度で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 生活扶助は現金給付である。
- 分娩費用は医療扶助である。
- 被保護人員は増加傾向である。
- 被保護世帯には障害者世帯が最も多い。
- 最低限度の生活を保障することが目的に含まれている。
▶110回午前39
生活保護について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 介護扶助は現物給付である。
- 所得保障の分類で社会手当に該当する。
- 保護開始の理由は「傷病による」が最も多い。
- 基本原理として補足性の原理が定められている。
- 社会保険制度として保険料によって運営される。
生活困窮者自立支援法
第5編2章 6.地域福祉 p243~245
概要
▶108回午後18改題
生活困窮者自立支援制度で正しいのはどれか。
- 生活保護世帯が対象となる。
- 雇用保険法に規定されている。
- 住居確保給付金の支給がある。
- 進学準備給付金の支給がある。
子ども・子育て支援法
第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239
概要
- 平成24年(2012年)に制定された子ども・子育て支援法に基づく新制度では、市町村を実施主体として、①認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付(施設型給付)および小規模保育等への給付(地域型保育給付)の創設、②認定こども園制度の改善、③地域子ども・子育て支援事業の充実などが図られた。
- 令和元年(2019年)の改正では、3歳から5歳までのすべての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの幼稚園、保育園、認定こども園などの費用が無償化された。
▶106回午後20
平成24年(2012年)に制定された子ども・子育て支援新制度に含まれるのはどれか。
- 子どもの事故予防強化
- 認定こども園制度の改善
- マタニティマークの配布
- 妊娠期からの児童虐待防止
- 医療的ケアを必要とする子どもへの支援の向上
児童福祉法
第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239
児童相談所
▶107回午前21
児童相談所について正しいのはどれか。
- 市町村に設置義務がある。
- 養子縁組の相談に応じる。
- 母親を一時保護する機能を持つ。
- 児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づき設置される。
児童虐待に係る通告
▶101回午前36
町立小学校で身体的虐待が疑われる外傷のある児童を発見した。
児童虐待の防止等に関する法律に基づき通告する機関として正しいのはどれか。
2つ選べ。
- 警察署
- 保健所
- 教育委員会
- 児童相談所
- 福祉事務所
次世代育成支援対策推進法
第5編2章 3.児童家庭福祉 p235~239
概要
- 次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のため、国・地方公共団体、事業主、国民の責務を規定している。
- 市町村は市町村行動計画、都道府県は都道府県行動計画を策定することができる。
▶110回午後28
A市では職員の仕事と子育ての両立を図るための市町村行動計画を策定した。
この取り組みの根拠となる法律はどれか。
- 健康増進法
- 児童福祉法
- 母子保健法
- 子ども・子育て支援法
- 次世代育成支援対策推進法
障害者基本法
第5編2章 4.障害者福祉等 p239~241
障害者計画
▶108回午後19
市町村に策定が義務付けられている計画はどれか。
- 障害者計画
- 医療費適正化計画
- 予防接種基本計画
- がん対策推進基本計画
▶101回午後34
市町村が策定しなければならない計画はどれか。2つ選べ。
- 障害者計画
- 医療費適正化計画
- 予防接種基本計画
- 特定健康診査等実施計画
- 感染症の予防のための施策の実施に関する計画
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律〈障害者虐待防止法〉
第5編2章 4.4〕障害者虐待防止対策 p240
概要
- 平成23年(2011年)に制定された障害者虐待防止法では、養護者や障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について、発見した者は速やかに市町村に通報しなければならないとされている。
- 市町村は障害者虐待防止センターを、都道府県は障害者権利擁護センターを設置して各種業務を行う。
▶102回午前11
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について正しいのはどれか。
- 市町村は障害者権利擁護センターを設置する。
- 障害児入所施設従事者による虐待に適用される。
- 障害者虐待には正当な理由なく障害者の身体を拘束することが含まれる。
- 障害者を雇用する事業主による虐待を発見した者は労働基準監督署に通報する。
食品表示法等
第7編2章 12.いわゆる「健康食品」対策 p290~291
保健機能食品
保健機能食品制度として、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類がある。これらの食品では、食品、栄養成分または機能性関与成分の機能に関する表示とともに、摂取上の注意事項や1日当たりの摂取目安量、摂取の方法などを表示しなければならない。
- 特定保健用食品は、食生活において特定の保健の目的(おなかの調子を整える等)が期待できる旨の表示ができるものである。特定保健用食品として販売する場合、食品ごとに有効性や安全性を消費者庁の個別審査を受け、許可を受けなければならない(健康増進法43条1)。
- 栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど栄養成分の補給のために利用される食品で、食品表示法に基づく食品表示基準で定められた栄養成分の機能の表示をして販売されるものである。
- 機能性表示食品は、食品関連事業者の責任において、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとして消費者庁長官に届け出られたものである。個別審査を行わない点で特定保健用食品とは異なる。
▶108回午前23
保健機能食品制度の説明で正しいのはどれか。
- 特定保健用食品の許可は厚生労働大臣が行う。
- 機能性表示食品は妊産婦に適する旨の表示ができる。
- 栄養機能食品は健康増進法に基づく一定の要件を満たしている。
- 保健機能食品は1日当たりの摂取目安を表示しなければならない。
▶107回午前19
食品に係る事項と法令との組合せで正しいのはどれか。
- 食中毒の届出――食品安全基本法
- 栄養機能食品の表示――食育基本法
- 特定保健用食品の許可――健康増進法
- アレルゲンを含む食品であることの表示――食品衛生法
労働安全衛生法
第8編 3.労働衛生管理の基本 p300~301
労働衛生の3管理
労働安全衛生法では、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理の労働衛生の3管理を整備している。
- 作業環境管理は、作業環境を的確に把握し、様々な有害要因を取り除いて、良好な作業環境を確保するものである。
- 作業管理は、作業の内容や方法によって有害な物質やエネルギーが人に及ぼす影響が異なるため、これらの要因を適切に管理して、労働者への影響を少なくすることである。
- 健康管理は、健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導であり、労働者の健康状態を把握し、作業環境や作業との関連を検討することにより、労働者の健康障害を未然に防ぐものである。
▶106回午後12
大型の石材を建築材料に加工する工場で、設置されている石材加工用の機械に防振ゴムを取り付け、工場内の騒音の低減を図った。この対策に該当するのはどれか。
- 健康管理
- 作業環境管理
- 作業管理
- 総括管理
▶105回午前14・101回午後14類問
産業保健における作業管理に該当するのはどれか。
- 定期的に健康診断を行う。
- 工場内の騒音を測定する。
- 労働時間内に休憩時間をとる。
- 作業場に排気装置を設置する。
▶109回午後13
産業保健における作業管理はどれか。
- 定期的に健康診断を行う。
- 適切に保護具を装着する。
- 作業環境の有害要因を除去する。
- 労働衛生に関する体制を構築する。
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)
▶108回午後12
労働安全衛生法に実施が規定されているのはどれか。
- 特定健康診査
- じん肺健康診断
- 情報機器作業配置前健康診断
- 心理的な負担の程度を把握するための検査
長時間労働者に対する面接指導制度
すべての事業所を対象に、長時間労働者に対する医師による面接指導制度が義務づけられている。
▶105回午後8
労働安全衛生法に基づき、労働者50人未満の事業者に義務付けられているのはどれか。
- 産業医の選任
- 衛生委員会の設置
- ストレスチェックの実施
- 長時間労働者への医師の面接指導
地域産業保健センター
▶102回午前13
労働安全衛生法に基づく産業保健について正しいのはどれか。
- 特定業務従事者の健康診断は年に1回以上実施する。
- 50人以上の事業場ではストレスチェックが義務付けられている。
- 300人以上の事業場では地域産業保健センターが健康管理を行う。
- 海外派遣労働者の健康診断は産業医の判断で省略することができる。
地域産業保健センターについて正しいのはどれか。
- 衛生管理者の育成を行う。
- 産業医の研修を実施する。
- 個別訪問による産業保健指導を行う。
- 労働者100人未満の事業場を対象とする。
衛生管理者
- 衛生管理者は受験資格を満たして試験に合格することで得られる国家資格で、衛生に関する技術的事項の管理を行う者であり、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者がある。
- 業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において衛生管理者を選任する。また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または常時500人以上の労働者を使用する有害業務事業場では、少なくとも1人を専任としなければならない。
▶107回午前37
衛生管理者について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国家資格である。
- 労働安全衛生法に規定されている。
- 安全に関する技術的事項を管理する。
- 作業者の健康障害を防止するための作業指揮を行う。
- 常時100人以上の労働者を使用する事業場は専任とする。
▶101回午前16
衛生管理者について正しいのはどれか。
- 労働基準法に規定されている。
- 都道府県知事が認定する資格である。
- 総括安全衛生管理者は事業場の経営者が兼ねる。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任する。
▶110回午後12
常時使用する労働者が35名の事業場(製造業)に選任が義務付けられているのはどれか。
- 産業医
- 保健師
- 衛生管理者
- 安全衛生推進者
作業場巡視
労働安全衛生規則において、週1回以上の職場巡視を行うことが規定されているのはどれか。
- 産業医
- 衛生管理者
- 安全衛生推進者
- 総括安全衛生管理者
労働基準法・労働者災害補償保険法
第8編 8.労働災害補償と業務上疾病 p306~308
労災保険制度
- 労働者が業務上負傷または疾病にかかった場合には、労働基準法に基づき事業主の災害補償責任が明確にされている。
- 一方、労働者災害補償保険法に基づき保険給付がなされた場合は、事業主は災害補償責任を免れる。労災保険は政府が管掌し、事業に要する費用は原則として事業主が負担する保険料で賄われる。
▶109回午前13
労災保険制度について正しいのはどれか。
- 事業主の災害補償責任は労働基準法に規定されている。
- 休業補償は休業1日目から補償の対象となる。
- 保険料は事業主と労働者が折半で負担する。
- 労災補償の申請は市区町村の窓口で行う。
学校教育法
第10編 1.学校保健行政の動向 p341~344
概要
▶108回午後32・102回午後28類問
学校教育法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- 食育の推進
- 学校保健の定義
- 健康診断の実施
- 学級閉鎖の実施基準
- 養護教諭の配置義務
学校保健安全法
第10編 1.学校保健行政の動向 p341~344
健康診断(保健管理)
●就学児の健康診断
市町村の教育委員会が実施する。学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。
●児童生徒等の定期の健康診断
学校において毎学年6月30日までに実施する。定期健康診断実施後、21日以内にその結果を児童生徒、保護者等に通知し、治療の勧告や指示などの事後措置を取ることとされる。
●教職員の定期・臨時健康診断の実施
学校の設置者が実施する。
▶107回午後31
学校保健安全法に基づく児童生徒の定期健康診断で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 学校行事に位置づく教育活動として行われる。
- 毎学年5月末日までの間に実施する。
- 座高は小学校低学年で測定する。
- 実施主体は教育委員会である。
- 結果に基づき事後措置を行う。
▶110回午後2
学校保健安全法で規定されている児童生徒等に実施する定期健康診断で正しいのはどれか。
- 実施責任者は養護教諭である。
- 毎学年5月31日までに実施する。
- 検査項目の1つに栄養状態がある。
- 15日以内に本人および保護者への結果の通知義務がある。
▶103回午前19
学校保健行政について正しいのはどれか。
- 対象に幼稚園が含まれる。
- 厚生労働省が所管している。
- 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。
- 都道府県教育委員会は都道府県内の市町村立学校を直轄している。
学校保健計画
- 学校では、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導など保健に関する事項についての計画(学校保健計画)を策定し、これを実施しなければならない。
- 文部科学大臣が定める換気、採光、照明、保温、清潔保持などの学校環境衛生基準に基づき、飲料水の検査など定期・臨時の環境衛生検査が、学校薬剤師を主として実施されている。
▶109回午後11
学校保健に関係する教職員と職務の組合せで正しいのはどれか。
- 校長――学校保健委員会の運営
- 栄養教諭――学校保健計画の立案
- 保健主事――学校医の任命
- 学校薬剤師――環境衛生検査への従事
▶106回午前34
学校保健活動で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 保健教育は学習指導要領を踏まえて行う。
- 定期の学校環境衛生検査は学校医が従事する。
- 就学時の健康診断は学校の設置者が実施する。
- 学校における救急処置は応急的なものである。
- 学校安全計画は学校保健計画に含めて策定する。
学校における感染症予防
- 校長は、感染症にかかっている、または疑いがある、かかるおそれのある児童生徒等の出席を停止させることができる。
- 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。
▶107回午前20
学校保健について正しいのはどれか。
- 保育所は学校教育法に規定されている。
- 学校保健行政は厚生労働省が所管している。
- 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。
- 学校の設置者は感染症の予防のための臨時休業を行うことができる。
養護教諭
- 養護教諭は保健室を経営し、健康相談または児童生徒等の健康状態の日常的な観察を行い、健康上の問題があると認められるときは遅滞なく児童生徒等への保健指導、保護者への必要な助言を行うこととされる。
- このほか、感染症・食中毒の予防、保健教育、健康診断の計画立案から評価、学校保健計画等の策定への参加などの取り組みが挙げられる。
▶104回午後21
健康上の問題がある児童生徒に対して、養護教諭を中心に行う個別の保健指導を規定しているのはどれか。
- 文部科学省設置法
- 学校保健安全法
- 学校教育法
- 教育基本法
▶106回午後30
児童に感染症の疑いがある場合の養護教諭の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 学級閉鎖の期間を決定する。
- 全学級に保健だよりを配布する。
- 保健所に出席停止の措置を連絡する。
- 当該児童の保護者に出席停止を指示する。
- 当該児童の保護者に医療機関受診を勧奨する。
▶103回午前14
養護教諭の職務で正しいのはどれか。
- 学校給食の衛生管理
- 定期健康診断の評価
- 学校保健委員会の設置
- 感染症による出席停止の決定
▶110回午前26
養護教諭の職務で正しいのはどれか。
- 保健室の経営
- 臨時休業の決定
- 学校保健計画の立案
- 定期環境衛生検査の実施
- 保健教育の年間計画の立案
学校給食法
第10編 3.学校給食 p346~347
概要
▶101回午後25
食に関する実践的な指導を行う者として学校給食法に規定されているのはどれか。
- 栄養教諭
- 養護教諭
- 保健主事
- 学校歯科医
- 食生活改善推進員
複合問題
▶101回午前6
健康診査と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
- 妊産婦健康診査――母体保護法
- 3歳児健康診査――母子保健法
- 就学時健康診断――児童福祉法
- 特定健康診査――健康増進法
▶107回午後22
医療費の助成と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。
- 医療扶助――社会福祉法
- 療育医療――障害者基本法
- 自立支援医療(更生医療)――障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度――難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
▶105回午前19
公衆衛生行政の制度・対策と法律の組合せで正しいのはどれか。
- 大気汚染の監視――大気汚染防止法
- 労働者の健康診断――労働基準法
- 食品等の収去検査――食品安全基本法
- 小学校における保健学習――学校保健安全法
▶106回午後19
学校保健行政に関する内容と法律の組合せで正しいのはどれか。
- 学校医の配置――労働安全衛生法
- 特別支援教育――障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
- 教職員の健康診断――学校保健安全法
- 不登校児童生徒の支援――教育基本法
保健師国家試験の出題分野の一つである疫学・保健統計学は、聞き慣れない専門用語が多く登場し、また計算問題も多くあるため、受験生が苦手意識を持ちやすい分野です。しかし、しっかりと理解すれば必ず得点に結びつき、他の受験生と差を付けやすい分野でもあり、かつ保健師実務上でも使用するシーンは多く、保健師を目指す上で避けては通れない分野でもあります。
疫学・保健統計学の勉強方法としては、複雑な理論を一つ一つ理解していくこと、さらになるべく多くの問題を解いて応用的な知識を定着させていくことが最も重要となります。
当ページでは、保健師国家試験出題基準(令和5年版)に沿って用語等の解説を行いながら、110回試験(2024年)から90回試験(2004年)までの21年分の過去問題の中から関連する問題を取り上げ、十分な理解とアウトプットを図れるように構成しています。
公衆衛生テキスト「国民衛生の動向」を合わせて活用しながら、効果的に保健師国家試験の勉強を進めていただければ幸いです。
厚生労働統計協会では、「生物統計学の道標」「厚生統計テキストブック」など実践的な統計学のテキストを出版しています。身に付けた統計知識をより深く理解したい方におすすめいたします。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
目次
疫学の概念・方法
疫学研究
- 疫学研究は、人間集団を対象として疾病発症などの頻度や分布を調査し、その要因を明らかにして集団の治療や予防につなげる科学研究である。
- 疫学研究を行うに当たっては、倫理指針に基づいて研究対象者の個人の尊厳と人権を守ることが重要となる。
▶90回午前59
疫学について誤っているのはどれか。
- 人間集団を対象としている。
- 作用因子と健康状態との関係を明らかにする。
- 個人の疾病の原因究明が主な目的である。
- 経験論的法則を導き出す。
▶101回午前23
疫学研究を行う上で最も重要なのはどれか。
- 研究の科学的価値
- 参加者の人権の尊重
- 地域の生活水準の向上
- 参加者への利益の還元
曝露
- 疫学における曝露とは、人の健康に危害を加える要因(危険因子)にさらされることをいう。例えば感染症や食中毒においては、細菌やウイルスなどの感染源・感染経路が危険因子となる。
- 横軸に日付、縦軸に患者数を設定したグラフでは、単一曝露では1峰性、複数回の曝露では2峰性、持続的な連続曝露では多峰性を特徴とする。
▶91回午前66
ある小学校で、腹痛と下痢を訴えて休む児童が集団発生した。図は患者発生数である。

解釈で正しいのはどれか。
- 9月1日の患者は誤分類である。
- 食中毒の集団発生である。
- 単一曝露による集団発生である。
- 2次感染が認められる。
▶99回午前24
A小学校で発生した感染症の発症状況を図に示す。

感染源への曝露について最も考えられるのはどれか。
- 単一曝露があった。
- 多量曝露があった。
- 連続曝露があった。
- 複数回の曝露があった。
介入研究

- 介入研究は、発症頻度の高い疾患について、研究者が調査対象者に対して意図的に介入を行い、介入を行わない群と比較してその影響を検討する。
- 介入研究の特徴として、介入と結果の間の時間的関係が明確で、観察研究よりもエビデンスレベルが高いことが挙げられる。
- 対象者を2群に振り分ける際に無作為化(ランダム化)を行うものを無作為化比較試験、行わないものを非無作為化比較試験という。
▶95回午後28・92回午前65類問
市内の中学校10校を無作為に2群に分け、一方の生徒に肥満予防のパンフレット配布に加え肥満予防教育の授業を実施し、他方の生徒に肥満予防のパンフレット配布のみを行った。実施の前後に肥満予防行動について意識調査を行った。
この調査方法はどれか。
- 介入調査
- 横断的調査
- 生態学的調査
- 症例対照調査
▶96回午後21
エビデンスレベルが最も高い研究デザインはどれか。
- 横断研究
- 症例対照研究
- コホート研究
- 無作為化比較試験
▶97回午前22
介入研究として正しいのはどれか。
- 発生頻度の低い疾患に適用可能である。
- 仮説設定のために用いられることが多い。
- 介入と結果との時間的関係が明確である。
- 複数の曝露要因の影響を検討することはできない。
▶101回午前38
介入研究で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 仮説設定のために用いられる。
- 無作為化(割付)を前提としている。
- 介入と結果との時間的関係が明確である。
- 複数の曝露要因の影響を検討することはできない。
- 観察研究より高いレベルのエビデンスを提供する。
記述疫学
●生態学的研究
国や都道府県、市町村などの集団(地域)単位で、異なる集団との比較を行う。
●横断研究(断面研究)
ある一時点における疾病の発症(有病率)と曝露との関連性を調べる。
▶97回午後21
ある時点における世界各国の一人当たり食塩摂取量と高血圧症有病率との関係を図示し、相関係数を求めた。
この研究方法はどれか。
- 横断研究
- 生態学的研究
- コホート研究
- 症例対照研究
▶91回午前60
断面調査で明らかにできる疾病頻度指標はどれか。
- 罹患率
- 有病率
- 死亡率
- 致命率
▶96回午前22
市の全住民を対象とした横断調査で喘息の患者は7%であった。
この数値が示すのはどれか。
- 有病率
- 罹患率
- 相対危険
- 寄与危険割合
分析疫学
●症例対照研究
目的となる疾患に罹患した集団(症例群)と罹患したことのない集団(対照群)を選び、仮説要因に過去に曝露した者の割合を比較することで、算出されたオッズ比などから疾病の原因を探る方法である。
●(前向き)コホート研究
対象となる集団(コホート)を要因(曝露・非曝露)ごとに分類し、将来に向かって追跡して疾病等の発生状態を観察し、相対危険度や寄与危険度などから疾病の原因を探る方法である(縦断調査)。
症例対照研究は調査時点から過去に向かって調査するため後ろ向き研究、コホート研究は調査時点から将来に向かって調査するため前向き研究という。
▶103回午後34
因果関係を推測することができる研究デザインはどれか。2つ選べ。
- 横断研究
- 記述疫学
- 生態学的研究
- コホート研究
- 症例対照研究
▶95回午後26
分析疫学はどれか。
- 断面調査で喫煙習慣と飲酒習慣との関係を検討した。
- 食中毒発生状況について季節変動の関係を検討した。
- 縦断調査で喫煙習慣と胃癌罹患率との関係を検討した。
- 脳血管疾患の死亡率について都道府県ごとの差異を検討した。
▶108回午前28
症例対照研究で計算が可能な指標はどれか。
- 受療率
- オッズ比
- 寄与危険
- 推計患者数
- 5年生存率
▶106回午後26
症例対照研究で正しいのはどれか。
- 寄与危険の近似値を推定できる。
- 研究対象とする疾病が治癒した者を対照群とする。
- 症例群と対照群の過去の要因曝露状況を比較する。
- 症例群と対照群を追跡調査して死亡率を比較する。
- 症例群に試験薬、対照群に偽薬〈プラセボ〉を投与する。
▶91回午前63
A市保健所は多施設共同疫学研究に参加し、がんの発生要因について調査することになった。住民票から無作為に選ばれた40歳以上の男女それぞれ100名の協力を得て、現在の健康状態および過去の生活習慣を把握した。協力者には以後毎年の基本健康診査の受診を勧奨し、死亡小票ともマッチングさせ、死亡および疾病発症を追跡した。
この調査方法はどれか。
- 横断的調査
- 症例対照調査
- 前向きコホート調査
- 無作為割付臨床試験
▶94回午前62
原子力発電所の事故による放射能汚染の人体への影響について、事故後から継続的に調査する疫学の手法はどれか。
- 横断調査
- 後ろ向き調査
- 症例対照調査
- 縦断調査
▶93回午前59
コホート調査はどれか。
- 都道府県別に肝臓癌の死亡率を調べて比較した。
- 胃癌患者群と胃潰瘍患者群との飲酒習慣を比較した。
- 喫煙習慣のある集団とない集団との脳卒中発生状況を経年的に追跡した。
- 1人当たりの牛乳消費量と大腿骨頸部骨折発生率との国際比較を行った。
▶105回午前28
コホート研究と比較した症例対照研究の特徴で正しいのはどれか。
- 研究期間が長い。
- 相対危険が直接計算できる。
- まれな疾病の研究に適している。
- 事象の発生順序が明らかである。
- 情報の偏り〈バイアス〉が少ない。
▶102回午前17
疫学研究に関する記述で正しいのはどれか。
- 記述疫学には介入研究が含まれる。
- 横断研究によって因果関係を証明できる。
- 分析疫学は記述疫学よりも疾病と要因との関連を示しやすい。
- 前向きコホート研究は稀少疾病の罹患リスクを検討するのに優れている。
▶94回午前59
疫学調査法で正しいのはどれか。
- 前向き調査は原因不明の疾患の発生要因の研究に適している。
- 生態学的研究は個人を分析の対象とする。
- 症例対照研究は介入研究の1つである。
- コホート研究は希少疾患の研究に適している。
因果関係
- 強固性:要因と疾病の間に強い関係があること。相対危険やオッズ比が大きいほど強い関連がある。
- 一致性:異なる条件下でも同じ結果が反復されること。一致性は因果推論を強める。
- 時間性(前後関係):要因と疾病の関係が続発的であること。時間性は因果推論に必須の必要条件である。
- 特異性:特定の要因が特定の疾病をもたらすこと。
- 整合性:異なる研究で得られた事実と一致すること。
▶110回午後23・96回午前21類問
因果関係を推論する上で相対危険やオッズ比の大きさが指標となるのはどれか。
- 関連の一致性
- 関連の強固性
- 関連の時間性
- 関連の整合性
- 関連の特異性
▶93回午前60
疫学研究における因果推論で正しいのはどれか。
- 特異性は因果推論に必須である。
- 関連の一致性は因果推論を強める。
- 統計学的に有意な相関は因果関係である。
- 時間的関係性は因果推論の十分条件である。
▶100回午後32
疫学研究における因果関係の推論で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 関連の一致性は因果推論を強める。
- 統計学的に有意な関連は因果関係である。
- 関連の整合性は因果推論の十分条件である。
- 関連の特異性は因果推論の必要十分条件である。
- 関連の時間的関係性は因果推論の必要条件である。
▶97回午後30
疫学的因果関係について正しいのはどれか。
- 関連の特異性は必須の条件である。
- 相対危険度が高いことは関連の強固性を示す。
- 有意な関連があれば因果関係があると判断する。
- 関連の一致性とは、動物実験で同様の結果となることを指す。
- 関連の時間性とは、曝露から発病までの時間が短いことである。
▶101回午後17・94回午前60類問
過去5年間にA工場(従業員数1,000人)で15人、B工場(従業員数850人)で9人の肝癌患者が発生していたことがわかった。両工場では機械の洗浄に薬品Cを使用している。
薬品Cと肝癌の疫学的関係で最も適切なのはどれか。
- 薬品Cは肝癌の原因である。
- 薬品Cと肝癌には関連がある。
- 薬品Cと肝癌には因果関係はない。
- 薬品Cと肝癌との関係は不明である。
必要条件・十分条件
- 「Aならば必ずB」の関係が成立するとき、BはAの必要条件、AはBの十分条件という。
- 「Aならば必ずB」「Bならば必ずA」両方の関係が成立するとき、A(B)はB(A)の必要十分条件という。
▶99回午前23
インフルエンザの原因と発症との因果関係で正しいのはどれか。
- ウイルスは発症の必要条件である。
- ウイルスは発症の十分条件である。
- ウイルスは発症の必要十分条件である。
- ウイルスは発症の必要条件でも十分条件でもない。
▶98回午前23
ある疾患の原因A・B・Uの状況を表に示す。A、Bは既知の原因、Uはその他の未知の原因である。A・B・Uの原因が重なって十分条件を満たすことになり罹患した「パターン1」の患者が全患者の30%、同様にA・Uの原因が重なって罹患した「パターン2」の患者が40%、B・Uの原因が重なって罹患した「パターン3」の患者が20%、Uの原因で罹患した「パターン4」の患者が10%であった。

Aの原因を完全に除去できたと仮定すると、この疾患の罹患を減らすことができる割合はどれか。
- 30%
- 40%
- 70%
- 100%
疾病頻度の指標
有病率
▶107回午前29
A市のある一時点におけるC型肝炎を有している人の割合を示す指標はどれか。
- 罹患率
- 被患率
- 有病率
- 寄与危険
- 相対頻度
▶102回午後19・98回午後18類問
有病率を上昇させる要因はどれか。
- 罹患率が低くなる。
- 平均有病期間が長くなる。
- 観察集団に健康な人が流入する。
- 重症化して短期間に死亡する人が増える。
▶92回午前61
基本健康診査の結果を表に示す。

受診者における疾病Aの有病率はどれか。
- 1.5%
- 2.5%
- 10.0%
- 16.7%
罹患率
- 罹患率は、一定期間に発生した疾病の患者数を、その期間の対象集団の観察人年で割った率をいう。
- 分母に用いる観察人年は、死亡率と同様に人数(人)と期間(年)を掛け合わせた数値を使用する(人年法)。
▶103回午前27
人口10万人の市において、ある一定期間の結核患者の発生頻度を表現する指標として適切なのはどれか。
- 罹患率
- 有病率
- 被患率
- 受療率
- 相対頻度
▶97回午前21
次の計算式で求められるのはどれか。
〈ある期間のある疾病の新規発症者数〉÷〈同一期間の対象集団の観察人年〉
- 罹患率
- 有病率
- 受療率
- 累積罹患率
▶107回午後35
計算するときに人年法を用いるのはどれか。2つ選べ。
- 死亡率
- 有病率
- 被患率
- 有訴率
- 罹患率比
▶99回午後35
人口122万人の市。1年間の結核新登録者数は183人、年末の活動性結核患者数は159人、年末の結核総登録患者数は549人であった。
年間の結核罹患率(人口10万人対)を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答: ① ②
▶93回午前62
人口1,000人のA村で10年間での死亡数は20人であった。
人年法によるA村の死亡率(10万人年対)はどれか。
- 20人
- 100人
- 200人
- 1,000人
累積罹患率
- 累積罹患率は、一定期間に発生した疾病の患者数を、観察開始時点の対象集団の人口で割った割合をいう。
- 罹患率とは異なり、分母に観察人年を用いない。
▶110回午前29
観察開始時点での観察集団の人数に占める、一定の観察期間内に新たに発生した患者数の割合はどれか。
- 罹患率
- 罹患率比
- 累積罹患率
- 寄与危険割合
- 人口(集団)寄与危険
▶100回午前38
分母に集団の人口全体を用いる指標はどれか。2つ選べ。
- 有病率
- 累積罹患率
- 致命率〈致死率〉
- 死因別死亡割合
- PMI〈proportional mortality indicator〉
▶109回午前37・96回午後16類問
累積罹患率の計算に必要なのはどれか。2つ選べ。
- 観察開始時点での患者数
- 各観察対象者の観察期間の総和
- 観察期間に新たに発生した患者数
- 観察開始時点での観察対象集団の人数
- 観察終了時点での観察対象集団の人数
▶95回午後27
女性1,000人を5年間追跡調査したところ、50人が子宮癌になり、そのうち20人が死亡した。
子宮癌の累積罹患割合(累積罹患率)で正しいのはどれか。
- 0.4%
- 1%
- 2%
- 5%
致命率
▶93回午前61
致命割合(致命率)で正しいのはどれか。
- 慢性疾患では計算できない。
- 罹患した後の累積死亡割合である。
- 算定には1年以上の観察期間が必要である。
- 地域人口の中で単位観察期間に死亡する危険の大きさを示す。
▶92回午前62
ある高齢者施設の入所者に感染症が集団発生した。その結果を表に示す。

致命率はどれか。
- 4%
- 10%
- 33%
- 40%
▶108回午前40
A市におけるある年の肺炎の罹患患者数は1,000人であり、そのうち死亡数は50人であった。これらの肺炎患者のうち感染症Bによるものは100人であり、そのうち死亡数は15人であった。
感染症Bによる致命率〈致死率〉を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答: ① ② %
▶90回午前60
100人の会食で40人が食中毒を発症し、そのうち4人が死亡した。
正しい組合せはどれか。
- 罹患率――40%
- 有病率――40%
- 死亡率――10%
- 致命率――10%
相対頻度
▶104回午前31
分母として人口データが得られない場合に、疾病の罹患や死亡などの全発生数を分母に用いて、ある疾病や年齢区分での発生が占める割合を示す指標はどれか。
- 相対危険
- 相対頻度
- 累積罹患率
- 人口寄与危険
- 人口寄与危険割合
▶109回午前28
相対頻度に含まれるのはどれか。
- 有病率
- 寄与危険
- 寄与危険割合
- 死因別死亡割合
- 年齢調整死亡率
▶107回午前40
人口10万人のA市におけるある年度の死亡数は1,000人であった。悪性新生物の罹患数は300人であり、その死亡数は200人であった。
死亡に占める悪性新生物の相対頻度を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答: ① ② %
曝露効果の指標
相対危険度(リスク比)
- 相対危険度は、疾病要因に対する曝露群・非曝露群など異なる2つのグループ間のリスク比を表し、曝露群の発生率(罹患率)÷非曝露群の発生率(罹患率)で求める。
- 相対危険度が高いことは、曝露と疾病との間の関連の強固性を示す。
▶105回午前27
危険因子に曝露した群の罹患リスクの、曝露していない群の罹患リスクに対する比はどれか。
- 罹患率
- 有病率
- 致命率
- 寄与危険
- 相対危険
▶100回午後14
40歳代男性を対象とした研究で、虚血性心疾患死亡率(人口10万人対)を観察した。喫煙群では20.0、非喫煙群では10.0であった。
次の計算で求めたのはどれか。
20.0÷10.0=2.0
- オッズ比
- 寄与危険
- 相対危険
- 寄与危険割合
▶98回午後19
脳卒中発症に対する喫煙の影響を調べるために、コホート研究を行った。10年間の追跡期間に、各対象者について、発症日または転出等によって追跡から脱落した日を特定することができた。
相対危険を計算する場合に最も適しているのはどれか。
- オッズ比
- 有病率比
- 罹患率比
- 累積罹患率比
▶92回午前64
多量飲酒者2,000人と非飲酒者3,000人とを5年間追跡し、多量飲酒者から200人、非飲酒者から150人のがん罹患を確認した。
多量飲酒のがん罹患に対するリスク比はどれか。
- 0.29
- 0.50
- 2.00
- 2.11
▶92回午前70
小学校で下痢、腹痛を発症した児童が集団発生し、原因曝露日と推定された日の学校給食の喫食調査を行った。
結果を表に示す。

解釈で正しいのはどれか。
- パンが原因食品である可能性が低い。
- 牛乳が原因食品である可能性が高い。
- サラダは予防要因である可能性が高い。
- 焼魚が原因食品である可能性が高い。
オッズ比
- 症例対照研究等で用いられるオッズとは、曝露を受けた割合と曝露を受けなかった割合の比を指し、症例群のオッズと対照群のオッズの比をオッズ比という。
- オッズ比が1よりも大きい場合は曝露因子が発症の危険因子、1よりも小さい場合は曝露因子が発症の予防因子とされる。
▶93回午前64
症例対照調査研究の結果を表に示す。

オッズ比はどれか。
- 0.3
- 1.8
- 2.0
- 3.5
▶103回午後35
心筋梗塞発症者100人と性・年齢をマッチングした心筋梗塞非発症者100人の5年前の健康診査の結果を調査し、糖尿病の有無を確認した。その結果、心筋梗塞発症者で20人、心筋梗塞非発症者で15人が糖尿病であった。
糖尿病であることの心筋梗塞発症に対するオッズ比を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答: ① .②
▶108回午後23
要因A「あり」の要因A「なし」に対する疾病B「あり」のオッズ比と95%信頼区間を求めた。
疾病Bの危険因子として統計学的に有意なのはどれか。なお、有意水準は5%と設定する。
- オッズ比2.0 95%信頼区間(1.5〜2.7)
- オッズ比2.0 95%信頼区間(0.5〜8.0)
- オッズ比1.0 95%信頼区間(0.5〜2.0)
- オッズ比0.5 95%信頼区間(0.1〜2.5)
- オッズ比0.5 95%信頼区間(0.4〜0.6)
寄与危険度(リスク差)
▶101回午後19
差をとって寄与危険を計算できる指標はどれか。
- 罹患率
- 有病率
- オッズ比
- 致命率〈致死率〉
▶91回午前62
寄与危険度で正しいのはどれか。
- 曝露を除くと曝露群の罹患率がどの程度減少するかを示す。
- 非曝露群の罹患率と比べ曝露群の罹患率が何倍になるかを示す。
- オッズ比を近似値とすることができる。
- コホート調査では間接的に算出する。
▶96回午後17
ある集団の喫煙者1,000人のうち肺癌になったのは50人、非喫煙者2,000人のうち肺癌になったのは40人であった。
人口千対の罹患率から求めた喫煙によって肺癌になる寄与危険はどれか。
- 1.25
- 2.50
- 10
- 30
▶93回午前63
大量喫煙者と非喫煙者の5年間の心疾患による死亡データを表に示す。

10万人年対の寄与危険はどれか。
- 1.2
- 1.25
- 40
- 200
▶98回午前25・92回午前63類問
ある地域における喫煙者と非喫煙者とに分けた疾患の罹患率(人口10万人年対)について調査した結果を表に示す。

喫煙による寄与危険が最も大きな疾患はどれか。
- 肺癌
- 咽頭癌
- 慢性閉塞性肺疾患
- 虚血性心疾患
寄与危険割合
▶99回午前31
アスベスト曝露の肺がん罹患に対する寄与危険割合の算出のために十分な情報を持つ指標はどれか。
- アスベスト曝露群の肺がんの罹患率
- アスベスト非曝露群の肺がんの罹患率
- アスベスト曝露の肺がん罹患に対する相対危険
- アスベスト曝露の肺がん罹患に対する寄与危険
- 全人口に対するアスベスト曝露を受けた者の割合
▶94回午前61
喫煙による肺がん発症のリスク比が8の場合の寄与危険割合はどれか。
- 12.5%
- 25.0%
- 75.0%
- 87.5%
▶109回午前40・104回午前40類問
40歳以上の男性を対象とした疫学研究で、虚血性心疾患死亡率(10万人年対)を観察した。虚血性心疾患死亡率は、喫煙群では50.0、非喫煙群では25.0であった。
このときの寄与危険割合を百分率で求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答: ① ② %
人口〈集団〉寄与危険割合
▶105回午後13
人口〈集団〉寄与危険割合を直接計算するのに必要な情報はどれか。
- 全死亡数
- 累積罹患数
- 平均有病期間
- 対象集団の疾病頻度
▶97回午前30
人口10万人当たりの年間の肺がん死亡率が、喫煙者では100、非喫煙者では20、集団全体では50であった。
人口寄与危険割合はどれか。
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 80%
疫学調査法
悉皆調査・標本調査
- 疫学調査に当たっては、対象となる集団(母集団)すべてを対象とする悉皆(全数)調査と、母集団から一部の標本を抽出(サンプリング)する標本調査がある。
- 悉皆調査としては人口静態を把握するために5年に1度実施される国勢調査が挙げられる。
▶94回午前69
悉皆調査はどれか。
- 国勢調査
- 患者調査
- 国民生活基礎調査
- 国民健康・栄養調査
無作為抽出
▶105回午前44
人口10万人のA市では、脳血管疾患の死亡割合が全国と比較して大きいことが明らかになった。そこで、脳血管疾患の予防対策の一環として血圧に注目し、一部の市民を対象とした塩分摂取量の把握のための聞き取りによる食事調査を行うこととした。
調査者の主観が影響しにくい標本を選ぶ方法はどれか。
- 制限
- 応募法
- 無作為抽出
- マッチング
- 無作為化(割付)
▶99回午前26
市の保健師が市内在住の成人の生活実態把握のために横断調査を行う。
対象者の選定で適切なのはどれか。
- 市内の主要駅の通行人
- 無作為に選定した1地区の成人全員
- 市の住民基本台帳から無作為に選定した成人
- インターネットで募集した成人
系統誤差
●選択の偏り〈バイアス〉
調査対象者の選択やその脱落により生じるバイアス。
●情報の偏り〈バイアス〉
対象から得た情報が検者間の測定方法や基準の相違、面接者の偏った質問等により発生するバイアス。
▶96回午後18
市全体のクラミジア感染率を推計するため、市内のある大学の学生から希望者を募り、抗体検査を実施した。
この方法で最も大きなバイアスはどれか。
- 選択バイアス
- 交絡バイアス
- リコールバイアス
- インフォメーションバイアス
▶94回午前63
社員数1万人のA社で職員の飲酒と肝機能に関する調査をするため、職員の約1割を標本として抽出することにした。
選択の偏りが最も小さいのはどれか。
- 誕生月が10月の者
- 日本酒換算で1日2合以上の飲酒者
- 会社の健康教室参加者
- 年齢の若い社員順
▶104回午後19・97回午後22類問
耐糖能異常の頻度の地域比較調査を行ったところ、A地区では空腹時血糖で評価し、B地区では随時血糖で評価していたことが明らかになった。
疫学調査法におけるこのような問題点はどれか。
- 交絡
- 偶然誤差
- 選択の偏り〈バイアス〉
- 情報の偏り〈バイアス〉
▶105回午後20
系統誤差の原因はどれか。
- マッチング
- 高い追跡率
- 低い抽出率
- 無作為化〈割付〉
- 検者間の測定差
▶95回午前31
情報バイアスが生じる可能性が高いのはどれか。
- 調査対象者を雑誌で公募した。
- 症例対照調査で肺癌患者に喫煙歴を詳細に尋ねた。
- 調査対象者をくじ引きで2グループに分けて比較した。
- 症例対照調査で対照群を大学病院の外来患者から選んだ。
信頼性・妥当性
- 疫学調査においては、同一対象に対して検査を繰り返しても同じ結果が得られる精度(信頼性)と、適切な調査デザインにより対象の特性を正確に測定できる精度(妥当性)の高さが重要となる。
- 信頼性は偶然誤差が小さいほど、妥当性は系統誤差が小さいほど高くなる。
▶102回午後29
保健活動で用いる尺度の妥当性の説明として正しいのはどれか。
- 測定する側が実施しやすい。
- 測定される側が受け入れやすい。
- 測定したい特性が正しく測定できている。
- 調査対象の測定結果が全体を代表している。
- 同一対象に対して繰り返し測定すると同じ値が得られる。
▶97回午後23
スクリーニングに用いられる検査方法の信頼性または妥当性で正しいのはどれか。
- 系統誤差が小さければ妥当性が高い。
- データ分布のばらつきの大きい検査方法は信頼性が高い。
- 同じ標本について反復した測定値がほぼ一定であるときは、妥当性が高い。
- 同じ目的で使用される別の検査方法との相関が高いときは、信頼性が高い。
交絡
- 交絡とは、原因(曝露)と結果の間にあると推定された因果関係とは別に、歪みを生じさせる交絡因子により生じるバイアスをいう。
- 例えば「飲酒者では肺癌の発症が多い」という結果の裏には、多くの飲酒者が喫煙しているという交絡因子が存在しており、実際は「喫煙者では肺癌の発症が多い」が正確となる。
▶92回午前66
多量飲酒と肺癌に関する症例対照調査を実施した。多量飲酒の肺癌発生に対するオッズ比は2.0であったが、多量飲酒と喫煙との関連が強いので、喫煙有無別に集計した。喫煙有群、喫煙無群ともにオッズ比は1.0となった。
多量飲酒と肺癌との関係に影響を与えている喫煙の作用はどれか。
- 危険因子
- 交絡因子
- 情報バイアス
- 選択バイアス
交絡因子の制御
【計画段階】
- 無作為化(割付):曝露群と非曝露群を無作為(ランダム)に振り分ける方法。
- 制限(限定):交絡因子となりうる要因を持つ人を対象者に限定する方法。
- マッチング:曝露群と非曝露群の間で性・年齢など交絡因子となりうる要因を一致させる方法。
【分析段階】
- 層化抽出:母集団を性・年齢などのグループに分けて(層化)、グループごとに標本を抽出する方法。
- 多変量解析:複数の変数・変量データを基にその関連性の発見や予測を行う方法。
▶94回午前64・110回午後16類問
分析時にできる交絡要因の制御方法はどれか。
- 層化
- 無作為抽出
- 無作為割付
- マッチング
▶90回午前62
交絡因子の制御方法と特徴との組合せで正しいのはどれか。
- 無作為化――観察研究で用いる。
- マッチング――交絡因子の分布が等しくなるよう対象者を調整する。
- 制限――交絡因子が完全に制御できる。
- 層化――結果の解釈が比較的困難である。
▶105回午前29
症例対照研究における交絡因子の制御方法はどれか。
- 無作為化
- マッチング
- 単変量解析
- ブラインド法
- 対象者数の増加
▶93回午前65
マッチングで正しいのはどれか。
- 後向き調査では用いない。
- 層化解析の一種である。
- 交絡因子の制御法である。
- 年齢の影響は調整できない。
▶96回午前25
市におけるある疾病の罹患率の調査をするために、20歳未満の群と20歳以上の群とに分け、それをさらに男女別に分け、各群の10%を抽出した。
この標本の抽出方法はどれか。
- 単純無作為抽出
- 層化抽出
- 系統抽出
- 多段抽出
年齢の標準化
- 疫学研究において年齢は交絡因子になり得る。例えば都道府県間で心疾患の死亡率を比較する際、心疾患は高齢になるほど発症リスクが高くなるため、高齢化率の高い県では必然的に心疾患死亡率が高くなる。
- 年齢構成の歪みを補正して異なる集団間で比較を行えるようにするために、年齢の標準化(年齢調整)が行われている。
▶92回午前67
基本健康診査の結果を中学校区別(人口数千人単位)に集計した。総コレステロール値が高い者の校区別割合に差があった。
次に行うことで正しいのはどれか。
- 年齢調整をして比較する。
- 症例対照調査を企画する。
- 小学校区別に集計する。
- 回帰分析を行う。
年齢調整死亡率(直接法)

▶104回午後32
直接法による年齢調整死亡率を算出する際に必要な情報はどれか。2つ選べ。
- 基準集団の死亡率
- 観察集団の死亡実数
- 観察集団の年齢別人口
- 基準集団の年齢別人口
- 観察集団の年齢別死亡率
▶102回午前38
直接法による年齢調整死亡率の特徴はどれか。2つ選べ。
- 小規模な集団の観察に適している。
- 高齢者の多い集団では高くなりやすい。
- 値は標準化死亡比〈SMR〉として示される。
- 異なる観察集団の死亡率を直接比較できる。
- 計算には観察集団の年齢階級別死亡率が必要である。
▶98回午前24
基準集団とA市との年齢階級別人口と死亡数とを表に示す。

直接法によるA市の人口10万人当たりの年齢調整死亡率はどれか。
- 160
- 200
- 320
- 370
標準化死亡比(SMR)

▶103回午後20
標準化死亡比〈SMR〉を求めるために必要な指標はどれか。
- 基準集団の死亡率
- 基準集団の年齢別人口
- 観察集団の年齢別人口
- 観察集団の年齢別死亡率
▶106回午後28改題
標準化死亡比〈SMR〉で正しいのはどれか。
- 人口の大きな集団ほど高くなる。
- 高齢化率の高い集団ほど高くなる。
- 平成27年モデル人口を基準人口として用いる。
- 計算には観察集団の年齢階級別人口が必要である。
- 直接法による年齢調整死亡率の計算過程で得られる。
スクリーニング
目的・要件
- 確定診断、治療方法が確立した疾病であること。
- 疾病の経過(自然史)が明らかで、発病までの無症状期間が長い疾病を対象とすること。
- 侵襲性が低く対象者に受け入れやすい検査であること。
- 測定者によって検査結果の変動が少ないこと。
▶104回午前37
疾病の罹患群や非罹患群のスクリーニングの要件で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 検査方法が対象者よりも測定者にとって受け入れやすい。
- 確定診断の手法が確立していない疾病も対象となる。
- 治療法が確立していない疾病も対象となる。
- 疾病予防対策の効率の向上が期待される。
- 測定者による結果の変動が少ない。
▶106回午前27
疾病のスクリーニングの要件で正しいのはどれか。
- 疾病の自然史が不明でも対象になる。
- 無症状の期間が無い疾病が対象となる。
- 治療方法が確立していなくても対象となる。
- 検査方法が、対象者より検者に受け入れやすい。
- スクリーニング陽性者の確定診断の手技が確立している。
▶95回午前32
スクリーニング検査で正しいのはどれか。
- 陽性判定の基準値は固定されている。
- 侵襲性の低いものでなければならない。
- 異常と判定されれば直ちに治療を開始する。
- 臨床的徴候の出現から発病までが短期間の疾患に適している。
▶97回午前39
スクリーニング検査で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 疾病の一次予防として行われる。
- 多疾患を対象とするものをマススクリーニングという。
- 偽陰性が多くても、偽陽性が少ない検査が適している。
- 早期発見した場合、治療法が存在する疾患を対象とする。
- スクリーニング陽性者に対して診断確定する方法がある疾患を対象とする。
敏感度
- 疾病を有する人を正しく陽性と判定する確率を敏感度といい、敏感度が低いと疾病を有する人を誤って陰性と判定する確率(偽陰性率)が高くなる。
- 計算には、疾病があるかつ陽性の者を分子、疾病がある者を分母に用いる。
▶93回午前66
スクリーニングで敏感度が低い場合の問題点はどれか。
- 判定に時間がかかる。
- 患者の見落としが多くなる。
- 精密検査の対象者が増える。
- 測定者によって結果に変動が起こる。
▶96回午前29
ある疾病に関するスクリーニング検査の結果を表に示す。

この検査の敏感度はどれか。
- 0.72
- 0.76
- 0.80
- 0.89
- 0.91
▶94回午前65
1,200人を対象とした疾病Aのスクリーニングの結果と精密検査の結果とを表に示す。

敏感度はどれか。
- 10.0%
- 80.0%
- 84.7%
- 99.5%
特異度
- 疾病を有していない人を正しく陰性と判定する確率を特異度といい、特異度が低いと疾病を有していない人を誤って陽性と判定する確率(偽陽性率)が高くなる。
- 計算には、疾病がないかつ陰性の者を分子、疾病がない者を分母に用いる。
▶92回午前68
集団健診で行うスクリーニング検査の特異度が低い場合の問題点はどれか。
- 判定に時間がかかる。
- 測定者によって結果に変動が起こる。
- 患者の見落としが多くなる。
- 精密検査の対象者が増える。
▶98回午後20
ある集団に対してスクリーニング検査と確定診断とを同時に実施した結果を表に示す。

特異度はどれか。
- 50.0%
- 62.5%
- 88.8%
- 95.2%
▶102回午前40
疾病Aの新しいスクリーニング検査の性能を評価するために、疾病Aの患者100人と疾病Aでない者100人に対して検査を実施した。疾病Aの患者のうち60人と、疾病Aでない者のうち10人とが検査の結果陽性であった。
特異度を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答: ① ② %
トレードオフ・ROC曲線
- 敏感度が上昇すると特異度は低下し、特異度が上昇すると敏感度は低下する(トレードオフの関係)。
- 縦軸を敏感度、横軸を1-特異度(偽陽性率)としたグラフをROC曲線といい、スクリーニング検査の妥当性を評価することができる。この曲線が左上隅に近づくほどより精度の高い検査であるといえる。
▶107回午後19
同じ集団における同一のスクリーニング検査で、基準値を変えて敏感度を上げた場合に上昇するのはどれか。
- 特異度
- 偽陽性率
- 偽陰性率
- 陰性者数
▶100回午前34
3種類のスクリーニング検査A、B、Cの受信者動作特性(ROC)曲線を示す。

検査の正確さについて正しいのはどれか。
- 3検査のうちAが最も正確な検査である。
- 3検査のうちBが最も正確な検査である。
- 3検査のうちCが最も正確な検査である。
- 正確さを評価するには足りない情報がある。
- この曲線は検査の正確さの評価には適していない。
▶97回午後31
ある事業所から発熱下痢の集団発生があった旨の連絡があり、疫学調査を行った。
分析において有用性が低いのはどれか。
- 流行曲線
- ROC曲線
- 量-反応関係
- 職場別発生地図
- マスターテーブル
陽性反応的中度・陰性反応的中度
検査で陽性と判定された人のうち実際に疾病を有している人の割合を陽性反応的中度という。
●陰性反応的中度
検査で陰性と判定された人のうち実際に疾病を有していない人の割合を陰性反応的中度という。
▶108回午後24
検査で陽性と判定された人のうち実際に疾病を有している人の割合を示す指標はどれか。
- 特異度
- 敏感度
- 有効度
- 偽陽性率
- 陽性反応的中度
▶106回午後16改題
陽性反応的中度が上昇する理由で適切なのはどれか。
- 疾患の治療法が進歩した。
- 疾患の有病率が上昇した。
- 検査を受けた人数が増加した。
- 検査の感度は変わらず特異度が低下した。
- 基準値の変更で陽性者が増加した。
▶101回午後20
スクリーニングについて正しいのはどれか。
- 確定診断を目的とする検査である。
- 敏感度100%の検査で陽性結果であれば疾患がある。
- 陽性反応的中度は有病率の影響を受けにくい指標である。
- 同一検査で敏感度と特異度の両方を改善することはできない。
統計グラフ
折れ線グラフ
▼例:108回保健師国家試験午前29問

▶106回午後18
結核の有病者数の年次推移を表す図表で適切なのはどれか。
- 散布図
- 円グラフ
- 帯グラフ
- 折れ線グラフ
円グラフ
▶104回午前25
A市の20歳から24歳までの年齢層における死因の内訳を表に示す。

表に示した内容を図で表現する場合に適しているのはどれか。
- 散布図
- 円グラフ
- 折れ線グラフ
- ヒストグラム
散布図
▼例:ある高校の男子生徒の身長と体重の分布

散布図の特徴の一つとして、図の右下にあるような他の値から極端に離れた外れ値を見つけやすい。
▶102回午後21・94回午前71類問
特定健康診査を受診した100人の腹囲とHbA1c値について、個人ごとの2つのデータを一度に示し両者の関連を表現するのに優れているのはどれか。
- 折れ線グラフ
- ヒストグラム
- 円グラフ
- 散布図
▶109回午後34
散布図から分かるのはどれか。2つ選べ。
- 相関
- 割合
- 中央値
- 年次推移
- はずれ値
ヒストグラム
▼例:所得金額階級別世帯数の相対度数分布(令和4年国民生活基礎調査)

▶103回午前29
ある集団の特定健康診査で得られたヘモグロビンA1c値の頻度の分布を確認するのに最も優れているのはどれか。
- 散布図
- 円グラフ
- 帯グラフ
- ヒストグラム
- 折れ線グラフ
▶100回午前23
ヒストグラムについて正しいのはどれか。
- 連続量や度数の経時的変化を折れ線で示す。
- 名義尺度の度数の分布を棒の高さとして示す。
- ある範囲にある連続量の度数を面積の大きさとして示す。
- 標本のもつ2つの連続量をプロットしてその関連を示す。
代表値と散布度
データの中心(代表値)
- 平均値:一般にも最も用いられる代表値で、例では(1+2+4+7+9+9+10)÷7=6となる。
- 中央値:データを小さな順で並べた際の真ん中の数値で、例では7となる。
- 最頻値:データの内で最も多く出現している値で、例では9となる。
▶108回午前36
代表値はどれか。2つ選べ。
- 分散
- 平均
- 最頻値
- 標準誤差
- 標準偏差
▶95回午前34
25人の体重(kg)のデータを表に示す。

中央値はどれか。
- 57
- 58
- 59
- 60
代表値の選択
▶91回午前71
図は健康教室参加者20人の収縮期血圧の分布である。主な代表値は以下のとおりである。

平均値147.3mmHg
幾何平均値145.5mmHg
中央値139mmHg
最頻値130~139mmHg
この集団の代表値で最も適切なのはどれか。
- 平均値
- 幾何平均値
- 中央値
- 最頻値
▶96回午後23
集団に対して、ある物質の血中濃度を測定した結果を示す。

この集団を代表するのに適した数値はどれか。
- 300
- 250
- 200
- 150
- 100
分散・標準偏差
▶105回午前30
散布度に含まれるのはどれか。
- 中央値
- 最頻値
- 相関係数
- 標準偏差
- 平均(算術平均)
▶104回午後33
測定値の偶然誤差の大きさを表す指標として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 分散
- 中央値
- 算術平均
- 標準偏差
- 最頻値〈モード〉
▶110回午前37
標準偏差の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 分散をもとに計算する。
- 変動係数の計算に用いる。
- 測定値の中で出現頻度が最大の値である。
- 測定値の合計をデータ数で除した値である。
- 標準偏差が大きいほどばらつきが小さいことを意味する。
▶101回午後21
分布の指標について正しいのはどれか。
- ヒストグラムで最も頻度が高い値は中央値である。
- 広く散らばった分布は標準偏差が小さい。
- 対象数が増えると標準偏差は大きくなる。
- 平均値は外れ値の影響を受けやすい。
▶97回午後25
デジタル血圧計で測定した被検者10名の収縮期血圧を表に示す。この表から(A)の数値を算出した。

(A)が表しているのはどれか。
- 分散
- 幾何平均
- 平均偏差
- 標準偏差
四分位偏差
- 四分位偏差とは、データを小さい順から並べたときに、25%になるものを第1四分位点、50%になるものを第2四分位点(=中央値)、75%になるものを第3四分位点とし、(第3四分位点-第1四分位点)÷2の値を指す。
- 第1四分位点は第2四分位点より小さいデータの中央値、第3四分位点は第2四分位点より大きいデータの中央値で求められる。
▶98回午前28
単位が同じである統計値の組合せで正しいのはどれか。
- 中央値――四分位偏差
- 平均値――分散
- 最頻値――変動係数
- 分散――範囲
▶94回午前70
ある町の基本健康診査受診者の最高血圧の度数分布を表に示す。低い方から第3四分位点はどの範囲に属するか。

- 130~139
- 140~149
- 150~159
- 160~169
▶110回午前40
12人の体重(kg)のデータを値の大きさ順に表に示す。
第3四分位数の値を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①②.③kg
範囲
▶106回午前19
健康寿命の都道府県格差を評価するための指標で適切なのはどれか。
- 範囲
- 最頻値
- 中央値
- 幾何平均
確率分布
正規分布

- 平均値、中央値、最頻値を中央の峰(ピーク)とする一峰性である。
- 平均値±1標準偏差の範囲に68.27%、平均値±2標準偏差の範囲に95.45%のデータが含まれる。
▶99回午前32
正規分布について誤っているのはどれか。
- 一峰性である。
- 左右対称である。
- 平均値と中央値が一致する。
- 平均値が決まれば一意に定まる。
- 平均値±2×標準偏差の範囲に全体の約95%が含まれる。
▶90回午前69
正規分布で正しいのはどれか。
- 中央値と最頻値は異なる。
- 平均値±標準偏差の範囲に対象の95%が含まれる。
- ヒトの身長は正規分布に従う。
- 二峰性である。
▶92回午前73
ある集団1,000人の体重を測定した結果、平均値55kg、標準偏差5kgで正規分布を示した。
正しいのはどれか。
- 中央値は平均値よりも大きい。
- 55kgから65kgの範囲におよそ339人いる。
- 60kg以上の人はおよそ49人である。
- 45kg以下の人はおよそ23人である。
二項分布
▶108回午前22
大きな集団から無作為に1,000人選び出したとき、その中の高血圧者数が従う分布はどれか。
- t分布
- 正規分布
- 二項分布
- χ2〈カイ2乗〉分布
▶100回午後16
日本人の血液型のうちAB型の割合が10%であるとする。無作為に選んだ100人の日本人集団の中にAB型の人が20人以上いる確率を知りたい。
この集団の中に含まれるAB型の人数が従う分布として最も適切なのはどれか。
- t分布
- F分布
- 正規分布
- 二項分布
関連の指標
相関
- 2つの変数の関係(相関)は散布図を用いることで視覚的に明らかとなり、それが直線関係にどれほど近いかを表した指標が相関係数である。
- 相関係数は1から-1の範囲で示され、1(右上がりの直線)や-1(右下がりの直線)に近いほど相関関係が強く、0の時は無相関となる。
▶108回午後26
2つの連続変数間の直線的な関係の強さを示すのはどれか。
- 分散
- 正規分布
- 相関係数
- 標準偏差
- クロス集計
▶103回午前28・109回午前30類問
生態学的研究によって、世界各国の1人当たりの食塩摂取量と高血圧症有病率との関連の程度を評価するために計算するのはどれか。
- 寄与危険
- 変動係数
- 相対危険
- 相対頻度
- 相関係数
▶100回午前35
相関について正しいのはどれか。
- 因果関係の必須項目である。
- 相関係数が大きいほど相関関係は強い。
- 相関が全くないときの相関係数は0である。
- 相関係数は0から100までの数値で示される。
- 2つの連続量の一方を使用して他方を推計することをいう。
回帰
▶104回午前38
ある集団の特定健康診査で得られたBMIと血圧との関連を表すのに適した指標はどれか。2つ選べ。
- 散布度
- 四分位数
- 相関係数
- 変動係数
- 回帰係数
クロス集計
▶97回午前25
健康診査受診者を対象に、肥満の予防方法の理解度について5項目のテストを実施した。テストの合計得点を求めた後に理解できている群とできていない群に分類した。
健康教室参加の有無との関係を調べるのに使用するのはどれか。
- 相関図
- 回帰直線
- クロス表
- 平均値の棒グラフ
統計分析
帰無仮説・対立仮説
- ある集団に関して仮定された命題を統計学的に検証することを仮説検定という。
- 仮説検定では、誤っているとして否定したい帰無仮説(相関なし)に加え、帰無仮説が否定された場合に正しいと判断される対立仮説(相関あり)を設定する。
- 帰無仮説を否定するには有意水準を用いて判断し、有意差があれば(統計学的に有意であれば)帰無仮説を棄却して対立仮説を採択し、有意差がなければ(統計学的に有意でなければ)帰無仮説が正しいかどうかわからない。
▶106回午前28
A市の2地区間で、喫煙率が異なると予想して両地区で喫煙状況に関する標本調査を行った。統計学的検定を行い「仮説B:2地区の母喫煙率は等しい」が棄却されたので、2地区の喫煙率には有意差があると判断した。
仮説Bはどれか。
- 閾値仮説
- 帰無仮説
- 研究仮説
- 対立仮説
- 直線仮説
▶96回午後19
検定の結果、有意差(有意確率0.05)が認められなかった。帰無仮説の解釈で正しいのはどれか。
- 帰無仮説は正しい。
- 帰無仮説は誤りである。
- 帰無仮説は5%の確率で起こり得る。
- 帰無仮説は正しいかどうか分からない。
▶99回午前25
共に正規分布すると仮定できる2つの連続変数X、Yについて散布図を描いた。標本数は300である。散布図は全体的に右上がりであり、特に外れ値はなかった。Pearson〈ピアソン〉の相関係数を計算したところ、r=0.60であった。「母相関係数は0である」とする帰無仮説を立て、統計学的検定を行ったところ、有意水準5%にて棄却された。
XとYとの相関について適切なのはどれか。
- 全く相関はない。
- 有意な相関がある。
- 相関の有意性は棄却される。
- 相関の有無については判断できない。
χ2検定
▶108回午前37・106回午後27類問・102回午前39類問
割合の差の検定について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 回帰分析で用いる。
- 相関係数が計算できる。
- クロス集計表は有用である。
- 検定の際に散布図を用いる。
- χ2〈カイ2乗〉検定で有意差を検定する。
▶110回午前18
喫煙習慣の有無と性別の関連を調べる検定方法で適切なのはどれか。
- t検定
- 相関係数の検定
- 一元配置分散分析
- χ2〈カイ2乗〉検定
▶107回午前7
A市の新生児訪問のデータを表に示す。

このデータの統計分析に適切なのはどれか。
- F検定
- t検定
- U検定
- χ2〈カイ2乗〉検定
▶103回午前36
A市の2地区でデータを収集した。各項目について地区間に差があるかどうかを統計学的に検定する。
χ2〈カイ2乗〉検定が適している項目はどれか。2つ選べ。
- 年齢
- 通院の有無
- 高血圧症の有病率
- 1日当たり飲酒量
- 1日当たり喫煙本数
t検定
▶105回午後15
2群間の平均の差の検定に用いるのはどれか。
- t検定
- 回帰分析
- χ2〈カイ2乗〉検定
- Fisher〈フィッシャー〉の直接確率法
▶97回午前31
特定健康診査時と1年後の特定健康診査時の体重変化量について、その間に行われた特定保健指導実施群と非実施群との間で平均値の差を検定したい。
用いる検定はどれか。
- F検定
- t検定
- χ2検定
- フィッシャー検定
- ウィルコクソン検定
▶99回午後23
A市の2地区でデータを取った。各項目について2地区間に差があるかどうかを統計学的に検定する。
t検定が適している項目はどれか。
- 性別
- 体重
- 年齢区分
- 5段階の自覚的健康度
▶98回午後22
男性の特定健康診査受診者について定期的運動の有無と腹囲との関連を分析し、t検定を行った結果を表に示す。

この結果で正しいのはどれか。
- 運動あり群の方が腹囲が2.4%小さい。
- 運動あり群の方が腹囲が小さくなる確率は2.4%である。
- 両群で腹囲に差がないのに、偶然これだけの差が出る確率が2.4%である。
- 運動あり群のうち運動なし群の平均よりも腹囲が大きいのは2.4%である。
U検定
▶109回午前29
2つの非正規分布の母集団の数量データの比較に用いるのはどれか。
- t検定
- 分散分析
- 多変量解析
- χ2〈カイ二乗〉検定
- Mann-Whitney〈マン・ホイットニー〉のU検定
平成25年2月15日実施の第99回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。
また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。
分野別解説付き問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ
- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ
を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。
なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
第99回保健師国家試験目次
第99回保健師国家試験・午前(55問)
▶午前1
日本の公衆衛生の歴史で最も新しいのはどれか。
- 厚生省の設置
- 保健所法の制定
- 国民体力法の制定
- 保健婦規則の制定
▶午前2
都道府県保健所が実施主体になる母子保健活動はどれか。
- 新生児訪問
- 母子健康手帳配布時の生活指導
- 小児慢性特定疾患児の親への生活指導
- 1歳6か月児健康診査の結果、支援を要する児の親への家庭訪問
▶午前3
へルスプロモーションの活動として適切なのはどれか。
- 地域活動の強化
- 二次予防活動の促進
- 感染症のコントロール
- 保健分野中心の政策づくり
▶午前4
4か月児健康診査における母親の相談内容で健康診査後に優先して家庭訪問をするのはどれか。
- 「子どもの足に湿疹がありかゆがる」
- 「子どもの泣き声にイライラしてしまう」
- 「2歳になる上の子が甘えるようになった」
- 「初めての子育てで、離乳食の進め方を知りたい」
▶午前5
18歳の母親。夫と新生児(出生時体重3,000g)との3人暮らし。3か月前に他の町から転入した。生後26日に新生児訪問を行った。母親は育児が大変で家事には手が回らないと訴えた。
確認する事項として優先度が高いのはどれか。
- 児の追視
- 近隣との関係
- 母親の最終学歴
- 夫の育児・家事への協力状況
▶午前6
50歳の男性。自営業。特定健康診査の結果が身長175cm、体重85kg、腹囲93cm、血圧140/90mmHgであり、特定保健指導の対象となった。
対象になった理由を説明した後の進め方の順で最も適切なのはどれか。
A 目標体重を本人と決める。
B 毎日の体重を測定・記録することを勧める。
C 体重が多い理由を本人と考える。
- A→B→C
- A→C→B
- C→A→B
- C→B→A
▶午前7
32歳の男性。会社員。潰瘍性大腸炎。仕事をしながら療養することを希望している。
保健指導として適切なのはどれか。
- 食事は1日5回に分ける。
- 食事はできる限り低脂肪食とする。
- 休日はできる限り安静に過ごす。
- 薬の飲み忘れがあった場合は次に2回分を服用する。
▶午前8
30歳の女性。夫から日常的に暴力を振るわれ、打撲などの傷害を受けている。
相談のために市保健センターに来所した。
本人の同意を得て保健師が通報する施設はどれか。
- 警察署
- 家庭裁判所
- 母子福祉センター
- 精神保健福祉センター
▶午前9
特別支援学校について正しいのはどれか。
- 大学部の設置がある。
- 研修を受けた教員は喀痰の吸引を実施できる。
- 病院の院内学校は高等学校までが対象である。
- 視覚障害者の教育は小学校入学以降に開始される。
▶午前10
事業と歯科保健指導の組合せで正しいのはどれか。
- 両親学級――歯科治療は妊娠初期に行う。
- 乳児健康診査――口腔体操を行う。
- 3歳児健康診査――大人による仕上げ磨きを行う。
- 介護予防教室――歯ブラシは硬めのものを用いる。
▶午前11
A町B地区は町の中心部から車で30分離れており、町の出張所がある。町外から転入した夫婦と子ども1人で構成される世帯が増加している。乳幼児健康診査では、近所に育児に関して相談する人がいないという声が多く聞かれ、保健師は地域で取り組む課題と考えた。
最初の取り組みとして適切なのはどれか。
- 自治会組織に現状を説明する。
- 対象者の一覧表を民生委員と共有する。
- 児童家庭支援センターに企画を依頼する。
- 出張所に母親が集まるための場所を確保する。
▶午前12
地域・職域連携推進事業ガイドラインに規定されている地域・職域連携推進協議会について正しいのはどれか。
- 三次予防事業を実施する。
- 都道府県協議会を設置する。
- 労働安全衛生法を根拠とする。
- 協議会メンバーは保健医療専門職とする。
▶午前13
市町村保健師が把握した事例と連絡先の組合せで適切なのはどれか。
- 虐待を受けていると思われる幼児――児童相談所
- 自傷他害のおそれがある精神障害者――地域包括支援センター
- 虐待を受けていると思われる高齢者――保健所
- 下痢・発熱が継続している海外からの帰国者――感染症情報センター
▶午前14
A町では閉じこもり傾向の高齢者が増加傾向にある。町内のB地区では、5年前から閉じこもり傾向の高齢者を対象にした交流会を月1回自治会主催で実施している。町保健師はB地区のような自治会主催の交流会を町内全地区で実施する必要があると考えている。
保健師の活動として最も適切なのはどれか。
- 他地区の自治会に交流会実施の依頼文書を送付する。
- 自治会長連絡会でB地区の成果を報告することを提案する。
- 一般住民向けにB地区の活動を紹介する写真展を実施する。
- B地区の交流会に他地区の閉じこもり傾向の高齢者の参加を促す。
▶午前15
在宅で人工呼吸器を装着している筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉のAさんの要望を受けて、保健所が隣県への外出支援を行うことになった。Aさんにとって、人工呼吸器の装着後初めての外出である。
保健師が最初に行うべきことはどれか。
- 隣県の人工呼吸器の管理会社に協力を依頼する。
- 外出先のバリアフリー設備環境について調査する。
- 想定できる外出時の問題点をAさんとリストアップする。
- 緊急時対応について外出先近くの医療機関に協力を依頼する。
▶午前16
核燃料物質の取り扱い業務に従事する労働者への安全衛生管理で適切なのはどれか。
- 放射線取扱主任者を選定する。
- 1日の被ばく線量限度で管理する。
- 年に1回の定期健康診断を実施する。
- 健康診断結果の保存義務は5年である。
▶午前17
訪問看護ステーションについて正しいのはどれか。
- 管理者は医師である。
- 薬剤師は人員に関する基準に含まれる。
- 保健師は看護職員の常勤換算人数に含まれる。
- 主治医の指示書がなくても訪問看護を提供できる。
▶午前18
災害発生後の初動体制における保健師活動で正しいのはどれか。
- 避難所のトイレの衛生管理
- 災害時の要援護者の安否確認
- 避難所の炊き出しメニューの工夫
- 避難者のストレスチェックの実施
▶午前19
健康増進法により健康増進計画の策定が義務づけられているのはどれか。
- 国
- 都道府県
- 保健所
- 市町村
▶午前20改題
厚生労働省の「令和4年人口動態統計」と警察庁の「令和4年中における自殺の状況」における自殺の現状で正しいのはどれか。
- 年間の自殺者は4万人を超えている。
- 自殺による死亡は全死因の第4位である。
- 自殺の動機で最も多いのは家庭問題である。
- 性・年齢階級別の死亡率は男性の50歳代が最も高い。
▶午前21
都道府県保健所の役割について正しいのはどれか。
- 3歳児健康診査
- 肝炎ウイルス検診
- HIV・エイズの相談
- 寝たきり高齢者の訪問指導
▶午前22
生活保護の基本原理として正しいのはどれか。
- 無差別平等
- 安全の保護
- 目的の明確化
- 連帯責任による保障
▶午前23
インフルエンザの原因と発症との因果関係で正しいのはどれか。
- ウイルスは発症の必要条件である。
- ウイルスは発症の十分条件である。
- ウイルスは発症の必要十分条件である。
- ウイルスは発症の必要条件でも十分条件でもない。
▶午前24
A小学校で発生した感染症の発症状況を図に示す。

感染源への曝露について最も考えられるのはどれか。
- 単一曝露があった。
- 多量曝露があった。
- 連続曝露があった。
- 複数回の曝露があった。
▶午前25
共に正規分布すると仮定できる2つの連続変数X、Yについて散布図を描いた。標本数は300である。散布図は全体的に右上がりであり、特に外れ値はなかった。Pearson〈ピアソン〉の相関係数を計算したところ、r=0.60であった。「母相関係数は0である」とする帰無仮説を立て、統計学的検定を行ったところ、有意水準5%にて棄却された。
XとYとの相関について適切なのはどれか。
- 全く相関はない。
- 有意な相関がある。
- 相関の有意性は棄却される。
- 相関の有無については判断できない。
▶午前26
市の保健師が市内在住の成人の生活実態把握のために横断調査を行う。
対象者の選定で適切なのはどれか。
- 市内の主要駅の通行人
- 無作為に選定した1地区の成人全員
- 市の住民基本台帳から無作為に選定した成人
- インターネットで募集した成人
▶午前27
1歳6か月児健康診査において児の発達を確認するために適切な質問はどれか。
- 「遊び友だちがいますか」
- 「クレヨンなどで丸(円)を書きますか」
- 「衣服の着脱をひとりでしたがりますか」
- 「手を使わずにひとりで階段をのぼれますか」
- 「ママ、ブーブーなど意味のあることばをいくつか話しますか」
▶午前28
28歳の女性。統合失調症。両親と3人で暮らしている。半年間入院し、退院後は自宅に閉じこもりがちで昼夜逆転の生活が続いている。
生活リズムを整えるために勧める社会資源で適切なのはどれか。
- 療養通所介護
- 生活訓練施設
- 居宅介護等事業
- 地域生活援助事業
- 地域活動支援センター
▶午前29
介護相談や会誌の発行をしている会員数60人の介護者の会。自主グループとして活動を始めて5年が経過した。会長は「今の活動でよいのか少し迷っている」と保健師に相談した。
保健師がこれまでの活動をねぎらった後、最初に勧めるのはどれか。
- 新規会員の勧誘
- 5年間の活動の振り返り
- 介護予防事業の行政方針の確認
- 隣接市町村の介護保険利用状況の把握
- 民間企業による介護サービスの提供状況の把握
▶午前30
法律と施策の組合せで正しいのはどれか。
- 健康増進法――受動喫煙防止
- 労働基準法――特殊健康診断
- 次世代育成支援対策推進法――長時間労働の防止
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律――子の看護休暇
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律――休日労働時間の削減
▶午前31
アスベスト曝露の肺がん罹患に対する寄与危険割合の算出のために十分な情報を持つ指標はどれか。
- アスベスト曝露群の肺がんの罹患率
- アスベスト非曝露群の肺がんの罹患率
- アスベスト曝露の肺がん罹患に対する相対危険
- アスベスト曝露の肺がん罹患に対する寄与危険
- 全人口に対するアスベスト曝露を受けた者の割合
▶午前32
正規分布について誤っているのはどれか。
- 一峰性である。
- 左右対称である。
- 平均値と中央値が一致する。
- 平均値が決まれば一意に定まる。
- 平均値±2×標準偏差の範囲に全体の約95%が含まれる。
▶午前33
Winslow〈ウインスロー〉による公衆衛生の定義について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 経済効率を最優先する。
- 環境衛生の改善を目指す。
- 保健従事者の質の向上を図る。
- 地方自治体が問題解決の義務を負う。
- 組織化された地域社会の努力で疾病を予防する。
▶午前34
保健活動の安全管理の視点からの評価指標はどれか。2つ選べ。
- 結核患者の服薬中断率
- 心筋梗塞による死亡率
- 健康教室参加者の脱落率
- BCG集団接種の手技による事故の発生率
- 家庭訪問時に保健師が受ける暴力被害の発生率
▶午前35
Aさんは第1子の3歳児健康診査に来所した。表情が暗く、周囲の母親たちとの会話もない。児は母親のもとを離れ、他児と一緒に遊んでいる。個別相談でAさんは「子どもが言うことを聞かず、どう関わればいいか分からない。子どもがかわいいと思えなくてつらい」と言う。保健師はAさんの気持ちを受け止めた。
保健師の対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 夫に、Aさんの状況を伝える。
- Aさんにいつでも相談が可能と伝える。
- Aさんに被虐待体験について確認する。
- Aさんに親子での遊びの教室への参加を勧める。
- Aさんに児に発達上の問題があると考えられると伝える。
▶午前37
地震発生後の避難所でインフルエンザが発生した。電気は復旧しているが、水道は復旧していない。
保健師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 高齢者を福祉避難所に移動する。
- 室内に次亜塩素酸ナトリウムを噴霧する。
- インフルエンザに罹患した避難者は別室に移す。
- 避難者にアルコールによる手指消毒を啓発する。
- 避難者の個人スペースを高さ100cmの段ボールで仕切る。
▶午前38
健康増進計画が根拠となる事業はどれか。2つ選べ。
- 快適な睡眠の推進に関する事業
- ひきこもり予防のための事業
- 歯の健康に関する事業
- 虐待防止キャンペーン
- 地域支援事業
▶午前39
学校で行う健康診断で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 定期の健康診断は毎年5月31日までに実施する。
- 定期の健康診断は学校保健安全法で規定されている。
- 就学時健康診断は入学した年の4月30日までに実施する。
- 皮膚疾患の有無の確認は定期の健康診断で全学年に実施する。
- 感染症または食中毒発生時は保健所長が臨時の健康診断を実施する。
▶午前40
高齢者の医療の確保に関する法律が根拠となる保健事業で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 75歳以上の者への健康診査
- 特定健康診査の結果の通知
- 糖尿病患者への生活習慣相談
- 家族介護者への健康管理指導
- 65歳以上の者への生活機能評価
次の文を読み41〜43の問いに答えよ。
Aさん(73歳、女性)。1人暮らし。民生委員が定期的に行っている状況確認のためAさんを訪問したところ「最近気分がすぐれず、この3か月ほとんど外出していない。かかりつけ医に1か月に1度受診しているが、加療中の高血圧以外は、特に悪いところはないと言われている。買い物にも出かけたくない。人と話すのもおっくうに感じる。介護保険の利用は、今のところ考えていない」と話した。
▶午前41
民生委員から、市保健センターの保健師にAさんについて情報提供があった。
保健師が連携する機関として優先度が高いのはどれか。
- 市の社会福祉協議会
- 地域包括支援センター
- 地区内の通所介護事業所
- Aさんが受診している診療所
▶午前42
その後、Aさんは要介護認定を申請したが非該当となり、介護予防サービスを受ける手続きをすることになった。
このサービスを受けるために必要なのはどれか。
- 生活機能評価
- 主治医意見書
- 特定健康診査の結果
- 介護保険被保険者証
▶午前43
保健師は、Aさんのような高齢者が必要に応じて介護予防サービスを受けられるように、市の介護予防サービスの周知が必要と考えた。
周知先として優先度が高いのはどれか。
- 市医師会
- 老人クラブ
- 訪問看護事業所
- 介護老人保健施設
次の文を読み44〜46の問いに答えよ。
A市は食育推進計画を策定することにした。
▶午前44
現状把握のために、市民に対して食育に関するアンケート調査を行うことにした。調査項目は国が実施している調査と同じ項目を設定して、全国平均との比較によるA市の特徴を分析することにした。
調査項目を参照すべき調査として適切なのはどれか。
- 食品産業動向調査
- 学校保健統計調査
- 国民健康・栄養調査
- 保健・衛生行政業務報告
▶午前45
市民アンケートの結果、子どもの野菜摂取不足が明らかになった。この課題を市民と共有して対策を検討するために、市民も含めた食育推進計画策定委員会を設置したい。
策定委員会の構成員を依頼する対象として優先度が高いのはどれか。
- 食品衛生協会
- 小児糖尿病の親の会
- 小学校のPTA連合会
- 要保護児童対策地域協議会
▶午前46
策定委員会での検討を経て、5年間のA市食育推進計画を策定した。
評価計画について適切なのはどれか。
- 質的評価は含まない。
- 評価結果の公表方法を含む。
- 評価方法は年度ごとに見直す。
- 成果評価として各事業の参加人数を集計する。
次の文を読み47〜49の問いに答えよ。
Aさんは従業員500人のコンピュータ会社に勤務している。課長補佐に昇任してから、食欲がなく不眠状態が続いている。「課長に相談してみたが、もう少したてば仕事に慣れるから大丈夫と言われた。仕事に集中できず、頑張ろうとしても頑張れない。自分が頑張らないとだめなのに」と健康管理室の保健師に相談があった。
▶午前47
保健師がAさんの状況を確認する事項として優先度が高いのはどれか。
- 趣味
- 残業時間
- 間食の状況
- 子どもの年齢
▶午前48
Aさんは、うつ病と診断され2か月の休職となった。
休職期間中の保健師の対応で適切なのはどれか。
- 服薬できているかAさんに毎日確認する。
- 同じフロアの職員にAさんの状況を説明する。
- Aさんの状況や意向を把握して産業医に伝える。
- 保健所保健師にAさん宅への家庭訪問を依頼する。
▶午前49
保健師は、Aさんのような従業員が今後増えないように産業医と相談して対策を立てることにした。
対策として優先度が高いのはどれか。
- 職場巡視の回数の増加
- 休憩時間の体操の実施
- 従業員の休暇取得状況の確認
- 管理職へのメンタルヘルス教育の実施
次の文を読み50〜52の問いに答えよ。
児数100名、職員数20名の保育所。給食とおやつは1歳から5歳まで同じメニューで形状を変えている。0、1、2、3歳児の部屋は1階で、4、5歳児の部屋は2階で交流はない。職員は担任制であるが延長保育は交代で担当している。10月12日朝に、保育所から「昨日、3歳児クラスで午前に3名、午後に5名が嘔吐をした。児が嘔吐した際には、職員が手袋を用いないで吐物を拭き取り、その後アルコールで床を消毒した。今朝、9名の保護者から児が嘔吐と下痢のため欠席すると連絡があった。食中毒ではないか」と保健所に連絡があった。保健所が確認した発症状況を図に示す。

▶午前50
保健所は、食中毒と感染症の両面から調査を行うことになった。
実施する調査として正しいのはどれか。2つ選べ。
- 全職員の検便調査
- 全児とその家族の検便調査
- 発症した児の自宅のふき取り調査
- 全児のうち発症者の給食の喫食調査
- 1週前からの保育所の行事と参加状況の調査
▶午前51
調査の結果、原因病原体はノロウイルスと判明し、10月9日の発症者を初発患者とする集団感染と推定された。保健所では保育所職員を対象に、集団感染の再発予防の健康教育を行うことにした。
教育内容で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 食品の保管方法
- 汚物の処理方法
- 児の消化機能に応じた調理方法
- 朝に行う児への健康チェック内容
- 保育所建物のホルマリン消毒方法
▶午前52
その後、管内の他の保育所でも同様にノロウイルス集団感染の事例が連続して発生した。保健所では地域への感染症予防対策を強化することにした。
保健所の対策として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 保育所向けの感染症情報の発信
- 食品納入業者向け健康管理指針の配布
- 保育所の給食施設への緊急立ち入り調査
- 保育所嘱託医への児の健康診断実施の依頼
- 保育所職員を対象とした感染症予防講習会の開催
次の文を読み53〜55の問いに答えよ。
運動習慣の死亡率に対する影響の調査のために1万人のコホート研究を行った。調査では、年齢や食習慣、経済状況など参加者の基礎的背景も併せて調査した。10年間追跡した結果を表に示す。

▶午前53
運動習慣があることに対して、運動習慣がないことの死亡に関する寄与危険はどれか。
- 0.05
- 0.10
- 0.50
- 2.00
- 2.11
▶午前54
研究の解析段階で、参加者の基礎的背景を補正することにした。
補正の方法として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 層化
- 無作為抽出
- マッチング
- 多変量解析
- 無作為割付け
▶午前55
参加者の基礎的背景を補正したところ、結果に大きな違いはなく、有意であった。この結果から「運動すれば長生きできる」とするのは誤りである。
誤りとする理由はどれか。
- 情報バイアスがある。
- 二重盲検がされていない。
- 死亡日が特定されていない。
- 因果関係の証明がされていない。
第99回保健師国家試験・午後(55問)
▶午後1
A町の胃がん検診精密検査の受診率を上げるための対応で最も適切なのはどれか。
- 精密検査受診啓発ポスターの掲示
- ケーブルテレビによる精密検査受診勧奨
- 保健師の家庭訪問による精密検査受診勧奨
- 健康推進員の家庭訪問による精密検査受診勧奨
▶午後2
A市保健センターで実施する1歳6か月児健康診査に、外国人の両親が男児を連れて来所した。両親とも片言の日本語しか話せなかった。男児の発育は順調だが、母子健康手帳の予防接種の記録欄はすべて空白であった。
この親に必要な社会資源で優先度が高いのはどれか。
- 主任児童委員
- 近所の小児科医
- 通訳のボランティア
- ファミリーサポートセンター
▶午後3
39歳の女性。「定期健康診断の結果に、BMI32、減量するようにと書かれていた。今まで運動しても続かなかった。この機会に再度運動に取り組みたい。どうしたらいいか」と市の健康相談に来所した。
保健師の支援で最も適切なのはどれか。
- 運動の必要性を説明する。
- 運動のパンフレットを渡す。
- 運動に関する講演会への参加を勧める。
- 運動の小集団健康教育への参加を勧める。
▶午後4
第1子の低出生体重児。生後6日、2,400gで退院した。生後20日に家庭訪問した。児の体重は3,000g。母親は、「この子はよく泣くし、母乳が足りているのか不安です」と言う。
保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 「この時期の子どもは泣くものですよ」
- 「泣くたびに母乳をあげましょう」
- 「ミルクを足してみましょう」
- 「体重増加は順調ですよ」
▶午後5
中学生を対象にした喫煙防止教室で適切なのはどれか。
- 喫煙経験を質問する。
- 喫煙経験のある生徒は対象としない。
- タバコの銘柄別ニコチン含有量の資料を配布する。
- 喫煙を勧められたときの断り方をロールプレイする。
▶午後6
日本の在宅生活をしている高齢者の虐待の傾向はどれか。
- 虐待者は被虐待者の娘が最も多い。
- 被虐待者は女性より男性が多い。
- 被虐待者は要介護認定を受けている人が半数を超えている。
- 被虐待者は要介護認定者のうち認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰが最も多い。
▶午後7
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者の入院形態とその説明の組合せで正しいのはどれか。
- 措置入院――指定病院への入院
- 緊急措置入院――入院期間は96時間以内
- 医療保護入院――患者本人の同意が必要
- 任意入院――入院時は指定医の診察が必要
▶午後8
最近、転入してきたDown〈ダウン〉症候群と診断された児の母親から相談があった。母親は「子どもは小児科に通院しており、主治医からは順調に成長していると聞いているが、今後の育児のイメージがわかない」と話した。
現時点で保健師が母親に紹介するのに最も適切なのはどれか。
- 保育所
- 市内の育児サークル
- 児童家庭支援センター
- Down〈ダウン〉症児をもつ親の会
▶午後9
84歳の女性。認知症。1人暮らし。日常生活自立度判定基準ランクⅡa、要支援2。身寄りはなく公営住宅の2階に住んでいる。民生委員から最近、金銭管理が困難になってきたようだと保健師に相談があった。
利用を勧めるサービスとして適切なのはどれか。
- 訪問介護
- 特別養護老人ホーム
- 日常生活自立支援事業
- 認知症対応型共同生活介護
▶午後10
歯周病の予防として正しいのはどれか。
- 歯間ブラシを使用する。
- 軟らかい食べ物を摂取する。
- 歯茎部のブラッシングは避ける。
- フッ素化合物を定期的に塗布する。
▶午後11
A市では近年、肥満傾向の住民が増加しているため、週1回3か月間の肥満予防教室を実施した。
プロセス評価の項目として適切なのはどれか。
- 教室の目標設定状況
- 毎回の教室で実施した内容
- 適正体重に変化した者の割合
- A市の特定健康診査受診者のうち肥満者の割合
▶午後12
特定保健指導の事業評価を行うにあたって必要な項目はどれか。
- 特定保健指導の脱落者数
- 特定健康診査の未受診者数
- 特定保健指導の新規対象者数
- 特定健康診査結果における要医療者数
▶午後13
市町村保健センターの予算編成で正しいのはどれか。
- 当初予算案は保健部門の長が議会に提出する。
- 議会の承認によって予算が成立する。
- 当該年度の予算編成は4月末までに行う。
- 介護保険事業費は衛生費に含まれる。
▶午後14
A市では総合的な障害者地域生活支援システムを構築するため、関係者による連絡会議を定期的に開催することにした。A市にはNPO法人〈特定非営利活動法人〉等の障害者を支援する団体が複数あるが、公的なネットワークは形成されていない。
初回の会議の議題として優先度が高いのはどれか。
- 連絡会議の開催頻度
- 支援困難事例の検討
- 各団体の活動内容の紹介
- 障害者の就労状況調査の企画
▶午後15
中学校の剣道部での熱中症の発生と予防について正しいのはどれか。
- 室内の練習では発生しない。
- 水分補給は休憩時間に限る。
- 暑い季節の休憩中は防具を外す。
- 休憩は90分に1回を目安とする。
▶午後16
従業員5,000人の企業に勤務する保健師。うつ病に対するポピュレーションアプローチを計画した。
適切なのはどれか。
- 職場復帰プログラムの作成
- 健康保険の給付状況の確認
- 従業員向けメンタルヘルス研修の実施
- 診療を行う常勤精神科医師の配置の提案
▶午後17
介護保険について正しいのはどれか。
- 認定調査は居宅介護支援事業者が行う。
- 要介護認定には主治医意見書が必要である。
- 居宅介護サービス計画費の1割を自己負担する。
- 通所リハビリテーションは地域密着型サービスである。
▶午後18改題
第4期がん対策推進基本計画の目標項目で正しいのはどれか。
- がん罹患率
- がん検診受診率
- 緩和ケア病棟数
- がん患者支援団体数
▶午後19
労働衛生管理の三管理でないのはどれか。
- 作業管理
- 健康管理
- 人事管理
- 作業環境管理
▶午後20改題
難病対策について正しいのはどれか。
- 障害者総合支援法に基づき実施している。
- 関節リウマチは医療費の公費負担の対象である。
- 各都道府県に難病相談・支援センターを設置している。
- 難病患者等居宅生活支援事業は、都道府県が実施している。
▶午後21
陽性反応的中度が上昇する理由として適切なのはどれか。
- 疾患の有病率が上昇した。
- 検査の特異度が低下した。
- 検査を受けた人が増加した。
- 基準値の変更で陽性者が増加した。
▶午後22
日本の結核対策で正しいのはどれか。
- 生後3か月に達するまでにBCGを接種する。
- 潜在性結核感染症は医師の届け出の対象ではない。
- 接触者健康診断は接触者の居住地の保健所が実施する。
- 定期健康診断は都道府県知事が実施義務者となって行われる。
▶午後23
A市の2地区でデータを取った。各項目について2地区間に差があるかどうかを統計学的に検定する。
t検定が適している項目はどれか。
- 性別
- 体重
- 年齢区分
- 5段階の自覚的健康度
▶午後24
人口動態統計の情報を用いて算出する指標はどれか。
- 受療率
- 生活影響率
- 年少人口指数
- 合計特殊出生率
▶午後25
公害健康被害の補償等に関する法律によって、第二種地域が指定された。
その汚染原因はどれか。
- 放射線
- アスベスト
- 六価クロム
- カドミウム
- ダイオキシン
▶午後26
介護予防を推進する住民ボランティアを県内市町村で養成することになった。
県庁介護予防担当課の保健師が市町村を介して、養成講座の実施を依頼するのはどれか。
- 居宅介護支援事業者
- 在宅療養支援診療所
- 地域包括支援センター
- 訪問看護ステーション
- シルバー人材センター
▶午後27
医療計画で正しいのはどれか。
- 予防接種計画を記載する。
- 地域保健法で策定が規定されている。
- 都道府県ごとに必要な医師数を定める。
- 一次医療圏ごとに必要な診療所数を定める。
- 二次医療圏ごとに一般病床の基準病床数を定める。
▶午後28
二次予防の行動はどれか。2つ選べ。
- 市の胃がん検診を受診した。
- 毎日ラジオ体操に参加した。
- 脳梗塞後に言語療法を受けた。
- 同僚が結核に罹患したので胸部エックス線撮影を受けた。
- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチンの接種を受けた。
▶午後29
平成12年(2000年)に国連ミレニアム宣言に基づき取りまとめられたミレニアム開発目標(MDGs)に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 飢餓の撲滅
- 認知症の減少
- 高等教育の充実
- 福祉施設の整備
- マラリアの蔓延防止
▶午後30
住民を対象にウォーキング教室を月2回の3か月コースで開催する。
コース終了3か月後に行う教室参加者への影響評価で、指標として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 参加者の出席回数
- 参加者の1日の歩数
- 参加者の健康診査の受診率
- 住民に対する参加者の割合
- 参加者のウォーキング継続者の割合
▶午後31
養護教諭の職務として正しいのはどれか。2つ選べ。
- 保健教育を行う。
- 給食の衛生管理を行う。
- 児童生徒の家族の健康管理を行う。
- 学校保健安全計画の立案に参画する。
- 感染症のおそれのある児童生徒の出席停止を決定する。
▶午後32
人口7万人、高齢化率30%の市。地震により市の大半が被災し、1か月が経過した。保健師による全戸訪問から、在宅の高齢者の中に褥瘡ができるなど状態が悪化している人がいることが分かった。
今後、状態が悪化している在宅の要介護高齢者の症状を改善するために、市保健師が行うことで適切なのはどれか。2つ選べ。
- 民生委員に配食サービスを依頼する。
- 居宅サービス事業者と情報を共有する。
- デイサービスを市役所庁舎で実施する。
- 災害ボランティアセンターに訪問介護を依頼する。
- 訪問医療チームに状態が悪化している要介護高齢者リストを渡す。
▶午後33
公衆衛生行政について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 日本国憲法第20条を法的基盤としている。
- 人材、法律による制度および予算が必要である。
- 一般衛生、産業保健、環境保健の3分野からなる。
- 国や地方自治体が国民の健康保持増進のために行う。
- 都道府県の公衆衛生行政部門の組織機構は一様である。
▶午後34
保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国勢調査は5年に1度実施される。
- 患者調査は2年に1度実施される。
- 人口動態調査は2年に1度集計される。
- 国民生活基礎調査から罹患率が得られる。
- 医療施設調査には静態調査と動態調査とがある。
▶午後35
人口122万人の市。1年間の結核新登録者数は183人、年末の活動性結核患者数は159人、年末の結核総登録患者数は549人であった。
年間の結核罹患率(人口10万人対)を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②
次の文を読み36〜38の問いに答えよ。
Aさん(85歳、男性)。肺癌の終末期である。病院から車で1時間かかる自宅への退院を希望しており、病院の地域連携室から保健所保健師に相談が入った。Aさんは軽度の呼吸困難と骨転移による激しい痛みとがあったが、現在は薬物による疼痛コントロールができている。子どもはなく、妻(80歳)と2人暮らしをしていた。
▶午後36
保健師は、Aさんと妻が在宅での看取りを希望していることを確認した。
疼痛コントロールを退院後も継続するために、最初に調整する機関はどれか。
- 保健センター
- 近隣の調剤薬局
- 在宅療養支援診療所
- 訪問看護ステーション
▶午後37
Aさんと妻は病院の主治医から在宅での療養生活についての説明を受けてから退院し、医師、看護師、薬剤師の在宅ケアチームによるケアが24時間体制で開始された。2週後に保健師は妻に電話をして様子を聞いた。妻は「時々、本人は自覚していないけど呼吸が苦しそうで心配です」と話した。
妻への説明で適切なのはどれか。
- 「苦しいときは救急車を呼びましょう」
- 「症状が落ち着くまで様子をみましょう」
- 「入院していた病院に相談してみましょう」
- 「訪問看護師にいつでも連絡してよいですよ」
▶午後38
Aさんは家族や近所の友人に看取られて亡くなった。保健所ではAさんの事例をもとに、在宅ターミナルケアの体制整備を図るため推進会議を開催することにした。
推進会議の初回の議題で最も優先すべきなのはどれか。
- 在宅ケア支援ボランティアの育成
- 住民対象の終末期に関する意識調査の内容
- 関係機関の在宅ターミナルケアの取り組み状況
- 診療所医師を対象とした緩和ケア研修会の内容
次の文を読み39、40の問いに答えよ。
Aさん(56歳、女性)。48歳のときに多系統萎縮症と診断された。現在、歩行困難となり、車椅子で移動している。構音障害と排尿障害とがあり、膀胱留置カテーテルを留置している。隣市の専門医療機関に月1回通院している。要介護4で、通所介護サービスを週2回利用している。61歳の夫(無職)と2人暮らし。市内に長女(26歳)が1人暮らしをしているが、仕事が多忙のため、Aさんの介護は夫が中心に担っている。夫は糖尿病で半年くらい前から血糖コントロールが不良である。
▶午後39
夫は血糖のコントロールのために入院を勧められている。
夫の入院中にAさんが利用する事業で適切なのはどれか。
- 神経難病患者在宅医療支援事業
- 難病患者地域支援対策推進事業
- 重症難病患者入院施設確保事業
- 難病患者認定適正化事業
- 短期入所療養介護
▶午後40
夫は入院し、インスリンの自己注射が開始された。退院後もAさんの介護をしている。翌年、Aさんの特定疾患医療費助成の更新申請に保健所に来所した。Aさんは、症状が進行したために、2週前から専門医療機関に入院し、呼吸管理のため気管切開をして吸引が頻回に必要な状況であるという。夫婦ともに在宅療養を望んでおり、夫はAさんの退院に向け、吸引の練習をしている。訪問サービスの利用について意向を確認すると、夫は「自宅に他人が入ると疲れるから利用は考えていない」と言う。
夫への対応で適切なのはどれか。
- 「療養型の入院医療機関を探しましょう」
- 「Aさんの通所介護は、週7日にしたほうがいいですね」
- 「専門医療機関の主治医に在宅療養担当医を決めてもらいましょう」
- 「Aさんと娘さんも一緒に担当の介護支援専門員と話し合いましょう」
次の文を読み41、43の問いに答えよ。
人口20万人のA市。保健センターの保健師は、潰瘍性大腸炎の患者を対象にした勉強会を企画した。市民病院の専門外来を中心に広報したところ、15人の申し込みがあった。勉強会の内容は、前半の1時間は市民病院の専門医による疾患の特徴、診断や治療法などについての講義、後半の1時間は保健師によるセルフケア能力の向上のためのグループワークとした。
▶午後41
グループワークで最も学習効果の高い方法はどれか。
- 参加者の達成目標を統一する。
- 専門医の講義で不明だった点の説明をする。
- 具体的な話し合いの内容は参加者が決める。
- 日常生活の留意点を網羅した詳細な資料を配布する。
▶午後43
約2年間、患者会は順調に運営された。3年目になって、会の活動への参加者は少なくなり、会費収入が減少して赤字になった。世話人代表のBさんは、1人で会の存続を目指して運営の工夫を行ってきたが、なかなかうまくいかないと保健師に相談に来た。保健師は「大変でしたね」と苦労をねぎらった。
次に行う助言として最も適切なのはどれか。
- 「私が世話人を引き受けます」
- 「赤字の分は市の予算を活用できます」
- 「他の会員と今後について一緒に考えましょう」
- 「せっかくの会なので解散しないことが重要です」
- 「会員のCさんに世話人を代わってもらいましょう」
次の文を読み44〜46の問いに答えよ。
Aさん(33歳、女性)。3歳6か月の長男と9か月の双子を育てている。長男はこれまでの健康診査で、異常は認められず順調に成長している。双子は在胎38週で生まれ、1人は出生体重2,600g、現在はいはいしている。もう1人は出生体重2,200g、3日前に1人座りができるようになった。2人とも体重増加は順調である。
▶午後44
Aさんは長男の3歳児健康診査に来所した。「離乳食も夫のお弁当も手作りしたいし、長男は家中におもちゃを散らかすし、毎日追われた感じで疲れます。長男に再び夜尿がみられるようになったり、双子の1人はなかなかお座りしなかったり気がかりです」と話す。
保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 「1人座りできたのが遅いですね」
- 「夜尿は専門の医師に診てもらいましょう」
- 「お子さんには平等に接してあげてください」
- 「家事の負担を減らす方法について検討しましょう」
▶午後45
半年後、Aさんから「長男が幼稚園に入園し、子育ての大変な時期を乗り越えることができた。自分の経験を子育て中の人に伝えたい」と相談があった。保健師は、子育ての仲間づくりを目的に「ふたご子育ての集い」を企画し、Aさんを含め3人から申し込みがあった。
集いの初日の保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 「機関誌を発行しましょう」
- 「子育て体験を話しましょう」
- 「もっと会員を増やしましょう」
- 「父親にも参加してもらいましょう」
- 「1か月に2回保健センターに集まりましょう」
▶午後46
この後半年、集いは順調に実施されている。保健師は自主的なグループ運営ができるよう「他の機関にも協力してもらいましょう」とグループに助言した。
協力を求める機関として適切なのはどれか。
- 児童相談所
- 都道府県保健所
- 母子福祉センター
- 子育て支援センター
次の文を読み47〜49の問いに答えよ。
Aさん(40歳、女性)。特定健康診査の結果は、身長155cm、体重70kg、BMI29、腹囲90cm、血圧136/80mmHg、中性脂肪160mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、空腹時血糖95mg/dL、喫煙なしであった。積極的支援レベルに該当したため、保健指導の利用を勧めたところ「運動も嫌いだし、食事も変えたくない。少し太っているかもしれないけれどどこも悪くない」と言っていたが、保健師の働きかけで初回面接の約束ができた。
▶午後47
初回面接ではAさんの思いを受け止めながら生活を振り返った。
併せて行う対応で最も適切なのはどれか。
- 食事の改善方法を提案する。
- 毎日体重を測ることを勧める。
- 運動に取り組んでいる自主グループを紹介する。
- 減量のメリットをAさんの興味に合わせて伝える。
▶午後48
面接で、Aさんから「1か月に1kgの体重減少を目標に、食事と運動の改善に取り組んでみたい」という発言が聞かれ、主食の量と間食を減らして毎日20分歩くことにした。初回面接から2週後に電話連絡したところ、Aさんは「ご飯を減らして間食もしないように気をつけているが、運動は3日しか続かなかった。体重も全然減らない。やっぱり私はだめなのだろうか」と話した。
保健師の最初の対応として最も適切なのはどれか。
- 体重を朝晩測定することを勧める。
- スポーツジムに通うことを提案する。
- 食事を減らす努力をしていることを認める。
- 食事と運動を併せて取り組む必要性を話す。
▶午後49
6か月後の最終評価面接では、体重65kg、腹囲85cmであり、Aさんは「何度も挫折しそうになったが、保健師さんに励まされてなんとか続けられた」と話した。Aさんは、翌年の特定健康診査を受診し、身長155cm、体重67kg、BMI28、腹囲86cm、血圧134/80mmHg、中性脂肪146mg/dL、HDLコレステロール45mg/dL、空腹時血糖90mg/dLという結果であった。
Aさんへの今後の対応として適切なのはどれか。
- 再度「積極的支援プログラム」の利用を勧める。
- 「動機付け支援プログラム」の利用を勧める。
- 「情報提供」を行う。
- 今年度は支援の非該当であると伝える。
次の文を読み50〜52の問いに答えよ。
人口12万人、高齢化率23%のA市。要介護者が増加傾向にある。国内で発生した震災を機に1人暮らしの高齢者から市役所に災害時の対応について相談が寄せられた。市は地域福祉計画の中に、災害時の1人暮らし高齢者への対策を盛り込むことを予定している。
▶午後50
A市は、すでに氏名、住所、生年月日の記載された1人暮らし高齢者のリストを保持している。
今後、災害発生直後の対応のために収集する情報はどれか。2つ選べ。
- 家族の連絡先
- 最終学歴
- 自力歩行の可否
- 住居の所有状況
- 経済状況
▶午後51
さらにニーズ把握のための聞き取り調査も実施することになった。
この調査の実施対象として優先度の高いのはどれか。
- 商工会議所の会員
- 肥満予防教室の参加者
- スポーツクラブの会員
- 介護予防事業の教室参加者
▶午後52
地域福祉計画が立案され、災害時の要援護者対策として、地域での1人暮らし高齢者の見守り体制を強化することにした。
保健師の活動で適切なのはどれか。
- 防災用品についての広報
- 高齢者への声かけボランティアの育成
- 避難所に指定されている施設のバリアフリー化
- 災害時の健康管理に関する市民向け講演会の開催
次の文を読み53〜55の問いに答えよ。
保健所に市内の介護老人保健施設から「本日20時ころから、下痢、嘔吐の症状がある入所者が多数いる。職員も数名が発症している」と22時に通報があった。保健所は食中毒を疑い、直ちに調査に入った。
▶午後53
昼食を検食した職員4名も腹痛、下痢の症状があり、夕食前に退所した者からも発症者が出たため、当日の昼食について喫食調査を行った。昼食の喫食状況と発症状況を表に示す。

原因として最も疑わしいメニューはどれか。
- ハンバーグデミグラスソース
- アサリと青菜のあえもの
- 煮豆
- フルーツポンチ
▶午後54
10人の発症者の便からウェルシュ菌が検出されたので、食中毒と判断された。
考えられるのはどれか。
- 嘔吐物から二次感染が起こる。
- 不顕性感染から二次感染が起こる。
- 3日目以降、有症状者が増加する。
- ほとんどの発症者は軽症で経過する。
▶午後55
この施設への保健所の対応で適切なのはどれか。
- 発症者を隔離する。
- 調理器具の変更を指導する。
- 調理従事者の就業制限を行う。
- 食材の保存方法について指導する。
資料 厚生労働省「第99回保健師国家試験、第96回助産師国家試験及び第102回看護師国家試験の問題および正答について」
平成26年2月14日実施の第100回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。
また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。
分野別解説付き問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ
- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ
を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。
なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
第100回保健師国家試験目次
第100回保健師国家試験・午前(55問)
▶午前1
保健師の歴史に関する事項とその対策の組合せで正しいのはどれか。
- 開拓保健婦制度――入植者の健康管理
- 保健婦駐在制度――健兵健民政策
- 保健婦の身分の確立――GHQ覚書による公衆衛生対策
- 国民健康保険保健婦の市町村移管――特定健康診査
▶午前2
市の健康課題の解決に適切なのはどれか。
- 市が現在実施している保健福祉事業の中で解決を考える。
- 健康課題の対象者を医療モデルで捉える。
- 地域のキーパーソンの意見を優先する。
- ソーシャルキャピタルを活用する。
▶午前3
保健師が行う家庭訪問の対象者と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。
- 1歳6か月の児――母子保健法
- 介護を要する者――介護保険法
- 特定保健指導対象者――高齢者の医療の確保に関する法律
- 結核登録票に登録されている者――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
▶午前4
要介護高齢者の多い町でコミュニティ・エンパワメントを示す状況はどれか。
- 住民による高齢者サロン活動が実施される。
- 介護予防の方法を介護支援専門員が話し合う。
- 住民との話し合いの場で専門職が積極的に解決方法を提案する。
- 要介護高齢者の家族が抱える問題を当事者たちの問題と住民が認識する。
▶午前5
3歳児健康診査において確認するのはどれか。
- しりとりができる。
- 円を描くことができる。
- 自分の「前後」「左右」がおおよそ分かる。
- 約束やルールを守って遊ぶことができる。
▶午前6
市の保健師は、認知症の高齢者への支援には地域で支え合いができる体制を構築することが必要と考え、市内の中学校に出向いて生徒に対して認知症に関する健康教育を行うことにした。
媒体として最も効果的なのはどれか。
- 認知症高齢者の頭部MRI
- 県内の認知症高齢者数の推移のグラフ
- 市内の介護ボランティアグループのリスト
- 認知症高齢者を介護する家族が介護体験を語る映像
▶午前7
2年前に発足し、定期的に活動している精神障害者の家族会。
今後も活発に活動するための保健師の対応で適切なのはどれか。
- 運営資金の確保
- 家族会の会の進行
- 年間行事計画の作成
- リーダーへの精神的支援
▶午前8
地区踏査による情報収集の特長はどれか。
- 地区の環境を把握することができる。
- 地区の医療費を分析することができる。
- 地区の健康指標の情報を得ることができる。
- 1回の地区踏査で十分な情報を得ることができる。
▶午前9
保健師は、BMI28以上の人を対象に生活習慣病予防のための健康づくり教室を企画した。教室は、1回目を講話、2回目を運動指導、3回目を調理実習で構成した3日間で行い、教室終了後6か月に参加者を集めて評価を行う。
評価を行う際のアウトカム指標で最も適切なのはどれか。
- 血圧の変化
- 腹囲の減少率
- 実施日ごとの参加者数
- 生活習慣病による通院者数
▶午前10
市ではボランティア組織の活動を活性化させるために、地区の健康づくりリーダーを養成することにした。
対象者を選定する方法で最も適切なのはどれか。
- 保健師の推薦
- 市民への募集
- 自治会長の推薦
- 自治会員の輪番制
▶午前11
人口4万人、高齢化率31%の市。保健師は高齢者の生活と健康問題の実態を把握するため、グループインタビューを行いたいと考えた。
優先的に行うグループはどれか。
- 民生委員
- 消防団員
- 商工会議所役員
- 食生活改善推進員
▶午前12
人口30万人の市。市内にロコモティブシンドローム予防を目的としたウォーキンググループが8つある。保健師は、これらのグループが交流することによって連携し組織化した活動を行うことを支援したいと考えた。
保健師の支援で優先度が高いのはどれか。
- 活動目的を提案する。
- 運営規則の作成を促す。
- ロコモティブシンドローム予防の資料を提供する。
- ロコモティブシンドロームに関連した地域の課題を共有する場を設定する。
▶午前13
市では、認知症高齢者の徘徊についての家族からの相談や、警察に保護される事例が増加した。保健師は認知症高齢者の徘徊について地域で対応するケアシステムの構築が必要と考え、地域の関係者を集めた会議を開催することにした。
初回の会議で検討する内容として最も適切なのはどれか。
- 認知症高齢者家族会の設立
- 徘徊高齢者の見守りの役割分担の決定
- 会議の構成員の徘徊高齢者への対応状況の共有
- 会議の構成員の認知症高齢者に関する知識の確認
▶午前14
3歳児の母親。「子どもが専門医療機関で自閉症と診断されました。夫は仕事で忙しく、育児は自分に任されてきました。子どもが多動でパニックを起こすと手が付けられないので、外出することは少ないです。主治医に対応の方法を聞きましたが、うまく対応できません」と保健センターに相談のため来所した。
保健師の支援で優先度が高いのはどれか。
- 保育所への入所を勧める。
- 自閉症児の家族会を紹介する。
- 夫と一緒に来所することを勧める。
- 地域子育て支援センターを紹介する。
▶午前15改題
令和4年(2022年)の歯科疾患実態調査結果で正しいのはどれか。
- 歯みがきの回数は1日3回以上が最も多い。
- う蝕を持つ者の割合は65~74歳が最も多い。
- 歯肉に所見のある者の割合は55~59歳が最も多い。
- 80歳では20歯以上自分の歯を有する者の割合が5割を超える。
▶午前16
医療費の助成と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。
- 自立支援医療――次世代育成支援対策推進法
- 結核児童の療育給付――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 小児慢性特定疾患治療研究事業――児童福祉法
- 妊娠高血圧症候群等の療養給付――母体保護法
▶午前17
35歳の男性から「職場の健康診断の結果通知を見たら、HDLコレステロールの欄が35mg/dLで正常範囲ではありませんでした。その他の項目はすべて正常範囲です。どのようにしたらよいでしょう」と保健師に相談があった。営業職で、毎日20本喫煙し、日本酒換算で週4合飲酒している。特記すべき既往歴はなく、現在治療中の疾患もない。保健師はHDLコレステロール値の意味を説明した。
併せて行う指導で適切なのはどれか。
- 禁煙する。
- 禁酒する。
- 医療機関を受診する。
- コレステロールの多い食品の摂取は避ける。
▶午前18
学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施期限と児童生徒等および保護者への実施日から結果通知までの期間の組合せで正しいのはどれか。
実施期限――結果通知までの期間
- 5月31日――28日
- 5月31日――21日
- 6月30日――28日
- 6月30日――21日
▶午前19
職場巡視について労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 保健師は週1回以上行う。
- 安全衛生推進者は週1回以上行う。
- 産業医は月1回以上行う。
- 衛生管理者は月1回以上行う。
▶午前20
保健所の平時の健康危機管理対策について正しいのはどれか。
- 健康被害情報の把握
- 積極的疫学調査の実施
- 情報の通信手段の確保
- ボランティアの配置の調整
▶午前21
有料老人ホームの職員から複数の入居者がノロウイルスによる胃腸炎と診断されたと保健所に連絡があった。
感染拡大の防止のための職員への指導で適切なのはどれか。
- 家族の面会は禁止する。
- 嘔吐物の処理は密閉した空間で行う。
- 嘔吐物で汚染されている場所に入居者を近付けない。
- 嘔吐物で汚染されている場所は逆性石けんで消毒する。
▶午前22
市では、毎年12月に次年度の地区活動計画を立案している。
保健師が担当地区の次年度の地区活動計画を立案する時に適切なのはどれか。
- 目標値の修正はしない。
- 保健事業の必要量を算出する。
- 昨年度の決算額を予算額とする。
- 地区の自治会長と一緒に立案する。
▶午前23
ヒストグラムについて正しいのはどれか。
- 連続量や度数の経時的変化を折れ線で示す。
- 名義尺度の度数の分布を棒の高さとして示す。
- ある範囲にある連続量の度数を面積の大きさとして示す。
- 標本のもつ2つの連続量をプロットしてその関連を示す。
▶午前24
統計調査と調査内容の組合せで正しいのはどれか。
- 国勢調査――健康保険の種別
- 人口動態統計――転出入
- 社会生活基本調査――生活時間の配分
- 国民生活基礎調査――栄養摂取状況
▶午前25
世界保健機関〈WHO〉の機能について正しいのはどれか。
- 青年海外協力隊の派遣
- 国際社会の平和と安全の維持
- 開発途上国における学校の建設
- 新興・再興感染症の監視網の構築
▶午前26
保健所について正しいのはどれか。
- 結核登録票を整備する。
- 保健所法に基づいて設置されている。
- 保健師は保健所長になることができない。
- おおむね人口10万人当たり1か所設置されている。
▶午前27改題
日本の令和2年(2020年)における社会保障給付費の割合の内訳について多い順に並んでいるのはどれか。
- 医療>介護>年金
- 医療>年金>介護
- 年金>医療>介護
- 年金>介護>医療
▶午前28
40歳の女性から「同居している74歳の姑が、最近物忘れがひどくなり、食事を食べているのに、嫁がご飯を作ってくれないと近所に言いふらすので困っています」と電話があった。
保健師の最初の対応で最も適切なのはどれか。
- 「様子を見に行かせてください」
- 「民生委員に相談してみましょう」
- 「認知症の高齢者にはよくあることです」
- 「かかりつけの医師に相談してください」
- 「お姑さんに食事を食べたことを伝えてみましょう」
▶午前29
在宅療養者の支援におけるヘルスケアチームについて正しいのはどれか。
- 病院と同等の治療環境を目指す。
- チームメンバーに在宅療養者の家族を含む。
- 最初に決めたチームメンバーは変更しない。
- チーム会議では情報の共有より役割の分担が優先する。
- ボランティアとして関わっている人はチームメンバーとしない。
▶午前30
担当地区に住むAさんから「48歳の夫が若年性認知症と診断され治療が開始されました。どうしたらよいかわかりません」と市の保健センターに電話があった。
保健師の最初の対応で最も適切なのはどれか。
- 夫への対応の仕方を指導する。
- 保健センターへの来所を勧める。
- Aさんが心配していることを聞く。
- 主治医に再度相談するよう勧める。
- 夫の職場の上司に相談するよう勧める。
▶午前31
セルフヘルプグループはどれか。
- 町内会
- 断酒会
- 母子保健推進委員会
- 公民館で行う太極拳の教室
- 絵本の読み聞かせグループ
▶午前32
Aさん(40歳、女性)。48歳の会社員の夫と2人暮らし。「夫が1か月前から夜眠れない様子で、ここ数日は『役に立たない人間は生きていてもしょうがない』と言っています。どう対応したらよいでしょうか」と市の保健センターに相談のため来所した。
最初に行う助言で最も適切なのはどれか。
- 「産業医に相談して仕事量を減らしてもらいましょう」
- 「市販の睡眠を改善するお薬を飲んでもらいましょう」
- 「できるだけ早く精神科医の診察を受けましょう」
- 「言動に注意しながら様子をみましょう」
- 「Aさんも体調に気をつけましょう」
▶午前33
癌と危険因子の組合せで正しいのはどれか。
- 乳癌――多産
- 胃癌――脂肪摂取
- 膀胱癌――喫煙
- 食道癌――アスベスト
- 大腸癌――炭水化物摂取
▶午前34
3種類のスクリーニング検査A、B、Cの受信者動作特性(ROC)曲線を示す。

検査の正確さについて正しいのはどれか。
- 3検査のうちAが最も正確な検査である。
- 3検査のうちBが最も正確な検査である。
- 3検査のうちCが最も正確な検査である。
- 正確さを評価するには足りない情報がある。
- この曲線は検査の正確さの評価には適していない。
▶午前35
相関について正しいのはどれか。
- 因果関係の必須項目である。
- 相関係数が大きいほど相関関係は強い。
- 相関が全くないときの相関係数は0である。
- 相関係数は0から100までの数値で示される。
- 2つの連続量の一方を使用して他方を推計することをいう。
▶午前36
Breslow〈ブレスロー〉の7つの生活習慣に該当するのはどれか。2つ選べ。
- 喫煙しない。
- ストレスを避ける。
- 食後に歯磨きをする。
- 1日3回の食事を摂取する。
- 1日7~8時間の睡眠をとる。
▶午前37改題
令和4年(2022年)の厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「令和4年中における自殺の概要」における自殺による死亡で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 死亡総数は4万人を超えている。
- 男性の死亡数は女性の約2倍である。
- 35歳から39歳に死亡率のピークがある。
- 原因・動機は経済・生活問題が最も多い。
- 10歳から39歳における死因の第1位である。
▶午前38
分母に集団の人口全体を用いる指標はどれか。2つ選べ。
- 有病率
- 累積罹患率
- 致命率〈致死率〉
- 死因別死亡割合
- PMI〈proportional mortality indicator〉
▶午前39
日本の社会保障の財源で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 雇用保険の財源は公債である。
- 生活保護の財源は保険料と税である。
- 医療保険の財源は保険料と税である。
- 介護保険の財源は保険料と税である。
- 労働者災害補償保険の財源は税と企業が支払う保険料である。
▶午前40改題
日本の自殺対策で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 法律の規定はない。
- 雇用対策が中心である。
- 遺族対策が含まれている。
- 平成20年に自殺対策加速化プランが策定された。
- 自殺総合対策大綱では、令和8年には平成27年の死亡率の5%減少を目標にしている。
次の文を読み41~43の問いに答えよ。
人口11万5千人、高齢化率25%の市。要介護高齢者が増加傾向にある。要介護高齢者の介護者の交流を目的に、月1回保健センターで「介護者の集い」を行っている。
▶午前41
介護者の集いのアウトプットとして最も適切なのはどれか。
- 継続参加者数
- 介護者の健康診査結果
- 介護者のストレス対処状況
- 介護者の介護に対する困難感
▶午前42
多くの参加者から「介護がとても大変だ」という声が聞かれた。保健師は、市全体の状況を把握するため、要介護高齢者の介護者の負担について調査を実施することにした。
調査項目で優先度が高いのはどれか。
- 介護に要する時間
- かかりつけ医の有無
- 介護技術の習得状況
- 要介護高齢者の要介護度
▶午前43
調査の結果、要介護認定を受けている者が介護保険サービスを十分に利用していないため、介護負担が大きい可能性があると考えた。保健師は関係者を対象に介護者の負担軽減を目的とした研修会を実施することにした。
研修会の対象者として優先度が高いのはどれか。
- 民生委員
- 精神保健福祉士
- 介護支援専門員
- 健康運動指導士
次の文を読み44~46の問いに答えよ。
山間部にある人口8,000人、高齢化率40%のA町。高齢者のうち独居者の割合35%。町に急な坂が多く、電車やバスが運行していないため、高齢者は買い物に不便を感じている。
▶午前44
保健師は、独居高齢者の状況について情報収集を行うことにした。
収集する資料で優先度が高いのはどれか。
- 診療報酬明細書
- 生活機能評価結果
- 特定健康診査結果
- 要介護認定者の状況
▶午前45
保健師が高齢者を対象に健康に関するアンケートを実施した結果、食事回数が1日2回と回答した割合が、独居高齢者では60%、同居者がいる高齢者では30%であった。
独居高齢者の食事回数が1日2回であることに対する寄与危険はどれか。
- 2.0
- 0.50
- 0.30
- 0.26
▶午前46
保健師は、独居高齢者の食生活上の問題を解決するには地域の協力が必要と考え、自治会役員を集めて町の独居高齢者の状況について説明した。
このときの保健師の自治会役員への働きかけとして最も適切なのはどれか。
- 独居高齢者に対して地域で取り組めることを一緒に考える。
- 独居高齢者が簡単に作れる料理教室の開催を依頼する。
- 自治会役員による買い物の代行を提案する。
- 独居高齢者への家庭訪問を依頼する。
次の文を読み47~49の問いに答えよ。
児童委員から担当地区のアパートに住む2歳の児について「見かけた時は元気がなくて、外で遊ぶ様子も見ません。いつも同じ服を着ていて身なりも汚れています」と町の保健師に相談があった。保健師が児童委員に詳しく話を聞いた結果、母親は児童委員に子育ての大変さを繰り返し訴えていることが分かった。
▶午前47
保健師が確認する情報として優先度が高いのはどれか。
- 乳幼児健康診査の状況
- 新生児訪問で把握した状況
- アパートの管理人からの情報
- アパートの近所の住民からの情報
▶午前48
保健師は児童委員と一緒に家庭訪問を行うことにした。
初回の家庭訪問で確認する事項として優先度が高いのはどれか。
- 母親の子どもとの遊びの状況
- 家の中の整理整頓の状況
- 子どもの発育・発達状況
- 母親の既往歴
▶午前49
家庭訪問で、父親は県外に単身赴任中であり、子どもと2人きりでずっと一緒にいてつらいこと、母親は疲労のため寝ていることが多いこと、子どもには食事の代わりにお菓子を食べさせていることが分かった。
保健師の支援で優先するのはどれか。
- 児童委員への見守り依頼
- 母親の医療機関への受診勧奨
- 地域生活支援センターへの連絡
- 要保護児童対策地域協議会実務者会議の開催要請
次の文を読み50~52の問いに答えよ。
Aちゃん(7歳、女児)は、B小学校に通学している。健康診断で尿蛋白+と指摘された。昨年までの健康診断では検尿を含めて異常を指摘されたことはなく、既往歴に特記すべきことはない。
▶午前50
養護教諭が尿の再検査についてAちゃんと保護者へ行う説明で正しいのはどれか。
- 「Aちゃんのお母さんの尿も検査する必要があります」
- 「腹痛があるときは尿を採らないでください」
- 「尿を採る12時間前から絶食してください」
- 「朝起きて一番の中間尿を採ってください」
▶午前51
Aちゃんは、再検査でも尿蛋白+となり、腎生検の結果、IgA腎症と診断され入院した。副腎皮質ステロイドを内服しながら院内学級に通っていた。3か月後、退院が決まりB小学校に再び登校することになった。B小学校は学校生活管理指導表の提出を求めた。
学校生活管理指導表を記載する者で正しいのはどれか。
- 保護者
- 入院先の主治医
- 入院先の看護師長
- 院内学級の担当教員
▶午前52
Aちゃんは副腎皮質ステロイドを内服しながら通学を再開した。
養護教諭が行う支援で適切なのはどれか。
- 内服薬は保健室で保管する。
- Aちゃんの尿検査を定期的に行う。
- Aちゃんの健康状態の観察を学級担任と協力して行う。
- Aちゃんの疾患について同じクラスの児童へ説明する。
次の文を読み54、55の問いに答えよ。
人口50万人の中核市のA市。市の保健医療計画に糖尿病対策の強化を盛り込むことになった。
▶午前54
A市には、特定機能病院1か所、200床規模の病院が3か所、診療所は200か所ある。市内の病院と医師会、歯科医師会、薬剤師会とで糖尿病医療連携推進会議を実施することになった。
この会議で検討する内容で適切なのはどれか。
- 糖尿病専門医の育成
- 人工透析患者の医療機関への送迎
- 病診連携のための連絡用フォーマットの作成
- 特定健康診査受診者のうち積極的支援対象者の選定方法
▶午前55
A市の糖尿病医療連携推進会議での検討の結果、市では糖尿病対策として、市の保健事業を強化することにした。そこで、保健師は、糖尿病発症予防対策としてウォーキング教室を企画した。
対象として適切なのはどれか。
- 糖尿病患者の家族
- 市の広報誌で募集する市民
- 市内のフィットネスクラブの指導者
- 特定健康診査において空腹時血糖100mg/dL以上で積極的支援とならなかった市民
第100回保健師国家試験・午後(55問)
▶午後1改題
令和4年度(2022年度)の保健師活動領域調査で正しいのはどれか。
- 地方自治体の常勤保健師数は5万人を超える。
- 常勤保健師数は、市町村(保健所設置市・特別区を除く)よりも都道府県保健所が多い。
- 都道府県保健所の活動項目別保健師1人当たりの平均時間数は、健康危機管理が最も多い。
- 市町村(保健所設置市・特別区を除く)の活動項目別保健師1人当たりの平均時間数は、直接対人支援が5割を超える。
▶午後2
健康づくりの自主グループで活動しているリーダーのAさんから、最近グループメンバーの参加が少なくなったと保健師に相談があった。
保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- グループ活動の休止を勧める。
- 新しい参加者の募集方法を提案する。
- 保健師が参加者一人一人の意見を聞く。
- メンバーの話し合いの場を設けるよう勧める。
▶午後3
市の健康診査の結果、糖尿病が強く疑われる者の割合が高いことが分かった。保健師は糖尿病予防のための教室を企画することにした。
最初に検討するのはどれか。
- 目標
- 周知方法
- プログラム
- 教室のテーマ
▶午後4
人口10万人の市。市では、電話相談と来所相談について相談の項目と件数をまとめている。その結果、育児不安の相談件数が増加傾向にあることから、保健師は地域診断を行うことにした。
最初に行うのはどれか。
- 家庭訪問で聞き取り調査を行う。
- 乳幼児健康診査でグループインタビューを行う。
- 乳幼児健康診査における相談内容のデータを分析する。
- 乳幼児健康診査の問診表に「育児不安の有無」の項目を入れる。
▶午後5
保健事業の評価について正しいのはどれか。
- 経済的評価は実施評価に含まれる。
- 形成的評価は事業の実施後に行う。
- 評価計画は活動計画の策定時に立てる。
- プロセス評価は事業実施後に総合的に行う。
▶午後6
市では健康増進計画を見直すことになり市役所内の関係部署の代表者による計画策定会議を設置した。保健師は事務局として会議を運営する。
市役所内のエンパワメントにつなげる計画策定方法として最も適切なのはどれか。
- 目標設定は事務局が担当する。
- 事務局が各部署の役割を指示する。
- 計画策定後に策定内容を市役所内に周知する。
- 各部署で検討された内容を策定会議で検討する。
▶午後7
市では、脳卒中後遺症による要介護認定者数が増加している。保健師は、脳卒中後遺症患者が退院後に適切にリハビリテーションを行っていないために、拘縮が進んだ状態で要介護認定の申請に至っていることが課題と考えた。そこで、病院から地域への円滑な移行に向けた地域リハビリテーションの体制整備を目的に、医療機関、訪問看護ステーション、通所介護事業所の関係者による会議を開催することにした。
初回の会議で出席者から収集する情報で最も適切なのはどれか。
- 要介護認定者の原因疾患
- 市内の理学療法士の従事状況
- 通所型介護予防事業の実施状況
- 各機関におけるリハビリテーションの利用状況
▶午後8
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく支援について正しいのはどれか。
- 更生医療の給付実績は、内臓障害で給付される割合が増大している。
- サービス内容は行政の決定に基づく措置制度である。
- 自立支援給付の申請は都道府県に行う。
- 養育医療は自立支援医療に含まれる。
▶午後9
Aさん(37歳、男性)。妻と2人の児との4人暮らし。会社員。3か月前に脊髄小脳変性症と診断された。最近、歩行障害が進行し、会社への通勤に支障がでてきたとAさんから保健所保健師に相談があった。
Aさんへの対応で適切なのはどれか。
- 介護保険の利用を勧める。
- 難病情報センターへ紹介する。
- 身体障害者手帳の申請を勧める。
- 勤務形態の変更について職場に相談するよう勧める。
▶午後10
人口40万人の中核市。定期的に地域・職域連携推進協議会を開催している。その会議で、市内の3つの事業所の出席者から、特定健康診査の結果では2年後に定年退職となる者に血中脂質検査の項目が異常の者の割合が高いことが報告された。市の保健師は、退職予定者を主な対象として健康づくりの講演会を各事業所の衛生管理者と企画することにした。
連携先として優先度が高いのはどれか。
- 商工会議所
- 地域活動支援センター
- 地域産業保健センター
- 地域包括支援センター
▶午後11
管内のA病院から、下痢のため3日前に入院した8歳女児の便から、サルモネラが検出されたと保健所に電話があった。同日、B病院からも同じ菌を検出したとの電話があった。
保健所の対応で適切なのはどれか。
- 患児の自宅を消毒する。
- 患児の喫食調査を実施する。
- A病院の検食の病原体検査を行う。
- 患児を第1種感染症指定医療機関に移送する。
▶午後12
Aさん(75歳、男性)。72歳の妻と2人暮らし。脳梗塞後遺症による右片麻痺がある。要介護3で車椅子の生活であり2週前に退院した。自宅から避難所になっている小学校までは、坂道の多い市街地を通り徒歩で15分かかる。息子はAさん宅から車で1時間の場所に家族と暮らしている。Aさんの妻から、災害時に2人だけでは心配だと保健師に相談があった。
保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 長男に徒歩圏内に転居することを勧める。
- 避難所になっている小学校の建物の構造を妻と確認する。
- Aさんと妻に災害の情報はテレビから入手するよう説明する。
- 緊急時にAさんを手助けする近隣のボランティアを育成していくと伝える。
▶午後13
新人保健師を対象とした現任教育で適切なのはどれか。
- 職場外研修(OFF-JT)を中心に行う。
- 基礎的な知識を獲得することに重点を置く。
- 職場の実地指導者が人材育成計画を立てる。
- 新人保健師が担当する対応困難な事例を課内で検討する。
▶午後14
40歳代男性を対象とした研究で、虚血性心疾患死亡率(人口10万人対)を観察した。喫煙群では20.0、非喫煙群では10.0であった。
次の計算で求めたのはどれか。
20.0÷10.0=2.0
- オッズ比
- 寄与危険
- 相対危険
- 寄与危険割合
▶午後15改題
令和2年(2020年)の患者調査で傷病分類別入院受療率が最も高い疾患はどれか。
- 糖尿病
- 心疾患
- 悪性新生物〈腫瘍〉
- 脳血管疾患
▶午後16
日本人の血液型のうちAB型の割合が10%であるとする。無作為に選んだ100人の日本人集団の中にAB型の人が20人以上いる確率を知りたい。
この集団の中に含まれるAB型の人数が従う分布として最も適切なのはどれか。
- t分布
- F分布
- 正規分布
- 二項分布
▶午後17改題
65歳男性の生命表に基づく死因別死亡確率(%)の表を示す。

ただし、A~Dは悪性新生物〈腫瘍〉、脳血管疾患、心疾患または肺炎のいずれかを示す。
脳血管疾患はどれか。
- A
- B
- C
- D
▶午後18
情報処理について誤っているのはどれか。
- データをコンピュータで使用可能な形にすることをデータの電子化という。
- 体系づけられたデータやファイルの集まりのことをデータベースという。
- 同じ形式のデータを連結することをレコードリンケージという。
- 氏名の削除や番号・記号への置き換えのことを匿名化という。
▶午後19
保健所が行う業務はどれか。
- 病院への立ち入り検査
- 介護保険事業者の開設許可
- 労働者災害補償保険給付申請の受付
- 精神障害者保健福祉手帳申請の受付
▶午後20
介護保険制度における都道府県の役割はどれか。
- 被保険者の資格管理
- 介護支援専門員の登録
- 介護給付費の1/4を負担
- 地域密着型サービス事業所の指定
▶午後21
39歳の女性。全身性エリテマトーデス〈SLE〉と診断された。「病院に掲示されていたポスターに保健所の住所と電話番号が書いてあったので来ました」と言う。
保健師の最初の対応として優先度が高いのはどれか。
- 就労状況の確認
- 婚姻状況の確認
- 相談内容の確認
- 治療状況の確認
- 全身性エリテマトーデス〈SLE〉の説明
▶午後22
Aさん(21歳、初産婦)。出生連絡票の子の父の氏名は母と違う姓が書かれ、相談したいことの欄には「子どもと接したことがなく、育て方がわからないことが多く不安」と書かれていた。
保健師の新生児訪問指導で最初に確認すべき事項として優先度が高いのはどれか。
- 妊娠の経過
- 授乳の状況
- 出産時の状況
- 子の父親の状況
- Aさんの交友関係
▶午後23
Aさん(60歳、男性)。Aさんの妻から「夫は身長165cm、体重68kgだったのが退職後6か月で体重が5kg増加しました。家でゴロゴロしていることが多く、食欲は旺盛です。夫にどのように対応したらよいでしょうか」と保健師に相談があった。
妻への対応として最も適切なのはどれか。
- 「毎朝、夫婦でウォーキングをしましょう」
- 「Aさんに栄養士の指導を受けてもらいましょう」
- 「Aさんに肥満予防教室に参加してもらいましょう」
- 「Aさんは体重増加をどう思っているか聞いてみましょう」
- 「Aさんに肥満は心臓病の原因となることを伝えましょう」
▶午後24
市では肺癌死亡率がここ数年上昇傾向にある。そこで、市の保健師は肺癌死亡率の低下を目標に事業を計画した。
ハイリスクアプローチはどれか。
- 妊婦に対する禁煙教室
- 高血圧の者に対する禁煙教室
- 街頭における分煙キャンペーン
- 喫煙者に対する肺がん検診の勧奨
- 特定健康診査と肺がん検診の同時実施
▶午後25
25歳の母親。専業主婦。夫と6か月の乳児(出生時体重2,900g、身長49cm)との3人暮らし。乳児健康診査未受診で何度か電話で受診勧奨したが来所しないため、市の保健師が家庭訪問した。訪問時、児は体重6,900g。首はすわり、寝返りはできているが、はいはいはできない。離乳食は開始したばかりであり、進め方が分からないと言うので保健指導した。人付き合いが苦手で、育児の相談相手もいないという。
保健師の対応として最も適切なのはどれか。
- 家庭訪問を継続する。
- 市の育児相談を勧める。
- 育児サークルを紹介する。
- 児童委員に情報を提供する。
- 児を発達障害の専門外来へ受診させるよう勧める。
▶午後26
学校保健安全法施行規則で規定されている疾病と出席停止の期間の基準の組合せで正しいのはどれか。
- 結核――特有の咳が消失するまで
- 水痘――すべての発しんが痂皮化するまで
- 風しん――解熱後2日を経過するまで
- 麻しん――特有の発しんが消失するまで
- インフルエンザ――解熱後1日を経過するまで
▶午後27改題
日本の令和元年(2019年)の健康寿命について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 女性より男性の方が長い。
- 男女ともに70歳を超える。
- 都道府県間の差は5年を超える。
- 平均寿命との差は5年未満である。
- 平均寿命との差は男性より女性の方が長い。
▶午後28
ノーマライゼーションについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- 北米から概念が広まった。
- 性的な生活をする権利を含む。
- 1970年代に初めて法律の中で用いられた。
- 国際障害者年のテーマを支える理念である。
- 最初に提唱されたときは身体障害者を対象とした。
▶午後29
21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))の目標について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 推進する期間は5年である。
- 9分野の目標が設定されている。
- 最終的な目標の1つに健康格差の縮小がある。
- 妊婦の喫煙率の目標は0%である。
- 1日の食塩摂取量の目標は10g未満である。
▶午後30
予防接種で生ワクチンはどれか。2つ選べ。
- 肺炎球菌
- B型肝炎
- おたふくかぜ
- 麻疹・風疹混合
- Hib〈インフルエンザ菌b型〉
▶午後31
Aさん(43歳、男性)は、23歳で統合失調症と診断された。精神科病院に20年間入院している。現在Aさんは任意入院であり退院を強く希望し、主治医も退院の方向で検討している。両親は亡くなっており、兄弟姉妹はいない。
Aさんが退院し、地域生活へ移行するために必要なのはどれか。2つ選べ。
- 日常生活支援体制の調整
- 親戚の退院への同意
- 地域住民への連絡
- 就労先の確保
- 居住先の確保
▶午後32
疫学研究における因果関係の推論で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 関連の一致性は因果推論を強める。
- 統計学的に有意な関連は因果関係である。
- 関連の整合性は因果推論の十分条件である。
- 関連の特異性は因果推論の必要十分条件である。
- 関連の時間的関係性は因果推論の必要条件である。
▶午後33
生活保護法について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 申請保護を原則とする。
- 世帯単位を原則とする。
- 実施機関は保健所である。
- 保護の種類は4種類である。
- 日本国憲法第11条に基づいている。
▶午後34改題
法令に基づき市町村が策定しなければならない計画はどれか。2つ選べ。
- 環境基本計画
- 障害者計画
- 介護保険事業計画
- 医療費適正化計画
- がん対策推進基本計画
▶午後35
都道府県が医療計画に記載すべき事項はどれか。2つ選べ。
- 医療の安全の確保に関する事項
- 介護サービス情報の公表に関する事項
- 住民の健康増進に係る達成目標に関する事項
- 5疾病5事業に係る医療連携体制に関する事項
- 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
次の文を読み36~38の問いに答えよ。
Aさん(80歳、女性)。1人暮らし。糖尿病で内服の自己管理をしながら自立して生活していた。半年前から認知機能が低下して、食べる回数が増え、内服を忘れることが多くなった。隣町に住む娘が同伴して医療機関を受診したところ、血糖値が上昇しており入院となった。入院中のMini-Mental State Examination〈MMSE〉は22点であった。1か月の入院治療により血糖値は安定し退院が予定された。
▶午後36
娘から退院後の生活について地域包括支援センターの保健師に相談があった。Aさんは自宅での生活の継続を希望しているが、娘は仕事があり日々の介護はできないと言う。
退院後の生活のアセスメントに必要な情報として優先度が高いのはどれか。
- 本人の経済状況
- 本人の家事能力
- 娘の健康状態
- 娘の勤務先
▶午後37
内服は朝1回となり、入院中に看護師が自己管理を指導したが、本人は内服したことを忘れてしまう状況であった。退院後の在宅療養生活に向けて要介護認定を申請し、要支援2と認定され、娘が週末に訪れることになった。
保健師が立案するケアプランのサービス内容として優先度が高いのはどれか。
- 介護予防通所介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防訪問リハビリテーション
▶午後38
保健師は、この事例への支援を契機に、慢性疾患のために健康管理が必要な独居高齢者の実態に即して支援体制を見直す必要があると考え、自治会役員、民生委員、開業医、介護支援専門員など、地域の関係者を集めて会議を行うこととした。
会議において最初に行う保健師の対応で適切なのはどれか。
- 独居高齢者への家庭訪問を依頼する。
- 地域の独居高齢者の個人情報を共有する。
- 慢性疾患の最新の診断法について講義を企画する。
- 健康管理が必要な独居高齢者への関わりの状況を共有する。
次の文を読み39~41の問いに答えよ。
Aさん(20歳、男性)。高校卒業後、就職したが職場の人間関係がうまくいかず退職して自宅にいる状態が1年半続いている。心配した母親(48歳)が保健所に来所した。保健所では精神保健相談を実施しており、管内にあるひきこもりの家族会やセルフヘルプグループを支援している。
▶午後39
最初の面接で、Aさんの様子を尋ねると「普段は家にいて、何もせず、テレビを観るか、インターネットをして過ごしています。午後は図書館に通っています」と話した。
母親への保健師の対応で正しいのはどれか。
- 家庭訪問を約束する。
- 本人の来所を勧めるよう話す。
- 保健所の精神保健相談を勧める。
- ひきこもりの家族会を紹介する。
- 外出しているので問題はないと説明する。
▶午後40
その後、Aさんは母親と精神科を受診したが精神疾患は否定された。Aさんは以前と変わらず夜遅くまでテレビを観るか、インターネットをしていると母親から連絡があった。
現在のAさんに対する援助目標として優先度が高いのはどれか。
- 作業所に通うことができる。
- 午前中に図書館に通うことができる。
- 睡眠導入薬で睡眠のコントロールができる。
- ひきこもりになった原因を自覚することができる。
▶午後41
最初の相談から3か月が経過し、Aさんは保健師に電話で、今後のことについて話すようになってきた。
保健師の対応で優先度が高いのはどれか。
- 相談終了の時期を決める。
- ハローワークで相談することを勧める。
- 精神保健福祉センターの相談を紹介する。
- ひきこもりのセルフヘルプグループを紹介する。
次の文を読み42~44の問いに答えよ。
Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。2か月前から軽い咳があったが放置していた。1週前から咳がひどくなり、倦怠感が出現したため病院を受診し入院した。Aさんは要支援2で週1回訪問介護を利用している。娘は夫と中学生と小学生の子どもの4人家族であり、車で30分の地区に住んでいる。
▶午後42
Aさんは喀痰塗抹菌検査Gaffky〈ガフキー〉5号の肺結核と診断され、主治医から保健所に結核患者発生届が提出された。
保健師の対応で最初に行うことはどれか。
- 入院中の病院に訪問し、Aさんと面接する。
- 娘にAさんと娘の家族の接触状況を聞く。
- 訪問していた訪問介護員の健康状態を確認する。
- 民生委員にAさんの入院前の生活状況を確認する。
▶午後43
娘は週1回Aさん宅を訪ね2時間ほど一緒に過ごしていたが、接触者健康診断では異常はなかった。娘は「子どもたちは咳や熱の症状はありません。半年以上前から父とは会っていません」と言う。
保健師の娘への対応で正しいのはどれか。
- 「お子さんはBCGを接種しましょう」
- 「お子さんは胸部エックス線検査を受けましょう」
- 「お子さんは接触者健康診断の必要はありません」
- 「お子さんはツベルクリン反応検査を受けましょう」
▶午後44
入院中にDOTSカンファレンスが開かれ、Aさんは退院した。
AさんのDOTSの実施について適切なのはどれか。
- 服薬支援者が月に1~2回以上訪問し、服薬確認を行う。
- 服薬支援者が週に1~2回以上訪問し、服薬確認を行う。
- Aさんは毎日病院の外来に通院して服薬する。
- 訪問介護員は服薬支援者になれない。
次の文を読み45~47の問いに答えよ。
保健師は、従業員600人のIT関連会社に勤務している。5月に実施した定期健康診断の問診では、肩こり、腰痛、目の疲れを訴える人が多かった。症状を訴えた従業員の業務内容を確認したところ、VDT作業に従事していることが分かった。保健師は職場巡視をすることにした。
▶午後45
職場巡視における作業環境の観察項目で優先度が高いのはどれか。
- 機器の配線
- 作業室の空調
- 作業台の高さ
- 作業室の清掃状況
▶午後46
職場巡視の結果、VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインが遵守されていないことが分かった。
保健師が行う対応で適切なのはどれか。
- 休憩時間を設定する。
- 衛生委員会で報告する。
- 職場の照明を変えるよう指導する。
- 特定業務従事者の健康診断を実施する。
▶午後47
その後、ガイドラインを踏まえて新たにVDT作業マニュアルが作成された。保健師は、このマニュアルを普及させるために研修会を企画した。
最も効果が期待できる対象はどれか。
- 新入社員
- 会社役員
- 各部署の管理者
- 頸肩腕症候群有症状者
次の文を読み48~50の問いに答えよ。
保育所長から「昨日午後から今朝にかけて、園児100人中35人に嘔吐、下痢症状がある。本日も多くの園児、職員が同様の症状で欠席している」との連絡が入った。保健所は感染症と食中毒の両面から調査を開始した。
▶午後48
初動時に保育所長に指導する内容として適切なのはどれか。
- 調理担当者の隔離
- 全園児の家族の検便検査
- 連絡調整の窓口の一本化
- 医療機関からの情報収集
▶午後49
保健師は調査した結果を分析することにした。
適切なのはどれか。
- 患者が受診した医療機関の場所をプロットする。
- 発症日時ごとの発症者数をプロットする。
- 全園児の家の場所をプロットする。
- 発症群と曝露群とを比較する。
▶午後50
調査分析の結果から、食中毒の可能性は低く、ノロウイルスの施設内感染と推定された。保育所長から「対応について保護者から質問が多く寄せられているので、説明会を開いてほしい」と依頼された。
患児がいる保護者への二次感染拡大防止の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 患児の兄弟姉妹は入浴させない。
- 患児と家族のタオルは共有しない。
- 手洗いは石けんを使って流水でする。
- 患児は解熱後3日を経過するまで登園させない。
- 汚染場所は0.001%次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。
次の文を読み51~53の問いに答えよ。
A市では大腸癌による死亡者数が増加する傾向がみられたため、その要因を分析し、対策を検討することにした。
▶午後51
A市と基準集団である県全体の50歳以上の男性の大腸癌死亡者数と年齢階級別人口を表に示す。

A市のこの年齢層における標準化死亡比〈SMR〉を求めよ。
ただし、基準を1とし、小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答:① . ②③
▶午後52
A市では大腸がん検診の評価のために、B市のデータと比較した。A市とB市の男性の大腸がん検診の実施状況を表に示す。

B市と比較して、A市が高いのはどれか。
- 検診受診率
- 検診陽性者割合
- 検診陽性者が精密検査を受けた割合
- 精密検査での大腸癌発見率
▶午後53
B市のデータを参考に、大腸癌の発見を増やすためにA市の保健師が行う方法で最も有効なのはどれか。
- 検診受診を勧奨する。
- 禁煙指導教室を開催する。
- 検診陽性者に精密検査の受診を勧奨する。
- 検診の敏感度を上げて検診陽性者を増やす。
次の文を読み54、55の問いに答えよ。
人口2万5千人、高齢化率28%のA町。今年度、健康増進計画策定後5年目を迎え、中間評価を行うことになった。保健師が各事業の評価を実施したところ、特定健康診査の受診率と特定保健指導の実施率が目標値を下回った。
▶午後54
特定健康診査の受診率を向上するためにA町の保健師が重点的に働きかける対象者を検討したい。
優先して分析するのはどれか。
- 特定健康診査の年齢別受診率
- 特定健康診査の実施機関別受診者数
- 特定健康診査対象者の通院治療者の医療機関別割合
- 特定保健指導対象者の地区別割合
▶午後55
保健師は、さらに地区ごとに分析を行った。その結果、住民の多くが農業に従事しているB地区の受診率が特に低いことが分かった。
B地区の受診率向上のための支援として最も効果的なのはどれか。
- 特定健康診査の受診を呼びかけるパンフレットを配布する。
- B地区の特定健康診査の受診者を対象とした結果説明会を開催する。
- 地区ごとの特定健康診査の受診状況に関する資料を町の広報誌へ掲載する。
- 生活習慣病予防対策について農業団体と共催で住民が話し合う場を設ける。
資料 厚生労働省「第100回保健師国家試験、第97回助産師国家試験、第103回看護師国家試験及び第103回看護師国家試験(追加試験)の問題および正答について」
平成27年2月20日実施の第101回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。
また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。
分野別解説付き問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ
- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ
を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。
なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
第101回保健師国家試験目次
第101回保健師国家試験・午前(55問)
▶午前1
Aさんは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクⅠで、要支援2である。Aさんは「来月から老人ホームに入ることが決まったと家族に言われた。私は自宅にいたい」と地域包括支援センターの保健師に相談した。
保健師の対応として最も適切なのはどれか。
- 老人ホームの入所を勧める。
- 介護支援専門員に対応を依頼する。
- Aさんと家族が話し合う機会を設ける。
- 施設入所について地域包括支援センターの職員間で検討する。
▶午前2
A市では健康診査の結果、血圧が高い人が増加傾向にあることが分かった。保健師は分析した結果を踏まえて、地域での高血圧予防に取り組むことにした。
この取り組みにおいて最も効果的なのはどれか。
- 医療機関への情報提供
- 結果説明のための個別訪問
- 健康診査の検査項目の見直し
- 地域住民を対象とした学習会の開催
▶午前3改題
環境汚染物質とそれに起因する疾病の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
- 石綿――じん肺
- カドミウム――気管支喘息
- ダイオキシン――中皮腫
- 有機水銀――水俣病
▶午前4
Aさん(26歳、初産婦)。妊娠40週1日に3,100gの女児を出産した。出生通知票が届き、保健師がAさんへ電話連絡したところ、初めての育児に対する不安があるという。
このときのAさんへの対応で優先度が高いのはどれか。
- 妊娠の経過を把握する。
- 医療機関への連絡を行う。
- 育児学級への参加を勧める。
- 育児で困っていることを具体的に聞く。
▶午前5
2歳男児の母親。1歳6か月児健康診査後から継続して、市町村保健センターの発達相談会に来ている。母親は、児とおもちゃの車で遊びながら「ブーブ速いね。かっこいいね」と言葉をかけている。児も楽しそうに「ブーブ、ブーブ、いいね」と言いながら遊んでいる。母親から「子どもの言葉が少ないのは私の対応が悪いのでしょうか」と相談があった。
母親への声かけで最も適切なのはどれか。
- 「上手に言葉かけができていますよ」
- 「毎日外でたくさん遊ばせましょう」
- 「毎日絵本を読んであげてくださいね」
- 「時間がたてば話せるようになりますよ」
▶午前6
健康診査と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。
- 妊産婦健康診査――母体保護法
- 3歳児健康診査――母子保健法
- 就学時健康診断――児童福祉法
- 特定健康診査――健康増進法
▶午前7
特定健康診査後の結果説明会について適切なのはどれか。
- 医療機関に通院している者は対象としない。
- 参加者の個人の特定健康診査結果を公表する。
- 検査結果と身体の機能との関係について説明する。
- 異常値があっても自覚症状がなければ心配ないと説明する。
▶午前8
地域診断に用いる手法とその説明の組合せで正しいのはどれか。
- エスノグラフィ――学習理論を基盤とする。
- プリシード・プロシードモデル――社会診断から開始する。
- プロジェクト・サイクルマネジメント――参与観察から開始する。
- コミュニティ・アズ・パートナーモデル――疫学診断から開始する。
▶午前9
地域ケアシステムの構築における最終目的で最も適切なのはどれか。
- 連携会議が活性化する。
- 行政サービスが効率化する。
- 地域の健康水準が向上する。
- 保健医療に従事する者の資質が向上する。
▶午前10
母子保健施策のうち最も新しいのはどれか。
- 母子健康手帳の交付
- マタニティマークの配布
- 妊婦健康診査の公費負担
- 新生児マススクリーニング検査におけるタンデムマス法の導入
▶午前11
精神保健対策の変遷で最も新しいのはどれか。
- 市町村の役割が明示された。
- 医療保護入院のための移送が規定された。
- 精神障害者保健福祉手帳制度が創設された。
- 保健所が精神保健行政を担うこととされた。
▶午前12
難病対策で正しいのはどれか。
- スモンの研究体制の整備から始まった。
- 難病対策要綱は昭和36年に定められた。
- 一律の自己負担限度額が設定されている。
- 各都道府県に難病情報センターが設置されている。
▶午前13
人口2万人の市。市では健康増進計画の評価のため、定期的に市民の生活実態調査を行っている。今年度の調査で、中学生では睡眠時間が5時間以下である層が最も多いことが明らかになった。また、市内の養護教諭との連絡会で授業中に居眠りをする生徒が増えたと報告を受けた。
睡眠不足を改善するために協力を得る対象で優先度が高いのはどれか。
- 保健所
- 自治会
- 教育委員会
- 地区公民館の協議会
▶午前14
Aさん(58歳、男性)。56歳の妻と2人暮らし。脊髄小脳変性症の症状が進行し、2週前から地域の専門医療機関に入院しているが、Aさんは在宅療養を強く希望している。妻は難病の医療費助成の申請のために保健所に来所し「これから症状がさらに進行することを考えると、通院も難しくなると思います。自宅で面倒をみることができるか心配です」と在宅療養への不安を訴えた。
保健師の対応として最も適切なのはどれか。
- 難病の医療費助成と介護保険とは併用できないと伝える。
- 通院ができない場合の在宅療養は困難であることを伝える。
- 在宅療養の決定の際は、Aさんの意思より家族の意思を尊重する。
- 病状の進行に合わせた保健医療福祉サービスが利用できることを説明する。
▶午前15
養護教諭が主体となって行う職務はどれか。
- 学校給食の衛生管理
- 学校生活管理指導表の記入
- 感染症に罹患した者の出席停止
- 健康上の問題がある児童の保護者への助言
▶午前16
衛生管理者について正しいのはどれか。
- 労働基準法に規定されている。
- 都道府県知事が認定する資格である。
- 総括安全衛生管理者は事業場の経営者が兼ねる。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任する。
▶午前17
地域における健康危機の事例で、厚生労働省による健康危機管理指針の策定のきっかけとなったのはどれか。
- 東海村臨界事故
- 阪神・淡路大震災
- 新潟県中越沖地震
- 新型インフルエンザ(A/H1N1)の発生
▶午前18
医療機関から男性(56歳)のレジオネラ症による肺炎が確認されたと保健所に連絡があった。男性は妻と息子の3人暮らしであり、自宅の風呂のほか、公衆浴場を週に1回利用している。
初動対応として最初に情報収集する者で正しいのはどれか。
- 近隣住民
- 環境衛生監視員
- 同居している家族
- 浴場組合の組合員
▶午前19
大規模な地震が発生した1週後。被害が大きかったA市の被災者は、一時避難先として被害が少なかった近隣のB市の市営住宅に入居した。
現時点のA市の被災者への支援で最も適切なのはどれか。
- 巡回訪問し健康相談を行う。
- 心のケアは高齢者を優先する。
- 被災地域の再建に向けた方針の検討を行う。
- 独居の高齢者にはB市の施設への入所を勧める。
▶午前20
人口4万人の市。市の保健センターでは、子育てに関する相談が5年間で10倍に増加した。子育て支援のニーズを把握するための調査として、乳幼児健康診査の受診者を対象に無記名式の調査を実施した。
この活動における公衆衛生看護管理で正しいのはどれか。
- 健康危機管理
- 情報管理
- 予算管理
- 人材管理
▶午前21
管理的立場にあるA保健師に、係内の中堅保健師から新人保健師の指導がうまくいかないと相談があった。
中堅保健師の育成も考慮した上で、A保健師が行う対応で最も適切なのはどれか。
- 新人保健師の指導は自分が直接行う。
- 新人保健師の指導者を別の保健師に代える。
- 新人保健師の指導を中堅保健師とともに行う。
- 新人保健師と中堅保健師を違う部署に配置する。
▶午前22
疾患と危険因子の組合せで正しいのはどれか。
- 喉頭癌――喫煙
- 甲状腺癌――紫外線
- 肝癌――A型肝炎
- 大腸癌――ピロリ菌
▶午前23
疫学研究を行う上で最も重要なのはどれか。
- 研究の科学的価値
- 参加者の人権の尊重
- 地域の生活水準の向上
- 参加者への利益の還元
▶午前24
統計分析について正しいのはどれか。
- 割合に関する検定にはt検定を用いる。
- 点推計値での偶然性の判定はできない。
- 多変量解析は情報バイアスを補正する。
- 帰無仮説を採択して統計学的有意性を確定する。
▶午前25
発達障害者支援法について正しいのはどれか。
- 学習障害は対象に含まれる。
- 発達障害者に療育手帳を交付する。
- 支援の対象は18歳未満の障害者と定めている。
- 市町村長は発達障害者支援センターを設置しなければならない。
▶午前26
市町村の介護保険事業計画について最も適切なのはどれか。
- 単年度の計画である。
- 計画案を公開し意見を募る。
- 計画策定を介護保険事業所に委託する。
- 学識経験者で構成される委員会で策定する。
▶午前27
ヘルスプロモーションの理念におけるエンパワメントに該当するのはどれか。
- 環境整備
- 住民の自主的な行動
- 多分野間の協調と統合
- 個人衛生に関する教育
- ヘルスサービスの方向転換
▶午前28
新興住宅地を担当している保健師は、地域の介護者が孤立して介護をしている状況を把握し、介護者の仲間づくりを目的として介護者の交流会を事業化した。
保健師が行った活動の中でPDCAサイクルの「C」に該当するのはどれか。
- 交流会の評価方法を決めた。
- 交流会で話し合いのファシリテーターを担当した。
- 地区での交流会の必要性を担当者間で話し合った。
- アンケートにより交流会の参加者の満足度を集計した。
- 参加者の要望をもとに介護者の健康管理についてのプログラムを導入した。
▶午前29
保健所にエイズに関する電話相談があった。
最初に確認することはどれか。
- 氏名
- 年齢
- 相談目的
- エイズに関する知識
- これまでに受けた検査
▶午前30
保健師が行う地区活動の考え方で最も適切なのはどれか。
- 評価項目の決定は行政主導で行う。
- 住民から相談があった順に取り組む。
- 地域に根差した活動の継続を目標とする。
- 住民の主観的評価の結果を主に用いて計画する。
- 地区活動の目標量は前年度の目標量と一致させる。
▶午前31
A市の健康増進計画を策定する際の住民意識調査で、喫煙者のうち、たばこをやめたい人は男女ともに6割以上いることが分かった。
この時点で当てはまるプリシード・プロシードモデルの要因はどれか。
- 環境要因
- 強化要因
- 行動要因
- 実現要因
- 準備要因
▶午前32
個人情報保護について正しいのはどれか。
- 疫学研究で遺伝子を扱うことは禁止されている。
- がん登録への情報提供には患者本人の同意は必要ない。
- 新規で保健事業を行う際は倫理審査を受ける必要がある。
- 無記名式のアンケート調査には文書による同意が必要である。
- 緊急時であっても個人情報を第三者に提供する際には本人の同意が必要である。
▶午前33
平成24年(2012年)の地域保健対策の推進に関する基本的な指針の改正で新たに加えられたのはどれか。
- 国民の健康づくりの推進
- ノーマライゼーションの推進
- 児童虐待防止対策に関する取組
- 次世代育成支援対策の総合的かつ計画的な推進
- ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進
▶午前34
医療保険でないのはどれか。
- 介護保険
- 国民健康保険
- 組合管掌健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 全国健康保険協会管掌健康保険
▶午前35
平成23年(2011年)の介護保険法改正によって創設されたのはどれか。2つ選べ。
- 予防給付
- 複合型サービス
- 居宅療養管理指導
- 地域包括支援センター
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶午前36
町立小学校で身体的虐待が疑われる外傷のある児童を発見した。
児童虐待の防止等に関する法律に基づき通告する機関として正しいのはどれか。2つ選べ。
- 警察署
- 保健所
- 教育委員会
- 児童相談所
- 福祉事務所
▶午前37
保健所における健康危機管理に関する業務で法令に定められているのはどれか。2つ選べ。
- 食中毒発生時の調査
- 狂犬病発生緊急連絡網の整備
- 感染症発生における医師からの届出の受理
- 保育所で乳児が突然死した時の届出の受理
- 虐待による介護老人福祉施設の指定の取消し
▶午前38
介入研究で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 仮説設定のために用いられる。
- 無作為化(割付)を前提としている。
- 介入と結果との時間的関係が明確である。
- 複数の曝露要因の影響を検討することはできない。
- 観察研究より高いレベルのエビデンスを提供する。
▶午前39改題
令和4年(2022年)の厚生労働省による食中毒統計調査について正しいのはどれか。
- 患者数は年間100万人以上である。
- 死亡者数は年間1,000人以上である。
- ノロウイルスによる患者が最も多い。
- 原因食品で最も多いのは肉類およびその加工品である。
▶午前40
世界保健機関〈WHO〉の活動内容で正しいのはどれか。2つ選べ。
- リプロダクティブ・ヘルスの推進
- 飢餓地域への食糧の配布
- 疾病の国際分類の設定
- 児童の就学支援
- 雇用対策
次の文を読み41〜43の問いに答えよ。
Aさん(46歳、女性)。48歳の会社員の夫、高校生の長男および中学生の次男との4人暮らし。筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉と診断され、難病の医療費助成の申請のため夫が夜勤の前に保健所に来所した。夫によると、Aさんは包丁を使うことが難しくなり、子どもたちの弁当を作るのに時間がかかるようになったことを気にしているという。1週後、保健師がAさん宅を訪問し状況を確認したところ、Aさんは「主婦としての役割が果たせなくなることがつらい」と話した。
▶午前41
訪問時に保健師が提案することで最も適切なのはどれか。
- 夫に家事を任せる。
- 料理することをあきらめる。
- 訪問介護員が家事を担当する。
- 家族で家事の役割分担をする。
▶午前42
Aさんは病状が進行し、1人で身の回りのことを行うことが難しくなり、家族が不在である平日の日中に訪問介護を利用することになった。担当する訪問介護員から「最近、Aさんはつまずいたり転んだりすることが多くなりました。この病気の患者さんを担当するのは初めてなので関わり方が分かりません」と相談を受けた。
保健師の対応で優先されるのはどれか。
- 訪問介護員の訪問に同行する。
- 経験の豊富な訪問介護員と交代するよう調整する。
- Aさんとの対応で注意することを主治医に確認するよう助言する。
- 訪問介護員に難病患者の支援に関する研修を受講するよう勧める。
▶午前43
3年後。Aさんは呼吸が困難になり、本人の希望による人工呼吸器装着のため1か月入院した。退院後は発語による意志疎通ができない状態になった。退院後3日に訪問すると、Aさんは保健師を見て涙を流した。子どもたちはAさんとの接触を避けている様子がみられた。
このときの家族への対応で優先度が高いのはどれか。
- 子どもたちから母親に対する思いを聴く。
- 家族でカウンセリングを受けるよう勧める。
- 子どもたちに1日1回Aさんに話しかけるよう指導する。
- 子どもたちがAさんを避けないよう話すことを夫に提案する。
次の文を読み44〜46の問いに答えよ。
A君(2歳)の母親。「初めての子どもで、対応が分かりません。食事が終わるまでに1時間もかかったりしてイライラします。他の子どもより落ち着きがないような気がします。この前の健康診査では問題ないと言われましたが不安です」と電話相談があった。保健師は話を聞いた上で、保健センターの育児相談に来るよう促した。
▶午前44
電話相談の翌日、母親はA君とともに育児相談に来所した。A君はすぐに育児相談室の本棚に行き、絵本を開いたり閉じたりしている。
最初の対応で最も適切なのはどれか。
- 発達相談を勧める。
- 子どもの発達を評価する。
- しつけに関する親子教室を紹介する。
- 母親の話から不安の内容を確認する。
▶午前45
保健師は母親に食事のときの様子を質問した。「息子は食卓について自分で食べます。おやつは好んで食べますが、食事は遊びながら食べて時間がかかることがあり困っています」と母親は話した。
このときの母親への助言で最も適切なのはどれか。
- 「食事の量を少なくしましょう」
- 「おやつをあげるのはやめましょう」
- 「時間を決めて食事を終えましょう」
- 「お母さんが食べさせてあげましょう」
▶午前46
最近、A君と同じ年代の児の食事に関する相談が増えている。保健師は幼児期における食育について講習会を企画することにした。
講習会の指導内容で最も適切なのはどれか。
- 嫌いなものは与えないようにする。
- 楽しい雰囲気で食べることができるよう工夫する。
- 昼寝が食事時間にかかるときは起こして食事させる。
- 栄養のバランスよりも必要エネルギー量を重視する。
次の文を読み47〜49の問いに答えよ。
Aさん(36歳、男性)。1人暮らし。従業員数300人のIT関連会社に勤務している。残業時間は月平均60時間で、3年前から15本/日の喫煙をしている。運動習慣はなく、昼と夜は外食が多い。会社の定期健康診断で中性脂肪が150mg/dLであった。既往歴に特記すべきことはない。
▶午前47
Aさんが勤める会社の保健師が行う指導で適切なのはどれか。
- 休暇の取得
- 医療機関の受診
- 生活習慣の見直し
- リラクセーションの実施
▶午前48
保健師がこの職場の喫煙状況について調査をしたところ、喫煙者は48%で、喫煙者のうち30%が禁煙を希望している。禁煙を希望する者のうち、保健師との面接において禁煙する気持ちはあるがうまくいかないと訴える者が多かった。
禁煙を希望する者に対する支援として最も適切なのはどれか。
- 喀痰検査を実施する。
- 肺がん検診の受診を勧める。
- たばこの代わりにお菓子を勧める。
- 禁煙のためのグループワークを実施する。
- 喫煙の健康被害についてのパンフレットを配布する。
▶午前49
衛生委員会に「喫煙室からたばこの煙が流れてくる」、「敷地内で歩きたばこをする人がいる」という投書があり、衛生委員会で職場全体の喫煙対策を検討することになった。
最初に行うことで最も適切なのはどれか。
- 喫煙室が設置されている環境について確認する。
- 敷地内に監視カメラを設置する。
- 喫煙者に携帯灰皿を配布する。
- 喫煙室を廃止する。
次の文を読み50〜52の問いに答えよ。
人口約35万人の中核市。午前10時、震度6強の地震が発生し、市は避難所の設置を決めた。家屋の損壊が確認され、多数の死傷者がいると予測された。県と市には災害対策本部が設置された。
▶午前50
健康の危機管理体制の中心となる管理責任者として最も適しているのはどれか。
- 市長
- 県知事
- 市の医師会長
- 市の保健所長
▶午前51
発災当日の市の保健師の対応で優先度が高いのはどれか。
- 健康調査票の作成
- 要援護者の安否の確認
- 家庭訪問による個別健康相談
- 住民一人一人の不安の受け止め
▶午前52
発災後2週。保健師は、避難所への巡回訪問中に5歳児の母親から「子どもが自分から全く離れようとしない。寝ている間に急に大声をあげて泣き出すようになり心配だ」と相談を受けた。
保健師の対応で適切なのはどれか。
- 子どもの心のケアに関する相談窓口を紹介する。
- 避難所の他の子どもと接触しないように伝える。
- 別の避難所に移動するように勧める。
- 様子をみるように伝える。
次の文を読み53〜55の問いに答えよ。
人口8万人、高齢化率30%のA市。最近、徘徊している高齢者を保護した事例が数件あったと警察から地域包括支援センターに情報提供があった。地域包括支援センターの保健師は、徘徊している高齢者について情報収集する必要があると考えた。
▶午前53
情報収集先として最も適切なのはどれか。
- 消防署
- 民生委員
- 保健センター
- 介護支援専門員
▶午前54
情報収集の結果、認知症高齢者の地域での見守りネットワークを構築することにした。自治会長に協力を求めたところ、自治会主催の自治会員向け行事として取り組むことになった。
取り組みの内容として優先度が高いのはどれか。
- 認知症高齢者と交流する。
- 認知症に関する専門医療機関を見学する。
- 高齢者の徘徊に関する新聞報道を分析する。
- 認知症高齢者への対応のロールプレイを行う。
▶午前55
保健師は地域に認知症高齢者の居場所を作りたいと考え、公民館を会場にした事業に取り組むことにした。
事業を実施する上で最も適切なのはどれか。
- 認知症高齢者と地域の住民が参加できるプログラムを設定する。
- 認知症高齢者と同居している家族の休息を促す。
- 活動内容は認知症の専門医が決める。
- 開催頻度は年4回とする。
第101回保健師国家試験・午後(55問)
▶午後1改題
令和2年(2020年)の衛生行政報告例における保健師の就業場所の構成割合で、市町村、保健所の次に多いのはどれか。
- 病院
- 事業所
- 社会福祉施設
- 訪問看護ステーション
▶午後2改題
日本の令和4年(2022年)の人口について正しいのはどれか。
- 総人口は前年より増加している。
- 出生数は70万人を超えている。
- 年少人口の割合は10%以下である。
- 世界で人口の多い国上位5位以内である。
▶午後3
Aさん(40歳、男性、会社員)。Aさんは特定健康診査で、腹囲84cm、BMI26、血圧140/85mmHgであり、動機付け支援の対象となった。「仕事でストレスが溜まり、夜食を食べずにはいられない。夜食がお腹に残り朝食は食べられない。残業が多く、今の生活は変えられない」と言う。
Aさんへの保健指導で最も適切なのはどれか。
- 「夜食はやめましょう」
- 「残業はやめましょう」
- 「医療機関を受診しましょう」
- 「食習慣は健康に影響します」
▶午後4
家庭訪問の対象で優先度が高いのはどれか。
- 3歳児健康診査でオムツを使用している児
- 妊婦教室で育児の不安を訴えた妊婦
- 育児相談に来ない10か月児の母親
- 3か月児健康診査未受診の母児
▶午後5
ケアマネジメントにおける権利擁護〈アドボカシー〉について正しいのはどれか。
- 利用者を支えるネットワークを発展させる。
- 利用者の満足度と変化を継続的に評価する。
- 利用者が公正にサービスを利用できるようにする。
- 利用者のニーズに即した社会資源を開発して組織化する。
▶午後6
障害者の社会参加や貢献が可能な共生社会の実現を目指すことを目的に、地域の住民を含めた懇談会を継続的に行うことにした。
懇談会の運営について最も適切なのはどれか。
- 障害者に関する講義を中心にする。
- 参加者の自己紹介は最小限にする。
- 障害の種類と程度に分けて参加者を募る。
- 障害者を受け入れている企業の見学を計画する。
▶午後7
児童虐待発生予防のためのハイリスクアプローチはどれか。
- 母子健康手帳の交付
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 10歳代の妊婦への訪問
- 乳幼児健康診査時の健康教育
▶午後8
人口15万人、高齢化率25%の市。独居高齢者に関する相談が増加している。保健師は、市の独居高齢者の生活状況および健康状態を把握するための実態調査を企画した。
調査の手法で最も適切なのはどれか。
- 要介護認定結果を用いた後向き調査
- 特定健康診査受診者の標本調査
- 地区住民への電話調査
- 個別の訪問調査
▶午後9
人口3万人の市。近年、糖尿病腎症による透析導入患者数が増加している。市は国民健康保険被保険者の糖尿病の重症化を予防することについて、関係団体と連携し5年間の健康づくり計画を策定することにした。
この計画におけるアウトカム指標で適切なのはどれか。
- 計画を普及するための保健師の出張回数
- 糖尿病の治療継続者の割合
- 糖尿病予防教室の参加者数
- 特定健康診査の予算額
▶午後10
保健師は新興住宅地を担当している。この地区では近隣に友人がなく、育児の不安を抱えている母親が多くいることがわかった。
この地区における子育て支援としての保健師の活動で最も適切なのはどれか。
- 育児の広報誌を作成して配布する。
- 要保護児童対策地域協議会を開催する。
- 子育て中の母親のための交流会を開催する。
- 乳幼児健康診査の結果を母子保健推進員に提供する仕組みを構築する。
▶午後11
成人を対象とした歯科保健活動において最も優先されるのはどれか。
- フッ化物塗布の推奨
- 口腔機能の訓練の指導
- 栄養状態の改善のための指導
- 歯間部清掃用器具の使用の推奨
▶午後12
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、診断した医師が直ちに届け出なければならないのはどれか。
- 結核
- 梅毒
- アメーバ赤痢
- 流行性角結膜炎
▶午後13改題
日本の令和4年(2022年)の労働災害について正しいのはどれか。
- 労災補償状況の請求件数は精神障害に比べ、脳・心臓疾患が多い。
- 災害性腰痛が業務上疾病発生状況の半数以上を占める。
- 新型コロナウイルス感染症り患による労働災害を除き休業4日以上の死傷者数は約13万人である。
- 死傷者数は昭和36年から増加傾向である。
▶午後14
産業保健における作業管理に該当するのはどれか。
- 定期的に健康診断を行う。
- 労働時間内に休憩時間をとる。
- 作業環境の有害要因を除去する。
- 労働衛生に関する体制を構築する。
▶午後15
幼稚園の園長から感染性胃腸炎が疑われる園児15人が欠席したと保健所に連絡があった。
この時点で最初に行う保健師の対応で優先度が高いのはどれか。
- 保護者向けの説明会を実施する。
- 感染予防のリーフレットを配布する。
- 園児の健康状態を保護者から聴取する。
- 幼稚園の床を次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。
▶午後16
都道府県の保健所の地域ケアの質を保証するのはどれか。
- 医療計画の策定
- 広域災害への対応
- 健康情報の収集分析
- 介護保険施設の指導監督
▶午後17
過去5年間にA工場(従業員数1,000人)で15人、B工場(従業員数850人)で9人の肝癌患者が発生していたことがわかった。両工場では機械の洗浄に薬品Cを使用している。
薬品Cと肝癌の疫学的関係で最も適切なのはどれか。
- 薬品Cは肝癌の原因である。
- 薬品Cと肝癌には関連がある。
- 薬品Cと肝癌には因果関係はない。
- 薬品Cと肝癌との関係は不明である。
▶午後18
ウイルス性肝炎対策で正しいのはどれか。
- A型肝炎ワクチンは定期予防接種である。
- B型肝炎の感染予防にはN95マスクを使用する。
- インターフェロン療法に対する医療費助成がある。
- 医療機関は特定感染症予防指針を策定しなければならない。
▶午後19
差をとって寄与危険を計算できる指標はどれか。
- 罹患率
- 有病率
- オッズ比
- 致命率〈致死率〉
▶午後20
スクリーニングについて正しいのはどれか。
- 確定診断を目的とする検査である。
- 敏感度100%の検査で陽性結果であれば疾患がある。
- 陽性反応的中度は有病率の影響を受けにくい指標である。
- 同一検査で敏感度と特異度の両方を改善することはできない。
▶午後21
分布の指標について正しいのはどれか。
- ヒストグラムで最も頻度が高い値は中央値である。
- 広く散らばった分布は標準偏差が小さい。
- 対象数が増えると標準偏差は大きくなる。
- 平均値は外れ値の影響を受けやすい。
▶午後22
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービスについて正しいのはどれか。
- 申請窓口は都道府県である。
- 発達障害者は対象である。
- 利用者負担は定額である。
- 措置制度である。
▶午後23
30歳の女性。全身性エリテマトーデス〈SLE〉と診断され難病の医療費助成の申請のため保健所に来所し「日常生活で特に気を付けることはありますか」と相談した。
保健指導で適切なのはどれか。
- 「直射日光を避けてください」
- 「転倒に気を付けてください」
- 「痰を出す練習をしてください」
- 「筋力強化の運動をしてください」
- 「食物繊維の多い食事を避けてください」
▶午後24
介護予防事業における二次予防対象者を抽出するための基本チェックリストの中で、うつ予防と支援のスクリーニングの項目として正しいのはどれか。
- 友人の家を訪ねている。
- 転倒に対する不安が大きい。
- 週に1回以上は外出している。
- 家族や友人の相談にのっている。
- ここ2週間わけもなく疲れたような感じがする。
▶午後25
食に関する実践的な指導を行う者として学校給食法に規定されているのはどれか。
- 栄養教諭
- 養護教諭
- 保健主事
- 学校歯科医
- 食生活改善推進員
▶午後26改題
日本の主要死因別にみた粗死亡率(人口10万対)の年次推移を図に示す。

CとDの組合せで正しいのはどれか。
C――D
- 自殺――心疾患
- 肺炎――不慮の事故
- 心疾患――脳血管疾患
- 不慮の事故――自殺
- 脳血管疾患――肺炎
▶午後27
地域保健法で規定されている市町村保健センターの役割で正しいのはどれか。
- 健康診査
- 結核の予防
- 衛生上の検査
- 人口動態統計調査
- 医療従事者届の受付
▶午後28
医療安全対策で最も重要なのはどれか。
- 患者による監視
- 医療者による相互監視
- 医療者個人への意識付け
- 組織として取り組む体制
- 医療機器の機械的な故障の防止
▶午後29
保健所に勤務する保健師に対して守秘義務を規定している法律はどれか。2つ選べ。
- 刑法
- 医療法
- 地域保健法
- 地方公務員法
- 保健師助産師看護師法
▶午後30
市では3、4か月児を対象とした健康診査を毎月1回行っている。
継続的な対応が必要な児の状況はどれか。2つ選べ。
- 抱くと体をそらす。
- うつぶせで頭を上げる。
- 名前を呼ぶと声のする方向を向く。
- 「アーアー」、「ウーウー」と声を出す。
- 出生時からの1日当たりの体重増加量が12gである。
▶午後31
障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律への改正時に、変更された内容はどれか。2つ選べ。
- 難病は支援の対象から除外された。
- 障害程度区分を障害支援区分とした。
- 支援の対象者に精神障害者を追加した。
- 利用者の負担額は利用した障害福祉サービスの額の3割とした。
- 地域生活支援事業として障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業を追加した。
▶午後32
エボラ出血熱について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 空気感染する。
- 一類感染症である。
- 定点把握対象疾患である。
- 致命率〈致死率〉は10%である。
- 患者は感染症指定医療機関に移送される。
▶午後33
国際生活機能分類〈ICF〉で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 健康と障害を生活機能の枠組みの中で捉えたものである。
- 世界保健機関〈WHO〉の国際統計分類の1つである。
- 国際疾病分類〈ICD〉を含む上位概念である。
- 分類が目的であり評価は行わない。
- 子どもの障害は対象としない。
▶午後34
市町村が策定しなければならない計画はどれか。2つ選べ。
- 障害者計画
- 医療費適正化計画
- 予防接種基本計画
- 特定健康診査等実施計画
- 感染症の予防のための施策の実施に関する計画
▶午後35
自殺対策基本法について適切なのはどれか。2つ選べ。
- 事業主に長時間労働の禁止を規定している。
- 自殺総合対策大綱で自殺対策の指針が策定された。
- 自殺者の親族に対する適切な支援が目的に含まれる。
- 保健所を自殺予防総合対策センターに位置付けている。
- 自殺予防総合相談窓口の設置を市町村に義務付けている。
次の文を読み36〜38の問いに答えよ。
市内の幼稚園に通う5歳の男児の母親から「幼稚園で子どもがたびたびかんしゃくを起こし、集団生活になじめていないようです。幼稚園の先生から保健師に相談してみてはどうかといわれました」と保健センターに電話相談があった。
▶午後36
このときの対応で最も適切なのはどれか。
- 男児の家庭での様子を聞く。
- 幼稚園を休ませるよう勧める。
- 男児に障害がある可能性を伝える。
- 発達障害者支援センターを紹介する。
▶午後37
男児は、近所の小児科を受診した際に広汎性発達障害の可能性があるといわれた。小児科医は、母親が育児に関する不安を訴えたため、身近な相談先として保健センターの発達相談を勧めた。その後、母親は発達相談のため来所し「最近、息子が言うことを聞かず、よくパニックを起こして手がつけられません。どうしたらよいでしょうか」と訴えた。
このときの対応で最も適切なのはどれか。
- 幼児が使う言葉で話すように伝える。
- 男児が嫌がることは避けるよう提案する。
- どのようなきっかけでパニックを起こすのか確認する。
- パニックを起こしたときは大きな声で話すように伝える。
▶午後38
保健師は母親の了解を得て、幼稚園と定期的に情報交換を行うことにした。1か月後、園長から「最近、男児の元気がない。母親も育児に疲れているようで表情が乏しい」と保健センターに電話相談があった。
このときの園長への対応で優先度が高いのはどれか。
- もう少し様子をみるよう伝える。
- 小児科を受診させるよう依頼する。
- 母親と一緒に保健センターへ来所するよう勧める。
- 男児の対応について保護者会で話し合うよう勧める。
次の文を読み39〜41の問いに答えよ。
Aさん(52歳、女性)。夫と市内の大学に通う息子(19歳)との3人暮らし。「息子の大学のサークルでは飲み会が頻繁にあるようで、先日は息子の友人が集団で酔いつぶれたようです。うちの息子も先輩からお酒を勧められているようで、断るのが大変だと言っています。先日も他の大学で急性アルコール中毒で救急搬送されたと報道もあって心配です。どうしたらよいでしょうか」と市の保健師に電話相談があった。
▶午後39
最初の対応で最も適切なのはどれか。
- 警察に通報するよう勧める。
- 大学に相談するよう伝える。
- アルコール依存症専門の病院を紹介する。
- 息子にサークルを辞めさせるよう勧める。
▶午後40
保健師は管轄地域での未成年の飲酒が問題化しているのではないかと考えた。保健師は地域の状況を把握するため、関係者を集めて会議を開催することにした。
会議のメンバーで適切なのはどれか。2つ選べ。
- 警察官
- 保護司
- 大学関係者
- 訪問看護師
- 食品衛生協会の会員
▶午後41
保健師は管轄地域で未成年の飲酒防止の啓発活動を行うことにした。
啓発活動として最も効果的なのはどれか。
- 大学祭でイベントを企画する。
- 市役所にポスターを掲示する。
- 保健センターで相談会を開催する。
- 警備員に大学内の巡回を依頼する。
次の文を読み42〜44の問いに答えよ。
Aさん(85歳、女性)。1人暮らし。要介護1の認定を受け、通所介護を利用している。Aさんは2か月前から持続する咳に加え、倦怠感が出現したため内科を受診し結核と診断され入院した。その5日後、同じ通所介護事業所の利用者で、Aさんと仲良しでよくおしゃべりをしていたBさん(79歳)も結核と診断され入院した。
▶午後42
接触者健康診断を実施する機関で適切なのはどれか。
- Aさんの居住地域にある検疫所
- Aさんの住所地を管轄する保健所
- Aさんを担当する地域包括支援センター
- AさんとBさんとが利用している通所介護事業所
▶午後43
数日後、AさんとBさんが通う通所介護事業所の利用者の家族から「うちのおばあちゃんも感染していないでしょうか。今後も事業所に通い続けていいのか心配です」と保健所に電話相談があった。
このときの対応で最も適切なのはどれか。
- 結核の予防接種を受けるよう勧める。
- 通所介護事業所の利用をやめるよう伝える。
- 今回の感染源がAさんであることを説明する。
- 通所介護事業所で行う説明会に出席するよう勧める。
▶午後44
2か月後。Aさんは検査の結果、外来治療が可能となり自宅に戻ることになった。退院に向けてDOTSカンファレンスを行うことになった。
DOTSカンファレンスの参加者として最も適切なのはどれか。
- 自治会長
- 民生委員
- 介護支援専門員
- 老人クラブ会長
次の文を読み45、46の問いに答えよ。
人口8万人、高齢化率30%のA市。地域包括支援センターは市内に3か所ある。A市では65歳以上の高齢者を対象に生活機能評価について郵送による調査を毎年実施している。
▶午後45
A市の地域包括支援センターの保健師は、調査票の回収率を高めて介護予防が必要な高齢者の把握を確実に行いたいと考えている。
調査票の回収率が低いB地区で、回収率を高めるために協力を求める対象として適切なのはどれか。
- 自治会
- シルバー人材センター
- 指定居宅介護支援事業所
- 指定居宅サービス事業所
▶午後46
A市の介護予防における二次予防の対象者を早期に把握するために、市内で協力を依頼する対象として最も適切なのはどれか。
- 診療所
- 農業協同組合
- 通所介護事業所
- 訪問看護ステーション
次の文を読み47〜49の問いに答えよ。
職員数が500人である企業の保健師2人は本社に配置され、週に4日、1日4回のメンタルヘルス相談を本社の健康管理室で実施している。この企業には県内に20か所の営業所があり、どの営業所でも時間外業務が多い。A営業所の職員数は40人で、この6か月で2人が仕事によるストレスに起因するうつ病と診断され、1人が休職した。
▶午後47
保健師がA営業所で行う対応で優先度が高いのはどれか。
- 休養室の整備
- 健康教室の開催
- メンタルヘルス相談の周知
- 職場でのストレスチェックの実施
▶午後48
昨年のメンタルヘルス相談は月平均20件であり、その9割が本社の職員であった。
メンタルヘルス相談の利用者を増やすための方法として最も効果的なのはどれか。
- 相談枠を増やす。
- 営業所でも実施する。
- 上司により対象者を選定する。
- 電子メールで定期的にメンタルヘルス情報を発信する。
▶午後49
保健師の活動によって1年間のメンタルヘルス相談の件数は延べ400件となった。相談内容は職場内の人間関係のトラブルによるものや時間外業務による疲労やストレスが過半数を占めた。保健師は、各営業所でのメンタルヘルスについて新たに取り組むことが必要と考えた。
最も効果的なのはどれか。
- 人間関係のトラブルを解消するため各営業所を訪問する。
- アサーショントレーニングに関する講演会を開催する。
- 営業所長に各相談者の悩みに関する情報提供を行う。
- 時間外業務の多い職員の転属を営業所長に提案する。
次の文を読み50〜52の問いに答えよ。
保健所で肥満防止を目的とした教室の参加者を対象に、運動と体重変化の関連を調べることにした。対象者は軽度肥満の40歳代の女性300人であり、本人の希望で軽い体操をする群100人(体操群)と中等度の運動をする群200人(運動群)とに分かれ、同じ保健師による集団指導を受けた。教室開始時に体重測定を行い半年後にどれだけ体重が変化したかを調べた。
▶午後50
この調査の研究デザインはどれか。2つ選べ。
- 横断研究
- 介入研究
- 前向き研究
- 症例対照研究
- 生態学的研究
▶午後51
半年間で体重が3.0kg以上減少した参加者を減量ありと判定した。体操群で減量ありは10人、なしは90人、運動群での減量ありは50人、なしは150人であった。脱落者はいなかった。
運動群の減量効果についてのオッズ比を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:① . ②
▶午後52
この調査は体操群と運動群とを本人の希望によって分けている。
くじで割付ける場合と比べて、仮説検証の妥当性からみたこの調査の問題点で最も大きいのはどれか。
- 二重盲検ができない。
- 相対危険が計算できない。
- 2群の人数を等しくできない。
- 2群の属性の分布が制御できない。
次の文を読み53〜55の問いに答えよ。
人口7万人、高齢化率20%の市。市が行った調査によると、40〜60歳のBMI25以上の者の割合が、男女ともに国民健康栄養調査の全国平均よりも高かった。また6割の者が運動不足を感じており、運動習慣のある者の割合は全国平均よりも低かった。
成人の肥満対策を検討するために、重点地区を定めることにした。
▶午後53
重点地区を選定するための情報で優先度が高いのはどれか。
- BMI25以上の成人の地区別割合
- 運動習慣のある者の地区別割合
- 特定健康診査の地区別受診率
- 地区別の高齢化率
▶午後54
現時点で、肥満対策と運動不足の改善のために重点地区で実施する企画で最も適切なのはどれか。
- 講演会の開催
- ポスターの掲示
- パンフレットの配布
- ウォーキング大会の開催
▶午後55
重点地区での事業に効果があることが分かり、全地区で実施したいと考えた。
次年度の予算要求で事業の必要性を説明するとき、関係する中長期計画で最も適切なのはどれか。
- 地域福祉計画
- 健康増進計画
- 人材確保支援計画
- 子ども・子育て支援事業計画
資料 厚生労働省「第101回保健師国家試験、第98回助産師国家試験、第104回看護師国家試験の問題および正答について」
平成28年2月16日実施の第102回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。
また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。
分野別解説付き問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ
- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ
を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。
なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
第102回保健師国家試験目次
第102回保健師国家試験・午前(55問)
▶午前1
市では新しい健康づくり計画とその事業経過とをホームページに掲載している。
この活動の目的はどれか。
- アドヒアランス
- アカウンタビリティ
- セルフ・エフィカシー
- ポピュレーションアプローチ
▶午前2
認知症高齢者を介護する家族の問題対処能力をアセスメントするにあたって収集する情報で適切でないのはどれか。
- 社会資源の活用状況
- 家族の各構成員の発達課題
- 家族と本人との情緒的関係
- 家族の介護に対する近隣の評価
▶午前3
保健所の保健師はエイズ予防週間に合わせて、大学の学園祭で若者を対象にヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症および性感染症〈STD〉に関する健康教育を行うことにした。
対象者が予防行動をとることを目標に設定し、実施する方法として最も適切なのはどれか。
- 性感染症〈STD〉に関するパネル展示
- ピア・エデュケーターによる相談
- 性感染症〈STD〉に関する講演会
- 希望者へのHIV検査
▶午前4
市町村による新生児の訪問指導について正しいのはどれか。
- 第2子以降は対象外である。
- 母子保健推進員が実施する。
- 新生児期を過ぎても継続できる。
- 母子が不在の場合は近隣住民に伝言を依頼する。
▶午前5
在宅ケアにおける高齢者のケアマネジメントに関する説明で正しいのはどれか。
- 介護支援専門員の独占業務である。
- 医療保険による訪問看護は対象としない。
- ケアプランに基づくサービスの利用開始時から始める。
- 既存のサービスによってニーズが満たされているかを査定する。
▶午前6
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針における子宮頸がん検診について正しいのはどれか。
- ヒトパピローマウイルス〈HPV〉ワクチン接種後の者は対象外である。
- 子宮頸部細胞診は検診項目の対象外である。
- 20歳以上の女性を対象とする。
- 同一人に対し1年に1回行う。
▶午前7
市町村における保健事業計画の策定で適切でないのはどれか。
- 予算要求書をもとに策定する。
- 市町村の総合計画との整合性を図る。
- 地区特性を重視して目標を設定する。
- 住民の力では解決できない公共性の高い事業を優先する。
▶午前8
市では健康増進計画を策定する委員会のメンバーを一般から公募することにした。
公募の目的として最も適切なのはどれか。
- 人権擁護
- 多文化共生
- ノーマライゼーション
- コミュニティ・エンパワメント
▶午前9
地域で難病患者の在宅ケアを支援するボランティアを育成するための研修内容として適切でないのはどれか。
- 褥瘡処置の方法
- 基本的な心構え
- 難病患者の介護者の経験談
- 難病患者が利用できる保健福祉サービス
▶午前10改題
令和2年(2020年)の患者調査における精神及び行動の障害に関する動向について正しいのはどれか。
- 外来受療率は入院受療率より高い。
- 精神病床の平均在院日数は約100日である。
- 年齢階級別外来受療率は年齢とともに上昇する。
- 血管性及び詳細不明の認知症の総患者数は減少している。
▶午前11
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について正しいのはどれか。
- 市町村は障害者権利擁護センターを設置する。
- 障害児入所施設従事者による虐待に適用される。
- 障害者虐待には正当な理由なく障害者の身体を拘束することが含まれる。
- 障害者を雇用する事業主による虐待を発見した者は労働基準監督署に通報する。
▶午前12
養護教諭が勤務する小学校で、ソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉の利用に関する調査を行った。その結果、小学校5年生でソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉の利用経験がある児童が6割を占め、夜12時以降も利用している児童が半数を占めることが明らかになった。そこで、保護者の意識を高め、児童の生活リズムを整えるための対策を講じることになり、保健だよりを配布して保護者に調査結果の報告を行った。
次に養護教諭が行う活動で優先度が高いのはどれか。
- 家庭での利用を禁止するよう保護者に伝える。
- 利用方法に関するポスターを作成して校内に掲示する。
- 児童に与える影響について保護者向けに講演会を開催する。
- 就寝時刻の目標を定めて各クラスで競争した目標達成状況を伝える。
▶午前13
労働安全衛生法に基づく産業保健について正しいのはどれか。
- 特定業務従事者の健康診断は年に1回以上実施する。
- 50人以上の事業場ではストレスチェックが義務付けられている。
- 300人以上の事業場では地域産業保健センターが健康管理を行う。
- 海外派遣労働者の健康診断は産業医の判断で省略することができる。
▶午前14改題
令和3年度(2021年度)の福祉行政報告例における児童虐待相談対応件数について正しいのはどれか。
- 児童相談所の対応件数は前年度に比べ横ばいである。
- 実父による虐待は前年度に比べ増加傾向である。
- 実母による虐待は全体の4割以下である。
- 身体的虐待は心理的虐待より多い。
▶午前15
災害時の医療体制で正しいのはどれか。
- 基幹災害拠点病院は原則として都道府県に1か所設置する。
- 災害拠点病院は避難所における感染症のまん延防止対策を行う。
- 広域災害・救急医療情報システム〈EMIS〉は海外との支援調整を行う。
- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は市町村と医療機関との協定に基づき活動する。
▶午前16
新任期から担う看護管理で正しいのはどれか。
- 地区管理
- 人材管理
- 組織管理
- 予算管理
▶午前17
疫学研究に関する記述で正しいのはどれか。
- 記述疫学には介入研究が含まれる。
- 横断研究によって因果関係を証明できる。
- 分析疫学は記述疫学よりも疾病と要因との関連を示しやすい。
- 前向きコホート研究は稀少疾病の罹患リスクを検討するのに優れている。
▶午前19
老年化指数はどれか。
- (老年人口÷総人口)×100
- (老年人口÷年少人口)×100
- (老年人口÷生産年齢人口)×100
- {(老年人口÷年少人口)÷生産年齢人口}×100
▶午前20改題
国連児童基金〈UNICEF〉について正しいのはどれか。
- 地球的規模の人口問題に取り組んでいる。
- 援助対象国は国連加盟を条件としている。
- 児童の権利に関する条約の普及活動を行っている。
- 令和3年(2021年)の日本の分担拠出金は世界第1位である。
▶午前21
プライマリヘルスケアの4原則として正しいのはどれか。
- 専門家によるリーダーシップの発揮
- 住民のディマンドの重視
- 高度先進医療の提供
- 資源の有効活用
▶午前22
地域包括支援センターについて正しいのはどれか。
- 概ね1万人ごとに設置する。
- 要介護状態区分の決定を行う。
- 地域密着型介護予防サービスの提供を行う。
- 介護支援専門員の地域ネットワークを構築する。
▶午前23
19世紀のイギリスにおいて公衆衛生法の成立に寄与した人物はどれか。
- ジョン・スノウ
- レスター・ブレスロー
- ウイリアム・ラスボーン
- チャールズ・ウィンスロー
- エドウィン・チャドウィック
▶午前24
学校保健統計調査から得られるのはどれか。
- ぜん息の被患率
- 自殺した児童生徒数
- 救急車による搬送件数
- 不登校の状態にある児童生徒数
- 学校の管理下における突然死の件数
▶午前25改題
市町村保健センターで正しいのはどれか。
- 市町村に設置義務がある。
- センター長は原則として医師である。
- 地域保健法に設置が定められている。
- 診療放射線技師の配置が定められている。
- 令和5年4月時点のセンター数は1,500か所である。
▶午前26
平成25年(2013年)の地域における保健師の保健活動に関する基本的な指針における記載事項でないのはどれか。
- 人材育成
- 地区担当制の推進
- 予防的介入の重視
- 個別課題の視点の重視
- 地区診断に基づくPDCAサイクルの実施
▶午前27
A県は、県内のB市で起きた震度7の地震による発災直後からB市にA県の保健師を派遣し、継続した支援を行っている。災害後2か月が経ち、避難住民の半数以上は仮設住宅への移住が進んでいる。B市の職員は自ら被災しながらも発災直後から休みなく働いている。
このときのA県の保健師の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。
- B市の職員が交互に休めるよう支援する。
- B市の支援活動の今後の方針が決まるのを待つ。
- B市の職員に精神科医の診察を受けるよう勧める。
- B市に対し職員の健康チェックを実施するよう提案する。
- 被災したB市の職員が優先的に仮設住宅へ移るよう提案する。
▶午前28
地域保健対策の推進に関する基本的な指針について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 健康危機管理体制の管理責任者は保健所長が望ましい。
- 科学的根拠に基づく地域保健対策の計画を策定する。
- 自助の推進から公助の積極的な活用への移行を図る。
- 専門家とのリスクコミュニケーションに努める。
- 災害対策基本法に基づいて定められている。
▶午前29
ヘルスプロモーションの理念に基づく保健師の活動はどれか。2つ選べ。
- 成年後見制度の申し立ての支援
- 受動喫煙防止の環境整備の推進
- 睡眠に関する正しい知識の普及啓発
- 新型インフルエンザ発生時の初動調査
- 脳卒中後遺症患者のリハビリテーション教室の実施
▶午前30改題
日本の令和22年(2040年)の推計について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 総人口が1億人を下回る。
- 75歳以上の高齢者が2,000万人を超える。
- 総人口のおよそ3人に1人が65歳以上になる。
- 世帯主が65歳以上の世帯における単独世帯の割合が50%を超える。
▶午前31
健康格差の社会的決定要因となるのはどれか。2つ選べ。
- 教育
- 収入
- 社会参加
- 職場環境
- 食品の入手可能性
▶午前32
1,000世帯の新興住宅地を担当する保健師は、担当地区内の乳幼児をもつ母親15人から子育て支援グループを作りたいと相談を受けた。
このグループへの支援で適切なのはどれか。2つ選べ。
- グループが形成された初期では受容的に見守る。
- メンバーが自発的に参加し始める時期では指示を与えて主導する。
- メンバー間の信頼や連帯感が生じる時期ではリーダーを指名する。
- メンバーが一丸となり活動する時期では活動内容を調整する。
- 支援を終了する時期ではグループが自主的に運営する力を評価する。
▶午前33
民生委員について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 任期は5年である。
- 児童委員を兼ねる。
- 厚生労働大臣が委嘱する。
- 市町村の推薦が必要である。
- 設置の根拠法令は地方自治法である。
▶午前34
A市のB地区では、認知症高齢者の徘徊に困っている家族が多いことが分かり、保健師はB地区の自治会と協働し、地域における認知症高齢者の見守り体制を構築することになった。
見守り体制の構成メンバーとして適切なのはどれか。2つ選べ。
- 小学校長
- 派出所の警察官
- 精神保健福祉センターの医師
- 特別養護老人ホームの介護福祉士
- 居宅介護支援事業所の介護支援専門員
▶午前35
Aさん(28歳、初産婦)。里帰り中に他県にあるB周産期母子医療センターで、妊娠28週0日に体重978gの男児を出産した。生後3か月、児は体重2,400gでGCUから自宅に退院した。地区担当保健師はGCUの看護師から情報提供を受け、Aさんに連絡した上で、退院の1週後に家庭訪問を行った。Aさんの表情はやや暗い様子で「未熟児だったので、体重が増えているのか心配です。風邪をひかせないように外には連れて行っていません」と話した。訪問時の児の体重は2,540gであった。
このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 感染症の予防のため父母以外の家族の接触は避けるよう説明する。
- 生後6か月になったら離乳食を開始するよう説明する。
- 予防接種は修正月齢で接種するよう説明する。
- 児の体重増加以外に不安がないか確認する。
- 児の体重増加は順調であると説明する。
▶午前36
精神障害者保健福祉手帳について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 市町村長が交付する。
- 高次脳機能障害は対象となる。
- 税制上の優遇措置が受けられる。
- 1~4級の等級に区分されている。
- 1年ごとに認定の更新が必要である。
▶午前37
災害救助法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- 防災計画の作成
- 職員の派遣義務
- 被災した住宅の応急修理
- 避難所及び応急仮設住宅の供与
- 地方公共団体とボランティアとの連携
▶午前38
直接法による年齢調整死亡率の特徴はどれか。2つ選べ。
- 小規模な集団の観察に適している。
- 高齢者の多い集団では高くなりやすい。
- 値は標準化死亡比〈SMR〉として示される。
- 異なる観察集団の死亡率を直接比較できる。
- 計算には観察集団の年齢階級別死亡率が必要である。
▶午前39
割合の差の検定について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 縦断研究が必要である。
- t検定で有意差を検定する。
- クロス集計表は有用である。
- ハザード比を求めることができる。
- χ2〈カイ2乗〉検定で有意差を検定する。
▶午前40
疾病Aの新しいスクリーニング検査の性能を評価するために、疾病Aの患者100人と疾病Aでない者100人に対して検査を実施した。疾病Aの患者のうち60人と、疾病Aでない者のうち10人とが検査の結果陽性であった。
特異度を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②%
次の文を読み41〜43の問いに答えよ。
Aさん(27歳、女性)。両親との3人暮らし。大学受験に失敗し、浪人していたときに幻覚と妄想とが出現し、統合失調症と診断され、3か月間精神科病院に入院したことがある。Aさんは半年前から受診を中断し、ぶつぶつ独り言を言うようになったため、母親が受診を勧めたがAさんは拒否している。対応に困った母親から保健所の保健師に相談の電話があった。
▶午前41
このときの母親への対応で最も適切なのはどれか。
- 家庭訪問することを提案する。
- 保健師から主治医に連絡すると説明する。
- Aさんが自分から受診するのを待つよう助言する。
- 保健師から電話でAさんに受療を勧めると説明する。
▶午前42
1か月後、「Aは受診を再開しましたが、予約した外来日に受診せず、内服も不規則のようです」と母親から保健師に電話で相談があった。
母親に確認する内容で優先度が高いのはどれか。
- 残薬数
- 次回の外来予約日
- 家族が代わりに受診できる可能性
- Aさんの治療に対する父親の理解
▶午前43
その後、定期的な受診が継続できるようになり、保健師に対しAさんから「母親からは体調が良いなら働いたらどうかと言われ、イライラするので家にいたくない」と相談があった。
Aさんに紹介するサービスで適切なのはどれか。
- 就労移行支援
- 地域定着支援
- 地域活動支援センター
- 共同生活援助〈グループホーム〉
次の文を読み44〜46の問いに答えよ。
人口2万人のA町。A町のB地区には新たに新幹線の駅ができ、300戸の温泉付のマンションが建設された。マンションの入居者の平均年齢は67.2歳で、都市部の会社を定年退職した者が多い。ほぼ全戸に入居が済んだことで、A町全体の老年人口割合が増加した。
▶午前44
B地区の健康課題を明らかにするために情報を収集する対象で優先度が高いのはどれか。
- A町の老人クラブの参加者
- マンションの自治会長
- B地区の民生委員
- B地区の開業医
▶午前45
保健師はB地区のマンションの入居者の世代や背景が似ていることに着目し、生活状況や健康に対する考え方などの質的なデータを得たいと考えた。
把握する方法として最も適切なのはどれか。
- 地区踏査
- 電話インタビュー
- インターネットアンケート
- フォーカス・グループインタビュー
▶午前46
調査の結果、B地区のマンション入居者からは「定年退職後、趣味がないので外出する機会が少なくなった」、「マンションに入居してから外部との交流が減った」、「最近体力が落ちてきたと感じる」、「自分に合った健康づくりをしたい」との意見が多かった。保健師はB地区の住民の健康増進のために住民同士の交流を促すことにした。
保健師の活動で最も適切なのはどれか。
- 健康診査の受診勧奨
- 介護予防事業の実施
- 健康に関する講演会の開催
- ウォーキングマップの配布
- 健康のための調理教室の開催
次の文を読み47〜49の問いに答えよ。
人口9万人、高齢化率28%のA市。介護保険の認定を受ける高齢者は増加傾向にある。市では介護における悩みを共有して、介護者の介護負担感を軽減することを目標に介護者の会を開催している。市内は10の地区に分かれ、各地区に集会所がある。月に1回、各集会所において保健師が運営し、毎回30人程度が参加している。
▶午前47
介護者の会の目標達成状況を評価するための指標として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 短期入所〈ショートステイ〉の利用状況
- 被介護者の介護状態区分
- ストレスへの対処状況
- 介護に対する困難感
- 新規参加者数
▶午前48
保健師は、A市における今後の介護者の支援方法について検討するために、介護者の負担を把握する目的で要介護認定者がいる世帯への調査を実施することにした。
介護に要する時間のほか、把握する項目として優先度が高いのはどれか。
- 福祉用具の貸与状況
- 家族内の介護者の構成
- 要介護認定結果の満足度
- 介護に係る自宅改築の費用
▶午前49
調査の結果、A市内の社会資源サービスの利用が有効に活用できていないこと、介護者が高齢者であること、負担感のうち身体への負担が多くを占めることなどが分かった。保健師は介護者への支援を充実させたいと考えた。
A市における介護者への支援で優先されるのはどれか。
- 要介護者を介護する家庭を全戸訪問する。
- 介護者を対象にした健康診査事業を実施する。
- 介護者を対象にした運動プログラムを事業化する。
- 地区の集会所で介護方法に関する講習会を開催する。
次の文を読み50〜52の問いに答えよ。
Aさん(35歳、女性、専業主婦)。夫(38歳)と幼稚園に通園する2人の子どもとの4人暮らし。Aさんは4か月前から咳が出現し診療所を受診したが、喘息と診断され経過をみていた。咳がひどくなったため病院を受診したところ、胸部エックス線写真で空洞性病変があり、喀痰塗抹陽性、結核菌PCR陽性が判明し、結核病床に入院した。診断した医師から保健所に結核発生の届出があった。
▶午前50
保健所の保健師の初動対応として適切なのはどれか。2つ選べ。
- Aさんに入院勧告書を渡す。
- 幼稚園の園長に休園を指示する。
- 病院を訪問しAさんと面接する。
- Aさんへ公費負担申請書類を送付する。
- 幼稚園の保護者向けに結核の説明会をする。
▶午前51
Aさんは、幼稚園に子どもを毎日送り迎えしていた。保健所の保健師は幼稚園の関係者に対して接触者健康診断を企画した。
幼稚園に出向いて収集する情報で優先度が低いのはどれか。
- 園児の家族構成
- 園児の呼吸器症状
- 園児のBCG接種歴
- 園児とAさんとの接触頻度
- 幼稚園教諭の定期健康診断の結果
▶午前52
接触者健康診断の結果、Aさんの夫と幼稚園教諭の1人とが喀痰塗抹陰性の結核であり、Aさんの子どものうちの1人と幼稚園児の3人とが潜在性結核感染症であった。
このときの結核の治療支援について正しいのはどれか。
- Aさん家族のDOTSを優先して行う。
- 幼稚園教諭のDOTSは教育委員会が行う。
- 潜在性結核感染症に罹患している者は地域DOTSの対象である。
- 喀痰塗抹陰性の結核に罹患している者は入院して院内DOTSが必要である。
次の文を読み54、55の問いに答えよ。
人口50万人のA市。A市総合計画の母子保健分野について「児童虐待やいじめのない、母と子どもの笑顔があふれる街A市」を目標としている。A市では、保健師が中心となって母子保健計画を新たに策定することとなった。平成25年(2013年)のA市の人口動態統計および母子保健に関する主な状況を表に示す。

▶午前54
A市の母子保健計画において取り組むべき重点課題はどれか。2つ選べ。
- 不妊治療の推進
- 特定妊婦の支援
- 妊娠中の母体の体重管理
- 初回妊婦健康診査の早期受診の勧奨
- 1歳6か月児健康診査受診率の向上
▶午前55
A市の母子保健計画の指標と目標とを設定し、達成のための具体的な取り組み及び事業の進捗状況の把握・評価を行うために、母子保健計画推進会議を開催することとした。
母子保健計画推進会議について適切なのはどれか。
- 非公開で開催する。
- 政策評価を母子保健計画の最終年度に行う。
- 委員の意見をもとに当該年度の事業内容を変更する。
- 保健センター以外の部署で実施している事業の実施状況を報告する。
第102回保健師国家試験・午後(55問)
▶午後1
従業員数1,500人の部品製造工場。製造部門ごとに責任者が置かれている。定期健康診断の問診の結果、腰痛の訴えが多い部門があった。
この健康課題に予防的な取り組みをするために優先して働きかける対象はどれか。
- 腰痛を訴えている者
- 定期健康診断の未受診者
- 定期健康診断の有所見者
- 腰痛が多く発生している部門の責任者
▶午後2
市では自立している独居高齢者の孤立死が続いたため、独居高齢者に対する活動を検討したいと考えている。自立している独居高齢者の調査をした結果、孤立死は他人事ではなく不安を感じるが、プライバシーには踏み込まれたくないという者が多いことが明らかになった。
孤立死を予防するための保健師の活動として適切なのはどれか。
- 老人クラブの加入者数を調査する。
- 自治会に独居高齢者が集う場を設定するよう促す。
- 地域活動支援センターに高齢者の見守りを依頼する。
- 孤立死への不安がある高齢者に地域包括支援センターでの相談を勧める。
▶午後3
社会福祉における相互援助の概念と具体的な内容との組合せで適切なのはどれか。
- 自助――ボランティア
- 互助――介護保険
- 共助――生活保護
- 公助――就労継続支援
▶午後4
家族のライフサイクル段階とその発達課題との組合せで正しいのはどれか。
- 養育期――夫婦間の生活習慣の調整
- 教育期――子どもによる役割の補充
- 排出期――子どもによる役割の分担の強化
- 向老期――子ども夫婦との役割期待の調整
▶午後5
Aさん(50歳、男性)。仕事のストレスからうつ状態になり会社に出勤できなくなった。妻は精神的に不安定になり、息子は母親を心配して不登校となった。
相互に影響し合うAさん家族の状況を理解するために最も適切な理論はどれか。
- 家族発達論
- 家族システム理論
- 家族セルフケア理論
- 家族ストレス対処理論
▶午後6
Aさん(30歳、男性)。Aさんの職場では、保健師による健康相談を定期的に実施しており、Aさんは「妻が妊娠したことをきっかけに禁煙しようと決めたが、今日からやめようと思っているうち、1週間が過ぎてしまった」と保健師に相談した。
Aさんへの最初の対応で最も適切なのはどれか。
- 禁煙できたときの自分への褒美を考えるよう助言する。
- どのようなときにたばこを吸ってしまうか確認する。
- たばこを吸いたいときはガムを嚙むよう勧める。
- 「禁煙」と書いた紙を職場に貼るよう促す。
▶午後7
保健師が個別支援を行う際のケアマネジメントのプロセスで、初回のモニタリングを実施する時期として正しいのはどれか。

- a
- b
- c
- d
▶午後8
保健師が支援するグループで社会変容機能が最も高いのはどれか。
- 精神障害者を対象とするデイケアのグループ
- 難病患者の機能訓練グループ
- 引きこもりの当事者の会
- 重症心身障害児の親の会
▶午後9
A市では2歳児を対象としたう歯予防事業を実施している。
事業の成果指標として適切なのはどれか。
- 3歳児の保護者の仕上げ歯磨きの実施状況
- 3歳児の保護者のう歯に関する知識
- 3歳児のう歯保有率
- 3歳児の間食の回数
▶午後10
妊娠届について正しいのはどれか。
- 都道府県知事に提出する。
- 医師の診断書が必要である。
- 届出の事項は定められていない。
- 届出をした者に対し母子健康手帳を交付する。
▶午後11
特定健康診査・特定保健指導について適切なのはどれか。
- 実施義務者は医療保険者である。
- 対象年齢は60~74歳と定められている。
- 服薬治療中の者は特定健康診査の対象でない。
- 動機付け支援対象者と積極的支援対象者に対して一緒にグループ面接を行う。
▶午後12
A市では、市の大腸がん検診受診率が全国平均に比べて低いことから、未受診理由の調査を行った。その結果、未受診理由には「時間がない」、「自分は大丈夫」、「検査が不安」などの意見が多かった。
受診勧奨を目的とした大腸がん検診に関する説明で適切なのはどれか。
- 「2年に1度は受けましょう」
- 「便検査で簡単に調べられます」
- 「大腸がんは男性のがんによる死亡の第4位です」
- 「初期の段階から自覚症状があるので注意しましょう」
▶午後13
介護予防・日常生活支援総合事業で正しいのはどれか。
- 地域生活支援事業である。
- 平成17年(2005年)に創設された。
- 要支援認定を受けている者も対象である。
- 一般介護予防事業の対象は第2号被保険者である。
▶午後14
感染症に対する健康危機管理の平常時の対応はどれか。
- 空港での水際対策
- 積極的疫学調査の実施
- 感染症発生動向調査の実施
- 厚生労働省対策本部の設置
▶午後15
A地区では梅雨末期の集中豪雨によって住宅近くの山間部に広範囲の土砂崩れが発生した。
発災翌日の市町村保健師の対応として優先度が高いのはどれか。
- 要援護者の安否確認
- 汚水による感染症の発生の確認
- 避難所での慢性疾患のある者への栄養指導
- ストレス反応による精神症状がある避難者の把握
▶午後16
A地区では震度6の地震が発生し、住宅の被害が大きく住民のほとんどは発災直後から避難所での生活を続けている。発災後2週が経過し、プライバシーが守られないなど、住民から集団生活への不満が出ている。
避難所での保健師の活動について正しいのはどれか。
- 自家用車内での避難生活を勧める。
- 高齢者は救護所に移動してもらう。
- 認知症高齢者のいる家族の居住スペースを広く確保する。
- 避難者同士の自主的な話し合いの場が設けられるよう支援する。
▶午後17
個人情報保護の観点から、個人情報を提供するのに本人の同意が必要なのはどれか。
- 通所介護の参加状況を主治医に提供する。
- 腸管出血性大腸菌感染症の発生届を保健所に提出する。
- 児童虐待の疑いがある児の家族の情報を児童相談所に通告する。
- 要介護認定に係る審査のために市町村に主治医意見書を提出する。
▶午後18
新たに地域保健活動を開始する際の組織の在り方について最も適切なのはどれか。
- 事業管理と地域管理とを連動させる。
- 各部門の役割は事業の開始後に決定する。
- 組織内の職位順に活動目標を伝達共有する。
- 住民からの苦情を優先的に活動内容に反映する。
▶午後19
有病率を上昇させる要因はどれか。
- 罹患率が低くなる。
- 平均有病期間が長くなる。
- 観察集団に健康な人が流入する。
- 重症化して短期間に死亡する人が増える。
▶午後20改題
脳血管疾患について正しいのはどれか。
- 年齢調整死亡率は増加している。
- 脳出血の最大の危険因子は糖尿病である。
- 脳梗塞よりくも膜下出血による死亡数が多い。
- 令和4年(2022年)の死因順位は第4位である。
▶午後21
特定健康診査を受診した100人の腹囲とHbA1c値について、個人ごとの2つのデータを一度に示し両者の関連を表現するのに優れているのはどれか。
- 折れ線グラフ
- ヒストグラム
- 円グラフ
- 散布図
▶午後22
国際疾病分類〈ICD〉について正しいのはどれか。
- 日本の死因統計では平成7年(1995年)にICD-10が採用された。
- 患者調査での疾病分類には用いられない。
- 各種疾病の治療指針が示されている。
- 国際疫学会が改訂を行っている。
▶午後23
国際協力に関わる機関とその活動の目的との組合せで正しいのはどれか。
- 国連世界食糧計画〈WFP〉――学校給食の普及
- 国連人口基金〈UNFPA〉――医薬品の研究開発
- 国連合同エイズ計画〈UNAIDS〉――感染症の監視網の構築
- 経済協力開発機構〈OECD〉――災害地域への医療人材の派遣
▶午後24
口唇口蓋裂の児に適用されるのはどれか。
- 療育医療
- 養育医療
- 医療扶助
- 自立支援医療
▶午後25
介護保険法における権利擁護事業を担当するのはどれか。
- 社会福祉協議会
- 地域福祉センター
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
▶午後26改題
令和4年(2022年)の健康日本21(第二次)最終評価結果で目標値に達した項目はどれか。
- 食塩摂取量の減少
- 糖尿病合併症の減少
- 日常生活における歩数の増加
- 運動習慣者の割合の増加
- 低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制
▶午後27
地域子育て支援拠点事業について正しいのはどれか。
- 従事者に条件はない。
- 一時預かり事業を実施する。
- 開催日数の基準が設けられている。
- ひろば型とセンター型との2種類がある。
- 根拠法令は子ども・子育て支援法である。
▶午後28
学校教育法で定められているのはどれか。
- 食育の実施
- 学校保健の定義
- 養護教諭の配置義務
- 学級閉鎖の実施基準
- 就学時健康診断の実施
▶午後29
保健活動で用いる尺度の妥当性の説明として正しいのはどれか。
- 測定する側が実施しやすい。
- 測定される側が受け入れやすい。
- 測定したい特性が正しく測定できている。
- 調査対象の測定結果が全体を代表している。
- 同一対象に対して繰り返し測定すると同じ値が得られる。
▶午後30
地方自治体の保健医療福祉計画の策定におけるパブリックコメントについて正しいのはどれか。
- 地方自治法に基づいて行われる。
- 計画策定における合意形成の方法である。
- 策定された計画を広く公表するために行う。
- 寄せられた意見に対する結果は個別に連絡する。
- 計画に関連する市民団体を選定して意見を求める。
▶午後31
Aさん(61歳、主婦)。昨年度までは異常がなかったが、今年度の特定健康診査では、身長158cm、体重70kg、腹囲90cm、血圧136/88mmHg、喫煙10本/日で特定保健指導の対象となった。Aさんは結果説明会に来所しなかったため保健師は電話で連絡した。Aさんは「自覚症状はないため、結果説明会には行かなかった。ここ1年ほど夫の帰りが遅く、夫と夕食を摂った後に家事をするので睡眠不足が続いている。昼間眠くてイライラしたばこを吸ってしまう」と訴えた。
このときの電話の対応で最も適切なのはどれか。
- 夫を待たずに寝るよう指導する。
- 標準体重になるよう減量を勧める。
- 動機付け支援の対象であると伝える。
- たばこの本数を増やさないよう指導する。
- 生活習慣の改善について一緒に考えることを提案する。
▶午後32
健康診査の評価をプロセス評価、影響評価および成果評価の3つに分けて考えるとき、プロセス評価にあたるのはどれか。2つ選べ。
- 要医療者の治療率
- 健康診査の受診者数
- 健康診査に従事する者の数
- 健康診査における疾患の発見率
- 健康診査後に行動変容があった者の数
▶午後33
労働者の心の健康の保持増進を目的に行われる事業場内のラインによるケアはどれか。2つ選べ。
- 労働者からの相談への対応
- カウンセリングの実施
- 職場環境の改善
- 教育研修の実施
- 外部資源の紹介
▶午後34
人口動態統計に含まれるのはどれか。2つ選べ。
- 出生
- 婚姻
- 妊娠
- 転出
- 入院
▶午後35改題
国の予算について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 特別会計は一般会計に含まれる。
- 予算は歳入と歳出とで構成される。
- 医療給付は社会保障関係費に含まれる。
- 各省からの概算要求の締め切りは3月31日である。
- 令和4年度(2022年度)の厚生労働省の予算は国の一般会計予算総額の5割を占める。
次の文を読み36〜38の問いに答えよ。
人口10万人のA市。A市は地域特性が異なるB、C地区からなっている。B地区の高齢者サロンで健康講話を行ったところ、腰痛や膝痛の訴えが多くあり、参加者の中には要支援と認定された者もいた。保健師はA市内での介護予防教室を実施する必要性を検討するため、各地区の高齢者サロンの参加者から情報を収集することにした。
▶午後36
収集する情報として優先度が高いのはどれか。
- サロンへの参加以外の外出頻度
- 持ち家の所有状況
- 世帯収入
- 職業歴
▶午後37
収集した情報を分析したところ、B地区はC地区と比較して、転倒の危険性や運動機能の衰えを感じている者が多いことが分かった。保健師は、まずはB地区で介護予防教室を実施することにした。
初回の介護予防教室の内容で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 介護保険の申請方法を説明する。
- 有効な運動方法について指導する。
- 関節可動域〈ROM〉訓練を実施する。
- 車椅子の使用方法について説明する。
- 基本チェックリストによる健康度評価を行う。
▶午後38
保健師はC地区でも介護予防教室を実施するため、C地区での介護予防教室のテーマを別途検討することにした。
C地区の情報で分析する優先度が高いのはどれか。
- 死因別死亡数
- 寝たきり高齢者数
- 要介護状態区分別の認定者数
- 高齢者サロン参加者の現病歴
次の文を読み39〜41の問いに答えよ。
A地区の高層マンションには若い世代が多く住んでいる。高層マンションに住むBさん(23歳、初産婦)は、市の両親学級に参加していたが、マンション内に親しい友人はいない。両親学級に参加した際にBさんは「夫は会社員で帰宅時間が遅く、両親は遠方に住んでいる」と話していた。出産後、母子ともに順調に経過し退院した。市の保健師は生後25日目にBさん宅へ新生児訪問することになった。
▶午後39
新生児訪問時、Bさんは「育児に不安がある」、「相談する相手がいない」などと保健師に話した。
このときのBさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 育児不安の内容を具体的に聞く。
- 近所の児童館を利用するよう勧める。
- 夫の育児への協力の有無を確認する。
- Bさんの実父母の健康状態を確認する。
- 両親学級のときに知り合った者に連絡するよう勧める。
▶午後40
新生児訪問時、Bさんは「引っ越してきたばかりで、妊娠中はあまり外に出ることがなかったので、家の近くに友人がいない」と話していた。このことをきっかけに保健師は、A地区の高層マンションに住む母親の育児に関する課題を検討することにした。
把握する項目として最も優先度が高いのはどれか。
- 両親学級の参加状況
- A地区の出生数の推移
- 3か月児健康診査の受診者数
- 新生児訪問記録における主訴
▶午後41
A地区の健康課題として高層マンションに住む育児中の母親の交流不足が明らかになった。市内には母親が集まって活動をしている育児サークルがあり、保健師は既存の育児サークルを活用して、A地区内の育児中の母親の交流を深めたいと考えている。
このような課題解決に向けて次年度に育児サークルと協働して行うのはどれか。
- 育児サークルのメンバーが両親学級に参加する。
- 母子保健推進員が育児サークルの運営に関わる。
- 新生児訪問で育児サークルのメンバーを紹介する。
- 育児サークルの活動を高層マンションの集会場で行う。
次の文を読み42〜44の問いに答えよ。
Aさん(21歳、女性)。高校卒業後就職したが職場では人間関係が築けず、1つの決められた作業に集中することはできるが、複数の仕事が重なるとパニック状態になってしまうため転職を繰り返した。半年前にAさんは仕事を辞め、最近は自信をなくして自室にひきこもり昼夜逆転の生活となっている。Aさんのことが心配だと母親から保健所に電話相談があった。保健師は母親に来所を勧め、面接を実施した。
▶午後42
保健師が母親に確認するAさんの情報として優先度が高いのはどれか。
- 交友関係
- 精神症状の有無
- 高校時代の学業成績
- これまでの転職の経緯
▶午後43
Aさんは保健師が紹介した医療機関を受診し、後日、Aさんが自閉症スペクトラム障害〈ASD〉と診断された。受診から3日後、母親がAさんと一緒に受診結果の報告に保健所を訪れた。母親は障害と診断されたことに戸惑っている様子であったが、30分ほど会話をする中で落ち着き「私がこんなに動揺していてはだめですね。娘のことをもっと考えてあげないといけませんね」と話した。
このときの母親への助言として最も適切なのはどれか。
- 「お母さんがしっかりしましょう」
- 「今までの子育てを振り返りましょう」
- 「Aさんとの散歩を日課にしてください」
- 「まずはAさんの病気を受け止めましょう」
- 「Aさんが何に困っているかよく聞きましょう」
▶午後44
診断から2か月後、少しずつ障害を理解できAさん自身も気持ちが落ち着いてきた。Aさんは「障害を理解してくれるところで働きたいので相談にのって欲しい」と話した。
Aさんが利用する社会資源として最も適しているのはどれか。
- 自立訓練
- 行動援護
- 地域活動支援センター
- 発達障害者支援センター
- コミュニケーション支援事業
次の文を読み45〜47の問いに答えよ。
Aちゃん(6歳、男児)。Aちゃんは保育所に通っている。3歳児健康診査の心理相談で療育教室への参加を勧められたが、これまで2回しか参加できておらず経過観察の対象となっていた。就学予定の小学校で行われた就学時健康診断で、Aちゃんは常に動き回り目立つ存在であった。母親はAちゃんについて元気過ぎる子どもと認識している。
▶午後45
就学時健康診断後、教育委員会が保護者の了解を得てAちゃんについて情報収集する先として優先度が高いのはどれか。
- 児童福祉司
- 保育所の担任
- 療育教室の指導員
- 3歳児健康診査時の心理相談担当者
▶午後46
その後、教育委員会が主催して関係者と母親とがAちゃんの就学先について協議を行った結果、Aちゃんは地元の小学校の通常の学級に在籍することと、小児専門医を受診することが決まった。受診の結果、注意欠陥多動性障害〈ADHD〉と診断され定期的に受診することになった。Aちゃんは地元の小学校に入学した。授業中、廊下の人の行き来をずっと見ていることや、前の席の児童にいたずらをして、担任から注意を受けては教室を飛び出すことなどが続いたため、養護教諭、担任および学年主任が参加して校内委員会を開き対応が検討された。
Aちゃんの行動上の問題への対応として、養護教諭が校内委員会に提案する内容で最も適切なのはどれか。
- 「席を教室の一番前にしてください」
- 「いたずらに対して放課後に注意してください」
- 「教室のドアに鍵をつけて飛び出しを防止してください」
- 「全地球測位システム〈GPS〉を衣服に装着してください」
▶午後47
Aちゃんは学校での衝動的な行動が減ったが、下校後の同級生とのトラブルが続いていた。そこで養護教諭を交えて担任が母親と話し合いを行った。
養護教諭と担任とが母親に提案することとして、最も適切なのはどれか。
- 「特別支援学校への転校を検討しましょう」
- 「Aちゃんの特性について学校から同級生に説明しましょう」
- 「主治医からAちゃんに注意してもらうようお願いしましょう」
- 「Aちゃんの困った点について学校が同級生にアンケート調査を行いましょう」
次の文を読み48〜50の問いに答えよ。
人口1万5千人のA町。台風の影響で大雨によって大規模な水害が発生した。町内の浸水面積は約3割であった。被害状況は床上浸水約1,500世帯、被災住民数は約3,500人で、家屋の倒壊が約200世帯であった。役場の1階にある保健センターも浸水し、町内5か所に避難所と救護所とが設置された。
▶午後48
災害発生後24時間以内の保健活動として優先度が高いのはどれか。
- 心のケアセンターの開設
- 保健センターの台帳類の避難
- 被災地区住民の健康相談の実施
- 災害時要援護者のリストの作成
- 救護所設置について住民への周知
▶午後49
2日目には水は引き始め、4日目にはほとんどの地域で自宅の片付けが開始された。片付け作業を手伝っているボランティアから「被災者は皆イライラしていて、少しでも水に浸かったものはすべて捨ててくれと言う人がいるが、どうすればよいか」という相談を受けた。
ボランティアへの助言で適切なのはどれか。
- 「言われる前に捨てましょう」
- 「捨てずに残しておきましょう」
- 「被災者の言うとおりにしてください」
- 「気持ちが落ち着いてから捨てるかどうか決めるように言いましょう」
▶午後50
ボランティアの支援を受けて家屋内外の片付けも進み、災害から1か月後、避難所に避難していた多くの住民は自宅に戻った。
自宅に戻った被災者への保健活動で適切なのはどれか。
- 地域での巡回健康相談を行う。
- 不要な外出を控えるよう説明する。
- 感染症予防のための家屋消毒剤を配布する。
- 新たなコミュニティづくりに向けて支援する。
次の文を読み51〜53の問いに答えよ。
出生10,000対6の発症率と言われている先天性神経疾患Aについて、その発症要因に関する症例対照研究を計画している。
▶午後51
調査対象者の登録について正しいのはどれか。
- 診断基準に基づいて症例を登録する。
- 多施設共同研究では代表性が損なわれる。
- 対照群からのインフォームド・コンセントは不要である。
- 調査施設の診療録を施設外に持ち出して情報を転記する。
▶午後52
先天性神経疾患Aの発症に、母親の出産時年齢が有意に関連することが既に分かっている。そのため、症例群の母親と同じ出産時年齢の母親を対照群として選定し、ペアを作成して調査対象者を集めた。
この制御方法はどれか。
- 層化
- 限定
- 無作為化
- マッチング
▶午後53
先天性神経疾患Aの発症に「妊娠前の栄養素Bの摂取不足が関与している」という仮説を立てた。調査対象者の母親に対して妊娠前の栄養素Bの摂取量に関する聞き取り調査を行った。
聞き取り調査について正しいのはどれか。
- 共通の聞き取り調査方法を用意する。
- 聞き取り調査員は、症例群か対照群かを事前に知っておく。
- 聞き取り調査員は、症例群と対照群とのどちらか一方を担当する。
- 栄養素Bの摂取不足が発症要因である可能性を調査前に知らせておく。
次の文を読み54、55の問いに答えよ。
人口30万人のA市。従業員50人未満の中小企業が多い。第1次A市健康増進計画を評価したところ、市民へのアンケート結果では、計画策定時と比べてストレスを感じている人が増えていた。また、この10年間自殺者数は横ばいで推移していたため、保健師は第2次A市健康増進計画においてメンタルヘルス対策を強化することが必要と考えた。
▶午後54
メンタルヘルス対策の検討のために、分析する項目で優先度が高いのはどれか。
- 中小企業の経営状態
- 要介護認定者の推移
- 10年間の自殺者の特徴
- 特定保健指導該当者数の推移
▶午後55
地域診断の結果、保健師は壮年期の労働者へのメンタルヘルス対策が必要だと考え、地域・職域連携会議を開くことにした。
地域・職域連携会議のメンバーで優先度が高いのはどれか。
- 商工会の代表
- 保険者協議会の代表
- 社会福祉協議会の代表
- 産業保健総合支援センターの所長
資料 厚生労働省「第102回保健師国家試験、第99回助産師国家試験、第105回看護師国家試験の問題および正答について」
平成29年2月17日実施の第103回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。
また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。
分野別解説付き問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ
- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ
を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。
なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
第103回保健師国家試験目次
第103回保健師国家試験・午前(55問)
▶午前1
保健師が行うアウトリーチはどれか。
- 言語の発達に遅れがある幼児のフォローアップ教室
- Parkinson〈パーキンソン〉病の患者会への支援
- 治療を中断している精神障害者への家庭訪問
- 後期高齢者への認知症予防教室
▶午前2
A市の保健師は、難病患者の家族会を支援するために、当事者、地域住民および関係機関による会議を開催し、パートナーシップを基盤にした活動を推進することとした。
第1回の会議の内容として最も適切なのはどれか。
- 予算確保の方法についての説明
- 近隣市町における活動事例の紹介
- 関係機関における研修の開催の検討
- A市の昨年度の保健事業全般の実績報告
▶午前3改題
日本の社会格差を示す指標の過去20年間の推移について正しいのはどれか。
- 雇用者に占める非正規職員・従業員の割合は減少している。
- 相対的貧困率は低下している。
- 完全失業率は低下している。
- ジニ係数は低下している。
▶午前4
家族に関連する内容の説明で正しいのはどれか。
- オマハシステムは家族システムの階層性を説明する理論である。
- ジェノグラムは家族と社会との関わりを示す図である。
- 家族の発達段階における最初の時期は養育期である。
- 1人の家族員の変化が他の家族員に影響を及ぼす。
▶午前5
都道府県が実施主体となり保健師が家庭訪問を行うのはどれか。
- 未熟児
- 発達障害児
- 認知症高齢者
- 小児慢性特定疾病児童
▶午前6
50歳代を対象とした運動教室修了後に受講者がとる行動で、ソーシャルキャピタルの醸成につながる行動として最も適切なのはどれか。
- 特定健康診査を受診する。
- 家族に教室で学んだ運動の話をする。
- 他の受講者と自主的に運動を継続する。
- 保健師に運動内容を定期的に報告する。
▶午前7
健康増進法に基づく市町村の役割はどれか。
- 生活習慣相談の実施
- 特定給食施設の指導
- 飲食店における利用者の受動喫煙の防止
- 健康増進の総合的な推進のための基本方針の策定
▶午前8
自治体で解決すべき健康課題の優先度を検討するときに最も重視するのはどれか。
- 課題解決に要する事業経費の額
- 課題解決のための社会資源の整備状況
- 同じ課題に取り組んでいる自治体の数
- 課題が解決されなかった場合の住民への影響
▶午前9
事業の計画策定および推進を行う際に、住民参加を促す方法として最も適切なのはどれか。
- 事業の評価は事業が終了してから公表する。
- 専門的な知識を有する集団から意見を聴取する。
- 公民館の情報閲覧コーナーで住民に情報提供する。
- 住民からの意見の反映方法について住民に提示する。
▶午前10改題
地域包括ケアシステムの推進に関する説明で正しいのはどれか。
- 公助が優先される。
- 実施主体は保健所である。
- 令和12年(2030年)に向けた対応策である。
- 高齢者のニーズに応じた住まいの整備が含まれる。
▶午前11改題
乳幼児健康診査について正しいのはどれか。
- 虐待予防の機会となる。
- 乳児の健康診査は対象月齢が法律で規定されている。
- 1歳6か月児健康診査では視聴覚機能検査が行われる。
- 令和3年度(2021年度)の3歳児健康診査の全国における受診率は約8割である。
▶午前12
Aさん(22歳、男性)。両親と兄との4人暮らし。知的障害があり、就労継続支援A型の事業所に通っている。事業所の職員から「Aさんの上腕に複数の小さなあざがあった」と市保健師に電話で相談があった。
事業所の職員から相談を受けた保健師の最初の対応として最も適切なのはどれか。
- Aさん宅の家庭訪問を行う。
- 事業所で職員とAさんに話を聞く。
- 成年後見制度の利用をAさんに勧める。
- 卒業した学校にAさんの在学中の様子を聞く。
▶午前13
8020運動について正しいのはどれか。
- う蝕予防に重点を置く運動である。
- 健康日本21(第二次)に目標値が設定されている。
- 日本医師会と日本歯科医師会とが推進を提言した。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づいて運動を開始した。
▶午前14
養護教諭の職務で正しいのはどれか。
- 学校給食の衛生管理
- 定期健康診断の評価
- 学校保健委員会の設置
- 感染症による出席停止の決定
▶午前15
健康危機管理について、厚生労働大臣が定めることが地域保健法に規定されているのはどれか。
- 地域保健対策検討会報告書
- 地域健康危機管理ガイドライン
- 厚生労働省健康危機管理基本指針
- 地域保健対策の推進に関する基本的な指針
▶午前16
保健所で医療機関から感染症の発生の届出を受けた。
保健師が患者を訪問するときに、N95マスクの着用が必須である感染症はどれか。
- デング熱
- 開放性結核
- レジオネラ肺炎
- 中東呼吸器症候群〈MERS〉
▶午前17
市町村の保健事業の予算編成について正しいのはどれか。
- 事業ごとに予備費を計上し事業費の不足を防ぐ。
- 予算の確保は具体的な実施方法を検討する前に行う。
- 事業評価をもとに既存事業の継続の必要性を検討する。
- 毎年実施している事業の予算の決定には議会の議決は必要ない。
▶午前18改題
令和2年度(2020年度)の国民医療費について正しいのはどれか。
- 制度区分別国民医療費では公費負担医療給付分が最も多くを占める。
- 傷病分類別の医科診療医療費では悪性新生物〈腫瘍〉が最も多くを占める。
- 65歳以上の人口一人当たり国民医療費は65歳未満の約4倍である。
- 訪問看護医療費は全体の5%を上回る。
▶午前19
学校保健行政について正しいのはどれか。
- 対象に幼稚園が含まれる。
- 厚生労働省が所管している。
- 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。
- 都道府県教育委員会は都道府県内の市町村立学校を直轄している。
▶午前20
精神保健福祉センターの業務で正しいのはどれか。
- 措置入院の決定
- 精神保健福祉相談員の任命
- 精神障害者保健福祉手帳の交付
- 精神障害者の福祉に関する困難な相談
▶午前21改題
令和3年度(2021年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」における養護者による高齢者虐待に関する説明として適切なのはどれか。
- 経済的虐待が全体の6割を占めている。
- 虐待者の続柄は息子の割合が最も高い。
- 虐待の種別にかかわらず、要介護度が高いほど虐待の発生割合が高い。
- 被虐待者の9割が認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅡ以上である。
▶午前22
A市では特定健康診査の結果、生活習慣病の該当者が年々増加していることが分かった。
A市の保健師が一次予防として行う活動はどれか。
- 夜間に受診できる健康診査を企画する。
- 精密検査が必要な人に受診勧奨を行う。
- 市民を対象に食習慣改善教室を企画する。
- 該当者の家族を対象に悪化予防の健康教室を開催する。
▶午前23
介護予防ボランティアグループのリーダーから「一部のメンバーが自分たちの活動は自己満足ではないかと悩んでいるようだ」と保健師に相談があった。
このグループのエンパワメントを支援するための対応として最も適切なのはどれか。
- 「住民の意見を聞いてみましょう」
- 「メンバー全員で話し合いましょう」
- 「市の保健事業の推進役として機能していますよ」
- 「介護予防事業の参加者の生活機能の改善状況を調査しましょう」
- 「介護予防担当の保健師からメンバーに活動の必要性を説明してもらいましょう」
▶午前24
健康日本21(第二次)の目標項目の1つである「健康格差の縮小」において、都道府県格差の指標としているのはどれか。
- 平均寿命
- 糖尿病の有病者数
- 脳血管疾患の年齢調整死亡率
- 日常生活に制限のない期間の平均
- メタボリックシンドロームの有病率
▶午前25
災害対策とその根拠法令の組合せで正しいのはどれか。
- 災害拠点病院――医療法
- 地域防災計画――災害対策基本法
- 応急仮設住宅――被災者生活再建支援法
- トリアージタグ――医師法
- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉――災害救助法
▶午前26
人口3万人の町において、先行文献が十分に存在し、要因が明らかになっている健康課題について、町民の状況を全数把握する方法として適切なのはどれか。
- フォーカス・グループインタビュー
- 半構造化面接法
- エスノグラフィ
- 質問紙調査
- 事例分析
▶午前27
人口10万人の市において、ある一定期間の結核患者の発生頻度を表現する指標として適切なのはどれか。
- 罹患率
- 有病率
- 被患率
- 受療率
- 相対頻度
▶午前28
生態学的研究によって、世界各国の1人当たりの食塩摂取量と高血圧症有病率との関連の程度を評価するために計算するのはどれか。
- 寄与危険
- 変動係数
- 相対危険
- 相対頻度
- 相関係数
▶午前29
ある集団の特定健康診査で得られたヘモグロビンA1c値の頻度の分布を確認するのに最も優れているのはどれか。
- 散布図
- 円グラフ
- 帯グラフ
- ヒストグラム
- 折れ線グラフ
▶午前30
Aさん(30歳、主婦)。夫(28歳、会社員)と長男(5歳)との3人暮らし。町の保健センターに長男を連れて来所した。Aさんは「幼稚園に息子を迎えに行ったところ、パパが怖いと言って帰りたがらなかった。息子を守るには、どうしたらいいでしょうか」と話した。Aさんの話から、Aさんの夫は日頃から大声で怒鳴ることが多いこと、昨夜は長男のいたずらに対して激しく怒り、おもちゃ箱をひっくり返して物を投げつけAさんも恐怖を感じたこと、今までAさんと長男に怪我はなかったことが分かった。
このときの保健師の対応として最も適切なのはどれか。
- 主任児童委員に連絡をする。
- 母子を保護できる場所を確保する。
- 幼稚園に電話をして情報収集をする。
- 夫の在宅時に家庭訪問をすることを伝える。
- Aさんの友人に泊まりに来てもらうよう勧める。
▶午前31
Aさん(65歳、女性)。1人暮らし。要支援2。認知症はあるが、他に治療をしている疾患はない。介護保険で介護予防訪問介護を週2回、介護予防通所介護を週1回利用している。介護予防通所介護以外に外出の機会はない。最近、空腹になると夜中でも満腹になるまで、家にある食べ物を何でも口に入れてしまうようになった。Aさんは自宅で生活することを希望していることから、地域包括支援センターの保健師はサービス担当者会議を開催することにした。
サービス担当者会議の参加者として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 訪問看護ステーションの理学療法士
- 訪問看護ステーションの訪問看護師
- 介護予防通所介護事業所の介護職員
- 介護予防訪問介護事業所の訪問介護員
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉の相談員
▶午前32
ノーマライゼーションに基づいた障害者のケアの考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国際生活機能分類〈ICF〉では障害の程度によって必要なケアが規定される。
- 支援がないことで社会参加が制約されている場合は対象に含む。
- 環境と個人との特性が加わって健康状態が決定される。
- 障害者に対する医療の確保を第一の目的とする。
- 援助者がリーダーシップを発揮して進める。
▶午前33
学校保健活動で正しいのはどれか。2つ選べ。
- BCG接種を行う。
- 食育推進計画を策定する。
- 児童生徒の保護者に助言を行う。
- 学校生活管理指導表は養護教諭が記載する。
- 学校保健委員会は地域の関係機関の代表も含めて構成する。
▶午前34
感染症発生動向調査において全数把握の対象となるのはどれか。2つ選べ。
- 風疹
- 百日咳
- 日本脳炎
- マイコプラズマ肺炎
- 性器クラミジア感染症
▶午前35
放射線の災害による影響で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 胸膜中皮腫の原因となる。
- クラッシュ症候群を起こす。
- 胎児は成人より感受性が低い。
- 呼吸によって内部被ばくを起こす。
- 晩発症状に甲状腺機能低下症がある。
▶午前36
A市の2地区でデータを収集した。各項目について地区間に差があるかどうかを統計学的に検定する。
χ2〈カイ2乗〉検定が適している項目はどれか。2つ選べ。
- 年齢
- 通院の有無
- 高血圧症の有病率
- 1日当たり飲酒量
- 1日当たり喫煙本数
▶午前37改題
日本の政府開発援助〈ODA〉について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 技術協力が含まれる。
- 国際協力機構〈JICA〉が援助を担っている。
- 援助開始以降、予算額は増加し続けている。
- 令和3年(2021年)の援助実績は援助国で最大である。
- 国連開発計画〈UNDP〉からの要請に基づき有償資金協力を行っている。
▶午前38
平成27年(2015年)に策定された認知症施策推進総合戦略〈新オレンジプラン〉の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 対象期間は20年間である。
- 目的は認知症高齢者の早期発見・早期治療である。
- 関係省庁で連携して取り組むことが示されている。
- 認知症施策を加速させるための戦略として5つの柱がある。
- 施策のアウトカム指標は定量的に評価することを目指している。
▶午前40
介護者のグループを育成するにあたり、初期段階における保健師の役割で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 活動計画の作成を支援する。
- 地域社会との関わりを強化する。
- グループ外からの支援を受けないよう助言する。
- 気の合うメンバー同士が活動を進められるよう配慮する。
- メンバーの発言を尊重して活動内容に取り入れるよう促す。
次の文を読み41〜43の問いに答えよ。
人口約1万人のA町は、後期高齢者が約3割を占める。町内に集落が点在しており、集落ごとに自治会の活動が活発である。休日の昼間、A町を震源とする震度6強の大規模な地震が発生した。建物の倒壊が見られ、下敷きになっている住民もいるとの情報があった。役場から約5kmの距離にある小学校に救護所が設置された。
▶午前41
地震発生30分後に、町の防災マニュアルに基づき、A町の保健師のうち1人が救護所となっている小学校に駆けつけることができた。
この保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 近隣住民へのボランティアの依頼
- 小学校の養護教諭への連絡
- 必要な医療物品の準備
- 県保健師への応援要請
▶午前42
地震発生当日に町内に避難所が設置された。1週後、町民の半数が避難所で生活を送っている。県外から派遣された医療チームが避難所での健康管理を行っている。
このときのA町保健師の活動で優先度が高いのはどれか。
- 避難所で傷病者の処置を行う。
- 町外への避難者の安否確認を行う。
- 避難所の高齢者の介護予防を行う。
- 避難所の要援護者の搬送先を検討する。
▶午前43
地震発生から2か月が経過した。小学校の近くに仮設住宅が設置され、避難者の大半が移った。住民の5割は自宅、4割は仮設住宅、1割は避難所で生活している。
このときのA町保健師の活動で最も適切なのはどれか。
- 町外施設に移った要介護者を訪問する。
- 避難所の住民の自治組織の立ち上げを支援する。
- 各集落の自治会長から住民の生活状況の情報を得る。
- 仮設住宅の住民に対して役場で運動教室を開催する。
次の文を読み45の問いに答えよ。
人口5万人の市。市の人口は平成20年度以降は変化はない。市はA、B及びCの3つの地区からなり、肺がん対策として検診の受診率の向上に取り組んでいる。市の肺がん検診は、平成26年度まではA地区の保健センターで行う集団検診のみであったが、平成27年度からはB地区にある病院でも検診を行っている。各地区の肺がん検診の受診者数および対象者数を表に示す。

▶午前45
C地区の地域診断を行ったところ、胃がん検診と大腸がん検診は肺がん検診より受診率が高く他の地区とも差がないことや、他の地区より喫煙率が高いことが分かった。また、過去10年間の肺がんによる死亡者18人のうち、肺がん検診の受診歴のない者が6人であった。
C地区の肺がん検診の受診率向上を目指して取り組む事業として優先度が高いのはどれか。
- 胃がん検診と同日での肺がん検診の実施
- がんの緩和ケアに関する講演会の開催
- がん登録事業の協力病院の拡大
- 肺がん検診の追加開催
- 禁煙教室の実施
次の文を読み46、47の問いに答えよ。
A市内にある、特別養護老人ホームを併設する病院から「特別養護老人ホームの入所者から消化器症状を訴える者が多発し、検便した結果、腸管出血性大腸菌が検出された」と1月24日に保健所に報告があった。保健師が調査したところ、週に1回、病院の医師が特別養護老人ホームの入所者の健康状態を確認していたことが分かった。看護・介護職員および調理従事者は、特別養護老人ホームと病院とでそれぞれ別の職員を雇用しており、施設間での行き来はなかった。給食は同じ食材を用い同じ方法で調理していたが、給食施設はそれぞれ独立していた。1月の発症日別の発症者数を表に示す。

▶午前46
感染が拡大した理由として最も可能性が高いのはどれか。
- 不適切な調理方法
- 病院の入院患者による媒介
- 原因菌による給食食材の汚染
- 特別養護老人ホームの看護・介護職員による媒介
▶午前47
今後の感染拡大を防止するために必要な措置のうち、検便の対象者として優先度が低いのはどれか。
- 病院の医師
- 病院の入院患者
- 特別養護老人ホームの入所者
- 特別養護老人ホームの調理従事者
- 特別養護老人ホームの入所者への面会者
次の文を読み48、49の問いに答えよ。
Aさん(50歳、女性、未婚)。28歳のときに統合失調症と診断され、43歳から7年間精神科病院に入院していた。両親は7年前に相次いで他界し、家族は姉(55歳、未婚)のみである。Aさんの病状が安定したため、Aさん姉妹は一緒に暮らすことを希望した。退院前に、病院内で地域の支援関係者を集めた会議が開かれ、Aさん姉妹も参加した。その際、姉が「妹と離れて暮らしていた期間が長いので不安はありますが、一緒に暮らせるのはうれしいです」と語っていた。退院後は市の保健師が家庭訪問することになった。
▶午前48
Aさんは姉との2人暮らしを開始した。
退院から7日後の初回の家庭訪問の目的として適切なのはどれか。
- 病院での退院指導内容の確認
- 就労移行支援サービス利用の勧奨
- 自宅での生活への適応状況の把握
- Aさん宅周辺の住民同士の交流状況の把握
▶午前49
初回訪問日の2週後に2回目の訪問を予定していたが、訪問予定日の3日前に、Aさんの姉から保健師に電話があった。姉は「一緒にしようと促しても妹は家事をしたがらず、何でも私に頼ってきます。私はイライラして、妹と口論になることが増えてきました。私自身、3、4日前から食欲がなく、体がだるいため家事をするのも大変です。このまま妹との生活を続けることに自信がなくなりました」と話した。
このときの姉への助言として適切なのはどれか。
- 「Aさんの再入院を考えてみましょう」
- 「Aさんの主治医に対応を相談してみましょう」
- 「食欲不振などの症状は一時的なものなので心配はいりませんよ」
- 「Aさんとの口論を近所の人たちに聞かれないように注意しましょう」
次の文を読み50、51の問いに答えよ。
Aさん(59歳、女性)。夫(66歳、無職)と2人暮らし。市の健康相談に参加したAさんは、ふらつきがあり歩行が不安定であった。相談に対応した保健師に対して「歩き出しがうまくできないし、思うように体が動かず困っています」とAさんは話した。保健師はAさんの訴えなどから神経変性疾患を想定し、Aさんの他の症状について確認することにした。
▶午前50
確認する症状として優先度が高いのはどれか。
- 耳鳴の有無
- 振戦の有無
- 視野欠損の有無
- 手足の浮腫の有無
▶午前51
その後、Aさんは指定難病と診断され、隣市の専門医療機関での月1回の通院治療を開始した。2年後、Aさんは要介護4に認定され、通所介護を週2回利用している。Aさんの介護と家事は夫が担っている。夫は糖尿病で半年ほど前から血糖コントロールが不良であり、血糖管理および指導の目的で5日間の入院を勧められている。
夫の入院中にAさんが利用する事業で最も適切なのはどれか。
- 夜間対応型訪問介護
- 短期入所療養介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
次の文を読み52、53の問いに答えよ。
A市では保育所を利用している家庭が増加しており、対応困難な児に関する保育士からの市保健師への相談が増えてきている。A市では子育て支援を強化するため、次年度の母子保健計画の策定にあたって、市内の15か所の保育所との連携システムをどのように構築していくかを検討することになった。
▶午前52
保健師が最初に取り組むこととして適切なのはどれか。
- 対応困難な児の保護者に保育所でインタビュー調査を行う。
- 市のホームページでパブリックコメントを募集する。
- 対応困難な事例の検討会を保育所と行う。
- 対応困難な児の家庭訪問をする。
▶午前53
保育所との連携システムの構築に取り組んでから3か月が経過した。その評価から母子保健担当の保健師は、保育所を定期的に巡回し、個別相談が必要な児に対して健康相談を行う巡回健康相談事業を検討している。
事業を計画するにあたり最初に検討するのはどれか。
- 事業評価の時期
- 事業担当者の確保
- 巡回健康相談の実施回数
- 保育所利用者に対する事業の広報
- 母子保健計画における事業の位置付け
次の文を読み54、55の問いに答えよ。
Aさん(80歳、女性)。1人暮らし。高血圧症で50歳から近くの医療機関を受診しており、降圧薬を内服し、自己管理をしながら自立して生活していた。長女(55歳)は他県に住み、月1回Aさんの様子をみに来ている。長女は、地域包括支援センターに来所し「母が物を探すことが多くなったと感じていたが、隣人から母が近所で道に迷っているのを見かけたと聞き、心配になった」と保健師に相談した。
▶午前54
このときに保健師が長女に勧める内容で最も適切なのはどれか。
- 保健所への相談
- かかりつけ医への相談
- 介護療養型医療施設の見学
- 認知症サポーター講座の受講
▶午前55
その後、Aさんは要支援1と認定された。長女は電話で「最近母が、病院でお金を支払うことや、ATMでお金をおろすことができなくなった」と地域包括支援センターの保健師に相談した。
保健師が勧める社会資源として優先度が高いのはどれか。
- 成年後見制度
- 消費者生活センター
- 訪問看護ステーション
- 介護予防・日常生活支援総合事業
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
第103回保健師国家試験・午後(55問)
▶午後1
地域における看護活動で用いるポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチについて正しいのはどれか。
- ケーブルテレビによる健康講座はハイリスクアプローチである。
- ポピュレーションアプローチでは健康問題のない集団に働きかける。
- 住民全体の健康レベルの向上にはハイリスクアプローチが適切である。
- 生活習慣病の受療者への健康教育はポピュレーションアプローチである。
▶午後2
市町村の保健師の活動として適切でないのはどれか。
- 細菌性赤痢の患者の積極的疫学調査
- 老人クラブでの健康教育の実施
- 統合失調症患者への家庭訪問
- 16歳の妊婦への保健指導
▶午後3
社会保障・税一体改革において推進する保健福祉事業はどれか。
- 保育サービスに係る量の拡充
- 障害者の虐待防止
- がん登録の推進
- 自殺の予防
▶午後4
地球温暖化対策と根拠の組合せで正しいのはどれか。
- グリーン経済への移行――特定家庭用機器再商品化法
- オゾン層の保護に向けた取り組み――アジェンダ21
- 先進国の温室効果ガスの排出量の削減――京都議定書
- 気候変動に関する国際連合枠組条約の批准――リオ+20
▶午後5
Aさん(39歳、初妊婦)。妊娠26週で市の母親学級に参加した。Aさんは、あまり楽しそうな表情をしておらず、グループワークでの発言も少なかった。終了後に母親学級担当の保健師がAさんに声をかけたところ「産後の育児が不安です」と話した。
不安な気持ちについて傾聴した後のAさんへの対応として最も適切なのはどれか。
- 「産後にホームヘルプサービスを利用してはどうですか」
- 「お住まいの地区を担当している保健師を紹介します」
- 「受診している産科の医師に相談してみましょう」
- 「育児に慣れるまで里帰りすることはできますか」
▶午後6
A市のB地区は肥満者の割合が市内の他の地区に比べて高い。B地区の担当保健師が健康相談を実施した際、夜食を摂る者が多くいることが分かった。
B地区の担当保健師の活動で最も優先されるのはどれか。
- 食生活改善推進員へのフォーカス・グループインタビュー
- 市の栄養士による栄養相談内容の分析
- 地区住民を対象とした食生活実態調査
- 国民健康保険の医療費分析
▶午後7
健康教育に関する理論で保健行動に対する個人の心理に着目しているのはどれか。
- アドボカシー
- ヘルスリテラシー
- ヘルス・ビリーフ・モデル
- プリシード・フレームワーク
▶午後9
健康診査の結果説明会で、受診勧奨の対象ではなかったが、血圧が高い者が8人いた。保健師は、メンバー間の相互作用を促しながら、生活習慣病を予防することを目的としたグループを作り支援を行うことにした。
このグループへの支援として最も適切なのはどれか。
- 他のグループと交流する機会を設ける。
- グループで1つの血圧の目標値を設定する。
- 高血圧症の専門医の講義を聞く機会を設ける。
- メンバーが各自の食生活の課題を話し合う機会を設ける。
▶午後10
インフルエンザの予防接種について正しいのはどれか。
- 二次予防である。
- ワクチンの種類はトキソイドである。
- 予防接種法におけるB類疾病である。
- 定期予防接種の対象は15歳未満である。
▶午後11
次年度の地域保健活動計画を立案するにあたって、保健師が最初に取り組むのはどれか。
- 福祉部門と計画について話し合う。
- 地域の医療機関の要望を確認する。
- 今年度の地域における保健活動の実績を評価する。
- 医療や福祉に関する施設整備計画の進捗状況を確認する。
▶午後12
肺がん罹患率が高いことから、市の健康増進計画で喫煙率の低下を目標とし、禁煙相談事業を実施した。
事業の評価の種類とその指標の組合せで正しいのはどれか。
- プロセス評価――肺がんの受療率
- 影響評価――禁煙相談事業参加者の禁煙に関する理解度
- 成果評価――肺がん検診の受診者数
- 成果評価――禁煙相談事業の参加者数
▶午後13
母子保健推進員について正しいのはどれか。
- 法律で定められた研修を受ける必要がある。
- 都道府県知事からの委嘱を受ける。
- 行政と住民とのパイプ役である。
- 母子保健法に規定されている。
▶午後14
Aさん(22歳、女性、専業主婦)。夫と生後2か月の児との3人暮らし。他県からB市へ転入直後に、住民票の手続きのため市役所を訪れた。保健師は3か月児健康診査や保健事業について説明をした。Aさんは「初めての育児なので不安なことが多いです。夫は残業が多いため帰りが遅く、両親は遠くに住んでいるので頼れない。慣れない土地でどこに何があるかもよく分からないんです」と話した。
このとき、保健師がAさんに紹介する社会資源として適切なのはどれか。
- 母子生活支援施設
- 児童家庭支援センター
- 母子・父子休養ホーム
- 地域子育て支援センター
▶午後15
国民健康づくりの目標として初めて自殺者の減少を掲げたのはどれか。
- 第一次国民健康づくり対策
- 第二次国民健康づくり対策〈アクティブ80ヘルスプラン〉
- 第三次国民健康づくり対策〈健康日本21〉
- 第四次国民健康づくり対策〈健康日本21(第二次)〉
▶午後16
日本の学校看護婦の歴史で正しいのはどれか。
- 学校医よりも先に配置された。
- 特定の科目の修得によって認定された。
- 欧米のスクールナースがモデルになった。
- トラコーマの洗眼や点眼を行うために始まった。
▶午後19
研修において面接技法の修得に適している学習方法はどれか。
- 事例検討
- ロールプレイ
- e―ラーニング
- 専門家による講義
▶午後20
標準化死亡比〈SMR〉を求めるために必要な指標はどれか。
- 基準集団の死亡率
- 基準集団の年齢別人口
- 観察集団の年齢別人口
- 観察集団の年齢別死亡率
▶午後21
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉で規定されている地域相談支援について正しいのはどれか。
- 地域定着支援を行う。
- 利用者の負担額は1割である。
- 障害支援区分の認定が必要である。
- 指定特定相談支援事業者が実施する。
▶午後22
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉について正しいのはどれか。
- 予防接種を行う疾病を定めている。
- 十分な説明と同意に基づいた入院勧告制度がある。
- 特定感染症指定医療機関は都道府県知事が指定する。
- 4類感染症を診断した医師は7日以内に届出を行わなければならない。
▶午後23
地域保健法における市町村の役割で正しいのはどれか。
- 健康危機管理の拠点
- 食品衛生に関する指導
- 関係機関への技術的な援助
- 地域保健対策に必要な人材の確保
▶午後24
障害児の放課後等デイサービスの定義を定めている法律はどれか。
- 児童福祉法
- 学校保健安全法
- 発達障害者支援法
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
▶午後25改題
令和4年(2022年)の日本における各年代と年代別死因第1位の組合せで正しいのはどれか。
- 20歳代――自殺
- 30歳代――悪性新生物〈腫瘍〉
- 40歳代――心疾患
- 50歳代――脳血管疾患
- 60歳代――肺炎
▶午後26
患者調査で把握できるのはどれか。
- 有訴者率
- 死亡率
- 致命率
- 有病率
- 受療率
▶午後27
妊娠前期の母親学級のプログラムに取り入れる歯科保健のテーマで優先度が高いのはどれか。
- 歯周疾患の予防
- フッ素化合物の効果
- 甘味食品の摂取制限
- 乳児の歯磨きの方法
- 小児の咀嚼機能の発達
▶午後28
ケアマネジメントについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- 導入する社会資源を検討する。
- 専門職の判断を優先してケアプランを作成する。
- 法律に基づいた制度を活用することが原則である。
- 利用者はサービス担当者の会議に参加することはない。
- 継続的なケアを行うには関係機関の連携が重要である。
▶午後29
地域包括ケアシステムの推進に向けて、実務者が集まって地域ケア会議を開催することにした。
地域ケア会議で取り扱う内容として正しいのはどれか。2つ選べ。
- 個別事例の検討を行う。
- ケアプランを作成する。
- 介護保険事業計画を策定する。
- 地域にある社会資源の課題を共有する。
- 地域支援事業の予算配分について検討する。
▶午後30
産業保健総合支援センターについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- 衛生管理者の選任を行う。
- 特殊健康診断の委託を受ける。
- 事業者に対する研修を実施する。
- 産業保健に関する情報提供を行う。
- 労働基準監督署ごとに設置されている。
▶午後31
特殊災害に分類されるのはどれか。2つ選べ。
- 原子力発電所の事故による放射線の漏えい
- 石油タンカーの座礁による海水の汚染
- 列車の脱線による交通網の障害
- 大雨による河川の氾濫
- 地震による橋の崩落
▶午後32
国民健康・栄養調査で把握できるのはどれか。2つ選べ。
- 健康寿命
- BMIの平均値
- 蛋白質の必要量
- 喫煙習慣者の割合
- 支出に占める食料費の割合
▶午後33
平成25年(2013年)に「地域における保健師の保健活動に関する指針」が改正された背景について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 健康日本21の策定
- 特定健康診査の導入
- 障害者の支援費制度の導入
- 地域包括支援センターの設置
- 感染症から生活習慣病への疾病構造の変化
▶午後34
因果関係を推測することができる研究デザインはどれか。2つ選べ。
- 横断研究
- 記述疫学
- 生態学的研究
- コホート研究
- 症例対照研究
▶午後35
心筋梗塞発症者100人と性・年齢をマッチングした心筋梗塞非発症者100人の5年前の健康診査の結果を調査し、糖尿病の有無を確認した。その結果、心筋梗塞発症者で20人、心筋梗塞非発症者で15人が糖尿病であった。
糖尿病であることの心筋梗塞発症に対するオッズ比を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:① . ②
次の文を読み36〜38の問いに答えよ。
Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。近所に住む友人のBさん(60歳、男性)からAさんについて地域包括支援センターの保健師に相談があった。Aさんは3年間介護していた妻が半年前に亡くなってから痩せ、最近は外であまり見かけなくなったという。翌日、保健師が民生委員に状況確認の連絡をしたところ、Aさんの現在の状況を把握していなかった。保健師はAさんの状況を把握するため、来週Bさんと一緒に家庭訪問を行うことにした。
▶午後36
家庭訪問時に収集すべき情報として最も優先度が高いのはどれか。
- 既往歴
- 毎日の食事内容
- 友人との交流状況
- 直近の健康診査の結果
- 自治会活動への参加状況
▶午後37
保健師がBさんとともに家庭訪問したところ、Aさんは訪問に戸惑っていたが、玄関先で話をしてくれた。Aさんの服装に乱れはなかった。室内にはごみ袋がいくつか置いてあり、捨てられていないようであった。Aさんは、少しずつ自分のことを話し始め「妻が亡くなってから楽しいことはなく、外に出かけたくない」と言い、表情は暗かった。Bさんが何か手伝うことがないか尋ねるとAさんは「心配してくれてありがとう。でも今は1人でいたいです」と言った。保健師は3日後に1人で訪問することを伝え、この日は訪問を終了した。
保健師の次回の訪問計画で適切なのはどれか。
- 外出の重要性を説明する。
- ごみを片付けるよう促す。
- 精神科への受診を勧める。
- 妻との別れを一緒に振り返る。
- ホームヘルプサービスの利用を勧める。
▶午後38
保健師は2週に1回の家庭訪問を続け、Aさんとの信頼関係が構築されてきた。Aさんは家の中を少しずつ整理し、散歩にも出かけるようになった。保健師の初回訪問から3か月後、Aさんから「亡くなった妻のためにも、自分が少しでも長生きしなければと思うようになったが、何をしたらよいのか分からない。少しずつ外に出てみようと思うが、人付き合いにはあまり自信がない」と相談があった。
Aさんに勧めることとして最も適切なのはどれか。
- 地域包括支援センター主催の介護予防教室への参加
- 老人福祉センターでのサークル活動への参加
- 高齢者サロンのボランティアへの登録
- シルバー人材センターへの登録
次の文を読み39〜41の問いに答えよ。
Aさん(40歳、男性)。妻と2人暮らし。Aさんは3年前に転職し、従業員数30人のコンピュータ関連の事業所に勤務している。6か月前から軽い咳が続いていたが、メンバー数5人の新規プロジェクトチームの責任者として忙しく、そのままにしていた。妻に痩せてきたことを指摘され、自宅近くの診療所を受診したところ、胸部エックス線写真で異常陰影があり病院を紹介され受診した。喀痰塗抹菌検査陽性、結核菌PCR陽性となり、肺結核と診断され入院した。診断した医師から保健所に結核発生の届出があった。
▶午後39
保健所の保健師がAさんに初回面接で確認する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 出勤状況
- 転職前の職場
- 運動習慣の有無
- 結核に対する認識
- 特定健康診査の結果
▶午後40
接触者健康診断を実施したところ、妻が感染し、プロジェクトチームのうち1人が発病し、2人が感染していることが分かった。
保健所が次に行う対策として最も適切なのはどれか。
- 事業所の消毒
- 健康相談窓口の設置
- 接触者健康診断の拡大実施
- 地域の医師会への結核発生報告
▶午後41
保健所の保健師は、今回の事例を踏まえ、管内の事業所を対象に結核に関する正しい知識を啓発するためにリーフレットを作成することにした。
リーフレットに掲載する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 「従業員のBCG接種を推奨します」
- 「定期的に作業場の換気をしましょう」
- 「結核は治療をすれば3か月で治ります」
- 「健康診断は6か月ごとに受診しましょう」
- 「咳が2週間以上続くときは医療機関を受診しましょう」
次の文を読み42〜44の問いに答えよ。
Aちゃん(9歳、女児)。4か月前から母親と親しくなった男性との3人暮らしを始めている。Aちゃんは「新しいお父さんができた」と喜んでいたが、1か月前から忘れ物が多くなり、この1か月に4日欠席をしている。担任が連絡をしたところ、母親から「家庭内のことに関わらないで欲しい」と激しい口調の拒絶を受けた。保健室で休むことも多くなったため、養護教諭がAちゃんに確認したところ、母親と男性が出掛けて戻らない日が多く、Aちゃんは菓子パンなどを買って食べているとのことであった。
▶午後42
養護教諭や担任などが集まって対応を協議した。
対応を協議する根拠となったAちゃんの状況はどれか。
- 低栄養
- 不登校
- ネグレクト
- 引きこもり
▶午後43
3日後、専門機関によるAちゃんへの支援が開始された。その後のAちゃんの出欠状況や家庭環境の変化などについて、専門機関から学校に定期的な情報提供の依頼があった。
窓口となった養護教諭の対応として適切なのはどれか。
- 情報提供は保護者の同意がなければ行わない。
- Aちゃんから情報収集するよう伝える。
- 3か月に1回情報提供を行う。
- 情報提供は書面で行う。
▶午後44
養護教諭は、Aちゃんのような児童が他にもいるのではないかと考え、これまでの発育および欠席状況による確認に加え、新たな対策を立てることとした。
緊急に対応する必要性の高い児童を抽出するための方法で最も適切なのはどれか。
- 学校教職員を対象にした研修会の実施
- 忘れ物の多い児童の把握
- 担任による親子面談
- 児童への食生活調査
次の文を読み45〜47の問いに答えよ。
運動習慣の死亡率に対する影響の調査のために1万人を対象とした10年間のコホート研究を行った。本研究では、年齢、食習慣および経済状況など参加者の基礎的背景も併せて調査した。脱落者を除いた結果を表に示す。

▶午後45
運動習慣があることに対して、運動習慣がないことの疾患Aによる死亡に関する1万人対の寄与危険はどれか。
- 0.4
- 0.7
- 1.4
- 10
- 40
▶午後46
運動習慣と死亡との関連が最も強いのはどれか。
- 疾患A
- 疾患B
- 疾患C
- その他の疾患
▶午後47
参加者の基礎的背景を補正しても、「運動習慣あり」の方が死亡率は有意に低かった。しかし、この結果からは「運動すれば長生きできる」という結論を導くことはできない。
その理由はどれか。
- 介入研究ではない。
- 情報バイアスがある。
- 二重盲検がされていない。
- 平均余命で比較していない。
次の文を読み48、49の問いに答えよ。
Aちゃん(生後5か月、女児)。父親(37歳)、母親(35歳)は病院の近くの市に2人で暮らしており、Aちゃんの祖父母は遠方に住んでいる。AちゃんはGCUに入院中である。
現病歴:在胎32週で羊水過多、胎児発育不全、心臓奇形および小脳低形成のため羊水の染色体検査を受け、18トリソミーと診断された。在胎週数37週0日、体重1,780gで出生し、NICUに入院した。食道閉鎖のため出生当日に胃瘻造設術を、気管軟化症のため生後3か月に気管切開術を受けた。気管切開下で24時間人工呼吸器管理、30分に1回程度の気管内吸引を実施している。
家族歴:特記すべきことはない。
身体所見:体重2,900g。体温37.0℃、脈拍130/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉94〜96%。定頸していない。
▶午後48
両親ともにAちゃんの退院を心待ちにしている。2か月以内の自宅への退院を目指すため、病院から保健所に退院調整カンファレンスへの参加依頼があり、地区担当保健師は事前に自宅を訪問することとした。
このときの訪問で保健師が両親から収集する情報で適切なのはどれか。
- 今後の治療方針
- 療育手帳の申請の有無
- 今後の予防接種の計画
- 自宅の療養環境の準備
▶午後49
家庭訪問から1週後、両親、主治医、病棟看護師、理学療法士、退院調整看護師、社会福祉士、訪問看護師および地区担当保健師が出席して、初回の退院調整カンファレンスが行われた。両親は退院後の生活に不安はあるものの、Aちゃんの面倒は自分達がみるべきであると考え、できるだけ他者の手を借りずに育てたいと思っているということであった。今後の方針として、小児科の一般病棟に転棟し、在宅療養に向けた医療的ケアの手技や育児の練習を行い、その後に自宅への外泊訓練を実施することが決まった。次回のカンファレンスは、院内で在宅療養に向けたシミュレーションを行った後、医療的ケアの手技などの習得状況の評価と外泊訓練に向けた準備について話し合う予定である。
次回のカンファレンスに参加を依頼する機関として優先度が高いのはどれか。
- 医療型児童発達支援センター
- 訪問診療を実施している診療所
- 医療型短期入所を実施している療育施設
- 訪問リハビリテーションを実施している事業所
次の文を読み50、51の問いに答えよ。
A県では50歳代の男性の自殺が増加傾向にあり、自殺予防対策の必要性が検討された。自殺者数が多いB市において、県と市が共催で自殺予防事業を実施することになった。
▶午後50
A県から事業実施の打診を受けたB市では、保健師を中心にプロジェクトチームを立ち上げることになった。
プロジェクトチームの参加機関として優先度が高いのはどれか。
- 精神保健福祉センター
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 県医師会
▶午後51
プロジェクトチームで検討した結果、地域における自殺予防の意識を高め、支援者を増やすため、ゲートキーパー養成の事業を実施することになった。まずは、市職員を対象に養成講座を実施し、民生委員やボランティアなどへ対象を段階的に広げてゲートキーパーを増やしていくこととした。講座の受講者からは「自殺予防の必要性を強く感じた」、「自殺予防のために自分にもできることがあることが分かった」などの意見が多く聞かれ、受講者数も増え続けたため、B市ではこの事業を継続することにした。
B市での事業の結果を受けて、A県で検討する内容として適切なのはどれか。
- 自死遺族の相談事業
- 他市町村への事業の展開
- ハイリスク者への家庭訪問
- 50歳代男性への質問紙調査
次の文を読み52、53の問いに答えよ。
Aさん(45歳、女性、会社員)。夫と2人暮らし。Aさんが勤務する会社では保健師が職員の健康管理のために面接による相談事業を実施している。Aさんは定期健康診断を受診し、結果は身長160cm、体重55kg、BMI21、血圧118/70mmHg。トリグリセリド90mg/dL、HDLコレステロール70mg/dL、LDLコレステロール139mg/dL、HbA1c5.0%、AST〈GOT〉20IU/L、ALT〈GPT〉15IU/L、γ-GTP20IU/Lであった。既往歴に特記すべきことはなく、現在治療中の疾患はない。飲酒はビール350mL/日を週5日、喫煙はしていない。
▶午後52
健康診断の結果から控えるよう指導するのはどれか。
- 食物繊維
- 飽和脂肪酸
- アルコール
- 総エネルギー量
▶午後53
保健師はAさんの健康診断の結果を受け、行動変容に向けて面接を行った。Aさんは「管理的な立場で仕事をしているため、帰宅は遅く21時くらいになってしまいます。家事もあり毎日が忙しいので、体調を崩したら困るなと思ってはいますが、具合が悪いところもないので具体的には何もしていません」と話した。
行動変容のステージから判断してAさんへの保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 生活パターンの問題を指摘する。
- 健康診断の結果の理解度を確認する。
- 生活習慣の改善に向けた目標を一緒に立てる。
- 生活習慣の改善に向けて夫の協力を得るように伝える。
次の文を読み54の問いに答えよ。
Aさん(39歳、女性、教員)。夫(40歳、会社員)と長男(7歳)との3人暮らし。Aさんは小学校で6年生の担任をしている。夫は仕事で土日も不在のことが多い。長男は放課後に学童保育に通っている。Aさんは2か月間月経がみられないため、自宅近くの産婦人科を受診したところ妊娠11週と診断され、妊娠届を提出するよう指導された。妊娠16週に妊娠届を提出するため保健センターに来所した。保健センターでは、妊娠届の提出に来所した妊婦全員に保健師による面接を実施している。保健師は現在の健康状態、妊娠経過および分娩予定施設についてAさんに確認した。
▶午後54
今後のAさんへの支援を計画するために最も優先して確認するのはどれか。
- つわりの有無
- 育児用品の準備状況
- 妊娠届が遅れた理由
- 子宮がん検診の受診歴
- 不妊治療の経験の有無
次の文を読み55の問いに答えよ。
Aさん(66歳、女性)。夫(70歳)が早期の直腸癌と診断され、手術を受けた直後に死亡した。1か月後、Aさんは、医療安全支援センターの相談窓口が設置されている保健所に、電話で相談し「主治医から簡単な手術だと説明を受けて手術に同意したが、夫は手術後に亡くなった。納得できないので調査して欲しい」と訴えた。Aさんの希望で、保健所が病院に対して文書でAさんの夫の治療経過を照会したところ「Aさんの夫はまれに発生する術後合併症によって死亡した。術後合併症のことは、患者とAさんとに事前に説明していた。医療事故とは考えていない」と回答があった。
▶午後55
保健所の対応で適切なのはどれか。
- Aさんと病院とで話し合いの場が持てるように支援する。
- Aさんの夫の手術に関する診療録を病院に開示請求する。
- 医療行為と死亡との因果関係の有無を明らかにする。
- 病院に対し事故調査委員会を設置するよう指導する。
資料 厚生労働省「第103回保健師国家試験、第100回助産師国家試験、第106回看護師国家試験の問題および正答について」
平成30年2月16日実施の第104回保健師国家試験の全問題と正答を掲載します。
また、内容に応じて保健師国家試験受験者の必携テキスト「国民衛生の動向2024/2025」の参照章・ページを示します。問題を解きながら本誌を確認することで、より問題の理解を深めることできます。
分野別解説付き問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の感染症問題まとめ
- 保健師国家試験 疫学・保健統計学問題まとめ
を合わせて活用しながら、合格に近づく過去問対策を進めて頂ければ幸いです。
なお、最新の統計の記載、法律の改正、不適切問題などにより、一部問題を改変、削除しています。
 |
厚生の指標増刊
発売日:2024.8.27 定価:2,970円(税込) 412頁・B5判 雑誌コード:03854-08
ご注文は書店、または下記ネット書店、電子書籍をご利用下さい。 |
ネット書店
電子書籍
第104回保健師国家試験目次
第104回保健師国家試験・午前(55問)
▶午前1
保健師に関する歴史上の出来事と社会的背景の組合せで正しいのはどれか。
- 開拓保健婦の設置――外地からの引き揚げ
- 駐在保健婦制度の創設――社会恐慌や凶作による農村の荒廃
- 国保保健婦の市町村移管――第一次ベビーブーム
- 小児保健所での保健婦活動――富国強兵策
▶午前2
保健師について正しいのはどれか。
- 保健師の記録の保存について保健師助産師看護師法に規定されている。
- 管轄する保健所長の指示を受けた場合はそれに従わなければならない。
- 保健師免許の申請には看護師免許の写しが必要である。
- 保健指導を業務独占としている。
▶午前3
市では、発達障害がある者の家族から、特別支援学校卒業後に地域で働きたいと希望しても周囲の理解が得られないので悩んでいるとの相談が増加した。保健師は発達障害がある者を支援する地域ケアシステムが必要と考えた。
地域ケアシステムの構築を最も推進する活動はどれか。
- 家族会の設立
- 就労相談会の開催
- ボランティアの育成
- ネットワーク会議の開催
▶午前4改題
令和4年(2022年)の労働力調査について正しいのはどれか。
- 女性の労働力人口は前年に比べ減少した。
- 女性の雇用形態は正規の雇用が約6割である。
- 労働力人口の総数に占める女性の割合は約45%である。
- 女性雇用者数に占める割合で最も多い産業は製造業である。
▶午前5
Aちゃん(1歳8か月、女児)は、1歳6か月児健康診査を受診した。1人で歩けるが有意語の発語はなく、絵本の指さしはしない。個別相談で言葉の発達について経過を観察したいと保健師が伝えると、母親は「そのうち言葉は出ると思うので心配はしていません。今、妊娠7か月で、疲れたので早く帰りたいです」と言う。
Aちゃんのフォローアップをするための保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 「出産後に連絡してください」
- 「3歳児健康診査のときに確認します」
- 「病院の発達相談を受診してください」
- 「1か月後に電話でAちゃんの様子を聞かせてください」
▶午前6
変化ステージ理論について正しいのはどれか。
- 対象者の行動変容の段階に合った保健指導に有用である。
- 糖尿病に対する行動変化の研究から見出された。
- 解凍、変化、再凍結の3段階がある。
- ステージは後戻りしない。
▶午前7
ヘルスリテラシーについて誤っているのはどれか。
- 健康管理を行うために活用するスキルである。
- ヘルスプロモーションの活動に関わる能力である。
- 情報提供の方法が適切か検討することが含まれる。
- 健康日本21(第二次)の目標にヘルスリテラシーの向上が挙げられている。
▶午前8
Aさん(60歳、女性)は、隣に住むBさん(48歳、男性)についての相談のため、初めて保健所に来所した。「Bさんは以前から酒好きで、仕事が休みの日には朝から酒を飲んでいることがよくあった。ここ1か月ほどは仕事にも行かず、泥酔して大声で騒ぎ、家の中で暴れているようだ」と言う。
初回相談の際のAさんへの地区担当保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- Bさんの勤務の状況を聴取する。
- 飲酒が身体に及ぼす影響を説明する。
- Aさんが今回相談に来所した目的を確認する。
- Bさんを医療機関に受診させるための協力を依頼する。
▶午前9
A市では特定健康診査の結果から、定年退職後の60歳代の男性は同年代の女性と比較して、退職後数年でHbA1cが基準値を超える者の割合が高いことが分かった。また、問診票から、日中は1人で過ごし昼食も1人で摂ることが多く、食事は全体的に外食や市販の惣菜に偏っていることが把握された。
定年退職後の男性を対象とし、地域への波及効果も目的とした糖尿病予防事業として最も適切なのはどれか。
- 食事の記録をつけてもらい栄養士が評価する。
- 高血糖を予防する食事のパンフレットを郵送する。
- 特定健康診査で高血糖を予防するための個別相談を行う。
- 高血糖を予防する食事づくりの調理実習をグループで行う。
▶午前10
Aさん(24歳、専業主婦)は、夫と生後6か月の乳児(出生体重2,900g)との3人暮らし。乳児健康診査が未受診で、電話にて受診勧奨を行ったが来所しないため、地区担当保健師が家庭訪問をした。訪問時、児の体重は7,500g。定頸しており、寝返りはできるがお座りはできない。「離乳食を開始したばかりで、進め方が分からない」と言うので、保健指導を行った。乳児健康診査については「風邪気味だったので連れて行けなかった。人付き合いが苦手で育児の相談相手もいないので、戸惑うことが多い」と話した。
今後の保健師の対応として最も適切なのはどれか。
- 市の育児相談の利用を勧める。
- 定期的な家庭訪問を継続する。
- 地域の子育てサークルの立ち上げを促す。
- 児の発達について小児科医に相談することを勧める。
▶午前11
保健師が行う地区活動について最も適切なのはどれか。
- 主に質的なデータを用いて評価する。
- 地区にある社会資源の範囲で活動する。
- 医療機関との連携を中心にして展開する。
- 住民登録の有無にかかわらず地区に居住する者を対象とする。
▶午前12
介護保険法で規定される市町村介護保険事業計画の日常生活圏域について正しいのはどれか。
- 市町村が範囲を設定する。
- 高齢者の人口で数を決める。
- 二次医療圏と同規模である。
- 介護保険法制定時に定められた。
▶午前13
健康日本21(第二次)の目標達成を目指した市計画を定めることにした。
住民の意見を幅広く取り入れる方法として最も適切なのはどれか。
- 計画素案の作成を市内の業者に委託する。
- 市民相談を担当する職員を策定委員に選任する。
- 計画策定の過程でパブリックコメントを求める。
- 前年実施した市民健康意識調査の結果を計画に盛り込む。
▶午前14
健やか親子21の主な指標の最終評価で正しいのはどれか。
- 10代の性感染症〈STI〉罹患率が増加した。
- 妊娠11週以下での妊娠の届出率が増加した。
- 全出生数中の極低出生体重児の割合が減少した。
- 育児期間中の両親の自宅での喫煙率が増加した。
▶午前15改題
計画と目標の組合せで正しいのはどれか。
- 健康日本21(第二次)――若年性認知症施策の強化
- 健やか親子21(第2次)――若い世代を中心とした食育の推進
- 第3期がん対策推進基本計画――受動喫煙対策の徹底
- 第五次薬物乱用防止五か年戦略――不適切な飲酒の誘因の防止
▶午前16
Aさん(28歳、男性)。8年前に統合失調症を発症し長期入院をしていたが、6か月前に退院し、自宅で母親と2人で暮らしている。母親から「退院時から通っていたデイケアに2週間ほど行っていません。食事は私と一緒に食べていて、服薬もできていますが、それ以外はあまり部屋から出てきません。デイケアの職員には少し様子をみるようにと言われましたが、心配で仕方がありません。こういうときはどうすれば良いでしょうか」と地区担当保健師に電話があった。保健師が家庭訪問したところ、Aさんは「デイケアにはそのうち行きます」と言って部屋に戻った。
このときに保健師が母親へ助言する内容で最も適切なのはどれか。
- 「すぐに主治医に相談してください」
- 「別のデイケア施設の見学に行きませんか」
- 「なるべく外に出かけることをAさんに勧めてください」
- 「家族会に参加して他の家族のお話を聞いてみてはいかがですか」
▶午前17
高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について正しいのはどれか。
- 施設に入所する高齢者への予防接種の実施は都道府県知事の責務である。
- 平成28年(2016年)4月から定期の予防接種が開始された。
- 予防接種法による健康被害の救済措置の対象となる。
- 予防接種法においてA類疾病に指定されている。
▶午前18
介護保険制度について正しいのはどれか。
- 利用者は居宅介護サービス計画を作成するための費用の1割を負担する。
- 介護保険認定の申請手続きの代行は被保険者の家族以外はできない。
- 利用者の日常生活能力の自己申告に基づき要介護認定が行われる。
- 利用者の選択によってサービスを決定することが基本である。
▶午前19改題
石綿による疾病に関する労災保険給付の支給決定件数で正しいのはどれか。
- 平成18年度(2006年度)がピークである。
- 平成22年度(2010年度)から令和3年度(2021年度)まで連続して増加している。
- 令和3年度(2021年度)では中皮腫より肺がんの方が多い。
- 令和3年度(2021年度)の肺がんに対する支給は1,000件を超えている。
▶午前21
災害時の健康危機管理における保健所の役割はどれか。
- 避難所の指定
- 傷病者の広域搬送
- 災害対策本部の設置
- 健康被害の拡大防止
▶午前22
在宅で人工呼吸器管理を要する難病患者の災害時の個別支援計画で適切なのはどれか。
- 自宅待機を想定に入れる。
- 避難先は災害拠点病院とする。
- 発災直後の安否確認は主治医が行う。
- 発災後の移動は災害派遣医療チーム〈DMAT〉が担当する。
▶午前23
A市では、今年から特定健康診査と特定保健指導を同じ事業者に委託し、市は市民への広報、受診勧奨、未受診者の支援を行うこととした。
委託した事業者の保健指導の質を評価する指標はどれか。
- 特定健康診査の受診率の変化
- 特定保健指導の対象者の割合
- 特定保健指導の未受診者の割合
- 特定保健指導前後のBMIの変化
▶午前24
職場における新人保健師の人材育成で最も適切なのはどれか。
- 職場外での研修を中心に行う。
- 新人保健師自身が自らの到達目標を設定する。
- 新人保健師が所属する部署で完結した指導体制とする。
- 新人保健師が活動事例を学会で発表することを最終目標とする。
▶午前25
A市の20歳から24歳までの年齢層における死因の内訳を表に示す。

表に示した内容を図で表現する場合に適しているのはどれか。
- 散布図
- 円グラフ
- 折れ線グラフ
- ヒストグラム
▶午前26
地域保健法に規定されている内容はどれか。
- 市町村保健センターの所長は原則として医師である。
- 市町村に対する必要な財政的援助は都道府県の責務である。
- 保健所には所管区域内の市町村職員の研修の実施が義務付けられている。
- 保健所が行う事業に母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項がある。
▶午前27
介護保険法に基づく地域支援事業について正しいのはどれか。
- 実施主体は保健所である。
- 包括的支援事業が含まれる。
- 家族介護を支援する事業はない。
- 地域支援事業に係る費用は介護報酬から支払われる。
▶午前28
がん患者の在宅療養支援における医療保険および介護保険の活用について正しいのはどれか。
- 同日に医療保険と介護保険の利用はできない。
- 居宅療養管理指導は医療保険による診療報酬の対象である。
- 訪問看護の利用にあたっては医療保険と介護保険のいずれかを利用者が選択できる。
- 40歳から65歳未満のがん患者は介護保険法で定める特定疾病の状態のときに介護保険が利用できる。
▶午前29
学校教育法に基づく特別支援教育について適切なのはどれか。
- 訪問教育の対象は中学生までである。
- 支援体制を確立するために校内委員会を設置する。
- 重度の肢体不自由児に対し通級による指導を行う。
- 特別支援学校の教員は研修を受けずに経鼻経管栄養を実施できる。
- 転校の手続きを取らなくても長期入院中であれば院内学級に通うことができる。
▶午前30
A地区では、豪雨による土砂災害から2か月が経つ。家屋が倒壊した被災者の仮設住宅への入居が始まり、新たなコミュニティの構築への支援が必要となった。A地区の仮設住宅入居者は単身高齢者が多く、かかりつけ医への受診以外に外出する機会がほとんどない。また、慣れない地域での不安を訴える声が聞かれた。
仮設住宅入居者の孤立を防止し、新たなコミュニティづくりを促進するためのA地区への支援として、最も適切なのはどれか。
- 茶話会の開催
- 在宅医療の拡充
- 電話相談の拡充
- 通所介護事業所の開設
- 訪問リハビリテーションの実施
▶午前31
分母として人口データが得られない場合に、疾病の罹患や死亡などの全発生数を分母に用いて、ある疾病や年齢区分での発生が占める割合を示す指標はどれか。
- 相対危険
- 相対頻度
- 累積罹患率
- 人口寄与危険
- 人口寄与危険割合
▶午前32改題
日本の死因別死亡率の年次推移を図に示す。

説明として正しいのはどれか。
- 縦軸の死亡率は年齢を調整した値である。
- 死因Aが上昇傾向にある主な理由は野菜摂取量の減少である。
- 死因Bの平成7年の急激な低下は国際生活機能分類〈ICF〉改訂の影響である。
- 死因Cが低下傾向にある主な理由は血圧の管理である。
- 死因Dが低下傾向にある主な理由は食生活の見直しである。
▶午前33改題
健康日本21(第二次)における健康寿命について正しいのはどれか。
- 患者調査の結果を計算に用いる。
- 年齢別死亡率は計算に不要である。
- 日常生活に制限のない者の平均年齢である。
- 健康寿命の増加分を上回る平均寿命の増加を目標とする。
- 令和元年(2019年)の健康寿命と平均寿命の差は男性より女性が大きい。
▶午前34
日本における再興感染症はどれか。2つ選べ。
- 麻疹
- デング熱
- エボラ出血熱
- ウエストナイル熱
- 重症急性呼吸器症候群〈SARS〉
▶午前35
Aさん(20歳、男性)。1人暮らし。下肢に障害があり車椅子を利用しており、障害支援区分3である。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づき、Aさんが利用できる障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。
- 行動援護
- 同行援護
- 居宅介護
- 生活介護
- 療養介護
▶午前36
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉における1類感染症はどれか。2つ選べ。
- コレラ
- 痘そう
- ペスト
- マラリア
- 急性灰白髄炎
▶午前37
疾病の罹患群や非罹患群のスクリーニングの要件で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 検査方法が対象者よりも測定者にとって受け入れやすい。
- 確定診断の手法が確立していない疾病も対象となる。
- 治療法が確立していない疾病も対象となる。
- 疾病予防対策の効率の向上が期待される。
- 測定者による結果の変動が少ない。
▶午前38
ある集団の特定健康診査で得られたBMIと血圧との関連を表すのに適した指標はどれか。2つ選べ。
- 散布度
- 四分位数
- 相関係数
- 変動係数
- 回帰係数
▶午前39
生活保護制度について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 扶助の種類は7種類である。
- 保護施設に更生施設がある。
- 日本国憲法第14条の理念に基づいている。
- 保護は世帯を単位とすることを原則とする。
- 介護扶助によって介護保険料が現金給付される。
▶午前40
40歳以上の男性を対象とした疫学研究で、虚血性心疾患死亡率(10万人年対)を観察した。虚血性心疾患死亡率は、喫煙群では40.0、非喫煙群では24.0であった。
このときの寄与危険割合を百分率で求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②%
次の文を読み41〜43の問いに答えよ。
Aさん(26歳、女性)。会社員の夫と長女のBちゃん(1歳8か月)との3人暮らし。Bちゃんは1歳児健康診査を受診しており、異常はなかった。1歳6か月児健康診査が未受診だったため、地区担当の保健師が電話で次回の1歳6か月児健康診査の日程を連絡した。Aさんが電話に出たが、対応の声は小さく「Bは元気です。心配なことはありません」と言い、保健師の受診の勧めに応じなかった。保健師は「健康診査の会場でお渡しする予防接種の書類がありますので、受診できないようならお持ちしますね」と伝えて電話を切り、家庭訪問を行うこととした。
▶午前41
家庭訪問時、夫は会社に出勤しており不在であった。Bちゃんは一人歩きが可能で、意味のある言葉を発している。Aさんはマスクをしており、左眼の下から顎にかけて紫色に変色した内出血がある。玄関から見える室内は、ふすまが破れているなど荒んだ様子がみられる。
保健師が追加で確認するBちゃんの状態で優先度が高いのはどれか。
- 偏食
- う蝕
- 身体の外傷
- オムツかぶれ
▶午前42
家庭訪問の間、Bちゃんは機嫌よく過ごしている。保健師が予防接種の書類の説明を行っている間、Aさんは顔を伏せたままであった。ドメスティック・バイオレンス〈DV〉のスクリーニングとして、保健師は「家庭訪問をした方にお聞きしている質問がありますのでお尋ねしますね」とAさんに説明してから質問を行った。
ドメスティック・バイオレンス〈DV〉のスクリーニングとして保健師が行う質問で最も適切なのはどれか。
- 「今一番困っていることは何ですか」
- 「何もできないと落ち込むことがありますか」
- 「嫌なことがあってもすぐに忘れることができますか」
- 「パートナーといるときに怖いと感じることがありますか」
▶午前43改題
Aさんは「実は昨夜、夫に殴られました。半年くらい前から夫に殴られることが時々あります。今まで誰にも言えませんでした」と言う。Aさんには腹部にも大きなあざがあった。
このときの保健師の対応で優先度が高いのはどれか。2つ選べ。
- Aさんの夫との面接を行う。
- Aさんの医療機関への受診を勧める。
- AさんとBちゃんの婦人保護施設への避難を勧める。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律〈DV防止法〉について説明する。
次の文を読み44〜46の問いに答えよ。
Aさん(65歳、女性)。夫、長女および長女の子どもとの4人暮らし。長女の夫は単身赴任中である。Aさんは2か月前から軽い咳があったが、1週前から咳が激しくなり、倦怠感が出現したため自宅近くのかかりつけ医を受診した。胸部エックス線写真で異常陰影が認められ、病院を紹介された。喀痰塗抹検査陽性および結核菌PCR陽性のため肺結核と診断され、入院した。診断した医師から保健所に発生届が提出された。既往歴に特記すべきことはない。
▶午前44
Aさんの治療や検査について正しいのはどれか。
- 抗結核薬3剤で治療する。
- 薬剤感受性検査を実施する。
- 喀痰培養検査は不要である。
- インターフェロンγ遊離試験〈IGRA〉を実施する。
▶午前45
保健師が病院を訪問し、Aさんに確認した接触者の情報を表に示す。

接触者健康診断におけるハイリスク接触者はどれか。
- 夫
- 長女
- 長女の夫
- 長女の子ども
- 友人
▶午前46
入院から4週後、Aさんは服薬を自己管理できており、薬剤による副作用〈有害事象〉もみられていない。喀痰塗抹検査が連続して3回陰性となったため退院することとなった。病院を訪問した保健師にAさんから「服薬を続ける以外に、自宅に帰ってから結核をうつさないために私や家族が何かすることはありますか」と相談があった。
退院後の結核の二次感染予防について、Aさんに行う説明で適切なのはどれか。
- Aさんと接する者はN95マスクをしてもらう。
- 長女の子どもとは服薬終了まで接触しない。
- 長女の夫にBCGの接種を勧める。
- 二次感染の予防対策は必要ない。
- Aさんが触れた物は消毒する。
次の文を読み47、48の問いに答えよ。
Aちゃん(日齢20、男児)は、両親と3人暮らし。出産の状態および早期新生児期の経過を記した母子健康手帳の一部を以下に示す。保健師は新生児訪問のため、6月30日に自宅を訪問した。訪問時のAちゃんは、身長49.5cm、体重3,150g。授乳後で機嫌よく活発に四肢を動かしていたが、その後は眠ってしまった。栄養は母乳のみで1日の授乳回数は8、9回程度、授乳間隔は約3時間であった。授乳前のオムツ交換のたびに排尿あり。排便は3〜5回/日。黄疸はない。顔面の湿疹および前頭部に脂漏性の湿疹あり。音への反応あり。父親の仕事の都合で、Aちゃんの1か月児健康診査は7月15日に予約している。

▶午前47
新生児訪問時のAちゃんのアセスメントを行うために、追加で確認すべき情報で最も優先度が高いのはどれか。
- 聴覚検査の結果
- 1回の授乳時間
- 股関節の開排の制限の有無
- 入浴時の石けんの使用の有無
▶午前48
保健師は、Aちゃんの新生児訪問時の状況を母子健康手帳に記載し、予防接種を受けるかかりつけの小児科クリニックを決めておくと良いことなどを説明した。保健師がAちゃんの母親に心配なことはないか聞くと「Aと視線が合わないことや、大きな音がしたときに驚いたように両手を広げることがあり、心配だ」と話した。
このときの保健師の対応で適切なのはどれか。
- 1か月児健康診査の受診日を早めるよう勧める。
- Aちゃんの近くで大きな音を立てて反応を確認する。
- 新生児にみられる正常なことであり心配ないと説明する。
- 予防接種は病気の有無を確認してから受けるよう説明する。
次の文を読み49、50の問いに答えよ。
人口5万人、高齢化率34%のA市。主な産業は農業と農産加工業である。平成25年度から第2期特定健康診査等実施計画に基づき、60歳未満の特定健康診査受診率の向上および生活習慣病の予防対策に取り組んできた。今後は重症化予防に力を入れて取り組む予定である。特定健康診査実施後の結果を表に示す。

▶午前49
この結果から読み取れるのはどれか。
- 特定健康診査受診率は今後横ばいとなる。
- 特定保健指導によって医療費が削減された。
- 特定保健指導によって健康状態が改善している。
- 60歳未満の者の特定健康診査受診率は今後増加する。
- 特定健康診査受診者のうち、メタボリックシンドローム該当者の割合は60歳未満より60歳以上で高い。
▶午前50
A市保健師は、A市郊外の農村地区にあるB地区を対象に、糖尿病の重症化予防に取り組むことにした。B地区は人口約3,000人、高齢化率44%であり、内科無床診療所が1か所あるが、市立総合病院までは車で30分かかる。糖尿病と診断されたことがある者の全戸訪問に取り組んだところ「B地区から市中心地区にある市立総合病院に受診すると、通院と待ち時間で半日以上必要なため、特に農繁期に治療を中断してしまう」と言う者が多かった。そこで保健師は、B地区の糖尿病患者が継続的に糖尿病の治療が受けられるよう検討することが必要であると考えた。
治療継続のための対策として最も適切なのはどれか。
- B地区での糖尿病患者会の発足
- 糖尿病の治療中断者への特定健康診査の受診勧奨
- B地区住民専用の市立総合病院への送迎バスの運行
- B地区診療所における月1回の糖尿病専門外来の開設
次の文を読み51、52の問いに答えよ。
Aさん(45歳、男性)。両親と3人暮らし。統合失調症で治療中。就労移行支援としてB事業所に週5日通所している。就労中に独語がみられるが、作業に支障はない。B事業所の生活指導員から市の保健師に「Aさんの父親が筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉で入院している。70歳になるAさんの母親は事業所の家族会でも積極的に発言するなどしっかりしている。しかし、Aさんは、自分が父親を1人で介護しなくてはならないと思い込み悩んでいるので、支援して欲しい」と連絡があり、Aさんの希望でB事業所において地区担当の保健師が初回の面接を行った。
▶午前51
Aさんに対する保健師の対応で最も適切なのはどれか。
- 保健所保健師への相談を提案する。
- 父親の介護は母親に任せるよう提案する。
- 筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉の症状について説明する。
- 父親の介護について母親を交えて話し合うことを提案する。
▶午前52
その後Aさんの父親の病状が安定したため、関係者によるAさんの父親の退院に向けた検討会を実施した。検討会には、Aさんの希望で地区担当の保健師も出席した。父親は介護認定審査中であり、父親の主治医は在宅療養をするためには訪問介護の利用が必要であるとの意見であった。それに対しAさんは「知らない人が家に来るのが不安だ。自分の病気のことを理解してもらえるだろうか」と話した。
このときのAさんに対する保健師の説明で最も適切なのはどれか。
- 「Aさんの主治医に相談しましょう」
- 「訪問介護員はいつでも交代できますよ」
- 「Aさんがご自身の病気について説明するときに私も同席しますよ」
- 「お父さんのサービス利用はAさんが不在の時間帯に行いましょう」
次の文を読み53、54の問いに答えよ。
A市は、平成18年に5つの市町村が合併してできた人口約6万人、高齢化率32%の市である。主要産業は漁業と農業である。市街地が分散しており、学校や福祉施設も多い。一部の町内会は活発に活動している。A市総合計画では、健康増進および居宅での介護体制の推進を掲げており、介護保険施設の入所定員は増やさない方針である。
▶午前53
A市の保健師は、健康相談のときに50歳代の住民から「自分の祖父母は70歳代から施設に入所していた。自分の親が80歳になり、できる限り自宅で暮らしたいと言っているが、将来自宅で親を看取ることについては想像がつかない」という話を聞いた。
市民全体の看取りの現状を把握するために収集する情報で優先されるのはどれか。
- 要介護認定者数
- 死亡場所別の死亡者数
- 長期入院中の高齢者数
- 介護保険施設の平均入所年数
- 介護保険の居宅サービスの利用者数
▶午前54
A市住民からは、「自宅で長く暮らしたい」という意見が多く聞かれた。一方で、従来とは労働形態や家族形態が変化し、高齢者のみの世帯も増えており、「1人では不安だ」との意見も聞かれる。
A市における共生社会の実現を目指して、保健師が取り組む事業で最も適切なのはどれか。
- 認知症予防教室
- 介護技術を学習する教室
- 住民相互の高齢者見守り活動の推進
- 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉の見学会
次の文を読み55の問いに答えよ。
従業員300人の文具会社。部署は開発部門、販売部門、広報部門に分かれている。この会社の定期健康診断の問診時の主訴で多かったのは、腰痛および眼の疲れであった。社内の健康管理室の保健師が、これらの主訴を配属別に分類したところ、腰痛は販売部門の配送センターの社員に特に多いことが分かった。配送センターには、注文に応じて商品の仕分け作業をする社員50人が働いている。健康管理室の保健師は、配送センターにおける腰痛への対策を行う必要があると考えた。
▶午前55
保健師が実施することで最も優先されるのはどれか。
- 職場巡視を行う。
- 腰痛を訴える者に保健指導を行う。
- 腰痛体操を休憩時間に行うことを計画する。
- 配送センターの社員に運動機能の測定を行う。
第104回保健師国家試験・午後(55問)
▶午後1
公衆衛生看護の基本理念について正しいのはどれか。
- プライマリヘルスケアはバンコク憲章で定義された。
- 生存権の保障は日本国憲法第11条に規定されている。
- ノーマライゼーションは障害者福祉の基本理念となっている。
- ヘルスプロモーションは日本では健康フロンティア戦略で初めて取り入れられた。
▶午後2
グループの発展過程を準備期、開始期、作業期、終結期に分類したとき、準備期における支援者の役割として最も適切なのはどれか。
- グループの目的の共有を促す。
- グループの相互作用を促進させる。
- メンバー間の信頼関係の確立を図る。
- グループに参加する対象を理解する。
▶午後3
市民と行政とのパートナーシップを基盤とした保健施策の推進について最も効果的なのはどれか。
- 保健福祉計画の策定を市民の代表と行う。
- 行政情報を複数の方法で市民に公開する。
- 市民の意見を受け付ける専門の部署を設ける。
- 市民の代表から地域の課題を聞き取る機会を設ける。
▶午後4
仕事が忙しく少し体調が優れないので、休日に十分な睡眠をとり静養した。
この行動は健康段階別保健行動のどれか。
- 健康増進行動
- 予防的保健行動
- 病気回避行動
- 病気対処行動
▶午後5
Aさん(80歳、男性)。民生委員から「最近、Aさんが老人クラブに参加しなくなったので心配している」と地区担当保健師に相談があった。民生委員から、Aさんは妻が亡くなって1人暮らしとなり食事や生活が不規則になっていることや、一人娘は結婚して遠方に住んでいることを聞いた。
地区担当保健師の今後の支援として優先度が高いのはどれか。
- 家庭訪問でAさんの状況を確認する。
- Aさんの娘に見守りを行うよう連絡する。
- 老人クラブのメンバーにAさんの参加の勧誘を依頼する。
- 地域包括支援センターの介護予防事業をAさんに紹介する。
▶午後6
保健師の家庭訪問の対象で最も優先度が高いのはどれか。
- 要介護2の独居高齢者
- 特定健康診査の未受診者
- A群β溶血性レンサ球菌感染症の罹患が疑われる幼児
- 治療中断していると病院から連絡があった統合失調症患者
▶午後7
A町では、がん検診の受診率向上対策に取り組んだ結果、受診率が向上した。しかし、毎年、がん検診の精密検査の対象者の中に精密検査を受診していない者がいる。
精密検査の未受診者への受診勧奨として最も効果が高いのはどれか。
- 町の広報誌に精密検査の日時を掲載する。
- 保健師が精密検査の未受診者に家庭訪問を行う。
- コミュニティ放送で精密検査の受診を呼びかける。
- がん検診における集団指導で精密検査の必要性を伝える。
▶午後8
人口8,000人のA町では妊婦とそのパートナーを対象として、妊娠、出産および子育ての知識の習得を目的に両親学級を実施していたが、1回当たりの参加者が年々減少している。そこで、次年度は家族同士の交流を促進するプログラムを導入することにした。
A町の保健師が次年度の両親学級の具体的な内容を検討するにあたり分析する項目で優先度が高いのはどれか。
- 両親学級の講師からの意見
- A町の合計特殊出生率の推移
- 近隣市町村の両親学級の実施状況
- 妊娠届出時の面接での聞き取り内容
▶午後9
母子保健活動の見直しのために地域診断を行うことになった。
地区担当保健師が最初に行うことで最も適切なのはどれか。
- 地区内の子どもがいる世帯にアンケート調査を実施する。
- 乳幼児健康診査の問診票から相談内容の集計を行う。
- 子育て広場に来ている母親に聞き取り調査を行う。
- 地区にある保育所の保育士と連絡会議を行う。
▶午後10
市の各地域で認知症サポーター養成講座を実施した。
地域におけるコミュニティ・エンパワメントが最も引き起こされた状態はどれか。
- 講座を受講した住民の数が増えた。
- 認知症サポーター同士の交流が深まった。
- 家庭内で認知症の話をすることが増えた。
- 認知症を有する住民を見守るボランティアグループができた。
▶午後11
地域ケアシステムを構築するための会議の開催について最も適切なのはどれか。
- 参加メンバーを固定する。
- 問題が生じたときに開催する。
- 住民の代表をメンバーに加える。
- あらかじめ議論の方向性を決めておく。
▶午後12
Aちゃん(3歳4か月、男児)。両親と祖母との4人暮らし。市の3歳児健康診査に母親と来所した。階段の昇り降りはできるが、泣いていて言語の理解や精神発達の観察ができなかった。母親は「家では簡単な単語は出ている。仕事が忙しいので、平日はほとんど同居する夫の母にみてもらっている。夫の母は外出を好まず、家でテレビを観て過ごすことが多い」と話した。市では、地区乳幼児相談、3歳児健康診査事後教室および4歳児子育て教室を実施している。
このときの保健師の対応として最も適切なのはどれか。
- 地区乳幼児相談への参加を促す。
- 3歳児健康診査事後教室への参加を促す。
- 日中の家庭訪問を早期に行うことを伝える。
- 4歳児子育て教室で経過を確認することを伝える。
▶午後13
精神保健医療福祉施策について正しいのはどれか。
- 精神通院医療は障害者基本法に規定されている。
- 市町村には基幹相談支援センターの設置義務がある。
- 精神障害者の在宅福祉サービスの実施主体は都道府県である。
- 精神疾患は医療計画で重点的に対策を推進する疾病に位置付けられている。
▶午後14
健康増進法に基づく健康増進事業による肝炎ウイルス検診について正しいのはどれか。
- 実施主体は都道府県である。
- 対象は満40歳以上の者である。
- 60歳から無料で検診が受けられる。
- 特定健康診査の検査項目に定められている。
▶午後15
口腔の疾患とその予防法の組合せで正しいのはどれか。
- う蝕――フッ化物を塗布する
- 歯周病――塩分摂取を制限する
- 口内炎――ビタミンKを摂取する
- 顎関節症――硬い食品を強く嚙む
▶午後16改題
業務上疾病で正しいのはどれか。
- 職業性疾病と同義である。
- 産業医によって認定される。
- 使用者は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- 令和3年(2021年)はじん肺症およびじん肺合併症が最も多い。
▶午後17
保健師が行う公衆衛生看護管理の事例管理はどれか。
- 子育ての支援者を育成する予算を確保する。
- 担当地域の地域診断を実施する。
- 対象者の支援計画を立案する。
- 地域の支援者を育成する。
▶午後18
A市の地域包括支援センターの保健師が、担当する要支援1のBさん(70歳、男性)を訪問した。Bさんは68歳の妻と2人暮らしだが、孫のCさん(17歳、高校2年生)が数日前から滞在していた。Cさんは妊娠30週であった。Cさんは他県で両親と3人で暮らしているが、A市の総合病院で出産予定のため、しばらくの間Bさん宅に滞在することが分かった。
現時点で保健師が連絡を取る先で最も適切なのはどれか。
- A市の地区担当保健師
- A市の総合病院の産婦人科
- Cさんの高校の養護教諭
- Cさんの住所地の地区担当保健師
▶午後19
耐糖能異常の頻度の地域比較調査を行ったところ、A地区では空腹時血糖で評価し、B地区では随時血糖で評価していたことが明らかになった。
疫学調査法におけるこのような問題点はどれか。
- 交絡
- 偶然誤差
- 選択の偏り〈バイアス〉
- 情報の偏り〈バイアス〉
▶午後20
地方自治体において、予算が会計年度の開始前に成立しないときに、必要な経費を支出できるよう組まれるのはどれか。
- 一般会計
- 暫定予算
- 特別会計
- 補正予算
▶午後21
健康上の問題がある児童生徒に対して、養護教諭を中心に行う個別の保健指導を規定しているのはどれか。
- 文部科学省設置法
- 学校保健安全法
- 学校教育法
- 教育基本法
▶午後22
管内の病院から、保健所に「複数の入院患者が多剤耐性菌に感染している」との報告があった。感染症担当の保健師は、患者の発生状況および病院が実施した対応について確認した後、立ち入り検査を行うこととなった。
立ち入り検査の根拠となる法律はどれか。
- 医療法
- 地域保健法
- 食品衛生法
- 労働安全衛生法
▶午後23
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉による介護保険法の見直し事項はどれか。
- 地域ケア会議の推進
- 地域密着型サービスの創設
- 介護予防訪問看護の地域支援事業への移行
- 市町村単位での医療機能の分化および連携の推進
▶午後24改題
令和3年(2021年)6月末における精神疾患を有する者の入院者数が最も多い入院形態はどれか。
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
▶午後25
ソーシャル・キャピタルの醸成に最も効果的な地域保健活動はどれか。
- 認知症の専門医による講演会を開催する。
- 地域に出向き生活習慣病予防の健康教育を行う。
- 育児不安が強い母親を対象に相談会を開催する。
- 民生委員児童委員協議会と協働して乳児家庭全戸訪問事業を行う。
- 自立支援医療(育成医療)の申請があった児に対して家庭訪問を行う。
▶午後26
日本版21世紀型DOTS戦略推進体系図を示す。

【A】から【C】に入る語句の組合せで正しいのはどれか。
【A】――【B】――【C】
- 潜在性結核感染症の者を除く結核患者――訪問DOTS――連絡確認DOTS
- 潜在性結核感染症の者を除く結核患者――地域DOTS――コホート検討会
- 喀痰塗抹陽性の結核患者――訪問DOTS――連絡確認DOTS
- 全結核患者及び潜在性結核感染症の者――外来DOTS――連絡確認DOTS
- 全結核患者及び潜在性結核感染症の者――地域DOTS――コホート検討会
▶午後27
法律に基づく全国の疾病登録があるのはどれか。
- がん
- 糖尿病
- 脳卒中
- 慢性腎臓病
- マイコプラズマ感染症
▶午後28改題
平成22年(2010年)から令和3年(2021年)における日本の社会情勢の変化で適切なのはどれか。2つ選べ。
- 完全失業率の増加
- 老年化指数の低下
- 平均世帯人員の減少
- 社会保障給付費の減少
- 65歳以上の雇用者数の増加
▶午後29
母子健康手帳の交付を受けるために保健センターに来所した女性から、公費の助成が受けられる妊婦健康診査について質問があった。
保健師の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 「血液検査を毎回行います」
- 「保健指導の費用は自己負担です」
- 「公費の助成が受けられる医療機関が決まっています」
- 「血液検査の項目にはHIV抗体検査が含まれています」
- 「妊娠初期は2週に1回の健康診査が助成の対象になります」
▶午後30
歯科保健施策について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 歯科疾患実態調査は3年ごとに実施されている。
- 健康増進法によって歯周疾患検診が義務化された。
- 平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。
- 第一次国民健康づくり対策の課題の1つとして歯の健康が取り上げられた。
- 食育の推進の一助として噛ミング30〈カミングサンマル〉運動が行われている。
▶午後31
災害対策基本法に基づき都道府県が行う災害対策はどれか。2つ選べ。
- 防災のための調査研究
- 指定緊急避難場所の指定
- 都道府県地域防災計画の作成
- 避難行動要支援者名簿の作成
- 住民の自発的な防災活動の促進
▶午後32
直接法による年齢調整死亡率を算出する際に必要な情報はどれか。2つ選べ。
- 基準集団の死亡率
- 観察集団の死亡実数
- 観察集団の年齢別人口
- 基準集団の年齢別人口
- 観察集団の年齢別死亡率
▶午後33
測定値の偶然誤差の大きさを表す指標として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 分散
- 中央値
- 算術平均
- 標準偏差
- 最頻値〈モード〉
▶午後34
保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 国勢調査は5年に1度実施される。
- 患者調査から死因別死亡率が得られる。
- 人口動態調査は2年に1度集計される。
- 国民生活基礎調査は2年に1度実施される。
- 国民健康・栄養調査の調査項目に腹囲がある。
▶午後35
医療提供体制について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 医療法において病床の種別は3つに分類されている。
- 医療計画には医療従事者の確保に関する事項を記載する。
- 日本の医療施設の病床数は過去10年間は増加傾向にある。
- 特定機能病院を称するには厚生労働大臣の承認が必要である。
- 診療所は20人以下の患者を入院させるための施設を有すると規定されている。
次の文を読み36〜38の問いに答えよ。
Aさん(35歳、女性、無職)。夫(37歳、会社員)と幼稚園に通う長男(5歳)との3人暮らし。半年前から倦怠感および不眠症状のため近所の心療内科に通院しており、境界性パーソナリティ障害と診断されている。Aさんの体調が悪いときは、夫が家事や長男の世話をしているが、仕事で帰宅時間が遅いため十分に行えていない。最近はAさんと夫が口論することも増え、夫はAさんとの接触を避けるようになった。また、Aさんは人付き合いが苦手で近隣との関係が悪く、Aさんの両親や親戚との交流もない。
▶午後36
Aさんは受診の際、主治医に長男の世話ができないと訴えたところ、主治医から保健所への相談を勧められ、保健所に電話してきた。電話の内容から長男へのネグレクトが懸念されたため、翌日、担当保健師がAさんの自宅を訪問した。夫は仕事で不在であり、Aさん及び長男と面談した。部屋の中は比較的片付いている。長男は年齢相応の成長発達をしているが、衣服の汚れが目立つ。
この訪問において最も優先して把握しておくべきことはどれか。
- 長男の予防接種状況
- 家の中の他の部屋の状況
- 夫が長男の世話をする頻度
- Aさんと接しているときの長男の様子
▶午後37
家庭訪問後、担当保健師がAさん家族への継続支援を開始した。しばらくすると、Aさんから担当保健師に頻繁に電話がかかってくるようになり、泣きながら「今すぐ訪問に来て」と訴えることも多かった。このような状況が繰り返されるうちに、担当保健師はAさんに苦手意識をもつようになった。ある日、担当保健師の不在時にAさんの電話を受けた別の保健師に対して、Aさんが「今の担当保健師は冷たいので担当を替えてほしい。あなたに私の担当になってもらいたい」と訴えた。
このような状況への担当保健師の対応として正しいのはどれか。
- 担当保健師を軸に保健師間でのAさんへの対応を統一する。
- Aさんの主治医にAさんの入院について相談する。
- Aさんの希望に合わせて担当保健師を交替する。
- Aさんとの面接頻度を増やす。
▶午後38
Aさんへの支援のため、担当保健師は関係者を集めて会議を開催することにした。
初回の会議に招集するメンバーで優先度が低いのはどれか。
- 市の地区担当保健師
- Aさんの心療内科の主治医
- 児童相談所の虐待担当の職員
- 精神保健福祉センターの職員
- 長男の通園している幼稚園の職員
次の文を読み39〜41の問いに答えよ。
A市にある定員80人の保育所。乳児保育も実施している。8月1日(金)に、腹痛と下痢症状で4人の園児が欠席した。8月5日(火)に、新たに4人の園児が同様の症状で欠席した。さらに、8月1日(金)から欠席していた園児4人のうち2人は症状が落ち着いたが、他の2人が重篤な下痢症状によって入院したと保護者から連絡が入った。保育所長は感染症の発生を疑い、保健所の感染症担当の保健師に相談した。
▶午後39
相談を受けた保健所保健師が聞き取る情報で優先度が高いのはどれか。
- 嘱託医への報告の有無
- 保育所でのイベントの開催状況
- 8月1日(金)より前の園児の欠席状況
- 社会福祉施設等主管部局への報告の有無
▶午後40
保育所長から相談があった8月5日(火)の夕方に、園児2人が入院しているA市内の病院から、園児2人の腸管出血性大腸菌感染症の発生届が提出された。
保健所の対応で優先度が高いのはどれか。
- 地域の医療機関へ情報提供を行う。
- 食品衛生監視員と保健師で立ち入り調査を行う。
- 保育所の保護者を対象とした説明会を開催する。
- 保育所のすべての園児および職員の検便を実施する。
▶午後41
8月6日(水)に、新たに2人の園児が下痢症状で欠席したと保育所から保健所に連絡があった。
このときの保健所の対応で適切なのはどれか。
- 排泄習慣が確立していない園児に対する登園停止の指示
- 欠席していない園児の保護者との個別面接
- 保育所職員に対する汚物処理方法の指導
- 患児の担任保育士への就業制限
次の文を読み42〜44の問いに答えよ。
糖尿病の有無とがん発症との関連を検討するために、地域における特定健康診査の受診者の中でがんの既往がない男女1万人ずつの2万人を登録し、糖尿病の有無を調査した。この調査から5年後に新規のがん発症の有無を確認した。
▶午後42
この調査の研究デザインはどれか。
- 横断研究
- 介入研究
- 生態学的研究
- 症例対照研究
- コホート研究
▶午後43
この集団では、がんの発症に男女差があることが分かった。そのため、男女別に結果を分析することにした。
この制御方法はどれか。
- 限定
- 層化
- 標準化
- 無作為化
- マッチング
▶午後44
脱落例がなかったと仮定して、男性1万人におけるベースライン時の糖尿病の有無別の5年間のがんの新規発症の有無を表に示す。

「糖尿病なし」に対する「糖尿病あり」のがん発症の累積罹患率比を求めよ。
ただし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:① . ②
次の文を読み45〜47の問いに答えよ。
人口3万人のA市。市の面積の70%を山間部が占めており、主要産業は農業と畜産業などで、一次産業従事者が多い。人口の分布は市街地のB地区に集中しており、市役所、公共施設、医療施設および商業施設が集中している。高齢化率は38%、国民健康保険加入者は1万人である。平成20年度から導入された特定健康診査の受診実績は、事業開始時から現在まで20%台を推移しており県内最下位である。
▶午後45
A市の国民健康保険加入者の生活習慣病を改善するために見直すべき計画はどれか。2つ選べ。
- 医療計画
- 地域福祉計画
- データヘルス計画
- 介護保険事業計画
- 特定健康診査等実施計画
▶午後46
A市の特定健康診査の受診率を5つの小学校区で比較すると、市街地のB地区が最下位である状況が続いている。A市では、従来は集団健診のみであった特定健康診査を、がん検診と組み合わせた健康診査、人間ドック、医療機関への委託による個別健康診査など様々な方式で行うことにした。また、B地区を受診勧奨の重点地区に設定し、個別訪問による受診勧奨を行うことにした。その上で、保健師はA市で実施している特定健康診査の評価をすることにした。
ストラクチャー評価に用いる指標で適切なのはどれか。
- 地区別受診率
- 協力医療施設の数
- 特定健康診査の実施回数
- 受診勧奨のための個別訪問件数
▶午後47
特定健康診査の実施方式の拡大などに取り組んだ結果、B地区の受診率は前年よりも向上したが他地区に比べて低く、特に男性の受診率は低いままである。受診率向上を目的とした家庭訪問の際に「病院にはいつでも行ける」、「病気とは無縁だ」、「病気が発見されるのが怖い」という声が多く聞かれた。保健師はB地区の住民に広く健康管理について啓発活動を行うことが必要と考え、健康診査の結果説明会を兼ねた「健康づくりの集い」を公民館で開催することにした。
B地区の健康づくりを活性化するために、企画をともに検討する者で最も適切なのはどれか。
- B地区小学校PTAの役員
- 自治会役員
- 健康推進員
- 民生委員
次の文を読み48、49の問いに答えよ。
A市は人口5万人の地方都市。地場産業である繊維工業などの小規模の事業所の就業者が、A市の産業別就業者の大部分を占める。郊外には大手自動車会社のB工場(従業員500人)があり、A市の住民200人が勤務している。A市では男性の健康寿命が短いことが問題視されており、男性の平均寿命は80.0歳(全国平均80.5歳)、健康寿命は67.0歳(同70.0歳)である。女性の平均寿命は87.0歳(同86.8歳)、健康寿命は74.0歳(同74.0歳)である。保健師は人口動態統計から主要死因別の標準化死亡比〈SMR〉を調べた。その結果を表に示す。

▶午後48
A市の健康寿命に影響する要因を明らかにするために、次に入手すべき情報はどれか。
- 特定健康診査受診率
- 疾患別の1人当たりの医療費
- 特定健康診査受診者の生活習慣
- 要介護認定者が罹患している疾患
▶午後49
A市では住民に対して健康意識調査を行った。男女ともに「塩辛い食べ物が好き」、「どこへ行くにも車で移動する」という意見が多く、就業者では「仕事が優先で健康のことは後回しになる」という意見が多かった。保健師がB工場の衛生管理者に問い合わせたところ、B工場の特定保健指導対象者の割合は全国平均よりも低いことが分かった。A市では、今後、医療保険医療費データを分析して成人期の生活習慣病対策を進めることにした。
分析に必要な情報を得るために連携する組織で優先されるのはどれか。
- 後期高齢者医療広域連合
- 全国健康保険協会
- 保険者協議会
- 健康保険組合
次の文を読み50、51の問いに答えよ。
Aさん(65歳、男性、無職)。妻との2人暮らし。定年退職後、年金の給付を受けて生活している。2年前から足の震えが出現したため病院を受診し、Parkinson〈パーキンソン〉病と診断された。定期的に病院を受診していたが、Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類でステージⅢとなり、主治医から医療費助成の申請を勧められた。Aさんの妻が申請のため保健所に来所した。
▶午後50
難病の医療費助成制度についての妻への説明で正しいのはどれか。
- 「どの医療機関でも医療費助成が受けられます」
- 「負担上限月額は所得に応じて決まります」
- 「更新手続きには診断書は必要ありません」
- 「更新手続きは2年に1回必要です」
- 「医療費の自己負担は1割です」
▶午後51
保健所保健師は、医療費助成の手続きの際に決めた日時に家庭訪問をした。Aさんは「入浴や通院のときに不安を感じることがあるが、何とか自分のことは1人でできている」と話した。
初回訪問時に情報収集することで最も優先されるのはどれか。
- 経済状況
- 家族関係
- 住宅内の環境
- 近隣との付き合い
次の文を読み52、53の問いに答えよ。
人口1万人のA市。5月23日に大規模な地震が発生し、家屋の倒壊などのため、住民の多くが避難所に避難した。地震発生から7日後、市の保健師は、避難所の巡回相談の際、被災者が夜間眠れずにいることが分かったが、それが主訴として現れないことから、大規模災害後の心の変化や対処方法を示したポスターを掲示した。また、他県から応援に来ている心のケアチームの精神科医に依頼し、災害後のストレス反応についての健康講座を行った。
▶午後52
ポスターの掲示や健康講座の開催によって、不眠や食欲不振を自覚して保健師に訴える被災者が増えた。
このときの保健師の対応で適切なのはどれか。
- 栄養補助食品を配布する。
- 睡眠時間の記録をつけるよう促す。
- 心のケアチームと巡回相談の実施を調整する。
- 災害時の出来事について保健師に話すよう促す。
▶午後53
発災から2か月後、避難者は自宅や親戚宅、仮設住宅へ入居し、避難所は閉鎖された。その1か月後、保健師は仮設住宅の入居者への健康調査を実施することとした。
保健師の行う健康調査について最も適切なのはどれか。
- 地区ごとに調査内容を変える。
- 仮設住宅の入居者の全戸訪問をする。
- 希望者にストレスチェックを実施する。
- 仮設住宅の集会所で聞き取り調査を実施する。
次の文を読み54、55の問いに答えよ。
Aさん(14歳、女子、中学2年生)は、両親と弟(2歳)との4人暮らし。中学校入学直後からクラスになじめず、無気力な様子がみられ、1年生の3学期から不登校になっている。学級担任と養護教諭は定期的に家庭訪問を行い、Aさんと母親の気持ちを聞き状況把握に努めた。Aさんは教室には入りづらいが、学校に行くことにはそれほど抵抗はないようだった。2年生の2学期になって「保健室なら行けそう」という言葉が聞かれるようになった。そこで、中学校の校内委員会でAさんの保健室登校について話し合うこととなった。
▶午後54
保健室登校を開始するにあたり、養護教諭が他の職員とともに確認する事項で適切でないのはどれか。
- Aさんの保健室登校に対応できる職員の支援体制が整っていること
- Aさんの保護者から保健室登校に対する協力が得られていること
- 全教職員の保健室登校に対する共通理解が得られていること
- 保健室登校を終了する期日が設定されていること
▶午後55
Aさんは不定期な保健室登校ができる段階を経て、2年生の3学期からは毎日、保健室登校ができている。スクールカウンセラーとも数回の面接を行い「欠席のきっかけは友人関係だった」などと自分自身を振り返ることもでき、情緒的に安定してきた。最近では時々、学級担任に会いに教室に行けるようになった。保健室へ来室する数人の同級生と会話する様子もみられてきたことから、養護教諭は学級担任や他の職員と相談して、この機会に、Aさんが教室に登校できるように働きかけることにした。
養護教諭が行う支援で最も適切なのはどれか。
- 1週間当たりの教室に行く回数を決める。
- 保健室をAさんの居場所として定着させる。
- Aさんが興味のある科目から参加するよう勧める。
- 同級生に毎日保健室に迎えに来てもらうように依頼する。
資料 厚生労働省「第104回保健師国家試験、第101回助産師国家試験、第107回看護師国家試験の問題および正答について」